| 宇宙創生以降 | |
| 138億年前 | 宇宙創生。プランク時代。クォークが生成。 |
| 宇宙創生から10-44秒後 | 超統一力が大統一力と重力に分かれる。グルーオンが生成。 |
| 宇宙創生から10-36秒後 | 大統一時代が終わり、大統一力が電弱力と色の力(核力=強い力)に分かれる。真空の相転移による超膨大なエネルギーでインフレーションが始まり、宇宙は急激に膨張。 |
| 宇宙創生から10-34秒後 | インフレーションが終わり宇宙は極超高温・高密度状態になる(いわゆる「ビッグバン」)。電弱時代。宇宙の大きさはこの時点で量子レベルから数cm程度にまで拡大したと考えられる。 |
| 宇宙創生から10-10秒後 | 電弱力が電磁気力と弱い力に分かれる。物質と反物質の釣り合いが崩れ、対消滅により物質だけが残る。 |
| 宇宙創生から10-4秒後 | 宇宙の温度が1兆度ほどにまで下がり、クォークやグルーオンからハドロン(陽子・中性子など)が出来るQCD相転移がおこる。ハドロン時代。 |
| 宇宙創生から1秒後 | 陽子と中性子から出来た重水素原子核の核融合が始まる。 |
| 宇宙創生から3分~20分後 | 重水素原子核融合によりヘリウムと、ほんのわずかなリチウム、ベリリウムの原子核が合成され終了。宇宙は原子核、電子、光子によるプラズマ状態となる。 |
| 宇宙創生から38万年後 | 宇宙の温度が3000k程まで下がり、電子と原子核が結合して原子が生成されるようになる。電子との相互作用で進むことが出来なかった光子が通るようになり、宇宙は見通しが良くなる(宇宙の晴れ上がり現象)。 |
| この期間を暗黒時代と呼ぶ。宇宙が晴れ上がった後、恒星が誕生するまでの間は、光る天体がないため。 | |
| 宇宙創生から1億年後頃 | 最初期の恒星(第一世代の天体)が生まれたと考えられる。 |
| 宇宙創生から1億~5億年後頃 | 最初期の銀河が生まれはじめる。地球のある銀河系もこの頃か。 |
| 宇宙創生から8億年後頃 | 宇宙の再電離。 |
| 70億年前 | 宇宙の膨張が再び加速。ダークエネルギーによるものか。 |
| 46億年前頃 | 半減期の短いヨウ素129からβ崩壊で生まれる安定同位体キセノン129が地球や隕石などから見つかることから、原始太陽が出来始める頃、比較的近い場所で超新星爆発があった可能性が高く、その際の衝撃で星間物質が圧縮し、その密度の差から微重力によって星間物質が集まるようになり、太陽と太陽系の元となる原始惑星系円盤の形成につながったと考えられる。 |
| 地球誕生以降 | |
| 46億年前(冥王代) | 太陽周辺の原始惑星系円盤内で、塵が衝突して微惑星へと成長し、微惑星がさらに衝突して成長し、原始地球を含む惑星がいくつか誕生する。 |
| 45億5000万年前(冥王代) | 地球の衛星「月」が誕生する。現在は地球に火星くらいの大きさのトロヤ惑星テイアが衝突し、分離した大量の破片が集合して月になったとするジャイアント・インパクト説が有力視されている。地球全体が溶融したことで、鉄などの重金属が沈降し、核の形成につながったと考える説もある。 |
| 44億年前頃(冥王代) | 地球がマグマオーシャンの状態から表面が冷えてきて地殻が出現する。海ができ始めたのもこの頃とされる。 |
| 42億8千万年前頃(冥王代) | カナダ・ケベック州の沖合海底の熱水噴出孔から見つかった微生物の化石は、この頃のものとする説がある。 |
| 41億年前~38億年前(冥王代) | 地球や月に多数の天体が衝突したとされる仮説(後期重爆撃期)の期間。月の「海」と呼ばれる玄武岩質の平地は、多数の隕石衝突で溶融したマントルの跡と考えられている。要因として木星のようなガスジャイアントの公転軌道の変化に影響を受けた多数の小天体の軌道が太陽近くにまで移動したためとされる(否定的な説もある)。 |
| 40億年前頃(冥王代) | 地球に海洋が出現し、この頃までには表面はほぼ海に覆われる。表面温度の低下で水蒸気が雨となって大量に降り注いだ結果と考えられる。なお30億年前ころまで海水温は100度前後あったとみられる。 |
| 40億年前頃(冥王代) | 地球に原始生命が出現したと考えられる。もっと古い43億年前くらいとする説もある。生命発生の起源については、粘土や鉱物などの界面で代謝が始まったとする表面代謝説、RNAの自己複製と代謝から始まったとするRNAワールド仮説、DNAの触媒を起源とするDNAワールド仮説、ペプチドやタンパク質分子の触媒から始まったとするプロテインワールド仮説、脂質分子膜内部での化学反応から始まったとするリピットワールド仮説、代謝や複製に似た機能を持った物質を生命の前段階として含めるガラクタワールド仮説、初期生命は宇宙から来たとするパンスペルミア説、これらの仮説を組み合わせた説などがある。発生場所も海中の熱水噴出孔説や陸上の温泉地帯説、地下説もある。 |
| 40億年前頃(冥王代) | この頃、火星の北半球にあるアラビア大陸で大規模な噴火が繰り返し起きたとみられる。 |
| 38億年前(太古代) | 生命が存在したと考えられる地質学的痕跡のある年代。真正細菌と古細菌の共通祖先から分かれたとされる。原始生命が地球環境が激変したと考えられる「後期重爆撃期」を生き延びたとする説が有力。また現在見られる最古の地殻岩石もほぼこの時代のもの。 |
| 35億年前頃(太古代) | 最古の化石の年代。 |
| 32億6千万年前頃(太古代) | 直径37~58kmほどの巨大な隕石が落下し、今の南アフリカ・バーバートングリーンストーンベルトを形成したとされる。 |
| 31億年前~28億年前頃(太古代) | 最初期の大陸のひとつ、バールバラ大陸が存在したとみられる年代。現在のアフリカ南部とオーストラリア西部に同時代の安定陸塊(クラトン)の痕跡が残っている。 |
| 29億年前頃(太古代) | 現在判明している最古の氷河期ポンゴラ氷河期の時代。 |
| 27億年前頃(太古代) | この頃から火山活動に伴い陸地が急速に広がり始める。ケノーランド大陸が形成されたと言われる。陸上の風化によって金属イオンが海中に溶け二酸化炭素とくっつき炭酸塩鉱物として固定化するため、大気中の二酸化炭素の量が減り始める。温室効果も弱まり気温も下がっていったとみられる。 |
| 27億年前頃(太古代) | 光合成を行うシアノバクテリアとみられるストロマトライトの最古の化石の年代。この頃から生物によって大量の酸素が生み出され、海中に溶けていた鉄イオンが酸化鉄として堆積するようになる(縞状鉄鉱床)。酸素の苦手なタイプが多い真正細菌・古細菌に代わり、古細菌より分かれたと考えられる酸素を利用する真核生物(細胞核を持つ生物)が現れ増えはじめる。この生物の置き換わりを大量絶滅のひとつに加える説もある。 |
| 25億年前(原生代) | シデリアン期。北半球高緯度地域にアークティカ大陸が広がる。 |
| 24億年前~21億年前(原生代) | ヒューロニアン氷期。地球全体が氷河期となる全球凍結もあったとされる。シアノバクテリアによる大規模な光合成による酸素発生によって大気の組成も変化し、二酸化炭素やメタンが大幅に減少して温室効果が薄れ、氷期が訪れたという説が有力。深刻で長期に渡る氷期によりシアノバクテリアを含む多くの生物が死滅したと考えられる。 |
| 21億年前頃(原生代) | 最古の真核生物の化石の年代(推定)。 |
| 20億2300万年前頃(原生代) | 現在の南アフリカフレデフォートに直径10~12km程度の小惑星が衝突。直径300kmのクレータが生じる。衝突のエネルギーは87Ttに達したとも。 |
| 19億年前頃(原生代) | 鉄イオンの酸化による鉄鉱床の生成が終わる。この頃、プレートテクトニクスにより最初の超大陸ヌーナが出現。 |
| 19億年前頃(原生代) | 遅くともこの頃までには、真核生物が現れたとされる。 |
| 18億5000万年前頃(原生代) | 現在のカナダ・サドベリー付近に直径10kmほどの小惑星が衝突。直径200~250kmほどのクレーターが生じる。 |
| 15億年前頃(原生代) | 18億年前からこの頃にかけて、超大陸コロンビアが存在していたとみられる。 |
| 12億年前頃(原生代) | この頃、陸上に微生物が進出し始めたとも考えられる。 |
| 12億年前頃(原生代) | この頃には多細胞生物が現れたものと思われる。エクタシアン期末の地層からは有性生殖をしていた藻類と見られる化石が見つかっている。 |
| 10億年前頃(原生代) | この頃、超大陸ロディニアが形成されたと考えられる。現在の南太平洋のあたりにあったと推測されている。 |
| 8億年前(原生代) | この頃、地球と月に大量の隕石が降ったという。地球近傍に近づいた直径100kmほどの天体が崩壊したため。 |
| 7億5000万年前(原生代) | ロディニア大陸が分裂。ゴンドワナ大陸、シベリア大陸、ローレンシア大陸などが形成。その前に再集結してパノティア大陸ができたという説もある。 |
| 7億4000万年前~6億3000万年前頃(原生代) | スターティアン氷期からマリノア氷期。地球全体が凍りつく最も激しい全球凍結時代だったとされている。生物の一部は深海や火山地帯で生き延びたと考えられる。この後の生命の大繁殖時代「カンブリア爆発」との関連も指摘されている。 |
| 6億年前~5億5000万年前頃(エディアカラン紀) | エディアカラ生物群が繁殖。軟体でしかも比較的大きな体格(数十cm程度)をした生物が多いのが特徴。 |
| 5億5000万年前(エディアカラン紀) | パノティア大陸が分裂し、ローレンシア大陸、バルティカ大陸、シベリア大陸が出現。 |
| 5億4500万年前頃(エディアカラン紀) | 生物の大量絶滅が起こる(V-C境界)。大規模な火山活動説、海洋無酸素事変説がある。 |
| 5億4200万年前~5億3000万年前頃(カンブリア紀) | この頃、多種多様な動物が出現。現在の動物のほぼすべての「動物門」が登場したとみられる。通称「カンブリア爆発」。目や殻(外骨格)を持つ生物が現れ始める。 |
| 5億2400万年前頃(カンブリア紀) | 最も初期の「広義の魚類」であるミロクンミンギアの生息していたと推定される年代。澄江動物群に見られる。 |
| 5億1800万年前頃(カンブリア紀) | 澄江動物群が繁殖。葉足動物や節足動物、古虫動物など、バージェス動物群と特徴がよく似ていて、種類も多い。 |
| 5億1800万年前頃(カンブリア紀) | シリウス・パセット動物群が繁殖。現在はグリーランドの北部に位置するが、当時は赤道近くに位置した。澄江動物群やバージェス動物群と共通点が多い。 |
| 5億800万年前頃(カンブリア紀) | バージェス動物群が繁殖。現在では類型が見られない動物も多数生息。ただこれらは原生動物の初期系統だとする説もある。1909年に古生物学者チャールズ・ウォルコットがロッキー山脈でバージェス頁岩を発見し、その後同地から多数の化石が採取されたことから付いた。 |
| 4億7900万年前(オルドビス紀) | この頃、六脚類が出現。昆虫や内顎類などの分類群。元々は多足類の一種と見られていたが、近年は甲殻類の一種と考えられている。 |
| 4億7000万年前(オルドビス紀) | この頃から徐々に陸上の湿地などに植物が広がり始めたと考えられる。 |
| 4億7000万年前(オルドビス紀) | この頃、カメロケラスが出現。非常に巨大な頭足類で、まっすぐの体をしたアンモナイトのような生物。6m~11mもあったとみられる。 |
| 4億4000万年前(オルドビス紀) | 生物の大量絶滅が起こる(O-S境界)。この期間にフデイシや三葉虫の一部など、動物の科の49%が絶滅する。超新星爆発によるガンマ線照射でオゾン層が破壊され、浅瀬に住む生物に影響したという説もあるほか、酸素の減少、海中の金属の含有率の増加説(酸素減少・火山噴火などによる)、さらに2度の絶滅期が短期的に起きた氷河期の発生時期と消滅時期に一致しているという。絶滅種の多さは史上2番めの規模だが、影響期間は短く、むしろその後、生物の多様性は広がっている。 |
| 4億4000万年前(オルドビス紀) | 分子系統学によれば昆虫はこの頃に現れたと考えられる。 |
| 4億3000万年前(シルル紀) | この頃から節足動物や植物の陸上進出が本格化する。この頃繁殖した植物の一つがクックソニア。 |
| 4億2000万年前(シルル紀) | ローレンシア大陸・バルティカ大陸・アバロニア大陸が衝突しユーラメリカ(オールドレッド)大陸となる。3大陸の間に広がっていたイアペトゥス海は消滅。 |
| 4億2000万年前(シルル紀) | この頃、現在のスコットランド・グレンコーにある火山が大規模なカルデラ噴火を起こす。 |
| 4億年前(デボン紀) | この頃から、陸上では昆虫が、水中では魚類が大幅に増加する。 |
| 3億8500万年前~3億6000万年前(デボン紀) | この頃、板皮類がほぼ世界中の海で繁栄する。魚類の一種で、顎に骨のある最初の脊椎動物。体を硬い骨板に覆われていた。最大のダンクルオステウスは4m~6mもあった。なぜかデボン紀のみの短期間で滅びた。 |
| 3億8000万年前(デボン紀) | 肉鰭綱のエウステノプテロンが繁殖。見た目は魚類だが、分厚い胸鰭と腹鰭の骨には指状のものがあり、この鰭で這うように、汽水域の浅瀬を、水生植物をかき分けて進むことができたと考えられている。手の原型と言える骨格や肺とエラの両方で呼吸できるなど、陸上動物の原型ともいえる。一方で陸上での重力から体を支えるような構造にはなっておらず、基本的には水中で生息していた。 |
| 3億7400万年前頃(デボン紀) | フラスニアン期とファメニアン期の境(F-F境界)で海洋生物の大絶滅が起こる。原因は不明だが、酸素濃度の低下が挙げられている。巨大隕石の衝突説、マントルプルームによる大噴火説のほか、大繁殖した植物の分解に伴う酸素の欠乏も指摘されている。隕石の方はスウェーデン中部にあるシリヤンリングクレーターが有力候補。生態系の回復に時間がかかっている。 |
| 3億6000万年前~3億5000万年前(デボン紀・石炭紀) | この頃、板皮類・無顎類・三葉虫のほとんどが絶滅する。 |
| 3億6000万年前~3億4500万年前(デボン紀・石炭紀) | この頃の地層からはその前後の地層に比べて化石の数が少なく、ローマーのギャップと呼ばれる。 |
| 3億1200万年前(石炭紀) | この頃、両生類から有羊膜類が分岐する。卵の中に羊膜が作られる種で、陸上での繁殖がよりしやすくなる要因の一つとなった。爬虫類・鳥類・哺乳類の共通先祖になる。 |
| 2億9000万年前(ペルム紀初期) | この頃、大気の酸素濃度が35%に達する。その為、動植物とも大型化したとみられる。 |
| 2億9000万年前(ペルム紀初期) | この頃より、地球や月に衝突する小天体の数が増加したという説もある。 |
| 2億9000万年前(ペルム紀初期) | 現在のカナダケベック州に2個の隕石が衝突。直径36kmと直径26kmの2つのクレーターを形成。クレーターは隣接しており、地球では珍しい双子クレーター。1個の小惑星が崩壊して2個になったか、衛星を連れた小惑星がそのまま衝突したものと考えられる。 |
| 2億6000万年前頃(ペルム紀中期) | テトラケラトプスが現れる。獣弓類と推測され、現哺乳類の最も古い先祖の一つ。 |
| 2億5160万年前(ペルム紀最末期) | この頃から以降の100万年で、海洋と陸上の生物の約95%が絶滅する。その約1000万年前のガダルピアン世末期の絶滅と共に「P-T境界の大量絶滅」と呼ばれる。他の絶滅期と異なり、生物種の回復までに非常に時間がかかっている。また、この頃より以降1億年に渡り、大気の酸素濃度が大きく低下した。マントルプルームによる大噴火で気候が変動したという説の他、隕石落下説もある(下記参照)。ちょうどこの頃、すべての大陸がつながり、超大陸パンゲアが出現している。 |
| 2億5000万年前(ペルム紀最末期) | 現在の南極ウィルクスランドの氷床の下に、直径480kmほどの重力異常地形があることが判明しており、これがクレーターである場合、2億5000万年前ころに直径50kmほどの小惑星が衝突した痕跡ではないかという説がある。これが「P-T境界の大量絶滅」を引き起こした要因ではないかとも考えられている。 |
| 2億2500万年前(三畳紀) | この頃、アデロバシレウスが出現。哺乳類の原型とも言える哺乳形類で最も古い種のひとつ。小型のネズミのような形状をしていた。卵生だったとみられる。 |
| 2億1600万年前(三畳紀) | この頃、コエロフィシスが出現。最初期の肉食恐竜。長さは長くて3mほど。脚が体の横側からでなく下側に出ているという恐竜の特徴を持っていた。 |
| 2億1400万年前(三畳紀) | 破砕した小惑星の破片が地球各地に降り注ぐ。現在でもカナダのマニクアガン・クレーターとセント・マーティン・クレーター、アメリカのレッド・ウィング・クレーター、フランスのロシュシュアール・クレーター、ウクライナのオボロン・クレーターなどがその痕跡と考えられている。小惑星は最大で直径8km弱、重さ5000億tほどあったとみられる。 |
| 2億130万年前頃(三畳紀最末期) | T-J境界の生物の大絶滅現象が起こる。中央大西洋マグマ分布域の火山活動の活発化、オスミウム層の存在から隕石の衝突などが原因とされている。陸上の方で先に起こり、海洋はあとから起きたと見られる。海洋生物の20%が滅んだほか、獣弓類、主竜類にも大きな影響を与えた。これ以降、絶滅期を生き延びた恐竜が繁栄していく。この大絶滅を境に地質学的にもジュラ紀へと移行する。 |
| 1億6000万年前頃(ジュラ紀) | この前後に大陸の乾燥化が急速に進み、生物の絶滅が起きたとされる。マントル内部などの要因で地殻が回転するように急に移動し、南へ25度移動したことが原因という説もある。 |
| 1億5000万年前頃(ジュラ紀) | アーケオプテリクス(いわゆる始祖鳥)が現れる。鳥類が恐竜から分かれたものかが論争になった生物。 |
| 1億4500万年前頃(ジュラ紀末) | この頃から地球最大の火山タム山塊が形成されていったと考えられる。 |
| 1億4200万年前頃(ジュラ紀末・白亜紀) | 現在のオーストラリア中央部に直径1~2kmほどの隕石が衝突。直径22kmほどのゴッシズ・ブラフ・クレーターを形成。現在は衝突でできたクレーターの中央丘部分だけが残っている。 |
| 1億4000万年前頃(白亜紀) | この頃、裸子植物から被子植物が分かれたと考えられる。 |
| 1億2000万年前頃(白亜紀) | この前後に、オントンジャワ海台を形成した巨大噴火が発生し、海中の酸素濃度が低下。魚竜や首長竜の一部(プリオサウルス)などの海棲爬虫類が絶滅したとみられる。 |
| 1億1600万年前頃(白亜紀) | アプティア中期の絶滅。ステゴサウルスなどの剣竜類はこの頃絶滅したとみられる。当時南インド洋にあったインド亜大陸で起きた大規模な火山活動によると考えられている。 |
| 9000万年前頃(白亜紀) | 絶滅が進行していた魚竜がこの頃までに完全絶滅。他の海洋生物でも多くが絶滅した。セノマニアン/チューロニアン境界の絶滅。主にマントルプルームによる大規模火山活動で起きた広範囲の海洋無酸素事変(OAE2/ボナレリイベント)が原因と考えられる。 |
| 8200万年前頃(白亜紀) | 現在のアラバマ州に長径300m以上の隕石が落下。直径6.5kmのウェタンカ・クレーターを形成。 |
| 7400万年前頃(白亜紀後期) | この頃までに翼竜の殆どは、非常に大型のケツァルコアトルスを除いて絶滅したものと思われる。 |
| 6800万年前頃(白亜紀末期) | この頃、ティラノサウルスが現れる。最も有名な恐竜だが生息期間は白亜紀の最末期マーストリヒチアンの時代のみ。 |
| 6600万年前頃?(白亜紀末期) | 現在のインド・ムンバイの西方海域に、直径40kmほどの小惑星が衝突し、シバクレーターを形成して、チクシュルーブ・クレーターの小惑星とともに恐竜絶滅のきっかけとなったという説がある(否定する説も有力)。 |
| 6600万年前頃(白亜紀末期) | 現在のユカタン半島の北部沿岸部付近に、秒速19kmほどの速度で、直径11~15kmほどの小惑星が衝突。チクシュルーブクレーターを形成。地球規模の災害を引き起こす。デカン高原の大火山噴火との関係を指摘する説もある(デカン高原の大噴火は隕石より数十万年早いという説もある)。年代は6604万年前頃で、ユリ植物の化石から6月に衝突したとする説が有力になってきている。数ヶ月から10年間、気温が大幅に低下する「衝突の冬」(インパクトウィンター)が発生したとみられる。 |
| 6600万年前頃(白亜紀末期) | K-Pg境界層の大絶滅。陸上の恐竜、翼竜、エナンティオルニス類などの鳥類、大型の哺乳類が絶滅。水生では、プランクトン、藻類、有孔虫の多く、二枚貝や腕足類の多くが絶滅し、淡水サメ、首長竜(プレシオサウルス)、モササウルス、アンモナイトは完全に絶滅した。一方で理由はわからないが、魚類、小型の爬虫類、小型の哺乳類、真鳥類は比較的生き残っており、その後大きく繁栄する。一部の恐竜は生き延びたとする説もある。またシダ植物もこの大絶滅期の直後に大繁殖しており、大地が荒廃していた可能性を示唆している。海洋の生態系回復に40万年、陸上の植生は回復までに150万年かかったという説も。大絶滅の要因として有力なのが、ユカタン半島に落ちた小惑星による大災害。 |
| 6000万年前(暁新世) | この前後に現れ繁栄したプレシアダピスが、霊長類の先祖とする説もある。 |
| 5500万年前(始新世) | この頃、一時的に温暖化が進む(始新世高温期)。 |
| 4500万年前(始新世) | この頃から、北上していたインド亜大陸がユーラシア大陸に衝突。浅いテチス海を押し上げるようにして隆起し、のちのヒマラヤ山脈が形成されていく。ヒマラヤ山脈は、今でも隆起し続けている。 |
| 4000万年前(始新世) | この頃、オーストラリア大陸と南極大陸が分離し、どちらもほぼ独立した大陸となる。 |
| 3900万年前(始新世) | 直径約2kmの隕石がデヴォン島に落下。直径23kmほどのホートン・インパクト・クレーターが生じる。デヴォン島はカナダの北極海クイーンエリザベス諸島にあり、風化や侵食が殆ど見られず、植生もないことから、衝突時の状態が保存されている。 |
| 3720万年前(始新世) | 現在のカナダのサドベリー付近にあるクレーターの端に隕石が落下。ワナピティクレーターが生じる。 |
| 3500万年前(始新世) | 現在のアメリカバージニア州チェサピーク湾口付近に、直径数kmの大型の隕石が落下。直径90kmのチェサピーク湾クレーターを生じる。ほぼ同時期に落下したポピガイ・クレーター隕石と共に気候変動を起こしたのではないかという説がある。両隕石が同じ天体から分裂したものかは不明。現在クレーター自体は海底に埋没している。 |
| 3500万年前(始新世) | 現在のロシア・シベリア中部アナバル地方に、直径数kmの大型の隕石が落下。直径100kmのポピガイ・クレーターを生じる。ほぼ同時期に落下したチェサピーク湾クレーター隕石とともに気候変動を起こしたのではないかという説がある。現在もクレーターは地表にあってほぼ原型をとどめており、地球上のクレーターでは4番目の大きさ。大量の衝突ダイアモンドが産出される。 |
| 2800万年前(中新世) | この頃、エジプト付近に隕石が衝突。古代エジプトの宝飾に使われたリビアングラスを生み出した要因だと見られている。 |
| 2700万年前(中新世) | 北アメリカのサンファン山脈ラ・ガリータ・カルデラが超巨大噴火。1980年のセントヘレンズ山噴火の5000倍規模。 |
| 2300万年前(中新世) | この頃、南極と南米大陸南端の陸橋が消滅し、南極周辺に南極環流が生じるようになる。このため、暖流が南極大陸へ到達しなくなり、南極は急速に寒冷化が進む。これ以前は、南極でも温暖な時代があり、植生のほか多様な動物が生息していたと考えられる。 |
| 1600万年前(中新世) | この頃までに、ヒト上科からヒト科とテナガザル科が分岐。 |
| 1500万年前(中新世) | 現在のドイツ・バイエルン州とバーデン=ヴュルテンベルク州に、直径1.5kmと150mの大小2つの小惑星がほぼ同時に落下。リースクレーターとシュタインハイムクレーターを生じる。クレーター間の距離はおよそ42km。2つの小惑星は、連星のような共通重心を回る二重小惑星だったとも言われている。 |
| 1500万年前(中新世) | この頃までに、南極大陸は現在のような氷床に覆われた状態となる。この氷床の重さで、地表は最大海面下2500mほどまで沈降している。 |
| 1400万年前(中新世) | この頃、ヒト科から、ヒト亜科とオランウータン亜科が分岐。 |
| 1100万年前(中新世) | この頃、哺乳類など15%ほどの生物が絶滅。原因は不明だが、現在の南鳥島近海の西太平洋に直径数kmの隕石が落ちたのが原因という説がある。 |
| 1000万年前(中新世) | この頃、ヒト亜科から、ヒト族とゴリラ属が分岐。 |
| 700万年前(中新世) | この頃、ヒト族から、ヒト亜族とチンパンジー亜族が分岐。大きな分類ではここでヒト(人類)のグループが誕生したことになる。 |
| 596万年前頃(中新世) | 地中海に蒸発岩が現れ始める。大西洋と断絶したことで、地中海の蒸発が進み、干上がり始めたためと考えられる。 |
| 580万年前頃(中新世) | 猿人アルディピテクス・カダッバが出現。 |
| 555万年前頃(中新世) | 地中海がかなりの範囲で干上がったとみられる。メッシニアン期塩分危機。 |
| 533万年前頃(中新世) | 地中海と大西洋がジブラルタルのところで再びつながり、大西洋の海水が地中海へと流れ込み始める。 |
| 440万年前頃(鮮新世) | 猿人アウストラロピテクス・アナメンシスが出現。 |
| 390万年前頃(鮮新世) | 猿人アウストラロピテクス・アファレンシスが出現。 |
| 360万年前頃(鮮新世) | この前後100万年の間に史上最大のサメ、メガロドンが絶滅。 |
| 350万年前頃(鮮新世) | 現在、銀河の中心から上下に広がるフェルミバブルという構造から、この頃、銀河の中心部で大規模な爆発現象が起きたと考えられている。 |
| 330万年前頃(鮮新世) | 猿人アウストラロピテクス・アフリカヌスが出現。ホモ(ヒト)属とパラントロプス属が分かれる直前の猿人。 |
| 300万年前頃(鮮新世) | この頃、パナマ地峡が出現して、南北両米大陸がつながる。それぞれの地域に生息していた生物が他方へと生息地を拡大する「アメリカ大陸間大交差」が起きた。 |
| 300万年前頃(鮮新世) | この頃、パラントロプス属の猿人が石器を使っていたという説がある。 |
| 260万年前頃(鮮新世) | 海洋生物の大量絶滅が起きる。 |
| 240万年前頃(更新世) | 最も古いヒト属であるホモ・ハビリスが出現。 |
| 215万年前頃(更新世) | 小惑星エルタニンが、南極大陸近海のベリングスハウゼン海に落下。直径が1km~4kmで、巨大津波が発生したと考えられる。 |
| 210万年前頃(更新世) | イエローストーン火山が超巨大噴火を引き起こす。2200から2450立方kmの噴出量があったとされる。 |
| 200万年前頃(更新世) | 猿人パラントロプス・エチオピクスが出現。 |
| 180万年前(更新世) | この頃ホモ・エレクトスが出現。二足歩行をしていたことが確実で、精巧な石器を作っていた。海岸沿いにアフリカとユーラシアに広がり、7万年前ころまでいたとされ、いくつもの種に分岐し、その一つがホモ・サピエンスへと進化した。 |
| 160万年前(更新世) | 旧称洪積世。氷河時代となる。海水面が下がり、陸地が広がる。 |
| 150万年前(更新世) | この頃、ホモ・エレクトスがユーラシア大陸沿岸部に広がる。 |
| 150万年前(更新世) | この頃の旧石器人の遺跡から火の痕跡、火を使わないと作れない土器の破片らしきものが見つかっているが、自然発火の可能性、あとから焼かれた可能性などもあり、確定ではない。 |
| 140万年前(更新世) | 現在のカナダ・ラブラドル半島の北西端に隕石が衝突。直径3.44kmの真円に近いピングアルイト・クレーター(ニューケベック・クレーター)が生じる。 |
| 130万年前(更新世) | イエローストーン火山が大噴火する。 |
| 100万年前(更新世) | 現在のガム星雲がその残骸とみられる超新星爆発が発生か。 |
| 100万年前(更新世) | 今のカザフスタンに隕石が落下。直径約14kmのザマンシンクレーターが生じる。 |
| 79万年前 | インドシナ半島に直径1kmほどの隕石が落下。直径が13~17kmのクレーターが出来たと見られる。 |
| 79万年前 | イスラエルのゲシャー遺跡で、この頃のホモ・エレクトスかホモ・エルガステルが火を使ったような痕跡がある。 |
| 70万年前 | 小御岳火山の噴火が始まる。現在の富士山の原型。愛鷹山と2つ並ぶように存在していたと見られる。 |
| 66万年前 | この頃から47万年前の間に、ホモ・サピエンスの原型となる原人がホモ・エレクトスから分岐したか。 |
| 65万年前 | 八甲田火山が大噴火。 |
| 64万年前 | イエローストーン火山が大噴火する。 |
| 52万年前 | 小林カルデラの大噴火。 |
| 40万年前 | ホモ・ハイデルベルゲンシス(ハイデルベルク人)が生存していた遅い推定年代。ネアンデルタール人より前のホモ属の原人だが、脳の容量はホモ・エレクトスよりは大きい。かなり大柄だったと見られる。 |
| 40万年前 | この頃、ホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人)が出現。ホモサピエンスとは別種の可能性が高いが、交雑が可能な近縁種でもあり、見た目はコーカソイドに似ているという説もある。中東からヨーロッパにかけて生息域を広げた。比較的高い技術を持ち、道具を作り、衣服を着用し、火炉もあった。壁画や装飾の痕跡もあり、屈葬するなど、宗教的な文化もあった可能性がある。一方で家族単位で暮らし、集団社会を形成せず、総人口も数万程度だったと考えられる。 |
| 40万年前 | 八甲田火山が大噴火。八甲田カルデラを形成。現在の八甲田山系はカルデラの縁にある。 |
| 33万年前 | 加久藤カルデラ噴火。現在の霧島山系はこのあとカルデラ南縁で噴火を繰り返し成長したとみられる。 |
| 30万年前頃 | 太陽系の比較的近傍で、現在のガンマ線源天体ゲミンガがその残骸とみられる超新星爆発が発生か。 |
| 現世人類出現以降 | |
| 25万年前頃 | 現生人類であるホモ・サピエンスが出現。ホモ・エレクトスの一種から分岐したものが、この頃までに進化したと思われる。アフリカで誕生したアフリカ単一起源説と、アフリカからユーラシア各地に生息域を広げたホモ・エレクトスが各地で同時期に進化していった多地域進化説に分かれる。 |
| 20万年前頃 | 中東地域ではホモ・エレクトスが絶滅。より進化したネアンデルタール人との生存競争に敗れたものか。他の地域でも、ネアンデルタール人やホモ・サピエンスに生息域を奪われていったものと思われる。 |
| 16万年前頃 | 東アフリカ沿岸部にホモ・サピエンス・イダルトゥが暮らしていたとされる年代。ホモ・サピエンスの一種で、現代人類(特にネグロイド)の直系の先祖と考えられる。 |
| 13万年前 | 現在、世界中で人に飼われているイエネコのミトコンドリア遺伝子の解析ではこの頃のリビヤヤマネコが先祖に当たるとされている。 |
| 12万5千年前 | ホモ・ローデシエンシス(ローデシア人)の生存していた最も遅い推定年代。ホモ・ハイデルベルゲンシスの一種とされる説も有力。現生人類の直接の先祖の可能性が高いホモ・サピエンス・イダルトゥの直接の先祖の可能性もある。虫歯の痕跡がある最も古い化石が出土している。 |
| 12万5千年前 | この頃、すでに人類は、日常的に火を使っていた見られる。 |
| 12万年前 | 屈斜路カルデラで大噴火が発生し、北海道の広範囲が火山灰で覆われる。 |
| 11万年前 | 阿多カルデラ噴火。 |
| 10万年前 | 小御岳火山のあとに古富士火山が噴火を始める。大量の噴出物で関東ローム層を作った。 |
| 9万年前 | 木曽御嶽山が大規模噴火。 |
| 9万年前 | 阿蘇カルデラで最大規模の噴火が起こる。約600立方kmの噴出量があり、九州の半分を火砕流が覆い、その先端は山口県に達する。降灰は北海道にまで到達。周辺地域に分厚い堆積台地を形成。 |
| 7万5000年前 | この頃、人類の遺伝子多様性が極度に減少。なにかの理由で現生人類であるホモ・サピエンスが千人から1万人程度にまで減少し、他のホモ属の人類(ホモ・エルガステル、ホモ・エレクトスなど)が滅びたためともいわれる。トバ火山の大噴火によると見られる気象変動が原因という説もある。現世人類が世界中へ広がり始めた理由にする説もある。 |
| 7万年前 | この頃、赤色矮星と褐色矮星の連星であるショルツ星系が太陽から約0.82光年の近傍を通過したとされる。 |
| 6万年前 | この頃、木曽御嶽山が噴火。摩利支天溶岩を流出する。 |
| 5万2000年前 | 現在のインド・ウッタル・プラデーシュ州に隕石が落下。直径1.2kmほどのロナール・クレーターを形成。現在も隕石湖となって残っている。 |
| 5万年前 | 現在のアメリカ・アリゾナ州に直径20~30mほどの小型の隕石(隕鉄)が衝突。直径1.2kmほどのクレーターが生じる。いわゆるバリンジャー隕石孔。 |
| 5万年前 | 現在の中国遼寧省鞍山市付近に隕石が衝突。直径1.8kmほどのクレーターが生じる。 |
| 4万5千年前 | この頃、倶多楽火山が繰り返し大規模噴火。倶多楽カルデラ(倶多楽湖)を形成。 |
| 4万年前 | 屈斜路カルデラで噴火が起こり、溶岩によって湖の南東部に円頂丘が生まれ、円形だった屈斜路湖は現在のようなそら豆状になる。 |
| 4万年前 | 支笏カルデラが形成される大噴火が起きる。 |
| 3万7000年前 | イタリア半島のカルデラ・フレグレイ平野で大規模な噴火が起こる(カンパニアン・イグニンブライト)。この噴火のほか、当時の南ヨーロッパなどで相次いだ噴火がネアンデルタール人を絶滅させたという説もある。 |
| 3万5000年前 | ルソン島の古期ピナトゥボ火山で大噴火が起こり、現在のピナトゥボ山の原型ができる。 |
| 2万9000年前 | この頃、姶良カルデラが短期間に二度も大爆発を起こす。一度目は妻屋火砕流を引き起こし、二度目は大規模な入戸火砕流を引き起こして、南九州一帯は噴出物に覆われ、関東平野にも10cmの降灰があった。 |
| 2万6500年前 | ニュージーランド北島のオルアヌイ火山が大噴火する。噴出量は1170立方km。 |
| 2万4000年前 | ネアンデルタール人のもっとも遅い絶滅推定年代。ジブラルタルなどイベリア半島の一部ではこの頃まで生存していたという説もある。ホモサピエンスの遺伝子には数%以上のネアンデルタール人由来の遺伝子があることから、広く交雑していたことは間違いないが、最終的に集団で生活し繁殖するホモサピエンスとの生存競争に破れた可能性が高い(ホモサピエンスとの交雑が進み、吸収消滅したという説もある)。 |
| 2万2000年前 | この頃から、姶良カルデラの一角に桜島が姿を現し始める。 |
| 2万年前 | 男体山が繰り返し噴火し、溶岩などによって湯川が堰き止められ中禅寺湖と戦場ヶ原のもととなった湖が形成される。 |
| 1万6000年前 | 浅間山が大噴火する。火山爆発指数VEI6。 |
| 1万5500年前 | 十和田火山が大噴火。大規模な火砕流が発生したと見られる。 |
| 1万5000年前 | 古富士火山の場所から新富士火山の噴火が始まる。山頂噴火も多く、現在の富士山へと成長。 |
| 1万5000年前 | 恵庭岳が大噴火。 |
| 1万2000年前前後 | この頃、ほ座超新星残骸のもとである超新星爆発が数百光年以内で発生か。 |
| 1万2900年前 | この頃、温暖化していた環境が急に寒冷化。ヤンガードリアス氷期に入る。温暖化に伴う氷床融解(特に当時世界最大の湖だった北米のアガシー湖からの流出)で起きた淡水の海洋流入が海流を変化させたのが原因という説、彗星もしくは隕石の北アメリカ大陸への落下もしくは空中爆発が原因という説もある。およそ1300年間続く。 |
| 1万2000年前 | この頃、インドネシアで起きた火山の大噴火によって、フロレス島にいた小型人類フローレス人(ホモ・フローレシエンシス)が絶滅したとみられる。身長1m程の原人で、新種かそれまで知られている原人の島嶼化(孤立した島でやや大型の動物が小型化していく現象)かはっきりしない。この頃すでに同島には現生人類も居住していたと考えられる。同じ頃、同島にいた象の近縁種であるステゴドンも滅びている。 |
| 1万1500年前 | 馬鹿洞人(ばろくどうじん)が生存していたとされる最も遅い推定年代。頭蓋骨の形が現生人類とかなり異なるため、新種の旧人の可能性もあるが、ホモサピエンスとデニソワ人の混血種、あるいはホモサピエンスの一種と考える説もある。広西チワン族自治区の老磨槽洞と、雲南省紅河ハニ族イ族自治州の黄家山馬鹿洞から化石が見つかっている。「赤鹿人」とも称される。 |
| 1万1000年前 | この頃にはすでに、メソポタミア西部ではライ麦を栽培する農業が始まっていたとみられる。ヤンガードリアス氷期の影響という説も。 |
| 1万前 | この頃までに、アメリカ大陸で繁栄していたネコ科のサーベルタイガーや、イヌ科のダイアウルフ、メガテリウム(オオナマケモノ)などの大型獣が滅んでいる。人間の進出による狩りで滅んだという説、気候と環境の変化による食糧不足説などがあるが、はっきりとはわかっていない。生息地についても草原説や森林説など諸説ある。同じ時代にすでにいたコヨーテなどは生き残った。 |
| 9500年前頃 | キプロス島ではこの頃、すでに猫を飼育していたことが遺跡で判明。 |
| 9000年前頃 | 中国の長江中流に彭頭山文化が、黄河流域に裴李崗文化が出現。どちらも農業を行い、土器を作っていたと見られる。 |
| 8200年前頃 | 世界最大の湖だった北米のアガシー湖(現在の五大湖とハドソン湾の間に広がっていた巨大氷河湖)が氷河の崩壊によって決壊しほぼ消滅。水の大半がハドソン湾を経て海へと流れ出たと考えられる。海面の上昇、海流の変化による寒冷化などを引き起こしたとされる。 |
| 8000年前 | この頃から5000年前ころまで、サハラ一帯の気候は湿潤化し砂漠が大きく減少していたとみられる。この後、乾燥化が再び始まり、それに伴い、ナイル川流域へ人々が移動し上下エジプト文明が発祥したとも言われる。 |
| 8000年前 | 燧ヶ岳が山体崩壊し、尾瀬沼が形成されていく。 |
| 7300年前 | 薩摩半島南方の海底にある鬼界カルデラが大噴火を起こす。海面まで噴出した火砕流が九州南部に到達し(幸屋火砕流)、東北にかけての広範囲に大量の火山灰が降る(アカホヤ火山灰)。薩摩大隅地方の縄文文明はこのとき滅亡したと考えられる。また、この火砕流に飲み込まれたため、屋久島の屋久杉はこれより古いものはない、という説が有力。現在、海底に超巨大溶岩ドームがあることがわかっている。 |
| 6000年前? | アラビア半島のルブアルハリ砂漠のワバールに隕石が落ちたという説がある。衝突年は1500年代ころ、19世紀後半という説もある。同地には複数のクレーターの他、ガラス質に溶けた鉱物や鉄なども見つかる。聖地メッカのカアバ神殿にある「黒石」はワバール隕石ではないかという説もある。 |
| 5900年前頃 | 三内丸山遺跡のある場所に縄文人が住むようになったと言われる。 |
| 有史以降 | |
| 紀元前5550年前頃 | |
| 温禰古丹島の黒石山幽仙湖カルデラで大規模な噴火が起きる。 | |
| 紀元前5500年頃 | |
| メソポタミアにウバイド文明が生まれる。 | |
| 紀元前5508年 | |
| ビザンチン歴(世界創造紀元)元年とされた年。988年に東ローマ帝国で導入されその滅亡まで使用された。天地創造神話をもとに作られた暦。 | |
| 紀元前5000年 | |
| 中国三峡付近に大渓文化が出現。環濠集落などを構成し陶器も生産していたとみられる。同じ頃、長江河口北岸から太湖付近一帯に馬家浜文化が、長江河口南岸付近に河姆渡文化も出現。狩猟や漁猟と稲作などの農業が混在したと考えられる。 | |
| 紀元前4860年頃 | |
| 北米西海岸近くの現在のオレゴン州にあるマザマ山が大噴火によって崩壊。山体上部にカルデラが形成され、その後水がたまりカルデラ湖となる。現在のクレーターレイク。 | |
| 紀元前4713年 | |
| 1月 1日 | ユリウス通日の起点となる日。1583年にグレゴリオ暦導入による換算の混乱に備えてスカリゲルによって考案された。ユリウス通日を使うと、新旧の暦の換算の他、特定の日の曜日や干支も計算で導き出せる。 |
| 紀元前3900年頃 | |
| メソポタミアに都市国家が生まれる。ウルク文化。 | |
| 紀元前3500年 | |
| ナイル川の中流域に上エジプト王朝が、ナイルデルタ地帯に下エジプト王朝が成立する。 | |
| この頃、長江下流域に良渚文化が出現。玉器や絹などを生産していたと見られる。夏王朝などとの関係を指摘する説もある。 | |
| この頃、人類は文字を使い始めたという説がある。 | |
| この頃、阿多カルデラの池田カルデラ火山が噴火。 | |
| 紀元前3200年頃 | |
| メソポタミアでウルク古拙文字が使われるようになる。最古の文字の一つ。 | |
| 紀元前3123年 | |
| 6月29日 | 古代メソポタミアの都市ニネヴェの遺跡で見つかったシュメールの粘土板にある記録から、この日、小惑星が大気圏に突入し、アルプス上空で四散、破片が地中海一帯に落ちたという説がある。旧約聖書にある「性的に乱れて神の怒りを買い、火と硫黄の雨によって滅ぼされたソドムとゴモラの町」の話に結びついたとも。 |
| 紀元前3100年頃 | |
| 上エジプト王朝のナルメル王が下エジプトも支配し統一王朝を立てる。エジプト第1王朝。後のギリシャ人歴史家ヘロドトスなどの記録ではエジプト第1王朝はメネス王によって始まったとされているが、遺跡から出土する遺物ではナルメルの記述しか見られないため、同一人物説もある。 | |
| 紀元前3000年頃 | |
| アナトリア西端のイリオス都市文明の始まり。 | |
| 長江中流域に屈家嶺文化が、黄河中下流域には龍山文化が出現。小規模の都市国家。陶器の生産、農業などが発達。 | |
| 紀元前2900年頃 | |
| エジプト第2王朝がこのころはじまる。最初の王はヘテプセケメイとみられる。 | |
| 紀元前2710年代頃 | |
| エジプト第2王朝セト・ペルイブセン王の時に、上下エジプトの間に内乱が起こる。 | |
| 紀元前2686年頃 | |
| エジプト第2王朝最後の王カセケムイが死去。内乱平定後30年ほど統治していたみられる。 | |
| カセケムイの娘ニマアトハピの夫サナクトが王位を継ぎ、エジプト第3王朝を開く。 | |
| 紀元前2668年 | |
| エジプト第3王朝2代目王ジョセル(ネチェルイリケト)が王位につく。大型の階段ピラミッドを最初に作った王。以後ピラミッドは大型化していく。 | |
| 紀元前2613年 | |
| エジプト第3王朝最後の王フニ王の息子であるスネフェルが異母妹ヘテプヘレスと結婚しエジプト第4王朝を開く。巨大ピラミッドが次々と建設された時代。 | |
| 紀元前2589年 | |
| スネフェルの子クフが第4王朝第2代王となる。最大のピラミッドを作ったファラオ。 | |
| 紀元前2566年 | |
| ジェドエフラーが第4王朝第3代王となる。巨大ピラミッドを作ったがほとんど破壊されている。在位期間がよくわかっていない。名前に太陽神ラーが最初に付いたファラオ。 | |
| 紀元前2558年? | |
| カフラーが第4王朝第4代王となる。ジェドエフラーの兄弟とみられる。2520年即位説も有力。スフィンクスとカフラー王のピラミッドを作ったファラオ(スフィンクスはもっと古いという説もある)。 | |
| 紀元前2532年? | |
| メンカウラーが第4王朝第5代王となる。クフ王、カフラー王のピラミッドに比べやや小ぶりのピラミッドを作る。 | |
| 紀元前2500年頃 | |
| この頃までに、メソポタミアのウルク古拙文字が絵文字から抽象化されて簡略化し、シュメール文字へと変化。その後、さらに簡略化が進み、楔形文字として周辺地方にも広まっていく。 | |
| 紀元前2500年頃 | |
| 長江中流域の石家河に城壁で囲まれた比較的規模の大きな都市が出現。一帯の集落を含めて石家河文化という。 | |
| 紀元前2498年 | |
| ウセルカフが第5王朝を興す。ジェドエフラーの孫で、メンカウラーの娘を妻にしている。ギザではなくアブシールに太陽の神殿を作ったファラオ。第5王朝はアブシールにピラミッドや太陽の神殿を作るが規模が小さく材質も粗雑。 | |
| 紀元前2345年頃 | |
| 第5王朝最後の王ウナス王の娘と考えられるイプト1世を妻にしたテティ1世が第6王朝を興す。古王国最後の王朝。この頃から地域を支配する州侯が勢力を拡大していく。 | |
| 紀元前2334年頃 | |
| メソポタミアの都市国家アッカドの王サルゴンが周辺地域も領有化していき、南東はペルシャ湾岸、北西は地中海に至るアッカド帝国を建国する。 | |
| 紀元前2180年頃 | |
| エジプト第6王朝が崩壊し、第7王朝が成立。しかし次の第8王朝も含めて短期間であり、州侯の力も拡大。エジプト第1中間期に入る。 | |
| 紀元前2160年頃 | |
| 上エジプトのヘウト・ネンネス侯メリイブラー・ケティが第9王朝を興す。実質統一王朝ではなく上エジプトの王朝。 | |
| 紀元前2130年頃 | |
| 上エジプトのヘウト・ネンネス侯政権を継ぐ第10王朝が成立したとみられるが詳細は不明。ほぼ同時にその南にテーベ侯の第11王朝も成立。両王朝は以後激しく争う。 | |
| 紀元前2115年頃 | |
| ウルク第5王朝の王ウトゥ・へガルの娘婿ウル・ナンムが、ウトゥ・ヘガルの死後、ウル第3王朝を興す。現存する最古の法典ウル・ナンム法典を制定した人物。 | |
| 紀元前2100年頃 | |
| 黄河中流域に都市国家が出現。二里頭文化。夏王朝との関係が指摘されている。 | |
| 紀元前2040年頃 | |
| 上エジプトのテーベ侯のメンチュヘテプ2世がエジプトを再統一。中王国時代に入る。 | |
| 紀元前2004年頃 | |
| エラムの軍勢がウルに侵攻してこれを破壊。ウル第3王朝が滅亡。ウルの最後の王イビ・シンはアンシャンへと連れ去られる。 | |
| 紀元前1991年頃 | |
| エジプト第11王朝最後の王メンチュヘテプ4世の宰相アメンエムハトと同一人物とみられるアメンエムハト1世が第12王朝を興す。 | |
| 紀元前1894年頃 | |
| スムアブムが都市国家バビロンの王となりバビロン第1王朝を興す。 | |
| 紀元前1792年頃 | |
| ハンムラビがバビロン第1王朝6代王となる。 | |
| 紀元前1782年頃 | |
| 第12王朝最後の王で女王のセベクネフェルの死後、大家令ヘテプイブラー・アアムサホルネジュヘルアンテフが王位を簒奪。さらにセベクヘテプ1世が王位につき第13王朝を興す。下エジプトが支配権から外れて独立(第14王朝)。第2中間期と呼ばれる時代になる。 | |
| 紀元前1757年頃 | |
| ハンムラビがシュメール、アッカドを含むメソポタミア地方を統一。 | |
| 紀元前1680年頃 | |
| アナトリア高原にヒッタイト王国が成立。 | |
| 紀元前1663年頃 | |
| 下エジプト地方でヒクソスと呼ばれた異民族(シリア方面から来た人々?)のサイテス王による第15王朝が成立。上エジプト系テーベの第17王朝が徐々に勢力を拡大しこれと争うようになる。また同時代に第15王朝影響下で同じヒクソスと見られる小規模の第16王朝も存在していたと考えられる。 | |
| 紀元前1628年頃 | |
| 地中海のサントリーニ島付近で海底火山の噴火が起こる。カルデラを形成。この大噴火により大津波が発生して各地を襲いミノア王国が滅ぶ。アトランティス伝説の元になったという説もある。 | |
| 紀元前1600年頃 | |
| この頃から黄河中流域に都市国家が勢力を拡大。二里岡文化。殷(商)王朝初期段階か。史記では夏王朝がこの頃、鳴条の戦いで、殷の湯王に滅ぼされたとされる。夏王朝の都と考えられている新鄭望京楼遺跡からは殺害された遺体も多数出土している。 | |
| 紀元前1595年 | |
| ヒッタイトの王ムルシリ1世が古バビロニア(バビロン第1王朝)を滅ぼす。カッシート人が勢力を拡大。 | |
| 紀元前1570年頃 | |
| 上エジプト系第17王朝カーメス王の弟であるイアフメス1世が下エジプトを滅ぼし、エジプトを統一。新王国時代最初の第18王朝を開く。 | |
| 紀元前1500年代頃 | |
| ミタンニ文明が興る。フルリ人がメソポタミア北方に興した国家。 | |
| 富士山の山頂噴火が終わり、山腹などからの噴火へ移行する。 | |
| 紀元前1479年頃 | |
| 第18王朝4代王トトメス2世の妻だったハトシェプストが女王となる。夫と側室の間の子トトメス3世が幼かったため実権を奪って君臨したとして批判される一方、安定した政権で統治を行いトトメス3世との関係も良かったという説もある。旧約聖書でモーセを拾って育てたファラオの王女を彼女だとする説もある。 | |
| 紀元前1475年頃 | |
| カッシート王国のウラム・ブリアシュがバビロン第2王朝を滅ぼしてメソポタミアを統一(バビロン第3王朝)。 | |
| 紀元前1450年前後頃 | |
| トゥドハリヤ1世がヒッタイト帝国の王位につく。これ以降をヒッタイト新王国時代と呼ぶ。即位年は諸説あり不明。 | |
| 紀元前1458年頃 | |
| 第18王朝5代王ハトシェプストが退位し、トトメス3世が第6代王として実権を握る。ハトシェプスト女王の事跡を抹消したと言われる。以降、第18王朝の絶頂期となる。 | |
| 紀元前1457年? | |
| メギドの戦い。第18王朝6代王トトメス3世がカナン連合軍と戦い勝利する。シリア南部がエジプトの影響下に置かれるようになる。記録に残る最古の戦争の一つ。 | |
| 紀元前1386年? | |
| 第18王朝9代王にアメンホテプ3世が即位。ルクソール神殿を作ったファラオ。 | |
| 紀元前1370年頃 | |
| ミケーネ文明によるクレタ島の支配が終わる。自然災害とも戦争とも言われる。 | |
| 紀元前1353年? | |
| 第18王朝10代王にアメンホテプ4世が即位。 | |
| 紀元前1343年? | |
| 第18王朝10代王アメンホテプ4世が、多神教であるアメンの神官らの勢力が強まったため、首都のテーベを捨て、唯一神アテンのための町アケトアテンを建設して遷都する。記録上に残る最初の唯一神信仰とも言われる。自らの名前もアクエンアテンと改める。 | |
| 紀元前1336年? | |
| スメンクカーラーが即位。正体のほとんど不明なファラオ。男性とみられるが女性のような偶像や女性用の棺になっているなど奇妙な点が多い。在位が短く記録も少ない。 | |
| 紀元前1333年? | |
| ツタンカーメン(トゥト・アンク・アメン)が即位。アメンホテプ4世とその同父同母姉妹の間の子。黄金のマスクで有名。記録は殆ど無い。病弱だが戦争を指揮したとも言われる。この代にアテン神からアメン神信仰に戻された(ツタンカーメンの名前の由来もアメン神)。実権は宰相アイ(アクエンアテンの王妃ネフェルティティの父親)と将軍ホルエムヘブ(後のファラオ)が握っていた。 | |
| 紀元前1330年頃 | |
| ヒッタイト帝国のシュッピルリウマ1世がミタンニを制圧する。 | |
| 紀元前1324年? | |
| ツタンカーメン(トゥト・アンク・アメン)が死去。遺体の損傷は激しく、また体の各所に生来の障害があり、また足の骨折が原因で死亡したとみられるが、事故か事件かは不明。宰相アイ(アクエンアテンの王妃ネフェルティティの父親)がツタンカーメンの王妃アンケセナーメンと結婚して王位継承権を得て即位(ケペルケペルウラー王)。この前後、エジプトの「ダハムンズ」からヒッタイトに対して王子を夫に迎えたいという縁談が持ち込まれる。ダハムンズ(王妃の意か)が誰かはわからないが、アンケセナーメン説もある。ヒッタイトから送られた王子ザンナンザが暗殺されたため、ヒッタイトの王子アルヌワンダがカナン方面へ軍事侵攻することになる。 | |
| 紀元前1323年? | |
| ケペルケペルウラー王(アイ)が死去。軍の司令官で王女ムトノメジットを妻にしていたホルエムヘブがナクトミンらを倒して王に即位。第18王朝最後のファラオ。 | |
| 紀元前1320年頃? | |
| ヒッタイト王シュッピルリウマ1世がエジプトとの戦争中に始まった疫病の大流行で死去。アルヌワンダが即位する。アルヌワンダもまもなく病死し、その弟のムルシリ2世が即位。 | |
| 紀元前1300年頃 | |
| 殷(商)王朝が殷墟に都を置く。史書では第19代王盤庚の時とされている。 | |
| 紀元前1295年 | |
| 第18王朝最後のファラオであるホルエムヘブ時代の軍司令官で宰相も務めた親友ラムセス1世が後継者に指名され即位。第19王朝を興す。共同統治者は息子のセティ1世。 | |
| 紀元前1294年 | |
| 高齢だった第19王朝初代ラムセス1世が死去。セティ1世が即位。領土を拡大し、エジプト美術を完成させたと言われるファラオ。 | |
| 紀元前1290年頃? | |
| セティ1世の子ラムセス2世が即位(年代は諸説あり)。66年間統治し、180人もの子がいたとも言われ、各地に遠征し、アブ・シンベル神殿など多数の神殿を作った。大王とも呼ばれる。 | |
| 紀元前1286年頃? | |
| エジプトのラムセス2世とヒッタイトのハットゥシリ3世が戦う。 | |
| 紀元前1274年? | |
| カデシュの戦い。エジプトのラムセス2世の軍がカデシュを攻略しようとしてヒッタイト帝国の罠にはまり敗北。その後、エジプト側の援軍が到着しヒッタイト軍は退却するが、両者の間で和平条約が結ばれた。記録上最古の和平条約。 | |
| 紀元前1208年 | |
| ペルイレルの戦い。第19王朝4代王メルエンプタハが、海の民と呼ばれる民族とリビア人がともにエジプトまで遠征してきたため、これと戦う。 | |
| 紀元前1200年前後 | |
| この頃、ヒッタイトやエジプトなど、東地中海沿岸の大国が軒並み滅亡や衰退する。その原因は不明だが、気象異変や大規模な噴火などの説もある。カナン地方(後のパレスチナ)では小規模の国家が多数成立。アイスランドのヘクラ火山の大噴火ではないかという説もある。 | |
| 紀元前1190年頃 | |
| ヒッタイトが滅亡。侵略を受けたという説もあるが、自滅崩壊したという説もある。最後の王はシュッピルリウマ2世。 | |
| 紀元前1185年 | |
| エジプト第19王朝最後のファラオで女王タウセルトのあと短期間の空位を経てセトナクトが即位。第20王朝が興される。セトナクトの正体はよくわかっていない。セトナクトはまもなく死去し、共同統治者で息子のラムセス3世が即位。 | |
| 紀元前1155年頃 | |
| 第20王朝のラムセス3世が喉を切られて暗殺される。王妃ティイが息子ペンタウアーを後継にするために計画し、多数の参画者がいたと言われる。裁判でほとんどが処刑された。ラムセス4世が王位を継ぐがエジプト文明はこれ以降衰退し始める。 | |
| 紀元前1141年 | |
| 第20王朝第4代ファラオのラムセス5世が天然痘で死去。ミイラの頭部に天然痘による痕跡があるため、天然痘に感染していたとわかる最も古い人物。 | |
| 紀元前1000年 | |
| ダビデがユダの王となる。後のイスラエル王。 | |
| この頃、箱根カルデラ中央の神山が噴火に伴い山体崩壊を起こし、大涌谷を形成。土砂で仙石原湖が埋まり、また早川の上流部を堰き止めて芦ノ湖ができる。 | |
| 紀元前961年 | |
| 古代イスラエルのダビデ王が死去。王位継承の争いを経てソロモンが跡を継ぐ。 | |
| 紀元前931年 | |
| 古代イスラエルのソロモン王が死去。神と契約して知恵を得たとされ、神と悪魔を使役した、動物と会話ができたなどの伝説がある人物。古代イスラエル王国最大の繁栄を築く。息子のレハブアムが跡を継ぐも王国は分裂の道を進むことになる。 | |
| 紀元前922年 | |
| イスラエル12支族のうち、レハブアムの政策に反発した10支族がヤロブアムを擁して、イスラエルはイスラエルとユダの南北に分裂。 | |
| 紀元前900年 | |
| この頃、西アフリカ・現ナイジェリアのジョス高原にノク文化が生まれる。土器・土偶の他、早くから製鉄技術を得ていたこともわかっている。 | |
| 紀元前900年 | |
| この頃、富士山で大規模な山体崩壊が起きる。古富士の残っていた山頂部分が崩壊か。 | |
| 紀元前800年 | |
| この頃、硫黄島で大規模な噴火があったと見られる。 | |
| 紀元前753年 | |
| 4月21日 | ロムルスが都市国家ローマを建設し、その初代王に即位。 |
| 紀元前721年 | |
| アッシリアがイスラエルに侵攻してこれを滅ぼす。部族指導者層が連れ去られたため、イスラエル民族の12支族のうちイスラエル王国を構成していた10支族はこれ以降消息不明となり、失われた十支族と呼ばれる。 | |
| 紀元前660年 | |
| 2月11日(神武天皇元年1月1日) | 「神武天皇の即位」。明治6年に天保暦から太陽暦へ変更される際に、記紀神話の記述から計算して都合をあわせたもので、グレゴリオ暦のこの年月日に即位したわけではなく、第2次大戦後は神武天皇の存在も否定的な説が主流。 |
| この頃、今のエストニアのサーレマー島に少なくとも9つの小隕石が落下。もっとも大きなクレーターは現在カーリ湖と呼ばれている。地元では神聖なる土地とみなされ、カレワラの叙事詩に異変を示唆するような神話が記述されている。 | |
| 紀元前624年 | |
| 南伝仏教では、この年に釈迦ことガウタマ・シッダールタがルンビニで生まれたとされる。ルンビニは現在のネパール最南部タライ平原にある村。シャーキヤ族の出自とされ、シャーキヤ族の聖者を意味するシャーキヤムニが音写されて、釈迦牟尼、釈迦となった。 | |
| 紀元前602年 | |
| 現在の天津付近にあった黄河河口の位置が南へと変遷する。黄河は黄土高原の大量の土砂を運ぶため、川底に堆積して洪水も多く、河道や河口の位置がしばしば変遷している。 | |
| 紀元前597年 | |
| 新バビロニア帝国の王ネブカドネザルがカナンの地に侵攻する。 | |
| 紀元前586年 | |
| 新バビロニア帝国の王ネブカドネザルがユダ王国を滅ぼし、ユダの指導者層ら多数が連れ去られる(バビロンの虜囚)。 | |
| 紀元前565年 | |
| 北伝仏教の一部では、この年に釈迦ことガウタマ・シッダールタがルンビニで生まれたとされる。 | |
| 紀元前551年 | |
| 9月28日 | 儒教の始祖、孔子こと孔丘が、魯国昌平郷陬邑に生まれる。 |
| 紀元前539年 | |
| 10月17日 | アケメネス朝ペルシャ王国の攻撃で、新バビロニア帝国が滅亡。ペルシャ王キュロス2世は、バビロンに移住させられていたユダヤ人やその他の諸民族を解放。 |
| 紀元前509年 | |
| 第7代ローマ王タルクイニウス・スペルブスが追放され、共和政ローマが成立する。 | |
| 紀元前490年 | |
| 9月12日 | マラトンの戦い。ペルシャ帝国と、ギリシャの都市国家アテナイとプラタイアの連合軍が戦い、連合軍が勝利。その報告を一人の兵士が、マラトンからアテナイまで走って伝えた伝説から、マラソン競技の元となった。 |
| 紀元前466年 | |
| 鳥海山で大規模な山体崩壊が発生。崩れ落ちた大量の土砂が沿岸に達して多数の島(流れ山)を形成。のちの「象潟」の原型となった。 | |
| 紀元前435年 | |
| アドリア海沿岸の植民都市エピダムノスの内紛を巡って、母都市ケルキラが調停の要請を無視したため、支援要請を受けたコリントスがこれに参入。それに対しケルキラがエピダムノス攻略を開始すると、コリントスもケルキラに宣戦を布告。ケルキラはアテナイに支援を要請。アテナイがこれを受けて参戦したことから、のちのペロポネソス戦争へと発展する。 | |
| 紀元前433年 | |
| シュボタの海戦。ケルキラの援軍要請を受けたアテナイの艦隊が出動したこと受け、コリントス側も同盟諸都市と艦隊を編成して派遣。両者はシュボタ諸島付近で交戦。数の多いコリントス側が圧倒するも、ケルキラ攻略は出来ず、両者痛み分けで退却する。 | |
| アテナイはデロス同盟国のポティダイアに圧力をかけて、コリントス勢力を排除しようと図る。ポティダイアはアテナイに反発しデロス同盟を離脱。アテナイはポティダイアへ兵を進め、コリントスも対抗して出兵。ポティダイアの戦いが始まる。スパルタが参戦するきっかけとなった。 | |
| 紀元前431年 | |
| スパルタがペロポネソス同盟軍を率いてアッティカに侵攻を開始。一方、アテナイは市民を城壁の内側へ退避させ籠城戦に入る。 | |
| 紀元前430年 | |
| この頃、アクラガス(現在のイタリア・シチリア島のアグリジェント)の哲学者だったエンペドクレスが神と一体となるため、エトナ山の火口に飛び込んで自殺したという伝承がある。 | |
| ポティダイアがアテナイに降伏し、ポティダイアの戦いが終結。 | |
| 紀元前429年 | |
| アテナイとスパルタの対立のさなかに、アテナイで疫病が流行。戦争を指導したアテナイの指導者ペリクレスも病死。多くの市民が死亡したと言われる。のちに「アテナイのペスト」と呼ばれるようになったが、ペストではなく、天然痘かチフスではないかと考えられている。 | |
| 紀元前425年 | |
| アテナイの指導者クレオンは、ペロポネソス同盟側からの講和に条件をつけて拒否。自ら軍を率いて戦い勝利する。 | |
| 紀元前423年 | |
| スファクテリアの戦い。アテナイの指導者クレオンは、スパルタに奪われていたアンフィポリス奪回のため出兵し、マケドニアに援軍を要請するが、単独での決戦を避けるために後退したところをスパルタのブラシダスの攻勢にあい戦死。ブラシダスも重症を負い、それがもとで死亡した。 | |
| 紀元前421年 | |
| ニキアスの和約。ペロポネソス戦争の終結を図るため、アテナイの穏健派ニキアスと、スパルタ王プレイストアナクスが、占領地の返還を条件に講和する。 | |
| 紀元前415年 | |
| アテナイが、シケリア遠征を行う。シケリアの各都市国家はアテナイと近かったが、唯一規模の大きな都市シュラクサイはスパルタと通じていた。ただアテナイの大規模で長距離の遠征を行った目的はよくわかっていない。 | |
| 紀元前414年 | |
| アテナイのシュラクサイ包囲がほぼ完成したところでスパルタとコリントス同盟から援軍が到着。スパルタ軍が城壁を築いて体制を整えたため、アテナイ遠征軍司令官の一人で遠征に消極的だったニキアスは退却を検討するも、アテナイ本国から援軍が到着。 | |
| 紀元前413年 | |
| スパルタ軍の攻勢でアテナイ軍は大敗を喫する。残ったアテナイ軍兵士は陸上を南下して脱出を試みるが失敗しスパルタとシュラクサイに対し降伏。しかし司令官のデモステネスとニキアスは処刑され、捕虜の殆ども疫病などで死亡し、アテナイ軍は文字通り全滅に終わった。アテナイは海軍戦力をほぼ失い、デロス同盟も事実上崩壊。 | |
| 紀元前405年 | |
| アイゴスポタモイの海戦。アイゴスポタモイ川河口でスパルタ率いるペロポネソス同盟軍艦隊が、アテナイ軍を撃破。黒海方面の制海権も奪われ、アテナイは食料輸入ルートを失う。 | |
| 紀元前404年 | |
| 4月25日 | 飢餓に追い込まれたアテナイがスパルタに降伏し、ペロポネソス戦争が終結。 |
| 紀元前399年 | |
| 4月27日 | アテナイのソクラテスが、無知の知を諭そうとして恨みを買い、「国家の信じない神々を導入し、青少年を堕落に導いた」として刑死する。処刑された理由に、アテナイの敗北を招いたアルキビアデスや、スパルタ支配下で成立した「三十人政権」の指導者となったクリティアスがソクラテスの弟子だったため、反感を買ったこともあるとされる。 |
| 紀元前387年 | |
| アッリアの戦い。ブレンヌス率いるガリア人セノネス族の軍勢がローマに侵攻。クイントゥス・スルピキウス率いるローマ軍は敗北し、はじめてローマが外敵に侵略された事件。記録では紀元前390年7月18日に起こったこととされているが、紀元前387年のことと考えられる。 | |
| 紀元前338年 | |
| 8月 2日 | カイロネイアの戦い。マケドニアとアテナイ・テーバイ連合との戦い。マケドニアのアレクサンドロス王子(後の大王)も軽装歩兵隊を率いて初陣。アテナイ・テーバイ連合は大敗を喫する。 |
| 紀元前336年 | |
| 10月 | マケドニア王ピリッポス2世が護衛をしていたオレスティスのパウサニアスに暗殺される。王位は20歳の息子アレクサンドロスが継ぐ。 |
| 紀元前334年 | |
| 5月 | グラニコス川の戦い。アレクサンドロス率いるマケドニア軍と、アルサメス、アルシテス、ミトリダテスらの率いるアケメネス朝ペルシア軍がグラニコス川で戦う。マケドニア軍が勝利し、小アジア征服へとつながっていく。 |
| 紀元前333年 | |
| 10月 | イッソスの戦い。アレクサンドロス率いるマケドニア軍3~4万と、ダレイオス3世率いるペルシア軍10万が激突。ダレイオス3世が途中で戦線を離脱して逃走したため、ペルシア軍は大敗を喫する。 |
| カナン地方がマケドニアのアレクサンドロスによって征服される。 | |
| 紀元前331年 | |
| 10月 1日 | ガウガメラの戦い。アレクサンドロス率いるマケドニア軍とダレイオス3世率いるアケメネス朝ペルシアの軍がティグリス川上流のガウガメラで激突。マケドニア軍が大勝し、ダレイオス3世は敗走。アレクサンドロスはバビロンへ入る。 |
| 紀元前330年 | |
| アケメネス朝ペルシアの王ダレイオス3世が、逃走先のバクトリアで総督のベッソスに殺害される。ペルシア王国滅亡。ベッソスはスピタメネスやオクシュアルテスらと同盟を結びペルシア王アルタクセルクセスを名乗る。 | |
| 紀元前329年 | |
| ペルシア王アルタクセルクセスを名乗っていたベッソスが捕らえられ、アレクサンドロス大王によって処刑される。 | |
| 紀元前327年 | |
| アレクサンドロス大王のインド遠征(~前324年)。 | |
| 紀元前323年 | |
| 6月10日 | アレクサンドロス大王死去。ハチに刺されたのが原因と言われる。 |
| 紀元前323年 | |
| アレクサンドロス大王の後継をめぐって有力者等によるディアドコイ戦争が起こる。以後約40年に渡り攻防を繰り返す。 | |
| 紀元前316年 | |
| (周慎靚王5年) | 秦が古蜀王国の内紛に乗じて蜀へ侵攻し、これを滅ぼして併呑する。 |
| 紀元前300年 | |
| この頃、富士山頂からの最後の大規模噴火が起きる。以降は側火山の噴火が中心となる。 | |
| 紀元前293年 | |
| 伊闕の戦い。秦が、同盟を結んだ韓・魏・東周の連合軍と戦う。連合軍は公孫喜が率い、秦軍は白起が率いる。秦軍が圧勝して、連合軍の将兵のほとんどである24万人を殺害。 | |
| 紀元前287年 | |
| 共和政ローマでホルテンシウス法が制定される。古くからのローマ市民のなかで貴族的な特権を持つ「パトリキ」と、それ以外の「プレブス(プレープス)」と呼ばれていた市民との間の法的平等を、独裁官クィントゥス・ホルテンシウスが定めたもの。これにより特にプレブス側から起こされていた身分闘争は終結。 | |
| 紀元前281年 | |
| セレウコス朝とリュシマコス朝によるコルペディオンの戦い。セレウコスが勝利。ディアドコイ戦争は終わり、アレクサンドロスの帝国の大半はセレウコス朝の支配下に置かれる。 | |
| 9月 | セレウコスがプトレマイオス・ケラウノスに暗殺される。プトレマイオスはマケドニア王を名乗る。一方、セレウコスの後は、息子のアンティオコス1世ソテルが継ぐ。 |
| 紀元前280年 | |
| 秦と楚の関係が悪化し、秦の司馬錯が軍を発して楚の黔中郡に攻め込む。 | |
| 紀元前279年 | |
| プトレマイオス・ケラウノスがガリア人との戦いで敗死。 | |
| 黽池の会。秦の昭襄王が趙の恵文王を招いて、秦の黽池で祝宴の会を行う。楚との全面戦争に向かっていた秦にとって趙と関係改善を図るのが目的だったが、一方で恵文王を格下として扱おうとしたため、趙の藺相如が機転を利かして恵文王を守ったという。 | |
| 秦の白起が大軍を率いて楚へ全面侵攻。鄧城を落とすと、つづいて鄢城へ進攻し、同城を水攻めにして陥落。そのまま西陵に進出。 | |
| 紀元前278年 | |
| 秦の白起が続けて、楚の領土を蹂躙。楚の都である郢を攻め落とす。 | |
| 楚が滅亡寸前まで追い込まれたことを悲嘆して、楚の政治家で詩人だった屈原が汨羅江に身を投じて自殺。 | |
| 紀元前277年 | |
| 秦と楚は休戦。両国の消耗戦は他の主要国を利するというのが理由。 | |
| 紀元前274年 | |
| 第一次シリア戦争がはじまる。エジプトのプトレマイオス2世とセレウコス朝アンティオコス1世との戦い。エジプトが勝利しシリア方面へ勢力を広げる。 | |
| 紀元前272年 | |
| 共和政ローマがイタリア半島の各都市国家を手中に収める。 | |
| 紀元前269年 | |
| 閼与の戦い。秦が公孫胡昜に命じて韓へ派兵。それに対し趙は、趙奢を指揮官として韓へ援軍を派遣。趙軍が圧勝する。 | |
| 紀元前262年 | |
| 秦が白起を派遣して、韓の野王を占領。韓の上党郡が孤立。韓では、上党を秦に割譲して和睦する派と、趙に割譲して共に秦と戦うという派に国論が二分。韓と趙で連合する方針に決まる。 | |
| 紀元前260年 | |
| 第二次シリア戦争がはじまる。エジプトのプトレマイオス2世とセレウコス朝アンティオコス2世との戦い。セレウコス朝が勝利し、再びフェニキアなどを支配下に収める。 | |
| 長平の戦い。韓と趙が連合したことを受けて、秦は王齕を趙へ派遣。趙は廉頗を迎撃に向かわせる。両軍は長平で衝突するが、秦軍が精強なのを見た廉頗は籠城戦による長期戦を企図。そこで秦の宰相范雎は趙の国内で廉頗を貶める噂を流し、それを真に受けた趙の孝成王は、廉頗を解任して、趙括を総司令官に任命。ここで秦は新たに白起を派遣。趙の名将趙奢の子で兵法家を自負する趙括は積極策に出たが大敗。長平に籠城するも食料が尽き、趙括は再出撃して戦死。20万の趙兵は降伏するが、食糧不足を理由に少年兵240人ほどを除いて全て殺されたと言う。范雎は、白起の名声と権力の増大を恐れ、韓・趙との和睦を図る。これにより白起との関係が悪化。 | |
| 紀元前259年 | |
| 贏政(後の始皇帝)が趙の国都邯鄲で生まれる。父親は秦の昭襄王の孫で、人質として趙に送られていた公子異人(子楚)、母親は呂不韋が寵愛していた趙姫とよばれる歌姫。 | |
| 紀元前258年 | |
| 秦が、将軍王陵を派遣して趙の国都である邯鄲を包囲。魏からは信陵君が独断で軍を動かして趙の援軍に駆けつける。秦から人質として送られていた子楚は呂不韋の手で秦に脱出し、趙姫と政の親子は匿われる。王陵は邯鄲を攻め落とすことができず、昭襄王は白起を起用しようとするが、白起はこれを受けず。代わりに王齕が派遣される。 | |
| 紀元前257年 | |
| 今のベトナム北部に甌雒国が建国される。都は古螺。古蜀王朝の王族出身だった蜀泮(開明泮)が文郎国を滅ぼして起こしたとされる。 | |
| 秦の名将白起が、昭襄王の不興を買い自殺に追い込まれる。白起の名声を恐れた宰相の范雎との不和がきっかけで、趙攻略戦における昭襄王と范雎の対応を白起が非難したため。巻き添えで白起の副将だった司馬靳も自害させられた。 | |
| 紀元前256年 | |
| 秦の昭襄王は、西周の文公が各国と合従して秦と敵対したことを受けて、楊摎に命じて西周を攻めさせ、文公は秦に降伏。これにともない文公を頼っていた周の赧王も秦の管轄下に置かれたが、まもなく死去。秦は周の都だった王畿(洛陽)を併合して九鼎(周の王権を象徴する宝物)を接収し、周王朝は事実上滅亡。なお、この時点ではまだ東周の昭文君が残っており、九鼎も確保していたという説もある。 | |
| 秦の昭襄王の宰相を務めた范雎が死去。権力の対抗者がいなくなったことを受けて引退し天寿を全うしたとも、恩人であるため推挙した王稽が他国と通じたために誅殺され、それに連座して殺されたとも言われる。 | |
| 紀元前251年 | |
| 50年に渡り秦王の地位にあり、秦を強大国に押し上げた昭襄王が死去。 | |
| 紀元前250年 | |
| 秦の昭襄王の子で、喪が明けて正式に秦王の地位に付いた孝文王がわずか3日で死去。呂不韋が支援した荘襄王が即位。 | |
| 紀元前249年 | |
| 東周が秦によって滅ぼされる。昭文君は呂不韋によって殺されたとも、命は救われ、周の祭祀を執り行うことを許されたとも言われる。東周の場所に秦の三川郡が設置される。 | |
| 紀元前247年 | |
| 河外の戦い。魏の公子信陵君(魏無忌)が率いる魏・趙・韓・燕・楚の合従軍が、秦に攻め込む。秦は大敗して函谷関まで後退する事態に追い込まれる。勝利した魏の安釐王と信陵君の兄弟は、その後、秦の工作によって関係が悪化し、信陵君は失意のまま前244年に病死。秦は勢いを盛り返すことになる。 | |
| 秦の荘襄王が死去。 | |
| 紀元前246年 | |
| 贏政が秦の王位を継ぐ。後見役として呂不韋が仲父の称号を与えられ、宰相として国政を担う。 | |
| セレウコス朝アンティオコス2世が、前妻のラオディケに暗殺される。後継に息子のセレウコス2世をつける。ラオディケはその前にアンティオコス2世の後妻でエジプト王プトレマイオス2世の娘ベレニケも暗殺しており、エジプトとの関係が悪化。第3次シリア戦争が始まる。 | |
| 紀元前240年 | |
| 5月 (秦王政7年) | 中国で彗星が目撃される。ハレー彗星か。 |
| この頃、エジプトのギリシャ人科学者エラトステネスが、ナイル川中流のシエネ(現在のアスワン)で、夏至の日に太陽が天頂に来ることを知り(北回帰線)、ナイル河口のアレクサンドリアで夏至の日に立てた鉛直の棒の影の角度から、両都市の緯度の差を計算。地球の50分の1であることを算出。両都市の距離から、地球の全周距離は250000スタディアと計算。スタディアの長さについては諸説ある。 | |
| 紀元前239年 | |
| (秦王政8年) | 秦王贏政の異母弟である成蟜が反乱を起こすも鎮圧される。 |
| (秦王政8年) | 秦王贏政の母である太后に仕える嫪毐が、長信侯に封じられ、山陽の地を与えられる。また嫪毐は自身の領地である太原郡の汾河以西を「毐国」と称する。 |
| 紀元前238年 | |
| (秦王政9年) | 贏政の母の太后と嫪毐の醜聞が発覚し、嫪毐は反乱を起こして咸陽へ攻め込むも、すでに備えていた嬴政側の昌平君と昌文君によって鎮圧され、嫪毐と、大后との間にできた2人の子、その一族が殺害される。嫪毐側の衛尉竭・内史肆・佐弋竭・中大夫令斉など20人も処刑され、4千家が爵位を剥奪されて蜀の房陵に移住させられる。大后も旧都の雍に移される。 |
| (秦王政9年) | 衍氏の戦い。秦の将軍の楊端和が魏の衍氏を攻略。秦による本格的な統一戦争が始まる直前にあった小規模の攻略戦。 |
| (秦王政9年) | 彗星が現れる。西から北の空に現れ北斗の南に80日間とどまる。 |
| (考烈王25年) | 楚の考烈王が死去。後を公子悍(幽王)が就く。その際、春申君が李園によって殺害される。考烈王の王后李環は李園の妹であったため権力闘争のためと見られるが、「史記」春申君列伝には、李環はかつて春申君に寵愛されており、生まれた子は王の子ではなく春申君の子であったため、その事を知る春申君を殺害したとも言う。 |
| 紀元前237年 | |
| (秦王政10年10月) | 秦の宰相の呂不韋が嫪毐の反乱に関与したとして相国を罷免されて領地の河南に蟄居となる。 |
| (秦王政10年) | 秦王政は桓齮を将軍とする。斉と趙が秦に使者を送る。その宴が開かれる。斉の茅焦は嬴政に対し「大王は母大后を追放すると噂されてます。これを聞けば諸侯は背くでしょう」と進言し、嬴政は大后を雍から都に呼び戻し甘泉宮に住まわせる。 |
| 紀元前236年 | |
| (秦王政11年) | 秦の王翦、桓齮、楊端和が、趙の将軍龐煖による燕への侵攻に乗じて、趙に侵攻。鄴と周辺の9城を攻略し、閼与と轑陽も攻略。通称「鄴の戦い」。秦の統一戦争の始まりとされる。 |
| 紀元前235年 | |
| (秦王政12年) | 秦の元宰相だった呂不韋が失脚後も各人と付き合い名声を保っていたことが贏政の警戒を招き、嬴政は詰問状を送って呂不韋に蜀への移住を命じる。呂不韋は将来を悲観し自殺する。一族と食客は蜀へ移住したと見られる。漢の武帝の時代に南越の相の呂嘉が益州に追放になった際に呂嘉が呂不韋の後裔だったため、追放先を呂不韋から「不韋県」としたとされ、三国時代の同地出身の呂凱は呂不韋の子孫と言われる。 |
| (秦王政12年) | 秦王政は呂不韋が自殺したことを受けて、蜀の房陵に流刑にしていた嫪毐の食客を赦免する。 |
| 紀元前234年 | |
| (秦王政13年 1月) | 彗星が現れる。 |
| (秦王政13年) | 秦の桓齮が、趙の平陽を攻撃し、趙軍は大敗を喫し、将軍扈輒は戦死する。通称「平陽の戦い」。秦王政は河南に巡行。 |
| 紀元前233年 | |
| (秦王政14年) | 秦の桓齮がふたたび趙に攻め込み、趙の宜安・平陽・武城を攻略。趙の王都邯鄲に迫ったため、趙の幽繆王は北方の匈奴を担当していた李牧を呼び戻す。 |
| (秦王政14年) | 趙の李牧率いる趙軍が、桓齮率いる秦軍を攻撃。秦軍は大敗を喫し退却。通称「肥下の戦い」。桓齮はこの戦いで敗死した説と敗走した説がある。 |
| (秦王政14年) | 韓王安が、秦に攻められたため、韓非を秦に送って和睦を図る。秦王政は韓非の著作を読んで気に入るが、李斯と姚賈の讒言に遭い、韓非は獄死する。 |
| 紀元前232年 | |
| (秦王政15年) | 秦軍が、鄴・太原を経由して狼孟と番吾を攻略。これに対し李牧が反撃、秦軍を撃破して、奪われていた領土を奪還。通称「番吾の戦い」。連続して李牧に敗れたことを受けて、秦は李牧を失脚させる工作を始めたと見られる。 |
| (秦王政15年) | この年、秦(?)で大きな地震が起きる。 |
| 紀元前231年 | |
| (秦王政16年 9月) | 秦は、韓の南陽を併合。 |
| (幽繆王5年) | 代で大地震があり、楽徐以西、北は平陰まで大きな被害を出す。 |
| 紀元前230年 | |
| (幽繆王6年) | 趙で大飢饉が起きる。 |
| (秦王政17年) | 秦の内史騰が韓を攻め滅ぼし、韓王安は捕らえられる。秦はここに潁川郡を設置。 |
| 紀元前229年 | |
| (秦王政18年) | 秦王政は、王翦・楊端和・羌瘣に趙を攻めさせ、趙都邯鄲を包囲。李信は別動軍を率いて太原へ侵攻。趙は李牧と司馬尚を迎撃に出すも、秦の工作を受けた郭開の讒言により李牧は殺され、司馬尚も解任される。趙は代わりに趙怱と斉將の顔聚を迎撃に出すも、趙怱は戦死し、顔聚は敗走。 |
| 紀元前228年 | |
| (秦王政19年) | 王翦と羌瘣の軍勢が東陽を攻略し、趙の幽繆王が捕虜となる。趙が滅亡。趙公子嘉が逃れて代王を称する。秦の軍勢はそのまま中山国へ侵攻。政は、出身地である邯鄲に入ると、母を貶めようとした人々を捕らえ生き埋めにする。 |
| (秦王政19年) | この年、中華の各地に飢饉が起こる。 |
| 紀元前227年 | |
| (秦王政20年) | 秦王贏政暗殺未遂事件。燕の太子丹が企図し、降伏の使者を装って贏政の前に現れた荊軻が贏政を刺殺しようとして失敗した事件。 |
| (秦王政20年) | 先の暗殺未遂事件を受けて、秦王政は王翦と辛勝に燕の攻略を命じる。 |
| 紀元前226年 | |
| (秦王政21年) | 秦王政、王賁に楚を攻めさせる。王翦には援兵を送り、燕の国都薊を攻め落とす。燕王喜と太子丹は遼東に逃走。降伏を望む燕王喜は反対する子の丹を殺すも秦王政はこれを許さず。 |
| (秦王政21年) | 燕の攻略後、秦王政は李信と王翦に楚の攻略に必要な兵数を問い、李信を採用したため、王翦は老病を理由に引退を表明。楚の公子であり秦王族の血も引く秦の相国だった昌平君が王翦引退を認めた秦王政を批判して失脚。 |
| 紀元前225年 | |
| (秦王政22年) | 秦王政が王賁に命じて、魏の国都大梁を水攻めにし、大梁は3ヶ月耐えたが城壁が崩壊。魏王假は降伏し魏は滅亡する。 |
| (秦王政22年) | 新鄭で旧韓の臣らによる反乱が起きる。これを受けて動揺が広がったため、昌平君を楚の旧都郢陳の民衆慰撫のため派遣。李信と蒙恬率いる20万の兵力による楚の攻略を開始。李信は平与を、蒙恬は寝丘を攻撃して勝利し、さらに李信は鄢と郢を攻略、城父で蒙恬と合流しようとしたが、三日三晩追撃してきた楚軍の攻撃を受けて7都尉を失う大敗を喫する。 |
| 紀元前224年 | |
| (秦王政23年) | 楚での敗戦を受けて、秦王政が引退していた王翦の元を訪れ、再登用して60万の兵を動員し楚の侵攻を命じる。王翦は楚に侵攻し、郢を攻略。楚王負芻を捕える(前223年説もある)。楚の将軍項燕は、秦・楚両王家の血を引く昌平君を楚王に擁立して淮南で抵抗を続ける。 |
| 紀元前223年 | |
| (秦王政24年) | 王翦と蒙武が率いる秦軍が楚を攻略。抵抗を続けていた公子昌平君と将軍項燕を殺害し(項燕は前224年に戦死という説もある)、楚は滅亡。 |
| アンティオコス3世がセレウコス朝の王となる。 | |
| 紀元前222年 | |
| (秦王政25年) | 李信と王賁率いる秦軍は燕の残存領土を攻め、燕王喜を捕らえ、燕を滅ぼす。広陽、上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東の6郡とする(広陽郡以外は燕の時代に設置された郡県制を踏襲)。 |
| (秦王政25年) | 王翦率いる秦軍は会稽に至り、百越(東越)を降伏させる。 |
| 紀元前221年 | |
| (秦王政26年) | 斉王田建は、宰相の后勝と諮り、西の国境に兵を送って封鎖。 |
| (秦王政26年) | 秦王政は、燕に駐留する王賁、李信、蒙恬に北から斉を攻めさせ、斉王田建は戦わずして降伏。 |
| (秦王政26年) | 秦王政は、六国を平らげたことから、丞相の王綰、御史大夫の馮劫、廷尉の李斯らと諮って、上古の三皇のうちの泰皇と五帝から、新たに皇帝の称号を作り、始皇帝と称する。また子が父に、臣が帝に、死後の諡を贈るのは良くないとして、以降は二世、三世と万世まで称するよう決める。 |
| 紀元前220年 | |
| アポロニアの戦い。セレウコス朝に反旗を翻し勢力を広げるメディア総督モロンに対しセレウコス王アンティオコス3世が行った遠征。モロンは敗れ自殺。モロンの兄弟でペルシス総督アレクサンドロスも自殺。 | |
| 紀元前219年 | |
| (始皇帝28年) | 始皇帝、第1回目の天下巡遊を行う。途中、泰山で封禅の儀式を行う。 |
| (始皇帝28年) | 秦の都咸陽の南、渭水を挟んだ対岸にある上林苑に、朝宮の前殿として阿房宮の建設が始まる。 |
| 紀元前218年 | |
| (始皇帝29年) | 始皇帝、第2回目の天下巡遊を行う。 |
| 紀元前217年 | |
| 6月22日 | ラフィアの戦い。セレウコス朝アンティオコス3世とプトレマイオス朝エジプトのプトレマイオス4世とのシリア領を巡る戦い。プトレマイオス朝側が勝利し領土を維持するが、被支配層だったエジプト人の力が強まることにもなる。 |
| 紀元前216年 | |
| 8月 2日 | 第二次ポエニ戦争・カンナエの戦い。カルタゴの将軍ハンニバルがローマ軍を包囲殲滅する。 |
| 紀元前215年 | |
| (始皇帝32年) | 始皇帝、第3回目の天下巡遊を行う。 |
| 紀元前214年 | |
| 8月 2日(始皇帝33年) | 秦が運河「霊渠」の開削工事を開始する。 |
| 紀元前213年 | |
| (始皇帝34年) | 秦に仕える儒者の淳于越が郡県制を否定し始皇帝の子息を各地の王にすべきだと進言したこと受けて、丞相の李斯が、挟書律を進言。始皇帝はこれを良しとして全国の郡に命じて、庶民が所有する四書六経(楽経を含む)や諸子百家の書物を没収して焚書させる。なお、生活に関わる医学書・農学書・卜筮(占い)書は除外とされた。 |
| 紀元前212年 | |
| (始皇帝35年) | 秦の始皇帝、学者・方士ら460人を生き埋めにする。いわゆる坑儒。不老不死の仙薬作りを命じられていた方士の盧生と侯生が、実際には仙薬を作れず、しかも始皇帝を誹謗して逃亡。激怒した始皇帝は同様の人物がいるか咸陽の学者・方士らを取り調べたところ、お互いの告発が相次ぎ、始皇帝は見せしめに彼らを処刑した。儒者が対象だったわけではなく、叔孫通のように引き続き始皇帝の顧問として残った儒者もいる。坑儒を諌めようとした皇太子の扶蘇は北方辺境の軍務を命じられたという。思想弾圧の言葉として焚書とまとめて呼ばれるが、焚書と坑儒は全く異なる事件。 |
| セレウコス王アンティオコス3世が東方遠征を開始。領土を拡大する。 | |
| 紀元前210年 | |
| (始皇帝37年) | 始皇帝、第4回目の天下巡遊を行う。巡遊中に平原津で病気に倒れる。 |
| 9月10日(始皇帝37年7月) | 始皇帝、巡遊の帰路、沙丘の平台で病死。趙高・李斯らの陰謀により始皇帝の末子胡亥が2代目皇帝として即位。皇太子だった扶蘇や他の皇子らは自害に追い込まれる。 |
| 紀元前209年 | |
| 陳勝呉広の乱が勃発。反乱が各地へ拡大。 | |
| 匈奴を大国家にした、記録上最初の単于である攣鞮頭曼(頭曼単于)が、息子の冒頓単于の謀反で殺害される。冒頓単于は後継者から外された上に月氏国へ人質に出され、その際に父親が月氏を攻撃して殺されかけたことから、反発していたと見られる。冒頓単于は、継母や異母弟らも殺害して王位を奪った。 | |
| 紀元前208年 | |
| 劉邦、沛公となり、泗水郡の秦軍と戦う。 | |
| 魏の周芾が、泗水・沛付近に侵攻し、胡陵・方与・豊などが降伏する。 | |
| 劉邦、碭を占領し、6千の兵を手に入れる。 | |
| 劉邦、項梁の軍勢に加わり、指揮官の一人となる。この頃、魏に奪われていた故郷の豊を奪還する。 | |
| 南越国の趙佗が、甌雒国を調略で分裂させた後、攻め滅ぼす。 | |
| 紀元前207年 | |
| 張良、景駒のもとへ向かう途上、留の町で劉邦と出会う。劉邦の度量の大きさに感銘し、そのまま劉邦の幕下に加わる。 | |
| 雍丘の戦い。秦軍を率いる三川郡守李由と、劉邦軍が衝突し、李由が敗死。 | |
| 定陶の戦い。秦軍を率いる章邯が定陶を攻撃。雍丘の戦いの勝利に油断していた項梁が敗死する。そのことを予測していた宋義が懐王の信任を受け楚軍のトップに立つ。 | |
| 鉅鹿の戦い。章邯と王離率いる秦軍は、秦からの独立を画策した趙を攻撃。章邯が首都邯鄲を攻める一方、王離らが趙王と張耳が逃げた鉅鹿を攻撃する。救援の要請を受けた楚軍の項羽は、時間稼ぎをする宋義を誅殺して卿子冠軍を吸収し、全軍を掌握すると英布を派遣。更に自ら出撃し、秦軍と交戦。秦軍は大敗を喫し、王離は捕虜となり、蘇角は戦死、渉間は自殺した。これにより項羽は反秦連合軍の事実上の盟主となる。 | |
| 章邯率いる秦軍が9度に渡り項羽率いる連合軍と交戦するが全て敗北し、司馬欣、董翳とともに項羽に降伏する。 | |
| 項羽、英布に命じて、投降した秦兵20万を、新安で坑(穴埋め)にして殺害。秦軍はここにほぼ壊滅する。 | |
| 劉邦の軍勢が武関を突破し、秦の中心地である関中へ進軍する。 | |
| 8月 | この頃、趙高が秦の二世皇帝胡亥の前で、鹿を馬と呼び、群臣の中で自分に味方する人間を探ったという(指鹿為馬)。 |
| 8月 | 秦の2世皇帝胡亥が宦官の趙高の指示で、趙高の娘婿の咸陽令閻楽に殺される(望夷宮の変)。 |
| 9月 | 趙高は子嬰を王に擁立するが、子嬰は病と称して出てこず。趙高は子嬰の見舞いに訪れたところ、子嬰は韓談とともに趙高を殺害。一族を滅ぼす。趙高は歴史上、悪宦官の代表的人物だが、閻楽という娘婿がおり、宦官ではないという説もある。 |
| 10月 | 劉邦が咸陽に攻め寄せ、子嬰は劉邦に降伏。劉邦は子嬰を殺さずにおく。なお子嬰については、始皇帝の長男扶蘇の子、胡亥の兄の子、扶蘇の弟で胡亥の兄、始皇帝の弟などの説があるが、はっきりしない。 |
| 紀元前206年 | |
| 項羽軍が函谷関を突破し関中へ侵入。先に首都咸陽を制圧し函谷関を閉じた劉邦の謀反の罪を問い、両者は項伯の仲介で鴻門の会を開く。劉邦は許される。 | |
| 項羽が、咸陽に進軍し秦王子嬰らを殺害。咸陽を焼き払い、秦が滅亡する。なお、阿房宮は焼失しなかったとみられる。 | |
| 項羽が秦への反乱軍に加わった諸将や旧六国の王族らを各地の王として封ずる。劉邦は漢王とされ、辺境の巴蜀漢中を領土として与えられる。この恩賞を受けられなかった各地の有力者や恩賞に不満を持つ王らが続出し、その後反乱や謀反が相次ぐことになる。項羽は主君筋の楚の懐王に義帝という称号を与えて辺境へ流し、九江王に封じた英布に命じて殺害。 | |
| 紀元前205年 | |
| (漢高祖2年) | 漢王劉邦が漢中から関中へと進出しこれを占拠。楚漢戦争が勃発する。 |
| (漢高祖2年4月) | 彭城の戦い。項羽が斉の攻略に手間取っているさなか、関中より出撃した劉邦に諸侯が集まり、総数56万の兵力で西楚の首都彭城になだれ込む。略奪に狂奔する連合軍に対し、項羽率いる3万が襲来。連合軍は大敗を喫し、10万人以上が殺害される。さらに睢水に追い詰められた10余万も殺害され、遺体は川をせき止めたという。 |
| (漢高祖2年8月) | 劉邦、韓信と張耳に魏を攻略させる。 |
| (漢高祖2年9月) | 井陘の戦い。韓信は張耳とともに趙を攻略するために出陣。対する趙の宰相陳余は、正攻法にこだわったうえ、韓信が「背水の陣」を敷いたことで油断し、城(王都?)を奪われる大敗を喫する。陳余は捕らえられ処刑。趙王歇も逃亡したが捕らえられて処刑された。 |
| 紀元前204年 | |
| 滎陽の戦い。彭城の戦いで大敗した劉邦は、九江王英布を寝返らせるが敗北。残兵を滎陽に集結する。項羽は滎陽を包囲。陳平が反間の計を用いて楚軍の君臣を離間させ項羽の軍師范増が失脚する。その上で囮を出して注意をそらし劉邦を関中へと逃がす。 | |
| (漢高祖3年6月) | 劉邦、再び関中より出撃し、宛・葉に進出。成皋へ軍を進める。この頃、彭越が下邳を攻撃。項羽、彭越軍に勝利したのち、滎陽を攻め落とす。漢の御史大夫周苛ら処刑される。さらに成皋を包囲。劉邦、成皋を脱出し韓信と張耳のいる趙の修武まで行く。ここで韓信の軍を奪い、韓信には斉攻略を命じる。 |
| プトレマイオス朝エジプトのプトレマイオス4世が死去。5歳のプトレマイオス5世が即位する。セレウコス朝アンティオコス3世は再びシリア方面への進出を再開。 | |
| 紀元前203年 | |
| (漢高祖4年) | 韓信、斉を制圧。濰水の戦いで楚の龍且を敗死させる。 |
| 成皋の戦い。項羽が彭越を討伐するため外黄攻略に向かった留守中に成皋で楚漢両軍が衝突。楚軍が大敗を喫し、曹咎・董翳・司馬欣ら自害。 | |
| 広武山の和睦。劉邦は広武山に陣取り、項羽と対峙。項羽との論戦中に劉邦は負傷。また食糧不足のため両者は領土を分割することで合意し和睦。楚軍は撤兵を開始。劉邦は張良・陳平の進言を受け、楚軍を攻撃するも失敗に終わる。 | |
| 固陵の戦い。劉邦は項羽軍を追い、韓信と彭越に出陣を要請して固陵に至るも、両軍は現れず敗北する。張良の献策で勝利すれば恩賞として広大な領地を約束することで両者に出兵を促す。韓信と彭越はこれを受けて出陣する。 | |
| 秦の南海郡尉だった趙佗が、秦王朝の滅亡を受けて南海郡、桂林郡、象郡などを領土として独立。南越と号する。その後は漢と交渉しながら領土を広げ、福建からベトナム北部までの広大な領地を支配した。趙佗は漢の景帝の代に100歳以上で死去したといわれる。 | |
| 紀元前202年 | |
| 垓下の戦い。項羽は劉邦を盟主とした韓信・彭越らの連合軍に敗れ、烏江に至りここで自刃。楚漢戦争が終結する。劉邦、項羽を弔う。 | |
| 2月28日 | 劉邦が皇帝に即位し、漢帝国が成立する。 |
| 10月19日 | ザマの戦い。第二次ポエニ戦争で、ローマとカルタゴが北アフリカのザマで衝突し、カルタゴが大敗を喫する。カルタゴは衰退していくことに。 |
| セレウコス朝がガザ方面へ侵攻。第5次シリア戦争が始まる。 | |
| 紀元前200年 | |
| (漢高祖7年) | 白登山の戦い。匈奴の冒頓単于が40万の兵力で太原に攻め込み、それを受けて、劉邦が自ら32万の兵力で迎撃に赴くが誘い込まれて大敗。劉邦は匈奴に毎年貢納することで和睦する結果となった。 |
| 紀元前198年 | |
| セレウコス朝がカナン地方を支配。 | |
| (漢高祖9年) | 劉邦の娘婿である趙王張敖の家臣貫高らが劉邦暗殺を企てたことが露見。貫高だけでなく張敖と劉邦の側室で元張敖の側室だった趙姫らも連座する。貫高の証言から張敖の罪は晴れるが、趙姫は呂后の嫉妬を受けて許されず、劉邦の子である劉長を産んで自殺。 |
| 紀元前196年 | |
| (漢高祖11年) | 春、淮陰侯韓信が鉅鹿太守の陳豨と反乱を計画。陳豨が挙兵するが、韓信の長安での挙兵は密告で露見し、蕭何の計略で捕らえられ一族ともども処刑される。陳豨も酈商に敗れ逃走。のち捕らえられ族誅となった。 |
| (漢高祖11年) | 梁王彭越が陳豨の反乱の際に出兵しなかったことで謀反の疑いをかけられ捕らえられる。一旦は蜀へ流罪とされたが、呂后の主張によって処刑される。 |
| (漢高祖11年) | 彭越の処刑を受けて疑心暗鬼となった淮南王英布が反乱を起こす。高祖劉邦自ら討伐に赴き激戦となるが、ついにこれを破る。英布、長沙王のもとへ逃走し、更に落ち延びようとして殺害される。 |
| (漢高祖11年) | 劉邦、英布討伐後、若い頃から暮らしていた沛に立ち寄り、「大風の歌」を披露。沛を永代免租とする。また沛の父老の訴えを受けて出身地である豊も同様の措置とする(豊の町はかつて劉邦を裏切ったことがあるため恨んでいたという)。 |
| 紀元前195年 | |
| (漢高祖12年) | 劉邦の幼馴染で、燕王であった盧綰が失脚。匈奴へ亡命する。盧綰の臣下だったとみられる衛満も千戸を率いて朝鮮に逃亡し、まもなく衛氏朝鮮を興す。 |
| (漢高祖12年 6月 1日) | 漢の高祖劉邦死去。 |
| 紀元前193年 | |
| 劉邦の覇業を支えた相国蕭何が死去。 | |
| 紀元前192年 | |
| セレウコス朝アンティオコス3世がテッサリア方面へ進出。 | |
| 紀元前191年 | |
| テルモピュライの戦い。テッサリアに進出したセレウコス朝に対し、ローマが遠征軍を送った戦い。セレウコス軍は敗北し撤退。 | |
| 紀元前190年 | |
| マグネシアの戦い。ローマ軍を率いるグナエウス・ドミティウスと、セレウコス王アンティオコス3世の軍勢が会戦し、セレウコスは大敗。 | |
| 紀元前188年 | |
| ローマとセレウコス朝との間でアパメイアの和約が結ばれる。セレウコス朝はタウロス以西の領土を失った他、ローマに多額の賠償金を払うことになり、軍事力も大幅に制限されることになった。 | |
| 紀元前187年 | |
| セレウコス朝アンティオコス3世が暗殺される。 | |
| (高后元年) | 漢の恵帝が「三族罪」と「妖言令」を廃止。三族罪は罪人の家族まで処刑する制度で、妖言令は世を惑わしたという理由だけで処罰するもの。どちらも権力者が恣意的に利用した悪法。この一時期だけ廃止されていたと見られる。宮廷では呂后が実権を握って劉氏との熾烈な権力闘争を引き起こし、息子の恵帝は傀儡とされるが、一方で対外戦争も内乱もなく、法も緩和されて、民衆には安寧の時代であったという。 |
| 紀元前186年 | |
| (高后2年) | 漢の高祖劉邦の名参謀として漢帝国創業を補佐した張良(張子房)が死去。知力で主君を支える「王佐の才」として中国史上では最も評価の高い人物。韓の宰相一家の出身で、太公望兵法を学んだという。建国後の重臣らの失脚が相次ぐ中でも疑われず、権力闘争を引き起こした呂后ですら張良の健康を案じて食を勧めたと言われる。 |
| 紀元前185年 | |
| (高后3年) | 中国の各地で河川が氾濫。 |
| 紀元前183年 | |
| 南越王の趙佗が、長沙国の数県を侵略。漢との交易をめぐる南越王と長沙王の紛争とみられる。 | |
| 紀元前181年 | |
| エジプトのプトレマイオス5世が暗殺される。治世下で周辺国の侵略や民衆の反乱が相次ぎ、プトレマイオス朝エジプトが衰退したときの君主。 | |
| 紀元前180年 | |
| 漢の高祖劉邦の妻で事実上女帝として君臨した呂后(呂雉)が死去。「史記」では歴代皇帝と同じ「紀」のカテゴリに含まれている。 | |
| 漢の斉王劉肥の次男である朱虚侯劉章が、兄の斉王劉襄、元勲の周勃・陳平らと図りクーデターを起こす。呂一族が滅ぼされる。 | |
| 代王劉恒が5代皇帝として周勃・陳平らに擁立され即位。文帝。劉恒は生存している劉邦の子で最年長であり、母親の薄氏が没落した旧魏王族の娘と薄姓の男性との間に生まれており、外戚の力が弱いとして選ばれたと言われる。一方でクーデターの首謀者である劉章は城陽王にされた。 | |
| 紀元前178年 | |
| (文帝前2年) | 陳平が死去。漢の高祖劉邦の軍師として策謀を担い、呂后の死後、呂氏一族の専横を排除して帝国の命脈を伸ばした人物。 |
| 紀元前177年 | |
| (文帝前3年) | 匈奴が漢の領土へ侵入。灌嬰が騎兵8万5千を率いて迎撃に出陣、文帝も太原まで親征を計画。しかし匈奴はその前に撤退。 |
| 済北王劉興居が匈奴侵攻に便乗して謀反を起こす。しかし柴武が討伐軍を率いこれを撃破。劉興居は捕らえられ自殺。先に呂氏を滅ぼした際の、皇位継承も絡んだ内紛で恩賞が得られなかったことが原因とみられる。 | |
| 淮南王劉長が長安に赴いた際に、審食其を襲撃して殺害する。貫高の皇帝暗殺未遂事件に連座した母趙姫の助命嘆願を審食其がまともに取り上げず、自殺に至った恨みから。 | |
| 紀元前174年 | |
| (文帝前6年) | 淮南王劉長が、柴奇らと反乱を計画し露見。文帝は死罪相当の意見を退け、劉長を蜀に流罪とするが、劉長は食を絶って自殺。 |
| 紀元前171年 | |
| 共和政ローマとマケドニアのペルセウスとの間で第三次マケドニア戦争勃発。 | |
| 紀元前168年 | |
| 6月22日 | ピュドナの戦い。ローマ側が勝利し、マケドニアのペルセウスは敗走。ローマのアエミリウスに降伏して第三次マケドニア戦争も終結。アンティゴノス朝マケドニア崩壊。 |
| 紀元前167年 | |
| エルサレムを占領したセレウコス朝に対するユダヤ人の反乱が勃発。安息日でも戦うことを示して反乱を起こしたユダヤの祭司マタティアの息子で、後継者として乱を指導したユダ・マカバイの名を取って「マカバイ戦争」という。マカバイは西欧では「九偉人」の一人。 | |
| 紀元前166年 | |
| 匈奴の老上単于(攣鞮稽粥)が14万騎を率いて漢の朝那・蕭関に侵攻し、彭陽まで攻略。漢の文帝は盧卿を上郡将軍、魏遫を北地将軍、周竈を隴西将軍、張相如を大将軍、董赤を前将軍に任じて討伐軍を派遣。老上単于は1ヶ月ほどして引き上げる。 | |
| 紀元前164年 | |
| (文帝16年) | 漢王朝で「人主延寿」の文字が彫られた玉杯が現れる。 |
| 紀元前163年 | |
| (文帝後元年) | 瑞兆をうけて文帝は新たに元年と定める。 |
| 紀元前157年 | |
| 7月 6日(文帝後7年 6月 1日) | 漢の文帝が崩御。重農主義で、戦争を極力回避し、土木を行わず、減税や刑罰を軽くするなどの政策で戦乱時代からの民力休養を図った。安寧で豊かな時代だったことから次の景帝と合わせて文景の治と呼ばれる。また母親(薄太后)への孝行から、二十四孝の一人に数えられる。 |
| 7月14日(文帝後7年 6月 9日) | 漢の文帝の5男劉啓が即位。景帝。 |
| 紀元前154年 | |
| (景帝3年) | 呉楚七国の乱が勃発。漢の西半分を直轄する皇帝政府に対し、東半分を支配していた劉氏諸王(呉王劉濞・楚王劉戊・趙王劉遂・膠西王劉卬・膠東王劉雄渠・菑川王劉賢・済南王劉辟光)が挙兵。直接的には呉王劉濞が、息子を皇太子時代の景帝に殺されたことと、景帝が晁錯の「中央集権化」の進言に従い呉王ら諸王の領土減封を図ろうとしたため。景帝は反乱鎮圧のため周亜夫を抜擢。 |
| (景帝3年) | 呉楚七国の乱が終結。景帝は大尉の周亜夫を抜擢して鎮圧軍の指揮を命じる。周亜夫は劇孟や鄧都尉らと協議し、呉軍とは直接戦わず、昌邑に城塞を築いて軍を集め、呉軍が梁を攻めている間にその補給線を断つ。窮した呉軍が昌邑に攻めてきたのを撃破。呉王劉濞は東越に敗走するが、すでに中央政府へ味方していた東越は呉王を殺害。また首謀者の一人である膠西王劉卬も斉の攻略に失敗後、遠征軍指揮官の頽当のもとに出頭して降伏し自決。他の王も自決し、反乱はわずか3ヶ月で鎮圧することに成功。 |
| 紀元前148年 | |
| 第四次マケドニア戦争勃発。マケドニア王国の後継者を称するアンドリスコスが共和政ローマに対し反乱を起こすがローマに敗れる。ファランクスが使われた最後の戦争とも言われる。 | |
| 紀元前142年 | |
| セレウコス朝の勢力が後退し、マカバイ戦争は終結。ユダヤ人が事実上の独立を果たす(ハスモン朝の成立)。 | |
| 紀元前141年 | |
| 3月 9日 | 武帝が前漢の第7代皇帝に即位。 |
| 紀元前132年 | |
| (元光3年) | 黄河下流の濮陽付近で南側の堤防が決壊し、大量の水が南の淮河方面へと氾濫。甚大な被害をもたらす。 |
| 紀元前120年 | |
| (元狩3年) | 武帝、財政再建のため、桑弘羊、孔僅らに塩鉄酒の専売制を実施させる。 |
| 紀元前119年 | |
| (元狩4年) | 武帝、匈奴の本拠を攻める。大将軍衛青と驃騎将軍で衛青の甥の霍去病をともに司令官として、前将軍李広、左将軍公孫賀、右将軍趙食其、後将軍曹襄らに騎兵10万、歩兵ら数十万を派遣。漠北の戦いで漢軍が大勝する。 |
| 紀元前110年 | |
| (元封1年) | 司馬談が死去し、その事業を司馬遷が受け継ぐ。 |
| 紀元前109年 | |
| (元封2年) | 武帝が衛氏朝鮮の王衛右渠討伐を命じる。 |
| 紀元前108年 | |
| (元封3年) | 衛氏朝鮮が滅び、遼東半島から朝鮮中部にかけて楽浪郡・真番郡・臨屯郡・玄菟郡が設置される。古朝鮮の時代が終わる。 |
| (元封3年) | この年、司馬遷が太史令となる。 |
| 紀元前104年 | |
| (太初1年) | 司馬遷、壺遂ら学者数十名によって、太初暦が制定される。司馬遷、この頃より『史記(太史公書)』の編纂を開始。 |
| 紀元前99年 | |
| (天漢2年) | 武帝、匈奴討伐の遠征を命じる。別軍を率いた李陵が寡兵で善戦するも敗北し捕らえられて匈奴に降伏する。武帝はこれに激怒。司馬遷は李陵を擁護したため、投獄される。 |
| 紀元前98年 | |
| (天漢3年) | 武帝のもとに、李陵が匈奴の兵に軍略を教えている誤報が届き(実際には李緒がしていた)、武帝は李陵の一族を処刑。司馬遷も宮刑に処せられる。 |
| 紀元前96年 | |
| (太始1年) | 司馬遷、釈放され中書令に任ぜられる。皇帝の詔書を扱う高官だが宦官が付く官職。 |
| 紀元前91年 | |
| (征和2年) | 巫蠱の獄が起こる。武帝の側近となっていた江充が、恨みを買った皇太子劉拠を陥れるため、呪詛を行っていると告発。劉拠は江充を捕らえて殺害するも、これにより武帝が劉拠の謀反を信じ、宰相劉屈釐に討伐を命じる。劉拠は敗北し、逃走先の湖県で自殺。一族や関係者も処刑される。しかしこれが江充の陰謀だと判明。武帝は江充の一族や関係者を処刑し、死んだ皇太子のために思子宮を建てた。 |
| 紀元前90年 | |
| (征和3年) | 匈奴討伐のため、李広利が出撃する。 |
| (征和3年) | 郭穰によって宰相劉屈釐らが武帝を呪詛していると告発され、一族とも処刑される。縁者である李広利の妻子も連座。それを遠征先で知った李広利は匈奴に降伏。 |
| (征和3年) | この年、司馬遷『史記』を完成する。 |
| 紀元前87年 | |
| (後元2年 3月30日) | 漢の武帝死去。劉弗陵が即位(昭帝)。8歳であったため、政治は大司馬・大将軍の霍光、太僕・左将軍の上官桀、車騎将軍で匈奴の王子でもあった金日磾の3人が担当し、丞相の田千秋がこれを補佐する体制となる。 |
| 紀元前86年 | |
| 昭帝の補佐役だった金日磾が死去。霍光と上官桀の両者が徐々に対立を深める。 | |
| 紀元前81年 | |
| (始元6年) | 漢の朝廷において、有識者60人を召集し、桑弘羊の推進した塩鉄専売の是非を問う論争(塩鉄会議・塩鉄論)を行う。専売制は批判を受け、酒の専売制度が廃止されるが、財政逼迫のため塩と鉄は専売制が継続する。 |
| 紀元前80年 | |
| (元鳳1年) | 上官桀、燕王劉旦、御史大夫桑弘羊が反乱を企て失敗に終わる。上官皇后以外の関係者すべて処刑される(上官皇后は上官桀の子上官安と霍光の娘との間にできた子でまだ8歳)。 |
| 紀元前75年 | |
| 1月10日 | 漢の朝鮮半島北部にあった植民行政区の一つ「玄菟郡」が廃止される。 |
| ローマとポントスとの間で第三次ミトリダテス戦争が勃発。 | |
| 紀元前74年 | |
| 漢の昭帝が急死したため、霍光によって劉賀が皇帝となる。しかし行いに問題があるとして、在位27日で廃位され海昏侯に落とされる。劉賀の臣下らが処罰されたことから、政変説もある。 | |
| 霍光に擁立され劉病已(劉詢)が皇帝となる(宣帝)。巫蠱の獄で自殺した劉拠の子で、親族がすべて誅殺された際に、当時獄吏だった丙吉(後の宰相)に助けられ、獄中で養育されたのち、民間で育った異色の皇帝。 | |
| 紀元前68年 | |
| (地節2年) | 漢の大権力者であった霍光が死去。宣帝は領尚書事を通さない封事を直接上奏することを認め、権力者霍一族の実態を知ることになる。 |
| 紀元前66年 | |
| (地節4年) | 霍禹らが反乱を企てたが露見し、一族及び関係する数千家が誅殺。霍皇后も廃され幽閉される。 |
| 紀元前65年 | |
| 第三次ミトリダテス戦争でローマが勝利し、ポンペイウスは各地へ領域を拡大。 | |
| 紀元前64年 | |
| ポンペイウスがシリアを占領し、ハスモン朝を事実上属国化する。 | |
| 紀元前57年 | |
| 新羅六部の村が赫居世居西干を王に擁立。新羅の建国とされる。神話上の話であるため、史実では辰韓十二国のひとつ斯蘆国を原点とする小規模国家から発展したものと考えられる。 | |
| サビス川の戦い。ガリア遠征に来たカエサル率いるローマ軍と、ベルガエ人系ネルウィ族のボドゥオグナトゥスらの率いるガリア人勢力との戦い。ネルウィ族らは大敗して降伏。 | |
| 紀元前55年 | |
| 8月23日 | ガリア遠征中のカエサルが、ブリタンニアに遠征。ブリタンニアがガリアと協力関係にあったため。遠征隊はホワイトクリフ一帯に上陸したが、ブリタンニア側の反撃もあり、ケント地方の海岸地帯付近にとどまったのみで冬になり撤退。 |
| 紀元前54年 | |
| ガリア遠征中のカエサルが、ふたたびブリタンニアに遠征。5個軍団、800隻の船を動員する大規模な遠征となった。ブリタンニア側はカッシウェッラウヌスが中心となって反撃したが敗れ、ガリアのアトレバテス族の王コンミウスを通じて和睦。カエサルも同地を維持する兵を置くこともなく撤退した。 | |
| アドゥアトゥカの戦い。ブリタンニア遠征から帰還後、ガリアに分散して冬営したローマ軍のうち、第14軍団をエブロネス族の王アンビオリクスらが攻撃。一旦は和睦するも、罠にはめてこれを壊滅する。ガリア遠征中、ローマ軍で最大の敗北となった。 | |
| 紀元前52年 | |
| アルウェルニ族のウェルキンゲトリクスが、全ガリア諸部族に呼びかけ、ローマに反乱を起こす。 | |
| アウァリクムの戦い。ウェルキンゲトリクスは、ローマ軍への補給を断つため、焦土作戦を展開し、主要拠点を除く町や村を焼き払うが、ビドゥリゲス族の城塞都市であったアウァリクムはそのままにしていたため、カエサル率いるローマ軍の攻撃を受ける。カエサルは25日かけて攻城塔を建設し、城壁を攻撃占拠。さらに城内のガリア軍の混乱に乗じて城内へ攻め込み、市民約4万人を殺戮、助かったのは逃れた800人だけだったと言われる。 | |
| ゲルゴウィアの戦い。アウァリクムを攻略したカエサルは、アルウェルニ族の城塞都市ゲルゴウィアの攻略にも取り掛かる。しかしローマ側についていたハエドゥイ族のコンウィクトリタウィス、リタウィックスらがウェルキンゲトリクスについたことや、ゲルゴウィアの攻略に失敗したため撤退。しかし追撃に来たウェルキンゲトリクスのガリア軍に反撃してこれを破る。 | |
| 8月 | アレシアの戦い。ウェルキンゲトリクス率いるガリア軍のこもるアレシアをローマ軍が大規模陣地を構築して包囲。 |
| 10月 2日 | アレシアの戦い。ウェルカッシウェラウヌス率いるアレシア救援のガリア軍が、ローマの攻囲陣地の一角を攻撃。アレシアからも出撃し、はじめはガリア軍が優勢に進めていたが、カエサルの反撃によって壊滅。ウェルキンゲトリクスはカエサルの前に進み出て降伏。ガリアはほぼ平定され、カエサルの事実上支配するところとなり、カエサルの勢力拡大に繋がった。 |
| 紀元前49年 | |
| 1月10日 | カエサルが、彼の勢力を恐れる元老院の召還命令に逆らい、「賽は投げられた」として、麾下の軍勢を率いてルビコン川を渡り、ローマ帝国本土へ侵攻する。 |
| 紀元前47年 | |
| 8月 2日 | ゼラの戦い。ボスポロス王国の国王ファルナケス2世とローマのガイウス・ユリウス・カエサルが戦い、カエサルが勝利。「来た、見た、勝った(Veni vidi vici:ウェーニー・ウィーディー・ウィーキー)」の言葉で有名。 |
| 紀元前46年 | |
| 古代ローマにおけるローマ暦最後の年。ガイウス・ユリウス・カエサルが改暦を行ったため、以降はユリウス暦となった。現在の9月、10月、11月、12月の英語名(September,October,November,December)がラテン語の第7、第8、第9、第10を意味するのは、3月から1年が始まるローマ暦の名残り。 | |
| 紀元前44年 | |
| 3月15日 | ガイウス・ユリウス・カエサルが元老院出席のためポンペイウス劇場に来た所で、ガイウス・カッシウス・ロンギヌスやマルクス・ユニウス・ブルートゥスらに暗殺される。その権力はガイウス・オクタウィウス・トゥリヌス(のちの初代皇帝インペラトル・カエサル・アウグストゥス)に受け継がれる。 |
| 紀元前37年 | |
| 扶余の金蛙王の子とされる朱蒙によって高句麗が建国されると建国神話にある。史実ははっきりしないが、旧玄菟郡の高句麗県侯となっていた在地の勢力とも考えられる。建国神話は夫余系民族に共通する東明聖王神話から来たものか。 | |
| ユダヤのハスモン朝がローマによって滅びる。ローマに従っていたヘロデが王位についてヘロデ朝が成立。 | |
| 紀元前32年 | |
| オクタウィアヌスが執政官として権力を握ったローマの元老院が、政敵であるアントニウスと手を組んだプトレマイオス朝エジプト王国に対し宣戦を布告。 | |
| 紀元前31年 | |
| 9月 2日 | アクティウムの海戦でオクタウィアヌス軍が、アントニウス軍に勝利。 |
| 紀元前30年 | |
| 8月12日 | プトレマイオス朝エジプト王国のファラオ、クレオパトラ7世フィロパトルが自殺。事実上最後のファラオ。 |
| 9月 8日 | 聖母マリアが誕生したとされる日。 |
| 紀元前27年 | |
| 1月13日 | 全権を掌握したオクタウィアヌスが、三頭政治時代の全ての特権を元老院に返還して共和政に復帰すると宣言。ただし実質的な権力である執政官にはとどまる。さらに属州を分けて、軍団駐屯地の属州統治権と軍の指揮権の法的権利を元老院から取り、事実上の全軍統括権を獲得する。 |
| 1月16日 | ユリウス・カエサルの副官だったルキウスが、オクタウィアヌスに「アウグストゥス(尊厳者)」の称号を贈ることを元老院に提案。元老院はこれを議決し、オクタウィアヌスは、「インペラトル・カエサル・アウグストゥス」と名乗ることに。これをもって形式上も含め、オクタウィアヌスをローマ帝国初代皇帝アウグストゥスとし、帝政ローマが誕生。 |
| 紀元前23年 | |
| 1月13日 | ローマ帝国初代皇帝アウグストゥスに、護民官職権が与えられ、権力が強化される。 |
| 紀元前18年 | |
| 高句麗建国の王朱蒙の三男温祚によって百済が建国される。これは建国神話に基づくもので、扶余系民族に共通する東明聖王神話に影響されているとみられる。 | |
| 紀元前8年 | |
| ローマ帝国初代皇帝アウグストゥスが、誤って運用されていたユリウス暦を修正する際に、8月に自身の名アウグストゥスを付ける(Augustの語源)。 | |
| 紀元前7年 | |
| (綏和2年) | 賈譲が黄河の治水案をまとめた「治河策」を著す。 |
| 紀元前6年 | |
| ローマがヘロデ王朝の王位を廃してユダヤの地を直轄領とする。ユダヤ属州の成立。 | |
| 紀元前4年 | |
| この頃、ナザレのイエス(いわゆるイエス・キリスト)が生誕。ルカ福音書の記載などからイエスはヘロデ王時代の末期に生まれているとみて間違いないので、ヘロデ王が死去したこの年までには生まれていたと考えられる。 | |
| 1年 | |
| 西暦1年。後の西暦525年にローマの神学者ディオニュシウス・エクシグウスが、新たな紀元歴を決めるため、復活祭の一巡とイエスの没年齢からディオクレティアヌス紀元248年がキリスト紀元532年として算出し、紀元1年を定める。実際に西暦が使われるようになるのは15世紀ころから。なお、西暦の略号ADは、ラテン語で「主の年」を意味するanno Dominiの頭文字。 | |
| この頃、日本列島南側で南海トラフの大地震が発生した可能性がある(高知県の津波堆積物のあとから)。 | |
| 8年 | |
| (居摂3年11月) | 王莽が前漢の皇太子の孺子嬰(劉嬰)より禅譲を受けて国号を「新」と改め建国。初始元年と改元。同12月朔日を始建国元年正月朔日と定める。孺子嬰を定安公とし、前漢は滅亡。 |
| 11年 | |
| (始建国3年) | 黄河が大氾濫を起こす。河口の位置がさらに移動し、現在の流路に近い形になる。 |
| 14年 | |
| 8月19日 | ローマ帝国の初代皇帝インペラトル・カエサル・アウグストゥス没。 |
| 17年 | |
| (天鳳4年) | 琅邪郡の老女呂母が人々をあつめて、天鳳元年に息子を死刑にした県令を襲撃して殺害。呂母はまもなく死去するが、集まった軍勢は解散せず後の赤眉軍につながる。 |
| この頃、王匡・王鳳らが人々をあつめて荊州江夏郡の緑林山に立て籠もる。緑林軍の反乱。 | |
| 21年 | |
| (地皇2年) | 黎丘郷の県吏秦豊、黎丘郷で挙兵。その後、勢力を広げ、楚の黎王を自称する。 |
| 22年 | |
| (地皇3年) | 疫病の発生により緑林軍が下江軍と新市軍とに分かれて緑林を離れる。転戦中に劉玄の平林軍や、同年挙兵した劉縯・劉秀兄弟の舂陵軍なども反乱軍に加わる。 |
| (地皇3年 3月) | 王莽は反乱に対して王邑・王尋らに100万と号する討伐軍を出陣させる。 |
| (地皇3年 5月) | 王邑ら討伐軍は、昆陽を包囲。劉秀は援軍を集めるため、昆陽を脱出。一方、劉縯は、宛を攻略。 |
| (地皇3年 6月) | 劉秀は数千の援軍を率いて昆陽に戻り、王邑・王尋らを攻撃。昆陽城内からも呼応して出撃した結果、王尋が戦死し、王邑は敗走。討伐軍は大敗を喫する(昆陽の戦い)。 |
| (地皇3年 冬) | 赤眉軍討伐のため出陣した新の更始将軍・平均公廉丹、太師王匡の軍勢と、軍閥董憲の軍勢が成昌で戦い、廉丹が討ち取られ、王匡は敗走する。 |
| 23年 | |
| (地皇4年 2月) | 平林軍の劉玄が更始帝として即位。更始元年。劉縯は大司徒となる。 |
| (地皇4年 夏) | 更始帝が舂陵軍の一派に支持されている劉縯と劉稷を殺害。劉秀は監視下に置かれる。 |
| (地皇4年 9月) | 更始帝の軍勢が長安(常安)に攻め込み、混乱の中、王莽が商人の杜呉によって殺される。 |
| この頃、隴西で隗囂が方望を軍師とし年号を漢復と称して独自勢力を拡大。 | |
| (更始1年10月) | 更始帝が劉賜の進言で、劉秀を河北への派遣軍の指揮官に任ずる。劉秀は各地を転戦。 |
| (更始1年12月) | 王郎が劉林らの支持を受け、邯鄲で即位。 |
| (更始1年) | この頃、盧江郡の李憲が淮南王を自称し独立。 |
| 24年 | |
| (更始2年 2月) | 更始帝が長安に都を遷し、有力者らを各地の王に封じる。しかしこれがきっかけで政権は分裂状態となる。 |
| (更始2年 5月) | 劉秀率いる軍勢が王郎を邯鄲に追い詰め、これを陥落。王郎は逃走を図るが殺害される。 |
| 25年 | |
| (更始3年 1月) | 隗囂から離反した方望が長安にいた孺子嬰(劉嬰)を擁立して臨涇に政権を起こすが、まもなく更始帝の軍勢に滅ぼされる。 |
| (更始3年 6月) | 劉秀、家臣の支持を受け即位。後の光武帝。建武と改元。 |
| (更始3年 6月) | 赤眉軍の樊崇と徐宣が関中に侵攻。劉盆子を皇帝に擁立する。年号を建世とする。 |
| (更始3年/建世1年/建武1年 9月) | 劣勢となった更始帝の重臣王匡が赤眉軍に寝返り、赤眉軍は長安を攻略。更始帝を捕らえ殺害。 |
| (更始3年) | 更始帝敗北を受けて、更始帝から梁王に封じられていた劉永が独立し皇帝を自称。 |
| 26年 | |
| (建世2年/建武2年春) | 赤眉軍政権は食糧を確保するため、長安を出て西へと進軍するが、隗囂の軍勢に敗れ長安に戻る。 |
| (建世2年/建武2年春) | 真定王劉楊、光武帝劉秀の召還命令に応じず、耿純らによって誅殺される。劉秀、謀反は起こしていないとして劉楊の子の劉得を真定王に封じる。 |
| (建世2年/建武2年12月) | 赤眉軍政権は秩序を保てず瓦解。食糧もなくなり長安を放棄。 |
| 27年 | |
| (建世3年/建武3年) | 赤眉軍が光武帝劉秀の臣下である馮異らの軍勢によって阻まれ降伏。 |
| (建武3年 7月) | 光武帝劉秀配下の征南大将軍岑彭が黎丘郷へ進攻。秦豊らは大敗を喫する。秦豊は、軍閥の延岑と田戎らと姻戚関係を結んで陣営に引き入れる。 |
| (建武3年 秋) | 劉永が光武帝劉秀配下の呉漢・蓋延の軍に本拠地の睢陽を攻め落とされ、敗走中に殺害される。 |
| (建武3年 秋) | この年、淮南王李憲が皇帝を称して九卿百官を置く。 |
| 28年 | |
| (建武4年 7月) | 光武帝劉秀と梁王劉永の子劉紆の両勢力が蘭陵をめぐって攻防戦となる。劉紆の重鎮となっていた董憲が勝利し蘭陵を確保。 |
| (建武4年 秋) | 光武帝劉秀自ら、寿春に親征。また舒で皇帝を自称し独立していた李憲に討伐軍を派遣。 |
| 29年 | |
| (建武5年 6月) | 光武帝劉秀の軍勢に黎丘郷を包囲され、窮した秦豊は一族を連れて降伏。洛陽に送られ処刑される。 |
| (建武5年 8月) | 光武帝劉秀の大司馬呉漢が、梁に攻め込み、梁軍は大敗。劉紆、董憲らは郯へ敗走。しかし郯も陥落し、劉紆は殺害され、董憲と龐萌はさらに朐へ敗走する。 |
| 30年 | |
| (建武6年 1月) | 長期の籠城戦となっていた舒が陥落。李憲は敗走し、部下の帛意に裏切られて殺害される。 |
| (建武6年 2月) | 光武帝劉秀の大司馬呉漢が、朐を攻め落とす。董憲と龐萌は降伏を決めるも呉漢軍校尉の韓湛によって殺害される。 |
| この頃、ユダヤ教の一派(初期のキリスト教)を率いたナザレのイエスがローマのユダヤ総督ポンティウス・ピラトゥスによって処刑される。 | |
| 33年 | |
| (建武9年) | 隴西の隗囂が病死し、後を継いだ隗純は光武帝に降伏。 |
| 35年 | |
| この頃、初期キリスト教の信者だったステファノがユダヤ教を批判して処刑される。最初の殉教者として聖人となっている。ユダヤ系ギリシャ人(ヘレニスト)で、初期教団内部のヘレニストの代表として教団内部のヘブライストとの調整役に就いていたという。 | |
| 36年 | |
| (建武12年) | 光武帝劉秀の軍勢が成都を攻略。蜀で独立していた公孫述を滅ぼし、公孫述と手を組んでいた軍閥の延岑らも滅ぼされ、中国を統一。 |
| 37年 | |
| ヘロデ・アグリッパ1世がトランス・ヨルダンの統治権を任される。 | |
| 40年 | |
| 南越で有力者であった徴側と徴弐の姉妹が自立の動きを見せ、合浦・九真・日南各郡で65県の貉将・貉侯がこれに同調する。いわゆる徴姉妹の乱(ハイバーチュンの乱)。 | |
| 41年 | |
| 1月24日 | ローマ帝国の第3代皇帝カリグラが暗殺される。 |
| 42年 | |
| 光武帝の派遣した伏波将軍馬援の遠征軍によって、徴姉妹は敗死。徴姉妹の乱(ハイバーチュンの乱)が鎮定される。ベトナムでは徴姉妹は英雄視されている。 | |
| ヘロデ・アグリッパ1世がユダヤ王を認められる。 | |
| 43年 | |
| ローマ帝国クラウディウス帝によるブリタンニア遠征。ブリトン人の王カラタクスを破り、その王都カムロドゥヌムを占領。ここを帝国ブリタンニア属州として植民地化。ブリタンニア属州はその後、ブリテン島全体へと拡大していく。 | |
| 48年 | |
| ヘロデ・アグリッパ2世がユダヤの統治権を認められる。 | |
| 54年 | |
| 10月13日 | ネロがローマ帝国の第5代皇帝に即位。 |
| 60年 | |
| この年、もしくは翌61年に、ブリタンニアのイケニ族の女王ブーディカが、圧政を敷いていたローマ帝国の総督ガイウス・スエトニウス・パウリヌス、行政官カトゥスらに対して反乱を起こす。反乱軍はカムロドゥヌム、ロンディニウム、ウェルラミウムの3つのローマ植民都市を攻め落として、市民7万人以上を殺戮。スエトニウスはモナ島の反乱から引き返して、ワトリング街道の戦いでブーティカの軍勢23万を打ち破る。ブーディカは敗戦後自殺したとも言われる。反乱は失敗に終わるが、スエトニウスの強権支配は批判され、皇帝ネロの宥和政策導入とも相まってスエトニウスは更迭。以後、ブリタンニア支配は穏健的な政策に変わった。 | |
| 64年 | |
| 7月19日 | ローマ大火。市内の大半を焼き尽くす。ネロが焼け跡に宮殿を立てたためにネロの仕業という噂が流れ、ネロはキリスト教徒を放火の罪で弾圧する。 |
| 66年 | |
| 第一次ユダヤ戦争勃発。 | |
| 68年 | |
| 6月 9日 | ローマ帝国皇帝ネロが元老院から公敵の宣告を受け自殺する。 |
| 70年 | |
| 4月14日 | ローマ軍によるエルサレム攻囲戦が始まる。 |
| 9月 7日 | ローマ軍がエルサレムを陥落する。市街地やエルサレム神殿も徹底的に破壊された。ユダヤ戦争は事実上終結し、一部がマサダ要塞へと逃げ込み抵抗を続ける。これ以降、ユダヤ人は国を失い、各地へと離散していくことになる。 |
| 73年 | |
| 5月 2日 | マサダ要塞の籠城戦が終わり、ユダヤ戦争が完全に終結する。 |
| 79年 | |
| 8月24日 | イタリア中南部ナポリ近郊にある活火山のヴェスヴィオ山が大噴火を起こし、火砕流や大量の灰などで麓にあったポンペイやヘルクラネウムなどの都市が壊滅する。艦隊指揮官のガイウス・プリニウス・セクンドゥスは救援に向かってガスにまかれて死亡し、その状況を、甥の文人政治家ガイウス・プリニウス・カエキリウス・セクンドゥスが、歴史家タキトゥスに伝えたことから、後世に詳しく残された。 |
| 97年 | |
| (永元9年) | 西域都護の班超が甘英を西の大秦に派遣。甘英は條支国を経て、大海の沿岸までくるが、安息国の西境の船乗りに大秦までの船旅の困難さを説かれて断念し帰国。大秦はローマ帝国、安息国はアルサケス朝パルティアとみられる。條支国については不明。大海はペルシャ湾・カスピ海・地中海など諸説ある。 |
| 115年 | |
| 各地のユダヤ人が反乱を起こす(キトス戦争)。これを第二次ユダヤ戦争と称する場合もある。 | |
| 132年 | |
| ローマ皇帝ハドリアヌスの政策に反発したユダヤ人が反乱(バル・コクバの乱:第二次ユダヤ戦争)。シメオン・バル・コクバというメシア(救世主)を称した人物が起こした反乱。エルサレムの再建に際して、かつてのユダヤの神殿あとにユピテル神殿を作るという計画と、割礼を禁止するという勅令が反乱の大きな要因。キトス戦争を含めた場合は、第三次ユダヤ戦争と称する。 | |
| 135年 | |
| ローマ軍がエルサレムを占領。バル・コクバは戦死し反乱は終結。またハドリアヌス帝は、ユダヤ的なものをなくすため、ユダヤ暦を廃止し、かつての王都エルサレムをアエリア・カピトリーナと改名し、ユダヤ人が入ることを禁止。ユダの地という意味のユダヤ属州の名称も廃止して、かつてユダヤ人と対立したペリシテ人の地という意味で、シリア=パレスチナ属州と改めた。このため、ユダヤ人の離散がさらに拡大した。 | |
| 140~190年頃 | |
| 倭国で大乱が続いたが、その関係者らが後に、共に卑弥呼という女性を王に立てることで収束させたと言われる。 | |
| 160年 | |
| 倭国王帥升等が生口160人を後漢朝廷に献上し、安帝の謁見を求める。後漢書の記載を書写した諸書物から、倭面上国王、倭面土国王という説もある。生口とは捕虜あるいは奴隷という説が有力。 | |
| 166年 | |
| 大秦国王の安敦から後漢の交州日南郡に使者が至り、象牙・犀角・玳瑁などを献上する。大秦国はローマ帝国、安敦はアントニヌスの音訳とみられるため、15代皇帝アントニヌス・ピウス、16代皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌスなどが考えられるが、ローマ帝国の正式な使者だったかは不明。 | |
| 181年 | |
| ニュージーランド北島のオルアヌイ火山が大噴火し、カルデラを形成。現在のタウポ湖。 | |
| 184年 | |
| 4月 2日(光和7年 3月 5日) | 太平道の教組張角らが中国各地で36万人ともいわれる兵で武装蜂起。黄巾の乱が勃発。各地の役所などを襲う。 |
| (光和7年10月) | このころ張角が病死し、主要幹部も戦死したため、組織的反乱は終息へ向かう。しかし以後も地域反乱は頻発することに。12月に中平元年に改元。 |
| 185年 | |
| 超新星SN185が観測されたことが中国の記録に見られる。ケンタウルス座の3,300光年離れた星。記録に残る最古の超新星。 | |
| 187年 | |
| 張純の乱。黄巾の乱の混乱を受けて、元中山太守の張純と烏丸大人の丘力居らが幽州で挙兵。華北各地を席巻する。朝廷は公孫瓚に討伐を命じるが、平定できなかったため、劉虞に討伐を命じ、劉虞は丘力居を降伏させる。 | |
| 188年 | |
| (中平5年10月) | 霊帝直属の西園八校尉(近衛軍司令官)を設置する。宦官(小黄門)の蹇碩を上軍校尉とし、その下に、虎賁中郎将の袁紹を中軍校尉、屯騎校尉の鮑鴻を下軍校尉、議郎の曹操を典軍校尉、趙融と馮芳を助軍校尉、夏牟と淳于瓊を左右校尉とするもの。 |
| 189年 | |
| (中平6年 3月) | 鮮卑へ逃亡した張純が暗殺され、張純の乱は平定。 |
| (中平6年 8月~9月) | 専横を極める宦官勢力を討伐するため、袁紹が宮中に乗り込むが、その混乱に乗じて皇帝を手に入れた董卓が権力を掌握。 |
| 190年 | |
| (初平元年 2月頃) | 群雄諸侯による反董卓連合が結成される。しかし群雄同士の駆け引きにより一向に行動に移さず。 |
| 192年 | |
| 5月22日(初平3年 4月23日) | 董卓が呂布に殺される。呂布、王允、士孫瑞、李粛らによる謀反。 |
| 194年 | |
| (興平元年) | 曹操が徐州へ出兵している間に、張超と陳宮が張邈を引き入れて反旗を翻し、呂布を迎え入れる。荀彧と夏侯惇が死守している間に、曹操は急遽引き返し、呂布と対戦。 |
| 195年 | |
| (興平2年12月) | 曹操が雍丘を攻め落とし、張超らが自殺し、曹操側の勝利で終結する。 |
| 196年 | |
| (建安元年 8月) | 曹操が献帝を自らの支配地域である許(のち許昌)に迎え入れる。 |
| 200年 | |
| (建安5年 2月) | 袁紹幕下の陳琳が檄文を記して曹操を誹謗し、袁紹対曹操の官渡の戦いが始まる。 |
| (建安5年 4月) | 曹操軍の関羽が白馬津で袁紹軍の顔良を斬り、さらに荀攸の献策で曹操軍は文醜軍を撃破。曹操軍の于禁と楽進は黄河を渡河し、北岸の袁紹軍の拠点を焼き払って退却する。 |
| (建安5年 8月) | 官渡まで退いた曹操軍に対し、袁紹軍が東西数十里に渡って陣を築き、総攻撃をかける。さらに曹操の本拠地である許周辺でも袁紹側に寝返る勢力が相次ぐ。曹操は許への退却を検討するが荀彧に諌められる。 |
| (建安5年10月) | 袁紹幕下の許攸が、袁紹を裏切って曹操に投降。烏巣にある袁紹軍の食料備蓄陣地の場所を教え、曹操自ら兵を率いて襲撃し焼き払う。その対応をめぐり袁紹軍内部で意見が対立し、張郃と高覧が曹操に投降。袁紹軍は撤退。官渡の戦いは終結する。 |
| 205年 | |
| (建安10年) | 袁紹と対立していた黒山賊の張燕が曹操に降伏する。張燕は平北将軍となる。 |
| 207年 | |
| (建安12年) | 袁熙と袁尚兄弟が烏桓王と組んで柳城で曹操と戦い敗れる。袁氏兄弟は遼東の公孫康のもとへ逃れる。 |
| (建安12年 9月) | 袁熙と袁尚兄弟が公孫康に殺害され、公孫康は曹操に降る。華北全域から遼東にかけてが曹操の勢力下に置かれる。 |
| 208年 | |
| (建安13年 9月) | 劉琮が曹操に降伏し、荊州は曹操の支配下となる。 |
| 12月15日(建安13年11月20日) | 赤壁の戦い。朝廷の実力者で中原を支配する曹操の水軍と、長江流域の地域軍閥である孫権・劉備の連合軍が戦い、孫権側が勝利。孫権側の火攻めと疫病の流行も勝敗を決した理由とされる。 |
| 211年 | |
| (建安16年 3月) | 曹操が漢中の張魯討伐を名目に、その手前にある関中へ進出。韓遂、馬超ら関中の各軍閥と対峙。 |
| (建安16年 7月) | 曹操と馬超らが潼関で衝突。曹操も危うく殺されかけるが、軍を大きく迂回して黄河を渡る。 |
| (建安16年 9月) | 曹操が渭水を渡河し、離間策を企て韓遂・馬超に個別会談を持ちかける。韓遂と馬超は疑心暗鬼に囚われ分裂。曹操軍に敗北を喫する。 |
| 213年 | |
| (建安18年) | 曹操が臣下としては異例の魏公となる。本来は皇族のみが認められた地位。 |
| 214年 | |
| (建安19年) | 合肥の戦い。孫権が兵力10万で合肥へ侵攻。対する守将の張遼・李典・楽進と護軍の薛悌は7000の兵力しかなかったが、張遼が寡兵で孫権の陣へ突撃するなどして打ち破り、また揚州刺史劉馥が事前に準備していた物資のお陰で持ちこたえ、孫権軍は退却。 |
| (建安19年) | 献帝の伏后が廃される。 |
| 215年 | |
| (建安20年) | 漢中の張魯が曹操に降伏。張魯を教祖とする五斗米道はその後各地へ広がり、のちに道教へと発展する。 |
| 216年 | |
| (建安21年) | 曹操が劉氏皇族以外では前漢初期を除いてほとんど例のない王位を与えられ、魏王となり、漢帝国内に魏国を興す。夏侯惇を除き曹操の家臣も魏の官職を与えられ魏臣となる(夏侯惇は曹操によって同列であるという特別扱いをうけ漢臣のままであった)。 |
| 217年 | |
| (建安22年) | この年、中国では疫病が流行。罹患した司馬朗は兵士を救うために自分の薬を分け与えたため、死亡したと言われる。また建安七子の王粲、応瑒、徐幹、陳琳、劉楨らはほぼ同時期にこの疫病で死亡した。この疫病かは不明だが、呉でも魯粛が同時期に病死している。 |
| 219年 | |
| (建安24年) | 漢中の定軍山で曹操軍と劉備軍が衝突し、曹操軍の総指揮官だった夏侯淵が戦死。劉備が漢中を制圧する。 |
| 220年 | |
| 3月15日(建安25年 1月23日) | 後漢の丞相で魏王だった曹操が死去し、曹丕が魏王位と丞相を継ぐ。 |
| 12月11日(建安25年10月29日) | 曹丕が献帝からの禅譲を受け、皇帝(魏文帝)となり、魏帝国を建国。年号は黄初と改められる。献帝は山陽公に封ぜられる。 |
| 221年 | |
| 5月14日(章武元年 4月 6日) | 劉備が蜀の皇帝に即位。蜀漢の昭烈皇帝。 |
| 7月 | 劉備が、関羽の復仇のため、呉に侵攻する(夷陵の戦い)。 |
| 222年 | |
| 6月 (章武2年) | 呉の陸遜が呉軍を率いて長江を遡上し蜀の陣営に放火。蜀の多くの武官文官が戦死し、劉備は白帝城へ退却する。長江北岸にいた蜀将の黄権は退路を失い、魏に降伏。 |
| 223年 | |
| 6月10日(章武3年 4月24日) | 劉備、白帝城で病没。劉禅があとを継いで即位する。 |
| 228年 | |
| (魏の太和2年・蜀の建興6年) | 街亭の戦い。蜀による第一次北伐で5回の北伐では最大の軍事作戦だったが、馬謖の作戦ミスから魏軍に大敗を喫し退却した。戦後、総司令官だった諸葛亮は自身を含む関係者を降格処分にし、愛弟子の馬謖を処刑した。「泣いて馬謖を斬る」の故事。 |
| 234年 | |
| (魏の青龍2年・蜀の建興12年) | 五丈原の戦い。蜀の第5次北伐戦だったが、魏の司馬懿は防衛に徹したため両軍対峙のまま、8月になって蜀の総司令官だった諸葛亮が病没し退却を余儀なくされた。追撃に出た司馬懿が蜀軍の反攻に驚いて退却し「死せる孔明生ける仲達を走らす」と言われたとされる。一方で司馬懿は諸葛亮の北進を阻止した功績もあり、魏の要人として権力を掴んでいくことになる。 |
| 238年 | |
| (魏の景初2年 6月?) | 邪馬台国の使者難升米と都市牛利が魏へ赴く。公孫淵が滅び通行が可能になったことで魏へ赴いたと考えられることから、6月ではまだ遼東の戦役は終わっていないため、景初3年の誤りとする説もある(公孫淵は遼東戦役の途中から戦意を喪失しているため通行許可が降りた可能性もある)。皇帝(景初3年1月に病没した明帝曹叡か、次の曹芳)によって、卑弥呼に親魏倭王の印が贈られたという。 |
| (魏の景初2年・燕の紹漢2年 8月23日) | 魏の司馬懿が遼東を支配する燕王公孫淵を滅ぼす。 |
| 241年 | |
| (魏の正始2年・呉の赤烏4年) | 芍陂の戦い。呉の孫権が、揚州と荊州の4路方面から魏に侵攻。全琮が淮南、諸葛恪が六安、朱然が樊城、諸葛瑾が柤中を攻撃。また蜀にも出兵を求める。しかし淮南で魏の孫礼と王凌に敗れ揚州方面から撤退。樊城では籠城戦となるが、魏の胡質が抗戦し、司馬懿が援軍に来たうえ、蜀も出兵しなかったため、呉軍は荊州攻勢も断念。撤退中に追撃を受け大敗を喫する。 |
| 244年 | |
| 2月11日 | ミシケの戦い。サーサーン朝とローマ帝国の戦い。ローマ皇帝ゴルディアヌス3世が戦死。暗殺説もある。 |
| (魏の正始5年・蜀の延熙7年) | 興勢の戦い。魏の有力者曹爽が、司馬懿に対抗するため、自らの軍歴を積もうと蜀出兵を計画。蜀の蔣琬が主力軍を引いたのを機に、10万の兵で攻め込む。しかし蜀将王平が興勢山まで迎撃に出て打ち破り、さらに費褘の援軍が到着したため、魏軍は撤退。 |
| 248年 | |
| (呉の赤烏11年) | 交州の九真で趙氏貞と兄の趙国達らが呉に対し反乱を起こす。交州刺史陸胤によって鎮圧される。 |
| 249年 | |
| (魏の正始10年 1月 6日) | 高平陵の変。魏の有力者司馬懿が病身を偽ったことで安堵した曹爽一派が、皇帝曹芳とともに先帝曹叡の高平陵を参拝して都洛陽を離れている間に、司馬懿がクーデターを決行。郭太后の勅を得て洛陽を制圧。洛水に陣を張り使者を送って曹爽らを説得。それを信じた曹爽らが降伏する。 |
| (魏の正始10年 1月10日) | 先の政変で捕らえられた曹爽一派が、謀反を企図していたとしてことごとく処刑が決定する。司馬懿が事実上の最高権力者となる。 |
| 251年 | |
| 7月 1日 | アブリットゥスの戦い。ゴート族らゲルマニア人がローマ帝国領内に侵攻し、ローマ皇帝デキウスと息子で共同統治者ヘレンニウスが戦死し、ゴート族が大勝利をおさめる。 |
| 9月 7日(魏の嘉平3年 8月 5日) | 魏の最高権力者である司馬懿が死去。司馬師が後を継ぐ。 |
| 252年 | |
| (魏の嘉平4年・呉の神鳳1年 4月) | 呉の初代皇帝孫権が死去。 |
| (魏の嘉平4年・呉の建興1年12月) | 東興の戦い。孫権の死を好機と捉えた魏は、司馬師主導のもと諸葛誕、胡遵、王昶、毌丘倹らに呉へ出兵させる。これを予期していた呉の諸葛恪は、巣湖の東興堤を強化。これを全端と留略が防衛し、さらに丁奉が魏軍に急襲をかけたため、魏軍は大敗する。しかしこの戦いで勝利した諸葛恪は権力を謳歌して呉に混乱を招き、敗れた司馬師は自ら敗戦の責任を表明して誰も罪に問わなかったため、支持を得ることになる。 |
| 256年 | |
| (魏の甘露元年・蜀の延熙19年) | 段谷の戦い。蜀の姜維が魏を攻めるが味方との連携が取れず魏の鄧艾に大敗を喫す。蜀将多数が戦死し多くの兵を失ったため、以後、姜維は戦線を漢城・楽城まで後退させて専守防衛に徹することになる。 |
| 259年 | |
| エデッサの戦い。ローマ帝国とサーサーン朝との戦い。ローマ側が大敗し、皇帝ウァレリアヌスが捕虜となりペルシアへ連行される(間もなく死去したとも)。これをうけて共同皇帝ガッリエヌスが単独皇帝となるが、ローマ帝国の権威は失墜。各地で皇帝僭称者が相次ぎ、「三十人僭帝」と呼ばれる時代に入る。 | |
| 260年 | |
| 6月 2日(甘露5年 5月 7日) | 魏の第4代皇帝曹髦が司馬昭の排除を企て、李昭・焦伯ら数百人と蜂起。王業・王沈の密告で事態を知った賈充が待ち構え、その命令で成済が曹髦を殺害。成済一族も皇帝弑逆の罪を着せられ処刑される。 |
| ローマ帝国の将軍マルクス・カッシアニウス・ラティニウス・ポストゥムスが、ローマ皇帝を僭称し、帝国属州のガリア、ゲルマニア、ブリタンニア、ヒスパニアを領域として事実上独立。いわゆるガリア帝国。 | |
| 261年 | |
| サーサーン朝の王シャープール1世が、ローマ帝国の弱体化を見て、ローマ領への侵攻を開始するも、東方属州の総司令官セプティミウス・オダエナトゥスに大敗。 | |
| 263年 | |
| (魏の景元4年・蜀の炎興元年) | 夏から秋にかけて魏は鐘会・鄧艾・諸葛緒ら18万の軍勢で蜀に攻め込み、剣閣で姜維が防衛している間に迂回した鄧艾が成都へ向けて進撃。蜀帝劉禅は降伏。蜀が滅亡する。 |
| 264年 | |
| (景元5年・咸熙元年) | 蜀で鐘会と姜維が組んで反乱を起こすも失敗に終わる。鐘会と姜維は殺され、またこの反乱に巻き込まれて鄧艾・張翼ら魏将、劉禅の子で蜀の太子だった劉璿、関羽の孫の関彝ら多数が殺害される。 |
| 266年 | |
| 3月10日(泰始2年 1月17日) | 魏の滅亡・晋の建国。魏の晋王司馬炎が、第5代元帝曹奐から禅譲を受け、晋を建国、魏が滅亡。 |
| 曹操の時代から続いた屯田制が廃止される。代わりに280年ころから占田・課田制が導入されることになるが、実態は不明。 | |
| 267年 | |
| ローマ帝国東方属州の司令長官だったセプティミウス・オダエナトゥスが暗殺される。妻ゼノビアが息子ウァバッラトゥスを後継者にし自ら後見人として実権を握る。パルミラ王国として事実上の独立。 | |
| 268年 | |
| 晋が泰始律令を制定。初めて律と令を区分した法令。 | |
| 269年 | |
| 2月14日 | ローマの司祭ウァレンティヌスが処刑される。皇帝クラウディウス・ゴティクスが決めた兵士の結婚禁止を破って式を挙げさせたため。聖バレンタインデーの由来のひとつとされる。ウァレンティヌスの実在性については諸説ある。 |
| 270年 | |
| 西晋の秦州で鮮卑禿髪部の樹機能が反乱を起こす。万斛堆の戦いで秦州刺史胡烈を敗死させ、反乱は雍州・涼州へも拡大。 | |
| 271年 | |
| ローマ帝国皇帝アウレリアヌスがパルミラの支配域へ攻略に乗り出す。ウァバッラトゥスは戦死。ゼノビアはパルミラ市へ敗走。 | |
| 呉が西晋の支配下にあった交州を制圧する。 | |
| 272年 | |
| 西陵の戦い。呉の西陵督である歩闡が西晋に寝返ったため、呉の将軍陸抗がこれを攻め滅ぼす。 | |
| 273年 | |
| ローマ帝国皇帝アウレリアヌスがパルミラ市を包囲攻撃し、ゼノビアは捕らえられ、パルミア王国は崩壊。 | |
| 274年 | |
| ローマ帝国皇帝アウレリアヌスがガリア帝国攻略に乗り出す。シャロンの戦いで、ガリア側が敗北。テトリクス1世が捕虜となり、ガリア帝国も崩壊。ローマ帝国に再統一される。 | |
| 275年 | |
| ローマ帝国皇帝アウレリアヌスがサーサーン朝遠征の途上、秘書官や将軍らの企てた陰謀で暗殺される。 | |
| 277年 | |
| 西晋の将軍文鴦によって樹機能の反乱は一旦鎮圧される。 | |
| 278年 | |
| 若羅抜能が樹機能と再び反乱を起こす。西晋は軍の主力を呉の攻略戦に振り向けていたため、馬隆を派遣してこれを鎮圧させる。樹機能は部下の没骨能によって殺害される。10年続いた反乱は平定されたが、西晋の呉攻略計画は大幅に遅延した。 | |
| 279年 | |
| (天紀3年) | 夏、呉の合浦太守脩允の部下だった郭馬が呉に対して広州で反乱を起こす。郭馬の乱、広州の乱ともいう。反乱は蒼梧郡・始興郡に拡大。呉は滕脩・陶璜・陶濬らに鎮圧を命じるがうまく行かないうちに晋の呉侵攻が始まる。 |
| (咸寧5年) | 西晋の司馬炎は、前年に亡くなった羊祜が推し進め、樹機能の反乱で大幅に遅れていた呉の攻略戦を開始。賈充は慎重論を説いて反対したが司馬炎は親征を匂わすことで賈充を半強制的に大都督にし、楊済を副将として、王濬と唐彬は水軍を率いて蜀から長江を下り、司馬炎の叔父の司馬伷は下邳から呉の都建業を目指して南下、王渾は寿春から建業を目指し、王戎は項城より武昌へ、胡奮は江夏から夏口へ、杜預は襄陽から江陵へそれぞれ進軍。 |
| 280年 | |
| (太康元年 1月) | 晋の王渾軍が長江の対岸から渡河して首都建業へ攻略の構えを見せたため、呉の皇帝孫皓は、張悌、沈瑩、孫震らを迎撃に向かわせるが大敗して呉軍は潰滅。 |
| (太康元年 2月) | 晋の王渾軍、司馬伷軍が建業周辺を制圧して孫皓に圧力を加える一方、王濬と唐彬の水軍は長江中流域の江陵まで進出、胡奮は夏口・江安を攻略、杜預は長江を横断して荊州南部を攻略。呉は建平太守吾彦のみが唯一維持している状態となる。 |
| 5月 1日(太康元年 3月15日) | 晋の各攻略軍が建業を包囲、呉軍からは降伏が相次ぎ、呉の皇帝孫皓は降伏し呉は滅亡。西晋によって中国が統一される。三国時代の終焉。 |
| 285年 | |
| 遼東の鮮卑慕容部の後継に慕容廆が就く。まもなく庶兄で分家した慕容吐谷渾との間で馬をめぐる紛争が起きる。慕容廆は和解を申し出たが吐谷渾は争いを避けるため故地を捨てて部衆を率い西へと向かう。慕容廆の子孫は勢力を拡大して前燕となり、慕容吐谷渾は遙か西方の甘松(青海)まで移り、子孫は同地に吐谷渾国を興した。 | |
| 290年 | |
| 5月16日(太熙元年 4月20日) | 晋の初代皇帝司馬炎が死去。皇太子司馬衷が即位(恵帝)。司馬衷の母親の一族である楊駿が権力を握る。 |
| 291年 | |
| (永平元年 3月) | 晋恵帝の后である賈南風が楚王・東安王らと組んで楊駿とその三族を殺害。八王の乱の始まり。 |
| 293年 | |
| ローマ皇帝ディオクレティアヌスが4人の東西正副皇帝によってローマ帝国の分割統治を行うテトラルキアを導入。ローマ帝国が分裂したわけではなく、便宜的に帝国を4人で分担した形。 | |
| 297年 | |
| (元康7年) | 『三国志』の著者陳寿が死去。 |
| (元康7年) | この年、李特が10万もの人民を連れて渭水上流から漢中を経て蜀へ移住する。 |
| 300年 | |
| (永康元年 4月) | 趙王司馬倫がクーデターを起こし、晋恵帝の后である賈南風、甥の賈謐ら賈一族が処刑される。また司馬倫と不仲であった張華らも処刑される(張華は元康年間に政権を担った人物で多くの人材を推挙。呉の生まれである文人政治家の陸機・陸雲兄弟を登用し、『三国志』の著者陳寿も孝廉に推挙されている)。 |
| (永康元年 8月) | 恵帝の弟淮南王司馬允が司馬倫に警戒されたことから石崇・潘岳らと挙兵するも敗死。司馬倫が九錫を授けられる。 |
| 301年 | |
| (永康2年 1月) | 司馬倫が恵帝に迫って退位させ、自ら即位。年号を建始とし、皇太孫である司馬臧を濮陽王に落としたうえで殺害。自分の気に入った人物に官位を乱発するなどしたため、他の皇族や朝臣らの反発を買う。 |
| (建始元年 4月) | 斉王司馬冏・長沙王司馬乂・成都王司馬穎らが挙兵。司馬倫は恵帝を復位させて自らは謹慎するが許されず、側近の孫秀らとともに殺害される。斉王司馬冏が実権を掌握。 |
| 9月 3日 | 現存する世界最古の共和国と言われるサンマリノが建国。ローマ帝国皇帝ディオクレティアヌスによるキリスト教徒の迫害から逃れた石工マリヌス(聖マリノ)が、イタリア半島中部のティターノ山に籠り、キリスト教徒たちの共同体を作ったとされる。 |
| 302年 | |
| (永寧2年 5月) | 李特が大将軍・益州牧を自称。晋書などではこの年、年号を建初と改める(もしくは翌年)。実質上の成漢の建国。 |
| (永寧2年12月) | 斉王司馬冏が長沙王司馬乂・成都王司馬穎・河間王司馬顒らに殺害される。年号を太安と改める。 |
| 303年 | |
| (大安2年/建初2年 3月) | 李特が成都へ侵攻するが羅尚に敗死する。弟の李流が後を継ぎ、さらに李特の子の李雄が後を継いで羅尚と戦う。 |
| (大安2年 8月) | 司馬乂と対立した司馬穎・司馬顒らが挙兵し、陸機が指揮をとって司馬乂を攻めるが大敗。一方司馬乂も洛陽に籠城するが、東海王司馬越に捕らえられ処刑される。司馬穎は、陸機に恨みを持っていた宦官の孟玖らの進言で陸機と陸雲の兄弟及びその一族を敗戦の罪でことごとく処刑。しかしこれが世論の反発を買ったため、孟玖を処刑せざるを得なくなる。 |
| 304年 | |
| 1月21日 | ローマ帝国によって13歳の聖アグネスが処刑される。帝国の長官センプロニウスの息子との結婚を宗教的理由で拒絶したため。 |
| (永安元年 7月) | 東海王司馬越・予章王司馬熾らが晋恵帝を擁して挙兵。蕩陰の戦いで司馬穎の軍に敗れる。 |
| (永安元年 8月) | 東海王司馬越・予章王司馬熾らを支持した幽州都督王浚・并州刺史司馬騰らが挙兵し司馬穎を打ち破る。司馬越、司馬熾を皇太弟とする。 |
| (建武元年10月) | 南匈奴の単于の家柄出身で、司馬穎と手を組んでいた劉淵が河西一帯で自立。国号を漢と称して建国。晋と激しく対立。五胡十六国の先駆け。 |
| (建初2年10月) | 李雄が成都王を自称し、年号を建興とする。 |
| 306年 | |
| (永興3年 2月) | 劉柏根と王弥が挙兵。 |
| (永興3年 5月) | 司馬越ら、長安を手中に収め、司馬穎ら殺害される。 |
| (建興3年 6月) | 李雄が皇帝に即位し、国号を大成と称する。成漢の建国。 |
| (永興3年12月) | 河間王司馬顒も殺害され、八王の乱はほぼ終息する。 |
| 307年 | |
| 1月 8日(光熙元年11月18日) | 晋恵帝司馬衷が死去(病死とも暗殺とも言われる)。司馬熾が即位(懐帝)。事実上の司馬越政権が樹立。司馬越は残った皇族を各地に配して政権の安定化に務める。 |
| 308年 | |
| (永嘉2年 3月) | 王弥が河東一帯を攻略して許昌を制圧。洛陽に迫る勢いとなる。 |
| (永嘉2年 6月) | 司馬越が宮中に入り、懐帝の親族や側近を粛清。 |
| (元熙5年10月) | 劉淵が皇帝を称する。国号は漢(のち趙)。永鳳と改元。 |
| 310年 | |
| 8月19日(河瑞2年 7月 8日) | 劉淵が死去。劉和が後を継ぐ。劉和は兵権を持つ異母弟劉聡を排除しようとして失敗し、逆に殺害される。劉聡が即位。 |
| 311年 | |
| (永嘉5年 1月) | 懐帝が苟晞に司馬越討伐の密詔を出し司馬越は軍を率いて洛陽を離れる。 |
| (永嘉5年 3月) | 復権を図ろうとしていた司馬越が項城で病死。その葬列のために集結した司馬越の一族や部下とその軍勢に対し、漢(劉淵)の将軍となっていた石勒の軍勢が襲いかかり、皇族ら100人余りを殺害し、その兵10万を壊滅させる。この事件で晋の軍事力は大幅に低下。 |
| 劉聡・石勒・王弥らが洛陽へ向けて進軍、蒙城で苟晞の軍勢を破る。 | |
| (永嘉5年 6月) | 洛陽が陥落し、晋懐帝は捕らえられ平陽へ連行され、3万人以上が殺害される。 |
| 313年 | |
| 3月14日(永嘉7年 2月 1日) | 懐帝が処刑される。生き延びていた甥の司馬鄴が長安で即位(愍帝)。しかしその支配域は長安とその周辺のみとなる。 |
| 316年 | |
| (建興4年11月) | 劉曜の軍勢に長安を包囲されていた愍帝が降伏し、平陽へ連行される。 |
| 318年 | |
| 2月 7日(建興5年12月20日) | 晋愍帝が処刑される。西晋は滅亡。江南の建業に派遣されていた丞相・大都督中外諸軍事の司馬睿が即位して晋王朝を興す(東晋)。 |
| 324年 | |
| ローマ帝国西方正帝コンスタンティヌス1世が他の勢力を打ち破って「唯一の正帝」となりテトラルキア(分割統治)が終了。しかし分割統治の影響は残り、コンスタンティヌス1世が死ぬと再びテトラルキアが復活する。 | |
| 325年 | |
| 5月20日 | 第一ニカイア公会議がはじまる。6月19日まで。キリスト教で最初の全教会会議。ユダヤ教の一派として誕生し、各地で徐々に教義や教典が定まっていたキリスト教は、地域によって多種多様な流派に分裂していた。特にイエスの神性について被造物として否定的な主張をしているとされたアリウス派に対する扱いが論争となった。アリウス派は破門される。 |
| 326年 | |
| この年、ローマ皇帝コンスタンティヌス1世の母親フラウィア・ユリア・ヘレナが、エルサレムを訪れてヴィーナス神殿をゴルゴダの丘と特定し、そこでキリストを磔にしたときの十字架を含む3つの十字架と聖釘を発見したとされる(2つはキリストと同時に処刑された2人の盗賊の十字架)。ヘレナはロンギヌスの槍も見つけたという伝説もある。同地はその後、聖墳墓教会となった。 | |
| (仁徳天皇14年) | 日本書紀に、猪甘津(いかいつ)に橋を架けたという記録がある。記録上では日本最古の架橋。西暦については計算上による。猪甘津は、現在の大阪市生野区桃谷付近。当時上町台地は河内湾の半島で、百済川河口付近に津(港)があったと考えられる。 |
| 330年 | |
| 5月11日 | ローマ帝国によって建設されたコンスタンティノポリスが開都する。 |
| 336年 | |
| 12月25日 | ローマ皇帝コンスタンティヌス1世が、古代ローマのミトラ教の冬至祭の日25日をイエス・キリスト生誕の日と定めたとされる。クリスマスの原点の一つ。 |
| 345年 | |
| 12月 6日 | ミラのニコラオスが死去。貧窮者や冤罪で処刑されかけている人を救い、サンタクロースのモデルとされる人。352年という説も。 |
| 346年 | |
| 百済第13代の王に近肖古王が即位。新羅と同盟し、高句麗を撃破し、東晋に朝貢。倭にも使者を送ったことで中国や古事記、日本書紀にも記載のある人物。これより以前の王は記録に乏しい。 | |
| 347年 | |
| 東晋の桓温が蜀にあった「成漢」を攻め滅ぼす。桓温の名声が高まり権力を強める。 | |
| 351年 | |
| 4月 | 後趙の将軍だった劉顕が冉閔討伐の遠征に失敗したことから、密かに冉閔に降伏して、後趙に戻ったあと後趙の君主石祗を始め、丞相楽安王の石炳、太宰の趙庶らを殺害して襄国を手中に収める。後趙は事実上滅亡。 |
| 7月 | 襄国の劉顕が冉閔からの独立を企てる。 |
| 352年 | |
| 1月 | 冉閔が、常山に侵攻した襄国の劉顕を撃破し、そのまま襄国まで侵攻。劉顕らは捕えられて処刑され滅亡。この混乱に乗じて後趙の将軍だった段勤が繹幕で独立。趙帝を称する。 |
| 11月 | 華北へと勢力を拡大した前燕の第2代王慕容儁が、皇帝に即位。東晋からは独立。 |
| 356年 | |
| 新羅の王に奈勿尼師今が即位。初めて記録に現れる『秦書』に377年に前秦に朝貢使節を送った新羅の王が彼とみられるため、史実の「新羅」と称した初代王か、初期の王という説もある。 | |
| 367年 | |
| (仲哀9年3月) | 筑紫に遠征していた神功皇后が、山門(筑後国山門郡)の土蜘蛛の女領主田油津媛を誅殺したとされる。土蜘蛛とは大和朝廷に従わなかった各地の在地勢力の総称。田油津媛は卑弥呼の子孫という説もあるが定かではない。史実とした場合の西暦には諸説あり。 |
| 378年 | |
| 8月 9日 | ハドリアノポリスの戦いで、ローマ帝国軍が西ゴート諸族に敗北、皇帝ウァレンスも戦死する。 |
| 381年 | |
| 第一コンスタンティノポリス公会議が始まる。ニカイア公会議に続く2回めの公会議で、前回同様アリウス派に対する問題が論議された。ニカイア・コンスタンティノポリス信条が定められる。 | |
| 393年 | |
| 超新星SN393が観測されたことが中国の記録に見られる。さそり座の方角にある星と考えられ、超新星残骸とされるRX J1713.7-3946がこれに該当すると考えられている。 | |
| ローマ帝国皇帝テオドシウス1世が古代オリンピックを廃止。 | |
| 395年 | |
| 1月17日 | ローマ帝国皇帝テオドシウス1世が死去。長男アルカディウスを東の正帝とし、次男ホノリウスを西の正帝として分担統治させたことから、これをもって東西ローマ帝国に分裂したとする場合もある。 |
| 404年 | |
| アルメニア人のメスロプ・マシュトツが、アルメニア文字を考案する。布教のためとも言われる。 | |
| 405年 | |
| (義熙元年 2月) | 東晋の益州刺史毛璩が出した桓振討伐の出兵命令に反発した蜀の兵らが安西府参軍で巴西梓潼二郡太守の譙縦を擁立して反乱。毛璩を殺して成都を占領し、譙縦は成都王を称する。後蜀の建国。 |
| 407年 | |
| ローマ帝国がブリタンニアから撤退。ブリテン島はブリトン人の小王国が乱立する時代へと移っていく。 | |
| 410年 | |
| 8月24日 | アラリック1世率いる西ゴート族4万の兵がローマに侵攻。3日間に渡り、暴行・略奪が繰り広げられる。その後もアラリック1世の軍勢はイタリア半島南部まで侵攻。古代都市ローマはすでに帝国首都ではなかったが、ローマに侵攻されたこと自体大事件であった。 |
| 413年 | |
| (義熙9年) | この年、倭王讃が東晋に朝貢。 |
| 415年 | |
| 3月 | アレクサンドリア図書館の女性科学者ヒュパティアが、キリスト教徒の手で惨殺される。異教徒に対する強硬派だったアレクサンドリア総主教キュリロスが関わっていたとされる。 |
| 416年? | |
| 8月22日(允恭5年7月14日) | 『日本書紀』に地震が起こったとある(日本の最古の記録。ただし年代は正確ではない)。地震のあと、允恭天皇は、反正天皇の殯(葬儀)を命じていた玉田宿禰の様子を尾張連吾襲に殯宮まで確認に行かせたところ、玉田宿禰はおらず、別のところで酒宴を開いていた。発覚を恐れた玉田宿禰は尾張連吾襲を殺害。允恭天皇は玉田宿禰を呼び出し、武装しているのを確認すると、兵を出してこれを捕らえ誅殺した。 |
| 423年 | |
| (永初2年) | この年、倭王讃が宋に朝貢し、武帝より称号を与えられる。 |
| 425年 | |
| (元嘉2年) | この年、倭王讃が宋に司馬の曹達を派遣する。 |
| 430年 | |
| (元嘉7年) | この年、倭王が宋に朝貢。 |
| この頃、東北から関東にかけての太平洋岸で大規模な地震と大津波があったとみられる。 | |
| 431年 | |
| エフェソス公会議が開催される。キュリロス派とネストリオス派の対立。 | |
| 438年 | |
| (元嘉15年) | この年、倭王珍が宋に朝貢。自らを「使持節都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭国王」と称し承認を求める。 |
| (元嘉15年 4月) | 宋の文帝、倭王珍を安東将軍倭国王に任ずる。また珍の求めに応じ、倭隋ら13人を平西・征虜・冠軍・輔国将軍とする。 |
| 443年 | |
| (元嘉20年) | この年、倭王済が宋に朝貢。安東将軍倭国王に任ぜられる。 |
| 449年 | |
| エフェソス強盗会議。キリスト教内部の宗派対立で開かれた公会議のひとつ。 | |
| 451年 | |
| 6月20日 | カタラウヌムの戦い。アッティラ率いるフン族・東ゴート族・ゲピド族などのゲルマン諸族の軍勢と、西ローマ帝国・西ゴート族・アラン族などが衝突。双方大損害を出し、アッティラは撤退。ローマ帝国の勢力も弱体化して、ゲルマン諸族が拡大する。 |
| (元嘉28年) | この年、倭王済、宋文帝から安東将軍に追加して「使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事」を加号される。 |
| 10月 8日 | カルケドン公会議が始まる。イエス・キリストの単性説を排除し、神性と人性がともにある両性説を採用する。 |
| (元嘉28年 7月) | 倭王済、安東大将軍に進号する。 |
| 460年 | |
| (大明4年) | この年、倭王が宋に朝貢。 |
| 462年 | |
| (大明6年 3月) | この年、宋の孝武帝、倭国王済の世子の興を安東将軍倭国王とする。 |
| 476年 | |
| 9月 4日 | 西ローマ帝国皇帝ロムルス・アウグストゥルスがゲルマン族の将軍オドアケルによって退位させられ、西ローマ帝国が滅亡。まだ年少だったロムルスは殺されず、恩給をもらい隠棲。ロムルスを帝位につけた、彼の父親オレステスは殺される。 |
| 477年 | |
| この年、倭王興が没し、その弟武が後を継ぐ。武、自ら使持節都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事安東大将軍倭国王と称する。 | |
| (昇明元年11月) | 倭王(武?)、宋に使者を送る。 |
| 478年 | |
| (昇明2年) | 倭王武、宋に上表して自ら開府儀同三司(府を開くことのできる三公(太尉・司徒・司空)と同じ扱いとするの意味)と称し叙正を求める。これに対し宋の順帝、武を「使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭王」とする。 |
| 479年 | |
| (建元元年) | 宋の斉王蕭道成が禅譲により即位し(高帝)、南斉を興す。高帝、倭王武を鎮東大将軍(征東将軍)とする。 |
| 481年 | |
| クローヴィス1世によってフランク人国家が統一される。メロヴィング朝フランク王国の成立。 | |
| 482年 | |
| (清寧天皇3年3月~4月頃) | 富士山が噴火し、熱い灰が降り、五穀が実らなかったという。年代の正確性は不明。 |
| 495年 | |
| この年、中国の南朝斉で天然痘と見られる疫病が流行する。 | |
| 500年代前半 | |
| 現在の超新星残骸ベラ・ジュニアを生み出したとみられる超新星爆発が発生。650光年以上離れているため、地球上で観測されたのは1200年ころ。 | |
| 502年 | |
| (天監元年) | 南斉の皇族である蕭衍が梁王朝を樹立(武帝)、倭王武を征東大将軍とする。 |
| 515年 | |
| (延昌4年6月) | 北魏で大乗の乱が起きる。冀州の仏教徒の法慶が李帰伯らと反乱。下生信仰(遠い未来に現れるはずの弥勒菩薩がまもなく現れるので世の中を変革すべきという終末論)を唱え、信徒5万人を率い、役所や仏教寺院などを攻撃。撫軍将軍・冀州刺史の蕭宝寅(もと南朝斉の皇族)の討伐軍を破るなどしたが、7月、征北大将軍の元遥の率いる援軍によって鎮圧される。 |
| 525年 | |
| ローマの神学者ディオニュシウス・エクシグウスが、ローマ教皇ヨハネス1世の要請で、復活祭暦表を改定するため、ディオクレティアヌス紀元暦に代わる紀元歴として、キリスト暦(西暦)を定める。実際に普及するのは15世紀ころから。ディオクレティアヌス紀元暦は、ローマ皇帝ディオクレティアヌスがキリスト教徒を迫害したことから、その殉教を記念して、皇帝の即位を1年とするキリスト教徒らが用いた暦。 | |
| この頃、榛名山二ッ岳が大規模噴火。遺跡などから火砕流が麓に到達して人的被害がでたと見られる。この時代、榛名山は頻繁に噴火していたと見られる。 | |
| 528年 | |
| 4月 | 河陰の変。北魏の有力者爾朱栄が長楽王元子攸を擁立し、軍を率いて洛陽に侵攻。政治を専横していた胡太后と、彼女が擁立した幼帝の元釗を捕らえると黄河に沈めて溺死させ、さらに皇族の諸王や朝臣ら2000人余りを殺害した政変。 |
| 12月 7日(継体天皇22年11月11日) | 磐井の乱が終結。筑紫国造磐井が、朝鮮半島へ出兵しようとした近江毛野の軍勢を、新羅からの賄賂を受けて阻止し、朝鮮からの朝貢船も押さえたことがきっかけで、物部麁鹿火の討伐を受けたとされる内乱。磐井はこの日、麁鹿火の軍と筑紫三井郡で交戦したが敗死した。日本書紀には詳細に記載があるが古事記には一文しかなく、磐井の地位、乱の規模なども含め諸説わかれる。 |
| 532年 | |
| 1月13日 | 東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルでニカの乱が起こる。政治党派とつながっていた戦車レースの観客らが、重税などに反発してユスティニアヌス1世に対し暴動を起こしたことをきっかけに元老院議員などが加わった騒乱。 |
| 1月13日 | 東ローマ帝国の将軍ベリサリウスがニカの乱を鎮圧。皇帝権力が強化されるきっかけとなる。 |
| 534年 | |
| ユスティニアヌス1世の命令でベリサリウスがシチリアに上陸し、少数の兵で同地を制圧。 | |
| 535年 | |
| この頃、クラカタウ山が大噴火を起こす。ジャワ島にあったカラタン文明が衰退した要因の一つと考えられる。世界各地で気象異変を引き起こしたとみられる。 | |
| 536年 | |
| ベリサリウスがイタリア半島の東ゴート軍を撃破し各都市を制圧。東ゴート軍も反撃しローマ包囲戦に。 | |
| 538年 | |
| (宣化天皇3年) | 日本に仏教が公式に伝わったと推定される有力な年。『上宮聖徳法王帝説』と『元興寺伽藍縁起并流記資財帳』に「欽明天皇御代の戊午年に百済の聖明王から仏教が伝来した」とあり、欽明天皇の御代が諸説あるため、近い戊午の年であるこの年が有力視されている。これ以前から大陸と繋がりのある個人で仏教を取り入れていたものはいたと考えられる。 |
| 540年 | |
| ベリサリウスが、サーサーン朝の侵攻を受けて、イタリア方面の指揮権を剥奪され、シリアへ送られる。 | |
| 542年 | |
| この頃、ローマ帝国で腺ペストが流行。東ローマ皇帝ユスティニアヌスも感染したことから、ユスティニアヌスのペストとも呼ばれる。交通網の整備されていた帝国領内で猛威をふるい膨大な死者を出したが、それより外側の地域では比較的影響が少なかったとも言われる。 | |
| 544年 | |
| ベリサリウスが、ふたたびイタリア方面の指揮官となり、東ゴート王トーテイラの軍勢と対峙。 | |
| 546年 | |
| 12月17日 | ローマを包囲していた東ゴート王トーテイラの軍勢が市内になだれ込む。翌年にかけてローマ市内を略奪し城壁などを破壊。ローマ側も内紛状態でまともに防衛も出来ない状態だった。 |
| 548年 | |
| (太清2年) | 南朝の梁に北朝東魏の有力者侯景が支配する河南13州をもって帰順。梁の武帝はこれを受け入れるが、反発した東魏の攻撃に敗北。10月、追い詰められた侯景は梁へ反乱を起こして首都建康に侵攻。 |
| 東ローマ帝国の将軍ベリサリウスが失脚。皇帝ユスティニアヌス1世による嫉妬とも、謀反を警戒されたともいわれる。イタリア半島での東ゴート王国の勢力が回復する。 | |
| 549年 | |
| (太清3年) | 侯景が梁の首都建康を攻め落とす。武帝は捕らえられて幽閉され、2ヶ月後に死亡。侯景は簡文帝を擁立し、実質侯景政権となる。 |
| 550年 | |
| ローマが再びトーテイラの軍勢によって陥落し破壊される。ローマ市はほぼ衰退。 | |
| 552年 | |
| ナルセス率いる東ローマ帝国軍がイタリア半島北方から南下し、トーテイラはローマを放棄して迎撃に向かう。ブスタ・ガロールム高原で両軍は衝突。ナルセスは弓兵を効率良く使いゴート軍を殲滅。 | |
| 7月 1日 | 負傷したトーテイラが死去。東ゴート王位はトーテイラの部下のテーイアが継ぎ、ローマ人捕虜や元老院の人質らを殺害。 |
| (承聖元年) | 侯景、梁皇族の蕭繹が派遣した王僧弁や陳覇先の軍勢に敗れ、擁立した簡文帝を殺し自ら即位して立て直しを図るも再敗北し、逃走中に殺害される。蕭繹が元帝として即位。 |
| (欽明天皇13年) | 百済の聖明王から仏僧と経典が贈られる。このため仏教公伝の有力な年代の一つとされている。天皇は群臣を集めて仏像を礼拝すべきかを問い、蘇我稲目は「諸国は礼拝しており、日本だけしないのはおかしい」と答え、物部尾輿と中臣鎌子は「蕃神を礼拝すれば、天地百八十の国神の怒りを招く」と反対した。天皇は稲目に仏像を預けて、信仰させる(なお物部氏の拠点にも寺院の遺構があることから、単純な崇仏是非論争ではなく、豪族同士の対立だったとする説もある)。 |
| 553年 | |
| イタリア半島南部のモンス・ラクタリウスで東ローマ帝国軍と東ゴート軍が衝突。テーイアが戦死し、東ゴート王国は事実上の滅亡。 | |
| 554年 | |
| (天成元年) | 西魏軍が傀儡として興した後梁の軍勢とともに江陵を攻め落とし、迎撃に出ていた元帝も捕らえられまもなく殺害。元帝を支えた王僧弁と陳霸先は北周との政策を巡って対立。 |
| 555年 | |
| (承聖元年) | 陳霸先が王僧弁を殺害し実権を握る。 |
| 557年 | |
| (永定元年) | 陳霸先が禅譲により即位し陳を興す。 |
| 558年 | |
| 突厥の有力者室点蜜と、娘婿でサーサーン朝の王ホスロー1世が、エフタルを攻撃。ブハラの戦い。エフタル傘下の多くの都市国家が突厥に奪われる。 | |
| 562年 | |
| (河清元年) | この年の4月に黄河と済水が澄んだため、北斉の武成帝がこれを瑞兆として「河清」と改元する。「河」は黄河のこと。黄河は上流から大量の黄土を運ぶため常に黄色く濁っており、水が澄むことは非常に珍しい。なお、かつての黄河はもっと北を流れていたため、現在の黄河の最下流はかつての済水の下流にあたる。 |
| 567年 | |
| この頃、突厥の室点蜜が、エフタルを攻め滅ぼし、その領土を奪う。ただし、その後もエフタルを称する勢力があったとみられる。 | |
| 568年 | |
| 突厥の室点蜜が、東ローマ帝国に使者を送り、貿易に関する盟約を交わす。 | |
| 574年 | |
| 2月 7日(敏達天皇 3年 1月 1日) | 用明天皇の子として厩戸皇子(聖徳太子)が誕生。 |
| 575年 | |
| 突厥の室点蜜が没し、玷厥(達頭可汗)が後を継ぐ。 | |
| 576年 | |
| (10月) | 平陽の戦い。北周の武帝が大軍を率いて長安を出立し、北斉の晋州攻略戦を開始する。晋州の各都市を攻略し、中心都市平陽に至る。対する北斉の後主(高緯)は、事態の深刻さを理解せず、馮淑妃と狩猟を楽しむなどしたため、対応が遅れ、平陽は陥落。 |
| (12月) | 平陽陥落を受けて、北斉の後主は、観戦を望む馮淑妃とともに平陽奪還のための軍を率いて出立。北周軍は撤退を開始したため、北斉軍が平陽を包囲。攻略一歩手前まで来るも、後主が馮淑妃に観戦させるための準備に時間をかけてしまい、攻略に失敗。北周の武帝が再び軍を率いて平陽に現れ、両軍は平陽郊外で激突。その様子を観戦していた馮淑妃が負けるのを恐れてしまい、後主とともに逃走してしまう。これにより北斉軍は総崩れとなり、大敗を喫する。この時、北斉の有力者の穆提婆(後主の乳母陸令萱の子)は北周軍に降伏。武帝はそのまま、北斉各地へと侵攻を継続。北斉の後主は、副都晋陽を安徳王高延宗に押し付け、帝位も長男の高恒に譲位して逃走。晋陽も陥落する。 |
| 577年 | |
| (3月) | 北周軍が北斉の都、鄴を攻め落とし、逃走していた後主ら皇族も北周軍に捕らえられ、北斉は滅亡。北斉の皇族らは北周武帝によって許され貴族とされたが、まもなく穆提婆が反乱を起こそうとした、という嫌疑で討伐され、それに連座して北斉皇族らのほとんども殺害された。北周武帝は華北を事実上統一。 |
| 578年 | |
| (2月) | 呂梁の戦い。陳の司空で歴戦の名将だった呉明徹は、猛将蕭摩訶とともに北周の徐州城を水攻めにするが、北周の武帝は王軌を派遣。王軌は水中に罠を仕掛けて陳の水軍を撃破し、退却した呉明徹を捕らえる。武帝は呉明徹を懐徳公に封じるが、すでに重病だった呉明徹はまもなく死去。蕭摩訶は帰還し、軍の重鎮となる。 |
| (6月) | 北周の武帝は突厥攻略のため出兵するが、まもなく病に倒れ、21日に死去。あとを宇文贇が継ぎ即位(宣帝)。しかし暴君であり、妻女にすら鞭で打つことを好み、一族や忠臣を相次いで粛清する。 |
| 579年 | |
| (4月) | 北周の宣帝は即位わずか1年弱で、帝位を息子に譲り(静帝)、自らは天元皇帝と称して、猟色にふけり、政治を皇后の父親である隋国公楊堅に一任。王朝滅亡を早める要因を作った。 |
| 581年 | |
| 3月 4日 | 北周の大将軍・隋国公の楊堅が静帝より禅譲を受けて隋王朝を興す。 |
| 585年 | |
| 4月 5日(敏達天皇14年 3月 1日) | 物部守屋が、疫病の流行は、異国の神(蕃神)である仏教を崇拝して、この国の神が怒っているためだとして、中臣勝海と仏教禁止の奏上を行う。 |
| 587年 | |
| 8月(用明天皇 2年 7月) | 仏教崇拝を巡って対立していた蘇我馬子と物部守屋の両勢力が衝突。馬子は諸皇子や諸豪族の軍勢を引き連れ勝利する。物部守屋は戦死。丁未の乱。 |
| (用明天皇 2年) | 蘇我馬子が、飛鳥寺建立を発願。 |
| 588年 | |
| (崇峻天皇 元年) | 百済から技術者の派遣を受けて飛鳥寺の建設がはじまる。飛鳥の地にあった飛鳥衣縫造祖樹葉の邸宅を壊した跡地を寺域とした。なお当時の寺の名前は法興寺とされる。 |
| 589年 | |
| 2月 2日(禎明3年/開皇9年1月12日) | 隋が、楊広、高熲、賀若弼、韓擒虎ら51万8000の兵を派遣して陳を滅ぼし中国を統一する。陳の後主は隋の軍勢を過小評価して抗戦の指示を出さず、隋の軍勢が首都建康に迫ってきてようやく軍を送り、白土崗で応戦させたがすでに遅く、後主だけでなく有力将の蕭摩訶・魯広達らも捕らえられた。隋の文帝は後主を含め陳の有力者らを許した。 |
| 592年 | |
| 12月12日(崇峻天皇5年11月 3日) | 蘇我馬子の意向を受けた東漢直駒による崇峻天皇弑逆事件が起こる。 |
| 593年 | |
| 5月15日(推古天皇元年 4月10日) | 厩戸皇子(聖徳太子)が推古天皇の摂政に就任。 |
| 596年 | |
| (推古天皇4年) | この頃、飛鳥寺がほぼ完成したと見られる。 |
| 599年 | |
| 5月26日(推古天皇7年 4月27日) | 大地震があり舎屋がことごとく破損したという。これを受け、四方に命じて地震の神を祭る。日本史上では最も古い地震被害の記録。 |
| 604年 | |
| 1月11日(推古天皇11年12月 5日) | 厩戸皇子(聖徳太子)が冠位十二階制度が定める。 |
| 5月 6日(推古天皇12年 4月 3日) | 厩戸皇子(聖徳太子)が十七条憲法を定める。ただし成立年は諸説がある。日本書紀に初出することや、その内容の文言の使い方から、奈良時代に日本書紀などと一緒に成立したという説も。 |
| 610年 | |
| この頃、ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフが、メッカのヒラー山で、ジブリール(大天使ガブリエル)の啓示を受けたとして、一族に独自の教義を広め始める。ムハンマドは以降も度々ジブリールの啓示を受けたとされる。 | |
| 隋の煬帝が京杭運河を完成させる。長江の南にある杭州から北上し、長江、淮河、黄河の三大河を横断して、天津に至るまでの総延長2500kmの大運河。いくつかの小運河をつなげ、文帝のときと煬帝のときで間を置いて実質わずか数年で完成させた。その工事には男女100万人以上が駆り出されたと言われ、特に工事の大半を推進した2代皇帝煬帝の評判は落ち、反乱が相次ぐ原因となった。一方で、南北の物流が盛んになり、次の唐王朝の繁栄の基礎にもなった。 | |
| 615年 | |
| この頃、ムハンマドの教えを受けた信者らが迫害を逃れてキリスト教徒の国アクスム王国へ逃れる。 | |
| 618年 | |
| 6月18日(武徳元年5月20日) | 李淵が隋の恭帝楊侑から帝位を禅譲されて皇帝に即位。唐を建国。隋は滅亡へと向かう。 |
| 619年 | |
| 王世充が隋の恭帝楊侗(恭帝楊侑の異母兄)に迫って帝位を禅譲させ皇帝に即位。鄭を建国。恭帝楊侗は翌月殺害される。 | |
| イスラムの開祖ムハンマドの最初の妻、ハディージャ・ビント・フワイリドが死去。ムハンマドはハディージャの親族で3番めの夫にあたり、彼女より年下だったが、ムハンマドにとって最愛の女性だったと言われる。ムハンマドはハディージャと結婚していたときは、他の女性を妻には迎えていない。ハディージャの産んだムハンマドの娘ファーティマの子孫が血統として続いている。 | |
| 620年 | |
| 12月30日(推古天皇28年12月 1日) | 「日本書紀」に「赤気」の記載がある。低緯度オーロラが目撃されたものか。 |
| 東ローマ帝国の公用語がラテン語からギリシャ語に変わる。 | |
| 621年 | |
| 王世充が唐の李淵に敗れ降伏。鄭は滅び、庶民に落とされた王世充も恨みを持っていた定州刺史独孤修徳により殺害される。 | |
| 622年 | |
| 5月15日(推古天皇30年 2月22日) | 厩戸皇子(聖徳太子)が病没。 |
| 7月16日 | ヒジュラ(聖遷)。メッカで布教を行っていたムハンマドは迫害を受けたため、信者を連れてヤスリブへ移住。のちにヒジュラ暦元年とされた。ヤスリブはマディーナ・アン=ナビー(メディナ)と改称。 |
| 624年 | |
| 3月17日 | バドルの戦い。メッカのクライシュ族と、メディナに移住したムハンマドが戦い、寡兵だったムハンマドが勝利。ムハンマドはメディナでの権威を確立。 |
| 625年 | |
| ウフドの戦い。メッカのクライシュ族が、各部族らを味方につけて、ムハンマド率いるメディナに反撃。当初はメディナ側が有利に進めていたが、後退したメッカ側をメディナ側が追撃したことで陣形が乱れ、メッカに味方したアラブ騎兵に襲撃を許してしまう。ムハンマドが負傷したことでメディナ側は敗走。 | |
| 626年 | |
| 7月 2日(武徳9年 6月 4日) | 唐王朝で玄武門の変が起こる。唐を建国した初代皇帝李淵の長男で皇太子の李建成と、次男で天策上将の称号を持つ李世民の対立から起きた李世民側のクーデターで、李建成が宮中へ参内した際に起こされた。李建成と弟の斉王李元吉が殺された。これを受けて李淵は李世民を後継者と定め、8月に譲位する。李世民は皇帝となったあと、この一件はあくまで家中の内紛であるとして臣下を処罰することはしなかったため、李建成側についていた人々も李世民に従い、貞観の治と呼ばれる繁栄を築くことになる。 |
| 627年 | |
| ハンダクの戦い。ウフドの戦いに勝利したメッカのクライシュ族は、メディナ攻略に乗り出す。これに対しムハンマドはメディナに塹壕(ハンダク)を築いて籠城。対陣が長期化したため、メッカ側は退却した。勢いを得たムハンマドはクライシュ族に味方したユダヤ教徒のクライザ族を殲滅。 | |
| ムハンマドがクライシュ族に味方したバヌ・ムスタリクとアル・ムライシで戦い勝利し、ムスタリクの部族とその財産を手に入れる。この戦いのあと従軍していたムハンマドの妻のアーイシャが、失くした首飾りを探していて軍の出発にはぐれてしまい、軍の兵士だったサフワーンが発見して軍に連れ戻る事件が起きる。この話が広まり、アリー・イブン・アビー・ターリブ(後の4代カリフ)が不義を疑って離縁すべきと主張したため、アーイシャやその父のアブー・バクルと対立するきっかけとなったと言われる。ムハンマドは天啓を受けて不義はなかったとして離縁を拒否した。 | |
| 628年 | |
| 3月 | ムハンマド、メッカ巡礼を企図。メッカのクライシュ族は、条件付きでこれを認め、両者はフダイビーヤで和議を結ぶ。 |
| 4月15日(推古天皇36年 3月 7日) | 推古天皇崩御。 |
| この年、真臘のイシャーナヴァルマン1世が扶南国を支配下に収め、これを滅ぼす。 | |
| 629年 | |
| 2月 2日(舒明天皇元年 1月 4日) | 蘇我蝦夷によって田村皇子が即位。舒明天皇。 |
| (貞観3年) | 玄奘三蔵法師がインドを目指し唐を密出国。高昌王麴文泰の支援を受けインドへ向かう。 |
| ムハンマド、多数の信者を連れてメッカを巡礼。フダイビーヤの和約を遵守したことから評価が上がり、メッカでもイスラムの信徒が増え始める。 | |
| 東ローマ皇帝ヘラクレイオスが、皇帝の称号を「インペラトル」から「バシレウス」に改める。公用語をギリシャ語にしたことと合わせて、後世、東ローマ帝国を古代ローマ帝国と切り離して、ギリシャ帝国、中世ローマ帝国、ビザンチン帝国などと称する要因ともなった。 | |
| 630年 | |
| (舒明天皇2年10月) | 舒明天皇、飛鳥岡に遷宮し岡本宮と称する。 |
| この年、メディナと同盟するフザーア部族と、メッカと同盟するバクル部族が紛争を起こし、ムハンマドはこれを機に、フダイビーヤの和約を破棄してメッカへ進軍。 | |
| この頃、吐蕃王のソンツェン・ガンポ(ティン・ソンツェン)がチベット高原を統一。 | |
| 632年 | |
| 6月 8日 | イスラム教の開祖、ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフが死去。指導者にムハンマドの親友でムハンマドの妻アーイシャの父親でもあるアブー・バクル・アッ=スィッディークが選出されカリフ(ムハンマドの代理人)となる。スンナ派ではこれ以降を正統カリフ時代とする。 |
| 634年 | |
| 8月23日 | イスラム教のカリフ、アブー・バクル・アッ=スィッディークが死去し、ウマル・イブン・アル=ハッターブが後を継ぐ。ムハンマドの4番目の妻ハフサの父親で、初期のイスラム共同体を支えた武将。ヒジュラ暦やシャリーア(イスラム法)を定めた人物。 |
| 636年 | |
| (舒明天皇8年6月) | 岡本宮が火災で焼失し、舒明天皇は田中宮に遷る。 |
| 正統カリフ第2代のウマル・イブン・アル=ハッターブがエルサレムを占領。人頭税(ジズヤ)を払うことを条件に、キリスト教徒とともにユダヤ教徒も保護する政策を行う。 | |
| 641年 | |
| 5月13日 | ウマル・イブン・アル=ハッターブの部下アムル・イブン・アル=アースがローマの属州アエギュプトゥス(エジプト)のアレキサンドリアを包囲。 |
| 11月 8日 | アレキサンドリア攻囲戦で、守備軍の東ローマ側指揮官キルスが降伏。 |
| 11月17日(舒明天皇13年10月 9日) | 舒明天皇崩御。 |
| 642年 | |
| 2月19日(皇極天皇元年 1月15日) | 皇極天皇即位。 |
| 643年 | |
| 4月(皇極天皇2年4月) | 板蓋宮が完成し、天皇が居を遷す。 |
| 12月20日(皇極天皇2年11月 1日) | 蘇我入鹿が巨勢徳多らと兵100名を派遣して山背大兄王の館を攻める。入鹿のいとこである古人大兄皇子を即位させるのに邪魔だったからとも言われる(ただし山背大兄王も入鹿のいとこであるため、皇族同士の後継者争いに蘇我入鹿が加担したという説も有力)。山背大兄王らは一旦、山中に逃れる。 |
| 12月30日(皇極天皇2年11月11日) | 山背大兄王が一族らとともに飛鳥寺で自害し上宮王家は滅亡。事件を知った蝦夷は入鹿の行動に怒り、自身を危うくすると嘆いたという。 |
| 644年 | |
| 11月 3日 | イスラム教の2代目カリフ、ウマル・イブン・アル=ハッターブがメディナのモスクで礼拝中、クーファの長官アル=ムギーラ・イブン・シュウバの奴隷アブー・ルウルウに襲われ、重症を負い、後継者のルールを定めた後死去。3代目カリフにムハンマドの親族で娘婿のウスマーン・イブン・アッファーンが就く。穏健派で大富豪としてイスラム共同体を支えた人物。 |
| 645年 | |
| 玄奘三蔵法師が唐に帰国。657部の経典を唐にもたらす。密出国については不問とされた。 | |
| 7月10日(皇極天皇4年 6月12日) | 乙巳の変が起こる。三国の調の儀式の最中、中大兄皇子と中臣鎌足によって、蘇我入鹿が暗殺される。外交儀式のさなかにクーデターが起きるという異様な点から、三国の調の儀式は史実かどうか疑問もあるが、外交は蘇我氏が担っていたため、蘇我氏と敵対したクーデター側が架空の外交儀式をでっち上げて事件を起こすという考え方にも無理がある。 |
| 7月11日(皇極天皇4年 6月13日) | 蘇我蝦夷が自邸に火を放って自害。蘇我本家が滅亡。この時、『国記』『天皇記』のうち『天皇記』が焼失したとも言われる。『国記』は船恵尺が焼ける前に拾い出したとされるが現存していない。一般に蘇我一族は滅亡したか権力を失ったかのように見られるが、実際にはこの後も大臣(オホマヘツキミ)の氏族として高い地位を保持しており、歴代天皇と婚姻関係をもち、また藤原不比等も蘇我氏から妻を迎えている。その不比等系藤原氏の台頭で蘇我氏は地位を失っていった(天皇家・藤原北家は蘇我氏の子孫でもある)。なお奈良県橿原市の菖蒲池古墳の近くに破壊された巨大な小山田遺跡が発見されたことから、蝦夷の墓は破壊され、入鹿の墓と合葬されたとする説もある。 |
| 7月29日(大化元年 7月 1日) | 日本最初の元号、大化が施行される。 |
| 10月 7日(大化元年 9月12日) | 舒明天皇の第一皇子で蘇我氏の血を引く古人大兄皇子が、乙巳の変後に隠棲していた吉野で、中大兄皇子の指示を受けたものらによって殺害される。日本書紀などでは古人大兄皇子が、蘇我田口川堀・物部朴井椎子・倭漢文麻呂・朴市秦田来津・吉備笠垂らと謀反を企てたが、吉備笠垂が密告したため露見し滅ぼされたとする。しかしこの謀反を企てた人物の殆どがその後も朝廷に仕えていることから、記録は古人大兄皇子を殺した口実だった可能性もある。この日付は密告日で殺されたのは11月30日ともされる。 |
| 646年 | |
| 1月22日(大化2年 1月 1日) | 乙巳の変で蘇我本宗家を滅ぼした朝廷は、より中央集権を目指した政治改革の「改新の詔」を発布する。これがいわゆる「大化の改新」。 |
| ニキウの戦い。アムル・イブン・アル=アースが東ローマ帝国の軍勢を破り、ローマの属州だったアエギュプトゥス(エジプト)は完全にイスラムの支配下に入る。 | |
| 647年 | |
| (大化3年) | 蝦夷に備えるため、越の国に渟足柵が作られる。 |
| 648年 | |
| 4月28日(大化4年 4月 1日) | 七色十三階冠の制度が施行される。冠位十二階の制度を改めたもので、十二階を大錦・小錦・大青・小青・大黒・小黒までの六階層に再編した上で、その上にさらに大織・小職・大繡・小繡・大紫・小紫までの六階層を追加し、一番下に建武の位を加えて十三階とした。 |
| (大化4年) | 蝦夷に備えるため、越の国に磐舟柵が作られる。記録上1回しか見つかっていない「都岐沙羅柵(つきさらのき)」も磐舟柵かその近辺とする説もあるが、出羽国の何処かにあったとする説もある。 |
| 649年 | |
| 3月(大化5年 2月) | 七色十三階冠の制度を改めて、冠位十九階の制とする。十三階の錦を花、青を山、黒を乙に変えてそれぞれ上下の2階級ずつにし、建武を立身と改めている。上位6階級はそのまま。より官僚制度に則したものにして、出世によって冠位が変わるようにした。地方の有力者も冠位を得るようになったとも言われる。 |
| 5月15日(大化5年 3月25日) | 乙巳の変で、中大兄皇子側に味方した蘇我倉山田石川麻呂が謀反の嫌疑をかけられ、討伐軍が派遣されたため、山田寺で妻子とともに自害。 |
| 7月10日(貞観23年 5月26日) | 唐の2代皇帝(太宗:李世民)が死去。国家制度を整え、国土を拡大し、臣下の諫言をよく聞き、「貞観の治」と呼ばれる安定して穏やかだった時代を生み出したことから、名君とされることが多い。呉兢が編纂した太宗と45名の臣下との間の言行録「貞観政要」は政治のバイブルとして長く使われた。 |
| 650年 | |
| 3月19日(大化6年2月 9日) | 穴戸国(のちの長門国)の国司草壁醜経から、麻山で捕らえた白雉が献上される。 |
| 3月22日(大化6年2月15日) | 白雉の元号に改元(1月1日に遡って改元)。白雉の瑞祥により。 |
| この頃、マオリ族のウイ・テ・ランギオラが嵐で漂流し南の氷の浮かぶ海に到達したという伝承がある。 | |
| 651年 | |
| サーサーン朝ペルシアのヤズデギルド3世が殺害され滅亡。 | |
| 第3代カリフのウスマーン・イブン・アッファーンが唐王朝にはじめて使者を送る。 | |
| 652年 | |
| 2月14日(白雉2年12月30日) | 難波長柄豊碕宮が完成し、孝徳天皇が遷都する。 |
| 653年 | |
| (白雉4年) | 中大兄皇子が難波宮から倭京へ戻るよう主張するが、孝徳天皇が同意しなかったため、中大兄皇子は皇祖母尊(先の皇極天皇のこと)、間人皇后、皇族、貴族らを連れて倭河辺行宮へと移る。孝徳天皇はこれを恨んで退位を願うようになる。 |
| 655年 | |
| (白雉5年) | 白雉の元号(年号)が使われた最後の年(白雉5年12月30日は、ユリウス暦で655年2月11日)。次の元号は686年に始まる朱鳥。 |
| 656年 | |
| 6月17日 | 第3代カリフのウスマーン・イブン・アッファーンが反乱を起こした兵士に邸宅で襲われ殺害される。一族を重用したことや、兵士の俸給を減らしたことで反発を買ったためと言われる。第4代カリフの地位をめぐり、ムハンマドのいとこで娘婿のアリー・イブン・アビー・ターリブと、3代目ウスマーンの近親者で有力武将だったウマイヤ家のムアーウィヤ・イブン・アビー・スフヤーンが争い、アリーが選出される。 |
| 12月 | ラクダの戦い。イスラム共同体内部のはじめての本格的内乱。第4代カリフのアリーと、ムハンマドの妻アーイシャら反アリー派が戦い、アリー側が勝利する。アーイシャがラクダの上に乗せた紅いハウダから指揮したことからこの名前がついている。アーイシャは敗北後、政治からは退き、ムハンマドの言行を伝える活動を行った。スンナ派ではアーイシャは尊敬される女性だが、シーア派は否定的に扱っている。 |
| 657年 | |
| 6月26日 | スィッフィーンの戦いが始まる。第4代カリフのアリーと、ムアーウィヤ・イブン・アビー・スフヤーンの間で起こった戦い。 |
| 7月27日 | スィッフィーンでアリー軍とムアーウィヤ軍が衝突。 |
| 7月30日 | アリー軍優勢の中、ムアーウィヤ軍の兵士が、槍の穂先に聖典クルアーン(コーラン)を掲げたためにアリー軍内部で動揺が走る。アリーは和平派に押し切られて講和を進めたため、反発した勢力が分裂しハワーリジュ派となる。アリーの勢力は低下し、逆にムアーウィヤは勢力を拡大する。 |
| 658年 | |
| (斉明天皇4年 4月) | 阿倍比羅夫が軍船180艘を率いて飽田・渟代の蝦夷征討を行う。飽田の蝦夷の長である恩荷に位を与える。渟代と津軽を郡領とする。さらに粛慎を攻め、羆2頭と羆の皮70枚を献上する。 |
| 第4代カリフのアリーが、分裂したハワーリジュ派をナフラワーンの戦いで打ち破る。 | |
| 659年 | |
| (斉明天皇5年 3月) | 阿倍比羅夫が軍船180艘を率いて飽田・渟代の蝦夷征討を行う。さらに津軽や胆振の蝦夷を従え、後方羊蹄(しりべし)に進出し政所を置く。後方羊蹄が現在のどこに当たるかは不明だが、江戸末期の松浦武四郎の探検時に尻別川付近とされて、同地の山は後方羊蹄山と名付けられた。 |
| (顕慶4年) | 唐の2代皇帝太宗の重臣であり、唐初期の有力者として「凌煙閣二十四功臣」の第一位にされている長孫無忌が、讒言によって失脚、自殺に追い込まれる。長孫氏は武川鎮軍閥(関隴集団)の名門で、長孫無忌の妹は、賢后として名高い、太宗の寵愛を受けた長孫皇后。 |
| (顕慶4年) | 唐が百済討伐の準備を整える。百済と親しい関係にあることから遣唐使の帰国が認められず。日本国内でも唐(及び新羅)と百済のどちらの立場に立つかで揉めた可能性がある。 |
| 660年 | |
| (斉明天皇6年 3月) | 阿倍比羅夫が軍船200艘を率いて粛慎征討を行う。その際、渡島の蝦夷に救援を求められたため、粛慎と交渉したが決裂し、幣賄弁島(へろべのしま)に渡って粛慎と戦い破ったが能登馬身龍が戦死した。渡島や幣賄弁島がどこに当たるのかは不明。津軽半島から北海道南西部にかけてのいずれかとも言われるが、幣賄弁島は樺太とする説もある。 |
| (顕慶5年 3月) | 唐は百済遠征を開始。蘇定方を神丘道行軍大総管として、総勢13万を動員。新羅もこれに呼応して金法敏・金欽純・金品日ら5万の兵力を派兵。 |
| (顕慶5年 7月) | 黄山の戦い。唐は百済に侵攻。百済の階伯らが応戦して新羅軍は足止めされたため、唐軍と新羅軍は一時対立するも、圧倒的兵力で百済の王都を包囲したため、義慈王は熊津に逃走し降伏。百済は滅亡し、唐は朝鮮半島南部を羈縻政策下に置き、熊津都督府を設置して旧百済領を傘下に置く。また新羅についても属国ではなく鶏林州都督府としてその領土を組み込み、形式上は国ではなくなる。唐軍は高句麗討伐のために北上。 |
| (顕慶5年 8月) | 旧百済領で鬼室福信、黒歯常之らが百済再興を目指して活動を開始し、各地で反乱が起きる。唐はこれに対応できなかったため、新羅が鎮圧に向かう。 |
| (顕慶5年10月30日) | 百済再興軍は新羅軍に大敗するが、鬼室福信・黒歯常之・僧道琛・余自信らは、倭国に救援を依頼し、倭国にいた太子豊璋を擁立して抵抗を続ける。 |
| ムアーウィヤ・イブン・アビー・スフヤーンがカリフを自称し始める。 | |
| 661年 | |
| 2月10日(斉明天皇7年 1月 6日) | 斉明天皇が西国へ向かうため難波宮を出立。 |
| 1月27日 | イスラム教第4代カリフのアリー・イブン・アビー・ターリブがクーファのモスクでハワーリジュ派のアブド=アルラフマーン・イブン・ムルジャムに暗殺される。ハワーリジュ派はムアーウィヤも狙うがこちらは失敗し、ムアーウィヤが事実上の5代目カリフとなる。ムアーウィヤは、世襲王朝ウマイヤ朝を開き、イスラム教正統カリフ時代が終了。世俗的イスラム帝国の時代へとシフトする。ウマイヤ朝に反発したアリー派は弾圧を逃れ、後にシーア派となっていく。 |
| 6月25日(斉明天皇7年 5月23日) | 済州島の耽羅国から王子の阿波伎らが倭国を訪れる。 |
| (斉明天皇7年 5月) | 倭国は百済の復興のため、朝鮮半島へ軍勢およそ1万を派遣する。 |
| 8月24日(斉明天皇7年 7月24日) | 斉明天皇が行幸先の筑紫朝倉橘広庭宮で崩御。 |
| 662年 | |
| (天智天皇元年 3月) | 倭国が、朝鮮半島へ軍勢およそ2万7千を派遣する。 |
| 663年 | |
| 10月 4日(天智天皇2年 8月27日) | 白村江の戦い。百済の復興のため、朝鮮半島へ派遣された倭の軍勢と百済遺臣勢力が、唐・新羅連合軍と衝突。 |
| 10月 5日(天智天皇2年 8月28日) | 倭軍は4度の攻勢にも関わらず大敗し、半数近くを失って退却。百済復興を図る遺民らも多くが日本列島へと逃れる。 |
| 664年 | |
| 10月 4日(天智天皇2年 8月27日) | 冠位十九階の制を改め、冠位二十六階の制に改める。十九階の花を錦に変え、錦・山・乙の大小各冠それぞれ上下2階層を上中下3階層にし、最下層の立身を大建・小建の2階層とした。国家体制が整うに連れて官職が増えたためか。 |
| 668年 | |
| 2月20日(天智天皇7年 1月 3日) | 中大兄皇子が即位(天智天皇)。661年に斉明天皇崩御後、称制としてすぐに即位していないため、年号的には即位年は天智天皇7年となる。なぜすぐに即位しなかったのかは諸説あり、蘇我氏との関係が強かった、有力者の支持がなかなか得られなかった、女性関係の問題(特に孝徳天皇の皇后で天智の同母妹の間人皇女との関係)、「万葉集」の中皇命の記載から間人皇女が即位していた説などもあるが、定説がなく不明点が多い。 |
| (総章元年 8月) | 唐と新羅の連合軍による攻勢によって平壌城が陥落し、高句麗が滅亡。 |
| (総章元年 9月) | 唐が平壌城に安東都護府を設置する。 |
| (天智天皇7年) | この年、僧の道行が草薙の剣を盗んで新羅に向かおうとするが、風雨に遭い戻ってきたという。 |
| (天智天皇7年) | この年、近江令が制定されたといわれる。日本初の律令という見方もある(ただし令のみ)。「藤氏家伝」と「弘仁格式」にはあるが「日本書紀」には見られないことから存在しないという説もあり、また令に相当する法令はあったとする説もある。 |
| 669年 | |
| 12月31日(総章2年12月 3日) | 唐の建国に大きく貢献した名将の李勣が死去。 |
| 671年 | |
| 6月 7日(天智天皇10年 4月25日) | 朝廷が漏刻(水時計)を設置し、鐘鼓を鳴らしてはじめて時を知らせる。この日はグレゴリオ暦に換算すると6月10日になるため、時の記念日は6月10日になるが、この時代はグレゴリオ暦は存在していない(ユリウス暦)。漏刻自体はもっと前から存在している。 |
| 672年 | |
| 1月 7日(天智天皇10年12月 3日) | 天智天皇が崩御。死の少し前に、同母弟の大海人皇子に皇位を譲ろうとしたが、大海人皇子は蘇我安麻呂の忠告からこれを受けず、大友皇子を推薦したとされている。天智天皇も実子の大友皇子を後継に望んでいたとされる。 |
| 1月 9日(天智天皇10年12月 5日) | 天智天皇の崩御により、第一皇子の大友皇子が後継者となる。明治3年に諡が贈られ弘文天皇として39代目の天皇に列せられたが、天皇に即位していたがどうかは定かではない。 |
| 7月24日(天武天皇元年 6月24日) | 大海人皇子が吉野を出立し東国へと向かう。壬申の乱が勃発。乱の原因は諸説あってはっきりしない。各地の有力者が大海人皇子に味方する。 |
| 7月26日(天武天皇元年 6月26日) | 大友皇子は群臣と軍議を開く。天智天皇時代から近江朝廷では少人数の大臣で構成されていたため、それ以前にはあった多数の群臣(マヘツキミ)との協議はなく、少数の大臣と対策を諮り、各地の支援を得にくかったとみられる。 |
| 7月31日(天武天皇元年 7月 2日) | 大海人皇子側が、美濃で集めた東国の兵力を大和と近江へ向けて派兵。大友皇子側の主力も出兵。 |
| 8月20日(天武天皇元年 7月22日) | 瀬田橋の戦いで大海人皇子軍が大勝。 |
| 8月21日(天武天皇元年 7月23日) | 壬申の乱に敗れた大友皇子が自殺。 |
| 673年 | |
| 3月20日(天武天皇2年 2月27日) | 大海人皇子が即位。天武天皇。多くの史料では天智天皇の同母弟(「日本書紀」では生年の記載がないため異父兄という説も一部にある)。 |
| (天武天皇2年) | この頃までに外位の制度が整備される。中央の有力者に与える内位に対し、地方出身者や低身分出身者の在庁官人に与えられたと考えられる。 |
| ウマイヤ朝がコンスタンティノポリスの攻略戦に乗り出す(687年まで)。 | |
| 676年 | |
| このころ、飛鳥の都の北側に大規模な条坊制の都の建設が始まる。後の藤原京(新益京)。 | |
| この年の11月ころ、新羅軍が唐の薛仁貴を破って唐勢力を朝鮮半島から駆逐し、半島を統一する。 | |
| 679年 | |
| 1月~2月(天武天皇7年12月) | 筑紫国で大地震。幅2丈(約6m)長さ3000丈(約10km)の地割れが生じ、上の住居ごと移動したという。豊後では五馬山が崩れて多数の温泉が出る。土塁や古墳の破損状態、噴砂痕などから、水縄断層が動いたと考えられる。 |
| 680年 | |
| 10月10日 | カルバラーの戦い。ウマイヤ朝の2代目カリフであるヤズィード・イブン・ムアーウィヤ・イブン・アブー・スフヤーンが、正統カリフ4代目アリーの子でムハンマドの孫であるフサイン・イブン・アリー一行72人を反乱防止の目的で3000の兵で襲撃し殺害。アリー支持派であったシーア派がスンナ派と決定的に敵対することになった事件。 |
| (天武天皇9年 7月) | 駿河国のうち2郡をもって伊豆国が設置される。 |
| 684年 | |
| 10月 (天武天皇13年) | 彗星が目撃される。ハレー彗星か。 |
| 11月(天武天皇13年10月) | 八色の姓が制定される。真人・朝臣・宿禰・忌寸・道師・臣・連・稲置の8つの姓で、地位と結びついており、真人・朝臣・宿禰・忌寸の4つを皇族や皇族に近い氏族に与えた。従来からあった臣・連・伴造・国造はそのまま使われている。のちに氏姓制度が広まると、朝臣以外は消滅した。 |
| 11月26日(天武天皇13年10月14日) | 白鳳大地震。西日本で大きな揺れがあり諸国の官舎、百姓倉屋、寺社が多数倒壊。人民と家畜の死傷多数。土佐沿岸は大津波に襲われ田苑50余万頃が海没。伊予や紀伊で温泉が止まる。東方より鳴動があったこと、伊豆島で300余丈が隆起(もしくは噴火)。南海トラフの南海大地震だが、地質調査で東海、東南海地震も同時に起きたという説も有力。 |
| 685年 | |
| 4月 (天武天皇14年 3月) | 信濃国で降灰があり草木が皆枯れるという。浅間山など周囲のいずれかの火山の噴火とみられる。 |
| 686年 | |
| 8月14日(朱鳥元年 7月20日) | 朱鳥の元号が制定される。前後に元号のない期間があり、唐突に定められ、同年だけ使われた。元号を定めた理由は不明だが、重病となった天武天皇の回復を祈願したものとも言われる(天武天皇は赤色を好んだとされる)。 |
| 10月 1日(朱鳥元年 9月 9日) | 天武天皇崩御。権力を自らに集中させて政治を見る「皇親政治」を行った数少ない天皇。「天皇」の称号をはじめて使ったとされているほか、国号を「日本」としたとする説もある。律令体制や位階制度、恒久的な都の建設、国家神道の確立、仏教保護など、のちの日本国家体制の基礎を作った。 |
| 10月24日(朱鳥元年10月 2日) | 天智天皇の第2子である川島皇子が、天武天皇の第3子大津皇子を謀反を企てたとして密告。大津皇子は捕らえられ、伊吉博徳、中臣意美麻呂、巨勢多益須、行心ら30人余りも捕らえられる。 |
| 10月25日(朱鳥元年10月 3日) | 大津皇子が自害。妃の山辺皇女が殉死。他の連座して捕らえられたものの多くは赦される。実際に謀反の企てがあったのかは定かではない。大津皇子は「日本書紀」で優れた人物と称賛されている。 |
| 689年 | |
| 5月 7日(持統天皇3年 4月13日) | 皇位継承第一位であった草壁皇子が死去。すぐに即位しなかった理由は定かではないが、日本書紀などで自殺した大津皇子が称賛されているのに対して目立たず、皇位継承者としての支持がなかなか得られなかった可能性がある。そのためか天武天皇の殯を繰り返し行い、草壁皇子がその喪主となっている。 |
| 7月21日(持統天皇3年 6月29日) | 飛鳥浄御原令が発布される。律令のうちの令だけと考えられる。天武天皇の時から進められ、日本最初の律令制度とする見方もある。 |
| 690年 | |
| 2月14日(持統天皇4年 1月 1日) | 天武天皇の皇后である鸕野讚良皇女が即位。持統天皇。自身の息子で天武天皇の皇位継承者だった草壁皇子が死去し、その子軽皇子がまだ幼かったことから、自身が即位したとされる。そのため年号上は持統天皇4年に当たる。 |
| 10月16日(天授元年11月 9日) | 唐の太宗の側室で、高宗の皇后だった武照(武則天・則天武后)が自ら即位して皇帝となり、国号を周と改める。武周王朝の成立。中国では唯一の女帝。 |
| (持統天皇4年) | 唐から訪日新羅使とともに大伴部博麻が帰国する。白村江の戦いに参加した兵士で、捕虜として唐に送られた後、唐の日本侵攻計画を聞き、日本に知らせるための遣唐使らの帰国資金を得るため自ら奴隷に身売りした人物。持統天皇はその愛国心を称えて褒賞し勅語を与えた。 |
| 694年 | |
| 12月27日(持統天皇8年12月 6日) | 藤原京に遷都。持統天皇が飛鳥浄御原宮から藤原京(新益京)に移る。藤原京は面積上は古代最大の都で平城京や平安京よりも規模は大きい。一方で平城京や平安京と違い、最縁部に城壁がなく、大路の幅も狭い。王宮(藤原宮)は都の中央付近にあった。それまで代ごとに頻繁に変わっていた都をはじめて恒久的に置き換えたもので、中国の都城のように条坊制が整備された。平城京遷都までに完成しなかったとみられる。藤原京の名前は大正2年に歴史学者喜田貞吉が「藤原宮」から称したもので、「日本書紀」では新益京(あらましのみやこ・しんやくきょう)と称している。 |
| 697年 | |
| 8月22日(文武天皇元年 8月 1日) | 文武天皇が即位。15歳という若年で即位したはじめての天皇。そのため祖母の持統天皇が初めて「太上天皇」と称して後見した。これは他の成人皇族の即位を抑える目的もあったとみられる。母親の阿閇妃は「皇太妃」とされた(のちの元明天皇)。 |
| ウマイヤ朝が北アフリカ地中海沿岸をほぼ制圧。 | |
| 698年 | |
| 大祚栄が唐(武周朝)から独立し、旧高句麗の東牟山で震国を建国。後に唐へ入朝した際に与えられた称号「渤海郡王」、さらに3代大欽茂が得た「渤海国王」から渤海国と呼ばれる(渤海という地名自体は中国の地名)。大祚栄の出自ははっきりしていないが、のちの新羅の孝恭王の唐の昭宗宛国書などからも、大祚栄は高句麗に仕えた靺鞨人の子孫と見られる。渤海の主な民族は靺鞨人で、領域は朝鮮北部、満州、沿海州にまたがる広大な地域となる。 | |
| 700年 | |
| 4月 3日(文武天皇4年 3月10日) | 法相宗の僧・道昭がその遺言によって火葬される。記録上は日本初の火葬とされる。 |
| この頃、ザガワ人の王セフによって、チャド湖の付近に王都ンジミが建設され、遊牧生活から定住交易生活をするようになる。カネム・ボルヌ帝国のはじまり。 | |
| 701年 | |
| 5月 3日(文武天皇5年 3月21日) | 新たに「大宝」の元号を施行する。それ以前の元号は一時的なもので、制度上の実態も不明なのに対し、大宝からは文書にも記されるようになり、途絶えることなく現代まで続くことになる。なお典拠は『易経』としているが、対馬から金が献上されたことによる(対馬ではない説もある)。 |
| 5月 8日(大宝元年 3月26日) | 大宝地震。丹波国(のちの丹後国)で大きな地震が起こり、3日にわたって揺れるという。若狭湾一帯を大津波が襲ったとみられる伝承が多数あるが詳細は不明。 |
| 9月 9日(大宝元年 8月 3日) | 大宝律令が完成。二官八省(太政官・神祇官の二官、中務省・式部省・治部省・民部省・大蔵省・刑部省・宮内省・兵部省の八省)の行政機関を設立。日本の国号が制定され、元号が本格導入される。 |
| 704年 | |
| 6月16日(大宝4年 5月10日) | 元号を大宝から慶雲に改元。藤原京で瑞兆を表す雲が現れたことから。漢籍の典拠としては『文選』『晋書』による。 |
| 705年 | |
| 2月22日(神龍元年 1月24日) | 武照(武則天)が退位し、彼女によって皇帝の地位を失っていた中宗が復位する。武周王朝は終り、唐王朝が復活。武照については、儒教の影響などから女性の権力化が否定的に扱われること、武照が一族や張易之・張昌宗兄弟を重用したことなどで評価が低い。一方で、後の開元の治に活躍する有能な人材も積極的に登用された他、支持基盤の弱さから低い身分からも人材を獲得すべく科挙制度が発達した。また国内的には比較的安定し平穏な時代でもあった。武照は独自の漢字を創作したことでも知られる。 |
| 707年 | |
| 8月18日(慶雲4年 7月17日) | 阿閇皇女(皇太妃)が即位。元明天皇。草壁皇子の妃で、文武天皇・元正天皇らの母親。息子の文武天皇が崩御したため、幼い孫の首皇子が成長して確実に皇位を継承するため、自身が中継ぎとして即位した。 |
| 708年 | |
| 6月 3日(和銅元年 5月11日) | 和同開珎(銀銭)の使用が始まる。 |
| 709年 | |
| 9月 9日(和銅2年 8月 2日) | 和同開珎の銀銭をやめ、銅銭のみの使用が決まる。 |
| 710年 | |
| 4月13日(和銅3年 3月10日) | 藤原京から平城京に遷都。まだ未完成の状態。 |
| 7月 3日(景龍4年 6月 2日) | 唐の第6代皇帝中宗が、韋皇后と娘の安楽公主の手で毒殺される。韋皇后が淫行を告発されたためとも、武則天に倣って権力掌握を画策した韋皇后と安楽公主が起こした政変とも言われる。韋皇后は温王李重茂を皇帝に擁立。武則天の即位と合わせて「武韋の禍」と呼ばれる。 |
| 7月21日(唐隆元年 6月20日) | 唐の太平公主と臨淄王李隆基(後の玄宗)が政変を起こし、韋皇后と安楽公主を殺害して両者の身分を庶人に落とす。 |
| 7月25日(唐隆元年 6月24日) | 唐の皇帝の李重茂は退位に追い込まれる(殤帝)。李重茂は元の温王に戻され、相王李旦(睿宗)が皇帝に復位。 |
| 睿宗は、吐蕃などの西方異民族に対応するため、はじめて亀茲に安西節度使を置く。軍事権と徴税権をもった地方官で、後に各地に置かれて軍閥となり、安禄山の乱や、五代十国の騒乱時代を生むことになる。 | |
| 711年 | |
| 7月19日 | ウマイヤ朝のターリク・イブン・ズィヤードが、イベリア半島の西ゴート王国と戦い、国王ロデリックは戦陣で消息不明となる(戦死したという説が有力)。翌年にかけて残存貴族も処刑されるなどして西ゴート王国は滅亡。ウマイヤ朝がイベリア半島を制圧する。 |
| (和銅4年10月) | 蓄銭叙位令が出される。銭の流通を促進する目的で、銭を貯めると位階を与えることを決めた法令。 |
| 712年 | |
| 3月 9日(和銅5年 1月28日) | 古事記が完成し、太安萬侶によって元明天皇に献上される。天武天皇の命で、記憶力に優れた稗田阿礼が「帝紀」「旧辞」を誦習し、それを太安万侶が編纂したとされる。「日本書紀」とともに記紀と呼ばれるが、内容はかなり異なる。日本書紀が勅撰であるのに対し、古事記は正史にその成立の記録がなく、序文の書き方が不自然なこと、稗田阿礼の記載に身分である「姓」がなく(太安万侶は「朝臣」とある。稗田阿礼には女性説もある)当時の氏族名鑑「新撰姓氏録」にも稗田氏がないこと(つまり相当身分が低いか実在しない)など奇妙な点が多く、平安から鎌倉頃に作られた「偽書」という説も古くからある(それでもかなりの古典)。一方で、神話の文学性は非常に高い。 |
| 715年 | |
| 10月 3日(和銅8年 9月 2日) | 元明天皇が、娘の氷高内親王に皇位を譲り(元正天皇)、自身は太上天皇となる。女性天皇から女性天皇への譲位は現在まで唯一の例(血筋は天武天皇、草壁皇子に続くので男系女帝だが、元明天皇は男性孫にではなく娘に生前譲位しているため、この部分を女系相続とする見方もある)。元号は霊亀に改元。 |
| 718年 | |
| 西ゴート王国の貴族で、ウマイヤ朝の攻撃から逃れたペラーヨが、この頃、イベリア半島北部のアストゥリアスにアストゥリアス王国を建国する。一般にはこれをレコンキスタの始まりとしている。 | |
| 720年 | |
| 4月11日(養老4年 2月29日) | 大隅国国史の陽侯史麻呂が殺害されたという報告が太宰府から朝廷にもたらされる。朝廷は討伐を決定。いわゆる隼人の乱の始まり。 |
| 4月19日(養老4年 3月 4日) | 朝廷は大伴旅人を征隼人持節大将軍に、笠御室と巨勢真人を副将軍に任命。 |
| 7月26日(養老4年 6月17日) | 隼人征討軍は隼人の立て籠もる7城のうち5城を攻め落とすが、曽於乃石城と比売之城は攻め落とせず膠着。 |
| 9月 9日(養老4年 8月 3日) | 藤原不比等が死去。藤原鎌足の次男(古くから天智天皇のご落胤説がある)。最初の正妻は蘇我氏。鎌足の子孫の内不比等の子だけが藤原氏を名乗れたため、藤原氏の祖でもある。養老律令の編集に関わった。ご落胤説では母親が車持氏のため『竹取物語』に登場する車持皇子のモデルの可能性がある。 |
| 9月18日(養老4年 8月12日) | 藤原不比等死去の報を受け、征隼人持節大将軍の大伴旅人も都へ呼び戻される。隼人征討は副将らが継続。 |
| 11月 2日(養老4年 9月28日) | 陸奥国で大規模な蝦夷の反乱が起きたという報告が朝廷に伝わる。反乱によって按察使の上毛野広人が殺害される。 |
| 11月 3日(養老4年 9月29日) | 長屋王の指示で、多治比縣守が蝦夷反乱に対する持節征夷将軍に、副将軍に下毛野石代が、持節鎮狄将軍に阿倍駿河が任命されて、遠征軍が派遣される。 |
| (養老4年) | この年、「日本書紀」が成立したとされている。漢文で書かれた編年体の「正史」で六国史の第一。「帝紀」「旧辞」などの和書、各家伝、漢籍、百済三書、個人の記録などを元にし、舎人親王を長とした編纂組織によってまとめられた。 |
| 721年 | |
| 5月(養老5年 4月) | 蝦夷の反乱討伐のために出兵していた多治比縣守らが都に帰還。 |
| 8月 4日(養老5年 7月 7日) | 隼人征討を終えて派遣されていた副将らが都に帰還。 |
| 722年 | |
| 6月13日(養老6年閏4月25日) | 百万町歩開墾計画が実施される。陸奥地方の開発計画。当時日本全国の開墾地ですら百万町歩もないため、陸奥だけでこれほどの開墾は不可能であり、一種のスローガンとも見られている。 |
| 723年 | |
| 5月25日(養老7年 4月17日) | 三世一身法発布。灌漑施設と共に開墾すれば本人・子・孫の3代、既存の灌漑施設を利用して開墾すればその人1代に限り私有を認めるという、開墾奨励法令。前年の百万町歩開墾計画の具体的法令とも考えられる。20年余りで開墾地を捨てるものが相次ぎ、効力を失ったとされる。戦後の通説では、公地公民制が崩壊するきっかけになったとされてきたが、改新の詔で私有地を禁じたのは形式のみで実際には私有地は認められており、公地公民制は、マルクス史観の「アジア的生産様式」理論に影響を受けたもので、実際の考古学・文献史学の研究結果と異なるとする見方もある。 |
| 724年 | |
| 3月 3日(神亀2年 2月 4日) | 聖武天皇が即位。直後に母親の藤原宮子(不比等の娘)を「大夫人(おおみおや)」と尊称するよう勅を出すが、これに対し翌月長屋王が、公式令を理由に「皇太夫人」とすべきだと反対。聖武天皇はそれに従ったが、これが天皇と藤原氏の不信を買い、のちの長屋王の変の遠因になったとされる(辛巳事件)。 |
| 728年 | |
| 10月20日(神亀5年 9月13日) | 皇太子の基王が病死。 |
| 729年 | |
| 3月14日(神亀6年 2月10日) | 長屋王の変。漆部造君足と中臣宮処連東人が長屋王が密かに左道を学び国家を傾けようとしていると密告(前年の皇太子死去のことを指していると思われる)。天皇と藤原氏は三関を封鎖させた上で、藤原宇合・佐味虫麻呂・津島家道・紀佐比物に六衛府の兵を率いさせて長屋王邸を包囲。 |
| 3月15日(神亀6年 2月11日) | 天皇、舎人親王・新田部親王・多治比真人池守・藤原武智麻呂・小野牛養・巨勢宿奈麻呂を長屋王邸に派遣して問責を行う。 |
| 3月16日(神亀6年 2月12日) | 長屋王と吉備内親王、二人の子の膳夫王・桑田王・葛木王・鉤取王が自殺。一方、長屋王の側室であり藤原不比等の娘であった藤原長娥子とその子や、長屋王の兄弟姉妹らは、みな赦免されており、連座して流罪となったものも上毛野宿奈麻呂ら7名と少なく、大赦も行われている。告発に関わった中臣宮処東人、漆部君足、漆部駒長は賞され位を与えられた。事件は藤原四兄弟の陰謀という側面があるが、長屋王は開墾や反乱鎮圧などに積極政策を進めて功績も大きい一方、非常に大きな権力を持ち、自身を特別扱いしていたこともあって敵が多く、天皇の夫人藤原光明子と、その子基王の地位を巡って批判的だったことから、天皇の不満も買っていたとみられる。 |
| 732年 | |
| 10月10日 | トゥール・ポワティエ間の戦い。イベリア半島のウマイヤ軍がピレネー山脈を超えてフランク王国へ侵攻。迎撃に出た宮宰カール・マルテルの軍勢と衝突し、ウマイヤ軍の指揮官アブドゥル・ラフマーン・アル・ガーフィキーが戦死したため、ウマイヤ軍は退却。勝利したカール・マルテルは権力を強め、息子ピピン3世の代にカロリング朝を興すことになる。 |
| 734年 | |
| 5月14日(天平6年 4月 7日) | 大地震。建物多数が倒壊し、圧死者多数。朝廷、諸国に使者を出して神社の被害を調べる。畿内の地震だったのか、南海トラフのような広域地震だったのかは不明。 |
| 5月19日(天平6年 4月12日) | 天皇、諸国に使者を出して神社の地震被害を調べる。 |
| 5月24日(天平6年 4月17日) | 天皇、陵墓と功ある王墓の地震被害を調べる。詔勅を出して、政治の欠失を認め、改めるよう指示。 |
| 5月28日(天平6年 4月21日) | 天皇、京と畿内各所に使者を送って人民の疾苦を調べる。 |
| 8月15日(天平6年 7月12日) | 天皇、地震を受けて大赦を行う。 |
| 735年 | |
| 新羅の使者が来訪し、国号を変更したことを伝えたため、朝廷は無断で国号変更をしたことを責め、使者を追い返す。 | |
| 九州北部で天然痘の流行が始まり、九州全土へと拡大する。異国船から広がったとも言われる。 | |
| 9月14日(天平7年 8月23日) | 大宰府は九州で拡大する天然痘を受けて、管内の調の免租を朝廷に申請し受理される。 |
| 736年 | |
| (天平8年 2月) | 遣新羅使を派遣。前年に続き両国関係は悪化しており、正使としての待遇を受けられず帰国の途につく。この派遣の最中に、使節一行に天然痘感染者が相次ぐ。随員の伊吉宅麻呂は、新羅へ向かう途中に壱岐で死去、正使阿倍継麻呂も翌年1月、帰国途中に対馬で死去。 |
| 737年 | |
| 1月(天平9年 1月) | 遣新羅使の生存者一行が帰国し京に入る。この頃、本州各地でも天然痘が広がり始め、新羅と関連付けられるようになった。 |
| 5月25日(天平9年 4月17日) | 藤原房前、天然痘で死亡。藤原氏主流北家の祖。 |
| 7月25日(天平9年 6月23日) | 中納言多治比縣守が死去。天然痘によるものとの説もある。 |
| 7月28日(天平9年 6月26日) | 太政官から疫病対策の指針が全国へ出される。症状に詳しく、治療法の記載、米の支給などを指示。この頃、朝廷を構成する多くの貴族が死亡したため、朝政の停止を余儀なくされる。 |
| 8月17日(天平9年 7月13日) | 藤原麻呂、天然痘で死亡。京家の祖。 |
| 8月29日(天平9年 7月25日) | 藤原武智麻呂、天然痘で死亡。死の直前、正一位左大臣を贈られる。南家の祖。 |
| 9月 3日(天平9年 8月 5日) | 藤原宇合、天然痘で死亡。式家の祖。 |
| 9月(天平9年 8月) | 天然痘の大流行を受けて、朝廷は九州のみに認めていた調の免租を全国に拡大。 |
| 天然痘による日本国内での死者は100万人から150万人(当時の日本の人口の25~35%)という説もある。国内で広がった疫病では、最も犠牲者の比率が高かった疫病の一つ。また詳細に記録された最初の疫病。貴族・官人が多く死亡したため朝廷が機能しなくなり、生き残った大納言橘諸兄が政権首班となって権力を握ることになる。また多くの農民が死亡して農生産力が低下したため、のちの開拓私有制度(墾田永年私財法)へとつながったとされる。 | |
| 738年 | |
| 7月30日(天平10年 7月10日) | 長屋王の変で、長屋王を密告した中臣宮処東人(この時右兵庫頭)が、もと長屋王に仕えていた左兵庫少属の大伴子虫と囲碁を打っている最中、長屋王のことで口論となり、大伴子虫の手で惨殺される。長屋王の変からかなり経っていること、身分違い同士で囲碁を打っていることから、単に敵討ちとも言えないが、この事件を書いた「続日本紀」には東人の密告を「誣告」としているため、「続日本紀」が編纂された平安初期には密告は虚偽であるという認識が広まっていたのは確か。 |
| 740年 | |
| 9月28日(天平12年 9月 3日) | 九州で大宰少弐藤原広嗣が挙兵したとの報が入り、大野東人を大将軍として征討軍の編成が命ぜられる。 |
| 10月 9日(天平12年 9月14日) | 板櫃川の戦いが始まる。広嗣軍は敗走。 |
| 11月16日(天平12年10月23日) | 藤原広嗣が逃亡潜伏していた値嘉嶋(五島列島の宇久島)で安倍黒麻呂に捕らえられる。 |
| 11月24日(天平12年11月 1日) | 藤原広嗣が斬首される。 |
| 741年 | |
| 3月 5日(天平13年 2月14日) | 国分寺・国分尼寺建立の詔が出される。 |
| 743年 | |
| 6月23日(天平15年 5月27日) | 墾田永年私財法が発布される。開墾をしたものに永年の私有を認めるという法令。 |
| 11月 5日(天平15年10月15日) | 聖武天皇紫香楽に大仏造営の発願を行う。 |
| 745年 | |
| 2月26日(天平17年 1月21日) | 民衆への布教と様々な社会事業を行った行基が日本最初の大僧正になる。大仏建立に協力したことが評価され。 |
| 6月 1日(天平17年 4月27日) | 美濃国で大きな地震が起こり、三日三晩揺れるという。正倉や寺院の堂塔、民衆の盧舎が大きな被害を受ける。以降20日間にわたって地震が続く。液状化とみられる現象もあったという。 |
| 6月12日(天平17年 5月 8日) | 地震を受けて、大安寺・薬師寺・元興寺・興福寺で読経を行う。 |
| 747年 | |
| 6月15日 | アブー・ムスリムがアッバース家を支持し、ホラーサーンの都市メルヴでウマイヤ朝に対して武装蜂起。いわゆるアッバース革命のはじまり。ウマイヤ朝はイスラムで初めて世襲化した王朝で、アッバース家はムハンマドの叔父の子孫に当たる。 |
| 749年 | |
| 8月 | ウマイヤ朝がアッバース家を弾圧。当主イブラーヒームを処刑。 |
| 9月 | アブー・ムスリム軍がクーファまで進出。 |
| 11月 | アッバース家の生き残りであるアブー・アル=アッバースがクーファでカリフに選ばれる。 |
| 12月 8日(天平勝宝元年10月24日) | 大仏の鋳造が完成。 |
| 750年 | |
| 1月25日 | ザーブの戦い。ウマイヤ朝のマルワーン2世がアッバース家討伐のために遠征するも、アッバース軍のアブドゥッラー・イブン・アリーに大敗。マルワーンはシリア、パレスチナを経てエジプトへと落ち延びる。 |
| 8月 5日 | ウマイヤ朝のマルワーン2世がエジプトでアッバース軍の兵に殺害され、ウマイヤ朝は崩壊へと進む。 |
| 751年 | |
| フランク王国の宮宰ピピン3世がメロヴィング朝のキルデリク3世を廃して自ら王位に即き、カロリング朝を開く。 | |
| 753年 | |
| 5月26日(天平勝宝4年 4月 9日) | 東大寺蘆舎那仏の開眼供養。 |
| 755年 | |
| 12月16日(天宝14年11月 9日) | 唐の節度使の安禄山が、唐王朝最大の反乱、安史の乱を起こす。李林甫の死後、宰相となった楊国忠との対立が最大の要因。安禄山の軍勢は洛陽へ向けて侵攻。玄宗皇帝は、信頼していた安禄山の反乱を信じなかったが、事実と知ると安禄山の妻の康氏と、安禄山の長男安慶宗を処刑。西域で活躍していた高仙芝や封常清、張介然、後に名将と讃えられる郭子儀やその配下の李光弼らが勅命を受けて迎撃に向かう。 |
| 756年 | |
| 7月15日(天宝15年 6月14日) | 馬嵬事変。安禄山の乱を受けて蜀へと落ち延びる途中の玄宗一行が、馬嵬に到着した際、陳玄礼や兵士らが、乱の原因を作ったとして宰相の楊国忠を襲って殺害。楊国忠の息子の楊暄や、楊貴妃の姉の韓国夫人らも殺害し、さらに、楊貴妃を殺すよう玄宗に迫る。玄宗は楊貴妃は無関係と拒否するも、事態の悪化を訴える韋諤や高力士の説得に玄宗は応じるしかなくなり、楊貴妃は高力士によって縊死させられた。 |
| 757年 | |
| 1月29日(聖武2年 1月 5日) | 燕王朝初代皇帝となった安禄山が次男の安慶緒に殺される。安禄山が後継者から安慶緒を排除して、側室が生んだ3男の安慶恩にしようとしたためとされる。 |
| 1月30日(天平勝宝9年 1月 6日) | 橘諸兄が死去。 |
| 7月18日(天平宝字元年 6月28日) | 山背王が橘奈良麻呂の反乱計画を密告。 |
| 7月22日(天平宝字元年 7月 2日) | 上道斐太都が小野東人の反乱計画を密告。東人は逮捕される。 |
| 7月23日(天平宝字元年 7月 3日) | 小野東人が拷問の末に反乱計画を自白。 |
| 7月24日(天平宝字元年 7月 4日) | 反乱を計画したとして、橘奈良麻呂、道祖王、黄文王、大伴古麻呂、多冶比犢養、賀茂角足らが逮捕され、拷問などにより相次いで獄死。佐伯全成が自白後に自殺。以後、連座して443人が処罰を受ける。通称「橘奈良麻呂の乱」。藤原仲麻呂が台頭する。 |
| (天平宝字元年) | この年、「養老律令」が制定される。「大宝律令」をより日本に適したものに改めたもの。藤原不比等によって律令撰修が進められ、不比等の死で一旦中断したが、その後改訂が進められて、藤原仲麻呂の手で施行された。平安中期には形骸化したが、明治維新後の「新律綱領」制定まで、公式に廃止はされなかった。 |
| 758年 | |
| 9月 7日(天平宝字2年 8月 1日) | 孝謙天皇が大炊王に譲位し、大炊王は淳仁天皇となる。しかし引き続き孝謙上皇が権力を維持。 |
| 759年 | |
| 4月10日(天成3年 3月 9日) | 燕の2代皇帝安慶緒を史思明が殺害。史思明は燕の3代皇帝となる。史思明は安禄山とは同郷の古い友人同士で、安禄山の乱に従って功績を上げた人物。安禄山が殺されると一旦唐に降ったが、唐の粛宗から命を狙われていると知り、自立を図って安慶緒を殺害、燕の皇帝となった。 |
| 12月 9日(天平宝字3年11月16日) | 近江国勢多の付近に保良宮の造営が始まる。 |
| この年、新羅征討計画が藤原仲麻呂を中心に進められるが、孝謙上皇との関係が悪化したことで中止となったという。 | |
| 760年 | |
| 藤原仲麻呂が太政大臣(太師)に任じられる。皇族以外では初。 | |
| 7月23日(天平宝字4年 6月 7日) | 光明皇太后が崩御。甥である藤原仲麻呂の後援者でもあったため、仲麻呂にとっては大きな痛手となる(それを予期して仲麻呂は自身の太政大臣就任工作をしたとも言われる)。 |
| 761年 | |
| 4月18日(順天3年 3月 9日) | 燕の第3代皇帝史思明が、長男の史朝義によって殺される。史思明が後継者に末子の史朝清を選んだため。史朝義が燕の4代皇帝となる。 |
| 11月14日(天平宝字5年10月13日) | 淳仁天皇と孝謙上皇が建設中の保良宮に行幸。 |
| 11月29日(天平宝字5年10月28日) | 淳仁天皇が保良宮を「北京」としてしばらく滞在する旨を勅する。 |
| 762年 | |
| 6月19日(天平宝字6年 5月23日) | 淳仁天皇が保良宮から平城京へ戻る。孝謙上皇との対立が原因か。保良宮の建設も止まり、まもなく廃止される。 |
| 10月21日(天平宝字6年 9月30日) | 御史大夫石川年足が死去。蘇我氏の出で、優れた政治家だったという。藤原仲麻呂の又従兄弟で補佐役だったため、仲麻呂の権勢を弱めることとなった。 |
| 11月12日(宝応元年10月22日) | 唐で権力を握っていた宦官の李輔国が失脚後、暗殺される。 |
| 763年 | |
| (顕聖3年 1月) | 燕の4代皇帝史朝義が唐とウイグルの連合軍に追い込まれ、逃亡先の莫県で自殺。安史の乱は終息する。 |
| 6月21日(天平宝字7年 5月 6日) | 唐の律宗の大僧正で、苦難の末に日本へ渡ってきた鑑真が唐招提寺で死去。 |
| 764年 | |
| 10月10日(天平宝字8年 9月11日) | 藤原仲麻呂の乱。孝謙上皇が道鏡を重用するようになり、それを諌めたことで孝謙との関係が悪化した藤原仲麻呂(恵美押勝)が、「都督四畿内三関近江丹波播磨等国兵事使」に任じられたのを利用して訓練の兵を動員しようとしたところ、反乱と判断した孝謙上皇側が淳仁天皇を幽閉し、御璽と駅鈴を押収。仲麻呂の官位を剥奪、三関を閉鎖する。仲麻呂は一族と都を脱出して近江へ向かう。孝謙上皇は重鎮の吉備真備に誅伐を命令。真備は兵を先回りさせて東山道を封鎖。仲麻呂は皇族出身の氷上塩焼を天皇に擁立して越前へ向かう。官軍側についた佐伯伊多智は仲麻呂の子で越前国司藤原辛加知を殺害して愛発関を封鎖。 |
| 10月17日(天平宝字8年 9月18日) | 琵琶湖を横断して北陸道へ向かおうとした藤原仲麻呂は、嵐のために失敗。愛発関攻略にも失敗し、三尾で佐伯伊多智と藤原蔵下麻呂の軍勢に挟まれて大敗。仲麻呂や氷上塩焼らは殺害され、仲麻呂一族も皆殺しにされた。藤原南家は没落。淳仁天皇は廃位の上で淡路へ流罪。また仲麻呂側についていた船親王、池田親王、三方王、宗形王らも流罪となった。 |
| 769年 | |
| 11月 7日(神護景雲3年10月 1日) | 宇佐八幡宮神託事件。宇佐八幡宮で「道鏡が皇位に就くべし」との託宣が出たと上奏があり、道鏡を寵愛する称徳天皇が確認のため、和気清麻呂を派遣するが、皇位は天皇家が継ぐべし、という託宣が下ったと報告したため、和気広虫・清麻呂姉弟が流刑になった事件。結局、天皇が詔で道鏡へ皇位を譲らないことを宣言し終息。 |
| (神護景雲3年) | 称徳天皇が河内国若江郡に離宮となる由義宮を造営。「西京」とも呼ばれた。道鏡の出身地であり弓削寺の辺りと思われる。 |
| 770年 | |
| (神護景雲4年) | 百万塔陀羅尼が印刷され、小型の塔に納めて10万基ずつ大安寺・元興寺・法隆寺・東大寺・西大寺・興福寺・薬師寺・四天王寺・川原寺・崇福寺に奉納される。藤原仲麻呂の乱で亡くなった人々を弔うために、称徳天皇が作らせた。現存する世界最古の印刷物。 |
| 3月(神護景雲4年 2月) | 称徳天皇が由義宮に行幸。 |
| 8月28日(神護景雲4年 8月 4日) | 称徳天皇崩御。病床に道鏡が呼ばれることもなく、平癒祈祷の記録もないことから、すでに権力体制が藤原永手・藤原百川らに移っていたとも見られる。 |
| 9月14日(神護景雲4年 8月21日) | 道鏡に造下野薬師寺別当の命が下り、下野国へ下向。後ろ盾であった称徳天皇の崩御で左遷されたもので、弟の弓削浄人らも配流された。 |
| 772年 | |
| 5月13日(宝亀3年 4月 7日) | 道鏡、左遷先の下野国で死去。早くから女帝との姦通が言われ、皇位継承にまで絡む問題を起こした割には、自身は左遷だけで終わっているため、誇張されたという説もある。 |
| 8月12日(宝亀3年 7月 9日) | 豊後鶴見岳の北側にある伽藍岳が噴火。泥流が発生し死者多数。 |
| ザクセン戦争勃発。 | |
| 775年 | |
| この頃、地球上に大量の宇宙線が降り注いだとみられることが屋久杉の年輪調査や南極の氷床の調査などで判明。超新星爆発説、ガンマ線バースト説、大規模な太陽フレア説などが考えられるが、原因を特定するまでには至ってない。 | |
| 780年 | |
| 5月 1日(宝亀11年 3月22日) | 陸奥上治郡の大領・伊治呰麻呂が陸奥牡鹿郡大領の道嶋大盾と、陸奥国按察使の紀広純を殺害し反乱を起こす(宝亀の乱)。藤原継縄が征討大使に任ぜられるも出兵しなかったため罷免され、藤原小黒麻呂が征討大使となる。 |
| 781年 | |
| 1月30日(宝亀12年 1月 1日) | 伊勢斎宮に美雲の瑞祥が現れたことを受けて天応と改元。元日改元唯一の例。 |
| (天応元年8月) | 伊治呰麻呂の反乱征討に出ていた持節征東大使藤原小黒麻呂が征討を終了して帰京。反乱の行方、伊治呰麻呂の消息については記録が乏しく不明。 |
| 782年 | |
| 2月26日(天応2年閏1月10日) | 氷上川継の乱。天武系皇族の氷上川継の家臣大和乙人が宮中で不審を咎められ捕縛。その尋問から氷上川継が反乱を企てたとして捜査が始まる。 |
| 3月 2日(天応2年閏1月14日) | 氷上川継が捕縛され、連座して京家藤原浜成、皇族の三方王、陰陽師の山上船主らが処罰される。大伴家持や坂上苅田麻呂も、短期間だが官職を解かれた。 |
| 3月(天応2年) | 勝道上人が日光男体山の登頂に成功。いわゆる「日光山」の開山。 |
| 9月30日(天応2年 8月19日) | 延暦に改元。後漢書を出典とする。25年続き、一世一元の制度導入以前では応永についで長い年号となる。 |
| 783年 | |
| この頃までの間に万葉集が成立したと見られる。万葉集は759年までに詠まれた多数の歌の中から複数の編纂者の手を経たのち、大伴家持によってまとめられたとする説が有力。大伴家持が首謀者と疑われた藤原種継暗殺事件の影響もあり、実際に広まったのはさらに20年以上も後と見られる。 | |
| 784年 | |
| 12月27日(延暦3年11月11日) | 建設中の長岡京へ遷都。奈良の仏教勢力から距離を置くための遷都と見られる。水運に便利で、水資源にも恵まれた場所として選ばれた。宮殿は難波宮の宮殿を移築したもので丘陵上にあった。短期間で廃止されたことから、前後の平城京・平安京と比べると認知度の低い都だが、規模は相応にあったと見られる。 |
| 785年 | |
| 11月 3日(延暦4年 9月23日) | 長岡京建設現場で指揮を採っていた造長岡宮使の藤原種継が弓で射られる。 |
| 11月 4日(延暦4年 9月24日) | 藤原種継が死亡。早良親王を含む十数名が逮捕される。多くが処刑される事件に発展。大伴家持が首謀者とされたが直前に没していたため、官位剥奪の処分となった。 |
| 11月 8日(延暦4年 9月28日) | 早良親王が抗議の絶食により、淡路国に配流の途中、河内国高瀬橋付近で死亡。 |
| ザクセン人の領主ヴィドゥキントがカール大帝に降伏し、キリスト教に改宗する。 | |
| 788年 | |
| (延暦7年 6月?) | 蝦夷征討で衣川まで来た紀古佐美率いる朝廷軍が蝦夷を攻撃するが大敗を喫する(巣伏の戦い)。 |
| 794年 | |
| 7月14日(延暦13年 6月13日) | 大伴弟麻呂、坂上田村麻呂が蝦夷征討を行い大勝する。 |
| 11月18日(延暦13年10月22日) | 桓武天皇が、物流の拠点と、仏教勢力から距離をおくため、山背国葛野郡と愛宕郡にまたがって建設された平安京に遷都する。山背国は山城国と改められることになる。 |
| 797年 | |
| 7月17日 | 東ローマ帝国イサウリア王朝の第4代皇帝コンスタンティノス6世が、母親エイレーネーのクーデターで失脚し、復位させないよう母親から目を潰される。 |
| 8月15日 | クーデターで失脚し母親から目を潰されたコンスタンティノス6世が、傷がもとで死亡する。 |
| 800年 | |
| 4月11日(延暦19年3月14日) | 富士山が大噴火し噴煙が覆う。火山雷などが観測され、大量の噴石や降灰があり、付近の河川の水が紅くなったという。 |
| (延暦19年) | 蓄銭叙位令廃止。銭の流通を促進する目的だったが、貯蓄するだけで流通する効果が必ずしも出なかったため。 |
| (延暦19年) | 藤原種継暗殺事件で流刑に処され憤死した早良親王へ、崇道天皇の称号を贈る。御霊を鎮め、呪いを解くため。 |
| 12月25日 | カール大帝が教皇レオ3世よりローマ帝国皇帝の帝冠を受ける。 |
| 802年 | |
| 2月13日(延暦21年 1月 8日) | 駿河の国司より富士山の噴火により相模国足柄路が廃止されたという報告が入る。 |
| 5月19日(延暦21年 4月15日) | 蝦夷の武将、阿弖流爲と母礼が降伏。 |
| 6月22日(延暦21年 5月19日) | 富士山の噴火により筥荷路が新たに開かれる。 |
| 8月11日(延暦21年 7月10日) | 阿弖流爲と母礼が京へ連行される。助命か処刑かで意見が分かれるが処刑が決定する。 |
| 9月13日(延暦21年 8月13日) | 阿弖流爲と母礼が処刑される。 |
| 803年 | |
| 5月31日(延暦21年 5月 8日) | 富士山の噴火で塞がれていた足柄路が復旧し、筥荷路が廃止される。 |
| 8月 9日 | 東ローマ帝国イサウリア王朝の皇帝で、初の女帝エイレーネーが没する。 |
| 806年 | |
| 4月 9日(延暦25年3月17日) | 桓武天皇崩御。 |
| (延暦25年3月) | 藤原種継暗殺事件に関わったとして処罰された人に対し、生死に関わらず恩赦が下され、復位や帰京などが認められる。 |
| (延暦25年3月) | 磐梯山が噴火。大規模な山体崩壊があったとも言われる。 |
| 807年 | |
| 10月 7日(大同2年 9月 6日) | 伊予親王の変。藤原宗成が桓武天皇の子で平城天皇の異母弟である伊予親王に謀反を勧めているという情報を藤原雄友が入手し藤原内麻呂に伝える。伊予親王も宗成が謀反を示唆したと奏上したが、宗成を尋問した所、謀反の首謀者は伊予親王であると白状したため、平城天皇は伊予親王と母親の藤原吉子を川原寺に幽閉。二人は無実を主張するも自殺。伊予親王の子等が流罪となった。藤原北家の藤原宗成、藤原南家の藤原雄友、藤原乙叡、藤原友人らも処罰。藤原南家はこの事件で衰退する。事件は藤原式家の藤原仲成が裏で暗躍したと言われ薬子の変の遠因の一つになった。 |
| 810年 | |
| 10月 7日(大同5年 9月 6日) | 平城上皇が平城京遷都の詔を発し「薬子の変」が勃発。嵯峨天皇と平城上皇の対立事件。「平城太上天皇の変」とも呼ばれる。平城上皇が復位を狙い、上皇の寵愛を受けていた藤原薬子と兄の仲成が画策したとされる。嵯峨天皇は遷都に従うふりをして坂上田村麻呂ら有力者を造宮使に任じ阻止を図る。 |
| 10月11日(大同5年 9月10日) | 嵯峨天皇が三関を封鎖。事実上遷都を拒否。藤原仲成を逮捕し左遷を決定。藤原薬子の官位を剥奪。 |
| 10月12日(大同5年 9月11日) | 平城上皇は天皇方の動きを知って反発。挙兵を決意し藤原薬子と東国へ向かう。嵯峨天皇は上皇阻止を坂上田村麻呂に命じ、田村麻呂は上皇派と見られて監禁された文室綿麻呂を釈放させてともに上皇の動きを抑えるために出陣。また平城上皇の寵臣、藤原仲成が、紀清成・住吉豊継の手で処刑される(正規の処刑に則っておらず、左遷の罰が下った直後のことなので、暗殺とも言える)。 |
| 10月13日(大同5年 9月12日) | 平城上皇が天皇方の兵力の動きを見て観念し、平城京に戻って剃髪し降伏。藤原薬子は自殺。薬子の変が終わる。 |
| 10月20日(大同5年 9月19日) | 弘仁に改元。 |
| 813年 | |
| 4月 3日(弘仁4年 2月29日) | 肥前の五島・小近島(小値賀島)に、5隻の船に乗った新羅人110人が現れ、島民9人を殺害し、101人を捕虜とする。 |
| 816年 | |
| 9月11日(弘仁7年 8月16日) | 大風によって平安京最南端の羅城門が倒壊する。 |
| 819年 | |
| 5月30日(弘仁10年 5月 3日) | 空海が天野社の地主神を高野山に勧請する。 |
| 821年 | |
| (長慶元年) | 唐王朝で、科挙を巡る不正をきっかけにして、権力闘争である「牛李の党争」が勃発。以後、20年にわたって、牛僧孺・李宗閔を中心とする牛党と、李徳裕を中心とする李党が頻繁に権力交代を繰り返し、国政を乱す。唐王朝滅亡の遠因となった。 |
| 833年 | |
| (天長10年) | 律令の解説書「令義解」10巻がまとめられる。淳和天皇の勅により、右大臣清原夏野を総裁として制作が進められた。これとは別に868年頃に惟宗直本によってまとめられた私撰本の解説書「令集解」がある。 |
| 835年 | |
| 4月22日(承和2年 3月21日) | 弘法大師空海没。 |
| (大和9年11月) | 甘露の変。唐の文宗に抜擢されていた李訓と鄭注が、権力を持つ宦官勢力を滅ぼそうと計画を立てるが、鄭注が節度使として鳳翔から兵を率いて宮中に乗り込む前に、功績独占を狙った李訓が「宮中に甘露が降った」ことを理由に宦官を集めて殺害しようと企てこれが露見。宦官の圧力を受けた文宗によって処刑される事件が起きる。鄭注も鳳翔で殺害された。李訓と鄭注は、牛李両党からは中立であったために抜擢されていた。これ以降、宦官の権力がさらに増大することに。 |
| 838年 | |
| 神津島で大噴火。島民全員が死亡したとされる。 | |
| 841年 | |
| 6月25日 | フォントノワの戦い。フランク王国の王位と領土をめぐって、ロタール1世、ルードヴィヒ2世、シャルル2世の兄弟が争う。 |
| 842年 | |
| 8月24日(承和9年7月15日) | 嵯峨上皇が崩御。 |
| 8月26日(承和9年7月17日) | 承和の変が勃発。伴健岑と橘逸勢が謀反を企てたとして逮捕される。仁明天皇と藤原順子との間に道康親王が生まれ、さらに嵯峨上皇の死によって皇太子恒貞親王の身に危険が及ぶ判断した両名が皇太子を東国へ連れ出そうとする計画を阿保親王が檀林皇太后に伝えたことで発覚したとされる。 |
| 9月 1日(承和9年7月23日) | 藤原良相が近衛府の兵を率いて皇太子恒貞親王の座所を包囲し、大納言藤原愛発、中納言藤原吉野、参議文屋秋津らを逮捕。恒貞親王は無罪とされるも廃太子となり、逮捕された有力者はことごとく左遷や流罪にされた。代わって藤原良房が大納言になり、良房の甥でもある道康親王が皇太子となる。良房の権力掌握の第一歩としてその陰謀とされるが、処罰された人物の多くは良房よりも位が高く実力者であることから、良房単独の陰謀ではなく、仁明天皇が主導し、朝廷内の派閥抗争によって起きた政変とする見方が有力。ただ当時の朝廷の人間関係は複雑で誰がどの派閥に属していたかはよくわかっていない。処罰を受けた人物でも春澄善縄のようにすぐに許され出世した人物もおり、廃太子となった恒貞親王も皇位継承候補としては残っている。 |
| 843年 | |
| 8月10日 | ロタール1世、ルードヴィヒ2世、シャルル2世は、ヴェルダン条約を締結し、フランク王国は3つに分裂する。 |
| 845年 | |
| (会昌5年4月) | 唐の宰相李徳裕と、皇帝武宗の師事する道士趙帰真が、かねてより進言していた廃仏政策を武宗のもとで実行に移す。4600の寺院が廃止され、26万人の僧が還俗させられる。いわゆる会昌の廃仏。唐に留学していた日本の僧侶らも影響を受けた。 |
| 846年 | |
| (文聖王8年) | 新羅の有力者で唐や日本との交易で勢力を築いた張保皐が反乱を起こし、閻長によって暗殺される。年代は異説あり。 |
| 848年 | |
| (大中2年) | 張議潮が帰義軍を組織し、唐の西域を占領していた吐蕃軍を打ち破り瓜州・沙州の二州を取り戻す。その後、11州まで取り戻す。 |
| 850年 | |
| 11月23日(嘉祥3年10月16日) | 出羽地震。東北地方で大きな揺れがあり死者多数。津波もあったとされる。 |
| 851年 | |
| (大中5年) | 張議潮が、唐の朝廷から帰義軍節度使に任じられる。帰義軍節度使は中央から事実上独立しており(張議潮自身は唐朝廷の高官となっている)、張氏および縁戚の曹氏に代々受け継がれて、1035年に西夏に滅ぼされるまで続いた。十国には含まれていない。 |
| 852年 | |
| 12月 5日(大中6年10月21日) | 朱全忠、唐の宋州に生まれる。 |
| アルメン・フィルマンという研究者がコルドバでパラシュート降下実験を行う。現在のものとは異なり、骨組みのついた大きな傘のようなものを使用。 | |
| 859年 | |
| (大中13年12月) | 唐で浙東の賊の裘甫が決起し象山を攻め落とす。裘甫の乱の勃発。裘甫は自ら天下都知兵馬使と称し、年号を羅平と改める。 |
| 860年 | |
| (大中14年 3月) | 裘甫の乱に対し、唐朝廷は王式を抜擢。王式は討伐軍を編成。 |
| (大中14年 7月) | 裘甫の乱が王式率いる南路軍に鎮圧される。裘甫は捕らえられて長安で処刑される。 |
| 861年 | |
| 5月19日(貞観3年 4月 7日) | 直方隕石が落下する。燃え残った隕石を人々は神社に奉納する。 |
| 862年 | |
| リューリクがラドガとノヴゴロド(ホルムガルド)を占領し、同地のスラブ人を征服。リューリクは半ば伝説化した人物で、ヴァリャーグのルス族の族長であるとされる。ヴァリャーグについては、スカンジナビアから来たバイキングであるという見方が主流。ロマノフ王朝以前の諸王朝はリューリクの子孫を名乗っていた。 | |
| 863年 | |
| 6月10日(貞観5年 5月20日) | 朝廷の主催で、神泉苑にて御霊会が行われる。かつて政争に敗れて死を遂げた6人の人物、早良親王(藤原種継暗殺の嫌疑をかけられ自殺)、伊予親王と藤原吉子(ともに謀反の嫌疑で自殺)、藤原仲成(薬子の変で殺害)、橘逸勢(承和の変で流罪)、文室宮田麻呂(謀反の嫌疑で流罪)の霊を鎮めるため。仲成を除く5人は死後に無実とされた人物。藤原仲成は有罪のままだが慰霊の対象にされている。 |
| 864年 | |
| 7月 2日(貞観6年 5月25日) | 駿河国から報告があり、富士山が大噴火を起こすと伝える。溶岩が大量に流出し、本栖湖と剗の海に流れ込み、剗の海を埋めて、2つの小さい湖(西湖・精進湖)に分かれる。この溶岩の広がった跡が後の青木ヶ原樹海。大地震が3回発生。 |
| (貞観6年) | 冬、朝廷の実力者である藤原良房が病で政務から離れる。太皇太后藤原順子、良房の弟藤原良相、伴善男の3人が実権を握る。 |
| 865年 | |
| (貞観7年) | 秋、朝廷の実力者である藤原良房が政務に復帰。この頃には藤原良相との関係が悪化したものと思われる。 |
| 866年 | |
| 4月28日(貞観8年閏3月10日) | 応天門の変。平安京大内裏の応天門が炎上する事件があり、伴善男は、対立関係にあった左大臣源信を放火犯として、右大臣の藤原良相に訴える。藤原良相が兵を源信の邸宅に差し向けるが、良相の兄で太政大臣の藤原良房は、養子の参議藤原基経よりこの話を聞いて驚き、清和天皇も知らなかったことから、勅により兵は引き上げさせる。 |
| 9月15日(貞観8年 8月 3日) | 備中権史生の大宅鷹取が、応天門が炎上する直前に、伴善男、伴中庸、紀豊城の3人を見た、と訴える(大宅鷹取はこの頃、伴中庸の命で生江恒山らに襲われて娘を殺され自身も重傷を負っている)。清和天皇は勅を出して伴善男、伴中庸、紀豊城、生江恒山、伴清縄らを捕えて尋問にかけさせる。その結果、伴中庸と伴善男が「自白した」として、関係者が流罪に処せられる(大宅鷹取親子殺傷事件も伴中庸の有罪)。また、藤原良相も失脚して間もなく病死、疑われた源信も隠棲したあと落馬がもとで死亡し、藤原良房が実権を握ることとなった。良房が伴氏と紀氏の排除を狙ってしかけた政変とも取れるが真相は不明。また能書家で地方官として優れた業績を残した紀夏井は事件と無関係ながら連座して土佐に流されている。 |
| 867年 | |
| 4月 6日(貞観9年 2月28日) | 豊後鶴見岳北側の伽藍岳が噴火。 |
| 868年 | |
| (咸通9年 7月) | 唐の桂州で同地に送られていた徐州の兵らが龐勛を盟主にして勝手に徐州へ帰還する動きを始める。地方官の横暴に反発していた豪族や民衆らがこれに参加し規模が拡大。龐勛の乱が勃発する。 |
| (咸通9年 9月) | 龐勛の軍勢が徐州に入り、彭城が攻め落とされる。龐勛は節度使の地位を要求するが、政府は交渉に応じつつ討伐軍を編成。康承訓、王晏権、戴可師らを司令官に任命する。 |
| 869年 | |
| 7月 9日(貞観11年 5月26日) | 貞観地震。東北の沖合を震源とするマグニチュード8.3~8.6の巨大地震が発生。建造物の倒壊、大津波で千人以上が死亡。 |
| 8月29日(貞観11年 7月14日) | 肥後の沿岸部で高潮か津波によるとみられる水害が起きる。 |
| (咸通9年 9月) | 龐勛の軍勢が朱邪赤心(李国昌)に攻められ壊滅。龐勛も討ち死にし反乱は終息。 |
| 870年 | |
| バイキングのインゴールヴル・アルナルソンらがアイスランドに移住。 | |
| 871年 | |
| 6月 7日(貞観13年 5月16日) | 鳥海山で噴火か。泥流が発生したとみられる。 |
| 872年 | |
| 10月 7日(貞観14年 9月 2日) | 藤原良房が病死。人臣で初めて皇女を妻に迎えた人物、人臣で最初に摂政となった人物、はじめて准三宮の待遇を受けた人物。朝廷の実力者として君臨した。 |
| 874年 | |
| 3月25日(貞観16年 3月 4日) | 薩摩開聞岳が大規模噴火。 |
| (乾符元年) | 唐で塩の密売業者である王仙芝が長垣で挙兵。仲間の黄巣も参加し、大規模な反乱へと発展する。いわゆる黄巣の乱。 |
| 875年 | |
| 6月(貞観17年5月) | 上総の俘囚が反乱を起こす。 |
| 後ウマイヤ朝の宮廷詩人で発明家でもあったイブン・フィルナースが、オーニソプター(羽ばたき式飛行機)を自作し、コルドバの花嫁の山(ジャバル・アル・アルース)で飛行実験を試み墜落、大怪我を負う。記録上人類最初の「飛行装置による飛行実験」ともいわれる。 | |
| (貞観17年) | 平安朝の文人貴族である都良香が、「富士山記」を著す。山頂の様子などが詳しいため、本人か取材した人が富士登山をした可能性もある。 |
| 878年 | |
| 10月28日(元慶2年 9月29日) | 相模・武蔵地震(元慶地震)。関東諸国で大きな地震が発生したという。関東は古代三関より東側、美濃・尾張より東方を指す。特に相模・武蔵両国で大きな被害があったという。 |
| 879年 | |
| ヴァリャーグの王でリューリク朝の始祖リューリクが死去。同じヴァリャーグのオレーグが、リューリクの幼い子イーゴリを擁して後継の座につく。 | |
| 880年 | |
| 12月(金統元年) | 黄巣の反乱軍が長安を攻め落とす。唐の皇帝僖宗は蜀へと逃れる。黄巣は皇帝と称し、国号を斉として建国。しかし虐殺や略奪などの非道が横行し、斉は国家としての体をなさず。 |
| 882年 | |
| ヴァリャーグの王オレーグが、キエフを征服して同地に拠点を移す。キエフ大公国の始まりとされる。 | |
| 883年 | |
| 12月13日(元慶7年11月10日) | 宮中で陽成天皇の乳母紀全子の息子である源益が殴殺される事件が起きる。事件は秘匿されるも宮中の行事がことごとく中止となる。事件の詳細は不明で犯人もわからないが、様々な記録には陽成天皇が何かしら関わっていると記されている。ただし天皇の生母藤原高子とその兄の藤原基経との関係が悪く、基経は皇位継承にも関与したため、後に陽成天皇を貶めた可能性もある。 |
| 884年 | |
| 3月 4日(元慶8年 2月 4日) | 陽成天皇が退位。源益殺害事件を受けて藤原基経から強制されたと見られる(表向きは病気による)。基経が諸公卿を抑えて仁明天皇の第三皇子で55歳の時康親王を即位させる(光孝天皇)。陽成天皇は暴君的逸話が残されているが、生母藤原高子とその兄の藤原基経との対立によって排除された面もある。陽成天皇は退位後に長生きし上皇歴は65年と歴代最長で、光孝・宇多・朱雀・村上の4代に渡る。陽成源氏の祖であり、清和源氏の祖と云う説もある。 |
| 5月(金統5年) | 王満渡の戦いで、黄巣軍は雁門節度使の李克用に大敗を喫し、斉はほぼ瓦解。 |
| 7月13日(金統5年 6月17日) | 黄巣は故郷へと落ち延び、狼虎谷で自害。 |
| 885年 | |
| 5月(仁和元年7月) | 薩摩開聞岳が大噴火。溶岩流出、および火砕流が発生。 |
| この頃、太宰大弐の源精が帰京した際に光孝天皇に黒猫を献上する。猫はすぐに天皇の子の源定省(のちの宇多天皇)に下賜された。宇多天皇がこの猫を非常にかわいがった様子が日記『寛平御記』に記されている。 | |
| 886年 | |
| (仁和2年) | 新島で大噴火が起き、島の南部が形成されて現在の形になる。島民全員が死亡したとされる。 |
| 887年 | |
| 8月22日(仁和3年 7月30日) | 仁和地震。五畿七道諸国の広範囲で大きな地震があり、畿内から日向にかけては津波の記録も残る。南海道地震とする説もあるが土佐での現存する被害の記録はないため、他の地域を震源とする広域地震の可能性もある。 |
| 9月16日(仁和3年 8月25日) | 光孝天皇の病が重くなったことから、藤原基経は公卿らに諮って天皇の第15皇子で臣籍降下していた源定省を皇族に戻した上で立太子を行うこととする。基経としては皇位継承に皇統の嫡流だが仲の悪い妹藤原高子の子である陽成天皇の同母弟貞保親王を外すため、仲の良い妹藤原淑子の猶子でもあった源定省を選ぶという異例の措置を行った。 |
| 9月17日(仁和3年 8月26日) | 光孝天皇が崩御。光孝天皇の第15皇子の源定省が皇族に戻り立太子の上で即位(宇多天皇)。皇統は嫡流から光孝系へと移動する。 |
| 12月 9日(仁和3年11月21日) | 阿衡事件。藤原基経の関白任命をめぐって、橘広相が起草した任命詔勅の関白を指す「阿衡」の文字が「中身のない役職を意味している」と藤原佐世が指摘したことで基経が問題にし、職務を半年にわたって放棄する。菅原道真が間に入り、宇多天皇が折れて橘広相を更迭、誤りを認める詔を発して収拾した。基経は歴史上はじめて、関白という名前の役職についた人物で、就任の年月日には異説もある。 |
| 888年 | |
| 6月20日(仁和4年 5月28日) | 前年の大地震で起きた八ヶ岳の山体崩壊によって出来た千曲川・大月川の天然ダムが決壊。下流域に大規模な洪水が発生する。潅水量5.8億立方mの巨大な天然ダム湖だったとされる。 |
| 889年 | |
| 891年 | |
| 2月24日(寛平3年 1月13日) | 絶大な権力を有した関白藤原基経が死去。関白職は廃止にはならなかったが、政務は宇多天皇親政になり、菅原道真が重用されることになる。 |
| 892年 | |
| 唐の盧州刺史楊行密が揚州一帯を手中に収め、淮南節度使となる。十国の一つ、呉の事実上の建国。 | |
| 894年 | |
| (寛平6年) | 前年からこの年にかけて、対馬にたびたび新羅の軍勢が攻め寄せる。対馬守文屋善友がこれを撃退。 |
| 896年 | |
| 杭州の軍閥杭州八都を率いる杭州刺史銭鏐が鎮海・鎮東両軍節度使となる。十国の一つ呉越の事実上の建国。 | |
| 福州の有力者王潮が威武軍節度使となる。十国の一つ閩の祖。 | |
| 潭州の有力者馬殷が湖南節度使となる。十国の一つ楚の事実上の建国。 | |
| 897年 | |
| 1月 | ローマのラテラン教会で「死体裁判」が行われる。 |
| 8月 4日(寛平9年 7月 3日) | 宇多天皇が、突如皇太子の敦仁親王を元服させて譲位する(醍醐天皇)。突然の譲位は仏道に専心するため、上皇となって藤原時平の専横を抑えるため、陽成上皇系の皇統復活を阻止するためなどの説がある。なお醍醐天皇は父の宇多天皇が臣籍降下していた源定省の時に生まれており(源維城と名乗った)、歴代天皇で唯一、臣籍生まれの人物。 |
| 威武軍節度使王潮が死去し、弟の王審知が後を継ぐ。閩の初代王。 | |
| 899年 | |
| 10月26日 | イングランドの原型を築いたウェセックスのアルフレッド大王が死去。 |
| 新羅の王族を称する弓裔が高句麗復興を唱えて挙兵。 | |
| 900年 | |
| 新羅の将軍甄萱が後百済(国号は百済)を建国。 | |
| 901年 | |
| 2月16日(延喜元年 1月25日) | 昌泰の変で菅原道真が大宰府へ左遷される。 |
| 弓裔が後高句麗を建国。最盛期には朝鮮半島の大部分を支配するに至る。 | |
| 902年 | |
| 南詔王の舜化貞が死去し、漢人の鄭買嗣が舜化貞の一族800人余りを殺して自ら皇帝を名乗り、大長和を建国。年号を安国と改める。 | |
| 904年 | |
| 封州刺史劉隠が、静海軍節度使の反乱を鎮圧して自ら静海軍節度使と名乗り、事実上独立。十国の一つ南漢の前身。 | |
| 905年 | |
| 5月21日(延喜5年 4月15日) | 古今和歌集成立(真名序による)。仮名序では旧暦4月18日(ユリウス暦5月24日)。 |
| 8月 8日(天祐2年 7月 5日) | 白馬の禍。朱全忠が、側近の李振の進言で、唐朝廷の「衣冠清流」と呼ばれる有力な官僚ら30数人を滑州の白馬駅で殺害。遺体を黄河に投棄した事件。李振は「清流を自称する者を黄河に放り込めば、永遠に濁流となる」とうそぶき、朱全忠も同調したが、この事件によって朱全忠は有能な士大夫層の協力を得られなくなり、他の軍閥勢力と敵対する要因にもなったと見られる。 |
| 907年 | |
| 2月27日 | 耶律阿保機が、可汗に即位。のちの契丹(遼)王朝の前身。 |
| 6月 1日(開平元年 4月18日) | 朱全忠が唐の哀帝から禅譲を受けて皇帝に即位。梁(後梁)を建国。五代十国のはじまり。 |
| 11月 3日(天復7年 9月25日) | 唐の蜀王だった王建が、唐の滅亡を知って、後梁には従わずに自立。皇帝を名乗り、国号を「蜀」とする(前蜀)。 |
| 909年 | |
| 4月26日(延喜9年 4月 4日) | 左大臣藤原時平が死去。39歳。優れた政治家であり、延喜の荘園整理令を実施するなど政治改革に取り組んで「延喜の治」の政策実行者であった人物。左右大臣として共に政策を行った菅原道真のことは高く評価していたが、菅原道真失脚を策した張本人とされて、道真を祀る天神信仰が広まると極悪人とみなされるようになった。 |
| 911年 | |
| 4月 4日(乾化元年 3月 3日) | 後梁の南海王劉隠が死去。弟の劉龑が後を継ぐ。 |
| 7月13日(延喜11年 6月15日) | 宇多上皇の主催で「亭子院酒合戦」が行われる。酒豪とされた8人が飲み比べを行い、藤原伊衡が勝利し駿馬を賜る。この時参戦した平希世は、後に清涼殿落雷事件で死亡した一人。紀長谷雄が「亭子院賜飲記」に記録。 |
| 912年 | |
| 7月18日(乾化2年 6月 2日) | 後梁の太祖朱全忠が、後継者問題で第3子の朱友珪に殺害される。 |
| 後梁の荊南節度使高季興が、荊州など3州をもって事実上独立。十国の一つ荊南。 | |
| 913年 | |
| 4月21日(延喜13年 3月12日) | 右大臣・左近衛大将の源光が、狩りの最中、泥沼に転落してそのまま浮かぶことなく溺死する事件が起きる。菅原道真の失脚に関わったと見られたことから、道真の祟りと噂される。 |
| 4月22日(延喜13年 3月13日) | 宇多法皇の主催で「亭子院歌合」が行われる。 |
| 915年 | |
| (延喜15年) | 十和田湖が大噴火。火山爆発指数はVEI5の大規模なもの。周辺に火砕流が広がり、大量の火山灰などの噴出物が、西側に降り積もり、ラハールとなって米代川流域に広がる。 |
| 916年 | |
| 3月17日 | 耶律阿保機が「契丹」を国号に定める。 |
| 917年 | |
| 南海王劉龑が皇帝を称し国号を大越とする。 | |
| 918年 | |
| 7月11日(光天元年 6月 1日) | 前蜀の初代皇帝王建が死去。無頼の徒から身を起こし、黄巣の乱で功績を上げ、唐の僖宗が蜀に脱出するのを助け、西川節度使から唐の蜀王、自立して皇帝を名乗った。独裁権力者として支配する一方、農業振興を図って内政を安定させ、文化事業も盛んに行った。王宗衍が後を継ぐ。 |
| 大越高祖劉龑が国号を漢(南漢)と改める。 | |
| 後高句麗の王弓裔が暴虐の振る舞いが増えたため、洪儒、裴玄慶、申崇謙、朴智謙らが実力者の王建を擁立、弓裔は追放されのち殺害される。王建は国号を高麗(高句麗の自称)と定める。ほぼ同時代の前蜀の王建とは別人。この高麗の太祖王建は、唐の皇族の末裔説、淮河流域から移住した漢人の子孫説、中国系商人の子孫説、満州族の子孫説などがあり、朝鮮系という説はあまり見られない。 | |
| 923年 | |
| 4月 9日(延喜23年 3月21日) | 皇太子の保明親王が死去。21歳。先の皇太子保明親王は藤原時平の縁者であり、藤原時平は菅原道真を失脚させ死に追いやった人物であることから、菅原道真の祟りとの風聞が広がる。 |
| 5月 8日(延喜23年 4月20日) | 醍醐天皇は大宰府に左遷されて死去した菅原道真の地位を太宰員外帥から右大臣に戻し、正二位を贈る。 |
| 5月13日(同光元年 4月25日) | 李存勗が皇帝を名乗って後唐を建国。先祖が唐より李姓を賜ったことから、国号を「唐」とした。 |
| 5月17日(延喜23年 4月29日) | 醍醐天皇は皇太子に保明親王の長男慶頼王を立てる。わずか3歳。 |
| 12月30日(同光元年11月20日) | 朱全忠の右腕として辣腕を振るった李振が李存勗によって処刑される。 |
| 924年 | |
| (天祐21年) | 後唐の李存勗が、鳳翔一帯を支配した政権「岐」に圧力をかけ、岐王李茂貞は降伏し「岐」は滅亡。李茂貞は李存勗から「秦王」に封ぜられる。「岐」は十国には含まれていない。 |
| 5月17日(同光2年 4月11日) | 李茂貞が死去。跡を子の李従曮が継ぐ。李従曮は946年まで生きて「岐王」に復し、その死で系統が断絶することから、「岐」を945年滅亡とする見方もある。 |
| 925年 | |
| 7月12日(延長3年 6月19日) | 皇太子の慶頼王が病死。慶頼王も父の保明親王同様、藤原時平の縁者であることから、道真の祟りであるとの風聞が広がる。皇太子には同母弟の寛明親王が立てられたため、祟りに合わないよう保護されて育ったという。 |
| 926年 | |
| 5月15日(同光4年 4月 1日) | 後唐の李存勗(荘宗)の悪政により反乱が多発。その鎮圧を任された李嗣源が、逆に部下によって皇帝に推戴される。追い詰められた李存勗は、禁軍の謀反により殺害される。李存勗は武将としては優れていたが、政治家としては暗愚で、側近の孔謙に一任して酒色に溺れ、演劇に熱を入れ、政治を顧みなかった。また宦官を重用して軍を監察させたため、軍の反感を買ったと言われる。 |
| 6月 3日(天成元年 4月20日) | 李嗣源が正式に後唐の2代皇帝となる。 |
| 契丹の皇帝耶律阿保機率いる軍勢が渤海の都である上京龍泉府を攻め落とし、渤海は滅亡。耶律阿保機は渤海の領地のうち、沿岸部を分離してあらたに東丹国を興して長男の耶律突欲を東丹王とし、残りを契丹国に編入する。この直後、耶律阿保機は遠征先で急死。耶律突欲は耶律阿保機の遺体とともに帰国。 | |
| 927年 | |
| 耶律阿保機の次男耶律堯骨が、契丹の皇帝位を継承。耶律阿保機の長男で東丹国王となったばかりの耶律突欲との間で対立を生むことになる。 | |
| 928年 | |
| 東川節度使の楊干貞が大長和の皇帝鄭隆亶を殺害し、清平侍中の趙善政を擁立し国号を大天興とする。 | |
| 929年 | |
| 東丹国の使者として、かつて渤海国使として来日したこともある裴璆が丹後に到着。しかし国号が変更になった理由を問われて、渤海が契丹に滅ぼされたこと、新しい支配者の非道を訴えたことが不興を買い、入京を認められなかった。 | |
| 東川節度使の楊干貞が、擁立したばかりの趙善政を廃して自立し、国号を大義寧とする。 | |
| 930年 | |
| アイスランド全島から各集落の代表者が集まり、アルシング(民主議会)が開かれる。 | |
| 7月24日(延長8年 6月26日) | 朝議の行われていた最中の夕刻、清涼殿の南西側に落雷。大納言民部卿藤原清貫、右中弁内蔵頭平希世が焼死し多数の公卿が負傷。また紫宸殿にも落雷があり、右兵衛佐美努忠包が焼死する。清涼殿では火災も発生。宮中は大混乱に陥る。藤原清貫は菅原道真の失脚に関わっていたことから、道真の祟りにあったという噂が立つ。 |
| 7月29日(延長8年 7月 2日) | 清涼殿落雷事件を受けて、穢れを祓うため、醍醐天皇が清涼殿から常寧殿に遷座するも、身近で起きた悲惨な事件の衝撃で病臥する。道真失脚に関わった人々の不審な死や、二人の皇太子の続けての急死、そして各地の飢饉に加えてこの落雷事件で、道真怨霊の話はかなり信じられていたと見られる。 |
| 10月16日(延長8年 9月22日) | 病臥中の醍醐天皇が皇太子寛明親王に譲位。 |
| 10月23日(延長8年 9月29日) | 醍醐天皇が亡くなる。 |
| 東丹王耶律突欲が、弟で契丹皇帝の耶律堯骨の圧力を受け、後唐の2代皇帝李亶の誘いに応じて亡命する。東丹国は消滅したとされるが、制度は維持され、徐々に契丹に併合されていったものと見られる。なお突欲の長男の耶律兀欲は耶律堯骨のもとに残って将軍として活躍、耶律堯骨の死後、武力で権力を奪い契丹の第3代皇帝となった。 | |
| 931年 | |
| 9月 3日(承平元年 7月19日) | 宇多法皇が崩御。 |
| 933年 | |
| 王建が後唐に朝貢し、明宗によって高麗王に封ぜられる。 | |
| 12月15日(長興4年11月26日) | 後唐の2代皇帝李嗣源(明宗)が死去。軍部に推されて即位したあとは、馮道を宰相に任じて内政を重視し、制度を固めて安定政権を築いたほか、文化事業も行い、五代十国時代では珍しい名君のひとり。しかしその死後、内紛が勃発し、3年で国家は崩壊した。 |
| 934年 | |
| 1月28日(承平4年12月21日) | 土佐の国司だった紀貫之が帰京のため土佐を出発。この旅の紀行文が『土佐日記』にまとめられる。日本最初の仮名で書かれた本。 |
| アイスランドのラキ火山(ラーカギーガル山)が巨大噴火。 | |
| 935年 | |
| 11月 | 新羅の敬順王が、後百済の圧力などで領土を大きく縮小したこともあり、高麗に降伏して、新羅は滅亡する。 |
| 936年 | |
| 後百済が初代甄萱と二代神剣の内紛で高麗につけこまれ滅亡する。高麗が朝鮮半島の大部分を支配下に収める。 | |
| 937年 | |
| 李嗣源の娘婿だった石敬瑭が、反乱を起こし、契丹の耶律堯骨の支援で皇帝を称し、後晋を建国。 | |
| 1月11日(清泰3年閏11月26日) | 石敬瑭が、後唐の都洛陽を包囲。後唐4代皇帝李従珂(末帝)は自殺し滅亡。 |
| (2月 4日) | 大義寧の通海節度使の段思平が自立して国号を大理とする。 |
| 十国呉の第4代王楊溥(睿帝)が徐知誥に禅譲して滅亡。徐知誥(李昪)は斉(南唐)を建国。 | |
| 12月18日(承平7年11月13日) | 富士山が噴火し、溶岩が流れ出て御舟湖を埋めたとされる。 |
| 939年 | |
| 4月19日(天慶2年 5月10日) | 鳥海山(大物忌明神の山)が噴火か。 |
| 940年 | |
| 1月 3日(天慶2年11月21日) | 常陸国府によって追補されていた藤原玄明を匿った平将門が、追補撤回を求めて、兵を率いて常陸府中へ侵攻。常陸国府との戦闘となる。常陸介藤原維幾は敗れて降伏。これにより将門が関わった戦乱は、一族同士の私闘から、朝廷に反旗を翻した形へと変質してしまうことに。 |
| 1月22日(天慶2年12月11日) | 平将門が下野国へ侵攻。下野守藤原弘雅らは、降伏するも追放される。 |
| 1月30日(天慶2年12月19日) | 平将門が上野国府を攻め落とし、坂東諸国を手中に収める。この直後「新皇」を称して、坂東諸国の除目を定める。除目の範囲が坂東のみで、朱雀天皇を「本皇」と呼んだことから、坂東限定の半独立国を想定したものか。 |
| 2月29日(天慶3年 1月19日) | 平将門討伐のため、藤原忠文が征東大将軍に任ぜられる。忠文は直ちに出立。 |
| 3月25日(天慶3年 2月14日) | 新皇と称し、関東平野の支配者となったばかりの平将門が、藤原秀郷ら討伐軍との戦闘で戦死する。 |
| 閩の景宗王曦と弟の建州節度使王延政との間で内戦が勃発。 | |
| 941年 | |
| 7月21日(天慶4年 6月20日) | 瀬戸内地方で海賊団を率い、天慶の乱を起こした藤原純友が死去。 |
| 呉越の都杭州で大火が起こり、大きな被害を出す。国王の銭元瓘も死去。敵国だった南唐の李昪は、このときだけは支援したと言う。 | |
| 942年 | |
| 契丹が高麗に使者を派遣し、ラクダを贈るが、高麗王王建は契丹を蛮族と嫌い、ラクダを餓死させた上、使者を離島に流したという。 | |
| 943年 | |
| 7月 4日(天福8年 5月29日) | 高麗の初代王王建が死去。 |
| 閩の王延政が建州において皇帝を自称し、国号を殷とする。 | |
| 944年 | |
| 閩の朱文進が反乱を起こし、景宗王延羲を殺害して閩主を名乗る。後晋に臣従して威武節度使、つづけて閩王に封ぜられる。 | |
| 945年 | |
| 殷帝を称していた王延政が閩に侵攻。朱文進は林仁翰に殺害され、王延政が第7代閩王となる。しかしこの混乱に乗じて南唐が侵攻してくると降伏。閩は滅亡。 | |
| 946年 | |
| 朝鮮半島北部の白頭山(長白山)が大噴火を起こす。東北から北海道にかけて大量の降灰がある。 | |
| 947年 | |
| 1月11日(会同10年 1月1日) | 契丹の太宗(耶律堯骨)による親征で、後晋の都開封は陥落。2代皇帝の石重貴(少帝)は契丹に拉致され後晋は滅亡。太宗は開封に入城し、国号を「大遼」と改称、年号を大同とする。 |
| 2月 | 後晋の河東節度使で、突厥沙陀族の劉知遠が、皇帝を称して即位。後漢(こうかん)を建国。 |
| 6月 | 劉知遠、遼の軍勢が引き上げたのを受けて開封へ入城。節度使の地位を安堵する。 |
| 948年 | |
| 1月 | 後漢高祖劉知遠が死去。劉承祐(隠帝)が2代目皇帝となる。 |
| 950年 | |
| 4月 | 後漢の有力軍閥、郭威が天雄軍節度使に任ぜられ、対遼政策のため鄴都へ赴任。この間に隠帝側近らが有力武臣らの粛清を開始。 |
| 4月 | 郭威が粛清に対抗するため、反乱を起こし、軍を率いて南下、開封へ向かう。 |
| 951年 | |
| 1月 | 郭威は軍を率いて開封へ入城。その混乱のさなか、隠帝も殺害される。郭威は劉知遠の甥の劉贇(徐州武寧軍節度使)を擁立。 |
| 2月13日 | 郭威、遼に備えて移った澶州で部下から皇帝に推戴され、自ら帝位に就き後周を建国する。劉贇は殺害され、それを知ったその父の劉崇(河東節度使)は、晋陽で自立し、北漢を建国。 |
| 楚の第6代王馬希崇が、内紛により南唐の支援を求め、南唐は潭州に攻め込み、楚は滅亡。 | |
| 954年 | |
| 5月21日(顕徳元年4月17日) | 五代十国時代を代表する政治家、馮道が死去。実に5つの王朝の11人の君主に仕えて政治を行った(五朝八姓十一君という)。名族である長楽馮氏の出自を称し、長楽老と号した。内政を重視して文化事業を行い、木版印刷の祖とも呼ばれる(木版印刷自体はそれ以前からある)。何度も政変や王朝交代に巻き込まれて左遷・失脚するも、その都度能力を買われて返り咲いている。そのため「忠臣は二君に仕えず」を良しとする中国では批判されることが多いが、戦乱時代に多くの民衆を救ったとする評価もある。 |
| 957年 | |
| 後周の軍勢が南唐の淮河から長江にかけての一帯をほぼ制圧。南唐は後周に臣従することになり、国号を江南と改め、皇帝の称号も廃する。 | |
| 960年 | |
| 陳橋の変。後周の陳橋で、後周軍の有力者だった殿前都点検の趙匡胤が、弟の趙匡義ら部下に推されクーデターを起こす。この後、都の開封に戻り、3代恭帝から禅譲を受け、帝位につき、宋王朝(北宋)を興す。 | |
| 962年 | |
| 2月 2日 | 東フランク王オットー1世が、教皇ヨハネス12世から皇帝の冠を授けられる。神聖ローマ帝国の誕生とされる。 |
| 963年 | |
| 荊南の王高継仲が宋王朝に降伏し荊南は滅亡。 | |
| 964年 | |
| ブワイフ朝の天文学者アブドゥル・ラフマーン・スーフィーが、アンドロメダ銀河を観測。 | |
| 969年 | |
| 4月14日(安和2年 3月25日) | 安和の変。左大臣の源高明が失脚し、藤原北家が権力を継続させるきっかけとなる。 |
| 971年 | |
| 北宋が南漢に攻め込み、第4代皇帝劉鋹は逃走を図るも失敗して捕らえられ、南漢は滅亡。 | |
| 975年 | |
| 北宋軍が江南(南唐)の都金陵を包囲。第3代王李煜は降伏し、江南(南唐)は滅亡。 | |
| 976年 | |
| 11月14日(開宝9年10月20日) | 宋の太祖、趙匡胤が急死。死の際にそばにいたと言われる弟の趙匡義が2代皇帝(太宗)となる。同時代から趙匡義が趙匡胤を殺害したのではないかという疑惑「千載不決の議」が取り沙汰された。趙匡胤は中国史上で名君に挙げられる。 |
| 978年 | |
| (太平興国2年) | 中国南部で最後まで残っていた呉越の王銭弘俶が家臣とともに自国を宋王朝に献上。銭弘俶は淮海国王に封ぜられる。呉越国は消滅。 |
| 979年 | |
| 北宋の太宗の親征により、十国最後の国家、北漢は滅亡。最後の皇帝である英武帝劉継元は宋より彭城公に封ぜられる。十国時代は終わり、再統一される。 | |
| 980年 | |
| 8月22日(天元3年 7月 9日) | 大風により平安京最南端の羅城門が倒壊。中にあった兜跋毘沙門天立像は東寺に移される。すでにかなり荒廃して遺体放置場所にされたともあり、以後、再建されることはなかった。 |
| 982年 | |
| 赤毛のエイリークがグリーンランドを発見して命名。グリーンランドという名前の由来ははっきりしないが、入植を進めるため、あるいは当時温暖化の時代だったため、沿岸部は緑に覆われていたと言った説がある。 | |
| 985年 | |
| 8月 7日(寛和元年 7月18日) | 花山天皇の寵愛を受けた女御、藤原忯子が急死。懐妊していたと言われる。花山天皇は衝撃を受け、これが翌年の寛和の変に発展する。 |
| この頃から、赤毛のエイリークら、ヴァイキングによってグリーンランドに入植が始まる。現在の自治政府首都ヌーク付近にも入植。ただしこの入植地は16世紀までにすべて滅んでいる。 | |
| 986年 | |
| (雍熙3年3月) | 北宋の太宗が遼に遠征軍を派遣。潘美、楊業、曹彬、王侁、劉文裕ら各将に指揮させる。 |
| (雍熙3年5月) | 北宋軍は、蔚州などで遼の耶律斜軫の軍勢に大敗を喫する。潘美・王侁らは楊業を讒言して耶律斜軫に対応させようと図り、楊業はかつて宋と敵対した北漢の武将で立場が弱く、出戦して陳家谷で耶律斜軫に敗北。捕らえられて自殺した。このことを知った太宗は潘美を降格、王侁、劉文裕らを更迭して流罪にした。中国で小説や京劇で人気の「楊家将演義」では楊業は前半の主人公で、潘美をモデルにした潘仁美は悪役。 |
| 4月14日(寛和2年 8月 1日) | 寛和の変。花山天皇が突如出家し一条天皇が即位する。右大臣藤原兼家が起こした政変で、兼家の三男道兼が、天皇の寵愛していた女御藤原忯子の急死を悲しむ天皇を誘って出家させ、その間に兼家が長男の道隆と次男の道綱を使って三種の神器を皇太子の元へ運んだ。これにより天皇の外叔父藤原義懐と乳母子藤原惟成も失脚し、関白藤原頼忠も事実上引退した。兼家は権力を掌握すると大臣職を辞して摂政となったため、以後の先例となった。花山天皇が皇太子時代の副侍読だった藤原為時は式部丞となっていたが、この変により辞任し以後10年間散位として不遇となる。娘の紫式部の式部はこれが由来とも言われる。 |
| 990年 | |
| 7月26日(永祚2年 7月 2日) | 藤原兼家が死去。右大臣・摂政・太政大臣・関白を歴任。藤原道隆・藤原超子・藤原道綱・藤原道兼・藤原詮子・藤原道長らの父親。藤原師輔の三男だったが次兄や一族らとの争いを制し、一条天皇の外祖父となって摂政に就任。氏長者として藤原氏の頂点に立った。 |
| 991年 | |
| 10月26日(正暦2年 9月16日) | 一条天皇の生母である皇太后藤原詮子が出家して皇太后位から降りたのに伴い、「東三条院」の院号が贈られる。院は上皇を指し上皇に准ずる待遇を意味する。女院号の初例。 |
| 995年 | |
| 5月 5日(長徳元年 4月 3日) | 藤原道隆が病のため関白を辞職。道隆は子の内大臣藤原伊周を後継の関白にするべく、天皇に伊周の「内覧」を願うが「関白病間」のみとして限定的にしか認められなかった。 |
| 5月12日(長徳元年 4月10日) | 藤原道隆が死去。糖尿病と見られる。 |
| 5月29日(長徳元年 4月27日) | 藤原道兼が関白宣下を受ける。道隆の弟で道長の兄。 |
| 6月 2日(長徳元年 5月 2日) | 『蜻蛉日記』の著者、藤原道綱母死去。 |
| 6月 8日(長徳元年 5月 8日) | 藤原道兼が病死。関白就任からわずか数日での死去により、七日関白と呼ばれる。すでに病を得ていた道兼を関白にしたのは長幼の順で道長を関白にしたい姉の東三条院の意向だったとも言われる。道兼は花山天皇の出家騒動に関わったこともあり、物語で容貌や言動を悪く描かれる事が多い。権力は弟の道長と甥の伊周の争いに移る。 |
| 6月11日(長徳元年 5月11日) | 藤原道長に内覧の宣旨が下る。 |
| 7月19日(長徳元年 6月19日) | 藤原道長が右大臣となり、藤原伊周を上回る。これにより、道長が藤原氏長者の立場を獲得。 |
| 7月19日(長徳元年 7月24日) | 藤原道長と藤原伊周が氏長者の所領帳を巡って激しい口論に及ぶ。 |
| 8月30日(長徳元年 8月 2日) | 藤原道長の随身(警護官)の秦久忠が藤原隆家(伊周の弟)の関係者に殺害される。 |
| (長徳元年) | この年、日本各地で疫病が流行し、有力貴族らも多数死亡。中関白家が衰退し、藤原道長が台頭するきっかけとなった。麻疹とも疱瘡とも言われる。 |
| 996年 | |
| 2月 7日(長徳2年 1月16日) | 長徳の変。藤原伊周が、弟の藤原隆家に命じて花山法皇の一行を襲撃させ、その衣の袖を射抜く事件を起こす。花山法皇が藤原為光の娘の四の君(藤原儼子)のもとに通い始めたのを知った伊周が、自身の交際相手で同じ邸宅に暮らす三の君(寝殿の上)のもとに通っていると勘違いして起こしたとされる。このことを知った藤原道長がこれを口実に関係者の左遷などの処罰を決める。なお同時代の事件に詳しい「小右記」のこの前後の記事が欠落しており、真相ははっきりしない。 |
| 2月19日(長徳2年 1月28日) | 25日の春の除目で淡路守に任ぜられてた藤原為時が、急遽越前守に変更される。藤原道長による人事とされ、先に越前守に任じられていた源国盛は秋の除目で播磨守に変更になったという。下国の淡路国に納得行かなかった為時が思いを書いた漢詩を宮中に提出し、それを読んだ一条天皇が苦悩したことを知った道長によって上国の越前国に変更されたとも、北宋商人朱仁聡が若狭に来航し越前に逗留していたことから、漢文の才を持つ為時に白羽の矢が立ったとも言われる。越前下向には娘の紫式部も同行した。 |
| 2月26日(長徳2年 2月 5日) | 藤原道長は、一条天皇を動かして、検非違使別当の藤原実資に対し、藤原伊周、同家司の菅原董宣、同家郎党の右兵衛尉致光の家宅捜索を行わせる。 |
| 4月21日(長徳2年 4月 1日) | 法琳寺の僧から、藤原伊周が私的に「大元帥法」を修したとの奏上が行われる。 |
| 5月14日(長徳2年 4月24日) | 宣旨が下され、内大臣藤原伊周を太宰権帥に、中納言藤原隆家を出雲権守とする除目が行われる。また他の兄弟、中関白家に近い人物等に対しても左遷などの処罰的人事が行われる。 |
| 5月20日(長徳2年 5月 1日) | 長徳の変。藤原伊周・隆家兄弟が、左遷の命令に応じなかったため、新たに宣旨が下され、二人が匿われていた姉の中宮定子の里第(私邸)二条宮を検非違使が捜索。隆家が逮捕され、留守にしていた伊周も3日後に出頭。これを受けて妊娠中の中宮定子は自ら髪を切って落飾する(出産後に再入内)。藤原道隆を祖とする中関白家が没落していく原因となった。 |
| 6月 3日(長徳2年 5月15日) | 勅により、藤原伊周を播磨に、藤原隆家を但馬に留めることが決まる。 |
| 11月24日(長徳2年10月11日) | 藤原伊周が、病臥した母親のために密かに京に戻って姉の定子のもとに匿われていたことが発覚し捕縛される。再度、太宰府へ送ることが決まる。 |
| 997年 | |
| 5月13日(長徳3年 4月 5日) | 大赦が行われ、藤原伊周と藤原隆家は赦免が決定する。 |
| (長徳3年) | この年、九州各地の沿岸を「高麗の賊」が襲来。長徳の入寇、南蛮の入寇などともいう。朝鮮半島からの他に奄美島人が加わっていたという記録もある。 |
| 997年 | |
| (長徳3年6月) | 一条天皇の希望で、長徳の変で落飾し脩子内親王を産んでいた藤原定子が中宮として再び入内する。異例の措置だったが、天皇の母親の東三条院や、その弟の藤原道長が意向を受けて動いたとみられる。一条天皇は大っぴらに定子の元に通うことをせず夜遅くに訪ねるなど配慮した。 |
| 999年 | |
| 2月10日(長保元年 1月17日) | 長保に改元。疫病が流行していたため。出典は『国語』。 |
| 7月29日(長保元年 6月14日) | 内裏で火災が起き焼け落ちる。 |
| 9月 9日(長保元年 7月22日) | 長保元年令が発布される。一条天皇の勅旨に基づき藤原道長等によってまとめられた新制(法典)。災異が相次いだことを受けて、神事違例・仏事違例、社寺破損、服装や道具の奢侈禁制などを定めており、その後の公家法の原典となった。 |
| 10月30日(長保元年 9月19日) | 内裏で生まれた子猫のために「産養」の儀式が内裏で行われ、皇太后藤原詮子やその弟の左大臣藤原道長らが多数が出席。人ではなく猫の子の儀式はかなり異例。一条天皇がかわいがった猫「命婦のおとど」と同じ猫と見られる。 |
| 1000年 | |
| 4月 2日(長保2年 2月25日) | 藤原彰子が皇后に冊立されて中宮を号し、中宮だった藤原定子が皇后宮となって、はじめて一帝二后となる。 |
| 4月(長保2年 3月) | 一条天皇がかわいがっている猫「命婦のおとど」を飼育していた「馬の命婦」が、猫が言うことを聞かないのに腹を立てて、飼われていた犬「翁丸」をけしかけたことで、驚いた猫が天皇のもとに逃げ込み天皇が激怒。犬を打擲して捨てさせ、馬の命婦も解任するよう命じる。犬は打擲されて捨てられたが、清少納言がそれを拾い中宮定子が保護したため、天皇が許したという。 |
| 12月25日 | イシュトヴァーン1世が戴冠し、アールパード朝ハンガリー王国を建国。1001年1月1日という説もある。 |
| 997年からこの頃にかけて、アイスランド出身のバイキング、レイフ・エリクソンが船団を率いて北アメリカに到達する。発見した土地を「ヘルランド(平らな石の地)」「マルクランド(森の地)」「ヴィンランド(葡萄の地あるいは草の地)」と名付ける。最初に上陸した土地はバフィン島かラブラドール半島と言われ、ヴィンランドと名付けられた土地は、バイキングの遺跡が見つかったランス・オ・メドーのあるニューファンドランド島と考えられているが、その呼称の意味から、もっと南のどこか温暖な土地ではないかという説もある。 | |
| 1001年 | |
| 1月13日(長保2年12月16日) | 藤原定子が媄子内親王を産んで間もなく死去。鳥辺野に埋葬される。 |
| 1004年 | |
| 4月 6日(寛弘2年 2月25日) | 藤原伊周が准大臣に定められる。大臣の下で大納言の上に当たる新たな地位で、伊周は儀同三司と自称した。一旦は失脚した伊周が復権したのは、この時点ではまだ一条天皇の皇子が伊周の姉定子が産んだ敦康親王しかいなかったため、藤原道長としても権力維持には親王を立てる必要があったため。 |
| 1005年 | |
| 遼の聖宗による南進を受けて、北宋と遼の間で交渉が行われ、宋から毎年絹20万匹・銀10万両を送ることで和睦が成立。澶淵の盟が結ばれる。 | |
| 1006年 | |
| 5月 1日(寛弘3年 4月 2日) | 超新星SN1006が観測される。明月記や宋史に記述がみられる。おおかみ座の7,200光年の距離にある星。 |
| この頃、アイスランドのバイキングが入植した現在のニューファンドランド島ランス・オ・メドー付近で、入植者と先住民「スクレリング」との間で戦闘があったとされる。先住民との対立が原因で、この付近の入植地は短期間で放棄されたと考えられる。 | |
| 1007年 | |
| 9月26日(寛弘4年 8月13日) | 藤原伊周と隆家の兄弟が、伊勢の平致頼とともに、大和の金峰山に参詣に向かった藤原道長を暗殺する陰謀があるとの噂が流れ、急遽、頭中将源頼定が勅使として派遣される。 |
| 1008年 | |
| 10月12日(寛弘5年 9月11日) | 中宮彰子が敦成親王を出産。一条天皇の第二皇子。後の後一条天皇。藤原道長にとって待ちに待った外孫の皇子誕生であり、これにより道長の御堂流と、伊周の中関白家の立場逆転は強まっていくことになる。 |
| 12月 1日(寛弘5年11月 1日) | この日の紫式部日記にはじめて源氏物語の内容について記載が出てくる。少なくともこの年までには源氏物語が書き始められていたということになる。 |
| 1009年 | |
| 3月19日(寛弘6年 2月20日) | 藤原伊周の叔母に当たる高階光子が、源方理らとともに、藤原道長と中宮彰子を呪詛する呪符の制作を円能に依頼していたことが発覚し捕縛される。伊周も出仕を一時停止させられた。 |
| 1010年 | |
| 2月14日(寛弘7年 1月28日) | 藤原伊周が病死。中関白家の当主として、叔父の藤原道長最大の政敵だった人物。一度失脚するも復位したが、道長の娘の中宮彰子が皇子を産んだことで権力を取り戻すことはできなくなった。中関白家は子の道雅の素行が悪かったこともあり衰退していくが、長女はライバルの道長の次男頼宗に嫁いで藤原全子を生み、全子は藤原師通に嫁いだため、女系子孫は五摂家や羽林家に残った。 |
| この頃、バイキングのソルフィン・カルルセフニ・ソルザルソンが、60~250人の人々を率いて、北米のヴィンランドへの移住計画を実施したという伝説がある(1009年とも言われる)。ソルザルソンの息子スノッリ・ソルフィンソンは、この頃ヴィンランドで生まれたと言われ、北米大陸で最初に生まれた白人とも言われる。エリクソンの発見からここまでに5回のヴィンランド遠征があった。ヴィンランド入植地はその後、原住民との争いや気候変動で短期間で失われたが、北米交易はしばらく続いたという説もある。 | |
| 11世紀の初頭に、イングランドのベネディクト会の修道士であったマルムズベリーのエイルマーが、両手両足に人工の翼を付けて、マルムズベリー修道院の塔から飛び降りる飛行実験を行う。一説には200mほど飛んで(滑空して?)路地に墜落し、エイルマーは重症を負って障害者となったが、それでも飛行実験に意欲を示したといわれる。 | |
| 1013年 | |
| 5月(長和2年4月) | 藤原道雅が、敦成親王の従者小野為明を拉致して暴行を加える事件を起こす。 |
| 1019年 | |
| 5月 4日(寛仁2年 3月27日) | 刀伊の入寇。朝鮮半島から賊船50隻3000人ほどが対馬を襲撃。殺戮放火略奪を行う。そのまま壱岐を襲い島分寺を焼き住民を連行、さらに筑前に上陸。太宰権帥であった藤原隆家や、松浦の源知らに率いられた武士団によって撃退される。住民365人が殺害され、1289人が連れ去られた。高麗人の捕虜が複数いたため、高麗の襲撃と考えられたが、対馬判官の長嶺諸近が家族を探して高麗へ行き得た情報と、高麗から救出された住民270人が送り返されたことから、「刀伊(とい)」と呼ばれる集団であったと判明。女真族の一派ではないかと見られている。 |
| 1024年 | |
| 6月24日 | イタリアの修道士グイード・ダレッツォによって音階を表す「階名唱法」が誕生する。いわゆるドレミファソラシの原型。 |
| 1025年 | |
| 1月 8日(万寿元年12月6日) | 花山法皇の皇女上東門院女房が夜間に路上で殺害される事件が起きる。 |
| 4月(万寿2年 3月) | 上東門院女房殺害事件で、法師隆範が犯人として捕らえられ、尋問の結果、藤原道雅の指示だったと自供。 |
| 8月24日(万寿2年 7月28日) | 上東門院女房殺害事件で、盗賊が自首する。この盗賊が犯人なのか、藤原道雅が法師隆範に命じたのか、また刑罰が行われたのか詳細は不明。ただ藤原道雅は翌年左遷されている。 |
| 1028年 | |
| 1月 3日(万寿4年12月 4日) | 藤原五摂家の祖である藤原道長が死去。当時の記録から、糖尿病、癌、ハンセン病などが死因の候補として考えられる。 |
| この年、上総・下総・常陸に勢力を持つ有力豪族の平忠常が安房守平維忠を殺害して反乱を起こす。 | |
| 1031年 | |
| (万寿4年 6月) | 平忠常の乱が、追討使となった源頼信に忠常が降伏したことにより終結。中央の権力争いや追討使の人選ミスで事態が悪化し長期化していた。この結果、源頼信の力が増し、関東に源氏勢力が地盤を築くきっかけとなった。 |
| 1034年 | |
| (景祐元年) | 黄河が大氾濫を起こす。以降、しばしば氾濫を繰り返すようになり、河道も細かく変遷するようになる。 |
| 1036年 | |
| 5月15日(長元9年 4月17日) | 後一条天皇が崩御する。糖尿病と見られる。急死だったことから譲位の儀式ができなかったため、喪を秘して、弟の敦良親王(後朱雀天皇)へ譲位を行ったことにし、「上皇」として葬儀を行った。これは後の先例となった。 |
| この年、西夏文字が公布される。李元昊の指示で野利遇乞・野利仁栄らによって創造された。タングート語を表す文字で、漢字に似た構造になっているがより複雑なものが多い。約6000文字があり、西夏滅亡後も長く使われ続けた。 | |
| 1038年 | |
| 8月15日 | ハンガリーの初代国王イシュトヴァーン1世が亡くなる。 |
| 10月11日 | 宋の夏国公で事実上独立勢力と化していた李元昊が皇帝を称し、国号を大夏と定め、いわゆる「西夏」を建国。 |
| 1041年 | |
| (長久2年) | この頃以降に、女流歌人の赤染衛門が死去したと見られる。曾孫の時代まで生きておりかなりの長命だった。赤染時用(もしくは平兼盛)の娘で多数の和歌を遺したほか、「栄花物語」全40巻のうちの正編30巻の作者と考えられている。大江匡衡と結婚しており、子孫は大江氏・毛利氏と続く。 |
| 1043年 | |
| 4月 3日 | エドワード懺悔王がイングランド王に即位。 |
| 1047年 | |
| 1月22日(永承元年12月24日) | 火災で興福寺の伽藍の殆どが焼失。 |
| 1054年 | |
| 6月16日 | ローマ教皇の使者としてコンスタンディヌーポリを訪れていたフンベルト枢機卿が、総主教ミハイル1世らへの破門状を渡し、ミハイル1世もローマ側を破門。東西教会の分裂。 |
| 7月 4日(天喜2年 5月26日) | SN1054と呼ばれる超新星が出現。23日間にわたって昼間でも見える。おうし座の7,000光年の距離にある星で、現在はその残骸が「かに星雲」となっている。藤原定家の『明月記』や中国の『宋史』に詳しく、『一代要記』『天文志』などにも記述がある。史上最も有名な超新星の一つ。 |
| 7月20日(天喜2年 8月25日) | 左京大夫藤原道雅が死去。藤原伊周の子で、歌人として名を知られた人物だが、素行が甚だ悪く、暴力事件や密通事件を繰り返し、皇女殺害の嫌疑もかけられた。そのため従三位まで昇進したにも関わらず、中関白家に権力を取り戻すことはできず終わった。 |
| 1056年 | |
| 4月 5日(天喜4年 3月18日) | 超新星が消える。653日間、夜空に輝いていた。最大で金星くらいの明るさがあったとされている。 |
| 1066年 | |
| 10月14日 | ヘイスティングスの戦い。ノルマンディー公ギヨーム2世と、イングランド王ハロルド2世が、ヘイスティングス郊外のバトルで戦い、ハロルド2世は敗死。 |
| 12月25日 | ノルマンディー公ギヨーム2世が、ウェストミンスター寺院で戴冠し、ウィリアム1世としてノルマン朝を開く。いわゆる「ノルマン・コンクエスト」。 |
| 1068年 | |
| 5月22日(治暦4年 4月19日年) | 後冷泉天皇が崩御し、皇太弟尊仁親王が即位(後三条天皇)。後朱雀天皇の第二皇子で後冷泉天皇の異母弟。170年ぶりに藤原氏を外戚に持たない天皇(ただし藤原道長の外孫ではある)。東宮時代に、尊仁親王では外戚にならない関白藤原頼通から、藤原氏所有で東宮の証である「壺切御剣」を渡されないなどの仕打ちを受けていた。 |
| 1069年 | |
| (延久元年) | 後三条天皇によって、延久の荘園整理令が実施される。審査機関として記録荘園券契所を設立し、全国の荘園を調査、公験などの公式文書の有無を確認し、違法に設立されたり土地交換が行われた荘園は没収する。それまでの荘園整理令が形式的なものだったのに対し、延久の荘園整理令は、藤原氏や大寺社の荘園まで詳細に調査された。これは後三条天皇が藤原氏を外戚に持たず、反摂関家公卿らを側近に置いて親政を強行できたため。摂関家の荘園は大打撃を受け、摂関政治の衰退につながったとも言われる。 |
| 1070年 | |
| (延久2年) | この年、後三条天皇の勅により、蝦夷征伐が行われる(延久蝦夷合戦)。陸奥守源頼俊が清原貞衡の軍事支援のもと陸奥北部へ侵攻。ところがこのさなかに陸奥の在庁官人藤原基通が国司の印と国倉の鍵を盗み逃走する事件が発生。基通は下野国まで逃亡後、下野守源義家に投降。義家はこれを理由に源頼俊罷免を朝廷に訴え、頼俊は解官され帰京することになるが、その際に大きな戦果を報告し、それを受けて清原貞衡が功績を賞せられて鎮守府将軍に任ぜられる。遠征や盗難事件自体、源頼俊と源義家の勢力争いが背後にあるともされる。蝦夷との合戦はその後も続き、下北半島北端まで朝廷の支配に入ったとする説もある。 |
| 1073年 | |
| 1月18日(延久4年12月 8日) | 後三条天皇が貞仁親王に譲位(白河天皇)。後三条は上皇となる。後三条が院政を敷くために譲位したのか、病によって譲位したのかは説が分かれる。 |
| 6月15日(延久5年 5月 7日) | 後三条上皇が崩御。 |
| 1075年 | |
| この頃、フマイ王によって、チャド湖周辺を基盤とするカネム帝国セフワ朝が成立する。イエメン人王朝を名乗っているが、ベルベル系王朝という説も有力。 | |
| 1077年 | |
| 1月25日 | カノッサの屈辱。神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世が、破門を解いてもらうため、ローマ教皇グレゴリウス7世の滞在するカノッサ城門で3日間立ち尽くした出来事。ただし皇帝は、破門解除後に教皇を軍事力で追い払っている。 |
| ハンガリー国王にラースロー1世が即位。国内の混乱を収め、勢力を拡大。 | |
| 1084年 | |
| 北宋の歴史家司馬光によって『資治通鑑』が完成する。紀伝体が一般的な中国で、編年体で書かれた歴史書の代表作。全294巻。 | |
| 1085年 | |
| イングランドで最初の土地台帳「ドゥームズデイ・ブック」が作られる。 | |
| 1087年 | |
| 12月11日(寛治元年11月14日) | 出羽清原氏の内紛から始まった後三年の役が終結。陸奥安倍氏の血を引き、出羽清原氏に育てられた藤原清衡が、奥州藤原氏の基礎を築く。 |
| 1088年 | |
| イタリアのボローニャ大学が創立されたとされる年。実際にはそれ以前から教育機関が存在していたとみられる。9つの中世大学(ストゥディウム・ゲネラーレ)の一つで、近代大学最古のひとつ。 | |
| 1095年 | |
| ローマ教皇ウルバヌス2世によって聖地エルサレムの回復のために十字軍派遣が決まる。第1回十字軍。 | |
| 1096年 | |
| 8月 | 第1回十字軍の本隊が出発。 |
| 10月21日 | 民衆十字軍壊滅。十字軍に合わせて編成された民衆や騎士らの十字軍が、ルーム・セルジューク朝のクルチ・アルスラーン1世の軍勢に襲われ壊滅する。 |
| 1097年 | |
| 5月14日 | 東ローマ帝国と十字軍がルーム・セルジュークの首都ニカイアを包囲。 |
| 6月19日 | 東ローマ帝国がニカイア側と降伏交渉を行い、ニカイアは降伏するも、十字軍は排除されたため、帝国と十字軍は対立。 |
| 6月26日 | 十字軍はニカイアを出発。 |
| 7月 1日 | 十字軍が、襲ってきたセルジューク軍とダニシュメンド朝の軍勢を破る。 |
| 10月20日 | 十字軍が、アンティオキアを包囲。 |
| 1098年 | |
| 6月14日 | アンティオキアを攻略中に、ペトルス・バルトロメオによってキリストを貫いた「ロンギヌスの槍」が「発見」される。 |
| 6月28日 | 十字軍がアンティオキアを陥落。 |
| 1099年 | |
| 2月16日(承徳3年1月24日) | 康和地震。興福寺や天王寺で建物の倒壊などの被害が発生。まもなく康和に改元。 |
| 4月 8日 | 幻視に従い「ロンギヌスの槍」を「発見」したペトルス・バルトロメオの主張が正しいかどうかを確かめるための神明裁判が行われる。炎の中を通り抜けようとしたペトルスは大やけどを負う。 |
| 4月20日 | ペトルス・バルトロメオが大やけどがもとで死亡する。彼が「発見」した「ロンギヌスの槍」も偽物とみなされ、その後行方不明に。なお、これより前に「発見」された「ロンギヌスの槍」は、東ローマ帝国首都コンスタンティノープルのアヤ・ソフィア大聖堂に保管されていた。 |
| 6月 7日 | 十字軍がエルサレムを包囲。 |
| 7月15日 | 十字軍がエルサレムを陥落し、一応の目的が達せられる。 |
| 1101年 | |
| (康和3年) | 大宰大弐大江匡房から対馬守源義親の乱暴狼藉の訴えがある。 |
| 1102年 | |
| (康和4年) | 朝廷は、源義親を隠岐流罪の処分と決定するが、義親は隠岐へは行かなかったのか、出雲で騒動を引き起こす。 |
| この年、ロンドンの郊外にある平原スミス・フィールドに、イングランド王ヘンリー1世の道化師レヒアが、聖バーソロミュー修道院を建設。周辺に市が立ち、劇場・見世物市・家畜市場として賑わうようになる。のちには処刑場としても知られるようになった。 | |
| 1105年 | |
| 3月 3日(長治2年 2月15日) | 藤原清衡が平泉に最初院多宝寺(中尊寺)を建立。 |
| 1108年 | |
| 2月 2日(嘉承2年12月19日) | 平正盛が、出雲で勢力を広げる源義親討伐を命ぜられる。 |
| 3月 3日(天仁元年 1月19日) | 平正盛が源義親討伐を終える。 |
| 3月13日(天仁元年 1月29日) | 平正盛が源義親の首級を掲げて京に凱旋。見物人で大騒ぎとなる。白河法皇の評価も高く、後の平清盛につながる伊勢平氏台頭のきっかけとなった。なお、源義親を名乗る人物がその後、次々と現れて、大きな騒動に発展するため、この討伐で殺されたのは別人ではないかという説も当時からあった。 |
| 8月29日(天仁元年 7月21日) | 浅間山が大噴火。大量の降灰により上野国に甚大な被害をもたらす。火砕流も発生。 |
| 1112年 | |
| 11月11日(天永3年10月20日) | この日以降何度か、京の都で東方から大きな音が響きわたり人々が不安におののく。東から上洛した人が、富士山の噴火を伝えるが駿河国司からの報告はなかった模様。 |
| 12月14日(天永3年11月24日) | 伊豆国司より使者が京に到着し、伊豆の東方沖合で火が見え大きな音がしたと報告。伊豆諸島で噴火があったと見て、27日に朝廷で吉凶を占う神事を行う。 |
| 1113年 | |
| 11月13日(永久元年10月 3日) | 鳥羽天皇暗殺計画が発覚。永久の変(千手丸事件)。鳥羽天皇の准母令子内親王のところに暗殺計画を訴える密告書が投げ込まれ、内親王から話を聞いた白河法皇が検非違使を派遣。犯行を計画していたのは醍醐寺座主勝覚に仕える千手丸という稚児で、千手丸は尋問で、計画を立てたのは勝覚の実兄で三宝院阿闍梨の仁寛であると自供。仁寛は法皇の異母弟輔仁親王の護持僧であることから、天皇が崩御して輔仁親王が皇位を継承することを狙ったものとされた。白河法皇は公卿らと協議し、千手丸を佐渡に、仁寛を伊豆に流罪としたが、勝覚や、仁寛と勝覚の実父である左大臣源俊房は無関係として無罪にした。輔仁親王は無罪を主張して自宅に蟄居した。事件は白河法皇黒幕説と、輔仁親王黒幕説とがある。後三条天皇が白河天皇に譲位したあと、摂関家との関係が薄い輔仁親王に皇位を継がせるよう遺したことに白河上皇が逆らって自身の子孫に皇位を継がせたことが遠因。 |
| 1115年 | |
| 1月28日(収国元年 1月 1日) | 女真族完顔部の族長阿骨打(アクダ)が、遼からの自立を図って皇帝を名乗り、大金国(アルチュフ)を建国。年号を収国と建元。上京路に会寧州を置いて都と定める。国号のアルチュフとは完顔部族の拠点だった按出虎水が砂金が採れることで「金」を意味するアルチュフと呼ばれていたこと、金は変質しない永遠の金属であることから。 |
| 1120年 | |
| (宣和2年) | 北宋は、金王朝の台頭を見て、遼を挟撃するための「海上の盟」を金との間で結ぶ。しかし宋は南方で起こった方臘の乱鎮圧のため、対遼作戦が遅れることに。 |
| 11月25日 | ホワイトシップの遭難事件。ノルマン朝のヘンリー1世の嫡男ウィリアムや、王族らが乗ったホワイトシップ号がノルマンディー沖で遭難。ウィリアムの代わりにマティルダが王位を受け継ぐも内戦となる。 |
| 1121年 | |
| 3月 7日 | 遼の天祚帝と、金の阿骨打が入来山で戦い、遼が大敗。天祚帝は燕京から逃走。 |
| 3月13日 | 天祚帝が敗走したことを受けて、遼の皇族の耶律大石と李処温らが、天祚帝を湘陰王に格下げし、その従父の耶律涅里(劉淳・天錫帝)を強いて擁立。北遼王朝。 |
| 6月 | 天錫帝が死去。耶律大石らは、耶律定を擁立。天錫帝の蕭徳妃が摂政となる。 |
| 1123年 | |
| 2月 (保大3年・徳興2年) | 阿骨打、燕京を攻め、耶律大石らは耶律定・蕭徳妃らと天祚帝のもとへ逃走。天祚帝によって、耶律定は王位に格下げされ、蕭徳妃は処刑される。 |
| 5月 8日(神暦元年) | 蕭徳烈らが耶律雅里を北遼の皇帝として擁立。 |
| 9月19日(天輔7年8月28日) | 阿骨打、遼の天祚帝を追撃中に部堵濼で病死。同母弟の呉乞買(ウキマイ)が後を継ぎ、第2代皇帝となる。 |
| 10月 (神暦元年) | 耶律雅里は病没。そのため、耶律朮烈(英宗)が擁立される。 |
| 11月 (神暦元年) | 金軍が燕京を包囲し、英宗は家臣たちに弑されて北遼は滅亡。 |
| 1124年 | |
| 呉乞買、遼を攻め、耶律大石は西方へ逃走。北庭都護府可敦城で自立。 | |
| 1125年 | |
| (天会3年) | 呉乞買、北宋との盟約に基づき遼を攻め、遼の天祚帝は捕らえられて、遼は滅亡。 |
| 1127年 | |
| 1月 9日(天会5年・靖康元年11月 5日) | 靖康の変。金の2代皇帝呉乞買の軍勢によって宋(北宋)の都開封が陥落し、皇帝欽宗と太上皇徽宗、多くの皇族や官僚、および皇族や貴族女性ら1万1千人あまりが尽く金に連行され滅亡する。女性らは戦利品として金の有力者に分配された他、公営の売春施設である洗衣院など各施設に送られたという。 |
| 6月12日(建炎元年) | 靖康の変を逃れた欽宗の弟の康王趙溝が江南に南宋王朝を興す。 |
| 1128年 | |
| 1月13日 | テンプル騎士団が教皇ホノリウス2世によって正式に騎士修道会として認可される。 |
| (建炎2年) | 南宋の杜充が金軍の南下を阻止するため、黄河を決壊させる。このため南側で大氾濫し、水は淮河と合流。黄河の水の大部分は黄海へと流れ込むようになる。現在の位置に戻るのは700年後の1855年。 |
| 1129年 | |
| 1月 (大治4年 1月) | 平清盛が、12歳で従五位下・左兵衛佐となる。 |
| 1130年 | |
| (天会8年) | 金、独立した耶律大石に対し、同族の耶律余賭を派遣して攻撃。しかし耶律大石は激戦を避けて西へ退却。ビシュバリクの天山ウイグル王国ビルゲ可汗のもとへ至る。ビルゲ可汗、耶律大石と対立するものちに従属。 |
| 1131年 | |
| 秦檜が南宋王朝の宰相となる。金と手を組んで和平政策を推し進める。 | |
| 1132年 | |
| (天承2年) | 平忠盛が、鳥羽上皇勅願の得長寿院造営を担当し、千体観音を寄進したことで、内昇殿を許される。武士としては当時かなり異例な破格の待遇で、反感を持った公家たちから命を狙われる。 |
| 5月 6日(天承2年(長承元年) 4月19日) | 末代と頼然が富士山頂に登る。頂上で金時上人・覧薩上人・日代上人らの遺品を発見したという。 |
| 耶律大石が西遼(カラ・キタイ)を建国。ベラサグンをグズオルドとあらため、都に定める。 | |
| (天会10年) | 耶律余賭・蕭高六・蕭特謀らが金の太宗暗殺の計画を立てるも露見。蕭高六は捕らえられ処刑、蕭特謀は自殺、耶律余賭は西遼を建国した耶律大石のもとへ逃走を図るが、中途にある西夏の崇宗(李乾順)が出兵したため、モンゴルへ向かうも捕らえられ処刑される。 |
| 1135年 | |
| 1月(天会13年 1月) | 高麗の西京で僧の妙清らが反乱を起こし、国号を「大為」とし、年号は中国のものを採用せず独自の「天開」とする。国粋的な思想から西京への遷都と金国討伐を主張して、中国寄りの守旧派の貴族層と対立したが、主張が受け入れられなかったため、西京の貴族層を取り込んで起こしたもの。仁宗は鎮圧軍を派遣。 |
| 2月 9日(天会13年 1月25日) | 金の2代皇帝呉乞買(ウキマイ・太宗)が死去。金の領土を拡大させた皇帝。阿骨打の孫の合剌(ホラ)が3代皇帝に即位。 |
| 1136年 | |
| 2月(天会14年 2月) | 高麗で起きた妙清の乱が金富軾らの率いる国軍によって鎮圧される。金富軾らは文官(文班)でこの功績により勢力を拡大。金富軾は「三国史記」を編纂したがその主張立場が出ている。 |
| 1141年 | |
| (紹興10年) | 南宋と金の間で、紹興の和議が結ばれる。領土が確定し、南宋は金に対し、銀25万両と絹25万疋を収めることになる。 |
| 1142年 | |
| 1月27日(紹興11年12月29日) | 南宋の将軍で対金強硬派の岳飛が、和平派である宰相の秦檜の手で誅殺される。 |
| 1143年 | |
| 耶律大石が、遼の故地を奪還するため、金に対し7万の兵で出兵するが病死し、遠征は中止される。西遼の皇位は耶律夷列が継ぐ。 | |
| 1147年 | |
| 7月14日(久安3年 6月15日) | 祇園闘乱事件。祇園社へ参詣に出た平清盛の一行が、携行する武器をめぐって神人と言い争いになり、清盛の家人が放った矢が宝殿に刺さった事件。 |
| 7月25日(久安3年 6月26日) | 祇園闘乱事件を受けて、比叡山延暦寺が事件を上皇に告訴。平忠盛は下手人7人を差し出す。 |
| 7月27日(久安3年 6月28日) | 祇園闘乱事件の平氏の対応を受けて、比叡山延暦寺が僧兵を繰り出し、忠盛と清盛の処罰を求めて強訴に及ぶ。上皇側が処置を決済すると院宣を出したので一旦は引き下がる。 |
| 7月29日(久安3年 6月30日) | 上皇のもとで公卿らが集まり、祇園闘乱事件の処置について詮議が行われる。藤原頼長が平忠盛の責任を主張するも、大方は忠盛に非はなしと判断。 |
| 8月13日(久安3年 7月15日) | 祇園闘乱事件の処置が遅れているため、延暦寺が再び強訴に及ぼうとしたため、上皇は院宣でこれを止めるよう延暦寺に求め、北面の武士を派遣する。 |
| 8月22日(久安3年 7月24日) | 公卿等による祇園闘乱事件の処置が決まらないため、上皇が平清盛を「贖銅三十斤」の罰金刑とする決定を下す。 |
| 8月25日(久安3年 7月27日) | 朝廷から祇園社に対して、祇園闘乱事件の謝罪のための奉幣使が派遣される。 |
| 9月 1日(久安3年 8月 5日) | 平清盛が「贖銅三十斤」の罰金を支払う。 |
| 1148年 | |
| 3月12日(久安4年 2月20日) | 祇園闘乱事件でこじれた関係を修復するため、平忠盛が祇園社へ自領を寄進し、法華八講を祗園社で行う。 |
| 1149年 | |
| 5月24日(久安5年4月16日) | 末代が富士山頂に大日寺を建立。 |
| 1150年 | |
| 1月 9日(皇統9年/天徳元年12月 9日) | 金の3代皇帝合剌(ホラ・熙宗)が、従弟の完顔迪古乃(テクナイ)、側近の徒単阿里出虎、大興国ら10人に寝室を襲われ、滅多斬りにされて殺害される。粛清を繰り返し暴虐だったことが理由とされる。迪古乃が4代皇帝に即位する。 |
| この頃、パリ大学が創設されたといわれる。9つの中世大学(ストゥディウム・ゲネラーレ)の一つ。 | |
| 1156年 | |
| 7月20日(保元元年 7月 2日) | 鳥羽法皇崩御。死に際に実子の崇徳上皇が見舞いに来るが拒絶される事件が起こる。 |
| 7月23日(保元元年 7月 5日) | 崇徳上皇と藤原頼長が手を組み、国家を傾けんと画策している、との噂が広がり、検非違使が招集される。 |
| 7月27日(保元元年 7月 9日) | 崇徳上皇が突如、鳥羽田中殿を脱出して、洛東白河の統子内親王の御所に入る。平氏の拠点六波羅に近いため、平氏の支援を期待したものか(清盛の父、平忠盛の妻池禅尼は崇徳の子重仁親王の乳母で忠盛が後見を務めていたため)。しかし池禅尼は、崇徳方敗北を予測し、平氏は動かず。 |
| 7月28日(保元元年 7月10日) | 崇徳上皇のもとに、藤原頼長、藤原教長、藤原盛憲、藤原経憲、源為義、平忠正らが合流。源為朝が夜襲を進言するが、藤原頼長はこれを卑怯だと一蹴する。一方、後白河天皇方にも藤原忠通、藤原基実、源義朝、平清盛、源頼政らが集結。軍議により相手方への夜襲が決定する。 |
| 7月29日(保元元年 7月11日) | 保元の乱が始まる。後白河天皇方の軍勢が、崇徳上皇方を夜襲。一進一退の攻防となるが、源義朝らが白河殿に隣接する藤原家成邸を放火。崇徳方は混乱に陥り大敗を喫する。藤原頼長は逃走の際に首に矢が刺さり重症を負う。 |
| 7月31日(保元元年 7月13日) | 崇徳上皇が仁和寺の弟覚性法親王を頼って出頭。 |
| 8月 1日(保元元年 7月14日) | 藤原頼長が重症の身で大和奈良の父忠実のもとに逃走するが受け入れてもらえず、叔父千覚のいる興福寺に入り、そこで死亡。 |
| 8月10日(保元元年 7月23日) | 崇徳上皇が讃岐へ配流となる。 |
| 8月15日(保元元年 7月28日) | 平忠正が平清盛の手で処刑される。死刑は薬子の変以来行われていなかった。 |
| 8月17日(保元元年 7月30日) | 源為義が、息子の義朝の手で処刑される。 |
| 9月12日(保元元年 8月26日) | 源為朝が捕らえられる。伊豆大島へ流罪。 |
| 11月 2日(保元元年閏9月18日) | 後白河天皇によって、保元新制の宣旨7カ条が発せられる。荘園整理を目的にしたもので、後白河の側近、信西が台頭し政権を担って国政改革に乗り出す。 |
| 1157年 | |
| 5月 6日(保元元年 3月26日) | 後白河天皇によって、武蔵守藤原信頼が抜擢され、右近衛中将となる。以後、急速に台頭。 |
| 1160年 | |
| 1月19日(平治元年12月 9日) | 平治の乱が始まる。政権を握っていた信西一族を滅ぼすため、平清盛の熊野参詣の留守中を狙い、藤原信頼を中心に、二条天皇派と後白河院派が連携して挙兵。源義朝、源光保、源頼政らが御所と三条殿を襲撃して、後白河上皇・上西門院を捕らえる。信西は逃走。 |
| 1月23日(平治元年12月13日) | 信西は逃走不可能と判断し、山城田原で郎党の藤原師光らに自分を埋めさせ自害した(追手に見つかった後自害したという説もある)。信西の死により、二条派と後白河派の対立が再燃。 |
| 1月27日(平治元年12月17日) | 京の異変を知った平清盛一行が、熊野から帰京。信西派の内大臣三条公教が清盛と二条天皇派を説得し反信頼派を形成。 |
| 2月 4日(平治元年12月25日) | 平清盛は、藤原信頼に恭順の姿勢を見せる名簿を提出。一方で三条公教らと二条天皇の六波羅行幸を画策。天皇は軟禁場所から脱出し、六波羅の清盛邸へ入る。 |
| 2月 5日(平治元年12月26日) | 二条天皇の六波羅行幸が知れ渡り、公卿らが相次いで平氏側に旗色を鮮明にする。源義朝は事態を知り、油断していた信頼を罵倒、信頼・藤原成親と出兵するが、源師仲は内侍所(神鏡)を持ちだして逃走。源頼政も離反。両勢力は六波羅付近の六条河原で衝突。兵力差で平清盛側が勝利する。 |
| 2月 6日(平治元年12月27日) | 平治の乱の首謀者、藤原信頼が公卿の身で斬首される。藤原成親は、妹経子が平重盛の妻だった関係で、解官の軽い罪で許された。 |
| 2月 8日(平治元年12月29日) | 平治の乱後、比叡山の僧兵による落ち武者狩りで負傷した源朝長が死亡。 |
| 2月11日(平治2年 1月 3日) | 源義朝と鎌田政清が東国へ落ち延びる途中、政清の舅で義朝の家人であった長田忠致の尾張の邸宅で長田に裏切られ殺害される(裏切りに気づいて自刃したとも)。 |
| 3月 4日(永暦元年 1月25日) | 源義平が捕らえられ六条河原で処刑される。 |
| 1161年 | |
| 10月27日(正隆6年/大定元年10月 7日) | 金の葛王の完顔烏禄(ウル)が、東京副守の高存福を殺害した上で、臣下に擁立される形で即位。5代皇帝世宗。4代皇帝迪古乃(テクナイ)が南宋遠征中に起きたクーデター。 |
| 12月15日(正隆6年/大定元年11月27日) | 金の4代皇帝の迪古乃が臣下に殺害される。世宗によって廃位され海陵郡王(さらに落とされて廃帝海陵庶人)とされたため、一般には海陵王と呼ばれる。文武両道だったが、即位後は奢侈が甚だしく、一族多数を次々と殺害した上でその妻女を後宮に入れ、さらに気に入った女性を次々と襲うなど淫乱暴虐な皇帝として記録されている。南宋を滅ぼそうと反対を押し切って侵攻したがそのさなかに完顔烏禄(世宗)が擁立される事態になり、臣下の完顔元宜(耶律阿列)によって揚州の亀山寺で殺害された。世宗が妻の烏林荅氏を自殺に追い込まれて恨んでいたことから、より悪く記録されるようになったという説もある。漢族を積極的に雇用し、国家制度を整え、析津府を大改造して中都大興府とし上京会寧府から首都を移した。これが今の北京の原型とされる。 |
| 1164年 | |
| 9月14日(長寛2年 8月26日) | 保元の乱で敗者側に付いた第75代天皇だった崇徳上皇(崇徳院)が、流刑先の讃岐で崩御。後白河上皇へ送った和解の写経を破られて送り返されたのを苦にして自殺したとも、暗殺されたという話もある。これらから怨霊伝説が生まれた。 |
| 1165年 | |
| 1月30日(長寛2年12月17日) | 三十三間堂が落慶。後白河上皇が平清盛に協力させて建設した院の御所「法住寺殿」の本堂。 |
| 1167年 | |
| 3月 4日(仁安2年 2月11日) | 平清盛が太政大臣に就任。武士階級では前代未聞の出世だが、摂関時代以降、官職そのものには実質的な権力はなかった。 |
| (大定7年閏7月18日) | 王重陽が馬丹陽を弟子に迎え入れ、のちに道教二大宗派のひとつとなる全真教を興す。教団名は馬丹陽が提供した庵「全真」の名前から。人々が弟子に志願して集まってくるが、新たに弟子として認められたのは、丘長春(丘処機)・譚長真(譚処端)・郝広寧(郝璘)・王玉陽(王処一)の4人。 |
| イングランド王ヘンリー2世が、イングランドの学生がパリ大学で学ぶことを禁じたため、あらたにオックスフォード大学が開学する。ただしその前から、前身の教育機関があったと考えられる。9つの中世大学(ストゥディウム・ゲネラーレ)の一つ。 | |
| 1169年 | |
| イタリア半島のエトナ火山が大噴火。16000人が死亡。 | |
| 1170年 | |
| 1月22日(大定10年 1月 4日) | 全真教の開祖、王重陽が死去。 |
| 4月23日(嘉応2年 4月 6日) | 源為朝自害。生き延びて琉球へ旅だった説もある。 |
| 8月16日(嘉応2年 7月 3日) | 殿下乗合事件。法勝寺に向かう途中の摂政松殿基房の一行が、鉢合わせした女車の無礼をとがめて乱暴。その後、女車の主が平資盛であることがわかり謝罪するが資盛の父平重盛が反発。 |
| 9月(大定10年 8月) | 高麗で庚寅の乱が起こる。文臣(文班)の権力横行に反発していた武臣(武班)派の李義方と李高が、上将軍の鄭仲夫とともに起こした反乱で、都の開京に攻め込み、文臣らを虐殺。武臣政権が樹立する。 |
| 11月22日(大定10年10月13日) | 高麗王毅宗が武臣政権によって退位させられ、巨済島へ流される。弟の明宗が即位。 |
| 11月30日(嘉応2年10月21日) | 高倉天皇の加冠の儀に参加するため朝廷に向かった松殿基房の車列を、平重盛の兵が襲撃し、4人が髷を切られる事件が起こる。加冠の儀は中止に。殿下乗合事件の報復とされる。 |
| 11月28日 | グウィネズの王で、ウェールズを事実上支配したオワイン・グウィネズが死去。グウィネズ家は内紛状態になる。またこの年、オワインの子とされるマドック王子が、100人の男女を率いて大西洋を横断し、北アメリカに到達し移住地を作ったとウェールズの伝承に出てくる。マドックは再度ウェールズに戻って移民を募り、再びアメリカへ渡り戻らなかったとされる。史実としては信憑性が薄いが、物語としては有名。 |
| 1171年 | |
| 1月21日(嘉応2年12月14日) | 松殿基房、太政大臣となる。事態収拾を図る平清盛の推挙とも言われる。なお、『平家物語』では清盛と重盛の立場が逆で、清盛が報復し、重盛が収拾を図っている。 |
| 1173年 | |
| (大定13年) | 高麗の文臣である東北面兵馬使の金甫当が毅宗の復位を図って武装蜂起するも鎮圧される(癸巳の乱)。武臣政権はこれを機会と捉えてさらなる文臣弾圧を実施。 |
| 11月 7日(大定13年10月 1日) | 高麗の前王が武臣政権側の李義旼によって背骨を折られ殺害される。李義旼はこれを認められて将軍となるが、その残忍さが後で大きな問題にされる。毅宗は在位中、文臣に政権を任せて遊興に耽り、土木工事に武臣を動員するなどして武臣側の反感を招いた人物。 |
| 1175年 | |
| モデナ・レッジョ・エミリア大学が創設される。9つの中世大学(ストゥディウム・ゲネラーレ)の一つ。 | |
| 1177年 | |
| 5月27日(安元3年 4月28日) | 平安京で大火。通称「太郎焼亡」。出火場所は樋口富小路付近で、北西方向へと延焼。大内裏に到達し、大極殿は焼失。高倉天皇と平徳子は、藤原邦綱邸へ避難。八省すべてと大学寮・勧学院・神祇官の建物も焼け落ち、朱雀門や応天門も焼失。関白松殿基房邸、内大臣平重盛邸、大納言徳大寺実定邸など公卿の邸宅14家が被害に遭い、面積にしておよそ200町近く、家屋2万軒、平安京の三分の一が焼失したとも言われる。死者は数千人とも。大極殿の天皇の政務所(朝堂)としての機能はすでに形骸化していたため、以降再建されることはなかった。 |
| 6月28日(安元3年 6月 1日) | 平氏打倒の鹿ヶ谷の陰謀が発覚。陰謀に加わった多田行綱が平清盛に訴えでた。後白河院による山門(延暦寺)攻撃強行を避けたい平清盛による陰謀とも言われる。後白河院の側近で山門紛争にも関わった西光、藤原成親が捕らえられる。 |
| 7月 1日(安元3年 6月 4日) | 鹿ヶ谷の陰謀に加わったとして俊寛、平康頼、藤原成経、中原基兼らが拘束される。西光は斬首され、藤原成親は備前に流罪(後に殺害)、中原基兼は奥州に流罪、俊寛、平康頼、藤原成経は鬼界ヶ島に流罪となった。鬼界ヶ島は喜界島、薩摩硫黄島などが候補にあるが平家物語の記載では火山島で硫黄島とも呼ばれるとあるため薩摩硫黄島の可能性がある。平康頼、藤原成経は翌年許されたが、俊寛は許されず絶食自殺している。 |
| 1178年 | |
| 4月13日(治承2年 3月24日) | 平安京でふたたび大火が発生。通称「次郎焼亡」。前年の太郎焼亡の延焼地域の南側、七条東洞院から出火し、七条通り沿いに西に向かって延焼。朱雀大路に至った。30数町が焼失。 |
| 1179年 | |
| 12月17日(治承3年11月17日) | 治承三年の政変。平清盛が反平氏勢力の一掃をはかり京を制圧。後白河院の院政を停止し、公卿ら多数が逮捕され殺害されたり所領を没収されたクーデター事件。諸国の国主の入れ替えも行われ、中央政権に与するものが抜擢された。それが後の源氏の蜂起に諸豪族が加勢する遠因となったとも言われる。 |
| 1180年 | |
| 5月18日(治承4年 4月22日) | 安徳天皇が2歳で即位。第81代天皇。 |
| 5月23日(治承4年 4月27日) | 源頼朝が、叔父の行家から以仁王の平家追討令旨を伝えられる。 |
| 6月20日(治承4年 5月26日) | 南都へ向かう途中の以仁王と源頼政の軍勢が、宇治橋で平家の追討軍と対峙。平家側の渡河により頼政ら摂津源氏の軍勢は敗北し、宇治平等院から脱出した以仁王も逃走中に討たれる。 |
| 9月 8日(治承4年 8月17日) | 源頼朝の軍勢が挙兵。伊豆目代山木兼隆と後見役の堤信遠を討ち取る。 |
| 9月14日(治承4年 8月23日) | 石橋山の戦い。源頼朝の軍勢が平家方の大庭景親、伊東祐親の軍勢に大敗を喫す。当初、大庭景親は翌朝に攻撃を計画していたが、背後から三浦勢が接近していることを知り、暴風雨の中で夜討ちをかけた。圧倒的な劣勢の中で頼朝軍は奮戦するも佐奈田義忠は俣野景久らと戦い討ち死に。頼朝らは大庭景親に従っていた飯田家義に助けられて一旦退き、山中に隠れているところを同じく大庭方に付いていた梶原景時に見逃され、土肥実平の助けで真鶴より船で房総へ向かう。頼朝側についた北条氏や工藤氏・佐々木氏らも一旦散開して落ち延びるが、その過程で北条宗時は祐親の軍勢と遭遇して討ち死にし、工藤茂光は足手まといになると自害した。 |
| 9月15日(治承4年 8月24日) | 小壺坂合戦。源頼朝の挙兵に応じた三浦義澄・和田義盛の軍勢が、大雨で酒匂川を渡れず、引き返す途中で、平家方に付いていた畠山重忠軍と遭遇。三浦氏と畠山氏は縁戚関係にあり、両軍は一旦争わずに引き返そうとしたが、あとから合流した和田義茂が事情を知らず攻撃したため、両者交戦に発展。畠山勢は50人余りが討ち死にし、三浦勢は衣笠城まで退却。 |
| 9月16日(治承4年 8月25日) | 波志田山合戦。大庭景親の弟俣野景久と駿河目代橘遠茂の軍勢が、甲斐源氏の安田義定と波志田山で交戦。俣野景久は敗走。波志田山の場所は特定されてないが、富士山北麓と見られる。 |
| 9月17日(治承4年 8月26日) | 衣笠城合戦。衣笠城まで退却した三浦勢に対し、畠山重忠・河越重頼・江戸重長ら秩父氏一族が攻撃。当主で89歳の三浦義明が籠城戦を展開する中、一族の三浦義澄、佐原義連、大多和義久、和田義盛、援軍に来ていた金田頼次、長江義景らは、船で安房へと脱出。衣笠城は落城し義明は戦死。 |
| 9月20日(治承4年 8月29日) | 源頼朝、安房に到着。三浦義澄、安西景益らと合流。千葉常胤、上総広常ら下総の有力豪族に使者を送る。 |
| 9月23日(治承4年 9月 3日) | 源頼朝、上総広常と会うために出立。その夜、民家に泊まったところを、長狭郡の領主、長狭常伴に襲撃される。三浦義澄が防戦して長狭常伴は討たれる。これを受けて頼朝は一旦安西屋敷へ移り、和田義盛が交渉のために上総広常の元へゆくことになったとも言われる。長狭常伴が討ち死にしたことで安房の武士団は頼朝に付く。 |
| 9月24日(治承4年 9月 4日) | 結城浜の戦い。源頼朝は安房を出立して、千葉常胤と上総広常が合流。これに平氏方の下総判官代藤原親正が応戦、親正は敗北し捕虜となる。日付と内容は『源平闘諍録』による。 |
| 10月 3日(治承4年 9月13日) | 源頼朝の要請を受けて千葉常胤が味方につき、下総国府を襲撃。平家方の下総目代を殺害。 |
| 10月 4日(治承4年 9月14日) | 千葉常胤と、下総守に任じられた判官代藤原親政が戦い、親政は敗北し捕虜となる。日付と内容は『吾妻鏡』による。 |
| 10月 9日(治承4年 9月19日) | 上総・下総で最大の勢力である上総広常が2万騎を率いて、隅田川まで進出した源頼朝軍のもとに参向する。この時、遅参を指摘した頼朝を見て広常は帰服することを決めたとされるが、頼朝挙兵の時点ですでに味方になることを決めていたという説もある。関東の諸豪族の多くは平氏の出自だが、これらが頼朝に味方したのは、治承三年の政変後に国主の入れ替えがあり地元豪族が不利に置かれたことが背景にあると言われる。 |
| 10月(治承4年 9月) | 肥後国で菊池隆直らが平家に対して挙兵。 |
| 10月22日(治承4年10月 2日) | 源頼朝ら、武蔵国へ入る。平家方についていた畠山重忠・河越重頼・江戸重長ら秩父氏一族も降伏し許される。 |
| 10月26日(治承4年10月 6日) | 源頼朝、鎌倉へ入る。 |
| 11月 7日(治承4年10月18日) | 源頼朝の軍勢と武田信義ら甲斐源氏の軍勢が合流。 |
| 11月 9日(治承4年10月20日) | 富士川の戦い。源頼朝ら関東諸豪族の軍勢と武田信義ら甲斐源氏の連合軍に対し、討伐のために遠征してきた平家軍が富士川両岸で対峙するが、戦闘に至る前に平家軍が総退却、壊乱状態となる。平家軍退却の理由で有名なのは鳥が飛び立つ音に驚いたというもの。しかし元々平家軍は統率に失敗し離反者が相次いでおり、戦闘前から結果は出ていたという。なお、日付は諸本によって違いがある。 |
| 11月12日(治承4年10月23日) | 平家方の富士川の敗戦を受け、逃げ道を失った大庭景親が源頼朝に降伏。 |
| 11月15日(治承4年10月26日) | 大庭景親が処刑される。 |
| 11月16日(治承4年10月27日) | 源頼朝は富士川の戦いの勢いに乗って追撃戦を主張するが、上総広常、千葉常胤、三浦義澄らが、先に常陸の佐竹氏を討つよう訴え、源頼朝はこれを受け入れ常陸へ向けて出陣。佐竹氏は平氏側についていたが、伊勢神宮の荘園だった相馬御厨の支配権を巡って千葉常胤らと争っていたことが背景にある。 |
| 11月22日(治承4年11月 4日) | 上総広常、縁者でもある佐竹義政が帰服の姿勢を見せたことを利用して誘い出し、大谷橋でこれを殺害。義政の弟秀義は、金砂城に立てこもる。 |
| 11月23日(治承4年11月 5日) | 金砂城の戦い。源頼朝軍が、金砂城を総攻撃。これを攻め落とす。佐竹秀義は城を脱出し、奥州方面へと逃走。 |
| 12月 5日(治承4年11月17日) | 美濃源氏の土岐光長らが挙兵。 |
| 12月 8日(治承4年11月20日) | 近江源氏の山本義経・柏木義兼兄弟が挙兵。園城寺も協力して近江一帯を制圧。 |
| 12月 9日(治承4年11月21日) | 各地で反乱が相次いでいることから、平氏政権は福原から京へ拠点を戻すことを決定。 |
| 12月14日(治承4年11月26日) | 平清盛らが入京。 |
| 12月19日(治承4年12月 1日) | 近江源氏の挙兵に対し、平氏側の攻撃が始まる。 |
| 12月24日(治承4年12月 6日) | 平知盛の軍勢が山本義経・柏木義兼らを打ち破り、園城寺も攻撃。園城寺の権利や所領をことごとく没収。 |
| 12月(治承4年12月) | 伊予の河野通清が挙兵。翌年はじめに阿波の田口成良と備後の沼賀西寂に攻められ討ち死に。通清の子通信が沼賀西寂を討ち取り、水軍を率いて源氏に味方する。阿波の有力者田口成良は南都焼討から壇ノ浦まで平家方として参戦。最後に源氏方に寝返ったが源氏方によって処刑された。 |
| この年から翌年にかけて、全国で飢饉が広がる。通称「養和の大飢饉」。特に平安京の惨状は大きく、築地沿いや路上に多数の死体が放置され、悪臭が漂ったという。 | |
| 1181年 | |
| 1月15日(治承4年12月28日) | 平清盛、対立する南都(奈良)の東大寺や興福寺などの寺院勢力に対しても、討伐の兵を送る。平重衡、平通盛が軍を率い、寺院勢力も応戦。平家軍は各地に放火して攻勢をすすめるが、これが予想以上の大火になったと見られ一帯に延焼。東大寺は伽藍の主要な建物が焼失。大仏殿も焼け落ち、大仏も焼け溶ける。興福寺も伽藍のほぼ全てを焼失。僧侶や住民3500人以上が焼死したという。 |
| 1月30日(治承5年 1月14日) | 平氏政権の後ろ盾で院政を始めたばかりの高倉上皇が病気で崩御。21歳。 |
| 3月20日(治承5年閏2月 4日) | 平清盛が高熱を発して死去。南都焼討の仏罰と噂される。 |
| 3月31日(治承5年閏2月15日) | 源頼朝挙兵後、尾張・三河に独自勢力を広げ始めた源行家に対し、平氏政権は討伐の兵を送ることになり、平重衡が出陣。 |
| 4月16日(治承5年 3月 1日) | 平宗盛、父清盛が東大寺と興福寺に出していた処分を撤回。 |
| 4月25日(治承5年 3月10日) | 墨俣川の戦い。平重衡率いる平家軍に対し、源行家、源義円、山田重満らが応戦。源氏方は奇襲を仕掛けるが失敗し大敗。阿野全成の同母弟で、源義経の同母兄である義円は戦死、山田重満らも戦死した。行家は矢作川の戦いでも敗北し、鎌倉の源頼朝の元へ逃走。 |
| 5月 3日(治承5年 3月18日) | 南都の被害状況を調べるため、興福寺に藤原(葉室)光雅と藤原(日野)兼光が、東大寺に藤原(葉室)行隆が派遣される。藤原行隆は造東大寺長官として、造東大寺大勧進となった重源と共に東大寺復興を担当。 |
| 5月24日(治承5年 4月10日) | 平宗盛が推挙して、平家と関係の深い筑前の有力者原田種直を太宰権少弐とする。九州で起きた菊池隆直の乱に対応するため。 |
| 5月28日(治承5年 4月14日) | 原田種直に菊池隆直追討院宣がくだされる。中央からは平貞能が派兵される。 |
| 7月26日(治承5年 6月13日) | 横田河原の戦い。平家より命を受けた越後の城助職が信濃に侵攻、木曽義仲と対戦し敗北、越後へ退却する。 |
| 8月 4日(治承5年 6月22日) | 超新星SN1181が出現。以降185日ほど輝いていた。カシオペア座26,000光年にある星。『吾妻鏡』や、藤原定家の日記『明月記』に書かれた超新星の一つで、これは同日記と同時代の現象となる。超新星残骸「3C 58」が残っており、中性子星か、クォーク星ではないか、と考えられている。 |
| 1182年 | |
| 3月21日(養和2年 2月15日) | 源頼朝と対立した伊東祐親が、娘婿の三浦義澄の奔走で助命されるが、それを良しとせず自殺。息子の伊東祐清も死を願い殺害されたという(祐清は平家方に加わり戦死したという説もある)。 |
| 5月(養和2年 4月) | 菊池隆直が平貞能に降伏。年号の養和は平家方で使われたもので、源氏方では治承5年。 |
| 1183年 | |
| 3月15日(寿永2年 2月20日) | 源頼朝の叔父で、源平どちらにも関わらず常陸信太荘で独自勢力を持っていた志田義広が、頼朝から鹿島社領の押領を責められたことを口実に挙兵。下野の足利俊綱、小山朝政ら3万騎で鎌倉攻めを企図。 |
| 3月18日(寿永2年 2月23日) | 野木宮合戦。志田義広らと源頼朝方の軍勢が下野国野木宮で戦う。志田義広に応じる姿勢を見せた小山朝政は、当初から頼朝方に味方しており、近づいた志田義広軍を奇襲攻撃、乱戦となる。これに鎌倉から派兵された下河辺行平らと、足利俊綱の異母弟で鎌倉方についた足利有綱ら、さらに八田知家、宇都宮信房ら御家人に、源範頼も加わり、志田義広は敗北。木曽義仲の元へと逃亡する。鎌倉攻めを主張しながら下野方面へ進出しているため、もとから木曽義仲と連携しての挙兵だったという説や、源範頼が初めて登場することから、源範頼勢力と志田義広勢力との私戦という説もある。源頼朝は坂東を平定。合戦の日付には異説あり。 |
| 5月20日(寿永2年 4月27日) | 平維盛率いる平氏軍が越前火打城を攻め落とす。 |
| 6月 2日(寿永2年 5月11日) | 倶利伽羅峠の戦い。木曽義仲、源行家、樋口兼光らが、平維盛・平通盛・平知度・平行盛、平忠度ら平氏10万の軍勢を奇襲して倶利伽羅峠の崖に追い落とし大勝する。牛の角に松明を付けて襲わせる話で有名だが後世に脚色された話とも言われる。 |
| 8月14日(寿永2年 7月25日) | 木曽義仲の軍勢が京に迫り、後白河法皇も比叡山に退避したことから、平宗盛ら平氏一門は安徳天皇と三種の神器とともに京都を脱出する。 |
| 8月17日(寿永2年 7月28日) | 木曽義仲、入京。 |
| 8月19日(寿永2年 7月30日) | 朝廷で論功行賞が沙汰され、第一が源頼朝、第二が源義仲(木曽義仲)、第三が源行家となる。 |
| 8月25日(寿永2年 8月 6日) | 後白河法皇は、平氏一門の解官を決定。天皇の権限である除目も強行。 |
| 8月29日(寿永2年 8月10日) | 後白河法皇は、源義仲を従五位下・左馬頭・越後守、源行家を従五位下・備後守とする。 |
| 9月 4日(寿永2年 8月16日) | 後白河法皇は、源義仲を伊予守に、源行家を備前守に遷す。 |
| 9月 8日(寿永2年 8月20日) | 平氏が連れ去った安徳天皇と神器を戻すことが困難だったため、後白河法皇によって、高倉天皇の子で、安徳天皇の異母弟に当たる尊成親王が即位し後鳥羽天皇となる。この際に、木曽義仲が以仁王の子である北陸宮を推挙したため、九条兼実ら公家から反感を買う。 |
| 10月 7日(寿永2年 9月19日) | 木曽義仲と後白河法皇が会談し、法皇は京の治安悪化などを問題にして責任を問うたため、義仲は平氏討伐を約束。西国へ向けて出陣する。 |
| 10月19日(寿永2年10月 2日) | 鎌倉へ下向していた中原康定が帰京し、源頼朝の申状を後白河法皇に提出。これによれば「平家横領の神社仏事領の返還」「平家横領の院宮諸家領の返還」「降伏者は斬罪にしない」という内容だったという。後白河法皇ら朝廷は、木曽義仲とは違うとしてこれを評価。 |
| 10月31日(寿永2年10月14日) | 朝廷より、源頼朝に対して「寿永二年十月宣旨」が下される。頼朝の提案(平氏に押領された寺社の領地や宮・公家の荘園を元に戻す、斬罪の計を緩和する)に基づき「東海・東山諸国の年貢、神社仏寺ならびに王臣家領の庄園、元の如く領家に随うべき」という内容。木曽義仲に対抗するため、後白河法皇と頼朝が手を組んだものとされる。頼朝は北陸道も加えようとするが義仲の反発を恐れて朝廷は了承しなかった。またこれと合わせて頼朝を従五位下右兵衛権佐に戻し、頼朝は名実ともに罪人の身分から脱した。頼朝は宣旨実行を名分に、範頼と義経を畿内へ向けて出陣させる。 |
| 11月17日(寿永2年閏10月 1日) | 木曽義仲軍の足利義清ら、水島の戦いで平重衡らに敗北。義仲軍の将兵多数が戦死する。なお、この日、金環日食があったことが記録されており、これが戦闘に影響したという説もある。 |
| 12月 1日(寿永2年閏10月15日) | 木曽義仲が少数の兵を連れて帰京。後白河院とその周辺は動揺し、義仲に対し懐柔策も検討。 |
| 12月 6日(寿永2年閏10月20日) | 木曽義仲が後白河法皇に対し、頼朝上洛を認めたことと、寿永二年十月宣旨を頼朝に下したことを抗議し、頼朝追討の院宣か御教書を要求、頼朝と敵対した源氏の一門志田義広の起用を要求する。 |
| 12月19日(寿永2年11月 4日) | 源義経軍が不破の関に到着。木曽義仲はこれに対応するため出兵するが、義仲に不満を持つ源行家らと後白河法皇、延暦寺、園城寺などが手を組み、兵を集めて法住寺に立て籠もる動きを見せる。 |
| 12月31日(寿永2年11月16日) | 摂津源氏を味方につけた後白河法皇は、義仲に対して対平家戦に向かうよう命じ、残るようなら謀反として扱うと通牒。義仲は頼朝が京に入らなければ西国へ向かうと返答。 |
| 1184年 | |
| 1月 3日(寿永2年11月19日) | 木曽義仲、後白河法皇らの籠もる法住寺を攻め落とす(法住寺合戦)。院御所であった法住寺南殿は焼失し、脱出した後白河法皇は捕らえられ幽閉され、明恵・円恵法親王・源光長(土岐光長)らは戦死。 |
| 1月 6日(寿永2年11月22日) | 木曽義仲と松殿基房が手を組み、基房の子、松殿師家が摂政となって、新政権が樹立。 |
| 1月12日(寿永2年11月28日) | 摂政松殿師家によって前摂政基通の家領八十余所を木曽義仲に与えられることになり、また、中納言藤原朝方以下43人が解官となる。 |
| 2月 3日(寿永2年12月20日) | 上総広常が源頼朝の命を受けた梶原景時・天野遠景によって誅殺される。嫡男の上総能常も自害。上総広常の大きな勢力が頼朝の権力にとって邪魔だったとも、朝廷の権威も認めない独立志向を危うんだとも言われる。 |
| 2月19日(寿永3年 1月 6日) | 鎌倉軍が美濃に進出。 |
| 2月28日(寿永3年 1月15日) | 木曽義仲、征東大将軍となる。 |
| 3月 4日(寿永3年 1月20日) | 宇治川の戦い。源範頼・源義経率いる5万騎を超える大軍に対し、この時点ですでに木曽義仲は千騎ほどにまで激減しており大敗。義仲は今井兼平が防戦していた瀬田方面へ逃走。義仲体制は崩壊。 |
| 3月 5日(寿永3年 1月21日) | 粟津の戦い。源範頼軍に追撃され木曽義仲戦死。今井兼平も自刃する。義仲の側室で今井兼平の妹とみられる巴御前は、直前に義仲より落ち延びるよう指示されたとも言われ、各地に生存説がある。 |
| 3月20日(寿永3年 2月 7日) | 一ノ谷の戦い。源義経の「鵯越の逆落し」の奇襲で平氏が大敗。 |
| 5月27日(寿永3年 4月16日) | 元暦に改元。ただし平氏側支配地では引き続き寿永が使われる。 |
| 6月 1日(元暦元年 4月21日) | 源義仲の嫡男で、人質として鎌倉にいた源義高が、義仲敗死をうけて頼朝に誅殺される可能性が出たため、頼朝の娘で義高の婚約者である大姫らの意を受けて、海野幸氏を身代わりにして鎌倉を脱出。事態を知った頼朝は御家人らに、捜索と討ち取りのため派兵を命じる。 |
| 6月 6日(元暦元年 4月26日) | 源義高が、逃走途中の入間河原で藤内光澄に討たれる。12歳だった。頼朝は甲斐や信濃方面にも派兵しているため、単に義仲の子の誅殺だけが目的ではなかったとみられる。なお海野幸氏も捕らえられたがその忠誠心に免じて許され御家人となっている。 |
| 7月25日(元暦元年 6月16日) | 甲斐源氏武田信義の嫡男、一条忠頼が、鎌倉に招かれて酒宴のさなかに頼朝の命を受けた天野遠景の手で殺害される。殺害された理由は不明。朝廷から武蔵守に補任されていること、直前に源義高捜索の理由で甲斐まで派兵が行われていることから、武蔵の支配を巡る頼朝と甲斐源氏の対立も考えられる。なお同じ信義の子である武田信光は頼朝側についている。 |
| 8月12日(元暦元年 6月27日) | 源義高を討った藤内光澄が処刑される。大姫が義高の死を知って病に臥せたことで、母親の北条政子の怒りを買ったためとされる。 |
| 10月 7日(元暦元年 9月 1日) | 源範頼軍が西国へ向けて出陣。 |
| 1185年 | |
| 1月10日(元暦元年12月 7日) | 藤戸の戦い。源範頼軍が平行盛の児島に築いた城を攻め、この時、佐々木盛綱が海峡を馬で渡りこれを落とす。 |
| 3月22日(元暦2年 2月19日) | 屋島の戦い。源義経軍が海を迂回し、陸側から奇襲をかけ、平氏の拠点だった屋島を落とす。那須与一の扇の的のエピソードが起こる。 |
| 4月25日(元暦2年 3月24日) | 壇ノ浦の戦いで平氏の主流は滅亡する。平氏側の年号は寿永4年。 |
| 5月16日(元暦2年 4月15日) | 源頼朝が、京で頼朝の許しなしに朝廷より任官を受けたものを批判。鎌倉への帰還を禁じる。後白河法皇と接近した源義経を警戒しての対応。 |
| 6月23日(元暦2年 5月24日) | 源義経、兄頼朝から鎌倉入りを拒絶されたため、大江広元に書状(腰越状)を託す。 |
| 7月 7日(元暦2年 6月 9日) | 源義経、兄頼朝から平宗盛親子を連れて京に行くよう命じられる。義経、兄を恨む言葉を残したとされ、領地没収となる。 |
| 7月19日(元暦2年 6月21日) | 平氏の頭領で壇ノ浦で捕らえられた平宗盛が、義経の命で処刑される。 |
| 9月23日(文治元年 8月28日) | 戦火の被害にあった大仏の再建に伴い開眼供養が行われる。 |
| 10月19日(文治元年10月17日) | 源頼朝の命を受けた土佐坊昌俊率いる83騎が京の六条にあった源義経の館を襲撃。義経自ら応戦し、これを撃退する。 |
| 10月20日(文治元年10月18日) | 源義経、後白河法皇に依頼していた頼朝追討の宣旨を受ける。しかし畿内の武士は義経のもとにはほとんど参集せず。 |
| 11月22日(文治元年10月29日) | 源頼朝、義経追討のため、鎌倉を出陣。 |
| 11月27日(文治元年11月 4日) | 前日に源義経一行ら数百騎が都落ちを決め西国へ向かおうとしたが、摂津河尻で太田頼基らがこれを襲撃。義経に撃退される。平家物語では3日。この後も、多田行綱、豊島冠者、藤原範資らが相次いで襲撃。義経の勢力は離散。 |
| 12月18日(文治元年11月25日) | 源義経追討の院宣が発せられる。 |
| 12月21日(文治元年11月28日) | 源頼朝が朝廷から諸国の守護・地頭の設置・任免を許可した勅許(文治の勅許)を得る。ただ、鎌倉時代の守護ではなく、その前段階にあたり、荘園地頭を発展させた、段別五升の兵糧米の徴税権と田地の知行権、武士の動員権を持つ国地頭の設置だったのではないかという説が有力。 |
| 1186年 | |
| 6月 1日(文治2年 5月12日) | 後白河院の頼朝追討の院宣に従い源頼朝と敵対していた源行家が、潜伏先の和泉国で北条時定に捕らえられ、この日処刑される。 |
| 7月 4日(文治2年 6月16日) | 源有綱が大和宇陀で義経探索を行っていた北条時定の手勢と交戦し自害。有綱は頼朝挙兵に参加し、義経の与力となっていた武将。義経の婿(もしくは妹婿)ともいわれる。 |
| 1187年 | |
| 3月21日(文治3年 2月10日) | この頃、源義経、弁慶ら側近と正妻郷御前(比企尼の孫娘)や娘らを連れて奥州藤原氏の元へ向かう。 |
| 7月 4日 | サラーフッディーンがヒッティーンの戦いで十字軍王国に勝利。エルサレムに侵攻。 |
| 11月30日(文治3年10月29日) | 奥州藤原氏の頭領藤原秀衡が死去。 |
| 1189年 | |
| 1月20日(大定29年1月2日) | 金の5代皇帝烏禄(ウル・世宗)が死去。3代皇帝、4代皇帝と暴君が続いたことと、南宋と盟約を結ぶなどして戦争が殆どなかったことから名君とされ、その治世は大定の治と呼ばれる。一方で4代皇帝に続き漢化政策が進められて女真族の文化が失われ(女真文字の創設もしている)、長期の安寧によって武力も衰えたという。また増税によって民衆の反乱が相次いだ可能性もある。世宗の嫡孫である完顔麻達葛(マダカ)が即位。 |
| 6月15日(文治5年閏4月30日) | 衣川合戦。藤原泰衡に攻められて、源義経、妻女を殺害後に自害。弁慶らも討ち死に。 |
| 10月14日(文治5年 9月 3日) | 鎌倉軍が奥州征伐を行い、藤原泰衡ら滅びる。 |
| この頃、モンゴル部族キヤト氏族のテムジンと、同部族ジャダラン氏族のジャムカの間で十三翼の戦いが起きる。ジャムカが勝利したと見られるが、ジャムカが捕虜に残酷な措置をしたことで、むしろテムジンの方に人望が集まるようになったと言われる。 | |
| 1190年 | |
| 1月(文治5年12月) | 藤原泰衡の郎従であった大河兼任の乱が陸奥で起こる。 |
| 2月13日(文治6年 1月 7日) | 源頼朝、大河兼任の乱討伐の動員令を発する。 |
| 3月19日(文治6年 2月12日) | 鎌倉軍と大河兼任の軍勢が栗原郡で衝突。大河兼任は敗北。 |
| 4月16日(文治6年 3月10日) | 大河兼任、逃走の末、栗原に戻ってきたところを、栗原寺で樵に殺害される。 |
| 1191年 | |
| 9月 7日 | 第3回十字軍アルスフの戦い。リチャード1世がサラーフッディーンの軍勢を破る。 |
| 9月10日 | 第3回十字軍。リチャード1世がヤッファを占領。 |
| 1192年 | |
| 4月26日(建久3年 3月13日) | 後白河法皇が崩御。 |
| 8月21日(建久3年 7月12日) | 源頼朝が朝廷より征夷大将軍に任じられる。頼朝は「大将軍」の官職を求めたのに対し、征東大将軍、征夷大将軍、惣官、上将軍の4案の中から、平宗盛の官職だった「惣官」(畿内惣官)と木曽義仲の官職だった「征東大将軍」は前例が良くないとして外し、「上将軍」は古例がないため、「征夷大将軍」にしたとも言われる。 |
| キプロス王国が建国される。エルサレム共同統治者だったギー・ド・リュジニャンが、第3回十字軍としてきていたリチャード1世より、エルサレムの王位継承権を放棄する代わりにキプロス島の領有権を得たことによる。 | |
| 1193年 | |
| 3月 4日 | アイユーブ朝の創始者で、聖地奪回を成し遂げたことから、イスラムの英雄とされるサラーフッディーン(サラーフ=アッディーン。本名ユースフ・イブン・アイユーブ)がダマスカスで病没。ティクリート出身のクルド人で、有能な軍事指揮官だった一方、捕虜を無条件で解放するなど、穏健な人物だったことから、イスラム世界で絶大な支持を得ただけでなく、キリスト教徒の間でも著名な人物であった。ヨーロッパではサラディンと呼ばれる。 |
| 6月28日(建久4年 5月28日) | 曾我兄弟の仇討ち。曾我十郎祐成、曾我五郎時致の兄弟が、父の仇である工藤祐経を富士の巻狩りで殺害。源頼朝も狙うが兄は殺害され、弟も処刑される。 |
| 1194年 | |
| (南宋 紹熙5年・金 明昌5年) | 分流していた黄河下流の流れが大きく南へ移り、それに押される形で黄河の一部が合流していた淮河も南へと遷移。湖沼地帯に水が大量に溜まり現在の洪沢湖が形成される。淮河の流れはそこからさらに南へと移り、現在のような長江へ流れ込むルートに変わった。 |
| 1196年 | |
| 6月 | ウルジャ河の戦い。テムジン(チンギスカン)が記録に初めて登場した戦い。金に反旗を翻し西遼側についたタタル部族のセチュに対して、金と同盟したモンゴル部キヤト氏族のテムジンが、同盟関係のケレイト部族王のトオリルとともに金朝の作戦に応じてタタルを攻撃し勝利。金朝の指揮官は完顔襄、完顔安国。テムジンはジャウト・クリ(百人長)の称号を得、トオリルは「王(オン)」の称号を得た(トオリルはオン・カンと称する)。テムジンは勢力を拡大していく。 |
| 12月16日(建久7年11月25日) | 九条兼実が関白を罷免される(建久七年の政変)。兼実の子九条良経も籠居。兼実の権力体制と保守的な政策に反発した土御門通親や新興中下級公家のクーデター。 |
| 1198年 | |
| この年、ローマ教皇インノケンティウス3世が第4回十字軍派遣を企画。しかし各地の王は参加せず、フランス貴族らによって計画が進められる。 | |
| 1199年 | |
| 1月25日(建久9年12月27日) | 稲毛重成が病死した妻(北条政子の妹)の追供養のため、相模川に橋を架ける。その落成供養に源頼朝も出席するが、その帰途に急に体調を崩す。落馬が原因という説もある。関東大震災の時に液状化によって地中から出土した木製橋脚群がこのときの橋のものとする説もある(橋があったのは鎌倉時代のみでそれ以降明治まで橋は作られなかったため)。 |
| 2月 9日(建久10年 1月13日) | 源頼朝が死去。死因は記録によって異なり、落馬による負傷、脳卒中などの病気(落馬の原因にもなる)、飲水病(糖尿病か)、亡霊を見て病気になったなどの説もある。 |
| 2月22日(建久10年 1月26日) | 源頼家が家督を相続する。 |
| 3月12日(正治元年 2月14日) | 一条能保の遺臣である後藤基清・中原政経・小野義成らが権大納言・土御門通親の襲撃を企てたとして捕縛される。3人の官職名から「三左衛門事件」と呼ばれる。頼朝危篤の情報から京の情勢が不穏になった際に起こった事件。同じ頃、文覚も逮捕される。 |
| 3月15日(正治元年 2月17日) | 「三左衛門事件」に連座して西園寺公経・持明院保家・源隆保が出仕停止。 |
| 4月 6日 | イングランド王リチャード1世(獅子心王)が、アキテーヌ公領のシャリュ城攻略中に、戦傷がもとで死去。 |
| 5月 8日(正治元年 4月12日) | 鎌倉幕府有力御家人13人による合議制が成立し、源頼家が直接訴訟を裁断することが禁じられる。いわゆる「十三人の合議制」。 |
| 1200年 | |
| 2月 6日(正治2年 1月20日) | 梶原景時の変。失脚した梶原景時一族が、上洛しようとしたところ、襲撃を受けて滅ぼされる。 |
| 1200年代前半 | |
| 超新星残骸ベラ・ジュニアの元となった超新星爆発の光が地球に到達したとみられる年代。実際の爆発は西暦500年代前半ころ。かなりの規模の地球近傍超新星だが、この時代の記録には見当たらない。星間物質などによって遮られた可能性もある。 | |
| 1201年 | |
| 2月27日(建仁元年 1月23日) | 城長茂が、京の大番役、小山朝政の邸宅を襲撃。小山朝政は留守だったため難を逃れる。長茂は後鳥羽上皇に鎌倉討伐の院宣を求めるが拒否される。建仁の乱。城一族は元平氏方だったが、鎌倉政権樹立後、身柄を引き受けた梶原景時のとりなしで許され御家人となっており、景時が滅ぼされたことに対して反乱を起こしたとみられる。また、同時期、越後で城資盛と坂額御前ら一族も鳥坂城に籠って反乱を起こす。 |
| 3月28日(建仁元年 2月22日) | 城長茂が、大和吉野で小山朝政らによって滅ぼされる。 |
| 4月 4日(建仁元年 2月29日) | 奥州藤原秀衡の4男で、城長茂に同調して挙兵した藤原高衡が討ち取られる。高衡も梶原景時のとりなしを受けていたため、反乱に同調したとも考えられる。 |
| 6月11日(建仁元年 5月 9日) | 坂額御前が負傷したことをきっかけに越後鳥坂城が陥落。城資盛は行方不明となり、坂額御前は捕虜となる。 |
| 7月29日(建仁元年 6月28日) | 坂額御前が鎌倉へ護送され、源頼家の面前に連れてこられる。堂々とした態度を崩さず、それに感銘を受けた甲斐源氏浅利義遠が頼家に申し出て妻に迎えたと言われる。 |
| 第4回十字軍の参加希望者が少なかったため、資金も乏しい状態で出発できず。そこへ先の東ローマ皇帝イサキオス2世が息子アレクシオスを送り、資金提供と東西教会統一を条件に自分の皇帝への復帰支援を要請する。 | |
| 1202年 | |
| 8月11日(建仁2年 7月22日) | 源頼家を従二位に叙し、征夷大将軍の宣下が出される。 |
| テムジンとオン・カン(トオリル)は、反ケレイト・キヤト諸部族と決戦し、これを打ち破る。 | |
| 1203年 | |
| 6月29日(建仁3年 5月19日) | 阿野全成が捕らえられる。源頼朝の異母弟(義経の同母兄)で、北条氏と組んで将軍頼家と対立したため、頼家が先手を打って、武田信光に命じて捕縛したとされる。 |
| 7月 | 第4回十字軍が同じキリスト教国の東ローマ帝国首都コンスタンティノポリスを攻撃。皇帝アレクシオス3世が逃亡したため、十字軍と組んだアレクシオス3世の兄イサキオス2世が復位し、その子のアレクシオス4世が共同皇帝となる。しかし市民と十字軍との関係は悪化。 |
| 8月 1日(建仁3年 6月23日) | 阿野全成が、将軍源頼家の命を受けた八田知家によって殺害される。 |
| 10月 8日(建仁3年 9月 2日) | 比企能員の変。将軍源頼家と御家人との対立から起こった事変で、頼家と近い比企氏の権力増大を恐れた北条氏によって滅ぼされる。頼家の子で、母親が比企氏の出身である一幡も殺害される。 |
| 10月13日(建仁3年 9月 7日) | 病床にあった将軍源頼家に比企氏討伐の報が伝えられ、頼家は激怒して堀親家を使者に和田義盛らに北条討伐を命じるも応じる御家人はいなかったという。また比企能員の変の前後に、北条政子から京に将軍頼家死去の虚報が伝えられ、7日に千幡に将軍宣下が出され(15日とも)、後鳥羽上皇により源実朝の名が与えられる。頼家は将軍職を失い、北条時政が大江広元とともに実権を握る。 |
| テムジンとオン・カンが対立し、一旦はオン・カンがテムジンを追い落とすも、勢力を盛り返したテムジンがオン・カンを襲撃。これに勝利し、オン・カン率いるケレイト部は壊滅。テムジンはモンゴル高原中央部を制圧。 | |
| 1204年 | |
| 1月(建仁3年12月) | 伊勢で、若菜盛高ら伊勢平氏が蜂起。伊勢守護山内首藤経俊の館を襲撃する事件が起きる。三日平氏の乱のはじまり。当初は伊勢国員弁郡郡司進士行綱が事件を起こしたと間違われた。 |
| 2月 8日 | 東ローマ帝国前皇帝アレクシオス3世の娘婿アレクシオス5世ドゥーカスが反乱を起こし、皇帝イサキオス2世と共同皇帝のアレクシオス4世を殺害。 |
| 3月(元久元年2月) | 伊賀で平惟基、伊勢で平度光が、武装蜂起。伊勢守護山内首藤経俊は敗走。三日平氏の乱。 |
| 4月11日(元久元年3月10日) | 鎌倉幕府は、伊賀・伊勢の平氏の反乱に対し、京都守護平賀朝雅に追討を命じる。 |
| 4月13日 | 第4回十字軍がふたたびコンスタンティノポリスを攻撃し陥落。東ローマ帝国の皇族らは周辺地域に逃亡。複数の亡命国家を建設する。十字軍の兵士らは市民を虐殺し婦女子を見境なく暴行、美術品を略奪し、貴重な文化財をことごとく破壊する。東ローマ帝国は一旦滅亡。この事件は、現代にまで続く正教会のカトリックに対する対立姿勢の要因にもなった。 |
| 4月22日(元久元年3月21日) | 後鳥羽上皇は、伊賀国を平賀朝雅の知行国と定める。 |
| 4月23日(元久元年3月22日) | 平賀朝雅、兵200を率いて京を出兵。 |
| 5月11日(元久元年4月10日) | 平賀朝雅率いる鎌倉軍が伊勢に入り、平氏軍を攻撃。 |
| 5月13日(元久元年4月12日) | 平賀朝雅、伊勢の平氏軍を鎮圧。続いて伊賀の残党を倒し、三日平氏の乱を平定。平賀朝雅はこの功績により、伊勢平氏の所領を得た他、伊勢と伊賀の守護を兼務することになる。また後鳥羽上皇に殿上人として加えられ、権勢が拡大する。山内首藤経俊は伊勢守護の地位を失った。 |
| 5月16日 | 旧東ローマ帝国の一部を領土とし、コンスタンティノポリスを首都とするラテン帝国が成立。フランドル伯ボードゥアン9世が皇帝ボードゥアン1世として即位。しかし十字軍本来の目的である聖地奪回・エジプト攻撃には向かわず。 |
| 8月14日(元久元年 7月18日) | 源頼家が幽閉先の伊豆修善寺で暗殺される。『吾妻鏡』には詳細がないが、『愚管抄』では北条義時の手勢によって入浴中に殺されたとある。 |
| 11月26日(元久元年11月 4日) | 三代将軍源実朝の正室となった坊門信清の娘を迎える使者として京へ赴いた御家人らの歓迎酒宴が開かれた平賀朝雅邸で、平賀朝雅と、畠山重保(畠山重忠の嫡男)が言い争う事件が起きる。 |
| 11月27日(元久元年11月 5日) | 北条時政と牧の方との間に生まれた北条政範が、三代将軍源実朝の正室となった坊門信清の娘を迎える使者として京へ赴いた際に急死する。前日の平賀朝雅と畠山重保の言い争いの話と共に北条時政・牧の方に伝わり、畠山氏に対する強行策に発展して畠山重忠の乱の要因の一つになったとされる(平賀朝雅は北条時政・牧の方夫妻の娘婿)。 |
| ヴィチェンツァ大学が設立される。9つの中世大学(ストゥディウム・ゲネラーレ)の一つ。 | |
| 1205年 | |
| 7月10日(元久2年6月22日) | 畠山重忠の乱。由比ヶ浜で畠山重保が、二俣川で畠山重忠が、鎌倉の騒動を理由に招集を受けて出向いたところを、北条義時らに攻め滅ぼされる。武蔵国の支配権をめぐる国司平賀朝雅と御家人畠山重保の対立から、朝雅が妻の母である北条時政の後妻牧の方をして畠山を讒言し、時政が義時らの反対を押し切って畠山討伐を強引に進めた冤罪事件。乱の直後から冤罪とみなされていた。重忠は北条氏が滅ぼした御家人でありながら、「吾妻鏡」で称賛されており、義時も重忠は無実であると発言したとある。一方で、畠山氏の所領は北条政子を介して討伐の功績として御家人らに分割され、畠山氏の家督も、重忠の妻(北条政子らの妹)が重忠の遺領を相続した上で河内源氏系足利義純に再嫁し、義純が畠山氏の家督を継いだため、秩父平氏畠山家は滅亡(義純は重忠の娘と婚姻して相続したとも言われる)。武蔵国は北条得宗家が支配していくことになる。 |
| 7月11日(元久2年6月23日) | 畠山重忠の乱討伐に加わっていた、同族の稲毛重成・小沢重政親子、榛谷重朝・榛谷重季・榛谷秀重親子らが畠山重忠を讒言して陥れたとして、三浦義村・大河戸行元・宇佐美祐村らの手で討伐される。 |
| 9月 5日(元久2年閏7月20日) | 北条時政が将軍源実朝を廃し、後妻牧の方の娘婿である平賀朝雅を将軍に据えようとしたが、畠山重忠の乱以来、時政と対立していた政子・義時が先手を打ち、時政の執権職を奪い、牧の方とともに幽閉。ふたりを伊豆に流罪とした。牧氏事件。平賀朝雅は新羅三郎義光の子孫で、頼朝の猶子にもなっていた源氏の出である。 |
| 9月11日(元久2年閏7月26日) | 平賀朝雅が北条義時の命を受けた在京御家人の軍勢に襲撃され、一旦は逃げ延びたが、山内首藤通基(三日平氏の乱で伊勢守護を解任された経俊の子)によって誅殺される。 |
| 旧東ローマ帝国の皇族が興したニカイア帝国とブルガリア王国が手を結び、ラテン帝国を攻撃。全土を蹂躙し、皇帝ボードゥアン1世も捕らえられ消息を絶つ。皇帝の弟アンリ・ド・エノーが摂政となって宥和政策を取ったことでかろうじて命脈を保つ。 | |
| テムジンは、ナイマン部族、メルキト部族を破り、長年敵対してきたジャムカを捕らえて処刑。オングト部族も傘下に入り、モンゴル高原を平定。 | |
| 1206年 | |
| 2月 | テムジンがオノン川上流に諸部族を集めてクリルタイを開催。チンギス・カンの称号を得て、モンゴル帝国を建国。チンギスの意味や由来はよくわかっていない。 |
| 6月14日(開禧2年/泰和6年 5月 7日) | 南宋の実力者韓侂冑らが主導して、金に対する北伐を開始。通称「開禧用兵」。 |
| 12月(開禧2年/泰和6年11月) | 「開禧用兵」は失敗に終わり、南宋は金との和平交渉を開始。金は強硬姿勢を貫き、戦争責任者として韓侂冑の身柄引き渡しを要求。南宋の権力者韓侂冑は一転して窮地に追い込まれる。 |
| 1207年 | |
| (建永2年2月) | 承元の法難。かねてより諸宗派から批判されていた法然の教団に対して、後鳥羽上皇が処罰を命じた事件。ただし宗教的な理由ではなく、法然の弟子である遵西と住蓮が、後鳥羽上皇の熊野巡幸の留守中に、宮中の女官らの招きで宮中で説法を行い、そのまま宮中に泊まったあげく、女官のうち2名が出家してしまったことに上皇が激怒したため。2人は密通の疑いで処刑され、法然や親鸞も流罪となった。ただし当時の公的な記録に処刑された記載がないことから、検非違使などによって私的に殺害されたという説も根強い。承元となっているのは、この事件のさなかに改元したため。 |
| 5月 3日(承元元年 4月 5日) | 九条兼実死去。平安末期から鎌倉初期の激動期に摂政・関白・太政大臣を務めた人物。有職故実家で、九条家・一条家・二条家の祖にあたる。同時代の一級史料『玉葉』の著者。 |
| 11月24日(開禧3年11月 3日) | 南宋の権力者韓侂冑が暗殺される。講和の条件に韓侂冑の身柄引き渡しを要求していた金との交渉を進めるため、楊皇后と史弥遠らによって起きた事実上のクーデター。首は金に送られ、講和が成立。史弥遠の権力掌握のきっかけとなる。 |
| 1208年 | |
| 12月29日(泰和9年11月20日) | 金の6代皇帝章宗(麻達葛)が死去。比較的穏健な皇帝で、前代世宗とともに安定した治世を行い、明昌の治と呼ばれる。一方でこの頃から徐々に国力が衰退し始める。子息6人が全員夭折したため、叔父の完顔果繩(ガジェン)が後をついで即位。 |
| 史弥遠が南宋の右丞相となる。和平派の代表。1233年に死ぬまで25年の長期政権を築く。 | |
| 1209年 | |
| オックスフォード大学の学者2人が市民とのトラブルで処刑されたことから、学者らが抗議して各地の大学に移り、一部が教会の教育施設があったケンブリッジに住んだことがきっかけでケンブリッジ大学が創設される。9つの中世大学(ストゥディウム・ゲネラーレ)の一つ。 | |
| 1210年 | |
| 12月12日(承元4年11月25日) | 後鳥羽上皇の意向で、土御門天皇が弟の守成親王(順徳天皇)に譲位。 |
| 1211年 | |
| ナイマン部族のクチュルクが、彼を皇女の婿に迎えた西遼王朝を簒奪。 | |
| モンゴル部族のチンギスが、兵を総動員して金遠征を開始。第1次対金戦争。 | |
| 4月 | モンゴル軍の侵攻を受けて、金は防衛のため宣徳行省と西京行枢密院を設置。 |
| 6月 | モンゴル軍が、撫州などにある金の運営する広大な牧場地帯を占領。ここに侵攻拠点を置く。また金に属していた現地の契丹人勢力はモンゴル側に寝返る。 |
| 8月 | 野狐嶺の戦い。金は完顔承裕、紇石烈らの率いる30万の兵で迎撃に向かうも、戦意は低く、モンゴル軍に大敗。 |
| 10月 | 澮河堡の戦い。金軍は澮河堡まで退却した後、立て直してモンゴル軍と再度衝突。金軍は再び大敗を喫し、宣徳行省軍は壊滅。大きな戦力を失う。 |
| 1212年 | |
| 2月29日(建暦2年 1月25日) | 浄土宗の開祖、法然死去。 |
| 金王朝に属していた遼の王族耶律留哥が、モンゴルの支援を受けて反乱。隆安・韓州地方で独立。いわゆる「東遼」王朝。 | |
| 1213年 | |
| 3月 8日(建暦3年 2月15日) | 信濃源氏の御家人泉親衡が、源頼家の遺児千寿丸を擁立して、執権北条義時を討とうと乱を起こす。泉親衡は敗北し逃亡。 |
| 5月23日(建暦3年 5月 2日) | 和田義盛らが、泉親衡の乱に関与したとして一族の和田胤長が罰せられたことなど北条義時からの屈辱的な扱いを受けた恨みから鎌倉で武装蜂起。市街戦となる。劣勢になった義盛勢は一旦退却。 |
| 5月24日(建暦3年 5月 3日) | 和田義盛軍と横山時兼の横山党が合流し鎌倉市内へ再突入。しかし時間とともに劣勢となり討ち取られる。和田義盛の三男の猛将朝比奈義秀は残党を引き連れて安房へ逃亡。 |
| 8月(貞祐元年 8月) | 金の将軍紇石烈胡沙虎(フシャリクシャク)が反乱を起こす。モンゴルによる大金遠征を迎え撃ったが敗北したことで、対立関係にあった官僚らによって処罰されそうになったため。宮中に攻め込み皇帝を捕らえる。 |
| 9月11日(貞祐元年 8月) | 反乱を起こした金の将軍胡沙虎が、宦官の李思中に命じて、皇帝果繩を毒殺。代わりに完顔吾睹補(ウトゥプ)を擁立して即位させる(宣宗)。果繩の帝位は剥奪され、東海郡侯とされたが、後に宣宗によって、即位前の地位である衛王に戻された上で、紹王と追贈されたため、衛紹王と呼ばれる。 |
| モンゴル軍が大規模に侵攻を再開し、金の領土を席巻する。胡沙虎が迎撃戦を展開し一定の成果を収めるも、朮虎高琪との連携に失敗して敗北。 | |
| 11月28日(貞祐元年10月15日) | 金の将軍胡沙虎が、遠征から戻った高琪に殺害される。モンゴル軍への応戦で連携できなかった高琪がその責任で単独迎撃を命じられて敗北したため、政敵である胡沙虎に対し先手を打った政変。 |
| モンゴル軍のケフテイ、サムカらが金の都、中都大興府を包囲。 | |
| 1214年 | |
| 5月 7日(貞祐3年 5月 2日) | モンゴル軍、全軍で中都大興府を包囲しつつ、講和交渉を行う。金側は完顔福興(承暉)が交渉に当たり、衛紹王の娘である岐国公主がチンギスに嫁ぐことで講和が成立。モンゴル軍は中都大興府の包囲を解く。もともとモンゴルは中都大興府を攻め落とすつもりはなかったと見られる。 |
| 5月 7日(貞祐3年 5月 2日) | 金王朝、南の開封に遷都を行う。モンゴルから距離を置くためと見られる。この時、契丹人で構成される傭兵部隊「乣軍」の武装解除をしようとして反乱を招き、「乣軍」が中都大興府近辺を占拠してモンゴル側に支援を要請。モンゴル側は和約違反として再出兵を決める。 |
| 5月(貞祐3年 5月) | モンゴルと契丹人の連合軍が中都大興府を再度包囲。 |
| 7月27日 | フランス王国対神聖ローマ帝国・イングランド王国連合によるブーヴィーヌの戦い。フランスが圧勝。 |
| 1215年 | |
| 2月 | 金は、中都大興府救援のため、完顔永錫、烏古論慶寿、李英、孛朮魯徳裕らに大軍を派兵させる。 |
| 3月 | 金の慶寿、李英らがモンゴル軍に敗北し、中都大興府救援は失敗。 |
| 5月31日(貞祐3年 5月 2日) | 中都大興府に残って防衛を担っていた右丞相・都元帥の完顔福興が、部下らにモンゴルへの降伏を認め、宣宗宛に高琪が救援を妨害したことを伝える書簡を残して自殺。福興は敵のチンギスからも高く評価されていた。抹撚尽忠は逃亡。中都大興府は陥落した。中都で金に仕えていた耶律楚材はこのあとモンゴルに仕えるようになった。 |
| 6月15日 | イングランド王ジョンが、マグナ・カルタを承認する。王の権限を制限した基本法。 |
| 金朝の女真将領・遼東宣撫使の蒲鮮万奴が自立を宣言し大真国を建国。 | |
| 1216年 | |
| 7月26日(建保4年閏6月10日) | 鴨長明死去。賀茂御祖神社の禰宜の子として生まれたが、一族との争いに敗れてその地位を失い、歌人として活躍。後鳥羽上皇から河合社の禰宜職に推挙されるがこれも一族の反対で認められず。以後出家して京の郊外に隠棲。随筆「方丈記」を記した。「方丈記」は無常観漂う中世文学の代表的な随筆だが、一方で同時代の事件、災害などが詳細に記載されている。 |
| 東遼の耶律留哥は、モンゴル帝国から派遣された耶律可特哥が大真国を興した蒲鮮万奴の妻の李僊娥を娶ったことを非難して対立に発展。耶律可特哥は耶律留哥が死んだと称して独自政権を樹立。「後遼」と呼ばれる。耶律留哥は高麗と手を組んで後遼を攻撃。 | |
| 1217年 | |
| 第5回十字軍遠征が始まる。 | |
| 1218年 | |
| モンゴルが、西遼を乗っ取ったクチュルクを滅ぼす。これにより領域が接することになったホラズム・シャー朝のスルターンに450人もの通商使節団を送る。交渉でモンゴルへの服属を求めたことからか、オトラルの長官イナルチュクが使節団をスパイ容疑で逮捕したことを受けて、イナルチュクの甥でホラズム・シャーのスルターンであるアラーウッディーン・ムハンマドは、使節団の殺害を命じる。チンギスカンはイナルチュクの処罰を求めたが受け入れられなかったため、ホラズム・シャーへの遠征を決定。 | |
| スペインのサラマンカ大学が創立される。9つの中世大学(ストゥディウム・ゲネラーレ)の一つ。それ以前から前身の教会付属の教育機関があったとみられる。 | |
| 1219年 | |
| 1月14日 | モンゴル帝国、大真国、高麗国が連合して後遼国に攻め込み、後遼は滅亡。耶律留哥が再び統治。 |
| 6月 5日(承久3年 5月14日) | 前年の右大臣昇進の祝賀のため、鶴岡八幡宮を参詣していた鎌倉幕府第3代将軍源実朝が、甥の公暁(八幡宮寺別当)に襲われて殺害される。同行していた源仲章も殺害され、襲った公暁は三浦義村に支援を求める途中にその義村が派遣した討手に襲われ、三浦邸にたどり着いたところで討たれた。源仲章は北条義時と間違えられたとも言われ、その義時は体調不良で退出していた、あるいは中門で控えていたなど諸説ある。公暁の動機や事件の背後関係など不明な点が多い。 |
| カラ・クムの戦い。ホラズム・シャーのスルターンであるアラーウッディーン・ムハンマドが、侵入してきたメルキト部族を迎撃するために自ら出兵。メルキトを追撃していたモンゴル軍の存在を知り攻撃を仕掛ける。モンゴル軍は少数だったため、メルキトの戦利品を贈って友好を結ぼうとしたが、ホラズム側の攻撃を受けて応戦。逆にアラーウッディーン・ムハンマドの中央軍は敗北し、王子ジャラールッディーン・メングベルディーの右翼軍が救援に駆けつけたことで撤退した。モンゴルは自信をつけ、ホラズム側は以後消極的になる。 | |
| モンゴルが、ホラムズ・シャー朝への侵攻を本格化。マー・ワラー・アンナフルへ進出し、オトラル、スィグナク、ジャンドを攻略。 | |
| 1220年 | |
| 1月 2日(興定3年11月25日) | 金の最高権力者となっていた高琪が宣宗によって誅殺される。高琪はモンゴル軍への応戦を行わず、開封の防備のみに兵を集中させたことで、中都大興府をはじめ、各州がモンゴルに奪われる結果を生んだことから、金を滅亡させた人物とみなされている。 |
| 2月 | モンゴルが、主要都市ブハラ、首都のサマルカンドを攻略。アラーウッディーンはナフシャブへ退却。ホラムズ・シャー朝は、各都市を守備したが、軍を集中させず個別に撃破されて壊滅。 |
| 4月 | アラーウッディーンはニーシャープールへ退却。短期間でここも離れる。ガズウィーン、ロレスターンを経由してマーザンダラーンまで落ち延びる。モンゴル軍はホラーサーンに侵攻。 |
| 12月 | ホラムズ・シャー朝第7代スルターンのアラーウッディーン・ムハンマドが、最後にたどり着いたカスピ海の島アバスクン島で死去。ジャラールッディーンが後を継ぐ。 |
| 1221年 | |
| 2月 | ホラムズ・シャー朝の都市メルヴが陥落。住民は職工など一部を除き虐殺される。 |
| 4月10日 | ホラムズ・シャー朝の都市ニーシャープールが陥落。住民は虐殺され、都市も破壊される。 |
| 4月 | ホラムズ・シャー朝の最後の王都ウルゲンチが陥落。住民は虐殺され都市も破壊され尽くした。 |
| 4月 | ホラムズ・シャー朝の都市ヘラートがモンゴルに降伏。 |
| 6月 5日(承久3年 5月14日) | 後鳥羽上皇が流鏑馬を口実に兵を集め、幕府に対し挙兵。承久の乱が始まる。 |
| 6月26日(承久3年 6月 5日) | 大井戸の戦い。幕府軍5万が2000ほどの上皇軍を撃破。上皇軍は京付近まで撤退。 |
| 7月 4日(承久3年 6月13日) | 宇治川の戦い。上皇軍と幕府軍が衝突し、上皇軍は宇治川の橋を落とすが、翌日に佐々木信綱らが増水の中、敵前渡河し、多数の溺死者を出しながらも敵陣を突破。京へなだれ込む。幕府軍の勝利に終わる。 |
| 9月 | パルワーンの戦い。ホラズム軍を率いるジャラールッディーンが、カーブルの北方にあるパルワーンでモンゴル軍を撃破。この報が広まり、モンゴルが占領しているメルヴやヘラートで反乱が起きる。 |
| 11月24日 | インダス河畔の戦い。ホラズム軍はモンゴル軍に包囲殲滅される。ジャラールッディーンはインド方面へ敗走。 |
| 1222年 | |
| 3月30日(貞応元年 2月16日) | 日蓮が安房で誕生する。 |
| 6月14日 | モンゴル軍の将軍イルジギデイがヘラートで起きた反乱を鎮圧。市民が大虐殺されたという。 |
| 1223年 | |
| 5月31日 | カルカ河畔の戦い。ジェベ率いるモンゴル軍と、ルーシ諸公国連合軍との戦い。モンゴル軍の圧勝に終わる。 |
| モンゴル軍、ヴォルガ・ブルガール地方へ侵攻。 | |
| ケルネク(サマラ屈曲部)の戦い。モンゴル軍と、ヴォルガ・ブルガール軍とが衝突し、ヴォルガ・ブルガールが勝利。 | |
| 1224年 | |
| 7月 1日(貞応3年 6月13日) | 鎌倉幕府第2代執権の北条義時が死去。 |
| 7月16日(貞応3年 6月28日) | 北条泰時が鎌倉幕府第3代執権となる。義時の最初の子で嫡子ではないが、後を継いだ。母親の正体が不明。泰時が執権制度を整えたとして初代執権とする説もある。 |
| 10月13日(貞応3年 8月29日) | 北条義時の後妻伊賀の方が、北条政子の手で伊豆に流罪となる。伊賀の方は12月末ころに配流先で死去。兄の伊賀光宗も信濃に流罪。伊賀の方が産んだ北条政村を次の執権に擁立しようとして、北条政子が弾圧した事件とされるが、北条泰時は陰謀を否定しており、伊賀光宗も後に赦されている。北条政村はこの後、長期にわたって幕府の宿老として政権を支えた。 |
| 12月31日(貞応3年11月20日) | 天変炎旱により年号を元仁に改元。 |
| フェデリコ2世・ナポリ大学が創立される。ローマ教皇と対立した神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ(フェデリコ)2世が、教皇の庇護下にあったボローニャ大学に対抗するために創立したと言われる。 | |
| 1225年 | |
| 5月28日(元仁2年 4月20日) | 年号を元仁から嘉禄に改元。疱瘡が流行したためとも、前年の元仁への改元に幕府が不満を唱えたためとも言われる。 |
| 7月16日(嘉禄元年 6月10日) | 大江広元死去。公家出身で源頼朝の側近となり鎌倉幕府初期の重鎮だった人物。 |
| 8月16日(嘉禄元年 7月11日) | 北条政子死去。実子でもある頼家と実朝の死によって源家将軍が絶えたあと、実弟の義時とともに幕府の最高権力者として政治に関与し、尼御台、尼将軍とも呼ばれた。 |
| 12月31日(太宗天彰有道2年12月1日) | ベトナム陳朝の始まり。李朝大越国の実力者、陳守度によって、李朝最後の皇帝である女帝李昭皇が、夫の陳太宗に譲位。 |
| 1226年 | |
| 2月25日(嘉禄2年 1月27日) | 藤原頼経が第4代征夷大将軍となる。九条道家の子だが、源頼朝の姉妹である坊門姫の曾孫に当たるため、源氏の血も引いている(坊門姫の娘で西園寺公経室が生んだ掄子と、坊門姫の娘で九条良経室が生んだ九条道家との間に生まれた)。 |
| 10月 3日 | アッシジのフランチェスコ(ジョヴァンニ・ディ・ピエトロ・ディ・ベルナルドーネ)が死去。フランシスコ会の創設者。生きているときから聖痕があらわれるなど聖人視されており、死後2年で列聖された。 |
| 1227年 | |
| モンゴル帝国の攻撃と、地震による飢餓などを受けて、西夏王朝の皇帝李睍が降伏。西夏は滅亡する。 | |
| 8月18日 | モンゴル帝国初代皇帝チンギス・カン没。 |
| 8月28日 | 西夏の最後の皇帝でモンゴル帝国に囚われていた李睍をはじめ、一族・有力者らが、オゴデイによって殺害される。 |
| 1228年 | |
| 3月 | 第一次大昌原の戦い。モンゴル軍8000を、完顔陳和尚率いる「忠孝軍」400騎が打ち破る。忠孝軍はモンゴルに滅ぼされた各国の亡命者で編成された軍という。モンゴルによる対金侵攻ではじめて、金軍の大勝利となり、陳和尚の名も知れ渡ることになる。 |
| 1229年 | |
| 9月13日 | モンゴル帝国でクリルタイが開催され、チンギス・カンの3男オゴデイが第2代モンゴル皇帝に選ばれる。以後、オゴデイ・カアンとなる(カアンは王を意味するカンより上の称号)。 |
| この年、ククダイとブベデ率いるモンゴル軍が、再びヴォルガ・ブルガール地方へ侵攻。 | |
| トゥールーズ大学が創設される。 | |
| 1230年 | |
| 1月 | 第二次大昌原の戦い。ドゴルク・チェルビ率いるモンゴルの侵攻軍先遣隊を、紇石烈牙吾塔・移剌蒲阿らが率いる金軍が撃破。ドゴルクは敗戦の責任を取って処刑されたが、オゴデイは処刑を悔いて「4つの過ち」の一つに上げている。 |
| オゴデイ・カアンによって本格的な第2次対金侵攻が始まる。本隊として、中軍はオゴデイ自ら指揮を取り山西から黄河流域へ、右翼はトルイが指揮して京兆府を攻略し開封の南方側へと回り込む作戦、左翼はオッチギンが指揮して東側からゆっくりと侵攻して混乱を助長させるというもの。 | |
| 1231年 | |
| 皇帝フリードリヒ2世の勅令によってサレルノ大学が創設される。9つの中世大学(ストゥディウム・ゲネラーレ)の一つ。前身のサレルノ医学校自体は9世紀ころにはすでに著名であった。 | |
| 倒回谷の戦い。侵攻するモンゴル軍に対し完顔陳和尚率いる「忠孝軍」が大勝。ただ陳和尚の勝利は局地的なもので、大勢はモンゴル軍の有利に進み、金は領土を次々と失う結果となる。 | |
| 8月15日 | ホラズム・シャー朝第8代スルターンのジャラールッディーン・メングベルディーが、モンゴル軍の襲撃から逃走中にマイヤーファーリキーンのクルド人集落で住民に捕らえられ殺害される。長期に渡り各地でモンゴル軍に抵抗し続けたことで英雄視され、その死後もモンゴルに抵抗する動きがあるたびに、存命しているかのような噂が流れたという。 |
| 1232年 | |
| 2月 8日(太宗4年/正大9年1月16日) | 三峰山の戦い。モンゴル帝国の右翼軍トルイが漢水を越えて背後に回ったため、金軍は完顔陳和尚のもと15万の歩兵・騎兵を動員して迎え撃つが、厳寒の猛吹雪の中で猛将トルイの4万の軍勢に大敗。そこにオゴデイ軍10万が殺到し金軍は壊滅し、完顔合達は戦死、捕虜となった完顔陳和尚、移剌蒲阿らも処刑され、金帝国は一気に衰退する。勝利を受けてオゴデイとトルイは帰国することになり、スブタイ、グユク、テムデイ、タガチャルが開封攻囲戦を指揮することに。 |
| 4月 8日(太宗4年/天興元年3月16日) | モンゴル軍、金の首都汴州(開封)を包囲。金側は和平を望むも、オゴデイ・カアンは唐慶を派遣し歳弊の貢納、皇族の人質、孔子の子孫である孔元措など文人27名の引き渡しを要求。金側は曹王訛可を人質に差し出したため、一旦休戦。 |
| 8月(太宗4年/天興元年7月) | オゴデイ・カアンは再度、唐慶を派遣し、金の皇帝号を廃止して臣下となるよう要求。金の哀宗は、これを拒絶することにし、臣下と図って、唐慶やその弟の山禄・興禄らモンゴルの使者17人を殺害。 |
| 8月27日(貞観元年 8月10日) | 鎌倉幕府は、初の武家法令である「御成敗式目」を制定。武家社会での先例や慣習などをもとに、律令などを参考にして、北条泰時指導のもとで51か条にまとめられた。基本的には武家だけに適用されるものだが、後に広く参考にされ各地の分国法の基にされた。土地の所有権と裁判に関する内容が多く、女性にも御家人の地位や所領の相続権・所有権を認めていることなどの特徴がある。当時はまだ読み書きの苦手な武士が多く、律令や公家法が理解できないことも多かったため、まとめられたとされる。 |
| トルイが遠征からの帰国途上に急死する。チンギスカンの4男で、末子相続により後継者と目されたが兄オゴデイに譲った。それまで「監国」の地位にあり、チンギスの遺産を継承して最大の勢力を持っていた人物。そのためオゴデイに暗殺されたという疑惑もある。モンケ、クビライ、フレグ、アリクブケ4兄弟の父親。 | |
| 金の第9代皇帝哀宗(完顔寧甲速)が、家族らも捨てて汴州(開封)から逃走。 | |
| 1233年 | |
| 1月22日 | 開封で守備の指揮を取っていた崔立がクーデターを起こし、参政の完顔奴申と習捏阿不を殺害。開封の実権を掌握。崔立は自分を顕彰する文を石碑に彫るよう元好問ら文人たちに要求したという。 |
| 4月18日 | 崔立が捕らえていた皇族500余名を差し出してモンゴルに降伏。開封が陥落する。 |
| 1234年 | |
| モンゴル帝国軍と南宋の連合軍、蔡州城を包囲。 | |
| 2月 9日(天興3年 1月 7日) | 金の第9代皇帝哀宗が、包囲された蔡州城で、軍の統帥であった完顔呼敦に帝位を譲り、幽蘭軒で自殺。その半日後、蔡州城は陥落し、第10代皇帝となったばかりの完顔呼敦(末帝)は、脱出を試みて捕らえられ、処刑される。末帝は中国歴代皇帝で最も在位が短かったとされる。 |
| 8月23日(天福4年 7月27日) | 竹御所が死去。源頼家の娘で、北条政子の庇護下で将軍家の内紛に巻き込まれずに生き延び、政子の権威的後継者として、寛喜2年にまだ少年だった16歳年下の4代将軍藤原頼経の正妻となった。しかし4年後に頼経との間にできた男児の出産が難産となり、子供は死産。自身も死去した。33歳。源家の血筋を引く将軍候補の誕生の期待も大きかっただけに、御家人らの落胆も大きかったと言われる。源頼朝の直系はこれで断絶した。 |
| 1235年 | |
| 1月18日(文暦元年12月28日) | 霧島山が大きな噴火。火口は御鉢と見られる。山中や周辺の多くの寺社が焼失。周囲の広範囲に大量の噴出物が積もる。 |
| キリナの戦い。マンディンカ(マンデ人)のスンジャタ・ケイタがソソ王国の呪術王スマングル・カンテと戦い勝利。スマングルは戦死したともいう。こののちスンジャタ・ケイタは、ニアニを首都と定めると、領土を拡大。マリ帝国へと発展していく。 | |
| 1236年 | |
| 2月 | バトゥ、モンゴル征西軍司令官となる。35000の兵を率いて西へ向かう。 |
| 3月12日 | バトゥ率いるモンゴル軍、ヴォルガ・ブルガールの首都ビリャルを攻め落とす。ビリャルは完全に破壊され、住民と守備軍は全員処刑されたと言われる。 |
| 1237年 | |
| 11月 | バトゥ、ウラジーミル・スーズダリ大公ユーリー2世に降伏を勧告。周辺のプロンスク公国、リャザン公国を攻撃してこれを滅ぼす。 |
| 1238年 | |
| 2月 4日 | バトゥ、ウラジーミル・スーズダリ大公国の首都ウラジーミルを攻め落とす。ウラジーミルは灰燼に帰し、ユーリー2世は脱出するが、一族は全員処刑される。 |
| 3月 4日 | シチ川の戦い。ウラジーミル・スーズダリ大公ユーリー2世率いる軍勢がモンゴル軍と戦うも大敗を喫し、ユーリー2世も戦死。 |
| この年、モンゴル軍はルーシ諸公国のうち、従属を決めた西部のスモレンスク、北西の湿地帯にあったため侵攻を免れたノヴゴロド、プスコフ以外の北側の諸都市をほぼ壊滅させる。これが後にモスクワなどが台頭する遠因となった。 | |
| 1239年 | |
| モンゴル軍、ルーシ南部へ侵攻。チェルニゴフ公国、ノヴゴロド・セヴェルスキー公国、フシチイシュ公国、ペレヤースラウ公国などを攻め滅ぼす。 | |
| 1240年 | |
| 9月 5日 | モンゴル軍、キエフに侵攻。 |
| 12月 6日 | モンゴル軍、キエフを攻め落とし、キエフ大公国を滅ぼす。つづけてハールィチ・ヴォルィーニ大公国も占領。 |
| モンゴルの四大漢人世侯のひとり厳実が死去。元々は金に仕えていた人物で、一旦は南宋に付き、東平一帯を支配下に置く。その後、モンゴルや金の侵攻に対し、南宋の協力を得られなかったため、モンゴルに降った。東平の他、大名、彰徳などに勢力を拡大。大軍閥となり、東平路行軍万戸とされた(四大漢人世侯で最大の史天沢と同格)。文人を保護し、文化復興のため東平府学を設立して教育を行い、後に多数の帝国高官を輩出した。 | |
| 1241年 | |
| 2月13日 | トゥルスクの戦い。バイダル率いるモンゴル軍とポーランド軍の戦い。モンゴル軍の勝利。 |
| 3月12日 | バトゥ率いるモンゴル軍、ハンガリーに侵攻。 |
| 3月18日 | フミェルニクの戦い。モンゴル軍とポーランド軍の戦いで、モンゴル軍が圧勝。 |
| 4月 1日 | モンゴル軍、クラクフに侵攻。クラクフを灰燼にする。 |
| 4月 9日 | ワールシュタットの戦い。ポーランドのレグニツァ近郊で、侵攻してきたモンゴル軍と、ポーランド王国、神聖ローマ帝国、ドイツ騎士団、聖ヨハネ騎士団、ホスピタル騎士団、テンプル騎士団の連合軍との戦い。モンゴル軍が圧勝。連合軍を指揮したヘンリク2世は戦死。モンゴル軍はヴロツワフに侵攻しこれを破壊。 |
| 4月10日 | ヘルマンシュタットの戦い。モンゴル軍とトランシルヴァニア軍とが衝突し、モンゴル軍が圧勝。 |
| 4月11日 | モヒの戦い。ズブタイ率いるモンゴル軍とハンガリー軍とが衝突。回回砲を使ったモンゴル軍が圧勝。ハンガリー軍はほぼ全滅する。 |
| 12月11日(太宗13年11月8日) | モンゴル帝国第2代皇帝オゴデイ・カアンが「大猟」のために赴いていたウテグ・クラン山で急死。過度の酒色による病死とされている。これを受けてモンゴル征西軍のヨーロッパ侵攻が中止することになる。 |
| 1242年 | |
| 2月10日(仁治3年 1月 9日) | 四条天皇が突如崩御。12歳。子供はおらず、兄弟もいなかったことから、後高倉院系の血統が断絶(京洛政変)。このため、承久の乱で幕府と敵対した後鳥羽上皇の血統から皇位継承者を出す事態に発展。太閤九条道家は順徳上皇の子忠成王を推挙、これに対し村上源氏土御門定通は土御門上皇の子邦仁王を対抗馬に推す。執権北条泰時は鶴岡八幡宮の神託という名目で、邦仁王を選んだ(後嵯峨天皇)。承久の乱の際、幕府打倒に積極的だった順徳上皇に対し、土御門上皇は消極的だったことが背景にある。なお四条天皇の死因は、いたずらで宮中の女官らを滑らせようと滑石の粉をまいたところ、自身が滑って転び、頭を打ったことによると言われる。 |
| 7月14日(仁治3年 6月15日) | 皇位継承騒ぎのさなか、執権北条泰時が急死。この直前に北条朝時ら有力者50人が出家する事態が起きており、北条重時、北条時盛らが京から鎌倉に入るなど、鎌倉幕府内部で、得宗家をめぐる内紛が勃発したとみられる。この期間だけ幕府の公式記録も残っておらず、先の皇位継承騒動と合わせて「仁治三年の政変」ともいう。 |
| 7月15日(仁治3年 6月16日) | 北条泰時の孫、北条経時が第4代執権の地位につく。 |
| 1243年 | |
| チンギス・ハンの長男ジョチの次男バトゥが、欧州遠征から撤退後、征服したキプチャク草原にとどまり、異母兄のオルダとともにジョチ・ウルスを事実上建国。金帳汗国やキプチャク汗国と呼ばれることもある。実質の宗主はバトゥだが、それを支えたオルダは敬意で以て遇され、オルダが東半分を、バトゥが西半分を支配したとされる。首都はヴォルガ川の支流アフトゥバ川のほとりにあるサライ。 | |
| 10月15日 | 聖女シロンスクのヤドヴィガが死去。ポーランド王ヘンリク1世ブロダティの妻で、経験なカトリック教徒。死後24年で列聖された。 |
| 1244年 | |
| 6月 5日(寛元2年 4月28日) | 執権北条経時によって4代将軍藤原頼経が将軍職を辞し、その子藤原頼嗣が第5代将軍となる。頼経は「大殿」と称して権力の座にとどまる。 |
| (寛元2年) | 道元が越前に傘松峰大佛寺を建立。のちに永平寺と改める。 |
| 1245年 | |
| 1月25日(寛元2年12月26日) | 執権北条経時の屋敷で火災が起き、政所にまで延焼。前将軍藤原頼経の上洛計画が中止になる。 |
| 1246年 | |
| 5月17日(寛元4年閏4月 1日) | 前執権北条経時が死去。北条一門の名越光時と反執権派の御家人らが執権北条時頼打倒を画策。 |
| 6月 3日(寛元4年閏4月18日) | 以後の数日、鎌倉市内で武士団が横行し、さらに周辺諸国から参集する騒動発生。 |
| 7月 8日(寛元4年 5月24日) | 鎌倉で地震。 |
| 7月 9日(寛元4年 5月25) | 執権北条時頼、鎌倉を封鎖。 |
| 7月 8日(寛元4年 5月24日) | 名越光時ら反執権派、北条時頼に降伏。 |
| 7月15日(寛元4年 6月 1日) | 名越光時自害。 |
| 8月23日(寛元4年 7月11日) | 前将軍藤原頼経が鎌倉を追放される。三浦光村が京まで同行し、頼経の復権を約束したといわれる。一連の騒動と頼経追放を総称して「宮騒動」と呼ばれる。 |
| 8月24日 | ココ・ナウルでクリルタイが開かれ、オゴデイの長男グユクがモンゴル帝国第3代皇帝に即位。父親とは異なりカアンとは名乗らず、カンと称した。後継者を巡る対立でオゴデイ死去から5年もかかり、その間はグユクの母親でオゴデイ第6皇后のドレゲネが監国として称制が続いたが、グユク親政に移行。グユクは手始めにドレゲネの側近として各属領の総督ら高官を失脚させた女官ファーティマ・ハトゥンを残虐な方法で処刑。ファーティマの支持でヒタイ(漢地)総督となっていたアブドゥッラフマーンも処刑する。一方、失脚していたチンカイ、マフムード・ヤラワチらが復権。 |
| (寛元4年) | 南宋出身の禅僧、蘭渓道隆が来日。 |
| 1247年 | |
| 7月 8日(宝治元年 6月 5日) | 宝治合戦。執権北条家と三浦氏の対立を危惧して、和平を模索していた北条時頼と三浦泰村を差し置いて、強硬派の安達景盛が三浦邸を急襲。一方、三浦側も強硬派の三浦光村主導で一族らが応戦。最終的に三浦一族は自刃して終結。有力御家人による合議制が終わり、北条(得宗)家の専制体制が確立する。 |
| 1248年 | |
| 4月20日(定宗3年 3月25日) | モンゴル第3代皇帝グユクがペルシア遠征の途上で急死。グユクは即位まもなく、過度の酒色によって病気がちとなり、政務を見れなかったと言われ、病死と見られるが、敵対したバトゥによる暗殺説もある。皇后のオグルガイミシュが監国として国政を代行(称制)。 |
| 1249年 | |
| 6月 | 第7回十字軍遠征で、総司令官ルイ9世はエジプトを攻撃。ダミエッタを占領する。 |
| 11月23日 | アイユーブ朝スルタンのサーリフが病死。サーリフの妻シャジャル・アッ=ドゥッルがマムルーク(奴隷軍)を率いて一時的に権力の座につき、サーリフの前妻の子トゥーラン・シャーが帰国するまで、ファフル・アッディーンとともに十字軍に抗戦し、サーリフ生存を装い権力の動揺を防ぐ。 |
| 1250年 | |
| 2月 8日 | マンスーラの戦い。侵攻してきた十字軍に対し、アイユーブ朝のファフル・アッディーンとマムルークのバイバルス・アル=ブンドクダーリーが応戦。ファフルは戦死するが、バイバルスの反撃もあり、11日、アイユーブ朝側が勝利する。 |
| 4月 7日 | ファルスクールの戦い。アイユーブ軍が十字軍を攻撃。追い詰められた十字軍は降伏し、総司令官だったフランス王ルイ9世も捕虜となる。のち莫大な賠償金と引き換えにルイ9世は帰国した。 |
| 5月 2日 | アイユーブ朝のトゥーラン・シャーが、スルタンの地位を継承するも、継母のシャジャル・アッ=ドゥッルが権力を維持していたため、その排除を企てて失敗。シャジャルの率いるマムルーク軍によって殺害される。アイユーブ朝の本体は滅亡(地方政権は残る)。このあとシャジャルがスルタンの地位につき、その3ヶ月後にマムルークの有力将軍イッズッディーン・アイバクと再婚して地位を譲ったことから、マムルーク朝の初代とされる。イスラム世界では珍しい女性の君主(アイバクを初代とする場合もある)。 |
| 1251年 | |
| 7月 1日 | コデエ・アラルでクリルタイが開催され、モンケがバトゥらの支持を得てモンゴル第4代皇帝に即位。トルイの長男。皇位継承を巡ってトルイ家一族と、オゴデイ家一族が対立したため、クリルタイの開催が大幅に遅れた。 |
| 1252年 | |
| 5月10日(建長4年 4月 1日) | 宗尊親王が11歳で鎌倉に入り、弟の後深草天皇から征夷大将軍の宣旨を受ける。皇族初の将軍。宗尊親王の立場を強化したい父親の後嵯峨院の意向と、前将軍藤原頼嗣の出自である摂関家・九条家による幕政への介入を阻止したい執権北条時頼の思惑が一致したことによって実現した。 |
| 5月15日 | ローマ教皇インノケンティウス4世が、異端根絶のための手法(拷問の方法)を定めた勅書「Ad extirpanda」を公布。 |
| 1253年 | |
| モンゴル四代皇帝モンケ・カアンが征西司令官に弟のフレグを命じ、モンゴル軍が出発。 | |
| 1254年 | |
| マムルーク朝2代目スルタンのアイバクが、自身の権力母体でもあったバフリー・マムルークを恐れ、有力者アクターイを殺害。バイバルスらもアイユーブ系有力者ナースィルの元へ亡命。 | |
| 1255年 | |
| 7月 7日 | ヒマラヤ山脈で大きな地震があり、カトマンズ盆地を中心に大きな被害を出し、当時の王も死亡したという。 |
| 1256年 | |
| (建長8年 5月) | 親鸞が息子の善鸞を破門にする。関東での布教で独自の教えを広めようとしたため。 |
| 11月27日 | フレグ率いるモンゴル軍がイスラム教ニザール派を滅ぼす。 |
| 1257年 | |
| 4月10日 | マムルーク朝の第2代スルタンで、初代スルタンのシャジャルの夫であるイッズッディーン・アイバクが、モースルのアミールの娘を妻に迎えようとしたため、地位を失うことを恐れた妻のシャジャルによって殺害される。 |
| 4月28日 | シャジャル・アッ=ドゥッルが夫アイバクの殺害に関与したとして、アイバクの元妻やマムルークらの手で殺害される。マムルーク朝のスルタン位はアイバクの前妻の子マンスール・アリーが後を継ぎ、マムルークの将軍ムザッファル・クトゥズが後見となる。 |
| 5月 | 小スンダ列島ロンボク島のリンジャニ山で大規模な噴火。10月ころまで続く。 |
| フランス王ルイ9世の宮廷司祭であったロベール・ド・ソルボンが、パリ大学に学寮を設立。後に神学部も興し、パリ大学は通称ソルボンヌ大学と呼ばれるようになる。 | |
| 1258年 | |
| 2月 | フレグ率いるモンゴル軍がアッバース朝バグダードを壊滅させる。 |
| この年、ヨーロッパでは異常低温・異常気象などで不作となる。前年のリンジャニ山大噴火の影響とする説も。 | |
| 1259年 | |
| 8月11日 | モンゴル第4代皇帝モンケ・カアンが南宋遠征中の途上、合州の釣魚山で流行病によって死去。関係が悪化していた弟のクビライ派によって暗殺されたという説もある。モンケは文武両道の有能な皇帝だったが、一族を信じずに排除したことから、その後のモンゴル帝国分裂の遠因を作った。 |
| 11月 | マムルーク朝の有力者ムザッファル・クトゥズが、モンゴルの侵攻に対抗できる人物をスルタンにすべきだと主張し、スルタンのアリーを廃して、自らスルタンに即位。 |
| 鄂州の戦いで長江を渡河したクビライ軍を賈似道の指揮する南宋軍が撃破。その功績により賈似道が宰相となる。クビライは、皇位継承を巡る争いのため、北方へ退却。賈似道との間で密約があったとも。 | |
| 1260年 | |
| 2月 | フレグ率いるモンゴル軍がシリアのアレッポを攻め落とす。 |
| 4月 | フレグ率いるモンゴル軍がアイユーブ朝の都ダマスクスを攻め落とす。 |
| 5月 5日 | クビライがクリルタイを開いて、モンゴル帝国第5代皇帝(大ハーン)に即位を宣言。 |
| フレグのもとに、兄の皇帝モンケの死去の報が入り、モンゴル帝国本土へ引き返すことになる。遠征軍はキト・ブカに委任。 | |
| 9月 3日 | アイン・ジャールートの戦い。中近東へ遠征していたモンゴル皇弟フレグの部下キト・ブカの軍勢とエジプト・マムルークのスルタン、クトゥズとの戦いで、クトゥズが勝利。モンゴル軍の遠征が止まり、マムルーク朝拡大のきっかけとなる。 |
| 10月24日 | マムルーク朝のスルタン、クトゥズが共にモンゴル軍と戦ったバイバルスによって、サラーヒーヤでの狩猟の最中に刺殺される。クトゥズがバイバルスにアレッポ総督の地位を約束していながら反故にしたことから恨みを買ったとされる。バイバルスがスルタンの地位につく。クトゥズもバイバルスもイスラムの英雄とされ、バイバルスが実質的なマムルーク朝の創始者とされることもある。 |
| 1261年 | |
| 7月25日 | 東ローマ帝国からの亡命国家ニカイア帝国が、コンスタンティノポリスを奪回。ニカイアの実質最高権力者であった共同皇帝で大貴族のミカエル・パレオロゴスがローマ皇帝ミカエル8世パレオロゴスとして即位し、東ローマ帝国を復活させる。ニカイアの形式上の皇帝ヨハネス4世ラスカリスは廃位され、目を潰された上で幽閉された。 |
| 1262年 | |
| アイスランドがノルウェーの支配下に置かれる。 | |
| 1263年 | |
| モンゴルがアムール川流域に進出し、同地域に住むギレミ(吉里迷)を服属させる。ギレミは何を指しているかわからないが、地元の民族ニヴフか、アイヌを指していると見られる。モンゴル帝国は同地に東征元帥府を設置。 | |
| 1264年 | |
| 9月 8日 | ポーランドのボレスワフ敬虔公によって「ユダヤ人の自由に関する一般契約」(カリシュの法令)が発布される。ユダヤ人の立場を法的に保護したはじめての法令。商業や旅行の自由を認め、キリスト教徒との争いに関してのユダヤ人の法的保護を認めた。この結果、ポーランドには多数のユダヤ人が移り住むようになる。この一帯の中小都市には「シュテットル」というコミュニティが多数誕生した。 |
| モンゴルの漢人世侯のひとりで済南を支配した張栄が死去。有力漢人世侯では最後にモンゴルの傘下に入った人物。モンゴル軍による虐殺を度々止めたと言われ、荒廃した地域の復興にも努めた。 | |
| モンゴル軍が、樺太に兵を派遣。樺太に住むギレミが、クイ(骨嵬)やイリウ(亦里于)が毎年のように入寇することを訴えたため。クイやイリウが何を指しているのかも不明だが、海を隔てた北海道のアイヌではないかという説がある。 | |
| 1266年 | |
| 2月26日 | ベネヴェントの戦い。ローマ教皇の依頼を受けたフランス王アンジュー家のシャルル・ダンジューが、シチリアのマンフレーディ王(神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世の庶子)を打ち破り、同地の支配を確立する。 |
| 1268年 | |
| 4月18日(文永5年 3月 5日) | 北条時宗が8代執権に就任。 |
| 8月 9日(至元5年 6月29日) | モンゴルの四大漢人世侯のひとり、張柔が死去。元は金の軍閥苗道潤に属していたが苗道潤が賈瑀に暗殺された後、賈瑀討伐を主張して兵を挙げ、モンゴルの侵攻を受けてその傘下に加わると、賈瑀を倒してその勢力圏を吸収。トルイの指揮下で開封攻囲戦、蔡州の戦いなどで功績を上げた。オゴデイ、モンケ、クビライのもとで南宋攻略にも貢献したという。 |
| アジュ率いるモンゴル軍による南宋攻撃で、襄陽・樊城の戦いがはじまる。 | |
| この年、津軽で蝦夷が武装蜂起し、蝦夷代官の安藤氏が殺害される。原因として鎌倉得宗家による支配の強化(安藤氏は得宗家の代官)、モンゴルによる樺太遠征がアイヌ交易に影響したとする見方もある。 | |
| 1270年 | |
| 8月10日 | エチオピア・アムハラの有力者となったイクノ・アムラクがザグウェ王朝を倒し、ソロモン朝エチオピア帝国の初代王となる。アムラクは古代イスラエルのソロモン王とエチオピアのシバの女王との血統とされるアクスム王国の後継者を名乗っていた。ソロモン朝エチオピア帝国は小中断を挟んで1975年まで続く。 |
| 1271年 | |
| 范文虎率いる襄陽援軍10万がモンゴル軍に大敗。 | |
| 1272年 | |
| 3月11日(文永9年 2月11日) | 二月騒動が起こる。北条一門の名越時章・教時兄弟が得宗被官・御内人である四方田時綱ら5人によって誅殺される。前将軍宗尊親王側近の中御門実隆、六波羅探題南方の北条時輔、安達頼景、世良田頼氏らも連座。前将軍宗尊親王は出家した。 |
| 3月17日(文永9年 2月17日) | 後嵯峨上皇が崩御。土御門天皇の子で、四条天皇急死を受けて、幕府の意向で即位。すぐに子の後深草天皇に譲位し長期に渡って院政を敷き、鎌倉幕府と協力して安定政権を築いた。一方で、後継者を、ともに自分の子である後深草天皇系統(持明院統)と亀山天皇系統(大覚寺統)に分けたため、のちの南北朝分裂につながった。 |
| 9月25日(文永9年 9月 2日) | 二月騒動で殺害された名越時章は冤罪であったとして、討手の御内人5人が処刑される。ただ二月騒動は執権北条時宗と連署北条政村の命で行われたとみられる。 |
| 1273年 | |
| アジュ、史天沢らモンゴル軍が、回回砲を投入し、南宋の樊城を攻略。守将張漢英は降伏。漢水を挟んで隣接する襄陽城への砲撃も開始され、守将呂文煥も降伏。南宋は重要拠点を失い、一気に長江流域まで危機的状況に陥る。 | |
| モンゴル帝国が塔匣剌(タカラ)を征東招討司に任命し、樺太侵攻を計画するも中止。 | |
| 1274年 | |
| 11月 4日(文永11年10月 5日) | 高麗の王子王賰(のちの忠烈王)の執拗な日本征討の主張により、元・漢・高麗の日本遠征軍4万が対馬に侵攻。文永の役(元寇)がはじまる。 |
| 11月13日(文永11年10月14日) | 元・漢・高麗の日本遠征軍が壱岐に侵攻。激戦となり両方に大きな被害を出す。 |
| 11月15日(文永11年10月16日) | 元・漢・高麗の日本遠征軍が平戸・松浦方面に上陸し、松浦党らと交戦。 |
| 11月19日(文永11年10月20日) | 元・漢・高麗の軍勢と九州の軍勢が博多周辺で交戦。日本側が大敗するも、元軍側も副将の劉復亨が負傷、矢玉も付き、高麗へ撤退。沖合で暴風に遭遇して、1万3500人が未帰還という大損害を出す。暴風は季節的に台風とは考えにくいが、元軍側の軍船は朝鮮で建造されたもので、河川で使用することの多い平底型をしたものもあり、海洋での波浪に耐えられなかったものも多かったと見られる。なお、通信速度の遅さから、鎌倉に元軍対馬侵攻の報が伝わったのは、元軍が撤退したあとである。 |
| 1275年 | |
| 2月21日(徳佑元年 3月19日) | 丁家洲の戦い。賈似道率いる南宋軍が、バヤン、アジュ、呂文煥らの率いるモンゴル軍に大敗。 |
| 3月 5日(至元12年 2月7日) | モンゴルの四大漢人世侯の一人で、クビライ即位後に宰相・南宋攻略総司令官となった史天沢が死去。真定の軍閥で金からモンゴルに降り、「真定・河間・大名・東平・済南」の五路万戸と呼ばれた。金の攻略、南宋の攻略には漢人軍閥を率いて功績を上げた。 |
| 5月12日(建治元年 4月15日) | モンゴルからの使者杜世忠、何文著ら一行が長門国室津に到着する、捕らえられて太宰府へ送られる。 |
| 9月27日(建治元年 9月 7日) | モンゴルからの使者杜世忠、何文著ら一行が鎌倉龍ノ口で処刑される。 |
| 10月 9日(徳佑元年 9月19日) | 南宋の宰相賈似道が敗戦の責任で失脚し、追放される途上、会稽県尉の鄭虎臣によって殺害される。 |
| 1276年 | |
| (建治2年 3月) | 鎌倉幕府は元軍の再来を警戒し、逆に高麗への遠征を行う予定だったが、中止となった。一方で博多周辺の石築地(元寇防塁)の建設は進められた。 |
| 1277年 | |
| 4月16日 | アブルスターンの戦い。ルーム・セルジューク朝のモンゴルからの解放を掲げたマムルーク朝の軍勢とモンゴル軍との戦い。マムルーク朝の勝利。バイバルスはセルジューク朝のスルタンとして迎え入れられるも、モンゴルの影響下にある有力者からの協力は得られず28日に撤退。 |
| 6月 8日 | 帰国したバイバルスが、急病に倒れる。毒をもられたとする説もある。 |
| 7月 1日 | バイバルスが死去。スルタンの地位は息子のバラカが継ぐ。 |
| 1278年 | |
| 8月26日 | マルヒフェルトの戦い。ボヘミア王オタカル2世とドイツ王に推戴されたルドルフ・フォン・ハプスブルクが戦い、オタカルは戦死し、ルドルフが勝利。ハプスブルク家の伸張のきっかけとなる。 |
| 1279年 | |
| 3月19日(祥興2年 2月 6日) | 崖山の戦い。元艦隊と南宋残存艦隊が戦い、祥興帝が陸秀夫とともに自殺して南宋は完全に滅亡。南越方面へ逃走した張世傑も船が嵐に遭遇して沈み死亡。 |
| 1280年 | |
| (至元17年) | 元の郭守敬・王恂・許衡らが、新たな暦法をまとめて、皇帝クビライ・カーンに提出。「授時暦」の名を与えられる。元朝および明朝の大半で使用された。日本でも授時暦を元に経度の差を取り入れて補正した大和暦が採用されている。 |
| 1281年 | |
| 5月22日(弘安4年 5月 3日) | 元が日本再侵攻を開始。弘安の役。元と高麗の東路軍900艘以上、兵力4万が朝鮮南部の合浦から順次出港。 |
| 6月 9日(弘安4年 5月21日) | 元と高麗の東路軍が対馬侵攻。激戦が繰り広げられる。 |
| 6月14日(弘安4年 5月26日) | 元と高麗の東路軍が壱岐侵攻。激戦が繰り広げられる。この時悪天候で被害を出している。 |
| 6月23日(弘安4年 6月 6日) | 元と高麗の東路軍が博多に侵攻してくるも、防塁や逆茂木などで要塞化されていたため、上陸を断念。志賀島へ移動し上陸する。日本側も同日夜半に東路軍の軍船を襲撃。 |
| 6月25日(弘安4年 6月 8日) | 志賀島の戦い。日本側は、二手に分かれて攻勢をかけ、東路軍の司令官で東征都元帥の洪茶丘をあと一歩まで追い詰めるも取り逃がす。東路軍は大敗して壱岐まで後退。 |
| 7月 1日(弘安4年 6月14日) | 元と高麗の東路軍の一部が長門に侵攻。 |
| 7月 2日(弘安4年 6月15日) | 旧南宋の江南軍が壱岐まで到達する予定日だったが、江南軍が現れず、東路軍内部では撤退の論議も出たという。この頃、江南軍約10万、軍船3500艘は、数日かけて慶元や定海など複数の港湾から出港。予定より遅れたのは総司令官の日本行省左丞相・阿剌罕が病になったため、司令官職を阿塔海に交代したことなどによる。江南軍は、複数のルートに分かれて、壱岐ではなく、平戸へと目標を変更して進行。 |
| 7月 9日(弘安4年 6月22日) | この頃、江南軍は平戸島に到達、上陸して防塁の建設を進め、島の周辺に軍船を集める。 |
| 7月15日(弘安4年 6月28日) | 鎌倉幕府は、九州と、石見、出雲、因幡、伯耆の、荘園の年貢米を兵糧として徴収することを朝廷に申し入れる。 |
| 7月16日(弘安4年 6月29日) | 主に九州の御家人らが数万の兵で壱岐の東路軍を攻撃。 |
| 7月18日(弘安4年 7月 2日) | 壱岐瀬戸浦の戦い。激戦となって両軍に損害が出るが、江南軍が平戸島へ到達したことが伝わり、東路軍は転進のため、壱岐を離れる。日本側では元軍が退却したと判断した様子。 |
| 8月12日(弘安4年 7月27日) | 7月半ばころから東路軍と江南軍は鷹島を占拠しここに拠点を築く。27日、元軍の動きを察知した日本軍が海から攻撃を仕掛け、海戦となる(鷹島沖の戦い)。 |
| 8月15日(弘安4年 7月30日) | この日の夜、台風と思われる暴風雨が九州北部に襲来し、元軍の軍船は波浪に飲まれたり、衝突大破するなどして甚大な損害を被る。なお被害の殆どは江南軍で、東路軍側の被害は比較的少なかった模様。それでも高麗王族で東路軍の左副都元帥・アラテムルは溺死している。 |
| 8月20日(弘安4年閏7月 5日) | 江南軍を実質率いていた范文虎と張禧の間で協議が行われ、退却が決定する。范文虎らは頑丈な軍船から兵士らを降ろして、自分たちが乗り込み先に戦線離脱。逆に張禧は軍馬を降ろして、兵4000人を収容すると離島した。日本軍側もその動きを把握しており、総攻撃を開始。御厨沖の戦い。元軍は司令官たちに見捨てられたも同然の状態だったため、大敗を喫する。 |
| 8月22日(弘安4年閏7月 7日) | 日本軍は、鷹島で取り残され孤立していた元軍を総攻撃。元軍は壊滅。鷹島は中国側では白骨山などとも呼ばれている。元側の未帰還者は最大6万人を超えるともいわれる(うち日本側の捕虜となったものが2~3万人いた模様)。 |
| (至元17年) | 元の郭守敬・王恂・許衡らが、新たな暦法をまとめて、皇帝クビライ・カーンに提出。「授時暦」の名を与えられる。元朝および明朝の大半で使用された。日本でも授時暦を元に経度の差を取り入れて補正した大和暦が採用されている。 |
| 1282年 | |
| 3月30日 | シチリアの晩祷事件。フランス系シチリア王シャルル・ダンジューの圧政に対し住民が蜂起した事件。教会の晩祷の鐘が鳴った時に住民が蜂起したため、こう呼ばれる。 |
| 1283年 | |
| 1月 9日(至元19年12月 8日) | 南宋の臣で、モンゴルに囚われた後も、クビライの誘いを『正気の歌』を詠んで断り続けた文天祥が処刑される。 |
| (至元20年 8月) | クビライ・カーンは第三次日本遠征計画を開始。各地に造船と徴発を命じる。疲弊した各地では群盗が跋扈し、反乱が起きたと言われる。 |
| 1284年 | |
| 4月20日(弘安7年 4月 4日) | 北条時宗が死去。2度の元寇を退けたことから評価は高いが、強権的な政権運営を批判されることもある。得宗家は嫡男の貞時が後を継ぐ。時宗の死の直後に北条家内部の紛争が起きた可能性がある。 |
| 6月26日 | ドイツ・ハーメルンの町で子供130人余りが消息不明になる事件が起こる。いわゆるハーメルンの笛吹き男事件。 |
| モンゴル帝国が、聶古帯(ニクタイ)を征東招討司に任命し、樺太の骨嵬を攻撃。 | |
| 1285年 | |
| 12月14日(弘安8年11月17日) | 霜月騒動。最後の有力御家人、安達泰盛が、得宗家被官の御内人で内管領の平頼綱の兵に襲撃され合戦、滅ぼされる。また同じ時期に全国の安達氏の一門、及び与党御家人も相次いで襲撃されて滅ぼされるなど、計画的なクーデターであった。泰盛による御家人の権力強化の弘安徳政で負担を強いられた平頼綱や小規模の御家人、公家などの反発を買ったとも、泰盛、頼綱ともに北条得宗家の縁者であることから得宗専制内部の闘争とも言われる。 |
| モンゴル帝国が、塔塔児帯(タタルタイ)・兀魯帯(ウロタイ)らをして、樺太の骨嵬を攻撃。 | |
| 1286年 | |
| (至元23年 1月) | 元による第三次日本遠征計画が中止になる。負担の重さに耐えかねて反乱などが相次ぎ、さらにチャンパ王国が元からの離脱を図ったため、そちらに派兵したことも影響した。 |
| モンゴル帝国が、前年に続いて樺太の骨嵬を攻撃し、屯田を置いたという。 | |
| 1287年 | |
| 11月27日(弘安10年10月21日) | 後宇多天皇の譲位により、持明院統の伏見天皇が即位。それまで大覚寺統の亀山上皇が院政を敷いていたが、安達泰盛と連携して徳政を進めていたため、霜月騒動の余波で亀山上皇の院政が停止。後宇多天皇が上皇として院政を敷き、亀山上皇と対立関係にあった持明院統の伏見天皇に皇位が移った。 |
| 1288年 | |
| 4月 | 白藤江の戦い。陳朝大越国に侵攻した元軍の補給線を攻撃した大越軍が、元軍の退却を見計らい、白藤江で奇襲。元軍は壊滅的な損害を被り指揮官のウマルは捕らえられる(後に殺害された)。また元軍司令官の鎮南王トガンは敗走したため、父のクビライの怒りを買ったと言われる。大越軍を率いたのは陳朝皇族の名将、陳国峻(陳興道)。 |
| この年、1220年から建設が続いていたアミアン大聖堂が落成。 | |
| 1289年 | |
| モンペリエ大学が創設される。9つの中世大学(ストゥディウム・ゲネラーレ)の一つ。それ以前から教育機関があったとされる。 | |
| 1290年 | |
| 4月19日(正応3年 3月 9日) | 浅原事件。浅原為頼とその2人の子の3人の武士が、天皇と皇太子を襲う目的で御所のある二条富小路殿に侵入。出くわした女官の機転で危険を察した伏見天皇と皇太子は、三種の神器と宝物の管弦2つを持って脱出。3人は失敗を悟って自害。霜月騒動に巻き込まれて所領を失い、悪党化した浅原親子が追補をうけたことを直接の原因とするが、為頼は大覚寺統系の公卿である前参議三条実盛の太刀「鯰尾」を所有していたことから、大覚寺統が、持明院統の天皇を狙ったという嫌疑も起きた。結局嫌疑不十分で三条実盛も釈放された。 |
| ポルトガル王ディニス1世によってコインブラ大学が創設される。9つの中世大学(ストゥディウム・ゲネラーレ)の一つ。 | |
| 1291年 | |
| 8月 1日 | 神聖ローマ帝国のウーリ州、シュヴィーツ州、ウンターヴァルデン州の代表者が、リュトリの野に集結し、ハプスブルク家アルブレヒト1世の支配権に対抗する永久同盟「誓約者同盟」を結ぶ。これが後のスイスの発祥となる。 |
| マムルーク朝スルタンのアシュラフ・ハリールの侵攻によって、最後の十字軍国家アッコが陥落する。 | |
| 1293年 | |
| 5月19日(正応6年 4月12日) | 鎌倉大地震。関東地方で津波を伴う巨大地震が発生。神社仏閣が多く倒壊。 |
| 5月29日(正応6年 4月22日) | 平禅門の乱。北条得宗家の御内人で鎌倉幕府の実権を握っていた平頼綱一族が、地震直後の混乱の中、執権貞時に誅殺され一族93人も殺された。なお、頼綱の弟ともされる長崎光綱は執権側についていたためか処罰されず、また霜月騒動で滅ぼされた安達一門の生き残り安達時顕などが登用されるきっかけともなった。一方、頼綱討伐の直接のきっかけとなった、頼綱讒訴を執権に行った嫡男の宗綱は執権側についたにも関わらず流罪となっていて、内管領内部の権力闘争の様相もある。 |
| 9月 6日(正応6年 8月 5日) | 地震や旱魃を受けて、永仁へ改元。出典は『晋書』。 |
| 1294年 | |
| 2月18日(至元31年 1月22日) | モンゴルの第5代皇帝で、元朝の初代皇帝でもあるクビライが、大都の紫檀殿で崩御。 |
| 5月10日(至元31年 4月14日) | クリルタイが開かれ、モンゴルの第6代皇族で、元朝の2代皇帝にテムルが即位。クビライの次男チンキムの3男にあたり、クビライから皇太子に指名されていたため、長兄のカマラを抑えて、母ココジンや知枢密院事バヤンらの支持を得られた(知枢密院事は軍政次官で、長官である枢密使が皇族を当てる形式上のものなので実質上の最高官)。 |
| 1295年 | |
| 1月 | モンゴルの皇族ボルジギン氏族ボドンチャルの子孫で、バアリン部の出自としてクビライ・カアンの重臣となり、テムル(オルジェイトゥ・カーン)の即位に貢献した将軍バヤンが死去。 |
| 1297年 | |
| 1月 8日 | ローマ教皇を支持するゲルフ派のフランソワ・グリマルディらが、修道士姿で神聖ローマ帝国皇帝派(ギベリン派)の抑えるモナコ要塞に侵入し占拠。すぐに奪い返されるが、これをしてモナコ建国としている。 |
| 3月30日(永仁5年 3月 6日) | 永仁の徳政令が発令される。越訴の停止、御家人所領の売買・質入れの禁止、債権・債務に関する訴訟非受理の3か条とみられる。分割相続等によって零細化が進む御家人の救済のため。 |
| 1301年 | |
| 9月24日(正安3年 8月22日) | 北条貞時が執権職を辞し、北条庶家出身の北条師時が第10代執権となる。貞時が引き続き権力を握り、幼い嫡男高時が成長するまでの間を、信頼関係のあった師時に中継ぎさせたものとされる。連署は北条時村が就任。 |
| 1303年 | |
| 9月 | アナーニ事件。フランス国王フィリップ4世が対立していたローマ教皇ボニファティウス8世を襲撃し、イタリアのアナーニで捕らえる。 |
| 1304年 | |
| (嘉元2年) | 鎌倉幕府前半の公式歴史書である『吾妻鏡』がこの頃までにほぼ編纂されたとみられる(下記後深草院の院号が記載されていないため)。北条氏を擁護する曲筆が多いとされ、戦後は史料的価値を低く見られたが、近年編纂のもととなった原史料の研究が進んだこともあり、鎌倉幕府研究の第一級史料として再評価されている。なお『吾妻鏡』は完成しなかったとみられる。 |
| 8月17日(嘉元2年 7月16日) | 第89代天皇だった久仁(後深草院)が崩御。持明院統の祖であり、長講堂領を支配した。 |
| 8月18日(嘉元2年 7月17日) | 後深草院の院号を追号する。 |
| 1305年 | |
| 5月16日(嘉元3年 4月22日) | 嘉元の乱。前執権で実権を握っていた北条貞時の屋敷で火災が起きる。 |
| 5月17日(嘉元3年 4月23日) | 嘉元の乱。北条貞時の仰せと称して得宗被官や御家人ら12人が、連署の北条時村邸を襲撃。時村ら50余人が殺害される。 |
| 5月25日(嘉元3年 5月 2日) | 嘉元の乱。北条時村邸を襲撃した12人のうち逃走した和田茂明以外の11人が捕らえられ、斬首される。 |
| 5月27日(嘉元3年 5月 4日) | 嘉元の乱。引付頭人の北条宗宣らが、得宗家執事北条宗方を襲撃し、宗方は討手の佐々木時清と相討ちとなり、宗方邸も焼け落ち一族郎党の多くが討ち死に。嘉元の乱は事象の詳細は判明しているが首謀者や動機がはっきりしない紛争で、北条宗方が権力を握ろうとして起こしたクーデター説、北条貞時が霜月騒動に倣って北条庶家を排除しようとした陰謀説、貞時と宗方の対立説、貞時と対立関係にあった北条宗宣による陰謀説など諸説ある。この乱後、貞時は政務を放棄し、御内人と北条外戚の御家人らによる寄合衆が実権を握って得宗専制体勢は崩壊。 |
| 1307年 | |
| 2月10日(大徳11年 1月 8日) | モンゴルの第6代皇帝で、元朝第2代皇帝のテムルが死去。過度の酒色による病死とされる。敵対したカイドゥを滅ぼしてモンゴル帝国の内紛を終わらせた。 |
| 8月22日(徳治 2年 7月24日) | 姈子内親王(遊義門院)が崩御。後宇多天皇が最も寵愛した女性で、後深草天皇の娘。持明院統と大覚寺統が対立する中、大覚寺統の後宇多天皇が持明院統の後深草天皇の娘を見初めて「盗み出し」問題になった。後宇多上皇は遊義門院の死去を受けて仁和寺で出家した。 |
| 10月13日 | フランス王フィリップ4世の陰謀によりフランス国内のテンプル騎士団が異端とされて摘発され壊滅する。同騎士団は聖地エルサレムとその巡礼を守護し、巡礼者の財産を預かる金融機関でもあったため、その経済力と資産を狙われたと言われる。この出来事が、13日の金曜日を不吉だとする説の要因の一つに挙げられる。なお、フランス以外では大きな弾圧には至らなかった。 |
| 11月18日 | 弓の名手ウィリアム・テルが息子の頭上のリンゴを射抜く。代官ヘルマン・ゲスラーに逆らったことで強制された出来事。 |
| 1308年 | |
| 9月 | 教皇クレメンス5世がフランス王国の要請で教皇庁をアヴィニョンに移し、アヴィニョン虜囚がはじまる。 |
| 1311年 | |
| 11月 3日(応長元年 9月22日) | 10代執権北条師時が評定中に死去。死去の直前に出家したとされる。 |
| 11月13日(応長元年10月 3日) | 11代執権に連署で北条庶家の大仏流北条宗宣が就任。宗宣は9代執権北条貞時とは関係が悪かったことから、病身の貞時にはすでに実権がなかったものとみられる。 |
| 12月 6日(応長元年10月26日) | 9代執権北条貞時が死去。満39歳。一旦は得宗専制政治を確立したが、嘉元の乱以降は酒色に溺れて政務を見なくなり、実権も失った。得宗家は9歳の高時が継ぐ。 |
| 1312年 | |
| 4月27日(応長2年 3月20日) | 天変地異により正和に改元。出典は唐記から。 |
| 7月 4日(正和元年 5月29日) | 幕府11代執権の北条宗宣が辞任。内管領長崎円喜や御家人安達時顕が実権を握っていたため、形式的な執権だったとみられる。 |
| 7月 6日(正和元年 6月 2日) | 幕府12代執権に連署の北条熙時が就任。嘉元の乱の際に一族が滅ぼされたが生き延びた人物。実権は長崎円喜らが握っていたためか、連署は置かれず。 |
| 7月16日(正和元年 6月12日) | 北条宗宣が死去。 |
| 1313年 | |
| 9月 | フランス国王フィリップ4世の側近で、数々の陰謀・工作に関わったギヨーム・ド・ノガレが死去。 |
| 1314年 | |
| 6月24日 | バノックバーンの戦い。スコットランドに侵攻したイングランド軍がバノックバーンの湿地帯で大敗を喫する。 |
| 1315年 | |
| 8月11日(正和4年 7月11日) | 北条熙時が執権職を辞任。第13代執権に北条庶家の普恩寺流北条基時が就任。 |
| 8月18日(正和4年 7月18日) | 北条熙時が死去。37歳。この頃の北条家有力者には30代で病死する例が多い。 |
| 11月15日 | モルガルテンの戦い。スイス原初同盟と神聖ローマ帝国オーストリア公国との戦い。同盟側が勝利し原初同盟は発展することになる。 |
| ニュージーランド北島のタラウェラ山が大噴火。 | |
| この年、ヨーロッパでは長雨と気温の低い状態が続き、穀物生産量が低下。家畜も多くが死に、大飢饉が起きる。タラウェラ山の噴火に伴う気象異変が原因という説が有力。 | |
| 1316年 | |
| この年も、ヨーロッパでは長雨と気温の低い状態が続き、大飢饉は継続。 | |
| 1317年 | |
| 3月16日(正和6年 2月 3日) | 地震などにより、文保に改元。出典は『梁書』から。 |
| (文保元年) | 皇位継承順位に関する文保の和談が幕府、大覚寺統、持明院統の間で行われる。いわゆる両統迭立が決まったものとされているが、実際には提案だけされて具体的な決定には至らなかったとする説もある。 |
| この年の夏になり、ようやくヨーロッパの異常気象が回復するも、大飢饉の影響は1325年ころまで続いたと言われる。 | |
| 1319年 | |
| 1月12日(文保2年12月20日) | 鎌倉殿中問答がはじまる。北条高時のもと、法華宗の日印が諸宗派と問答を行う。日静によって記録された。 |
| 10月28日(元応元年9月15日) | 鎌倉殿中問答が終わる。日印がことごとく論破し法華宗が布教を許されたという。 |
| 1320年 | |
| (元応2年) | この年、蝦夷代官の安藤季長と従兄弟の安藤季久の内紛に、出羽の蝦夷までが武装蜂起。幕府が裁定に乗り出すも収まらず、紛争は1328年まで続く。 |
| この頃から数年間、中国でペストが流行する。 | |
| 1322年 | |
| 1月16日(元亨元年12月28日) | 後醍醐天皇の親政。院政の後宇多法皇の引退に伴い親政へ。 |
| 1324年 | |
| 7月16日(元亨4年 6月25日) | 後宇多法皇が崩御。生前の法皇の意向に従い、大覚寺統の後二条天皇の皇子邦良親王に皇位を譲る動きが起こる(持明院統はこの次の皇位を受け継ぐことで了承)。本来中継ぎとして即位した後醍醐天皇はこれに反発し、鎌倉幕府の倒幕へ乗り出す。 |
| 10月 7日(元亨4年 9月19日) | 後醍醐天皇の意を受けた日野資朝、日野俊基らが倒幕のための工作を進めていることが発覚(倒幕派の土岐頼員が妻(六波羅評定衆の斉藤利行の娘)に漏らして発覚したと言われる)。倒幕側に与して上洛していた御家人多治見国長・土岐頼兼らが六波羅探題の小串範行、山本時綱らの討伐を受ける。日野資朝らは捕縛。正中の変。日野資朝が首謀者として佐渡流罪となるが、天皇は無関係として不問とされた。 |
| マリ帝国の第9代王マンサ・ムーサが数万の従者を連れてメッカへの巡礼を行う。大量の金を持っていき、エジプトのカイロでばらまいた大量の金のために、金相場が下落したと言われる。 | |
| 1325年 | |
| 6月 | モロッコのイスラム教徒イブン・バットゥータが聖地メッカへの巡礼の旅に出る。以後30年に渡り、彼は中東、アフリカ東岸、西アジア、南アジア、東南アジア、中国、さらにサハラなど世界各地へ大旅行を行ったと言われる(ただし記録はイブン・ジュザイイが彼の口述を聞いて記した書しかないため疑問点も多い)。 |
| 1326年 | |
| 4月16日(正中3年 3月13日) | 14代執権北条高時が病のために出家する。後継を巡って、高時の弟北条泰家を推す安達時顕(高時の妻の父)と、高時の長男邦時を将来の候補として中継ぎに金沢貞顕を推す内管領長崎高資が対立。 |
| 4月19日(正中3年 3月16日) | 北条家の一門金沢貞顕が15代執権に就任。対立候補だった北条泰家は出家。 |
| 4月29日(正中3年 3月26日) | 金沢貞顕の執権就任に反対するものが多数出て身の危険を感じた貞顕は、出家して執権職を辞任。 |
| 5月26日(正中3年 4月24日) | 北条家の一門赤橋守時が16代執権に就任。最後の執権。実権は高時と長崎高資にあり、形式的なものだったとも言われる。なお守時は鎌倉幕府を倒した足利尊氏の義兄でもある。 |
| 1328年 | |
| フランス・カペー朝のシャルル4世が男児の後継者を残さず没したため断絶(カペー朝は男系相続)。分家のヴァロワ家のフィリップ6世が即位し、ヴァロワ朝フランス王国が成立。母方がカペー朝の血筋であるイングランド王エドワード3世がカペー朝の王位継承権を主張し、百年戦争の要因の一つとなった。 | |
| 1329年 | |
| 8月30日(天暦2年 8月 6日) | モンゴル帝国第13代皇帝で元の第9代皇帝コシラが死去。モンゴル帝国第7代皇帝カイシャンの長男。内乱の中でチャガタイに亡命していたが、一旦カアンを名乗った弟トク・テムルに帝位を譲らせ、8月に入ってモンゴル高原から上都に入ったが、まもなく急死した。トク・テムルを擁立していたキプチャク軍閥のエル・テムルによる毒殺と見られる。実質数日の帝位となった。トク・テムルとエル・テムルがコシラ一派から権力を奪い返す事態に発展。 |
| 1331年 | |
| 9月26日(元弘元年 8月24日) | 後醍醐天皇、京を脱出。 |
| 9月29日(元弘元年 8月27日) | 後醍醐天皇、笠置山に入る。 |
| 10月 4日(元弘元年 9月 2日) | 幕府軍が笠置山を攻撃。笠置山の戦い。 |
| 10月13日(元弘元年 9月11日) | 楠木正成、下赤坂城で挙兵。 |
| 10月22日(元弘元年 9月20日) | 光厳天皇即位。 |
| 10月30日(元弘元年 9月28日) | 笠置山陥落。後醍醐天皇ら捕らえられる。 |
| 11月21日(元弘元年10月21日) | 下赤坂城陥落。楠木正成は行方をくらます。 |
| 1332年 | |
| 4月 2日(元弘2年 3月 7日) | 後醍醐天皇、隠岐の島へ流される。 |
| 9月 2日(至順3年 8月12日) | モンゴル帝国第12代皇帝で元の第8代皇帝であるトク・テムルが病死。側近のエル・テムルが実権を握っており、権力者としては傀儡皇帝に過ぎなかった。一方、文化事業には熱心だった。死の間際に暗殺された兄コシラの子供を後継とするよう遺言した。 |
| 10月23日(至順3年10月 4日) | モンゴル帝国第14代皇帝で元の第10代皇帝にコシラの次男のリンチンバル(イリンジバル)が即位。叔父トク・テムルの遺言に、実質の最高権力者エル・テムルが消極的ながらも従ったため(エル・テムルはリンチンバルの弟のエル・テグスを擁立していた)。 |
| 12月14日(至順3年11月26日) | モンゴル帝国第14代皇帝で元の第10代皇帝のリンチンバル(イリンジバル)が急死。在位わずか43日。エル・テムルは改めてエル・テグスの擁立を図るも、皇太后のブダシリが反対し、コシラの長男トゴン・テムルを立てることになる。 |
| 1333年 | |
| 4月 9日(元弘3年閏2月24日) | 後醍醐天皇、隠岐の島を脱出。 |
| 5月(至順4年 4月) | モンゴル帝国の最高権力者として皇帝より力のあったエル・テムルが病死。キプチャク軍閥の出身。 |
| 6月19日(元弘3年 5月 7日) | 足利高氏が幕府に対して反旗を翻し、六波羅探題を攻撃。六波羅の南北両探題は脱出し、京都及び西国監視機関であった六波羅探題は崩壊。 |
| 6月20日(元弘3年 5月 8日) | 新田義貞が鎌倉に対し150騎あまりで挙兵。 |
| 6月21日(元弘3年 5月 9日) | 新田義貞の軍勢に足利尊氏の嫡男千寿王(後の足利義詮)が合流し、関東中の軍勢が参集し始める。 |
| 6月23日(元弘3年 5月11日) | 新田義貞率いる軍勢と鎌倉幕府軍が衝突。小手指原の戦い。新田軍が勝利する。 |
| 6月24日(元弘3年 5月12日) | 新田義貞率いる軍勢と鎌倉幕府軍が衝突。久米川の戦い。新田軍が勝利する。 |
| 6月27日(元弘3年 5月15日) | 翌16日にかけて新田義貞率いる軍勢と鎌倉幕府軍が衝突。分倍河原の戦い。一旦は鎌倉軍が勝利するも、新田軍が逆転勝利。 |
| 7月 4日(元弘3年 5月22日) | 新田義貞率いる軍勢が3方から鎌倉を攻める。赤橋守時、大仏貞直らが応戦し激戦となるが、義貞自ら潮が引いたところを稲村ヶ崎から回って市街地へ侵入。鎌倉市街は火災となり、北条基時、北条高時、北条貞顕ら北条一族283人と、長崎高重、安達時顕らを含む計870人が東勝寺で自刃し、鎌倉幕府は滅亡。北条高時の子のうち、北条時行は諏訪盛高の手で落ち延びるが、北条邦時は同行した五大院宗繁が裏切ったため捕らえられ処刑された。なお、稲村ヶ崎の海岸部は干潮でも海底は露出しないため、どうやって海を渡ったかについて詳細は不明(船で渡った、稲村ヶ崎ではなく極楽寺坂を突破したなどの説もある)。 |
| 7月 7日(元弘3年 5月25日) | 後醍醐天皇が、光厳天皇の即位と正慶の元号を無効と宣言。 |
| 7月17日(元弘3年 6月 5日) | 後醍醐天皇らが京に入る。事実上の建武の新政の開始。足利高氏を鎮守府将軍とする。 |
| 7月19日(至順4年 6月 8日) | モンゴル帝国15代皇帝・元の11代皇帝に、トゴン・テムルが即位。コシラの長男。 |
| 7月25日(元弘3年 6月13日) | 後醍醐天皇の皇子護良親王が征夷大将軍に補任される。足利高氏を警戒した護良親王は独自の軍事活動をしていて、後醍醐天皇との間には方針の違いなどから不和があり、一種の妥協案とされる。 |
| 9月14日(元弘3年 8月 5日) | 元弘の乱における論功行賞として叙位除目が行われる。足利高氏には「尊」の偏諱がおくられ、足利尊氏となる。 |
| 9月25日(元弘3年 8月16日) | 鎌倉幕府最後の将軍だった守邦親王が死去。死因は不明で、死去した場所は武蔵国比企郷とされるが詳細は不明。親王の位を与えられるも、その生涯はほぼ鎌倉在住で京に上ったこともなく、詳細な事歴もわかっていない。 |
| 10月19日(元弘3年 9月10日) | この頃までに雑訴決断所が設立されたとみられる。記録所から公家武家の所領などに関する訴訟関係を扱う部署として独立。 |
| 11月19日(元弘3年10月12日) | 後醍醐天皇の皇后であった西園寺禧子が病死。天皇が皇太子時代に知り合い、駆け落ち同然の事実婚の関係となったことを受けて皇太子妃として認められ、そのまま天皇の即位で皇后になった。そのため天皇の寵愛が深く、破格の待遇を受けた女性。死を受けて即日「後京極院」の院号が授けられる。 |
| 11月(元弘3年10月) | 護良親王が征夷大将軍から解任され、拘束される。敵対関係にあった足利尊氏の謀略とも言われるが、後醍醐天皇の不興も買っていたという。身柄は足利直義の元へ。 |
| 1334年 | |
| 1月17日(元弘3年12月11日) | 北条氏の一門名越時如と安達高景(異説あり)らが御内人の曽我道性のもとへ逃亡。陸奥大光寺城に籠城する。地元豪族らと交戦(大光寺合戦)。 |
| 1月30日(元弘3年12月24日) | 足利直義が、鎌倉府将軍となった成良親王を奉じて、いわゆる鎌倉将軍府が成立。 |
| 3月 5日(元弘4年 1月29日) | 建武に改元。後漢(東漢)王朝を開いた中国の名君光武帝の元号「建武」にあやかったとされる。 |
| 12月15日(元弘4年11月19日) | 大光寺城・石川城・持寄城などで繰り広げられた大光寺合戦が終結。名越時如らは降伏する。 |
| ポーランド王国を整備し発展させたカジミェシュ3世大王がユダヤ人を保護するカリシュの法令を改めて承認。 | |
| 1335年 | |
| 6月(正慶4年/建武2年 6月) | 西園寺公宗(元関東申次)と北条泰家(北条高時の同母弟)が、後醍醐天皇を暗殺して後伏見法皇(あるいは光厳上皇)を擁立するクーデターを企図するも、公宗の異母弟西園寺公重の密告で露見し、公宗は捕らえられ、泰家は逃走。 |
| 8月 3日(正慶4年/建武2年 7月14日) | 北条高時の遺児である北条時行が諏訪頼重らと信濃で挙兵し鎌倉へ向けて侵攻。足利直義、渋川義季などが鎮定のために兵を挙げる。中先代の乱。中先代とは、鎌倉の主として、先代(北条高時)、当代(後代:足利尊氏)の間に位置するため。 |
| 8月11日(正慶4年/建武2年 7月22日) | 女影原の戦い。北条時行軍が渋川義季軍を打ち破り、渋川義季、岩松経家らが敗死。 |
| 8月12日(正慶4年/建武2年 7月23日) | 北条時行軍が鎌倉に迫る中、足利直義は、鎌倉で幽閉していた護良親王を、淵辺義博に命じて殺害。殺害した理由は、北条時行と連携することを恐れたとするのが通説だが、倒幕に積極的だった護良親王が時行と組むのはおかしいため、足利氏とも敵対していたことや、単に足手まといが理由とする説もある。 |
| 8月14日(正慶4年/建武2年 7月25日) | 北条時行らが鎌倉を占拠する。 |
| 8月19日(正慶4年/建武2年 8月 1日) | 足利尊氏が北条時行討伐のための出兵と、征夷大将軍と総追補使の官職を求めたのに対し、後醍醐天皇は出兵を認可せず、成良親王を征夷大将軍とする。 |
| 8月20日(正慶4年/建武2年 8月 2日) | 足利尊氏が、後醍醐天皇の認可を得ないまま兵を率いて出立。後醍醐天皇は尊氏を征東将軍と追認。北条時行は応戦の準備を進めるが大嵐となり、兵が避難していた大仏殿が倒壊。多数の圧死者が出たという。 |
| 8月20日(正慶4年/建武2年 8月 2日) | 西園寺公宗が処刑される。 |
| 8月27日(正慶4年/建武2年 8月 9日) | 19日まで足利尊氏軍と北条時行軍が連戦。 |
| 9月 6日(正慶4年/建武2年 8月19日) | 足利尊氏軍が鎌倉まで侵攻し、諏訪頼重らが自刃。北条時行は落ち延び、後に後醍醐天皇の南朝方に帰順する。 |
| 1336年 | |
| 1月 2日(建武2年11月19日) | 建武の乱勃発。鎌倉に居続けて京への帰還を拒否し、新田義貞排除を訴えた足利尊氏に対し、後醍醐天皇が討伐を命じる。尊氏自身は恭順の意を示して出家引退を宣言するが、足利直義らが抗戦の姿勢を示す。 |
| 1月 8日(建武2年11月25日) | 矢作川の戦い。鎌倉へ向けて進攻する新田義貞に対し、高師泰、足利直義が矢作川付近で応戦するも敗北。 |
| 1月18日(建武2年12月 5日) | 手越河原の戦い。さらに鎌倉へ向けて進攻する新田義貞に対し、足利直義らが安倍川河口付近で応戦。激戦となるが足利方が敗北し鎌倉方面へ退却。新田軍は伊豆まで進攻。 |
| 1月24日(建武2年12月11日) | 箱根・竹ノ下の戦い。直義らの敗北をうけて、足利尊氏自ら出兵を決め、箱根まで進出。新田義貞軍と衝突。足利軍が勝利し、京へ向けて進軍する。 |
| 2月15日(建武3年 1月 3日) | 瀬田と宇治で足利軍と新田軍が衝突し、足利方が勝利。京への侵攻を開始。 |
| 2月23日(建武3年 1月11日) | 足利尊氏入京。 |
| 3月10日(建武3年 1月27日) | 糺河原の戦い。北畠顕家が軍勢を率いて京へ到着。比叡山を守る楠木正成・新田義貞の軍勢と合流して、鴨川三条河原近辺で足利方を攻撃。 |
| 3月13日(建武3年 1月30日) | 糺河原の戦い。北畠顕家・楠木正成・新田義貞の軍勢が勝利し、足利尊氏らは京を退去し丹波へ向かう。 |
| 3月23日(建武3年 2月10日) | 豊島河原の戦い。足利尊氏・直義らと、北畠顕家・楠木正成・新田義貞の軍勢が再度衝突し、尊氏ら大敗を喫して播磨室津へ退却。その後、赤松円心の進言で九州まで落ち延びる。豊島河原の場所は諸説ある。 |
| 4月 2日(建武3年 2月20日) | 足利尊氏ら九州に到着。九州の少弐頼尚、宗像氏範、大友氏泰ら北部九州の有力諸将が味方につく。この間、赤松円心らは播磨白旗城を中心に播磨各地で新田・楠木軍に抵抗して足止めを図る。円心はもともと護良親王派で楠木正成とも縁戚関係にあったが、恩賞で冷遇されたために足利尊氏に味方したとされる。 |
| 4月11日(建武3年/延元元年 2月29日) | 後醍醐天皇、年号を建武から延元に改元。足利方はこれを採用せず。改元した理由は庶民の間で不吉との声が上がったためと言われ、公家や寺社では建武の年号は好意的に受け止められており、改元に反対するものが続出している。また尊氏が改元に従わなかったのは、建武政権は自ら立てたという自負説や、政治的にはともかく心理的には尊氏は後醍醐帝を崇敬していたためとする説もある。 |
| 4月13日(建武3年/延元元年 3月 2日) | 多々良浜の戦い。足利尊氏、少弐頼尚ら兵2000に対し、後醍醐天皇方に付いた菊池武敏、阿蘇惟直ら九州諸勢力の兵2万が戦う。兵力差は10倍だったが、九州の諸豪族らは尊氏側に寝返るなどして、尊氏側が勝利。阿蘇惟直は戦死し、菊池武敏は敗走。 |
| 5月14日(建武3年/延元元年 4月 3日) | 足利尊氏、京に向かうため、博多を出発。 |
| 6月12日(建武3年/延元元年 5月 3日) | 足利尊氏、光厳上皇の使者として来た三宝院賢俊(日野賢俊)から院宣と錦旗を受け取る。 |
| 7月 4日(建武3年/延元元年 5月25日) | 湊川の戦い。東上してきた足利尊氏ら西国諸将の水陸軍と、楠木正成・新田義貞らの後醍醐天皇方諸軍が衝突。新田勢が後退したため、楠木勢は孤立し大敗。楠木正成・正季兄弟は自害。新田勢は立て直しを図るが大敗し退却した。建武政権に不満を持つ西日本の有力諸将の多くが足利方に付き、新田勢などからも離反が相次いだことと、水軍の有無が勝敗を決めたとされる。なお楠木正成はこれを予測し、新田義貞排除と足利尊氏との和睦を訴えていたと言われる。 |
| 7月22日(建武3年/延元元年 6月14日) | 足利尊氏、京に戻る。 |
| 7月23日(建武3年/延元元年 6月15日) | 光厳上皇、年号を延元から建武に戻す。 |
| 9月20日(建武3年/延元元年 8月15日) | 光明天皇が光厳上皇の院宣により即位。北朝の最初の天皇だが、兄の光厳天皇が後醍醐天皇によって即位していないことにされたため、光厳天皇を北朝初代と数え、光明天皇は2代目としている。光厳上皇が治天の君として院を開く。この時点では三種の神器がないままの即位だが、これは後鳥羽天皇が三種の神器がないまま、後白河法皇の院宣で即位した前例にならっている。 |
| 11月13日(建武3年/延元元年10月10日) | 後醍醐天皇、京に戻り、花山院に幽閉される。三種の神器が光明天皇側に移される。 |
| 12月10日(建武3年/延元元年11月 7日) | 足利尊氏、建武式目17条を制定。 |
| 1337年 | |
| 1月23日(建武3年/延元元年12月21日) | 後醍醐天皇が花山院を脱出。 |
| 1月30日(建武3年/延元元年12月28日) | 後醍醐天皇が吉野吉水院に行宮を定め、南北朝対立が始まる。 |
| 11月 1日 | ギュイエンヌをめぐる対立と、フランスの王位継承問題、スコットランド問題が絡んで、プランタジネット朝イングランド王エドワード3世が、ヴァロワ朝フランス王国フィリップ6世に対し宣戦を布告。百年戦争が始まる。 |
| 1338年 | |
| 1月14日(建武4年/延元2年12月23日) | 杉本城の戦い。北畠顕家、北条時行、新田義興の連合軍勢が鎌倉に攻め込み、応戦した足利家長は敗死。連合軍勢は鎌倉を占拠。 |
| 1月23日(建武5年/延元3年 1月 2日) | 北畠顕家、北条時行、新田義興の連合軍勢が京へ向けて鎌倉を出立。 |
| 2月10日(建武5年/延元3年 1月20日) | 青野原の戦い。北畠顕家、北条時行、新田義興の南朝軍と、土岐頼遠、高師冬ら北朝の軍勢が、墨俣川から青野原にかけて連戦。最終的に29日に青野原で南朝方が勝利するも兵を失ったのか、京への進軍をやめ、また越前の新田義貞との合流もせず、伊勢から伊賀経由で吉野へと転進。 |
| 6月10日(建武5年/延元3年 5月22日) | 石津の戦い。南朝方の北畠顕家と、北朝方の高師直・高師冬らが、和泉国堺浦・石津で衝突。北朝方が勝利し、北畠顕家・名和義高・南部師行らは戦死。北条時行は脱出し落ち延びる。 |
| 8月17日(暦応元年/延元3年閏7月 2日) | 藤島の戦い。新田義貞、脇屋義助兄弟は、平泉寺宗徒を率いて北朝方の斯波高経の拠点である越前黒丸城攻略に向かうが、延暦寺と係争中だった平泉寺は藤島荘の寺領安堵を条件に北朝方へ寝返り、藤島城に籠城。黒丸城を攻撃中だった新田義貞は藤島城攻めに向かうも、その途中で斯波高経の派遣した細川出羽守らと遭遇戦になり討ち死に。新田軍は総崩れとなって敗走した。 |
| 9月24日(暦応元年/延元3年 8月11日) | 足利尊氏、征夷大将軍となる。 |
| 1339年 | |
| 9月18日(暦応2年/延元4年 8月15日) | 後醍醐天皇が義良親王に譲位。後村上天皇(南朝2代目、歴代で97代目)。 |
| 9月19日(暦応2年/延元4年 8月16日) | 後醍醐天皇が崩御。 |
| 1340年 | |
| 6月24日 | 百年戦争スロイスの海戦。 |
| 7月26日 | 百年戦争サン・トメールの戦い。 |
| 1342年 | |
| 1月30日(暦応4年12月23日) | 足利直義と夢窓疎石が交渉し、天龍寺造営のための資金を集めるため、元へ天龍寺船を派遣することを決める。8月(康永元年)天龍寺船を元に派遣。 |
| 1345年 | |
| 9月25日(貞和元年8月29日) | 足利尊氏を開基とし、夢窓疎石を開山とする天龍寺が落慶供養。足利尊氏が、敵対した後醍醐天皇の供養のために、夢窓疎石の進言で創建したもので、落慶供養は後醍醐天皇の七回忌に合わせた。 |
| 10月21日 | 百年戦争オーブロッシェの戦い。 |
| この年、イスラムの旅行家イブン・バットゥータが元朝の都、大都を訪れる。 | |
| 1346年 | |
| 7月26日 | 百年戦争カーンの戦い。 |
| 8月26日 | 百年戦争クレシーの戦い。 |
| 10月17日 | 百年戦争ネヴィルズ・クロスの戦い。 |
| 1347年 | |
| 8月 3日 | 百年戦争中に起こったカレー包囲戦で、カレー住民がイングランドに降伏。この際、市民6人が、全市民の命を救うために処刑になるのを覚悟で自らイングランド王エドワード3世に出頭し、「カレーの市民」として有名になる。6人は最終的に許された。 |
| 10月 | シチリア島メッシーナに到着したコンスタンティノープルからの船でペストが上陸。以降、沿岸交易都市などへ徐々に広がっていく。年代は1346年説あり。 |
| 1348年 | |
| 2月 4日(正平3年/貞和4年 1月 5日) | 四條畷の戦い。南朝方の楠木正行と北朝方の高師直との間で行われた闘いで、楠木正行は敗死。高師直は勢いに乗って吉野まで攻め、後村上天皇らは賀名生にまで落ち延びる。 |
| 4月23日 | イングランド王エドワード3世がガーター騎士団を創設。 |
| 11月18日(正平3年/貞和4年10月27日) | 崇光天皇が即位。光厳天皇の子で、北朝の第3代天皇。 |
| ペスト禍がヨーロッパ全土へと拡大。1350年までにヨーロッパの人口の3分の1から3分の2(2000万から3000万人)が死亡し、農民の減少で荘園制が大きなダメージを受ける。また人手のかからない牧羊が盛んになったといわれる。また多数のユダヤ人がペストの原因だとして殺された。ペスト菌は非常に致死率が高く、感染力も高い。内出血で皮膚が黒くなるため、「黒死病」とも呼ばれた。酒で消毒するなど生活習慣の違いや、ネズミを捕食する肉食獣の存在から感染が広がらなかった地方もある。全世界では8500万人が死亡したとみられ、人類史上もっとも規模の大きかったパンデミックのひとつ。 | |
| 1350年 | |
| 8月29日 | 百年戦争ウィンチェルシーの海戦。 |
| 1351年 | |
| 3月 4日 | ラーマーティボーディー1世がアユタヤ王朝を興す。 |
| 10月14日(正平6年/観応2年 9月24日) | 観応の擾乱で、対立する足利尊氏と足利直義が、近江興福寺で和睦交渉を行うが決裂。 |
| 11月13日(正平6年/観応2年10月24日) | 観応の擾乱で、足利直義・直冬勢力に対し劣勢となった足利尊氏・義詮は、佐々木道誉らの提案を受け、南朝方に降伏する。これにより、南朝方の直義・直冬追討の綸旨を得る。いわゆる正平一統。 |
| 11月26日(正平6年/観応2年11月 7日) | 南朝方により崇光天皇が廃され、年号を正平に統一することとなる。 |
| 1352年 | |
| 1月10日(正平6年/観応2年12月23日) | 南朝方勢力が京へ進出し、三種の神器が引き渡される。ここで一旦南朝政権となる。 |
| 1月14日(正平6年/観応2年12月27日) | 駿河まで進出した足利尊氏勢と、足利直義勢が由比・蒲原付近で衝突。尊氏側が大勝する。一般には薩埵峠の戦いと言われる。 |
| 1月22日(正平7年/観応3年 1月 5日) | 足利尊氏が鎌倉に入り、足利直義は降伏。 |
| 3月12日(正平7年/観応3年 2月26日) | 足利直義が急死する。敵対した兄尊氏による毒殺説も。 |
| 4月 5日(正平7年/観応3年閏2月20日) | 観応の擾乱が終息する方向へ動き出したことから、南朝方の北畠親房は足利尊氏排除を決め、正平の一統を破棄。楠木正儀、北畠顕能らを京に侵攻させる。七条大宮の戦いで足利方の細川頼春が戦死し、足利義詮は近江へ脱出。南朝の後村上天皇は、行宮を賀名生から摂津住吉を経て、京に近い男山八幡へと移す。 |
| 4月 5日(正平7年/観応3年閏2月20日) | 新田義興、新田義宗、脇屋義治、北条時行らも鎌倉へ侵攻。新田義宗軍は敗れるが、新田義興、北条時行らは足利基氏を破って鎌倉を占拠。 |
| 4月13日(正平7年/観応3年閏2月28日) | 小手指原の戦い。足利尊氏が新田義宗ら南朝軍を破る。義宗は越後へ、宗良親王は信濃へ敗走。 |
| 4月16日(正平7年/観応3年 3月 2日) | 新田義興、北条時行ら、鎌倉を放棄。新田義興、新田義治は越後へ向かう。北条時行は鎌倉周辺に潜伏。 |
| 4月26日(正平7年/観応3年 3月12日) | 足利尊氏、鎌倉を再奪還。 |
| 4月29日(正平7年/観応3年 3月15日) | 足利義詮は近江で各地の有力守護の軍勢を集結、京へ侵攻し奪還する。更に男山八幡の行宮を包囲。 |
| 6月23日(正平7年/観応3年 5月11日) | 後村上天皇らが光厳・光明・崇光の北朝3上皇及び廃太子直仁を連れて男山八幡の行宮を脱出。 |
| 9月25日(正平7年/観応3年 8月17日) | 足利尊氏・義詮は、三種の神器がないまま、南朝方の拉致を免れた第3皇子弥仁親王を即位させる(後光厳天皇)。即位の名分は廷臣によって擁立された継体天皇に倣ったが、権威としては弱い立場にあった。治天の君として祖母の広義門院(西園寺寧子。光厳天皇・光明天皇の母親)がつく。皇族ではない上に女性で治天の君となった唯一の例。 |
| 1353年 | |
| 6月21日(文和2年 5月20日) | 北条高時の子で、中先代の乱で擁立され、その後は南朝方武将として各地を転戦した北条時行が鎌倉龍ノ口で処刑される。子孫は横井氏を名乗った(幕末の横井小楠(北条平四郎時存)など)。 |
| 1355年 | |
| (正平10年/文和4年) | 南朝方に拉致されていた北朝3上皇のうち光明上皇のみ京に戻される。 |
| 1356年 | |
| 9月19日 | 百年戦争ポアティエの戦い。 |
| (正平11年/延文元年10月) | 南朝方の菊池武光らが、侵攻してきた北朝方の一色範氏を打ち破る。 |
| 1357年 | |
| (正平12年/延文2年 2月) | 南朝方に拉致されていた北朝3上皇のうち残っていた光厳上皇と崇光上皇が京に戻される。この結果、北朝方の後光厳天皇と、戻った崇光上皇との間で、次の皇位継承に関する対立が起こる(後光厳天皇は緒仁親王を、崇光上皇は栄仁親王を推した)。皇位は緒仁親王が継ぐことになるが(後円融天皇)、のちに称光天皇のあとを崇光天皇のひ孫である後花園天皇が受け継ぎ、その弟貞常親王が伏見宮となるため、現在の皇室と、伏見宮家の血統である旧皇族11宮家は、すべて崇光天皇の系統となる。 |
| 1358年 | |
| 5月 | フランス北部で農民主体の反乱ジャックリーの乱が勃発。ギヨーム・カルルを指導者として各地へと拡大。 |
| 6月 | フランス王国軍によってジャックリーの乱が鎮圧される。 |
| (正平13年/延文3年)11月) | 南朝方の菊池武光らが、日向守護で独立勢力を保っていた畠山直顕を破り、豊後へと敗走させる。これにより、九州から北朝方の主な勢力は失われる。 |
| 1359年 | |
| 8月29日(正平14年/延文4年 8月 6日) | 筑後川の戦い。南朝征西府の懐良親王と菊池武光らが、侵攻してきた北朝方の少弐頼尚、大友氏時らと筑後川で対陣。この日激戦となり、南朝方が勝利。以後13年に渡り、九州は南朝方が席巻することとなる。 |
| 1360年 | |
| 4月21日(正平15年/延文5年 4月 6日) | 洞院公賢死去。最終官位は従一位太政大臣。有職故実の大家として歴代天皇の相談役となった。北朝の重臣だが、後醍醐天皇の側室阿野廉子(後村上天皇の母)の養父でもある。同時代の一級史料『園太暦』の著者。 |
| 1361年 | |
| 7月24日(正平16年/康安元年 6月22日) | 正平地震(康安地震)。京・大和で大きな地震がある。難波浦では大津波が襲い死者多数。雪が降ったという記録もある。 |
| 7月26日(正平16年/康安元年 6月24日) | 大きな地震があり、京・大和・摂津の各寺社の被害多数。 |
| 1362年 | |
| (正平16年/康安元年) 8月) | 長者原の戦い。九州探題斯波氏経が、大宰府を攻撃するが、菊池武義、菊池武光、城武顕らによって撃退される。 |
| 12月28日(正平22年/貞治6年12月 7日) | 幕府2代将軍足利義詮が病死。死の前に管領細川頼之に後事を頼み、幼少の足利義満が跡を継ぐこととなる。 |
| 1368年 | |
| (至正28年1月) | 朱元璋が、応天府で即位。明朝を建国。 |
| (正平23年/応安元年 2月) | 将軍足利義詮の死去の混乱をついて、南朝征西府の懐良親王、菊池武光らは、全九州の諸勢力7万騎を率いて、東征を計画。手始めに周防・長門への進出を図るが、大内弘世に敗れ、早々に挫折することとなる。 |
| 9月10日(至正28年閏7月28日) | 明の軍勢が大都に迫り、元朝の第11代皇帝(モンゴルの第15代皇帝)トゴン・テムル(恵宗)は大都を放棄して北走する。明は大都を北平府と改称。一般的には、これをもって元朝は滅亡したとするが、モンゴルはその後も中国の北方からモンゴル高原、西域にかけて大きな勢力を維持したため(北元ともいう)、厳密には滅んではいない。なお北京は、首都が置かれているときは北京だが、そうでないときは北平と呼ばれる。 |
| 1370年 | |
| 5月23日(至正30年4月28日) | 元朝の第11代皇帝トゴン・テムル(恵宗)が落ち延びた先の応昌府で崩御。明朝からは天命を失い、明に譲ったという皮肉を込めた意味で順帝の諡号を贈られた。子のアユルシリダラが即位するが、直後に明軍の遠征によって応昌府も陥落。 |
| 1371年 | |
| 4月 9日(応安4年 3月23日) | 緒仁親王が即位(後円融天皇)。崇光上皇は自身の子である栄仁親王を即位させようと図ったが、幕府管領細川頼之らが後光厳天皇側についたため、後光厳天皇の子である緒仁親王の即位が決まった。 |
| (洪武4年) | 明が、四川の大夏を攻め、2代皇帝明昇が降伏して、大夏は滅亡。 |
| 1372年 | |
| 9月 9日(文中元年/応安5年 8月12日) | 今川了俊率いる北朝方が、大宰府を攻め落とし、南朝征西府の懐良親王、菊池武光らは、高良山へと撤退。征西府は事実上崩壊。 |
| 1373年 | |
| 9月12日(文中2年/応安6年 8月25日) | 婆沙羅大名として知られた佐々木道誉(高氏)が死去。 |
| 12月29日(文中2年/応安6年11月16日) | 南朝方の有力武将として九州を席巻した菊池武光が死去。 |
| 1375年 | |
| 9月22日(永和元年/天授元年 8月26日) | 水島の変。北朝方の今川了俊が九州探題になって以降、勢力を拡大したため、同じ北朝方だった少弐冬資と対立。了俊は肥後の南朝方に対抗するため、九州の有力守護である島津氏久、大友親世、少弐冬資を肥後水島に呼ぶが、少弐冬資のみ応じなかったため、島津氏久を介して来援を求める。しかし現れた少弐冬資を宴席で暗殺に及んだ。この事件を受けて島津氏は反発し、北朝方から離脱。大友親世も協力しなくなる。少弐氏は少弐頼澄があとを継ぎ、南朝方に転じる。 |
| 9月25日(永和元年/天授元年 8月29日) | 水島の変を受けて、南朝方の菊池武朝が菊池武義らとともに筑後で蜂起し、今川方が大敗する。 |
| マムルーク朝によってアナトリア南岸にあったキリキア・アルメニア王国が滅亡する。国王レヴォン6世らは捕虜になった後出国。 | |
| 1376年 | |
| この頃、カネム帝国は、内紛と周辺諸国からの攻撃により、王都ンジミから、チャド湖西岸のボルヌへと中心を移す。ボルヌ帝国とも呼ばれる。 | |
| 1377年 | |
| 2月21日(永和3年/天授3年 1月13日) | 肥前蜷打の戦い。水島の変以降、勢いを盛り返した九州の南朝方勢力だったが、九州探題今川了俊が、大友親世・大内義弘の協力を取り付けることに成功し反撃。南朝方は大敗し、菊池武義、阿蘇惟武などが討ち死に。阿蘇氏はこれ以降内紛状態となり、菊池氏も肥後まで撤退。 |
| 1378年 | |
| 4月 7日(天授4年/永和4年 3月10日) | 足利将軍家の邸宅として造営された花の御所(室町第)に幕府が置かれる。いわゆる「室町幕府」の語源。 |
| 9月20日 | カトリック教会大分裂(大シスマ)。ローマ教皇ウルバヌス6世に反発したフランス人枢機卿らが、ロベール・ド・ジュネーヴを教皇(クレメンス7世)に選出し、カトリックの教皇がローマとアヴィニョンに分裂並立する。 |
| フィレンツェ共和国で、下層梳毛工らが反乱を起こす。チョンピの乱(~1382年)。 | |
| 1379年 | |
| 4月 7日(天授5年/康暦元年閏4月14日) | 康暦の政変。管領細川頼之が、対立した守護や宗教勢力の圧力を受けて失脚。足利義満が権力を強めるために画策したとも言われる。 |
| 1380年 | |
| 2月12日(洪武13年 1月 6日) | 明の洪武帝によって、建国の功臣である胡惟庸が処刑される。洪武帝の軍師だった劉基と対立したことや、敵対した勢力に対する弾圧などを行ったことから、洪武帝の猜疑心が強まり、「北元や日本と通じた」として粛清された。胡惟庸の一派もことごとく処刑されたため、胡惟庸の獄と呼ばれる。ただ、洪武帝の権力強化や海禁政策のための口実で処刑されたという見方もある。 |
| 1381年 | |
| 5月30日 | イングランドで農民らが反乱。農民ワット・タイラー、ジョン・ボール神父らを指導者とし、カンタベリー、ついでロンドンに侵攻。国王リチャード2世と会見。 |
| 6月15日 | ワット・タイラー、国王リチャード2世との2度めの会見のさなかに、同席していたロンドン市長ウィリアム・ウォールワースによって殺害される。反乱も終息。 |
| 7月15日 | ワット・タイラーの乱の指導者の一人ジョン・ボール神父が処刑される。 |
| (洪武14年) | 明が、雲南を平定して、中国を統一。 |
| (洪武14年) | 明の初代皇帝朱元璋(洪武帝)が、「文字の獄」を引き起こし知識層を弾圧。知識層が文書などに「光」などの文字を使っただけで「皇帝をそしっている」と難癖をつけて処罰した。出自の身分が低かったために、過剰反応したものと思われる。 |
| 1382年 | |
| 5月24日(永徳2年 4月11日) | 後円融天皇が幹仁親王に譲位(後小松天皇)して、院政を開始。3代将軍足利義満の支持を得ての譲位となったが、この後、権力を持つ義満と上皇との関係は悪化の一途をたどり、即位礼すらなかなか進まず、結局後円融上皇の参列のないまま即位礼が行われる。 |
| (洪武15年) | 明の洪武帝によって「空印の案」の粛清事件が起きる。中央への収支報告書の煩瑣な手続きをなくすため、あらかじめ印を押しておいた書類を用意して記載する慣習が行われていることに洪武帝が激怒し、各地の地方長官と印の管理者を処刑した事件。 |
| 1383年 | |
| 3月19日(永徳3年 2月15日) | 後円融上皇が自殺未遂騒動を起こす。絶大な権力者足利義満に対する反発からか、妻妾と義満の密通を疑うなどして騒ぎ、義満と、もうひとりの実力者の二条良基が、上皇と近い公家を派遣して応対しようとしたところ、自分を配流すると疑って自殺を図ろうとした。 |
| 1385年 | |
| 4月 7日(洪武18年2月27日) | 明の洪武帝の側近で、明朝建国に多大な功績のあった徐達が死去。右丞相・魏国公にまでのぼったが、あまりに功績が大きすぎたのと、地位に奢ることのなかった性格から人望が厚く、猜疑心の強くなった洪武帝に疎まれるようになっていたと言う。そのため、病死説のほかに暗殺説もある。 |
| 1386年 | |
| かねて同盟関係にあったイングランドとポルトガルの間でウィンザー条約が結ばれる。現存最古の二国間同盟条約。 | |
| 1388年 | |
| 7月16日(嘉慶2年/元中5年 6月13日) | 二条良基死去。何度も失脚しながらも復活し、摂政・関白・太政大臣を歴任して、武家の足利義満とともに朝廷で絶大な権力を握った人物。「菟玖波集」を編纂して連歌を大成させ、能を保護して世阿弥を後援するなど文化人でもあった。『増鏡』の作者の可能性がある。 |
| 9月 2日(嘉慶2年/元中5年 8月 2日) | 三代将軍足利義満が、紀伊国和歌浦玉津島神社参詣のため京を出発する。 |
| 9月 8日(嘉慶2年/元中5年 8月 8日) | 三代将軍足利義満が、紀伊国和歌浦玉津島神社を参詣し、帰京の途に就く。 |
| 9月17日(嘉慶2年/元中5年 8月17日) | 平尾合戦。南朝方の武将楠木正勝が、足利義満の動向を聞いて奇襲を企て、花山院長親とともに兵1000を率いて出陣。しかし赤坂城にいた北朝方の山名氏清は情報を掴み、兵3500で河内国平尾に先回りした。正勝は攻勢に出たが氏清は守りを固めて疲弊を待ち反撃したため、南朝方は大敗。正勝は千早城へ退却できたが、南朝方はほぼ戦力を失い南北朝合一の遠因となった。 |
| 1389年 | |
| 6月15日 | コソボの戦い。セルビア、ボスニア、ワラキアなどバルカン諸侯軍と、オスマン帝国軍が会戦し、オスマン軍が大勝。オスマン帝国のバルカン半島征服のきっかけとなる。 |
| 1390年 | |
| 閏3月(明徳元年/元中7年4月) | 土岐康行の乱。将軍足利義満が任命した尾張守護を巡って起こった土岐氏の内紛から起きた反乱。敗北した土岐康行は美濃・伊勢の守護職を失い一時没落する(明徳の乱での功績で伊勢北半国守護に復帰)。 |
| 1392年 | |
| 1月13日(明徳2年/元中8年12月19日) | 明徳の乱。11カ国を守護領有した「六分一殿」山名氏が、将軍足利義満と対立し挙兵。京・内野で戦闘となるが、1日で山名氏は大敗し、3カ国にまで減らされる。 |
| 2月(明徳3年/元中9年 1月) | 南朝方の千早城が北朝方の畠山基国に攻め落とされる。城主の楠木正勝は大和へ落ち延びた。 |
| 11月12日(明徳3年/元中9年10月27日) | 明徳の和約。北朝(持明院統)と南朝(大覚寺統)の皇位継承で合一が決まる。元々は将軍足利義満と、南朝総大将ながら一時北朝に属した経験のある和平派の楠木正儀との間で協議が行われ、その後を、北朝からは義満側近の神祇官吉田兼煕、南朝からは前内大臣阿野実為と、右大臣吉田宗房が交渉を受け継いだ。南朝の強硬派だった長慶天皇から穏健派の後亀山天皇に代わり、一気に交渉が進んだと見られる。南朝が北朝に「譲国」し、国衙領は大覚寺統に、長講堂領は持明院統に与えられ、後亀山天皇は京都へ戻り、皇位は北朝の後小松天皇がそのまま引き継いで、以降は両統迭立とするという内容だった。 |
| 11月19日(明徳3年閏10月5日) | 後亀山天皇が入った大覚寺から、後小松天皇のいる土御門内裏へ三種の神器が移される。南朝の終了に伴い、南朝が使用した年号も廃止される。 |
| 1393年 | |
| 3月27日 | 権知高麗国事として事実上高麗国の王となっていた李成桂が正式に朝鮮王となる。李氏朝鮮の初代国王。なお出自は全州李氏とされているが、李成桂以前の歴代の記録が曖昧なため、女真族、モンゴル族という説もある。 |
| 明の洪武帝によって、大将軍・涼国公の藍玉が粛清され、一族や関係者ら最大3万人が連座する。藍玉が大きな権力を持ったことと、傲慢な振る舞いが目立ったことが要因。 | |
| 1394年 | |
| 4月 7日(明徳5年 3月 7日) | 梶山城の戦い。九州探題今川了俊と対立する島津氏討伐のため、了俊とその指揮下の肥後相良氏、日向伊東氏・北原氏・土持氏が島津方の和田正覚が籠もる梶山城を攻撃。島津氏と一族の北郷氏が応戦するが、北郷久秀らが討ち死にし、梶山城は陥落。 |
| 1395年 | |
| 1月 8日(応永元年12月17日) | 足利義満が、9歳の子、足利義持を元服させ将軍位を譲る。 |
| ルケニ・ルア・ニミがコンゴ一帯を統一し、コンゴ王国を成立させる。 | |
| 1396年 | |
| 9月25日 | ニコポリスの戦い。オスマン帝国と、ハンガリーを中心としてフランス、イングランド、スコットランド、ワラキア、スイス同盟、ポーランド、神聖ローマ帝国、ジェノヴァ、ヴェネチアの諸国連合軍が衝突し、オスマン帝国が圧勝する。 |
| 1398年 | |
| この頃、スコットランドとノルウェーの貴族であるオークニー伯ヘンリー・シンクレアが、グリーンランドと北アメリカを探検したという伝承がある。1400年ころにヴェネツィアのゼノ兄弟によって書かれたとされる手紙と北大西洋を描いたゼノマップ(1558年の書物に出てくる)に登場する人物ジクムニ王子に比定されているが史実の信憑性は低い。 | |
| 1400年 | |
| 1月17日(応永6年12月21日) | 応永の乱が終結。最大の守護大名、大内義弘と鎌倉公方による幕府への反乱。義弘は戦死するが、大内氏は滅亡せず、弟らが反乱し続けた結果、幕府が譲歩し守護大名に復帰する。 |
| 1(応永7年7月) | 信濃守護の小笠原長秀が京から下向し、信濃支配を強めようとしたため、善光寺平で、村上氏・海野氏・高梨氏・井上氏など中小国人領主の連合軍と合戦となり、小笠原長秀は敗北して京へ逃げ帰る。大塔合戦。 |
| 1402年 | |
| 7月20日 | アンカラの戦い。バヤズィト1世率いるオスマン帝国軍と、ティムール率いる各国連合軍との会戦。退却中にバヤズィトが捕虜となりオスマン帝国は大敗。 |
| 1404年 | |
| 李氏朝鮮、済州島の耽羅王朝王族が称していた各種称号を廃止。事実上の耽羅国の滅亡。 | |
| 1405年 | |
| 2月18日 | ティムール帝国を築いたティムールが明への遠征の途上で病死。死後ティムール王朝は分裂。 |
| 7月11日(永楽3年6月15日) | 明の時代の武将で宦官の鄭和、第1次航海へ出発。 |
| 1407年 | |
| 明の鄭和艦隊、インドのカリカットに到着。同年帰国後、すぐに2回目の航海に出発。 | |
| 1408年 | |
| 3月21日(応永15年2月24日) | 那須岳が噴火。以後2年にわたって活発に活動する。溶岩流出、火砕流、泥流などを繰り返し、180人余りが死亡。 |
| 1409年 | |
| 3月25日 | ピサ教会会議でローマとアヴィニョンの枢機卿が集結し、全会一致でアレクサンデル5世の選出を決めるも、二人の教皇が了承せず、教皇が3人鼎立する異常事態となる。 |
| 明の鄭和艦隊、セイロンに到着。同年帰国後、すぐに3回目の航海に出発。 | |
| 1411年 | |
| 明の鄭和艦隊、インドやシャムなどをまわり帰国。 | |
| 1412年 | |
| 1月 6日 | ジャンヌ・ダルクがフランスのロレーヌ地方にあるドンレミ村の農家に生まれる。 |
| 1413年 | |
| 明の鄭和艦隊、4回目の航海に出発。 | |
| (応永20年) | 薩摩島津氏の一族伊集院頼久が、かねて島津家家督相続の問題で対立していた守護島津久豊の留守中に居城清水城を奪う。伊集院頼久の乱のはじまり。 |
| 1414年 | |
| 11月 1日 | 神聖ローマ皇帝ジギスムントの提唱により、コンスタンツ公会議がはじまり、3人の教皇が立つ教会大分裂の解消や、宗教改革運動などが議題となる。カトリックを批判したジョン・ウィクリフの著書が禁止され、ヤン・フスの処刑が決まる。 |
| 1415年 | |
| 7月 6日 | 宗教改革を訴えたヤン・フスが火刑に処せられる。 |
| 明の鄭和艦隊、東南アジア、インド、セイロン、中東各地や東アフリカをまわり帰国。 | |
| 1416年 | |
| 10月22日(応永23年10月2日) | 上杉禅秀の乱勃発。鎌倉公方足利持氏に対し、関東管領職を追われた上杉氏憲(禅秀)が一族や縁者らを集めて起こした反乱。 |
| 明の鄭和艦隊、5回目の航海に出発。 | |
| 1417年 | |
| 1月18日(応永24年 1月 1日) | 上杉氏憲らが足利持氏側に付いた江戸氏、豊島氏の勢力を世谷原の戦いで破るも、この隙に駿河より今川軍が侵攻してきたため鎌倉へ退却。 |
| 1月27日(応永24年 1月10日) | 上杉氏憲らが自刃して上杉禅秀の乱が終息。しかしこの乱に関わったとして中央でも政変が相次ぐことに。 |
| 11月11日 | ローマ教皇マルティヌス5世が選出され、教会分裂が収束する。 |
| (応永24年) | 数年に渡り争っていた島津久豊と伊集院頼久が、久豊が後妻に頼久の娘を娶り、頼久は家督を息子に譲って隠居することで和解し、伊集院頼久の乱が終結。 |
| 1418年 | |
| 5月(応永25年4月) | 上杉禅秀の乱後の影響を恐れた上総の武士らが一揆を起こす。上総本一揆。 |
| 7月 2日(応永25年 5月28日) | 平三城が陥落して上総本一揆が一旦終息。 |
| 1419年 | |
| 3月29日(応永26年 3月 3日) | 上総本一揆が再燃し、坂本城で戦闘が繰り広げられる。 |
| 5月30日(応永26年 5月 6日) | 上総本一揆の指導者埴谷重氏らが降伏し一揆は終結。 |
| 5月31日(応永26年 5月 7日) | 倭寇の集団が朝鮮庇仁県などを襲撃。 |
| 7月12日(応永26年 6月20日) | 李氏朝鮮の軍隊が対馬に侵攻。倭寇の拠点とみなされたため。 |
| 7月18日(応永26年 6月26日) | 対馬糠岳の戦い。 |
| 7月19日(応永26年 6月27日) | 李氏朝鮮の軍隊が退却を開始。朝鮮側の記録では宗貞盛が修好を求めたことと暴風の季節になったためとしているが、少弐満貞の記録では前日の糠岳での戦いで朝鮮側に大きな被害が出たためとしている。 |
| 7月30日 | 第一次プラハ窓外投擲事件。ボヘミアで宗教改革を訴えたフス派がカトリックや国王の態度に腹を立て、市庁舎を襲い、市長らを窓の外に放り投げて殺害する。 |
| 8月16日 | プラハ窓外投擲事件を聞いてショックを受けたボヘミア王ヴァーツラフ4世が死亡する。 |
| 明の鄭和艦隊、東南アジア、インド、セイロン、中東各地や東アフリカをまわり帰国。 | |
| 1421年 | |
| 明の鄭和艦隊、6回目の航海に出発。 | |
| 1422年 | |
| 明の鄭和艦隊、アラビア半島、東アフリカを回って帰国。 | |
| この年、小栗満重の乱が勃発。常陸の豪族小栗満重が、対立関係にあった鎌倉公方足利持氏に対し、宇都宮持綱らと反乱を起こす。 | |
| 1423年 | |
| この年、鎌倉公方足利持氏によって小栗満重の乱が鎮圧される。小栗満重は自刃したとも、三河に落ち延びたとも言われる。浄瑠璃や歌舞伎などの演目として知られる「小栗判官と照手姫」のモデルとなった事件。 | |
| 1425年 | |
| ジャンヌ・ダルクが、聖女カトリーヌ、マルグリット、大天使ミカエルの、「オルレアンの包囲を解いてフランスを救うように」という「声」を聞き、王太子シャルルの元へ向かう。 | |
| 1426年 | |
| 6月27日(洪熙元年 6月12日) | 明朝の第5代皇帝として朱瞻基が即位(宣宗・宣徳帝)。 |
| 10月 6日(宣徳元年 9月 6日) | 明朝の第5代皇帝宣徳帝の即位に反対し、自ら帝位につこうとクーデターを起こした朱高煦(宣徳帝の叔父)が捕らえられ処刑される。面会の場で温情を施そうとした皇帝を足蹴にしたため、巨大な銅釜に閉じ込められて火をかけられ、蒸し焼きにされたという。 |
| 1427年 | |
| 12月 1日(応永34年11月13日) | 将軍足利義持の側近だった赤松持貞が自害に追い込まれる。義持が播磨の有力者赤松満祐の3カ国守護職継承を認めず、側近の持貞に与えようとしたことで、反発した満祐が播磨に戻って反乱を画策。管領畠山満家らは、事態収拾のため、持貞が義持の側室と密通したという告発を、3代将軍足利義満の側室で義持の相談役だった「高橋殿」の密書という形で行い、義持は持貞に自害を命じた。 |
| 1428年 | |
| 9月(正長2年 8月) | 正長の土一揆が起こる。徳政などを求めた記録上最初の大規模農民一揆。 |
| 1429年 | |
| 6月12日 | ジャンヌ・ダルク率いるフランス軍がジャルジョーを占領し、イギリス軍司令官サフォーク伯を捕らえる。 |
| 6月18日 | パテーの戦いで、リッシュモン大元帥、ジャンヌ・ダルク、アランソン公らの率いるフランス軍が、シュルーズベリー伯ジョン・タルボットとジョン・ファストルフの率いるイングランド軍に大勝利を収める。 |
| 7月17日 | シャルル王太子がノートルダム大聖堂で戴冠式を挙げ、正式にフランス国王シャルル7世となる。 |
| 8月15日(正長2年 7月15日) | 大和永享の乱勃発。大和で豊田氏と井戸氏が紛争を起こし、これに長年対立している越智氏と筒井氏がそれぞれに加勢。興福寺や幕府を巻き込む戦乱に発展。 |
| 1430年 | |
| 5月23日 | ジャンヌ・ダルクがコンピエーニュの戦いでフィリップ善良公の率いるブルゴーニュ軍に捕えられる。 |
| 12月24日 | ジャンヌ・ダルクがイングランド軍に引き渡され、ルーアンのブーヴルイユ城に監禁される。 |
| 明の鄭和艦隊、7回目の航海に出発。 | |
| 1431年 | |
| 2月21日 | フランスのルーアンにおいて、イングランドの影響下でジャンヌ・ダルクの異端審問裁判が始まる。 |
| 5月24日 | ジャンヌ・ダルクにサン=トゥアン修道院の仮設法廷で死刑判決が言い渡される。一旦は改宗を条件に永牢に減刑されるが、ジャンヌが牢内で男装したとして、異端再犯として死刑が確定する。 |
| 5月30日 | ジャンヌ・ダルクが火刑に処される。 |
| 1432年 | |
| 5月 6日 | フランドル派を代表する祭壇画である『ヘントの祭壇画』が公開される。 |
| 1433年 | |
| 10月28日(永享5年9月16日) | 永享大地震。関東から近畿にかけて大きな地震が発生。特に鎌倉で被害甚大。利根川が逆流したという記録があり津波があったとみられる。相模トラフを震源とするマグニチュード7以上の地震か。 |
| 明の鄭和艦隊、インド、セイロン、マラッカなどをまわり帰国。鄭和は間もなく死去。記録では鄭和艦隊の最大の船は全長137m、幅56m、重量8000t、9本マストの巨大なジャンクだったという。 | |
| 1435年 | |
| (永享7年) | この頃、窪八幡神社別当上之坊普賢寺の『王代記』に、富士山中腹で火炎を観測したという記録がある。若干の溶岩流出を伴う噴火があったものか。 |
| 1437年 | |
| 6月25日(永享9年 5月22日) | 大和永享の乱で、越智維通と斯波持有ら幕府方が合戦となる。決着つかず。 |
| 8月12日(永享9年 7月11日) | 足利義教の弟で対立関係にあった大覚寺義昭が大覚寺を出奔。大和吉野へ向かったという風聞が広まる。 |
| 1438年 | |
| 7月(永享10年 6月) | 関東公方・足利持氏が、不和となっていた関東管領上杉憲実の諫言を無視して、将軍の許しを得ずに嫡男賢王丸の元服を鶴ヶ岡八幡宮で行い、八幡太郎義久と名乗らせる。永享の乱の始まり。 |
| 8月(永享10年 8月) | 上杉憲実、上野平井城へ逃れる。足利持氏、討伐軍を派遣。将軍足利義教は持氏討伐を命じる。 |
| 9月(永享10年 9月) | 大和吉野で大覚寺関係者などが討伐される。大覚寺義昭が関与していたかは不明。 |
| 10月16日(永享10年 9月27日) | 幕府軍の今川範忠、上杉持房らが持氏方の軍勢を破り、鎌倉に迫る。 |
| 10月22日(永享10年10月 4日) | 上杉憲実、上野平井城を出陣。持氏を攻めることをよしとしなかったため、家宰の長尾忠政が兵を率いて鎌倉へ向かう。 |
| 11月21日(永享10年11月 4日) | 足利持氏、称名寺に入り出家。将軍足利義教は、上杉憲実の持氏助命嘆願に対し、討伐を命じる。 |
| 1439年 | |
| 3月24日(永享11年 2月10日) | 足利持氏、上杉憲実の軍に攻められ、永安寺で自刃。 |
| 4月(永享11年 3月) | 越智維通が討ち死にし、大和永享の乱は終息。 |
| 1440年 | |
| 4月(永享12年 3月) | 結城合戦が勃発。永享の乱で滅ぼされた足利持氏に代わり、将軍足利義教は自らの子息を鎌倉公方にしようとしたため、結城氏朝・持朝らが持氏の遺児を擁して起こした反乱。 |
| 6月14日(永享12年 5月15日) | 4カ国の守護を兼ねた有力者一色義貫が、大和永享の乱の関係者を匿ったという嫌疑で、将軍義教の命を受けた武田信栄に攻められ、大和信貴山で一族とともに自害。 |
| 6月15日(永享12年 5月16日) | 伊勢の守護だった土岐持頼が、大和永享の乱の越智氏討伐の出兵中に、将軍義教の命を受けた長野満藤らによって攻められ自害。将軍義教が一色義貫、土岐持頼を滅ぼしたのは、その勢力を警戒したからとも言われるが、これにより赤松満祐の不信を招き、「嘉吉の乱」の遠因となった。 |
| 7月23日(永享12年 6月24日) | 結城氏朝・持朝らに呼応した東北諸将が篠川御所を襲撃し、篠川公方足利満直を滅ぼす。 |
| 8月26日(永享12年 7月29日) | 上杉清方や今川範忠らの率いる幕府軍が結城城を包囲攻撃。結城氏朝・持朝は滅亡、持氏の遺児春王丸、安王丸は捕らえられる。 |
| 1441年 | |
| 4月 4日(嘉吉元年 3月13日) | 日向国串間に潜伏していた大覚寺義昭が、将軍義教の命を受けた島津忠国配下の山田忠尚・新納忠臣らに包囲され自刃。 |
| 6月 5日(嘉吉元年 5月16日) | 足利持氏の遺児春王丸、安王丸が、将軍足利義教の命を受けた長尾実景によって美濃国垂井宿金蓮寺で処刑される。 |
| 7月12日(嘉吉元年 6月24日) | 嘉吉の乱が起こる。播磨の有力守護大名赤松満祐が、京の自邸に結城合戦勝利の祝いと称して6代将軍足利義教を招待し、その宴席上で殺害。招待されていた守護大名山名熙貴も殺害、京極高数と大内持世も重症を負い、後死亡。細川持春も重症を負い、正親町三条実雅も負傷した。大名への圧力を強める将軍と対立したことが原因。伏見宮貞成親王の『看聞日記』には将軍が満祐を殺そうとして返り討ちにあったとある。 |
| 7月28日(嘉吉元年 7月11日) | 赤松満祐討伐の大手軍が出発。 |
| 8月17日(嘉吉元年 8月 1日) | 細川持之の要請で、赤松満祐討伐の綸旨が出される。 |
| 9月25日(嘉吉元年 9月10日) | 討伐軍に包囲された播磨城山城で、赤松満祐らが自刃し嘉吉の乱が終結。 |
| 1443年 | |
| 1月11日 | フランスの傭兵司令官ラ・イルが戦傷がもとで死去。本名エティエンヌ・ド・ヴィニョル。ジャンヌ・ダルクの戦友として知られ、トランプのハートの従者(ジャック)のデザインの元ネタになった人物。 |
| 9月(嘉吉3年) | 禁闕の変。後南朝の皇族を称する金蔵主、通蔵主、源尊秀らと有力公卿の日野有光・日野資親らが京の宮中を襲い、天叢雲剣と神璽(八尺瓊勾玉)を奪い、比叡山へ逃亡。しかし幕府の軍事介入を嫌った比叡山側に討伐され、剣は奪還したが神璽は持ち去られる。金蔵主、日野有光、楠木正威らは討ち死に、通蔵主は謀殺され、日野資親は処刑、源尊秀は行方知れずとなった。 |
| 1446年 | |
| 10月 9日(世宗28年 9月10日) | 李氏朝鮮第4代国王の世宗が朝鮮独自の文字としてハングルを発表する。 |
| 1447年 | |
| 4月(文安4年 3月) | 足利持氏の遺児である足利成氏が鎌倉公方に任じられる。関東諸将の要請によるものと言われる。なお年月には宝徳元年(1449年)説など異説あり。 |
| 1449年 | |
| 9月 8日 | 土木の変。オイラトの首長でモンゴル高原を統一したエセンが、朝貢貿易が減額されたことと明の皇女の降嫁が守られなかったことを不服として明に侵攻。明の皇帝英宗(正統帝)は、宦官の王振が主張する「親征」を認め、自ら50万の軍勢で北京を出撃(司令官は王振)。しかしオイラトが長城を突破し大同まで侵攻したため、明軍は撤退を決めるが、オイラトの軍勢に追いつかれて土木堡でほぼ全滅するという大敗を喫する。英宗もオイラトに捕らえられた(王振は護衛将軍の樊忠に暗殺された)。 |
| 10月 | エセンは英宗の身代金と朝貢貿易の復活を要求するが、兵部尚書于謙・吏部尚書王文らは英宗の弟の郕王朱祁鈺(景泰帝)を即位させて拒否。エセンは北京に侵攻するが、明側は北京に籠城して時間を稼ぎ、エセン以外の部族と交渉。エセンは大勝したにも関わらず、戦略的に行き詰まり、やむなく撤退した。 |
| 11月10日 | シャルル7世はイングランド軍を破ってルーアンに入城。 |
| 1450年 | |
| 1月28日 | イングランド王ヘンリー6世の側近である初代サフォーク公ウィリアム・ド・ラ・ポールが逮捕される。大陸領を割譲する方向でフランスとの講和を模索していたが、その反発に加え、一連の敗戦により権威が失墜し失脚した。 |
| 2月15日 | シャルル7世がジャンヌ・ダルク異端裁判の調査を命じる。 |
| 5月 2日 | 国外追放刑に処せられたサフォーク公ウィリアム・ド・ラ・ポールがフランス行の船中で暗殺される。どの勢力による事件かは不明。 |
| 6月 1日 | イングランドでジャック・ケイドの反乱が起きる。サフォーク公暗殺事件後の政界の混乱に巻き込まれたケント地方の農民らが、政治改革を要求して起こした反乱。指導者ジャック・ケイドから。 |
| 6月18日 | ジャック・ケイドの反乱で、国王ヘンリー6世の軍と反乱軍が衝突。反乱軍が勝利し、ロンドンへ侵攻。 |
| 7月12日 | 国王軍の反撃に敗れたジャック・ケイドが逃走中に戦傷がもとで死亡。恩赦が出たこともあり、反乱軍は瓦解。 |
| 1451年 | |
| 琉球王国の那覇の港に浮かぶ浮島と陸地とを結ぶ全長1kmほどの堤防と7つの石橋からなる「浮道」が建設される。のちに中国の冊封使とともに琉球を訪れた胡靖が「長虹の如し」と評したことから、長虹堤と呼ばれるようになった。 | |
| 1452年 | |
| 翌年にかけて現在のバヌアツ・シェパード諸島にある海底火山クワエが大噴火を起こす。火山爆発指数はVEI6とかなり大規模で、これが原因と見られる寒冷現象が、北欧や中国などで記録される。穀物生産に影響があったという。 | |
| 1453年 | |
| 5月29日 | コンスタンティノポリスがオスマンの君主メフメト2世によって陥落し、東ローマ帝国は滅亡。 |
| 10月19日 | 百年戦争でイングランド軍最後の拠点であったボルドーが陥落。事実上イングランドが敗北。 |
| ポーランド王国のカジミェシュ4世王がユダヤ人の法的保護を定めたカリシュの法令を改めて承認する。 | |
| 琉球王国で、王位継承権に伴う志魯・布里の乱が勃発。5代王尚金福の世子である志魯と、尚金福の弟である布里が争い首里城も焼失した。両者とも死亡し、王位は布里の弟の尚泰久が継いだ。 | |
| 1455年 | |
| 1月15日(享徳3年12月27日) | 鎌倉公方足利成氏が、関東管領上杉憲忠を殺害。以後30年に及ぶ享徳の乱が勃発する。 |
| 7月30日(享徳4年 6月16日) | 上杉家援軍のために出陣した駿河守護今川範忠が、鎌倉を制圧。足利成氏は御料所があり支持者が多く住む下総古河に拠点を移す。以後、古河公方と呼ばれるようになる。 |
| 11月 7日 | ローマ教皇カリストゥス3世の命で、ジャンヌ・ダルクの復権裁判が行われる。 |
| グーテンベルクが、ヨハン・フスト、ペーター・シェッファーらと、金属活版で聖書を印刷する。 | |
| 1456年 | |
| 7月 7日 | ジャンヌ・ダルクの処刑裁判の判決破棄が宣告される。 |
| 8月11日 | オスマン帝国をベオグラードの戦いで破ったハンガリーの摂政フニャディ・ヤーノシュがペストで病没。 |
| 1457年 | |
| 2月11日(景泰8年 1月17日) | 奪門の変。土木の変でオイラトに捕らえられ、帰国後も監禁されていた明朝の上皇英宗が、弟の景泰帝が病に臥せったのを捉えて、石亨・徐有貞・曹吉祥らとともにクーデターを起こし、帝位を奪って重祚する。景泰帝は幽閉される。 |
| 2月16日(天順元年 1月22日) | 土木の変の際に景泰帝を擁立し王都北京を守ったうえ、エセンと交渉して英宗の帰還にこぎつけた于謙が、奪門の変で重祚した英宗らに反逆罪の名目で処刑される。成化帝の代になって名誉が回復した。 |
| 2月24日(天順元年 2月 1日) | 景泰帝が死去。病死とも、兄の英宗によって暗殺されたとも言われる。 |
| 5月 1日(長禄元年 4月 8日) | 太田道灌が江戸氏の拠点跡に新たに築城した江戸城に移転。 |
| 12月18日(長禄元年12月 2日) | 長禄の変。後南朝に奪われていた神璽(八尺瓊勾玉)を、嘉吉の乱で一旦滅亡した赤松氏の家臣上月満吉、石見太郎、丹生屋帯刀左衛門、丹生屋四郎左衛門がお家再興のために奪い返そうとした事件。後南朝に付くふりをして1年以上をかけて実行に移した。奪取には一旦失敗するが、翌年3月に再び実行して成功、神璽は京に戻された。この功で赤松氏は再興を認められ、加賀半国を与えられた。なおこの事件で南朝の皇胤とも言われる自天王・忠義王兄弟が殺されている。 |
| 1458年 | |
| 1月 4日(長禄元年12月19日) | 古河公方足利成氏に対抗するため、将軍足利義政の命で、異母兄の天龍寺香厳院主清久が還俗し、鎌倉公方に任命される。名も義政から偏諱を受けて足利政知と改める。 |
| 7月(長禄2年 6月) | 足利政知が、伊豆の堀越に入る。しかし鎌倉には入れず、以後、堀越公方と呼ばれる。 |
| 8月 | 琉球王国で護佐丸・阿麻和利の乱が勃発。建国の功臣で有力按司の中城城主護佐丸盛春が謀反の疑いで討伐を受け自殺。直後に有力按司の勝連城主阿麻和利も反乱を企てたとして討伐され滅亡する。従来、王位簒奪を狙う阿麻和利が忠臣護佐丸を讒言で滅ぼしたという物語で知られるが、実際に護佐丸は反乱を起こそうとした、弱体化していた尚王家が二大按司の両者を滅ぼした、といった見方もある。 |
| 1459年 | |
| (長禄3年) | この年、旱魃などの自然災害が相次ぎ、大規模な飢饉となる。いわゆる「長禄・寛正の飢饉」のはじまり。 |
| 1461年 | |
| (寛正2年) | 数年に及ぶ長禄・寛正の飢饉で、この年はじめの2ヶ月だけで洛中での病死者・餓死者が8万2千人に達する。後花園天皇は、将軍足利義政に「生き残った者らは首陽の蕨を食べている」という内容の漢詩を贈って、奢侈な政治を諌める。 |
| 1462年 | |
| (寛正3年 9月) | 京都で徳政令を求める大規模な土一揆が起きる。 |
| (寛正3年10月) | 奈良でも馬借らが大規模な一揆を起こす。 |
| 1464年 | |
| 2月23日(天順8年 1月17日) | 明の英宗が死去。通常明の皇帝は一世一元の制により、「元号+帝」で呼ばれることが多いが、英宗は土木の変で帝位を失い、奪門の変で復辟したことから、2つの元号を持つため、英宗と呼ばれている。宦官の王振を重用して土木の変を招いたことや、于謙を処刑したことなどで暗愚な皇帝とみなされることが多い。一方、永楽帝のクーデターから50年以上も監禁されていた建文帝の皇子朱文圭を解放している。 |
| 2月28日(天順8年 1月22日) | 明の英宗の長男朱見深が即位(成化帝)。 |
| 1465年 | |
| 2月 4日(寛正6年 1月 9日) | 比叡山の衆徒が、蓮如のもとで独自の活動をするようになった大谷本願寺を襲って破却。いわゆる「寛正の法難」。本願寺が分離独立するきっかけともなった。 |
| 10月15日(文正元年9月6日) | 文正の政変。権力を強めようとする将軍足利義政と大名との対立から、細川勝元らの圧力を受け、義政の側近、伊勢貞親、季瓊真蘂、斯波義敏、赤松政則らが追放される。 |
| 1467年 | |
| 黒羊朝最大の版図を築いたジャハーン・シャーが、白羊朝のウズン・ハサンを討伐するために出兵するも、野営地の奇襲を受けて殺害される。黒羊朝はこの後一気に崩壊。 | |
| 1468年 | |
| 1月17日 | アルバニアの領主スカンデルベグが死去。本名ジェルジ・カストリオティ。オスマン帝国に仕えてその勇猛さからアレクサンドロス大王の名をもらいイスケンデル・ベイ(スカンデルベグ)と呼ばれたが、後にオスマン帝国に反旗を翻し、ムラト2世・メフメト2世の軍を撃退し独立を保った。アルバニアの民族的英雄。 |
| 2月 3日 | 活版印刷術を発明したヨハネス・グーテンベルクが死去する。印刷の権利を失ったり、騒乱に巻き込まれるなどして財産を失い、聖書の印刷の功績でアドルフ大司教に召抱えられ、ひっそりとこの世を去ったと言われる。 |
| 1471年 | |
| 1月18日(文明2年12月27日) | 退位して後花園院となっていた後花園天皇が崩御。各地の騒乱に対して綸旨を発給し、将軍家の失政を諌めるなど、皇室の権威を復活させた人物。北朝の世襲親王家伏見宮系統の出身で、現在に至る天皇家の直接の祖となる(弟の貞常親王が現在の「旧皇族11宮家」の祖であり男系で天皇家と分かれたのはこの代からなので、旧皇族と言っても、非常に離れている)。 |
| 9月10日(文明3年 8月26日) | 天皇の支持を得られていなかった西軍が南朝の18歳の皇族を京へ招く。小倉宮を称しているが、系譜や諱などは不明。「西方新主」「西陣南帝」などと呼ばれる。 |
| 10月25日(文明3年 9月12日) | 桜島文明噴火。死者多数。 |
| 1472年 | |
| 6月27日 | ブルゴーニュ公シャルルがボーヴェ占領を企図するが、住民の農民の娘ジャンヌ・レーケが、城壁を登ってきた兵士を手斧で叩き落としたことで城兵の士気が上がり、撃退に成功する。ルイ11世が彼女を称賛したこともあり、「手斧のジャンヌ(ジャンヌ・アシェット)」と呼ばれるようになった。シャルルは「猪突公」などとも呼ばれる無鉄砲な君主で知られる。 |
| 1473年 | |
| オトゥルクベリの戦い。オスマン帝国と白羊朝による軍事衝突。オスマンが勝利しアナトリア半島全域を支配下に置く。 | |
| 1474年 | |
| (文明6年) | 後土御門天皇が、勅命で一休宗純を大徳寺48世の住持に任ずる。一休は大徳寺の再興に尽力したが、自身は都の郊外にある酬恩庵に暮らした。 |
| 1475年 | |
| 9月15日(文明7年 8月15日) | 桜島南西部で噴火(文明溶岩が流出)。 |
| この頃、インカ帝国がチムー王国を滅ぼす。 | |
| 1476年 | |
| 9月29日(文明8年 9月12日) | 桜島大噴火。死者多数を出し、沖小島と烏島が形成される。 |
| 1477年 | |
| 1月 5日 | ナンシーの戦い。ブルゴーニュ戦争最後の戦いで、ロレーヌ公国首都ナンシーをめぐり、ブルゴーニュ公シャルルと、ロレーヌ公ルネの軍勢が衝突。吹雪の中、相手の陣形を見抜いたルネの軍勢が迂回攻撃に成功。ブルゴーニュ軍は殲滅され、シャルルも戦死した。男子後継者がいなかったブルゴーニュ公国は滅亡。 |
| 12月16日(文明9年11月11日) | 11年続いた応仁の乱が、西軍の解体で公式に終結。乱後に織物業者が西軍本陣跡地に集まって「西陣」(西陣織)と呼ばれたことから、乱終結の日は西陣の日とされている。 |
| 1478年 | |
| 白羊朝最大の版図を築いたウズン・ハサンが死去。 | |
| 1479年 | |
| 8月 6日(文明11年 7月19日) | 後南朝の皇族が、越後から越中を経て越前北ノ庄に移ったという。後南朝皇族の消息に関する史料上最後の記録。擁立されていた西軍解散後、東国各地を放浪していたとみられる。 |
| 1481年 | |
| 12月12日(文明13年11月21日) | 臨済宗大徳寺派の僧一休宗純が酬恩庵で死去。一休は後小松天皇の子という説があり、悟りを開いたのち、数々の風狂的言動を行い、森侍者と呼ばれる女性と暮らすなど異色の僧侶だが、天皇からも信頼され、能筆家、詩人としても知られる。茶道では一休の作品が崇められたため、江戸時代に広く一般に名前が知られるようになった。 |
| 1482年 | |
| この頃、仏教界で一大勢力だった佛光寺の14世経豪が、主要48坊のうち42坊を率いて、蓮如の本願寺に帰依するという事件起きる。経豪は蓮敎の名を与えられ興正寺を興す。佛光寺13世光教は、経豪の弟経誉を新たに「14世」としたものの、佛光寺は急速に衰退し、本願寺が勢力を拡大することとなった。 | |
| 1483年 | |
| 1月 6日(文明14年11月27日) | 古河公方足利成氏と幕府との間で和議が成立し、享徳の乱が終結(都鄙合体)。成氏は伊豆一国の堀越公方支配を認める。 |
| 1485年 | |
| 8月22日 | ボズワースの戦い。リッチモンド伯ヘンリー・テューダーが、ヨーク朝リチャード3世を打ち破り、薔薇戦争は終結。テューダー朝のきっかけとなる。一方リチャード3世は敗死し、英国王では戦死した最後の王となっている。2012年に発見された遺体から、脳を損傷する頭部への刺突で即死したと見られている。シェイクスピア作品で奸物として描かれたが、近年再評価されている。 |
| 1486年 | |
| 8月25日(文明18年 7月26日) | 太田道灌が、主君扇谷上杉定正の居館糟屋館に招かれた際に暗殺される。定正が実力者道灌に恐れを抱いたためと言われるが、これを機に扇谷上杉家は離反者が相次ぎ、衰退していく。 |
| 1487年 | |
| 6月16日 | ストーク・フィールドの戦い。テューダー朝ヘンリー7世がヨーク派に対して最終的な勝利を収める。薔薇戦争は終結。 |
| 9月 9日(成化23年 8月22日) | 明の成化帝が死去。即位後は奪門の変で処刑された于謙の名誉を回復したり、比較的まともな皇帝だったが、後半は方術に傾倒し、乳母の万貴妃を寵愛したことでその専横を招き、さらに宦官の汪直を重用して、特務機関の「西廠」を設立し恐怖政治を敷いた。そのため暗愚の皇帝の評価が強い。 |
| 9月22日(成化23年 9月 6日) | 明の成化帝の三男朱祐樘が即位(弘治帝)。 |
| 1490年 | |
| 1月27日(延徳2年 1月 7日) | 第8代将軍足利義政死去。東山文化の担い手となったが、政治力は弱く幕府の衰退につながった。 |
| 1491年 | |
| 8月 6日(延徳3年 7月 1日) | 堀越公方足利政知の子で、幽閉されていた茶々丸が、牢獄を脱して、自身を讒言した継母の円満院とその子の潤童子を殺害。堀越公方の座につく。茶々丸はまもなく伊豆の混乱に乗じた伊勢宗瑞(北条早雲)によって追放され、その後殺されたため諱が伝わっていない。 |
| 9月30日(延徳3年 8月27日) | 将軍の座について間もない足利義材(のち義稙)が、近江の六角高頼征伐を行い、これを追放。 |
| 1492年 | |
| 1月 2日 | イスパニア半島のイスラム教国ナスル朝が滅亡し、キリスト教徒によるレコンキスタが終結。 |
| 4月 8日 | フィレンツェの事実上の支配者で大富豪メディチ家の当主ロレンツォ・デ・メディチが43歳で死去。メディチ家黄金期の当主で、芸術家たちのパトロンになってルネサンス文化の担い手になった他、庶民のためのカーニバルを開催するなど人気が高かった人物。 |
| 10月12日 | クリストファー・コロンブスが率いたスペインの艦隊が「西インド諸島」に到達し、「サン・サルバドル島」に上陸。 |
| 11月16日 | 神聖ローマ帝国オーバーエルザス(現フランス・オー=ラン県)エンシスハイムの農園に隕石が落下する。 |
| 11月 | スンニ朝ソンガイ帝国のスンニ・アリ大王が死去。ソンガイ帝国の領域を拡大し、国家制度を整備。強力な水軍でニジェール川流域を支配下に置いた。あとをスンニ・バルが継ぐ。 |
| 1493年 | |
| 3月15日 | コロンブスの一行が帰国。大絶賛される。 |
| 4月 2日 | ソンガイ帝国の将軍アスキア・ムハンマド・トゥレが、スンニ朝の王スンニ・バルに対し反乱を起こし、ガオ近郊でスンニ・バルを破り追放する。アスキアは王に即位し、アスキア朝を建てる。反乱を起こした要因は、スンニ・バルが非イスラム化をさらに進めたため。ソンガイ帝国は、スンニ・アリ時代、アスキア・ムハンマド時代、アスキア・ダーウード時代に最も栄えた。 |
| 5月 7日(明応2年 4月22日) | 畠山氏への対応などで将軍足利義材と対立した管領細川政元が日野富子らとともにクーデターを起こし、義材が河内出兵の留守を狙い、堀越公方足利政知の子で天龍寺香厳院の清晃を還俗させて(足利義遐のち義澄)将軍職に奉じる(ただし後土御門天皇の反感を買い将軍宣下がすぐには降りず)。 |
| 教皇アレクサンデル6世の教書によって教皇子午線が引かれ、その東をポルトガル、西をスペインとすることが決まる。 | |
| 1494年 | |
| 6月 7日 | 教皇子午線に不満なポルトガルがスペインと交渉し、トルデシリャス条約締結。ブラジルはポルトガルが、それ以外のアメリカ両大陸はスペインが進出することになる。 |
| 1495年 | |
| 1月23日(明応3年12月27日) | 足利義遐(義澄)の将軍宣下が降りる。 |
| 9月 3日(明応4年 8月15日) | 鎌倉で大きな地震があったとみられる。津波で大仏殿などの堂舎が壊れ、溺死者200余人という。明応7年の巨大地震の誤記という説もあったが、複数の史料で確認できることから、この日にも地震があった可能性が高い。なお鎌倉高徳院の大仏殿が失われた年月日には諸説ある。 |
| 9月(明応4年 9月) | 伊勢宗瑞が大森藤頼の小田原城を計略を用いて奪取する。ただし年月日には異説も複数ある。 |
| 1497年 | |
| 7月 8日 | ポルトガルのヴァスコ・ダ・ガマ艦隊の4隻がリスボンを出発。約120人を乗せアフリカ周りでインドへ向かう。インド諸国との交易路確立が目的。バルトロメウ・ディアスが途中まで同行することに。 |
| 11月25日 | ヴァスコ・ダ・ガマ艦隊が南アフリカで輸送艦のキャラック船を解体処分し3隻となる。 |
| この年、ジョン・カボット率いるイングランドの探検隊が、現在のケープ・ブレトン島に到達。ヨーロッパ人による北米到達はバイキング以来とみられる。 | |
| 1498年 | |
| 5月20日 | ヴァスコ・ダ・ガマの艦隊が西インド洋を横断してインドのカレクト(カリカット:現コージコード)に到着。 |
| 6月30日(明応7年 6月11日) | この日、九州と畿内でそれぞれ比較的大きな地震が発生したと記録にある。南海地震説と日向灘地震説、両方の連動説がある。畿内と九州の被害は同一地震の記録の可能性も高い。家屋倒壊や山崩れなどにより死者多数。 |
| 8月29日 | カレクト側と紛争状態になっていたヴァスコ・ダ・ガマの艦隊が帰国のためカレクトを離れる。貿易風が弱く、一旦インド西岸を北上。 |
| 9月11日(明応7年 8月25日) | 南海トラフを震源とする明応地震が発生。大津波が関東から紀伊半島にかけての太平洋岸を襲い、甚大な被害を出す。鎌倉大仏が露坐になったのは、この津波で大仏殿が流出したためとされているが、明応4年の大地震の津波で倒壊したとも、応安2年に倒壊して以降は再建されず、この地震時にはすでに露座だったとする説もある。 |
| ミラノにあるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院の食堂に、レオナルド・ダ・ヴィンチによって「最後の晩餐」の壁画が完成する。透視図法を使って食堂から続く空間にイエスと弟子たちがいるように描かれており、壁画としては珍しいテンペラ画の技法を使っている。 | |
| 1499年 | |
| 1月 9日 | ヴァスコ・ダ・ガマの艦隊が復路アフリカ東部のマリンディに到着。インドからここまでの間に病死者が相次いで人員が減ったため、ここでサン・ラファエル号を焼却処分し、艦隊は2隻となる。 |
| 7月10日 | ヴァスコ・ダ・ガマの艦隊のうち先行していたニコラウ・コエリョ指揮のベリオ号がリスボンに帰還。 |
| 1500年 | |
| 1月26日 | スペイン人のビセンテ・ヤーニェス・ピンソンの艦隊がブラジル北部に到着。アマゾン一帯の探検を行う。 |
| 2月(弘治13年 2月2日) | 琉球王国尚真王は、大里親雲上を将軍に定めて、宮古領主の仲宗根豊見親(空広)に案内させて、軍船100艘、兵力3000人を付けて、八重山領主オヤケアカハチ(堀川原赤蜂:ホンカワラアカハチ)を攻める。少数の島民を除きほぼ全島民がアカハチに従って抵抗したと言われる。 |
| 2月(弘治13年 2月13日) | 琉球王国の八重山遠征軍が、石垣を二方面から攻め、八重山領主オヤケアカハチが滅ぼされる。琉球王国側の記録では、朝貢を怠り、謀反を企てたので滅ぼしたとされているが、実際には独立していた宮古八重山のうち、宮古領主仲宗根豊見親が琉球王国に従ったのを機会に、琉球王府が八重山の武力併合を図って侵略したものとみられる。八重山は長田大主が勢力を拡大していく。 |
| 4月22日 | ポルトガル人のペドロ・アルヴァレス・カブラルの艦隊がブラジル(後のポルト・セグーロ)に到着。新発見の地としてポルトガル領を宣言したこともあり、一般にはカブラルが「ブラジル発見者」とされている。なおこの時、赤い染料ブラジリンが取れるスオウ(ブラジル)に似た木があったため、地名も「ブラジルの地」と名付けられた。 |
| ウズベクの部族長ムハンマド・シャイバーニー・ハンが、ティムール朝の内紛に介入してスルタン・アーリーからサマルカンドを奪い占領。一旦はティムール朝のバーブルがサマルカンドを奪い返すも維持できず間もなく放棄してタシュケントへ退き、シャイバーニーは、マー・ワラー・アンナフルを支配下に置いてシャイバーニー朝ウズベク=ハン国を興す。 | |
| 1503年 | |
| ムハンマド・シャイバーニー・ハンが、タシュケントを攻略。同地を支配していたマフムード・ハンはモグーリスタンへ追放され、同家にいた甥のバーブルも敗走。モグール人らを糾合しホラーサーンへ向かう。 | |
| 1504年 | |
| 9月 | バーブルがカーブルを攻めて領主ミールザー・ムキームを降し、同地を征服。 |
| 1505年 | |
| 1月 | バーブルが北インドに遠征。 |
| 6月 8日(弘治18年 5月 7日) | 明の弘治帝が死去。風寒に罹り治療を受けた際に、大医が治療を誤って、鼻血が止まらなくなり死亡したと言われる。英宗、成化帝と暗愚な皇帝が続いたのに対し、弘治帝は、皇帝に取り入って権力を握っていた宦官・道士・僧を追放して、賢臣を登用するなど、まともな政策を行ったため、明の中興の祖と呼ばれる。 |
| 6月19日(弘治18年 5月18日) | 弘治帝の長男の朱厚㷖が即位(正徳帝)。 |
| 1506年 | |
| 5月20日 | スペイン王室からも見捨てられたコロンブスがスペインのバリャドリッドで病死。 |
| 5月 | シャイバーニーによるバルフ攻略戦に、バーブルらティムール朝系の君主らが連合軍を派遣。バルフは陥落したため、連合軍は解散。 |
| 1507年 | |
| 2月 | バルフ攻防戦の遠征に出ていたバーブルが、冬季行軍の苦難の末カーブルへ帰国。シャー・ベギムらの反乱を鎮圧。 |
| 6月 | シャイバーニーがヘラートを征服。 |
| 8月 1日(永正4年 6月23日) | 細川政元が細川澄之支持派の手で暗殺される。細川家は細川澄之、細川澄元、細川高国の三派に分かれて後継者争いに発展。 |
| 1508年 | |
| 5月15日(永正5年 4月16日) | 10代将軍でクーデターにより地位を追われていた足利義尹(義材)が大内義興の支持を得て軍を京に進めたため、近江へ逃れた11代将軍足利義澄は失脚。 |
| 7月28日(永正5年 7月 1日) | 足利義尹が細川高国らに迎えられて入京し征夷大将軍に復帰。 |
| サファヴィー教団の教主でサファヴィー朝を建国したイスマーイール1世が白羊朝を滅ぼす。同教団は白羊朝と対立したが、イスマーイール1世自身は白羊朝のウズン・ハサンの孫でもあるため、白羊朝を支えた部族らの支持を得たと言われる。 | |
| この年から、カーブルの君主バーブルが、パーディシャー(皇帝)の称号を名乗り始める。 | |
| この年、人文主義者デジデリウス・エラスムスが、友人トマス・モアの自宅で、「痴愚神礼讃」を執筆。出版は1511年。痴愚女神モリアーのセリフを介して人間の愚かさを風刺。王侯貴族や教会、学者らもその対象にしたことから禁書目録に入れられるも、欧州中で大ベストセラーになった。 | |
| 1510年 | |
| (中宗4年 4月 4日) | 李氏朝鮮の貿易規制策などに不満を持つ慶尚道三浦の倭人が対馬の宗盛順らの支援を受けて反乱を起こす。 |
| (中宗4年 4月19日) | 三浦の乱が鎮圧される。 |
| サファヴィー朝のイスマーイール1世がシャイバニー朝ウズベク・ハン国に侵攻し、迎え撃ったムハンマド・シャイバーニーは敗死。 | |
| 1511年 | |
| 9月15日(永正8年 8月23日) | 船岡山合戦。足利義尹を支持する細川高国、大内義興、畠山義元らの軍勢と、失脚した足利義澄派の細川澄元、畠山義英、赤松義村らの軍勢が衝突。義尹派が勝利する。なおこの時すでに義澄は病死している。また細川氏、畠山氏、六角氏らの内紛も要因の1つ。 |
| (永正8年 8月) | 『妙法寺記』などから、富士山の6~7合目付近にあった「カマ岩」が燃えたという。その直前に大きな音がしていることなどから、小規模の噴火と考えられる。 |
| サファヴィー朝によってシャイバーニーが敗死したことをうけて、カーブルのバーブルは、サファヴィー君主イスマーイール1世に臣従を申し出て、マー・ワラー・アンナフルへ進出。かつての領地であるサマルカンドに再入城するが、シーア派系のサファヴィー朝に反発する住民の抵抗にあう。 | |
| 4月28日 | 勢力回復を目指すシャイバーニーの甥ウバイドゥッラーと、バーブルがクリ・マリクで戦う。バーブルは敗北。 |
| 11月 | ウバイドゥッラーとバーブルがグジュドワーンで戦い、バーブルはふたたび敗北。サマルカンドを失い、マー・ワラー・アンナフルから撤退。暫くの間バーブルはサマルカンドを伺っていたが、やがてティムール朝の旧領回復をあきらめ、東のインドへ進出するようになる。 |
| 1513年 | |
| 9月25日 | 黄金郷を目指すバスコ・ヌーニェス・デ・バルボア率いる探検隊が、パナマ地峡を横断し南側の海に到達。いわゆる「太平洋の発見」。これによりアメリカは2つの大洋に挟まれた独自の大陸であることも判明した。 |
| この年、オスマン帝国の軍人アフメット・ムヒッディン・ピーリーによって作成されたピーリー・レイースの地図が皇帝セリム1世に献上される。おそらくアジア大陸から南北アメリカ東海岸までの世界地図だったと思われるが、現存するのは大西洋沿岸部分のみ。様々な地図をもとに作られ、コロンブスのアメリカ到達から20年ほどしか経っていないのに正確に描かれている。南米に続くようにアフリカの下まで陸地が描かれているため、南極が描かれているとする説もあるが、単に羊皮紙の大きさに入り切らなかったため、南米南部を下の方に曲げて描いている。 | |
| 1514年 | |
| 8月23日 | チャルディラーンの戦い。アナトリア東部へ勢力を拡大していたサファヴィー朝のイスマーイール1世に対し、オスマン帝国のセリム1世が親征をおこない、両軍はチャルディラーンで衝突。銃火器を装備したオスマン軍に対してサファヴィー軍は大敗。イスマーイール1世はこれ以降、積極性を失い、宗教的権威も衰えるようになる。ティムール朝カーブル君主のバーブルもサファヴィー朝から離れる。 |
| 1516年 | |
| 4月23日 | バイエルン公ヴィルヘルム4世がビール純粋令を定める。「ビールは、麦芽・ホップ・水・酵母のみを原料とする」とし、価格や罰則などを定めたもの。 |
| この年、中国明朝のドン族とヤオ族の住む南丹に隕石が降る。現在の広西チワン族自治区南丹県。隕石そのものも1958年に大躍進政策で鉄の原材料調査を行って発見された。 | |
| この年、トマス・モアの著作『ユートピア』が発刊。現実のイングランド社会を風刺する意味合いで、「素晴らしいがどこにもない場所」という意味の造語「ユートピア」の名を持つ架空の国家を描いている。共産主義のように私有財産を持たず、また人々は平等であることから、ユートピアは理想郷という意味になったが、作中の同国は都市も地形もすべて人工的に作り変えられ、住民は規則的な生活を送り、個性も存在しないことから、反理想郷(ディストピア)的に見られることもある。 | |
| 1517年 | |
| カーブル君主のバーブルがサファヴィー朝の支配するカンダハールを攻めるが失敗。 | |
| 1518年 | |
| ティムール朝系君主であるカーブルのバーブルが、かつてティムールが遠征したインド北部のパンジャーブへ進出し同地を制圧。この頃からバーブルは重火器を多用するようになる。 | |
| 1519年 | |
| 11月 8日 | コンキスタドールのスペイン人エルナン・コルテスがアステカの都テノチティトランに現れ、アステカ王モクテスマ2世から、コルテスはケツァルコアトルス神の化身と勘違いされる。 |
| 11月14日 | エルナン・コルテスがアステカ王モクテスマ2世に改宗を強要し、さらに口実を作って王を幽閉する。 |
| 1520年 | |
| 5月21日(永正17年 5月 5日) | 等持院の戦い。中央復帰を図り摂津まで進出した細川澄元の軍勢を指揮する三好之長と、細川高国らが京で衝突。三好之長が敗北。細川澄元の復帰はならず。なお高国と対立していた将軍義尹は澄元と和解していたため、戦後義尹と高国は対立。 |
| 5月27日(永正17年 5月11日) | 三好之長が捕らえられ処刑される。 |
| 6月24日(永正17年 6月10日) | 伊丹から阿波に逃げ戻った細川澄元が死去。 |
| 7月 1日 | アステカ王モクテスマ2世が、エルナン・コルテスに反発するアステカ軍や市民をなだめようとして石や投げやりをぶつけられ、その傷が元で死去。 |
| 10月21日 | マゼラン(マガリャンイス)の艦隊が南米大陸南端とその先の島の間に海峡を発見。島の原住民ヤーガン族が点けたと見られる火を目撃。海峡はマジェラン海峡、島はフエゴ島と名付けられる(ティエラ・デル・フエゴは火の島という意味)。 |
| 11月 8日 | ストックホルムの血浴。デンマークの支配下にあったスウェーデンの反乱を鎮圧したクリスチャン2世が、スウェーデンの反乱関係者を和解の晩餐会と称して集め、皆殺しにした事件。生き延びた若き貴族のグスタフ・ヴァーサが反乱を起こす。 |
| カーブルの君主バーブルが再びインド遠征を行う。 | |
| 1521年 | |
| 4月13日(大永元年 3月 7日) | 将軍足利義尹が京を出奔し堺へ逃れる。細川高国は、代わりに義澄の遺児の足利義晴を将軍に擁立。 |
| 4月20日(正徳16年 3月14日) | 明の正徳帝が死去。前年に水遊び中に船が転覆して水に落ちたのが原因で病気になり、それが元で病死したという。淫乱な上に戦争好きで、不要な出兵を繰り返しては、遠征先で美女を拉致して暴行するという悪行を繰り返したという。出兵の負担が重くのしかかり各地で反乱が相次いだ。中興の祖と呼ばれた弘治帝によって建て直された国力は失われ、明の滅亡のきっかけを作った人物。自覚があったのか、死ぬ直前に「罪己詔」を出した。 |
| 5月27日(正徳16年 4月22日) | 弘治帝の弟興王の次男朱厚熜が即位(嘉靖帝)。 |
| 4月27日 | 航海途中のマゼランがフィリピンのマクタン島でイスラム教徒の領主ラプラプの手勢によって殺害される。マゼランが、友好関係を結び改宗までしたセブ島の領主ラジャ・フマボンへの従属と改宗を求めて周辺の諸領主に武力をもって圧力をかけたことがラプラプの反感を招いたとみられる。 |
| 5月 1日 | マゼラン艦隊の指揮権を継いだドゥアルテ・バルボサら主な幹部24人のほとんどが、ラジャ・フマボンに招かれた席で殺害される。バルボサが、マゼランの奴隷だった「マラッカのエンリケ」(マラッカ人。マゼランは自分の死後、遺産を分け与え、奴隷から解放すると遺言していた)を引き続き奴隷にすると脅したため、エンリケがフマボンをそそのかしたと言われる。艦隊は幹部の一人だったバスク人フアン・セバスティアン・エルカーノが率いることに。 |
| 8月13日 | エルナン・コルテスらの率いる軍隊によって、アステカの都テノチティトランが陥落。 |
| 1522年 | |
| 9月 6日 | マゼラン艦隊で唯一残ったビクトリア号がスペインのサンルーカル・デ・バラメーダに帰港。世界一周を果たす。出発時の乗員265名のうち最後まで残ったのは最後の指揮をとったフアン・セバスティアン・エルカーノ、詳細な記録を残したアントニオ・ピガフェッタなど18名のみ。 |
| この頃、琉球王国尚真王が、宮古領主の仲宗根豊見親を派遣して、与那国の領主鬼虎(うにとら)を滅ぼす。仲宗根の兵力は精鋭数十人規模だったとある。年代は1513年以前とする説もある。鬼虎は宮古島の出身で怪力無双の豪傑であり、女領主サンアイイソバに従っていたが、野心をあらわにしたため、イソバが仲宗根豊見親を介して鬼虎討伐を求めたともされる。 | |
| カーブルの君主バーブルがインド遠征から戻り、サファヴィー朝の勢力圏であったカンダハールを制圧。 | |
| 1523年 | |
| グスタフ・ヴァーサが、スウェーデン議会の承認で国王グスタフ1世として即位。デンマーク(カルマル同盟)からの独立を果たす。 | |
| 1524年 | |
| 8月23日 | サファヴィー朝を建国したイスマーイール1世が死去。10歳のタフマースブ1世が受け継ぐが、サファヴィー教団の信者でもあり同王朝を軍事的に支えた遊牧部族集団クズルバシュが内紛状態になる。 |
| カーブルの君主バーブルが3度めのインド遠征を開始。パンジャーブの中心ラホールまで進出する。 | |
| 1525年 | |
| カーブルの君主バーブルが4度めのインド遠征を開始。ダウラト・ハンを降す。 | |
| 1526年 | |
| 4月21日 | パーニーパットの戦い。カーブルの君主バーブルと、ローディー朝イブラーヒーム・ローディとが戦闘し、堅牢な陣と銃火器を多用したバーブルが、10倍の兵力と1000頭の象軍を率いたローディ軍に対し勝利。イブラーヒームは戦死。 |
| 4月27日 | バーブルがデリーに入城する。デリーの大モスクで金曜礼拝を自身の名で唱え、インド支配を宣言。ムガル帝国を樹立する。ムガルとはペルシャ語でモンゴルを意味するムグルから。バーブルの出自であるティムール王朝はモンゴル帝国の後継王朝の一つ。 |
| 5月10日 | バーブルがローディー朝の王都アーグラに入城する。ローディー朝は滅亡。ローディー朝王族によるバーブル暗殺未遂事件が起きる。 |
| 1527年 | |
| 3月14日(大永7年 2月12日) | 桂川原の戦い。管領細川高国に弟香西元盛を自害に追い込まれ恨みを持つ波多野稙通・柳本賢治兄弟に細川晴元から援軍として合流した三好勝長・政長らの軍勢と、細川高国、武田元光の軍勢が衝突。高国らが大敗を喫し、京都から近江方面へ退却する。 |
| 3月17日 | カーヌワーの戦い。ムガル帝国を興したバーブルと、ローディ朝の復興を目指すマフムード・ローディ、ローディに味方したラージプートの諸勢力連合軍が衝突。火器を使うバーブル側が大勝。マフムード・ローディは敗走。 |
| 6月21日 | ニッコロ・マキャヴェッリが死去。『君主論』の作者でマキャベリズムのもととなった思想家。 |
| インカ帝国の皇帝で領土を拡張したワイナ・カパックが疫病により死去。同時期に皇太子のニナン・クヨチや、多くの兵士らも同じ疫病で死去していることから、各地に進出を始めていたヨーロッパ人から天然痘が広がり感染したという説も有力(マラリア説もある)。インカ帝国はこのあと、子のワスカルとアタワルパによる内戦が起き、スペイン人のフランシスコ・ピサロにつけこまれた。 | |
| 1529年 | |
| 4月22日 | アジアの領土分割を決める、スペインとポルトガルのサラゴサ条約が締結。 |
| 5月 6日 | ガーグラー川の戦い。ムガル帝国のバーブル軍に対して、ふたたびマフムード・ローディが攻撃を仕掛ける。ローディにはベンガル王国のヌスラット・シャーなどが味方につくも、バーブル側が勝利。ローディは再び敗走し、ヌスラット・シャーはバーブルと和睦。 |
| 1530年 | |
| 12月26日 | ムガル帝国を興したバーブルが死去。 |
| 1531年 | |
| 7月17日(享禄4年 6月 4日) | 大物崩れの合戦。将軍側の細川高国、浦上村宗の軍勢が、堺公方側の三好元長、赤松政祐に敗北する。翌日、高国が尼崎で捕縛される。 |
| 7月21日(享禄4年 6月 8日) | 細川高国が自害させられる。 |
| 7月 | ムガル帝国2代皇帝フマーユーンが、ラクナウの戦いでマフムード・ローディを撃破。 |
| 8月 | 彗星が出現し、ペトルス・アピアヌスが観測する。ハレー彗星。 |
| シェール・ハーンが、ムガル帝国2代皇帝フマーユーンからの独立を宣言。のちのスール朝。 | |
| 1532年 | |
| 7月22日(享禄5年 6月20日) | 堺公方の有力武将だった三好元長が、一向宗徒に襲われ和泉の顕本寺で自害。堺公方体制も崩壊する。 |
| 9月23日(天文元年 8月24日) | 法華宗徒の三好元長が一向宗徒に襲われ自害したことに反発した、京の法華宗徒や町衆が、六角氏らの支援を受けて山科本願寺を襲い、これを焼き討ちする。法華宗は京に勢力を拡大していく。 |
| 11月16日 | フランシスコ・ピサロが、改宗を拒否し聖書を冒涜したという理由で、会見に現れたインカ皇帝アタワルパを捕らえ、インカ兵を攻撃。インカ兵7000人が殺され、アタワルパは幽閉される。 |
| 1533年 | |
| 7月26日 | フランシスコ・ピサロが、インカ皇帝アタワルパを偶像崇拝と実兄ワスカルを殺害した罪で処刑。ワスカルは側近に殺されているため、アタワルパが殺害した証拠はない。 |
| 1534年 | |
| 6月23日(天文3年 5月12日) | 織田信長、清洲三奉行のひとり織田信秀の嫡男として那古屋城で生誕(月日と出生地には異説あり)。 |
| サファヴィー朝の2代目君主タフマースブ1世が、クズルバシュ出身の大アミール・フサイン・ハーン・シャームルーを処刑。以降、親政を行い、クズルバシュの権力を削ぐようになる。 | |
| 1535年 | |
| ムガル帝国皇帝フマーユーンが、グジャラート・スルターン朝のバハードゥル・シャーを破り、グジャラートとマールワーを併合。 | |
| 12月29日(天文4年12月 5日) | 森山崩れ。西三河の有力者となった松平清康が尾張へ侵攻するが、この日の早朝、森山の陣中で家臣の阿部正豊にいきなり惨殺される。正豊は植村氏明に殺害された。松平宗家はあとを継いだ広忠も若くして亡くなったため、家康が出るまで衰退する。なお正豊の父親である阿部定吉は特に咎められておらず、事件の要因ははっきりとわかっていない。 |
| 1536年 | |
| 4月 7日(天文5年 3月17日) | 駿河の守護大名今川氏輝と弟の彦五郎が急死。先代氏親の正室寿桂尼と太原雪斎らは、氏親の子である栴岳承芳を還俗させ(今川義元)、後継に押し立てる。 |
| 6月13日(天文5年 5月25日) | 今川氏親の子で、今川義元の異母兄に当たる玄広恵探が、義元擁立に反発した母方の祖父(もしくは同族の)福島正成(もしくは福島越前守)に擁立されて久能山で挙兵。花倉の乱が勃発。 |
| 6月28日(天文5年 6月10日) | 今川義元らの軍勢が、花倉城を攻め、玄広恵探は逃走。普門寺で自刃し、花倉の乱は終結。 |
| 7月12日 | 人文主義者デジデリウス・エラスムス・ロッテルダム死去。宗教改革に大きな影響を与えた人物だが、本人は敬虔なカトリック。 |
| 8月13日(天文5年 7月27日) | 天文法華の乱。比叡山の僧兵と六角氏の軍6万が、京に勢力を伸ばしていた法華宗の寺院21カ寺を襲い放火。京の市街地も大きな被害を出す。 |
| 1538年 | |
| 7月 8日 | フランシスコ・ピサロが、対立していたコンキスタドール(征服者)のディエゴ・デ・アルマグロを処刑。 |
| 10月29日(天文7年10月 7日) | 第一次国府台の戦い。小弓公方の足利義明が真里谷信応、里見義堯らを率いて国府台まで進出。古河公方と組んだ北条氏綱も兵を出し合戦となる。足利義明は討ち死。北条氏綱は下総方面へ進出し、無傷だった里見義堯も上総方面へ勢力を拡大。 |
| この年、ゲラルト・デ・クレーマー(メルカトル)が最初の世界地図を出版。すでに南北米大陸がアメリカという名前になっており、アジア大陸とは切り離して描かれている。 | |
| 1539年 | |
| ポーランド王国のジグムント1世王がユダヤ人の法的保護を定めたカリシュの法令を改めて承認する。 | |
| 12月 | チャウサーの戦い。シェール・ハーンの軍勢と、ムガル帝国軍が衝突。ムガル皇帝フマーユーンは大敗を喫し、アーグラへ敗走。シェール・ハーンはシェール・シャーとして即位し、スール朝を興す。 |
| 1540年 | |
| 5月17日 | カナウジの戦い。シェール・シャー率いるスール朝軍がムガル帝国のフマーユーンの軍勢と衝突。ムガル帝国側が大敗を喫し、シェールはデリーとアーグラーを占領。ムガル皇帝フマーユーンはシンド地方へ逃走した後、一旦ペルシャのサファヴィー朝のタフマースプ1世のもとへと落ち延びる。 |
| 7月28日 | トマス・クロムウェル処刑。イングランド王ヘンリー8世の離婚と再婚のために宗教改革まで行った挙句に、そのヘンリー8世の怒りを買って処刑された。同日、ヘンリー8世は、キャサリン・ハワードと再婚。 |
| 1541年 | |
| 6月26日 | インカ帝国を征服したコンキスタドール(征服者)フランシスコ・ピサロが暗殺される。殺したのは、ピサロによって処刑されたコンキスタドールのひとりディエゴ・デ・アルマグロの息子。 |
| 1542年 | |
| 1月26日(天文11年 1月11日) | 大内義隆が出雲尼子氏攻略のため出陣。 |
| 9月 6日(天文11年 7月27日) | 大内軍が尼子側の赤穴城を攻略。 |
| 11月27日(嘉靖21年10月21日) | 壬寅宮変。嘉靖帝の後宮の2人の側室と女官16人が、就寝中の嘉靖帝の首を縄で締めて殺そうとした事件。騒ぎの連絡を受けた方妃(孝烈皇后)が女官らを取り押さえさせた。嘉靖帝は一時昏睡状態に陥った。事件の背景は不明だが、皇帝が道教に凝って不老不死になるため処女の経血を欲して女性らを拉致監禁し、恐れた女性らが事件を起こした説や、側室が多いために相手にされない女性らが恨んで事件を起こした説などがある。首謀者とされた曹端妃、王寧嬪らは凌遅刑に処されたという。 |
| 1543年 | |
| 3月(天文12年 4月) | 第一次月山富田城の戦いが始まる。 |
| 6月 9日(天文12年 5月 7日) | 大内軍、月山富田城から撤退を開始。帰路、大内義隆の養嗣子である大内晴持は海路で遭難。殿軍の毛利勢も大敗を喫する。大内氏が衰退する一因となった。 |
| 9月23日(天文12年 8月25日) | 種子島の西村に中国のものと見られる大型船が漂着。乗客の中にいた儒者五峯と筆談したところ、2名のヨーロッパ人(フランシスコ、モッタ)がおり、彼らが持参していた火縄銃を領主の種子島時尭に披露。時尭が2丁を購入し、研究させる。いわゆる鉄砲伝来。それ以前にも鉄砲という正体不明の武器の記述は各地に見られるが、銃火器かどうかははっきりしない(蒙古襲来時の「てつはう」のような火薬兵器か)。なお銃火器の原型は中国宋王朝のときに発明され、西へ運ばれ、ドイツなどで「銃」へと発展した。 |
| 1544年 | |
| インカ帝国の15代皇帝マンコ・インカ・ユパンキが、フランシスコ・ピサロを殺害したアルマグロ一派の手で殺害される。最後の皇帝。子のサイリ・トゥパックがあとを継ぎ、地方政権である「ビルカバンバのインカ帝国」皇帝となった。 | |
| 1545年 | |
| 5月22日 | スール朝を建国したシェール・シャーが砲弾の暴発事故で死去。イスラーム・シャーが後を継ぐも内紛状態へ。 |
| 10月31日(天文14年 9月26日) | 小田原の北条氏が駿河東部で今川・武田と対立したことを受け、関東の山内上杉憲政、扇谷上杉朝定、古河公方足利晴氏が同盟して、8万の大軍で北条氏の河越城を包囲。河越城主北条綱成は籠城。 |
| 12月(天文14年11月) | 北条氏康、武田晴信の仲介の元、河東(駿河富士川以東)を放棄することで今川義元と和睦。 |
| 1546年 | |
| 5月19日(天文15年 4月20日) | 北条氏康、河越城周辺の両上杉・古河公方連合軍に対して夜襲を仕掛ける。また河越城からも北条綱成が出撃し、連合軍は壊乱。上杉朝定、朝定の重臣で松山城主の難波田憲重らが討ち死に。上杉憲政は上州平井城へ逃走、足利晴氏も古河へ敗走する。通称「河越夜戦」。記録に乏しいため、詳細については諸説ある。北条氏は以後関東制覇へ向けて動き出す一方、扇谷上杉氏は滅亡、山内上杉氏も衰退し、越後長尾氏を頼ることになり、上杉謙信の関東進出へとつながっていく。 |
| 7月10日 | シュマルカルデン戦争勃発。カトリック教徒の神聖ローマ帝国皇帝カール5世に対し、皇帝の政策に不満を持つ反皇帝派プロテスタント諸侯同盟(シュマルカルデン同盟)が起こした反乱。 |
| 1547年 | |
| 1月16日 | イワン雷帝の即位。モスクワの生神女就寝大聖堂でツァーリとして戴冠式を行う。 |
| 4月24日 | ミュールベルクの戦い。神聖ローマ帝国皇帝カール5世がプロテスタント軍のザクセン選帝侯ヨハン・フリードリヒを奇襲攻撃で破り勝利する。 |
| 5月19日 | ヴィッテンベルク降伏条約が締結され、シュマルカルデン戦争はカトリック側の勝利で終結。 |
| 8月 6日(天文16年 9月19日) | 小田井原の戦い。信濃へ勢力を広げる武田晴信に対し、信濃佐久郡の志賀城主笠原清繁は籠城。武田晴信は兵を出して城を包囲する。これに対し、上野の上杉憲政が笠原支援のため、金井秀景率いる軍勢を派遣。両軍は小田井原で衝突し、武田軍が勝利。 |
| 8月11日(天文16年 9月24日) | 志賀城が落城し、笠原清繁らは討ち死に。武田晴信は捕虜とした敵兵やその家族女子供を人身売買にかけるなど、かなり厳しい処置を行う。 |
| 1548年 | |
| 3月10日(天文17年 2月 1日) | 武田晴信率いる軍勢が、北信濃に進出。同地の村上義清も出兵し、千曲川支流沿いに兵を展開。 |
| 3月23日(天文17年 2月14日) | 上田原の戦い。武田晴信と村上義清との戦いで、武田軍が大敗。板垣信方、甘利虎泰、才間河内守、初鹿伝右衛門ら重臣が戦死する。 |
| 3月26日(天文17年 2月17日) | 敗戦後も上田原にとどまっていた武田晴信が甲府へ帰還する。 |
| 5月 | 神聖ローマ帝国の帝国議会でアウクスブルク仮信条協定が結ばれる。皇帝カール5世が、帝国内の反発を回避するため、カトリック有利ながら、プロテスタントにも一定の妥協を図った協定。 |
| 1549年 | |
| 1月28日(天文17年12月30日) | 長尾景虎が隠居する兄の晴景のあとを受けて家督を継ぎ、越後国の守護代となる。有能な景虎を兄に代わって推す勢力が強まり、越後守護上杉定実の調停によって。 |
| 3月23日(天文18年 2月24日) | 織田信長と、斎藤道三の娘「濃姫」が結婚。 |
| 4月15日 | フランシスコ・ザビエルがインドのゴアを出発し、日本へ向かう。 |
| 6月(天文18年 5月) | 島津家家臣の伊集院忠朗が、樺山善久・北郷忠相らと、肝付兼演の加治木城を攻めた際に、鉄砲を使用したといわれる。 |
| 8月15日(天文18年 7月22日) | フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸。 |
| 1550年 | |
| 12月21日(天文19年11月14日) | 東山の戦い。足利義輝・細川晴元と、三好長慶側の三好長逸・十河一存らが京の市中で衝突した戦い。この戦闘で、幕府軍側が鉄砲を使用し、三好側の武将三好長虎の与力が撃たれたと、山科言継が日記に記録している。明確な鉄砲使用の実例が分かる最初の記録。 |
| 12月28日(天文19年11月21日) | 中尾城の戦い。三好軍が東山の中尾城に籠もる足利義輝の背後に回ろうとしたため、義輝は中尾城を放棄して近江へ退却。 |
| 1551年 | |
| 9月28日(天文20年8月28日) | 大寧寺の変。周防・長門の戦国大名・大内義隆の重臣で守護代の陶晴賢が主導する反乱が起こる。 |
| 9月30日(天文20年9月 1日) | 大内義隆が長門大寧寺で自刃し、大内家は事実上滅亡。 |
| 1552年 | |
| 3月 | プロテスタントながら、カトリックの神聖ローマ帝国皇帝カール5世に組みしたザクセン選帝侯モーリッツが、皇帝の政策に反発してカール5世を攻撃。 |
| 8月 | ザクセン選帝侯モーリッツと、カール5世の弟でローマ王(神聖ローマ帝国におけるドイツ王)のフェルディナンド1世が交渉し、カトリックとプロテスタントの融和を図るパッサウ条約を締結。モーリッツはカール5世と和睦。 |
| 10月 | イヴァン雷帝が、カザン・ハン国の首都カザンを攻略。タタール人の多くは殺されるか追放され、カザン・ハン国は形式上は残ったものの、事実上滅亡。 |
| 12月 3日 | フランシスコ・ザビエルが中国上川島で病死。 |
| 1553年 | |
| 7月 9日 | ジーフェルスハウゼンの戦い。ザクセン選帝侯モーリッツらが、パッサウ条約を拒否したブランデンブルク=クルムバッハ辺境伯アルブレヒト・アルキビアデスを攻撃。戦いには勝利するがモーリッツは戦死する。 |
| 9月 8日(天文22年 8月 1日) | 東山霊山城の戦い。将軍位を継いだ足利義藤(義輝)が、京の三好政権を倒すため、三好長慶が留守を狙い、細川晴元とともに京に侵攻。船岡山と東山霊山で、三好側の今村慶満と戦うが敗北。義藤は近江朽木谷へと逃れ、しばらく逼塞することとなった。 |
| 10月 8日(天文22年 9月 1日) | 第一次川中島の戦い。村上義清救援のために出陣した上杉軍が武田軍と衝突。 |
| 1554年 | |
| 6月 | シュヴァルツァハの戦い。ブランデンブルク=クルムバッハ辺境伯アルブレヒト・アルキビアデスはプフォルツハイムへと落ち延びる。 |
| 12月 | ペルシャのサファヴィー朝に亡命していたムガル帝国2代目皇帝フマーユーンが、スール朝の内紛を機に軍勢を率いてインド北部へ侵攻。 |
| 1555年 | |
| 6月22日 | ムガル帝国2代目皇帝フマーユーンが、スール朝の第6代君主シカンダル・シャーの軍勢をシルヒンドで打ち破る。 |
| 7月23日 | ムガル帝国2代目皇帝フマーユーンが、スール朝を滅ぼし、ムガル帝国を復活させる。 |
| 8月 6日(天文24年 7月19日) | 第二次川中島の戦い。上杉・武田両軍は以降200日に渡って対峙。 |
| 9月25日 | アウクスブルクの和議。神聖ローマ帝国皇帝カール5世、弟でローマ王フェルディナンド1世が、プロテスタント諸侯の圧力でルーテル派を認める。各領主は宗派を選ぶことが出来、その領民はその宗派に属すると定める。帝国自由都市はこの原則の除外として宗教的自治権を認めず。 |
| 10月15日(天文24年 9月30日) | 厳島に布陣した大内家の実力者陶晴賢軍を攻めるため、毛利軍が荒天の中、二手に分かれて渡海。 |
| 10月16日(天文24年10月 1日) | 厳島の戦い。毛利軍が陶晴賢の軍勢を攻撃。狭い島内に数万の軍勢がひしめき合い、大混乱となった陶軍は大敗。陶晴賢は敗死し、毛利家伸張のきっかけとなる。 |
| 1556年 | |
| 1月27日 | ムガル帝国2代目皇帝フマーユーンが事故死。あとを13歳の息子のアクバルが継ぎ、バーブル時代からの重臣バイラム・ハーンが摂政となる。 |
| 5月28日(弘治2年 4月20日) | 斎藤道三が実子の斎藤義龍と長良川河畔で戦い戦死する。 |
| 8月 3日(弘治2年 6月28日) | 長尾景虎が、春日山城を出奔し、高野山へ向かう事件を起こす。家臣団同士の抗争や国人衆の謀反が頻繁にあったことに嫌気が差したためと言われるが、出奔してみせることで家臣団を結束させる狙いがあったという説もある。 |
| 9月20日(弘治2年 8月17日) | 長尾景虎の家臣らが、大和葛城で景虎に追いつき説得して出家を思いとどまらせる。 |
| 9月27日(弘治2年 8月24日) | 斎藤道三の戦死を機会と見た織田信長の同母弟織田信勝(信行)が、柴田勝家、林秀貞らと挙兵する。しかし稲生の戦いで敗北。 |
| 10月 6日 | ムガル皇帝アクバルと摂政バイラム・ハーンが遠征中に、スール朝の将軍だったへームーがムガル帝国領へ侵攻。デリーを占領する。 |
| 11月 5日 | 第二次パーニーパットの戦い。ムガル皇帝アクバルと摂政バイラム・ハーンが、スール朝の将軍へームーの軍勢と衝突。兵力差ではへームーの方が多く勝利目前だったが、へームーが片目を負傷して意識を失い軍は壊乱。ヘームーは捕らえられて処刑される。 |
| 11月 7日 | ムガル皇帝アクバルと摂政バイラム・ハーンが、デリーを奪還。 |
| 12月 7日 | スール朝最後の君主シカンダル・シャーが蜂起し、マーンコートに籠城。ムガル皇帝アクバルと摂政バイラム・ハーンが出陣し、これを包囲。 |
| 1557年 | |
| 7月25日 | マーンコートの籠城戦でシカンダル・シャーがムガル帝国に降伏。 |
| 9月(弘治3年 8月) | 第三次川中島の戦い。 |
| 11月22日(弘治3年11月 2日) | 織田信長が河尻秀隆らをして清洲城内で弟の織田信勝(信行)を暗殺。 |
| シャイバニー朝ウズベク・ハン国の実力者アブドゥッラーフ2世が首都をサマルカンドからブハラへ遷す。以降ブハラ・ハン国と呼ばれる。 | |
| 1558年 | |
| 2月23日(弘治4年 2月 5日) | 寺部城の戦い。三河寺部城主鈴木重辰が今川氏から離反し織田方についたため、今川より松平元康が派遣されて、上野城主酒井忠尚とともにこれを火攻めにする。周囲の挙母城や、三宅高清の広瀬城なども攻撃した。これが松平元康(徳川家康)の初陣と言われている。今川義元はこの戦功に「山中三百貫」を松平家に戻したという。また今川家はこの戦いで初めて鉄砲を使用したともいう。 |
| 3月18日(弘治4年 2月28日) | 正親町天皇即位に合わせて改元が実施され「永禄元年」となる。しかし本来改元の協議を行う将軍足利義輝には相談されず、京の支配者三好長慶との間で決定したため、義輝は反発。各地でも永禄の年号はすぐには浸透しなかった。 |
| 7月 4日(永禄元年 6月 9日) | 北白川の戦い。京の三好政権に対し、将軍足利義輝と細川晴元が、六角義賢の支援を受けて、京方面へ侵攻。東山の将軍山城と如意ヶ嶽で攻防した後、この日、北白川で衝突する。しかし戦闘の膠着と、六角氏の消極な姿勢を受け、両者は協議し、6日に足利義輝と三好長慶は和睦。義輝が京に戻り、反発した細川晴元は離脱することになる。将軍が復権したこともあり、永禄の改元は全国に通達される。 |
| 11月17日 | イングランドで、エリザベス1世が即位。主に信仰上の理由で敵対した異母姉の女王メアリー1世が病死したことを受けて。テューダー朝最後の王。 |
| 1559年 | |
| 1月15日 | エリザベス1世がウエストミンスター寺院で戴冠。 |
| 10月(永禄2年 9月) | 降路坂の戦い。石見銀山攻略のため山吹城を攻めていた毛利元就が、門司城を大友義鎮に攻められたことから退却を開始したところ、降路坂で追撃に遭い大敗を喫する。 |
| 1560年 | |
| 3月 | ムガル帝国摂政のバイラム・ハーンが皇帝側の起こしたクーデターで失脚。バイラムは一旦皇帝の勧告を了承し、引退してメッカ巡礼に向かうも、追討の兵が来たため反乱を起こす。のちバイラムは降伏し、皇帝アクバルもこれを許す。 |
| 6月12日(永禄3年 5月19日) | 桶狭間の戦い。織田信長が2000ほどの兵で10倍する今川軍を奇襲し、今川義元は戦死。 |
| 9月16日(永禄3年 8月26日) | 長尾景虎(上杉謙信)が安房里見義堯の救援要請を受けて、北条氏討伐のため出陣。北関東の諸勢力も長尾側に参陣。北条氏は各拠点で籠城戦を強いられる。武田信玄と今川氏真は北条方に付くことを決める。 |
| 1561年 | |
| 1月31日 | ムガル帝国の元摂政バイラム・ハーンがメッカ巡礼に向かう直前に暗殺される。個人的な怨恨だったとされる。皇帝アクバルはこれを悼み、妻子を引き取る。 |
| 3月(永禄4年 3月) | 長尾軍とその同盟軍が、小田原城を包囲。 |
| 4月30日(永禄4年閏3月16日) | 長尾景虎、小田原包囲戦のさなかに、鎌倉鶴岡八幡宮で山内上杉家の家督と関東管領職を相続。就任式を行う。名を上杉政虎と改める。 |
| 5月28日(永禄4年 4月15日) | 善明堤の戦い。松平元康が深溝松平好景とともに吉良義昭の東条城を攻めたが、吉良義昭の作戦にはまり、松平好景らが戦死する。 |
| 5月(永禄4年 4月) | 北条方についた武田信玄が北信濃へ出兵。また、北関東の諸将が長期遠征に不満を唱えて離反し始めたため、上杉政虎は小田原城包囲を解き、越後へ向けて退却を開始。 |
| 10月17日(永禄4年 9月 9日) | 第四次川中島の戦い。武田軍の高坂昌信ら別働隊が妻女山の上杉軍を背後から衝くために移動。しかし上杉軍は察知し、夜半、密かに山を降り、武田軍本隊の前へ展開。 |
| 10月18日(永禄4年 9月10日) | 第四次川中島の戦い。上杉・武田両軍の本隊が直接衝突。武田軍は武田信繁、山本勘助、諸角虎定らが討ち死にする大敗を喫する。しかし高坂昌信の武田別働隊が駆けつけ、上杉軍を挟み撃ちにしたため、上杉軍も大きな被害を出す。両者撤退。 |
| 10月21日(永禄4年 9月13日) | 藤波畷の戦い。松平元康家臣の本多広孝・松井忠次らが、吉良義昭の東条城攻略を目指し、藤波畷で吉良家の将富永忠元と交戦、これを討ち取る。富永の戦死で吉良側は戦意喪失し東条城を明け渡し降伏。 |
| 1562年 | |
| 7月12日 | スペイン出身のユカタン司教ディエゴ・デ・ランダが、マヤの絵文書を布教の障害になるとして焚書を命じ、マヤの貴重な書物のほとんどが失われる。 |
| 1563年 | |
| 2月(永禄6年 1月) | この頃、西三河で三河一向一揆が勃発。本願寺派の三河本證寺に侵入した無法者を松平家臣の西尾城主酒井正親が捕縛したことから、守護使不入を侵害したとして起きたとする説、松平氏家臣の菅沼定顕が上宮寺の兵糧を強奪したため起きたとする説などがある。一向宗、守護の吉良家、今川残党に加え、松平家臣団からも同調者が多数出たため、松平家康にとって危機的な状況となった。 |
| 4月25日(永禄6年 4月 3日) | 湯所口の戦い。因幡守護山名豊数が、毛利氏に通じて離反した鳥取城主の武田高信を攻めるも、城内に討ち入った中村豊重が戦死したことで大敗。因幡国において山名勢が衰退するきっかけとなる。 |
| 8月31日(永禄6年 8月13日) | 白鹿城攻防戦が始まる。毛利氏による月山富田城攻略の前哨戦。 |
| 1564年 | |
| 2月19日(永禄7年 1月 7日) | 第二次国府台の戦い。江戸城守将の太田康資が北条氏から離反したことをきっかけに進出した里見義弘と北条氏康の戦い。里見側が大敗し退却。上総は北条氏の勢力圏となる。この前年の正月に起こった両軍の戦闘と混同していると考えられている。 |
| 2月27日(永禄7年 1月15日) | 小豆坂・馬頭原合戦。三河一向一揆勢と松平家康が戦い家康が勝利する。家康に味方した水野信元が仲介し、また家康が一揆方に付いた家臣を赦免することで一揆は解体へと向かう。一揆側に付いていた本多正信は追放された。 |
| 1565年 | |
| 5月16日(永禄8年 4月17日) | 第二次月山富田城の戦いが始まる。 |
| 6月17日(永禄8年 5月19日) | 永禄の変。松永久通と三好三人衆(三好長逸・三好政康・岩成友通)が、二条城に軍勢1万を送り、13代将軍足利義輝を襲撃。義輝側も激しく応戦したが、義輝を含め昼ころにほぼ全員が討ち死に・自害した。三好・松永側の動機は、将軍との対立、足利家の内紛への介入、訴訟取次から起きた偶発的な出来事など諸説ある。なお、この時大和にいた松永久秀が事件に関わっていたかははっきりしない。 |
| 8月23日(永禄8年 7月28日) | 松永久秀の監視下に置かれていた覚慶(足利義輝の実弟で興福寺一乗院門跡。後の足利義昭)が一色藤長・細川藤孝らの手で助け出される。 |
| 1566年 | |
| 1月12日(永禄8年12月21日) | 松永久秀と対立した三好三人衆の軍勢が大和に侵攻。筒井氏らと連携し松永久秀の居城多門山城を攻撃する。しかし攻略に至らず。 |
| 1月22日(永禄9年 1月 1日) | 第二次月山富田城の籠城戦の最中、城の補給を担っていた宇山久兼が、大塚与三衛門の讒言を信じた尼子義久に殺害される。尼子勢内部で動揺が走り滅亡の要因の一つとなった。大塚与三衛門もこの後、大西高由に殺害された。 |
| 2月24日(永禄9年 2月 5日) | 備中の戦国大名である備中松山城城主の三村家親が、美作興善寺で遠藤秀清・俊通の兄弟により火縄銃で撃たれて死亡。美作方面で対立する備前の戦国大名宇喜多直家が示唆した暗殺事件。三村家は次男の元親が跡を継ぐも、美作方面からの撤退を余儀なくされる。 |
| 12月 7日(永禄9年10月26日) | 三ツ山城の戦い。日向の戦国大名伊東義祐が米良重方に命じて築城中の三ツ山城を、島津義久・義弘・歳久が2万の兵で攻撃。籠城戦となるが、米良重方・矩重兄弟の防戦により島津側は大敗し撤退する。島津義弘はこの戦いで重傷を負った。 |
| 1567年 | |
| 1月 1日(永禄9年11月21日) | 尼子義久が毛利側に降伏し、第二次月山富田城の戦いが終結。 |
| 1月23日(嘉靖45年12月14日) | 明の嘉靖帝が死去。死因は「丹薬」(水銀や鉛などで作る「不老長寿」の薬と考えられていた)の服用による薬物中毒。即位直後は正徳帝時代の悪政を改めたが、「大礼の議」の尊号問題で、皇帝ではない実父の興献王を「皇考」と定めるかどうかで臣下と長期にわたり対立することになり、反対した臣下を処刑・投獄。加えて道教に凝っていたことから道士を重用し朝政を混乱に陥らせた。また壬寅宮変を招くなど、暗愚な皇帝の一人とされている。 |
| 2月 4日(嘉靖45年12月26日) | 嘉靖帝の三男の朱載坖が即位(隆慶帝)。 |
| 2月 8日(永禄9年12月29日) | 松平家康が個人として勅許を得て名字を徳川に改める(このときは源氏ではなく藤原姓)。その後、秀忠も徳川を認められるが、それ以外の松平家は含まれず。 |
| 8月(永禄10年7月) | 明善寺城の戦い。父親を暗殺された三村元親が、暗殺の黒幕である宇喜多直家を攻めるため、明善寺城を攻略。宇喜多直家も明善寺城周辺の豪族を調略。三村元親は、石川久智、植木秀長、庄元祐ら総勢2万で侵攻するが、直家は先手を打って明善寺城を攻略。続いて庄元祐、石川久智の軍勢を破ったため、三村元親は自らの軍で宇喜多直家を攻撃するも失敗。撤退した。この結果、三村氏は弱体化し、宇喜多氏が勢力を伸ばすことになる。 |
| 9月16日(永禄10年8月14日) | 甘水・長谷山の戦い。毛利勢の支援を受け古処山城に入った秋月種実に対し、大友宗麟は兵2万で侵攻。続けて邑城、休松城を攻略。 |
| 9月25日(永禄10年8月23日) | 三船山合戦。上総まで進出した北条氏政が、里見氏の拠点であった上総南部の佐貫城を攻略するため、三船台砦に入ったところ、里見義弘がこれを迎え撃ち、北条側が敗れ相模まで撤退した。これにより再び上総方面は里見勢力圏に入ることとなった。 |
| 10月 5日(永禄10年9月 3日) | 休松の戦い。古処山城攻略中に毛利勢の動きを警戒した大友軍が撤退を始めたところを秋月種実が急襲。一旦は撃退されるも、翌4日も再度夜襲をかけ、大友勢に大きな損害を出す。 |
| 11月10日(永禄10年10月10日) | 東大寺の戦い。松永久秀と三好三人衆が、東大寺の境内で戦い、おそらく失火から大仏殿などが焼失。大仏も溶け落ちてしまう。 |
| 1568年 | |
| 11月 7日(永禄11年10月18日) | 足利義昭が従四位下に昇叙し、征夷大将軍の宣下を受け、室町幕府15代将軍となる。 |
| 12月24日(永禄11年12月 6日) | 武田信玄が駿河侵攻を開始し、甲府を出発。 |
| 12月30日(永禄11年12月12日) | 薩埵峠の戦い。駿河侵攻を開始した武田勢に対し、今川氏真が迎撃の大軍を出すも、武田方の調略によって今川方の武将ら21名が内通し、氏真は駿府へ退却。これにより今川軍は総崩れとなり、武田軍は一気に駿府へ攻め込む。氏真、駿府籠城を諦め、朝比奈泰朝の居城、掛川城へ落ち延びる。この時、氏真正室の早川殿(北条氏康息女)が徒歩で落ち延びたことを知った北条氏康が激怒し、武田と手切れを決めたと言われる。 |
| 12月31日(永禄11年12月13日) | 武田軍が駿河を占領。一方、徳川家康も遠江へ侵攻を開始。 |
| 1569年 | |
| 1月14日(永禄11年12月27日) | 徳川家康、遠江の各国衆を取り込み、各地を攻略。掛川城を包囲する。 |
| 1月21日(永禄12年 1月 5日) | 本圀寺の変。織田信長の畿内進出に反発する三好三人衆、斎藤龍興、小笠原信定らが、足利義昭の宿所である本國寺(現本圀寺)を襲撃した事件。明智光秀らが指揮する若狭衆が防衛に当たる。 |
| 1月22日(永禄12年 1月 6日) | 本圀寺の変で、細川藤孝、三好義継らのほか、摂津衆らが織田方の援軍として京に入り、三好方は退却。桂川での戦いで三好側は敗北し小笠原信定が戦死。織田信長は連絡を受けて急遽岐阜を発ち、8日に本國寺に入る。本國寺に変わる京の拠点として二条城の建設構想が立てられたとされる。 |
| 1月27日(永禄12年 1月11日) | 上杉謙信が、今川・北条から塩を止められた武田領へ塩を送る。 |
| 2月 3日(永禄12年 1月18日) | 北条氏康、今川家支援のため、氏政に4万5千の兵で駿河へ出陣。対する武田信玄は迎撃に向かう。両軍薩埵峠で対陣。武田信玄は常陸佐竹義重らを動かして北条を攻めさせ、北条氏康も越後上杉謙信と組んで信濃侵攻を画策。 |
| 6月 1日(永禄12年 5月17日) | 今川氏真が掛川城を開城し、徳川家康に降伏。武田勢が遠江に侵攻したため、家康が武田との関係を切り、北条の仲介で今川家存続に方針転換したことを受けたため。しかしこれ以降、氏真は徳川の庇護下に置かれ、駿河国主に復帰することはなく、大名としての今川家は滅亡。 |
| 7月 1日 | 元来関係の深かったポーランド王国とリトアニア大公国による同君連合が成立。ポーランド・リトアニア共和国となる(王国だがまもなく貴族と法による支配体制へ移行し、王権の法的規制が強くなったことから、一般に共和国と呼ばれる)。実質、ポーランドによるリトアニア大公国の支配。6月28日に貴族らの合意が成立し、7月4日にルブリンで調印したため、ルブリン合同と呼ばれる。現在のポーランド、バルト三国の他、ウクライナ、ベラルーシ、ロシアの一部を含む大国。 |
| 7月(永禄12年 7月) | 八流の戦い。土佐中央部を支配する長宗我部元親が、土佐東部に勢力を持つ安芸国虎と、土佐西部に勢力を持つ一条兼定とが同盟し、和睦を拒否したことなどから、安芸国虎に対して兵を動かす。安芸国虎も迎え撃つも、家臣の内応などで敗北。安芸城に撤退し籠城する。 |
| 9月21日(永禄12年 8月11日) | 籠城していた安芸国虎が、家臣と領民の命を救う代わりに自刃。長宗我部元親が土佐東部を併合。 |
| 11月13日(永禄12年10月 5日) | 武田信玄が小田原城の包囲を解き、退却を開始。北条方はこれを追撃する作戦を取り、北条氏照と北条氏邦の兵2万が三増峠に向かう。 |
| 11月14日(永禄12年10月 6日) | 三増峠付近で武田・北条両軍が対峙。 |
| 11月16日(永禄12年10月 8日) | 三増峠の戦い。武田・北条両軍が衝突し、前半は北条方が、後半は武田方が有利に進める。武田軍の箕輪城代浅利信種らが戦死。両軍とも自軍の勝利としている。戦に間に合わなかった北条氏政は進軍を停止し引き上げる。 |
| 1570年 | |
| 3月30日(元亀元年 2月14日) | 布部山の戦い。尼子氏再興を図る尼子勝久・山中幸盛らの軍勢に対し、毛利輝元らの率いる軍勢が到着。布部山で激突し、尼子再興軍が敗れる。 |
| 5月24日(元亀元年 4月20日) | 織田・徳川連合軍は、公家や畿内諸侯とともに、朝倉勢を攻めるために京を出発する。 |
| 5月30日(元亀元年 4月26日) | 金ヶ崎の戦い。織田・徳川連合軍が、朝倉勢との戦いのさなか、浅井長政が朝倉方について出撃し、織田信長は躊躇せず京へ向けて撤退。朽木氏の協力と、羽柴秀吉ら殿軍の尽力で京にたどり着く。 |
| 9月25日(元亀元年 8月26日) | 三好三人衆と織田信長の戦闘(野田城・福島城の戦い)が始まる。 |
| 10月11日(元亀元年 9月12日) | 本願寺顕如の命により、門徒衆らが摂津福島で三好三人衆と対陣していた織田勢の陣を攻撃。石山合戦が始まる。 |
| 11月 1日 | オールセインツの大洪水。オランダからドイツにかけての沿岸で大規模な高潮災害が発生。2万人が死亡したとされる。 |
| 12月(元亀元年12月) | 上杉輝虎、不識庵謙信と称する。 |
| 1571年 | |
| 9月30日(元亀2年 9月12日) | 織田信長による延暦寺焼き討ち。織田の敵対勢力に味方し、兵を擁し、女性を囲うなどの行為が要因となって、明智光秀らが主体となって攻撃。記録では堂宇500余りが焼失し、僧侶男女ら約1500~4000人が殺害されたという。なお被害の内容は主に焼き討ちに批判的な側からの記録による。後の発掘調査で山上の諸施設に焼け跡の痕跡が少ないことから、山下の近江坂本が主な攻撃対象だったという説もある。公家や諸大名の間で焼き討ちを非難する意見がある一方で、同時代から比叡山の堕落を批判する意見もあった。 |
| 10月21日(元亀2年10月 3日) | 北条氏康死去。 |
| 12月 6日(元亀2年11月20日) | 大隅の肝付氏・禰寝氏と日向の伊東氏が連合して島津氏の領する桜島を攻める。 |
| この年、イドリス・アローマが、カネム・ボルヌ帝国の皇帝に即位。火縄銃を導入して武力を高め、帝国建国の地カネム地方を奪還し、チャド湖周辺を制圧。さらに各地へ領土を拡張し、北西のアガデス・ビルマ地方や、北のフェザーン地方などを併合した。オスマンとサハラ交易を行い、カネム・ボルヌ帝国最盛期を生み出す。 | |
| 1572年 | |
| 6月14日(元亀3年 5月 4日) | 木崎原の戦い。日向伊東氏が大敗し、島津家九州制覇の端緒となる。 |
| 7月 5日(隆慶6年 5月26日) | 明の隆慶帝が死去。先帝に取り入っていた道士を一掃して賢臣を登用し、対外政策を緩和するなど、比較的まともな政策を行ったが、自身は酒色に耽り、そのため36歳の若さで死去した。 |
| 7月19日(隆慶6年 6月10日) | 隆慶帝の3男朱翊鈞が即位(万暦帝)。 |
| 8月17日 | フランスでカトリックとプロテスタント「ユグノー」の対立を解消する名目で、ユグノーの指導者で王位継承権もあるナバラ王アンリと国王の妹マルグリットの結婚式が行われ、ユグノー派貴族も集まる。 |
| 8月22日 | フランスでユグノーの指導者の一人、コリニー提督が狙撃され負傷。ユグノー派貴族らの反発が高まる。 |
| 8月24日 | フランスでカトリック教徒の貴族ギーズ公アンリによるユグノー派貴族の虐殺事件が起こり、全土へと拡大する。サン・バルテルミの虐殺。 |
| 9月24日 | 地方政権である「ビルカバンバのインカ帝国」最後の皇帝トゥパク・アマルがスペイン人によって処刑される。インカ帝国は完全に滅亡。この後も、権力への反乱の名前に「トゥパク・アマル」が使われている。 |
| 11月 6日 | ヴォルフガング・シューラーが超新星SN1572を観測。カシオペア座の12,000光年ほどの距離にある。 |
| 11月11日 | ティコ・ブラーエが超新星SN1572を消滅するまで詳細に観測し、「新星」と名付ける。これによりティコの星と呼ばれる。ティコ・ブラーエはこの功績によって天文学者としての道を開くことになった。白色矮星に連星から降着した物質によって質量が増大し、その重力収縮の結果引き起こされたIa型超新星爆発と考えられている。 |
| 11月18日(元亀3年10月13日) | 一言坂の戦い。三河に侵攻した武田信玄に対し、徳川家康が派遣した偵察部隊の本多忠勝・内藤信成ら3000と、山県昌景・馬場信春らの率いる5000の兵との遭遇戦から拡大した合戦。徳川方が敗北し退却。二俣城の戦いへとつながる。 |
| 11月21日(元亀3年10月16日) | 武田信玄は遠江の要衝二俣城の攻略に入る。城主の中根正照は降伏を拒否して籠城。 |
| 1573年 | |
| 1月22日(元亀3年12月19日) | 武田軍は二俣城の天竜川の水を汲み上げる井戸櫓を破壊し、水の補給が絶たれた二俣城は開城。しかし武田軍は徳川家康のいる浜松城を無視するように三河方面へと進軍。 |
| 1月25日(元亀3年12月22日) | 三方ヶ原の戦い。三河に侵攻した武田信玄に徳川家康が決戦を挑んで大敗した合戦。 |
| 3月19日(元亀4年 2月16日) | 武田軍が東三河の野田城を攻め落とす。 |
| 5月(元亀4年 4月) | 武田信玄の病状が悪化し、重臣らの協議で武田軍は本拠へ引き返し始める。 |
| 5月13日(元亀4年 4月12日) | 武田信玄、病死。 |
| 8月25日(元亀4年 7月26日) | 室町幕府の将軍、足利義昭が、彼を必要としなくなった信長によって京を追放される。征夷大将軍の地位を失ったわけではないが、事実上の室町幕府滅亡。 |
| 9月 4日(元亀4年 8月 8日) | 織田信長が北近江に侵攻。 |
| 9月10日(元亀4年 8月14日) | 刀根坂の戦い。織田信長が朝倉氏を急襲。朝倉勢は大敗し敗走、一乗谷の攻防戦に続く。この戦いで信長と敵対し続けた斎藤龍興も戦死。26歳。 |
| 9月14日(元亀4年 8月18日) | 織田信長の軍勢が、朝倉氏の拠点一乗谷に侵攻。一乗谷は焼け落ち、朝倉義景は一門の朝倉景鏡の勧めで大野郡へ落ち延びる。 |
| 9月16日(元亀4年 8月20日) | 朝倉義景が避難していた六坊賢松寺で、朝倉景鏡に攻められ自害。越前朝倉氏は事実上の滅亡。 |
| 9月26日(元亀4年 9月 1日) | 織田信長が越前侵攻に続けて北近江を攻略。小谷城が落城し、浅井長政、弟の浅井政元、重臣の赤尾清綱らが自刃。北近江浅井氏も滅亡する。 |
| 1574年 | |
| 7月11日(天正2年 6月23日) | 浅井・朝倉勢を滅ぼした織田信長は、伊勢長島一向一揆の討伐戦に、水軍も含む過去最大の軍勢を投入し、攻撃を開始。 |
| 10月13日(天正2年 9月29日) | 最後まで残っていた伊勢長島城(長島願証寺)の下間頼旦らが飢餓状態の門徒を救うため、織田方に降伏を申し出るが、織田信長は城から出てきた下間頼旦、願証寺顕忍ら指導者層を射殺。これに反発した門徒らが捨て身の出撃をして乱戦となり、信長の弟織田秀成、叔父の織田信次、従兄弟の織田信成、一門の織田信直、義弟の佐治信方らが戦死。信長は激怒し、残っていた輪中を包囲の上で放火、門徒2万人が焼死したと言われる。約4年続いた長島一向一揆は終結。 |
| 11月(天正2年11月) | 毛利氏が宇喜多直家と同盟を組んだことに反発し、三村元親が離反し織田信長に付く。毛利勢は備中へ侵攻して三村氏領内の諸城の攻略を開始する(備中兵乱)。毛利・宇喜多同盟については、吉川元春が信義にもとるとして反対したが、推進派の小早川隆景の主張が通った。元春は三村氏攻略にも反対している。一方三村元親の叔父である三村親成は毛利からの離反に反対し、毛利側へ出奔している。 |
| 1575年 | |
| 6月29日(天正3年 5月21日) | 織田・徳川連合軍と武田軍が長篠設楽原で戦い、鉄砲を多用するなどして織田・徳川連合軍が勝利。武田氏は重臣らが多数戦死し衰退していく。 |
| 6月30日(天正3年 5月22日) | 戦国大名三村氏の本拠である備中松山城が毛利勢によって陥落。 |
| 7月 9日(天正3年 6月 2日) | 三村元親が自害し、大名としての三村氏直系は滅亡。 |
| 7月13日(天正3年 6月 6日) | 三村氏の最後の拠点だった備中常山城も毛利方の攻勢で陥落。城主上野隆徳は自害。妻の鶴姫も乃美宗勝に一騎討ちを挑むが拒否されたため、城に戻って自害した。 |
| 7月(天正3年 7月) | 四万十川の戦い。長宗我部氏の圧力で一旦豊後に逃れていた一条兼定が旧領回復を企図して挙兵し3500の兵を集める。それに対し長宗我部元親は7500の兵を派遣。両軍は四万十川(渡川)で衝突。一領具足制で多数の兵を短期間で集められた長宗我部氏側が勝利し、一条兼定は再び落ち延びることとなる。長宗我部氏が土佐を統一。 |
| 1576年 | |
| 8月 7日(天正4年 7月13日) | 第一次木津川口の戦い。石山本願寺を包囲している織田軍に対し、本願寺の求めに応じた毛利氏が兵糧などを運び込むため、毛利水軍、小早川水軍、村上水軍、宇喜多氏などの兵力を動員。対する織田方も九鬼水軍を出したが、毛利軍の使用する焙烙玉によって、織田方は大敗。 |
| 9月21日 | イタリアの数学者・哲学者・医学者のジェロラモ・カルダーノが自殺。虚数や確率論に業績を残し、腸チフスを発見し、カルダンジョイントを発明するなど、多大な功績を残した人物だが、占星術にも凝っていて、自分の死没日時を占ったことにより、その予言当日に自殺した。 |
| 11月 4日(天正4年10月14日) | 羽柴秀吉の子ではないかとされる石松丸(羽柴秀勝)が死去した日。秀吉の実子説と養子説、秀吉と無関係説がある。実子の場合でも母親が誰かははっきりしない。 |
| 12月15日(天正4年11月25日) | 三瀬の変。織田信長が、前の伊勢国司北畠氏を完全に滅ぼすため、伊勢の三瀬御所に滝川雄利、柘植保重、加留左京進を派遣。北畠具教らを襲撃して殺害。北畠氏の養子となっていた織田信意(信雄)も、田丸城で長野具藤、北畠親成、坂内具義、大河内具良らを殺害。 |
| 12月23日(天正4年12月 4日) | 三瀬の変で北畠一族が討ち取られたことを知った家臣らが、北畠政成の霧山城に立てこもるも、織田信長が派遣した羽柴秀吉、神戸信孝、関盛信らの兵15000人によって陥落。北畠政成らは自害。 |
| 1577年 | |
| 2月19日(天正5年 2月 2日) | 織田信長が、石山本願寺に加勢する紀伊雑賀勢力の攻略を開始する。 |
| 7月(天正5年 7月) | 北条・里見両者の間で房相一和(「相房御和睦」)がなされる。安房上総の両者の勢力圏を確定することと北条の姫(龍寿院)が里見氏へ嫁ぐことで和睦が成立した。 |
| 11月 3日(天正5年 9月23日) | 手取川の戦い。能登攻略に出た上杉謙信と、七尾城の救援に赴いた織田軍が衝突。上杉軍の攻撃に対し、手取川に退却路を阻まれた織田軍は大敗を喫する。 |
| 11月19日(天正5年10月10日) | 信貴山城の戦い。織田信長に反旗を翻した松永久秀が、信貴山城に籠り、筒井順慶らを先陣に織田軍が攻撃を行う。久秀は落城の際に平蜘蛛の茶釜に火薬を詰めて自爆したとも言われる。 |
| 1578年 | |
| 1月14日(天正5年12月 7日) | 島津軍が高原から日向の伊東領へと侵攻を開始。伊東義祐の重臣福永祐友と野村文綱が島津方に寝返る。 |
| 1月17日(天正5年12月10日) | 島津軍が日向南部を攻略して伊東氏の拠点佐土原へ接近したため、伊東義祐は領地を放棄。縁戚関係の大友宗麟を頼り、一旦は沿岸部を北上したが、財部城主落合兼朝が反旗を翻したため、やむなく米良山中を通って豊後へと落ち延びる。飫肥の伊東祐兵(後の飫肥藩初代藩主)も脱出。伊東家臣団の崩壊は、伊東一族の伊東祐松の横暴が反感を買った事が要因の一つ。 |
| 2月 8日(天正6年 1月 2日) | 日向懸領主の土持親成が島津方へ寝返る。土持氏は伊東氏が関東から下向する以前の平安時代から南北朝期頃まで日向各地に勢力を持っていた一族。元々は豊後とつながりが強かった。土持氏離反の動きを、高千穂領主三田井親武が大友側に通報。 |
| 3月29日(天正6年 2月21日) | 伊東義祐が島津方に敗れて落ち延びてきたことから、大友宗麟・大友義統は、伊東氏復帰を名目に日向へ侵攻。大友家臣団には反対意見もあったと言われる。 |
| 4月15日(天正6年 3月 9日) | 上杉謙信が春日山城内の厠で倒れ、意識不明となる。 |
| 4月19日(天正6年 3月13日) | 上杉謙信が春日山城内で死去。15日ころを予定していた遠征の出陣は取りやめとなる。 |
| 5月16日(天正6年 4月10日) | 日向へ侵攻した大友勢が、島津方へ寝返った懸領主土持親成の松尾城を攻め落とす。土持親成は捕らえられ殺害される。大友宗麟は縣領の寺社をことごとく破却したという。 |
| 6月12日(天正6年 5月 7日) | 武田四天王の一人で甲越同盟を推進した春日虎綱(高坂昌信)が死去。 |
| 8月 4日 | アルカセル・キビールの戦い(マハザン川の戦い)。ポルトガル王セバスティアン1世が、モロッコのサアド朝の内紛に乗じてに侵攻するも、この戦いで大敗を喫し、セバスティアンも消息を絶つ(戦死したものと思われる)。ポルトガル軍と戦ったサアド朝のアブー・マルワーン・アブドゥルマリク王も戦死し、アブドゥルマリクによって追放されセバスティアンに支援を求めた前王ムーレイ・ムハンマドも戦死したため、「三王の戦い」ともいう。ポルトガルはこの戦争で王を失い、多数の貴族の子弟が捕虜となり、その身代金の支払と軍事費で財政が破綻したため、スペインに併合されることになる(セバスティアンは死んではおらず、いつか帰還して祖国を救うという伝説が広まった)。一方サアド朝は、戦死したアブドゥルマリクの跡を継いだ弟のアフマド・アル=マンスール・アル=ザハビーのもとで繁栄する。 |
| 11月13日(天正6年10月 4日) | 月岡野の戦い。越中月岡野で織田方の武将斎藤利治と、上杉方の武将河田長親、椎名小四郎が今泉城を巡って戦い、織田方が勝利する。飛騨の姉小路頼綱も織田方で出兵している。越中は織田方が優勢となる。 |
| 11月24日(天正6年10月25日) | 伊賀国進出を狙う織田信雄が、滝川雄利に命じて伊賀丸山城の改修に動き出したことから、伊賀国衆がこれを襲撃。第一次天正伊賀の乱の始まり。 |
| 12月 7日(天正6年11月 9日) | 耳川の戦い。日向高城川原で、大友勢と島津勢が戦い、島津軍が勝利。敗北した大友勢は耳川まで撤退したが大きな損害を出し、大友家臣団が崩壊していくきっかけとなった。 |
| 12月 4日(天正6年11月 6日) | 第二次木津川口の戦い。織田信長は九鬼嘉隆に建造させた6隻の鉄甲船を回航させて大坂湾に配備。侵攻してきた毛利水軍に対し砲撃戦を行い、毛利方は退却。織田方が勝利する。 |
| 12月 8日(天正6年11月10日) | 織田信長に反旗を翻した荒木村重の居城有岡城の包囲戦が始まる。 |
| 1579年 | |
| 8月24日(天正7年 8月 3日) | 徳川家康が岡崎城に入り、長男の松平信康を岡崎城から大浜城へ移す。その後信康は、さらに堀江城、二俣城と移される。 |
| 8月30日(天正7年 8月 9日) | 明智光秀が丹波黒井城を攻撃し攻め落とす。丹波平定戦はほぼ終結。 |
| 9月19日(天正7年 8月29日) | 徳川家康の正室、築山殿が殺害される。武田方に内通したという説も有力だが、息子信康の自刃に至った問題に連座した可能性が高く、密通などの築山殿の不行状は後世記されたものが多い。 |
| 10月 5日(天正7年 9月15日) | 徳川家康の長男、松平信康が切腹。従来は乱暴狼藉を正室の五徳姫を経由して知った織田信長の命令で殺されたというのが通説だったが、近年は家康と信康の対立に家臣団を巻き込んだ内部紛争という見方が有力になっている。なお信康に粗暴な面があったのは事実と見られる。 |
| 10月 6日(天正7年 9月16日) | 織田信雄が独断で兵力8000を率い、伊賀国に侵攻。しかし伊賀十二人衆らの反撃で大敗。柘植保重らが戦死する。織田信長はこれを知って激怒し、信雄を叱責。第一次天正伊賀の乱。 |
| 11月 7日(天正7年10月19日) | 有岡城が陥落。 |
| 1580年 | |
| 2月 2日(天正8年 1月17日) | 秀吉が別所氏の播磨三木城を兵糧攻めにした三木合戦「三木の干殺し」が終結。 |
| 4月20日(天正8年閏3月 7日) | 正親町天皇の勅命で立入宗継が織田信長と石山本願寺の調停を行い、石山合戦が終結。 |
| 5月22日(天正8年 4月 9日) | 顕如が石山本願寺から鷺森別院に退去。 |
| 9月10日(天正8年 8月 2日) | 織田信長が石山本願寺を接収。直後に火災が起き、寺域の堂舎・寺内町が二日一夜に渡り燃え続け灰燼に帰す。失火説のほか、講和反対派による放火との説もある。 |
| 1581年 | |
| 3月27日(天正9年 2月23日) | 織田信長とアフリカ・モザンビーク付近の出身とされる黒人「弥助」が面会。信長に気に入られ家臣となる。 |
| 4月 1日(天正9年 2月28日) | 織田信長が京都御馬揃えを行う。正親町天皇の御前で、信長の他、信長の武将、織田一門、公家衆、信長側近、柴田与力などが参列。 |
| 9月14日(天正9年 8月17日) | 織田信長、各地で捕らえた多数の高野聖を安土で処刑。荒木村重配下の者が高野山に逃げ込み、高野山が引き渡しに応じなかったことへの対抗措置と言われる。 |
| 9月30日(天正9年 9月 3日) | 織田信長、織田信雄を総大将に兵力5万で伊賀に侵攻。第二次天正伊賀の乱。日付は諸説あり。伊賀国衆は比自山と平楽寺の2箇所を拠点に抵抗。 |
| 10月 8日(天正9年 9月11日) | 織田軍勢、伊賀をほぼ制圧したとみられる。第一次と異なり、織田方の調略で伊賀国衆は分裂していた。 |
| 10月29日(天正9年10月 2日) | 織田信長、高野山攻めを開始。同山を巡る攻防は本能寺の変を受けて織田軍が撤退するまで続いたと言われる。 |
| 11月24日(天正9年10月28日) | 伊賀柏原城の滝野吉政が降伏。第二次天正伊賀の乱は終結。伊賀国の人口9万のうち、3万が死亡したと言われる。日付は諸説あり。 |
| 12月 1日 | 元イングランド国教会執事で信条からカトリック教会へ変わりイエズス会に所属した司祭エドマンド・キャンピオンが、カトリック普及のため亡命先のネーデルランドドゥエーからイングランドへ戻っていたところを逮捕され、信仰を捨てなかったことから、エリザベス1世殺害の企図容疑で首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑で処刑される。1970年に列聖。 |
| 1582年 | |
| 2月 3日(天正10年 1月 1日) | 近江近隣の大名・小名、御連枝衆、それらの従者等による安土城参賀が行われる。百々橋から摠見寺へ続く道で、人の重みで石垣が崩れて多数の人が落ち死傷者が出たという。参賀者はまた、摠見寺毘沙門堂、天主白州、江雲寺殿、さらに本丸、御幸(みゆき)の間などを見学。織田信長自ら見物料を取ったという。 |
| 2月20日(天正10年 1月28日) | 天正遣欧少年使節が長崎を出航する。 |
| 2月23日(天正10年 2月 1日) | 武田信玄の娘婿で木曽の領主だった木曽義昌が、武田勝頼が進める新府城建設の賦役の負担に反発して織田方に寝返る。勝頼、人質としていた木曽義昌の母親と側室及びその子供を殺害。 |
| 2月25日(天正10年 2月 3日) | 織田信長が、武田攻めを下知し、動員令を発する。森長可、団忠正ら先発軍が岐阜城を出発。 |
| 3月 5日(天正10年 2月11日) | 浅間山が大噴火。織田軍の武田領侵攻と重なったため、武田側の敗北の要因の一つとも言われる。 |
| 3月10日(天正10年 2月16日) | 織田の支援を受けた木曽義昌と、武田勝頼の派遣した軍勢が鳥居峠で戦闘し、武田側が敗北。 |
| 3月12日(天正10年 2月18日) | 織田信忠軍の信濃侵攻を受けて保科正直は飯田城を、武田信廉は大島城を放棄。徳川家康は掛川城を発って、依田信蕃の田中城攻略を開始。 |
| 2月15日(天正10年 2月21日) | 徳川軍が駿府城に入る。 |
| 3月24日(天正10年 3月 1日) | この前後に武田の御一門衆であった穴山梅雪が徳川方に寝返る。 |
| 3月25日(天正10年 3月 2日) | 武田方の高遠城が陥落。仁科盛信、小山田昌成らは討ち死に。 |
| 3月26日(天正10年 3月 3日) | 武田勝頼は新府城を放棄、小山田信茂の要害岩殿城へと向かう。なお、武田信勝は新府城での籠城を、真田昌幸は真田領の上野岩櫃城への退避を、長坂光堅が岩殿城への退避を主張したとも言われる。 |
| 3月30日(天正10年 3月 7日) | 織田信忠が甲府に入り、武田残党狩りを始める。 |
| 4月 1日(天正10年 3月 9日) | この頃、小山田信茂が武田家を離反。武田勝頼一行は行き場を失い、天目山へと向かう。 |
| 4月 3日(天正10年 3月11日) | 滝川一益の軍勢に追いつかれた武田勝頼らは、天目山の戦いで敗れ自刃。甲斐武田氏が滅亡する。 |
| 4月 6日(天正10年 3月14日) | 武田方で最後まで残っていた駿河田中城の依田信蕃が開城。徳川家康に家臣に誘われるも、これを断り本拠地信濃へ戻る(のち徳川家臣となる)。 |
| 4月16日(天正10年 3月24日) | 織田家に帰順を表明した小山田信茂が、人質に出す息子を連れて織田陣営に出頭したところ、織田信忠の命で、武田勝頼に対する不忠を理由に妻子ともども処刑される。 |
| 6月21日(天正10年 6月 2日) | 本能寺の変。明智光秀が謀反し、京に織田信長を襲撃。織田信長、織田信忠親子は自刃。グレゴリオ暦では7月1日。 |
| 6月23日(天正10年 6月 4日) | 羽柴秀吉の高松城水攻めで、城主清水宗治が自刃し開城となる。秀吉は本能寺の変の情報を得ていたが、切腹を見届けてから、畿内へ向かう。 |
| 6月27日(天正10年 6月 8日) | 天正8年に織田家を追放されていた安藤守就が本能寺の変の混乱を機と見て西美濃で挙兵。北方城を攻めるも、北方城主の稲葉一鉄に敗北。一族ともに自刃し安藤氏は滅亡。ただ甥の山内可氏は母親が山内一豊の姉だったため、守就8男安東郷忠とともに山内家に仕えたことからその系統は残った。 |
| 7月 1日(天正10年 6月12日) | 羽柴秀吉率いる諸将の軍勢と明智光秀の軍勢が摂津と山城の境にある山崎で対陣。 |
| 7月 2日(天正10年 6月13日) | 羽柴秀吉軍の中川清秀隊と、明智光秀軍の伊勢貞興隊が衝突。山崎の合戦が始まる。一旦は明智勢が優勢に進めるが、池田恒興隊、加藤光泰隊らの襲撃で逆転し、明智軍は敗走する。明智光秀は敗走中に百姓の落ち武者狩りに襲われ殺害される(負傷後自刃したとも)。 |
| 7月16日(天正10年 6月27日) | 清州会議。織田信長の後継を決める重臣会議。織田信孝を推す柴田勝家と、織田信忠の子、三法師を推す羽柴秀吉が対立。諸将の協議の結果、三法師を後継、織田信雄・信孝が後見し、羽柴秀吉・柴田勝家・丹羽長秀・池田恒興が補佐することでまとまる。柴田勝家も三法師を後継とすることでは一致していた可能性が高い。またお市の方が柴田勝家に再嫁することは、勝家と秀吉の間で合意していたことが勝家の書簡でわかるため、秀吉が勝家に譲歩するため斡旋した可能性もある。領地の再配分も決定。 |
| 10月15日 | カトリック教会がグレゴリオ暦を導入。イタリア半島諸国とスペイン、ポーランド・リトアニアが改暦を実施。ユリウス暦10月5日。 |
| 12月26日(天正10年12月 2日) | 羽柴秀吉が、近江長浜の柴田勝豊を攻め降す。 |
| 1583年 | |
| 1月13日(天正10年12月20日) | 羽柴秀吉が、岐阜城の織田信孝を攻め降す。 |
| 1月24日(天正11年 1月 1日) | 滝川一益が、柴田勝家側に与して伊勢長島で挙兵。 |
| 5月 3日(天正11年 3月12日) | 柴田勝家、佐久間盛政、前田利家ら兵力3万が近江柳ケ瀬に進出し、賤ヶ岳の戦いが始まる。 |
| 5月10日(天正11年 3月19日) | 羽柴秀吉も、兵力5万で木ノ本へ進出。 |
| 6月 6日(天正11年 4月16日) | 織田信孝が、柴田勝家、滝川一益に呼応して挙兵し、美濃へと侵攻を開始。羽柴秀吉はこれに対応するため、美濃へと軍を移動させる。 |
| 6月 9日(天正11年 4月19日) | 柴田軍佐久間盛政による攻勢により羽柴勢の中川清秀が戦死。 |
| 6月10日(天正11年 4月20日) | 羽柴秀吉が大垣より前線に引き返し、丹羽長秀も琵琶湖を横断して賤ヶ岳の佐久間盛政を攻撃。 |
| 6月11日(天正11年 4月21日) | 前線から柴田勢の前田利家が撤退を開始し、その影響で柴田勢は混乱に陥る。羽柴軍が佐久間盛政を撃破したため、柴田勝家も退却。 |
| 6月14日(天正11年 4月24日) | 羽柴軍の攻勢により、北ノ庄城が落城。柴田勝家、お市の方ら一族80余名は自害。お市の方の3人の娘は、主筋だから身柄を保証するよう求めるお市の手紙とともに秀吉に引き渡された。佐久間盛政は加賀へと逃走を図るが捕らえられる。 |
| 6月19日(天正11年 4月29日) | 織田信孝が自害。 |
| 7月 1日(天正11年 5月12日) | 佐久間盛政が秀吉の臣下への誘いを断り、自害も拒否して処刑される。 |
| 7月(天正11年 5月) | 滝川一益が出家して秀吉に降伏する。 |
| シャイバニー朝ブハラ・ハン国王イスカンダルが死去し、実質上の最高権力者だった子のアブドゥッラーフ2世が10代目として即位。シャイバニー朝は最盛期を迎える。 | |
| エディンバラ大学開学(国王の勅許は前年)。 | |
| 1584年 | |
| 4月16日(天正12年 3月 6日) | 織田信雄が、3人の家老(浅井長時・岡田重孝・津川義冬)を秀吉方に与しているとして処刑。小牧・長久手の戦いが始まる。 |
| 4月27日(天正12年 3月17日) | 羽黒の戦い。小牧・長久手の戦いの一つ。 |
| 5月 4日(天正12年 3月24日) | 沖田畷の戦い。島津方に付いた有馬晴信を討伐するため出陣した龍造寺隆信が川上忠堅に討ち取られ、龍造寺軍は大敗を喫する。百武賢兼、成松信勝、江里口信常、円城寺信胤、木下昌直らもことごとく討ち死に。出兵を諌めた鍋島信生(直茂)もあわや7騎まで撃ち減らされるも、かろうじて脱出に成功。 |
| 5月18日(天正12年 4月 9日) | 長久手の戦い。羽柴秀吉勢と、織田信雄・徳川家康同盟軍が衝突。森長可、池田恒興、池田元助らが戦死する。 |
| 6月 9日(天正12年 5月 1日) | 羽柴秀吉が、正覚院豪盛と徳雲軒全宗に比叡山の再興を認める。 |
| 8月10日(天正12年 7月 5日) | 天正遣欧少年使節がポルトガルの首都リスボンに到着。ローマを目指し各国を訪問していく。 |
| 12月12日(天正12年11月11日) | 織田信雄が、羽柴秀吉の求めに応じて単独講和が成立する。徳川家康は名分を失い戦争は終結。近年、信雄が家康を説得する書簡なども発見されている。 |
| 1585年 | |
| 3月 1日 | 天正遣欧少年使節がローマ教皇グレゴリウス13世に謁見。ローマ市民権を与えられる。 |
| 3月31日(天正13年 3月 1日) | 羽柴秀吉による紀州根来攻めのため、小早川隆景に毛利水軍の進発を命じる。 |
| 4月 4日 | 八十年戦争のさなか、スペインによるアントワープ包囲戦(現ベルギー。当時はオランダ最大の都市)で、スヘルト川に掛かる橋を要塞化したスペインに対し、オランダ側が爆薬を満載した4隻の火船「ヘルバーナー」を投入。うち1隻が橋までたどり着き、スペイン人が調べているさなかに大爆発を起こす。スペイン人800人が死亡。元フリースラント総督のカスパー・デ・ロブレスも巻き込まれ死亡。 |
| 4月19日(天正13年 3月20日) | 羽柴秀次軍が和泉の紀州勢力攻めを開始。 |
| 4月21日(天正13年 3月22日) | 千石堀城が羽柴軍の火攻めを受けて落城。畠中城の城兵は城に火を放って逃走。 |
| 4月21日(天正13年 3月23日) | 貝塚御坊の卜半斎了珍の説得を受け、積善寺城が降伏。同日、沢城も降伏し、和泉から紀州・根来勢力は撤退。羽柴軍はそのまま根来寺攻略を開始。根来寺の伽藍の多くが炎上する。 |
| 4月22日(天正13年 3月24日) | 粉河寺、雑賀勢の有力者土橋氏、日高郡の有力者湯河氏も攻められる。 |
| 5月 9日(天正13年 4月10日) | 羽柴秀吉、高野山に降伏を勧告。 |
| 5月15日(天正13年 4月16日) | 高野山が秀吉に降伏。 |
| 8月 6日(天正13年 7月11日) | 羽柴秀吉が、近衛家の猶子となった上で関白に就任する。五摂家ではない上に公家でもない武家の秀吉が関白に就任するのは前代未聞の出来事。 |
| 8月17日 | アントワープがスペイン軍に降伏。住民の多くがアムステルダムへ移住し、後にオランダ黄金時代と呼ばれる繁栄を築く。 |
| 8月31日(天正13年 8月 7日) | 羽柴秀吉が越中の佐々成政討伐のため出陣。 |
| 9月12日(天正13年 8月19日) | 羽柴軍が越中に侵攻。また同時期に金森長近をして飛騨にも侵攻し、佐々成政と同盟していた姉小路頼綱や内ヶ島氏理らを攻撃。 |
| 9月19日(天正13年 8月26日) | 佐々成政が、織田信雄を介して羽柴秀吉に降伏。 |
| 11月29日(天正13年10月 8日) | 粟之巣の変。二本松義継が伊達輝宗を拉致して逃走を図るが、輝宗の子である政宗は父親もろとも義継を殺害。 |
| モンゴルのカラコルム近郊ハルホリンに仏教寺院エルデネ・ゾーが建立される。仏塔が連なる独特の長い外壁をもった大規模寺院。建築物の多くは共産党によって破壊されているが外壁などは現存。 | |
| 1586年 | |
| 1月 2日(天正13年11月13日) | 徳川家康の重臣で徳川家の外交交渉を担当した石川数正が豊臣秀吉のもとに出奔。 |
| 1月16日(天正13年11月27日) | 天正地震(前震)が発生。庄川断層のズレによるものか。 |
| 1月18日(天正13年11月29日) | 天正大地震が発生。養老断層のズレによるものか。2つの大地震は、ともに近畿全域、東海・北陸地方で大きな揺れをもたらす。飛騨の帰雲城は帰雲山の山体崩壊の直撃を受け、城下町もろとも埋没。秀吉によってほぼ本領安堵が決まった城主の内ヶ島氏一族はその祝宴のために在城していて一族滅亡の憂き目にあった(篠脇城主東常慶の子常堯も在城して死亡)。越中木舟城も倒壊し、城主になったばかりの前田秀継らが死亡。近江長浜城も倒壊し、山内一豊の娘と、助けようとした家老の乾和信らも死亡。ほかに美濃大垣城、尾張蟹江城、伊勢長島城も倒壊。京市中も大きな被害を出す。琵琶湖と、若狭湾・伊勢湾、富山湾などで津波を観測。三陸でも津波があったとされるが、別の地震の可能性もある。飛騨焼岳が噴火したという記録もある。かなりの死者があった模様。他に余震、誘発地震が複数起きている。 |
| 3月(天正14年 2月) | 聚楽第の建設が京の内野(かつての大内裏の跡地)で始まる。 |
| 8月28日(天正14年 7月14日) | 島津軍が大友領へ侵攻し、岩屋城の戦いが始まる。島津忠長らの島津軍2万以上が、大友側岩屋城の高橋紹運を攻めるが、高橋紹運は763名で防戦に徹する。 |
| 9月10日(天正14年 7月27日) | 岩屋城が陥落し、高橋紹運ら城兵は全滅。しかし半月もの籠城戦と兵の損害を受けて島津軍の侵攻は中断。 |
| 10月(天正14年 8月) | 奥熊野で国侍や農民らが一揆を起こす。天正の北山一揆。太閤検地が原因ともいうが詳細は不明。 |
| 11月 4日(天正14年 9月23日) | 羽柴秀長軍により北山一揆がほぼ鎮圧される。 |
| 11月(天正14年10月) | 島津軍が再び大友領へと侵攻を開始する。日向から侵攻した島津家久軍は豊後大野郡の諸城を次々と攻略し北上する。一方、肥後路から豊後へ侵攻した島津義弘軍は、志賀親次の岡城と周辺の支城の攻略に失敗。 |
| 12月 3日(天正14年10月23日) | 島津家久は栂牟礼城の佐伯惟定に降伏を勧告するが、惟定はこれを拒否。攻撃を開始した島津軍に対し、佐伯家の軍監となっていた山田匡得(日向伊東氏の家臣)が反撃を指揮して島津軍は大敗。これを受けて、先に島津方に降伏していた柴田紹安の家臣芦別大膳が佐伯勢に内応して星河城が陥落。柴田氏は滅ぼされる。岡城と栂牟礼城の攻略に失敗したことで、島津軍は戦略が狂うことになった。 |
| 1587年 | |
| 1月 5日(天正14年11月26日) | 島津家久は、大友宗麟の籠城する丹生島城の手前にある鶴賀城の攻略に取り掛かるが、城将利光宗魚、成大寺豪永らの徹底抗戦によって12月に入っても落とすことができず。 |
| 1月20日(天正14年12月12日) | 戸次川の戦い。鶴賀城攻略中の島津家久軍に対し、大友義統、仙石秀久、長宗我部元親、十河存保の軍勢が攻勢をかける。しかし仙石秀久の強行論と、長宗我部元親らの慎重論が対立し、意見が一致しないまま出撃にいたり、島津側が勝利。長宗我部信親、十河存保らが戦死する。 |
| 1月21日(天正14年12月13日) | 戸次川の勝利の勢いで、島津家久は豊後府内城を攻略。大友義統はすでに城を離れており、ほぼ抵抗なく占領した。一方、大友宗麟の籠もる海上の丹生島城には攻略に手間取り、宗麟がポルトガル人から手に入れたとされる複数の大砲「国崩し」(弾倉後装式のフランキ砲)による反撃もあり被害を出す。丹生島城の支城である鶴崎城は抗戦の末に降伏するが、このとき城代として指揮した妙林尼は、巧みに島津方をもてなして油断させ、豊臣軍の侵攻に便乗して奇襲をかけ大きな損害を与えたと言われる。 |
| 1月27日(天正14年12月19日) | 羽柴秀吉が、太政大臣となる。この頃、氏を藤原から豊臣朝臣に変えたと考えられる(当時は氏姓と名字は別であり、羽柴秀吉が豊臣秀吉になったわけではなく、羽柴藤原朝臣秀吉が羽柴豊臣朝臣秀吉になったということ)。 |
| 4月 8日(天正15年 3月 1日) | 九州征伐で秀吉が大坂を出陣。 |
| 7月24日(天正15年 6月19日) | 九州に遠征していた豊臣秀吉が、筑前箱崎においてキリスト教の布教に関する禁制を発する。バテレン追放令。 |
| 10月(天正15年 9月) | 聚楽第の大部分が完成する。 |
| 11月 1日(天正15年10月 1日) | 豊臣秀吉が北野天満宮の森で、北野大茶会を催す。 |
| 1588年 | |
| 2月 9日(天正16年 1月13日) | 形式的にも室町幕府が滅亡する。豊臣秀吉が島津氏を降服させるのに合わせるように足利義昭が将軍職を辞して出家。 |
| 5月 9日(天正16年 4月14日) | 後陽成天皇が聚楽第に行幸。 |
| 5月15日(天正16年 4月20日) | 黒田長政が、地元豊前の有力者だった城井鎮房を中津城に招いて謀殺。合元寺にいた城井家臣団もことごとく討ち取られる。また肥後国人一揆鎮圧のため出陣していた城井朝房も黒田孝高の手で殺害。鎮房の娘も磔に処せられ殺害された。黒田家は後々まで「城井家の呪い」に悩まされたという。なお懐妊していた朝房の妻龍子は子の宇都宮朝末を生んで父秋月種実のもとに逃れ、子孫は越前松平家に仕えた。鎮房の弟も薩摩に逃れたと言われる。 |
| 5月 | スペインの無敵艦隊が、イングランド侵攻のために出発。 |
| 7月31日 | スペインとイングランドによるプリマス沖海戦。いわゆるアルマダの海戦の始まり。イングランドではまだユリウス暦で7月21日。 |
| 8月 2日 | スペインとイングランドによるポートランド沖海戦。 |
| 8月 5日 | スペインとイングランドによるワイト島沖海戦。 |
| 8月 7日 | スペインとイングランドによるカレー沖海戦、続けてグラヴリンヌ沖海戦となる。 |
| 8月18日 | エリザベス女王が軍隊を鼓舞するためティルベリーで演説。 |
| 8月29日(天正16年 7月 8日) | 豊臣秀吉の刀狩令が発令される。百姓らの所有する刀のみを対象にしたもので、完全な武装解除ではなく、身分制を定めるためとも言われている。 |
| 8月 | アルマダの海戦で敗北したスペインの無敵艦隊が、補給のためアイルランドに向かうが、多くが座礁し、兵も殺される。 |
| 9月22日 | スペイン無敵艦隊の残存艦が母国に帰還をはじめる。兵の過半を失う。 |
| サファヴィー朝5代目君主として、アッバース1世がクズルバシュの支援を受けて即位。しかしアッバース1世はクズルバシュの権力を削ぎ、宮廷奴隷や異民族から有能な人材を抜擢し、衰退していた同王朝を復興させる。 | |
| 1589年 | |
| 1月21日(天正16年12月 5日) | 豊臣秀長の家臣で紀伊湊の領主吉川平介が、紀伊産材木の売買代金を着服したとして大和西大寺で処刑される。この一件は秀長も秀吉の不興を買ったという。秀吉政権の確立で京や大坂では建築ラッシュとなり、材木の需要が高まっていた。 |
| 1590年 | |
| 1月18日(天正17年12月13日) | 豊臣秀吉が、惣無事令の違反を咎めて、北条氏討伐の陣触れを発する。 |
| 5月19日(天正18年 4月11日) | 茶人で豪商だった山上宗二が処刑される。利休の弟子と言われ、秀吉の茶匠でもあったがその言動が秀吉の怒りを買い、北条氏のもとにいた。小田原の戦いが始まり、交流のあった北条方武将の皆川広照が秀吉側に投降した際に同行。利休の仲介で秀吉の赦免を受けたが、茶席で北条側に義理を立てる言動をしたため、秀吉の怒りを買って処刑された。茶道の秘伝書「山上宗二記」の作者で、同書の自筆写本は皆川広照にも贈られている。 |
| 7月 6日(天正18年 6月 5日) | 小田原遠征に関連して、忍城の攻防戦が始まる。 |
| 8月 4日(天正18年 7月 5日) | 北条氏直が豊臣秀吉に降伏、小田原城開城。 |
| 8月16日(天正18年 7月17日) | 北条側で唯一陥落しなかった忍城が開城する。 |
| 8月25日(天正18年 7月26日) | 豊臣秀吉が宇都宮に入り関東・東北各地の諸大名の配置を決定。宇都宮仕置、奥州仕置。徳川家康の関東移封、蒲生氏郷の会津移封、木村吉清の大崎移封、小田原に参陣した佐竹義重、岩城常隆・貞隆、津軽為信、戸沢盛安・光盛、南部信直ら各在地領主を本領安堵、遅れて小田原参陣した最上義光も本領安堵、相馬義胤も本領はほぼ安堵したが伊達氏との係争が惣無事令違反として一部領地替え、小田原参陣に遅れた伊達政宗は一揆扇動もあり減封、秋田実季は安藤通季との湊合戦が惣無事令違反で減封(ただし失った領地は太閤蔵入地となりその代官となる)、小野寺義道は仙北一揆を理由に減封、伊達氏に従属していた石川昭光・留守政景・田村宗顕・白河結城義親は小田原には参陣せず伊達政宗に仲介を頼むも認められず改易、葛西晴信、大崎義隆、和賀義忠、稗貫広忠、江刺重恒、黒川晴氏ら在地領主も小田原参陣せずに改易。ただ小田原参陣をしなかった領主でも参陣の予定が領内の事情でできなかったものや秀吉に反発してしなかったものなど事情は異なる。不満を持った領主らの反乱が相次ぐ一方、領地が確定して領主同士の係争関係が解消した地域もある。また早くから秀吉に接近し南部氏影響下から独立した津軽氏と南部氏との対立は江戸時代後期まで続く。 |
| 8月30日(天正18年 8月 1日) | 徳川家康が江戸城に入る。いわゆる八朔の記念日。 |
| 10月12日(天正18年 9月 4日) | 織田信長、豊臣秀吉が寵愛した絵師の狩野永徳が、東福寺法堂天井画の制作中に病で倒れ死去。 |
| 11月13日(天正18年10月16日) | 豊臣政権による奥州仕置で没落した在地領主等による反乱「葛西・大崎一揆」が起きる。改易された葛西晴信・大崎義隆の旧領13郡は木村吉清が入封したが、実際には旧主の影響が強く残っていたとも。木村吉清・清久親子は佐沼城に籠城。 |
| 11月23日(天正18年10月26日) | 伊達政宗と蒲生氏郷が「葛西・大崎一揆」の鎮圧で協力することで合意。 |
| 11月25日(天正18年10月28日) | 豊臣政権による奥州仕置で没落した在地領主等による反乱「和賀稗貫一揆」が起きる。和賀義忠、稗貫広忠らが主体となり、旧領の二子城を攻め落とし、同じく旧領の鳥谷ケ崎城に迫る。南部信直が応戦するも冬が到来したことで一旦三戸城へ引き上げ、鳥谷ケ崎城は一揆勢が入城。 |
| 12月11日(天正18年11月15日) | 蒲生氏郷のもとに伊達政宗の家臣の須田伯耆・曾根四郎助が「葛西大崎一揆」は政宗の扇動で起きたと訴え出て、政宗が出したとする密書を提出。蒲生氏郷は単独で出兵し豊臣秀吉に事態を通報。伊達政宗も独断で出兵。 |
| 12月20日(天正18年11月24日) | 蒲生氏郷が、佐沼城の一揆勢を打ち破って木村吉清・清久親子を救出。政宗に対し人質を要求し、政宗は伊達成実・国分盛重を送る。 |
| 1591年 | |
| 1月13日(天正18年12月18日) | 改易された大崎義隆が石田三成を介して謝罪したことから、豊臣秀吉は大崎義隆の旧領のうち3分の1を還すことを認める朱印状を出す。ただこの約束は実行されず。 |
| 2月 3日(天正19年 1月10日) | 葛西大崎一揆の調査のため、石田三成が現地に到着。 |
| 3月21日 | トンディビの戦い。ソンガイ帝国の王イツハーク2世は、スペイン生まれでサアド朝のアフマド・アル=マンスールに仕える軍事指導者ジュデル・パシャに敗北し、翌年サアド朝の攻勢で滅亡する。 |
| 3月28日(天正19年 2月 4日) | 葛西大崎一揆の弁明のため、伊達政宗が上洛し査問が行われる。政宗は一揆扇動の密書は捏造されたものと主張。秀吉は弁明を受け入れ政宗に対し一揆鎮圧を命じる。 |
| 4月21日(天正19年 2月28日) | 千利休切腹。 |
| 5月 6日(天正19年 3月13日) | 陸奥南部氏の一族である九戸政実が、南部一族の内紛から挙兵。九戸政実の乱。 |
| 7月29日(天正19年 6月 9日) | 九戸政実の乱に対応するため、南部信直が息子の南部利直と重臣の北信愛を秀吉のもとに派遣し支援を求める。 |
| 8月 9日(天正19年 6月20日) | 豊臣秀吉は奥州各所で起きている争乱に対応するため、再仕置軍を編成し派遣。豊臣秀次を総大将に、東日本各地の大名を動員して平定させる。稗貫広忠・和賀義忠は敗走し、稗貫広忠は大崎氏に匿われて出家、和賀義忠は落ち武者狩りにあって死亡したと言われる。 |
| 8月22日(天正19年 7月 4日) | 伊達政宗ら寺池城を攻め落とす。葛西大崎一揆は終息に向かう。 |
| 10月 1日(天正19年 8月14日) | 伊達政宗は葛西大崎一揆の関係者を集めて謀殺。 |
| 11月 9日(天正19年 9月23日) | 伊達政宗に一揆で荒廃した旧大崎義隆領の葛西・大崎13郡30万石が与えられ、代わりに伊達氏歴代の領地だった長井・信夫・伊達・安達・田村・刈田の6郡44万石が没収され蒲生氏郷に与えられる。この措置から、伊達政宗が冤罪を主張した一揆扇動に対する実質的な懲罰との見方が強い。なおこのあおりで大崎義隆の旧領回復の約束は反故にされたため、大崎義隆は蒲生氏郷、ついで上杉景勝に仕えた。 |
| 1592年 | |
| 2月11日(天正19年12月28日) | 豊臣秀吉が関白を辞職し、秀次が2代目の武家関白となる。太政大臣はもとのまま。 |
| (天正19年) | 豊臣秀次の名で人掃令が布告される。村単位で老若男女の人数と職分を記録提出させた政令。朝鮮出兵のための兵士・人夫の動員数を調べるのが目的だったものか。 |
| 5月24日(天正20年 4月13日) | 釜山近郊に上陸した豊臣軍が総攻撃を開始し、文禄の役が始まる。 |
| 1593年 | |
| 2月27日(文禄2年 1月26日) | 文禄の役、碧蹄館の戦い。日本軍と明軍が衝突し、日本軍が勝利をおさめる。中国では万暦21年。 |
| 5月30日 | 劇作家クリストファー・マーロウが酒場での喧嘩に巻き込まれて刺殺される。29歳。単なる事件ではなく、マーロウが諜報機関と関わっていたために謀殺された、マーロウが無神論を主張し結社に関わっていたため殺されたなどの説もある。またマーロウの死の前後にシェイクスピアが活動を始めており、作風に共通点があることから、マーロウがシェイクスピアになった説まである。 |
| 7月25日 | ユグノーのアンリ4世が、国民の支持を獲得するため、サン=ドニ大聖堂でカトリックに改宗。 |
| 1594年 | |
| 2月27日 | フランス王の地位についたアンリ4世が、正式に戴冠。ブルボン王朝初代フランス王となる。 |
| 10月 8日(文禄3年 8月24日) | 京で盗賊団が捕らえられ、その首領、石川五右衛門が処刑される。 |
| 12月 2日 | 地図製作者ゲラルト・デ・クレーマーが死去。一般にはゲラルドゥス・メルカトルと呼ばれる。メルカトルとはラテン語で「商人」という意味。メルカトル図法の原型を作った人物。 |
| 1595年 | |
| 3月17日(文禄4年 2月 7日) | 会津の大大名、蒲生氏郷が癌とみられる症状で死亡。40歳。蒲生家お家騒動の始まり。 |
| 8月13日(文禄4年 7月 8日) | 豊臣秀次の元に石田三成らが訪れ、高野山追放を伝える。 |
| 8月20日(文禄4年 7月15日) | 豊臣秀次、雀部重政、東福寺の僧・玄隆西堂が青巌寺で切腹(豊臣秀次事件)。 |
| 9月 5日(文禄4年 8月 2日) | 豊臣秀次の妻子ら39人が処刑され、遺体は地面に掘った穴に捨てられる。この事件で秀次の側室になる前だったにもかかわらず娘を処刑された最上氏は、豊臣家を恨み、徳川家へ接近することになる。 |
| 9月22日(文禄4年 8月19日) | 豊臣秀次の重臣で、秀吉の側近として活躍してきた前野長康が秀次事件の責めを受けて自害。 |
| 10月13日(文禄4年 9月10日) | 豊臣秀吉主催で、方広寺千僧供養が行われる。各宗派に出仕を命じたため、法華宗(日蓮宗)が受不施派と不受不施派に分裂する原因となった。 |
| 前年に亡くなったゲラルト・デ・クレーマー(ゲラルドゥス・メルカトル)の息子ルモルドが、父親の遺した世界地図107葉を完成させる。遺言で地図帳の名前を、ギリシャ神話の天を支える巨人の名前(もしくは最初に地球儀を作ったマウレタニアの王)から「アトラス」と名付けたため、地図帳のことをアトラスと呼ぶのが広まった(アトラスという呼び方自体はそれ以前にも見られる)。 | |
| 1596年 | |
| 9月 1日(文禄5年閏7月 9日) | 慶長伊予地震。 |
| 9月 4日(文禄5年閏7月12日) | 慶長豊後地震。瓜生島沈没伝説で知られる。 |
| 9月 5日(文禄5年閏7月13日) | 慶長伏見大地震。伏見城が崩壊し死者多数を出す。大和の大名で秀吉直参の横浜一庵も巻き込まれて圧死。石田三成との対立で謹慎中の加藤清正が、秀吉を救出して許されたという俗説もあるが真偽不明。方広寺の大仏も壊れたため、秀吉が怒り、破却させたとも言われる。阪神・淡路大震災と同じ震源域とする説もある。 |
| 10月?(文禄5年 9月) | 豊臣秀吉と明の使者との会談が行われるが、明側が秀吉に順化王の称号を与えて冊封しようとしたため、秀吉は、明の皇女の天皇への降嫁、朝鮮南半の割譲という秀吉の要求が一切認められてないのを知り、会談は決裂する。秀吉は再戦を決定。事前の講和交渉で小西行長・石田三成らと沈惟敬らの偽装講和の工作が裏目に出たとみられる。 |
| 12月16日(文禄5年10月27日) | 相次ぐ災害を受けて、慶長に改元。 |
| 12月23日(慶長元年11月 4日) | 服部正成(半蔵)死去。家康の重臣で伊賀衆・甲賀衆を率いる。 |
| 1597年 | |
| 2月 5日(慶長元年12月19日) | 長崎でキリシタンの日本二十六聖人が処刑される。日本人は20名で、スペイン人が4名、メキシコ人、ポルトガル人がそれぞれ1名。 |
| 5月26日(慶長2年 4月11日) | 徳川秀忠と江の娘、千姫生誕。 |
| 9月(慶長2年 8月) | 聚楽第に変わる豊臣氏の邸宅「京都新城」が完成する。当時は太閤御屋敷などと呼ばれた。のちの仙洞御所(現在の京都御所南東部)の位置に当たる。 |
| イングランドで最初の救貧法が制定される。貧困層が増加し、社会的不満が高まったことに対して、病気などで働けず貧困に陥った人々を救済する制度。 | |
| 朝鮮半島北部の白頭山(長白山)が大噴火を起こす。 | |
| 1598年 | |
| 4月20日(慶長3年 3月15日) | 豊臣秀吉が醍醐寺で豪華絢爛な花見を行う。いわゆる醍醐の花見。 |
| 4月30日 | フランス国王アンリ4世がナントの勅令を出して、プロテスタントの信仰を認め、ユグノー戦争以来の宗教紛争は終結。 |
| 9月18日(慶長3年 8月18日) | 豊臣秀吉、伏見城にて死去。 |
| 11月13日(慶長3年10月15日) | 朝鮮半島に在陣する諸将に対し、半島からの撤退命令が発せられる。 |
| サファヴィー朝のアッバース1世が王都をカズヴィーンからイスファハーンに遷す。同年、北のホラーサーン地方へ侵攻しこれを奪う。 | |
| 1599年 | |
| 4月 4日(慶長4年 3月 9日) | 薩摩藩主島津忠恒が、伏見島津邸内で、島津家宿老で日向庄内8万石の領主である伊集院忠棟を殺害。忠棟が謀反を企てたとも、中央政権に近かった忠棟を島津家が警戒したためとも、島津家の内紛に巻き込まれたとも言われる。 |
| 4月27日(慶長4年閏3月 3日) | 島津義久が、日向庄内地方への交通を遮断。伊集院忠棟の息子の伊集院忠真は家臣の白石永仙の意見を入れ、島津家に対し反乱を起こす。庄内の乱。 |
| 6月 5日(慶長4年 4月13日) | 豊臣秀吉を阿弥陀ヶ峰山頂に埋葬。麓には木食応其により鎮守社が創建される。 |
| 6月 8日(慶長4年 4月16日) | 朝廷より豊臣秀吉に豊国大明神の神号が与えられる。 |
| 6月10日(慶長4年 4月18日) | 鎮守社を元に豊国神社が設立される。 |
| 9月11日 | ベアトリーチェ・チェンチ斬首される。横暴で暴力的な父親を家族と共に殺害したことで家族ともども罪に問われた。背景にはチェンチ家の財産を狙ったローマ教皇クレメンス8世の暗躍も。 |
| 1600年 | |
| 2月17日 | ジョルダーノ・ブルーノが異端を理由に火刑に処せられる。ドミニコ会出身の神学者・哲学者で、当時カトリックで主流だった天動説とは異なる理論を主張。ヨーロッパ各地を転々としながら著作を発表した。各国でその優秀さが評価される一方、トラブルも多く、最終的に異端審問にかけられ有罪と認定された。1979年にヨハネ・パウロ二世によって名誉回復。 |
| 4月28日(慶長5年 3月15日) | 伊集院忠真が徳川家康の調停を受けて島津氏に降伏。庄内の乱も終結する。忠真は島津義弘の娘婿であり、再反乱も警戒されて、義弘が関ヶ原で島津家の支援を得られず孤立参戦の原因のひとつとなったという。また、加藤清正は忠真に密かに味方していたことが発覚して家康の怒りを買い、会津征伐(ひいては関ヶ原)に直接参戦できなかった(九州で東軍方についている)。 |
| 4月29日(慶長5年 3月16日) | オランダの極東船団で唯一アジアまでたどり着いたリーフデ号が豊後の臼杵に漂着。 |
| 9月 8日(慶長5年 8月 1日) | 伏見城の戦いで伏見城が落城。関ヶ原の戦いの前哨戦。 |
| 10月21日(慶長5年 9月15日) | 関ヶ原の戦い。徳川家康率いる東軍が勝利し、石田三成の西軍は壊滅。 |
| 10月24日(慶長5年 9月18日) | 石田家の佐和山城落城。開城交渉が進んでいるさなかに城内にいた長谷川守知が東軍に寝返り(間者だったとも)、これに乗って東軍に寝返っていた小早川秀秋、小川祐忠、脇坂安治と、東軍の田中吉政が城を攻撃したため、石田一族は自刃。石田方で開城交渉にあたっていた石田正澄の家臣津田清幽はこれに激怒し、人質をとって旧知の徳川家康の陣へ赴き抗議。家康が非を認め、清幽が連れてきた三成の子と11人の石田家臣を助命している。 |
| 10月26日(慶長5年 9月20日) | 伊達政宗が、上杉景勝を巡る一連の騒乱「慶長出羽合戦」に乗じて、庇護していた和賀忠親を扇動し二子城で蜂起させ南部領へ侵攻させる。通称「岩崎一揆」。和賀忠親らは南部氏が出羽合戦や田瀬・安俵一揆に出兵して手薄の花巻城を夜襲。しかし和賀氏の縁者でもあった柏山明助の通報で知った城主北信愛の指示でわずか十数名で籠城。南部勢の援軍到着を受けて一揆勢は退却。蜂起は失敗に終わる。柏山明助はこの功で南部氏に仕え、伊達政宗はこの一件が露見してしまい、徳川家康よりの「百万石のお墨付き」を反故にされてしまった。 |
| 10月27日(慶長5年 9月21日) | 石田三成が田中吉政の軍勢によって捕縛される。 |
| 11月 4日(慶長5年 9月29日) | 長曾我部元親の三男の津野親忠が謀殺される。父との諍いで幽閉されていたが、関ケ原の敗戦を受け、旧知の藤堂高虎・井伊直政らを通じて長宗我部家の本領安堵を徳川家康に願い出るも、長宗我部家重臣の久武親直の讒言で殺された。長宗我部家が改易された理由の一つとされている。 |
| 11月 6日(慶長5年10月 1日) | 石田三成が京の六条河原で処刑される。一方で三成の子どもたちはいずれも家康から助命されたり落ち延びるなどして、子孫は津軽氏や各松平家の庇護も受け、次女の子孫は徳川家光の側室となり、尾張徳川家、公卿の二条家と九条家を経て皇室にまで血が繋がっている。 |
| この年、南米アンデス山脈のワイナプチナ山が大噴火を起こす。 | |
| 1601年 | |
| 1月 5日(慶長5年12月 1日) | 土佐浦戸一揆。関ケ原の戦いで西軍についた長宗我部氏が改易され、井伊直政が浦戸城の明け渡しを求めたのに対し、長宗我部家の一領具足らがこれを拒否し一揆を起こす。長宗我部家重臣の桑名吉成らが一揆勢を浦戸城外に出して鎮圧。 |
| 1月 9日(慶長5年12月 5日) | 浦戸城が徳川方に接収される。 |
| 2月10日(慶長6年 1月 8日) | 山内一豊が浦戸城に入る。 |
| イングランドでエリザベス救貧法が制定される。救貧法を改正し、国家管轄のもとで救貧を行うようにした初の法令。労働不能者の救済や孤児の養育をすすめる一方、健常な貧困層に強制労働させるなどの問題も残る。 | |
| 12月26日(慶長6年閏11月 2日) | 江戸で大火。記録上最初の江戸の大火だが詳細は不明。 |
| この年、異常気象の影響で、西ヨーロッパでぶどうの収穫が激減。ワインの生産が大打撃を受ける。また各地で飢饉と疫病が広がったという。前年のワイナプチナ山の大噴火が原因という説が有力。 | |
| ロシアでも寒冷気候によって穀物生産が壊滅的な打撃を受け、1603年にかけて大飢饉が起き、人口の3分の1に当たる200万人が死亡したと言われる。その後の大動乱の要因ともなった。 | |
| 1602年 | |
| 10月 2日(慶長7年 8月17日) | 薩摩藩主島津忠恒が上洛の途中、日向野尻で催した狩りの最中に、同行させていた伊集院忠真を射殺。表向きは押川則義と淵脇平馬の誤射とされ、両人は切腹。しかし忠真の妻と娘を除く家族も同じ日に殺害されており、計画的暗殺であった。なお重臣平田増宗の嫡男宗次も巻き添えで死亡しているが、のちに増宗ら一族も処罰されており、島津家の内紛にともなう暗殺説もある。 |
| 12月 1日(慶長7年10月18日) | 岡山藩主、小早川秀秋が21歳で死去。 |
| 1603年 | |
| 1月15日(慶長7年12月 4日) | 再建中の方広寺大仏殿と大仏が失火により焼失。 |
| 3月24日 | イングランド女王エリザベス1世がリッチモンド宮殿で死去。生涯結婚をせず、後継者も定めなかった。 |
| 3月24日(慶長8年 2月12日) | 後陽成天皇が勧修寺光豊を派遣し、徳川家康を征夷大将軍、右大臣、源氏長者・淳和院奨学院両院別当に任ずる。江戸開幕。 |
| 5月 8日(慶長8年 3月27日) | 二条城で徳川家康の将軍就任の祝賀の儀が行われる。 |
| 5月26日(慶長8年 4月16日) | 徳川秀忠が右近衛大将に任官される。征夷大将軍ではない秀忠の任官は、次期将軍を意味する。 |
| 7月25日 | スコットランドの王ジェームズ6世が、イングランド王ジェームス1世としても戴冠し、イングランドとスコットランドの同君連合が成立。 |
| 9月21日(慶長8年 8月16日) | 山形藩主最上義光の長男で、ほぼ後継者の立場にあった最上義康が失脚し暗殺される。義康側近の浦山源左衛門、寒河江良光らも殺害された。元々義光と義康の親子関係は良好で、文武両道の義康は君主の資質も備えた人物だったが、義光の近臣里見氏らによる讒言、義康が豊臣家や伊達家と親しかったこと、徳川家康の近侍となっていた次男の最上家親を後継者にしたほうが得策と考えたことなどから、親子関係が悪化して起きたとされる事件。しかし義光が命じたかは不明で、義光は義康の死後、失意で病がちになったとも言われる。里見一族は後に誅殺された。この事件は後の最上騒動の遠因にもなった。 |
| 12月16日(慶長8年11月14日) | 米子藩中村一忠の重臣横田村詮が、藩主の慶事の催しの最中に暗殺される。米子の開発に辣腕を振るった横田を妬み権力を握ろうとした藩主の側近安井清一郎、天野宗杷らが、14歳の藩主一忠に讒言したため。横田は三好一族で、中村一氏に抜擢され、中村家本領安堵の際に家康から家老に任命された経緯から、家康はこの事件に激怒。首謀者の安井、天野両人を切腹させた。中村一忠にお咎めはなかったが、これが心理的に尾を引いたのか、20歳で死去し米子藩は無嗣断絶として改易となった(側室との子はいたが鳥取藩池田氏に仕える)。 |
| 星図書『ウラノメトリア』が発刊される。編纂したヨハン・バイエルは天文の専門家ではなかったが、同書は天文学に大きな影響を与え、同書に記載された星の命名規則バイエル符号は現在でも使われている。 | |
| 1604年 | |
| 3月 4日(慶長9年 2月 4日) | 江戸幕府が、大久保長安を奉行に、東海道・東山道・北陸道に一里塚の設置をはじめる。 |
| 10月 9日 | 超新星SN1604が地球上で初めて観測される。へびつかい座20,000光年以内。通称ケプラーの星。銀河系内で起こったものとしては記録上最後に観測された超新星(超新星自体は珍しくないが、地球から観測できていないだけと考えられる)。 |
| 10月17日 | この日、超新星SN1604をヨハネス・ケプラーが観測し記録を残す。ケプラーの星と呼ばれる所以。18ヶ月輝き、金星に次いで明るかったとされる。白色矮星に降着した物質による質量増大で引き起こされたIa型超新星爆発とみられる。 |
| 1605年 | |
| 2月 3日(慶長9年12月16日) | 大規模な地震が発生。マグニチュードは推定7.9。地震そのものの被害より、大津波による被害の記録が多く、伊豆諸島、遠江、紀伊、阿波、土佐などで大きな被害を出す。 |
| 5月24日(慶長10年 4月 7日) | 徳川家康が、朝廷に将軍職の辞任と、嫡子秀忠の推挙を奏上。 |
| 6月 2日(慶長10年 4月16日) | 徳川秀忠が征夷大将軍に任じられる。 |
| 7月13日(慶長10年 5月27日) | 織田秀信が死去。織田信忠の嫡男で、信長の孫。岐阜中納言。関ケ原で西軍に付いたため、改易され高野山に送られたが、高野山で冷遇され、山麓の向副に追放され同地で死去した。病死とも自殺とも言う。26歳。真偽不明ながら子孫とされる人物が各地にいる。 |
| 9月 6日(慶長10年 7月23日) | かつて二条昭実と関白の座をめぐって争い、その結果、豊臣秀吉に関白の地位を奪われた近衛信尹が関白に就任する。 |
| 11月 5日 | イングランドの国王ジェームズ1世を国会もろとも爆殺しようと計画された火薬陰謀事件で、実行直前に主要メンバーのガイ・フォークスが逮捕される。 |
| 1606年 | |
| 4月12日 | イングランド王ジェームス1世がユニオンフラッグを制定する。 |
| 4月25日 | 神聖ローマ帝国にある、プロテスタントが多数を占める帝国自由都市ドナウヴェルトで、カトリック信徒が行進しようとしたのを市の評議員が止めようとして対立に発展。 |
| 1607年 | |
| 2月(慶長12年 2月) | 公卿で左近衛少将の猪熊教利が宮中の女官と密通したことが後陽成天皇に露見し、勅勘を受けて追放される。しかしまもなく密かに戻って公卿らと乱交に耽るようになる。 |
| 4月 5日(慶長12年 3月 9日) | 徳川家康の元側近で駿河興国寺藩主の天野康景が改易される。同藩の藩材を盗んだ人物を追った家臣が天領領民を殺傷した事件で、家康から派遣された本多正純の発言に康景が腹を立て、一族とともに領地を捨てて出奔したため。 |
| 4月25日 | ジブラルタルの海戦。八十年戦争で、オランダ海軍艦隊が、ジブラルタルに入港していたスペイン艦隊を奇襲し圧勝する。 |
| 8月16日(慶長12年 6月24日) | 御牧藩主津田高勝、清水藩主稲葉通重、旗本天野雄光、織田有楽斎の子の織田頼長らが、祇園で酒宴した際に商人の妻女らに狼藉を働くなどの事件を起こす。津田、稲葉、天野は改易。織田も咎めを受けたとされる。 |
| 10月26日 | 佐賀藩の主権回復を訴えていた龍造寺高房が急死。一説には藩を事実上支配した鍋島家への恨みで、妻である直茂の孫娘を殺害して自殺をはかり、その傷が悪化して死亡したとも言われる。 |
| 10月27日 | 彗星が出現し、ヨハネス・ケプラーが観測する。ハレー彗星。 |
| 神聖ローマ帝国皇帝ルドルフ2世が帝国自由都市ドナウヴェルトに対して「帝国アハト刑」の適用を決め、弟のカトリック教徒であるバイエルン公マクシミリアンに執行を命じて軍を派遣させる。同市はバイエルンに接収される。さらにカトリックとプロテスタントの和約であったアウクスブルクの和議を修正する動きを見せたため、プロテスタント側の反発を買う。 | |
| 1608年 | |
| 5月14日 | 神聖ローマ帝国に属するプロテスタント派の諸侯らが、プファルツ選帝侯フリードリヒ4世を盟主としてプロテスタント同盟(ウニオン)を結成。 |
| 7月27日(慶長13年 6月16日) | 丹波八上藩主前田茂勝が改易となる。茂勝が発狂したため、という理由だが、酒色に溺れて政務を見なくなった茂勝を諌めた尾池清左衛門親子らを茂勝が殺害したことで、尾池を知っていた徳川家康の怒りを買ったためと言われる。 |
| 10月 2日 | ハンス・リッペルハイが、凸レンズと凹レンズを組み合わせた実用的な屈折式望遠鏡を世界で初めて開発し、この日特許を申請。この技術情報が広まって、翌年ガリレオ・ガリレイがより高倍率の望遠鏡を開発したことからガリレオ式とも言う。 |
| イングランドでカルヴィン裁判の判決が出される。臣民とは国王との個人的関係であり、イングランドとスコットランドが同君連合になったあとにスコットランドで生まれたカルヴィンは、スコットランド王の臣民であり、スコットランドの王はイングランドの王であるため、カルヴィンはイングランド王の臣民と認められ、イングランド王の保護の元、イングランドの土地を所有する権利を有するというもの。国籍の出生地主義(血統に関係なく生まれた場所の国籍を得られる)を明文化した先例。 | |
| (慶長13年) | 幕府が永楽通宝の通用を禁ずる。国産の慶長通宝が十分でなかったため、実際にはこの後も流通していたとみられる。また、永楽銭を年貢貫高の計算基準とする永高も引き続き使われた。永楽銭は本来明銭だが、国内流通規模から国内で私鋳されていた説も有力。 |
| カール1世リヒテンシュタインが、神聖ローマ皇帝となった主君のマティアス・ハプスブルクより侯爵に叙任される。現在まで続くリヒテンシュタイン家の直接の始祖となる。現在のオーストリアとスイスの間にあるリヒテンシュタイン国は後に購入した領土の一部(シェレンベルク=ファドゥーツ領)で、この頃はニーダーエスターライヒや、モラビア、シュタイアーマルク、シレジアなど各地を領有していた。 | |
| (慶長13年) | 伊賀上野藩主筒井定次が改易される(筒井騒動)。定次の寵臣であった中坊秀祐が徳川家康に定次の悪政や不行状を訴えたためとされる。しかし定次は伊賀の開発を進めた人物でもあるため、悪政は口実で、家康が豊臣寄りで要衝を領する筒井氏を排除するために中坊秀祐を利用したという説もある。伊賀には藤堂高虎が入封された。中坊は旗本に取り立てられ奈良奉行に抜擢されている。 |
| 1609年 | |
| 4月 3日(慶長14年 2月29日) | 筒井騒動のきっかけを作り、筒井家が改易になった後、旗本として奈良奉行の地位についていた中坊秀祐が急死。筒井家の旧臣山中氏に暗殺されたと言われる。 |
| 7月10日 | 神聖ローマ帝国に属するカトリックの諸侯らが、プロテスタント同盟(ウニオン)に対抗してカトリック連盟(リーガ)を結成する。 |
| 7月~8月(慶長14年 7月) | 猪熊教利と公卿らが、女官らと乱交を繰り返していたことが、後陽成天皇の耳に達し、天皇は激怒。全員を死刑にせよと命じる。いわゆる「猪熊事件」が発覚し、幕府が調査に乗り出す。猪熊教利は日向へ逃亡するも懸藩領内で捕らえられる。 |
| 10月20日(慶長14年 9月23日) | 朝廷の大スキャンダル「猪熊事件」の関係者の処罰が決まる。中心人物の左近衛少将猪熊教利と宮中歯科医の兼康頼継が斬首。左近衛権中将の大炊御門頼国(甑島流罪)、いずれも左近衛少将の花山院忠長(蝦夷松前流罪)・飛鳥井雅賢(隠岐流罪)・難波宗勝(飛鳥井の弟、伊豆流罪)・中御門宗信(硫黄島流罪)、新大典侍広橋局・権典侍中院局・中内侍水無瀬・菅内侍唐橋局・命婦讃岐の女官5人が伊豆新島に流罪、参議烏丸光広と右近衛少将徳大寺実久は赦免された。後陽成天皇は処分が軽いと非常に不満だったという。 |
| 10月26日(慶長14年 9月29日) | 三河水野藩主水野忠胤の江戸屋敷で、親族の浜松藩主松平忠頼を茶席に招いた際、水野の与力であった久米佐平次と服部半八郎が口論となり、それを仲裁しようとした忠頼を、久米佐平次が刺し殺すという事件が起きる。水野忠胤は責任を問われて切腹、水野藩は改易、服部半八郎も切腹となり、殺された忠頼の浜松藩も改易となった。浜松は混乱状態になり、水野一族が鎮圧。忠頼の嫡男忠重はのちに掛川藩主として大名に復帰した。 |
| 1610年 | |
| 1月 6日(慶長14年12月12日) | マードレ・デ・デウス号焼き討ち事件。マカオでのトラブルを受けて、長崎に寄港したデウス号を有馬晴信が家康の許可を得て攻撃し撃沈する。これがその後の岡本大八事件へ発展し、有馬晴信が改易されることに。 |
| 1月 7日 | 木星の衛星イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストがガリレオの観測によって発見される。いわゆるガリレオ衛星。 |
| 3月26日(慶長15年閏2月 2日) | 越後福嶋騒動。越後福嶋藩45万石の家老職を巡って、死去した家老堀直政の長男で三条藩主の堀直清と、その異母弟の坂戸藩主堀直寄が争い、この日、駿府城で福嶋藩主堀忠俊と、堀直清、堀直寄らが呼び出されて徳川家康・秀忠の審問を受ける。家康は直清が年少の藩主を利用した讒臣として改易、藩主忠俊も大藩主の器にあらずとして改易を決定。直寄の言い分は通ったものの、飯山藩4万石に減らされ転封となった。 |
| 5月10日 | 中国にヨーロッパ文化を伝え、宣教活動を行う一方、中国文化を西洋に紹介したマテオ・リッチが北京で死去。 |
| 9月24日(慶長15年 8月 8日) | 織田秀雄が江戸で死去。織田信雄の嫡男で参議・越前大野城主だったが関ケ原で西軍に属したため改易。その後は江戸で暮らしたと言う。父親に先立っての死去。27歳。 |
| 12月 3日(慶長15年10月18日) | 徳川家康の側近中の側近で、徳川四天王に数えられた猛将、本多忠勝が死去。 |
| 1611年 | |
| 4月18日 | ジョン・セーリス率いる日本派遣船団がイングランドを出発。 |
| 5月10日(慶長16年 3月28日) | 徳川家康と豊臣秀頼が京の二条城で会見。 |
| 8月 2日(慶長16年 6月24日) | 肥後熊本藩主の加藤清正死去。徳川家康と豊臣秀頼との会見に警護で同行した帰りの船中で発病したことから、会見時に毒をもられたという説もある(同じ会見に同行した平岩親吉が年末に、浅野幸長と池田輝政も2年後に死去しているため出た説か)。 |
| 9月27日(慶長16年 8月21日) | 会津で大きな地震。3700人が死亡。山崩れで会津川と只見川が河道閉塞し氾濫。 |
| 10月30日 | グスタフ2世アドルフが17歳でスウェーデン王に即位。スウェーデンを軍事大国化し「北方の獅子王」と呼ばれた人物。 |
| 12月 2日(慶長16年10月28日) | 慶長三陸地震。大津波が起き、仙台藩で1783人が死亡、南部藩・津軽藩領内では人馬3000あまりが死ぬ。 |
| デンマーク=ノルウェーとスウェーデンの間でカルマル戦争が起こる。 | |
| ヨハネス・ケプラーが、凸レンズと凸レンズの組み合わせの望遠鏡のアイデアを発表(制作はせず)。いわゆるケプラー式屈折望遠鏡。 | |
| 1612年 | |
| 5月13日(慶長17年 4月13日) | 宮本武蔵と佐々木巌流(岩流・小次郎)が舟島(巌流島)で決闘。佐々木巌流が倒される。 |
| 6月 5日(慶長17年 5月 6日) | 岡本大八事件で領地獲得のために贈賄を行ったとして流罪になっていた有馬晴信が切腹を命ぜられ、キリスト教徒であったため、妻たちの見守る中で家臣に首を切り落とさせて死す。 |
| 11月 9日(慶長17年10月17日) | 越前騒動。藩の重臣久世但馬守の領民と岡部自休の領民との争いから、重臣同士の対立に発展。久世派に家老の本多富正、重臣の竹島周防守・由木景盛・上田隼人らが、岡部派に家老の今村盛次・中川一茂・清水孝正らが参加。今村らが兵を出して北ノ庄城を押さえ、藩主忠直の身柄を確保し竹島周防守を捕縛し投獄。 |
| 11月12日(慶長17年10月20日) | 越前騒動。今村盛次らが藩主の名前で久世派の本多富正に対し、久世但馬守を切腹させるよう命令を出す。久世は切腹を拒否し本多はやむなく久世一派を討伐し、久世但馬守と家臣らは全員討ち死にもしくは自害。 |
| 11月13日(慶長17年10月21日) | 越前騒動で今村盛次らは久世派の由木景盛・上田隼人を自害させ、その家臣らを討伐。岡部・今村派が騒動に勝利し幕府に報告。しかし幕府は越前藩祖結城秀康が家康の次男ながら秀吉の養子だった関係で豊臣家とも関係が深く、騒動が大坂方に利用されることを警戒して調査に乗り出す。 |
| 1613年 | |
| 1月13日(慶長17年11月27日) | 徳川家康と秀忠は越前騒動の関係者を江戸城に呼び出し裁定を行う。当初は今村派の主張が優位に立ったが、本多正信の介入もあり、本多富正の久世但馬討伐の際に今村派が後ろから銃撃したことや、今村盛次の越権行為などが問題視され、それに今村が若年である藩主忠直の責任を出したことで家康の怒りを買い、騒動の結末とは逆に岡部・中川らは流罪、今村・清水らは各藩へ預けとなり、本多ら久世派はお咎めなしとなった。なお竹島周防守は今村らに罪人扱いを受けたことを恥じて自害。 |
| 1月20日 | デンマーク=ノルウェーとスウェーデンの間でクネレド条約が結ばれ、カルマル戦争は終結。デンマークは莫大な賠償金を獲得したが、スウェーデンはその代償に領土保全に成功。 |
| 4月25日(慶長18年 6月13日) | 幕府勘定奉行大久保長安が死去。優れた財務官僚として江戸幕府草創期の財政を一手に支えた人物。 |
| 6月11日(慶長18年 4月23日) | ジョン・セーリス率いるイングランドの日本派遣船グローブ号が平戸に到着。<イングランド王からの書状と献上品を幕府に提出。 |
| 8月24日(慶長18年 7月 9日) | 大久保長安の子息7人が切腹に追い込まれる。長安の莫大な不正蓄財が主な原因とされるほか、長安が所属した老中大久保忠隣と本多正信らとの対立や、大久保忠隣の権勢を排除する目的が原因とする説もある。この後に起こる複数の大名の改易にも影響したとされている。 |
| 9月26日(慶長18年 8月12日) | 盗賊の向崎甚内(高坂甚内)が密告によって捕らえられ、この日、浅草鳥越で処刑される。様々な伝承が広まり、処刑の際に、「我は瘧に罹らなければ捕まることはなかった。我の魂魄はこの世に長く残るゆえ、瘧に悩むものは我に祈るがよい。そのものの瘧を治してやろう」と言い残したため、彼を祀る甚内神社が創られたという。 |
| 10月28日(慶長18年 9月15日) | 伊達政宗がヨーロッパへ派遣する使節団が陸奥国月の浦を出港。ルイス・ソテロを正使、支倉常長を副使とする。いわゆる慶長遣欧使節。目的は貿易の交渉であったという説もある。 |
| 10月28日(慶長18年10月 1日) | 上野板鼻藩主里見忠重(義高)が、職務怠慢を理由に改易される。改易後は妻の弟である酒井忠勝の家臣となった。後に僧侶となり、民衆を救うために即身仏になった伝承がある。 |
| 11月19日(慶長18年10月 8日) | 伊予宇和島藩主富田信高が改易される。信高夫人の弟で石見津和野藩主坂崎直盛の婢と夫人の甥の宇喜多左門が密通したことを知った直盛がその婢を家臣に斬らせたところ、左門がその家臣を殺害。直盛の父宇喜多忠家が左門を出奔させ当時伊勢津藩主だった富田信高に預けたために、直盛と信高の対立に発展。直盛は家康に訴えたが取り合ってもらえず、信高は宇和島に転封。左門は日向懸藩主高橋元種のもとに身を寄せたが、信高夫人が密かに支援していたことが発覚。幕府は夫人の行動を問題にし、富田信高を改易とした。ただ罪が曖昧なことから、大久保長安事件の縁者として連座したとも言われる。 |
| 12月 5日(慶長18年10月24日) | 日向懸藩高橋元種が改易される。富田信高と坂崎直盛の争いの要因となった直盛の甥宇喜多左門を密かに匿っていたことが発覚したため。元種は棚倉藩主立花宗茂に預けられる。 |
| 12月 5日(慶長18年10月24日) | ジョン・セーリスが平戸から出国。家康からは貿易の朱印状が下されて、平戸にイングランド商館を開設し、商館長にリチャード・コックスを残す。翌年イングランドに帰国し、国王に献上品を提出した後、日本から持ち帰った品々はイングランドで最初のオークションにかけられた。 |
| 1614年 | |
| 1月28日(慶長18年12月19日) | 慶長遣欧使節の一行がヌエバ・エスパーニャのアカプルコに到着。日本人として初めて太平洋を横断。 |
| 2月27日(慶長19年 1月19日) | 小田原藩主大久保忠隣が突如改易される。京でキリシタン取締の任を開始した翌日、所司代板倉勝重より言い渡された。理由として常陸牛久藩主山口重政の息子と、自身の娘との婚儀を幕府の許可無く進めたためとされる(山口重政も改易)。本多正信との対立、謀反の噂が流れた、豊臣方や上方大名との関係を疑われたなどの説もある。 |
| 5月24日(慶長19年 4月16日) | 豊臣秀頼による方広寺大仏殿の再建にあわせて梵鐘が完成する。しかし銘文「国家安康・君臣豊楽」が徳川家康の名を分断し豊臣家の繁栄を謳ったものだとして問題に。言いがかりとも取れるが、諱を分けるのは当時はかなり重大な問題でもあった。もっともこの鐘は豊臣氏滅亡後も特に鋳潰されてはいない。 |
| 6月10日(慶長19年 5月 3日) | 慶長遣欧使節の一行がヌエバ・エスパーニャ大西洋側のベラクルスを出港。ハバナを経由してスペインへ向かう。 |
| 9月 1日(慶長19年 7月27日) | 下野佐野藩主佐野信吉が改易される。表向きの理由は前年に改易された兄の富田信高に連座したものとされるが、大久保長安事件や大久保忠隣改易の連座とも言われる。 |
| 10月 5日(慶長19年 9月 2日) | 慶長遣欧使節の一行がスペインのサンルーカル・デ・バラメーダに上陸。日本人で初めて大西洋を横断。 |
| 11月 2日(慶長19年10月 1日) | 豊臣秀頼の重臣片桐且元が大坂城を退去。徳川方との内通を疑われ、他の重臣たちとの不和が解決しなかったため。これが大坂の陣の直接の理由とされた。 |
| 11月26日(慶長19年10月25日) | 東北から四国に至るかなり広範囲で地震を観測。池上本門寺五重塔が傾いたほか、銚子や越後高田で津波を観測、京でも多数の負傷者、大坂では寺社の被害が大きく、伊予松山の温泉が一時的に涸れたなどの記録がある。ただ被害が広範囲なことから震源域がはっきりせず、一部の被害を疑問視する説もある。 |
| 12月19日(慶長19年11月19日) | 大坂木津川口で徳川・豊臣両軍が衝突。大坂冬の陣の始まり。 |
| 12月26日(慶長19年11月26日) | 鴫野・今福の戦い(大坂冬の陣)。 |
| 12月29日(慶長19年11月29日) | 博労淵の戦い、野田・福島の戦い(大坂冬の陣)。 |
| 1615年 | |
| 1月 2日(慶長19年12月 3日) | 大坂城南・真田丸を巡る戦いで徳川方に大きな損害が出る(大坂冬の陣・真田丸の戦い)。同時に和睦交渉も始まる。 |
| 1月15日(慶長19年12月16日) | この頃より徳川・豊臣両軍の砲撃戦が激しくなる(大坂冬の陣)。徳川軍は海外から輸入した大型砲を投入。大坂城本丸付近にも着弾し淀殿の側仕えのものが死傷するなどして豊臣方に動揺が走る。 |
| 1月19日(慶長19年12月20日) | 徳川・豊臣両軍の間で和睦が成立。大坂冬の陣が終結する。 |
| 1月27日(慶長19年12月28日) | 今川氏真が江戸で死去。 |
| 1月30日(慶長20年 1月 2日) | 慶長遣欧使節の一行が、スペイン国王フェリペ3世に謁見。 |
| 2月 4日(慶長20年 1月 8日) | キリシタン追放でマニラに移った高山右近が客死する。 |
| 4月12日(慶長20年 3月15日) | 大坂城の浪人処遇問題で豊臣・徳川の間で再び対立が起こる。 |
| 5月 1日(慶長20年 4月 4日) | 徳川義直の婚儀に出席するという理由で、徳川家康が駿府を出立。 |
| 5月 3日(慶長20年 4月 6日) | 徳川家康が、諸大名に軍令を発する。 |
| 5月 7日(慶長20年 4月10日) | 徳川家康が名古屋に到着。徳川秀忠も江戸を出発。 |
| 5月15日(慶長20年 4月18日) | 徳川家康が京に入る。 |
| 5月18日(慶長20年 4月21日) | 徳川秀忠が京に入る。翌日、徳川軍の軍議が開かれる。 |
| 5月24日(慶長20年 4月27日) | 大和郡山城の戦い。豊臣軍の大野治房、箸尾高春、細川兵助ら2000の兵が大和郡山城を攻撃。大坂夏の陣の始まり。1万石の大和郡山藩主筒井定慶には僅かな兵しかなく、浪人や農民ら1000人ほどを集めて応戦したが、侵攻軍の兵数を見誤り、多勢に無勢と判断して城を放棄し福住中定城へと落ち延びた。筒井定慶は大坂落城後の5月10日に逃亡を恥じて自害したとも言われるが、逼塞して生き延びたという説もある。 |
| 5月26日(慶長20年 4月29日) | 樫井の戦い。豊臣軍の大野治房、塙直之、岡部則綱、淡輪重政らが、徳川方の浅野長晟を攻撃。豊臣方は一揆を起こす予定だったが失敗し、また武将間の連携が取れず大敗。塙直之、淡輪重政らが討ち死にする。 |
| 6月 2日(慶長20年 5月 6日) | 道明寺・誉田の戦い。大和路を大坂へ向けて進軍する徳川軍に対し、豊臣方の後藤基次が迎撃。連携が出来ないまま、明石全登、薄田兼相、さらに真田信繁らが順次援軍に来るも間に合わず、後藤基次、薄田兼相らが相次いで討ち死にする。同日、河内路を進む徳川本隊に対して、木村重成、長宗我部盛親、増田盛次らが奇襲をかけ一定の戦果を上げるも、衆寡敵せず木村重成らが討ち死に(八尾・若江の戦い)。 |
| 6月 3日(慶長20年 5月 7日) | 天王寺・岡山の戦い。天王寺口に集結した豊臣方は、野戦築城の上で、真田信繁・毛利勝永・大野治房・大谷吉治・御宿政友・明石全登らが猛攻し、徳川方は総崩れとなる。先鋒大将の本多忠朝が討ち死に、小笠原秀政が重症を負い(後死亡)、徳川旗本衆も壊乱。家康自身も敗走し援軍に出た秀忠の陣も混乱状態に陥るなどの事態になるが、豊臣方の被害も大きく、最終的に兵力差で徳川方が勝利。真田信繁らは討ち死に。毛利勝永は残存部隊を率いて大坂城へ撤退。午後4時ころ大坂城が炎上する。 |
| 6月 4日(慶長20年 5月 8日) | 豊臣秀頼・淀殿が自刃。介錯を務めた毛利勝永も自刃し、大坂の陣は終結。豊臣姓羽柴宗家は滅亡する。 |
| 6月26日(慶長20年 6月 1日) | 江戸で大きな地震が起き死傷者が多数出る。 |
| 7月 6日(慶長20年 6月11日) | 古田織部が豊臣側に内通した嫌疑で切腹。将軍茶頭木村宗喜の豊臣方内通疑惑に巻き込まれる形で。 |
| 7月28日(慶長20年閏6月 3日) | 飛騨高山2代藩主金森可重が急死。死因は不明で、自刃説や暗殺説もある。理由は不明だが跡を長男重近や次男重次ではなく3男の重頼が継いだ。可重自身は長屋景重の子で金森長近の養子であり、後継者の重頼は初代長近の実子伊東治明の子という記録もあり、死因及び家督継承には謎が多い。 |
| 8月 7日(慶長20年閏6月13日) | 徳川秀忠が諸大名に対し一国一城令を発令。国持大名は一国につき一城ずつ、一国に複数の大名の場合、一藩に一城というもの。 |
| 9月 5日(慶長20年 7月13日) | 元和(げんな)に改元。後水尾天皇の即位と、戦乱を理由にしている。徳川家康が漢朝年号の吉例を使うよう朝廷に示し、唐の憲宗時代の年号「元和(げんわ)」をもとに採用された。将軍が中国の元号を採用するよう求めたのはこの一例のみ。なおこの時候補に上がったものの1つとして、平安時代後期にも候補に上がり文字の縁起が悪いとして却下された「天保」があり、後に採用されている。 |
| 9月 9日(慶長20年 7月17日) | 江戸幕府が天皇と公家の道徳的規範と、僧侶の地位について定めた禁中並公家諸法度を発布。 |
| 10月25日(元和元年 9月 1日) | 慶長遣欧使節の一行が、ローマに到着。 |
| 11月 3日(元和元年 9月12日) | 慶長遣欧使節の一行が、ローマ教皇・パウロ5世に謁見。 |
| 1616年 | |
| 1月 7日(元和元年11月18日) | 慶長遣欧使節の一行が、帰国の途につくべくローマを出発。セビリアを経由して、ヌエバ・エスパーニャへと向かう。 |
| 4月23日 | 劇作家ウィリアム・シェイクスピアが亡くなる。歴史上最も著名な作家の一人だが、劇壇に登場するまでの前半生はよくわかっていない。 |
| 6月 1日(元和2年 4月17日) | 徳川家康、駿府城にて死去。元来は天ぷらの食中毒説が知られていたが、近年は胃がん説が有力。 |
| 8月18日(元和2年 7月 6日) | 徳川家康の6男で越後高田藩主の松平忠輝が、将軍徳川秀忠の命で改易される。改易の理由は過去の軍律違反などだが、家康晩年からの冷遇、岳父伊達政宗との関係、大久保長安との関係なども理由とされる。後に流罪地となった諏訪で長命を保った。粗暴だったとする一方、文人だったとも言われる。 |
| 10月21日(元和2年 9月11日) | 石見津和野藩主坂崎直盛(宇喜多詮家)が幕府と対立して死亡。自害とも家臣に殺害されたとも屋敷に立てこもって幕府に攻め滅ぼされたとも言われる。対立の原因は坂崎が大坂の陣で救出したと主張する千姫を巡る処遇にあるとされ、坂崎に再嫁する約束を反故にされた、あるいは坂崎が千姫と公家との再縁組を斡旋したところ幕府に無視され面目を失ったなどの説がある。坂崎は千姫の身柄を奪おうとして露見し幕府に攻められたともいう。津和野藩は改易。 |
| 1617年 | |
| 1月19日(元和2年12月12日) | 旗本の別所孫次郎の邸宅で、別所と客としてきていた旗本の伊東治明が喧嘩になり、別所の家人が伊東を斬殺、仲裁しようとした客の桑山一直も負傷する事件が起きる。別所は切腹し改易、桑山も閉門の処分を受けた。別所は戦国大名別所重棟の甥、伊東は飛騨高山藩主金森長近の子、桑山は大和新庄藩主。 |
| 3月28日(元和3年 2月21日) | 朝廷は、徳川家康を祀る久能山東照社に対し、正一位を贈り、東照大権現の神号を宣下。 |
| ネイティブアメリカンのポウハタン族出身の女性マトアカ(通称ポカホンタス)がイギリスのケント州グレーブゼンドで病死。23歳。当時彼女は新大陸でタバコ栽培業をしていた商人ジョン・ロルフの妻となっていたが、イギリスに連れてこられ、インディアンの姫という扱いで話題になっていた。3月21日に同地で葬儀。彼女の死後に、ポウハタン族領地に作られたヴァージニア入植地の指導者ジョン・スミスが「白人である自分を救ってくれた美談」を創作して広めた。彼女の孫娘がボーリング家に嫁いだため、ポウハタン族の血を引く多数の著名な子孫がいる。 | |
| 1618年 | |
| 4月 2日(元和4年 3月 7日) | 慶長遣欧使節の一行が、ヌエバ・エスパーニャのアカプルコを出港。 |
| 5月23日 | 第二次プラハ窓外投擲事件。ハプスブルク家出身でカトリック強硬派のフェルディナンドが、ボヘミア王に即位してプロテスタント諸侯らを迫害。これに反発したプラハの市民が、王の顧問官2人と秘書官を捕まえてプラハ城の3階の窓から外へ放り投げた事件(干し草の上に落ちたため助かる)。プロテスタント諸侯は、プファルツ選帝侯フリードリヒ5世をボヘミア王に迎えて神聖ローマ帝国からの離反の動きを見せる。 |
| 7月24日(元和4年 6月 3日) | 肥前龍造寺氏に代わって佐賀藩の基礎を築いた鍋島直茂が耳の腫瘍で苦しみながら亡くなる。そのため、主権を回復できずに恨んで死亡した龍造寺高房の呪いと噂され、鍋島化け猫騒動の話が生まれる。 |
| 8月10日(元和4年 6月20日) | 慶長遣欧使節の一行が、ルソンのマニラに到着。 |
| 1619年 | |
| 明軍10万が後金の拠点ヘトゥアラ(のちの興京)攻略に向かう。 | |
| 2月12日 | ガルシア・デ・ノダルの探検隊が、南米最南端のホーン岬よりさらに南方約100kmのドレーク海峡の中にディエゴ・ラミレス諸島を発見する。南緯56度29分に位置する。 |
| (3月 1日) | サルフ山付近でヌルハチ率いる後金軍が明軍を奇襲攻撃。後金軍が大勝し、明軍の司令官杜松らは戦死。 |
| (3月 2日) | ヌルハチ率いる後金軍は、続けてシャンギャンハダの明軍を攻撃。乱戦になるも、後金軍が勝利し、明軍は退却に追い込まれる。 |
| (3月 4日) | ダイシャン、ホンタイジらの率いる後金軍が、アブダリおよびフチャの一帯で劉綎率いる明軍を攻撃。後金軍が勝利。明軍に参加していた朝鮮軍は降伏。 |
| 5月 1日(元和5年 3月17日) | 肥後で地震。八代麦島城などに被害が出る。 |
| 10月25日(元和5年 9月18日) | およつ御寮人事件。天皇家に娘の徳川和子を嫁がせることを企図していた徳川秀忠が、後水尾天皇と四辻与津子との間に男女二人の子(賀茂宮・文智女王)が生まれていたことを知って激怒し、四辻与津子と子供を宮中から追放し、万里小路充房・四辻季継・高倉嗣良を流罪、中御門宣衡・堀河康胤・土御門久脩を出仕停止にする。憤慨した天皇は譲位を口にするが、幕府の使者藤堂高虎が和子入内が実現しないなら宮中で切腹すると脅し、天皇は幕府に従うことになった。四辻与津子は猪熊事件の猪熊教利の妹でもある。 |
| オランダ船ホワイトライオン号がスペイン船と交戦した際にアフリカから連れてこられた奴隷20人を捕らえバージニア植民地へ輸送する。アメリカに送られたアフリカ人奴隷でもっとも古い記録。この頃はまだ年季奉公に近く、年季明けには解放されていた例もあったとみられるが、彼らがアフリカに戻れたわけではない。 | |
| 1620年 | |
| 1月23日(元和5年12月19日) | 直江兼続が死去。上杉景勝の家老で、上杉藩のトップとして差配した戦国武将。 |
| 5月26日(元和6年 4月24日) | イングランド出身の船乗りで徳川家康の外交顧問だったウィリアム・アダムス(三浦按針)死去。 |
| 7月28日(元和6年 6月29日) | 宇和島藩で和霊騒動が起きる。初代藩主伊達秀宗に父親の政宗がお目付けとして付けた筆頭家老山家公頼が、重臣桜田元親の一派に自邸を襲撃され殺害される。子供と、娘婿の塩谷内匠、その子供も殺害された。桜田元親は大坂にいたことや秀宗がこの事件を幕府にも仙台の政宗にも報告しなかったため、秀宗が山家公頼を疎んじて命じた事件とされる。政宗がこれを知って激怒し宇和島藩の改易を幕府に申し出たが老中土井利勝は受理せず事なきを得た。その後、桜田元親をはじめ山家公頼の政敵だった重臣らが相次いで事故死し、秀宗の子供らも早世するなど不幸が続いたことから、山家公頼の怨念の噂が広がり、秀宗は後に山頼和霊神社(のち和霊神社)を創建した。なお、政宗と秀宗の関係は事件以前に悪化していたが、これを機会に話し合って改善したという。 |
| 8月18日(万暦48年 7月20日) | 明の万暦帝が死去。初期の10年は厳格で権力者だった宰相の張居正のもとで大規模な改革が行われ、経済も盛んになり、国家財政も良くなったが、張居正死去後はその反動で堕落し、党人官僚と宦官の党争、対外戦争や反乱の頻発で財政が悪化。増税と厳しい取り立てで民衆の反感を買い、国家崩壊を加速させた。「明朝は万暦に滅ぶ」と史書にある。 |
| 8月28日(泰昌元年 8月28日) | 万暦帝の長男朱常洛が即位(泰昌帝)。 |
| 9月20日(元和6年 8月24日) | 慶長遣欧使節の一行が、日本に帰国。 |
| 9月26日(泰昌元年 9月 1日) | 即位したばかりの明の泰昌帝が急死。下痢となったため、紅丸(丸薬)を服用したところ、2回目の服用時ににわかに悪化して死亡したという。そのため暗殺説もある。即位に伴う改元は翌年元日のため改元されていなかったが、皇帝が急死したため、遡って予定されていた泰昌に改元した。 |
| 10月 1日(泰昌元年 9月 6日) | 泰昌帝の長男朱由校が即位(天啓帝)。 |
| 11月 8日 | 白山(ビーラー・ホラ)の戦い。ボヘミアのプロテスタント諸侯らが神聖ローマ帝国から離反しようとしたため、ボヘミア王国の支配者ハプスブルク家などが制圧を図った戦い。半日でカトリック側の勝利に終わり、諸侯ら27人が処刑され、多くのプロテスタント諸侯や市民が追放される。ハプスブルク家によるボヘミア支配が強化され、三十年戦争が激化する要因となった。 |
| 11月20日 | メイフラワー誓約が交わされる。アメリカ初期の移民が乗った船、メイフラワー号が、目的地と違う場所に到着したため、乗船していた亡命ピューリタンらが安定した入植のために、公正で平等な法律を整備することをお互いに契約する。 |
| 1622年 | |
| 5月29日(元和8年 4月19日) | 日光参詣に赴いていた将軍徳川秀忠が、帰路に泊まる予定だった本多正純の宇都宮城を素通りして壬生城に入る。宇都宮城内で将軍暗殺の仕掛けが用意されているという話が起きたため。いわゆる宇都宮城釣天井事件。 |
| 8月19日(元和8年 7月13日) | 朱印船船長の平山常陳とスペイン人で宣教師のペトロ・デ・スニガ、ルイス・フロレスほか、船員12名が処刑される。朱印船に2人を乗せていたことを、スペイン・ポルトガルから日本市場を奪おうと考えていたイギリスとオランダの商館が問題視したことから起きた事件。以降のキリシタン弾圧事件のきっかけとなった。 |
| 9月10日(元和8年 8月 5日) | 元和の大殉教。キリスト教の司祭9名を含む信徒55名が、長崎西坂で処刑される。 |
| 9月26日(元和8年 8月21日) | 出羽山形57万石が改易となる。若年の藩主最上家信(義俊)に対して家臣らが反発し、家信の叔父で山野辺家を継いでいた山野辺義忠の擁立を画策したことで藩内が分裂。幕府が仲裁に入ったが両者譲らず、改易処分となた。通称「最上騒動」。家信は近江大森1万石を新たに与えられ、山野辺義忠は岡山藩に預けられたが、後に幕命で水戸徳川家に仕えることになり家老職を与えられた。また改易に伴う山形城接収のさなかに、城受取の役についていた本多正純へ、謀反の問使が送られる事件が発生。 |
| (元和8年 9月) | 宇都宮15万石藩主本多正純が改易となる。直接の原因は4月に起きた宇都宮城釣天井事件だが、実際には権勢を誇った正純への不満が、将軍秀忠や幕閣らにあったためとも言われる。 |
| 1623年 | |
| 2月10日 | アンボイナ事件。オランダ領東インドに属していたアンボイナ島で、オランダ東インド会社が、同地のイギリス東インド会社を襲撃した事件。モルッカ諸島の香辛料については、オランダ・イギリス両政府で交渉が成立していたが、現地総督ヤン・ピーテルスゾーン・クーンはこれに不服で、独断でイギリス勢力の排除に乗り出したものと思われる。 |
| 3月 9日 | アンボイナ事件で、オランダ東インド会社は、捕らえたイギリス東インド会社の関係者のうち、イギリス人9人、日本人10人、ポルトガル人1人を処刑。この時代、東南アジア一帯に大勢の日本人が渡っており、傭兵などをしていたとされる。イギリスはこの事件を機に極東・東南アジアから撤退しインドの植民地化に乗り出す。のちに英蘭講和条約でこの事件の解決が図られ、その内容として賠償金の他アメリカ東岸のマンハッタン島の支配権も移ることになる。結果的にこの事件はイギリス躍進のきっかけになっている。 |
| 12月 4日(元和9年10月13日) | 江戸高輪大木戸の処刑場でキリスト教徒50人が処刑される。 |
| 1624年 | |
| 4月 2日(寛永元年 2月15日) | 山城の狂言師出身の猿若勘三郎が江戸で座を開き興行をはじめる。のちの中村座。江戸歌舞伎の始まり。 |
| 8月26日(寛永元年 7月13日) | 豊臣秀吉の親族で、安芸広島藩の大名だったこともある福島正則が死去。 |
| 10月17日(寛永元年 9月 6日) | 豊臣秀吉の正室、高台院が死去。通称北政所ねね。「北政所」は公卿の正室の呼称だが、ねね以降は彼女を指す言葉になった。大名並みの約1万7000石を遺し、そのうち、3000石を親族で養子の羽柴利次(のち木下利次)が受け継いだ。利次は豊臣家の社稷継承を幕府から許されており、子孫は豊臣姓木下家として旗本寄合となっている。 |
| 1625年 | |
| 1月21日(寛永元年12月13日) | 安芸国で大地震。広島城などに大きな被害が出る。 |
| 7月21日(寛永2年 6月17日) | 肥後国で大地震。熊本城内の火薬庫が爆発し、城内に大きな被害が出る。地震の死者はおよそ50人。 |
| (寛永2年11月) | 上野山に寛永寺が創建される。創建したのは天海。このときは徳川家の菩提寺ではなく祈願寺。 |
| 1626年 | |
| 5月 6日 | オランダ西インド会社がインディアンからマンハッタン島を25ドルで買収し、ニーウアムステルダムと命名(25ドルの話はあくまで伝承)。実際、この頃入植が始まったと見られる。 |
| 5月30日(天啓6年 5月 6日) | 王恭廠大爆発事件。北京の西南にあった兵器廠・火薬庫である「王恭廠」が突如大爆発を起こす。家屋など多数が倒壊。爆風などで2万人以上が死亡、膨大な数の負傷者が出る。紫禁城内でも爆風で飛ばされたり、破片が当たるなどして多数が死亡。幼児だった皇太子も死亡した。爆音は北京郊外にまで轟き、地面が大きく揺れて振動は遠く天津や大同などにまで到達。大きなキノコ雲が上がり、瓦礫や人畜のばらばらになった死体が降り注いだという。また遺体の多くが裸になっていた。記録などからTNT火薬換算で20ktもの爆発だったとされる(広島の原爆とほぼ同じ)。火薬庫だったため、大量の火薬の爆発とも考えられるが、当時の黒色火薬でここまでの爆発が同時に起きるのか、また爆心地付近で火災が起きてないことなどから、小型の隕石が衝突したという説も有力。天啓帝は「罪己詔」を発して反省を唱えざるを得なかった。 |
| 11月 3日(寛永3年 9月15日) | 江戸幕府の第2代将軍徳川秀忠の正室、崇源院(江)が死去。浅井三姉妹の三女。 |
| 1627年 | |
| 9月30日(天啓7年 8月21日) | 明王朝16代皇帝の天啓帝が死去。政治の実権は宦官の魏忠賢が握っていたため、傀儡の皇帝だった。 |
| 10月 2日(天啓7年 8月24日) | 明王朝15代皇帝の泰昌帝の5男の朱由検が17代皇帝に即位(崇禎帝)。 |
| 10月22日(寛永4年 9月14日) | 信濃松代で大きな地震。 |
| 12月11日(天啓7年11月 4日) | 明王朝の宦官で政治の実権を握り権勢を誇っていた魏忠賢が、即位したばかりの崇禎帝により罪に問われたことで自殺。一族も処刑された。 |
| この年、江戸幕府は、朝廷が幕府に相談もなく紫衣を勅許したとしてこれを無効にし、紫衣を取り上げる(紫衣事件)。沢庵宗彭らがこれに抗弁。 | |
| この年、ドイツの天文学者ヨハネス・ケプラーが「ルドルフ星表」を作成。占星術などに使うため惑星の位置推算表や恒星カタログなどを付けたもので、神聖ローマ帝国皇帝ルドルフ2世の勅命によって作られた。 | |
| この年、家畜牛の先祖でもある野生のオーロックスが絶滅。 | |
| 1628年 | |
| 6月(寛永5年 5月) | 台湾のオランダ支配地タイオワン(台南安平)でオランダ行政長官のピーテル・ノイツと朱印船貿易商人浜田弥兵衛が紛争を起こしノイツを人質にする事件が起きる。貿易船への関税と日本人への態度が原因とされる。この一件で長崎代官の末次平蔵は解任・捕縛されたが、オランダ側がノイツの身柄を差し出したため、オランダ貿易は存続することになり、台湾も自由貿易地となった。 |
| 8月10日(寛永5年 7月11日) | 武蔵国から相模国にかけて大きな地震が発生。江戸城などで被害。 |
| 8月10日 | スウェーデンで建造された大型の戦列艦ヴァーサ号が初航海の出港まもなく横風を受けて横転沈没。333年後の1961年に引き上げられたが、低温のバルト海海底だったこともあり保存状態がよく、原型の姿を留めていた。 |
| 9月 7日(寛永5年 8月10日) | 江戸城西の丸で、旗本で目付の豊島信満が老中井上正就を突如斬り殺す。初の江戸城中刃傷事件。また、その場に居合わせた番士の青木義精が豊島を押さえようとしたところ、豊島は脇差を自分に突き刺し自害、脇差は体を貫いて青木に突き刺さり、青木も死亡。事件の背景には、井上正就の子正利と大坂町奉行島田直時の娘の縁談を、豊島が仲立ちして成立したのに、春日局が横槍を入れて鳥居成次の娘の縁談を持ち込んで破談させたことにある。老中酒井忠勝は、豊島の行為を認めた上で嫡男のみを連座で切腹させて収拾を図った。紀州藩は信満の別の子を藩士に登用。正就の横須賀藩は正利が相続。 |
| 10月23日(寛永5年10月 7日) | 江戸城西の丸での旗本豊島信満による老中井上正就殺害事件を受けて、原因となった破談の当事者であった島田直時は豊島信満に申し訳ないとして切腹。 |
| ウイリアム・ハーベーが、『動物における血液と心臓の運動について』を発表。この中で初めて血液循環説を唱える。これは大論争に発展するが、徐々に浸透していく。 | |
| 1629年 | |
| 1月19日 | サファヴィー朝のアッバース1世が死去。絶対君主制、近代化、西欧諸国との同盟で同王朝の最盛期を作り上げたが、その死後、サファヴィー朝は徐々に衰退していく。 |
| 江戸幕府、紫衣事件に抗弁した沢庵宗彭らを流罪とする。 | |
| 翌年にかけて、ミラノなどでペストが流行。大勢の死者を出す。 | |
| 1630年 | |
| 6月10日(寛永7年 4月30日) | 織田常真(信雄)死去。織田信長の次男。本能寺の変の後、一時期織田家の当主だったともいわれる。秀吉政権下で改易された後、御伽衆の筆頭。関ケ原では親子ともども西軍についたとされ改易。大阪の陣では一旦豊臣方に付くも離脱。役後に大和や上野など各地に5万石を与えられ大名に復したが子供に任せ、自身は京で悠々自適に暮らしたという。 |
| 7月 5日(寛永7年 5月25日) | 元長崎代官の末次平蔵が、江戸で収監中に殺害される。詳細は不明。幕府高官の密貿易を知っていたための謀殺とも。 |
| 8月 2日(寛永7年 6月24日) | 江戸で大きな地震。江戸城で石垣などに被害。 |
| 9月22日(崇禎3年 8月16日) | 明の武将袁崇煥が、崇禎帝によって凌遅刑に処され殺害される。明に侵攻していた後金のホンタイジ側にとって、袁崇煥の存在は邪魔だったため、謀反の噂を流し、崇禎帝がそれを信じたと考えられる。袁崇煥を殺害したことで、明は防衛能力を大幅に失い、滅亡を早めた。 |
| 11月15日 | 近代天文学の祖と呼ばれる天文学者であり数学者でもあるヨハネス・ケプラー死去。 |
| 1631年 | |
| 6月17日 | ムムターズ・マハルが亡くなる。ムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーンの第1皇妃。皇帝は彼女の死をいたみ、タージ・マハルの建設を開始。 |
| 1632年 | |
| 7月 9日(寛永9年 5月22日) | 肥後熊本藩主加藤家の2代目加藤忠広が、江戸参府途上、入府を禁じられて、池上本門寺で改易を言い渡される。身柄は出羽庄内藩へ預けられた。加藤家改易の理由は諸説あるがはっきりしない。 |
| この頃、オスマン帝国の発明家だったヘザルフェン・アフメト・チェレビが、人工の翼を発明して、イスタンブールのガラタ塔から飛び降りる飛行実験を実施。ボスポラス海峡を飛び越え、ユスキュダルのドアンヂュラル広場に無事着陸したと言う。飛行距離は3000m以上と言われる。グライダーのようなものか。 | |
| 1633年 | |
| 1月26日(寛永9年12月17日) | 江戸幕府が大目付を設置する。 |
| 3月 1日(寛永10年 1月21日) | 相模国、伊豆国、駿河国で大きな地震と津波が発生。小田原では小田原城や城下町で大きな被害を出す。 |
| 4月 6日(寛永10年 2月28日) | 江戸幕府が鎖国令を発する。 |
| 6月22日 | 検邪聖省の裁判でガリレオ・ガリレイに有罪判決が下り、自説の地動説を撤回する異端誓絶文を読み上げさせられる。 |
| オスマン帝国の発明家だったラガリ・ハサン・チェレビが、7枚の羽がついたロケットのような装置に火薬を詰め、それに乗り込んだ上で点火し有人飛行実験を行ったといわれる。数十メートル飛行し、火薬が燃え尽きると、体につけた翼で降下し、ボスポラス海峡に着水したという。この実験の話はヨーロッパにも伝えられた。事実であれば、記録上人類最初の動力装置による飛行実験をした人物となる。ラガリの兄は人工の翼で飛行実験をしたヘザルフェン・アフメト・チェレビ。 | |
| 1634年 | |
| 12月26日(寛永11年11月 7日) | 鍵屋の辻の決闘。日本三大仇討ち一つ。渡辺数馬と荒木又右衛門が、数馬の弟で岡山藩主池田忠雄の小姓だった渡辺源太夫の仇である河合又五郎とその護衛を討つ。 |
| この年、将軍徳川家光が向井将監に建造を命じた御座船「安宅丸」が完成。竜骨の長さが125尺、肩幅53.6尺、二層の天守があり、銅板張りで、帆と2人掛かりの100挺の艫で動かす巨船。軍船構造だったが実用性は乏しかったとみられる。 | |
| 1636年 | |
| 9月18日 | マサチューセッツ湾植民地議会でカレッジの創設が決定する。ジョン・ハーバードの遺産をもとに設立されたのがハーバード大学。 |
| 1637年 | |
| 2月 3日 | オランダで庶民まで巻き込んだチューリップバブルが崩壊。 |
| 12月11日(寛永14年10月25日) | 島原の乱勃発。肥前島原半島を領有する島原藩(藩主松倉勝家)と、肥前唐津藩(藩主寺沢堅高)の飛地である肥後天草諸島の領民が、それぞれに圧政に抵抗して起こしたもので、改易された小西家や加藤家の旧藩士やキリシタンも加わっていた。一揆勢はその後合流して益田四郎時貞(天草四郎)を擁立。島原では島原藩の代官所を襲い、天草では本渡城を襲うなど大規模なものに発展。長崎を襲う計画もあったと言われる。 |
| 12月30日(寛永14年11月14日) | 天草諸島の一揆勢が、富岡城を攻め、富岡城代の三宅重利は自刃。三宅重利は明智秀満の子と言われる。両藩で手に負えなくなったことから、幕府は板倉重昌と石谷貞清を派遣して、九州諸藩の大名に動員令を発する。 |
| 1638年 | |
| 1月24日(寛永14年12月10日) | 島原の乱で、板倉重昌が原城を攻めるが失敗。 |
| 2月 3日(寛永14年12月20日) | 島原の乱で、板倉重昌が再度原城を攻めるが失敗。原城が堅固な上に、一揆勢の士気は高く、逆に攻め手側の九州諸藩は負担が重い上に、指揮を執る板倉重昌は1万5千石の三河深溝藩主、石谷貞清は旗本と地位が低かったこともあって、その指揮下に置かれることに反発もあったと見られる。 |
| 2月14日(寛永15年 1月 1日) | 幕府は島原の乱で進展が見られないことから、老中松平信綱が新たに指揮官として派遣されることになり、それを知った板倉重昌が焦りから総攻めを強行。4000人が戦死する大敗を喫し、板倉自身も三会村金作(駒木根友房)に狙撃されて戦死する。 |
| 2月19日(寛永15年 1月 6日) | オランダ商館長クーケバッケルが、長崎奉行の依頼を受けて、艦載砲を幕府方に提供。 |
| 2月24日(寛永15年 1月10日) | 幕府は島原の乱への増援を決め、水野勝成と小笠原忠真に出陣を命じる。 |
| 2月26日(寛永15年 1月12日) | オランダ船デ・ライプ号が、原城への艦砲射撃をはじめる。 |
| 3月13日(寛永15年 1月28日) | 川越で大火。市街地と川越城、喜多院、中院、南院、東照宮なども焼失。このあと松平信綱が新たに町割りをして再建したのが現在の川越の原型。 |
| 4月11日(寛永15年 2月27日) | 松平信綱指揮する12万の兵が、原城への総攻撃を行い、原城は陥落する。乱側はほぼ全滅。天草四郎は肥後藩士陣佐左衛門に討ち取られた(幕府は天草四郎の容姿を知らなかったため、天草四郎の母親マルタが陣佐左衛門の討ち取った少年の首を見て泣いたので判断した)。実質の指導者とも言われる天草四郎の父親益田好次や参謀役の蘆塚忠右衛門らも討ち死にした。なお一揆軍は脱出に成功したものや降伏したものもかなりいるという説もある。 |
| 1640年 | |
| 7月31日(寛永17年 6月13日) | 蝦夷駒ヶ岳の噴火が始まる。山頂600mほどが大きく崩壊し、土砂が内浦湾になだれ込んで大津波が発生。火道が崩壊したことで火砕流が起き、続けて大規模なプリニー噴火が発生する。規模の大きな噴火は3日ほどで収束したが津波被害などで約700名が死亡、100艘あまりの船が流出。 |
| 11月23日(寛永17年10月10日) | 加賀大聖寺で地震。多数の家屋が損壊。死傷者多数。 |
| (寛永17年) | この頃から各地で飢饉が広がり始める。蝦夷駒ヶ岳噴火による降灰の影響もあったと見られる。 |
| 1641年 | |
| 3月10日(寛永18年 1月29日) | 桶町の大火。江戸京橋桶町1丁目から出火。強風に煽られて延焼していき、東は海岸まで、南は芝宇田川町まで、西は麻布まで広がる。97町が被害を受け、大名・旗本屋敷121、同心屋敷56、全体で1924軒が焼失。数百人が焼死。消火活動の陣頭指揮を執った旗本で大目付の加賀爪忠澄も煙に巻かれて死亡。要所の火消役(所々火消)を担当した相馬中村藩主の相馬義胤は消火作業中に落馬して重症を負う。大名火消し制度の設立のきっかけになった大火。 |
| (寛永18年) | 天候不順などで飢饉が全国規模に拡大。寛永の大飢饉。幕府による武断政治の悪影響も大きかったとされる。 |
| 1642年 | |
| (寛永19年 5月) | 幕府が各大名に、帰藩して飢饉対策をするよう命じる。 |
| 7月10日 | 第1次イングランド内戦勃発。王党派(国王軍)と議会派(議会軍)の内戦。王党派はアイルランドと、議会派はスコットランドと盟約。 |
| 8月10日 | ポーツマス包囲戦(第1次イングランド内戦)。 |
| 1643年 | |
| (寛永20年 3月) | 幕府より田畑永代売買禁止令が発布される。大飢饉による農民の没落を防ぐため、天領の代官あてに出された法令。 |
| 6月30日 | アドウォルトン・ムーアの戦い(第1次イングランド内戦)。この頃まではまとまりの欠く議会軍が劣勢にあった。 |
| 7月25日(寛永20年 6月10日) | オランダの金銀島探索隊の2隻の船のうちブレスケンス号が補給のため盛岡藩山田浦に現れる。住民は歓待し、補給を受けて出港。この一件が盛岡藩に伝わる。 |
| 9月11日(寛永20年 7月28日) | ブレスケンス号がふたたび盛岡藩山田浦に現れる。乗員10人が歓待を受けているところを狙い盛岡藩によって捕縛される。藩主南部重直は、彼らを謁見して身元を確認。オランダ人で、宣教師ではないことから、その後は待遇を改め、身柄は江戸へ移される。 |
| 11月 6日 | ベイジングハウス包囲戦が始まる(第1次イングランド内戦)。 |
| この年、エヴァンジェリスタ・トリチェリが、水銀を満たしたガラス管を使って実験を行い、水銀の高さが約76cmで止まり、その上は真空になることを発見。大気圧によるものであるとの結論に至る(トリチェリの真空)。水銀気圧計の元ともなった。 | |
| 1644年 | |
| 1月17日(寛永20年12月 8日) | ブレスケンス号の船長以下10人が、江戸に出府したオランダ商館長の交渉もあり、帰国が認められる。 |
| 1月25日 | ナントウィッチの戦い(第1次イングランド内戦)。 |
| 4月25日(崇禎17年/永昌元年 3月19日) | 李自成が北京を陥落させて、崇禎帝が自殺し明王朝が滅亡。李自成による順王朝が成立。崇禎帝は自ら家族を斬ったうえで自殺したが、ただ一人最後まで皇帝に従っていた宦官の王承恩は負傷した長平公主らを逃した後で殉死した。そのため、崇禎帝の評価は低いが、王承恩は宦官には珍しく忠義の人として評価されている。一方、山海関の守将だった呉三桂が満洲族の清王朝に寝返り(寵愛する陳円円を李自成軍に奪われたためという)、清軍とともに南下し北京を攻略。李自成はわずか40日で北京から敗走した。 |
| 7月 2日 | マーストン・ムーアの戦い(第1次イングランド内戦)。議会派が圧勝。東部連合軍を率いたオリバー・クロムウェルが台頭する。 |
| 7月22日(崇禎17年 6月19日) | 明の鳳陽総督の馬士英・阮大鋮らによって福王朱由崧が擁立されて即位(弘光帝)。南明政権の初代皇帝。 |
| 10月18日(正保元年 9月18日) | 羽後で大地震。本荘藩の本荘城や周辺で大きな被害を出す。 |
| 1645年 | |
| 4月 3日 | イングランド長期議会で、辞退条例が可決成立。貴族の軍司令官のいい加減さを批判したオリバー・クロムウェルが訴え、上下両院議員は軍人を兼任しない(40日以内に辞任する)という内容が成立。新軍編制のニューモデル軍が強化される。司令官のロバート・フェアファクスや、オリバー・クロムウェル自身も辞任し、ロバートの息子のトーマス・フェアファクスが司令官に、またクロムウェルは例外的に副司令官に再登用される。この二人が議会軍を勝利へと導くことになる。 |
| 4月11日(正保2年 3月15日) | 赤穂藩主池田輝興が、突如正室の亀子姫と侍女数人を斬殺、側室を負傷させる事件を起こす。それまで比較的まともな治世を行っていた人物だけに何があったのか不明。後の浅野内匠頭改易(「元禄赤穂事件」)、脇坂家在番時代の家臣刃傷事件(「脇坂赤穂事件」)、森主税暗殺(「文久赤穂事件」)と区別し、「正保赤穂事件」と呼ばれる。 |
| 4月16日(正保2年 3月20日) | 赤穂藩主池田輝興が改易され岡山藩主池田光政預かりとなる。赤穂には笠間藩主浅野長直が転封。 |
| 6月10日(永昌2年 5月17日) | 各地を転戦していた李自成が九宮山で農民の手で殺される(僧侶に変装して落ち延びたという説もある)。李自成を単に時勢に乗った流賊とみるか、圧政に抗した農民反乱指導者と見るかは、中国でも意見が分かれている。 |
| 6月14日 | ネイズビーの戦い(第1次イングランド内戦)。王党派(国王軍)が甚大な被害を出して敗退。 |
| 6月(順治2年/弘光元年) | 清朝の予親王多鐸の率いる軍勢が南明の揚州に攻め込み南京も攻略。弘光帝も捕らえられる。この際、多鐸軍が揚州で大虐殺を行う(いわゆる「揚州十日」)。80万人が殺されたと言われるが、人口よりかなり多い数なので誇張と見られる。 |
| 9月10日 | ブリストル包囲戦(第1次イングランド内戦)。王党派(国王軍)のブリストルが陥落。 |
| 10月13日 | ベイジングハウス包囲戦が終結(第1次イングランド内戦)。最終的に議会派が勝利するも、国会議員に多数の犠牲者を出す。 |
| 1646年 | |
| 1月19日(正保2年12月 3日) | 神号東照大権現となっていた徳川家康に対し、朝廷から東照宮の宮号が宣下される。 |
| 2月16日 | トリントンの戦い(第1次イングランド内戦)。王党派と議会派の市街戦のさなかに、トリントン教会に保管されていた火薬に引火、大爆発を起こし、王党派は敗退。 |
| 6月 9日(正保3年 4月26日) | 東北南部から関東にかけて大きな地震。仙台や会津、日光などで被害。 |
| 6月24日 | オックスフォード包囲戦(第1次イングランド内戦)。王党派の拠点だったオックスフォードが陥落。国王チャールズ1世は敗走してスコットランドへ亡命することになる。 |
| 1647年 | |
| 1月 2日(大順3年11月27日) | 大西の皇帝を称していた張献忠が、清の粛親王ホーゲの軍勢に敗れ射殺される。張献忠は蜀の主要部分を一時支配して「大西」を建国したが、人民から官僚、部下の兵士、側近、自分の家族に至るまで空前の大虐殺を行ったと言われる人物。蜀の人口は1578年に310万人いたが、1685年には1万8000人しかいない。四川人がほぼ絶滅し、その後、中央から大規模な移民が行われたため、四川方言が中央の言葉に近い要因ともされる。この大虐殺を「屠蜀」と呼ぶ。ただし、張献忠の記録の多くが清朝時代に書かれており、清朝軍による蛮行も張献忠の仕業に置き換えられたという見方もある。 |
| 6月16日(正保4年 5月14日) | 武蔵国から相模国にかけて大地震。江戸市中や小田原城下で建物や城壁などの倒壊被害。 |
| 1648年 | |
| 4月 7日(正保5年 2月15日) | 正保から慶安に改元。正保が焼亡に似ているとか、保元の時のように乱世になると否定的な意見が広まったため。 |
| 10月24日 | ヨーロッパの主要国が参加してヴェストファーレン条約締結。カトリック勢力とプロテスタント勢力の講和を図るオスナブリュック講和条約と、神聖ローマ皇帝とフランス国王との講和を図るミュンスター講和条約が成立。三十年戦争は終結。神聖ローマ帝国の集権化が崩壊し、以後主要な地域大国に分かれていく。またスイス誓約者同盟とネーデルラント連邦共和国が神聖ローマ帝国から公式に分離し独立国となる。 |
| ロシアの探検家セミョン・デジニョフがロシアとアラスカの間の海域(のちのベーリング海)を探検。 | |
| 1649年 | |
| 7月30日(慶安2年 6月21日) | 武蔵国から下野国にかけて大地震。江戸や川越などで大きな被害を出す。上野東照宮の大仏の頭が落下。石垣の崩落や建物の倒壊が多数発生し死者多数を出す。 |
| 9月 1日(慶安2年 7月25日) | 武蔵国南部で大地震。川崎で町家の150軒ほどと寺院7つで建造物が倒壊。死傷者多数。 |
| 1650年 | |
| 5月 7日(慶安3年 4月 7日) | オランダ東インド会社からの特使が江戸城に登城。老中と会見(将軍家光はこの時病臥中だった)。ブレスケンス号事件の際に幕府が乗員の釈放を認めたことに対する返礼がなかったことで幕府が態度を硬化させたため、オランダ東インド会社側から謝礼使として送られたもの。外科医のカスパル・シャムペルゲル(蘭方医学カスパル流外科術の祖)も同行。また先のオランダ商館長でこの時同社のバタヴィア商務総監だったフランソワ・カロンは、幕府が破壊力のある炸裂弾を発射できる臼砲を欲しがってることを知っていたため、同社のスウェーデン人砲術士官ユリアン・スヘーデルを一行に加え、同じ砲術士官のヤン・スミットとともに、幕府に臼砲2門を献上している。 |
| 5月13日(慶安3年 4月13日) | 町奴の頭領、幡随院長兵衛が死去。なお、歌舞伎などの物語では1657年8月27日(明暦3年7月18日)に敵対する水野十郎左衛門の屋敷で殺害されたことになっている。 |
| 5月 7日(慶安3年 9月 1日) | オランダ東インド会社からの特使とともに来て江戸に残っていた砲術士官ユリアン・スヘーデルとヤン・スミットが、江戸郊外の牟礼野(現三鷹市牟礼)で、軍事演習と実地指導を行う。スヘーデルの測量砲術は北条氏長(北条流軍学者で鉄砲頭・後大目付)を経て紅毛流測量術として伝わる。また三角測量法を日本に最初にもたらした人物と言われる。 |
| 11月 4日(慶安3年10月11日) | 沢野忠庵ことクリストヴァン・フェレイラが死去。もとはポルトガルの宣教師で日本管区長代理を務めていたが幕府に捕らえられ、拷問の末に棄教。以後は沢野忠庵と名乗り、キリスト教弾圧に協力した他、天文学や医学の知識を伝えた。フェレイラの棄教はカトリック教会、宣教組織である修道会イエズス会にとって大きな衝撃だったと言われる。 |
| 1651年 | |
| 6月 8日(慶安4年 4月20日) | 徳川家光死去。 |
| 9月 7日(慶安4年 7月23日) | 密告により丸橋忠弥が捕縛され、由井正雪の陰謀が露見する。いわゆる慶安の変。 |
| 9月10日(慶安4年 7月26日) | 由井正雪が駿府の宿で捕り方に囲まれ自決。 |
| 9月14日(慶安4年 7月30日) | 由井正雪の同志だった金井半兵衛が由井正雪の死を知り大阪で自決。 |
| 9月24日(慶安4年 8月10日) | 丸橋忠弥が処刑される。長宗我部盛親と側室との子、長宗我部盛澄という説もある。 |
| 10月 2日(慶安4年 8月18日) | 徳川家綱が第4代征夷大将軍となる。 |
| 1652年 | |
| 10月15日(慶安5年 9月13日) | 承応事件。浪人別木庄左衛門らが徳川秀忠夫人崇源院の27回忌を利用して火を放ち老中らを暗殺しようとした事件。 |
| 1653年 | |
| 2月10日(承応2年 1月13日) | 幕府が玉川上水建設を許可。 |
| このころ、タージ・マハルが完成する。 | |
| 1654年 | |
| 5月 8日 | マクデブルクの半球実験。神聖ローマ帝国の都市マクデブルクの市長で科学者のオットー・フォン・ゲーリケが、自作した銅製の半球同士をくっつけて内部を真空にした球体を馬16頭で引っ張って分離する実験を、レーゲンスブルク市の帝国議会議事堂前で行う。神聖ローマ皇帝フェルディナント3世がこれを見学。この実験で、真空と大気圧の力が証明される。 |
| 10月12日 | オランダのデルフトで、クラリスト修道院の火薬庫に保管してあった火薬店の火薬約30tが爆発。市街地に大きな被害をだし、100人以上が死亡。 |
| 1655年 | |
| 3月25日 | オランダの天文学者クリスティアーン・ホイヘンスが自作の望遠鏡で土星の衛星タイタンを発見。 |
| 12月17日(明暦元年11月20日) | 「最後の戦国大名」宇喜多秀家が八丈島で死去。戦国大名宇喜多直家の子で、秀吉の猶子となり豊臣政権の五大老の一人。関ヶ原後に改易され八丈島に流される。元和2年に幕府より罪は許されたが、妻の実家の加賀前田家や元宇喜多家重臣で旗本の花房正成による大名復帰の斡旋を断ったという話もある。 |
| 1656年 | |
| 8月22日(明暦2年 7月 3日) | 美濃青野の領主で旗本の稲葉正吉が、駿府城護衛のさなか、男色のもつれから、家臣の安藤甚五右衛門・松永喜内と争いになり、殺害される。領地は嫡男の稲葉正休があとを継ぎ、正休は要職を歴任して加増され大名となったが、のちに江戸城中で老中堀田正俊を殺害する事件を起こす。 |
| 11月(明暦2年10月) | 幕府は江戸日本橋葺屋町に隣接していた吉原遊郭に対し、本所か浅草への移転を命じる。吉原遊廓は浅草日本堤への移転に同意(新吉原)。幕府は移転の代わりに遊郭の敷地拡大、夜間営業の許可、風呂屋と呼ばれた私娼窟の取り締まり、周辺火事への対応免除、15000両の賦与を決定。 |
| 1657年 | |
| 1月30日(明暦2年12月16日) | 茶人金森宗和が死去。元は武将で金森可重の嫡男だったが、大坂の陣に異論を唱えたことで廃嫡となり、以後茶人として生きた。皇族や公家、将軍家にも親しまれた宗和流茶道の祖。御室焼の陶工野々村仁清を指導したことでも知られる。 |
| 2月 7日(明暦2年12月24日) | 吉原遊郭を日本橋から浅草千束日本堤へ移転させる。幕府は約束通り、丹前風呂と呼ばれた堀丹後守下屋敷前の風呂屋群など200軒を廃業とした。丹前風呂の人気湯女で「丹前文化」の担い手だった勝山、幾夜、采女なども、新吉原に移っている。 |
| 3月 2日(明暦3年 1月18日) | 明暦の大火「振袖火事」が起こる。死者3万~10万人とも言われ、江戸入府以来の江戸の街は焼失し、新たに拡大された江戸が誕生することになる。 |
| 4月10日(明暦3年 2月27日) | 水戸藩で『大日本史』の編纂がはじまる。 |
| 8月27日(明暦3年 7月18日) | 歌舞伎などで、町奴の頭領、幡随院長兵衛が敵対する旗本奴の水野十郎左衛門の屋敷で殺害された日(あくまで創作上の日付)。 |
| 11月16日(明暦3年10月11日) | 肥前大村藩で郡村矢次の農民でキリシタンの兵作が捕らえられる。キリシタン大量検挙となった郡崩れのはじまり。 |
| この年、メディチ家の支援で科学研究団体アカデミア・デル・チメントがフィレンツェに設立される。活動期間は10年ほどだったが、各国の科学アカデミー設立へと広がっていくことになる。 | |
| 1658年 | |
| この年、明の復興を目指す鄭成功が大軍を率いて北伐に向かう。しかし南京攻略戦に失敗。 | |
| 1659年 | |
| 4月21日(万治2年 2月30日) | 会津から下野にかけて大きな地震。猪苗代城で石垣崩落、会津田島で民家297軒倒壊、塩原温泉郷で土砂崩れにより死者多数。 |
| 1660年 | |
| 7月25日(万治3年 6月18日) | 大坂城青屋門の焔硝蔵に落雷があり、貯蔵していた火薬2万1985貫600匁が大爆発。爆風で天守・御殿などが損壊、城外も含む1481戸が倒壊する。城内にいた29人と城外の3人が死亡。130人以上が負傷する大惨事となる。青屋門は東に14kmの生駒山系暗峠まで飛んだと言われる。 |
| 8月23日(万治3年 7月18日) | 幕府は仙台藩3代藩主の伊達綱宗を、放蕩を理由に強制的に隠居させ、嫡子でまだ2歳の亀千代を4代藩主に据える。一関藩主で叔父に当たる伊達宗勝が縁戚の池田光政、立花忠茂、京極高国と連名で老中首座の酒井忠清に願い出たものを受けてのこと。伊達騒動の始まりとなり、のちの寛文事件の原因となった。伊達綱宗が放蕩だったかははっきりせず、後西天皇の従兄弟だった綱宗を隠居させて伊達氏の力を削ぎたい酒井忠清と、仙台藩の実権を握りたい伊達宗勝による陰謀説もある。綱宗の4人の側近も殺害された。隠居後の綱宗は絵画や工芸に没頭し、多数の名作を残している。 |
| 1661年 | |
| この年、鄭成功が再起を図るため、台湾に移動。オランダ東インド会社の勢力を駆逐し、政権を樹立。 | |
| 1662年 | |
| 5月 4日(寛文2年 3月16日) | 徳川家光の側近で川越藩主の老中、松平信綱が死去。 |
| 6月16日(寛文2年 5月 1日) | 畿内を中心に東海・信濃にかけて大地震。特に琵琶湖周辺の被害が甚大で、唐崎、大溝、彦根などでそれぞれ家屋倒壊千軒以上、死傷者多数。京都でも町家など千軒以上が倒壊し200人余りが死亡する。比良断層、花折断層などが震源か。 |
| 6月23日(永暦16年 5月 8日) | 鄭成功死去。台湾政権はのちに東寧王朝と呼ばれる。 |
| 10月31日(寛文2年 9月20日) | 外所(とんところ)地震。日向灘で発生した推定マグニチュード7.6の大地震。日向国内各藩で大きな揺れを観測後、大津波が日向国と大隅国の沿岸部に襲来。沿岸部の7つの村8500石が水没し、また家屋3700件が損壊。死者200人以上。飫肥藩領の正連寺平野(宮崎平野南部)一帯は水没。清武川の流れが変わり水没した入江に流れ込む。この水没地域に近い現宮崎市木花島山には、災害を伝えるため50年ごとに供養碑が作られており、現在も続いている(7基目は2007年建立)。近年、もっと巨大地震だった可能性が指摘されている。 |
| 1663年 | |
| 8月16日(寛文3年 7月14日) | 有珠山が大規模噴火。焼け石などが麓に降り注ぎ、火災で5人が死亡。 |
| スコットランドの数学者ジェームス・グレゴリーがグレゴリー式反射望遠鏡を考案。どちらも凹面の主鏡と副鏡を対面させ、反射した像を主鏡の中央の穴を通して見る方式。実際に制作されるようになったのはニュートン式よりあと。 | |
| 1664年 | |
| 1月23日(寛文3年12月25日) | 明暦の大火の際に焼けた金銀の吹き直しを行った際に、目方をごまかして利潤を得ようとしたとして銀座人5人が遠島の処分を受ける。 |
| 4月23日(寛文4年 3月27日) | 旗本奴として知られた水野十郎左衛門こと水野成之が行跡怠慢を理由に祖母の出自である蜂須賀家にお預けとなるところ、伊達男を気取った姿で出頭したため、切腹となる。息子百助も処刑され旗本水野家は断絶。町奴との対立を懸念したという事情もあるとみられる。 |
| 1665年 | |
| 翌年にかけてロンドンでペストが流行。7万人が死亡したとされる。 | |
| 1666年 | |
| 1月22日 | ムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーン、幽閉先のアーグラ城で死去。タージ・マハルの建造者。 |
| 2月 1日(寛文5年12月27日) | 越後西部地震。大雪の中、越後高田などで、武家屋敷や町屋敷多数が倒壊。高田城にも被害出す。火災も発生し、1500人余りが死亡する。 |
| 9月 1日 | ロンドン大火。市内のパン屋から出火した火災が4日間燃え続け、市街地の85%を焼失する大火となる。死者は5名と人的被害は少なかったが、木造家屋の殆どが焼失した。現在のロンドンの原型はこのあとの都市再開発による。市街地が焼失し、菌を媒介するネズミが激減したことでペストの流行が収まったという説もある。 |
| 3月11日(寛文6年 2月 6日) | 千姫死去。 |
| 深良用水の建設が始まる。水資源に乏しい駿河東部に、箱根芦ノ湖から外輪山中を通って水を引く計画。深良村名主大庭源之丞の計画に江戸の4人の商人が資金を出して進められた。1670年完成。 | |
| 1667年 | |
| 7月31日 | 第二次英蘭戦争が終結。ブレダの和約で、北米ニーウネーデルラント(現ニューヨーク州)はイングランド領、南米ギアナはオランダ領となる。ニーウアムステルダム市もヨーク公領となってニューヨーク市と改められる。 |
| 11月 9日(寛文7年 9月23日) | 蝦夷樽前山が大噴火。 |
| この年、ジョン・ミルトンが長編叙事詩『失楽園』を完成する。神と戦うルシファーと、知恵の実を食べたアダムとエヴァが楽園を追放される物語。旧約聖書を題材にしているが、この作品自体がその後のキリスト教にも影響を与えた。ルシファーを英雄として描くのは、ミルトンが絶対王政と戦う共和主義者だったことも影響している。 | |
| 1668年 | |
| 3月31日(寛文8年 2月19日) | 宇都宮藩「追腹一件」事件。この日、宇都宮藩藩主奥平忠昌が病死。この直後、世子の奥平昌能は、忠昌の寵臣だった杉浦右衛門兵衛に「まだ生きてるのか」と詰め寄り、杉浦は切腹。当時主君の死に家臣が殉死するという悪弊が流行っており、幕府は殉死を禁じていたが、この一件を聞くと問題視し、8月に奥平家を2万石削減の上で山形9万石に転封。杉浦家の相続者を死刑とした。 |
| 4月13日(寛文8年 3月 2日) | 宇都宮興禅寺刃傷事件。宇都宮藩前藩主奥平忠昌の法要の席で、奥平家の親族である奥平内蔵允と奥平隼人の重臣同士の口論から刃傷事件が起こる。奥平内蔵允は切腹。この後、藩は両家を取り潰したが、内蔵允の子息・親戚は追放処分にし、隼人とその親族は護衛を付けて江戸に送ったため、藩内でこの処分に反発し脱藩するものが40人以上でた(「追腹一件」の不満もあったとみられる)。彼らがのちに「浄瑠璃坂の仇討事件」を引き起こす。 |
| 5月31日(寛文8年 4月21日) | アイヌ部族シュムクルの指導者でハエクルの首長だったオニビシが、対立していたアイヌ部族メナシクルの首長シャクシャインとの仲介をしていた砂金堀りの和人文四郎宅で、シャクシャインの軍勢に攻め込まれ殺害される。シュムクルは松前藩と関係が良かったが、これ以降勢力を失う。 |
| 6月 7日(寛文8年 4月28日) | 仙台藩士の伊東重孝が、藩主の隠居を訴えた一関藩主伊達宗勝を討つ計画が露見して処刑される。伊達騒動の事件の一つ。儒学者で剛直の士であったことから評判となり、寛文事件の要因の一つとなった。後に神社も立てられている。 |
| アイザック・ニュートンがニュートン式反射望遠鏡を開発。凹面の主鏡で反射した像を焦点の手前で斜めの平面鏡で方向を変え筒外に出し、焦点の接眼レンズで拡大して見る方式。コストが抑えられる上に、観測姿勢が楽なので天体観測用の大型望遠鏡で普及した。 | |
| 1669年 | |
| 3月 8日 | イタリアのエトナ山で噴火が始まる。7月まで大規模な噴火が続き、死者1万人。 |
| 6月21日(寛文9年 6月 4日) | 蝦夷でシャクシャイン主導のもと2000人以上のアイヌの大規模蜂起が起きる。シャクシャインの戦い。各地の和人が襲われ、主に老人や婦女子ら356人が殺される。背景にはシャクシャイン率いるアイヌ部族メナシクルと、オニビシが率いていたシュムクル部族の争いがあり、アイヌ交易の独占権を得た松前藩による蝦夷島各地での商場知行制への移行(アイヌの交易範囲が限定された)などによる和人への不満のなか、シャクシャインに殺されたオニビシの一派が松前藩に武器の提供を求め、争乱を避けたい松前藩に拒否される。ところが、この交渉にあたったオニビシの姉婿のウタフが病死したことで、和人に殺されたという話が広がり、これに乗じてシャクシャインが蜂起を呼びかけた。松前藩は幕府に支援を要請し、幕府は弘前藩、南部藩、秋田藩に援兵を命じる。 |
| 7月 | コサックのアタマン(指導者)スチェパン・ラージン率いる盗賊団に対し、ペルシアが討伐軍を出すも敗北。 |
| 9月16日(寛文9年 8月21日) | 松前藩がシャクシャインに対し攻勢を開始。兵を指揮した松前泰広(松前藩主の一族で旗本)は、各地の部族の首長に恭順を呼びかけ、部族間の対立や、松前藩と親しい関係にあったものもあり、シャクシャインから離反する部族が相次ぐ。 |
| 11月16日(寛文9年10月23日) | 松前藩がシャクシャインに和睦を呼びかけ、それに応じたシャクシャインがピポクの松前陣営に出向いたところ、和睦の酒宴中に謀殺される。松前藩としては戦乱が長期化して交易ができなくなることや、蝦夷島の権益を失ったり改易を恐れたためと見られる。 |
| 11月17日(寛文9年10月24日) | シャクシャインの居城だったシブチャリのチャシも陥落。シャクシャインの戦いは終結に向かう。これ以降松前藩のアイヌに対する支配が強まる。一連の背景には1600年代前半に相次いだ蝦夷地での火山の大噴火による環境の悪化もあるとされる。この戦いで弘前藩の援兵を率いた杉山吉成は、石田三成の孫(石田重成の子)で、石田家と交流があった弘前藩津軽家に保護され、藩主津軽信枚の娘を妻にして重臣となった人物。幕府に乱鎮定の報告をし褒賞を受けていることから、幕府もその出自を知っていたと見られる。 |
| この年、ドイツの研究者ヨハン・ベッヒャーが、物質の元素を「空気」「水」「石の土」「燃える土」「流動する土」と区分する。 | |
| 1670年 | |
| 4月 9日(寛文10年2月20日) | 紀伊国宮崎を出帆した阿波国所属の蜜柑輸送船が遭難漂流し、無人島だった母島へ流れ着く。同船に乗っていた荷主の長右衛門ら生き残った6人は、しばらく島で滞在した後、乗ってた船の廃材や見つけた和船などを利用して帆船を作り出帆。 |
| 6月12日(寛文10年4月25日) | 母島から出帆した長右衛門ら6人が、父島、聟島を経由して八丈島にたどり着く。5月5日に八丈島を出帆し、5月7日に下田に到着。奉行所に報告したことで幕府に小笠原諸島の詳細が伝わる。 |
| 6月24日 | スチェパン・ラージン率いる盗賊団が、アストラハンを占領し、同地に平等社会の共和国建設を唱え、ロシア・ツァーリ国に対して反乱。 |
| 10月 1日 | ロシア・ツァーリ軍とスチェパン・ラージン率いる反乱軍が、スヴィリ川で戦う。 |
| イタリアの司祭フランチェスコ・ラナ・デ・テルツィが、小型船に真空球を4つ付けて浮かばせる空飛ぶ船「真空飛行船」を発案。これを使った空襲も考えている。実際には作成はされなかったが、軽い気体で浮かせる「飛行船」のアイデアの原型とも言える。 | |
| 1671年 | |
| 5月 6日(寛文11年 3月27日) | 寛文事件。仙台伊達家の親族(伊達宗重と伊達宗倫)の領地争い(谷地騒動)で、一関藩主伊達宗勝の介入を受けたことに反発した伊達宗重の訴えで、両者から関係者が出席し幕閣による審問が行われた大老酒井忠清邸で、出席していた伊達家重臣で宗勝側の原田宗輔が抜刀し伊達宗重を斬殺。宗重側で出席していた柴田朝意と、聞役の蜂屋可広が応戦するが、事態に駆けつけた酒井家家臣によって3人共区別なく殺害される。事件を受けて、原田家は男子すべて処刑となり断絶。仙台藩の実権を握っていた伊達宗勝は改易となり、宗勝とその家族は各藩に永預りとされた。創作では真の黒幕とされる大老酒井忠清だが、宮将軍擁立に動くなど絶大な権力を振るった一方、5代将軍綱吉の代になって将軍との確執で失脚したことも悪役にされた可能性がある。歌舞伎の演目「伽羅先代萩」や山本周五郎の小説「樅ノ木は残った」のモデルとなった。 |
| 6月16日 | スチェパン・ラージンがロシア・ツァーリ国によって赤の広場で処刑される。 |
| 10月25日 | ジョバンニ・カッシーニが土星の衛星イアペトゥスを発見する。このあと数度に渡って観測するが、土星の東側では観測できず、西側にいるときだけ観測できた。これはイアペトゥスの表面の公転先行側と側面が非常に暗く、公転後行側と極地方が非常に明るいという極端な二色構造になっており、そのどちらが地球側に向いているかで変わるため。 |
| 1672年 | |
| 3月 2日(寛文12年 2月 3日) | 浄瑠璃坂の仇討事件。奥平藩で起きた刃傷沙汰で自刃した奥平内蔵允の子、奥平源八と支持者計42人が江戸市ヶ谷浄瑠璃坂の鷹匠頭戸田七之助邸に匿われていた奥平隼人を襲撃。十数人を倒すも、奥平隼人を見つけられず引き上げる途中、牛込御門近くで手勢を率いて追ってきた奥平隼人と交戦。隼人を討ち取る。出頭した奥平源八らに対し、幕府は私闘として厳罰に処す方針であったが、大老井伊直澄が減刑し伊豆大島流罪に処した。6年後に天授院13回忌の恩赦で許されている。赤穂浪士が討ち入りと処罰の参考にしたとも言われる。 |
| 8月20日 | 第三次英蘭戦争のさなか、ネーデルラント共和国の指導者ヨハン・デ・ウィットが兄コルネリスとともに、戦争に苦しむ民衆の怒りを買い殺される。ホラントの君主オラニエ=ナッサウ家が事実上の復位。 |
| この年までに、フランス人司祭で天文学者だったローラン・カセグレンがカセグレン反射望遠鏡を考案したと考えられる。凹面の主鏡と凸面の副鏡を対面させて反射した像を主鏡の中央の穴を通して見る方式。構造とカセグレンの姓だけ伝わったため発明の詳細は不明。ローランは有力候補の一人。 | |
| 1673年 | |
| 2月 4日(寛文12年12月18日) | 徳川秀忠の子で、松平会津藩の祖である保科正之が死去。 |
| (康煕12年) | 清朝で三藩の乱が勃発。康熙帝がこの年、漢人の平西王呉三桂が領する雲南、平南王尚之信が領する広東、靖南王耿精忠が領する福建の三藩の廃止を決定。これを受けて呉三桂が反乱。 |
| 1674年 | |
| アントニ・ファン・レーウェンフックが自作顕微鏡でバーケルス湖から採取した水を観察し、微生物を発見。アニマルクルと名付ける。 | |
| (康煕13年) | 呉三桂の反乱が拡大。耿精忠も呼応し、陝西、広西でも反乱が相次ぐ。 |
| 1675年 | |
| 3月 4日 | イングランド王チャールズ2世によって、ロンドン市郊外にグリニッジ天文台が設立される。初代イングランド王室天文官にジョン・フラムスティードが任命され、初代天文台長となる。フラムスティードの時代に、グリニッジ標準時が定められた。 |
| 5月23日(延宝3年4月29日) | 母島へ漂流した長右衛門らの報告から幕府は32人の調査団を富国寿丸に乗せて派遣。この日、父島に到着。6月6日まで小笠原諸島を調査。この報告がのちの領有権問題で日本領とする根拠となった。 |
| この年、デンマークはスコーネ領を奪還するため、スウェーデン・バルト帝国へ宣戦布告。スコーネ戦争が始まる。 | |
| この年、ロンドンの商人アンソニー・デ・ラ・ロッシュがフォークランド諸島の1000km東でサウスジョージア諸島・サウスサンドイッチ諸島を発見する。サウスジョージア島は、古地図では「ロッシュ島」と記載されている。 | |
| 1676年 | |
| イギリス領バージニア植民地でナサニエル・ベイコンらが反乱を起こす。重税や物価高騰などに伴う貧困への不満やインディアン部族への強攻策を主張してバージニア総督らに対して起こしたとみられる。 | |
| 10月26日 | ナサニエル・ベイコンが病死。反乱はそのまま継続するも、バージニア総督ウィリアム・バークリーの反撃で終息していく。 |
| この年、加賀藩4代藩主前田綱紀が、金沢城そばの御作事所跡地に別荘「蓮池御殿」を建設。ずっとのちの1822年(文政5年)前田斉広が同地に竹沢御殿を作った際に松平定信によって兼六園と命名される。 | |
| 1677年 | |
| 5月14日(延宝5年 4月13日) | 延宝八戸沖地震。 |
| 11月 4日(延宝5年10月 9日) | 延宝房総沖地震。夜、突如大津波が関東から東北南部の太平洋岸を襲う。沿岸各地で千軒以上の家屋が流失。船舶にも大きな被害を出し、房総から磐城までの沿岸で数百人が流されるなどして死亡。大きな地震の揺れの記録がないことから、房総半島沖合で起きたマグニチュード8クラスの巨大地震による津波と考えられる。 |
| 1678年 | |
| 2月27日(延宝6年 1月 7日) | 初代夕霧太夫が死去。京の花街島原の「扇屋」の太夫となり、のちに大坂新町に移転したことから新町の太夫としても知られた女性。江戸文学・浄瑠璃などの題材となった。命日は夕霧忌ともいう。 |
| 4月(康煕15年/昭武元年 3月) | 三藩の乱を起こした呉三桂が即位して周王朝を興し昭武と改元。 |
| 10月 2日(康煕15年/昭武元年/洪化元年 8月17日) | 呉三桂が病死。孫の呉世璠が後を継ぎ、元号を洪化とする。 |
| 1679年 | |
| 9月 | ルンド条約により、スウェーデンとデンマークが和睦し、スコーネ戦争は終結。領土は結局変わらず。フランスが介入してきたことに両国は反発し、結果として両王家は婚姻関係を結び、両国は同盟国となる。 |
| 12月 5日(延宝7年11月 3日) | 130人も殺したと言われる辻斬り強盗の平井権八が処刑される。絵画や歌舞伎の演目では白井権八という名で知られるほか、白浪五人男の赤星十三郎のモデルともされる。 |
| 1680年 | |
| 9月13日(延宝8年 8月21日) | 徳川綱吉に征夷大将軍宣下。第5代将軍となる。 |
| 1681年 | |
| 8月 5日(延宝9年 6月22日) | 将軍徳川綱吉が越後騒動の決着をつける。親藩である越後高田藩の家臣同士の内紛で、一度は幕府の裁定で決着がついていたものを再審したもの。逆意方と呼ばれた元家老小栗美作とその子に切腹、小栗と対立しお為方を自称した永見大蔵、荻田本繁らを遠島とする両成敗となる。 |
| 8月 9日(延宝9年 6月26日) | 越後高田藩は改易となる。先に裁定を下した幕府関係者も改易などの処分を受けた他、高田藩松平家の旧本家越前松平家の一門である姫路藩松平家は減封の上豊後へ移され、出雲広瀬藩松平家は減封となった。 |
| 12月31日(天和元年11月22日) | 沼田藩真田家が改易される。藩主真田信利(信直)は、松代藩真田家初代真田信之の庶長子信吉の次男だが、松代藩は信之の次男信政が2代藩主となり信利は沼田領のみ相続した。藩主信政の死後は、その子の幸道が3代目となったため、信利は自分こそ後継者であると訴えたものの認められず、代わりに沼田領は3万石の独立藩となった。信利は本藩に対抗して検地を行い実高14万4000石と届け出、江戸屋敷も豪奢に建て替えたが、その負担が領民にかかる。さらに幕府からの両国橋架替えの材木調達に失敗。領民杉木茂左衛門が、輪王寺宮の文書を偽って将軍綱吉に圧政を上訴したため実態が発覚。沼田藩真田家は治世不良として改易となった。 |
| (康煕20年/洪化4年) | 清朝政府軍が昆明を攻め落とし、周王朝2代目呉世璠は自害して滅亡。 |
| この年、マスカリン諸島モーリシャス島で最後のドードー鳥(モーリシャス・ドードー)が目撃される。間もなく絶滅。最初の目撃例からわずか83年。人間による乱獲と人間が持ち込んだ動物による捕食、森林伐採が原因。 | |
| 1682年 | |
| 9月15日 | 彗星が出現し、エドモンド・ハレーが、過去の彗星と同じではないかと気づく。次の彗星の出現を予言。 |
| (天和2年) | 江戸幕府、勘定吟味役を設置。老中に属し、勘定所を監察、幕府直轄領や代官を監督する役職。 |
| 1683年 | |
| 1月25日(天和2年12月28日) | 天和の大火。この大火で罹災した少女、八百屋お七が、避難先で出会った寺小姓に会いたいがために、後に放火をして処刑されたことから、通称「お七火事」と呼ばれる。死者3500人以上。 |
| 6月 | イングランドでライハウス陰謀事件が発覚。カトリックへ接近する国王チャールズ1世とその後継者ヨーク公ジェームズの排除を狙った「ホイッグ」(ジェームズ即位反対派)による暗殺計画の陰謀が発覚し、一網打尽となる。陰謀は国王あるいは「トーリー」(ジェームズ即位支持派)による捏造という説もある。なおカトリックに対する抵抗感は、ホイッグもトーリーも共通しており、あくまでジェームズ即位の是非による違いでしかなく、後に両者は手を組み名誉革命を引き起こしてジェームズ2世を追放する。 |
| 7月13日 | オスマン帝国の大宰相カラ・ムスタファ・パシャによって第二次ウィーン包囲戦が始まる。直前に脱出した神聖ローマ皇帝が各地の諸侯に救援を要請。 |
| 8月17日(天和3年 6月25日) | 江戸城西の丸で下馬をめぐり旗本柳沢信花と大番士高橋正武が口論から刃傷沙汰となり、柳沢信花が殺害される。信花が婿養子に入っていた叔父柳沢安忠の実子が柳沢吉保。 |
| (康煕22年/永暦37年 8月) | 台湾東寧王国の鄭克塽が清朝に降伏し、鄭氏王朝は3代で滅亡。鄭克塽は海澄公に封じられた。 |
| 9月12日 | オスマン帝国軍に包囲されているウィーン郊外に救援のポーランド国王ヤン3世ソビエスキ率いるポーランド・ドイツ諸領邦連合軍が到着。ロレーヌ公シャルル5世、バイエルン選帝侯マクシミリアン2世、ザクセン選帝侯ヨハン・ゲオルク3世、バーデン辺境伯ルートヴィヒ・ヴィルヘルム、ヴァルデック侯ゲオルク・フリードリヒらも参戦。夕刻、救援軍は早々にオスマン陣地を攻撃。オスマン軍は大敗を喫し、退却。オスマン帝国の衰退のきっかけとも言われる一方、トルコ行進曲やコーヒーなどのトルコ文化が西洋に広まるきっかけともなった。勝利を祝してクロワッサンやベーグルが作られたとも言われる。 |
| 10月20日(天和3年 9月 1日) | 下野国で大きな地震。三依川沿いで山崩れにより河道閉塞。日光、会津などでも被害。 |
| 12月25日 | オスマン帝国の大宰相カラ・ムスタファ・パシャが、第二次ウィーン包囲戦の敗北の責任を問われ、メフメト4世の勅によって処刑される。強権的だったことで政敵が多かったことも要因の1つ。同時に指導者を失いオスマン帝国は弱体化していく。 |
| 1684年 | |
| 10月 7日(貞享元年 8月28日) | 堀田正俊暗殺事件。江戸幕府大老・堀田正俊が、江戸城内で、従叔父で若年寄の地位にあった稲葉正休に殺害される。正休は駆けつけた老中の大久保忠朝、阿部正武、戸田忠昌らに斬り殺される。事件の原因は不明だが、前年に正休が提出した淀川治水工事の見積りを正俊が採用せず、その任から正休を外したことで恨んだとする説もある。正休の青野藩は取り潰しとなったが、正俊の剛直な性格を嫌い、加害者である正休への同情論のほうが強かった。事件の背後には正俊を嫌った将軍綱吉がいるという説もある。 |
| 1685年 | |
| 7月15日 | イングランド国王ジェームズ2世に対して反乱を起こし失敗に終わった初代モンマス公爵ジェイムズ・スコット(ジェームズ2世の甥)が、タワーヒルで斬首される。死刑執行人ジャック・ケッチによって処刑されたが、斧での斬首を何度も失敗し、結局ナイフで首を切り落とされた。 |
| 8月24日(貞享2年 7月25日) | 岡本三右衛門ことジュゼッペ・キアラが死去。もとはイタリア出身のイエズス会宣教師。師であり日本管区長代理のフェレイラが棄教したという話を聞いて日本へ渡航。幕府に捕らえられ、拷問を受けて棄教。刑死したキリシタン岡本三右衛門の妻女を娶り、名を受け継いだ。幕府の宗門改方の職につき、キリスト教について「天主教大意」を執筆提出しており、後に新井白石のシドッティ尋問の際にも参考にされた。遠藤周作の小説「沈黙」の主人公ロドリコ司祭のモデルとなった人物。 |
| 10月18日 | フランス国王ルイ14世がフォンテーヌブローの勅令に署名。ナントの勅令を破棄し、新教徒ユグノーをカトリックに改宗させるための法令。多くのユグノーがフランス国外へ脱出・亡命し、ユグノーを受け入れたオランダでは金融業が、ドイツでは農業が、スイスでは時計産業が発達するきっかけとなった。一方のフランスでは産業・経済が大打撃を受けたと言われる。 |
| 1686年 | |
| 1月 4日(貞享2年12月10日) | 安芸国・伊予国・周防国・長門国で大きな地震。 |
| 4月30日(貞享3年閏3月 8日) | 石田三成の嫡子で、家康によって助命された石田重家(宗享)が104歳で亡くなる。年齢は諸説あるが、いずれにせよかなりの長命だったとみられる。 |
| 11月29日(貞享3年10月14日) | 信濃松本藩で大規模な一揆「貞享騒動」が起きる。重税に反発した農民らが多田加助の指導で年貢減免の要求を提示したもので、藩は一旦条件を呑むも撤回し、加助ら28名が処刑された。藩主は藩士の説得で刑執行を中止にしたが間に合わなかったとも。 |
| この年、イングランドの死刑執行人ジャック・ケッチが死去したとされる。下手なのか意図してなのか、斧での斬首に何度も失敗して受刑者を苦しめることで悪名高き人物だった。 | |
| 1687年 | |
| 7月 5日 | アイザック・ニュートンが『自然哲学の数学的諸原理』(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)を発刊。万有引力の法則などが記された古典力学の書。題名を略して「プリンキピア」「プリンシピア」とも呼ばれる。科学史上非常に重要な書だが、この時は王立協会からの支援が得られず、執筆のきっかけを作ったエドモンド・ハレーが資金を支援して出版にこぎつけた。 |
| 9月26日 | ヴェネツィアとオスマン帝国とのモレアス戦争のさなか、アテネを占領したヴェネツィア軍が、パルテノン神殿にあったオスマン軍の火薬庫に向けて迫撃砲で攻撃。火薬庫が大爆発を起こし、爆風と火災で神殿の壁やレリーフが大きく崩れ落ちる。トルコ兵300人も死亡。 |
| 生類憐れみの令発布。 | |
| 1688年 | |
| 3月(貞享5年 2月) | 水戸藩主徳川光圀が建造させた「快風丸」が蝦夷地探検を行う。通算3度めでようやく石狩川まで到達。蝦夷の産物を積んで帰還。「快風丸」は通説では長さ37間、幅9間、積載量1万2千石といわれ、将軍家光が建造させた御座船「安宅丸」を上回る巨船だった。本来は大船建造の禁令に触れているが、水戸徳川家であるため黙認されたものか。 |
| 8月25日 | イギリスの海賊で、後に判事やジャマイカ代理総督など要職を歴任し、海賊を取り締まる側に付いたヘンリー・モーガンが死去。 |
| ドイツのザールラント州で炭層火災が発生。鎮火せず、21世紀の現在も内部でくすぶり続けている。ブレンネンダー・ベルク(燃える山)と呼ばれて早くから観光地化した。 | |
| 1689年 | |
| 2月13日 | オランダ総督ウィレム3世が、国王と対立する英国議会の要請を受けて、オランダ軍を率いてイングランドに侵攻。叔父のジェームズ2世を追放してイングランド王ウィリアム3世となる(妻のメアリー2世が女王として即位し、その共同統治者となる)。少数の犠牲者だけで権力を確立し、権利の章典、議会政治の確立、カトリックに代わるイングランド国教会体制など、イギリスの歴史的転換点の一つとなったことから、「名誉革命」と呼ばれる。 |
| 9月 6日(康熙28年7月23日) | ロシア帝国と清がネルチンスク条約に調印。満洲地方の両国の国境を定めた条約。 |
| 1690年 | |
| 10月20日(元禄3年 9月19日) | 日向国坪谷・山陰一揆が起こる。有馬氏延岡藩の圧政に苦しんだ農民1422名が高鍋藩領に逃散、高鍋藩に保護される。 |
| 11月14日(元禄3年10月14日) | 徳川光圀が隠居。水戸藩の家督相続で差し置いてしまった兄の松平頼重(讃岐藩主)の子である綱條に藩主の地位を譲る。 |
| 12月頃 | パリ天文台の天文観測図の中に、ジョバンニ・カッシーニが木星面で小天体の衝突痕のようなものを観測し記録したものがある。当時は天体衝突とは気づいていないと思われるが、1994年のシューメーカー・レビィ彗星の衝突痕とよく似ている。 |
| 1691年 | |
| 7月18日(元禄4年 6月23日) | 日向国坪谷・山陰一揆の幕府の裁定が下る。農民7名が首謀者として処刑され7名が遠島処分となり、残りは元の土地へ戻ることとされたが、一方で延岡藩の郡代梶田十郎左衛門と代官大崎久左衛門も追放。 |
| 8月27日 | 名誉革命でイングランド王となったウィリアム3世が、北部ハイランド地方の氏族らに翌年1月1日までに、自身と妻メアリー2世に忠誠の契約を行うよう命令。 |
| 12月27日(元禄4年11月 8日) | 延岡藩主有馬清純は糸魚川へ転封処分となり、山陰・坪谷は天領となる。 |
| 1692年 | |
| 2月13日 | グレンコーの虐殺事件。イングランド名誉革命の強硬派だったステア伯と、ハイランドで革命側にいち早く味方したキャンベル氏族が組んで、国王ウィリアム3世が許可し、キャンベル氏族と対立していたマクドナルド氏族を「忠誠の誓約が遅れた」として襲撃。族長ら一族38人を殺害し、グレンコーの同家領地の家々に火を放って住民ら40人が焼き殺される。犠牲無しで革命を成功したとして「名誉革命」と称賛されたウィリアム3世らは内外から激しい非難を受ける結果となる。またマクドナルド家は村に来たロバート・キャンベルをもてなした後で虐殺されたことから、キャンベル一族はその行為を長く責められることになる。 |
| 3月 1日 | セイラム魔女裁判が始まる。アメリカ合衆国マサチューセッツ州セイラムで、悪魔と契約したという理由で、住民同士が告発しあい、村人19名が処刑され、1名が拷問で死亡し、5名が獄死した事件。 |
| 1693年 | |
| 5月 5日(元禄6年 3月30日) | 美濃郡上八幡藩2万4千石の藩主遠藤常久が7歳で病死。当然嗣子もなく改易となるはずが、藩祖遠藤慶隆の功を賞するという理由で、遠藤家とは全く無関係の、徳川綱吉の側室「お伝の方(瑞春院)」の妹と旗本白須正休の長男数馬を遠藤家の親族である戸田氏成の養子にした上で、遠藤家の再養子にして遠藤胤親に改め、常陸・下野1万石で存続することとなった(のち近江三上藩)。親族を大名にしたい瑞春院の意向が働いたとみられる。なお遠藤常久の死因には重臣池田主馬による毒殺説がある。 |
| この年、シチリア島で大地震が起こり、カターニアは壊滅。 | |
| 1694年 | |
| 3月 6日(元禄7年 2月11日) | 高田馬場の決闘。伊予西条藩藩士の菅野六郎左衛門と村上庄左衛門が江戸高田馬場で決闘におよび、剣客中山安兵衛(のちの赤穂浪士堀部武庸)が助太刀した事件。 |
| 6月19日(元禄7年 5月27日) | 能代地震。羽後国能代付近の能代断層を震源とする。能代一帯の42ヶ村が被害に逢い、家屋倒壊1273戸、焼失859戸、死者394人。被害の殆どは能代に集中し壊滅状態となった。 |
| 11月28日(元禄7年10月12日) | 松尾芭蕉が、大坂の御堂筋の旅宿・花屋仁左衛門方で死去。 |
| 1695年 | |
| 1月 8日(元禄7年11月23日) | 江戸小石川の水戸藩邸で行われた能会において、家老の藤井徳昭が、前藩主の徳川光圀の手で刺殺される。光圀は自ら舞台で演じる直前に藤井を部屋に呼んで殺害したと言われる。藤井は光圀に重用されて小姓から家老にまで登った人物であり、なぜ光圀が藤井を直接殺害したのか、動機は不明。 |
| 12月 5日(元禄8年10月29日) | 江戸幕府5代将軍徳川綱吉の生類憐れみの令によって、現在の中央線中野駅付近に16万坪もの広大な犬飼育施設「中野犬屋敷」が完成する。 |
| 1696年 | |
| 10月25日(元禄9年 9月30日) | 明からの来日僧である東皐心越が死去。明末の混乱で日本へ亡命。各地を巡るが、幕府によって長崎で幽閉された。その後、徳川光圀の尽力で釈放されると、水戸に居住し篆刻や古琴を伝授したため、日本篆刻の祖、鎌倉以降衰微していた日本琴楽の中興の祖とも言われる。 |
| 1697年 | |
| 9月11日 | ゼンタの戦い。神聖ローマ帝国を主体とする神聖同盟とオスマン帝国の戦いで、神聖同盟が勝利。オスマンの大宰相エルマス・メフメト・パシャは戦死。 |
| 9月20日 | レイスウェイク条約締結。大同盟戦争終結。 |
| ドイツの医師ゲオルク・エルンスト・シュタールが、ヨハン・ベッヒャーの唱えた元素「燃える土」を元に、物が燃える現象を司る元素を「フロギストン(燃素)」と名付ける。フロギストン説。物質が燃えたり錆びたりするのは、物質とくっついたフロギストンが離れる現象とした。以降、フロギストン説は広まっていく。 | |
| 11月25日(元禄10年10月12日) | 鎌倉で地震により鶴岡八幡宮の鳥居が倒壊。江戸城などでも石垣に被害。 |
| 1698年 | |
| 7月31日 | ウィーンで細川ガラシャをモデルにした戯曲「勇敢なる婦人、その真実の価値は遠い果てより到来した真珠のような婦人グラツィア。丹後国の王妃である彼女は、キリストのための受難に耐えて光り輝く」が上演される。作曲はヨハン・ベルンハルト・シュタウト、戯曲の作者はヨハン・バプティスト・アドルフ。内容は史実とはかなり異なり、典型的な殉教劇。 |
| 9月(元禄11年 8月) | 将軍徳川綱吉の50歳誕生日を祝って、隅田川に永代橋が架けられる。 |
| 10月 9日(元禄11年 9月 6日) | 江戸で勅額火事が起こる。昼少し前に京橋南鍋町(山下町)の仕立物屋より出火し、強風により数寄屋橋の大名邸へ類焼、更に北側へと広がり、神田一帯を焼き、火勢は北上して下谷、浅草に、更に東進して両国橋を超え本所に達する。夜、雨によって鎮火。死者3000人を超える。落成したばかりの寛永寺根本中堂に掲げる東山天皇の勅額が届いた日に火災になったことから勅額火事と呼ばれる。 |
| 1699年 | |
| オスマン帝国とロシアを除くヨーロッパ各国が、カルロヴィッツ条約を締結。ゼンタの戦いで敗北して後、勢力が弱まったオスマン側が、各国に領土を割譲。 | |
| 1700年 | |
| 3月 | 大北方戦争が勃発。北方同盟(反スウェーデン同盟)のデンマーク軍がスウェーデン(バルト帝国)の同盟国ホルシュタイン=ゴットルプ公領へ侵攻しテンニングを包囲。ほぼ同時期、ザクセン・ポーランド王アウグスト2世もスウェーデン領へ侵攻しリガを包囲。 |
| 4月15日(元禄13年 2月26日) | 壱岐・対馬で大きな地震。家屋倒壊や石垣の崩壊多数。 |
| 7月14日 | ロシア・ツァーリ国とオスマン帝国が、コンスタンティノープル条約を締結。オスマン側はロシアが占領したアゾフ地方の割譲に同意。一方ロシアもスウェーデン・バルト帝国との大北方戦争が迫り余裕がなく、黒海の自由航行権は取り下げて妥協が成立。露土戦争は終結。 |
| 7月 | スウェーデンはイングランド、ネーデルラントの両国の支持を得て、デンマークの王都コペンハーゲンへ侵攻。 |
| 8月18日 | スウェーデンとデンマークはトラヴェンタール条約を締結。大北方戦争からデンマークが離脱する。 |
| 11月30日(スウェーデン暦11月20日) | ナルヴァの戦い。バルト海沿岸の都市ナルヴァでスウェーデン軍とロシア軍が衝突。スウェーデン軍が吹雪の中ロシア軍を奇襲攻撃し勝利。 |
| 1701年 | |
| 1月16日(元禄13年12月19日) | 深堀事件。長崎で佐賀藩深堀領の重臣深堀三右衛門が雪どけの泥をはねたことに対し、長崎会所の有力町人高木貞親の家来が咎めて口論となり、高木家の家臣10数人が深掘邸を襲撃する事態に発展。それをうけて三右衛門と深堀家家臣の計12人が高木邸を襲撃し、高木貞親が殺害される(深堀三右衛門と志波原武右衛門はその場で自刃)。長崎奉行から報告が上がった幕府が判決を出し、深堀家の10人を切腹、後から加勢に来た9人を五島に遠島にし、先に騒ぎを起こした高木家の9人を斬首とし、高木家は家財没収となった。江戸でも話題になったと記録にあり、まもなく起きた赤穂浪士討ち入りの参考にされたとする説もある。 |
| 3月13日(元禄14年 2月 4日) | 東山天皇の勅使饗応が行われることになり、饗応馳走役は播磨赤穂藩主浅野長矩と伊予吉田藩主伊達村豊で、高家肝煎の吉良義央が指導に当たることと決まる。 |
| 4月21日(元禄14年 3月14日) | 東山天皇の勅使饗応が行われる予定にあった江戸城中松の廊下において、突如、赤穂藩主の浅野内匠頭長矩が、高家筆頭吉良上野介義央に対して抜刀の上襲いかかり、吉良上野介は額などに負傷するも品川伊氏と畠山義寧によって助けられる。浅野内匠頭は梶川頼照に取り押さえられ、即日、収監された田村建顕の屋敷で切腹。赤穂藩は取り潰しと決まる。 |
| 5月26日(元禄14年 4月19日) | 赤穂城が開城となる。龍野藩主脇坂安照が赤穂城を預かる。 |
| 7月19日(スウェーデン暦 7月 9日) | ドヴィナ川(ダウガヴァ川)の戦い。スウェーデン軍がリガ救出のためにドヴィナ川を渡河し、ザクセン・ポーランド軍を撃破。リガを解放。 |
| 7月29日(元禄14年 6月24日) | 赤穂城在番中の龍野藩脇坂家家臣左次兵衛が同僚の貞右衛門を惨殺する事件が起きる。 |
| 9月21日(元禄14年 8月19日) | 幕府は吉良義央に旗本松平信望が本所に持っていた比較して小さな屋敷への屋敷替えを命じる。吉良への贔屓が批判されたためとも、赤穂浪士の討入を黙認したため、とも言われる。 |
| 9月23日(元禄14年 8月21日) | 幕府は吉良義央実弟の東条冬重、吉良よりの高家大友義孝、浅野長矩を室内ではなく庭で切腹させた大目付庄田安利も役職を取り上げる。これも世情の批判をかわすためとみられる。 |
| 1702年 | |
| 1月 9日(元禄14年12月12日) | 吉良義央は高家肝煎職を返上し隠居。吉良義周が跡を継ぐ。 |
| 1月 9日(スウェーデン暦1701年12月30日) | 大北方戦争、エーレスターの戦い。ロシア軍がリヴォニアのスウェーデン軍を撃破。 |
| 8月11日(元禄15年 7月18日) | 播磨赤穂浅野家再興の最後の可能性であった内匠頭弟浅野大学長広が広島の浅野本家に預けられることになり、再興の望みが消える(のち旗本となった)。大石内蔵助良雄ら再興派が討ち入りを決意することになったとされる。 |
| 8月23日 | カディスの戦い。八十年戦争。イングランド・オランダ連合軍が、スペインのカディスを9月30日まで1ヶ月以上に渡って攻めるが失敗に終わる。 |
| 1703年 | |
| 1月30日(元禄15年12月14日) | 元禄赤穂事件。赤穂浪士四十七士が吉良邸へ討ち入る。吉良義央は死亡。吉良義周も重症を負う。四十七士に死者は無し。 |
| 3月20日(元禄16年2月 4日) | 赤穂浪士四十七士のうち、姿を消した足軽寺坂信行以外の46人は預けられた四大名邸で切腹し、その子らも流罪の処分を受ける。一方の吉良家も正式に改易され、吉良義周は信濃諏訪藩高島へ配流となる。 |
| 5月27日 | サンクトペテルブルク建都の日。ユリウス暦では5月13日。ロシア初代皇帝ピョートル1世によって建設。 |
| 11月19日 | バスティーユ監獄に収監され、人と会うときは面布を付けることを命ぜられていた「仮面の男」が死亡する。のちアレクサンドル・デュマ・ペールの小説で「鉄仮面」として取り上げられる。位の高い人物と考えられるが正体は諸説ある。 |
| 12月31日(元禄16年11月23日) | 元禄大地震。房総半島南端を震源とする大震災。深夜2時ころに発生。マグニチュードは8以上と推定される。小田原城下で火災が起き、天守も焼失するほどの大きな被害を出す。小田原藩領内で家屋8000が倒壊し、死者およそ2300人。川崎などでも被害が出る。江戸でも建物の倒壊が起き御堀の水が溢れたという。江戸市中にまで津波が押し寄せる。各藩が提出した家屋被害は28000軒、死者6700人。直後の11月29日の大火の犠牲者も合わせると、死者20万人以上とも言われる。震源は相模トラフか。三浦半島や房総半島の突端が大きく隆起した。この震災を受けて宝永に改元することになる。同日、名古屋や京都でも地震を観測。液状化や発光現象も記録されている。 |
| 12月31日(元禄16年11月23日) | 元禄豊後地震。早朝に豊後で大きな地震があり、府内を中心に数百軒の家屋が倒壊。震源は由布院付近と見られ、元禄大地震とは別の地震。 |
| 1704年 | |
| 1月 6日(元禄16年11月29日) | 江戸で大火。通称「水戸様火事」。小石川の「水戸宰相御屋敷」から出火し、本郷へ延焼した後、風向きが変わり東へと拡大。本所に到達した。武家屋敷275、寺社75、町家2万軒が焼失。元禄地震でも火災が起きたことから、被害面積は明暦の大火より広い。かなりの死者を出した可能性があるが、元禄地震直後の混乱で詳細は不明。地震全体の犠牲者とあわせて20万人以上が死亡したとも言われる。 |
| 3月24日(元禄17年 2月19日) | 歌舞伎役者初代市川團十郎が、市村座で『移徙十二段(わたましじゅうにだん)』の佐藤忠信役を演じている最中に、役者の生島半六に舞台上で刺殺される。 |
| 5月 6日(宝永元年 4月 3日) | 生島半六が獄死。 |
| 5月 6日(宝永元年 5月27日) | 羽後陸奥地震。津軽から羽後能代にかけて、家屋2000戸が焼失。死者70余人。西津軽の崩山崩壊により河道閉塞が起きて十二湖(33の湖沼)が形成される。10年前に起きた能代地震の復興間もなく再び起きた大地震により甚大な被害を出す。それまで「野代」と記載されていたが、「野と代わる」と読めることから「能代」に改めたと言われる。 |
| 8月 1日 | スペイン継承戦争で、イングランド、オランダ、オーストリアの連合軍がジブラルタルへ派兵。4日までに占領。ジブラルタルがイングランドの海外領土となる。 |
| 8月24日 | マラガの海戦。スペインのマラガ沖でフランス・スペイン連合艦隊とイングランド・オランダ連合艦隊の間で海戦となる。 |
| 1705年 | |
| 10月14日 | ポーランド=リトアニア共和国の大半を占領したスウェーデン(バルト帝国)は、スタニスワフ・レシチニスキを同国の国王に就ける。同国国王であったザクセン選帝侯でもあるアウグスト2世との間で内戦状態に。 |
| エドモンド・ハレーが『彗星天文学概論』を発表。過去に観測記録のある彗星が、実は同じ彗星で、太陽の周りを周回しており、次の出現年を予測した。この彗星が後にハレー彗星と名付けられる。 | |
| 1706年 | |
| 10月13日 | スウェーデン(バルト帝国)とザクセン・ポーランド=リトアニアとの間でアルトランシュテット条約締結。ザクセン選帝侯兼ポーランド=リトアニア共和国国王アウグスト2世は大北方戦争から離脱。 |
| 1707年 | |
| 10月28日(宝永4年10月 4日) | 宝永大地震。震源域は紀伊半島沖から、四国沖、日向灘にかけて。いわゆる東海地震と南海地震が連続して起こったもので、激しい揺れと大津波の襲来で、大坂や土佐など西日本各地で大被害を出す。揺れは東北から九州の広域で観測。死者は推定で2万人。駿河の安倍川上流にある大谷嶺が大規模な山体崩壊を起こしたほか、各地で山体崩壊や山崩れが起きた。土佐では各地で地盤が隆起した一方、高知付近では沈降している。震源域が広いためか、数分から20分以上の長時間揺れたという記録が多い。津波は中国大陸にも到達し被害を出している。 |
| 10月29日(宝永4年10月 5日) | 大地震の約16時間後に富士宮付近を震源とする強い地震が発生。富士宮などで大きな被害を出した他、江戸や名古屋でも大きな揺れを観測。 |
| 11月20日(宝永4年10月27日) | 江戸幕府、震災後の物価統制のため、買い溜め禁止令を発する。 |
| 12月16日(宝永4年11月23日) | 昼少し前に富士山の噴火が始まる。宝永の大噴火。直前に鳴動と地震が観測されている。江戸などで空振を観測。江戸でも灰が降り、日没頃その色が黒く変色したため、マグマ噴火に変化したとみられる。宝永大地震がきっかけになったという説もある。 |
| 12月17日(宝永4年11月24日) | 富士山の噴火は収束の方向へ向かう。この日の夜、比較的広範囲で大きな地震を観測(噴火に関連するものか、宝永地震の余震かは不明)。 |
| 12月25日(宝永4年12月 2日) | 富士山が再び活発に噴火を始める。 |
| 12月31日(宝永4年12月 8日) | 夜、富士山で大きな爆発があった後、翌未明の爆発を最後に終息する。 |
| 1708年 | |
| 2月28日(宝永5年閏1月 7日) | 江戸幕府、大名・旗本に石高100石に付き2両を供出させる「諸国高役金令」を公布。火山被害対策として。 |
| 12月 9日(宝永5年10月28日) | 富士山が再び噴火。『鸚鵡籠中記』などでは江戸でも降灰があったという。約1ヶ月で沈静化。 |
| 1709年 | |
| 7月 8日(ユリウス暦 6月27日) | 大北方戦争、ポルタヴァの戦い。スウェーデン軍および同盟軍であるウクライナ・コサック軍と、ロシア軍が、ウクライナ東部で会戦。スウェーデン軍は大敗を喫する。北方同盟は復活し、バルト帝国は凋落へ進むことに。 |
| 8月 8日 | ポルトガルの飛行研究者バルトロメウ・デ・グスマンが、屋内で熱気球を飛ばすことに成功。 |
| 1710年 | |
| 4月 4日(宝永7年 3月 6日) | 勘定奉行荻原重秀が、幕府の財政窮乏の打開策として、勘定組頭保木弥右衛門、勘定小宮山友右衛門、鋳造を担う御用達商人である銀座人とともに、将軍の承認を得ないまま、銀の含有量を減らした銀貨の吹き替え(貨幣改鋳)を密かに行う。宝永永字丁銀とよばれるもの。 |
| 4月30日(宝永7年 4月 2日) | 勘定奉行荻原重秀は、さらに悪銀の銀貨吹き替え(貨幣改鋳)を実施。宝永三ツ宝丁銀とよばれるもの。 |
| 6月25日(宝永7年 5月29日) | 桑名藩「野村騒動」で野村増右衛門が処刑される。桑名藩の財政改革を推進した野村が、譜代の重臣らによる告訴を受け、突如逮捕。公金横領などの疑惑18か条の尋問内容のうち3つに明確に反論できなかったため処刑されたもので、一族44人(13人の子供を含む)も死刑、関係者370余人が処罰されるという大規模な粛清事件に発展。事態を知った幕府は久松松平家を越後高田藩に懲罰転封とする。譜代重臣らの私怨による冤罪とも、強引な改革による反発ともいわれる。 |
| 10月 3日(宝永7年閏8月11日) | 伯耆国・美作国で地震。死傷者多数。 |
| 1711年 | |
| 9月14日(正徳元年 8月 2日) | 勘定奉行荻原重秀が、三度目の悪銀の銀貨吹き替え(貨幣改鋳)を実施。宝永四ツ宝丁銀とよばれるもの(改元後の鋳造だが宝永と呼ばれる)。前年からの宝永永字丁銀・宝永三ツ宝丁銀・宝永四ツ宝丁銀の3種類の悪貨は将軍の承認がなく、密かに市場に流され、市場を混乱させた。物価高騰を招いた他、鋳造の一部を支給される銀座人(御用達商人)の利益にもつながった。この件で荻原重秀は将軍家宣から問い糾されるが財政悪化を理由に正当性を主張。このため新井白石との間で激しく対立することになり、荻原の失脚の要因となったほか、銀座人の粛清に発展する。3種の銀貨は享保7年に通用停止となるまで市場に出回っていたが、品質の良い慶長銀とは交換されず、正徳銀とも扱いに差が付き、停止後はほとんどが正徳銀と交換されたため、皮肉にも現在では非常に希少価値が高くなっている。 |
| 1713年 | |
| 2月26日 | イングランドとフランスの間でユトレヒト条約締結。スペイン継承戦争にともなう北米でのアン女王戦争が終結。 |
| 1714年 | |
| 2月26日(正徳4年 1月12日) | 絵島生島事件。江戸城大奥御年寄の江島が、月光院の名代として徳川家宣の墓参のため、奥女中の宮路らと共に寛永寺、増上寺へ参詣し、その帰途、呉服商後藤縫殿助の誘いで木挽町の芝居小屋・山村座に行き、芝居を見物。看板役者の生島新五郎と宴会を開き、大奥の門限に遅れてしまったことが問題となり、多くの処分者を出した事件。 |
| 3月 6日 | 神聖ローマ帝国とフランスの間でラシュタット条約締結。スペイン継承戦争が終結。 |
| 4月28日(正徳4年 3月15日) | 信濃大町で地震。家屋全壊194軒、半壊141軒。死者56人。 |
| 6月24日(正徳4年 5月13日) | 正徳の銀座粛清事件。勘定奉行荻原重秀が密かに行った貨幣改鋳による市場の混乱と物価の高騰の責任と、さらに鋳造に関わった銀座人(御用達商人)らが不当に利益を得たとして、貨幣をもとに戻すことを狙った新井白石が銀座年寄り深江庄左衛門、荻原と手を組んでいた銀座人関久右衛門らを捕縛し、遠島に処す。荻原と関によって失脚させられた五代目大黒長左衛門常栄が復帰。 |
| 8月 7日(ユリウス暦 7月27日) | 大北方戦争、ハンゲ沖海戦。フィンランドのハンコ半島(ハンゲ・ウト。ロシア語でガングート)の沖でスウェーデン海軍とロシア海軍が海戦。ロシア海軍が勝利し、バルト海東方の制海権を得る。 |
| 11月27日(正徳4年10月21日) | 宣教師ジョヴァンニ・バッティスタ・シドッティが収容されていた江戸茗荷谷の「切支丹屋敷」で獄死。世話人の老夫妻に対し布教したことが発覚したため投獄されて10ヶ月ほどであった。それまではその学識や丁寧な態度もあり、高待遇を受けており、面談した新井白石も上策としては本国に帰すべきと進言していた。 |
| 12月 8日(正徳4年11月 2日) | 柳沢吉保死去。将軍徳川綱吉の館林藩主時代からの側近で、大老格に昇り、甲府藩15万1200石の大名にまでなった。朝廷とも交流があり文化人としても知られる。 |
| 1715年 | |
| 2月 2日(正徳4年12月28日) | 尾張・美濃・越前などで地震。大垣城、名古屋城などで被害。 |
| 7月 6日(正徳5年 6月 6日) | 万役山事件。周防国の萩藩と支藩徳山藩の境界付近にある丘「万役山」で、萩藩の西久米村の農民喜兵衛とその子らが、以前植えた松の木を伐採したところ、それを徳山藩の山回り方の足軽井沢里右衛門と福田久助に咎められて争いになり、里右衛門が喜兵衛を殺害。これが萩藩と徳山藩の領有権争いに発展。 |
| 8月 4日(正徳5年 7月 6日) | 府中秣場騒動が発生。是政村の農民ら80人が下小金井村の秣場で刈り取りを行う。下小金井村民が代官所に訴えると、是政村民が下小金井村を襲撃する騒動に発展。 |
| 8月 6日(正徳5年 7月 8日) | 下小金井村民が是政村の行為を代官所に訴える。代官所は両村の住民の出頭を命じる。 |
| 8月 7日(正徳5年 7月 9日) | 是政村、上染谷村、下染谷村、車返村、人見村の村民など1500人余りが下小金井村を襲い、伐採などを強行。 |
| 8月21日(正徳5年 7月23日) | 評定所から是政村など5ヶ村の関係者に出頭を命じる。 |
| 11月29日(正徳5年11月 4日) | 勘定奉行の伊勢貞敕により秣場騒動を起こした是政村の3人を流罪、4人を追放するなどの処分を決める。のちに罪が軽いとして問題になる。 |
| 1716年 | |
| 6月 2日(正徳6年 4月13日) | 万役山事件で、萩藩からの訴えを受けた幕府は、老中らの審議の結果、徳山藩の改易を言い渡す。支藩の改易という重い処分は、訴えた萩藩にとっても予想外の事態だったとみられる。 |
| 10月 8日(享保元年 8月23日) | 8代将軍徳川吉宗が諸国調査のため、御庭番を創設。 |
| 4月26日 | イギリスの海賊で海賊プリンスとも呼ばれたサミュエル・ベラミーが、マサチューセッツ州ケープコッド近海で遭難し消息を絶つ。はるか後の1984年にベラミーの海賊船ウィダー号が発見される。 |
| 5月13日(享保2年 4月 3日) | 東北で地震。仙台や花巻で被害。地割れや液状化現象を観測。 |
| 1718年 | |
| 8月22日(享保3年 7月26日) | 信濃から三河にかけて地震。伊那遠山谷で山崩れにより遠山川が河道閉塞。その後決壊して50人余りが死亡。 |
| 11月22日 | 黒髭のあだ名で知られたイギリスの海賊エドワード・ティーチが殺害される。 |
| 12月11日(スウェーデン暦11月30日) | 大北方戦争のさなか、スウェーデン(バルト帝国)のカール12世が、フレデリックスハルドを包囲中に、何者かの狙撃で死亡。独身で子がいなかったため、妹のウルリカ・エレオノーラが王位を継承することに。 |
| 1719年 | |
| 5月25日 | オスマン帝国(現在のトルコ)にあるイズミットのイズミット断層を震源とする巨大地震が発生。イズミット、ヤロヴァ、アダパザル、イスタンブールなどマルマラ地方一帯で約6000人が死亡。 |
| 1721年 | |
| 9月10日 | ロシアとスウェーデン(バルト帝国)の間でニスタット条約締結。大北方戦争が終結。スウェーデンはロシアに対してカレリア、エストニア、リヴォニア、イングリアなどを割譲し、バルト海の覇権を失う。ロシアは列強へと名乗り出ることに。 |
| 1722年 | |
| 3月 8日 | ミール・マフムード・ホータキー率いるホータキー朝カンダハール王国の軍勢がサファヴィー朝の王都イスファハーンに迫ったため、サファヴィー朝の9代目君主フサインが迎撃軍を出すも、グルナーバードの戦いで大敗。王都は包囲される。 |
| 4月 5日 | オランダ海軍提督、ヤーコプ・ロッヘフェーンがイースター島を発見。 |
| 7月25日 | 北アメリカのイングランド植民地であるマサチューセッツ湾植民地の総督サムエル・シュートが、かねて紛争状態にあったネイティブのワバナキ連邦アベナキ族に対し宣戦を布告。背景には英仏の北米での対立と、それに巻き込まれた本来の住民であるネイティブの反発にある。ネイティブ側で指導していたセバスチャン・ラル神父の名をとってラル神父戦争とも、シュートのあとに総督になったウィリアム・ダマーからダマー戦争とも呼ばれる。ほかにネイティブ側の指導者としてはグレイ・ロック、ポーガスなどの部族長が有名。 |
| 10月23日 | サファヴィー朝の君主フサインが、ホータキー朝のミール・マフムードに降伏し、サファヴィー朝は滅亡。マフムードはイスファハーンで旧王朝関係者などを虐殺。そのため信頼を失ったホータキー朝の支配は短期で終わる。 |
| (享保7年) | 江戸幕府、財源を確保するため、大名に対し1万石につき100石を幕府に上納すれば、参勤交代での江戸滞在期間を半年に短縮する「上米の制」を定める。 |
| 1723年 | |
| 1月10日(享保7年12月 4日) | 小石川薬園に小石川養生所が設立される。発案者の町医者、小川笙船が肝煎職に任命され、幕府の7人の医者が就任。 |
| 12月19日(享保8年11月22日) | 肥後国・筑後国などで地震。980軒あまりが倒壊。2名が死亡。 |
| 1724年 | |
| ハンス・エゲデによってグリーンランドの再入植が行われる。ヴァイキングがかつて入植した場所の付近に入植地を作りゴットホーブ(希望)と名付ける(現在の自治政府首都ヌーク)。 | |
| (享保9年) | 江戸小石川茗荷谷の切支丹屋敷が火災で焼失。棄教した宣教師や、キリシタンの縁者などを収容していた施設で、もとは宗門改役だった大目付井上政重の下屋敷。この頃には収容者もいなかったため、のちに宗門改役廃止とともに形式上も廃止された。跡地の発掘でジョヴァンニ・シドッティの遺骨と見られる遺体が見つかっている。 |
| 1725年 | |
| 6月29日(享保10年 5月19日) | 新井白石死去。将軍徳川家宣のもとで正徳の治を行う。数多くの著作物を残した。無役で小禄の旗本という身分でありながら将軍の信任を得て幕政を動かした異色の人物。 |
| 8月14日(享保10年 7月 7日) | 信濃諏訪地方で地震。諏訪高島城、高遠城などで石垣などが崩落し、塀や門などが倒壊。周辺36ヶ村でも347軒が倒壊。4人が死亡。 |
| 9月 4日(享保10年 7月28日) | 江戸城中で、信濃松本藩主水野忠恒が、自身の婚儀の報告を将軍吉宗にした直後、松の廊下ですれ違った長府藩世子毛利師就に対し斬りかかる。師就は刀を抜かずに応戦し重症を負ったが、忠恒の刀を叩き落としている。忠恒は近くにいた大垣新田藩主戸田氏房が取り押さえ、目付の長田元鄰が師就を押しとどめた。忠恒が事件を起こした動機は不明だが、自分が領地を奪われ、師就に与えられると思ったと供述しており(そのような事実はない)、普段から暗愚な人物だったとされる。松本藩水野家は改易となり、叔父の水野忠穀が7000石で存続し、忠恒の身柄も預けられた。水野忠恒が事件の日に将軍に報告した結婚相手は、大垣藩主戸田氏定の娘で、氏定は赤穂事件でも巻き添えを受けている。忠恒を取り押さえた戸田氏房は氏定の弟の子。 |
| 12月15日 | マサチューセッツ湾植民地と、ネイティブのワバナキ連邦との間で和平条約が結ばれ、ラル神父戦争は終結。背景には、フランスとの植民地争奪戦があり、フランス寄りだったネイティブと戦争するより取り込むほうが良いと判断したことがある。 |
| 1726年 | |
| 10月26日 | ジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』初版が刊行される。イギリス人に対する強烈な批判・風刺内容だったため、出版したベンジャミン・モットによって内容の一部が改変・改竄されたものであったが、またたくまに人気作品となった。 |
| 1728年 | |
| 8月16日 | ヴィトゥス・ベーリングがロシアとアラスカの間の海域を探検。その名が付いてベーリング海と呼ばれるようになる。 |
| 1729年 | |
| 5月18日(享保15年 4月15日) | 8代将軍徳川吉宗の紀州時代のご落胤を自称して浪人らを集めていた山伏の天一坊改行が、関東郡代伊奈忠逵と勘定奉行稲生正武の取り調べの上、鈴ヶ森刑場で処刑される。いわゆる「天一坊事件」。 |
| 8月 1日(享保14年 7月 7日) | 能登国で地震。珠洲郡・鳳至郡で791軒が損壊、山崩れ1731箇所。輪島で28軒が損壊。5人が死亡。 |
| 1730年 | |
| 5月31日(享保15年 4月15日) | 江戸幕府、上米の制を停止し参勤交代制度を元に戻す。 |
| 7月 9日(享保15年 5月25日) | チリのバルパライソ沖で起きた大地震の津波が日本に到達。陸前などで被害。 |
| 12月19日(享保15年11月10日) | 8代将軍徳川吉宗が、次男宗武をして田安家を起こす。御三家に変わる新たな藩屏を興すことを想定したもの。のちに一橋家、清水家が興され、御三卿と呼ばれる。 |
| 1731年 | |
| 10月 7日(享保15年 9月 7日) | 岩代などで地震。白石城などに被害。桑折で300軒あまりが倒壊し、84の橋が落ちる。仙台などでも被害。 |
| この年、ジョン・ベヴィスによって、かに星雲が発見され名付けられる。1054年に出現した超新星の残骸。 | |
| 1733年 | |
| 7月 7日(享保18年 5月26日) | 大森代官兼笠岡代官の井戸正明(正朋?)が、備中笠岡の陣屋で死去。享保の大飢饉の際に、独断で年貢の減免や官金の投入を行い、またサツマイモの栽培を奨励して民衆を救った人物。過労死とも独断で行った対策の責任を取って切腹したとも言われる。 |
| 7月 9日(享保18年 5月28日) | 両国の花火大会がはじめて開催される。 |
| 1734年 | |
| 7月26日(雍正12年 6月26日) | 平敷屋・友寄事件。琉球王国で平敷屋朝敏と友寄安乗ら15人が処刑され、関係者多数が流罪となる。詳細は不明だが対立関係にあった三司官の蔡温を批判した文を薩摩藩琉球在番奉行の屋敷に投書したという。平敷屋朝敏は文学者・歌人として知られた人物で、友寄安乗は三司官友寄安満の弟。 |
| 1735年 | |
| ジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』の未改変版が、ジョージ・フォークナーによって刊行される。現在のガリヴァー旅行記の初版はこちらを指す場合が多い。 | |
| 1736年 | |
| 9月16日 | ポーランド出身の物理学者ガブリエル・ファーレンハイト没。水銀温度計を開発し、温度の単位「華氏」のもととなった人物。 |
| 1738年 | |
| ヴェスヴィオ山の噴火で埋没していたヘルクラネウムが発見される。 | |
| アフシャール朝の君主ナーディル・シャーが、ホータキー朝の王都カンダハールを攻め落とし、ホータキー朝は約30年で滅亡。 | |
| 1739年 | |
| 9月20日(元文4年8月18日) | 蝦夷樽前山が大噴火。30日まで噴火が継続。四方山麓へ4回の大きな火砕流が発生。北海道の広範囲に降灰。噴火に伴う総噴出物量は4立方km。頂上部に外輪山が形成される。 |
| フランス人の探検家ジャン=バティスト・シャルル・ブーヴェ・ド・ロジエがアフリカのはるか南方で、絶海の孤島を発見。この際、正確な位置の記録が出来なかったため、再発見が遅れた上に、再発見ごとに新しい島と勘違いされ、複数の名前を付けられた。後にブーベ島と名付けられる。地球上で最も他の陸地から隔絶された島。 | |
| 1740年 | |
| 10月20日 | 神聖ローマ帝国皇帝カール6世が崩御。娘のマリア・テレジアがハプスブルク家の後継となるが、各国が介入を始める。オーストリア継承問題に発展。 |
| 12月16日 | オーストリア継承問題に介入したプロイセンが、シュレージエンに侵攻。同地域を制圧。マリア・テレジアは抗戦を決意。オーストリア継承戦争勃発。 |
| 1741年 | |
| 4月10日 | モルヴィッツの戦い。プロイセンとオーストリアがモルヴィッツで衝突。プロイセンが勝利し、列強としての地位を得る。 |
| 8月18日(寛保元年 7月 8日) | 蝦夷の渡島大島の寛保岳が大噴火。 |
| 8月29日(寛保元年 7月19日) | 蝦夷渡島大島の大噴火に関係するとみられる大津波が日本海沿岸各地を襲う。山体崩壊が起きたためか。松前藩では家屋791棟・船舶1521艘が被害を受け、和人1467人が溺死。他も含めて和人2033人が死亡した。アイヌの被害については記録がなく不明。弘前藩でも33人が死亡。 |
| 1742年 | |
| 5月17日 | コトゥジッツの戦い。プロイセンとオーストリアの戦い。プロイセンが勝利。 |
| 6月11日 | プロイセンとオーストリアの間でブレスラウ条約が締結される。シュレージエンとグラッツはプロイセンに割譲される。プロイセンはこれを受けて同地方を担保としたオーストリアの債権を引き受ける。また、プロイセンは神聖ローマ帝国皇帝選挙でマリア・テレジアの夫であるロートリンゲン公フランツ1世を支持することを確約。またオーストリアは対フランス戦に戦力を集中することで継承戦争を優位に進めることになる。 |
| (寛保2年) | 江戸幕府の法典である公事方御定書がまとめられる。 |
| 8月28日(寛保2年 7月28日) | 京で暴風雨。桂川が氾濫を起こす。以降、信濃や関東でも暴風雨が広まる。 |
| 8月30日(寛保2年 8月 1日) | 江戸で暴風雨。江戸で高潮が発生。さらに利根川などの洪水が江戸に達する。 |
| 9月 6日(寛保2年 8月 8日) | 江戸で再び暴風雨。洪水が広がる。幕府は西国10藩に救援を指示。 |
| 1744年 | |
| 5月22日 | オーストリアのハプスブルク家伸長に対抗するため、プロイセン、バイエルン、プファルツ、ヘッセン=カッセルがフランクフルト同盟を締結。 |
| 8月 2日 | プロイセンがオーストリアのベーメンに侵攻。第二次シュレージエン戦争勃発。 |
| 9月 8日 | プロイセンによるプラハ攻略戦が始まる。 |
| 9月16日 | プラハ市がプロイセンに降伏。しかし、フランスが参戦を取りやめた他、在地の協力が得られず、プロイセン軍は物資不足が目立つようになる。 |
| 10月26日 | オーストリア側の反撃と物資不足のため、プロイセン軍はベーメンからの撤退を開始。 |
| 1745年 | |
| 3月14日(延享2年 2月12日) | 六道火事。江戸千駄ヶ谷の青山六道辻付近から出火。北西風に煽られて南東方角へと火災が広がり、麻布、白金、高輪へと延焼。2万8678棟が焼失し1323人が死亡する。 |
| 5月11日 | フォントノワの戦い。オーストリア継承問題に端を発し、ネーデルラントを巡ってフランスとイギリス・ハノーファーなどの連合軍が衝突。フランス側が勝利。 |
| 1747年 | |
| 4月20日(延享4年 3月11日) | 東海地方を荒らし回った盗賊団の頭だった日本左衛門こと濱島庄兵衛が処刑される。歌舞伎「白浪五人男」に出てくる日本駄右衛門のモデル。 |
| 9月19日(延享4年 8月15日) | 江戸城中で、肥後熊本藩主細川宗孝が、厠に立ったところ、突如旗本寄合席板倉勝該に背後から襲われ殺害される。板倉勝該は普段から狂疾だとして、板倉本家の老中板倉勝静が勝該を廃する予定でいたとされ、恨みに思った勝該が、勝静と間違えて、家紋がよく似た細川宗孝を襲ったと見られる(勝該と宗孝の屋敷同士が隣接していることから排水の揉め事が原因という説もある)。板倉勝該は切腹。細川家は子がいなかったため改易の可能性があったが、現場に駆けつけた仙台藩主伊達宗村が、宗孝はまだ息があると証言して時間を稼ぎ、肥後藩は急遽宗孝の弟紀雄を末期養子として申請し、その後、宗孝は死亡したことにした。家紋を見間違えたため、細川家では家紋のデザインを変更している。 |
| 1748年 | |
| 9月 6日(寛延元年 8月14日) | 大坂竹本座で人形浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵」初演。 |
| ヴェスヴィオ山の噴火で埋没していた古代都市ポンペイが発見される。 | |
| 1749年 | |
| 1月19日(寛延元年12月 1日) | 大坂中の芝居で歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」初演。 |
| 1751年 | |
| 5月21日(寛延4年 4月26日) | 深夜に宝暦高田地震が発生(宝暦はこの年改元)。高田城などで被害。各地で山崩れが多発し、特に越後国頸城郡名立小泊で山体崩壊が発生。海岸沿いの名立小泊村の家屋の殆どを海まで押し流す。通称「名立崩れ」。住民525人のうち406人が死亡(生存者数は諸説あり)。全体の死者は1500人以上。 |
| 1752年 | |
| 2月 3日(宝暦元年12月19日) | 大岡忠相が死去する。 |
| 5月 | 第6代ロシア皇帝エリザヴェータがエカテリーナ宮殿の建設に取り掛かる。設計は宮廷付き建築家バルトロメオ・ラストレッリ。 |
| 6月ころ | ベンジャミン・フランクリンが、雷雲に凧を上げ、ライデン瓶を繋いで雷が電気であることを確認。先にトマ・ダリバードが行ったともいわれる。 |
| 9月14日 | イギリスとその植民地で、グレゴリオ暦が導入される。 |
| 1753年 | |
| 8月 6日 | ドイツの物理学者ゲオルク・ヴィルヘルム・リヒマンが、サンクトペテルブルクの研究室で、雷の中での絶縁の実験をしている最中に感電死。雷に打たれたとも、窓から飛び込んできた球電の直撃を受けたとも言われる(球電は雷雨のときなどに稀に発生する発光体。プラズマとも言われる)。 |
| 1754年 | |
| 3月20日(宝暦4年 2月27日) | 宝暦治水工事着工。薩摩藩の財政弱体化が目的の公共工事で、幕府の妨害により抗議の自害や、疫病による病死で大勢の犠牲者を出すことになる。ただ死者の詳細な要因はわかっていない部分が多い。薩摩藩は莫大な借金を抱えることになった。 |
| 1755年 | |
| この年までに、スコットランド・エディンバラ大学の研究者ジョゼフ・ブラックが炭酸カルシウムなどの研究から、「燃焼を止めてしまう」固定気体を発見。のちに二酸化炭素と名づけられた。 | |
| 1756年 | |
| 7月30日 | ロシア・サンクトペテルブルク郊外プーシキンのツァールスコエ・セローにエカテリーナ宮殿が完成。 |
| 1757年 | |
| 3月27日 | ルイ15世の殺害を図ったとしてロベール=フランソワ・ダミアンが八つ裂きの刑に処される。死刑執行人「ムッシュ・ド・パリ」ことシャルル=アンリ・サンソンが詳細に記録したことで知られる。 |
| 1758年 | |
| 5月 9日(宝暦8年 4月 3日) | 広島宝暦八年大火。広島城下白神5丁目から出火。夕方に鎮火するも、翌日国泰寺から出火。比治山町まで延焼。 |
| 9月12日 | シャルル・メシエが「かに星雲」を観測し、メシエ・カタログの1番目(M1)に記載。 |
| 12月25日 | エドモンド・ハレーが予言したのとほぼ同時期に彗星が出現しヨハン・ゲオルク・パリッチュが観測。ハレー彗星と名付けられる。 |
| 1759年 | |
| 1月15日 | ハンス・スローンの膨大なコレクションを収蔵展示するための博物館として大英博物館が開館。 |
| 1月27日(宝暦8年12月29日) | 講釈師で近世講談の祖とも言われる馬場文耕が処刑される。幕府が審理中だった金森騒動を素材にした講談を行い、それを『平良仮名森の雫』という本にして頒布したことが咎められたためとされる。馬場文耕の出生や経歴ははっきりしないが、多数の著作物がある。 |
| 9月 6日(宝暦9年閏7月15日) | 人吉藩竹鉄砲事件。肥後人吉藩薩摩瀬屋敷で、藩主相良頼央が、何者かに狙撃されて負傷。9月26日(8月3日)に死亡。しかし、何故か藩は狙撃事件ではなく、狙撃音は子供の遊ぶ竹鉄砲(爆竹)だったとして、縁戚関係の日向高鍋藩藩主秋月種美の3男晃長を末期養子にし、藩主は病死と公表した。なお晃長は秋月家出身の上杉鷹山の実弟にあたる。 |
| 1760年 | |
| 2月 6日(宝暦10年 3月22日) | 宝暦の大火(明石屋火事)。同日夜、江戸神田旅籠町の足袋屋「明石屋」から出火。北西付の風に煽られて佐久間町、馬喰町、日本橋、木挽町へと延焼。更に火災は大川を超えて深川、洲崎まで広がった。460町、寺社80、橋104などを焼失。 |
| 10月31日(宝暦10年 9月23日) | 葛飾北斎生誕とされる日。生誕地は武蔵国葛飾郡本所の割下水付近とされる。出自、生誕日、生誕地、若い頃の経歴など不明なところの多い人物。 |
| 1761年 | |
| 7月 4日 | 近代小説初期の作家で書簡体小説を書いたサミュエル・リチャードソンが死去。 |
| 1762年 | |
| 2月27日(宝暦12年 2月 4日) | 人吉藩9代藩主相良晃長が病死。11歳だったため、17歳未満の末期養子は認められないことから、藩上層部は急遽縁戚の公家鷲尾隆煕の子頼完(晃長より3歳年上)を密かに藩主にして、幕府には晃長が病気回復したと「同一人物」を装う報告をした。 |
| 9月15日(宝暦12年 7月27日) | 後桜町天皇が即位。第117代。令和に至るまでの時点で最後の女性天皇。 |
| 10月31日(宝暦12年 9月15日) | 佐渡・越後で地震。佐渡では銀山道が崩れる。津波、液状化、地割れなどを観測。 |
| 1763年 | |
| 1月29日(宝暦12年12月16日) | 宝暦八戸沖地震。マグニチュードは7.4以上。夜間に発生し、津波が襲来。寺社・民家などが損壊。十勝沖地震と同様とする説も有力。余震が相次いだ。 |
| 2月10日 | パリ条約が調印され、ヨーロッパ中を巻き込み、北米やインドでも戦った七年戦争が終結する。 |
| 3月22日(宝暦13年 2月 8日) | 米沢藩の有力者、森利真が米沢城内で竹俣当綱らによって暗殺される。藩主上杉重定の側近として強引な商業主義と増税による藩財政建て直しを図ったことと一族重用が恨みを買ったため。 |
| 5月22日(宝暦13年 4月10日) | 豊後国耶馬渓の崖を掘った青の洞門が開通。 |
| メルヒオール・バウアーが「空中車」という飛行装置を考案。揚力を生む主翼と、推力を生む可動翼を分けた航空機の原型のようなもの。ロイス=グライツ侯ハインリヒ11世らに図面を提示したが、実物は制作されなかったとみられる。 | |
| ジャマイカのフォートオーガスタ要塞で、落雷が原因で火薬庫が爆発。300人が死亡する。 | |
| 1764年 | |
| 4月 5日 | 英国議会で砂糖法が成立。西インド諸島の非英領植民地から輸入される糖蜜にかかる関税を下げる代わりに、消費財に課税し、徴税逃れや密貿易を取り締まり、確実に徴税するための関税法。フレンチ・インディアン戦争の負債を減らす目的もあったが、英領アメリカでは経済的悪影響と「代表がいないのに課税される」ことに不満が高まっていく。 |
| 1765年 | |
| 清の軍勢が雲南省からミャンマーに侵攻。清緬戦争。チャイントンで起きた殺人事件を理由にミャンマーのコンバウン王朝を影響下に収めようとした。しかしミャンマー側の反撃で敗走。以後、清は1769年まで4回に渡ってミャンマーに攻め込む。 | |
| 1766年 | |
| 3月 8日(明和3年 1月28日) | 津軽で大地震。マグニチュードは7クラス。津軽藩領内で甚大な被害を出す。家屋倒壊5000軒あまり、焼失200軒あまり。死者1300人。 |
| ヘンリー・キャベンディッシュが、金属と酸が反応した際に出る、軽くて燃える気体を、フロギストンではないかと発表。のちにこの気体が(酸素と反応して)水を生むことがわかり、ラヴォアジエによって水素(hydrogen)と名づけられた。 | |
| 1767年 | |
| 第一次マイソール戦争勃発。南インドのマイソール王国と、イギリス東インド会社との戦争。 | |
| 9月14日(明和4年 8月22日) | 明和事件。尊王論・大義名分論を唱えて幕府に警戒されていた山県大弐、藤井直明が、不敬罪を理由に処刑される。直接的には山県と関係の深かった小幡藩の内紛に巻き込まれた形となっている。竹内敬持も流罪処分。 |
| 1768年 | |
| 7月22日(明和5年 6月 9日) | 琉球で大きな地震。石垣などが崩落。津波を観測。 |
| 8月 8日 | ジェームズ・クックのエンデバー号がイングランドのプリマスから出航。第一回太平洋探検の航海はじまる。 |
| 9月 | ゴルカ王プリトゥビ・ナラヤン・シャーが複数の小王国を征服してネパールのカトマンズ盆地を統一。シャー王朝を興す。 |
| 1769年 | |
| 4月 2日 | 南インドのマイソール王国と、イギリス東インド会社との間でマドラス条約が締結され、第一次マイソール戦争終結。戦争は一進一退を繰り返したが、最終的にマイソール側がマドラスに攻め寄せたことから、イギリス東インド会社側が譲歩した。 |
| 8月18日 | イタリアのブレシアにある聖ナザロ教会で、ヴェネツィア共和国が保管していた90tともいわれる大量の火薬が、雷によって発火。大爆発を起こす。爆風の他、吹き飛んだ巨石が落下するなどしてブレシア市街地の6分の1が破壊され、死者は多い記録で3000人、公式記録では400人を出す惨事となる。各国で避雷針の研究・導入や、火薬の保管に関する法律が検討されるきっかけとなった。 |
| 8月29日(明和6年 7月28日) | 日向国、豊後国、肥後国、伊予国で大地震。家屋損壊多数。延岡城、大分城に被害。津波襲来により沿岸部で水没地域も発生。死者多数。日向灘地震かプレート内地震かは説が分かれる。 |
| 11月 9日(明和6年10月12日) | 青木昆陽が病死。甘藷の関東地方普及に関わったと言われる他、書物奉行として古文書の調査、古銭の分類、オランダ語の研究なども行った人物。 |
| 清緬戦争、清の4回目のミャンマー侵攻。6万の大軍を擁したが反撃され大敗。皇帝の命により退却する。4回すべて清の敗北に終わる。清軍から和平が求められたため、ミャンマー側のマハティハトゥラ将軍が独断で和睦に応じる。清王朝はこれをもってミャンマーに勝利し朝貢国としたと称した(乾隆帝十全武功のひとつ)。 | |
| 1770年 | |
| 3月 5日 | ボストン虐殺事件。当時のマサチューセッツ湾植民地のボストンで、駐留イギリス軍兵士と住民との間でトラブルとなり、住民5人が銃で撃たれて殺害された事件。アメリカ独立戦争のきっかけの一つ。 |
| 9月17日(明和7年 7月28日) | 蝦夷地から九州に至る各地で夜空に「赤気」が出現。北極での大規模なオーロラの発生に伴う低緯度オーロラとみられる(オーロラの色はエネルギーの量と反応する窒素や酸素との違いで、高度が上がるほど紫→緑→赤と変わるため、低緯度で見えるときは高高度の赤い部分だけが見える)。 |
| 1771年 | |
| 4月18日(明和8年 3月 4日) | 杉田玄白、前野良沢、中川淳庵が小塚原刑場で「腑分け」を見学。オランダ語の医学書「ターヘル・アナトミア」の図解の正確さを確認。 |
| 4月24日(明和8年 3月10日) | 八重山地震が発生し、地震の被害は記録がないが、大津波が宮古・八重山地方を襲う。「八重山地震」「明和の大津波」「八重山地震津波」「八重山大津波」「乾隆大津波」などと称される。石垣島が特に大きな被害を受けた。波高は石垣島宮良で最大85mとされているが不正確であり、現代の計測では石垣島で25~30m、多良間島で18mほどと考えられる。それでも巨大な津波であり、全体の家屋流出2000軒あまり、死者・行方不明者1万2000人で、八重山では人口の3分の1が死亡。田畑が海水につかったことで塩害が起き、翌年以降大規模な飢饉をもたらす。明治初期の人口でも津波の前の3・4割程度。一方、沖縄本島以北には被害がなく、津波襲来は限定的だったとみられる。地質調査から600年周期で大津波が襲来していたとされる。 |
| 6月12日 | ジェームズ・クックの最初の航海が終わり、エンデバー号は南イングランドのダウンズに帰還。 |
| この年、スウェーデンの研究者カール・ヴィルヘルム・シェーレが炎を強くする気体を発見する。いわゆる酸素の発見。しかしシェーレはこれをしばらく発表しなかったため、後に別に酸素を発見したプリーストリーに発見者の地位を奪われた。 | |
| (景興32年) | この年、ベトナム中南部の西山(タイソン)県で、阮岳・阮侶・阮恵の三兄弟が、広南国(後黎朝大越の有力者広南阮氏の半独立国)で摂政張福巒排除を唱えて反乱を起こす。西山党の乱。 |
| 1772年 | |
| 4月 1日(明和9年 2月29日) | 明和の大火。目黒行人坂大円寺の真秀という僧侶の放火による。904町が焼失し、死者は1万5000人、行方不明者は4000人。出火場所から目黒行人坂の火事とも言われる。 |
| 6月 3日(安永元年 5月 3日) | 陸奥国で地震。各地で山崩れ、家屋倒壊。死者12人。 |
| 1773年 | |
| 1月17日 | ジェームズ・クック率いる探検隊が、初めて南極圏に達する(南極大陸から121kmの地点まで進む)。伝説の南方大陸(テラ・アウストラリス・インコグニタ)を探している途上。この後、北上したため、南極大陸の発見には至らず。しかしクックは、テーブル型氷山の存在などから大陸があると確信し、氷雪に覆われた不毛地帯であると推測。これにより理想化された伝説の南方大陸という考え方は衰退していく。 |
| 9月 | ロシアでプガチョフの乱が勃発。ドン州のコサック領主の生まれであるエメリヤン・プガチョフが、ピョートル3世を名乗って挙兵。反乱はヴォルガ川からウラル山脈にかけての広大な地域に拡大。 |
| 11月28日(安永2年10月15日) | 京都西町奉行の山村良旺が朝廷の財務管理に関する不正の調査に乗り出す。朝廷側の財務担当をしている地下官人らによる架空請求と帳簿改ざん、横領、収賄、幕府への批判などが明るみになる。天皇・上皇らの助命嘆願があったものの、翌年、官人154名と御用商人らの処罰が決定され、うち4名が死刑となる。 |
| 12月16日 | ボストン茶会事件。植民地をめぐるフレンチ・インデアン戦争での莫大な負債に苦しむイギリス政府が、新大陸における東インド会社の茶葉独占販売権を決めたことで、貿易独占と課税権に反発した急進派市民約50人が、ボストン港に停泊していた貿易船を襲い、大量の茶箱を海に放り込んだ出来事。100万ドルもの損害を出し、イギリスは植民地支配を強化。これがアメリカ独立戦争の直接のきっかけとなった。 |
| (景興34年) | ベトナム中南部で起きた西山党の乱で、反乱軍は広南国の歸仁(クイニョン)を攻略。さらに広義(クアンガイ)、広南(クアンナム)へと北上し、中南部地方から広南阮氏の勢力を追放。 |
| 1774年 | |
| 7月12日 | カザンの戦い。プガチョフの乱で、エメリヤン・プガチョフ軍2万5千人がカザンに侵攻。皇帝軍を打ち破り、市街地を占領・破壊する。しかしまもなく皇帝軍に増援が到着し、プガチョフ軍は大敗。以後、反乱は急速に縮小していく。 |
| 9月14日 | エメリヤン・プガチョフが捕らえられる。 |
| ジョゼフ・プリーストリーが、水銀灰(酸化第二水銀)を燃焼させて新たな気体を発見する。翌年再実験を行い、これが「火を強くし」「動物を長生きさせる」「良い気体」と結論。当時広く信じられていた物質「フロギストン(燃素)」を吸収する「脱フロギストン空気」と発表する。しかし、プリーストリーはフロギストン説支持者であったため、これがいわゆる酸素だとは気づかなかった。 | |
| (景興35年) | ベトナム中南部で起きた西山党の乱で広南国が衰退したのを受け、ベトナム北部を勢力圏とする東京鄭氏(後黎朝大越の有力者「鄭主」10代目鄭森)が、中南部へ侵攻。富春を攻略。西山阮氏三兄弟は、鄭森に臣従して「広南鎮守宣撫大使」となり、一転してベトナム南部へ侵攻を開始。 |
| 1775年 | |
| 1月21日 | エメリヤン・プガチョフがモスクワで処刑される。反乱は終息。 |
| 4月19日 | レキシントン・コンコードの戦い。イギリス軍と大陸民兵軍が衝突。アメリカ独立戦争に拡大。 |
| この年、ジェームズ・クックの探検隊が、サウスジョージア諸島を再発見し、イギリス領を宣言。 | |
| 1776年 | |
| 1月10日 | 思想家トマス・ペインが、『コモン・センス』というパンフレットを売り出す。アメリカ独立を主張した内容で、民衆の間にも独立機運が高まる。 |
| 6月10日 | アメリカ独立宣言起草委員会が発足。独立宣言書は、トーマス・ジェファーソンが起草し、ジョン・アダムズ、ベンジャミン・フランクリンが修正を加えて完成する。 |
| 7月 2日 | バージニア植民地代表のリチャード・ヘンリー・リーが提出していた『独立の決議』が、大陸会議で可決承認。 |
| 7月 4日 | アメリカ独立宣言書が大陸会議で承認され、13植民地が、イギリスからの独立を宣言。アメリカ独立記念日。 |
| (景興37年) | ベトナム中南部で起きた西山党の乱で西山党軍は、南部の嘉定を攻略し広南阮氏を滅ぼす。しかしこのとき、阮福暎のみ逃亡に成功する。阮福暎はのちの阮朝越南国(グエン朝ベトナム)の初代皇帝。 |
| 1777年 | |
| 6月14日 | アメリカの国旗として正式に星条旗が選定される。フラッグデー。 |
| 1778年 | |
| 1月18日 | ジェームズ・クック率いる調査隊がハワイ諸島に到着。クックはこの諸島を調査探検の後援者であるサンドウィッチ伯爵の名を取って、サンドウィッチ諸島と命名。 |
| (景興37年) | 西山党の阮岳が、歸仁で西山王に即位。西山朝が成立。 |
| 1779年 | |
| 2月14日 | ジェームズ・クックが、北西航路探検の拠点にしていたハワイ島のケアラケクア湾で、盗品を巡って先住民といさかいになり、小競り合いで殺害される。 |
| 6月18日 | アメリカ独立戦争に絡んで、アメリカ大陸軍のジョン・サリバンによってサリバン遠征が始まる。イギリス王党派とイロコイ連邦のイギリス側についたインディアン部族討伐を目指したもの。 |
| 8月29日 | アメリカ独立戦争、ニュータウンの戦い。サリバン率いる大陸軍と、イギリス王党派・イロコイ連邦の連合軍との戦い。 |
| 11月 8日(安永8年10月1日) | 桜島各所で噴火。火砕流と降灰を伴い、翌9日には溶岩の流出が始まる。10日に溶岩が海岸に到達(安永溶岩)。 |
| この年、アントワーヌ・ラヴォアジエが、プリーストリーの発見した気体を、金属と結合して酸化させる物質という意味で「oxygène(オキシジェーヌ)」と名付ける。酸素の語源。ラヴォアジエは、プリーストリーと異なり、フロギストン説にこだわらず、空気は2つの気体から構成されていると考えた。 | |
| 1780年 | |
| 1月24日(安永8年12月18日) | 科学者、発明家、戯作者などで知られた平賀源内が死去。大工の棟梁秋田屋九五郎とのトラブルで殺傷事件を起こし投獄中に獄死したと言われるが、田沼意次や高松藩松平家に匿われて生き延びたといった異説もある。 |
| 8月 6日(安永9年 7月6日) | 桜島北東海上で海底噴火。 |
| 1781年 | |
| 3月13日 | ウィリアム・ハーシェルが天王星を発見。当初は彗星と考えていたが、アンデル・レクセルが軌道計算をして惑星と判明。なお、これ以前にも何度か観測されているが新惑星とはみなされなかった。 |
| 4月11日(安永10年3月18日) | 桜島北東海上で海底噴火。津波が発生。安永の一連の噴火の死者は153人。 |
| 1782年 | |
| 4月 6日 | アユタヤの王族で、トンブリー王朝の将軍ソムデットチャオプラヤー・マハーカサット・スックが、遠征先から戻り、乱心していた国王タークシンを処刑。自ら即位してチャクリー王朝シャム王国を興す。初代国王ラーマ1世。 |
| 8月23日(天明2年 7月15日) | 関東地方で2回大地震。小田原城で被害。家屋800軒あまりが損壊。箱根山・大山・富士山で山崩れ。津波を観測。 |
| 1783年 | |
| 4月13日(天明3年 3月12日) | 岩木山が噴火。 |
| 6月 5日 | モンゴルフィエ兄弟による無人熱気球の公開飛行実験に成功。 |
| 6月 8日 | アイスランドの活火山ラキ山(ラーカギーガル山)が大噴火を起こす。二酸化硫黄ガスやフッ素化合物が大量に噴出。膨大な量の玄武岩質溶岩も流れ出す。多くの家畜が死亡し、住民も2割が死亡。ヨーロッパ各地へも大量の火山性ガスの流出と降灰があり、多数の死者を出す。その後、数年にわたって北半球全体で気象異変が起こる。この時、隣接するグリムスヴォトン山も噴火。 |
| 8月 4日(天明3年 7月 7日) | 小規模の噴火が続いていた浅間山が大噴火を起こす。大量の溶岩が流れ出す。現在の「鬼押出し」。 |
| 8月 5日(天明3年 7月 8日) | 浅間山の中腹で大規模な爆発が起きる。溶岩、火砕流、土石流が麓へ広がり、比較的大きな街道の集落だった蒲原村は土石流で完全に埋没し村人の9割が死亡。噴火はこのあと急速に終息するが、土石流は吾妻川をせき止め、決壊後の洪水によって流された人馬の遺体は江戸川にまで流れ着く。 |
| 9月 3日 | パリ条約でアメリカ独立宣言書がイギリスに承認され、アメリカ合衆国が正式に独立。 |
| 9月19日 | モンゴルフィエ兄弟、フランス国王ルイ16世とマリー・アントワネットの前で動物を乗せた気球飛行実験に成功。 |
| 11月21日 | モンゴルフィエ兄弟、世界初の熱気球有人飛行の実験を行なう。当初は死刑囚を乗せるはずだったが、研究者ピラトール・ド・ロジェとフランソワ・ダルランド侯爵の二人が名乗りを上げ、25分の飛行に成功。 |
| 1784年 | |
| 2月 7日 | 噴火していたアイスランドのラキ山がほぼ終息。 |
| 2月27日 | 音楽家・画家で、錬金術を行い、不老不死者などの噂もあったサンジェルマン伯爵が死去。スペイン王妃マリー=アンヌ・ド・ヌブールの私生児とも言われる。 |
| 4月12日(天明4年 2月23日) | 筑前志賀島で「漢委奴國王」の金印が発見される。 |
| 5月13日(天明4年 3月24日) | 江戸城中で、旗本佐野政言が、若年寄田沼意知に襲いかかり重症を負わせる。事件を起こした動機は諸説あるがはっきりしない。政言は乱心ということで切腹、佐野家は改易となった。天災などで米価が高騰していたこともあり、世間では佐野を称える風潮となった。 |
| 5月20日(天明4年 4月 2日) | 江戸城中で佐野政言に襲われ重症を負っていた田沼意知が死去。 |
| 広南阮氏の生き残りである阮福暎が、シャム王国の援軍5万を率いて西山朝へ侵攻し嘉定を占領。シャム軍による略奪などで反発を買う。 | |
| 1785年 | |
| 1月19日(泰徳7年12月 9日) | ラックガム=ソアイムットの戦い。シャム軍の侵攻に対し、西山朝は阮恵が5万で迎撃に当たり、前江(メコンデルタの東側)流域で両軍は激突。阮恵はメコンデルタの大きな干満差を利用するなどしてシャム軍を撃破。シャム軍は大敗を喫して退却。阮福暎も敗走した。 |
| 6月15日 | 世界最初の気球飛行者ピラトール・ド・ロジェが自ら考案した気球で、ドーバー海峡横断に挑戦中、爆発事故で墜落死し、同乗していたジュール・ローマンとともに人類最初の航空事故死者になる。 |
| 備前の表具屋だった浮田幸吉が自作のグライダーで、岡山の旭川に架かる京橋から滑空飛行を行う。騒動を聞きつけた岡山藩士によって捕らえられ岡山を追放された。のち、移り住んだ駿府でも飛行実験を行ったといわれる。 | |
| この頃から、ラヴォアジエは、フロギストン説を否定する理論を主張。妻マリー・アンヌとともに批判を展開し、支持者を増やしてフロギストン説は衰退していく。化学が大きく進むきっかけを作った。 | |
| 1786年 | |
| (泰徳9年 6月) | 西山朝が北進を開始し、富春を占領。 |
| 8月 8日 | 医者のジャック・バルマとポーターのミッシェル・ガブリエル・バッカールが、近代登山の祖オラス=ベネディクト・ド・ソシュールの支援を受け、初めてモンブラン登頂に成功。 |
| 8月(泰徳9年 7月) | 西山朝が昇龍に到達し、事実上の権力者だった東京鄭氏(鄭氏東京国)を破って、形式的な君主である大越後黎朝を支配下に置く。皇帝顕宗は侵攻軍の司令官阮恵を元帥に任じ娘を嫁がせる。 |
| 8月10日(泰徳9年 7月17日) | 後黎朝の皇帝顕宗が崩御。黎維祁が即位(黎愍帝)。 |
| 1787年 | |
| 1月11日 | ウィリアム・ハーシェルが天王星の衛星チタニアとオベロンを発見する。天王星で1番目と2番目に大きな衛星。 |
| 5月(泰徳10年 4月) | 西山朝の阮岳が歸仁で皇帝に即位(泰徳帝)。北平王阮恵を富春に封じ、北定王阮侶を嘉定に封じて南定王とする。 |
| 7月21日 | 畿内で飢饉が深刻化する中、京の市民が御所の周りに集まり回り始める。いわゆる「御所千度参り」の始まり。次第に人数が増え、大坂や近江などからも人が集まり、7万人に達する事態に発展。後桜町上皇は御所内にあった和りんご3万個を人々に提供。公家衆も、お茶やおにぎりを供出した。光格天皇と関白鷹司輔平は事態を受けて幕府に飢饉難民への救済策を求める。政治行為は「禁中並公家諸法度」に反する行為だったが、幕府は非常事態を受けてのこととして問題にせず、京に1500俵の米を出した。幕末に天皇家が発言力を持ち始めるきっかけになったとも言われる。 |
| 9月17日 | フィラデルフィア憲法制定会議が、アメリカ合衆国憲法案を採択。 |
| 10月(泰徳10年/乾隆53年 9月) | 西山朝の阮恵と阮有整の内紛を受けて、黎愍帝が清朝に支援を要請。清の乾隆帝は両広総督の孫士毅に後黎朝支援の遠征を命じる。 |
| 11月 7日 | フランス国王ルイ16世が、ヴェルサイユの勅令に署名。フォンテーヌブローの勅令を廃止し、カトリックへの強制改宗をやめ、プロテスタントの信仰の自由が認められることになる。 |
| 12月 7日 | アメリカ独立13植民地のうち、デラウェアが最初に合衆国憲法を批准。1番目の州となる。デラウェア州の愛称は「First State」。 |
| 12月19日(泰徳10年11月22日) | 西山朝の軍勢を駆逐して昇龍に入城した孫士毅が黎愍帝を安南王に封じる。 |
| 1788年 | |
| 1月26日 | イギリスから囚人や貧困者ら1030人が、アーサー=フィリップ海軍大佐に率いられ、オーストラリアのポート・ジャクソン湾に到着し、初めて上陸する。 |
| 3月 7日(天明8年 1月30日) | 京都天明の大火。京の市街地の大半が焼失した大火で、御所や二条城、京都所司代、主要な寺社も焼け落ちた。焼亡した地域は応仁の乱の被害を上回るともいう。何者かによる宮川町団栗辻子の町家への放火が原因で、出火場所から団栗焼けとも呼ばれてる。死者は150~1800人。 |
| 4月 9日(天明8年 3月 4日) | 第11代将軍徳川家斉が、老中松平定信を将軍輔佐に任命。寛政の改革がはじまる。 |
| 4月 9日(天明8年 3月 4日) | イギリス人ジョン・ミアーズ率いる船が、伊豆諸島で海から突き出た巨大な岩を発見。聖書の「ソドムとゴモラ」のエピソードに出てくる塩の柱にされたロトの妻から「ロッツワイフ」と名付ける。これをもとに明治になって孀婦岩と命名された。 |
| 7月27日(天明8年 6月24日) | 幕府の側用人・老中として権力をふるった田沼意次が病死。松平定信の政権下では非常に冷遇された。 |
| 8月 3日 | ベルサイユ広場で車裂きの刑に処せられる予定だった死刑囚ジャン=ルイ・ルシャールが、無実を訴えたことに群衆が同情し、処刑台を破壊して助け出す。これ以降、苦痛の大きい刑罰は行われなくなり、即死するギロチンの開発へとつながっていく。 |
| 10月(泰徳11年 9月) | 西山朝の内紛を受け、広南阮氏の阮福暎がふたたびシャム王国の支援のもと侵攻し、嘉定を占領。 |
| 12月22日(泰徳11年/光中1年12月28日) | 西山朝の泰徳帝阮岳の弟阮恵が、自ら光中皇帝と称して即位を宣言。清軍の侵攻に対抗するためか。阮岳との関係は破綻。 |
| 1789年 | |
| 1月30日(泰徳12年/光中2年 1月 5日) | ドンダーの戦い。光中皇帝阮恵率いる西山軍が、埬栘(ドンダー)で正月の準備で油断していた清軍を攻撃。清軍は大敗を喫して敗走。これを受けて後黎朝の昭統帝も清朝へ亡命し、後黎朝は滅亡する。清朝は両広総督の孫士毅を更迭し、各地の総督を歴任した有力者の福康安(フカンガン)をあらたに両広総督とする。また清朝は、阮恵が講和を求めてきたとして安南王に封じ、勝利を装った(乾隆十全武功)。後黎朝の昭統帝は事実上見捨てられることになる。 |
| 2月 4日 | ジョージ・ワシントンが初代アメリカ合衆国大統領に選出される。 |
| 2月26日 | サラブレッドの近代始祖エクリプス死す。 |
| 5月11日(寛政元年 4月17日) | 阿波国・土佐国で地震。阿波冨岡・土佐室津などで被害。 |
| 7月14日 | バスティーユ監獄襲撃。第三身分の一般市民が政府に反発して蜂起。フランス革命の勃発。 |
| 8月26日 | フランス革命の基本原則として「人間と市民の権利の宣言」が採択される。通称「フランス人権宣言」。 |
| 8月28日 | ウィリアム・ハーシェルが土星の衛星エンケラドゥスを発見する。近年の探査機カッシーニの観測で氷の地殻の下に広大な海が存在することが判明し、生命体がいる可能性も指摘されている。 |
| 9月17日 | ウィリアム・ハーシェルが土星の衛星ミマスを発見する。後にボイジャー1号が観測した際に、直径の3分の1もある巨大なハーシェルクレーターを持つ姿が、映画『スターウォーズ』に出てくる宇宙要塞デス・スターにそっくりだったことから話題になった。 |
| 10月10日 | フランスの医師で議員のギヨタンが立憲議会に、当時複数の手段があった死刑方法を斬首に統一することと、苦痛の少ない機械的な斬首法の導入を提案。この提案を元に処刑執行人シャルル=アンリ・サンソン、外科医アントワーヌ・ルイ、楽器製造者トビアス・シュミットが開発したのがギロチン。なおギヨタン自身がギロチンで処刑されたというのは間違い。 |
| 1790年 | |
| 5月29日 | アメリカ独立時の13植民地の最後の1つロードアイランドが合衆国憲法を批准し州となる(イギリスからの独立には積極的だったが、中央集権体制には反発していたため最後になった)。 |
| 7月 6日(寛政2年 5月24日) | 松平定信が、朱子学を正学とし、それ以外の学問を禁止する、寛政異学の禁を通達。主に幕府の教育行政についての指導で、諸大名・一般に対する強制では必ずしもない。 |
| 1791年 | |
| 3月 | フランスでメートル法が導入される。地球の大きさをもとに長さの単位を決めたもので、その大きさをもとに決められた質量から重さの単位(g)もこれに合わせる。度量衡の不正がフランス革命の要因の一つにもなっていたため、革命後に統一化が進められた。 |
| 6月22日 | フランス国王一家が、国外の支援者と合流するため、一家で宮殿を脱出、国境へ向かうも発見され捕らえられる。ヴァレンヌ事件。 |
| 1792年 | |
| 2月10日(寛政4年 1月18日) | 雲仙の普賢岳地獄跡火口で噴火が始まる。 |
| 4月25日 | ギロチンが初めて死刑に使用される。死刑に処されたのはニコラ・ジャック・ペルティエという人物。 |
| 5月17日 | ニューヨーク証券取引所の前組織「ぼたんの木協定」(Buttonwood Agreement)が設立される。 |
| 5月21日(寛政4年 4月 1日) | 島原半島で大きな地震が起き、雲仙普賢岳のそばにある火山眉山が山体崩壊し島原城下が飲み込まれて壊滅。大量の土砂はそのまま有明海に流れ込み、発生した大津波で、対岸の肥後や天草も甚大な被害をうける。死者は1万5千人(島原で約1万人、肥後で約4600人、天草諸島で約300人)。いわゆる「島原大変肥後迷惑」。 |
| 8月10日 | フランス革命で、ジャコバン派がテュイルリー宮殿を襲撃して国王一家を拘束。 |
| 8月16日(寛政4年6月29日) | 甲府、江戸などで大きな地震があり、富士山では落石により20数人が死亡する。 |
| 9月 2日 | フランス革命で、ジャコバン派に扇動された民衆が反革命派に対する九月虐殺事件を引き起こす。収監されていた貴族や聖職者などを含む1万4千人以上が殺されたと言われる。多くは特に反革命とは無関係だったとみられる。 |
| 9月16日(泰徳15年/光中5年 8月 1日) | 西山朝大越の光中皇帝阮恵が、南部で勢力を盛り返す広南阮氏の阮福暎を討伐する軍を起こす直前、急病に倒れ崩御。阮恵はベトナムでは、徴側・徴弐姉妹、陳興道とならんで英雄視されている。 |
| 9月21日 | フランス革命で、王政が廃止される。 |
| 9月22日 | フランス革命で、革命歴起点日。革命歴1年ヴァンデミエール(葡萄月)1日となる。 |
| 1793年 | |
| 1月21日 | フランス革命で、ジャコバン派が主導して、国王を処刑。 |
| 2月 8日(寛政4年12月28日) | 西津軽地震。陸奥国沖合の日本海で発生した大地震で、津軽藩領に津波が襲来。鰺ヶ沢・深浦などで大きな揺れを観測。154軒が倒壊。12人が死亡。大戸瀬一帯の海岸が隆起する。 |
| 2月17日(寛政5年 1月 7日) | 寛政地震。仙台沖の太平洋側で発生した地震で、東北・関東地方でやや強い揺れを観測。東北沿岸に津波が襲来。仙台などで家屋1千軒が損壊。気仙沼では津波で家屋300軒が流出。マグニチュード8クラスの大地震。 |
| 3月11日 | ヴァンデの反乱勃発。フランス革命による教会弾圧と三十万人募兵令に反発したフランス西部ヴァンデ地方の農民らが王党派と組んで武装蜂起。大規模な反乱へと発展する。革命政府が強権的になるきっかけとなった事件。 |
| 5月15日 | スペインのディエゴ・マリン・アギレラがオーニソプター(羽ばたき式飛行機)を開発し初飛行。360mほど滑空して墜落したという。 |
| 7月14日 | ヴァンデの反乱を指揮したジャック・カトリノーが戦傷がもとで死亡。もと行商人で軍隊経験はないが指揮能力が高く、農民らに支持されていた。その死により反乱軍は求心力を失っていく。のちの王政復古時にカトリノー家は貴族に列せられた。 |
| 7月17日 | フランス革命で「暗殺の天使」シャルロット・コルデーが処刑される。ジャコバン派の中心人物ジャン=ポール・マラーを暗殺したため。 |
| 8月 8日 | フランス革命に反発したリヨン市を共和国軍が包囲。いわゆるリヨンの反乱が起きる。 |
| 9月18日 | フランス革命に反発した王党派とそれを支援するイングランド、スペインなどがトゥーロンを占領したため、共和国軍が攻勢を開始。共和国軍を率いたジャン・フランソワ・カルトーが負傷したため、ナポレオン・ボナパルトが指揮権を委ねられる。 |
| 10月 9日 | リヨン市が共和国政府に降伏。政府の有力者ジョルジュ・クートンは穏便に済ませようとしたが、国民公会はジャン=マリー・コロー・デルボワとジョセフ・フーシェを派遣。両者は市内を徹底的に破壊したうえ、市民2000人以上を処刑した。リヨンの大虐殺とも言われ、これがもとでロベスピエールとフーシェらとの間で対立に発展。テルミドールのクーデターの遠因の一つになった。 |
| 10月16日 | フランス革命で、マリー・アントワネットらが処刑される。 |
| 11月24日 | フランス革命で、革命歴が採用される。前年9月22日を起点とし、時間の単位を十進法に改めたもの(1週は10日、1日は10時間、1時間は100分、1分は100秒)。 |
| 12月18日 | フランス共和国軍が、トゥーロンを攻略。指揮をしていたナポレオンは負傷したが准将に昇進。イギリス軍などは港湾施設などを焼き払って退却。制圧後、ポール・バラスやルイ=マリ・スタニスラス・フレロンらが到着し、捕らえた王党派や市民を虐殺。フレロンはこの虐殺でロベスピエールとの関係が悪化し、テルミドールのクーデターに加わることになる。 |
| 1794年 | |
| 7月27日 | フランスで、国民公会会議中にロベスピエールに反発する議員ら主導で「テルミドールのクーデター」が起こる。恐怖政治に対する穏健派や市民の反発だけでなく、恐怖政治を強行してロベスピエールと対立した強権派の議員もクーデターに加わっていた。一方、ロベスピエールを支持する国民衛兵や市民も集結するが、ポール・バラス率いる国軍がパリ市中心部を制圧。ロベスピエールら恐怖政治を敷いていたジャコバン派の主要幹部らが逮捕される。 |
| 7月28日 | ロベスピエールら22人が処刑される。クーデターを実行したテルミドール派が権力を握る。 |
| 1795年 | |
| 6月 8日 | マリー・アントワネットの息子ルイが病死。テルミドール派が実権を握ったのち、幽閉されていたタンプル塔の日の射さない汚物だらけの部屋で衰弱しているのが発見され、医者の手で治療が施されたが手遅れだった。10歳。 |
| 6月26日(寛政7年 5月19日) | 火付盗賊改方長官を8年務めた長谷川宣以が死去。 |
| 8月25日 | 詐欺師・山師として知られ「首飾り事件」に巻き込まれたこともあるカリオストロ伯爵ことアレッサンドロ・ディ・カリオストロ(本名ジュゼッペ・バルサーモ)が獄死。様々な創作に登場するカリオストロ伯爵のモデル。ちなみに投獄されたのはフリーメイソンに関わって、カトリック教会の総本山ローマでエジプト・メイソンリーのロッジ(支部)を開いたため。 |
| 10月 5日 | フランスのテルミドール派政府が、法改正をして選挙に有利になる工作を行い、反発した王党派や民衆が暴動を起こす。通称「ヴァンデミエールの反乱」。ナポレオンが砲兵隊で鎮圧。ナポレオンはこの功績で国内軍総司令官となり、暴徒を鎮圧した「革命広場」は、後に融和を意味する「コンコルド広場」と改められた。 |
| 10月24日 | ブランデンブルク=プロイセン王国・ハプスブルク帝国・ロシア帝国による第三次ポーランド分割で、ポーランド・リトアニア共和国は消滅。 |
| カメハメハ1世がハワイ王に即位しカメハメハ王朝ハワイ国が成立。 | |
| 1796年 | |
| 4月11日(嘉慶元年 3月 4日) | 清朝に対する大規模な民衆の反乱、白蓮教徒の乱が起こる。 |
| 5月15日 | エドワード・ジェンナーが、ウシの牛痘の膿を用いることで、病気にならずに体内で抗体を作り、天然痘を予防する「種痘」を行なう。なお、この種痘に使われたウイルスは、正確には牛痘ではなく、牛に感染していた馬痘の一種と考えられる。これ以前にも経験的に天然痘に感染して治癒した人は発症しないことがわかっており、患者の膿を使う「人痘」はあったが、リスクが大きかった。ジェンナーの「種痘」は当時の医学界から批判を受けるも、またたく間に世界中へと広がった。この手法はラテン語の「牛(ヴァッカ)」から「ヴァクチン」と呼ばれるようになり、「ヴァクチン(ワクチン)」は免疫療法の代名詞になる。 |
| 6月 9日(寛政8年 5月 4日) | 油屋騒動事件(古市十人斬り)。日本三大遊郭、伊勢古市の遊郭「油屋」で刃傷事件が起こる。客の医者孫福斎が、酒の相手をしていた遊女のお紺が別の客のところへお呼びがかかって座敷を離れたことに腹を立て、脇差しで店の遊女や下男らを次々と襲い、3人が死亡し、6人が負傷。孫福斎は6日に自殺を図り14日に死亡。お伊勢参りで賑わう古市の大規模遊郭で起きた事件のためすぐに広まり、わずか10日後には松坂で芝居になり、2ヶ月後には後に歌舞伎の人気演目となる『伊勢音頭恋寝刃』が作られた。 |
| 1797年 | |
| 2月13日(寛政9年 1月17日) | 昌平坂学問所設立。幕府の朱子学以外の学問を規制する寛政異学の禁により、林大学頭家の私塾だった湯島聖堂を改称。幕府の機関とする。 |
| 9月 4日 | フランス総裁政府のポール・バラス、ジャン・フランソワ・ルーベル、ルイ=マリー・ド・ラ・ルヴェリエール=レポーが、五百人会選挙で王党派の勢力が盛り返してきたことを受けて、ナポレオンを取り込んでクーデターを起こす。議員216人が逮捕される。通称「フリュクティドールのクーデター」。 |
| 10月22日 | フランスの気球研究者アンドレ=ジャック・ガルヌランが自作の熱気球から自作の布製の落下傘で飛び降り、無事着陸。それまでとは違い骨組みのない現代のパラシュートの起源となる。 |
| ロバート・フルトンが手動式潜水艦ノーチラス号を設計。 | |
| 1799年 | |
| 2月20日(寛政11年 1月16日) | 幕府はロシアの蝦夷方面への進出に備えるため、松前藩から浦河より東の東蝦夷を7年間上知とすることを決定。 |
| 6月29日(寛政11年 5月26日) | 加賀国で大地震。金沢城下で4169軒が倒壊。能美郡・石川郡・河北郡で家屋倒壊964軒、家屋損壊1003軒。死者15人。 |
| 7月15日 | ナポレオン・ボナパルトによるエジプト・シリア遠征の際、戦役の途上フランス軍人ピエール=フランソワ・ブシャールによってエジプトの港湾都市ロゼッタでロゼッタ・ストーンが発見される。 |
| 9月11日(寛政11年 8月12日) | 幕府は、松前藩から残りの蝦夷地の大半(浦河から箱館まで)も上知とすることを決定。代わりに松前家には武蔵国に5千石を与える。 |
| 11月 9日 | ブリュメールのクーデター。ナポレオンがシエイエスの要請でポール・バラスの総裁政府を打倒し、権力を握る。フランス革命の終結。 |
| (景盛7年) | 広南阮氏の阮福暎が西山朝大越の歸仁へ侵攻し、これを占領。 |
| 1800年 | |
| 8月21日(寛政12年 7月 2日) | かねてより問題視されていた銀座の幕府への上納滞銀を受けて、銀吹役の大黒長左衛門常房を3900両余の滞納により家職召放しの上永蟄居とし、銀座人らは解雇。銀座を京橋から蛎殻町へ移転し、新たに銀座人を雇い、御勘定附切り(事実上の幕府直轄)に切り替える。 |
| 10月27日(寛政12年 9月10日) | 日本美術史上類例のない独特の画風を描いた絵師、伊藤若冲が死去。 |
| 1801年 | |
| 1月 1日 | パレルモ天文台長ジュゼッペ・ピアッツィによってケレス(セレス)が発見される。最初に発見された小惑星で、小惑星帯では極端に大きな天体。2006年、IAU総会により、冥王星、エリスとともに準惑星に指定される。 |
| 5月14日 | 北アフリカのオスマン帝国自治州トリポリのパシャ(知事領主)ユサフ・カラマンリが在トリポリアメリカ合衆国領事館の星条旗を旗竿から切り落とす。 |
| 6月14日 | オスマン帝国自治州トリポリとアメリカ合衆国の間で開戦する。第一次バーバリ戦争。 |
| ロゼッタ・ストーンがイギリスに奪われる。 | |
| 1802年 | |
| ロゼッタ・ストーンが大英博物館に収められる。 | |
| (宝興2年/嘉隆1年 7月22日) | 広南阮氏の阮福暎が昇龍に入城して西山朝大越を滅ぼし、広南阮氏を再興。同年、年号を嘉隆と定める。事実上の阮朝越南国(阮朝大南国)の成立。西山朝の阮光纘、阮光紹、阮光維、阮光盤ら王族や、有力者の陳光耀と裴氏春らは処刑された。 |
| 1803年 | |
| 8月 9日 | ロバート・フルトンが、フランスのセーヌ川で、小型蒸気船の試験航行をする。 |
| 10月31日 | アメリカの派遣艦隊に所属する軍艦フィラデルフィアが座礁。乗員307人がトリポリ側の捕虜となる。アメリカ軍は小型船でフィラデルフィアに接近し爆破。第一次バーバリ戦争。 |
| 1804年 | |
| 2月21日 | リチャード・トレビシックが、製鉄所の製品輸送のために試作した蒸気機関車ペナダレン号の試運転が行われる。9マイル(約14.5km)を、5両編成で鉄10tと70人の乗客を乗せて、時速5マイル(約8km)で走行。世界最初の蒸気機関車と言われる。 |
| 8月 3日 | アメリカ海軍が、トリポリ市街を艦砲射撃。第一次バーバリ戦争。 |
| 8月11日 | 神聖ローマ帝国皇帝フランツ2世が、オーストリア皇帝を称する。 |
| 9月 4日 | アメリカ海軍が、トリポリ港に潜入してトリポリ側軍艦の爆破を狙うが、事前に発見され失敗。第一次バーバリ戦争。 |
| 10月 7日(文化元年 9月 4日) | ロシアの遣日使節船ナジェシダ号が長崎に来航。使節団長はニコライ・レザノフ、使節船艦長はクルーゼンシュテルンで、同船には漂流民で偶然にも日本人初の世界一周をする結果となった津太夫(仙台藩出身の水夫)と、他日本人3名も乗っており、日本に帰国している。 |
| 11月14日(文化元年10月13日) | 華岡青洲が全身麻酔による乳癌の摘出手術を成功させる。麻酔手術自体は、古代エジプトや古代中国、インカ帝国などにもあったことが、書物の記述や考古学上の研究から推測できるが、明確に医療記録された全身麻酔手術としては世界初。以降も多数の手術を行い、術後の生存率も高かった。ただ青洲自身は麻酔の材料と比率については記録を残しておらず、弟子本間玄調による記録でも不明な点は多い。 |
| 12月 2日 | ナポレオン・ボナパルト、フランス皇帝に即位。ノートルダム大聖堂で自ら戴冠式を行う。 |
| イングランドの工学研究者ジョージ・ケイリーが模型のグライダーを制作。固定翼の概念を確立する。のちに実物のグライダーを作り、飛行に成功している他、回転翼機の模型も制作。内燃機関やキャタピラ車両の開発、建築など幅広く活動している。 | |
| 1805年 | |
| (文化元年 3月) | 天領で島原藩が預かっていた天草地方で、島原藩によるキリシタン探索が行われ、5000人が発覚。いわゆる「天草崩れ」。ただし、島原藩、幕府共に、キリシタン弾圧が、大規模な一揆などを誘発することを恐れたことと、領民側もキリシタンではなく先祖伝来の「異宗」を信じていただけで、指示には従うと訴えたことから、踏み絵と誓約書の提出だけで収拾が図られた。 |
| 4月 2日 | 童話作家、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの生誕日。4月2日は「国際こどもの本の日」。 |
| 4月27日 | ダーネの戦い。アメリカ海兵隊と傭兵部隊が、トリポリ側の都市ダーネを攻略。第一次バーバリ戦争。 |
| 10月21日 | トラファルガーの海戦。フランス艦隊とイギリス艦隊がトラファルガル岬沖で艦隊戦を行う。フランス艦隊が大敗。しかしイギリス艦隊のネルソン提督も戦死。 |
| 12月 5日 | アウステルリッツの戦いで、神聖ローマ帝国皇帝フランツ2世とロシア帝国皇帝アレクサンドル1世が、フランス帝国のナポレオンに大敗を喫する。三帝会戦とも。 |
| 12月26日 | プレスブルクの和約。フランスとオーストリアが講和。 |
| 1806年 | |
| 4月22日(文化3年 3月 4日) | 文化の大火。江戸芝車町の材木座付近から出火。近くの薩摩藩上屋敷、芝増上寺を焼き、増上寺五重塔は焼失。西南からの風に煽られて北へと延焼。木挽町、数寄屋橋、京橋、日本橋を焼き尽くす。さらに神田方面、浅草方面へと拡大した。翌日、雨によって鎮火。530町12万6000軒、大名屋敷80、寺社80余が焼失。1200人以上が死亡。車町火事、牛町火事、丙寅の大火ともいう。 |
| 7月12日 | 神聖ローマ帝国内のドイツ諸侯がフランス・ナポレオンを盟主とするライン同盟を結成。帝国宰相カール・テオドール・フォン・ダールベルクが首座大司教侯となる。神聖ローマ帝国の事実上の崩壊。 |
| 8月 6日 | 神聖ローマ帝国皇帝フランツ2世が、アウステルリッツの戦いに敗れフランスに降服したことで、皇帝位を降り、神聖ローマ帝国の解体を宣言する。 |
| 11月21日 | ナポレオンが、イングランドを経済封鎖しようと大陸封鎖令を発令。 |
| 1807年 | |
| 1月12日 | ホラント王国(オランダ)の都市ライデンで、大量の黒色火薬を荷揚げしようとしていた輸送船が爆発。爆風で市街地の建物の多くが損傷し、151人が死亡。調理用の火が移ったという説や、乗員が火薬を盗もうとして誤って火をつけてしまったという説がある。 |
| 3月30日(文化4年 2月22日) | 幕府は蝦夷地の上知の期限に合わせて、松前藩を陸奥国伊達郡梁川9千石に転封。松前藩はアイヌとの交易である商場制で収益を得ていたため苦境に陥り、幕閣らに蝦夷復帰運動を行う。 |
| 6月10日 | 第一次バーバリ戦争終結。アメリカとトリポリが講和。 |
| 8月17日 | ロバート・フルトンが、ニューヨークからオールバニまで、ハドソン川で実用蒸気船の試験航行を行い、高い評価を得る。 |
| 9月 4日 | ロバート・フルトンが、ハドソン川で蒸気船の運行営業を始める。 |
| 9月 1日(文化4年 7月29日) | 津軽藩が幕府の命を受け、ロシアの進出に備えて、警備のため蝦夷地シャリ会所(現在の斜里町)へ藩士らを派遣。順次100人が派遣され越冬することに。 |
| 9月20日(文化4年 8月19日) | 富岡八幡宮祭礼の参拝客の重みで、隅田川にかかる永代橋の東側が崩落する。死者行方不明者1400人。 |
| 1808年 | |
| 9月25日 | スコットランド・オークニー諸島のストロンゼー島に、巨大な生物の死骸が漂着する。長さは16.8m以上とされ首が4m以上もあり、尾の部分が途中で切れていた。また3対6本の足があったという。伝説によく出てくるシーサーペントの一種だとして「Halsydrus pontoppidani」(ポントビダンのウミヘビ※ポントビダンは著名なウミヘビ研究者の名前)の学名まで付いた。写真のない時代で正体はわかっていない。足は腐ったヒレの誤認、長さももっと短いという説もあり、ウバザメの死骸説も有力。ウバザメは独特の形状をしていて、10m以上の個体もあり、腐敗すると下顎がなくなり、間延びすることから、首長竜と間違えられるなど未確認生物のネタにもなりやすいサメ。 |
| 9月 1日(文化5年閏6月24日) | 津軽藩が警備に当たっていた蝦夷地シャリ会所から撤収。派遣された100人のうち72人が病死する大きな犠牲を払う結果となる。 |
| 10月 4日(文化5年 8月15日) | フェートン号事件。ナポレオン戦争の余波で、イギリスの軍艦が、フランスの属国となっていたオランダの植民地や港湾を襲い、その一環で、フェートン号がオランダ国旗を掲げて長崎に入港し、出迎えたオランダ商館の職員や長崎奉行所の通詞らを捕縛し、さらに食料などを要求、応じなければ攻撃すると脅す。 |
| 10月 6日(文化5年 8月17日) | フェートン号が長崎奉行やオランダ商館の提供で食料を確保し、人質を解放して港外に去る。責任をとって長崎奉行松平康英や鍋島藩家老らが切腹する。 |
| 11月 | ヤーコプ・デーゲンが、水素気球付きオーニソプター(羽ばたき式飛行機)を開発し、飛行に成功したと言われる。浮上は気球で行い、翼を動かして移動するもので、純粋な飛行機ではない。デーゲンは時計職人で、晩年は紙幣の偽造防止印刷技術も発明している。 |
| 1809年 | |
| この頃、熱帯地方のいずれかで大規模な火山の噴火があったと考えられる。翌年以降異常気象が起こる。 | |
| 1810年 | |
| 8月16日 | フランス軍によるポルトガルのアルメイダ包囲戦のさなかに、着弾したフランス軍の砲弾から落ちていた火薬に引火、火薬庫へと火災が広がり、大爆発を起こす。要塞の一部が崩壊し、600人が死亡し、300人が負傷。守将のウイリアム・コックス准将は継戦が困難になったとして降伏。 |
| 10月23日(文化7年 9月25日) | 男鹿半島の寒風山付近で大きな地震があり、57名が死亡、1400棟あまりが全半壊するなど大きな被害を出す。寒風山が噴火したという記録もあるが、地質学上の痕跡がないため、被害を大きく見せる虚偽報告か。 |
| (文化7年) | この年、江戸の花火師「鍵屋」の番頭清吉が暖簾分けして市兵衛と称し、「玉屋」を興す。 |
| ハワイ王国のカメハメハ1世が、ハワイ諸島を統一。 | |
| 1811年 | |
| 5月31日 | ドイツ・ヴュルテンベルク王国の仕立て屋で発明家アルプレヒト・ルートヴィヒ・ベルブリンガーが、自ら発明したグライダーの飛行実験を行い失敗に終わる。 |
| 7月30日 | メキシコの独立を訴えた司祭ミゲル・イダルゴが処刑される。 |
| 12月 7日 | ロンドンのラドクリフ街道にある洋品店で一家と店員の4人が惨殺される事件が起きる。 |
| 12月19日 | ロンドンのラドクリフ街道の酒場で再び3人が惨殺される同様の事件が発生。 |
| 12月23日 | ロンドンのラドクリフ街道連続惨殺事件で船員のジョン・ウィリアムズが逮捕される。本人は容疑を否認。 |
| 12月27日 | ロンドンのラドクリフ街道連続惨殺事件で逮捕されたジョン・ウィリアムズが拘置所内で自殺(他殺説もあり)。犯人と断定され、遺体を衆人に晒される。しかしウィリアムズの単独犯行説には疑問も多く、治安と捜査の不備が論議される契機となった。のちのロンドン警視庁発足のきっかけとも言える事件のひとつ。 |
| 1812年 | |
| 6月23日 | ナポレオン率いるフランス帝国の大陸軍と同盟軍77万人以上がモスクワ侵攻を開始。 |
| 9月14日 | ナポレオン軍、モスクワに入城するが、脱落兵が多数出ており、モスクワ自体もロシア軍が放棄して空城になっていて、得るものは殆ど無かった。 |
| 10月19日 | ナポレオン軍、モスクワ退却を開始。 |
| 12月24日(文化9年11月21日) | 宇和島藩で萩森騒動が起きる。前日に行われた藩の財政難に関する討議で、藩の老中稲井甚太左衛門の政策に反対した番頭の萩森宏綱が稲井に侮辱された恨みから、この日、稲井家を襲撃し取り押さえられる。 |
| 1813年 | |
| 1月24日 | イギリスでロンドン・フィルハーモニック協会が設立される。現在のロイヤル・フィルハーモニック協会。 |
| 3月11日(文化10年 2月 9日) | 宇和島藩の萩森騒動で刃傷事件を起こした萩森宏綱が切腹。萩森は下士に対する負担軽減策を唱えていたことから、藩内で萩森に同情する意見が高まり、藩も負担軽減策を導入せざるを得なくなり、萩森神社も創設された。 |
| 4月27日 | ヨークの戦い(米英戦争)。英領アッパーカナダの首都ヨーク(現カナダ・オンタリオ州トロント)で起きた戦い。アメリカ軍が街の要塞を攻撃。守備側のイギリス軍は退却する際に火薬庫を爆破したため、接近していたアメリカ軍が巻き込まれ、指揮官のゼブロン・パイク准将を含む38名が爆死、222名が負傷する。 |
| 4月28日 | ヨークの戦いに勝利したアメリカ軍は同地で大規模な略奪・破壊行為を行う。 |
| 8月26日 | ドレスデンの戦い。ナポレオン率いるフランス軍と、オーストリア帝国、ロシア帝国、プロイセン王国との戦い。フランス軍が勝利。 |
| 10月24日 | ロシアとガージャール朝(今のイラン付近の王国)との間で、ザカフカース地方の支配域を決めるゴレスターン条約が締結。ロシアの軍事力に押されたガージャール朝は、ジョージア(グルジア)・アゼルバイジャン地方の大部分を失い、ロシアのカスピ海航行権も認めざるを得なくなる。 |
| 10月16日 | ライプツィヒの戦い。ナポレオン率いるフランス軍とライン同盟などの同盟軍に対し、対仏大同盟を組んでいたオーストリア帝国、ロシア帝国、プロイセン王国、スウェーデン王国などの連合軍が、ライプツィヒで交戦。フランス軍がやや優勢に進める。 |
| 10月18日 | ライプツィヒの戦い。連合軍に大幅な増援があったため、フランス軍に対し総攻撃を行う。9時間の交戦の結果、ナポレオンは退却を命令。 |
| 10月19日 | ライプツィヒの戦い。フランス軍と同盟軍は退却。ワルシャワ公国のユゼフ・アントニ・ポニャトフスキなどが戦死。4万人以上の死傷者を出す。連合軍も5万4000人が死傷。フランスはライン以東を失う。 |
| 諏訪之瀬島が噴火。溶岩が島の西海岸まで流れ下り、島民は全員島外へ移住。1883年まで無人島となる。 | |
| 1814年 | |
| 4月11日 | 1814年フランス戦役で大敗したナポレオンが退位。 |
| 5月 4日 | ナポレオンがエルバ島領主として追放され、ルイ18世が即位して王政復古する。 |
| 11月 1日 | ネパール王国とイギリスの間でグルカ戦争が勃発。 |
| 1815年 | |
| 2月26日 | ナポレオンがエルバ島を脱出。 |
| 3月20日 | ナポレオンが、兵を率いてパリに入城。皇帝に復位。 |
| 4月10日 | インドネシア中南部のスンバワ島にあるタンボラ山が大爆発を起こし、上部1000m程が消失し、膨大な量の噴出物が周辺1000kmに降り注ぐ。 |
| 6月 9日 | ウィーン会議で体制維持に各国が合意し、ウィーン体制がはじまる。 |
| 6月16日 | リニーの戦い。フランス軍とプロイセン軍が衝突。プロイセン軍が大きな被害を出す。 |
| 6月18日 | ワーテルローの戦い。ナポレオン率いるフランス軍と、ウェリントン公率いるイギリス・オランダ軍およびブリュッヒャー率いるプロイセン軍が戦う。フランス軍の敗北。 |
| 6月22日 | ナポレオンが退位し、百日天下が終わる。 |
| 1816年 | |
| 3月 4日 | グルカ戦争が終わり、スゴウリ条約が締結されてネパールは領土の多くを失う。 |
| この年、北アメリカ、北ヨーロッパ、中国北部などで低温現象が続き、夏でも降雪や氷が張るほど気温が低く、「夏のない年」と呼ばれている。作物は壊滅的な打撃を受けた。一方、温帯南部から亜熱帯では大雨となるなど異常気象が続いた。前年のタンボラ山の大爆発による噴出物で日光が遮られたことによる「ヴォルカニック・ウィンター」と考えられる。大規模な火山の噴火はこの頃世界中で頻発しており、さらに太陽の活動縮小期(1790年から1830年まで続いたダルトン極小期)でもあったため、タンボラ山の噴火だけではないとも言われる。また異常気象は1810年ころからという説もある。 | |
| 1817年 | |
| 4月12日 | フランスの天文学者シャルル・メシエが死去。メシエ天体カタログを作った人物。 |
| 5月 8日 | ボタンの木協定、New York Stock & Exchange Board に改称。現在のニューヨーク証券取引所スタート。 |
| 12月29日(文化14年11月22日) | 八王子周辺に隕石多数が落下。金剛院のそばに90cmほどの大きな隕石が落ちたという。東から飛来し多摩川上空付近で爆発して破片が降り注いだものと考えられる。隕石のその後の行方ははっきりしない。 |
| この年も北半球各地で低温現象が起こった。 | |
| 1818年 | |
| 1月 1日 | メアリー・シェリー作のゴシック・ホラー『フランケンシュタイン』出版。 |
| 1819年 | |
| 8月16日 | ピータールーの虐殺。イギリスの都市マンチェスターで不況と失業に不満を持つ6万人の民衆が集会を開くが、政府が武力弾圧を行う。11人が死亡し600人以上が負傷。集会がセント・ピーター教会前の広場で行われたことから、ワーテルロー(ウォータールー)の戦いになぞらえて、ピータールーの虐殺と呼ばれた。 |
| 2月22日 | スペインとアメリカ合衆国はアダムズ=オニス条約で合意し、フロリダをアメリカ合衆国領とする替わりに、アメリカ合衆国はテキサスからカリフォルニアにかけての領有権主張を取り下げる。 |
| この年 | ロシアの世界周航遠征隊のファビアン・ゴッドリープ・フォン・ベリングスハウゼンがサウスジョージア諸島・サウスサンドイッチ諸島を「再発見」。この諸島は最初の発見から何度か「発見」されているが、亜南極の厳しい環境のため、20世紀初頭に捕鯨が盛んになるまで人が住まなかった。 |
| 1820年 | |
| 1月28日 | ロシアの世界周航遠征隊のタデウス・ベリングスハウゼンとミハイル・ラザレフらが南極大陸を発見する。 |
| 1月 | アメリカの黒人解放・祖国再建運動の一環としてリベリア建国運動が行われる。 |
| 4月 8日 | エーゲ海のメロス島の農夫ヨルゴスが『ミロのヴィーナス』像を発見。 |
| 5月12日 | ナイチンゲールの生誕日。 |
| 1821年 | |
| 2月 7日 | アメリカ人のアザラシ漁師ジョン・デイビスが南極大陸沿岸に上陸したとされる。 |
| 3月25日 | アレクサンドロス・イプシランディス率いる、オスマン帝国のギリシャ独立運動組織フィリキ・エテリアが武装蜂起。各国や住民の協力が得られず反乱は失敗し、のちにイプシランディスは逮捕されるが、影響を受けたギリシャ各地で反乱が続発し、ギリシャ独立へとつながる。3月25日はギリシャ独立記念日。 |
| 5月 5日 | 元のフランス皇帝ナポレオン・ボナパルトが、南大西洋の孤島セントヘレナ島で死去。胃がん説およびヒ素中毒による病死説、医療ミスによる急死説も有力だが、暗殺かどうかは議論が分かれる。 |
| 5月24日(文政4年 4月23日) | 相馬大作事件。相馬大作こと盛岡藩士下斗米秀之進らが、弘前藩主津軽寧親を暗殺しようとして情報が漏れ失敗した事件。ともに南部一族から出ている盛岡藩主南部氏と、弘前藩主津軽氏との軋轢から、主君の名誉のために狙ったとされる。すぐに演劇に取り入れられ相馬大作は義挙の人に、津軽藩は悪く言われることになるが、津軽藩は一方的に迷惑を被っただけという意見もあった。 |
| 6月24日 | カラボボの戦い。シモン・ボリバル率いる独立革命軍とスペイン軍が衝突し、革命軍が勝利して、南米諸国のスペインからの独立につながっていく戦い。 |
| 8月 7日(文政4年 7月10日) | 伊能忠敬らが測量し高橋景保らが製作した大日本沿海輿地全図が完成。 |
| 12月30日(文政4年12月 7日) | 陸奥国梁川藩に転封になっていた松前家が蝦夷に戻される。 |
| 1822年 | |
| 3月12日(文政5年閏1月19日) | 有珠山が噴火。 |
| 3月15日(文政5年閏1月22日) | 有珠山が大噴火する。大量の焼け石が周辺地域へと落下。 |
| 3月15日(文政5年 2月 1日) | 有珠山が再度大噴火。火砕流と火砕サージが山麓へと流れ、交易地であったアブタコタンに到達。アイヌ住民ら50人以上が死亡。文政噴火とも呼ばれる。 |
| ジャン=フランソワ・シャンポリオンがロゼッタストーンのヒエログリフ解読に成功する。 | |
| アメリカの解放奴隷らによって、西アフリカに最初のリベリア移住区が建設される。 | |
| 1823年 | |
| 5月16日(文政6年 4月 6日) | 大田蜀山人死去。三大狂歌作者の一人。 |
| 6月 1日(文政6年 4月22日) | 千代田の刃傷事件が起こる。イジメが原因で起こった旗本同士による殺傷事件。 |
| 1824年 | |
| 5月 7日 | ベートーベンの交響曲第9番がウイーンのケルントネル門劇場で初演される。ベートーベン本人はすでに聴力を失っていたため、ミヒャエル・ウムラウフが正指揮者としてともに式台に立った。演奏後、聴衆の拍手が聞こえていなかったベートーベンを、アルト歌手のカロリーネ・ウンガーが向きを変えて示した、というエピソードがある。 |
| 6月24日(文政7年 5月28日) | 水戸藩領の常陸大津浜に英国船数隻が現れイギリス人船員12名が上陸。水戸藩に捕らえられる。尋問の結果、水と食料を求めていることがわかり、提供の上で船員も釈放し船に帰す。この対応を巡って論争になり、翌年の異国船打払令に繋がったと言われる。 |
| 8月(文政7年 8月) | 薩摩領の宝島に英国船が現れ、イギリス人船員が上陸して牛を要求したため島民がこれを拒否すると、兵が多数上陸して牛3頭を奪い逃走。薩摩在番兵との間で紛争となり、イギリス兵1名が死亡。大津浜事件とともに翌年の異国船打払令に繋がったと言われる。 |
| 1825年 | |
| 4月 6日(文政8年 2月18日) | 異国船打払令が出される。 |
| 9月 8日(文政8年 7月26日) | 四代目鶴屋南北作の歌舞伎演目、「東海道四谷怪談」が江戸・中村座で初演。 |
| 10月 9日 | ノルウェーからアメリカへ最初に組織的に移住した人々の乗った船がニューヨークに到着。ヨーロッパ人で最初に北米へ到達したバイキングのレイフ・エリクソンの日として記念している。 |
| 12月26日(ロシア歴12月14日) | サンクトペテルブルクでデカブリストの乱が起こる。政治改革を訴えた青年貴族らの秘密結社が、皇帝代替わりの混乱に乗じて起こした反乱。即位したばかりのニコライ1世によって、翌日鎮圧される。 |
| 1826年 | |
| 7月 4日 | アメリカ独立宣言書の作成に携わったトーマス・ジェファーソンとジョン・アダムスが、ともに独立50周年記念のこの日に亡くなる。 |
| 1827年 | |
| 4月30日(文政10年 4月 5日) | 淡路出身の廻船問屋で、蝦夷交易で財を成し、ゴローニン事件で拿捕され、ロシア外交を仲介した高田屋嘉兵衛が亡くなる。 |
| 1828年 | |
| 1月13日(文政10年11月27日) | のちの東大赤門が建立される。加賀前田氏の第12代藩主前田斉泰が第11代将軍徳川家斉の第21女、溶姫を迎える際に、藩邸に作った御守殿門。 |
| 2月10日 | ロシア帝国とガージャール朝との間で、トルコマーンチャーイ条約が締結され、ガージャール朝は、アルメニアと、アラス川以北の北アーザルバーイジャーン(1813年に失ったアゼルバイジャンの南側)を失う。 |
| 9月18日(文政11年 8月10日) | シーボルト事件。長崎出島のオランダ商館づきの医師だったシーボルトが、幕府禁制品の日本地図などを持ち出そうとしたことが発覚し、学者らが取締を受けた事件。 |
| 1829年 | |
| 4月24日(文政12年 3月21日) | 文政の大火。江戸神田佐久間町(現在の秋葉原の東方)の材木小屋から出火。タバコの火の不始末で引火した鋸屑が風によって飼葉屋に飛んで炎上したとされる。北西からの強風に煽られ拡大。西は今川橋付近、東は大川端両国橋から永代橋一帯、東南に向けて霊岸島から佃島人足寄場、南は数寄屋橋を超えて新橋汐留付近まで延焼。翌日鎮火した。大名屋敷73、旗本屋敷130、町家11万8000軒など約37万軒と橋65が焼失し、2801人が焼死(被害は諸説あり)。神田大火、己丑火事とも呼ばれる。 |
| 6月14日(文政12年 5月13日) | 寛政の改革を推進した松平定信が死去。 |
| 9月29日 | イギリスの首都警察スコットランドヤードが発足。初代庁舎が置かれた場所、ホワイトホールにあったスコットランドヤード広場から、スコットランドヤードと呼ばれる。 |
| 1830年 | |
| 7月27日 | フランス7月革命勃発。王政復古後の旧態依然とした政策に対する市民の不満が爆発して蜂起。 |
| 7月29日 | フランス7月革命で、革命勢力が王宮を占拠。内閣は総辞職。 |
| 7月31日 | フランス7月革命で、アメリカ独立戦争の英雄として人気のあったラファイエット侯爵が国民軍司令官となり、オルレアン家のルイ・フィリップとともに収拾に動き出す。 |
| 8月 2日 | フランス国王シャルル10世は退位しオーストリアへ亡命。立憲君主制としてルイ・フィリップが国王に即位。 |
| 8月25日 | ベルギー独立革命勃発。当時オランダ(ネーデルラント連合王国)の支配下にあった南ネーデルラントのブリュッセルで、フランス7月革命の影響を受けた人々が、革命を題材にした人気オペラ「ポルティチの唖娘」鑑賞後に暴動を起こす。 |
| 9月15日 | イギリスで世界初の営業鉄道リバプール・アンド・マンチェスター鉄道が開業。鉄道自体はこれより古くからあるが、定時運行の旅客鉄道はこれが最初とされる。当日、参列した政治家が轢かれて死亡する世界最初の鉄道人身事故も起こる。 |
| 9月23日 | オランダ王国軍が、ブリュッセルの反乱鎮圧のために出動するが失敗に終わる。王国軍に地元出身の兵士が多くいたため、彼らが逃亡したことによる。 |
| 9月26日 | ブリュッセルに臨時政府が樹立する。 |
| 10月 4日 | ベルギーの独立宣言。 |
| 11月29日 | ポーランドの士官学校生徒ら武装蜂起。ワルシャワのベルヴェデル宮殿と武器庫を襲う。11月蜂起。総督のコンスタンチン・パヴロヴィチ大公は脱出。 |
| 12月 3日 | ポーランド革命を図る急進派モフナツキらが愛国協会を組織。ロシアと穏便に解決を図ろうとするポーランド行政評議会を批判し臨時政府樹立を主張。 |
| 12月 5日 | ポーランド議会(セイム)が、ユゼフ・フウォピツキを臨時政府独裁官に任命。 |
| 12月13日 | ポーランド議会(セイム)が、「市民蜂起」を宣言。 |
| 12月20日 | ヨーロッパ列強各国はベルギー独立を容認。オランダはこれに反発。 |
| 1831年 | |
| 1月 8日 | ロシアとの交渉が失敗に終わり、フウォピツキがポーランド臨時政府独裁官を辞任。 |
| 1月25日 | ポーランド議会(セイム)は、ポーランド王ニコライ1世(ロシア皇帝)の廃位を決議。ロシアとの同君連合を解消する。 |
| 1月29日 | ポーランド国民政府樹立。ロシア帝国首席大臣や外相も勤めたポーランド貴族チャルトリスキ公が政府首班に就く。間もなくロシア軍がポーランドへ向けて侵攻を開始し、ロシア・ポーランド戦争勃発。 |
| 2月14日 | ストチェクの戦い(ロシア・ポーランド戦争)。ポーランド軍はかろうじてロシア軍を撃退する。しかし以後もロシア軍は攻勢を強め、列強各国もポーランド独立には消極的な対応に終始。 |
| 2月25日 | ベルギー王に推された、ルイ・フィリップの息子ヌムール公ルイが拒否したため、一旦、シュルレ・ド・ショキエ男爵がベルギー摂政となる。 |
| 2月14日 | オルシンカ・グロホフスカの戦い(ロシア・ポーランド戦争)。ポーランド軍はワルシャワを防衛。 |
| 7月21日 | 初代ベルギー王としてザクセン=コーブルグ=ゴータ家出身のレオポルドが就く(後の英女王ヴィクトリアの叔父)。 |
| 8月 2日 | オラニエ公ヴィレム率いるオランダ軍がベルギーに侵攻。十日間戦争が勃発。 |
| 8月 4日 | オランダ軍がアントウェルペンを占領。 |
| 8月12日 | オランダ軍が撤退。フランスとの関係悪化を避けるためなどの理由による。事実上のベルギーの敗北に終わる。 |
| 8月21日 | バージニア州でナット・ターナーの反乱が起きる。50名ほどの黒人が加わり、57人の白人男女を殺害。まもなく民兵によって鎮圧される。 |
| 10月 5日 | ポーランド軍の残党兵力2万が、プロイセン側で降伏。ロシア・ポーランド戦争はほぼ終結し、11月蜂起から続いたポーランド独立への動きは失敗に終わる。多数のポーランド人がフランスなどへ亡命。チャルトリスキやユゼフ・ベム将軍などはその後も外国で独立運動を続けた。列強各国政府はポーランド独立に冷淡だったが、各国一般市民の間では支持する動きが大きかったと言われる。 |
| 10月30日 | ナット・ターナーが捕らえられる。 |
| 11月 5日 | ナット・ターナーに死刑判決がくだされる。 |
| 11月11日 | ナット・ターナーが絞首刑に処せられ、遺体は皮を剥がされバラバラにされる。この他に、反乱に関わったとして、55名の黒人が処刑され、無関係の黒人およそ200名も白人によるリンチなどで殺害されたと言われる。 |
| 12月27日 | チャールズ・ダーウィンを乗せたビーグル号がポーツマスを出港。ビーグル号としては2回めの航海となる。 |
| 1832年 | |
| 9月13日(天保3年 8月19日) | 大名屋敷・武家屋敷専門の盗賊、鼠小僧次郎吉が、市中引き回しの上、獄門にかけられる。次郎吉は派手に着飾って刑場へ連れていかれた。 |
| 10月(天保3年 9月) | 富士講の一派「不二孝」の指導者小谷三志が、女性信者の高山たつを連れて富士山頂へ登る。基本的には女人禁制だったため、女性が富士山頂まで登った記録では最初の例。 |
| 1833年 | |
| カスパー・ハウザー暗殺事件。ドイツで地下牢獄で育てられたとされて有名になったカスパー・ハウザーが、何者かに刺殺される。20歳。16歳で放浪しているところを保護された当初は言葉も喋れず一般的な常識もなかったが、言葉を学び、自分の置かれていた境遇を説明するようになってまもなくだったという。並外れた五感の持ち主だったとされている。出自については、乳児のときに死んだ(あるいはさらわれた)と言われるバーデン大公カールとステファニー夫妻の嫡男ではないかとする説が広まった。 | |
| アフリカ西岸の解放奴隷による移住区がリベリアを中心に連邦になる。 | |
| 1834年 | |
| 1月15日 | ビハール・ネパール大地震。死者8519人。カトマンズ盆地で大きな被害を出す。カトマンズ盆地はヒマラヤ山脈中にあり、8000年前まで湖だった場所で地盤が非常に弱く、地震の多い土地でもあり、地震のたびに被害が出る。 |
| 3月16日(天保5年 2月 7日) | 甲午火事。江戸神田佐久間町の藤堂和泉守屋敷前にあった湯屋から出火。西北からの風に煽られて拡大。東は両国まで、西は今川橋、南は築地から鉄砲洲、霊岸島を経て、佃島に到達。延焼地域は文政の大火とほぼ同じ。470町~480町が焼失、死者4000人というが疑問もある。このあと数日間、火災が頻発した記録がある。 |
| 4月 9日(天保5年 3月 1日) | 水野忠邦が老中に就任。天保の改革がはじまる。 |
| 1835年 | |
| 9月15日 | チャールズ・ダーウィンがガラパゴス諸島チャタム島に到着する。 |
| 10月 2日 | メキシコ合衆国のコアウイラ・イ・テハス州(現アメリカ合衆国テキサス州)ゴンザレスでメキシコ政府が入植地に配備されていた大砲を回収しようとしたことに住民が反発し、軍と戦闘となる。ゴンザレスの戦い。戦闘は小規模だったがテキサス革命の最初の戦闘となる。 |
| 1836年 | |
| 2月23日 | テキサス反乱軍とメキシコとのアラモの砦の戦いがはじまる。 |
| 2月25日 | サミュエル・コルトがリボルバー式拳銃の特許を取得。 |
| 3月 2日 | テキサスの住民が独立宣言。 |
| 3月 6日 | アラモの砦が陥落する。英雄デイヴィッド(デイヴィー)・クロケットも処刑される。 |
| 4月21日 | サンジャシントの戦い。テキサス軍がメキシコ軍を奇襲し勝利。メキシコ軍を率いていたメキシコ大統領サンタ・アナは捕らえられる。 |
| 5月14日 | テキサス共和国政府と捕虜となっていたメキシコ大統領サンタ・アナの間でベラスコ条約が締結されテキサス共和国は独立。ただしサンタ・アナ個人との間のこととして、メキシコ政府は認めず。 |
| (天保7年) | 南部藩で盛岡南方一揆が起きる。御用金の賦課と藩札の増発によるインフレに苦しんだ庶民によるもの。藩は処罰しないことを約束して解散させた後で首謀者を処罰し要求も一切応じなかった。 |
| 1837年 | |
| (天保8年) | 南部藩でふたたび盛岡南方一揆が起きる。前年の一揆で藩が約束を反故にしたことから、仙台藩領へ逃散した上で仙台藩に訴えた。南部藩は一揆関係者を処罰しないとして仙台藩に幕府へ内密にすることを求め仙台藩も応じるが、一揆勢が戻ってくるとこれを処罰。仙台藩の反発を買う。 |
| 3月25日(天保8年2月19日) | 大坂で大塩平八郎の乱が起こる。天保の大飢饉の影響と幕府の腐敗による米価高騰を受けて決起した事件。天満一帯を焼失する被害を出し、幕府軍に鎮圧される。 |
| 5月 1日(天保8年3月27日) | 大坂船場の商家美吉屋五郎兵衛宅に潜伏していた大塩平八郎の所在が通報され、養子の格之助と共に火薬に火を放ち自決。 |
| 7月30日(天保8年6月28日) | モリソン号事件。中国にいた独立宣教師カール・ギュツラフが、日本に関心を示し、各地で保護された日本人漂流民7人(音吉・岩吉・久吉・庄造・寿三郎・熊太郎・力松)を日本に送り届けることで日本入国を企図。日本との通商を考えていたアメリカ商人チャールズ・W・キングの協力を得て、アメリカ船モリソン号で浦賀に接近するが、沿岸より砲撃を受け退去した。その後モリソン号は薩摩山川に寄港し、薩摩藩家老島津久風と交渉するも、漂流民はオランダ船に乗せ換えて帰国させるという当時の対応策により交渉は成らず、モリソン号はマカオに帰港した。この事件が後に蛮社の獄に発展する。 |
| 1838年 | |
| 1月 6日 | モールス、ヴェイル、ガレが電信の実験に成功。 |
| 12月 1日(天保9年10月15日) | 尚歯会(学者らの会)の集まりの席上で、幕府のモリソン号に対する方策案が示される。実際には幕府の評議で却下された「漂流民は受け取らず、船は打ち払う」という内容のみだったため会員らの反発を買う。 |
| 1839年 | |
| 4月19日 | オランダを含めたヨーロッパ列強がロンドン条約に調印し、ようやくベルギー独立が正式に認められる。なおこの際に、ルクセンブルク大公国領とリンブルフ公国領は、ベルギーとオランダで半分ずつに分けられた。 |
| 6月11日(天保10年 5月 1日) | 「樋口一件」事件。公家の樋口寿康が自宅で襲われ殺害される。妾だった花井も殺害。捜査の結果、同家雑掌の岡田重武と苅田小四郎の犯行とわかり、両者に指示したのは寿康の息子の樋口功康と判明。幕府は公家の身分のある犯人らの処分に苦慮したが、身分剥奪の上で、実行犯2人を死刑、功康は隠岐に流罪とした。功康が父の妾の花井を恨んで殺害したところ、その場に現れた寿康を誤って殺害したものと後にわかる。 |
| 6月24日(天保10年 5月14日) | 鳥居耀蔵が、渡辺崋山らに出頭を命じ、蛮社の獄が起こる。尚歯会メンバーによるモリソン号についての幕政批判や無人島渡航計画を問題にして行われた蘭学の弾圧とされているが、異説もある。 |
| 7月 2日 | アミスタッド号事件。スペインの奴隷船アミスタッド号で、輸送途中だったアフリカ人奴隷53名が反乱を起こす。しかし船員が彼らを騙して進路をアメリカへ向ける。 |
| 8月26日 | 補給のためにアメリカ東海岸に停泊したことから、アミスタッド号の反乱が明らかになる。アフリカ人は拘束される。 |
| 1840年 | |
| 1月17日 | メキシコの北東に位置するコアウイラ、ヌエボレオン、タマウリパスの各州がメキシコから独立を宣言。リオグランデ共和国とし、ラレドに首都を置いて、ヘスス・デ・カルデナスが大統領に就任する。 |
| 2月 6日 | イギリスがニュージーランドのマオリ族とワイタンギ条約を締結し、同地の土地収奪をはじめる。 |
| 3月24日 | メキシコ軍とリオグランデ軍がモレロスで戦闘し、リオグランデ軍が敗北。アントニオ・サパタ大佐らリオグランデ共和国軍の指揮官らが処刑される。アントニオ・カナレス・ロシリョ司令官はテキサス共和国へ敗走。同地で兵を募る。 |
| 7月 2日 | アララト山で噴火。火砕流と、同時に起きたマグニチュード7.4相当の地震で地すべりが発生。麓のアコリ、アラリックなどの村や、ロシア軍の駐屯地などを襲い、約1万人の死者を出す。 |
| 11月 6日 | メキシコ政府とリオグランデ軍の司令官アントニオ・カナレス・ロシリョが妥協し、カナレスがメキシコ側に降伏して、リオグランデ共和国は消滅。 |
| ハワイ王国に憲法が制定され、立憲君主制に移行する。 | |
| 1841年 | |
| 3月 9日 | アミスタッド号事件を起こしたアフリカ人が、奴隷貿易は非合法であること、アフリカで拉致されたことを理由に、解放されることが最高裁で確定。 |
| 8月 1日(天保4年6月15日) | 口永良部島新岳で噴火。島民多数が死傷。 |
| この年、りゅうこつ座η星が擬似的超新星爆発を起こしたときの光が地球で観測される。この時出たガスは現在人形星雲となっている。 | |
| 1842年 | |
| 5月 5日 | ハンブルク大火。8日まで延焼が続き、市街地の4分の1が焼失。教会3つを含む1700棟が失われた。死者は51名。一方で都市が近代化するきっかけともなった。 |
| 11月11日 | チェコのプルゼニ(ピルゼン)で、はじめてピルスナー・ウルケルが一般に披露される。ドイツ人醸造家ヨーゼフ・グロルが生み出し、今や世界中のビールの主流となっているピルスナービールの元祖。 |
| アミスタッド号事件を起こしたアフリカ人が、支援者の資金でアフリカへ帰郷する。 | |
| 1843年 | |
| 5月16日(天保14年4月17日) | 江戸の二大花火師である玉屋から失火。周囲の半町を焼失する。玉屋は闕所(財産没収)、主人の市兵衛は江戸お構い(江戸追放)となり、一代で家名断絶となる。 |
| 1844年 | |
| 8月13日(弘化元年6月30日) | 江戸伝馬町牢屋敷で火災が起き、蛮社の獄で永牢処分を受けて入獄していた高野長英が脱獄。その後、戻らず逃亡を続ける(火災による出獄は期日までに戻れば罪一等を減じられるが戻らなければ死罪となる)。なおこの火災も長英が放火させたという説がある。 |
| 1845年 | |
| 2月28日 | 米国議会が、米国がテキサス共和国を併合する法案を可決。 |
| 3月 9日(弘化2年 1月24日) | 青山火事。江戸青山から出火し、北西風の風によって拡大。武家屋敷400、寺社187など126町が焼失。死者800人~900人。新門辰五郎率いる町火消の浅草十番組「を組」と久留米藩主有馬頼永率いる大名火消の火消し同士が乱闘になって死傷者を出す。有馬側に非があったとされるが、新門辰五郎が出頭したため、江戸所払いとなった(が守らなかったため人足寄場送りになっている。後赦免され火消しや香具師などの大元締めとなった)。 |
| 3月29日(弘化2年 2月22日) | 水野忠邦政権下で権力を振るった鳥居耀蔵が有罪の判決を受け、家禄を没収の上、人吉藩への「預け(幽閉)」となる。のち秋田藩、丸亀藩へ移された。蘭学者や洋式軍学者を処罰し、矢部定謙を失脚させ、密偵政治で人々を恐れさせた。反水野派に寝返ったことが失脚の理由。医術の心得があり、丸亀藩幽閉時代には領民の治療などをして慕われた。明治元年に赦免されたあとも、洋化政策を厳しく批判している。 |
| 4月18日(弘化2年 3月12日) | アメリカの捕鯨船マンハッタン号が、小笠原諸島で救助した日本人漂流船員22人を乗せて浦賀に到着。4日間滞在した後出港。 |
| 12月29日 | アメリカ合衆国が、テキサス共和国を併合。テキサス州が成立する。米墨戦争のきっかけとなる。テキサス政府が抱えていた借金の肩代わりに、現在のコロラド州、カンザス州、オクラホマ州、ニューメキシコ州、ワイオミング州にまたがる広大な地域がアメリカ政府へ割譲される。 |
| 1846年 | |
| 4月25日 | 米墨戦争が始まる。 |
| 6月15日 | イギリスとアメリカの間で、英領カナダとアメリカの国境問題を解決するオレゴン条約を締結。ただし大陸とバンクーバー島の間の諸島は曖昧のままに。 |
| 8月10日 | イギリス人の鉱物学研究者だったジェームズ・スミソンが、「知識の向上と普及」にとアメリカ政府に寄付した遺産で、スミソニアン博物館が設立される。 |
| 9月23日 | ベルリン天文台のヨハン・ガレとハインリッヒ・ダレストが、ユルバン・ルヴェリエの天王星の軌道の変化をもとに計算した結果に基づいて観測し、海王星を発見。太陽系の惑星で唯一、計算の結果に基づいた観測で発見された惑星。 |
| 10月10日 | イギリスの天文学者ウィリアム・ラッセルが、発見されたばかりの海王星の衛星トリトンを発見。直径2710kmと、海王星の衛星系では極端に巨大で、海王星の自転とは逆行する公転軌道を持つ特異な天体。 |
| ネパール王国の宰相ジャング・バハドゥールのクーデターにより、シャー王家は傀儡と化し、以後はラナ家が支配。 | |
| インド北方のカシミール地方をめぐるチベット仏教系ラダック王国とイスラム教系カシミール諸侯との争いにイギリスが介入し、ジャンムー・カシミール藩王国が成立する。 | |
| 1847年 | |
| 3月 | 京都に公家の教育機関が設立される。平安時代の大学寮を模したもので、のちの学習院大学の原点。 |
| 5月 8日(弘化4年 3月24日) | 善光寺地震。松代藩、松本藩、飯山藩の領地で死者8600人以上。家屋全壊21000軒、焼失家屋3400軒に上る。 |
| 7月26日 | アメリカ合衆国の解放奴隷によって建国したアフリカ西岸の国リベリアが憲法を制定しアメリカから独立。 |
| 11月 4日 | スイスで分離同盟戦争が勃発。「スイス盟約者団(誓約者同盟)」を構成するカントン(自治州)のうちカトリック系保守派の「分離同盟」と、それ以外の自由主義的なカントンとが争った内戦。 |
| 11月29日 | スイスの分離同盟戦争が終結。「分離同盟」は敗北。憲法制定へと動き出す。翌年ヨーロッパで吹き荒れる1848年革命の端緒とも言われる。 |
| 12月(弘化4年11月) | 南部藩三閉伊一揆勃発。南部藩は先の南方一揆を受け、今度は三閉伊と呼ばれた海岸地帯に重税と御用金を課したため、これに苦しんだ庶民を救済するため、浜岩泉村牛切の牛方弥五兵衛が扇動して一揆を起こす。1万2千人余りが参加する大規模なものとなり、遠野南部家と交渉。その結果を受けて一旦は解散するが、藩を信用できなかった牛方弥五兵衛は再び一揆を起こす。 |
| 1848年 | |
| 2月 2日 | アメリカとメキシコでグアダルーペ・イダルゴ条約締結。米墨戦争が終結し、アメリカは1500万ドルと債務帳消しを条件に、カリフォルニア、ネバダ、ユタと、アリゾナ、ニューメキシコ、ワイオミング、コロラドを併合し、さきに併合したテキサスの権利をメキシコに認めさせる。 |
| 2月21日 | 『共産党宣言』が出版される。社会主義秘密結社の正義者同盟から国際的運動のために依頼されて、マルクスが体系的にまとめた宣言文。 |
| 6月27日(嘉永元年 5月27日) | 日本に強い関心を持っていたカナダ人ラナルド・マクドナルドが焼尻島に上陸。 |
| 7月13日(嘉永元年 6月13日) | 三閉伊一揆を受けて、南部藩は藩主南部利済が隠居して南部利義に地位を譲り、家老の横澤兵庫が罷免される。一方で首謀者を調査し牛方弥五兵衛を殺害。 |
| 9月12日 | スイス連邦憲法が成立。前年に起きたカントン(自治州)同士の内戦の結果を受けて、盟約者団を発展させたカントンによる連合政府が成立。スイス連邦となる。 |
| 9月16日 | ウィリアム・クランチ・ボンドと息子のジョージ・フィリップス・ボンドが土星の衛星ヒペリオンを発見する。360km×205kmの非球形で、表面が空孔だらけでスポンジのような異様な姿をした衛星。 |
| 1849年 | |
| 1月13日(嘉永元年12月19日) | 薩摩藩家老調所広郷が江戸芝の薩摩藩邸で急死。薩摩藩の琉球を介した密貿易の件で老中阿部正弘の聴取を受けた直後であったため、藩主斉興をかばうため服毒自殺したものと言われる。 |
| 4月18日(嘉永2年 3月26日) | 米国軍艦プレブル号長崎に来航。幕府へ漂流民の受け取りを求め、代わりに日本に滞在していたラナルド・マクドナルドを乗せる。 |
| 4月26日(嘉永2年 4月 4日) | 米国軍艦プレブル号が、日本に滞在していたラナルド・マクドナルドを乗せて出港する。 |
| 11月10日(嘉永2年 9月26日) | 南部藩主南部利義が、父親で先の藩主だった南部利済の圧力で隠居に追い込まれ、実弟の南部利綱が後を継ぐ。南部利済が院政を敷き、罷免していた横澤兵庫を戻し、田鎖高行、石原汀、川島杢左衛門らを登用してふたたび重税などの悪政が敷かれる。反利済派に対する弾圧も行われた。 |
| 1850年 | |
| 1月15日(嘉永2年12月 3日) | 薩摩藩でお由羅騒動が勃発。この日、町奉行兼物頭・近藤隆左衛門、同役・山田清安、船奉行・高崎五郎右衛門の3名が突如解任され切腹に追い込まれる。島津久光とその母お由羅、久光派の重臣らに対する暗殺謀議の嫌疑により。以後、島津家世子斉彬派と見られた家臣50名以上が相次いで処罰される。 |
| 3月19日 | ヘンリー・ウェルズ、ウィリアム・ファーゴ、ジョン・バターフィールドの3人が、荷馬車宅配業としてアメリカン・エキスプレスを設立。現在はクレジットカードやトラベラーズ・チェックが主な業務。 |
| 6月13日(嘉永3年 5月 4日) | 陸奥国気仙郡(現在の陸前高田市気仙町丑沢)にある長圓寺前の畑に隕石が落下。通称気仙隕石。陸前高田市気仙町で行われている二日市虎舞は、この隕石がきっかけで始まった厄除けの芸能行事。 |
| 8月28日 | ワーグナーのオペラ『ローエングリン』がヴァイマル宮廷劇場で初演。 |
| 12月 3日(嘉永3年10月30日) | 高野長英が、潜伏先の江戸青山百人町で捕り方に襲撃され殺害される。 |
| 1851年 | |
| 1月11日 | 洪秀全の組織した拝上帝会が、拠点の広西省桂平県金田村で太平天国を称して挙兵する。 |
| 2月 3日(嘉永4年 1月 3日) | 出漁中に遭難し漂流後に米国の捕鯨船に拾われてアメリカで暮らしていたジョン万次郎が帰国。 |
| 3月 4日(嘉永4年 2月 2日) | 薩摩藩主島津斉興が将軍徳川家慶から茶器を下され藩主の座を降りる(茶器の下賜は引退勧告)。斉興が嫡子斉彬への家督相続を拒絶し、お由羅騒動にまで発展したことを受け、島津家出身の筑前藩主黒田長溥と八戸藩主南部信順兄弟が、老中阿部正弘に働きかけた結果と言われる。島津斉彬が薩摩藩主の座に付く。 |
| 5月 1日 | 世界最初の万国博覧会であるロンドン万国博覧会開催。メイン会場の建物の名前から「水晶宮博覧会」とも呼ばれる。10月15日まで。 |
| 8月22日 | 万国博覧会に合わせて、ロイヤル・ヨット・スコードロン主催によるワイト島一周ヨットレースが開催される。出場したニューヨークヨットクラブのスクーナー「アメリカ号」が優勝して優勝カップ「RYS£100カップ」を授与されたため、大会名が優勝艇の名をとって「アメリカズカップ」と呼ばれるようになった。 |
| 11月20日 | のちのイタリア王妃で、ピザ・マルゲリータの名前のもととなった、マルゲリータ・マリーア・テレーザ・ジョヴァンナ・ディ・サヴォイア=ジェノヴァが生誕する。 |
| 1852年 | |
| 3月18日 | アメリカンエキスプレスを創設したヘンリー・ウェルズとウィリアム・ファーゴが、金融会社ウェルズ・ファーゴを設立。 |
| 8月 6日(嘉永5年 6月21日) | 宮津藩藩主松平宗秀(本庄宗秀)が、幕府の許可を得られなかったため、密かに富士山頂まで登る。近世大名で富士登山を行った記録がある唯一の人物。 |
| 9月24日 | フランスの技術者バティスト・ジャック・アンリ・ジファールが、蒸気エンジンで動くプロペラの付いた飛行船の初飛行に成功。人類史で判明している初の動力飛行。 |
| 11月24日 | ペリーが、蒸気船ミシシッピ号に乗ってノーフォーク港を出港。極東へ向かう。 |
| 11月27日 | 数学者で世界最初のプログラマと呼ばれることもある女性エイダ・ラブレスが死去。 |
| 12月 2日 | フランス大統領ルイ・ナポレオンが、国民投票の結果を受けて皇帝に即位。ナポレオン3世となる。フランス第二帝政。 |
| 1853年 | |
| 4月(嘉永6年 3月) | 悪政が続く南部藩で三閉伊一揆が再発。 |
| 5月23日(嘉永6年 4月16日) | ペリー率いるアメリカ艦隊が、琉球王国に来航。開国を求めたあと、小笠原へ向かう。 |
| 6月23日(嘉永6年 5月17日) | 小笠原を探検していたペリー率いるアメリカ艦隊が、再度琉球に来航。 |
| 7月 2日(嘉永6年 5月26日) | ペリー率いるアメリカ艦隊が、日本に向けて琉球を出港。 |
| 7月 8日(嘉永6年 6月 3日) | 黒船来航。ペリー率いるアメリカの蒸気船ミシシッピ号、蒸気船サスケハナ号、帆船プリマス号とサラトガ号の4隻が浦賀に現われる。幕府はオランダからの情報で来航を知っており、庶民にも通知していたため、大きな混乱は起こらず。多くの人が海岸まで見学に行ったと言われる。 |
| 7月 8日(嘉永6年 6月 3日) | 三閉伊一揆の集団が田野畑村より南下。海岸地帯を移動しみるみる参加者が増え、1万6千人に達する大規模な一揆に発展。一揆勢は仙台藩領へ入り、三閉伊地方の天領もしくは仙台藩領への移し替え、税の軽減、失脚した南部利義の復位などを仙台藩に要求。南部藩は一揆勢の引き渡しを求めるも、先の一揆の南部藩の対応から仙台藩は応じず。この件は幕府の知るところとなり、南部藩は一揆側の要求のうち南部利義の復帰以外を対応し、一揆関係者の処罰はせず、家老の南部土佐が失脚し、悪政を敷いた横澤兵庫の蟄居、田鎖高行、石原汀、川島杢左衛門らの罷免と財産没収・流罪を決定。また幕府は悪政の中心人物である元藩主南部利済に江戸での蟄居を命じ、利義も押し込めとなった。 |
| 7月17日(嘉永6年 6月12日) | 幕府に親書を渡したペリー一行が、日本を離れる。 |
| 7月27日(嘉永6年 6月22日) | 12代将軍徳川家慶が死去。61歳。 |
| 8月 5日(嘉永6年 7月 1日) | ペリー来航を受けて、老中阿部正弘が大名・幕臣・庶民らに広く意見を求める。 |
| イングランドの貴族政治家で、科学者でもあったジョージ・ケイリーが、単葉グライダーの飛行に成功する。操縦者については、孫のジョージ・ジョン説、ケイリー家の執事説、使用人説など諸説ある。ケイリーは固定翼機の概念を考えた人物。それまで研究されていた飛行装置はオーニソプター(羽ばたき式飛行機)が主流だった。 | |
| 1854年 | |
| 3月28日 | オスマン帝国の権益をめぐって、イギリスとフランスが、ロシア帝国に宣戦布告。クリミア戦争が始まる。 |
| 7月 9日(嘉永7年 6月15日) | 伊賀上野地震(安政伊賀地震)。6月13日に最初の小規模の地震があり、この日伊賀と伊勢で大きな揺れを観測。伊賀上野城と城下が大きな被害を受け、死者995人のうち625人は伊賀上野一帯で死亡した。 |
| 12月23日(嘉永7年11月 4日) | 安政東海地震。マグニチュード8.4。激しい揺れと大津波により、東海道一帯で甚大な被害を出す。駿府の萩原四郎兵衛の記録によれば、地震のあと、富士山から煙と火が見えたという。小規模の噴火か、地震による大規模な土砂崩れが発生した可能性もある。 |
| 12月24日(嘉永7年11月 5日) | 安政南海地震。マグニチュード8.4。安政東海地震のわずか32時間後に起こる。大坂湾岸や土佐などで甚大な被害を出す。なお安政東海・安政南海地震は、正確には嘉永7年に発生しており、この地震災害を受けて安政に災異改元が行われた。 |
| 12月26日(嘉永7年11月 7日) | 豊予海峡地震。マグニチュード7.4。安政南海地震のわずか40時間後に起こる。豊後や伊予で大きな被害が出たと思われるが、南海地震との記録上の区別ができないため、詳細は不明。 |
| 1855年 | |
| 1月15日(嘉永7年11月27日) | 内裏炎上、大地震、黒船来航など異変が相次いだことから、安政に改元。なお、この日より前の一連の大地震にも安政の名が付いているが、正確には嘉永年間に起きたもの。伊賀上野地震から飛越地震までの各地震を安政大地震と総称する場合もある。 |
| 1月28日 | パナマ地峡鉄道が開業。大西洋岸の港町コロンと太平洋岸の首都パナマシティを結ぶ。パナマシティからカリフォルニアへ船が出ていたため、アメリカ国内の横断鉄道とパナマ運河ができるまでの間、北米太平洋岸を目指す人々の主要な交通ルートになった。 |
| 3月18日(安政2年 2月 1日) | 飛騨地震。白川郷一帯で山崩れが多発。 |
| 4月 8日(安政2年 2月22日) | 開国に伴い、幕府はふたたび蝦夷地直轄を図り、松前藩から渡島半島の一部を除く蝦夷地のほとんどを召し上げる。その代わりに松前藩には、前回転封時と同じ陸奥国梁川と、他に出羽国に計3万石、預かり地として1万4千石、手当金年1万8千両が与えられる。しかし藩の財政は悪化。のち一部戻るも維新まで続いた。 |
| 11月11日(安政2年10月 2日) | 安政江戸地震。江戸直下を震源とするマグニチュード6.9の大地震で、江戸を中心に死者4000人~7000人を出したと言われる。 |
| この年、黄河が大氾濫を起こし、河道が北側へと大きく変遷して済水と合流。1128年の人為的洪水以来700年ぶりに渤海へと流れ込むようになる。 | |
| 1856年 | |
| 8月23日(安政3年7月23日) | 安政八戸沖地震。東北北部から北海道で強い揺れと大津波が襲来。 |
| 10月 8日 | 清の官憲がアロー号を臨検し、海賊容疑で乗員3人を逮捕。フランスとイギリスが反発。 |
| 1857年 | |
| 1月13日(安政3年12月18日) | 徳川家定と島津篤子が婚儀をあげる。 |
| 5月10日 | インド北部のメーラトで、イギリス東インド会社に雇われていたインド兵(シパーヒー、セポイ)が反乱を起こす。直接的にはエンフィールド銃の薬包の防湿剤として牛や豚の脂が使われていたため、牛を神聖視するヒンドゥー教徒や、豚を忌むイスラム教徒の反発を買ったとされるが、イギリス東インド会社やインド総督の統治の仕方に反発したのが大きな理由。やがて反乱にはイギリスに取り潰された旧藩王諸侯の一族、東インド会社に土地を奪われた地主、そして都市や農村の民衆も加わり各地に広がる。一方、イギリスは反乱に否定的な藩王国や周辺諸国から兵を集めて鎮圧に乗り出す。 |
| 8月(安政4年) | 土佐藩士山本琢磨が酔った勢いで拾った金時計を売り払ったことが問題になり、親戚である坂本龍馬、武市半平太の助けで逃亡。のち箱館で沢辺家の養子となり沢辺琢磨と改名。 |
| 9月17日 | 帝政ロシアに、コンスタンチン・エドゥアルドヴィチ・ツィオルコフスキーが誕生。のちに帝政ロシアおよびソビエト連邦の科学者、ロケット研究者となった人物。現代ロケット工学の草分け的存在。 |
| 12月 7日(安政4年10月21日) | アメリカの駐日本総領事タウンゼント・ハリスが江戸城に登城し、アメリカの国書を提出。 |
| 12月29日 | アロー号事件をめぐってフランスとイギリスが侵攻。広州を占領する。アロー戦争。アメリカ、ロシアも乗り出す。 |
| (安政4年) | この年、箱館奉行村垣範正の訴えを受け、桑田立斎らが蝦夷地でアイヌに対し大規模な種痘を実施。当時蝦夷地では天然痘が広がっており、多くの犠牲者が出ていた。幕府による公式の種痘の実施はこれが初めてで、国内でもまださほど行われていない。 |
| この年、フランス人エドワール=レオン・スコット・ド・マルタンヴィルが、音の振幅を紙の上に書き写す装置フォノトグラフを発明。音を目に見える形に記録するためのもので、再生はできなかったが、録音機としては世界最古となる。 | |
| 1858年 | |
| 1月14日 | オルシーニ事件。イタリア統一運動を支持していたフランス皇帝ナポレオン3世が態度を変えたと見て失望した運動のメンバーオルシーニ伯爵が、パリのオペラ座に来たナポレオン3世夫妻を爆弾で暗殺しようとした事件。ナポレオン3世夫妻は軽傷で済んだが、付近にいた18人が死亡、150人が負傷した。ただオルシーニは、裁判でナポレオン3世の統一運動への支持を求め、ナポレオン3世も、イタリアへの影響力を強めるため、統一運動の支持を続けることになった。 |
| 1月15日(安政4年12月 1日) | 南部藩の大島高任が、日本で初めて高炉による連続した製鉄に成功する。鉄の記念日。 |
| 1月25日(安政4年12月11日) | 日米間で通商条約交渉が始まる。 |
| 3月29日 | インド大反乱の形式上の最高指導者だったムガル帝国皇帝バハードゥル・シャー2世がイギリスによって退位させられ、ビルマへ追放される。ティムール朝系ムガル帝国は滅亡。反乱は継続するも、勢力は弱体化。 |
| 4月 9日(安政5年 2月26日) | 飛越地震(安政飛越地震)。飛騨と越中で大きな揺れを観測し死者426人。立山連峰の鳶山が崩壊し、その土砂が常願寺川をせき止める。山体崩壊の土砂量は4億立方メートルを超えると見られ、有史以降に記録のある日本国内の山体崩壊としては最大のもの。 |
| 4月23日(安政5年 3月10日) | 飛越地震の余震で常願寺川が決壊。大量の土砂が下流域に流れる。 |
| 4月25日(安政5年 3月12日) | 廷臣八十八卿列参事件。関白九条尚忠が朝廷に日米修好通商条約の議案を提出。これに対し反対する公家88人と、地下官人97人が条約撤回を求める。孝明天皇が幕府に対し反対を示し、これが安政の大獄の一因になった。 |
| 5月 3日(安政5年 3月20日) | 孝明天皇、通商条約締結の勅許を拒否。 |
| 6月 4日(安政5年 4月23日) | 彦根藩主井伊直弼、大老に就任。 |
| 6月 8日(安政5年 4月26日) | 大町地震。飛越地震の影響によるものとみられ、常願寺川が再び決壊。一度目の決壊後の修復工事中に発生し、多数の死者を出す。 |
| 6月13日 | アロー戦争をめぐって、清とロシアが天津条約を締結。 |
| 6月18日 | 清とアメリカが天津条約を締結。 |
| 6月18日 | インド大反乱の指導者の一人である元ジャーンシー藩王国王妃ラクシュミー・バーイーが戦死。優れた戦術指揮能力、個人的な戦闘力、それに美貌を兼ね備えていたとして、敵対したイギリス側からも評価され、インドでは歴史的英雄の一人になっている。 |
| 6月26日 | 清とイギリスが天津条約を締結。 |
| 6月27日 | 清とフランスが天津条約を締結。 |
| 7月29日(安政5年 6月19日) | 日米修好通商条約が神奈川沖の米艦ポーハタン号で締結される。大老井伊直弼は条約調印に消極的だったが、老中の堀田正睦、松平忠固ら幕閣の大勢は調印積極派で、交渉担当の井上清直・岩瀬忠震らが井伊直弼の意向を無視して調印に踏み切ったと言われる。 |
| 8月 2日(安政5年 6月23日) | 老中の堀田正睦、松平忠固が罷免される。安政の大獄の始まり。一般に開国を推進し将軍継嗣問題で南紀派だった井伊直弼が、攘夷派で将軍継嗣に一橋慶喜を推す派を弾圧したとされるが、直弼は開国には消極的で、幕政に絡む権力闘争が発端でもあり、積極開国派の幕閣が真っ先に処分されている。 |
| 8月 2日 | イギリスで「1858年インド政府法」が成立。インド大反乱の原因となったイギリス東インド会社を解散し、インドをイギリス皇帝による直接統治に置き換えるもの。イギリス領インド帝国の事実上の成立。 |
| 8月 3日 | アフリカ最大で、世界第3位の湖であるヴィクトリア湖がイギリスの探険家ジョン・ハニング・スピークによって「発見」される。白ナイル川の源流と判明。 |
| 8月13日(安政5年 7月 5日) | 水戸前藩主徳川家斉、越前藩主松平慶永、尾張藩主徳川慶恕、一橋慶喜らが、勅許無しの条約調印に関して井伊直弼を詰問する不時登城を咎められて謹慎処分となる。 |
| 8月16日(安政5年 7月 8日) | 薩摩藩主島津斉彬が軍事調練中に倒れる。 |
| 8月17日(安政5年 7月 9日) | 日蘭修好通商条約が締結される。 |
| 8月19日(安政5年 7月11日) | 日露修好通商条約が締結される。 |
| 8月24日(安政5年 7月16日) | 島津斉彬死去。コレラによる病死説が有力だが、当時から暗殺説があった。 |
| 8月26日(安政5年 7月18日) | 日英修好通商条約が締結される。 |
| 10月 9日(安政5年 9月 3日) | 日仏修好通商条約が締結される。 |
| 10月27日 | アメリカ大統領セオドア・ルーズベルトの誕生日「テディベアズ・デー」。 |
| 12月20日(安政5年11月16日) | 西郷隆盛と月照が入水自殺を図る。安政の大獄で幕府に追われた月照を薩摩藩が庇護せず東目送りと決めたため。東目送りとは薩摩藩領の東境(日向国)へ追放することで、そこで斬り捨てたり幕府に引きわすことから事実上の処刑を意味する。西郷は平野国臣らに助け出されるが月照は死亡。 |
| ニュージーランドのマオリ族が、イギリスの土地収奪に反発し、対抗するため、ワイカト族の首長ポタタウ・テ・フェロフェロをマオリ王に選出。 | |
| 1859年 | |
| 1月13日(安政5年12月28日) | 薩摩藩主に島津忠教(久光)の子で、先代斉彬の甥に当たる忠徳(後の島津忠義)が就任。後見人として島津久光がつくが、実質は祖父の島津斉興が復権した。 |
| 2月 6日(安政6年 1月 4日) | 薩摩藩は、幕府に追われている西郷隆盛を隠すため奄美送りとし、この日山川港から出帆する。 |
| 2月14日(安政6年 1月12日) | 西郷隆盛、奄美大島へ到着。奄美の在地領主である龍家の庇護を受ける。この頃、奄美に流罪になっていた若き日の重野安繹(明治期の歴史学の第一人者)と知り合う。 |
| 6月15日 | アメリカと英領カナダの間で、ブタ戦争(サンフアン諸島国境紛争)が起こる。帰属が曖昧だったサンフアン島で一頭のブタが射殺されたことがきっかけで起こった国境紛争。軍隊同士がにらみ合うも、人間の犠牲者はなし。 |
| 6月17日 | フランスとイギリスの艦隊が、天津条約の批准を求めて天津まで北上。清側と軍事衝突に発展。 |
| 7月 1日(安政6年 6月 2日) | 安政五ヶ国条約により神奈川が開港する。実際には神奈川ではなく横浜となったため、各国から抗議を受けるが、これが現在の横浜港の始まり。 |
| 9月 1日 | 大規模な太陽フレアが発生。翌日にかけて大量の電磁波、放射線、放出物質が地球に到達、地球の磁気圏、電離層に衝突し、比較的低緯度地方でも激しいオーロラが観測され、昼間のように明るくなったという。デリンジャー現象や磁気嵐も観測され、送電線や電信装置の故障も相次いだ。イギリスの天文学者リチャード・キャリントンの観測で知られることから、キャリントンのスーパーフレアとも呼ばれる。 |
| 9月17日 | ジョシュア・エイブラハム・ノートンが「アメリカ皇帝」への就任を宣言。 |
| 9月19日(安政6年 8月23日) | イギリスの貿易商トーマス・ブレーク・グラバーが長崎・大浦に、「ジャーディン・マセソン商会」の長崎代理店としてグラバー商会を設立。 |
| 10月 7日(安政6年 9月12日) | 島津斉興が死去。薩摩藩の実権は藩主忠義の父親で、斉興の子である島津久光が握る。 |
| 10月 7日 | 北京を占領したフランス軍が、離宮円明園へに入り略奪の限りを尽くす。 |
| 10月 9日(安政6年 9月14日) | 上田藩主で元老中の松平忠固が急死。暗殺説もある。開国貿易を積極的に推進した人物。 |
| 10月18日 | 北京を占領したイギリス軍が、捕虜殺害の報復として離宮円明園に放火。廃墟と化す。 |
| 11月11日 | インド大反乱がほぼ終息する。形式上反乱軍の最高指導者だったムガル帝国皇帝バハードゥル・シャー2世は、ビルマへ追放され、ムガル帝国は滅亡。一方で反乱の原因になったイギリス東インド会社も解散となり、イギリスによる直接統治が始まる。 |
| 11月21日(安政6年10月27日) | 吉田松陰が、安政の大獄で、死刑に処せられる。 |
| 11月24日 | ダーウィンがイギリスで『種の起源』を出版。 |
| 1860年 | |
| 2月 9日(安政7年 1月18日) | ポーハタン号と咸臨丸によって万延元年遣米使節団が出発。 |
| 3月24日(安政7年 3月 3日) | 大老井伊直弼が江戸城桜田門外で水戸藩浪士らに襲われ殺害される。桜田門外の変。 |
| 4月 9日 | フォノトグラフで紙に記録された音声データのうち再生に成功した最も古い録音日。2008年にコンピュータの解析で、フォノトグラフの発明者マルタンヴィル自身がフランス民謡『月の光に』の2番を歌っていることが判明した。現在判明している人類最古の音声データ。 |
| 6月30日 | オックスフォード進化論論争が行われる。ダーウィンの『種の起源』について、宗教関係者、科学者、哲学者らが論争したとされるもの。特にサミュエル・ウィルバーフォース大司教と、生物学者トマス・ヘンリー・ハクスリーとの皮肉を交えたやり取りが有名。 |
| 9月11日(万延元年 7月26日) | 英国公使オールコックが、測量を名目に富士山山頂まで登山。 |
| 9月20日 | 八里橋の戦い。アロー戦争に伴う英仏軍と清朝軍の戦い。英仏軍が勝利する。 |
| 9月29日(万延元年 8月15日) | 水戸の徳川斉昭が急死。強硬な尊王攘夷派で、幕末の尊王攘夷運動に大きな影響をもたらした人物。一方で西洋の技術を積極的に取り入れる面もあった。 |
| 10月24日 | 清朝とイギリスが北京条約を締結。 |
| 10月25日 | 清朝とフランスが北京条約を締結。 |
| 11月 9日(万延元年 9月27日) | 万延元年遣米使節団が地球を一周して帰国。 |
| 11月14日 | 清朝とロシアが北京条約を締結。 |
| 11月27日(万延元年10月15日) | 江戸周辺での禁猟を破り、マイケル・モースが狩猟を行ったため幕府の役人とトラブルになり捕縛される。役人ひとりが負傷。モースは釈放後、領事裁判でオールコック公使により追放処分となる。 |
| 1861年 | |
| 3月 4日 | ロシアの軍艦が対馬に現れる。その後、水兵が上陸し略奪を働く。 |
| 4月13日(文久元年 3月 4日) | 土佐国井口村刃傷事件。土佐藩郷士中平忠次郎が、通行中に肩がぶつかった上士山田広衛と口論の末に殺害され、同行者宇賀喜久馬から事態を聞いた忠次郎の兄池田寅之進が山田広衛と同行者の益永繁斎を殺害した事件。上士と郷士が一触即発の事態になるが、池田寅之進と宇賀喜久馬が自害したことで終息した。なお宇賀喜久馬を介錯した兄の寺田利正は物理学者寺田寅彦の父親。 |
| 3月17日 | イタリア王国が成立。首都をトリノに置く。 |
| 7月 5日(文久元年 5月28日) | 第一次東禅寺事件。オールコック英公使が長崎から江戸まで陸上を移動したことに反発した攘夷派志士がイギリス公使館の東禅寺を襲撃。 |
| 8月(文久元年 8月) | 土佐勤王党が結成される。一藩勤王を目指して武市瑞山がまとめた組織。 |
| 11月 8日 | トレント号事件。アメリカ南北戦争のさなか、北軍のアメリカ合衆国海軍USSサンジャシント号が、中立国イギリスの郵便船RMSトレント号を拿捕して乗船していた南軍アメリカ連合国の外交官メイソンとスライデルの2人を連れ去った事件。2人はアメリカ連合国をヨーロッパ諸国に承認させるべく英仏へ向かおうとしていた。イギリス政府と国民は怒り、アメリカ合衆国に対して軍事動員を図る。 |
| 11月 | 辛酉政変。清の西太后が、東太后や恭親王奕訢らとともにクーデターを起こし実権を握る。粛順、載垣、端華らは失脚し粛順は処刑、載垣と端華は自殺に追い込まれた。 |
| 12月29日 | リンカーン政権は、トレント号事件で拘禁したアメリカ連合国の外交官メイソンとスライデルの2人の釈放を決定。 |
| この年、イギリスの科学者マイケル・ファラデーの「ロウソクの科学」が出版される。ファラデーが行ったクリスマス・レクチャーの内容を編集したもので、現在も出版され続けている科学啓蒙書。複数のノーベル賞受賞者が科学に目覚めたきっかけとして取り上げることでも知られる。 | |
| この年、イギリス出身の地質学者エドアルド・ジュースが、植物の化石が共通するインド、アフリカ、南アメリカが、かつて一つのゴンドワナ大陸だったという説を発表。大陸が沈降する地向斜説を元にしており、地向斜説自体はプレートテクトニクスの登場で廃れたが、ゴンドワナ大陸は実在したと考えられている。ジュースはのちにテチス海が存在したこと、そして生物圏という考え方も提唱した。 | |
| 1862年 | |
| 1月14日 | トレント号事件で拘禁され、その後釈放されたアメリカ連合国の外交官メイソンとスライデルがイギリスへ向かう。イギリスはこの問題は解決したとして、軍事動員を取りやめ、最終的にアメリカ連合国の要求にも応じなかった。 |
| 3月 7日(文久2年 2月 7日) | 人吉藩寅助火事。城下鍛冶屋町の鉄砲鍛冶恒松寅助の家から出火し、人吉城と城下町の大半が焼失する大火となる。奇跡的に死者はなかったが、復興に1万5千両もかかった(大坂の豪商と薩摩藩から借金)。出火元の恒松寅助は軽い過料で済んでいる。 |
| 3月11日(文久2年 2月11日) | 皇女和宮と徳川家茂の婚儀が執り行われる。 |
| 3月12日(文久2年 2月12日) | 西郷隆盛、島津久光の上洛に伴う京都斡旋の任務役のため、奄美から召喚される。 |
| 3月15日(文久2年 2月15日) | 西郷隆盛、島津久光と対面。久光の上洛については、久光に向かって「おそれながら地ゴロ(田舎者)」には無理として、その上洛政策の不可を主張し不興を買ったと言われる。なおこの日、大島三右衛門と名を改めている。 |
| 4月20日(文久2年 3月22日) | 西郷隆盛、下関の豪商白石正一郎邸で平野国臣から脱藩した過激浪士らが挙兵の計画を進めていると聞き、上京するため出帆。 |
| 4月22日(文久2年 3月24日) | 坂本龍馬が土佐藩を脱藩。武市瑞山の土佐勤王党に加盟していたが、藩を挙げての勤王方針で武市と意見が対立した上、草莽崛起を唱えた久坂玄瑞と面会したこと、島津久光が藩兵を率いて上洛するという情報から、先に脱藩していた吉村寅太郎らの誘いに乗ったとされる。脱藩していた沢村惣之丞が迎えに戻り、那須俊平・那須信吾の協力で、伊予大洲藩領へと越境した。脱藩には姉の乙女が刀を渡すなど協力したという(創作では姉の栄が協力したとなってることが多いが、実際にはこの時点ではすでに故人とみられる)。 |
| 5月 4日(文久2年 4月 6日) | 島津久光、西郷隆盛が待機の命に背き、過激浪士らと関わっているとして捕縛するよう命じる。 |
| 5月 6日(文久2年 4月 8日) | 土佐藩参政の吉田東洋が、武市瑞山の指示を受けた那須信吾・安岡嘉助・大石団蔵の3人に暗殺される。土佐藩による勤王政策案を吉田が相手にしなかったことに反発した武市らと、吉田の藩政改革にともなって失脚した藩の保守有力者が手を組んだクーデター事件。暗殺した3人はそのまま脱藩。小説などでは吉田東洋は郷士に対する冷淡な態度で憎まれていたとされるが、上士の吉田家は郷士と同じ長宗我部旧臣でもある。 |
| 5月 8日(文久2年 4月10日) | 薩摩藩、西郷隆盛や村田新八らを薩摩へ護送。 |
| 5月21日(文久2年 4月23日) | 伏見寺田屋事件。朝廷から過激志士の対処を命じられた島津久光が、京都所司代襲撃を計画し寺田屋に集結していた藩士を説得するため奈良原喜八郎、大山格之助ら9人を使者として派遣するが、志士側の有馬新七、田中謙助らはこれに応じず、戦闘に発展。奈良原と真木和泉らが残りの数十人を説得し終結。使者9人のうち1人が死亡、5人が重軽傷を負い、志士側は6人が死亡、2人が重傷を負い後に切腹。 |
| 6月 8日 | 豊臣時代に処刑された日本二十六聖人が、ローマ教皇ピウス9世によって列聖される。 |
| 7月 7日(文久2年 6月11日) | 西郷隆盛、徳之島への流罪のため、山川を出帆。 |
| 7月28日(文久2年 7月 2日) | 西郷隆盛、徳之島へ到着。同日、西郷が大島に残した妻愛加那が長女を出産。 |
| 8月15日(文久2年 7月20日) | 島田左近が尊王攘夷派の薩摩藩士田中新兵衛らによって暗殺される。九条家青侍で高利貸しでもあった。安政の大獄で暗躍したことが恨みを買ったため。 |
| 8月18日 | ダコタ・スー族の反乱が起こる。不毛な居留地へ追い込まれ、さらに条約による補償すら支払わなかったアメリカ政府に対し、スー族の戦士らがミネソタ州で起こした。インディアン管理局の事務所を襲撃。鎮圧に出動した州民兵は敗走。 |
| 8月21日 | ダコタ・スー族が、リッジリー砦を攻撃。 |
| 9月 2日 | バーチクーリーの戦い。ダコタ・スー族とミネソタ州民兵隊が戦い、州民兵隊が大敗。この後、リンカーン大統領は、ダコタ・スー族の武力鎮圧を命じる。 |
| 9月14日(文久2年 8月21日) | 生麦事件。江戸から京へ戻る途中の島津久光の行列に入り込んだ騎馬の英国人4人に藩士が斬りかかり、1人が死亡、2人が重症を負う。 |
| 9月19日(文久2年 8月26日) | 徳之島の西郷隆盛のもとに愛加那らが子供2人と来訪。まもなく沖永良部島への遠島処分が決定される。 |
| 9月22日 | 南北戦争のさなかに、リンカーン米大統領が「奴隷解放宣言」。但し、敵対する南軍の奴隷解放を宣言したもので、味方である北軍の奴隷については除外。 |
| 9月23日 | ウッドレイクの戦い。シブレー大佐率いる民兵軍とダコタ・スー族の戦士らが衝突。マンケイトー酋長らが戦死し、民兵軍が勝利する。その後、ダコタ・スー族の大半が降伏。 |
| 10月 7日(文久2年閏8月14日) | 西郷隆盛、沖永良部島に到着。 |
| 12月 | ダコタ・スー族に対する裁判で307人が死刑判決。ミネソタ州の有力者ヘンリー・ウィップル主教の請願によりリンカーン大統領は264名の死刑を減刑し39名の処刑に署名。スー族の穏健派で反乱に反対した族長らも処刑されたと言われる。 |
| 12月26日 | ミネソタ州マンカトのスネリング砦でダコタ族死刑囚39人中38人(1人は執行猶予)の同時絞首刑が執行される。同時の処刑数ではアメリカ史上最大。この後、ダコタ・スー族は収容所や不毛地帯で多くが死亡し絶滅寸前にまで追い込まれた。 |
| 1863年 | |
| 1月10日 | 世界最初の地下鉄路線であるロンドン地下鉄が開通。メトロポリタン鉄道のパディントン駅-ファリンドン駅間で現在のハマースミス&シティー線およびメトロポリタン線の一部。 |
| 4月30日(文久3年 3月13日) | 壬生浪士組が会津藩預かりとなり、のちの新選組の原型となる。 |
| 5月 3日(文久3年 3月16日) | 英国艦隊の横浜入港に合わせて攘夷派が横浜居留地を襲撃するとの風聞が広がり、神奈川奉行が住民に避難を命じ、住民らの避難騒ぎに発展。 |
| 5月12日(文久3年 3月25日) | 壬生浪士組のまとめ役だった殿内義雄が近藤勇・沖田総司に暗殺される。最初の粛清。粛清の理由ははっきりしないが、ほぼ同時期に根岸友山ら根岸派が浪士組から離脱しているため、その関係か。 |
| 6月 9日(文久3年 4月23日) | 14代将軍徳川家茂、幕府海軍の順動丸に乗船。神戸に海軍操練所を設立することを認める。 |
| 6月25日(文久3年 5月10日) | 朝廷が攘夷決行日と定めた日。孝明天皇の勅書が出される。長州藩は馬関海峡でアメリカ船に対し砲撃。しかし幕府も諸藩も特に何もせず。攘夷派の人々は、攘夷決行を促すため、天皇の大和・伊勢行幸を画策。 |
| 7月 1日 | アメリカ南北戦争でゲティスバーグの戦いがはじまる。 |
| 7月 3日(文久3年 5月18日) | 幕府と英仏両国が、横浜に英仏両軍を駐屯させることで合意。 |
| 7月 5日(文久3年 5月20日) | 京都御所朔平門外で、姉小路公知が暗殺される。遺留品から薩摩藩士田中新兵衛が犯人として疑われる。朔平門外の変、猿ヶ辻の変。 |
| 7月11日(文久3年 5月26日) | 姉小路公知暗殺の犯人として京都町奉行の取り調べを受けていた薩摩藩士田中新兵衛が隙を見て自殺。真犯人かどうか不明で、また自殺も含め動機もはっきりせず。 |
| 7月18日(文久3年 6月 3日) | 新選組と大坂相撲の力士らとの乱闘事件が起きる。 |
| 8月11日(文久3年 6月27日) | 生麦事件について薩摩藩と交渉するため、イギリス艦隊が鹿児島沖に到着。 |
| 8月12日(文久3年 6月28日) | イギリス艦隊のニール代理公使と薩摩藩との間で交渉が始まる。イギリス側は賠償金と犯人の処罰を要求。薩摩藩側は鹿児島城内での会談を求める。 |
| 8月13日(文久3年 6月29日) | イギリス側は鹿児島での会談を拒否し、薩摩藩側の回答を求める。奈良原喜左衛門ら一部藩士がイギリス艦隊に乗り込む計画を立てるが失敗に終わる。 |
| 8月14日(文久3年 7月 1日) | イギリス側は武力攻撃を示唆。薩摩藩側も開戦やむなしとして、藩主島津茂久と、国父島津久光は鹿児島郊外の西田村に陣を置く。 |
| 8月15日(文久3年 7月 2日) | イギリス艦隊のうち5隻が、薩摩藩の蒸気船を武力で奪取。それを見た薩摩藩側も攻撃を決定。鹿児島の天保山砲台と桜島の袴腰砲台が艦隊に向けて砲撃。イギリス艦隊は鹵獲していた薩摩藩船3隻を沈め、沿岸の砲台へ向けて砲撃を開始。悪天候の中、午後3時頃、旗艦ユーライアラスの艦橋付近に砲弾が命中炸裂し士官らが戦死する。夜になり、艦砲で集成館を破壊。また城下で火災が発生する。 |
| 8月16日(文久3年 7月 3日) | イギリス艦隊は城下を砲撃。市街地を焼く。 |
| 8月17日(文久3年 7月 4日) | イギリス艦隊は人的被害(死傷者63人)と弾薬の消耗などを受け、鹿児島を離れ横浜へ向かう。一方薩摩藩側は死傷者は少なかったものの、鹿児島城の一部、集成館、各砲台、火薬庫などが破壊され、城下の1割を焼失し、蒸気船3隻を失う。国際的にはイギリス側が退却したと捉えられ、また賠償金を得ているのに無用の戦争を行ったと批判された。国内では薩摩藩が攘夷を実行したと受け止められている。 |
| 9月25日(文久3年 8月13日) | 長州派公卿らの活動により天皇の大和行幸の詔が出る。しかし、孝明天皇は攘夷主義者ではあるが秩序を乱す過激な攘夷思想を嫌い、これを受けて会津藩や薩摩藩は、長州藩追い落としを画策するようになる。 |
| 9月25日(文久3年 8月13日) | 新選組の芹沢鴨らが、資金援助を断った大和屋に放火し焼き討ちする事件を起こす。芹沢一派粛清の遠因となったとも言われる。 |
| 9月27日(文久3年 8月15日) | 公卿中山忠光、土佐浪士吉村寅太郎らが天皇の大和行幸に伴う攘夷決行を促すため、兵を率いて堺に上陸。天誅組の変の勃発。河内狭山藩などに協力を要請。 |
| 9月29日(文久3年 8月17日) | 天誅組一党が大和五条の幕府代官所を襲撃して同地を占拠。隣接する高取藩に協力を要請。三条実美は平野国臣を派遣して自重の説得を試みる。 |
| 9月30日(文久3年 8月18日) | 八月十八日の政変。長州藩と長州派公卿の失脚を求める天皇密勅を受け、会津藩主体で薩摩藩、淀藩、岡山藩、鳥取藩、徳島藩などが参加し、御所九門を封鎖。三条実美ら長州派公卿を禁足。朝議が開かれ、長州派公卿の追放、大和行幸の延期、長州藩主親子の処罰が決まり、長州藩は堺町御門警備の任を解かれる。 |
| 10月 1日(文久3年 8月19日) | 七卿落ち。失脚した長州派公卿7人(三条実美・三条西季知・四条隆謌・東久世通禧・壬生基修・錦小路頼徳・澤宣嘉)が、長州藩兵とともに京都を離れる。 |
| 10月 2日(文久3年 8月20日) | 政変を知った天誅組一党は、天の辻へ拠点を移す。十津川郷士を脅迫して集め、抵抗した人々を処刑。高取藩は天誅組への協力を拒否。 |
| 10月 7日(文久3年 8月25日) | 天誅組一党は、高取藩へ攻め込むが、少数の高取藩兵に大敗を喫する。 |
| 10月 4日 | フランスの写真家ナダールが、巨大熱気球の公開飛行実験を行うが失敗に終わる。 |
| 10月14日(文久3年 9月 2日) | 井土ヶ谷事件。武蔵国久良岐郡井土ヶ谷村でフランス人士官3名が攘夷派の浪士3人に襲われ、カミュ少尉が死亡。他の二人は逃走して助かる。フランス公使ベルクールは幕府に謝罪の特使をフランスへ送ることを幕府に勧める。幕府は鎖港談判使節団を送るのに合わせて特使を派遣することを決定。 |
| 10月17日(文久3年 9月 5日) | 幕府の天誅組追討令をうけ、周辺諸藩が出兵。 |
| 10月22日(文久3年 9月10日) | 天誅組への総攻撃が開始される。 |
| 10月25日(文久3年 9月13日) | 新選組副長で、芹沢一派と見られていた新見錦が切腹に追い込まれる。乱暴狼藉とも、職務怠慢とも、薩長や水戸藩との尊皇攘夷運動が原因とも言われる。なお、日付や切腹場所は諸説あり。正体不明の人物で、記録が殆ど残っていない。長門国監察使正親町公董の陪従として三田尻まで赴いた際に起こした不祥事で9月15日に三田尻で切腹させられた新家粂太郎(新見久米次郎)が新見錦で、新選組から離れたあとの話という説もある。また13日に田中伊織なる隊士が近藤勇の手で殺害されたという記録があるため、同一人物という説もある。 |
| 10月26日(文久3年 9月14日) | 天誅組の本陣があった天の辻が陥落。朝廷からの逆賊追討令旨が降りたことを受けて、十津川郷士らが離反。 |
| 10月30日(文久3年 9月18日) | 新選組の局長芹沢鴨と副長助勤の平山五郎が、壬生の八木邸で土方歳三、沖田総司らに襲撃されて殺害される。芹沢の愛人のお梅も殺害。同邸宅にいた芹沢家の家臣筋に当たる平間重助は難を逃れ逃亡。芹沢らの横暴行為の数々が朝廷や会津藩、諸藩で問題になったのが直接の理由とされている。 |
| 10月31日(文久3年 9月19日) | 中山忠光は天誅組を解散。残党は包囲網からの脱出を図る。 |
| 11月 5日(文久3年 9月24日) | 鷲家口で天誅組残党と紀州藩兵・彦根藩兵が遭遇。天誅組側は彦根藩陣地を襲撃し、その間に中山忠光と池内蔵太は脱出に成功するが、松本奎堂、藤本鉄石、那須信吾など主なメンバーが討ち死に。中山忠光は長州藩に匿われるが後に暗殺され、池内蔵太は禁門の変などに参加したのち亀山社中に加わるが海難事故で遭難死した。 |
| 11月 7日(文久3年 9月26日) | 新選組隊士の御倉伊勢武、荒木田左馬之助、楠小十郎の3人が、突如他の隊士に襲われ殺害される。長州藩の間者であることが露見したためとされるが、真偽不明。芹沢一派の暗殺事件を長州の陰謀に仕立てる工作に利用されたとも言われる。 |
| 11月 8日(文久3年 9月27日) | 天誅組の幹部で、負傷して一行と離れていた吉村寅太郎が、津藩兵と遭遇し射殺される。 |
| 11月 9日(文久3年 9月28日) | 薩摩藩とイギリスとの間で和睦交渉が始まる。 |
| 11月15日(文久3年10月 5日) | 薩摩藩とイギリスとの間で和睦が成立。薩摩藩が賠償金に相当する2万5000ポンドを出してイギリスから軍艦を購入することが決まる(金は幕府が薩摩藩へ貸した)。以降、イギリスは薩摩藩と接近。 |
| 11月22日(文久3年10月12日) | 生野の変。攘夷派の平野国臣と北垣晋太郎らが七卿のひとり澤宣嘉を擁して、但馬生野に入る。天誅組壊滅の情報は入っていたため、兵を挙げるかどうかで論議となるが、強硬派の河上弥市らの主張が通り挙兵。攘夷の挙兵として農民らが集まる。 |
| 11月23日(文久3年10月13日) | 生野代官所の通報を受け、周辺諸藩が討伐に乗り出す。動揺した澤宣嘉が逃走。農民らも話と違うと激昂し河上弥市ら強硬派を襲ったため、河上らは自刃。平野国臣は部隊を解散させたが、鳥取藩に向かうも捕縛される(のち禁門の変の際に獄中で謀殺)。澤宣嘉、北垣晋太郎、進藤俊三郎らは逃げ延び、維新を無事迎えた。 |
| 1864年 | |
| 2月 4日(文久3年12月27日) | 新選組副長助勤の野口健司が切腹させられる。粛清の理由は不明。水戸派で唯一残っていた人物。 |
| 2月 6日(文久3年12月29日) | 幕府がフランスに横浜鎖港談判使節団を派遣。正使は池田長発、副使は河津祐邦、井土ヶ谷事件特使は竹本正雅で、総勢34名。フランス軍艦で出発する。朝廷の求めた攘夷実行に基づく横浜鎖港のための交渉と、井土ヶ谷事件の謝罪・賠償を目的とする。途中立ち寄ったエジプトのスフィンクスでの記念撮影で知られる。鎖港交渉は失敗に終わるが、井土ヶ谷事件の被害者遺族に賠償を行った。 |
| 3月28日(元治元年 2月21日) | 西郷隆盛の沖永良部島からの召還が決まり、蒸気船胡蝶丸で薩摩へ向かう。 |
| 4月 4日(元治元年 2月28日) | 西郷隆盛、薩摩に帰郷。 |
| 5月 2日(元治元年 3月27日) | 幕府へ攘夷の横浜鎖港を実施させることを目的として、水戸藩の藤田小四郎、田丸稲之衛門ら62名が筑波山で挙兵。天狗党の乱が起こる。 |
| 7月 8日(元治元年 6月 5日) | 池田屋事件。新選組が勤王浪士を支援していた古高俊太郎を捕らえ、その情報を元に京三条木屋町の池田屋にいた攘夷志士を襲撃。長州、土佐、肥後の志士らが9人が殺害され、町人を含む20数人が捕縛される。新選組や、会津・桑名・彦根藩士らにも犠牲者が出る。新選組が一躍名を挙げた事件。 |
| 7月13日(元治元年 6月10日) | 明保野亭事件。池田屋事件の残党を追っていた新選組と会津藩が京東山の料亭「明保野亭」に捜査に入ったところ、そこに居た土佐藩士麻田時太郎が驚いて逃げようとしたため、会津藩士柴司が槍で突き負傷させる。麻田が土佐藩士とわかり、会津藩は身柄を引き渡して見舞いの使者を送り、柴司も不問となったが、翌日、土佐藩は麻田が逃走を図ったことを問題にして切腹に処す。この件で土佐勤皇党らが反発して騒ぎ出したため、責められた会津藩は対応に苦慮。事態を知った柴司が自刃して事態収拾を図った。 |
| 7月19日(元治元年 6月16日) | 一橋家家老並平岡円四郎が、水戸藩士林忠五郎・江幡広光に襲われ、従者二人とともに殺害される。一橋当主徳川慶喜の信任厚かった平岡が、慶喜を介して幕政を裏で操っているという風聞が立ち、その結果幕府が尊皇攘夷をやめたと思った水戸藩士らの標的にされたことによる。林・江幡は、平岡円四郎の家臣だった川村恵十郎と斬り合いになり殺害される。川村は重傷。なお川村恵十郎は、渋沢栄一を平岡円四郎に紹介し一橋家に奉公させるきっかけを作った人物。 |
| 8月20日(元治元年 7月19日) | 禁門の変。八月十八日の政変で謹慎となった毛利藩主親子の処分撤回を朝廷に求めるため、国司親相、益田親施、福原元僴の三家老や、久坂玄瑞、来島又兵衛らが軍を率いて京に攻め込む。武力で御所に突入するも、長州藩各隊は連携が取れず、会津・薩摩・福井・一橋および新選組の連合軍に敗れる。御所鷹司邸付近と長州藩邸周辺から出た火災がひろがり、京都市街地は一条から七条に至る、全市街地の半分、27500戸が焼失。市民300人以上が死亡した(いわゆる「どんどん焼け」)。出火は長州側によるものと、会津や新選組によるものと両方の説があるが、勤王派と見られた寺院などが焼かれており、京の市民は会津側の放火と見ていたらしく、京に攻め込んだ長州に同情するものが多かったという。またこの火災騒動の中、京都町奉行滝川具挙の命令で、六角獄舎の勤王派未決囚33人が殺害されている。 |
| 8月24日(元治元年 7月23日) | 長州藩追討の勅命が幕府に対して下される。第一次長州征伐のはじまり。幕府は西国を中心に35藩に動員令を下し、15万人が動員される。征長総督は徳川慶勝、副総督は松平茂昭。 |
| 10月26日(元治元年 9月26日) | 長州藩正義派の有力者だった周布政之助が、椋梨藤太らの圧力を受け切腹。 |
| 10月30日(元治元年 9月30日) | 薩摩藩と長州支藩岩国藩の吉川経幹との間で交渉が始まる。 |
| 11月20日(元治元年10月21日) | 長州藩は藩内の非正規軍である諸隊に解散命令を出す。 |
| 11月21日(元治元年10月22日) | 大坂城で征長軍の軍議が行われ、元治元年11月18日を総攻撃と決定する。 |
| 11月21日(元治元年10月22日) | 鎌倉事件。相模国鎌倉郡大町村で休暇中のイギリス人士官のボールドウィン少佐とバード中尉が2名の武士に斬られて、ボールドウィン少佐は即死。バード中尉は地元の医師の手当を受けるも夜になり死亡した。イギリス側が強硬姿勢を取ったため、幕府神奈川奉行が捜査。別件の強盗事件の犯人蒲池源八と稲葉紐次郎、および彼らの首領の清水清次が関与したと判断される。 |
| 11月23日(元治元年10月24日) | 西郷隆盛、征長総督徳川慶勝に対し、吉川経幹との間でまとめられた長州藩降伏の条件を進言。徳川慶勝はこれを受け入れ、西郷を参謀として交渉を命じる。 |
| 12月 2日(元治元年11月 4日) | 西郷隆盛、岩国で吉川経幹と会談し、降伏条件として提案を受けていた、禁門の変の責任者の三家老の切腹・四参謀の斬首・長州派五卿の長州からの追放を受け入れる。 |
| 12月 7日(元治元年11月 9日) | 長州藩が三家老の切腹を決定するが、諸隊幹部らは反対したため、萩の藩政府は鎮静奉行を山口へ送る。 |
| 12月 9日(元治元年11月11日) | 長州藩家老益田親施が徳山惣持院で切腹。 |
| 12月10日(元治元年11月12日) | 長州藩家老国司親相が徳山澄泉寺で切腹。同じく長州藩家老の福原元僴も岩国龍護寺で切腹。禁門の変の参謀だった宍戸真澂、竹内正兵衛、中村九郎、佐久間左兵衛の4人も野山獄で斬首。三家老の首は幕府側へ送られる。諸隊幹部らはこれに反発。 |
| 12月14日(元治元年11月16日) | 広島国泰寺で三家老の首実検が行われる。幕府大目付の永井尚志が藩主処罰等を求めたのに対し、吉川経幹はこれ以上の処罰は長州側の徹底抗戦につながるとして難色を示し、西郷隆盛も妥協を進言。 |
| 12月16日(元治元年11月18日) | 鎌倉事件に関わったとして蒲池源八と稲葉紐次郎が処刑される(事件の主犯清水の率いる強盗一味のメンバーだが鎌倉事件とは無関係と見られる)。 |
| 12月16日(元治元年11月18日) | 鎌倉事件の主犯と見られる清水清次が千住で逮捕される。清水は高橋藤次郎という人物と犯行に及んだと自供。 |
| 12月22日(元治元年11月24日) | 長州藩の俗論派を率いる椋梨藤太が政務役となり幕府恭順を示す俗論派政権が実権を掌握。対する正義派藩士らが弾圧される(弾圧は吉川経幹の指示、あるいは幕府の要求説もある)。 |
| 12月28日(元治元年11月30日) | 鎌倉事件の主犯とされる清水清次が処刑される。清水は浪人とも谷田部藩士ともいわれるが諸説ある。共犯の高橋藤次郎なる人物は見つからず、清水の知人の田中春岱、天方一を相次いで逮捕するも関与を否定。 |
| 12月29日(元治元年12月 1日) | 福岡藩から長州藩に対して、長州派五卿の身柄を九州の五藩で預かる提案がなされる。以後数度に渡って、五卿と、五卿に近い諸隊幹部への説得が行われる。 |
| 1865年 | |
| 1月 2日(元治元年12月 5日) | 長州藩主親子の謝罪文が征長総督府へ提出される。 |
| 1月 9日(元治元年12月12日) | 西郷隆盛と交渉した福岡藩の月形洗蔵の説得で長州派五卿は九州行きを了承。 |
| 1月10日(元治元年12月13日) | 高杉晋作、諸隊幹部らに挙兵を訴えるが賛同は得られず。 |
| 1月12日(元治元年12月15日) | 高杉晋作、伊藤俊輔、石川小五郎ら84人が、俗論派政権打倒のため功山寺で挙兵。 |
| 1月13日(元治元年12月16日) | 高杉ら遊撃隊は馬関新地会所を襲撃。馬関奉行根来親祐は降伏し協力。 |
| 1月16日(元治元年12月19日) | 長州藩俗論派政権によって正義派の毛利登人・大和国之助・山田亦介・前田孫右衛門・松島剛蔵・渡辺内蔵太・楢崎弥八郎の7名が野山獄で斬首される。征長軍巡見使長谷川敬の意向だったとも言われる。 |
| 1月22日(元治元年12月25日) | 長州藩俗論派政権によって正義派の家老清水親知が切腹に追い込まれる。 |
| 1月24日(元治元年12月27日) | 征長軍解兵令により第一次長州征伐は終結。 |
| 1月25日(元治元年12月28日) | 高杉らの遊撃隊を鎮圧するための萩藩政府軍が出発。この頃、他の諸隊の多くは藩政府に恭順していたものと思われる。 |
| 1月28日(元治2年 1月 2日) | 高杉らの遊撃隊が伊崎会所を襲撃。 |
| 2月 1日(元治2年 1月 6日) | 絵堂の戦い。高杉らの遊撃隊に味方することに決した山県有朋率いる奇兵隊など200人が藩政府軍の駐屯する絵堂を襲撃。これを占拠する。ただし兵数が少ないこともあり、すぐに絵堂を放棄して転進。 |
| 2月 3日(元治2年 1月 8日) | ぜんざい屋事件。新選組大坂屯所の谷万太郎が、谷三十郎、正木直太郎、阿部十郎の4人で、土佐脱藩浪士が隠れているというぜんざい屋の石蔵屋政右衛門宅を襲撃。元土佐勤王党の大利鼎吉を討ち取る。 |
| 2月 5日(元治2年 1月10日) | 大田の戦い。翌日にかけて奇兵隊などの諸隊と藩政府軍が衝突。 |
| 2月 9日(元治2年 1月14日) | 呑水峠の戦い。奇兵隊などの諸隊が藩政府軍を撃退。またこの日、高杉晋作ら遊撃隊メンバーも諸隊に合流。 |
| 2月11日(元治2年 1月16日) | 赤村の戦い。高杉率いる遊撃隊と、山県率いる奇兵隊などの諸隊が、赤村で藩政府軍を挟み撃ちにして撃破。山口も抑える。この時点で、萩の俗論派政府と、山口の諸隊政府とで長州藩は二分された状態となる。 |
| 2月23日(元治2年 1月28日) | 萩藩政府が諸隊に対して、休戦を申し出るが、諸隊は受け入れず。この頃すでに、各支藩は高杉側に付く動きを見せており、萩藩政府からの援軍要請にも従わない状態になっていた。 |
| 2月25日(元治2年 1月30日) | 諸隊は、陸海より萩への進攻を開始。これを受けて藩主の毛利敬親は俗論派政権の幹部らを罷免。俗論派政権瓦解により諸隊は進撃を停止。 |
| 3月19日(元治2年 2月22日) | 四ツ塚志士事件。美作国勝田郡百々村で資金調達と同士募集のために訪れた勤王志士4人(岡元太郎、井原応輔、島浪間、千屋金策)が、村人から強盗と誤解されて追われ、逃げた先の土居宿の門番役人に阻まれ、争いになり自殺。遺体は村人によって傷つけられたあと河原に捨てられる。維新後、村人への批判が出たため、村は顕彰碑(四ツ塚)を建てて祀った。 |
| 3月20日(元治2年 2月23日) | 新選組総長の山南敬助が粛清される。新選組結成時からの幹部だが、屯所移転を巡って近藤・土方と意見対立して出奔し、捕らえられて隊紀により切腹したとされる。温厚で人格者だったと言われる。 |
| 4月14日 | リンカーン大統領が、フォード劇場で観劇中に、南部連合を支持する俳優のジョン・ウィルクス・ブースに暗殺される。 |
| 4月27日 | ミシシッピ川の貨客船サルタナ号が爆発火災を起こし、1450人が死亡。数百人が行方不明となる。 |
| 5月18日(同治4年 4月24日) | 高楼寨の戦い。張宗禹・頼文光・任柱らの率いる捻の乱を討伐中、山東省曹州荷沢県で清朝軍が大敗。清朝軍を率いていたセンゲリンチン・全順・何建鰲らが戦死する。センゲリンチンはモンゴル系だが、清朝皇室と縁戚関係にあり、その強さもあって有力な武将であった。その死により、清朝軍の主力だった「八旗」は弱体化し、漢人の曽国藩が「湘軍」を、李鴻章が「淮軍」を編成して台頭することになる。 |
| 6月 9日 | イングランドのケント州ステープルハーストで、高架橋工事のために線路を外していたところへ列車が進入し脱線、一部車両が転覆して川に落ち、10人が死亡、40人余が負傷する。作家チャールズ・ディケンズが乗車していて遭遇したことでも知られる(ディケンズは無事)。 |
| 7月 3日(慶応元年閏5月11日) | 土佐勤王党の盟主、武市半平太(瑞山)が切腹。 |
| 7月20日(慶応元年閏5月28日) | 長州藩俗論派の首領だった椋梨藤太が処刑される。自分1人の罪なので自分だけを処罰するよう求めたと言われる。 |
| 8月13日 | 医師のセンメルヴェイス・イグナーツが死去。産褥熱による死亡率を下げるには、担当医師が手洗い消毒をすれば良いことに気づき、消毒法の普及を訴えた人物。しかし医学界から受け入れられず批判嘲笑され続けたため、精神疾患となり、収容された精神病院から逃げようとして衛兵に殴打され、それがもとで死亡した。彼の死後まもなく消毒法を唱えたジョセフ・リスターや、細菌による腐敗現象を発見したルイ・パスツールの業績で再評価された悲運の先駆者(リスターも当初は激しく批判されるなど、衛生に関する理解がない時代だった)。 |
| 8月31日(慶応元年 7月11日) | 鎌倉事件で新たに幕府は間宮一を逮捕。その供述から飯田晋之介を捕縛。 |
| 10月20日(慶応元年 9月 1日) | 新選組四番隊組長の松原忠司が死去。記録上は病死だが、粛清説もある。 |
| 10月30日(慶応元年 9月11日) | 鎌倉事件で間宮一が処刑される。イギリス側は間宮の処刑をもって、この件は終了とし賠償金の請求は行わなかった。イギリス士官を殺害した犯人は先に処刑された清水ではなく間宮一と飯田晋之介とする説もあり不明点も多い。 |
| 12月24日 | ネイサン・ベッドフォード・フォレストらによって、黒人迫害組織KKK(クー・クラックス・クラン)が設立される。 |
| この年、ジュール・ヴェルヌのSF小説の古典『月世界旅行』が発刊。アメリカ南北戦争直後を舞台に、元砲術士官らが集まり、地面に埋めた超巨大な大砲で砲弾型宇宙船を打ち上げ、月へ人を送ろうとする物語で、科学的な計算もされた内容だが、風刺小説という側面もあると言われている。後に書かれたウェルズの『宇宙戦争』とともに、様々な小説や映画に影響を与え、のちのロケット研究者らの多くにも影響を与えた作品。 | |
| 1866年 | |
| 3月 7日(慶応2年 1月21日) | 京の薩摩藩家老小松帯刀邸で坂本龍馬仲介の元、薩長同盟が成立。元々は長州藩寄りで五卿受入に奔走した福岡藩の藩医早川勇が発案し、月形洗蔵やパークスらと内々に高杉晋作・西郷隆盛らに話を進めた後、早川と知己にあった中岡慎太郎、坂本龍馬、土方久元、田中光顕ら土佐浪士が関与し、最終的に坂本の仲介で決まったとみられる。 |
| 3月 9日(慶応2年 1月23日) | 寺田屋事件。坂本龍馬と三吉慎蔵が未明に伏見寺田屋で伏見奉行配下の幕吏に襲撃される。寺田屋で働いていたお龍の通報で気づいた二人は応戦、坂本龍馬は手を負傷。戦闘の末に脱出し、薩摩藩に助けられる。幕吏側も数人が死亡。 |
| 4月24日(慶応2年 3月10日) | 坂本龍馬とお龍が怪我の治療と庇護を兼ねて薩摩へ到着。小松帯刀に出迎えられる。そのまま日当山温泉・塩浸温泉へ向かう。10日ほど静養して釣りや鳥撃ちなどをしたあと、二人で霧島高千穂峰に登り、山頂に刺さっていた「天の逆鉾」を引っこ抜くなどした。 |
| 6月14日 | ドイツ連邦議会でプロイセンとオーストリアの対立が決定的となり、プロイセンがドイツ連邦を離脱。 |
| 6月15日 | 普墺戦争勃発。ドイツ連邦諸邦のうちドイツ中北部の諸国と自由都市はプロイセンに、主に中南部のバイエルン、ザクセン、ヴュルテンベルク、ハノーファー、ヘッセン=カッセルなどの主要国はオーストリア側につく。プロイセン軍は直ちに対オーストリア戦と、対南部ドイツ諸国戦に乗り出す。 |
| 6月18日 | プロイセン軍が、ザクセン王都ドレスデンを占領。 |
| 6月20日 | イタリアがプロイセン側に味方する。 |
| 6月27日 | ランゲルザルツァの戦い。 |
| 6月29日 | ハノーファー王国がプロイセンに降伏し、同王国は滅亡。各諸邦がプロイセンへ恭順の動きを示す。 |
| 7月 3日 | ケーニヒグレーツの戦い。オーストリア軍が大敗する。 |
| 7月10日 | キッシンゲンの戦い。 |
| 7月14日 | アシャッフェンブルクの戦い。 |
| 7月16日 | プロイセン軍、フランクフルトを占領。 |
| 7月18日(慶応2年 6月 7日) | 幕府艦隊が周防大島へ砲撃を開始。第二次長州征伐始まる。薩摩藩は反対して参加せず。 |
| 7月20日 | リッサ海戦。アドリア海でオーストリア海軍とイタリア海軍が交戦し、オーストリア軍が勝利。 |
| 7月22日(慶応2年 6月11日) | 幕府軍と松山藩軍が周防大島へ上陸占領。松山藩兵による乱暴狼藉が問題になり長州藩は大島派兵を決定。 |
| 7月23日(慶応2年 6月12日) | 夜、高杉晋作の指揮する小型蒸気船丙寅丸が幕府艦隊に接近して砲撃し逃走。 |
| 7月28日(慶応2年 6月17日) | 長州軍が周防大島を奪還。また関門海峡を横断して田野浦に上陸。征長軍小倉口総督となった老中小笠原長行(唐津藩世嗣で小倉藩小笠原家の親族)の指揮のまずさに九州諸藩は消極的となり、長州藩優勢で推移。 |
| 7月28日 | プロイセン軍、ヴュルツブルクを占領し、ドイツ西部はプロイセン側の勝利で終結。 |
| 7月29日(慶応2年 6月18日) | 長州軍が浜田城を占領。長州藩と隣接する津和野藩や広島藩は中立を表明して参戦せず。 |
| 8月11日(慶応2年 7月 2日) | 大里の戦い。長州軍と小倉藩軍による本格的な戦闘。九州諸藩が消極的なため小倉藩単独で応戦することになり苦戦。 |
| 8月16日 | ジェネラル・シャーマン号事件。アメリカの帆船ジェネラル・シャーマン号が李氏朝鮮との通商を求めて平壌の羊角島に来航するが、朝鮮側の攻撃を受けて座礁。乗員は全員殺害される。朝鮮側の記録ではシャーマン号が一方的に住民を攻撃したために地元住民の怒りを買ったとしている。 |
| 8月23日 | プラハ条約締結。普墺戦争はオーストリア側の大敗で終結。プロイセン王国がオーストリアを排除する形でドイツ諸邦を吸収。 |
| 8月29日(慶応2年 7月20日) | 大坂城で将軍徳川家茂が死去。21歳。脚気衝心が死因と見られる。 |
| 9月 5日(慶応2年 7月27日) | 赤坂の戦い。長州軍と、小倉藩に援軍を出した熊本藩軍が戦闘に参加。熊本・小倉藩側が勝利。 |
| 9月 6日(慶応2年 7月28日) | 熊本藩軍が突如撤兵を開始。小笠原長行が熊本藩の援軍要請を拒否したことに反発したことが主な要因とみられる。小倉藩は劣勢に立たされる。 |
| 9月 9日(慶応2年 8月 1日) | 小倉藩が小倉城に火を放ち、香春に撤退して徹底抗戦に入る。九州諸藩も相次いで撤兵。 |
| 9月28日(慶応2年 8月20日) | 一橋慶喜が徳川宗家を継ぐ。しかし将軍職については拒否。 |
| 10月 8日(慶応2年 8月30日) | 廷臣二十二卿列参事件。第二次長州征伐で幕府軍の敗北が必至の状況を受けて、失脚していた尊攘派公家の復帰を、22人の公家が孝明天皇に訴えた事件。しかし天皇のさらなる怒りを買う結果となり、天皇が信任していた徳川慶喜の将軍就任が進むことになった。 |
| 10月10日(慶応2年 9月 2日) | 幕府側から勝海舟、長州側から広沢真臣と井上馨が出席して、宮島で休戦交渉を行い、第二次長州征伐の休戦が成立する。なお長州藩と小倉藩の戦闘は継続し、両者は翌慶応3年1月に和睦。 |
| 10月20日(慶応2年 9月12日) | 三条制札事件。京鴨川の三条大橋西詰に建てられていた幕府の制札が引き抜かれる事件が相次いだため、新選組が見張っていたところ、土佐藩士8人が引き抜きに現れたため、新選組がこれを襲い乱闘となる。土佐藩士藤崎吉五郎が死亡、宮川助五郎は捕らえられ、安藤正勝は逃走に成功したが重症を負い藩邸で自刃。禁門の変で長州藩に同情的だった京の市民に対して、長州藩の罪を問う内容の制札だったため、反発を買っていたと見られる。 |
| 11月26日(慶応2年10月20日) | 豚屋火事。横浜の港崎遊郭(現在の横浜公園)そばにあった豚肉料理屋鉄五郎から出火し、港崎遊郭は全焼。さらに横浜居留地などへと拡大し、一帯を焼き尽くした。大勢の遊女が焼死するなど甚大な被害となった。横浜はこのあと、再建計画に基づき、西洋風の町並みへと変わっていく。 |
| 12月23日(慶応2年11月17日) | 松山藩が周防大島での乱暴狼藉について長州藩に対し正式に謝罪。この頃、幕府敗北の影響が諸藩に広がる。 |
| 1867年 | |
| 1月10日(慶応2年12月 5日) | 徳川慶喜が将軍宣下を受け、第15代将軍となる。 |
| 1月17日(同治5年12月12日) | 八戸事件。清国広州の「中外新聞」に、英領香港在住の日本人「八戸順叔」なる人物が「江戸幕府が軍制を洋式化し、260の諸侯を集め、朝鮮を征討しようとしている」という記事を寄稿。この内容が清国政府へ伝えられ、清国政府から朝鮮政府にまで伝わり、外交問題に発展する。江戸幕府はこの疑惑を否定する文書を対馬藩経由で朝鮮政府に提出し一旦は落着するが、明治に入って再燃する。なお、この新聞記事が実際にあったものか不明で、八戸順叔という人物の正体もわかっていない。 |
| 2月17日(慶応3年 1月13日) | 「清風亭会談」。土佐藩参政の後藤象二郎が、幕府の弱体化と薩長雄藩の伸張という情勢変化を受けて、薩長と関係を持ち、亀山社中を経営していた坂本龍馬と会談。土佐藩は坂本らの脱藩を赦免、亀山社中を土佐藩に組み込み、同社中は「海援隊」となる。 |
| 4月 1日(慶応3年 2月27日) | パリ万国博覧会開幕。幕府と薩摩藩、佐賀藩がそれぞれ独自に出展する。特に薩摩藩は、「日本薩摩琉球国太守政府」と名乗り、外交用に現地で独自に勲章(薩摩琉球国勲章)を制作。現地で大問題に発展する。 |
| 4月14日(慶応3年 3月10日) | 新選組参謀の伊東甲子太郎が、新選組を離脱して御陵衛士を結成。新選組隊士15名からなる。離脱の理由は思想の違いによるものだが、表面上は孝明天皇の御陵守護と、薩長の動向を探るためとして、近藤勇らも同意しての離脱となっている。もともと勤王派であった伊東は薩摩に近づき倒幕を目指したと言われるが、朝廷を中心とした穏健な新政権樹立を目指したという説もある。 |
| 4月26日 | 普墺戦争の結果を受けて、プロイセン王国はドイツ諸邦を傘下に収めた北ドイツ連邦を成立させる。後のドイツ帝国。なお、プロイセンに敗北した南部のバイエルン、ヴュルテンベルク、バーデン、ヘッセンの各国は加わっていない。 |
| 5月 1日(慶応3年 3月27日) | 徳川昭武欧州使節団の通訳を務めていたフランス人神父メルメ・カションが、突如、「日本は連邦制国家で徳川幕府は日本の全権をもたない」と新聞に投稿。これがきっかけでフランス政府の日本への600万ドルの借款計画は中止される。カションは琉球・日本の滞在歴が長く、日本語も非常に堪能だったが、性格に問題があったのか、幕府関係者の評判はすこぶる悪かった。なお、パリ万博前後に、薩摩藩と密約を交わしたモンブラン伯シャルルも、日本は連邦制であり徳川家も一大名にすぎないと触れ回っている。 |
| 5月17日(慶応3年 4月14日) | 高杉晋作、肺結核で死去。 |
| 7月23日(慶応3年 6月22日) | 元新選組五番隊組長の武田観柳斎(福田廣)が暗殺される。甲州流軍学者で武芸も優れていたため近藤勇に重用されたが、徐々に地位を失い、御陵衛士への参加も認められず、近藤の許可で脱退。しかし京で倒幕運動に関わったとして新選組によって殺害された。子母澤寛の小説で悪く描かれたこともあり、創作で悪役にされることの多い人物。 |
| 10月18日 | ロシアがクリミア戦争の戦費調達のため、アラスカをアメリカに720万ドルで売却する。 |
| 12月10日(慶応3年11月15日) | 近江屋事件。京の近江屋に潜伏していた坂本龍馬と、たまたま来ていた中岡慎太郎が数人の武士に襲撃され、坂本龍馬は間もなく死亡。取次に出て斬られた山田藤吉が翌日死亡。中岡慎太郎が重症を負う。新選組の大石鍬次郎の証言などから犯人は見廻組の佐々木只三郎、今井信郎、渡辺篤ら数名という説が有力。坂本は幕臣とも繋がりがあるため、倒幕派の中岡慎太郎が狙われ、坂本は巻き込まれたという説もある。 |
| 12月12日(慶応3年11月17日) | 近江屋事件で重症を負った中岡慎太郎が死亡。絶命するまでの間に谷干城に語ったとされる内容が広まり、特に新選組が疑われることになった。これがこのあとの天満屋事件、および近藤勇・大石鍬次郎らの処刑にも影響を与えている。 |
| 12月13日(慶応3年11月18日) | 油小路事件。新選組と、新選組から離脱して結成された御陵衛士(高台寺党)との間で起こった闘争。近藤勇から酒宴に呼ばれた御陵衛士代表の伊東甲子太郎が帰途に新選組の大石鍬次郎らに暗殺され、その遺体を探しに来た御陵衛士の藤堂平助らと新選組との間で戦闘になり、藤堂らが殺害された。伊東は朝廷や薩長に徳川も加えた穏健な新政府樹立を訴えていたこともあり、新選組を裏切って薩摩藩に寝返ったという説を疑問視する意見もあるが、創作では悪役にされることが多い。 |
| 12月24日(慶応3年11月29日) | 出流山事件。下野出流山で薩摩藩の意を受けた志士らが地元の若者らを集めて倒幕挙兵した事件。幕府・諸藩軍によって壊滅した。 |
| 1868年 | |
| 1月 1日(慶応3年12月 7日) | 天満屋事件。当時海援隊のメンバーだった陸奥宗光(紀州藩出身)が、坂本龍馬が暗殺された近江屋事件の黒幕は、いろは丸沈没事件で海援隊に恨みのある紀州藩であると疑い、特に紀州藩側の交渉担当者だった三浦安(休太郎)の襲撃を計画。それを知った紀州藩が新選組に護衛を頼み斎藤一らが担当するが、この日夜、天満屋で紀州藩士と新選組隊員が酒宴を開いているところを、陸奥ら海援隊士と陸援隊士16人が襲撃。乱闘の結果、襲撃側の中井庄五郎と、新選組の宮川信吉と舟津釜太郎が死亡し、新選組の梅戸勝之進が重症、三浦安も負傷した。なお陸奥も三浦も後に明治政府の高官となっている。 |
| 1月 3日(慶応3年12月 9日) | 王政復古の大号令。武力で御所9門を封鎖した薩摩藩、土佐藩、尾張藩、越前藩、安芸藩の5藩と岩倉具視らによって、御所内学問所にて「王政復古の大号令」が発せられ、天皇親政と、江戸幕府や摂政・関白職の廃止、総裁・議定・参与の設立が宣言される。同日夜、天皇臨席のもと、小御所会議が開かれ、徳川慶喜に対して辞官納地を命じることが話し合われるが、徳川慶喜の大政奉還の功績を賞せず、譴責しようとする薩摩派公卿や岩倉具視、大久保利通らに対し、山内容堂や松平春嶽、徳川慶勝、後藤象二郎らが反発、慶喜の出席を求めて紛糾。最終的に容堂らが折れて、慶喜の辞官納地は決定するものの、その後の変遷で慶喜への処罰的な色彩は薄れることになり、薩摩藩の武力政策につながっていく。 |
| 1月 4日(慶応3年12月10日) | 松平春嶽と徳川慶勝が徳川慶喜と会談。慶喜は辞官納地に応じる姿勢を見せるも明確な返答はせず。 |
| 1月 7日(慶応3年12月13日) | 徳川慶喜が大坂城に入り、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、プロイセン、アメリカの各公使に対し、引き続き外交権を主張。この頃から、大坂に幕府方が集結し始める。 |
| 1月12日(慶応3年12月18日) | 墨染事件。新選組局長近藤勇が伏見墨染で狙撃され重症を負う。御陵衛士の阿部十郎、篠原泰之進、加納鷲雄、富山弥兵衛らによる事件。 |
| 1月17日(慶応3年12月23日) | 江戸薩摩藩邸にいた浪人らが江戸市中で騒動を繰り返し、三田の庄内藩屯所などを襲う。 |
| 1月18日(慶応3年12月24日) | 新政府側が、松平春嶽と徳川慶勝を大坂城に派遣し、慶喜に対し再度辞官納地を求める。慶喜はこれに同意し、京へ戻ることも決定する。 |
| 1月19日(慶応3年12月25日) | 江戸薩摩藩邸焼き討ち事件。度重なる浪人らの乱暴狼藉に対し、老中稲葉正邦らは薩摩藩に浪人の処分を求めたところ、これを薩摩藩が拒否したため、庄内藩・上山藩・鯖江藩・岩槻藩の兵らが薩摩藩邸を襲った事件。幕府側に先に手を出させる薩長側の謀略と言われる。薩摩藩邸にいた一部は品川沖に停泊していた薩摩軍艦翔凰丸で逃走。幕府海軍の咸臨丸、回天丸がこれを追撃。逃走には成功したが損傷を受けた。 |
| 1月21日(慶応4年12月27日) | 京都で薩摩・長州・土佐・安芸の4藩上洛兵による軍事演習が天皇臨席のもとで行われる。 |
| 1月25日(慶応4年1月 1日) | 徳川慶喜、「討薩の表」を発表。薩摩藩への宣戦布告と、朝廷への威圧を意味したもので、ずっと後に慶喜は、情勢によって出しただけで、その後は放って置いたと語っている。 |
| 1月26日(慶応4年1月 2日) | 幕府軍1万5千が大坂から京都へ進軍を開始。伏見淀姫社に本営を置く。 |
| 1月27日(慶応4年1月 3日) | 鳥羽・伏見の戦いが始まる。鳥羽街道で進軍してきた幕府軍が、街道を封鎖していた薩摩軍と対峙。幕府軍を率いる大目付滝川具挙と、鳥羽関所を守っていた薩摩藩士椎原小弥太らとで交渉が行われるが、夕刻、薩摩藩側が突如砲撃したことから戦端が開かれる。幕府軍先鋒は混乱に陥り、見廻組や後方から上がってきた桑名藩兵が奮戦するも、薩摩軍側の銃砲撃に敗走。この鳥羽での開戦の銃声を聞いて伏見でも戦端が開かれる。こちらは薩長側が伏見奉行所を包囲。これに竹中重固率いる幕府軍、会津藩兵や新選組などが応戦する形となるが、伏見奉行所が炎上したこともあり、幕府軍側は退却を開始。幕府軍は大坂まで潰走。近江大津には新政府側に与した大村藩兵が入る。少数だったがこれを誤認した幕府軍が近江方面への進出を回避。 |
| 1月28日(慶応4年1月 4日) | 仁和寺宮嘉彰法親王(のちの小松宮)が、征討大将軍に任じられ、錦の御旗、節刀を授けられる。 |
| 1月28日(慶応4年1月 4日) | 大津に、新政府側に付いた佐土原藩、岡山藩、徳島藩の西国外様藩と、本来幕府の西国監視の立場にあった彦根藩が新政府側に寝返り加わる。 |
| 1月28日(慶応4年1月 4日) | 阿波沖海戦。阿波沖で、兵庫から鹿児島へ向かっていた薩摩藩の蒸気軍艦春日丸、翔凰丸、平運丸3隻と、幕府海軍の開陽丸が遭遇。砲撃戦となる。日本における蒸気船同士の初の海戦。両方被害は軽微で死傷者も出なかったが、翔凰丸はさきに薩摩藩邸焼き討ち事件で江戸から回航した際、幕府軍の追撃で損傷しており逃走できないと判断。拿捕されるのを避けるため自焼した。 |
| 1月29日(慶応4年1月 5日) | 山崎を守備していた津藩藤堂家が勅使四条隆平の説得を受けて新政府側に寝返る。 |
| 1月30日(慶応4年1月 6日) | 鳥羽・伏見の戦いは幕府軍の退却に伴い新政府軍の勝利に終わる。幕府軍は老中稲葉正邦の居城、淀城を拠点に反撃を企図するが、淀藩重臣らが独自に薩摩藩などと交渉し、入城を拒否。幕府軍は橋本方面まで敗走するが、ここで味方であったはずの津藩兵からの銃撃を受けて壊乱状態になる。 |
| 1月30日(慶応4年1月 6日) | 大坂城にいた徳川慶喜が、鳥羽・伏見の戦いの敗北と、薩長軍が「錦の御旗」を掲げたことを知り、大坂の幕府軍には抗戦を命じる一方で、夜半に会津藩主松平容保、桑名藩主松平定敬、老中板倉勝静・酒井忠惇らと大坂城を脱出。沖合の開陽丸に乗り、江戸へと引き上げる。このことが知られると幕府軍は戦意を失い事実上解散。徳川慶喜が戦線離脱した理由ははっきりしないが、のちに伊藤博文に語ったという「水戸徳川家は代々幕府よりも朝廷を重んじる」という庭訓が影響し、徳川家が朝敵になることを恐れたことは考えられる。 |
| 2月10日(慶応4年1月17日) | 若年寄兼外国総奉行の堀直虎(須坂藩藩主)が江戸城内で突如自刃。理由は不明。 |
| 2月13日(慶応4年1月20日) | 尾張藩で青松葉事件が起こる。藩の実権を握る元藩主徳川慶勝によって、藩内佐幕派「ふいご党」の主要メンバー渡辺在綱ら14名を斬首し、同派の家臣が多数が処分された事件。 |
| 2月20日(慶応4年1月27日) | 新政府によって大坂の大坂町奉行管轄域に「裁判所」が設置される(総督は醍醐忠順)。この「裁判所」とは、大名領地ではない旧幕府の奉行・代官・郡代の支配地だった地域を新政府が管轄する際に置いた行政機関(今でいう県庁に近い)のことで、司法裁判所ではない。順次、他の地方でも設置が進む。 |
| 3月 2日(慶応4年 2月 9日) | 徳川慶喜は、鳥羽・伏見の戦いで幕府軍の指揮を採った老中格松平正質、若年寄並陸軍奉行竹中重固、若年寄並外国奉行塚原昌義らを免職・登営禁止に処する。松平正質は領地の大多喜へ隠棲、竹中重固は抗戦を貫き箱館まで行く。塚原昌義は大坂町奉行並松本寿太夫とともにアメリカへ亡命(両者は明治後に帰国し許されて明治政府に仕える)。 |
| 3月 8日(慶応4年 2月15日) | 堺事件が起こる。堺で警備にあたっていた土佐藩士が上陸したフランス水兵を船に戻そうとしてトラブルになり、銃撃して11人を殺害。 |
| 3月16日(慶応4年 2月23日) | 堺事件で、土佐藩士20人がフランス人立ち会いのもと堺の妙国寺で切腹することになるが、腸を引き出して投げつけるなどの凄惨な状況と、藩士らが英雄扱いされることを恐れたフランス側が11人の切腹で中止し、9人を助命する。 |
| 3月29日(慶応4年 3月 6日) | 甲州勝沼の戦い。近藤勇率いる甲陽鎮撫隊と、板垣退助率いる新政府東山道軍迅衝隊および鳥取藩兵とが、甲府城争奪をめぐり、勝沼で戦う。新政府軍の圧勝に終わり甲陽鎮撫隊は壊走した。直接の兵数ではほぼ互角なうえ、江戸からも近く周辺にいた兵力を含めると幕府側が有利だったが、甲陽鎮撫隊は混成軍で統率も規律も悪く、近藤らは隊を維持するために宴会を催しながら進む有様で、逆に迅衝隊らは統率がよく、近代兵器の扱いにもなれており、先んじて甲府城を占拠できたことも勝敗を分けた。 |
| 4月 1日(慶応4年 3月 9日) | 梁田の戦い。下野国足利郡梁田宿にいた、古屋佐久左衛門(高松凌雲の兄)が率いる衝鋒隊約900人(旧幕府軍脱走兵400と新規動員兵500)に対し、川村純義率いる東山道軍のうち薩摩・長州・大垣の混成部隊200人が、早朝の霧の中を奇襲。衝鋒隊は混乱に陥り敗走。梁田宿は40軒余りが焼失。衝鋒隊は62名以上が戦死し、東山道軍は3名が戦死した。 |
| 4月 3日(慶応4年 3月12日) | 甲陽鎮撫隊の永倉新八・原田左之助らが、会津転戦について近藤勇に提案したところ、近藤が永倉らが家臣になる条件で話に応じると返答したことから対立。永倉・原田ら隊員たちは離脱して、元松前藩士の芳賀宜道と組んで靖兵隊を結成する。 |
| 4月 4日(慶応4年 3月13日) | 太政官布告により神仏分離令が発布される。それまでは神仏習合で、寺院の中に神社があることも一般的だったが、神仏分離を唱えた水戸学などの影響と、仏教の腐敗が要因となって分離令が出された。 |
| 4月 5日(慶応4年 3月12日) | 公家学校が新政府によって再開され、大学寮代となる。 |
| 4月13日(慶応4年 3月21日) | 天皇が大坂に行幸。 |
| 4月24日(慶応4年 4月 2日) | 沢辺琢磨・酒井篤礼らがニコライによってキリスト教に受洗。 |
| 5月 3日(慶応4年 4月11日) | 江戸城無血開城。 |
| 5月17日(慶応4年 4月25日) | 元新選組局長近藤勇、新政府軍の手で処刑される。流山の戦い後、新政府軍に投降(捕らえられたとも)、大久保大和と名乗ったが、新政府軍にいた御陵衛士の加納鷲雄、清原清らによって正体が露見し、土佐藩の谷干城の主張で処刑された。 |
| 5月27日(慶応4年閏4月 6日) | 幕府の外国奉行や軍艦奉行を務め、日本近代造船の礎を築いた小栗忠順が、隠棲先の上野国群馬郡権田村で、新政府東山道軍の軍監豊永貫一郎、原保太郎らの兵に捕縛され、この日、家臣3名とともに斬首される。取調もなく、一方的な処刑であった。遺族は会津藩に匿われた後、かつて小栗家に仕えていた三野村利左衛門(三井財閥中興の祖)に保護された。 |
| 6月10日(慶応4年閏4月20日) | 長州藩士で奥羽鎮撫総督府下参謀の世良修蔵が、福島城下の金沢屋で、仙台藩士や福島藩士ら20数名に襲われ、共にいた長州藩士勝見善太郎とともに斬首される。またこのあとに戻ってきた長州藩士松野儀助も殺害されている。襲われたのは、世良が会津藩への処分で強硬姿勢をとり、仙台藩などへ出兵を促したことに加え、新庄にいた同じ下参謀の大山格之助宛の書簡に「奥羽皆敵ト見テ逆撃之大策ニ至度候ニ付」とあったのを、福島藩士を経由して入手した仙台藩士らが激昂したため。この事件がのちの奥羽越列藩同盟が新政府と開戦する直接の原因となった。この書簡については、後に仙台藩が降伏する際に会津藩が偽造したものに乗ってしまったという趣旨の説明をしているが、世良の書簡は奥羽諸藩が会津討伐に消極的なため、兵力増援の方針を示したもの。 |
| 6月10日(慶応4年閏4月20日) | 白河藩阿部家の転封に伴い二本松藩が預かっていた白河城を、会津藩兵と新選組が攻撃、これを占領する。白河口の戦いのはじまり。 |
| 6月11日(慶応4年閏4月21日) | 新政府、政体書を発布。国家体制の基本方針、三権分立、官僚機構などについて定めたもの。府藩県三治制に移行。行政機関の「裁判所」を廃止し、旧幕府領のうち城代・京都所司代・奉行の管轄を「府」、それ以外を「県」、大名の領地は「藩」として引き続き統治させるもの。公式にはこのとき初めて大名領を「藩」と呼称するようになった。 |
| 6月20日(慶応4年 5月 1日) | 伊地知正治率いる新政府軍が白河城攻略を開始。激戦の末、新政府軍がこれを占領。会津藩、庄内藩、白河藩などは大敗し敗走。 |
| 6月22日(慶応4年 5月 3日) | 奥羽25藩によって奥羽列藩同盟が成立。会津・庄内両藩への寛大な処置を朝廷に直接求めるための盟約で、盟約書とともに太政官建白書もまとめられた。成立の日については諸説あり。 |
| 6月23日(慶応4年 5月 4日) | 奥羽列藩同盟に越後長岡藩も加入。 |
| 6月25日(慶応4年 5月 6日) | 奥羽列藩同盟に北越同盟5藩が加わり、奥羽越列藩同盟となる。各方面で薩長に対し武力で対応することや、江戸への侵攻、諸外国との交渉などの方針が決まる。 |
| 7月 4日(慶応4年 5月15日) | 上野山に籠った旧幕府側の彰義隊と長州・薩摩・土佐からなる新政府軍が衝突。通称上野戦争。新政府側の指揮官大村益次郎の采配で半日で新政府側勝利で終結。上野寛永寺は焼失。 |
| 7月13日(慶応4年 5月24日) | 徳川家が駿府70万石に移される。 |
| 7月19日(慶応4年 5月30日) | 病気療養のため新選組から離れていた沖田総司が江戸で病死。 |
| 8月 4日(慶応4年 6月16日) | 伏見宮家出身で、新政府に反発していた寛永寺貫主・日光輪王寺門跡の「輪王寺宮」が奥羽越列藩同盟の盟主となる。東武皇帝に擁立されたかどうかは諸説ある。のちの北白川宮能久親王。 |
| 8月 7日(慶応4年 6月19日) | 首都をどこに置くかで、木戸孝允と大木喬任が江戸を調査。 |
| 8月12日(慶応4年 6月24日) | 板垣退助率いる新政府軍の攻勢によって棚倉城が陥落。 |
| 8月18日 | ピエール・ジャンサンが日食の観測で新たな物質の輝線を発見する。後にノーマン・ロッキャーとエドワード・フランクランドによってヘリウムと名付けられる。 |
| 8月24日(慶応4年 7月 7日) | 新政府部内で江戸を首都にすることが決まる。 |
| 9月 3日(慶応4年 7月17日) | 東京奠都。明治天皇が詔勅「江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書」を発し、東京で政務に当たることを宣言して、江戸から改称した東京が事実上の首都となる。一部では「東亰」という文字も使われていた。 |
| 9月25日(慶応4年 8月10日) | 日本最初の本格的な西洋式ホテル「築地ホテル館」が完成。江戸開市にともなう外国人増加を想定し、イギリス公使ハリー・パークスの助言で、小栗忠順が計画を進めたものを引き継いで建設した。設計はリチャード・ブリジェンス。運営は建設を担当した清水組(のちの清水建設)。1部2階建て部屋数102室とかなり大きな和洋折衷の建物で、改称したばかりの「東京」の新名所となった。なお、オランダ商館長の宿泊所を除いて、日本最初のホテルは1860年に横浜居留地でオープンした日本家屋の「横濱ホテル」(ホテルフフナーゲル)。幕末には横浜に同様の宿泊所が複数あったが、1866年の火災で全て焼失している。 |
| 10月 6日(慶応4年 8月21日) | 会津戦争で、新政府軍の薩摩・土佐・長州・佐土原の諸藩の部隊が、母成峠の戦いで、会津や新選組ら旧幕府勢を打ち破る。 |
| 10月 8日(慶応4年 8月23日) | 会津戦争で、新政府軍が若松城下に突入。白虎隊のうち士中二番隊に属する20人が、若松城周辺の火災を落城と誤認し飯盛山で自決を図る。飯沼貞吉を除く全員が死亡する。 |
| 10月23日(慶応4年 9月 8日) | 明治に改元。一世一元の詔が出される。法的には慶応4年1月1日(1868年1月25日)より明治としている。 |
| 10月26日(慶応4年/明治元年 9月11日) | 咸臨丸事件。榎本武揚率いる旧幕府艦隊に参加し、暴風雨で破損し下田港で修理を受けていた咸臨丸を、新政府軍が攻撃。多数の死傷者を出す。遺体は逆賊として放置されていたが、侠客清水次郎長が収容して埋葬した。 |
| 10月31日(慶応4年/明治元年 9月16日) | 国学・神道の皇学所と、漢学・儒学の漢学所の設立が決定し、大学寮代が廃止される。 |
| 11月 4日(慶応4年/明治元年 9月20日) | 盛岡藩が新政府軍に降伏。 |
| 11月 6日(慶応4年/明治元年 9月22日) | 会津藩が新政府軍に降伏。会津戦争が終結。終結後に藩への負担に耐えかねた農民一揆が起こるなど混乱が継続。会津藩も斗南への転封処分を受けることになる。 |
| 11月 7日(慶応4年/明治元年 9月23日) | 野辺地戦争。新政府に降伏したばかりの盛岡藩の野辺地地区を、新政府側の弘前藩・黒石藩の藩兵180人余りが襲撃。盛岡藩・八戸藩藩兵に撃退される。新政府は調査に乗り出すが、両藩による私戦ということで処分は行わなかった。 |
| 11月 9日(慶応4年/明治元年 9月25日) | 濁川焼き討ち事件。弘前藩兵30人ほどが盛岡藩領の濁川村を襲い焼き討ちを行って引き上げる。村にいた藩士1名が応戦して戦死。野辺地戦争同様、新政府が調査に乗り出し、両藩の私戦として処理。野辺地戦争と濁川事件は、新政府側に付いたものの事態の推移を見守って消極的だった弘前藩が、急ぎ実績を作ろうとして行ったとする見方もある。 |
| 11月10日(慶応4年/明治元年 9月26日) | 庄内藩が新政府軍に降伏。奥羽越列藩同盟は全て降伏する。なお庄内藩は藩外に進攻して戦線を拡大していたこともあり、降伏時まで新政府軍の藩内侵攻を阻止している。また降伏後の藩主転封の措置に対し豪商本間家と領民が上杉家の協力などで30万両を集めて新政府に献上し嘆願するなどしたことから、庄内藩は比較的軽い処分で済んだ。またこの処分は西郷隆盛の意向があったとして、以後、庄内と薩摩との間で交流が行われた。 |
| 11月27日 | ワシタ川の虐殺。アメリカ陸軍のカスター連隊が、シャイアン族バンドの野営を襲撃し、女子どもも含めて虐殺する。 |
| 1869年 | |
| 1月27日(明治元年12月15日) | 戊辰戦争のさなか、旧幕府軍の関係者によって、いわゆる「蝦夷共和国」が発足。入れ札により榎本武揚が総裁となる。 |
| 3月11日 | フランス人宣教師のアルマン・ダヴィドが、現在の四川省宝興県でジャイアントパンダの毛皮を目撃。西洋人にその存在を知られるきっかけとなる。 |
| 5月16日 | ポーランドの大工ヤン・ヴネンクが、オーストリア・ハンガリー帝国のオトポルイシェフで行われたカーニバルで、グライダー飛行を行い墜落、まもなく死亡。ヴネンクは鳥の翼の形状をもとにグライダーを設計し、何度か飛行に成功していた記録がある。ただ航空研究家ではなかったため、グライダーに関する技術的な記録が残されていない。 |
| 6月20日(明治2年 5月11日) | 土方歳三が箱館戦争で一本木関門の防戦中に馬上で銃弾に当たり戦死。 |
| 6月27日(明治2年 5月18日) | 会津藩家老の萱野長修が戊辰戦争での会津藩側の責任者として処刑される。 |
| 7月25日(明治2年 6月17日) | 版籍奉還。大名が領地と領民を朝廷に奉還する。藩主は知藩事として旧所領の管轄官となり、旧領の収入の10分の1を家禄とする。また同日行政官布達54号に基づき、公家142家は公家華族、諸侯285家は武家華族に列せられる。なお、この時は華族に階級はなかった。 |
| 7月31日(明治2年 6月23日) | 盛岡藩家老の楢山佐渡が、戊辰戦争の盛岡藩の責任者として処刑される。 |
| 8月15日(明治2年 7月 8日) | 職員令が発布され、太政官制が導入される。神祇官と太政官、太政官の下には民部省・刑部省・大蔵省・兵部省・外務省・宮内省が置かれる。政体書体制は終了。 |
| 8月19日(明治2年 7月12日) | 高輪談判。イギリス・フランス・イタリア・ドイツ・アメリカの5カ国の駐日公使が、新政府に対して、贋貨の回収と国際水準の貨幣制度の導入を求める。もともと幕末の安政五カ国条約に付属した改税約書で品質の安定した貨幣の鋳造を求められていたが、幕府・諸藩ともこれに従わず、明治新政府も質の低い貨幣を鋳造し続けていたため、業を煮やしたパークスらが直談判を行ったもの。 |
| 10月 8日(明治2年 9月 4日) | 兵部大輔の大村益次郎が大阪で静間彦太郎、安達幸之助と会食中に神代直人、団伸二郎ら8人の刺客に襲われ重症を負う。静間と安達は死亡。 |
| 12月 7日(明治2年11月 5日) | 大村益次郎が大阪病院で死亡。足を切断する手術をうける際に勅許が必要となって手遅れになったともいわれる。 |
| 1870年 | |
| 1月 1日(明治2年11月30日) | 長州藩の奇兵隊、振武隊などの諸隊で解雇された兵士らが脱退騒動を引き起こす。 |
| 1月 3日(明治2年12月 2日) | 旗本領の上知が決定され、府・藩・県に吸収される。 |
| 2月 3日(明治3年 1月 3日) | 「大教宣布の詔」が発布される。国教を神道とするもので、先の神仏分離令をより鮮明にしたもの。これを受けて、各地で廃仏毀釈運動が吹き荒れることになるが、この詔自体は仏教を排斥するものではない。また廃仏毀釈運動には、江戸時代に幕府の権威と結びついた仏教諸勢力が腐敗したことも背景にある。 |
| 2月13日(明治3年 1月13日) | 脱退騒動を引き起こした兵士らが大森県浜田裁判所を襲う。 |
| 2月24日(明治3年 1月24日) | 脱退騒動を引き起こした兵士らが山口を襲い藩兵と交戦。更に勢力を拡大する。 |
| 3月12日(明治3年 2月11日) | 木戸孝允率いる鎮圧軍が脱退兵の軍勢を打ち破る。最終的に脱退兵らは60人が戦死し、133人が処刑された。 |
| 5月 1日 | 世界最初の近代高層ビルと言われるエクイタブル生命保険ビルがニューヨーク市に完成。高さ40m。 |
| 6月20日 | 「天津教案」事件。中国天津で起きた幼児誘拐事件に対し、民衆らが西洋のキリスト教関係者を疑い教会を包囲。そこへ天津の知県劉傑と、フランスの駐天津領事のアンリ・フォンタニールが来て争いになり、民衆が教会を襲撃。フォンタニールをはじめ、フランス人ら教会関係者が多数殺害される。 |
| 6月21日 | スペインの王位継承問題で、プロイセン国王ヴィルヘルム1世が、ホーエンツォレルン本家であるホーエンツォレルン=ジグマリンゲン家のレオポルドを後継とすることを承認。フランスは猛反発する。 |
| 6月24日 | 「天津教案」事件を受けて、ヨーロッパ7カ国の艦隊が天津に来て清朝政府に抗議。のちに曽国藩が交渉に当たり、関係者の処刑と賠償金の支払いで解決するも、民衆の不満は逆に高まる結果となった。 |
| 7月12日 | スペインの王位継承問題で、フランスの反発を受けて、ヴィルヘルム1世と、レオポルドが、スペイン王位を辞退することを決定。 |
| 7月13日 | スペインの王位継承問題で、フランス外相グラモン公爵が、ドイツのバート・エムスに滞在中のプロイセン国王ヴィルヘルム1世にベネデッティ伯爵を大使として派遣し、今回だけでなく将来に渡って、ホーエンツォレルン家からスペイン王位候補者を出さないよう文書を求める。これに対しヴィルヘルム1世は無礼であるとして拒否。宰相ビスマルクに事後を委任。 |
| 7月14日 | エムス電報事件。ヴィルヘルム1世から電報を受け取った宰相ビスマルクは、電報文の一部を意図的に省略して、フランス大使が無礼な振る舞いをしたために国王が激怒して会見も拒否したように装って新聞等に公表。これを知ったプロイセン、フランス両国民は一気に過熱し、相手国に対し戦争を主張。普仏戦争へと発展する。また従来プロイセン主導の北ドイツ連邦とは一線を画していた南ドイツ諸国も、プロイセンに同調し、ドイツ統一へのきっかけにもなった。 |
| 7月15日 | エムス電報事件を受けて、フランスでは上下議会が圧倒的多数で開戦を議決。閣議も開戦を決定する。ナポレオン3世は戦争には消極的だったが、閣僚、議会、世論に押される形で開戦を決意。 |
| 7月19日 | ナポレオン3世がプロイセンに宣戦布告。対するプロイセンも宣戦の詔勅を発して普仏戦争が開戦。プロイセンは普墺戦争勝利から間もなく、フランスに対して軍事力で優位にあったため、ドイツ統一を目論むビスマルクの思惑通りになったと言われる。 |
| 7月28日 | ナポレオン3世がルイ皇太子とともに出陣。皇后ウジェーヌの強い意向があったとされる。 |
| 8月 2日 | 普仏両軍がザールブリュッケンで衝突。フランス軍が占領。 |
| 8月 4日 | ヴィサンブールの戦い。フランス軍は大きな損害を出し退却。 |
| 8月 5日 | スピシャランの戦い。フロサール率いるフランス第2軍に対し、プロイセン軍が猛攻を仕掛け、フロサールは退却。 |
| 8月 6日 | ヴルトの戦い。南ドイツ諸国も参戦し、圧倒的兵力でフランス軍に勝利する。 |
| 8月15日(明治3年 7月19日) | 太政官札贋造事件で摘発が行われる。福岡藩が財政難のため、密かに太政官札の偽札を作り、それを各地で使用していたことを知った新政府が密かに証拠を集め、この日、弾正台の渡辺昇らが博多の福岡藩庁・通商局・銀会所を一斉に捜索。関係者らを摘発した。 |
| 8月16日 | マルス・ラ・トゥールの戦い。フランス軍は兵力で大きく勝っていたが大敗。 |
| 8月18日 | グラヴロットの戦い。フランス・プロイセン両軍最大の戦闘となる。損害ではプロイセン側のほうが大きかったが、フランス軍側がメス要塞まで敗走してしまう。プロイセン軍はメスを包囲。ナポレオン3世はメス救援のため自ら軍を率いる。 |
| 8月30日 | ボーモンの戦い。メス救援に向かっていたフランス軍を、プロイセン軍からムーズ軍団を分けて迎撃、プロイセン軍も大きな被害を出すものの、フランス軍はセダンに敗走。 |
| 9月 1日 | セダンの戦い。セダンで包囲下に置かれたナポレオン3世率いるフランス軍が、包囲しているプロイセン軍に対し攻撃を仕掛けるが、失敗に終わる。 |
| 9月 2日 | セダンから脱出できなかった皇帝ナポレオン3世は、10万4千の兵とともにプロイセンに降伏。なお、この時点でフランス軍にはメス市に籠もるバゼーヌ軍18万が残っていた。プロイセン王ヴィルヘルムは、ナポレオン3世をヴィルヘルムスヘーエ城にて暮らすことを認める。 |
| 9月 2日(明治3年 8月 7日) | 福井藩越前府中で武生騒動が勃発。福井藩の重臣で越前府中2万石の領主だった本多副元を福井藩が府中支配を外して士族の身分にしたことで、本多家の家臣が本多家の府中領主の地位と家格の回復を新政府に陳情したことを受け、福井藩が関係者を捕縛。これに反発した領民が暴動を起こす。藩の物産を扱っていた松井耕雪・山本怡仙・松村友松ら商家14軒が襲撃を受ける。越前府中本多家は福井藩の陪臣ながら江戸幕府からは大名並の待遇を受けていたことが背景にあり、これに凶作などでの困窮が影響したため。 |
| 9月 3日(明治3年 8月 8日) | 武生騒動を受けて福井藩は鎮圧に乗り出し、本多家の家臣23人、町人91人、村人33人などを捕縛。その後、竹内円、大雲蘭渓と町人11人が獄死、米屋庄八、箒屋末吉が処刑される。元海援隊士で福井藩士の関善臣は藩上層部との対立からこの事件を口実に処刑されかかるが明治政府に助けられた。本多副元は明治12年に華族に列することになり、同17年に男爵となった。 |
| 9月 4日 | 皇帝ナポレオン3世がプロイセンに降伏したとの情報が入り、フランス国内でルイ・トロシュ、ジュール・ファーヴル、レオン・ガンベタらによる政変が勃発。フランス第二帝政が崩壊。フランスの君主制の終焉となる。プロイセンはフランス臨時国防政府に対し和平を提案。 |
| 9月 6日 | フランス臨時国防政府は戦争継続を決定。プロイセンに宣戦布告。 |
| 9月19日 | プロイセン軍、パリを包囲。パリ攻囲戦が始まる。なお、パリは包囲されたがフランス各地は占領されておらず各地でプロイセンに対する抵抗戦が激化する。 |
| 10月 7日 | フランス臨時国防政府の内相レオン・ガンベタが、写真家で気球研究者だったナダールの協力で、軍事用気球「アルマン・バルベス」号に乗って、パリを包囲しているプロイセン軍を飛び越えて脱出。トゥールに行き、ここで徴兵と抵抗組織を編成する。 |
| 10月13日(明治3年 9月19日) | 明治政府から平民苗字許可令が出される。 |
| 10月18日(明治3年 9月24日) | 明治政府が府県物産表を交付。近代日本最初の国家統計データ。 |
| 10月27日 | メスのフランス軍18万もプロイセンに降伏。 |
| 11月 2日(明治3年10月 9日) | 岩崎弥太郎が土佐開成社(九十九商会)を引き受ける。後の三菱商会。 |
| 11月 9日 | クルミエの戦い。フランス軍がプロイセン軍に勝利する。 |
| 1871年 | |
| 1月 3日(明治3年11月13日) | 徴兵規則が制定される。徴兵令の前段階の規則で、全国の府・藩・県から1万石に付き5人を、身分を問わずに徴兵するというもの。 |
| 1月18日 | 普仏戦争のパリ攻略戦のさなか、パリ郊外にあるヴェルサイユ宮殿でプロイセン王ヴィルヘルム1世が皇帝に即位し、ドイツ帝国が成立。 |
| 1月25日 | フランス臨時国防政府のトロシュ首相が辞任。ジュール・ファーブルが首相となる。 |
| 1月28日 | プロイセン軍がパリを占領し、休戦協定が成立。 |
| 2月 6日 | フランス臨時国防政府、全軍の休戦を命令。 |
| 2月 8日 | フランス議会選挙。 |
| 2月17日 | フランス、アドルフ・ティエール政権樹立。 |
| 2月23日(明治4年 1月 5日) | 寺社領も上知となり、府・藩・県に吸収される。それまでは広大な領地、広い境内を持つ寺院も少なくなかった。また、この頃までに多くの寺院が廃仏毀釈の被害にあっており、消滅した有力寺院も少なくない。また多くの施設・文化財が失われている。 |
| 2月26日 | フランス・ティエール政権と、ドイツ・ビスマルク政権との間で、講和予備条約調印。フランスはドイツ系住民の多いアルザス=ロレーヌ地方を失い、50億フランの賠償金を支払うことになった。 |
| 2月27日(明治4年 1月 9日) | 深夜、広沢真臣が自宅で惨殺される(広沢真臣暗殺事件)。犯人は不明。 |
| 3月 1日 | プロイセン軍が、戦勝パレードのためパリに入る。3日まで同市を占拠し、市民や国民衛兵の反発を買う。 |
| 3月18日 | モンマルトルを占拠したパリ市民らに対し鎮圧部隊が派遣されるが、逆に市民の抵抗によってルコント将軍らが殺害される。ティエール政権は、首都をパリからベルサイユへ移す。 |
| 3月28日 | パリ市民らによる革命自治政府樹立宣言。いわゆるパリ・コミューン。ティエール政権は、革命政府鎮圧のため、プロイセンと交渉して、捕虜となっているフランス人兵士の解放を求める。 |
| 4月 2日 | フランス・ベルサイユ政府のマクマオン元帥率いる軍が、パリ・コミューンに対し攻撃を開始。 |
| 4月 2日(明治4年 2月13日) | 御親兵が編成される。廃藩置県実施時の不測の事態に備えて、薩摩・長州・土佐より天皇直属の兵として置かれた。兵数は8000人未満。薩摩兵を上京させるのに合わせて、当時鹿児島にいた西郷隆盛を政府に加える目的もあったとされる。 |
| 4月26日(明治4年 3月 7日) | 広沢真臣暗殺事件の捜査中に、公卿の愛宕通旭と外山光輔、元長州藩士大楽源太郎らによるクーデター計画が発覚。外山光輔が逮捕される(二卿事件)。 |
| 4月29日(明治4年 3月10日) | クーデター計画に関わったとして久留米藩への捜査がはじまり、藩知事有馬頼咸が弾正台の捜査を受け幽閉される(二卿事件)。 |
| 5月 2日(明治4年 3月13日) | 熊本藩から久留米藩へ兵が出され、久留米城が接収される。久留米藩参政で攘夷派の水野正名らが逮捕される(二卿事件・久留米藩難事件)。同藩に匿われていた大楽源太郎は逃亡。 |
| 5月 3日(明治4年 3月14日) | 愛宕通旭が逮捕される(二卿事件)。 |
| 5月 5日(明治4年 3月16日) | 大楽源太郎が久留米藩応変隊の川島澄之助らの手で殺害される(二卿事件)。 |
| 5月10日 | フランクフルト講和条約が締結。フランスとプロイセンの講和成立。予備条約で決まったアルザス=ロレーヌ地方の割譲、50億フランの賠償金がフランスに課せられる。またその賠償金を支払うことに同意するまでの間、フランス北東側はプロイセン軍が占領下に置いた。 |
| 5月21日 | フランス・ベルサイユ政権軍がパリ・コミューン政府のパリ市内に突入。パリ市街戦「血の週間」が始まる。 |
| 5月28日 | ベルサイユ政権軍がパリ市を制圧。パリ・コミューン政府崩壊。ベルサイユ軍による虐殺事件が起こり、その後多数の関係者が処刑された。また市街戦時にはコミューン側も市内にいたブルジョア銀行家などを殺害している。 |
| 6月10日 | 辛未洋擾。ジェネラル・シャーマン号事件の調査に来た米国アジア艦隊が朝鮮江華島で砲台と砲撃戦。その後、海兵隊が島に上陸。 |
| 6月27日(明治4年 5月10日) | 新貨条例公布。四進法の江戸時代の貨幣「両・分・朱」をあらためて、現代の通貨単位「円・銭・厘」とし、十進法に切り替えた法律。 |
| 7月 2日 | フランス議会選挙。国民議会が成立。 |
| 7月10日(明治4年 5月23日) | 太政官布告第251号により古器旧物保存方が布告される。全国で吹き荒れた廃仏毀釈運動による文化財の被害を受けて、町田久成らが提言し調査する『壬申検査』が始まる。町田のほか古美術研究者蜷川式胤、写真家横山松三郎、洋画家高橋由一らが協力して記録を進める。 |
| 8月17日(明治4年 7月 2日) | 前年に摘発された福岡藩による太政官札贋造事件の弾正台による判決がくだされる。黒田藩の最後の藩主で知藩事の黒田長知は免職され閉門。贋造に深く関与した大参事の立花増美、矢野安雄ら5名を処刑、ほか100名余りが処罰された。発案者の通商局山本一心はすでに死亡しており、同じく通商局の郡成巳は獄死した。太政官札贋造は各藩で行われ、二分金に至っては旧幕府、新政府、各藩も贋造していた。各国から批判を受けていた明治政府は、偽札を広く使用しその証拠が明白な福岡藩を見せしめに処罰した面もある。ただ福岡藩前藩主が島津家の出身だったこともあり、西郷隆盛の執り成しで処分は軽減されたという。知藩事は黒田家には継がせず、有栖川宮熾仁親王が就任。そのため、まもなく廃藩置県となったが、福岡藩黒田家は最後に改易された藩とする見方もある。 |
| 8月19日(明治4年 7月 4日) | 太政官布告322号により「大小神社氏子取調」が発布される。江戸時代の寺院に登録する民衆管理制度「寺請制度」を神社単位に置き換えたもの。寺請制度によって権威・権力と結びついた寺院が腐敗したことに対する民衆の不満も背景にあったとされる。氏子調制度は明治6年5月29日で廃止された。 |
| 8月29日(明治4年 7月14日) | 廃藩置県。全国の藩が一斉に廃止となり、府県制へ移行。統一国家体制樹立の目的とともに、維新前後の戦乱などで各藩の財政が深刻化していた事情もあった。そのため、大名らの抵抗は殆どなかった。地方分権が一気に中央集権へと抵抗もなく移行した珍しい例。 |
| 8月31日 | アドルフ・ティエールが正式にフランス大統領となり、実質のフランス第三共和政が発足。ただし内実は、共和派、オルレアン派、ボナパルト派、王党派などが入り乱れる不安定な体制であった。 |
| 10月 8日 | シカゴ大火。死者250人以上、焼失建造物17400棟以上。高層建築が増えるきっかけとなった。 |
| 10月11日 | ハインリッヒ・シュリーマンがトロイアの発掘に着手。 |
| 1872年 | |
| 1月12日(明治4年12月 3日) | 二卿事件の首謀者、愛宕通旭と外山光輔が切腹。 |
| 1月13日(明治4年12月 4日) | 創作物などで人斬りと称される幕末の尊皇攘夷志士、河上彦斎が明治政府によって処刑される。表向きは二卿事件や広沢真臣暗殺事件への関与嫌疑によるものだが、開国和親に転じた明治政府にとって、尊攘派の有力者だった河上彦斎の存在は危険と見られたため。 |
| 3月 1日 | 世界最初の国立公園「イエローストーン国立公園」設置。 |
| 4月 5日(明治5年 2月28日) | 明治政府が、兵部省を廃止して、陸軍省と海軍省を設置。 |
| 4月16日(明治5年 3月 9日) | 近衛条例制定。「近衛」兵の設立へ。 |
| 7月 9日(明治5年 6月 4日) | マリア・ルス号事件。横浜港に寄港していたペルー船籍のマリア・ルス号から数人の清国人が逃亡しイギリス軍艦アイアンデューク号に助けを求める。イギリス政府は清国人が奴隷として輸送される途中であったと見て、日本政府に救助を要請。外務卿副島種臣の判断で、大江卓神奈川権令が指揮し、船内捜索で230人の清国人が劣悪な環境に置かれているのを発見する。 |
| 7月26日(明治5年 6月21日) | 元土佐藩主山内容堂が死去。幕末四賢侯の一人。豪放な性格で武術も得意。気に入れば相模屋政五郎のような身分の低いものとも親しく付き合った。長宗我部系上士の吉田東洋を抜擢し藩政改革を行う一方、長宗我部系郷士主体の土佐勤皇党を弾圧。酒豪の上感情に左右されやすく、「酔えば勤王覚めれば佐幕」などと揶揄された。良くも悪くも幕末史を動かした人物の一人。 |
| 8月 7日(明治5年 7月 4日) | マリア・ルス号事件で、明治政府は同船の横浜出港を禁止。 |
| 8月30日(明治5年 7月27日) | マリア・ルス号事件に関する特設裁判で、清国人を解放することを条件に出港を許可す |
| 8月30日(明治5年 7月27日) | マリア・ルス号事件に関する特設裁判で、清国人を解放することを条件に出港を許可する判決が出される。これに対し同船側は不服を申し出る。また同船側弁護士フレデリック・ヴィクター・ディキンズは、奴隷問題について、日本の芸娼妓制度も人身売買と指摘。この事件はさらにペルー政府が日本を訴え国際仲裁裁判に発展した。 |
| 10月 1日 | ベルギーに「国際寝台車会社」が設立される。のちオリエント急行を運行した会社。 |
| 10月14日(明治5年 9月12日) | 日本で始めての、新橋駅-横浜駅の鉄道開業。この時の新橋駅は現在の新橋駅ではなく、汐留にあった旧新橋駅で、現在の新橋駅は1909年開業の旧烏森駅。 |
| 10月21日 | サンフアン諸島国境紛争に、ドイツ皇帝が仲介し、アメリカ側の主張に基づいて、イギリスとアメリカの両国が合意。国境が確定する。 |
| 10月22日 | 国際寝台車会社が、ベルギーのオーステンデとドイツのベルリンの間で特急の運行をはじめる。 |
| 11月 2日(明治5年10月 2日) | 芸娼妓解放令。マリア・ルス号事件裁判で芸娼妓制度が人権問題にされたため、借金によって強制奉公させられてる遊女を解放する目的で発布される。急に決定されたことから、解放娼妓の社会復帰等政策がなかったため、実質私娼の身分等で妓楼に残ることになり、効果は低かったと言われる。一方で根本原因である貧困対策、女性教育普及、女性を雇用する軽工業発展へのきっかけにもなった。 |
| 12月 4日 | メアリー・セレスト号事件。10人が乗っていた同船が、アゾレス諸島付近の海域で無人で漂流しているのを、デイ・グラツィア号が発見。積み荷の工業用アルコールと食料はほぼそのままだったが、船内は荒らされており、救命ボートも降ろされていた。何が起きたのか、乗っていた10名も不明のまま。積み荷のアルコールが引火したのに驚き急いで脱出したが遭難したという説が有力。のちにコナン・ドイルが小説に書いたことで有名になり、まるで人だけがこつ然と消えたかのようなオカルト的な話として広まった。 |
| 12月15日(明治5年11月15日) | 太陽暦への変更に合わせて、太政官布告第342号により、神武天皇即位紀元(いわゆる「皇紀」)が制定される。紀元前660年を基準とした暦。 |
| 12月28日(明治5年11月28日) | 徴兵告諭が出される。 |
| 12月29日(明治5年11月29日) | 奇兵隊出身の御用商人山城屋和助(野村三千三)が陸軍の公金およそ65万円(国家歳入の1%に及ぶ)を不正に融資を受けて生糸相場に手を出し、莫大な負債を抱えた責任を取るため陸軍省内で割腹自殺。通称山城屋事件。 |
| 1873年(明治6年) | |
| 1月 1日(明治5年12月 3日) | 明治政府が、太陰暦(天保暦)をやめ、太陽暦を採用。明治5年12月3日を同6年1月1日と改める改暦を実施。 |
| 1月 8日 | ハワイ王国の第5代国王カメハメハ5世が死去したため、憲法により王国初の選挙が行われ、カライママフ系のウィリアム・チャールズ・ルナリロが即位する。 |
| 1月10日 | 徴兵令施行。 |
| 2月 7日 | 太政官布告で敵討ちが禁止される。 |
| 6月12日 | 筑前竹槍一揆。この日、干ばつに苦しむ農民らが、参拝していた嘉麻郡高倉村の日吉神社で目取り(米相場の情報を伝える旗振りなどの手段)を見つける。米相場が操作されているから高騰していると農民らは反発。 |
| 6月13日 | 筑前竹槍一揆。高倉村の農民らが、猪膝宿で目取りを行っていた相撲取りの筆海の元を訪れ、目取りの中止を訴えたところ争乱となり、逮捕者が続出。 |
| 6月16日 | 筑前竹槍一揆。逮捕者が出たことを知った嘉麻郡の農民らが、猪膝宿の筆海をはじめ目取りの関係者、商人宅を襲撃。大規模な一揆に拡大。一揆勢は県庁のある福岡へと向かい、それに次々と民衆が参加。総勢10万人に達する。 |
| 6月20日 | 筑前竹槍一揆。一揆勢は博多市内へ入り、豪商らを次々と襲う。県は黒田藩の最後の大老だった三奈木黒田一雄らが説得に当たる。 |
| 6月21日 | 筑前竹槍一揆。県は一揆勢に対し武力鎮圧を決定。 |
| 6月25日 | 筑前竹槍一揆はほぼ終息するが、4590軒が被害にあい、70人以上が死傷した。一揆を主導したなどで4人が処刑、何かしらの処罰を受けた人は膨大な数に上る。一揆勢の説得に当たったがうまくいかなかったことから鎮撫総督の中村用六ら3人が自殺、県参事らは罷免された。 |
| 7月28日 | 税制の統一のため、地租改正法と地租改正条例を公布。年貢・田租に代わる地価の3%の地租を定める。トラブルが相次ぎ、地租改正一揆が各地で起こる。 |
| 夏、北極海の島スピッツベルゲン島にあるスヴェンスクフーセットの小屋で前年から滞在していた17人のノルウェー人アザラシ漁師が死亡しているのが発見される。17人は前年に島に足止めされたグループのメンバーで、食料のある同小屋に調達しに行ったきり戻ってこず、この夏に救助隊が調査に行き全員が病死していたことが判明した。長いこと壊血病と見られていたが、2008年の再調査の結果、当時の缶詰に使われていた鉛による中毒死と判明した。 | |
| 10月15日 | 征韓論の是非を巡る対立で、西郷隆盛が下野をちらつかせて三条実美を脅し、朝鮮への使節派遣を決定させる。しかし責任を感じた三条実美はまもなく病気で倒れる。 |
| 10月23日 | 明治六年政変。三条実美の代わりに岩倉具視や大久保利通らが主導権を握り、朝鮮への使節派遣は延期。西郷隆盛、板垣退助、江藤新平らが下野する。 |
| 1874年(明治7年) | |
| 1月14日 | 喰違の変。赤坂にある仮皇居を退出した岩倉具視が、赤坂喰違坂で高知県士族武市熊吉、武市喜久馬、山崎則雄、島崎直方、下村義明、岩田正彦、中山泰道、中西茂樹、沢田悦弥太の9人に襲われ負傷。 |
| 1月17日 | 武市熊吉ら9人が逮捕される。 |
| 2月 1日 | 佐賀の乱。前参議江藤新平らを擁立した征韓党などが佐賀で官金預かり業者小野組の店舗を襲う。政府、これを反乱とみなす。 |
| 2月 3日 | ハワイ王国の第6代国王ルナリロが肺結核で病死する。 |
| 2月 4日 | 政府、熊本鎮台司令官谷干城に佐賀鎮圧を命令。谷は反対したが派兵を決める。 |
| 2月 5日 | 三条実美、佐賀出身で初代秋田県権令(知事)の島義勇に佐賀鎮撫の説得を依頼。島は受諾して佐賀へ向かうも、新任の岩村高俊県令と同船した際の岩村の態度に反発し、江藤らの軍に加わることを決意。憂国党代表に擁立される。 |
| 2月 9日 | 内務卿大久保利通、佐賀に対して、東京鎮台、大阪鎮台を動員して征討軍を派遣。 |
| 2月12日 | ハワイ王国の第7代国王デイヴィッド・カラカウアが即位する。 |
| 2月15日 | 佐賀県令岩村高俊と江藤新平らの交渉が成立せず、江藤らは佐賀城の佐賀鎮台を攻撃。鎮台軍は大きな被害を出して敗走。 |
| 2月20日 | 大久保利通、政府軍を率いて博多に到着。 |
| 2月22日 | 政府軍本隊が朝日山で、佐賀軍と衝突。 |
| 2月23日 | 寒津川・田手川で、政府軍と佐賀軍が戦い、佐賀軍が敗走。情勢打開のため、江藤新平は味方にも内密に離脱し鹿児島の西郷隆盛の元へ支援要請に向かう。 |
| 2月27日 | 政府軍が佐賀軍に対し総攻撃を行う。佐賀軍は大敗を喫する。乱は事実上終結。 |
| 2月27日 | 江藤新平、鹿児島で西郷隆盛に支援を要請するも同意を得られず、高知県へ向かう。 |
| 2月27日 | 島義勇、鹿児島で逮捕される。 |
| 3月29日 | 江藤新平、高知県で逮捕される。 |
| 4月13日 | 大久保利通、助命嘆願を黙殺し江藤新平、島義勇を処刑。 |
| 5月 6日 | 日本による台湾出兵。 |
| 7月 9日 | 喰違の変の首謀者らに死刑判決が下る。 |
| 10月 9日 | 万国郵便連合が設立される。 |
| 10月11日 | 新橋駅構内で、ポイント通過中の機関車と貨車が脱線転覆、客車が脱線する事故が起こる。日本で最初の鉄道事故とみられる。死傷者はなし。 |
| 1875年(明治8年) | |
| 1月 8日 | 外国郵便の業務が日本に移管され、横浜郵便局(現・横浜港郵便局)で開業式が行われる。 |
| 2月13日 | 平民苗字必称義務令により、国民は公的に名字を持つことになる(江戸時代は公家や武士以外の百姓や町人らの名字は公的に使えなかっただけで、名字がなかったわけではない)。 |
| 4月 4日 | 花見のため水戸家を訪れた明治天皇に木村屋のあんパンが提供される。天皇・皇后ともこれを非常に気に入り、宮中御用達となる。 |
| 5月20日 | パリでメートル条約制定。フランス革命時に定められたメートル法をもとに度量衡の国際基準を制定。またこの基準となるメートル原器とキログラム原器を正確で安定的なものに置き換えることも話し合われた。 |
| 6月 1日 | 気象記念日。東京気象台が気象観測を始める。 |
| 9月20日 | 江華島事件。22日にかけて、朝鮮の首都漢城に近い漢江河口の江華島付近で、測量中の日本の軍艦雲揚と朝鮮側の砲台が交戦した事件。 |
| 1876年(明治9年) | |
| 2月26日 | 前年の江華島事件を受けて、朝鮮の江華島において、日本と朝鮮の間で日朝修好条規が締結される。日本側は外交関係の樹立と開港の目標が達成できたことで、朝鮮側は冊封国としての体面を保てることで成立した。しかし日本側が圧力をかけたこと、当初朝鮮側が問題にしていなかった関税や裁判権の問題が噴出したこと、欧米がこれに倣って開国を迫ったことで、後々朝鮮の反感が膨らむこととなった。 |
| 3月 3日 | ケンタッキー州のランキン近郊で、空から生肉のようなものが降ってくるという現象が起きニュースとなる。竜巻に巻き込まれた動物の肉という説の他に、肉ではなく塊を作る藍藻のネンジュモなどの説もある。 |
| 3月17日 | アメリカ陸軍と先住民とのパウダー川の戦い。 |
| 5月 1日 | イギリスのヴィクトリア女王が「インド帝国皇帝」に推戴される。 |
| 5月 8日 | タスマニアン・アボリジニの最後の一人と呼ばれた女性トルガナンナ(トルガニニ)が死去。白人によるアボリジニ迫害を生き延びた生き証人とも言える人物。タスマニアン・アボリジニは他にも生き残っているため、彼女が最後ではないが、その生涯(及び死後の扱い)が取り上げられたことから文化的に大きな影響を残しており、地名などにもなっている。 |
| 5月 9日 | 上野山の寛永寺の境内跡に上野公園開園。 |
| 6月17日 | アメリカ陸軍と先住民とのローズバッドの戦い。 |
| 6月25日 | リトルビッグホーンの戦い(グリージーグラス川の戦い)。アメリカ陸軍のカスター第7騎兵連隊長がスー族やシャイアン族を掃滅しようとして奇襲をかけるが逆襲されて全滅する。 |
| 7月20日 | 明治天皇が灯台巡視船「明治丸」に乗って、東北地方巡幸を終え横浜港に帰着。海の日の起源(1941年に村田省蔵逓信大臣の提唱により制定)。 |
| 9月23日 | 儒学者安井息軒が死去。日向飫肥藩の出身。儒学の他、漢学・兵学・海防論なども学んだ。昌平坂学問所の教授の他、私塾「三計塾」を開いて2000人もの子弟を教え、その中には幕末の志士や、明治期の政治家・軍人・学者なども多数含まれている。 |
| 10月24日 | 熊本で神風連(敬神党)の乱が勃発。敬神党を結成した太田黒伴雄らが熊本鎮台司令官種田政明、参謀長高島茂徳、熊本県令安岡良亮らを邸宅に襲撃し殺害、さらに熊本城内の熊本鎮台を襲って兵士らを殺害して営所を制圧する。 |
| 10月25日 | 熊本鎮台士官で難を逃れた児玉源太郎が指揮して神風連に対し反撃。指導者層の加屋霽堅・斉藤求三郎が戦死、太田黒伴雄が負傷して自刃したため神風連は瓦解。多数が自殺するなど死者124名を出す。政府側も兵士ら60名が死亡。鎮台兵の弱さが西南戦争に至る各地の反乱を招いたとも言われる。 |
| 10月27日 | 秋月の乱。福岡県秋月で、神風連の乱の発生を知った秋月士族らが今村百八郎(宮崎増賀)を擁立して挙兵。今村の実兄の宮崎車之助(重遠)や磯淳らも加わることに。今村は警察官穂波半太郎を殺害し、兵を率いて豊津に向かう。 |
| 10月28日 | 萩の乱。山口県の萩で元参議前原一誠ら殉国軍が武装蜂起。県庁襲撃は断念し東上を計画。 |
| 10月29日 | 武装決起した秋月党の勢力が同時挙兵を約した旧豊津藩士族の杉尾十郎らのもとへ来るが杉尾らは挙兵せず。決起の交渉中に、豊津側の通報を受けた小倉鎮台の乃木希典率いる歩兵第14連隊が襲撃。秋月党は応戦するも敗走。 |
| 10月29日 | 思案橋の変。萩の乱の発生を知った旧会津藩士族永岡久茂ら14人が千葉県で蜂起するために思案橋から出港しようとして、通報で駆けつけた警察官と斬り合いとなった事件。 |
| 10月31日 | 秋月党は解散し、宮崎車之助、磯淳、土岐清、戸原安浦、戸波半九郎、磯平八、宮崎哲之助ら幹部7人は自刃。今村百八郎ら27人は抗戦のため秋月へ戻り、翌11月1日、秋月の政府軍を襲撃するも戦局は好転せず散開。 |
| 10月31日 | 萩の殉国軍は悪天候で東上を断念し、萩に戻るが、すでに到着していた広島鎮台などの政府軍と交戦。前原は幹部5人で天皇直訴を計画し、殉国軍を小倉信一らに任せて別行動を取る。 |
| 11月 5日 | 前原一誠ら宇竜港で通報され逮捕される。 |
| 11月 6日 | 萩の殉国軍も鎮圧され、萩の乱は終結。 |
| 11月24日 | 今村百八郎が逮捕され秋月の乱は終結。 |
| 12月 3日 | 福岡裁判所にて、秋月の乱で逮捕された今村百八郎と、佐賀士族に挙兵の協力を求めていた益田静方が死刑判決となり即日執行。 |
| 12月 3日 | 山口裁判所・萩臨時裁判所にて、萩の乱の幹部らに対する死刑判決が言い渡され即日執行。 |
| 12月23日 | オスマン帝国が成文憲法を発布し、議会を招集。立憲君主制となる。 |
| 1877年(明治10年) | |
| 1月 1日 | イギリスのヴィクトリア女王のインド皇帝戴冠式が行われ、正式に即位。 |
| 1月 | 地租改正反対の一揆を受けて、地租を100分の3から100分の2.5に減額。 |
| 1月11日 | 大警視川路利良の命で、中原尚雄ら鹿児島県出身の警視庁警察官24名が帰郷。 |
| 1月29日 | 政府、陸軍の鹿児島にある草牟田火薬庫の弾薬を密かに運び出し赤龍丸に移す。事態に気づいた鹿児島私学校の生徒らが、火薬庫を襲撃。 |
| 2月 1日 | 鹿児島私学校の使者として西郷小兵衛が大隅小根占の西郷隆盛の元を訪れ、火薬庫襲撃事件と警官24名の帰郷について説明。西郷は鹿児島へと戻る。 |
| 2月 3日 | 私学校の関係者が、鹿児島に帰郷した中原尚雄らを西郷暗殺を図ろうとしたとして捕らえ、拷問にかけ自白を強要し、これが西南戦争のきっかけの一つとなる。 |
| 2月 9日 | 川村純義が海路鹿児島に到着し、西郷隆盛との会談を求めるが失敗に終わる。また鹿児島に帰郷していた野村綱(鹿児島出身。元宮崎県学務課長・宮崎学校校長)も捕らえられ、大久保利通から西郷暗殺の密命を受けていたと自白させられる。 |
| 2月15日 | 西郷軍が鹿児島を出発。西南戦争が始まる。 |
| 2月19日 | 日本が万国郵便連合に加盟。 |
| 2月19日 | 明治政府、西郷軍征討の勅令を発する。 |
| 2月19日 | 熊本城内で火災が発生し天守閣などが焼失。原因は不明だが、西郷軍に対する籠城作戦のため、政府軍側が燃やしたという説が有力。 |
| 2月21日 | 西郷軍が熊本城の包囲攻撃を開始。 |
| 2月25日 | 野村文夫が神田雉子町(現・東京千代田区神田司町)に『團團社』を設立。 |
| 3月 1日 | 田原坂方面で政府軍と西郷軍の戦闘が激化。以降、両軍は一進一退を繰り返す。 |
| 3月 1日 | 政府軍の軍艦「孟春」が日向細島港に入港。 |
| 3月 4日 | チャイコフスキーのクラシックバレエの代表作品『白鳥の湖』が初演される。 |
| 3月10日 | 政府の勅使柳原前光らが鹿児島に入り、島津久光の上京を促す。久光、中立を表明した上でこれを拒絶。前光、西郷軍の武器などを没収。また私学校生徒らによって投獄されていた中原尚雄ら帰郷警察官24名を救出。神奈川丸で東京へ移送。 |
| 3月12日 | 熊本城そばの段山を巡って西郷軍と鎮台兵が戦闘。 |
| 3月19日 | 政府軍別働第2旅団が洲口・八代付近に上陸。続けて日奈久にも上陸を開始し、そのまま北上。 |
| 3月20日 | 政府軍、田原坂方面の西郷軍に対して集中砲火を行い、突撃を開始。西郷軍は応戦できず田原坂から植木方面へ退却。政府軍も田原坂攻防の20日間で大きな人的被害を出す。 |
| 3月20日 | 八代から北上中の政府軍と熊本から南下した西郷軍が氷川付近で交戦。 |
| 3月23日 | 政府軍、植木方面への攻撃を開始。 |
| 3月24日 | 野村文夫が『團團珍聞』(マルマルチンブン)を創刊。日本における週刊誌の原点。 |
| 3月25日 | 政府軍別働第3旅団も八代へ上陸を開始。政府軍再編成。西郷軍も鹿児島で追加徴兵。 |
| 3月26日 | 西郷軍が熊本市街を流れる坪井川と井芹川の水をせき止め氾濫させる水攻めを実施。熊本城西側などが水没。熊本南方の小川方面の西郷軍を破り、政府軍別働第1旅団(第2旅団から再編)が占領。 |
| 3月28日 | 福岡の変勃発。西郷挙兵を待っていた武部小四郎、越智彦四郎、加藤堅武ら福岡藩士族500名あまりが紅葉八幡宮で挙兵。福岡城の福岡鎮台や県庁、事前に察知した警察の摘発で同志が収監されていた藤崎監獄などを襲撃。福岡鎮台は出兵して1小隊のみだったが、かろうじて死守。政府軍歩兵第7連隊などが到着し、士族軍は敗れ退却。 |
| 3月29日 | 政府軍軍艦「浅間」が日向細島港に入港。 |
| 3月30日 | 政府軍近衛鎮台軍が、隈府を攻撃。西郷軍がこれを撃退。一方、政府軍別働第1旅団、第2旅団は、熊本南郊の松橋、甲佐、宇土の一帯へ進出。西郷軍と激しく交戦。 |
| 4月 1日 | 政府軍別働第1旅団が、宇土を占領。 |
| 4月 1日 | 福岡藩士族等による挙兵は失敗に終わり、鎮圧される。 |
| 4月 3日 | 政府軍別働第3旅団が、甲佐を占領。西郷軍は退却。 |
| 4月 4日 | 鹿児島から人吉方面へ迂回しながら北上してきた西郷軍が八代の政府軍を攻撃。以降2週間に渡り八代近郊で戦闘を繰り返す。 |
| 4月 5日 | 政府軍第3旅団が、鳥巣方面へ進出。西郷軍敗走。 |
| 4月 6日 | 政府軍別働第4旅団が、宇土に上陸。八代萩原堤で政府軍と戦闘中の西郷軍熊本共同隊メンバーだった宮崎八郎(中江兆民の弟子で宮崎滔天の兄)が戦死。 |
| 4月 7日 | 政府軍が、鳥巣方面から退却。 |
| 4月 8日 | 熊本城内の鎮台兵が出撃し、北上してきた政府軍と連絡。また西郷軍から物資を奪って城内へ引き上げる。 |
| 4月 9日 | 政府軍が再度、隈府を攻撃。西郷軍の反撃に遭うも、西郷軍も退却。 |
| 4月10日 | 政府軍が再度、鳥巣再攻略を開始。 |
| 4月12日 | 政府軍別働第1旅団、別働第3旅団が緑川中流を横断して北上。西郷軍は敗走し永山弥一郎が自刃。一方、緑川下流の別働第2旅団と第4旅団は一進一退。 |
| 4月13日 | 政府軍別働第2旅団と別働第4旅団が緑川を突破し川尻を占領。別働第2旅団の山川浩中佐率いる選抜隊が熊本城に到達。 |
| 4月14日 | 西郷軍、本営を熊本城外の二本木から東の木山(益城町)へ移し、各方面の部隊に大津-木山-御船の南北線へ兵力を集中させるよう指令。 |
| 4月15日 | 西郷軍が植木、木留など城北方面から、熊本城南方面へ退却。 |
| 4月16日 | 札幌農学校教頭のクラーク博士が、Boys, be ambitious の言葉を残して辞任。 |
| 4月17日 | 熊本市街東方に陣を敷いた西郷軍に対し政府軍が順次攻撃を開始。 |
| 4月19日 | 政府軍と西郷軍が全面衝突。翌20日、戦況不利の中で野村忍介、池辺吉十郎らの意見により更に東方の矢部浜へ退却することを決定。 |
| 4月21日 | 西郷軍矢部浜で軍議を開き、人吉を拠点として薩摩・大隅・日向に勢力を広げることを決め、諸隊を再編成する。 |
| 4月23日 | 政府軍別働第1旅団・別働第3旅団の一部を鹿児島に派遣。 |
| 4月27日 | 西郷軍、人吉に本営を置く。 |
| 4月28日 | 西郷軍、中島健彦率いる振武隊を鹿児島に派遣。 |
| 4月30日 | 西郷軍、野村忍介率いる奇兵隊を豊後方面へ派遣。椎葉山を経て、日向富高・細島方面へ進出。 |
| 5月 1日 | 政府軍別働第2旅団、球磨方面攻略を開始。一方、西郷軍振武隊は鹿児島攻略を開始。以降、約1ヶ月に渡って鹿児島周辺で攻防が繰り広げられる。 |
| 5月 2日 | 福岡の変を起こした越智彦四郎、加藤堅武が処刑される。 |
| 5月 3日 | 岩村通俊が鹿児島県令として鹿児島に着任。 |
| 5月 4日 | 政府軍別働第3旅団、大口方面攻略を開始。西郷軍、日向三田井(高千穂)を抑え、延岡方面へ進出。ここを拠点に、宮崎方面へも兵を出し、旧日向国の支配化を進めていく。 |
| 5月 4日 | 福岡の変を起こした武部小四郎が処刑される。 |
| 5月 5日 | 政府軍、田ノ浦に上陸。 |
| 5月 6日 | アメリカ先住民族ラコタ・スー族の一支族、オグララ族の戦士クレイジー・ホースがアメリカ政府に降伏する。 |
| 5月 8日 | 辺見十郎太率いる大口の西郷軍雷撃隊が政府軍に反撃し勝利。 |
| 5月11日 | 辺見十郎太率いる西郷軍雷撃隊が久木野まで、淵辺群平率いる鵬翼隊が佐敷まで、池辺吉十郎率いる熊本隊が矢筈岳まで進出。 |
| 5月12日 | 野村忍介率いる奇兵隊が、豊後重岡を占領。 |
| 5月13日 | 野村忍介率いる奇兵隊が、豊後竹田を占領。 |
| 5月14日 | 西郷軍正義隊、延岡鏡山の熊本鎮台軍を攻撃。 |
| 5月15日 | 政府軍第1旅団、熊本鎮台軍が豊後竹田の攻略戦を開始。 |
| 5月20日 | 久木野に進出した政府軍別働第3旅団に対し、淵辺群平率いる大野の西郷軍干城隊が政府軍に反撃し勝利。 |
| 5月23日 | 政府軍別働第3旅団、大野を攻略。また矢筈岳の西郷軍を撃破。 |
| 5月24日 | 鹿児島紫原で政府軍と西郷軍が激戦となる。西郷軍敗走するも政府軍にも大きな被害が出る。 |
| 5月25日 | 政府軍第1旅団、三田井を占領。日之影の西郷軍と対峙。 |
| 5月28日 | 西郷軍の桐野利秋、鹿児島県宮崎支庁(現宮崎県宮崎市)に入り、宮崎軍務所を置く。不換の軍票(軍事紙幣)である「西郷札」の印刷を始める。この西郷札の強制通用により、宮崎では甚大な経済被害が出る。 |
| 5月29日 | 政府軍が豊後竹田を攻略。 |
| 5月31日 | 西郷隆盛が宮崎軍務所に入る。 |
| 6月 1日 | 政府軍が人吉への総攻撃を開始する。西郷軍奇兵隊は臼杵を占領。 |
| 6月 4日 | 人吉の西郷軍が降伏。 |
| 6月 7日 | 政府軍、久木野を攻略。 |
| 6月10日 | 政府軍、臼杵を攻略。西郷軍奇兵隊は、日向方面へ撤退。 |
| 6月12日 | 西郷軍、都城で軍を再編成。 |
| 6月19日 | 西郷軍の河野主一郎率いる破竹隊が飯野を攻撃するも失敗。 |
| 6月20日 | 政府軍、大口を攻略。 |
| 6月23日 | 政府軍、川内川流域の西郷軍に対し総攻撃を行い、翌日にかけて鹿児島までの西郷軍勢力を駆逐。 |
| 6月25日 | 西郷軍雷撃隊、大口再攻略を断念し退却。 |
| 7月 6日 | 政府軍、国分に進出し、踊の西郷軍を攻撃。西郷軍、大窪まで退却。 |
| 7月 8日 | 西郷軍振武隊、百引の政府軍を攻撃し勝利する。 |
| 7月11日 | 政府軍、小林を占領。 |
| 7月12日 | 西郷軍雷撃隊、財部に進出し、赤坂の政府軍を攻撃するも攻略ならず。また西郷軍奇兵隊・振武隊は大崎方面で政府軍に勝利するも末吉への転進のため退却。 |
| 7月14日 | 政府軍、高原を占領。 |
| 7月17日 | 西郷軍、高原の政府軍に対し全面攻勢に出て、激戦となるが攻略は失敗に終わる。 |
| 7月21日 | 政府軍幹部、都城総攻撃のための軍議を行い、各軍の配置を決定。 |
| 7月22日 | 政府軍、野尻を占領。 |
| 7月23日 | 政府軍と西郷軍が岩川で交戦し激戦となるが、西郷軍は末吉へと退却。 |
| 7月24日 | 政府軍、都城へ総攻撃を行う。西郷軍、防衛ならず敗走。政府軍、庄内、末吉、財部など都城盆地一帯を制圧。 |
| 7月25日 | 政府軍、山之口を制圧。 |
| 7月27日 | 政府軍、飫肥を占領。 |
| 7月28日 | 政府軍、紙屋で西郷軍と交戦。 |
| 7月29日 | 政府軍、高岡を占領。 |
| 7月30日 | 政府軍第3旅団、第4旅団、別働第3旅団が宮崎総攻撃を開始。 |
| 7月31日 | 政府軍、増水している大淀川を渡河して宮崎へ侵攻し、虚を突かれた西郷軍は、佐土原へ退却。 |
| 8月 1日 | 政府軍、佐土原の西郷軍を撃破。宮崎周辺を占領下に置く。政府軍新撰旅団が宮崎に入港。 |
| 8月 2日 | 西郷隆盛、延岡大貫村に入る。米良方面の干城隊も美々津へ退却。同日、政府軍、高鍋を占領。 |
| 8月 3日 | 政府軍、美々津攻略を開始。西郷軍も応戦し、激戦となる。 |
| 8月 4日 | 政府軍別働第2旅団が、迂回して鬼神野・渡川方面を攻撃。西郷軍、山陰(やまげ)方面へ退却。 |
| 8月 6日 | 西郷隆盛、各部隊に教書を出して督励。 |
| 8月 7日 | 政府軍、山陰を攻略し、続けて富高も攻撃。西郷軍、美々津から退却。また本営を熊田(北川)へ移す。 |
| 8月10日 | 西郷隆盛、大貫から無鹿・長井へと拠点を移す。 |
| 8月12日 | 政府軍第1旅団、別働第2旅団、別働第3旅団、別働第4旅団、新撰旅団で、延岡総攻撃を開始。西郷軍も応戦するが衆寡敵せず和田峠方面へ敗走。 |
| 8月14日 | 政府軍延岡市街地へ突入。西郷隆盛、可愛岳に到着し自ら陣頭指揮を取ることを決断。 |
| 8月15日 | 西郷隆盛、この戦争で初めて自ら陣頭指揮を行い、和田越で政府軍と交戦。政府軍も山県有朋が指揮を取り、激戦となる。しかし政府軍の猛攻によりついに長井へ敗走。 |
| 8月16日 | 西郷隆盛、長井村の児玉熊四郎邸に置いた本営で、全軍の解散を命令。関係書類や、自らの陸軍大将の軍服を焼却。西郷が降伏も認めたことから、降伏者が相次ぐ。西郷はここで最終決戦に及ぶつもりだったとも言われるが、一旦三田井(高千穂)まで退くことを決定。 |
| 8月17日 | 西郷軍残存兵1000名前後が、夜半に可愛岳に移動。 |
| 8月18日 | 西郷軍残存兵が、政府軍包囲網を攻撃。不意を突かれた政府軍は混乱して後退。西郷軍は武器弾薬食料を奪って、三田井方面へと向かう。 |
| 8月21日 | 西郷軍が、三田井に到着。 |
| 8月22日 | 西郷隆盛、残存軍をもって、山中を鹿児島方面へ向かうことを決める。 |
| 8月24日 | 西郷軍、神門に到着。 |
| 8月26日 | 西郷軍、村所に到着。 |
| 8月28日 | 西郷軍、小林に到着。しかしここで政府軍第2旅団が行く手を塞いでいたため、加治木方面を経て鹿児島に入ることを断念。迂回路を進む。 |
| 9月 1日 | 西郷軍、政府軍の隙きを突いて鹿児島へ入る。私学校と城山を占領。鹿児島市街地を制圧。 |
| 9月 3日 | 政府軍が次々と鹿児島へ到着。西郷軍は米倉の占領に失敗し城山へ退却。 |
| 9月 5日 | クレイジー・ホースが白人らによって刺殺される。 |
| 9月 6日 | 政府軍、城山を包囲。 |
| 9月 8日 | 山県有朋が鹿児島に到着。攻略より包囲を優先させる。 |
| 9月19日 | 西郷軍の山野田一輔と河野主一郎が、西郷の助命を談判するため、西郷の縁者である政府軍の海軍中将川村純義の元へ軍使として赴く(西郷隆盛は二人を政府側に「決死と義挙の意」を伝えるためとして送り出した)。 |
| 9月22日 | 西郷隆盛、決死の檄を飛ばす。 |
| 9月23日 | 山野田一輔が川村純義の降伏勧告書を持って戻る。 |
| 9月24日 | 城山の戦い。早朝、政府軍が城山の総攻撃を開始。負傷した西郷隆盛は、別府晋介の介錯で自刃し、残りの幹部も皆戦死、もしくは自決して、午前9時ころ戦闘は終了。西南戦争が終結する。 |
| 10月 1日 | 東海道線の住吉駅と西ノ宮駅の間で上り旅客列車と下り回送列車が衝突。乗員3名が死亡。日本最初の鉄道死亡事故とみられる。回送列車は西ノ宮駅で旅客列車と行き違う予定だったが、間に臨時列車が入ったため、臨時列車の後に出発してしまい旅客列車と正面衝突してしまった。 |
| 10月17日 | 華族学校が開校。廃止された皇学所と漢学所(大学寮代を受け継いだもので、その後の大学校代)の再興という形で、幕末以来の京にあった公家の教育機関を受け継いだもの。 |
| 12月 6日 | エジソンが蝋管蓄音機での録音再生に成功する。この時録音されたのは、童謡『メリーさんのひつじ』。この時録音されたレコードはすでに再生不可能になっている。 |
| 12月 | ハートレー事件。イギリスの商人ジョン・ハートレーが、上海から日本へアヘンを密輸入しようとして発覚。日本政府はハートレーを、日英修好通商条約の貿易章程違反で告訴。ところが翌年の領事裁判でイギリス政府はアヘンを「薬用」と主張し無罪判決。上訴はイギリスで行われることから、日本政府は外交交渉で解決を求めたが失敗に終わる。この事件と、後に起こるヘスペリア号事件は、不平等条約撤廃運動を盛り上げるきっかけとなった。 |
| この年、内国勧業博覧会で美術館が作られる。 | |
| 1878年(明治11年) | |
| 2月 4日 | 法制局の大書記官尾崎三良と少書記官桜井能堅が、華族を「公」「侯」「伯」「子」「男」の5等級とする案を提出。 |
| 2月14日 | オスマン帝国皇帝アブデュルハミト2世が制定間もない憲法を停止し、専制体制を復活する。 |
| 3月25日 | 家庭用の配電が始まり、また東京・銀座木挽町に開設された中央電信局の開局祝賀会が虎ノ門の工部大学校で開かれ、その大ホールに50個のアーク灯が点灯される。 |
| 5月14日 | 紀尾井坂の変が起こる。内務卿大久保利通が、麹町区紀尾井町清水坂付近を馬車で走行中に石川県士族島田一郎ら6人によって殺害される。 |
| 6月22日 | フィンランド人アドルフ・エリク・ノルデンショルド率いるスウェーデンの北東航路探検隊の一行がスウェーデンのカールスクルーナを出港。 |
| 11月 2日 | 東京府に15区が設置される。 |
| 12月 5日 | 軍令を担当した陸軍参謀本部が陸軍省から独立する。海軍軍令機関も兼任。 |
| 12月 | イングランドの研究者ジョゼフ・ウィルスン・スワンが、40時間ほど持続する白熱電球を完成。 |
| 1879年(明治12年) | |
| 1月 4日 | 梟首刑が廃止される。罪人を斬首にしたあと、その首を晒す刑罰。 |
| 1月11日 | 南部アフリカでイギリス軍が在地の独立国ズールー王国へ攻撃を開始。ズールー戦争が始まる。 |
| 1月22日 | ズールー軍が、イサンドルワナの戦いで、イギリス軍を撃破する。 |
| 1月31日 | 高橋お伝が斬首刑に処される。愛人の男の借金返済のため、金を借りようとした相手の古物商の男とトラブルとなり殺害した罪で。日本最後の斬首刑。 |
| 3月11日 | 明治政府が琉球藩を廃して沖縄県を設置するため、琉球藩王・尚泰王に東京居住を命じる。 |
| 3月27日 | 琉球処分官松田道之が首里城で廃藩置県を宣言。 |
| 3月29日 | カンブラの戦いでズールー軍が大敗。 |
| 4月 4日 | 琉球藩が廃止され、沖縄県が設置される。 |
| 4月 5日 | チリが、資源をめぐって対立するペルーとボリビアの同盟破棄を求め、両国に宣戦布告。「太平洋戦争」が勃発する。 |
| 6月 1日 | ズールー戦争で、イギリス軍に加わっていたナポレオン3世の息子ナポレオン・ウジェーヌ皇太子が戦死する。 |
| 6月 4日 | 東京招魂社を靖國神社に改称する。 |
| 7月 4日 | イギリス軍が、ズールーの首都ウルンディを攻め落とし、ズールー戦争が終結。同国は13の部族領に分割される。のち、トランスヴァールとナタールに分割合併され、イギリス植民地となる。 |
| 7月15日 | ヘスペリア号事件。コレラの流行している清からきたドイツ船ヘスペリア号に対し、日本政府が検疫のため長浦港への停泊を求めたのに対し、ドイツ政府は従わず、砲艦を護衛につけて横浜港へ入港を強行する。日本政府はドイツに抗議。またこれと前後して関東地方でコレラが流行したこともあり、日本国民の間で不平等条約撤廃を求める運動が高まる。 |
| 9月 2日 | ロシア北極海沿岸の北東航路探検を一人も犠牲を出さず成功させたアドルフ・エリク・ノルデンショルドの一行が横浜に到着。各地で大歓迎を受ける。旗艦ベガ号の修復の間、鉱物学者でもあるノルデンショルドは日本各地で鉱物や化石を収集、武具や工芸品、古典籍などを多数購入して、10月21日に長崎から出国。インド航路を経由して翌年4月24日にスウェーデンに帰国した。 |
| 10月 8日 | アンガモスの海戦。ペルーとチリの艦船同士が砲撃戦を行い、チリがペルー唯一の装甲艦を拿捕。 |
| 10月21日 | エジソンが竹の繊維を使ったフィラメントを用いた白熱電球を発表する。 |
| 1880年(明治13年) | |
| 1月 1日 | フランスのレセップスらが、パナマ運河の建設に取り掛かる。後に失敗に終わる。 |
| 2月28日 | 貿易金融・為替取引の横浜正金銀行が営業を開始する。 |
| 4月 5日 | 集会条例が制定される。 |
| 5月31日 | タイの国王ラーマ5世の后スナンダ・クマリラタナが、娘とともに避暑地へ向かうため船で移動中、別の船と衝突して転覆し娘ともども溺死する。一説には庶民は王族に触れてはならないという法律のために助けに行けなかったと言われる。同船していた船長が助けたものの間に合わなかった。なおラーマ5世の異母妹に当たる。 |
| 8月14日 | 1248年から建設が始まり、たびたび中断したドイツのケルン大聖堂が完成。 |
| 10月25日 | 現在の国歌のもととなった『君が代』が初演奏される。奥好義が旋律をつくり、林廣守が作曲し、フランツ・エッケルトが編曲したもの。 |
| 11月 3日 | 高評価を受けた『君が代』が天長節にあわせて発表される。当初は国歌としてではなく祝日の賀歌としての要素が強かった。 |
| 11月 6日 | シャルル・ルイ・アルフォンス・ラヴランがマラリア患者の血液中から、マラリア原虫を発見。 |
| 12月17日 | 最後の敵討ち事件。慶応4年に秋月藩の保守派干城隊の一派に惨殺された臼井亘理夫妻の息子の臼井六郎が、父親を殺害した一瀬直久を追い続け、この日、東京銀座付近でついに直久を発見し殺害、自首。世間を賑わし、日本最後の敵討ちと評された。臼井六郎は終身刑となった後、憲法発布の恩赦で釈放された。 |
| 1881年(明治14年) | |
| 1月 | チリとペルー・ボリビアによる「太平洋戦争」で、チリ軍がペルー首都リマへ侵攻。ペルー政府はアンデス山中へ避難して抵抗するも劣勢に追い込まれる。 |
| 3月 | ハワイ王カラカウアが日本を訪れる。外国元首で初の訪日。日本との関係強化のため、カイウラニ王女と山階宮定麿親王との婚姻を要請する(のち謝絶される)。 |
| 6月30日 | 地租改正のための検地が終わり、地租改正事務局を閉鎖。地租改正は終了。 |
| 8月 1日 | 華族らが資金を出した日本最初の私鉄、日本鉄道の設立が決定する。 |
| 10月11日 | 明治十四年の政変。開拓使官有物払下げ事件をきっかけに、これを批判した大隈重信らが失脚。 |
| 11月11日 | 日本最初の私鉄、日本鉄道の設立特許条約書が下付されて設立される。 |
| 上野山に博物館が建設される。 | |
| この年から1884年にかけて、ロシアや東ヨーロッパ各地で、ユダヤ人に対する虐殺事件「ポグロム」が頻発。難民がオーストリアなどに流入する。 | |
| 1882年(明治15年) | |
| 3月24日 | ロベルト・コッホが結核菌の発見を学会で報告する。 |
| 4月 6日 | 岐阜事件。板垣退助が岐阜で演説後に暴漢に襲われ重症を負う。「板垣死すとも自由は死せず」の事件。 |
| 10月 5日 | アメリカでロバート・ゴダード生誕。ツィオルコフスキーと並ぶ、ロケット研究者の草分け的人物。 |
| 1883年(明治16年) | |
| 5月20日 | スンダ海峡のクラカタウ火山のひとつラカタ島のラカタ山で噴火が始まる。 |
| 7月28日 | ラカタ島が大噴火し、島の3分の2が吹き飛ぶ。火砕流は40km離れたスマトラ島ランプン湾に到達。大津波も発生し、死者は36417人に及ぶ。津波は日本にも到達しているほか、フランスでも潮位の変化が観測された。 |
| 7月28日 | 日本最初の私鉄、日本鉄道の上野~熊谷間が開業。華族らによる出資で建設されたが、予算不足の政府の代わりに鉄道敷設を進めたため、政府のバックアップが大きかった会社。計画上は東北、上越、中山道、北部九州で建設する予定だった。 |
| 10月 4日 | ベルギーの「国際寝台車会社」がパリからコンスタンティノープル(現イスタンブル)へ向かう国際豪華列車オリエント急行の運行を開始。 |
| 10月20日 | アンコン条約の締結。ペルー・ボリビアとチリの「太平洋戦争」が終結する。 |
| 11月28日 | 明治時代の迎賓館で、社交クラブだった鹿鳴館が開館。 |
| 1884年(明治17年) | |
| 1月 4日 | イギリスでフェビアン協会が設立。暴力革命ではなく、議会政治などを経て漸進的に社会主義を進めていく組織。 |
| 1月 4日 | 松島事件。松島遊郭で兵士が警察署員に対して尿をかけたことがきっかけで、兵士1400名、警察官600名が出動して乱闘となる。死者2名、重軽傷者50名以上を出す。 |
| 1月 9日 | 大阪東区「本町曲がり焼」の大火。約1500戸が焼失。 |
| 4月 4日 | チリとボリビアがバルパライソ条約を締結し講和。ボリビアは唯一の沿岸領土をチリに譲渡することになり、内陸国になる。 |
| 6月 1日 | 東京気象台がはじめて天気予報を発表。6時、14時、21時の1日3回。 |
| 7月 7日 | 華族令制定。公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の5爵を定める。 |
| 7月20日 | ロシアの技術者アレクサンドル・モジャイスキーが蒸気エンジン付の飛行機を滑走台から発進させ、30mジャンプすることに成功。しかし操縦はできず、機体は落下して大破した。モジャイスキーは、1854年にプチャーチンが来日した際に同行しており、津波で沈没したロシア船ディアナ号の代わりに、戸田でヘダ号の設計建造を指揮した人物でもある。 |
| 11月15日 | 列強によるアフリカ大陸の分割を話しあうベルリン会議が開催(翌年2月26日まで)。 |
| この年、シカゴにホームインシュアランスビルが完成。鉄骨構造を持つ最初の高層ビルと言われる。10階建て42m。 | |
| 1885年(明治18年) | |
| 2月 5日 | ベルギー王レオポルド2世の私領「コンゴ自由国」が成立。残虐非道な支配が行われたことで知られる。 |
| 4月18日 | 特許を認める法律として明治18年太政官布告第7号が公布。 |
| 6月 2日 | 琵琶湖疏水起工。 |
| 8月14日 | 日本初の専売特許証を交付。特許第1号は、堀田瑞松が出願した「堀田錆止塗料及其塗法」。 |
| 8月19日 | 超新星SN1885Aをアイザック・ワードとエルンスト・ハルトヴィッヒが観測。アンドロメダ銀河内254万光年の距離にある星。supernovaと呼ばれた最初の星。他の銀河で発見された最初の星でもある。 |
| 10月13日 | 東海道線大森駅で深夜、旅客列車が分岐器上で脱線転覆。乗客1名が死亡。 |
| 11月23日 | 大阪事件。旧自由党の大井憲太郎らが朝鮮の改革派を武力支援しようとして139人が逮捕される。 |
| 12月22日 | 内閣制度が発足。太政官達第69号と内閣職権の制定により太政官制を廃止し、参議の伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任して、第1次伊藤内閣を組閣。 |
| イタリアがエリトリア地方を占領する。 | |
| 1886年(明治19年) | |
| 2月23日 | アルミニウムの電気分解法(ホール・エルー法)が発明される。 |
| 3月 2日 | 帝国大学令公布。東京の帝国大学が正式に設置される。 |
| 5月 8日 | コカ・コーラ、アトランタで発売開始。 |
| 6月10日 | ニュージランド北島のタラウェラ山が大噴火。約150名が死亡。 |
| 7月13日 | 時刻の基準となる標準時を定めた勅令第51号「本初子午線経度計算方及標準時ノ件」が公布される。1888年1月1日の東経135度の子午線上の時刻を日本標準時とする、と定める。 |
| 9月 9日 | 著作権について定めたベルヌ条約が成立。これにより同条約加盟国では、著作した時点で著作権が自動で発生する無方式主義になる。 |
| 10月28日 | フランスから贈られたニューヨークの「自由の女神像」の除幕式が行われる。 |
| 10月18日 | フランスで建造された大甲鉄艦「畝傍」がル・アーヴルを出港。 |
| 12月 3日 | 大甲鉄艦「畝傍」が寄港地のシンガポールを出港。しかしその後消息を絶つ。日本海軍や各国船舶が南シナ海から日本南方で捜索するが発見できなかった。 |
| 1887年(明治20年) | |
| 10月19日 | 前年に消息不明となった「畝傍」の亡失が認定される。乗員らフランス人79名、アラブ人9名、日本人8名は不明のまま。この事件の影響か、日本はこれ以降フランスに軍艦の発注をせず、また「畝傍」という名称も使われていない。 |
| 12月26日 | 保安条例の公布。三大事件建白運動を受けて、自由民権運動を弾圧するための法律。570人が東京市外へ追放される。 |
| 1888年(明治21年) | |
| 4月 3日 | イギリスのロンドン市内にあるホワイトチャペルで売春婦が殺される事件が起きる。以後のおよそ1年にわたって連続する「ホワイトチャペル殺人事件」の一例目。8月から11月にかけての「切り裂きジャック事件」とも関連付けされる。 |
| 4月25日 | 市制および町村制公布。 |
| 5月 7日 | 25人に日本初の博士号が授与される。 |
| 7月15日 | 磐梯山で水蒸気噴火が発生。小磐梯が北側に向かって山体崩壊を起こし、大規模な岩屑なだれが発生。山麓の5か村11集落を飲み込み、461人が死亡する大惨事となる。設立されたばかりの日本赤十字社が救護に出動した。長瀬川がせき止められ、桧原湖、雄子沢湖、小野川湖、秋元湖、五色沼など大小300あまりの堰き止め湖沼が形成される。桧原村が桧原湖の形成で水没。 |
| 8月31日 | イギリスのロンドン市内で売春婦を狙って体を切り刻んで殺害する「切り裂きジャック事件」が発生する。少なくとも11月9日までに5人の女性が殺害される。うち4人は被害者の年齢、職業、遺体の損壊状況が類似しているため、これが同一犯「切り裂きジャック」の犯行で間違いないとされているが、犯人の正体もわからないことから、ホワイトチャペル事件との関連も不明のまま。 |
| 10月14日 | 現存する最古の映画フィルムとされる『ラウンドヘイの庭の場面』が撮影される。監督・撮影はルイ・ル・プランス。ウェスト・ヨークシャー州のラウンドヘイにあるオークウッド邸の庭で、プランスの親族らが歩いている様子を撮影したもの。 |
| 11月 8日 | ロンドン警視庁のウォーレン警視総監が辞職。内務大臣との不和が原因だが、一連の猟奇殺人事件の影響、捜査を巡る対立なども要因。 |
| 華族学校に対し、明治天皇から『学習院』の勅額が下賜されて、宮内省管轄の官立学校「学習院」となる。 | |
| 大阪市浪速区の遊園地に高さ31mの眺望閣と呼ばれる5階建ての建物が完成。日本最初の近代的高層ビルとされる。 | |
| 1889年(明治22年) | |
| 2月11日 | 大日本帝国憲法、皇室典範、議院法、貴族院令などが公布される。 |
| 2月11日 | 文部大臣、森有礼暗殺。歐化主義者だった彼の伊勢神宮での不敬な行動が原因とされるが、その元となった不敬事件の真相は不明。 |
| 2月12日 | 黒田清隆首相の超然主義演説。政府は政党の主張に対し超然として政策を進めていく、という意味の内容。 |
| 3月29日 | ニューヨークのオーバーン刑務所で、史上初めて電気椅子によって死刑が執行される。受刑者はウィリアム・ケムラー。すぐには死亡せず数度に渡る送電で死亡まで8分かかったと言われる。電気椅子を導入した背景には、直流送電を主張したエジソンが、ジョージ・ウエスチングハウスやニコラ・テスラの主張する交流送電を危険なものとして宣伝するために電気椅子を後押ししたという事情もある。 |
| 4月11日 | 東海道線安倍川付近で工事列車同士が衝突。4名が死亡。また名古屋へ向かうため便乗していた静岡県知事の関口隆吉が重症を負う。 |
| 4月20日 | オーストリアの都市ブラウナウで、税関吏アロイス・ヒトラーと妻クララの間にアドルフ・ヒトラーが生まれる。 |
| 4月22日 | アメリカ政府がインディアン・テリトリーへの白人の入植を認可。これにともない「ランドラッシュ」と呼ばれる移住ブームが起こる。 |
| 5月 5日 | パリ万博の目玉「エッフェル塔」が公開される。高さは312.3m。1930年にニューヨークにあるクライスラービルが完成するまで、世界一高い建物となる。当初はパリの文化人の間で大不評だった。 |
| 5月16日 | 博物館が、帝国博物館と改められる。現在の国立博物館の原型。 |
| 5月17日 | 東海道線の列車事故で重傷を負った静岡県知事の関口隆吉が破傷風で死亡。 |
| 9月23日 | 山内房治郎が「任天堂骨牌」という名称の花札製造会社を京都で創業。のちの任天堂。 |
| 11月15日 | ブラジル帝国の崩壊。近代改革や奴隷解放に反発した保守派らがデオドロ・ダ・フォンセカを擁立して軍事クーデター。皇帝一家は本家筋であるポルトガルや、フランスへ亡命。 |
| 11月18日 | 北海道炭礦鉄道設立。 |
| 12月11日 | 北海道の官営幌内鉄道の譲渡を受けて、北海道炭礦鉄道が営業を開始。 |
| この年、シカゴにオーディトリアムビルが完成(塔まで入れて高さ106m)。 | |
| この年、大阪市北区に建てられた高さ39m、9階建ての凌雲閣が完成する。 | |
| 1890年(明治23年) | |
| 2月10日 | 裁判所構成法成立。 |
| 2月25日 | 日本麦酒醸造會社からヱビスビールが発売される。 |
| 3月 6日 | 明治政府が、三菱に丸の内一帯を払い下げる。 |
| 4月11日 | エレファント・マンことジョゼフ・ケアリー・メリックが死去。プロテウス症候群と言われる細胞・組織の異常増殖を起こす病気にかかった男性。 |
| 7月25日 | 集会及政社法制定により集会条例は廃止される。 |
| 7月 1日 | 第1回衆議院議員総選挙。 |
| 9月 9日 | 大阪西区「新町焼」の大火。約2100戸が焼失。 |
| 9月16日 | オスマン帝国の訪日使節団が乗った軍艦エルトゥールル号が紀伊半島沖で遭難。地元住民が救助に当たる。 |
| 10月 9日 | フランス人発明家クレマン・アデールが蒸気エンジン搭載の動力飛行機エオール号の飛行試験を実施。20cmほど浮いて50m飛行したと言われる。コウモリのような独特の形状で軽量機だったが、操縦はできない構造であり、初飛行とは認定されていない。 |
| 10月29日 | 浅草に凌雲閣が完成。12階建て、高さ173尺(約52m・基盤も入れると66m)。10階まではレンガ造り、その上が木造2階建て。エレベーター搭載。これを日本の高層ビルの元祖という場合もある。 |
| 10月30日 | 『教育ニ関スル勅語』(教育勅語)の発布。近代日本の新たな道徳教育の基本とされたもの。 |
| 11月 7日 | 鹿鳴館の隣接地に帝国ホテルが開業。設立は渋沢栄一と大倉喜八郎。 |
| 11月29日 | 大日本帝国憲法を、第1回帝国議会の開会の日に施行する。憲法とともに皇室典範、議院法、貴族院令、衆議院議員選挙法、会計法など基本的な法律も定められる。 |
| 11月29日 | 貴族院が開設される。 |
| 12月 4日 | 北里柴三郎とエミール・ベーリングが「血清療法」に関する論文を発表。 |
| カリフォルニア州知事で、パシフィック鉄道の創設者であるリーランド・スタンフォードが、亡くなった息子の名をつけたリーランド・スタンフォード・ジュニア大学を創設。通称スタンフォード大学。 | |
| 1891年(明治24年) | |
| 5月11日 | 日本を公式訪問中のロシア皇太子ニコライ(後のニコライ二世)が津田三蔵巡査に斬りつけられ負傷する(大津事件)。 |
| 5月12日 | 6個鎮台が廃止され6個師団が設置される。 |
| 5月31日 | シベリア鉄道起工式典がロシア皇太子ニコライ(後のニコライ二世)臨席のもとウラジオストクで挙行される。 |
| 9月 1日 | 日本鉄道上野-青森間全通。 |
| 10月28日 | 濃尾地震発生。6時38分にマグニチュード8程度の大規模な地震が発生。大規模な断層のズレによるもので、岐阜県と愛知県を中心に死者は7273人、重軽傷者17175人、家屋全壊14万2177戸と甚大な被害を出した。海外でも報道された。また近代地震研究のきっかけになった自然災害でもある。この時、富士山頂火口縁北側の牛ヶ窪から釈迦ヶ岳にかけて大規模な土砂崩れがあったという報告が静岡県より出ている。 |
| 12月14日 | 近衛が「近衛師団」となる。 |
| 12月22日 | 第2回帝国議会で自由党など「民党」が海軍予算の削減を主張し、樺山資紀海軍大臣が藩閥政府を支持する発言「蛮勇演説」を行い議会は紛糾。 |
| 12月25日 | 松方正義首相が初めて衆議院を解散。衆議院選挙が始まるが、選挙妨害で大混乱となる。 |
| ニューヨークワールドビルがニューヨークに完成。高さ106.4m、1955年に解体。 | |
| 1892年(明治25年) | |
| 10月31日 | アーサー・コナン・ドイルのシャーロック・ホームズシリーズの最初の短編集『シャーロック・ホームズの冒険』が刊行。 |
| 11月25日 | ピエール・ド・クーベルタンが、ソルボンヌ大学で講演し、近代オリンピックの創設を訴える。 |
| 1893年(明治26年) | |
| 1月 6日 | アメリカの地主やサトウキビ業者らによる武力クーデターでハワイ女王リリウオカラニが退位を強制され、ハワイ王国が滅亡。しかしアメリカ政府が併合を認めなかったため、暫定的にハワイ共和国が樹立する。日本は邦人保護を目的に巡洋艦2隻を派遣し牽制する。 |
| 3月 6日 | 三多摩地区が神奈川県から東京府に編入される。 |
| 3月17日 | 川越大火。午後8時頃に養寿院門前付近から出火し、市の中心部など戸数3315戸のうち1302戸が焼失。複数の土蔵が焼け残ったこともあり、復興時に蔵造りの建物が多く作られた。 |
| 5月10日 | トマト裁判。米国連邦最高裁でトマトが野菜か果物かの論争で野菜の裁定がくだされる。 |
| 1894年(明治27年) | |
| 6月25日 | ヘルマン・オーベルト生誕。ドイツで宇宙旅行協会を立ち上げ、ロケット開発に大きな影響を与えたロケット愛好家にして研究者。 |
| 7月25日 | 日本艦隊と清国艦隊が朝鮮半島西岸の豊島沖で海戦。日本側が英国国旗を掲げていた清国の兵員輸送船高陞号を撃沈したことが戦時国際法上正しかったのかが問題になる。 |
| 7月29日 | 成歓の戦い。日本軍と清国軍が朝鮮半島で衝突、日本軍が勝利。戦死したラッパ手の木口小平が死ぬまでラッパを離さなかったことから、日本中で賞賛される。しかし当初は同日に死亡した白神源次郎が間違ってラッパ手として発表され賞賛された。 |
| 7月31日 | 発明家ハイラム・マキシムが、ロンドン郊外で「フライングマシン」という全長60m・翼長32mもある巨大な複葉機で浮上試験を行う。滑走レールから浮き上がったとされるが機体は大破。飛行したとは認められていない。マキシムはマキシム式機関銃の発明者として有名。 |
| 8月 1日 | 日本と清国が宣戦布告により、正式に開戦。 |
| 9月 | フランス軍内部で、ドイツへの情報漏洩の噂が広がる。 |
| 10月 5日 | 日本初の月刊列車時刻表が発売される。 |
| 10月15日 | フランス軍情報漏洩事件で、参謀本部付きのユダヤ人アルフレド・ドレフュス砲兵大尉が証拠のないまま逮捕される。数少ないユダヤ人将校であるということが大きな要因となった。 |
| 11月24日 | 孫文がハワイのホノルルで反清組織の興中会を創立する。 |
| マンハッタン生命保険ビルがニューヨークに完成。高さ106m、1964年に解体。 | |
| この年、イギリスの作家アンソニー・ホープが『ゼンダ城の虜』を発表。冒険小説のジャンルである「ルリタニアン・ロマンス」の原点となった小説。 | |
| 1895年(明治28年) | |
| 1月 5日 | ドレフュス事件で、ドレフュスが流刑の有罪となる。証拠はなかったが、反ユダヤメディアの追求で軍部は軍法会議で有罪とした。シオニズム運動のきっかけとなる。実際の犯人はフェルディナン・ヴァルザン・エステルアジ少佐。少佐は無罪となったが、このことが世間に漏れ、ユダヤ人を迫害するために国を裏切った男を許した、と大きな反発を買うことになる。 |
| 1月14日 | 日本帝国政府が尖閣諸島が清朝に帰属していないことから、日本領に編入する閣議決定を行う。 |
| 2月12日 | 威海衛の北洋艦隊を包囲。司令官の丁汝昌は降伏を拒否した上で、兵員の助命を条件に戦艦鎮遠の艦内で自殺。 |
| 4月17日 | 日清戦争の講和条約である下関条約(馬関条約)に調印。場所は下関の料亭春帆楼。伊藤博文、陸奥宗光、李鴻章、李經方が出席。 |
| 7月25日 | 夜半、山陽鉄道(現山陽本線)尾道駅-糸崎駅間を走行していた上り軍用列車が、高潮で300mに渡り崩壊した築堤に差し掛かり、機関車と客車23両のうち6両が脱線して瀬戸内海に転落。乗員乗客358人中11名が死亡、98名が負傷。 |
| 10月 8日 | 乙未事変。ロシアの力を借りて開化派政権にクーデターを起こした李氏朝鮮王妃閔妃に対し、三浦梧楼公使らが大院君を擁して再クーデターを図り、日本軍守備隊、朝鮮親衛隊、朝鮮訓練隊などが景福宮に突入。その混乱のさなかに閔妃が殺害される。朝鮮王族同士の権力闘争や朝鮮内部の開化派と事大党の勢力争いに、ロシア、日本の思惑が絡んで起きた事件。 |
| 11月 8日 | フランス、ドイツ、ロシアの三国干渉で、圧力に屈した日本が、清との間で「遼東半島還付条約」に調印。日清戦争で得た遼東半島を返還する。国内は世論が沸騰。政府は臥薪嘗胆をスローガンに掲げる。 |
| 11月27日 | ノーベルが遺言「遺産を管理し、その基金で、人類に貢献した人に分配する」に署名(ノーベル賞制定記念日)。 |
| 11月29日 | 春生門事件。朝鮮の景福宮春生門で、親露派の李範晋らが、閔妃派の旧侍衛隊とアメリカ兵やロシア兵を使って、クーデターを企てた事件。 |
| 12月28日 | 写真技術者であったリュミエール兄弟が独自開発したカメラ映写機シネマトグラフ・リュミエールを使って、初めてパリのグランカフェで投影式の映画を商業公開。 |
| 1896年(明治29年) | |
| 1月25日 | リュミエール兄弟が、『ラ・シオタ駅への列車の到着』を一般公開。ラ・シオタ駅に列車が入ってくる様子をワンショットで撮ったドキュメンタリー映画。観客がその迫力に驚いて逃げ惑った、という俗説があるが、真相は不明。 |
| 2月11日 | 李氏朝鮮王の高宗が、廃位の計画情報を受けてロシア公使館に逃げ込む。露館播遷。 |
| 2月29日 | 日本銀行本店が竣工。辰野金吾設計。 |
| 4月12日 | 逆川事件。静岡県東部の水資源に乏しい駿東地区へ、神奈川県芦ノ湖から供給される深良用水をめぐり、分水を求めていた神奈川県仙石村の須永伝蔵らが、深良用水の権利を持つ水利組合の許可が得られないとして用水施設を壊そうとした事件。水利組合との間で大審院にまでもつれる裁判沙汰となった。深良用水は江戸時代前半の1670年に手掘りで箱根外輪山の山中を通って完成したもので、当時は小田原藩領内だったので問題なかったが、明治維新後に神奈川県と静岡県に分かれてしまった。裁判では静岡県側に水利権があると判決。現在でも芦ノ湖の水利権は静岡県側が持っている。 |
| 6月 3日 | 清とロシアとの間で、露清密約が結ばれる。日本が清(朝鮮を含む)かロシアのどちらかに侵攻した場合は、お互いに軍事援助することと、ロシアによる満洲での鉄道権益を認めることが大きな柱。ロシアは清が抱えた日清戦争賠償金の借款供与の代償にこれを要求し、清側の代表だった李鴻章はこれを受け入れた。 |
| 6月15日 | 明治三陸地震。東北沖200kmの太平洋海底で起きた巨大地震。マグニチュードは8.2以上。揺れはさほどでもなかったが大津波が沿岸一帯を襲い、死者21915人、行方不明者44人。 |
| 8月10日 | 航空技術者オットー・リリエンタールが、試験飛行中に墜落、脊椎を損傷して死亡する。 |
| 8月27日 | 史上最も短い戦争とされる、イギリス・ザンジバル戦争が勃発。約40分で終了。 |
| ドレフュス事件を取材したテーオドール・ヘルツルが『ユダヤ人国家』を出版して、ユダヤ人国家建設についての詳細な提案を行い、シオニズム運動に影響与える。 | |
| 1897年(明治30年) | |
| 2月 5日 | インディアナ州議会下院本会議で、246号議案(通称インディアナ州円周率法案)が可決される。地元のアマチュア数学者エドワード・グッドウィンが発見し著作権を取得したと称した「円積問題の解決法」を、州の公教育でのみ無償で教えるとする法案。 |
| 2月12日 | インディアナ州円周率法案に対し、予算獲得のために来ていたパデュー大学のワルドー教授が異論を唱え、マスコミも奇妙な法案と報道したため、上院では一転して凍結となる。そもそも円積問題は解決できないこと、円周率を3.2にするという間違いを含んでいたこと、数学の公式を著作物として有料化することが許されるのか、という問題を含んだ事件。 |
| 2月20日 | 李氏朝鮮王の高宗がロシア公使館から慶運宮に戻る。 |
| 6月10日 | 古社寺保存法公布。 |
| 8月29日 | 第一回シオニスト会議が、スイスのバーゼルで開催。西ヨーロッパのシオニズム運動家テーオドール・ヘルツルが主催し、東ヨーロッパのシオニズム運動家ナータン・ビルンバウムが協力した。 |
| 10月 6日 | ロシアの駐朝鮮公使アレクセイ・ニコラヴィッチ・ジュペイエルが、度支(財務官庁)の顧問をイギリスの推薦したジョン・マクレヴィ・ブラウンから、ロシア人のキリル・アレキセーフに変えるよう要求。度支顧問事件。 |
| 10月12日 | 李氏朝鮮の高宗、国号を大韓帝国と改め、自主独立を宣言。高宗は皇帝(光武皇帝)を称する。もともと李氏朝鮮は中国系王朝である箕子朝鮮を朝鮮の祖とし、中華帝国を宗主国としていたが(皇帝は中国の君主の称号とする)、清王朝は満州族であることと、その清が日本に敗れたことも影響した。 |
| 10月14日 | クレマン・アデールが、アヴィオン号と名付けた飛行機で飛行に成功したとされる。失敗したという説もあり詳細は不明。フランス政府の支援を受けていたが、この試験の後打ち切られているため、失敗したものか。フランス政府は、ライト兄弟の成功後、アヴィオン号は成功していたと発表。フランスでは飛行機のことをアヴィオンという。 |
| 10月26日 | 大韓帝国、度支顧問のジョン・マクレヴィ・ブラウンの解雇通告。 |
| 11月 5日 | 露韓合同条約締結。大韓帝国、度支顧問にキリル・アレキセーフを任命。 |
| 12月27日 | 度支顧問を巡る問題を受けて、イギリス東洋艦隊が朝鮮仁川に到着。 |
| この年、スコットランドの物理学者チャールズ・ウィルソンが、「ウィルソンの霧箱」を発明。過飽和蒸気の箱の中では粒子や放射線の軌跡を直接観測できることから、物理学の発展に大きく寄与した。1927年にノーベル物理学賞を授与。 | |
| 1898年(明治31年) | |
| 1月21日 | 絶影島問題。朝鮮半島南部の絶影島の日本人借入地にロシア軍艦が入り、貯炭庫を作ろうとした事件。 |
| 2月15日 | メイン号事件。キューバのハバナで米戦艦メイン号が謎の爆沈。米西戦争のきっかけとなる。 |
| 4月25日 | 日本とロシアの間で西・ローゼン協定が締結される。大韓帝国の内政に関する干渉を控え、韓国政府の依頼を受けて軍事・財政顧問を送る場合はお互いに事前承認を求めるとするもの。 |
| 6月10日 | ダルマチア語の最後の話者とされるトゥオネ・ウダイナが爆弾テロに巻き込まれて死亡。ダルマチア語は死語となる。ダルマチア語はアドリア海東岸、クロアチアのダルマチア海岸とダルマチア諸島、モンテネグロのコトル湾沿岸地域でのみ話されていた言語。 |
| 6月11日 | 清の光緒帝が、「明定国是詔」の詔勅を発し、国家全般の近代改革を開始。いわゆる「戊戌の変法」。西洋列強の進出や日本の明治維新と日清戦争の敗北を受けて、近代改革を実施し自強化することを目指したもの。 |
| 6月25日 | 保安条例廃止法により保安条例が廃止。 |
| 7月 7日 | ハワイ共和国をアメリカに併合するニューランズ決議が発効し、ハワイは準州となる。 |
| 8月11日 | 毒茶事件。大韓帝国の高宗と皇太子が、晩餐中にコーヒーに毒をもられる暗殺未遂事件が起きる。10月10日に金鴻陸ら3名が処刑される。 |
| 9月18日 | ファショダ事件。アフリカに植民地を広げていたイギリスとフランスがスーダンのファショダで出くわし軍事対立する。 |
| 9月21日(光緒24年 8月 6日) | 清朝で戊戌の政変が勃発。「戊戌の変法」と呼ばれる近代改革を行おうとした光緒帝と康有為らの官僚グループが、改革を進めるために西太后らを監禁もしくは殺害するという計画があると袁世凱から伝えられ、先手を打って西太后と保守派がクーデターを起こす。改革派は逮捕され、光緒帝も軟禁。康有為や梁啓超らは日本へ亡命することになる。背景には急激な近代化、権力を失うことを恐れた官僚、日本や英米など外国勢力への接近への警戒、康有為が改革思想として独特の儒教解釈をしたことなどが反発を招いた。一方でわずか103日で改革が潰されたことに、清朝への失望も強まり、のちの辛亥革命への動きが生まれることにもなる。 |
| 9月28日(光緒24年8月13日) | 「戊戌の変法」を推進していた譚嗣同・林旭・楊鋭・劉光第・楊深秀・康広仁の6人が、北京の菜市口で処刑される(6人は「戊戌六君子」と呼ばれる)。 |
| 12月 3日 | 山陽鉄道の夜行列車内で、陸軍第12師団の大尉が、金品を盗もうとした二人の男に殺害される事件が起こる。日本の鉄道内で起きた最初の殺人事件とされている。当時の客車に貫通扉がなく一種の密室状態にあったことも事件の要因となったため、改善されることになった。 |
| 12月28日 | ツァボの人食いライオン事件が終結する。ウガンダ鉄道建設中、同年3月ころからツァボ川の鉄橋工事現場に現れた2頭のライオンによって少なくとも28人の建設労働者が殺された事件。ライオンは2頭とも若いオスで、数カ月に渡って対策をとってきた現場総監督のジョン・ヘンリー・パターソンによって射殺された。ツァボ川の現場以外にも、この2頭のライオンによる犠牲者がいるとされ、その数最大で135人ともいわれるがはっきりとはわかっていない。 |
| H・G・ウェルズのSF小説の古典『宇宙戦争』が発刊。 | |
| この年、帝国博物館及び東京美術学校内での九鬼隆一と岡倉天心の関係悪化から岡倉が辞職する事態になり、教授らが分裂する美術学校騒動が起こる。 | |
| 1899年(明治32年) | |
| 3月 2日 | 北海道旧土人保護法公布。経済的に困窮する北海道のアイヌを保護する名目で、同化を図った法律。 |
| 7月20日 | 現在の超高層オフィスビルのはしりとも言えるパークロウビルがニューヨーク市マンハッタン・パークロウに完成。119m、29階建て。 |
| 8月 4日 | 日本で最も古いビアホールとされる「ヱビスビヤホール」が銀座8丁目に開店。ヱビスビールの宣伝のため。 |
| 9月19日 | ドレフュス事件で世間の反発を買ったフランス政府は、冤罪のまま南米のディアブル島に流刑にしていたドレフュスを「特赦」によって釈放する。無罪と認めたわけではなかったため、ドレフュスはその後も無実を主張することになる。 |
| 10月 2日 | 発明家で飛行家のパーシー・シンクレア・ピルチャーが、グライダーのデモ飛行中に墜落。2日後に死亡。すでにこの時、動力式三葉機を設計・完成しており、そのスポンサー探しのためのデモ飛行だったが、エンジンが故障したため、グライダー飛行をしていて墜落した。飛行可能な機体設計だったことから、ライト兄弟より先に初飛行に成功していた可能性が高かった人物。 |
| 10月 7日 | 大雨の中、日本鉄道(現東北本線)矢板駅-野崎駅間の箒川鉄橋で、上野発福島行き第375列車が通過中に突風にあおられて、緩急車と客車7両が濁流の箒川へ転落。死者19名、負傷者38名。 |
| ヘンリー・フォードらがヘンリー・フォード社を設立。しかしフォードは後に退社。社名はキャディラックに変更される。 | |
| 日本初の劇映画「ピストル強盗清水定吉」が制作上映される。制作は駒田好洋・柴田常吉。警官役の横山運平は「日本初の映画俳優」と呼ばれる。 | |
| 1900年(明治33年) | |
| 3月20日 | 元新選組二番組伍長の島田魁が死去。新選組には最後まで残って箱館戦争まで転戦した。新選組に関する記録を多数残している。 |
| 3月30日 | 治安警察法施行。 |
| 4月30日 | 神戸での観艦式で、戦艦富士の軍楽隊によって初めて『軍艦マーチ』が演奏される。 |
| 5月10日 | 皇太子嘉仁親王と九条節子が結婚。 |
| 5月19日 | 陸軍省官制・海軍省官制を改正し、軍部大臣の現役武官制が定められる。 |
| 6月10日 | 山東省で発生した排外主義の義和団の軍勢20万が、北京に侵攻。北京の外国公使館が襲われ、日本公使館書記官の杉山彬が清国兵に殺害される。 |
| 6月15日 | タイ国王ラーマ5世が、インド北部で発見された釈迦の骨とされる「真舎利」を日本に分与するため、日本から各宗派の代表がタイを訪問。ラーマ5世から金銅仏像とともに直接授与される。これをうけて超宗派の寺院「日泰寺」が建立される(当時は「日暹寺」)。 |
| 6月20日 | 義和団の乱のさなか、ドイツ公使クレメンス・フォン・ケーテラーが清国兵に殺害される。 |
| 6月21日 | 義和団の乱を支持した西太后が欧米列強に対し宣戦を布告する。民衆の反乱が国家間戦争へと発展。北京の公使館街「東交民巷」には外国人やキリスト教徒が取り残され籠城。ただし清国政府はここを攻めるつもりはなかったと見られる。一方、劉坤一・張之洞・李鴻章・許応騤・奎俊・袁世凱ら東南各地の総督や有力者らは、列強が進攻してこないよう図り、西太后の布告を否定、独自に列強と交渉して不介入に成功している(「東南互保」)。 |
| 7月13日 | 義和団の乱の軍勢が黒竜江(アムール川)対岸まで進出してきたことを名目に、ロシアは満洲侵攻を企図。黒竜江左岸にあった清国人居留地「江東六十四屯」を攻撃。以降8月にかけて同地で住民への大虐殺を行いこれを占領する。日本がロシアを警戒するようになった事件の一つ。 |
| 7月17日 | 安達太良山で噴火。火口近くにあった沼尻鉱山硫黄採掘所の施設が火砕流に遭い、72名が死亡、10名が負傷。 |
| 8月14日 | 義和団の乱で居留民保護を名目に八カ国連合軍が北京に侵攻。8カ国とは、アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・ドイツ・オーストリア・イタリア・日本。連合軍による破壊と略奪が行われる。馬蹄銀や財宝が強奪される一方、特に欧米人には価値のわからない古書などの文化財の多くが破壊焼却された。 |
| 8月15日 | 義和団の乱で混乱する中、西太后が北京を脱出する際に、光緒帝が寵愛した珍妃の殺害を命じ、宦官の崔玉貴によって紫禁城内の井戸に放り込まれ殺害される。 |
| 8月20日 | 西太后は一転して列強との講和に方針を転換。李鴻章に列強との交渉を委任。光緒帝は自己批判的な「罪己詔」を発する。 |
| 9月14日 | 津田梅子が女子英学塾を創立。 |
| 10月 2日 | 娼妓取締規則発布。娼妓名簿登録制となる。 |
| 10月14日 | ジークムント・フロイトの『夢判断』が出版される。 |
| 3つの帝国博物館を帝室博物館と改称。 | |
| 1901年(明治34年) | |
| 1月10日 | テキサス州のボーモント近郊にあるスピンドルトップのルカス1号油井から原油がはじめて噴出。テキサス油田の始まり。 |
| 1月22日 | イギリス帝国の黄金期と呼ばれた「ヴィクトリア朝」時代の女王、アレクサンドリナ・ヴィクトリアが崩御。現ウィンザー朝の祖でもある。 |
| 2月25日 | アメリカ最大の製鉄会社USスチールが創業。 |
| 7月13日 | 碓氷線退行事故。20時40分ころ横川駅-軽井沢駅を登坂中の長野行き第51列車機関車で、蒸気管が破裂し、噴出した蒸気によって機関車内の機関助士2名が車外に飛ばされ重軽傷。残った機関士が制動を行うも上手く行かず、列車は坂道で自然停止後、退行しはじめたため、乗客1名が飛び降りて軽井沢駅へ向かい事故を通報。さらに同乗していた日本鉄道副社長の毛利重輔男爵は、技術者であったため、危険と判断。乗客に飛び降りるよう指示し、息子の助三郎と列車を飛び降りる。しかし2人は列車に巻き込まれて死亡。列車は約1.9km退行したところで、機関士の制動が成功し停止。車内に残った乗客は無事。 |
| 8月14日 | ドイツ生まれのアメリカ人技術者グスターヴ・ホワイトヘッドが、コネティカット州フェアフィールドで動力飛行試験を実施。最大高度15m、距離800mを飛行したと、当時の新聞に記載されている。しかし写真などの裏付ける証拠は見つかっていない。この前後にも飛行に成功したと主張しているが、正確な記録はない。設計上は飛行可能だったという説もあり、飛行とは認められない「無操縦浮上」という見方もある。 |
| 9月 7日 | 義和団の乱の処理を決める清と8カ国との辛丑条約(北京議定書)が締結される。賠償金として39年間分割で4億5000万両(利息を含めると8億5000万両・歳入の10倍近く)を銀で払う、公使館街の拡張、排外主義の禁止、租界の設置など清にとっては厳しい内容となる。賠償の支払いは減額などを経て中華民国時代の1938年まで続いた。 |
| 9月16日 | 沖縄那覇の辻にある遊郭街で大火。 |
| 11月14日 | カール・ラントシュタイナーがABO式血液型(当時はABC式)を発表。 |
| 11月18日 | 日清戦争で得た莫大な賠償金を元手にして、官営八幡製鉄所が操業開始。当時は官営製鐵所という名称だった(八幡製鉄所は民営の日本製鐵になってから)。 |
| 12月10日 | 田中正造が足尾鉱毒事件の解決を求め、日比谷で明治天皇に直訴しようとするも取り押さえられる。 |
| フィラデルフィア市庁舎が竣工。高さ167m。ルネサンス様式のオフィスビルで、塔の部分が当時世界で最も高かった。 | |
| ペルセウス座GK星の新星爆発が観測される(ペルセウス座新星1901)。その後、この星は矮新星を繰り返すようになる。白色矮星と主系列星の連星で、主系列星から降り積もる物質の質量で白色矮星が新星爆発を起こし、その後は白色矮星の周りにできた降着円盤が崩壊するたびに増光するようになっていると見られる。 | |
| 1902年(明治35年) | |
| 1月23日 | 日本陸軍第8師団の歩兵第5連隊が八甲田山での行軍訓練のため、青森の駐屯地を出発。のち遭難。 |
| 1月25日 | 北海道旭川市で日本における最低気温の記録-41℃を観測(日本最低気温の日)。 |
| 1月30日 | 日英同盟成立。 |
| 5月 8日 | プレー火山噴火。火砕流により、死者3万人以上。 |
| 8月 7日 | 伊豆諸島の鳥島が大噴火。八丈島の実業家玉置半右衛門によってアホウドリを乱獲する事業が行われており、その出稼ぎ労働者125人全員が噴火に巻き込まれて死亡。島の労働環境が劣悪だったことも多数の犠牲者を出した要因か。災害義援金も玉置が受け取ったと言われる。乱獲によりアホウドリはあわや絶滅寸前にまで至った。 |
| 8月22日 | 都電の元祖、東京電車鉄道が、新橋-品川間で路面電車の運行を開始する。 |
| 9月 1日 | 映画『月世界旅行』公開。ジュール・ヴェルヌの『月世界旅行』とH・G・ウェルズの『月世界最初の人間』を組み合わせた内容で、砲弾型ロケットで月に行くストーリー。監督は「世界初の職業映画監督」と呼ばれるジョルジュ・メリエス。ファンタジックな舞台劇風の演出になってはいるが、様々な特撮技法を考案して作られており、SF映画の元祖といわれる。 |
| 10月19日 | 東京専門学校から改名した早稲田大学で、創立20周年記念式典と「大学開校式」が行われる。 |
| 12月17日 | 教科書疑獄事件。当時、学校教科書は道府県単位の検定制度であったため、各教科書出版社は、採用してもらうよう各道府県の担当者に働きかけていた。その一人、普及舎の社長山田禎三郎が置き忘れた手帳から発覚。この日、各社が一斉摘発された。157人が逮捕され、116人が有罪となっている。これを機に政府はかねてより進めていた国定教科書へ変更することにした。 |
| 12月22日 | 年齢計算ニ関スル法律が施行される。年齢を出生の日を起算として暦に従って計算し、起算日応答日の前日に満了する(満年齢)と定める。日本独自の「数え年」から世界で一般的な「満年齢」への移行が進んでいないことと、加齢の日時設定が曖昧だったため。 |
| ヘンリー・フォードが経営方針で対立し、ヘンリー・フォード社を追い出される。社名はキャディラックに変更。 | |
| 1903年(明治36年) | |
| 1月 3日 | アロイス・ヒトラー死去。息子アドルフ・ヒトラーとは対立関係にあり、それがヒトラーの思想に影響したという説もある。アロイスは父親が不明でユダヤ人説もある。 |
| 1月 4日 | コニーアイランド遊園地で買われていた象のトプシーが、飼育員を殺した理由で殺されることになり、直流送電を推していたエジソンの交流送電は危険という宣伝のために交流電流によって公開処刑される。 |
| 2月23日 | スペインより独立したキューバ政府により、グァンタナモ基地がアメリカに永久租借される。 |
| 3月 1日 | 第5回内国勧業博覧会が大阪天王寺で開かれる。7月31日まで。最後の内国勧業博覧会。 |
| 3月15日 | 沖縄県の硫黄鳥島が噴火。8月まで噴火を繰り返し、島民は島外へ移住するかどうかで協議。 |
| 4月21日 | 無鄰庵会議。京都の山県有朋別邸である無鄰庵の洋館で、山縣有朋・伊藤博文・桂太郎・小村寿太郎によって対ロシア政策が話し合われる。桂太郎首相のロシアの満洲権益優越権を認める代わりに日本の朝鮮における権益をロシアに認めさせることで交渉し、そのためには武力も辞さないという態度をとることが決定する。 |
| 5月 7日 | ロシア帝国、李氏朝鮮との間で結んだ森林伐採事業に関する約定を利用し、朝鮮半島への軍事進出を決定。鴨緑江河口の龍岩浦に軍事基地の建設を開始。いわゆる龍岩浦事件。 |
| 6月10日 | 七博士建白事件。東京帝国大学の戸水寛人、富井政章、小野塚喜平次、高橋作衛、金井延、寺尾亨教授と、学習院の中村進午教授の計7人が、政府に対ロシア強硬論を主張する建白書を提出する。 |
| 6月12日 | ロシアの陸軍大臣アレクセイ・クロパトキンが来日。 |
| 6月16日 | ヘンリー・フォードが、自動車製造会社フォードを設立する。 |
| 6月23日 | 無鄰庵会議で決定された対ロシア政策が御前会議で承認される。 |
| 7月20日 | 韓国とロシアが、龍岩浦租借条約を締結。日本政府これに抗議。 |
| 8月13日 | ドイツ人研究者のカール・ヤトーが、ハノーファーで動力飛行試験を行う。30cmほど浮いて、20m飛行したと言われる。操縦していない浮上であるため、初飛行とは認定されていないが、操縦機能は就いており、実際このあと、ヤトーは操縦飛行にも成功し(ドイツで最初に飛行した人物となる)、飛行機会社を設立している。 |
| 10月 7日 | ライト兄弟にも技術を教えたスミソニアン協会のサミュエル・ラングレーが、エアロドロームという動力飛行機の実験を行い失敗。 |
| 11月 4日 | 黄興らが反清組織の華興会を創立する。 |
| 11月21日 | 初の早慶戦。早稲田大学野球部と慶應義塾大学野球部が、三田綱町球場で野球対戦を行う。 |
| 12月 7日 | サミュエル・ラングレーが、動力飛行機エアロドロームの実験を再度行うが失敗に終わる。 |
| 12月17日 | ライト兄弟がノースカロライナ州キティホークの南郊にあるキルデビルヒルズ付近で、動力飛行に成功する。12秒間飛行した。同日4回飛行を行っている。滑走レールを使い、浮上しやすい強風に向かって滑走離陸した。一方で機体を操縦している。正確な記録が残っているものとしては人類初の動力飛行となるため、それ以前の他の研究者が行った浮上記録や、はっきりしない飛行記録については、初飛行と認められていない。なお、この日の飛行は、多くの新聞で否定的に取り上げられ、学者らから批判された。また特許裁判に巻き込まれた他、先を越されたラングレーによって初飛行無効を宣伝されたため、兄弟は不遇な半生を過ごしている。 |
| 1904年(明治37年) | |
| 1月 9日 | ジダーリ平原の戦い。ソマリランドでキリスト教徒の支配からの独立を図ったイスラム教のダラーウィーシュ国とイギリス・エチオピア連合軍が衝突。イギリス側が勝利する。ダラーウィーシュの指導者サイイド・ムハンマドは逃走し、以後各地を転々としながらソマリ族の居住地域で独立運動を展開する。 |
| 2月 6日 | 日露国交断絶。 |
| 2月 8日 | 日本海軍、第一次旅順口閉塞作戦および旅順港内ロシア艦隊への攻撃を開始。日露戦争開戦。 |
| 2月 9日 | 仁川沖海戦。 |
| 2月10日 | 日本政府、公式にロシアへ宣戦布告。 |
| 2月11日 | 日本、大本営を設置。 |
| 2月11日 | 前年の噴火を受けて、硫黄鳥島の住民全員が、主に久米島へ移住。島はいったん硫黄採掘関係者だけになる。その後、国策もあり、再び島に移住者が増えていく。 |
| 2月17日 | プッチーニの歌劇『蝶々夫人』が初演。大失敗に終わるが、以降改良を加えて、代表作になる。 |
| 2月23日 | 日韓議定書締結。 |
| 3月27日 | 第二次旅順口閉塞作戦のさなかに、広瀬武夫中佐が戦死する。最初の「軍神」に指定。 |
| 4月 2日 | 小泉八雲がアメリカで『怪談(Kwaidan)』を刊行。 |
| 4月30日 | 鴨緑江会戦。日本側が勝利し、鴨緑江渡河作戦は成功する。 |
| 5月 2日 | 第三次旅順口閉塞作戦開始。天候悪化により中止が決まるが、連絡が間に合わず、沿岸砲台の攻撃で多数が戦死。閉塞作戦は失敗に終わる。 |
| 5月 4日 | 日本政府、軍事費調達目的の第1回目の外債発行調印にこぎつける。日本側に好意的だったイギリスや、ロシア帝国のユダヤ人虐殺(ポグロム)に反発したアメリカのユダヤ系投資家などを引受先として500万ポンドを発行。 |
| 5月15日 | 旅順港外の老鉄山沖で、日本海軍の主力戦艦6隻のうち、戦艦初瀬が2度触雷し爆沈。救助に当たろうとした戦艦八島も触雷で沈没。八島救援に向かった通報艦龍田も旅順港外で座礁。同日、巡洋艦吉野に巡洋艦春日が衝突し、吉野が沈没。日本海軍は大幅に戦力を失う。 |
| 5月23日 | 主力戦艦2隻を同時に失ったことを受けて、日本海軍は急遽、装甲巡洋艦2隻の建造を決定する(筑波型巡洋戦艦)。 |
| 5月25日 | 南山の戦い。ロシアが金州城市街地南郊に築いた要塞を第2軍が攻撃。同戦役初の要塞攻略戦となる。 |
| 5月26日 | 南山の戦い。日本軍は大きな損害を出すも、ロシア軍が要塞を放棄して旅順へ撤退。乃木希典の長男乃木勝典はこの戦いで腹部に銃弾を受け27日に死亡している。 |
| 6月14日 | 得利寺の戦い。第2軍が得利寺に展開中のロシア軍を攻撃し勝利する。 |
| 6月15日 | 常陸丸事件。ロシアのウラジオストク巡洋艦隊が、通商破壊作戦のため、輸送船和泉丸を拿捕後、乗船者を退去させて撃沈。続けて兵員輸送船常陸丸と佐渡丸を発見しこれを砲撃。常陸丸は撃沈され、船長らイギリス人3名と、将兵ら1091名が戦死(147名は救助)。佐渡丸は大破して236名が戦死するが沈没は免れ沖ノ島へたどり着く。国内ではウラジオストク巡洋艦隊を見失った海軍第2艦隊への批判が噴出。 |
| 6月16日 | ロシアのウラジオストク巡洋艦隊が、イギリス輸送船アラントンを拿捕。 |
| 6月23日 | ロシアの旅順艦隊が、ウラジオストク回航を図り出港するも、連合艦隊に遭遇し断念。 |
| 7月12日 | 日本海軍、旅順港閉塞によるロシア旅順艦隊の無力化を断念。海軍軍令部長伊東祐亨は、陸軍参謀総長山縣有朋に旅順艦隊壊滅の協力を要請。 |
| 7月22日 | ロシアのウラジオストク巡洋艦隊が、ドイツ輸送船アラビアを拿捕。 |
| 7月24日 | ロシアのウラジオストク巡洋艦隊が、イギリス輸送船ナイトコマンダーを撃沈。 |
| 7月24日 | 大石橋の戦い。第2軍がロシア軍の展開する大石橋を攻撃し勝利する。 |
| 7月25日 | ロシアのウラジオストク巡洋艦隊が、ドイツ輸送船テアを撃沈し、イギリス輸送船カルカスを拿捕。 |
| 7月26日 | 日本陸軍による大孤山などの攻略を開始。 |
| 7月30日 | 大孤山陥落。 |
| 8月 5日 | 日本陸軍、東京湾要塞と芸予要塞に設置されている二十八珊米榴弾砲(二十八サンチ砲)を朝鮮鎮海湾と対馬大口湾に移設することを決定。さらにその後、旅順攻略戦への投入を決める。 |
| 8月 7日 | 日本海軍、大孤山に観測所を置き、旅順港へ12センチ砲での砲撃を開始。 |
| 8月 9日 | 旅順艦隊の各艦に日本側の砲弾が命中。旅順艦隊は再びウラジオストク回航を決定。 |
| 8月10日 | 黄海海戦。旅順艦隊を発見した連合艦隊が追撃し、混乱して各艦ばらばらになった旅順艦隊は、各地で座礁、拿捕、鹵獲などが相次ぎ艦隊戦力を喪失。 |
| 8月14日 | 蔚山沖海戦。旅順艦隊と合流すべく南下していたウラジオストク巡洋艦隊と、第2艦隊が遭遇。砲撃戦によりロシア側は巡洋艦1隻が沈没、2隻が小破。 |
| 8月19日 | 日本陸軍第3軍による旅順要塞総攻撃を開始。熾烈な砲撃戦のあと、各要衝攻略のため歩兵突撃を開始。 |
| 8月20日 | コルサコフ海戦。黄海海戦から逃れた旅順艦隊の巡洋艦ノヴィークが太平洋側からウラジオストクを目指すも燃料不足で樺太コルサコフに寄港。追ってきた日本側の巡洋艦千歳と対馬との間で砲撃戦となる。ノヴィークは自ら座礁して乗員は対艦。 |
| 8月24日 | 乃木希典、旅順要塞第1次総攻撃を中止。戦死者5017名という甚大な被害を出す。 |
| 8月30日 | ロシア軍、日本軍が占領した盤龍山堡塁を奪還するため攻撃をしかけるも失敗に終わる。 |
| 9月 1日 | 第3軍、旅順要塞攻略のため、塹壕の建設を開始。 |
| 9月19日 | 第3軍、旅順要塞第2次総攻撃1回目を開始。 |
| 9月20日 | 第3軍、水師営と海鼠山を占領。 |
| 10月 1日 | 第3軍、海鼠山に観測点を置き、二十八糎榴弾砲を投入し旅順港砲撃を開始。 |
| 10月 9日 | 日露両軍による沙河会戦。沙河でロシア側が積極攻勢をかけるが、膨大な死傷者を出し断念。しかし日本側も反撃で大きな被害を出す。 |
| 10月16日 | ロシアのバルチック艦隊が出港。 |
| 10月26日 | 第3軍、第2次総攻撃2回目を開始。 |
| 10月30日 | 乃木希典、第2次総攻撃を中止。多数の戦死者を出すも、ロシア側の被害も深刻となる。 |
| 11月14日 | 御前会議で203高地攻略が決定する。艦隊砲撃用観測点を確保するため。しかし現地の満洲軍総司令官大山巌は、要塞攻略を目的とすべきと反発。 |
| 11月26日 | 第3軍による旅順要塞第3次総攻撃が開始される。 |
| 11月27日 | 乃木希典、旅順要塞攻撃から、203高地攻略へ方針を変更(観測点確保ではなく、ロシア側に消耗を強いるためともいわれる)。二十八糎榴弾砲による砲撃を開始。 |
| 12月 1日 | 乃木希典、203高地攻略を一時中断。ここまで、何度か山頂の一部を占領するも、奪還されることを繰り返す。乃木希典の次男も戦死。 |
| 12月 5日 | 第3軍が203高地を完全占領。すぐに観測点を設け、残存旅順艦隊への砲撃を開始。旅順艦隊は壊滅。日本側5052名が戦死。 |
| 12月10日 | 第3軍が東鶏冠山北堡塁への攻撃を開始。 |
| 12月15日 | 旅順艦隊で唯一港外へ脱出していた戦艦セヴァストポリが日本海軍の水雷艇の攻撃を受けて大破着底。 |
| 12月15日 | ロシア軍の勇将コンドラチェンコ少将が戦死。ロシア側の士気を大きく下げたと言われる。 |
| 12月18日 | 第3軍、東鶏冠山北堡塁が陥落。 |
| 12月20日 | 三越デパートの誕生。江戸時代の呉服商「越後屋」が元の三井呉服店が三越呉服店と改称。「デパートメントストア」宣言を行う。 |
| 12月28日 | 第3軍、二龍山堡塁攻撃を開始。 |
| 12月29日 | 第3軍、二龍山堡塁陥落。 |
| 12月31日 | 第3軍、松樹山堡塁への攻撃を開始し、これを占領。 |
| この年、ドイツは南西アフリカ(現ナミビア)で、ドイツの侵攻に抵抗した先住民のヘレロ族とナマクア族に対する虐殺を行う。ヘレロ族の8割、ナマクア族の5割が殺されたと言われる。 | |
| 東北帝大大学院生の矢部長克が異常巻きアンモナイトを発見したことを発表。当初は奇形の可能性が指摘されていたが、後に同様の化石が発見されたことで種と認められ、Nipponites mirabilisと名付けられた。3次元的に絡まったような異常巻の形状は長いこと進化の終末期の異常形態とみなされていたが、近年は環境に適応した独自の進化(適応放散)と考えられている。矢部長克は当初から異常ではないと見ていた。矢部は後に日本地質学・古生物学の第一人者となっている。 | |
| 1905年(明治38年) | |
| 1月 1日 | 第3軍、望台への攻撃を開始し、これを占領。旅順要塞司令官のアナトーリイ・ミハーイロヴィチ・ステッセリ中将は降伏を決定。 |
| 1月22日 | ロシア血の日曜日事件。サンクトペテルブルクで社会状況の改善を求めた労働者に兵士が発砲。千人以上が死亡する。ロシア革命の遠因。ロシアのユリウス暦で1月9日。 |
| 1月23日 | 奈良県東吉野村鷲家口でニホンオオカミの最後の一匹が捕獲される。 |
| 1月25日 | 日露両軍による黒溝台会戦。機関銃の投入と塹壕戦が本格的に行われたはじめての戦い。ロシア軍が退却したため、日本側の辛勝。 |
| 1月28日 | 日本政府は閣議で竹島を島根県隠岐島司の所管の島と決定。 |
| 2月21日 | 日露両軍による奉天会戦。両軍甚大な被害を出すがロシア軍が退却。 |
| 5月27日 | 日本海海戦。大国ロシアのバルチック艦隊を小国日本の連合艦隊が撃破したことで世界中に衝撃を与える。艦隊規模はロシアのほうが上だったが、長距離回航だった上に、日本側が新技術の導入や情報収集で優位に立ったことが結果につながった。また斉射という制御された長距離砲戦術が導入されたことは、戦艦設計思想に影響を与え、ドレッドノート級戦艦の建造に発展する。 |
| 5月28日 | バルチック艦隊の特務艦のイルティッシュ号が島根県和木の沖合で航行不能となり投降。同艦は翌日沈没。 |
| 5月31日 | 小村寿太郎外相が米国政府にロシアとの交渉仲介を依頼するよう高平小五郎駐米公使に訓電。 |
| 6月 7日 | スウェーデンの属領となっていたノルウェーが、デンマークのカール王子を国王ホーコン7世として迎えた上でスウェーデンからの独立を宣言。スウェーデン国民の反発を買うも、スウェーデン国王オスカル2世による説得もあり、10月26日に承認された。なお、ホーコン7世はオスカル2世の大甥でもある。 |
| 6月22日 | 堀江六人斬り事件。大阪の堀江遊郭にあった「山梅楼」の主人中川萬次郎が、妻女とのもつれから狂気に走り、家族や芸妓ら6人を日本刀で斬り5人が死亡、1人が重症を負った事件。 |
| 6月27日 | ロシア帝国海軍黒海艦隊に所属する戦艦ポチョムキンで水兵らが反乱。 |
| 6月30日 | アルベルト・アインシュタインが特殊相対性理論に関する最初の論文「運動している物体の電気力学について」をドイツの物理雑誌『アナーレン・デル・フィジーク』に提出。 |
| 7月 7日 | 樺太の戦いが始まる。講和を有利に進めようとした日本側が樺太に侵攻。 |
| 7月31日 | 樺太の戦いが終結。ロシア軍のリャプノフ中将が降伏し、日本は樺太を占領する。 |
| 8月10日 | 日露講和会議が米国の仲裁で、アメリカポーツマスの海軍造船所で始まる。 |
| 8月24日 | 戸水寛人東京帝国大学教授が日露講和会議に反対する論文を発表して休職となる。 |
| 8月28日 | 御前会議で、賠償金取得や領土割譲を放棄してでも講和すべきだと決定する。 |
| 8月29日 | 日露講和成立。 |
| 9月 1日 | 日露休戦条約締結。 |
| 9月 4日 | ポーツマス条約締結。革命前夜の不穏な状況にあるロシアに対し、継戦能力を失った日本側が妥協したため、ロシア軍が満洲から撤退し、日本が南樺太の領有権と、満州南部・関東州の租借権と鉄道の運営権、沿海州の漁業権、大韓帝国に対する排他的権利を得るという当初目的を達成するも、賠償金は得られず。 |
| 9月 5日 | 日比谷焼打事件。日露戦争の講和交渉で、賠償金を得られないという内容を知った民衆が暴動を起こす。これは交渉前、マスコミや一部学者・知識人らが賠償金30億円は取れるなどと煽ったことと、対ロシア交渉のため、日本政府が継戦能力喪失という実情を国民に説明できなかったため。 |
| 9月 6日 | 東京に戒厳令が敷かれる。 |
| 9月11日 | 佐世保港内で戦艦三笠の弾薬庫が爆発し沈没。339名が死亡。原因は不明。 |
| 9月14日 | 日本陸軍満洲軍が戦闘停止。 |
| 9月27日 | アインシュタインの特殊相対性理論の論文『物体の慣性はその物体のエネルギーに依存するか?』が科学雑誌に掲載される。有名なE=mc2が掲載。 |
| 10月10日 | 日本政府、ポーツマス条約を批准。 |
| 10月14日 | ロシア政府、ポーツマス条約を批准。日露戦争終結。 |
| 10月17日 | 小村寿太郎が帰国。講和を批判する右翼などから狙われていたため、特別列車で新橋駅に到着した際に、桂太郎首相と山本権兵衛海相が小村寿太郎を挟むようにしてかばったと言われる。 |
| 11月17日 | 第二次日韓協約締結。大韓帝国の外交権が失われる。 |
| 12月12日 | 日清両国が満洲善後条約を締結。ポーツマス条約によってロシアから日本へ満洲・関東州の諸権限が移ったことを清国が承認するという内容。 |
| 12月21日 | 韓国統監府設置。伊藤博文が初代統監となる。 |
| 1906年(明治39年) | |
| 2月10日 | 英海軍の戦艦「ドレッドノート」が進水。「弩級(ド級)」「超弩級(超ド級)」の語源となった軍艦。副砲などを廃止し単一連装主砲を5基も搭載して斉射力を高め、蒸気タービン機関を採用して高速化を図ったもので、旧式艦に比べて長距離砲戦で絶対有利になったことから、これを機に各国海軍の建艦計画は根底から変更されることになった。 |
| 3月31日 | 鉄道国有法公布。陸上輸送の要である鉄道の国家管理の目的の他、日露戦争戦費調達のため発行した莫大な外債を低利に切り替えるための担保という目的があった。 |
| 7月12日 | ドレフュス事件で冤罪のまま流罪となったユダヤ人将校ドレフュスの無罪が認められる。軍に復帰するも、流刑中の環境により健康を害しており、まもなく退役。 |
| 8月 8日 | 佐世保港内で事故で爆沈した戦艦三笠を引き上げる。 |
| 9月11日 | 路面電車を運行する東京電車鉄道、東京市街鉄道、東京電気鉄道が統合し、東京鉄道が誕生。 |
| 10月 1日 | 鉄道国有法により私鉄の買収が始まる。翌年にかけて主要な私鉄が順次買収国有化。 |
| 11月 1日 | 日本鉄道が国有化。ここまでに東日本の大半の鉄道路線を敷設した。 |
| 11月26日 | 南満洲鉄道(満鉄)設立。 |
| 1907年(明治40年) | |
| 1月12日 | セルゲイ・パーヴロヴィチ・コロリョフ生誕。ソ連の航空技術者、ロケット技術者として大陸間弾道ミサイルと宇宙ロケット開発にあたった人物。 |
| 3月20日 | 東京府の主催で、上野公園などを会場に「東京勧業博覧会」が開催される。7月31日まで。 |
| 4月 1日 | 国有鉄道の現業部門、帝国鉄道庁が発足。 |
| 5月 7日 | 新たに皇室令が公布され、それにともない華族令も新たに公布され、旧華族令は廃止される。 |
| 5月31日 | 大阪駅の駅員清水太右衛門が同駅西第一踏切で踏切番の勤務中、踏切内に入った幼女を発見し保護するも西成線の列車に接触。太右衛門は翌日死亡。その後、多数の義捐金が集まり、殉職記念碑が建てられた。 |
| 6月 | 大韓帝国皇帝高宗が第2回万国平和会議に密使を送り、列強に支援を求めるも拒否される。いわゆるハーグ密使事件。 |
| 7月20日 | 大韓帝国皇帝高宗が退位させられる。純宗が即位。 |
| 7月24日 | 第三次日韓協約で日本が韓国内政権を得る。 |
| 8月 1日 | 大韓帝国軍が解散させられる。 |
| 8月 1日 | ロバート・ベーデン=パウエルが、21名の少年を連れて、ブラウンシー島でキャンプを行う。ボーイスカウト活動の始まり。 |
| 9月26日 | ニュージーランドが英連邦内の自治国として独立。 |
| 11月16日 | アメリカ政府が、オクラホマ準州とインディアン・テリトリーを統合して、オクラホマ州に格上げし、インディアン・テリトリーはすべて消滅。 |
| 12月17日 | ブータンの東部トンサの有力者ウゲン・ワンチュクがチベット仏教界や有力貴族、国民の代表らの会議で、宗教・世俗を超えた国王として認められ、初代ブータン国王に即位。 |
| この年、アドルフ・ヒトラーは、ウィーン美術アカデミーを受験するも失敗。課題提出が足りなかったことや作風が当時の流行に合わなかったことなどがあると言われる。この年、ヒトラーの母クララも病死し、ヒトラーの思想形成に大きな影響があったとされる。 | |
| 1908年(明治41年) | |
| 3月 5日 | 日本初の美人コンテスト。日本初のミスに選ばれたのが、学習院女子部3年生の末弘ヒロ子。 |
| 3月 7日 | 青函連絡船に日本初の蒸気タービン船比羅夫丸が就航。 |
| 3月22日 | 東京大久保で風呂屋から出てきた女性が殺害される。池田亀太郎が犯人として逮捕され、彼のあだ名が出歯亀だったことから、覗き魔を意味する「出歯亀」の語源となる。「でばがめ」は、でしゃばりの亀(出張亀)という説も。 |
| 5月 | 実業家の山田禎三郎が、小笠原諸島の東北東560浬に「中ノ鳥島」を発見し、前年に調査したとする詳細な報告書を小笠原庁に提出。以降、「中ノ鳥島」は日本の領土とすべく政府にまで報告が上がり、閣議で承認されたが、幾度かの調査にも関わらずその比定場所に島は存在せず、1943年に公式記録から抹消された。山田禎三郎がなぜ詳細な報告書を提出したのかは謎のまま。ちなみに山田禎三郎は教科書疑獄事件のきっかけを作った人物でもある。 |
| 6月30日 | シベリアのエニセイ川の支流、ポドカメンナヤ・ツングースカ川上流の森林地帯で、謎の大爆発が起こる。落下してきた小規模の隕石が空中爆発を起こしたものと考えられ、その規模は5Mtに匹敵すると言われる。2150平方kmの範囲で樹木が倒壊。天然ガスの大規模爆発説のほか宇宙人の乗った宇宙船の爆発説まで登場したが、近年の調査で隕石とほぼ断定されている。また、8kmほど離れたところにあるチェコ湖という小さな湖が、この時生じたクレーターかどうかで論争となっている。 |
| 7月 3日 | オスマン帝国の軍の青年士官らが、憲法復活を求めて武装蜂起。鎮圧軍も加わる。 |
| 7月 4日 | グレン・カーチスが自作の飛行機での飛行に成功する。ライト兄弟の初飛行(1903年)は、この時は公式に認められていなかったため、カーチスが初飛行を「公認」された最初の人物となった。 |
| 7月23日 | オスマン帝国皇帝アブデュルハミト2世が軍の反乱を受けて憲法復活を認める。議会も復活。青年トルコ人革命。 |
| 8月25日 | ウランから出る放射線(アルファ線)を発見した物理学者アンリ・ベクレルが死去。アルファ線はアルファ粒子の流れで、アルファ粒子はヘリウム4の原子核(陽子2個・中性子2個)のこと。不安定な原子核はアルファ崩壊を起こしてアルファ粒子を放出し、陽子2個・中性子2個分減っていく。ウラン238はアルファ崩壊すると不安定なトリウム234に変わる。アルファ崩壊が繰り返されると、最終的に鉛などの安定物質になる。 |
| 8月30日 | ナータン・ビルンバウムらの指導のもと、チェルノヴィッツでイディッシュ語世界会議を開催。「ユダヤ民族」の定義と主導権をめぐり、イディッシュ語を使う東欧ユダヤ人と、西欧ユダヤ人の間で対立が大きくなる。 |
| 9月17日 | ライト兄弟のライトフライヤー号が、バージニア州のフォートマイヤー陸軍基地でデモフライト中に墜落。操縦していたセルフリッジ中尉が死亡。飛行機事故による最初の死亡者となった。 |
| 11月14日 | 清朝の光緒帝が崩御。病死と考えられてきたが、近年、遺髪から猛毒のヒ素が検出されたことから、毒殺説が有力になりつつある。その場合、殺害を命じたのは、対立関係にもあった西太后、戊戌変法の際に裏切った袁世凱、宦官の有力者として専横していた李蓮英等が挙げられている。 |
| 11月15日 | 清朝の西太后も崩御。 |
| 11月15日 | ベルギー政府は、ベルギー王レオポルド2世の私領「コンゴ自由国」での住民に対する残虐非道な行為の数々が各国で批判を浴びたことを受け、国王と条約を結び、国王に補償金を出す代わりに、領地を事実上買い上げて、国王の私有地から、ベルギー領コンゴとなる。 |
| 12月 5日 | 帝国鉄道庁が内閣鉄道院となる。 |
| シンガーミシンの本社ビルとなったシンガービルがニューヨークに完成。186.57m。ほんの一時期世界一の高さだった。1968年解体。倒壊や崩壊ではなく、解体作業で壊されたビルではもっとも高いとされている。 | |
| 1909年(明治42年) | |
| 4月 6日 | ロバート・ピアリーの探検隊が北極点に到達。 |
| 4月18日 | ジャンヌ・ダルクがローマ教皇ピウス10世によって列福される。 |
| 5月 6日 | 大学昇格を目指していた東京高等商業学校の専攻部について、文部省が文部省令を出し、1911年をもってこれを廃止すると決定。代わりに本科生の学生は帝国大学商科大学に入学を認めるとする。いわゆる申酉事件。 |
| 5月11日 | 文部省の東京高等商業学校専攻部廃止の決定に反発した、東京高等商業学校の全学生が、総退学を決議。神戸高等商業学校もこれに同調する。 |
| 5月20日 | 鈴木製薬所が味の素を発売。 |
| 6月11日 | 佐賀市内で嬰児60人以上を金銭で引き取ったあと殺していた夫婦に死刑確定。1913年2月8日に死刑執行。 |
| 6月19日 | 太宰治、青森県北津軽郡金木村に生誕。本名は津島修治。父親は地元の名士である大地主。 |
| 6月25日 | 申酉事件を受けて、渋沢栄一が調停に乗り出し、東京高等商業学校専攻部の4年間存続が決定。 |
| 7月27日 | オーストラリアからイギリスへ向かっていた大型貨客船ワラタが南アフリカダーバンを出港した翌日、乗員乗客211名とともに消息を絶つ。直前まで複数の船に目撃されているにもかかわらず忽然と姿を消したため、原因は諸説ある。英海軍をはじめ多くの調査が行われたが今以て不明のまま、残骸も遺体も発見されていない。一発大波と呼ばれる巨大波に遭遇して短時間で転覆沈没したという説もある。 |
| 7月31日 | 大阪「北の大火」。空心町のメリヤス工場から出火し、強風の中、翌日にかけて西へ類焼し福島に達する。軍まで動員して消火を行ったが、焼失家屋11,365戸、官公庁11、学校8、橋21などが焼け落ちた。死者は3名、負傷者は689名。 |
| 10月 8日 | クロアチアの地震学者アンドリア・モホロビチッチによってモホロビチッチ不連続面が発見される。地震波P波の伝達が速くなる場所で、地殻とマントルの境界面を指す。すなわちマントルは柔らかいのではなく逆に硬いということが判明。 |
| 10月12日 | 鉄道院告示第54号によって鉄道院の各路線名が制定される。現在まで続く鉄道路線名の始まり。 |
| 10月26日 | 韓国統監伊藤博文がロシアとの交渉でハルビンを訪れた際に、安重根に射殺される。 |
| ニューヨークにメトロポリタン生命保険会社タワーが完成。時計塔の部分が高さ213.36m。1913年まで世界一。 | |
| この年、パレスチナの地中海沿岸にある古代都市ヤッフォ(ヤッファ、ヤーファー)の近郊砂丘に東欧から移住したユダヤ人が新都市建設を始める。テルアビブ(春の丘)と命名。 | |
| 1910年(明治43年) | |
| 1月23日 | 逗子開成中学校の生徒ら12人が、無断で学校のボートに乗り込んで海に出たところ遭難。全員が死亡する。歌や小説の題材にもなった事故。 |
| 3月26日 | 安重根の死刑執行。 |
| 4月15日 | 第六潜水艇事件。第六潜水艇がガソリン潜航実験の訓練中に浸水沈没。乗員はパニックに陥ることもなく配置についたまま死亡していたため、世界から賞賛される。 |
| 5月14日 | イギリスロンドンのシェパーズ・ブッシュで日英博覧会が始まる。10月29日まで。 |
| 5月19日 | ハレー彗星が地球にもっとも接近する。シアンガスで人類は全滅するといった噂が流れパニックになる。 |
| 5月31日 | 南アフリカ連邦が成立。 |
| 8月20日 | 世界最初の超弩級戦艦オライオンが英国ポーツマス海軍造船所で進水。 |
| 8月22日 | 韓国統監寺内正毅と大韓帝国首相李完用が漢城で「韓国併合ニ関スル条約」に調印。 |
| 10月23日 | タイ・チャクリー王朝5代王ラーマ5世が死去。奴隷制の廃止や教育改革などを推し進め、タイの近代化を行った人物として評価が高い。タイが植民地化されなかったのはこの近代改革が影響しているとも言われる。 |
| 11月14日 | アメリカ海軍は、軽巡洋艦バーミングハムに飛行甲板を取り付け、飛行機の発艦実験を行う。ユージン・バートン・イーリーが操縦するカーチスDで成功(発艦のみ)。 |
| 11月22日 | ブラジル海軍の反乱。この時代、ブラジル海軍は士官が白人であるのに対し、水兵はムラートや黒人が当てられ、ちょっとしたことでも鞭打ち刑などを行っていた。11月21日、黒人水兵に対する250回もの鞭打ちが行われたことに反発した新鋭弩級戦艦ミナス・ジェラエスの水兵が反乱。他の艦船でも次々と反乱が起こり、海軍は機能停止状態に追い込まれる。 |
| 11月26日 | ブラジル海軍の反乱に対し、ブラジル議会は、海軍の奴隷的制度の廃止と、反乱参加者への恩赦を決定。 |
| 12月13日 | ビタミンの日。鈴木梅太郎が、脚気を予防する成分を抽出する方法を確立し「アベリ酸」と命名して東京帝国大学講堂で発表。オリザニンとして発売され、のちビタミンB1と判明。 |
| 12月14日 | 日野熊蔵が、代々木練兵場で、飛行機を滑走中に浮上する。これをして日本人で初めての飛行機操縦とする説もある。ただし一時的な浮上で「飛行操縦」をしたと言えないという説も。 |
| 12月19日 | 徳川好敏と日野熊蔵が、代々木練兵場で、日本人で初めて飛行機を離陸させ操縦する。 |
| 1911年(明治44年) | |
| 1月12日 | オーストリア=ハンガリー帝国の軍人テオドール・エードラー・フォン・レルヒ少佐が高田歩兵第58連隊に、高田の金谷山などで指導。日本近代スキーの発祥。 |
| 1月18日 | 大逆事件(幸徳事件)の判決で、幸徳秋水ら24名に死刑、2名に有期刑の判決が下される。12名が処刑され、5名が特赦による死一等減刑で無期刑となり獄死。 |
| 1月18日 | アメリカ海軍は、装甲巡洋艦ペンシルベニアの後部に飛行甲板を取り付け、飛行機の着艦実験を実施。前年世界で初めて発艦に成功したユージン・バートン・イーリーが操縦して成功。この頃はまだ航空機も初期型で、海上での運用は現実的ではなかったため、空母への発展までは行かなかった。 |
| 1月30日 | フィリピンのルソン島にあるタール湖内のタール火山で噴火。火砕サージが発生して1307人が死亡。 |
| 3月29日 | 日本ではじめて、労働時間や年齢制限などを定めた「工場法」が公布される。 |
| 4月 3日 | 日本橋が石造りアーチ橋になる。設計には米元晋一、妻木頼黄、渡辺長男らが関わる。 |
| 4月 9日 | 吉原大火。午前11時30分頃、東京市浅草区の吉原遊郭の一角から出火し、吉原全体に火は広がる。さらに周辺の家屋などにも延焼していき、約6500戸を焼失する大火災となる。 |
| 8月 1日 | 東京市が東京鉄道を買収。路面電車は東京市電となる。 |
| 8月 8日 | 長野県北安曇郡小谷村の稗田山で大規模な山体崩壊が発生。26人が死亡。豪雨が原因か。川をせき止めて天然ダムができ、後に決壊して住居・農地に大きな被害を出す。 |
| 10月10日 | 中国の武昌で反清武装蜂起が起こり、辛亥革命が勃発。 |
| 10月19日 | 世界で初めて飛行機で艦船からの発艦と、艦船への着艦を成功させたパイロット、ユージン・バートン・イーリーが墜落事故死する。 |
| 10月24日 | アメリカ・ロードアイランド州ニューポート市にあるライムロック灯台の女性灯台守アイダ・ルイスが死去。女性の灯台守としても、また多数の遭難者を救ったことでも知られる人物。 |
| 11月 1日 | 鴨緑江橋梁が開通。船舶を通すため、中央部分が90度回転する可動橋。 |
| 12月14日 | ノルウェーのロアール・アムンセン隊が南極点に史上初めて到達。 |
| 12月29日 | モンゴルの独立運動で、チベット人活仏のジェプツンダンバ・ホトクト8世がハーンに即位する(ボグド・ハーン)。 |
| 1912年(明治45年・大正元年) | |
| 1月 6日 | アルフレート・ヴェーゲナーが大陸移動説を発表。 |
| 1月 9日 | 世界最初の高層ビルとも言われるエクイタブル生命保険ビルが火災で崩壊。 |
| 1月16日 | 白瀬矗率いる日本の南極探険隊が南極大陸に到着。 |
| 1月16日 | 大阪南区「ミナミの大火」。難波新地乙部遊廓、千日前繁華街が全焼。約5000戸が焼失。再開発に伴い移転を求められた各遊郭は阪南土地会社を設立し、1916年、南の天王寺村阿倍野墓地のそばの何もなかった場所に移転開業する(いわゆる飛田遊郭。遊郭全体を一種の企業とした初期の例)。千日前繁華街は千日土地建物会社が設立され、テーマパークの建設へと動き出すことに。 |
| 1月17日 | イギリスの南極遠征隊(テラノバ遠征隊)のうち極点へ向かったスコット大佐ら5名がアムンセンに遅れること1ヶ月で南極点に到達。アムンセンが帰途に遭難した場合を想定し、2番めに到達する隊へ宛てて、南極点に到達したことをノルウェー国王に報告する手紙を残していたことから、スコットはそれを持って帰途につく。 |
| 1月31日 | 日本ではじめて、中央線に女性専用車両が導入される。 |
| 2月 4日 | 発明家フランツ・ライヒェルトが、自作のパラシュートスーツを着てエッフェル塔のデッキから飛び降りるが、パラシュートは開かず、地面に激突して死亡。一部始終は映像に残されている。飛び降りる寸前に心臓発作を起こして死亡したという説もある。 |
| 3月23日 | ヴェルンヘア・マグヌス・マクシミリアン・フォン・ブラウン生誕。一般にはヴェルナー・フォン・ブラウンで有名なロケット研究者。ドイツの貴族で、のちナチスのV2やアメリカのアポロ計画に深く関わった人物。 |
| 3月25日 | 文部省は東京高等商業学校専攻部の専攻部の存続を決定。1909年から続く申酉事件は一旦、東京高商側の勝利に終わる。しかし、その後も文部省内部で、東京高商を廃止し、東京帝国大学に一本化する動きが続く。 |
| 3月29日 | 南極点から帰途中のスコット大佐が日記を最後に記した日。残っていた3人全員が間もなく凍死したものと思われる(他2人はその前に死亡)。猛吹雪に阻まれ、物資補給キャンプのわずか18km手前だった。 |
| 4月14日 | 豪華客船タイタニック号が氷山に衝突し翌日未明に沈没。死者は1513人(犠牲者数は諸説あり)。 |
| 4月22日 | 膃肭獣保護条約締結により臘虎膃肭獣猟獲禁止ニ関スル法律が制定される。臘虎はラッコ、膃肭獣はオットセイのこと。毛皮確保のための乱獲を取り締まる法律。 |
| 5月 5日 | 第5回夏季オリンピックストックホルム大会開催。日本がアジア諸国で初めて参加した近代オリンピックで、長距離走の金栗四三と、短距離走の三島弥彦の2名が出場。金栗はマラソンに出場し、途中で棄権したが記録されなかったため、1967年の55周年記念イベントに招待された際にゴールし、非公式ではあるものの54年8か月6日5時間32分20秒3で世界一遅いマラソン完走記録となった。このマラソンは異常な暑さという気象条件から棄権が続出。ポルトガルのフランシスコ・ラザロは死亡しており、オリンピック初の死者となっている。この大会までは金メダルはメッキではなく純金製だった。エジプトがアラブ諸国で初参加しているほか、アイスランド、ポルトガル、セルビアも初参加。 |
| 7月 3日 | 初代通天閣が遊園地「ルナパーク」にオープン。 |
| 7月30日 | 明治天皇が崩御。 |
| 8月 5日 | 東京有楽町に設立されたタクシー自働車株式会社が、この日に、日本最初のタクシー営業を開始する予定だったが、明治天皇の崩御やタクシーメーターの取り付け遅れから、延期になる。しかしこれを記念したタクシーの日となっている。 |
| 8月15日 | タクシー自働車株式会社が、上野駅、新橋駅でタクシーの営業を開始。 |
| 9月13日 | 明治天皇の大葬が青山練兵場で行われる。遺体は列車で京都へ。乃木希典夫妻が殉死。 |
| 9月14日 | 明治天皇の遺体は、京都の伏見桃山陵に埋葬。 |
| 10月 8日 | 第一次バルカン戦争勃発。オスマン帝国・オーストリア=ハンガリー帝国と、バルカン同盟との戦争。 |
| 1913年(大正2年) | |
| 3月28日 | バルセヴァール飛行船の公開テスト飛行で、所沢-青山練兵場間の飛行に成功。しかし着陸に失敗。さらに飛行に並走した陸軍の軍用機が所沢に帰還する際に突風で翼が折れて墜落。木村鈴四郎陸軍歩兵中尉と徳田金一陸軍歩兵中尉が300m上空から地上に落下し殉職。日本最初の航空死亡事故となる。 |
| 4月24日 | 当時世界一高いオフィスビル、ウールワースビルがニューヨークで開業。241.4mで、1930年まで世界一の座にあった。ゴシック・リバイバル様式で、教会聖堂を思わせるデザイン。 |
| 5月30日 | 第一次バルカン戦争終結。オスマン帝国はバルカン半島の一部の領有権を放棄。放棄した土地を巡って、バルカン諸国同士で対立。 |
| 6月 4日 | イギリスのエプソム競馬場で開催されたダービーステークスで、女性参政権運動「サフラジェット」のメンバーだったエミリー・ワイルディング・デイヴィソンが、コースに侵入し、ジョージ5世の所有する馬アンマーと衝突。アンマーは転倒し、騎手のハーバート・ジョーンズが重症を負い、エミリーは跳ね飛ばされて4日後に死亡。彼女が王の馬と知って衝突したのか、何をしようとしていたのかは諸説ある。 |
| 6月10日 | 森永ミルクキャラメルが誕生。 |
| 6月13日 | 陸軍省官制および海軍省官制を改正し、軍部大臣・次官の任用資格を現役将官に限るとする規定を削除し、予備役に拡大。軍部大臣現役武官制の廃止。 |
| 6月25日 | 日本ハリストス正教会のクリスチャンで、最初の日本人司祭だった沢辺琢磨が死去。坂本龍馬のいとこでもある人物。 |
| 6月29日 | 鹿児島で火山性の地震が発生。桜島大噴火の前兆現象とみられる。以後異変が相次ぐも、鹿児島測候所が噴火はないと発表したため、信じなかった住民は自主避難を始める。 |
| 6月29日 | ブルガリアがセルビアとギリシャに侵攻。バルカン諸国は対ブルガリア連合を組んでこれに対抗。第二次バルカン戦争。 |
| 7月10日 | ルーマニアが第二次バルカン戦争に参戦。ブルガリアに侵攻を開始。 |
| 7月15日 | 小林一三によって宝塚唱歌隊(現在の宝塚歌劇団)が創設される。 |
| 7月20日 | オスマン帝国も第二次バルカン戦争に参戦し、ブルガリアに侵攻。 |
| 7月31日 | ブルガリアが休戦を申し出て、一時休戦が成立。 |
| 8月10日 | バルカン同盟・ルーマニアと、ブルガリアとの間でブカレスト条約が成立し、第二次バルカン戦争終結。マケドニアの地を三分割し、大部分をセルビア、エーゲ海沿岸部をギリシャ、一部がブルガリアの領土となる。 |
| 8月13日 | 名古屋市で繭小売商の男性が殺害される強盗事件が起こる。のちに無実の吉田石松が逮捕され、吉田巌窟王事件となった事件。 |
| 8月16日 | イギリス・ヴィッカース社に発注されていた日本海軍の巡洋戦艦「金剛」が竣工。最後の外国製戦艦。 |
| 8月26日 | 木曽駒ヶ岳大量遭難事故。悪天候となり中箕輪高等小学校の生徒ら11人が死亡。後に新田次郎が小説『聖職の碑』にしている。 |
| 9月 4日 | ドイツのミュールハウゼン村で、エルンスト・アウグスト・ワグナーという教師が、家族と住民9人を無差別に殺害するワグナー事件が起こる。責任能力が問われて実刑とはならなかった初めてのケース。 |
| 9月30日 | オスマン帝国とブルガリアとの間でコンスタンティノープル条約成立。 |
| 10月10日 | 袁世凱が初代中華民国大総統に就任。 |
| 10月17日 | 東岩瀬駅事故。午前4時23分頃、富山市の北陸本線東岩瀬駅(現東富山駅)で、上り臨時列車と下り臨時貨物列車の行き違いを行う予定のところ貨物列車がオーバーランして本線に進入し停止。その退行作業中に、上りの善光寺参詣客を乗せた臨時団体旅客列車が停止信号を見落として冒進。貨物列車に衝突して脱線転覆。24名が死亡、107名が重軽傷。この事故を受けて、単線の行き違い時の衝突を避けるため、安全側線(オーバーラン時に強制的に脱線させて本線に進入しないようにする側線)が設けられることになる。 |
| 11月14日 | ギリシャとオスマン帝国との間でアテネ条約が成立。 |
| 12月21日 | 『ニューヨーク・ワールド』紙の日曜版にワードクロスパズルと呼ばれるパズルが掲載される。クロスワードパズルの始まり。 |
| 12月 | 宝塚唱歌隊が宝塚少女歌劇養成会に改められる。 |
| 1914年(大正3年) | |
| 1月12日 | 午前10時過ぎに桜島の2箇所で大噴火。大量の軽石によって海面が覆われ、島民の避難が混乱。午後6時28分、桜島沖合の鹿児島湾海底地下を震源とするマグニチュード7の大きな地震も発生。鹿児島市周辺は震度6に達し、各地で土砂崩れが起きて29人が死亡。パニックが鹿児島側でも拡大。 |
| 1月13日 | 桜島から火砕流が麓の小池、赤生原、武の集落を襲い、焼失。溶岩も流出が始まる。15日には海岸に達する。 |
| 1月18日 | オーストリアの徴兵を拒否し、ミュンヘンで暮らしていたアドルフ・ヒトラーが逮捕され送還される。ただし徴兵検査は不合格に。まもなく第一次世界大戦が勃発すると、一転、志願兵として出兵する。 |
| 1月29日 | 桜島の噴火で流出した大量の溶岩で瀬戸海峡が埋まり、大隅半島と陸続きになる。最終的に58名が死亡。 |
| 2月12日 | ブラジャーの日。アメリカ人女性メアリー・フェルプス・ジェイコブ(カレス・クロスビー)が乳房を支える下着を開発して特許を取得し、ブラジャーと命名する。ただし、他にもエルミニー・カドルなど複数のブラジャーの発明者なる人物がいる。 |
| 3月14日 | セルビアとオスマン帝国との間でコンスタンティノープル条約が成立。バルカン戦争の主要な国が関係を回復する。 |
| 3月20日 | 東京府が主催で上野公園で「東京大正博覧会」開催。7月31日まで。会場を結ぶエスカレーターや、不忍池にロープウェイが架けられた。 |
| 4月 1日 | 宝塚少女歌劇養成会が、宝塚新温泉で初演。演目は歌劇『ドンブラコ』『浮かれ達磨』、ダンス『胡蝶』など。 |
| 6月28日 | サラエボ事件。オーストリア皇太子フランツ・フェルディナントとその妃ゾフィーがサラエボでセルビア民族主義者「黒手組」のガヴリロ・プリンツィプに暗殺される。当日午前に起きた「黒手組」のチャブリノヴィッチによる爆弾を使った暗殺未遂事件で負傷した人を見舞うためサラエボ病院に向かうが、連絡ミスで運転手が道を間違え、同乗者のポティオレク総督が進路を変更するよう命じて止まったところ、偶然その近くにいたプリンツィプに至近距離から撃たれた。 |
| 6月29日 | オーストリア皇太子夫妻が暗殺されたサラエボをはじめ、各地で、大規模な反セルビア暴動が起こる。また多数のセルビア人が逮捕される。 |
| 6月30日 | ウラジーミル・チェロメイ生誕。ソ連のロケット研究者で、弾道ミサイルの研究を進めた人物。現代のロシアの宇宙船に大きな影響を残す。 |
| 7月23日 | オーストリア・ハンガリー帝国は、セルビア政府に対して、サラエボ事件に関する調査や、反帝国プロパガンダの抑制、民族主義組織の解散などを求める最後通牒を送付。 |
| 7月25日 | セルビア政府が、オーストリア・ハンガリー帝国の最後通牒に対して公式に回答。要求の殆どについては飲む意向を示すもサラエボ事件の調査に関する帝国関係者の参加には同意せず。これに反発した帝国公使ウラジミル・ギースルはそのままベオグラードを離れ、帝国とセルビアの国交は断絶。 |
| 7月26日 | オーストリア・ハンガリー帝国と、セルビアの軍勢が、ドナウ川で対峙。軍事衝突と拡大されて情報が帝国内に伝わる。 |
| 7月28日 | オーストリア・ハンガリー帝国がセルビアに宣戦布告し、第一次世界大戦がはじまる。 |
| 7月29日 | オーストリア・ハンガリー帝国軍がセルビアの首都ベオグラードを攻撃。以後2週間に渡りセルビアへ侵攻を進めるが、最終的に失敗に終わる。 |
| 7月30日 | セルビア側についたロシア帝国が総動員令を発する。ドイツ帝国皇帝ヴィルヘルム2世は、いとこのロシア皇帝ニコライ2世と交渉。 |
| 8月 1日 | ロシア帝国はドイツ側の和平要請を拒否し、ドイツ帝国はロシア帝国に宣戦布告。フランス政府は、ロシア帝国の要請を受け、総動員令を発する。 |
| 8月 2日 | ドイツ帝国がルクセンブルクへ侵攻を開始。 |
| 8月 3日 | ドイツ帝国がフランスに対し宣戦布告。 |
| 8月 4日 | ベルギー政府、ドイツ帝国に対し、フランス侵攻軍のベルギー通過を拒否。これを受けドイツはベルギーに宣戦布告。更にこれを受けて大英帝国がドイツに対し宣戦布告。オーストリア・ハンガリー帝国は総動員令を発する。 |
| 8月 5日 | リエージュの戦いが始まる。以後、独仏国境沿いで戦闘が継続。 |
| 8月 9日 | ムーミンの原作者、トーベ・ヤンソンが生まれる。 |
| 8月15日 | パナマ運河が開通。 |
| 8月23日 | 日本政府、連合側についてドイツに宣戦布告。 |
| 8月25日 | ベルギーに侵攻したドイツ軍が、ルーヴェン・カトリック大学に放火し、図書館などが焼失。国際的な非難を浴びる。 |
| 10月21日 | 愛知県で、坂倉しげ・沖つた・猪飼なかの3人の女が、金銭とともに引き取った幼児を200人以上殺害していたことが1913年に発覚し、この日死刑判決。1915年9月9日に死刑執行。同様の幼児大量殺害事件がこの前後に各地で相次いで発覚している。 |
| 12月18日 | 旧新橋駅に代わり、東京の新たな玄関口として、東京駅が開業。第一次世界大戦でドイツ領青島を占領した神尾光臣中将の凱旋とあわせて開業式が行われる。 |
| 森永ミルクキャラメルが黄色い箱入りで発売される。 | |
| 1915年(大正4年) | |
| 1月 5日 | 元新選組二番隊組長だった永倉新八(長倉載之・杉村義衛)が死去。松前藩の出身で、沖田総司・斎藤一と並び新選組最強と言われ、粛清されたものも含め多くの隊士と交流があった。維新後に逆賊・暴力集団扱いされた新選組の名誉回復に奔走。記録も残している。 |
| 1月18日 | 日本政府が、中華民国に対して、権益を求める対華21ヶ条の要求を出す。 |
| 3月 3日 | NASAアメリカ航空宇宙局の前身である国家航空諮問委員会NACAが設立される。 |
| 3月18日 | 英戦艦ドレッドノートが、ドイツ潜水艦U-29に体当りしてこれを撃沈する。戦艦が潜水艦を沈めた唯一の例。ドレッドノートにはそれまでの戦艦に付いていた体当たり用の衝角は不必要として付いていなかった。 |
| 4月22日 | イーペルの戦い。ドイツ軍によって史上最初の大規模な毒ガス攻撃が行われる。使用したのは糜爛剤のマスタードガス。このため、マスタードガスのことをイーペルから採ってイペリットとも呼ぶ。 |
| 5月 7日 | ルシタニア号事件。イギリス海域で無制限潜水艦作戦を行ったドイツがイギリスの豪華客船ルシタニア号をアイルランド沖で撃沈。乗員乗客1959人のうち、1198名の乗客が死亡。このうちアメリカ人128名が含まれていたため、アメリカの反発を買う。 |
| 5月 9日 | 中華民国の袁世凱政権が、対華21ヶ条のうち第5号(日本人の顧問を採用する)を除く残りについて受諾。 |
| 5月25日 | 対華21ヶ条のうち16ヶ条が、2つの条約と、13の交換公文として日中両国で締結。 |
| 6月 6日 | 焼岳が噴火。大量の泥流が発生して梓川を堰き止め、大正池ができる。 |
| 7月14日 | 翌年にかけて、イギリスのエジプト駐在高等弁務官ヘンリー・マクマホンとメッカの太守であるフサイン・イブン・アリーとの間で複数の書簡が交わされ、イギリス政府の外交方針としてアラブ人の独立を認める。敵対するオスマン帝国領のアラブ地方を取り込むための方策。 |
| 8月19日 | ドイツの潜水艦が客船アラビック号を撃沈。 |
| 8月27日 | ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が無制限潜水艦作戦を中止させる。 |
| 9月11日 | 朝鮮の京城景福宮で「始政五年記念朝鮮物産共進会」がはじまる。10月31日まで。 |
| 9月28日 | 元新選組副長助勤・三番隊組長の斎藤一(藤田五郎)が死去。沖田総司・永倉新八とともに新選組最強説がある人物で、戊辰戦争では会津藩に加わって戦った。その後、警視庁に入り、西南戦争では政府軍の抜刀隊として参戦している。新選組以前の経歴が不明で、剣術の流派もはっきりしない。 |
| 12月 9日 | 三毛別羆事件。北海道苫前郡苫前村三毛別六線沢(現在の苫前町古丹別三渓)の集落に巨大なヒグマが現れ、たった2日で女性と子供(胎児を含む)7人が殺され、一部を除き食べられた他、男性ら複数の重軽傷者を出した事件。軍隊まで出動した。ヒグマは14日にマタギの手で倒される。 |
| 1916年(大正5年) | |
| 1月22日 | 初の国産飛行船「雄飛号」が所沢-大阪間でテスト飛行を実施。 |
| 3月25日 | カリフォルニアのインディアン部族ヤヒ族の最後の一人とみられるイシが死去。ヤヒ族は他の部族同様白人の虐殺政策によってほぼ絶滅し、イシは家族らとラッセン山付近に隠れ住んでいたとみられる。その後1911年8月29日にビュート郡オーロビルに現れて保護された。人類学者アルフレッド・クローバーらの研究に協力した。イシは本やドラマにもなっている。イシはヤヒ語で「人」を意味し、本名を明かさなかったので、不明のまま。 |
| 5月16日 | オスマン帝国領分割を定めた英仏露によるサイクス・ピコ協定が結ばれる。シリア領をめぐる権利ではフサイン=マクマホン協定とは矛盾する内容だった。 |
| 7月 1日 | ソンムの戦いがはじまる。英仏軍とドイツ軍がフランス北部ベルギーとの国境近くにあるソンム河のそばに塹壕を築いて対峙。英仏軍側が侵攻し、この日だけでイギリス軍は2万人近い死者を出し、5万人を超える負傷者を出す。このとき伝令兵だったヒトラーも負傷したと言われる。 |
| 7月30日 | ブラック・トム爆破事件。アメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティのブラックトム埠頭で、軍需物資が連合国側諸国に輸送されるのを阻止するため、ドイツ帝国の工作員によって起こされた爆破事件。7人が死亡、多数の負傷者を出す。大規模な爆発によって吹き飛んだ破片と爆風により、ジャージーシティだけでなく、対岸のマンハッタン島でも多数の建物で窓ガラスが割れるなどの被害が出た他、自由の女神も損傷した。 |
| 8月15日 | イギリスの航空母艦フューリアスが進水。元はバルト海作戦用に建造されたカレイジャス級巡洋戦艦で、前部砲塔を撤去して70mの甲板に変えたもの。艦橋以降の中央・後方はほぼ元のままだった。そのため、発艦のみで着艦は困難であった(艦と平行に飛行して速度を合わせ、横滑りするように着艦できたが、事故が相次いだ)。その後、後部砲塔を撤去して後部甲板を設置(真ん中に艦橋と煙突が残る)、さらに上部構造を撤去して全通甲板となり、発艦用の下部甲板を持つ二段式甲板となった。第1次大戦・第2次大戦を生き延び、1954年に解体。 |
| 12月13日 | ロシア皇帝一家に取り入り政治的権力を握っていたグリゴリー・ラスプーチンが、フェリックス・ユスポフ公爵、ドミトリー大公、ウラジーミル・プリシケヴィチらによって暗殺される。モイカ宮殿新築祝いのパーティに招待した上で、青酸カリによる毒殺を図るもうまくいかなかったため、酔わせた上で多数の銃弾を撃ち込んで殺害。 |
| 12月22日 | 明治時代の公害事件である大阪アルカリ事件で、大審院は会社側の上告を受けて、控訴院での審理差し戻しを命じる。再審理で公害予防措置としての設備(煙突)を設けてないことを理由に大阪アルカリ側の敗訴が確定するが、「予防措置がされていれば故意の不法行為とはみなさない」という判例になった。 |
| 1917年(大正6年) | |
| 1月18日 | ヴァシーリー・ミシン生誕。ソ連のロケット開発に貢献した人物。 |
| 1月31日 | ドイツがふたたび無制限潜水艦作戦をはじめる。 |
| 2月27日 | ロシア国会議員らがメンシェヴィキと組んで「ソヴィエト」を結成。皇帝を退位させる。 |
| 3月 7日 | 千葉心中事件。芳川顕正伯爵の四女で、婿養子芳川寛治の妻であった鎌子が、伯爵家のお抱え運転手倉持陸助と恋仲になり、駆け落ちして千葉駅近くで列車に飛び込み自殺を図る。ふたりとも重症を負い、倉持は自殺。鎌子は回復後、ふたたびお抱え運転手の出沢佐太郎と駆け落ち事件を起こしている。 |
| 6月19日 | 理化学研究所創設。総合自然科学研究機関。 |
| 10月15日 | フランスでダンサーをやっていたマタ・ハリが、ドイツ軍に情報を漏らしたという理由でフランス政府によって処刑される。 |
| 11月 2日 | バルフォア宣言。イギリスのバルフォア外相が、ロスチャイルドへ書簡を出し、パレスチナにユダヤ人の「民族的郷土」の建設を援助すると約束。一方で、アラブ民族にも国家建設を認める約束(フサイン・マクマホン協定)をしており、のちのパレスチナ問題の原因の一つとなる。 |
| 12月 2日 | イギリスの航空母艦アーガスが進水。世界で初めての全通甲板を持った軍艦。イタリアの客船「コンテ・ロッソ」を建造中に改装したもの。第1次大戦には間に合わなかったが、戦間期や第2次大戦中の多くの軍事作戦に参加、戦後まで生き延び、1946年に解体された。 |
| 12月 6日 | ハリファックス港の大爆発。貨物船同士の衝突で積荷の火薬2600tが爆発。市街地が壊滅する。1500人が即死し、さらに重症者や家屋の下敷きになった人ら数百人が死亡。 |
| 1918年(大正7年) | |
| 3月 7日 | 松下幸之助が松下電気器具製作所(現パナソニック)を創業。 |
| 3月21日 | ドイツ軍が超大型砲「パリ砲」でパリの攻撃を開始。8月まで実施。 |
| 4月 1日 | イギリス空軍(王立空軍)の発足。世界最初期の独立した空軍。 |
| 4月16日 | 軍需工業動員法公布。 |
| 4月21日 | ドイツ軍のエース「レッドバロン」ことマンフレート・フォン・リヒトホーフェン戦死。 |
| 6月 | ロシアで、チェコスロバキア兵が蜂起し、これがきっかけで、内乱が勃発する。 |
| 7月17日 | 内乱中のロシアで、ボリシェビキのヤコフ・ユロフスキーらの手により、エカテリンブルクのイパチェフ館に幽閉されていたロシア皇帝一家ら(皇帝ニコライ2世、皇后アレクサンドラ、娘のオリガ、タチアナ、マリア、アナスタシア、皇太子のアレクセイおよび、主治医のボトキン、メイドのデミドヴァ、料理人のハリトーノフ、フットマンのトルップの11人)が殺害される。館の地下2階につれていき銃撃し、即死しなかった皇女らを銃剣で刺した上で、再度銃で頭を撃ったとされる。所有していたものは略奪されている。ユロフスキーらは、遺体を激しく損壊した上で郊外の沼地の多い場所を通るコプチャキ街道の道路脇の森に埋めた。ユリウス暦7月4日。料理人の助手を務めていたセドニョフ少年のみ殺されずに済んだ(成人後に処刑されたとも言われる)。殺害の命令がどこから出たかは曖昧だが、白軍が迫っていたことを受けて、最終的にはレーニンの承認を得ていたと見られる。同館は所有者のニコライ・イパチェフ(ロシア軍の技術将校)に戻されたのち、内乱後に博物館となった。後のブレジネフ政権下で証拠隠滅のため跡形もなく壊された。現在は跡地にロシア正教の「血の上の教会」の聖堂が建っている。 |
| 7月22日 | 富山県魚津港に主婦らが集結し、北海道へ米を輸送する「伊吹丸」の輸送中止を訴える。米騒動の勃発。 |
| 9月29日 | 原敬が第19代内閣総理大臣に就任し、原内閣が成立。 |
| 9月29日 | 中央同盟国の1つだったブルガリア王国が、連合国との間にサロニカ休戦協定を結び、第1次世界大戦から離脱。 |
| 10月29日 | ドイツ太洋艦隊の水兵らが出兵を拒否。ドイツ革命がはじまる。 |
| 10月30日 | オスマン帝国がムドロス休戦協定を締結して連合国に降伏。 |
| 11月 3日 | オーストリア・ハンガリー帝国とイタリア王国が、ヴィラ・ジュスティ休戦協定を結ぶ。 |
| 11月11日 | コンピエーニュの森に置かれた列車の中で、ドイツ帝国と連合国の休戦協定が締結。第一次世界大戦は終結へと向かう(正式な終戦は翌年のヴェルサイユ条約をはじめ各国が締結した条約による)。なお、この列車は、のちにヒトラーがフランスと休戦協定を結ぶ際にも利用している。 |
| 12月 1日 | ロシアの航空機研究者ニコライ・ジュコーフスキーによって、モスクワ郊外に中央航空流体力学研究所が設立される。略称TsAGI(ツアギ)。研究機関で航空機製造はしていないが、後に設立されるツポレフやミグ、スホーイなど各メーカーと合同研究を行っている。ジュコーフスキーは空気力学の研究者として翼の形状を理論化した人物。研究所のある自治体は、現在ジュコーフスキー市となっている。 |
| 1919年(大正8年) | |
| 1月 3日 | ファイサル・ワイツマン合意。アラブとの友好協力の下ユダヤ人入植が進められる。 |
| 1月16日 | アメリカで国家禁酒法が成立。1933年12月5日まで「禁酒法時代」。 |
| 1月18日 | パリ講和会議が始まる。第一次世界大戦の講和条件を話しあい、戦後処理を行うために行われる。 |
| 1月 | 宝塚音楽歌劇学校が設立され、これにあわせて少女歌劇養成会は解散して、新たに宝塚少女歌劇団として発足。 |
| 3月 1日 | 朝鮮の京城にあるパゴダ公園で天道教やキリスト教各派、仏教指導者など33人が独立を宣言。33人は逮捕されるが、学生などが集まり、市内をデモ行進。これが朝鮮半島全体へと拡大し各地で暴動が起きる。いわゆる「三一独立運動」。 |
| 3月 3日 | 信玄公旗掛松事件の大審院判決が出される。中央本線日野春駅そばに生えていた「信玄公旗掛松」と呼ばれた著名な巨木が蒸気機関車のばい煙などで枯死したことを受けて、松の所有者で地元の名士だった清水倫茂が国に損害賠償を請求した事件。大審院は「鉄道という公共性を持ってしても、他人の権利を侵害することは出来ない」として国側敗訴というこの時代では異例の判決を下す。「権利濫用」に関するの初期の事例としても有名。 |
| 3月23日 | ベニート・ムッソーリニによって反共主義の「イタリア戦闘者ファッシ」が結成される。のちのファシスト党。反共主義だが左派勢力も参加していた。 |
| 4月 1日 | 新たな帝国大学令が施行され、旧帝国大学令は廃止される。 |
| 4月13日 | 大英帝国支配下のインド・アムリッツァルで軍がローラット法(令状なしの捜査や陪審員なしの裁判を認める法令)に抗議する市民集会に発砲し1500人以上が死傷する虐殺事件がおこる。 |
| 4月15日 | 堤岩里教会事件。三一独立運動のさなか、暴動が多発していた京畿道水原郡発安に派遣された朝鮮軍歩兵第40旅団の有田中尉と歩兵11人の部隊が、暴動を起こしているのは天道教であると聞き、堤岩里の教会に首謀者や信者らを集めて殺害。また教会を放火したため周囲に延焼する。計29人が死亡したとされ、内外で大きな問題となる。 |
| 5月 4日 | 中国北京大学の学生らが、ベルサイユ条約に反対して起こした大規模な反日デモ、五・四運動が北京の天安門で始まる。 |
| 5月19日 | ジャワ島のケルート山が噴火。火山泥流が発生して麓の村を直撃し5000人以上が死亡。この調査で、火山泥流という現象が明らかとなり、現地の言葉をとって「ラハール」と呼ぶようになった。 |
| 5月29日 | アーサー・エディントンとフランク・ダイソンが、アフリカのプリンシペ島で、皆既日食のさなかにヒアデス星団の複数の恒星を観測し、『一般相対性理論』で指摘された重力場によって光が曲げられることを証明。 |
| 5月 | 朝鮮で起きた三一独立運動がほぼ終息する。暴動による日本人の死傷者、軍の鎮圧による朝鮮側の死傷者数については諸説あるが、朝鮮側の死傷者は数千人に上るとみられる。日本国内でも同情論があり、武断統治を変更するきっかけになった。検挙者も数万人にのぼったが重い懲役刑は課せられずその後減刑された。ただし獄死したものもいる。国外に逃亡した運動家も多い。これ以降、朝鮮半島での大きな独立運動は日本の統治が終わるまで起きていない。 |
| 6月 1日 | 史蹟名勝天然紀念物保存法が施行される。 |
| 6月28日 | ヴェルサイユ条約調印。戦勝国によるドイツの処分を主とした条約。以降ヴェルサイユ体制となる。 |
| 7月31日 | ドイツ議会がヴァイマル憲法を採択。 |
| 7月11日 | 元新選組九番隊組長で御陵衛士に移った鈴木三樹三郎が死去。伊東甲子太郎の実弟。戊辰戦争では新政府軍側で戦う。その後、警察官となった。 |
| 8月14日 | ドイツでヴァイマル憲法が公布・施行される。 |
| 9月12日 | アドルフ・ヒトラーがドイツ労働者党(党首はドレスクラー・後のナチ)に参加する。ヴァイマール共和国軍の調査任務で調べていて興味を持ったとも言われる。 |
| 10月10日 | 中華革命党が中国国民党に改組。 |
| 11月18日 | 神道系新興宗教の「大本」(大本教)が、本拠とするため、亀山城を買収する。 |
| 1920年(大正9年) | |
| 1月30日 | 東洋コルク工業設立。後の自動車メーカーマツダ。 |
| 2月 1日 | 久原鉱業所から日立製作所が独立。 |
| 3月11日 | ニコラエフスクで、共産パルチザンと日本軍守備隊が衝突。守備隊全滅。日本人も多数殺害される。いわゆる尼港事件。 |
| 3月15日 | 鈴木式織機製作所が株式会社化。のちの自動車メーカースズキ |
| 4月 1日 | 前年施行された大学令に基づき、10校が大学に昇格。文部省と対立を続けていた東京高等商業学校専攻部も東京商科大学となる(のちの一橋大学)。 |
| 4月11日 | アメリカ最初の空母ラングレーが進水。給炭艦ジュピターを改装したもの。 |
| 5月 2日 | 上野公園で友愛会主催による第1回メーデー開催。 |
| 5月15日 | 時ノ展覧会を開催。 |
| 5月15日 | 鉄道省が発足。 |
| 5月16日 | ジャンヌ・ダルクが、ローマ教皇ベネディクトゥス15世によって列聖される。 |
| 5月25日 | ふたたび共産パルチザンによるニコラエフスク市民虐殺事件が起こる。市民6000人が犠牲になり、日本人も700人が殺される。尼港事件。ニコラエフスクは廃墟と化す。 |
| 6月 7日 | 鳳梧洞の戦い。朝鮮独立武装組織が拠点にしていた満州汪清県鳳梧洞を、日本陸軍第19師団が攻撃。日本兵1人、武装組織33人が死亡。韓国では独立運動側の大勝利としているが、実際は小規模の戦闘だったとみられる。 |
| 8月10日 | 連合諸国とオスマン帝国との間で講和条約であるセーヴル条約が締結される。パレスチナの英国統治、エジプトの英国保護下、モロッコ・チュニジアのフランス保護下、レバノンとシリアのフランス統治、トラキア・イズミルのギリシャ移管、アナトリア南部のイタリア支配、アルメニア、ヒジャーズ王国の独立などが決まり、オスマン軍の軍備縮小も決定される。 |
| 9月12日 | 第一次琿春事件。馬賊の集団300人ほどが琿春市街を襲い、放火略奪を行う。 |
| 9月30日 | 第二次琿春事件。馬賊の集団50人ほどが琿春県大荒溝の中国軍を襲い武器弾薬を奪う。 |
| 9月30日 | 市街地建築物法施行令公布。建築物の高さを百尺(30.3m。のち31m)に規制する。ただし例外規定もあり塔屋など一部が百尺を大きく超えているものもある。この規制は地震が多いための防災目的という説もあるが、景観目的でロンドンに倣ったものとも言われる。 |
| 10月 2日 | 第二次琿春事件。馬賊の集団400人ほどが琿春市街を襲撃し、日本領事館を焼き討ちしたあと、居留地を襲う。日本人9人、朝鮮人3人、中国人1人が殺害される。日本側と現地中国工兵らの反撃で馬賊も30数人が殺害される。馬賊には朝鮮独立武装組織なども含まれていたとされる。 |
| 10月 7日 | 日本政府、琿春事件を受けて、間島出兵を閣議決定。これに同調する形で張作霖の奉天軍閥も出兵を決定。中国政府は抗議。 |
| 10月21日 | 青山里の戦い。満州の間島和龍県で、日本軍と、朝鮮独立運動武装組織、それに馬賊とが武力衝突。当時の記録などから日本軍は11人が戦死し、武装組織も数十人が死亡したとみられるが、韓国では年々誇張されて日本兵3000人以上が戦死した独立運動側の大勝利という話になっている。 |
| 11月25日 | 八八艦隊計画最初の戦艦、「長門」が竣工する。世界で初めて16インチ級の主砲を搭載。 |
| 12月17日 | ヴェルサイユ条約を受けて、旧「ドイツ領ニューギニア」だった南洋群島が日本の委任統治領となる。 |
| ロバート・ゴダードが論文『高々度に達する方法』を発表しロケットで宇宙へ出ることを説明。ニューヨーク・タイムズは社説で、<「何もない」真空中をロケットが飛行するのは不可能だと誰でも知っている>と痛烈に批判。同紙は49年後のアポロ月着陸の直前に、この社説の「過ちを後悔する」と表明した。 | |
| 通天閣に広告看板が取り付けられる。企業はライオン歯磨。 | |
| 1921年(大正10年) | |
| 1月 | 日本軍、間島から撤兵。 |
| 2月12日 | 第一次大本事件。神道系新興宗教の「大本」(大本教)が、政府の弾圧を受ける。 |
| 4月21日 | コミンテルンによって、モスクワに植民地や途上国の共産主義者養成用教育学校「東方勤労者共産大学」が設立される。開校は10月21日。ロシア語の略称からクートヴェとも呼ばれる。1938年まで続いた。 |
| 6月 8日 | 長門級戦艦2番艦の戦艦陸奥が就役。ただし軍縮交渉で廃艦の対象になりかねなかったため、完成を急ぎ、艤装などは完全ではなかったとされる。 |
| 7月11日 | ソビエト連邦の支援を受けたモンゴル人民党が、モンゴル人民政府を樹立。君主はジェプツンダンバ・ホトクト8世(ボグド・ハーン)。 |
| 7月21日 | アンワールの戦い。スペイン領モロッコの独立を目指すベルベル人系リーフ人の軍勢3000人に対し、2万以上のスペイン軍が大敗。1万3千人以上が戦死、もしくは殺害された。一方ベルベル諸部族の間でも対立があり、リーフ人の勝利にも関わらず他のベルベル部族は味方しなかった。この敗戦はスペイン国内の分裂・内戦に発展し、王制廃止へとつながっていく。 |
| 7月23日 | 中国で興されていた複数の共産主義政党を統合して中国共産党が結党される。 |
| 7月24日 | ソビエトで高速輸送用に研究されていたエアロワゴンが、モスクワと郊外のトゥーラとの間をテスト走行中、脱線事故を起こし、乗っていた22人のうち、開発したバレリアン・アバコフスキー、政治家でジャーナリストのフョードル・セルゲイエフら7人が死亡。エアロワゴンは車両にプロペラを付けて時速140km程で走行する鉄道の一種。 |
| 9月21日 | オッパウ大爆発事故。ドイツ南西部のオッパウにあったバーディシェ・アニリン・ウント・ソーダ・ファブリーク社の化学工場で製造していた約4500トンの硫硝安混成肥料の塊を崩すためダイナマイトを使用したところ、大爆発を起こし、工場は全壊。周辺の都市も大被害を受けた。死者509人、行方不明160人、負傷者1952人。230km離れたバイロイトにも爆風が到達したという。 |
| 10月 | 宝塚少女歌劇団に花組・月組が誕生。 |
| 11月 4日 | 原敬首相が関西政友会大会に向かうため、東京駅丸の内南口コンコースに現れたところを、右翼青年中岡艮一(大塚駅転轍手)に刺殺される。 |
| 11月 9日 | イタリアのファシスト運動家や民兵などで構成される連合組織「イタリア戦闘者ファッシ」が政治組織「国家ファシスト党」へ発展。ムッソリーニが最高指導者となる。 |
| 12月 6日 | 英愛条約締結。大英帝国政府と、アイルランド共和国暫定政府との間で、アイルランド独立戦争の休戦が結ばれ、大英帝国内の自治国(同君連合)として、アイルランド自由国が建国されることに。 |
| 1922年(大正11年) | |
| 2月 6日 | ワシントン海軍軍縮条約締結。 |
| 2月 8日 | ソ連に「ゲーペーウー(GPU)」が設置される。人民委員会のチェーカーを前身とし、のちのKGBにつながる秘密警察。 |
| 2月11日 | 日本とアメリカが、南洋群島に関する「『ヤップ』島及他ノ赤道以北ノ太平洋委任統治諸島ニ関スル日米条約」に調印。 |
| 2月25日 | 『旬刊朝日』が創刊される。 |
| 3月10日 | 東京府が主催して、第一次世界大戦終結を記念した「平和祈念東京博覧会」開催。7月31日まで。1100万人が訪れたという。 |
| 3月31日 | ヒンターカイフェック事件。ドイツ・バイエルン州のヒンターカイフェックで農場一家と使用人の計6人が何者かに襲われ全員が惨殺される。犯人の目的、人数などは一切不明。事件が発覚したのは翌週の4月4日で、不審な様子に気づいた村人が訪ねたことによる。犯人は事件後、しばらく農場に滞在していた痕跡を残したが、捜査は難航し犯人は不明のまま。 |
| 4月 1日 | 南洋庁官制を施行し、南洋庁をパラオのコロール島に設置し、各諸島にも6つの支庁を設置。統治を本格的に開始する。 |
| 4月 2日 | 『サンデー毎日』が創刊され、『旬刊朝日』が『週刊朝日』となる。現在のタイプの週刊誌が登場する。 |
| 8月10日 | ジュリアーノ・ゴジによってサンマリノにサンマリノファシスト党が結成される。 |
| 9月 9日 | チャナク危機。希土戦争でトルコ軍がイスタンブール付近まで進撃したことから、ダーダネルス海峡を守るチャナクのイギリス軍とフランス軍の基地が脅かされる事態に発展。 |
| 9月15日 | イギリスのロイド・ジョージ政権は、チャナク駐留軍の現状維持を決定し、トルコに対しセーブル条約違反であるとして威嚇的な声明を出し、宣戦布告の準備に入る。 |
| 9月18日 | ロイド・ジョージ政権のカーゾン外相が、この件でトルコ寄りのフランスと交渉するため、渡仏。休戦を求めることで合意。しかしカナダなどのイギリス系自治領政府は、イギリスとは異なる独自の外交権を主張。後の英連邦成立への布石となっていく。 |
| 9月23日 | イギリス政府は東トラキアのトルコへの譲渡を決定。 |
| 9月28日 | イギリス政府から最後通牒が出される。トルコ政府、イギリス政府に対し、休戦交渉に応じることを伝える。 |
| 10月 3日 | イギリスとトルコの間でムダンヤ休戦交渉が始まる。 |
| 10月11日 | ムダンヤ休戦協定成立。戦争は回避されるが、あわや開戦という事態に至ったことにロイド首相への批判が起こる。 |
| 10月19日 | チャナク危機や、アイルランド独立問題、叙爵濫用問題などでロイド首相への批判から、連立を組んでいた保守党が事実上の離脱を決定。ロイド政権は総辞職に追い込まれる。こののち自由党は没落していく。 |
| 10月22日 | ソ連の航空技術者アンドレーイ・トゥーポレフによって航空機設計のツポレフ設計局が設立される。のちの爆撃機や旅客機メーカーツポレフの前身。 |
| 10月27日 | ムッソリーニ率いる国家ファシスト党が、政権奪取を目指して武装民兵などをローマへ向かわせるため集結。いわゆる「ローマ進軍」。 |
| 10月28日 | イタリア王国ファクタ政権が、国家ファシスト党の武装進軍計画に対し戒厳令施行を目指すも、国王が署名を拒否。ファクタ首相は辞任し、ファクタ政権は崩壊。ムッソリーニは政府と交渉。 |
| 10月29日 | ムッソリーニがローマで国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世に謁見し、国王はムッソリーニに組閣を命じる。黒シャツ隊25000名も鉄道などで続々ローマに入城。 |
| 10月31日 | ムッソリーニ政権樹立。 |
| 11月 5日 | ハワード・カーターによって発見されたツタンカーメン王墓が開かれ、調査が始まる。 |
| 12月 6日 | 英愛条約をもとに、イギリス皇帝の勅により、アイルランド南部26州で構成されたアイルランド自由国が建国される。北部アルスターはイギリス領として残る。 |
| 12月 8日 | 島原地震。マグニチュード6・9と6.5の2回大きな揺れを観測。死者27人、家屋600棟あまりが倒壊。 |
| 12月27日 | 最初から空母として設計された世界初の航空母艦「鳳翔」が竣工。 |
| 12月30日 | 世界最初の共産主義国家、ソビエト連邦が正式に誕生する。 |
| 帝都防衛用の航空基地として、立川飛行場が開港。 | |
| 航空技術者エルンスト・ハインケルによってハインケル航空機製造会社がヴァーネミュンデに設立される。 | |
| 中華民国済南府で宗教団体「道院」によって世界紅卍字会が設立される。慈善事業団体で、中国や満州では赤十字以上の活動をした。 | |
| 1923年(大正12年) | |
| 1月 4日 | ドイツがハイパーインフレ状態に陥り、賠償金支払い能力を喪失。フランスとベルギー政府は肩代わりとしてドイツの工業地帯ルール地方の占領を開始する。ドイツ人のさらなる反発を買うことに。 |
| 1月 9日 | ファン・ド・ラ・シェルバによって発明されたオートジャイロが初飛行。 |
| 1月22日 | 宝塚のパラダイス劇場・公会堂劇場が焼失。 |
| 2月 1日 | スペイン領モロッコのベルベル人系リーフ人指導者アブド・エル・クリムがリーフ地方を領土とするリーフ共和国を樹立。首都はアジール。ソ連が独立を承認。スペインは軍を派遣。 |
| 2月 5日 | 現在の国際刑事警察機構(インターポール)につながる国際刑事警察委員会が創設される。 |
| 2月20日 | 東京駅の正面に丸ノ内ビルヂングが竣工する。 |
| 3月26日 | フランスの女優サラ・ベルナールが死去。世界最初の国際女優であり、その肖像や舞台のデザイン様式はアール・ヌーヴォーの代表とされた。また自身も彫刻や絵画を描く芸術家であった。フランス政府によって国葬。 |
| 6月 | ヘルマン・オーベルトの論文を元に『惑星空間へのロケット』が出版されドイツで評判となる。ドイツで先進的にロケット研究が進んだ要因の一つ。 |
| 8月31日 | コルフ島事件。バルカン諸国の国境線を確定するための国際調査に加わっていたイタリア軍のエンリコ・テルリーニ将軍が暗殺されたため、調査に反発していたギリシャ政府による犯行を疑ったイタリア政府がギリシャ領ケルキラ島(コルフ島)を武力占領。 |
| 9月 1日 | 関東大震災発生。マグニチュード7.9。東京と横浜を中心に大きな被害を出し、死者は10~14万人に達する。 |
| 9月16日 | 甘粕事件。関東大震災の混乱の中、アナキストの大杉栄、その内縁の妻の伊藤野枝、大杉の甥の橘宗一の3人が、憲兵隊に連行され、殺害される。 |
| 9月17日 | 日本橋にあった各市場が関東大震災で大きな被害を受けたため、芝浦に仮市場が設置される。この後、海軍用地のある築地へ移転が進められる。 |
| 10月 3日 | 関東大震災の直後、沼津測候所の職員が、富士山頂近くの伊豆ヶ岳で噴気を確認したため、10月3日から5日に富士山とその周辺で調査が行われる。 |
| 11月 8日 | ヒトラーなどのドイツ国家社会主義労働者党のメンバーやルーデンドルフらが、イタリア・ファシスト党のローマ進軍をモデルにして独立性の強いミュンヘンで蜂起しベルリン進軍を計画する(ミュンヘン一揆)。しかし協力姿勢を見せていたバイエルン総督グスタフ・フォン・カールが鎮圧したため失敗に終わる。 |
| 11月11日 | ヒトラー逮捕される。しかし法廷での弁舌が彼の支持者を増やす結果につながる。 |
| 11月15日 | ドイツでハイパーインフレと化した紙幣パピエルマルクの暴走を終息させるため、不動産を担保とする金不換紙幣のレンテンマルクが発行される。 |
| 12月27日 | 虎ノ門事件。摂政皇太子が自動車で移動中に虎ノ門で難波大助に狙撃される。皇太子は無事。難波は群衆に取り押さえられる。天皇制打破といった理由ではなく、皇室を崇拝するプロレタリア階層へのインパクトに皇族を狙ったのが動機とも。難波の父、難波作之進衆議院議員は絶食自殺。 |
| 1924年(大正13年) | |
| 1月 5日 | 二重橋爆弾事件。大韓民国臨時政府から送られてきた金祉燮が皇居外苑で警官や近衛兵に向けて爆弾を投げつけるが不発に終わる。 |
| 1月 7日 | 虎の門事件を受けて山本権兵衛内閣が総辞職。 |
| 1月20日 | 中国国民党の蒋介石が、共産党との連携を決定。第一次国共合作。北京政府(北洋軍閥政府)に対抗する共同戦線。 |
| 4月 1日 | ヒトラー、ミュンヘン一揆の首謀者として要塞禁錮5年の判決。しかし要塞刑務所にも彼の賛同者は多く、待遇は良かったという。収監後、『我が闘争』の執筆を開始。 |
| 4月 9日 | 第1次大戦のドイツ賠償問題で、ドーズ案が策定される。経済状況に合わせて年ごとに増額する。ドイツマルクで支払う。ドーズ債と呼ばれる公債を発行してドイツに借款するなどの内容で、ドイツにとっては負担が減ることから容認。 |
| 6月 6日 | イギリスのエベレスト第三次遠征隊が頂上を目指すが失敗に終わる。 |
| 6月27日 | 大阪市内に、市内1円均一のタクシー「円タク」が登場。 |
| 6月27日 | 紫禁城の宦官らが、美術品の管理を図ろうとした溥儀に対して、横領が発覚するのを恐れて建福院に放火。この事件を受けて溥儀は宦官を一斉追放する。 |
| 7月15日 | 宝塚大劇場が竣工。雪組が新設される。 |
| 10月23日 | 第二次奉直戦争により北京政変が勃発。馮玉祥らは溥儀を始めとする旧清朝皇族らの「清室優待条件」を一方的に破棄し、紫禁城からの追放を決める。 |
| 10月31日 | 大阪商船の貨客船宮古丸が、西表島から石垣島へ向かう途中、海面が軽石で覆われているのを目撃し、海底火山の噴火を判断。西表島へ引き返す。西表海底火山の噴火によるものとみられる。膨大な量の軽石が八重山諸島から沖縄本島の各沿岸に漂着。一部は日本列島の各沿岸にも流れ着く。噴出量からVEI5相当の噴火だったと考えられるが、その後、噴火が確認されていないため、海底火山の正確な場所の特定はなされていない。 |
| 11月29日 | 溥儀ら旧清朝皇族らの身柄について、イギリスやオランダが受け入れを拒否したため、レジナルド・ジョンストンが間に入り、日本が受け入れを決め、北京の日本公使館に入る。 |
| 12月20日 | ヒトラー、予定より大幅に前倒しで釈放される。 |
| 1925年(大正14年) | |
| 1月 3日 | それまで連立政権維持に努め、野党とも交渉していたムッソリーニが、議会で独裁体制へ移行することを宣言。 |
| 3月 1日 | ラジオの試験放送が始まる。 |
| 3月22日 | 社団法人東京放送局(現在のNHK東京放送局)がラジオ放送を開始。送信施設は東京芝浦にあった東京高等工芸学校(現在の千葉大学工学部)。 |
| 4月22日 | 治安維持法公布。 |
| 5月 5日 | 普通選挙法(衆議院議員選挙法の改正)公布。 |
| 5月12日 | 治安維持法施行。 |
| 6月 1日 | 大阪でラジオの仮放送が始まる。三越大阪支店の屋上から送信。 |
| 7月12日 | 社団法人東京放送局(現在のNHK東京)によるラジオ本放送がはじまる。愛宕山送信所から送信。 |
| 7月12日 | 名古屋でもラジオの本放送がはじまる。 |
| 7月18日 | ヒトラーの『我が闘争』第一巻が発売される。のちナチス時代にはほぼ義務的に各家庭に一冊ずつ置かれたと言われるが、戦後は逆に発禁処分となり、現在も継続している。 |
| 9月28日 | 信玄公旗掛松事件の損害賠償額決定裁判が終結。地裁での和解額案500円から72円にまで大幅に減額され(銘木を基準とせず薪材としての価格を基準とした)、さらに原告側が訴訟費用9割を負担するという、事件そのものを審議した国側敗訴の判決とは真逆の結果となった。 |
| 12月 1日 | 京都学連事件。マルクス主義の研究や普及をすすめる京都帝国大学を始めとした各大学の学生社会科学連合会(学連)が特高警察の摘発を受ける。 |
| 12月21日 | 鶴見騒擾事件。西日本を基盤とした東邦電力の松永安左エ門が関東での電力事業のために作った東京電力(現在の東京電力とは別会社)が、川崎白石町に進めていた火力発電所建設工事の利権をめぐって、ヤクザ組織同士が起こした抗争事件。 |
| 12月24日 | ムッソリーニが新たに首席宰相及び国務大臣職を創設し、権限を大幅に強化した政府の長として自ら就任。 |
| 12月28日 | 大日本大相撲協会設立。摂政皇太子の台覧と奨励金の下賜で、摂政宮賜杯(現天皇賜杯)を作ったことをきっかけに。大阪相撲も吸収することになる。 |
| 1926年(大正15年/昭和元年) | |
| 2月16日 | バンベルクでナチ党幹部会議が開かれ、ヒトラー収監中に起こった分裂に対し、ヒトラーの指導体制が確立。党内左派勢力は衰退する。 |
| 2月28日 | 松島遊郭疑獄事件。大阪の松島遊郭を移転する構想に関して、与党憲政会の箕浦勝人、野党政友会の岩崎勲、野党政友本党の高見之通などが収賄の疑いを持たれる。 |
| 3月16日 | ロバート・ゴダードが、マサチューセッツ州オーバーンの農場で初めての液体燃料ロケット「ネル」の発射実験を行い成功。しかし、危険な実験だと騒ぎになり、新聞記者らの間違った記事や、「専門家」らによる「科学的」批判を受ける。 |
| 5月24日 | 北海道中央部にある十勝岳が二度大きな噴火。一度目の噴火で望岳台まで泥流が流れ、二度目の噴火で火口壁の一部が崩壊、岩屑なだれが発生して硫黄鉱山の宿舎を破壊。噴火の熱で雪が大量に溶けて大規模な土石流が発生。美瑛川と富良野川をなだれ下り、わずか20分ほどで美瑛と上富良野の市街地に到達。372棟が破壊され、死者行方不明者144名、負傷者200名以上を出す大惨事となる。 |
| 5月27日 | スペイン領モロッコっから独立したリーフ共和国がスペイン・フランス両軍の攻勢の前に崩壊する。スペイン軍に対しては勝利していたが、フランス領モロッコに波及したことを受けて侵攻してきたフランス軍に敗北した。大統領のアブド・エル・クリムはフランス側に降伏。フランスはスペインの引き渡し要請を無視してクリムをレユニオンに流罪とした。 |
| 6月10日 | 大阪に続き、東京にも市内1円均一のタクシー「円タク」が登場。 |
| 10月31日 | 奇術師ハリー・フーディーニが病死。「脱出王」の異名で呼ばれ、マジックショーの出演、映画俳優、さらに著述家としても活躍。その技術と知識から、科学雑誌などで自称超能力者や霊媒師のトリックを暴露するハンターとしても知られた。 |
| 12月25日 | 大正天皇崩御。昭和天皇即位。 |
| 12月25日 | 浜松高等工業学校電気学科の助教授だった高柳健次郎が、ブラウン管を使ったテレビの送受信の実験に初めて成功する。最初に表示されたのは、カタカナの「イ」の字。走査線は40本だった。 |
| 1927年(昭和2年) | |
| 3月14日 | 第52回帝国議会で、片岡直温大蔵大臣が「東京渡辺銀行がとうとう破綻を致しました」と失言し、取り付け騒ぎが起こる。 |
| 3月18日 | アメリカより青い目の人形1万2739体が贈られる。 |
| 3月20日 | イギリスとサウード家がジッダ条約を結び、ヒジャーズ・ナジュド王国として独立。後のサウジアラビア。 |
| 3月27日 | 台湾銀行が貿易商社鈴木商店への融資打ち切りを通告し、すでに負債を抱えていた同社の資金繰りが悪化。 |
| 3月29日 | 日本帝国海軍の戦艦日向が朝鮮半島の西側はるか沖合の東シナ海を航行中に暗礁に接触。調査され「日向礁」と名付けられる。韓国は戦後、可居礁と呼んで施設を建造。 |
| 4月 5日 | 鈴木商店が倒産。台湾銀行の貸付金も焦げ付く。ふたたび金融不安が広がる。 |
| 4月12日 | 蒋介石が上海クーデターを起こし、共産党を攻撃。国共合作は瓦解。北京北洋軍閥政府の勢力を弱体化させ、張作霖とは反共で一致したために、国共合作の意味が無くなったことから、従来の反共に戻ったことによる。 |
| 6月 5日 | ドイツのヨハネス・ヴィンクラーらロケット愛好者、研究者らが「宇宙旅行協会(VfR)」を設立。月へ行くことのできる宇宙飛行可能なロケットの研究が目的。軍にも接近し、ベルリンに実験場「ベルリンロケット発射場」を確保。 |
| 7月13日 | 中国共産党が対時局宣言を発し、国共内戦が始まる。 |
| 9月21日 | 日本で初めてのファッションショーが、三越ホールで行われる。一般から募集したデザインの着物を水谷八重子、東日出子、小林延子の3人の女優が着用して披露。 |
| 11月19日 | 名古屋で行われた陸軍特別大演習で、陸軍歩兵第68連隊の北原泰作二等兵が、軍隊内の部落差別を昭和天皇に直訴しようとするも取り押さえられる。北原は大阪衛戎刑務所に1年間服役した後、陸軍教化隊(問題があるとされた兵士を教育する部隊)に編入。除隊後に部落解放運動に関わった。 |
| 12月30日 | 日本初の地下鉄、東京地下鉄道・浅草駅-上野駅間が開業。現在の銀座線。 |
| のちにセブンイレブンを生んだ会社「サウスランド・アイスカンパニー」が設立。 | |
| ドイツ映画『メトロポリス』が公開される。フリッツ・ラングとテア・フォン・ハルボウ夫妻の制作。100年後の未来を舞台にしたSF映画で、その緻密な設定とストーリー仕立て、映像美から、その後の映画に大きな影響を与えた。オリジナル版は非常に長時間の作品だが、興行目的でカットされたり、戦争などを経たため、フィルムの多くが失われており再編集版しか残っていない。 | |
| 1928年(昭和3年) | |
| 3月24日 | 東京商工会議所の主催で、昭和天皇の即位大礼を記念した「大礼記念国産振興東京博覧会」がはじまる。5月27日まで。 |
| 5月20日 | ドイツ国会議員選挙でナチ党が初出馬するが、12人の当選にとどまる。景気が好転したために、政府批判寄りで危機感を煽るナチ党に支持が集まりにくかった。 |
| 6月 4日 | 張作霖爆殺事件。関東軍の河本大作主導により、北京から奉天へ列車で移動中だった張作霖を狙い、南満州鉄道との立体交差地点で爆破。列車は大破し、重症を負った張作霖はまもなく死亡した。張作霖は満州最大の軍閥を率い、中華民国政府にも影響力をもっていたが、蒋介石の北伐に伴い勢力を弱めつつあった。関東軍が直接満州統治を考えるようになったことから、排除したという説が有力だが、河本大作の動機や独断だったかどうか、また爆破の具体的方法など、不可解な点も多い。奉天軍閥は張学良が後を継ぐ。 |
| 6月 4日 | 第1次大戦のドイツ賠償案で、ヤング案が決定する。最終的な買収総額を、減額の上で決定。それを基準に年賦の期限を59年として毎年の支払いを計算し、ヤング債を発行する他、物納は以降10年で終了する。国際決済銀行が設立され、支払いを管理し、連合国による政治的な管理は終了する。ドイツにとってはかなり負担が減るものだったが、ドイツ国民の間で将来に渡る賠償の確定に反発が広がる。ナチスが権力を掌握していく理由の一つにもなった。 |
| 6月18日 | 北極探検飛行で遭難した飛行船「イタリア」の救援に水上機で向かっていた探険家のアムンセンが消息を絶つ。 |
| 6月29日 | 治安維持法改正。厳罰化。 |
| 6月 | 清東陵事件。軍閥直魯聯軍の有力将だった孫殿英が、国民党に降伏した直後、配下の兵を率いて清の歴代皇族が眠る清東陵で盗掘略奪を行う。溥儀ら清皇族を始め、国民からも批判されたが、国民党の有力者に略奪品などを賄賂として送ったため、不問に付された。これが溥儀が国民党に敵意を抱き、日本による満洲建国に参加する主要因となる。 |
| 7月28日 | アムステルダムオリンピック開会。 |
| 8月12日 | アムステルダムオリンピック閉幕。日本は織田幹雄が三段跳びで、鶴田義行が200m平泳ぎで金メダルを、人見絹枝が陸上800mで銀メダルを、高石勝男が100m自由形で銅メダルを取る。女子800mはドイツのリナ・ラトケと人見絹枝がゴールに倒れ込む激戦となったため、次の大会から女子陸上は200mまでとなり、800mが復活するのは1960年のローマ大会となった。 |
| 9月28日 | 細菌学者アレクサンダー・フレミングが、黄色ブドウ球菌の培養中に混ざった青カビのコロニー周辺に黄色ブドウ球菌が生育しないことを発見。青カビが産生する物質によるものと考え、翌年この物質をペニシリンと名付ける。 |
| 10月 2日 | のちにバチカンの「属人区」(教会区の一種)となるオプス・デイがホセマリア・エスクリバーによりスペインで創立される。 |
| フリッツ・ラングによる映画『月世界の女』が公開。この作品ではロケット研究者らが制作に関わった。 | |
| 1929年(昭和4年) | |
| 2月11日 | イタリア政府とバチカンとの間でラテラノ条約が成立。バチカン市国が誕生。 |
| 2月14日 | 聖バレンタインデーの虐殺。シカゴのギャング、アル・カポネが命じて、敵対組織モラン一家の構成員と市民をマシンガンで射殺した事件。 |
| 3月24日 | イタリア総選挙が実施され、国家ファシスト党の党大評議会によって選出された定員400名の候補者を信任するかどうかの2択投票という形になる。賛成98.43%。 |
| 4月 8日 | 個性と人格を重んじた全人教育を主張する小原國芳が玉川学園を創設。 |
| 4月14日 | 第1回モナコグランプリ開催。モナコのモンテカルロ市街地コースを使ったレースの始まり。 |
| 4月15日 | 阪急百貨店開店。日本初のターミナルデパート。 |
| 6月17日 | 北海道駒ヶ岳が大噴火。死者2名。大量の泥流が発生。 |
| 7月 1日 | 国宝保存法施行。国宝が指定される(旧国宝で現在の国宝重要文化財ではない)。 |
| 7月 2日 | 張作霖爆殺事件にともなう処分をめぐって天皇の怒りを買った田中義一首相が辞表を提出し、内閣総辞職。 |
| 8月15日 | エルサレムにある「嘆きの壁」で、ユダヤ人青年らの自衛団であるベタルのメンバーが同地のユダヤ人の権利を求めるデモを行う。この話が拡大してアラブ側に伝わり、アラブ側のデモを誘発。 |
| 8月23日 | エルサレムなど各地で武装したアラブ側の住民らがユダヤ人居住区を襲撃。統治者のイギリス軍も出動して、アラブ民兵を攻撃したため、ユダヤ人、アラブ人に多数の死傷者を出す。いわゆる「ヘブロン虐殺事件」。 |
| 9月 3日 | ニューヨーク株式市場が史上最高値に達する。以降、徐々に下落を始める。 |
| 9月12日 | 朝鮮の京城・景福宮で「朝鮮博覧会」がはじまる。韓国併合20周年記念行事の一つ。10月31日まで。 |
| 10月 1日 | ソビエトでソビエト連邦暦が導入される。グレゴリオ暦はそのままに、7曜制をなくして週5曜日とし、各曜日を5色に色分けして、国民全員にそれぞれの色を配色、自分の色の日が休日となるシフト制システム。宗教色を排し、休日が増える代わりに生産を止めることなく効率を高める目的で導入された。国民からは大不評だったと言われる。 |
| 10月24日 | ニューヨーク株式市場が一気に大暴落。いわゆる「暗黒の木曜日」。世界恐慌の始まり。 |
| イギリス空軍のフランク・ホイットルがターボジェット機の論文を軍需省に提出する。 | |
| 1930年(昭和5年) | |
| 1月 1日 | 東京地下鉄道が上野から万世橋仮駅まで延長。開削式で建設していたため、神田川をくぐる工事が困難なことから、一旦、川の手前で開業したもの。 |
| 1月21日 | 海軍国である英、米、日、仏、伊の5カ国で、ロンドン海軍軍縮会議が始まる。 |
| 2月 9日 | 重光葵駐華公使が中華民国国民政府外交部の王正廷部長に対し、吉林省など中国各地で広まっている「田中上奏文」は偽物であるため取り締まるよう要請する。「田中上奏文」というのは田中義一首相が昭和天皇に対して、世界征服のためにまず中国を支配しなければならず、中国を支配するためにはまず満蒙を支配しなければならないとして、その具体的な政策を記したもの。内容に現実と異なる部分が多々あり、偽文書であるのは確かだが、極東裁判の直前まで米・中・ソ連の対日プロパガンダに利用された。誰が制作したかは諸説あり不明。 |
| 2月18日 | アメリカのクライド・トンボーが、師のパーシヴァル・ローウェルの主張をもとに、1万枚以上の写真の中から冥王星を発見する。 |
| 3月16日 | 和歌山県紀三井寺町(現和歌山市)沖合で、和歌山中学校の漕艇部員8名が遭難。全員が死亡。悪天候の中、新人生徒のみが定員オーバーで6人乗りのボートに乗り込み、沖合に出たため。 |
| 4月10日 | 台湾総督府が進めていた、嘉義庁、台南庁一帯の大規模灌漑施設である嘉南大圳が竣工。 |
| 4月22日 | ロンドン海軍軍縮会議で英、米、日の妥協が図られ軍縮条約が成立。仏、伊は条件が折り合わず事実上の離脱。 |
| 4月 | バンク・オブ・マンハッタン・トラスト・ビル(283m、70階・のち40ウォール・ストリートと改名)がニューヨークに完成し、高層ビル世界一の座をウールワースビルから奪う。 |
| 5月17日 | 第一次世界大戦のドイツの賠償案の変更を定めたヤング案が発効する。ドイツへの資本投下を行うアメリカの思惑を反映し、ゼネラル・エレクトリック社会長オーウェン・ヤングらによってまとめられた賠償軽減案だが、ドイツ国民の反感を買い、ナチ党飛躍の要因の一つとなった。大幅に減額し超長期の返済期間を定めている。 |
| 5月28日 | 建設中から世界一競争をしていたクライスラービルが完成し、バンク・オブ・マンハッタン・トラスト・ビルを追い抜いて、世界一となる(塔頂部まで高さ320m)。エッフェル塔(当時312m)も追い抜いたことでビル以外の高層建築も含めて世界一に。アールデコ様式の独特のデザインで有名。 |
| 5月30日 | 間島共産党暴動。満洲の東方、朝鮮との国境沿いにある豆満江北岸の間島で、日本および奉天軍閥と対立していた朝鮮独立派社会主義者らが、中国共産党の支援を受け武装蜂起。日本領事館や鉄道施設などを襲う。以後1年ほど暴動が頻発。無関係の一般朝鮮人市民も巻き込まれて土地を追われる。日本軍と奉天軍閥が鎮圧のため出兵。 |
| 8月18日 | 作家谷崎潤一郎が、妻・千代と離婚し、作家佐藤春夫がその千代と再婚することを連名で発表し、細君譲渡事件と世間で騒がれる。 |
| 9月14日 | ドイツ国会議員選挙。世界恐慌の影響で社会不安が強まり、ナチ党が15.7%の得票率で第二党(107議席)、ドイツ共産党が13.1%の得票率で第三党(77議席)に躍進する(総数は577議席)。 |
| 10月 1日 | 枢密院でロンドン海軍軍縮条約を可決。 |
| 10月 2日 | 日本がロンドン海軍軍縮条約に批准。天皇の統帥権干犯問題に発展する。 |
| 11月26日 | 早朝に北伊豆の丹那断層を震源とするマグニチュード7.3の北伊豆地震が発生。激しい揺れを伴い、伊豆半島北部を中心に建物の倒壊、山崩れなどで死者行方不明者272人、家屋全壊2165戸などの被害を出す。建設中の丹那トンネルが大きくずれた他、江間尋常小学校校庭の忠魂碑そばに展示されていた魚雷表面に、地震で揺れた台座の擦過傷が地震計の波のように刻みこまれ、後に人工物ながら天然記念物に指定された。 |
| 11月28日 | 太宰治が、知り合ったばかりの女給田部シメ子と心中を図り、田部だけが死亡。 |
| この年、香川県に豊稔池堰堤が完成。日本国内では非常に珍しい5連式マルチプルアーチダムで、地元の資材と、地元住民の労働力で作られた。 | |
| インドからイギリスへ留学していた19歳のスブラマニアン・チャンドラセカールが、白色矮星の質量には上限があることを発見し、さらに、質量の大きな恒星は自重によって押しつぶされ、光も抜け出ない星になることを理論で示すも、師であった学界の重鎮アーサー・エディントンににべもなく否定される。この結果、ブラックホール研究が大幅に遅れたと言われる。 | |
| 1931年(昭和6年) | |
| 1月21日 | ドイツ宇宙旅行協会が、液体ロケットの発射実験を行う。高度90mに到達。 |
| 1月28日 | メキシコとフランスが領有権を争ったクリッパートン島事件の仲裁判決が出される。太平洋の無人島である同島の発見はスペイン(継承者はメキシコ)のほうが古いが、同島の主権を主張し公表したのはフランスのほうが先であるため、フランスの領土とするもの。無人島の領有権は、同地に主権の表示を残さず離島したとしても、公的に通告し新聞等で公表した時点で成立するという国際法上の慣例となった。なお島の名前は、同島を拠点にしたイギリスの海賊ジョン・クリッパートンから来ている。 |
| 2月14日 | 映画『魔人ドラキュラ』公開。監督はトッド・ブラウニング。ハンガリー人俳優ベラ・ルゴシ(ルゴシ・ベーラ)の演じるドラキュラは、その後のドラキュラのイメージのもとになった。 |
| 3月14日 | 宇宙旅行協会のヨハネス・ヴィンクラーらがデッサウでロケットHW-Iの打ち上げ実験を行う。 |
| 4月18日 | アマチュアの考古学者、直良信夫が、兵庫県明石市の西八木海岸で、腰骨の一部を発見。いわゆる「明石原人」。のち空襲で失われ、実際にいつの時代の人間の骨だったのかは不明。 |
| 5月 1日 | ニューヨークのエンパイア・ステート・ビルディングが完成。高さは443.2m、102階建て。クライスラービルを抜いて世界一高いビルとなり、その後42年間世界一の座を守った。 |
| 6月21日 | ドイツの鉄道車両シーネンツェッペリンが、230km/hを達成。 |
| 7月 2日 | 万宝山事件。中国長春の近郊にある万宝山で入植した朝鮮人(間島共産党暴動に巻き込まれ住居を失い、日本政府の政策で万宝山に移住した)が地主郝永德から土地を借り水路を掘ったところ、中国人農民と対立、騒動に発展。中国と日本の警察が出動して収拾を図る。死者はなし。ところが朝鮮日報などが朝鮮人多数殺害と報道。 |
| 7月 3日 | 万宝山事件で朝鮮人多数が犠牲になったという誤報を信じた朝鮮市民が、京城、仁川などで中国人襲撃事件を次々と起こす。いわゆる朝鮮排華事件。 |
| 7月 5日 | 平壌で中華街が襲われる大規模な暴動が発生。中国人88人が死亡。警察と駐屯軍が出動。 |
| 7月 9日 | 日本と中華民国両政府関係者が各地で起こっている中国人襲撃暴動について会合。 |
| 7月12日 | 万宝山事件について「朝鮮人多数殺害」の誤報を書いたとされる朝鮮日報の長春支局長金利三が訪ねてきた朝鮮人3人に連行され暴行の上、謝罪文を書かされる。 |
| 7月15日 | 朝鮮日報の長春支局長金利三が射殺される。 |
| 7月16日 | エチオピア帝国で初の成文憲法が公布される。 |
| 8月25日 | 羽田空港が開港。当初は300m×15mの滑走路1本。 |
| 9月18日 | 柳条湖事件。南満州鉄道が爆破され、それを理由に関東軍が満洲の武力制圧に動く。満洲事変の始まり。 |
| 9月18日 | ヒトラーが結婚まで考えたほど溺愛していた姪のゲリ・ラウバル(異母姉アンゲラの娘)が自殺。画家との交際を反対された挙句の自殺だったと言われる。なお叔父と姪の結婚「叔姪婚」自体は欧州ではさほど珍しくはない。 |
| 10月 1日 | 東京日日新聞が、政府の行財政整理原案を報道し、その中で東京商科大学の予科と専門部を廃止することが含まれていたため、東京商科大学の教授、学生、およびOBで作る如水会が反発。その後、校舎に籠城し、警察と衝突するなどの事件に発展。いわゆる「籠城事件」。最終的には政府側が折れて、廃止は撤回された。 |
| 11月21日 | 東京地下鉄道が神田まで延長。万世橋駅は廃止。 |
| 12月 5日 | ソ連政府により、モスクワの救世主ハリストス大聖堂が爆破解体される。跡地に大ソビエト宮殿の建設が進められるが、戦争とスターリン体制の崩壊で中止となった。大聖堂は2000年に再建。 |
| 12月11日 | 英国で、英連邦を法的に定めるウェストミンスター憲章が成立。イギリス、アイルランド自由国、カナダ、ニューファンドランド、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ連邦が同格の連邦を構成する。 |
| 映画『フランケンシュタイン』が公開される。メアリー・シェリーの原作とはかなり異なった内容だが、この映画でボリス・カーロフが演じた面長で四角い顔に縫い目、ボルトがはまった不気味な怪物「フランケンシュタイン」のイメージが定着するきっかけとなった。原作ではフランケンシュタインは発明家の名前で、人造人間は見た目は悪いものの知的な存在であり必ずしも「怪物」ではない。 | |
| 1932年(昭和7年) | |
| 1月 6日 | 春秋園事件。天竜や大ノ里ら多数の力士が、相撲協会に対し待遇改善と、集客増加のための改革を求める。 |
| 1月 8日 | 桜田門事件。陸軍始観兵式を終えて戻る途中の昭和天皇が乗車した馬車(御料車)に韓人愛国団のメンバー李奉昌が爆弾を投げつける。一木喜徳郎宮内大臣の乗る馬車が破壊される。 |
| 1月 9日 | 春秋園事件。天竜や大ノ里らは協会側との意見対立が解消せず、新たな賛同者も含めた幕内・十両力士の大半の48人が脱退して新組織を起こす。協会側は番付編成が混乱し、十両や幕下からも急遽昇進させる事態に。 |
| 1月18日 | 上海で日蓮宗僧侶らが襲われ、1人が死亡、2人が重症を負う。 |
| 1月28日 | 第一次上海事変。桜田門事件に関する「民国日報」の報道と、日蓮宗僧侶襲撃事件を受けて現地日本人が反発。これをきっかけに日中両軍が衝突。 |
| 2月 9日 | 井上準之助前蔵相が血盟団員・小沼正に射殺される。血盟団事件の始まり。 |
| 3月 1日 | 満洲国建国宣言。 |
| 3月 5日 | 三井銀行本店の玄関前で三井財閥の團琢磨が血盟団の菱沼五郎の手で射殺される。 |
| 3月 7日 | 玉ノ井バラバラ事件。バラバラ殺人事件という表現の始まりとなった殺人事件。 |
| 3月11日 | 血盟団の代表、井上日召が自首。血盟団が一斉摘発される。 |
| 3月28日 | ロシアのザバイカルにイルクーツク航空第125工場が設立される。のちのイルクート。各試作設計局が設計した航空機の製造を担当。ソ連崩壊後はエアバスなど西欧の航空機製造にも関わっている。 |
| 4月29日 | 上海天長節爆弾事件。韓人愛国団のメンバー尹奉吉によって、天長節の集会会場に爆弾が投げ込まれ、上海派遣軍司令官白川義則大将と上海日本人居留民団行政委員長の河端貞次が死亡、第9師団長植田謙吉中将・第3艦隊司令長官野村吉三郎海軍中将・在上海公使重光葵・在上海総領事村井倉松・上海日本人居留民団書記長友野盛が重傷を負う。 |
| 5月 9日 | 坂田山心中事件。新聞の「純潔の香高く 天国に結ぶ恋」で有名に。 |
| 5月15日 | 五・一五事件勃発。海軍の青年将校らによって、首相の犬養毅が暗殺される。 |
| 5月20日 | アメリカ人女性飛行士アメリア・イアハートが、ニューファンドランド島からアイルランド島のロンドンデリーまで飛行し、単独大西洋横断に成功。 |
| 6月12日 | サンマリノ鉄道が開業。イタリアの沿岸都市リミニから丘陵の上にある独立国家サンマリノの首都まで31.5kmの電気鉄道。 |
| 7月 8日 | ニューヨーク株式市場が再び最安値に達する。 |
| 7月31日 | ドイツ議会の選挙が行なわれ、国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)が230議席を獲得し第一党となる。 |
| 9月23日 | アラビア半島のサウード家が、ヒジャーズ・ナジュド王国とハッサ、カティフなどの地域を統合して、サウジアラビア王国を興す。 |
| 10月 1日 | 東京府東京市に、近隣の荏原郡・豊多摩郡・北豊島郡・南足立郡・南葛飾郡の5郡82町村全域が編入されて、新たに20区を置き東京市35区となる。 |
| 10月 1日 | イギリスでオズワルド・モズレーが英国ファシスト連合を設立。ファシスト系政党の連合体。反共、保護貿易、コーポラティズムを主張したが、反ユダヤ主義、暴力主義へと変貌した。大戦が勃発すると政府への協力姿勢を見せるが、「防衛規則18B」の施行により関係者が強制逮捕され解体。 |
| 10月 3日 | 満洲開拓武装移民団第一陣416人が出発。 |
| 10月 6日 | 宇宙協会のヨハネス・ヴィンクラーらが、政界関係者の視察の中、ロケットHW-IIの公開打ち上げを行うも、爆発して失敗に終わる。しかしこれらの実験で政界・軍部の注目を得るようになる。 |
| 10月10日 | 桜田門事件の李奉昌が処刑される。 |
| 11月 9日 | スターリンの2番めの妻ナジェージダ・アリルーエワが、寝室で死亡しているのが発見される。公式には虫垂炎の悪化によるとなっているが、自殺、もしくはスターリンに殺されたという説も有力。 |
| 11月 | 宇宙旅行協会のフォン・ブラウンが、ドイツ陸軍のロケット開発に携わるようになる。当時のロケットは大砲の延長線上のようなイメージだったため、陸軍砲兵部隊の管轄。 |
| この年頃から数年にかけて、スターリン指揮下のソビエト共産党の政策により、ウクライナの農村から農産物が徹底的に収奪され、膨大な数の農民が餓死する「ホロドモール」が起きる。農産物は、計画経済がうまく行っているように見せかけるために輸出に当てられた。死者は150万から1450万まで諸説ある。カザフなど他の地域でも同様の収奪による大飢饉が起きたという説もある。ジェノサイドの一つに認定すべきだという意見もある。 | |
| 1933年(昭和8年) | |
| 1月13日 | ソ連の航空技術者セルゲイ・イリューシンによってS・V・イリユーシン試作設計局が設立される。戦前は軍用機、戦後は旅客機の開発で知られる。ロシア語では「イリユーシン」。 |
| 1月30日 | ヒトラーが首相となり、ヒトラー内閣が成立。 |
| 2月 1日 | ヒトラー、ドイツ国会を解散し、総選挙を決定。 |
| 2月20日 | 築地署事件。プロレタリア作家の小林多喜二が特高警察による拷問で死亡する。 |
| 2月24日 | 国際連盟ジュネーブ特別総会で、満洲をめぐる日本と中華民国の紛争を調査したリットン調査団の報告書(日中和解対策法)が可決される。松岡洋右代表らが退席。ただし言われているような、ここで脱退の宣言をしたわけではない。 |
| 2月27日 | ドイツ国会議事堂放火事件。ドイツ共産党への非合法化と弾圧の口実となる。 |
| 3月 2日 | 映画『キング・コング』公開。怪獣映画のはしりとも言える作品で、その後の映画に大きな影響を与える。メリアン・C・クーパー、アーネスト・B・シェードザックが監督・制作。 |
| 3月 8日 | 国際連盟ジュネーブ特別総会での、リットン調査団の報告書可決を受け、日本政府は国際連盟の脱退を決める。 |
| 3月22日 | ナチス・ドイツの強制収容所のモデルと言われるダッハウ強制収容所が開所する。 |
| 3月24日 | ドイツでナチ党に国家人民党と中央党が協力する形で全権委任法が成立し、ヒトラー内閣に立法権が与えられ、大統領と議会は形骸化。法制度上もナチスの独裁となる。 |
| 3月28日 | ドイツで「反ユダヤ主義的措置の実行に関する指令」が出され、ナチス党員によるユダヤ商店への妨害・破壊行為が日常化する。 |
| 4月 1日 | 重要美術品等ノ保存ニ関スル法律施行。国宝保存法で定めていない美術品の保護に関する法律。 |
| 4月 4日 | 航空機5機を搭載できる大型硬式飛行船「空中空母」アクロン号が、嵐の中、ニュージャージーの沖合に墜落。乗員73名が死亡。 |
| 4月 7日 | ドイツで職業官吏団再建法が成立し、ユダヤ人が公務員職から追放される。 |
| 5月 6日 | ナチス政権、性研究者で同性愛擁護運動を行っていたマグヌス・ヒルシュフェルトの性学研究所を破壊しその蔵書を焼却する。 |
| 5月10日 | ドイツ各地の大学のある34の都市で、ナチス高官や大学教授、学生等によって、「非ドイツ的」な書物を焚書する一大儀式が行われる。 |
| 6月17日 | ゴー・ストップ事件が起こる。陸軍兵士の交通ルール違反をめぐって陸軍と警察が対立した事件。 |
| 7月10日 | 戸塚球場で行われた早大ニ軍対新人戦で、初めてナイター試合が行われる。なおプロ野球の初ナイター試合は1948年8月17日。 |
| 7月14日 | ヒトラー政権、ナチ党以外の政党を禁止。 |
| 7月20日 | ナチ党とバチカンのコンコルダート(政教条約)締結。カトリック教徒への迫害を避けるため。 |
| 7月25日 | 山形県山形市で40.8℃の気温を観測。2007年に更新するまで日本最高気温であった。 |
| 7月 | 宝塚少女歌劇団に星組を新設。東京での公演増加に伴い。 |
| 8月11日 | 関東防空大演習が行われる。信濃毎日新聞の主筆、桐生悠々が、帝都上空に敵機を侵入させた時点ですでに負けているのを前提とした演習を批判する『関東防空大演習を嗤う』の社説を執筆して大問題となる。 |
| 9月30日 | 宇宙旅行協会のロケット発射場「ベルリンロケット発射場」が閉鎖。水道料金の未払いが大きな理由。 |
| 10月10日 | ユナイテッド航空機爆破事件。アメリカ・ニューヨーク発、クリーブランドおよびシカゴ経由オークランド行ボーイング247型機が、インディアナ州チェスタートン上空300mで突如炎上し墜落。乗員乗客7人全員が死亡。残骸の調査から爆発物の爆発によることが判明しているが、犯人は不明。記録上世界最初の航空機爆破墜落事件。 |
| 11月12日 | ネス湖の怪物「ネッシー」がはじめてヒュー・グレイによって写真に撮られ報道される。 |
| 11月12日 | 新疆省政府に反乱を起こしたウイグル人によって東トルキスタン・イスラム共和国が成立。翌年崩壊。 |
| 11月15日 | 東京朝日新聞が、赤坂のフロリダダンスホールの主任教師が検挙された事件を報道。この男の情事相手が吉井勇伯爵の妻徳子であったこと、徳子が複数の華族の妻女など上流階級の女性らを男に斡旋していたことから、不良華族事件として注目される。 |
| 11月20日 | 昭和天皇の特命を受けた白根竹介兵庫県知事の調停で、陸軍と警察が和解。ゴー・ストップ事件は終結。 |
| 12月 5日 | アメリカで憲法修正第18条が廃止され、国家禁酒法は違憲となり、禁酒法時代が終了。 |
| 12月21日 | 不良華族事件を受けて、宗秩寮審議会が開かれ、関係した吉井徳子を礼遇停止、近藤廉治・泰子夫妻を除族などとする処分を決める。 |
| 12月26日 | 日本産業のグループ会社として自動車製造株式会社が設立される。後の日産自動車。 |
| この年、口永良部島新岳の噴火で、島内七釜地区は壊滅的な被害を出す。死者8名、負傷者26名。 | |
| 1934年(昭和9年) | |
| 1月 1日 | 東京宝塚劇場が開場。 |
| 1月15日 | ロシアの航空機技術者アレクサンドル・セルゲーエヴィチ・ヤコブレフによって、A・S・ヤコヴレフ記念試作設計局が設立される。略称Yak(ヤク、ヤーク)。戦前はソ連の戦闘機の主力メーカーだったが、戦後は旅客機やヘリコプター、VTOL、スポーツ機、無人機など多種類の航空機メーカーとなった。ヤコブレフは航空スポーツの創設者のひとり。 |
| 2月 7日 | 中島久万吉商工相が、1921年(大正10年)に静岡の清見寺で足利尊氏自作の木造を拝観し、同人雑誌『倦鳥』に尊氏を再評価すべきではないかと投稿した文章が、雑誌『現代』に転載されたことから、議会で「逆臣」足利尊氏を礼賛していると攻撃される。 |
| 3月16日 | 瀬戸内海・雲仙・霧島が、日本で初めて国立公園として指定される。 |
| 3月21日 | 函館大火。市街地の1/3(4146平方m)1万1105棟が焼失、2166名の死者を出す。 |
| 5月23日 | ボニーとクライドが射殺される。 |
| 6月 1日 | 自動車製造株式会社の商号を日産自動車株式会社に改称。 |
| 6月21日 | 東京地下鉄道が当初の予定である新橋まで開通。 |
| 6月30日 | ヒトラー、「長いナイフの夜」事件を引き起こして、党内突撃隊(当時ドイツ最大の軍事組織)のレーム一派、元左派のグレゴール・シュトラッサー、元首相のクルト・フォン・シュライヒャーなどを殺害。 |
| 7月22日 | アメリカで大衆に人気のあった銀行強盗のジョン・デリンジャーがFBIに射殺される。 |
| 7月25日 | オーストリアの独裁者で反ナチス政策を推進したエンゲルベルト・ドルフースがオーストリア・ナチス党員8人に首相官邸で射殺される。 |
| 8月 2日 | ドイツのヒンデンブルク大統領が死去。ヒトラーは大統領職は継がず、フューラー(指導者・総統)として首相職と兼任して最高指導者となる。 |
| 8月19日 | ドイツでヒトラー信任の民族投票を行い89.93%という支持率を得て承認される。 |
| 10月 1日 | ロシアの航空機技術者グレゴリー・ベリエフによって、タガンログに海洋航空機中央試作設計局が設立される。主に水上機、飛行艇を製造。現在のベリエフ・タガンログ航空機。超大型水陸両用貨物機や、地面効果翼機(エクラノプラン)など異色の航空機の研究でも知られるメーカー。 |
| 11月 2日 | アメリカ・メジャーリーグの選抜選手が来日。 |
| 11月16日 | 昭和天皇誤導事件が起こる。群馬県桐生市で、視察に訪れた昭和天皇を道案内する際に道を間違え、担当した警部が責任をとって自殺を図り、重症を負った事件。 |
| 11月19日 | 噴火をきっかけに要望の高まっていた桜島と対岸の鹿児島を結ぶ村営定期船が運行開始。今の桜島フェリー。 |
| 12月 1日 | 東海道本線の丹那トンネルが開業。 |
| 12月 5日 | エチオピアと、イタリア領ソマリランドとの国境問題から、エチオピア・オガデン地方のワルワルで両者が武力衝突。ワルワル事件。 |
| 12月 | ドイツでA2ロケットの発射実験に成功。フォン・ブラウンらが開発に関わったロケット。V2ロケットの前段階的な機体。 |
| この年、ドイツの宇宙旅行協会が解散。軍部の協力要請を拒否したことや、資金面の問題などが理由といわれる。メンバーの多くは、その後、軍のミサイル開発に関わるようになる。 | |
| 1935年(昭和10年) | |
| 1月11日 | アメリカ人女性飛行士のアメリア・イアハートが、ハワイからカリフォルニア州までの単独飛行に成功。 |
| 1月 | 宝塚大劇場が火災で焼失。 |
| 2月12日 | 硬式飛行船「空中空母」メイコン号が、カリフォルニア州サー岬沖で嵐に遭遇し、海上へ墜落。同型艦アクロン号の遭難の教訓で乗員の犠牲は2名にとどまる。 |
| 2月14日 | 日本の野球選抜チームが渡米。 |
| 2月18日 | 天皇機関説事件。貴族院本会議で菊池武夫議員が機関説の代表的主唱者であった憲法学者の美濃部達吉議員を非難。 |
| 3月 8日 | 忠犬ハチ公が渋谷駅前の稲荷橋付近で死亡しているのが発見される。 |
| 3月16日 | ヒトラーによりドイツ再軍備が決定。ドイツ空軍(ルフトバッフェ)が発足する。 |
| 3月20日 | 大井川電力の専用鉄道線として、千頭-大井川発電所間の運行が始まる。大井川鐵道。 |
| 3月21日 | 世紀の冤罪事件、吉田巌窟王事件で、吉田石松が出獄。再審請求がはじまる。 |
| 4月21日 | 台湾の新竹州を震源とするマグニチュード7.1の大地震が発生。台湾新竹州と台中州で死者3279名、家屋全壊17927戸と大きな被害を出す。 |
| 4月 | 宝塚大劇場が再建される。 |
| 5月18日 | マクシム・ゴーリキー号墜落事件。ソ連が空中宣伝用に製造した巨人機ANT-20「マクシム・ゴーリキー」が、モスクワ上空で宣伝飛行中に、並走していたポリカルポフI-5戦闘機が宙返り飛行をして衝突。マクシム・ゴーリキーは墜落して、乗員や招待されていた共産党幹部ら45名が死亡した。原因となった宙返り飛行も当局の命令だったと言われる。 |
| 5月28日 | バイエルン航空機製造社(後のメッサーシュミット社)の戦闘機Bf109が初飛行。3万3984機が製造された史上最も生産された戦闘機。設計に関わったのはウィリー・メッサーシュミット、ヴァルター・レーテル、ロベルト・ルッサーら。 |
| 6月 7日 | 日本放送協会名古屋中央放送局(現在のNHK名古屋放送局)が、愛知県の鳳来寺山で「ブッポウソウ」と鳴く鳥の声を中継放送を行う。その後、放送に反応して鳴いた鳥が東京浅草でみつかり、調査の結果、ブッポウソウと鳴くのは、ブッポウソウ科の鳥ではなく、コノハズクであることが判明。 |
| 8月12日 | 相沢事件。統制派の陸軍省軍務局長永田鉄山少将が皇道派の相沢三郎中佐に陸軍省軍務局長室で斬殺される。 |
| 9月15日 | ドイツで「ドイツ人の血と名誉を守るための法」と「帝国市民法」が制定(ニュルンベルク法)。本来宗教で区別されるユダヤ人を、祖父母及び両親の何れかにユダヤ教徒がいれば、本人の宗教は関係なくユダヤ人とする「人種化」を定めた法律。 |
| 9月19日 | ソ連のロケット研究者ツィオルコフスキーが78歳で死去。国葬が行われる。運搬装置のロケットだけでなく、人工衛星や軌道エレベーターの構想もしていた先進的な人物。SF作家でもあり、「ロケット工学の父」と呼ばれている。 |
| 9月26日 | 第四艦隊事件。日本海軍が演習のために編成した第四艦隊が、三陸沖の太平洋上で、台風の中で演習を強行したところ、参加艦艇の半数が損傷するという事態に。 |
| 10月 2日 | イタリア政府、エチオピア帝国に対して宣戦布告。 |
| 10月11日 | 国際連盟でイタリア政府の侵略行為に対する経済制裁が決議される。ただイギリスやフランス政権内部にもファシズムに好意的な閣僚がいたため、石油などは対象から外される。 |
| 11月24日 | ドイツで、帝国市民法第一次施行令が発布され、祖父母4人のうち1人がユダヤ教徒である場合はドイツ人とし、2人以上であればユダヤ人とする厳密な区別が定められる。 |
| 12月 8日 | 第二次大本事件。新興宗教団体大本(大本教)が、政府によって徹底的に弾圧され、本部も完全に破壊される。 |
| 博文館より国語辞典『辞苑』発行。 | |
| この年、物理学者エルヴィン・シュレーディンガーが、「シュレーディンガーの猫」の思考実験を発表。自ら発展させた量子論が「確率的」であることをマクロ的事象に展開して見せることで、その不完全を示そうとしたもの(それまでの物理学は決定論的であった)。 | |
| 1936年(昭和11年) | |
| 1月15日 | 日本、ロンドン海軍軍縮条約から離脱。 |
| 2月 5日 | 現在のプロ野球の前進組織、職業野球連盟が設立。東京巨人軍、大阪タイガース、名古屋ドラゴンズ、東京セネタース、名古屋金鯱軍、阪急軍、大東京軍の7チームが加盟。 |
| 2月 5日 | チャールズ・チャップリンの『モダンタイムス』がアメリカで公開。 |
| 2月26日 | 二・二六事件勃発。陸軍皇道派の青年将校が、近衛歩兵第3連隊、歩兵第1連隊、歩兵第3連隊、野戦重砲兵第7連隊を率いて帝都中枢を占拠。斎藤内大臣、高橋蔵相、渡辺教育総監を殺害。鈴木侍従長が重症を負う。警備の警官数名も死傷。 |
| 2月29日 | 二・二六事件終結。反乱と甘い対応策に激怒した昭和天皇の鎮圧の命令と、蹶起部隊を所属原隊に撤退させよという奉勅命令が下り、軍は鎮圧に動くことになり、反乱将校らは一部が自決し、残りは法廷闘争のため降伏。 |
| 3月 7日 | ヒトラー政権、ヴェルサイユ条約とロカルノ条約に反して、非武装地帯ラインラントへ進駐。各国からは明確な批判がなく、ヒトラーの拡張政策につながっていく。 |
| 4月 9日 | 中国共産党の周恩来と、国民党に従っていた旧奉天軍閥の張学良が極秘に会談。 |
| 5月 2日 | イタリア軍がエチオピア全土を制圧し、皇帝ハイレ・セラシエは列車でジブチへ落ち延びる。 |
| 5月 5日 | イタリア軍を率いたバドリオ元帥がエチオピアの王都アディスアベバに入城。ムッソリーニは対エチオピア戦争の勝利を宣言し、イタリア王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世が皇帝となり、イタリアはローマ以来の帝国となった事も併せて宣言する。 |
| 5月18日 | 軍部大臣現役武官制が復活する。 |
| 6月26日 | 世界初の実用ヘリコプター、Fw61が初飛行。ドイツの研究者ハインリヒ・フォッケが開発。 |
| 7月15日 | 国際連盟で対イタリア経済制裁が解除される。エチオピア戦争がイタリアの勝利に終わったため、経済制裁を強く主張した反ファシズム派のイギリス外相イーデンに対し、イタリアを支持していたチェンバレンやチャーチルが力を持ったことによる。 |
| 7月17日 | スペイン植民地のモロッコで反乱が発生。人民戦線政府に反発していた軍部や資本家などもこれに加わり、スペイン内戦が始まる。 |
| 7月19日 | 人民オリンピックが開催される予定だった日。ナチスドイツのベルリンオリンピック開催を批判したスペイン人民戦線政府がバルセロナで開催を進めていた競技大会で、22カ国が選手団を送ることにしていた。しかし17日に勃発したスペイン内戦により幻となった。 |
| 7月31日 | 第12回夏季オリンピックを東京で開催することが決定される。 |
| 8月 1日 | 第11回夏季オリンピック、ベルリン大会開催。16日まで。聖火リレーのイベントが始めて行われる(聖火自体は古代オリンピックから、聖火台は1928年のアムステルダムオリンピックから存在)。 |
| 9月 5日 | ロバート・キャパがスペイン内戦のさなかに『崩れ落ちる兵士』を撮影。 |
| 9月 7日 | オーストラリア・タスマニアの動物園で飼育されていた有袋類の一種フクロオオカミの最後の1頭「ベンジャミン」が死亡し絶滅。 |
| 9月19日 | 関門海底トンネルの建設を開始。 |
| 9月25日 | 澤村栄治が日本プロ野球初のノーヒットノーラン。 |
| 10月 1日 | フランコがスペイン内戦の反乱軍総司令官に就任。スペイン・フランコ独裁政権の原点。 |
| 10月 4日 | ケーブル・ストリートの戦い。ロンドンのイーストエンドで、ユダヤ人排斥を訴える「イギリスファシスト連合(BUF)」のデモに対し、住民やユダヤ人、社会主義らが反ファシズムを掲げて抵抗したため、争乱に発展した事件。 |
| 10月 1日 | 東京府東京市世田谷区に北多摩郡砧村と千歳村が編入される。現在の東京都区部の範囲が定まる。 |
| 11月 7日 | 国会議事堂竣工。高さ65.45mで日本一の建物となる(それまでは三越本館)。 |
| 11月25日 | 日独防共協定締結。 |
| 11月30日 | ロンドンのクリスタル・パレス(水晶宮)が火災で焼失。ロンドン万国博覧会の会場になった鉄骨とガラスでできた巨大な建物をロンドン南郊シデナムに移築拡張したもの。再建はされず、現在は地名となって残っているのみ。 |
| 12月12日 | 西安事件。国民党の蒋介石が対共産党戦「剿共」の督戦に赴いた西安で張学良・楊虎城のクーデターで監禁される。のちの抗日国共合作に至った事件。張学良は、直前まで共産党軍と戦っていて、弱体化していた共産党勢力を軽視しており、なぜこの事件を起こしたのか動機ははっきりしない。張学良は国共合作後に国民党によって逮捕監禁され、台湾に移ったあとも監禁は1991年まで続いたが、2001年に100歳で亡くなるまで西安事件の動機を一切語らなかった。中共側では共産党を救った人物として評価が高く帰国の招聘もしたが、張学良はそれを拒絶し生涯大陸には戻らなかった。楊虎城は国民党第17路軍の司令官だが、地元の軍閥であり、事件後大規模な略奪などを行っている。のちに国民党によって監禁され、1949年に処刑された。 |
| 12月13日 | 西安事件を受けて、国民党の黄埔軍官学校書記長鄧文儀は猛反発し、西安攻撃を主張。国民党軍は共産党の拠点に対し攻勢を強める。 |
| 12月19日 | 中華民国政府の要人である宋子文が、蒋介石夫人の宋美齢の依頼で張学良との交渉を行うため、西安に入る。事件に対する支持が乏しかったことから張学良もこれに応じる。 |
| 12月22日 | 宋美齢も西安に到着して交渉に入る。 |
| 12月25日 | 蒋介石の身柄が解放され洛陽へと移動。共産党の周恩来らとの間で、張学良が事件の際に示した抗日のための8項目を遵守することで解放が決まったとされる。またソ連のスターリンが、中国共産党の温存と、日本を対中国戦に向けさせることを目的に、毛沢東に蒋介石と合意するよう圧力をかけたとされる。 |
| 1937年(昭和12年) | |
| 1月20日 | アメリカ合衆国憲法修正第20条の成立により、大統領の任期の切り替えが1月20日となる。フランクリン・ルーズベルトの2期目から実施。 |
| 2月17日 | 死のう団事件。日蓮会殉教衆青年党の信者5人が皇居前広場などで「死のう死のう」と叫んで切腹する。全員軽症。 |
| 4月 3日 | 愛新覚羅溥傑と嵯峨浩が、東京の軍人会館で結婚式を挙げる。 |
| 4月 6日 | イギリス皇帝ジョージ6世の戴冠式の奉祝として、朝日新聞社主催の亜欧連絡飛行計画で「神風号」が東京立川飛行場を離陸。 |
| 4月 9日 | 亜欧連絡飛行の「神風号」がロンドンに到着し成功する。立川を離陸して94時間17分56秒(実際の飛行時間は51時間19分23秒)かかる。 |
| 4月19日 | スペイン領ギニアで、ブビ族バヒターリ王朝の国王マラボ・ロペロ・マラカ(マラボ1世)が獄死。スペイン植民地政府に反抗したとして捕らえられていた。現在の赤道ギニアの首都マラボは、この王の名から採っている。 |
| 4月26日 | スペイン内戦でゲルニカがドイツ空軍「コンドル軍団」によって無差別爆撃される。 |
| 5月 6日 | ドイツの飛行船ヒンデンブルク号爆発事故。アメリカ合衆国ニュージャージー州レイクハースト海軍飛行場で、ドイツ・フランクフルトから飛来したドイツの硬式飛行船・LZ129ヒンデンブルク号が爆発炎上し墜落。乗員乗客35名と地上の作業員1名が死亡。当初は浮揚ガスの水素が炎上したとされていたが、のちに外皮の塗料が放電によって発火したという説が有力になる。 |
| 5月17日 | 日本初の気象観測船「凌風丸」が進水。室戸台風の被害を受けて建造された。 |
| 6月 4日 | 普天堡の戦い。朝鮮の咸鏡南道甲山郡普天面保田里(普天堡)を東北抗日聯軍第6師が襲撃。警察署を襲撃後、市街地を襲って住民から金品などを強奪して撤収。警察署員らが追撃を行い交戦。警官隊は死傷者21人、聯軍第6師は死傷者50人程度。市民の被害の多くは朝鮮人だが、北朝鮮や韓国では日本に勝利したとしている。金日成の名が初めて知れ渡った事件。 |
| 7月 1日 | 南樺太の豊原町が市制を施行して豊原市となる。南樺太では唯一の市。 |
| 7月 2日 | アメリカ人女性飛行士で冒険家のアメリア・イアハートが、赤道上世界一周飛行中に南太平洋で消息を絶つ。 |
| 7月 7日 | 北平(北京)郊外の盧溝橋で日本陸軍支那派遣軍と中華民国国民革命軍第29軍が武力衝突。盧溝橋事件。現地での衝突に至る経緯には諸説ある。 |
| 7月11日 | 盧溝橋の武力衝突で、日本の松井特務機関と、現地自治政府である冀察政務委員会の間で休戦協定が締結される(松井・秦徳純協定)。しかし日本政府は追加派遣を決定。蒋介石も抗日戦を主張し、日中戦争へと拡大する。 |
| 9月 6日 | 岸田國士、久保田万太郎、岩田豊雄の3人の発起により劇団「文学座」が創立される。 |
| 9月10日 | 写真化学研究所(PCL)、ピー・シー・エル映画製作所、ゼーオー・スタヂオ、東宝映画配給の4社が合併し、東宝映画株式会社が誕生する。 |
| 9月11日 | 後楽園スタヂアムがオープン。 |
| 10月 2日 | ドミニカ共和国西部のチバオなどで、8日にかけてハイチ系住民への虐殺事件が起きる。通称「パセリの虐殺」。ドミニカ共和国のトルヒーヨ大統領は民族主義を訴え、隣国ハイチから流れ込んでくる住民の排除を名目に軍を動員して虐殺した。犠牲者数ははっきりしないが2万人を超えると言われる。パセリの発音からドミニカ人かハイチ人かを区別したと言われる。 |
| 10月25日 | 企画庁と内閣資源局が統合して企画院が発足。 |
| 11月 6日 | 日独伊防共協定成立。 |
| 11月11日 | 小串鉱山山津波災害。群馬県と長野県の県境、毛無峠にある硫黄鉱山「小串鉱山」で、鉱山施設の背後の斜面が崩壊。鉱員たちは山中に入坑していて助かったが、会社施設とその周辺にあった家族らの住宅や小学校など350戸以上が土砂に飲み込まれ、家族や児童ら245人が死亡。32人が重軽傷を負う。また倒壊した製錬所の火が施設内にあった火薬庫に燃え移って爆発し周辺施設や病院など38戸が焼失した。硫黄鉱山操業のため木々を燃料にし、また排煙で木が枯れてはげ山になっており、そこに大雨で地盤が緩んだものとみられる。 |
| 11月18日 | 京城日報に、満州国軍によって「共産匪 金日成」殺害の記事が掲載される。普天堡の戦いなどを起こした当時のゲリラ軍にいたとされる「金日成」と後に北朝鮮を建国した「金日成(金成柱)」では、中国共産党や北朝鮮で粛清された甲山派などの証言から年齢などが異なるため、別人説もある。 |
| 12月12日 | 挹江門事件。日本軍の攻略が始まった南京で、南京城内から脱出しようとする国民政府軍第87師・88師・教導総隊の兵士らが、唯一通過可能だった挹江門(長江に面した西北の城門)に殺到。それに対して、南京守備司令官唐生智の命令で城門を守備し、逃走兵の阻止を任務としていた督戦隊の国民政府軍第36師212団が銃撃。双方で銃撃戦に発展し、1000名以上の国民政府軍兵士が死亡する。唐生智は城門だけでなく道路封鎖や渡し船の破壊を行い、市民も避難できないようにしたが、自身は途中で逃走している。 |
| 12月26日 | 第1回極東ユダヤ人大会で、陸軍ハルビン特務機関長だった樋口季一郎少将が出席して、「ユダヤ人に土地を与えよ」とナチスを批判する祝辞を述べて、ドイツから猛反発を買い大問題に発展する。 |
| 1938年(昭和13年) | |
| 1月21日 | 映画監督ジョルジュ・メリエス死去。大衆向けの映画製作者として映画界黎明期に活躍しその発展に貢献した。世界初の職業映画監督と呼ばれる。SF、ファンタジー、ホラー、ドキュメンタリーからポルノ映画まで531本の映画を作成したが、軍による没収、本人の焼却処分、劣化などで200本ほどしか残っていない。 |
| 1月26日 | ヒトラー、国防相ブロンベルク元帥をスキャンダルを理由に罷免。 |
| 1月27日 | 東京帝国大学経済学部の河合栄治郎教授(自由経済主義者)の書籍が発禁処分を受けたことをうけて、平賀譲総長が、河合栄治郎への休学処分にあわせて、河合と激しく対立する土方成美教授(統制経済主義者)も休学処分とする。同学部の教授らが学問に対する侵害だとして辞表を提出する事態に発展する。 |
| 1月28日 | ヒトラー、国防相ブロンベルク元帥に続き、陸軍総司令官フリッチュ上級大将をスキャンダルを理由に罷免し、独立志向のあった軍を掌握。 |
| 2月16日 | ソ連の発注で、耐氷貨物船の「ボロチャエベツ」が、川南工業香焼島造船所で進水。後の南極観測船「宗谷」。 |
| 3月 3日 | 「黙れ事件」。衆議院の総動員委員会で、陸軍軍務局の佐藤賢了中佐の発言が長引いたことに対し政友会の宮脇長吉議員が批判をしたところ、佐藤中佐が「黙れ」と発言し委員会が紛糾したもの。杉山陸軍大臣が遺憾の意を示して収拾を図った。 |
| 3月 3日 | 愚連隊の万年東一と配下3人の計4人が、社会大衆党党首安部磯雄を、居住していた同潤会江戸川アパートに襲撃。殴打して重症を負わせる。すぐに衆議院でこの事件が取り上げられ、末次内相の責任問題に発展。内相及び近衛首相は政府の責任で議員の保護と、犯人検挙を約束。まもなく万年ら6名が逮捕される。社会大衆党が翼賛体制に協力するふりをして社会主義体制にしようと画策しているという憶測から、党首安部磯雄と書記長の麻生久を狙ったもの。警視総監安倍源基が裏で動いていたとも言われる。 |
| 3月12日 | ヒトラーに併合への最後通牒を受けたオーストリア首相クルト・シュシュニックが、やむなく要求を飲んで辞任。ドイツ軍がオーストリアに進駐を開始する。 |
| 3月13日 | あらたにオーストリア首相となったアルトゥル・ザイス=インクヴァルトが合併法を発布し、オーストリアはドイツに併合される。いわゆる「アンシュルス」。 |
| 3月17日 | 西尾末広除名事件。衆議院本会議で、国家総動員法成立を目指す近衛内閣に対する賛成演説を行った社会大衆党の西尾末広議員が「ヒットラーの如く、ムッソリーニの如く、あるいはスターリンの如く大胆に進むべき」と発言したことに、スターリンの名を出すのはけしからんとして除名処分に発展。なお全く同様の発言をあえてした尾崎行雄議員にはなんのお咎めもなかった。 |
| 3月25日 | 文学座の初公演。「みごとな女」「我が家の平和」「クノックス」の3本が上演される。 |
| 3月30日 | ムッソリーニは、イタリア帝国の統帥権を持つ帝国元帥首席を創設。国王と自らが共同就任。国王はムッソリーニを公爵にしようとしたがそれは断っている。 |
| 3月 | この頃、ソ連を横断して満洲国境沿いのオトポールまで逃げてきたユダヤ人に対し、ハルビン特務機関長の樋口季一郎少将が、上海のユダヤ人租界まで行けるよう手配。少なくとも1940年までは同様の手配がされてユダヤ人が入国しているが、その総数は不明。100人程度から2万人という説まである。ドイツが前年の樋口少将のユダヤ人擁護の発言とこれを取り上げ日独間の外交問題に発展するが、東条英機によって不問にされた。オトポール事件とも言う。樋口は戦後、ソ連から戦犯に指定されたが世界ユダヤ人会議などの依頼で米国に保護された。 |
| 4月 1日 | 国家総動員法施行。電力国家統制法3法も施行され、配電を除く発送電事業は日本発送電株式会社に統合される。 |
| 4月24日 | チェコスロバキア・ズデーテンのズデーテン・ドイツ人党党首コンラート・ヘンラインが、チェコスロバキア政府に対し、同地方に多く住むドイツ人の自治権を要求。これがきっかけでナチス・ドイツとチェコスロバキアの対立に発展。 |
| 4月 | 宝塚少女歌劇団の星組が一旦廃止される。 |
| 5月28日 | ヒトラー、チェコスロバキア侵攻を決定。 |
| 6月 9日 | 「黄河決壊事件(花園口決堤事件)」。中国国民党軍が、日本軍の侵攻を阻止する目的で花園口で黄河の堤防を爆破。大氾濫となり54,000平方km、11都市・4,000村が水没し100万人が死亡したとも言われる。黄河の河道が変わったことによる農作物等の被害も大きかった。国民党政府は日本軍の仕業と発表したが、日本軍が侵攻方向に洪水を引き起こすというのは理屈として矛盾しており、各国の報道機関も中国軍側の行為と報じた。皮肉にも侵攻軍である日本軍が被災民の救助にあたることになり、住民の国民党への信頼が失われる結果となった。戦後の1947年に堤防は再建。 |
| 7月15日 | 第12回オリンピック東京大会の開催中止が閣議で決定される。日中戦争勃発に伴う内外からの批判を受け。第5回冬季オリンピック札幌大会も中止に。 |
| 7月22日 | スターリンの大粛清の中、ジェット推力研究所の所長コロリョフが冤罪により逮捕される。拷問の末に「自白」しシベリアへ流刑。友人だったロケット研究者ヴァレンティン・グルシュコが逮捕され尋問を受けた際にコロリョフの名を出したことが原因だとされる。両者は戦後のミサイル開発で重要な地位に就くも、このことと技術方針の対立で死ぬまで不和が続いた。 |
| 8月17日 | ドイツでユダヤ人の強制改名(ドイツ風ではなくユダヤ風の名前に変える)が始まる。 |
| 8月24日 | 大森民間航空機空中衝突事故。羽田飛行場から訓練飛行に飛び立った日本飛行学校のアンリオHD.14EP-2型機と、続けて訓練飛行のために飛び立った日本航空輸送のフォッカースーパーユニバーサル旅客機が、まもなく大森上空で空中衝突。アンリオ機は大森区森ヶ崎の置屋「四曼」の敷地に、フォッカー機は同区大森9丁目の「山本螺子製作所」の工場敷地に墜落。従業員や近所の人々が救助に駆けつけた所、航空燃料が引火爆発。付近一帯に類焼し、負傷者の死亡などもふくめ最終的に死者85名、負傷者76名を出す惨事となる。 |
| 9月15日 | ドイツ・ベルヒテスガーデンで、ズデーテン問題に関して、ヒトラーとイギリス首相ネヴィル・チェンバレンの首脳会談が行われる。 |
| 9月18日 | ズデーテン問題に関して、イギリス首相ネヴィル・チェンバレンと、フランス首相エドゥアール・ダラディエの首脳会談が行われる。 |
| 9月19日 | イギリスとフランス政府は、チェコスロバキア大統領エドヴァルド・ベネシュに対して、ズデーテン地方のドイツへの割譲を勧告。ベネシュはこれを拒絶。 |
| 9月22日 | チェコスロバキア政府、ズデーテン割譲に同意し、翌日ミラン・ホッジャ内閣は総辞職。ヤン・シロヴィー政権樹立。チェンバレンとヒトラーが会談。ヒトラーは強硬姿勢を変えず。 |
| 9月23日 | チェコスロバキア政府、総動員令を出す。 |
| 9月24日 | チェコスロバキアと同盟しているフランスも動員令を発する。 |
| 9月25日 | イギリス首相チェンバレン、ヒトラーに、チェコスロバキアのベネシュ大統領と仲介する意図を伝えるがヒトラーは拒否。 |
| 9月27日 | ヒトラー、ズデーテン問題で最後通告。 |
| 9月28日 | イタリア首相ベニート・ムッソリーニが仲介に乗り出し、ヒトラーもこれに応じる。 |
| 9月29日 | ヒトラー、イギリス首相ネヴィル・チェンバレン、フランス首相エドゥアール・ダラディエ、イタリア首相ベニート・ムッソリーニとミュンヘン会談をおこない、翌30日、チェコスロバキア西部のズデーテン地方のドイツ割譲、チェスキー・チェシン地方のポーランド割譲、南部スロバキアのハンガリー割譲、カルパティア・ルテニア(カルパト・ウクライナ)の自治拡大を認めさせる。チェコスロバキア政府は受諾しベネシュは辞任。スロバキアとカルパティアの割譲を求めたハンガリーは納得せず。英仏では戦争が回避されたと市民らが歓迎する。 |
| 10月 1日 | ドイツ軍がズデーテン地方へ進駐を開始。チェコスロバキア第二共和国政府樹立。 |
| 10月 2日 | ポーランド軍がチェスキー・チェシン地方に進駐を開始。 |
| 10月 6日 | ポーランド政府が旅券法を更新し、ドイツのポーランド系ユダヤ人のポーランド入国を制限。これによりユダヤ人のポーランド移送を進めようとしたドイツとの間で対立が生じる。ポーランド系ユダヤ人が両国の間に挟まれて難民化。 |
| 10月 8日 | チェコスロバキアのスロバキアとカルパティア・ルテニアが自治権を獲得。 |
| 10月30日 | アメリカでラジオドラマ『宇宙戦争』が放送され、そのリアルな導入部(臨時ニュース形式)を実際の事件と勘違いした市民100万人がパニックを起こす。事前に放送予告もしているため、それほど大騒ぎにはならなかったという説も。この話は都市伝説化し、のちに映画も作られた。 |
| 11月 7日 | ポーランド系ユダヤ人の措置問題を知ったフランス在住のポーランド系ユダヤ人ヘルシェル・グリュンシュパンが、事態を世界に訴えようとパリのドイツ大使館で、応対した三等書記官エルンスト・フォム・ラートを銃撃、ラートはまもなく死亡する事件が発生する。 |
| 11月 9日 | エルンスト・フォム・ラートの死亡事件がドイツに伝わり、全土でユダヤ商店やシナゴーグを襲う暴動が発生。いわゆる「帝国水晶の夜事件」。ナチスによる官製暴動だとも言われる。なおラート自身はナチスに批判的だったとも言われ皮肉な結果となっている。 |
| 11月11日 | ドイツでユダヤ人の武装禁止が定められる。 |
| 11月12日 | ドイツでユダヤ団体に暴動に関する罰金、ドイツ企業にユダヤ人の解雇、破壊された施設の修復をユダヤ人に命じる3政令が発せられる。 |
| 11月15日 | ドイツでユダヤ人の子供がドイツ人学校へ通うのが禁止される。 |
| 11月18日 | 地下鉄東京高速鉄道の青山六丁目(表参道)-虎ノ門間が開業。後の銀座線の一部だが、当時は別会社だった。 |
| 11月23日 | ドイツでユダヤ人の文化施設(劇場・映画館・音楽会・ダンス場)入場が禁止される。 |
| 12月20日 | 東京高速鉄道の渋谷-青山六丁目間が開通。 |
| 12月31日 | ドイツでユダヤ人の身分証明書にユダヤ人であることを示す「J」の文字が記入されることになる。 |
| 12月 | ドイツ海軍の空母A(グラーフ・ツェッペリン)が進水。 |
| ドイツ海軍の空母B(ペーター・ストラッセル)が起工される。 | |
| 1939年(昭和14年) | |
| 1月16日 | 東京高速鉄道の虎ノ門-新橋が開業し、渋谷から新橋までが全通。 |
| 3月14日 | チェコスロバキアのスロバキアと、カルパト・ウクライナが分離独立。 |
| 3月15日 | ヒトラーとチェコスロバキアのエミール・ハーハ大統領が会談。ハンガリーの圧力を恐れるハーハを脅し、ドイツ軍介入を要請させ、それを口実に、チェコを「ベーメン・メーレン保護領」として吸収、分離したスロバキア共和国を傀儡国家として事実上併合させる。 |
| 3月16日 | ハンガリーがカルパト・ウクライナに軍事侵攻しこれを併合。 |
| 3月23日 | ヒトラー政権、リトアニア政府からメーメル地方を割譲させる。 |
| 3月25日 | ムッソリーニ政権、アルバニアに対し宣戦を布告。 |
| 3月27日 | スペイン内戦で、マドリードが陥落し、フランコ政権が樹立。 |
| 4月10日 | イタリア軍、アルバニアの王都ティラナを占領。アルバニア王を称していた独裁者アフメト・ベイ・ゾグーはイギリスへ亡命。ゾグーはもともとムッソリーニとは協力関係にあった。 |
| 4月17日 | イタリア王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世が、アルバニア王も兼任することとなり、イタリアとアルバニアは同君連合となる。 |
| 5月11日 | ノモンハン事件勃発。満洲国軍とモンゴル軍が領有権係争地のハルハ川付近で武力衝突。日本・ソ連両軍が介入。 |
| 5月13日 | 国産テレビの試験放送開始。日本放送協会の放送技術研究所が電波を発射。 |
| 6月20日 | ハインケル社の開発した液体燃料ロケット飛行機He176が初飛行。 |
| 7月10日 | イェドヴァブネ事件。ポーランド・イェドヴァブネで住民がユダヤ系住民を虐殺する。ナチスによる直接的な犯行ではなく、住民に反ユダヤ主義が広がったために起こった事件。 |
| 7月29日 | ソ連の航空技術者パーヴェル・スホーイが政府の承認を受けスホーイ試作設計局(OKB-51)をハリコフ(現ウクライナ領ハルキウ)に設立。航空機メーカースホーイの前身だが、スホーイはスターリンに嫌われていたため、メーカーとして大きくなるのは戦後。 |
| 8月20日 | ノモンハン事件で、ソ連軍が攻勢に出る。 |
| 8月 2日 | 後に原爆開発につながったアインシュタインとシラードの手紙署名。 |
| 8月23日 | 独ソ不可侵条約が締結され、日本に衝撃を与える。 |
| 8月24日 | イギリスで緊急権限(国防)法が可決。 |
| 8月27日 | ドイツのハインケル社が開発したHe178が世界初のジェット飛行に成功。 |
| 8月28日 | 独ソ不可侵条約を受けて、ドイツと反共軍事同盟を進めていた平沼騏一郎内閣が「欧州情勢は複雑怪奇」と表明して総辞職。 |
| 8月31日 | グライヴィッツ事件が起こる。当時ドイツ領だったグライヴィッツ市(現ポーランド領グリヴィツェ市)のラジオ局に、ポーランド人を装ったナチスの工作員が侵入。同地のポーランド系ドイツ人にストライキを呼びかける放送を行う。ドイツ政府はこの事件を「ポーランドによる襲撃」として発表し、翌日以降始まるポーランド侵攻の正当化に利用した。 |
| 9月 1日 | 午前4時40分、ドイツ軍がポーランドへ侵攻を開始。第二次世界大戦が始まる。モクラなど一部ではポーランド軍の反撃も成功するが、多くの地域でドイツ軍優勢に進む。 |
| 9月 1日 | ドイツでユダヤ資本が完全に禁止される。 |
| 9月 1日 | イギリスで緊急権限(国防)法に基づき、防衛規則18Bが施行される。敵国に同調する組織に属する人物を、裁判抜きで無期限拘束できる規則。当初はドイツ系イギリス人など14人が逮捕される。 |
| 9月 3日 | ポーランドと同盟を結んでいたイギリス・フランス両国がドイツに対し宣戦布告。ただしポーランドが期待したようなドイツ領への攻撃は行わず。 |
| 9月 9日 | ブズラ川付近でポーランド軍が反撃を試み、ドイツ軍と激戦となる。18日にポーランド軍は敗退。軍による反撃戦はほぼ終わる。 |
| 9月10日 | 準備不足と兵力差で押されていたポーランド軍の総司令官ルィツ=シミグウィ元帥は、全軍の東南部への撤退を指令。 |
| 9月11日 | 神奈川県の鵠沼海岸で営業していた大旅館「東屋」が突如廃業。数多くの作家や画家が逗留したことで「文士旅館」とも呼ばれた。同旅館の二代目女将長谷川たかの長男は、フレスコ・モザイク画やキリスト教絵画で知られる画家の長谷川路可。 |
| 9月16日 | ノモンハン事件で、日本・ソ連両国が休戦協定を結び、紛争は終結する。 |
| 9月16日 | 東京地下鉄道と東京高速鉄道が新橋駅で相互乗り入れ。 |
| 9月17日 | ソ連軍がポーランド東部へ大規模侵攻を開始。ドイツとの秘密協定による侵略。 |
| 9月28日 | ワルシャワ陥落。 |
| 10月 6日 | ポーランド軍で最後まで抵抗していたポレシェ部隊がルブリンで降伏。ポーランド侵攻は終結。なおポーランド政府、ポーランド軍は正式に降伏はしておらず、イギリスなどへ亡命して活動を続ける。ドイツ・ソ連両軍は市民や捕虜多数を殺害。市民15万人が犠牲になったと言われる。 |
| 10月21日 | ルーズベルト大統領が設立させた「ウランに関するブリッグス諮問委員会」会合。のちの原爆開発につながる委員会で、レオ・シラード、ユージン・ウィグナー、エドワード・テラーのハンガリー系物理学者3人が議論を進めたため、ハンガリー陰謀団とも呼ばれた。 |
| 11月 8日 | ミュンヘンの巨大ビアホール「ビュルガーブロイケラー」でヒトラー爆殺未遂事件が起きる。同ホールは1923年にヒトラーがミュンヘン一揆を起こした場所で、毎年その日にヒトラーが演説するのが慣例であった。それを狙い、反ナチスの労働者だったゲオルク・エルザーは爆弾を仕掛けるが、ヒトラーは戦争の情勢に関する打ち合わせのため、早めに切り上げてしまい、ヒトラーが退出してまもなく爆弾は炸裂。7人が死亡し、63人が負傷した。エルザーはスイスへの逃走を図ったが同日逮捕され、単独犯行を主張。1945年4月9日に処刑された。すぐに処刑しなかった理由はわかっていない。 |
| 11月10日 | 朝鮮総督府が、制令で「朝鮮人ノ氏名ニ関スル件」を発布。いわゆる創氏改名。新たに「氏」を創設する創氏と改名の法的手続きが定められる。任意の制度で、「氏」は宗族制度が浸透している朝鮮にはない「家」ごとの名前であるため、反発するものも出たが、行政サービスや社会的運動から8割が創氏する。 |
| 11月30日 | ソ連軍がフィンランドに侵攻。冬戦争が勃発する。寡兵で貧弱な装備しかないが統制されたフィランド軍に、大軍を擁しながらずさんな作戦を実行したソ連軍が大敗を喫する。 |
| 12月 8日 | ソ連の航空技術者アルテム・ミコヤーンとミハイル・グレーヴィッチが、政府の承認を受けA・I・ミコヤーンとM・I・グレーヴィチ記念試作設計局(OKB-155)を設立。略称のMiG(ミグ、ミーク)で有名。戦闘機メーカー。 |
| 12月12日 | ソ連の貨客船インディギルカ号が北海道北西の猿払村沖合で挫傷沈没。住民らが救助にあたり429名を救助するも、700名以上が死亡したと見られる。ソ連は船の目的や乗客の素性について明かさず、遺体の返還にも応じず、慰霊にも消極的だった。この船に乗っていたのは強制収容の収容者、すなわち政治犯だったため、冷淡だったのではないかと言われている。 |
| 12月15日 | 映画『風と共に去りぬ』がアトランタでプレミア公開。南北戦争時代を舞台に裕福な南部の農園主の娘の波乱の人生を描いたマーガレット・ミッチェルの小説を映画化。全世界で空前の大ヒットとなり、映画史上でもトップクラスの評価をされている。戦時中の日本では表向き上映禁止対象にされていたが、占領地で見た人も多く、国内にも輸入され軍関係者向けに上映されている。 |
| 1940年(昭和15年) | |
| 1月10日 | ドイツ空軍第2航空艦隊参謀将校が乗った航空機が墜落し、機密の一部がベルギー側に漏れる事件(メケレン事件)が発生。ヒトラーはこれを理由に対フランス作戦の方針を、ベルギー主要部を通過してフランス北部へ侵入する古いシュリーフェン・プランから、アルデンヌの森を通過してフランス領に入るマンシュタインプランに変更する。 |
| 1月21日 | 浅間丸事件。豪華客船浅間丸がイギリス巡洋艦に臨検され、ドイツ人乗客が連れ去られた事件。 |
| 1月29日 | 大阪で、西成線列車脱線火災事故が起こる。当時普及していたガソリンカー(気動車の一種)が脱線・転覆で炎上。死者189名、重軽傷者69名という大惨事になる。 |
| 2月29日 | アメリカの第12回アカデミー賞で「風と共に去りぬ」が8部門で受賞。「チップス先生さようなら」「嵐が丘」「スミス都へ行く」「駅馬車」「オズの魔法使い」「二十日鼠と人間」「ノートルダムのせむし男」など名作揃いとなった激戦回で「風と共に去りぬ」が圧勝した。ロサンゼルス・タイムズが結果をリークしたため、受賞内容の入った封筒を封切りする制度が導入されることになる。 |
| 3月15日 | 「紀元2600年記念日本万国博覧会」開催予定だった日。戦争などにより中止となった。なお、この大会の前売り券は1970年の大阪万博と、2005年の愛・地球博でも使用できた(前売り券所有者に各博覧会の招待券を発行する形をとった)。 |
| 3月30日 | 汪兆銘政権の樹立。日本と協力関係を決めた汪兆銘と、中華民国の反蒋有力者や旧北洋軍閥政府の閣僚らによって興された政権。中華民国の正統政権を主張する。 |
| 4月 9日 | ナチスドイツがデンマーク、ノルウェーに侵攻。 |
| 4月13日 | 初めてのテレビドラマ『夕餉前』が試験放送される。14日、20日にも放送。 |
| 5月 1日 | 国民優生法公布。「悪質なる遺伝性疾患を持つ人物」等を断種する法律。優生学に基づいて実施され、戦後の優生保護法、母体保護法につながる。 |
| 5月10日 | ナチスドイツがデンマークに侵攻したのを受けて、イギリス軍がデンマーク領アイスランドに侵攻。 |
| 5月10日 | ナチスドイツ、フランスに侵攻を開始。 |
| 5月13日 | アメリカの試作ヘリコプターVS-300が初飛行。開発したのは亡命ロシア人の研究者イーゴリ・シコルスキー。 |
| 5月22日 | イギリスで緊急権限(国防)法の防衛規則18Bの適用範囲が拡大決定される。これにより、敵国に通じたものだけでなく、国内の極右勢力なども適用対象となる。政治家、思想家、軍人、文化人など1000人以上が逮捕され、刑務所および収容所に収監された。その後、徐々に釈放されたものの、大戦期間中は当局の監視下に置かれた。 |
| 5月23日 | イギリスでオズワルド・モズレーが防衛規則18Bの適用を受け逮捕される。イギリス・ファシスト連合は逮捕者が相次ぎ崩壊。 |
| 6月 5日 | 紀元二千六百年奉祝東亜競技大会開催。明治神宮外苑などの東京大会が9日まで、13日から16日までは橿原神宮外苑と甲子園で関西大会が行われた。参加国は、日本、満洲、中国(汪兆銘政権)、モンゴル(蒙古聯合自治政府)、フィリピン・コモンウェルス、ハワイ準州の6カ国。 |
| 6月10日 | イタリア政府、イギリスとフランスに宣戦布告。ムッソリーニや国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世は、参戦には慎重であったが、ドイツ軍の電撃的勝利を受けて、戦争は短期間で終わるとの見通しもあり方針を変更。 |
| 6月14日 | ナチスドイツ、パリに入城。 |
| 6月17日 | フランス政府内部で和平派が権力を握り、ペタン元帥が首相に就任。 |
| 6月21日 | フランス、ナチスドイツに降伏。 |
| 6月22日 | ドイツとフランスがコンピエーニュの森で独仏休戦協定締結。フランスは中南部のペタン首相率いるフランス政府が統治する「自由地域」と、北西部のドイツが占領する地域に分けられる。この段階では、フランス人の多くが、欧州大戦は短期間でドイツの勝利で終わると考え、独仏戦の終結を決めたペタン政権を支持していた。 |
| 6月25日 | ドイツ、フランス政府を使って、ユダヤ人をマダガスカルへ移住させる計画案が出される。いわゆるマダガスカル計画。 |
| 6月27日 | ソ連のソビエト連邦暦が廃止される。 |
| 7月 1日 | フランス政府、首都を臨時首都のボルドーから中部のヴィシーに移転。 |
| 7月 2日 | メルセルケビール海戦。フランス領アルジェリアのメルセルケビール港でイギリス海軍とフランス海軍が戦闘。イギリス側が勝利するも、フランス艦隊の被害は一部にとどまり、さらにフランス国民の反発を買う結果となったと言われる。 |
| 7月25日 | スイスで軍の最高司令官となっていたアンリ・ギザンが、中立を保ち、ナチスドイツへの協力を拒絶する「リュトリ演説」を行う。リュトリはスイスの建国とされる「リュトリの誓い(リュトリ盟約)」がなされた場所。 |
| 7月18日 | 杉原千畝カウナス領事代理がユダヤ系難民に日本通過ビザの発行をはじめる。 |
| 7月 | 十二試艦上戦闘機が制式採用され零式艦上戦闘機となる。中国戦線へ投入。 |
| 8月30日 | ヒトラー政権、ウィーン裁定によりトランシルバニア地方の領土問題を調停。 |
| 9月 4日 | この日まで、杉原千畝によって日本通過ビザの発給が行われた。最後は出発前のベルリン行の列車の中で記されている。 |
| 9月21日 | 第12回オリンピック東京大会の開会が予定されていた日。実際には中止。 |
| 9月23日 | ダカール沖海戦。イギリスと自由フランス軍が、フランス領ダカールを占領しようとして艦隊を派遣。同地のフランス艦隊と戦闘になり、フランス側の勝利に終わる。 |
| 9月25日 | 映画『燃ゆる大空』公開。 |
| 9月27日 | 日独伊三国同盟締結。 |
| 10月11日 | 紀元二千六百年特別観艦式が横浜沖の東京湾で行われる。艦艇98隻、航空機527機が参加。 |
| 10月15日 | チャールズ・チャップリン監督・主演の映画『独裁者』が初公開。制作時には様々な圧力があったとされる。ヒトラーをモデルにした架空の独裁者アデノイド・ヒンケルが顔がそっくりのユダヤ人床屋と入れ替わってしまうストーリー。ヒトラーがこの映画を見たかは不明だが、ナチスが押収した映画のリストに同作も含まれている。 |
| 10月28日 | ドイツ軍、バルカン半島に侵攻。 |
| 10月 | 宝塚少女歌劇団が宝塚歌劇団に改められる。 |
| 11月10日 | 紀元二千六百年式典が宮城外苑で開催。 |
| 11月24日 | 「最後の元老」西園寺公望死去。中国情勢などを悪化させた近衛文麿を首相に推挙したことを悔い、死ぬ間際まで日本の将来を憂いていたと言われる。 |
| ドイツ海軍の空母B(ペーター・ストラッセル)の建造が中止になる。 | |
| 1941年(昭和16年) | |
| 3月 1日 | 国民学校令公布。尋常小学校6年と高等小学校2年が廃止され義務教育8年制の国民学校に変更される。 |
| 3月10日 | 治安維持法改正。適用対象が拡大し、さらに厳罰化。 |
| 3月28日 | マタパン岬沖海戦。地中海のギリシャマタパン岬沖からクレタ島沖合にかけて、イギリス海軍及びオーストラリア海軍とイタリア海軍の間で行われた海戦。イギリス海軍が勝利し、制海権を確保。北アフリカ戦線へも影響することになる。 |
| 3月30日 | 根井三郎ウラジオストク総領事代理が、杉原千畝カウナス領事代理がユダヤ人難民に対して発給したビザについて、外務省本省の再検閲の方針に反発し、独断で日本渡航許可を出す。またこの前後2月から6月にかけてビザのないユダヤ人に対しても独自にビザを発給する。杉原千畝に比べ、根井三郎は知名度が低く、評価されていない。 |
| 4月 6日 | 琵琶湖遭難事件。第四高等学校(現金沢大学)漕艇部員8名と京都帝国大学学生3名が、ボートで琵琶湖に出て遭難。11名全員が死亡。春にこの一帯で吹く突風が原因とされる。 |
| 4月 9日 | デンマークのヘンリック・カウフマン駐米大使が、本国がナチスドイツに占領されたことを受けて、独断でアメリカ政府と交渉。デンマーク植民地のグリーンランドに米軍が駐留する協定を結ぶ。 |
| 4月12日 | グリーンランドに米軍が進駐。 |
| 4月12日 | 皇居に爆撃に耐えられるよう設計された防空施設の皇族の居館「御文庫」の建設が始まる。 |
| 4月14日 | 東京府、肉無し日を制定。月2回、肉の販売を制限するというもの。 |
| 5月 8日 | 東京肉無し日スタート。 |
| 5月10日 | ルドルフ・ヘス事件が起こる。ナチ党副総統のルドルフ・ヘスが、独英講和の交渉を行うとして、ヒトラーに相談せず戦闘機メッサーシュミットBf110で渡英。英国政府はヘスに面会後、拘禁。 |
| 5月15日 | グロスター社による最初のジェット機グロスターE.28/39が初飛行。 |
| 6月22日 | バルバロッサ作戦が発動され、ドイツ軍はソ連領に侵攻する。 |
| 7月 2日 | 御前会議において「情勢ノ推移ニ伴フ帝国国策要綱」が決定され対ソ戦準備と、南部仏印進駐などが決まる。 |
| 7月 4日 | 非採算事業目的の特殊法人「経営財団」として住宅営団、農地開発営団、帝都高速度交通営団が設立される。 |
| 8月12日 | 皇居内に建設中の防空施設「御文庫」の近くに、防空壕として「御文庫附属庫」の建設も始まる。 |
| 8月30日 | 配電統制令公布。即日施行。全国の配電事業者を統合し国内9ブロックの配電会社に再編成される。 |
| 9月 1日 | 帝都高速度交通営団が東京地下鉄道、東京高速鉄道、それに運行事業準備中だった京浜地下鉄道を引き継いで、地下鉄の運行を開始。 |
| 9月 6日 | 御前会議で「帝国国策遂行要領」が決定され、対米交渉案がまとめられる。 |
| 9月10日 | 反骨のジャーナリスト、桐生悠々が病没。 |
| 10月11日 | チトーがパルチザン活動を開始。後のユーゴスラビア・チトー政権。 |
| 10月17日 | 東条内閣成立に伴い、帝国国策遂行要領が一旦白紙に戻される。 |
| 11月 5日 | 御前会議で、帝国国策遂行要領が再決定され、対米交渉についての条件案と、交渉失敗時の武力行使の予定期日が定められる。 |
| 12月 7日 | ヒトラーによって「夜と霧」法令が発せられる。占領地における反ナチス政治犯やレジスタンスなどを収監し、その人物の情報を消し去ることで、批判や抗議を回避し、住民統治をすすめるための法令。少なくとも6639名が捕らえられ、340名は処刑され、多くは強制収容所へ送られたが、消息のわからない者も多い。 |
| 12月 8日 | 真珠湾攻撃。太平洋戦争開戦。連合艦隊の航空部隊が真珠湾に停泊中のアメリカ太平洋艦隊と、港湾施設、航空基地を攻撃。戦艦5隻を撃沈。 |
| 12月10日 | マレー沖海戦。日本海軍第二十二航空戦隊の一式陸上攻撃機などが、イギリス東洋艦隊の戦艦プリンス・オブ・ウェールズと、巡洋戦艦レパルスを撃沈する。 |
| 12月13日 | ボン岬沖海戦。アフリカ戦線への輸送を行うイタリア巡洋艦隊と、転進中のイギリス・オランダ海軍の駆逐艦隊の夜戦。イギリス側の勝利。 |
| 12月21日 | 日本とタイの間で日泰攻守同盟条約が締結される。 |
| 1942年(昭和17年) | |
| 1月20日 | ベルリンのヴァンゼーで、ナチス親衛隊幹部や東方占領地の行政官らが集まり、「ユダヤ人問題の最終的解決」を確認するヴァンゼー会議が開かれる。 |
| 1月25日 | タイが米英に宣戦布告。 |
| 2月 1日 | 毛沢東がマルクス主義思想を整えるための談話を発表。これに基づく「整風文献」が出版され、中国共産党内部で「整風運動」が起こる。複数の派閥からなっていた中国共産党の党内権力を、毛沢東が掌握するために行った運動で、党員同士の告発を使った党内粛清により多数の犠牲者を出すことになった。特に文化人、知識階級が犠牲になっている。 |
| 2月 8日 | ナチス政権の軍需大臣フリッツ・トートが飛行機事故で死亡。トート機関を設立し、アウトバーンやUボート・ブンカーの建設を担当したが、一方で戦争の早期終結を主張し、前日の7日にヒトラーと会談していた。会談翌日であるため、暗殺説や、将来を悲観して自爆による自殺をしたという説もある。 |
| 2月24日 | 日本海軍の潜水艦伊17が、カリフォルニア州サンタバーバラのエルウッド石油製油所を砲撃。 |
| 2月25日 | 「ロサンゼルスの戦い」。ロサンゼルス都市圏で謎の飛行物体が目撃され、日本軍機の襲来として砲撃を行う騒ぎになる。砲撃の破片などで市民3名が死亡、心臓麻痺などで3名が死亡する。日本側に記録がないことから、誤報か、何かを見間違えたかという説が有力。UFO説もささやかれている。 |
| 2月27日 | スラバヤ沖海戦。蘭領インドシナの制海権をめぐる日本軍と連合軍の海戦。オランダ海軍のドールマン少将が戦死。 |
| 2月 | マンハッタン計画に基づき、テネシー州オークリッジで、計画本部とウラン生成工場のための土地取得を開始。安い買収価格で2週間の猶予しか与えない強制移住が行われたため、住民やテネシー州知事の反発を買った。 |
| 3月 1日 | バタビア沖海戦。スラバヤ沖海戦に続く日本軍と連合軍の海戦。米重巡洋艦ヒューストンなど複数艦艇を撃沈。戦闘中、ヒューストンを狙った重巡洋艦最上の雷撃が、味方船団に命中。陸軍輸送船佐倉丸が沈没、同輸送船龍野丸、陸軍病院船蓬莱丸、揚陸艦である陸軍特殊船龍城丸(神洲丸)などが大破着底した。海軍は非公式に陸軍に謝罪し、これを受けて公式には敵の攻撃によるものとする工作がされている。 |
| 3月17日 | マレーの虎「ハリマオ」こと谷豊がシンガポールで病死。 |
| 3月27日 | 宮崎県高岡町で、鉄道省の省営バスが大淀川に転落。5人が死亡、28人が重軽傷を負う。 |
| 4月 2日 | 軽巡洋艦大淀が進水。艦種は軽巡洋艦だが、満載排水量が1万1千トンを超え、15.5cm砲を搭載するなど重巡クラスの軍艦で、水上機格納庫とカタパルトを持っていた。のちに司令部機能を追加される異色の艦。 |
| 4月18日 | ドーリットル隊B-25爆撃機16機が東京市、川崎市、横須賀市、名古屋市、四日市市、神戸市を爆撃。 |
| 4月26日 | 大倉財閥系列の満洲にある本渓湖炭鉱で粉塵爆発。坑夫1549人が死亡。日本関係の炭鉱で最悪の事故。 |
| 5月 8日 | 珊瑚海海戦。米海軍空母レキシントンが沈没、ヨークタウンが中破。日本海軍の祥鳳が沈没、翔鶴が大破。日本側の辛勝となるも、航空兵力の損失でポートモレスビー攻略が不可能になる。 |
| 5月26日 | 湧別機雷爆発事件。少し前に北海道紋別郡下湧別村の海岸2箇所に2つの機雷が漂着。1箇所にあつめて爆破処理する際に誘爆しないよう移動させていたところ爆発。爆破処理作業は広く伝わっており、各地から見学客が集まっている中で起きたため、106名が死亡する惨事となった。 |
| 5月31日 | 特殊潜航艇「甲標的」によるシドニー港攻撃。豪海軍の宿泊艦1隻が沈没。参加した甲標的も全て沈没。 |
| 5月 | アイザック・アシモフの小説『ファウンデーション』の第一話が、『アスタウンディング・サイエンスフィクション』誌に掲載される。 |
| 6月 6日 | セヴァストポリ要塞攻略戦で、ドイツ軍は80cm列車砲グスタフを投入。10日間で48発を発射した。この他巨大な60cmカール自走臼砲、第1次大戦で使われ唯一残っていた42cmガンマ臼砲なども投入している。 |
| 6月 7日 | ミッドウェー海戦終結。日本側は赤城、加賀、蒼龍、飛龍の4空母と重巡三隈を失い大敗を喫する。アメリカも空母ヨークタウンを失う。 |
| 6月11日 | 関門鉄道トンネルが開通し試運転が行われる。海の下を通るトンネルとしては世界で最初。 |
| 6月12日 | アンネ・フランクが、日記を書き始める。いわゆる『アンネの日記』。1944年8月1日まで。 |
| 6月28日 | ドイツ軍は資源地帯カフカース方面進出のブラウ作戦を発動し、その途上のスターリングラード攻略に乗り出す。 |
| 7月16日 | ドイツ親衛隊全国指導者ハインリヒ・ヒムラーが、ポンドの偽札を製造するベルンハルト作戦を認可。 |
| 7月18日 | メッサーシュミットMe262が、ジェットエンジンだけでの初飛行に成功。 |
| 7月19日 | ドイツ親衛隊全国指導者ハインリヒ・ヒムラーが、ポーランド各都市のゲットーに押し込められているユダヤ人を収容所へと強制移送することを命じる。 |
| 8月 7日 | 米軍がガダルカナル島の日本軍を攻撃。ガダルカナル島の戦いが始まる。 |
| 8月19日 | カナダ軍主体のジュビリー作戦が実施され、フランスのディエップに上陸するも、ドイツ軍に大敗を喫して失敗に終わる。 |
| 9月 9日 | 日本海軍潜水艦伊25搭載の零式小型水上偵察機によるアメリカ本土空襲。オレゴン州ブルッキングス郊外の森に、焼夷弾を投下。 |
| 9月29日 | 日本海軍潜水艦伊25搭載の零式小型水上偵察機によるアメリカ本土空襲。オレゴン州オーフォード郊外の森に、焼夷弾を投下。 |
| 10月 3日 | ナチス・ドイツがV2ロケット(A4)の打ち上げに成功する。史上最初の宇宙に出た飛行物体であり、成功した初の弾道ミサイル。 |
| 10月26日 | 南太平洋海戦(サンタ・クルーズ諸島海戦)。日米の空母部隊による海戦。米海軍の空母ホーネットが沈没、エンタープライズが中破。日本海軍の空母翔鶴と瑞鳳が中破。米軍の主力空母はほぼすべて損失か修理に追い込まれるが、日本側の航空兵の損害も大きく(ミッドウェー海戦よりも大きい)、ガダルカナルへの支援は困難になり、また海軍戦力の後退のきっかけとなった。 |
| 11月26日 | 映画『カサブランカ』公開。親独ヴィシー政権の植民地だったモロッコのカサブランカを舞台にしたラブロマンス。主演を務めたハンフリー・ボガートとイングリッド・バーグマンは本作でイメージを決定づけた。アカデミー賞受賞。 |
| 11月30日 | 横浜港に停泊していたドイツのタンカー・ウッカーマルクで火災が発生し、その後大爆発を起こす。付近に停泊していた仮装巡洋艦トール、客船ナンキン、軍徴用船第三雲海丸も巻き添えで沈没。ドイツ人将兵、中国人、日本人ら102名が死亡。 |
| 11月 | マンハッタン計画ディレクターのロバート・オッペンハイマーの主張を受けて、ニューメキシコ州ロスアラモスに研究施設が置かれることになる。オッペンハイマーは、アメリカの主だった科学者に参加を呼びかける。 |
| 12月31日 | 御前会議でガダルカナル島からの撤退が決定する。 |
| 12月31日 | 皇居に建設中だった爆撃に耐えられるよう設計された防空施設の皇族の居館「御文庫」が完成する。 |
| 1943年(昭和18年) | |
| 1月15日 | アメリカ陸軍省ビルとして世界最大のオフィスビル「ペンタゴン」が竣工。 |
| 1月31日 | スターリングラードのドイツ軍が降伏。 |
| 1月 | マンハッタン計画のプルトニウム生産工場建設のため、ワシントン州ハンフォードで土地収用が始まる。 |
| 2月 1日 | アメリカとイギリスが、ソ連の暗号解読を行なって情報を探るヴェノナ計画をスタートさせる。 |
| 2月 7日 | 日本軍がガダルカナル島から撤退する。死者2万を出し、うち1万5千人が病死や餓死。 |
| 2月13日 | 通天閣の解体が始まる。金属供出のためと、足元の映画館の火災で損傷したため。 |
| 2月22日 | 反ナチスの「白いバラ」運動メンバー、ハンス・ショルとその妹ゾフィー・ショルの兄妹が処刑される。 |
| 3月13日 | ドイツ軍のトレスコウ少将によるヒトラー搭乗機爆破未遂事件が起こる。 |
| 4月 1日 | 南樺太が法律上内地へと編入される。 |
| 4月 7日 | 独伊首脳会談で、ムッソリーニはソビエトと講和して対英米戦に集中すべきだと意見を述べるが受け入れられず。 |
| 4月 9日 | 金鉱業整備に関する方針要旨、いわゆる金鉱山整備令が出される。金本位制での貿易決済に必要な金の増産が進められてきたが、戦争で貿易が減ったこと、軍需に必要な鉱山に人員を振り分ける必要性から、2回の閣議決定を受けて、国内の金鉱山の操業は中止となった。 |
| 4月13日 | ドイツがソ連領のカティンの森でポーランド人が多数虐殺された事件を世界中に公表する(カティンの森事件)。その後ソ連によってナチスによる犯行とされたが、実際にはソ連の犯行だった。 |
| 4月14日 | スターリンの長男で、ドイツの捕虜となっていたヤーコフ・ジュガシヴィリがドイツブランデンブルク州オラニエンブルクのザクセンハウゼン強制収容所で死亡。捕虜交換に応じなかった父スターリンに絶望しての自殺、あるいは自殺目的で逃走を図り射殺されたとも言われる。 |
| 4月18日 | 海軍甲事件。「い号作戦」指揮のためラバウルに来ていた山本五十六連合艦隊司令長官が、ブーゲンビル・ショートランド方面へ前線視察することを暗号解読で知ったアメリカ軍が、山本殺害を企図して「ヴェンジェンス作戦」を計画。山本長官機をブーゲンビル島上空で待ち伏せし撃墜。山本五十六らは戦死した。宇垣纏参謀長の2番機も被弾し不時着水している。山本は銃撃されて機内で戦死したとされているが、遺体の状況から不時着時に重症を負い翌朝死亡したとする説もある。 |
| 4月19日 | ナチスドイツの親衛隊少将ユルゲン・シュトロープによって第二次ユダヤ人移送計画がはじまり、これに抵抗して、ワルシャワ・ゲットーでユダヤ人レジスタンスが武装蜂起。しかし鎮圧される。 |
| 5月17日 | イギリス空軍によるチャスタイズ作戦が実行される。ドイツのルール工業地帯にある複数のダムを反跳爆弾によって攻撃するもので、特別編成の第617飛行中隊によって実施される。メーネダムとエーデルダムの破壊に成功し、下流に洪水をもたらしたため、1249名と家畜6500頭が死亡、125の工場が停止に追い込まれた。一方飛行中隊も133名中53名が戦死。 |
| 5月21日 | ブーゲンビルで戦死した山本五十六の遺骨が東京に到着し、政府はその戦死をはじめて公表。あわせて元帥の称号が贈られる。一方、軍神扱いされるのを嫌がっていたことから、死後の山本神社創設の動きを海軍関係者が止めている。アメリカ側は、暗号を解読していることを日本側に気づかれないよう、作戦の成功にも関わらず、偶然遭遇した日本軍の攻撃機を撃墜したかのように発表している。 |
| 6月 5日 | 山本五十六の国葬が日比谷公園で行われる。皇族や華族ではない平民としては初めての国葬であり、国葬とすることに対し、昭和天皇から疑問が示されたとも言われる。 |
| 6月 8日 | 広島県呉の柱島泊地で戦艦陸奥が突如大爆発を起こし、船体が折れて沈没する。 |
| 7月 1日 | 東京都制が施行される。東京府と東京市が統合され、一元的な帝都行政となる。首長は任命制の東京都長官。市電は都電と呼ばれるようになる。 |
| 7月10日 | 連合軍、シチリアに侵攻を開始。ハスキー作戦。 |
| 7月19日 | 連合軍によるローマ空襲。 |
| 7月25日 | イタリアでファシスト政権の最高諮問機関「ファシズム大評議会」が開催され、ムッソリーニの統帥権の返上と首席宰相の退任要求が決議される。通称グランディ決議。午後ムッソリーニは、離宮ヴィッラ・サヴォイアに赴き、国王に謁見して仲裁を期待するが、ムッソリーニ排除を決めていた国王は会談で後継首席宰相にピエトロ・バドリオを指名しムッソリーニを解任逮捕。バドリオは国家ファシスト党の解党や大評議会の解散を決定。 |
| 7月28日 | イタリア国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世は、ピエトロ・バドリオに米英との休戦交渉を命じる。バドリオはドイツの介入を避けるため表向き継戦を伝えつつ、密かにスペインやポルトガル、スイスを介して米英と休戦交渉を開始。 |
| 9月 3日 | イタリアバドリオ政権と連合軍の間で秘密休戦協定が成立。しかしバドリオ政権は連合軍との協力体制には消極的だったため、アイゼンハワー司令官の怒りを買う結果に。 |
| 9月 8日 | 連合軍が突然、バドリオの了承なく、イタリアは休戦に応じイタリア軍は無条件降伏したと発表。イタリア本土に連合軍が侵攻を開始。ベイタウン作戦。バドリオは慌てて休戦を公表するも、これを受けてドイツ軍もローマへ向けて侵攻を開始(アラリック作戦)。国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世とバドリオらは国民も軍部も見捨てて南部プッリャ州ブリンディジへ逃走(この醜態は戦後イタリア王制が廃止される要因となった)。イタリア軍は大混乱状態に。 |
| 9月 9日 | 連合軍に投降するためマルタへ向けて出港したイタリア艦隊の戦艦3隻(ヴィットリオ・ヴェネト、ローマ、イタリア)、巡洋艦3隻、駆逐艦8隻に対し、ドイツ空軍が空襲。当時最新の誘導爆弾フリッツX(ルールシュタール/クラマーX-1)によって戦艦ローマは爆沈、戦艦イタリアが大破する。 |
| 9月 9日 | イタリアのファシスト政権に抵抗していたパルチザンなどがイタリア国民解放委員会を設立する。 |
| 9月10日 | ドイツ軍がローマを占領。 |
| 9月12日 | グラン・サッソ襲撃。失脚し逮捕されたイタリアのムッソリーニを救出するため、ナチスドイツ空軍と親衛隊が、グラン・サッソ山のホテルを急襲。ムッソリーニを連れ出すことに成功する。 |
| 9月15日 | ドイツ軍に救出されたムッソリーニが、ラステンブルクの総統大本営でヒトラーと会談。 |
| 9月18日 | ムッソリーニが、共和ファシスト党を結成。 |
| 9月23日 | ムッソリーニが、イタリア北部にイタリア社会共和国(RSI)を樹立。修正マルクス主義も取り入れた独自のファシズムを導入し、労働者と協調したコーポラティズム国家を目指す。当初サロに首都を置いたため、連合側からはサロ共和国と呼ばれる。同政権は最大でイタリア半島の半分を領土とした。 |
| 10月 2日 | 「在学徴集延期臨時特例」公布。これにより文科系大学生の徴兵猶予が廃止され、学徒出陣が始まる。 |
| 10月13日 | バドリオ政権がナチスドイツに宣戦布告。 |
| 10月14日 | ナチスドイツのソビボル絶滅収容所で収容者が大量脱走する事件が起こる。 |
| 10月19日 | アメリカ・ラトガース大学のセルマン・ワクスマン、アルバート・シャッツらによってストレプトマイシンが発見される。結核に効く抗生物質。なお抗生物質(antibiotics)という単語はワクスマンの造語。 |
| 10月21日 | 明治神宮外苑で、雨の中、出陣学徒壮行会が行われる。 |
| 10月26日 | 常磐線土浦駅列車衝突事故。18時48分、土浦駅構内で引上線へ入換中の貨物貨車が転轍操作のミスから上り線に進入。約3分後に上り貨物列車が到着してこれに衝突。貨車が転覆して今度は下り線に入り、その約3分後、下り線にやって来た旅客列車がこれに衝突して脱線転覆。うち1両がそばの桜川へ落下する。この多重事故で死者110名、重軽傷者107名を出す大惨事となった。この時衝突した貨物列車の機関車は、のち下山事件で下山定則国鉄総裁を轢いてしまう機関車。また旅客列車には幼い頃の坂本九が乗っており、危うく遭難しかけたと言われる。 |
| 11月 1日 | 鉄道省が運輸通信省に改変。 |
| 11月 5日 | 東京で大東亜会議が開催される。参加したのは、タイ王国、満洲帝国、中華民国(南京政府)、フィリピン、ビルマ、自由インド仮政府。インドネシアのスカルノらは参加を認められず。 |
| 11月22日 | カイロ会談。アメリカのルーズベルト、イギリスのチャーチル、中華民国の蒋介石が、対日戦争の継続と、戦勝後の日本の領土処理について話しあった会談。蒋介石が日本と講和することを恐れたルーズベルトが中国への領土返還などを条件に戦争継続をすすめるのが目的だったとも言われる。 |
| 12月26日 | 北岬沖海戦。ノルウェーのノールカップ(北岬)近海で、ソ連への輸送船団攻撃に向かったドイツ艦隊と、その情報を得たイギリス艦隊が数度に渡り交戦。ドイツ戦艦シャルンホルストが撃沈される。 |
| 1944年(昭和19年) | |
| 1月11日 | ムッソリーニが、ナチスドイツの圧力や党員らの決定を受け、ファシズム大評議会でムッソリーニ失脚に賛成票を投じたガレアッツォ・チャーノや、エミーリオ・デ・ボーノ、ジョヴァンニ・マリネッリらを処刑。チャーノはムッソリーニの娘婿であった。 |
| 1月18日 | レニングラード包囲戦が終結。ドイツ・フィンランド同盟軍は退却。市民も100万人前後が死亡した。 |
| 2月17日 | トラック島大空襲。 |
| 2月 | 劇団俳優座が創設される。 |
| 3月 | ナチス・ドイツのV2ロケット開発を担当していたフォン・ブラウンが、ゲシュタポに連行される。ミサイル兵器より宇宙旅行が可能なロケット開発を主張し続けたことが国家反逆罪に問われたとされる。V2ロケット開発の功績と、ヒトラーの仲裁でのちに釈放される。 |
| 3月12日 | 山田線列車転落事故。山田線第二小滝トンネル付近を走行中の貨物列車が雪か小雪崩によって視界不良に陥った直後、大規模な雪崩で崩壊していた鉄橋に気付かず突入してしまいそのまま転落。機関士が死亡。機関士が死亡する前、危険を知らせるよう機関助手に伝えたエピソードは後に映画化された。 |
| 3月13日 | ソ連のエースパイロット、レフ・シェスタコフが戦死。ドイツ軍の爆撃隊を攻撃しているさなかにドイツのエースパイロットであるハンス・ウルリッヒ・ルーデルと遭遇。空戦中にルーデル機のエンジンの余波を受けて操縦不能に陥ったか、ルーデル機の銃撃手ガーデルマンに撃墜されたものと見られる。 |
| 3月19日 | ドイツ、マルガレーテ作戦を実施し、ハンガリーを占領。 |
| 3月30日 | パラオ大空襲。 |
| 3月31日 | 海軍乙事件。パラオ空襲を受け、連合艦隊司令長官だった古賀峯一海軍大将がフィリピンへ向かう途中に低気圧に遭遇して行方不明になり、福留繁参謀の乗る機体が不時着水。乗員らがゲリラに捕えられ、機密書類が奪われる。 |
| 4月14日 | インドのボンベイ(現ムンバイ)のビクトリア埠頭で、13時頃に荷降ろし中だったリバティ船(戦時輸送船)のフォートスティキン号で火災が発生。船員や消防艇などが消火に当たるも、積んでいた約1400tの爆弾などの爆発物、可燃物、戦闘機や各種軍需品、綿俵、石油などに引火し、16時に大爆発を起こす。爆風などで周辺の船舶、市街地を破壊し、30分後に更に大きな爆発を起こす。火の付いた積み荷が遠くまで飛散し、火災も拡大。二度の爆発で800人~1300人が死亡。軍艦3隻を含む13隻が破壊され(大型客船シャンティイは大破、同じく大型客船で揚陸艦となっていたエルハインドは沈没)、5万tの食料も喪失した。 |
| 6月 6日 | 連合軍、ノルマンディー上陸作戦(オーバーロード作戦)開始。海岸に防御陣地を構築していたドイツ軍の攻撃で膨大な死傷者を出しながらもノルマンディー地方の海岸に拠点を構築。 |
| 6月 9日 | 連合軍がローマに進駐。バドリオもローマに入るが、イタリアでは連合軍に対する抵抗も強く、その連合側に降伏しナチスドイツの侵攻にも対応しなかったバドリオに対する反発が大きく、バドリオはイヴァノエ・ボノーミ元首相に首相の座を譲って引退。 |
| 6月17日 | アイスランドがデンマークから独立し、アイスランド共和国となる。 |
| 6月22日 | 明石駅構内で線路の置石が原因と見られる急行列車脱線転覆事故が起こり、32名が死亡、36名が重軽傷を負う。 |
| 6月23日 | 有珠山東麓の畑作地で噴火が始まる。一帯が大きく隆起した上に、溶岩ドームが形成されていく。のちの昭和新山。 |
| 6月26日 | ノルマンディー地方の港湾都市シェルブールのドイツ軍降伏。 |
| 6月28日 | ボルネオで、日本軍による軍法会議により武装蜂起などの陰謀に関わったとして現地民47名が処刑される。いわゆるポンティアナック事件。実際の犠牲者はもっと多数に上ると言われる。 |
| 7月 3日 | インパール作戦が中止となる。ずさんな補給計画によって、動員された9万2千人の兵士のうち、帰還できたのは1万2千人のみ。 |
| 7月17日 | ポートシカゴ爆発事件。アメリカ・カリフォルニア州のポートシカゴのコンコード海軍兵器廠兵器庫で輸送船E.A.ブライアン号に弾薬を積みこむ作業中、大爆発が起こり、兵士・市民ら320名が死亡、390名が負傷。犠牲者の多くが黒人下士官らで、低い待遇を受けており、事故後、黒人兵らは任務を拒否する「ポートシカゴの反逆」事件を起こすことになる。アメリカ軍内部での差別待遇が問題になるきっかけとなった。 |
| 7月20日 | ドイツ軍クラウス・フォン・シュタウフェンベルク大佐によるヒトラー爆殺未遂事件が起こる。東プロイセンの総統大本営「狼の巣」でヒトラーも出席した会議中に爆弾を起爆させることに成功するが、偶然の条件が重なってヒトラーは軽症で済み、その後のクーデター計画も失敗に終わった。 |
| 7月21日 | 未明にヒトラー暗殺計画とクーデター計画に関わったクラウス・フォン・シュタウフェンベルク大佐、フリードリヒ・オルブリヒト大将、アルブレヒト・メルツ・フォン・クイルンハイム大佐、ヴェルナー・フォン・ヘフテン中尉の4人が処刑され、ルートヴィヒ・ベック元参謀総長が自殺。計画を知っていたとされ、独断で処刑を実行に移したフリードリヒ・フロム上級大将もヒトラーの怒りを買い後に処刑される。独断で処刑したのは自己保身のためか、関係者が拷問を受けたりしないよう配慮したためかは不明。 |
| 7月21日 | グアム島の戦いが始まる。 |
| 7月22日 | 連合国に属する44カ国の代表が、アメリカのニューハンプシャー州にあるブレトンウッズに集まり、戦後の国際通貨体制について話し合い、ブレトン・ウッズ協定を締結。 |
| 8月 4日 | アンネ・フランクの一家及び共に隠れていた人々がゲシュタポに連行される。 |
| 8月 4日 | フィンランドのリスト・リュティ大統領が、軍事協定を結んでいたドイツが独ソ戦で敗北したことと、ソ連からの和平要請を受け辞任。ソ連とドイツに挟まれ、外交を駆使してフィンランドを維持し続けた人物。リュティは後継者のカール・グスタフ・エミール・マンネルヘイムに親独政策は自分の個人的方針だったことにして連合国との和睦を進めさせる。 |
| 8月11日 | 日本軍守備隊が壊滅し、グアム島の戦いが終結。残存日本兵がゲリラ戦に入る。 |
| 8月20日 | 沖縄からの児童疎開船「暁空丸」「和浦丸」「対馬丸」が鹿児島へ向けて出港。 |
| 8月22日 | 沖縄からの児童疎開船「対馬丸」が悪石島付近で米潜水艦ボーフィンの雷撃を受け爆沈。疎開児童708名を含む1484名が死亡。 |
| 8月23日 | ルーマニア国王ミハイ1世が宮廷クーデターを起こし、親独派の国家指導者イオン・アントネスクを逮捕。枢軸陣営からの離脱を図る。ただちにソ連軍と休戦協定を結ぶ。 |
| 8月25日 | パリ解放。フランスのパリ市からドイツ軍が撤退。自由フランス軍やレジスタンス系フランス国内軍が入城。ドイツ軍司令官(パリ軍事総督)のコルティッツ大将はヒトラーの命令に従わず、焦土作戦を行わずに降伏したが、その意図はパリを守るため、保身のためと諸説ある。市民らによって親ナチ派の市民殺害や、ドイツ軍人と交際していた女性を暴行するなどの事件も発生。 |
| 8月25日 | ルーマニアがドイツに宣戦布告。 |
| 8月26日 | 枢軸国のブルガリア王国が中立を宣言。 |
| 9月 3日 | 高野山電気鉄道紀伊細川駅-上古沢駅間の勾配で、下り2両編成電車が火災を起こして停止。点検中にブレーキが外れて逆走し、カーブで脱線転覆。71名が死亡し、138名が重軽傷を負う大惨事となる。 |
| 9月 5日 | ソ連軍がブルガリアに侵攻を開始。 |
| 9月 7日 | ハンガリーの最高権力者である摂政ホルティ・ミクローシュとラカトシュ首相が、ソ連軍が迫っていることを理由にドイツに増援を要請。ドイツは増派を行うが、ホルティは連合軍との休戦を決意。 |
| 9月20日 | ハンガリーの摂政ホルティ・ミクローシュはイギリス軍に休戦工作を始める。 |
| 9月24日 | コロン湾空襲で水上機母艦秋津洲や特設給油船興川丸などが沈没、給糧艦伊良湖が大破着底。もと水上機母艦で給油艦となっていた神威は爆弾が命中するも沈没は免れ退避。 |
| 10月 1日 | ハンガリーの摂政ホルティ・ミクローシュ、ソ連に使者を送り、休戦交渉を開始。 |
| 10月10日 | 沖縄大空襲(十・十空襲)。沖縄本島、慶良間諸島、宮古八重山諸島、奄美群島に、アメリカ海軍第38任務部隊に属する複数の空母から艦載機が多数襲来。潜水母艦迅鯨をはじめ、多数の軍艦・商船が沈没した他、那覇市街地の大部分が焼失。鉄道も大損害を受ける。少なくとも市民330名が死亡。防戦が遅れたのは、この日予定されていた陸軍第32軍の演習と誤解したことや、レーダーによる探知報告を誤報と判断したことなどがある。これ以降、本土への疎開が急がれることとなった。 |
| 10月12日 | ヒトラー、ハンガリーの休戦への動きを抑えるため、ツェレウスキー親衛隊大将をハンガリーへ派遣。また同時期にオットー・スコルツェニー指揮の部隊にブダペスト襲撃、およびホルティの息子を誘拐するミッキーマウス作戦を指示。 |
| 10月15日 | ハンガリーの摂政ホルティ・ミクローシュ、ソ連との休戦を決定。放送を行う。 |
| 10月15日 | オットー・スコルツェニー、ブダペストでハンガリーの摂政ホルティ・ミクローシュの次男ミクローシュ二世を拉致。摂政ミクローシュを脅迫。ミクローシュ、ドイツの要求を拒絶するも、最終的に親独派矢十字党のサーラシ・フェレンツを首相に指名することを決める。サーラシ、ドイツ側と交渉してミクローシュの安全を約束させ、ミクローシュはドイツへ移送される。 |
| 10月20日 | クリーブランド・東オハイオガス爆発事故。東オハイオガス会社の液化天然ガス貯蔵タンクの一つからガス漏れが起き、漏れたガスが下水に流れ込んで爆発。その約30分後にガスタンクも爆発し、市民130人余りが死亡。 |
| 10月23日 | パラワン水道海戦。米潜水艦の雷撃により、重巡愛宕、重巡摩耶が沈没。重巡高雄、重巡青葉が大破する。 |
| 10月23日 | アメリカ軍のルソン島上陸を警戒して、民間人や捕虜などを台湾へ輸送していたマタ30船団が、米海軍の7隻の潜水艦の襲撃を受け、大型輸送船など12隻のうち9隻を失う。輸送中だった捕虜の殆ども死亡。なお船団護衛の駆逐艦の反撃を受けて、米側も潜水艦1隻が撃沈されたと見られる。 |
| 10月24日 | 栗田艦隊がシブヤン海で米軍と遭遇し、空襲を受ける。戦艦武蔵が沈没。同日、日本軍航空部隊の爆撃で米空母プリンストンも大爆発を起こし、放棄の上、味方の雷撃で自沈。救援中の駆逐艦数隻も爆発に巻き込まれて大破。 |
| 10月25日 | スリガオ海峡で西村艦隊が米軍と遭遇。猛烈な雷撃を受けた戦艦扶桑は船体が折れて沈没。続いて戦艦山城も猛烈な砲撃で転覆沈没。重巡最上も大破。生存者が僅かという全滅状態になる。小沢艦隊も空襲を受け、空母千歳、瑞鶴、千代田、瑞鳳が沈没し、空母部隊は全滅。栗田艦隊がレイテ湾へ向かい、サマール島沖で米護衛空母群と遭遇。護衛空母ガンビアベイや駆逐艦などを砲撃で撃沈するが、重巡洋艦部隊が空爆を受け、鳥海、筑摩、熊野、鈴谷が大破。栗田艦隊は、レイテ湾突入を中止して反転。鳥海と筑摩を失い退却。この日、特攻機が空母セント・ローに激突し、セント・ローは誘爆沈没。空母カリニンベイが大破、キトカンベイ、ホワイト・プレインズも小破する。一連の海戦で日本海軍は壊滅的な損害を被る。 |
| 11月 7日 | ゾルゲ事件で、リヒャルト・ゾルゲと尾崎秀実が死刑に処せられる。 |
| 11月10日 | 汪兆銘が名古屋で客死。かつて受けた狙撃の後遺症による悪化が原因。 |
| 11月10日 | ニューギニア島近くのアドミラルティ諸島マヌス島ゼーアドラー湾に停泊していた米軍弾薬輸送艦マウントフッドが大爆発を起こす。近くにいた工作艦ミンダナオが大破した他、護衛空母(ペトロフベイ・サギノーベイ)、駆逐艦、給油艦、輸送艦などが巻き込まれ損傷。上陸用舟艇など22隻が沈没。このときマウントフッドに乗艦していた296人全員と、ミンダナオの乗員82人が死亡。爆発の原因は不明。 |
| 11月15日 | 人員輸送と石油受け取りのためフィリピンへ向かう途中のヒ81船団に属していた陸軍特殊船あきつ丸が雷撃による弾薬庫の誘爆で沈没。フィリピンへ向かっていた士官兵士ら2000名以上が死亡。あきつ丸は全通甲板をもつドック型揚陸艦。 |
| 11月17日 | フィリピンへ向かう途中のヒ81船団に属していた陸軍特殊船摩耶山丸と、空母神鷹も雷撃によって撃沈される。摩耶山丸に乗船していた士官兵士ら3000人以上が戦死し、あきつ丸の戦死者も含めて、同船団でフィリピンへ向かっていた第23師団は壊滅的被害を受けた。神鷹も乗員1160人中1100人が戦死している。 |
| 11月27日 | イギリスのスタッフォードシャーにあるフォールド英空軍基地で、4000tの爆弾や砲弾を格納していた地下弾薬庫が爆発。長径279mのクレーターができ、衝撃ですぐ南にあるハンベリー村の貯水池や複数の農場が破壊され、流れ出た大量の貯水池の水でセメント工場なども破壊された。死者は70人~90人で、英軍兵、軍属、地元の住民、それに弾薬庫で働いていたイタリア兵捕虜。また農場の牛200頭が死んでいる。原因は捕虜が従事していた爆弾の解体作業で、金具を使ったことによる火花の引火と推測される。 |
| 11月28日 | 当時世界最大の空母である「信濃」が、呉へ回航するため、護衛の駆逐艦3隻を引き連れて横須賀を出港。呉へ回航することにした理由は、横須賀空襲を避けるためと、横須賀工廠の技術力の低下だったとされる。当初は昼間沿岸を航行する案もあったが、結局夜間に回航することとなった。 |
| 11月29日 | 空母「信濃」が、遠州灘でアメリカ軍潜水艦「アーチャーフィッシュ」に発見される。この時点でアメリカは「信濃」の存在を知らなかったが、新型の大型空母とみて攻撃。信濃側も気づき、回避行動を繰り返すも4発の魚雷攻撃を受ける。「アーチャーフィッシュ」からの追撃は逃れたものの、駆逐艦による曳航に失敗し、紀伊半島の南東沖合で転覆沈没。前倒しで突貫建造されたために内部はまだ未完成で水密区画も防水試験も完全ではなく、乗員の練度も低かったため、ダメージコントロールがうまくいかなかったことが大きな要因。 |
| 12月 7日 | 昭和東南海地震。マグニチュードは7.9。最大で9mの津波も発生し、死者・行方不明者数は1223名。戦時中のことであるため、国民の士気への影響や英米などへの情報漏れを懸念した政府・軍部により情報が統制された。 |
| 12月 7日 | 国際民間航空条約(シカゴ条約)署名。 |
| 12月11日 | 沖縄県営鉄道糸満線で兵員と弾薬、及び通学途中の女子生徒らを乗せた輸送列車が南風原村付近で突如爆発。約220人が死亡する大惨事となる。 |
| 12月10日 | レイテ湾に停泊して弾薬と石油の積荷を降ろしていた米海軍リバティ船の輸送艦ウィリアム・S・ラッドに神風特別攻撃隊の戦闘機が衝突、内部で爆弾が起爆し、同艦は火災を起こした後、爆沈。 |
| 12月16日 | バルジの戦いが始まる。ヒトラー最後の賭とも呼ばれるアントウェルペン(アントワープ)攻略作戦。アントウェルペンは連合軍の補給点で、ヒトラーはここを占領して物資を補給し、米英とは講和を図り、ソ連と決戦するつもりだったとも言われるが、作戦のために残っている兵力と兵器・物資を総動員したため、あとのない作戦でもあった。一方、連合軍もドイツ軍はすでに消耗しており、攻勢に出るとは考えておらず、パルチザンや捕虜から得た情報も無視した。戦場となったアルデンヌ地方には新兵や後送する負傷兵などが集められており、悪天候の中で行われた初戦のドイツ軍の奇襲に惨敗する。 |
| 12月17日 | マルメディ事件。バルジの戦いのさなかに、ドイツ軍が捕虜にした連合軍兵士を虐殺。戦場で完全な武装解除がされない状態だった捕虜が逃走する騒ぎになり捕虜への銃撃へと発展したとみられる。この直前にはアメリカ軍の爆撃で民間人に多数の犠牲者も出ている。犠牲者は72人とも84人ともいわれるが、捕虜の半数ほどは逃走に成功している。 |
| 12月18日 | ヒトラーの予想より早く、アイゼンハワーはバルジの戦いに援軍の増派を決定。最初の部隊が到着する。これによりドイツ軍の早期攻略の思惑は外れることになった。 |
| 12月19日 | 空母雲龍が第二水雷戦隊とともに特攻兵器桜花と陸軍滑空歩兵第一連隊を輸送して呉からマニラに向かう途中、アメリカ軍の潜水艦レッドフィッシュの雷撃を受け、艦内の桜花に誘爆し沈没。乗員の大半である1241名が戦死。また乗艦していた陸軍滑空歩兵第一連隊もほぼ全滅した。 |
| 12月21日 | 輸送任務中の給糧艦「間宮」が海南島東方沖合の南シナ海で二度の雷撃を受けて沈没。間宮は排水量1万5千トンもある大型の食料輸送艦で、冷凍保存により1万8千人3週間分の生鮮食料を輸送できた他、艦内でも食品製造を行っていた。各種和洋スイーツも製造しており、特に羊羹は間宮羊羹として海軍の将兵の間では人気だったという。他に病院船、無線監査艦としての機能もある多機能特務艦だった。 |
| 12月23日 | バルジの戦いで、天候が回復したのを受けて、連合軍が空爆を再開。連合軍側の反撃が始まる。 |
| 12月28日 | レイテ湾にいた米軍リバティ船の輸送艦ジョン・バークに神風特別攻撃隊の99式艦上爆撃機(もしくはゼロ戦)が突入、ジョン・バークは大爆発を起こし沈没。後続の陸軍大型貨物補給船(FS)も巻きこまれ沈没。ジョン・バークの乗員40人と武装警備兵28人全員は即死だったと見られる。 |
| 12月30日 | 日本海軍の「潜水空母」伊号第四〇〇潜水艦が竣工。 |
| 12月 | 有珠山東麓の噴火地で、粘性の高い溶岩ドームが盛り上がりはじめる。 |
| スターリンの粛清に巻き込まれシベリア送りとなったロケット研究者コロリョフが、関係者の尽力で釈放される。まもなく名誉回復を受け、ミサイル開発を担当することになる。 | |
| 1945年(昭和20年) | |
| 1月 1日 | ドイツがバルジの戦いの一環として急遽ボーデンプラッテ作戦を実施。空軍戦力によって連合軍の航空兵力に打撃を与えるものであったが、大きな被害を出し、事実上空軍兵力を失う結果となる。 |
| 1月 9日 | 米軍がルソン島に上陸。 |
| 1月13日 | 三河地震。三河湾を震源とし、愛知県、三重県などで大きな揺れを観測。昭和東南海地震の余震、あるいは誘発されたものという説もある。少なくとも死者2306人、1100人以上が行方不明。戦時下で被害の全貌ははっきりしない。 |
| 1月13日 | バルジの戦いで、ドイツ軍が撤退を開始。 |
| 1月15日 | 海軍が特設給油船として運用していたタンカー「みりい丸」が台湾左営港で空襲のため火災を起こし喪失。米軍潜水艦がウルフパック戦術を展開する中で、日本本土と南方を何度も往復に成功し、複数回攻撃を受け損傷しながらも生き延びたタンカーだった。 |
| 1月23日 | ドイツ軍は「ラインの守り作戦」を中止し、バルジの戦いは終結。初戦の油断から連合軍にも大きな被害を出すが、結果的にドイツ軍の惨敗に終わり、ドイツの継戦能力は事実上失われる結果となった。 |
| 1月23日 | ドイツ海軍総司令官カール・デーニッツが、ソ連軍の包囲下で孤立している東プロイセンから住民や兵士を船舶で安全地域まで輸送する「ハンニバル作戦」を指示。終戦までに民間人80万人以上、兵士35万人が脱出に成功した。 |
| 1月24日 | 駆逐艦時雨がタンカーさらわく丸の護衛中に、マレー半島の沖合で潜水艦の雷撃を受けて沈没。数多くの激戦をくぐり抜けてきたことから、同様の駆逐艦雪風と『呉の雪風、佐世保の時雨』と称された。 |
| 1月27日 | アウシュヴィッツ強制収容所が解放される。 |
| 1月30日 | ヴィルヘルム・グストロフ事件。ソ連の潜水艦S-13が、ポメラニア沖のバルト海でドイツの避難民船ヴィルヘルム・グストロフ号を撃沈。海難史上最悪の9343名が死亡する。大勢の難民を緊急輸送していたため、正確な数はわかっておらず、死者数は諸説あるが、何れにせよ史上最悪とされる。 |
| 2月 4日 | ヤルタ会談開催。ソ連のヤルタで、米大統領ルーズベルト、英首相チャーチル、ソ連共産党書記長スターリンが、ソ連の対日参戦を話し合い、ヤルタ協定を結ぶ。 |
| 2月 9日 | ヴィルヘルム・グストロフ号を沈めたソ連軍潜水艦S-13が、ドイツ軍民輸送船シュトイベンを撃沈。乗船していたのは負傷兵、民間避難民、医療関係者で、3000~4000人が死亡したと見られる。2隻の大型ドイツ船を沈めたS-13の艦長アレクサンドル・マリネスコは、難民船を沈めたという非難に加え、素行が悪かったこともありあまり評価されず、軍を批判して解任された。 |
| 2月13日 | 英米軍によるドレスデン無差別爆撃。市民の死者は2万5千人から15万人と言われる。 |
| 2月14日 | 近衛文麿が、昭和天皇に対し、英米との講和を訴える上奏を行なう。いわゆる近衛上奏文。もともとは海軍の井上成美、米内光政らが始めた終戦工作が軍関係者や政治家、皇族らの間へと拡がった。 |
| 2月19日 | 硫黄島の戦いがはじまる。 |
| 2月23日 | 米軍海兵隊員5人と海軍兵士1人の6人が硫黄島の摺鉢山頂上に星条旗を掲げる。ジョー・ローゼンタール撮影のこの時の写真は米軍史で最も有名でピューリッツァー賞を受賞したほか、アーリントン墓地にこれをモデルにした巨大な像が作られた。実際には1回目に掲揚した旗が小さくて海岸で交戦中の友軍に見えなかったため、すぐに別の旗を用意して立て直されたのが一般に有名な「硫黄島の星条旗」。このために「ヤラセ疑惑」が浮上した(一部始終の映像もあるため「ヤラセ掲揚」ではない)。6人のうち3人がまもなく戦死し、写真を見たルーズベルト大統領が戦時国債の宣伝に使えるとして残り3人を米本土に呼び戻すが、6人の正体調査で人違いが発生、軍がそれを隠蔽したため、帰国した3人(うち2人は現場にはいたが写真の人物ではない)ものちのち苦悩の人生を送ることになったと言われる。 |
| 3月 1日 | 鹿児島2区選挙無効事件。1942年の第21回衆議院議員総選挙(いわゆる翼賛選挙)は政府の選挙妨害があったとして、鹿児島2区の選挙結果は無効であるという落選した候補者からの訴えに対し、大審院が選挙無効と判決。翼賛選挙は帝国憲法の理念に反すると国を批判する。挙国一致の戦時社会としてはかなり異例の判決。 |
| 3月 7日 | レマーゲンの戦い。アメリカ軍が、ライン川沿いの各都市を攻略中、レマーゲンのルーデンドルフ橋がまだ無事なのを発見。橋を破壊しようとするドイツ軍と、それより先に通行を目指すアメリカ軍が衝突。ドイツは橋の一部を破壊しただけにとどまり、アメリカ軍は対岸に橋頭堡を築くことに成功。ヒトラーはこの報に激怒したと言われ、破壊に失敗したと言う理由で士官4人が処刑され、4人の将軍が懲戒されている。 |
| 3月 8日 | レマーゲンの戦い。ドイツ軍はルーデンドルフ橋の破壊作戦を継続。Ar234ブリッツジェット爆撃機やJu87シュトゥーカ急降下爆撃機などを投入して爆撃するも失敗。砲兵部隊による砲撃を開始。大型のカール自走臼砲も投入。 |
| 3月10日 | 東京大空襲。公式には死者8万3793人(実際は10万人以上とも)、負傷者4万918人、被災者100万8005人、被災家屋26万8358戸。 |
| 3月12日 | ヒトラー暗殺計画を知っていたとされ、爆殺未遂事件を起こしたシュタウフェンベルク大佐らを独断で処刑したフリードリヒ・フロム上級大将が処刑される。 |
| 3月13日 | フランス領インドシナ解体に伴い、カンボジアが独立宣言。 |
| 3月15日 | ドイツ軍によるブダペスト奪還作戦が失敗に終わる。 |
| 3月17日 | ドイツ軍は、引き続きレマーゲンのルーデンドルフ橋破壊に固執し、V2ロケットを投入。11発を発射。国内へ向けて発射された唯一の例。1発を除いて大きく外れ、ケルンなどに着弾し多数の死傷者を出す。1発はすぐ近くに着弾するも破壊に至らず。つづけて、海軍特殊部隊を投入してルーデンドルフ橋破壊工作を進めている中、ルーデンドルフ橋は崩壊。一連の破壊工作による損傷と、砲爆撃による振動などで崩れたと見られる。橋の上にいた約200人が巻き込まれ、28人が死亡・行方不明、93人が負傷した。米軍はすでに仮設の浮橋を完成させており、作戦への影響は殆どなかった。 |
| 3月19日 | ヒトラーが国内焦土作戦を命じるが、アルベルト・シュペーアらの反対で実行されず。 |
| 3月21日 | 日本の戦時標準タンカー最後の1隻となっていたさらわく丸がヒ88J船団で18日にシンガポールを出港後、シンガポール海峡で触雷して擱座。積荷を搬出するも横転沈没。同船団もその後29日までに全船喪失し全滅した。 |
| 3月26日 | 硫黄島の戦いがほぼ終結。 |
| 3月 | このころ、アンネ・フランクが、収容されていたベルゲン・ベルゼン強制収容所でチフスにより15歳で亡くなる。姉のマルゴット・フランクもほぼ同じ頃に同収容所で腸チフスにより亡くなる。 |
| 3月 | 日本軍が独立を支援していたビルマのアウンサンらがイギリス側に付き、対日武装蜂起。 |
| 3月26日 | 米軍が慶良間諸島に上陸。沖縄戦が始まる。 |
| 4月 1日 | 米軍が沖縄本島読谷海岸に上陸を開始。 |
| 4月 1日 | 阿波丸事件。捕虜米兵のための物資輸送船「阿波丸」がシンガポールから内地に戻る際、米潜水艦クイーンフィッシュに撃沈され、乗員・乗客2130名の内、2129名が死亡する。 |
| 4月 5日 | 天一号作戦で沖縄海上特別攻撃作戦が発令される。 |
| 4月 5日 | 米海軍による香港空襲で給油艦神威が大破。その後浸水して着底。放棄される。 |
| 4月 7日 | 天一号作戦で沖縄へ向かう途中の戦艦大和、軽巡洋艦矢矧、防空駆逐艦の冬月と涼月、駆逐艦の磯風、浜風、雪風、朝霜、初霜、霞が、坊ノ岬沖で300機を超える米軍機の攻撃を受け、大和、矢矧、磯風、浜風、霞、朝霜が撃沈・自沈する。 |
| 4月 9日 | 元ドイツ国防軍情報部部長だったヴィルヘルム・フランツ・カナリス海軍大将が、ヒトラー暗殺未遂計画に関与していたとして、ディートリヒ・ボンヘッファーやハンス・フォン・ドホナーニ、ハンス・パウル・オスターなど同計画に関わった人々とともに処刑される。カナリスはユダヤ人の国外脱出に手を貸したり、ヒトラー暗殺計画にかかわる一方で、ヒトラー政権の対外侵略に関して情報工作にも携わっており、その評価は分かれる。 |
| 4月16日 | ソ連軍潜水艦L-3がドイツ避難民輸送船ゴヤを雷撃。2発命中しゴヤは轟沈。乗船していた6000人以上は逃げるまもなく死亡(正確な乗員数は不明)。生存者は182名のみと言われる。 |
| 4月20日 | ベルリンの戦いが始まる。 |
| 4月23日 | ドイツ国家元帥ヘルマン・ゲーリングが連合軍との交渉をヒトラーに求め、ゲーリングと対立していたボルマンの示唆を受けたヒトラーの怒りを買い、親衛隊に監禁される。 |
| 4月23日 | 鳥取県西伯郡境町の岸壁に停泊していた玉栄丸の積み荷の爆薬が爆発。火薬倉庫が誘爆し、市街地大火となる。431戸が焼失し115名死亡、309名が重軽傷を負う。 |
| 4月25日 | ドイツ海軍唯一の空母グラーフ・ツェッペリンが、ソ連軍の接近を受けて自沈。 |
| 4月25日 | ムッソリーニとイタリア国民解放委員会との交渉が決裂。ムッソリーニはミラノを離れ、政権は事実上崩壊。 |
| 4月28日 | コモ湖付近でムッソリーニがクラレッタ(クララ)・ペタッチとともに共産党系パルチザンの「イタリア北部決起委員会」のメンバーに捕らえられ、ヴァレリオ大佐なる人物によってこの日銃殺。同行していた他の人も無裁判で処刑されている。 |
| 4月28日 | ナチス親衛隊指導者ヒムラーが、連合国と和平交渉をしているという情報がBBCラジオ放送から流れ、ヒトラーが激怒したと言われる。 |
| 4月29日 | ムッソリーニとクララの2人の遺体はミラノのロレート広場でさらされた後、ガソリンスタンドの建物から他の3人とともに逆さに吊るされる。無裁判での処刑やクララなど民間人を殺したことなどは後に問題となった他、パルチザンや群衆が遺体を痛めつけたことも批判された。そのため、パルチザンと関係のあったボノーミ首相は無関係を主張している。 |
| 4月29日 | アドルフ・ヒトラーは、後任として大統領職・全軍司令官にカール・デーニッツ元帥、首相にヨーゼフ・ゲッベルス、外相にザイス=インクヴァルト、ナチ党担当にマルティン・ボルマンを指名し、日陰の存在だった愛人エヴァ・ブラウンと結婚式を挙げる。 |
| 4月29日 | アメリカ陸軍によってダッハウ強制収容所が解放される。同収容所はナチス最古の強制収容所で、4万人以上が死亡したが、絶滅収容所ではないため、他に比べると犠牲者数は少ない。それでも解放時に数千もの遺体が発見されている(劣悪な環境による病死が非常に多い)。それを知った米兵によって、降伏した親衛隊員や収容所の所員が殺害される事件も起きる(解放された収容者による殺害もあったとされる)。また米軍は周辺の女性や子どもを含む住民に遺体処理を強制した。 |
| 4月30日 | アドルフ・ヒトラーとエヴァ・ブラウンが自殺。遺体は焼却。 |
| 4月30日 | スウェーデンによるドイツの強制収容所からの収容者移送作戦「白バス」計画で、女性収容者のみの輸送船マグダレーナとリリー・マティエッセンの2隻がリューベックを出発しスウェーデンに向かう。 |
| 5月 1日 | ドイツ宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルスも妻子とともに自殺。 |
| 5月 2日 | ベルリン市街をソ連軍が占領し、ベルリンの戦いは終結。 |
| 5月 3日 | スウェーデンによる収容者移送作戦「白バス」計画で捕虜輸送のための客船カップ・アルコナ、客船ティールベク、病院船ドイッチュラントの3隻が、リューベック湾でイギリス空軍機の爆撃を受け沈没。3隻の収容者(ドイツ軍の捕虜となりノイエンガンメ収容所にいたロシア人やポーランド人など)4000人以上が死亡したと見られる。 |
| 5月 4日 | 沖縄本島中南部で日本軍が反転攻勢を仕掛けるも失敗に終わる。 |
| 5月 4日 | ソ連軍兵士がベルリンの国会議事堂(ライヒスターク)に赤旗を掲げて従軍写真家エフゲニー・ハルデイが写真を撮る。いわゆる「ライヒスタークの赤旗」。今でもプロパガンダ写真として使われるが、実際には4月30日の夜に1回掲げられたものを、宣伝のためにやり直された(いわゆるヤラセ写真)。また実際に掲げた人と別人物が宣伝に使われるなどし、1995年になるまで真実は明らかにならなかった。 |
| 5月 5日 | 風船爆弾で初めての犠牲者が出る。オレゴン州で6人が死亡。 |
| 5月 7日 | カール・デーニッツを首班とするドイツ・フレンスブルク政府が、連合国に対し無条件降伏。 |
| 5月 8日 | 原爆の予備実験である108t爆発実験がニューメキシコ州アラモゴルドで行われる。通常爆薬を使用し、いわゆる核実験ではない。 |
| 5月 9日 | ドイツの降伏文書調印がベルリンで行われる。 |
| 5月14日 | 名古屋大空襲。死者338人。21905戸が被災し、名古屋城の天守や本丸御殿などほとんどの建造物が焼失。周辺の春日井市、瀬戸市、守山町、宇治山田市、多治見市、各務原市でも名古屋空襲に参加した米軍機によると見られる空襲があった。 |
| 5月22日 | イギリスのチャーチル首相指示の下、イギリス軍が「アンシンカブル作戦」を立案。英米連合軍が降伏したばかりのドイツ軍を加えて、侵攻中のソ連軍を攻撃する作戦。イギリスにとってすでにソ連は仮想敵国に想定されていた。 |
| 5月25日 | この日の東京大空襲により「明石原人」の骨が失われる。 |
| 5月27日 | 沖縄、首里への砲爆撃によって、首里城とその周辺の市街地が灰燼に帰す。第32軍は南部へと後退し、首里城地下の地下壕に残された負傷兵らは自決。進駐した米軍が財宝などを略奪する。 |
| 5月29日 | オランダの画家で贋作者のハン・ファン・メーヘレンが、ナチスドイツにフェルメールの絵画などオランダの文化財を売ったとして逮捕される(実際に売ったのは画商)。メーヘレンは当初黙秘していたが、マスコミなどに騒がれたため、ゲーリングに売った『キリストと悔恨の女』が実は自分の作品であること、画風が同じで国宝扱いされていた『エマオの食事』も自分の作品だと告白。それを証明するために、後に法廷でフェルメール風の絵を描いて見せ、さらに科学的鑑定の結果、メーヘレンによる贋作だと証明された。ゲーリングへの売却代金としてナチスが略奪していた200点の絵画がオランダに戻ったことなどから、売国奴から一転英雄扱いされる皮肉な結果となる。 |
| 5月30日 | 沖縄の日本陸軍守備隊が最南端の摩文仁に移動。海軍陸戦隊は豊見城に残る。 |
| 6月 4日 | スイスの最高権力者で、武装中立政策を推進してナチスドイツから国を防衛していた軍の最高司令官アンリ・ギザンが、ナチスドイツの降伏を受けて、権力の座から引退する。 |
| 6月 6日 | 沖縄の海軍陸戦隊指揮官、太田実少将が海軍次官宛に県民の実情を訴え、「沖縄県民斯ク戦ヘリ、県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ」という電報を発する。 |
| 6月 9日 | 熱田空襲。関西方面へ空襲に向かっていた米軍機130機の一部40機ほどが、転進して熱田の工場地帯を空襲したもので、空襲警報解除後に空襲が行われる結果となった。そのため逃げ遅れた従業員や市民ら2000人以上が死亡したとも言われるが詳細は不明。 |
| 6月13日 | 沖縄の太田実少将らが豊見城海軍司令部壕で自決。 |
| 6月18日 | ひめゆり学徒隊に解散命令が出される。このあと学徒隊の女学生らは戦闘に巻き込まれ、最終的に教師を含む240名のうち136名が戦没。 |
| 6月18日 | 沖縄攻略部隊指揮官のバックナー中将が戦死。 |
| 6月20日 | アメリカのハル国務長官が、フォン・ブラウンらドイツのロケット技術者のアメリカ移送を認める。ペーパークリップ作戦。 |
| 6月22日 | 各務原空襲。死者169人。赤星山などに投下された1t爆弾による被害が大きかった。各務原市は陸軍各務原飛行場や関連する航空関係の軍需工場が多かったため、何度も空襲にあっている。 |
| 6月23日 | 日本陸軍沖縄守備隊の牛島司令官、長参謀長らが自決して組織的抵抗が終結。 |
| 6月24日 | 米軍占領下の沖縄で交通が右側通行に切り替えられる。 |
| 6月27日 | 久米島で日本海軍の電探守備隊を指揮していた兵曹長によって、米軍の降伏勧告文書を持ってきた住民がスパイとして処刑される。以後も兵曹長は、次々と住民や部下の兵士を利敵行為などの理由で殺害。住民・兵士ら少なくとも25人以上が殺されたと言われる。自身は9月4日に米軍に降伏した。 |
| 6月29日 | 岡山空襲。空襲警報が出されず、逃げ遅れた市民1737人が死亡。 |
| 6月29日 | 延岡空襲。死者130人。化学工場が多かったことが目標となったとみられる。 |
| 6月29日 | 門司空襲。死者55人。 |
| 6月29日 | 佐世保大空襲。死者1226人。雨天だったために空襲を警戒していなかったことが大きな被害を生んだと言われる。 |
| 6月 | ビルマの独立運動家アウンサンらが実権を握る。 |
| 7月 4日 | 徳島大空襲。死者約1000人。徳島城鷲の門や大滝山三重塔などが焼失。 |
| 7月 9日 | 岐阜空襲。死者863人。人的被害は諸説ある。市街地中心部は焼失。 |
| 7月 9日 | 和歌山大空襲。死者1208人、行方不明者216人。犠牲者のうち748人は避難していた旧和歌山県庁舎跡の空き地で焼死している。和歌山城天守をはじめ城内の殆どの建物が焼失。 |
| 7月15日 | 多治見駅列車空襲。太多線多治見付近を走行中の旅客列車と周辺の建物を米軍のP51戦闘機が機銃掃射。列車は多治見駅までたどり着くも、乗客ら多数が死傷。 |
| 7月16日 | 世界初の核実験トリニティがニューメキシコ州アラモゴルド実験場で行われる。核出力は19Kt。技術力を要する爆縮型原子爆弾の検証試験。 |
| 7月17日 | ポツダム会談が始まる。アメリカ、イギリス、ソビエトの首脳がドイツのポツダムでドイツの処遇、国境の画定、日本への対応について話し合う。 |
| 7月20日 | 米軍が原爆投下訓練を兼ねて、通常爆薬の原爆模擬爆弾パンプキン(1万ポンド軽筒爆弾)を目標候補の都市周辺で投下を開始。 |
| 7月25日 | 日本に対しポツダム宣言が出される。 |
| 7月26日 | 米軍の重巡洋艦インディアナポリスが、原爆を輸送してテニアン島に到着する。 |
| 7月28日 | 大山口列車空襲事件。山陰本線大山口駅近くを走行中の旅客列車および赤十字標章掲示中の病客車に対し、多数の米軍艦載機が銃撃を行い乗客ら多数が死傷。 |
| 7月28日 | ニューヨークのエンパイア・ステート・ビルディングにB-25爆撃機が衝突。13名が死亡し、エレベーター1基が300mも落下。乗っていたエレベーターガールが奇跡的に重症で助かる。 |
| 7月29日 | 原爆輸送を終えて転進中の米重巡洋艦インディアナポリスが伊58潜水艦に撃沈され、発見が遅れて800名以上が死亡。生き残った艦長が軍法会議にかけられ有罪となり、のち自殺(純粋な戦闘の敗北による軍法会議の有罪は稀なケースで、政治的意図があるとも。通常は命令違反や逃亡、利敵行為などが軍法会議の対象)。死後、名誉回復された。 |
| 7月29日 | 大垣空襲。死者50人。市街地の殆どが焼失し、大垣城天守なども焼け落ちたが、人的被害は規模に比して少なかった。これは軍が消火活動より市民の避難を優先したためと言われる。 |
| 8月 2日 | 水戸空襲。死者300人。水戸東照宮、水戸城御三階櫓なども焼失。 |
| 8月 2日 | 富山大空襲。地方都市への空襲では最大規模で、死者は2275人~2695人とはっきりしていない。 |
| 8月 2日 | 八王子空襲。死者445人。 |
| 8月 2日 | 長岡空襲。死者1486人。この日の各地方都市への一斉空襲では、事前に爆撃予告として都市名を記した伝単(ビラ)が米軍によって散布されていたが、その内容には「長岡」は記されていないため、伝単に記載がありながら小規模の空襲だった「高岡」と間違えたのではないかという説がある。 |
| 8月 5日 | 湯の花トンネル列車銃撃事件。正午過ぎ、中央本線浅川駅(現高尾駅)を大幅に遅れて出発した新宿発長野行第419列車が湯の花トンネル手前で複数の米軍P51戦闘機の攻撃を受け、列車はトンネル内へ避難しようとしたが途中で停止してしまい、トンネル外に残った車両が繰り返し攻撃を受けて乗客に多数の死傷者を出す。 |
| 8月 6日 | 米軍のB-29爆撃機「エノラ・ゲイ」がガンバレル型のウラン原子爆弾「リトルボーイ」を広島市に投下。爆心地点は現在の中区大手町にある島病院(現島外科内科)の南西角の上空600m付近(以前は南東側と言われていた)。核出力は15Kt。35万人程度がいたとされる市街地で14万人が死亡。市街地の殆どが焼失。爆心地から1kmにあった広島城天守は、火災こそ起こさなかったが、爆風を受けた際に下層部分が耐えきれず、そのまま自重で崩壊したとみられる。日本側もすぐに新型爆弾による攻撃と判断。 |
| 8月 7日 | 日本海軍が開発した日本初の国産ジェット機「橘花」が初飛行。 |
| 8月 7日 | インドネシアに、日本軍政府主導で独立準備委員会が設立。後に独立運動を主導するスカルノやハッタも参加。 |
| 8月 8日 | ソ連外相モロトフが、日本の佐藤尚武駐ソ連大使に宣戦布告を通告。その直後に、満洲・朝鮮・樺太でソ連軍が一斉に進撃を開始。 |
| 8月 8日 | 筑紫駅列車空襲事件。西鉄大牟田線筑紫駅で停車中の2編成の旅客列車に米軍のP51戦闘機が機銃掃射を行い、乗客ら多数が死傷。 |
| 8月 8日 | 八幡大空襲。八幡、若松、戸畑などの工業地帯、市街地が空襲にあい、2900人以上が死傷。小伊藤山の横山防空壕では市民300人以上が窒息死するなど大きな被害が出た。 |
| 8月 8日 | 福山大空襲。354人が死亡。市街地の大半が焼け、福山城天守も焼失。 |
| 8月 9日 | 御前会議で終戦について協議が行われる。条件付き降伏が決定。 |
| 8月 9日 | 長崎市へプルトニウム爆縮型原子爆弾ファットマンが投下される。核出力は22Kt。約7万4千人が死亡する。当初は小倉に投下予定だったが、視界が悪かったため長崎に変更されたとされる。日本軍もアメリカ軍の特殊任務機の動きを探知していたが対応できず。 |
| 8月10日 | 日本政府、連合国へ、スイスを通じて条件付き降伏について通告。 |
| 8月10日 | アメリカの先進的ロケット研究者だったゴダードが死去。アメリカでは最後まで評価は低いままで、特許の多くも死後に認められた。そのために孤独に研究を進めざるをえず、アメリカのロケット・ミサイル開発の遅れの原因ともなった。彼が評価されるのは戦後の冷戦下になって以降。 |
| 8月10日 | 東安駅爆破事件。満洲国東満省東安市(現在の中華人民共和国黒竜江省密山県)の南満洲鉄道東安駅で、駅構内に野積みされていた日本陸軍の弾薬が爆発、直前に出発した黒咀子開拓団の避難民を載せた列車が巻き込まれ、3両が横転、市民・兵士ら125名が死亡したとされる。ソ連軍侵攻のため、憲兵が火薬を処分しようとして火を放ち爆発したとみられるが、詳細は不明。また死亡者数もこの事件の直後にソ連軍の攻撃によって避難民が多数巻き込まれたため、正確なところはわかっていない。 |
| 8月12日 | 連合国側の回答が放送され、改めて無条件降伏について協議。 |
| 8月12日 | 麻山事件。満洲国鶏寧県麻生区(麻山)で侵攻してきたソ連軍と反乱を起こした満州国軍が、避難中の日本の哈達河(ハタホ)開拓団を攻撃。追い詰められた開拓団員が集団自決。多くが女性と子供で421人が死亡し生存者は7人だったという。この後方にいた団員らは事態を知り脱出を決めたが多くが殺害された。 |
| 8月13日 | 総武本線成東駅に到着していた軍用輸送列車が米軍機の機銃掃射を受け炎上。消火作業中に搭載していた本土決戦用高射砲と弾薬が誘爆し、駅員や将兵ら42人が死亡、多数が負傷する。 |
| 8月14日 | 葛根廟事件。満州国興安総省葛根廟で、避難していた日本人婦女子千数百名に対し、ソ連軍が攻撃。機銃掃射や戦車で踏み潰すなどして千名以上が虐殺される。子供200名あまりも虐殺された。 |
| 8月14日 | 御前会議で、ポツダム宣言受諾による無条件降伏が決定。夜、天皇陛下による終戦詔書の録音が行われる。深夜、近衛師団の一部将校らが、無条件降伏阻止のため武装蜂起し、近衛第一師団長森赳中将らを殺害。皇居と放送会館を占拠するクーデター事件が起こる(宮城事件・玉音盤事件)。クーデターは東部軍管区による派兵で鎮圧。阿南惟幾陸相が敗戦の責任を取って割腹自殺を図り、翌朝死亡。 |
| 8月15日 | 正午に玉音放送が流され、日本政府は国民に向けてポツダム宣言受諾を発表し、第二次世界大戦が終結する(このため、日本では一般に同日が終戦の日だが、無条件降伏を決定伝達したのは14日であり、降伏文書調印は9月2日のため、世界的には9月2日が第二次世界大戦終結日)。 |
| 8月15日 | 夜、第五航空艦隊長官の宇垣纏中将が、大分基地から艦爆「彗星」で沖縄方面の米海軍艦艇に対し特攻を実施。すでに玉音放送も放送され、周囲から中止の要請もあったが、宇垣は翻心せず実行。当初5機を連れて行く予定が11機まで増えた。うち2機は故障で不時着、1機は米軍施設爆撃後に不時着し、3名が生存したが、残りは全機撃墜され宇垣を含む18名が戦死した。宇垣中将に対しては、戦争責任を取ったとして評価する意見もある一方、部下らを巻き込んでの無意味な特攻と玉音放送後であることから海軍内部でも批判は多く、死後の大将昇進は認められなかった。 |
| 8月15日 | 海軍軍令部次長の大西瀧治郎中将も割腹自殺。井上成美大将は、自己満足であり国家の損失であると自殺流行を戒める発言をしている。 |
| 8月15日 | 日本敗戦を受けて、朝鮮総督府政務総監の遠藤柳作は、混乱回避のため、穏健独立派の呂運亨に朝鮮政府の樹立を要請。呂運亨も安在鴻と建国同盟を元に朝鮮建国準備委員会を発足させる。 |
| 8月16日 | インドネシアで日本の降伏を受け、駐在武官の前田精海軍少将が、ジャカルタの自邸にスカルノやハッタ、スバルジョら要人50人ほどを集め、独立について協議させる。このとき、独立強硬派の青年らがすでに集まって、スカルノらに独立を迫っていた。前田はインドネシア人の手による独立宣言を後押しした。 |
| 8月17日 | 東久邇宮内閣が成立。軍の平和的武装解除が再優先の課題となる。 |
| 8月17日 | 双明子事件。満州国興安総省双明子で、東京荏原開拓団964名がソ連軍によって虐殺された事件。 |
| 8月17日 | スカルノらが、インドネシア独立宣言を発表。 |
| 8月18日 | 千葉県上空から伊豆諸島方面へ偵察飛行中のB-32ドミネーター2機が迎撃に上がった日本軍機17機に銃撃され、米軍機の乗員1名が戦死、2名が重傷を負う。第2次世界大戦最後の空戦となった。米国側は現場判断による偶発的な戦闘で日本政府の指示ではないとし、問題にはしなかった。 |
| 8月18日 | 成立した東久邇宮内閣の国務大臣近衛文麿の要請で、警視総監坂信弥や内務省警保局長橋下政実らによって「外国軍駐屯地の慰安施設」の企画・通達が出される。 |
| 8月19日 | マニラで日米代表団による日本進駐についての調整が話し合われる。 |
| 8月19日 | 国文学者で陸軍中尉だった蓮田善明が、赴任地のジョホールバルで、上官の中条豊馬大佐の敗戦の責任を天皇に帰する等の発言に反発し、大佐を射殺し、自らも拳銃自殺する。蓮田の文学同人に参加していた三島由紀夫に大きな影響を与えた人物。 |
| 8月21日 | ロスアラモス研究所で中性子反射体の実験を行っていた物理学者のハリー・ダリアンが、誤って反射体のタングステンブロックをプルトニウムコアの周りに落としてしまい、中性子反射によって核分裂臨界状態となる事故が発生。ダリアンはとっさにブロックを除去したが、発生した5.1シーベルトもの大量の中性子線照射を受け、25日後に死亡(デーモン・コア第一の事件)。 |
| 8月22日 | 内地の日本軍全部隊に戦闘停止命令。 |
| 8月22日 | 三船殉難事件。北海道増毛沖から留萌沖にかけて、南樺太からの引き揚げ船小笠原丸、第二号新興丸、泰東丸が相次いで停戦を無視したソ連軍の潜水艦L-12とL-19に攻撃され、小笠原丸と泰東丸が沈没。少なくとも1708名が死亡。小笠原丸は一旦稚内に寄ったあとでの遭難。泰東丸は浮上砲撃してきた潜水艦に白旗を示したが撃沈された。一方、元が特設砲艦であった第二号新興丸は雷撃で大破したが応戦し、この時の損傷からかL-19は礼文島沖合で沈没したものとみられる。また同日には南樺太で回航中の貨物船能登呂丸も雷撃で沈没している。 |
| 8月22日 | 肥薩線列車退行事故。肥薩線山神第二トンネル内で、復員兵で超満員の13両編成の列車が進行できなくなり立ち往生。排煙から逃れるため降りて線路を歩いていた乗客に向かい列車が退行してきて、53名が轢死する惨事となる。 |
| 8月24日 | ソ連軍が満洲帝国通化省通化市に進駐し、市民女性らを次々と襲うなどの事件を引き起こす。ソ連軍撤退後、代わって中国共産党八路軍が進駐し、同様に中国人を含め市民殺害や女性への暴行事件が相次ぐ。 |
| 8月25日 | 仁義佛立講開拓団遭難事件。満州国竜江省洮南県で仁義佛立講開拓団の避難民400名余りがソ連軍の襲撃を受け、機銃掃射などで子供も含む殆どが虐殺される。 |
| 8月26日 | 日本人女性を守るためとして占領軍相手の慰安施設「特殊慰安施設(RAA)」が設立される。国営であり、設立には占領軍側の要請もあった。売春施設の他にビアホールやキャバレーもあった。女性は業者を介さず一般公募で集められ、困窮した戦争未亡人なども多かった。最大時には全国で7万人の女性が働いていたという。少数の男性の慰安夫もいた。これとは別に花街などにも呼びかけられた他、民間で独自に設立された占領軍相手の売春店もあったという。 |
| 8月27日 | 敦化事件。22日に満洲国吉林省敦化に進駐したソ連軍の兵士らが、日満パルプ製造会社に残っていた女性社員や従業員の女性家族らを襲って集団強姦し、絶望した女性らがこの日青酸カリで集団自殺。23人が死亡。ソ連軍将校らが事態に気づき、集団強姦を止める一方で、事件の隠蔽を図った。 |
| 8月29日 | 終戦によりウルシー泊地攻撃作戦から戻る途中の、当時世界最大の潜水艦「伊号第四〇〇」が米軍に降伏。 |
| 8月30日 | 連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥が専用機「バターン号」で来日し、旧厚木海軍飛行場に到着。横浜へ向かう。立川や福生などの航空基地ではこれより前から米軍の進駐が行われている。 |
| 9月 2日 | 日本政府、東京湾の戦艦ミズーリで降伏文書に調印。マッカーサーの指揮のもとで、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、オランダ、中華民国、ソビエト、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの代表が、連合国側として調印。海外では一般に正式な日本の降伏はこの日とされている。 |
| 9月 2日 | ホー・チ・ミンが旧宗主国のフランスと、占領国であった日本に対してベトナム民主共和国の独立を宣言。 |
| 9月 3日 | 中華民国が9月3日から3日間の対日勝戦休日とする。後に成立した中華人民共和国もこの日を抗日戦争勝利記念日としている。 |
| 9月 6日 | 朝鮮建国準備委員会が京畿女子高講堂で朝鮮人民共和国の成立を宣言。呂運亨が主導し、金日成や李承晩、許憲、曺晩植ら左右両派を統合した統一朝鮮国を目指したが、米ソの対立から承認されずまもなく瓦解。 |
| 9月 7日 | 沖縄の日本軍残存部隊が降伏。 |
| 9月 7日 | アメリカ軍が朝鮮半島の仁川に上陸。 |
| 9月 8日 | アメリカ軍が朝鮮半島で軍政を開始。 |
| 9月 9日 | 朝鮮総督府が降伏文書に調印。 |
| 9月17日 | 枕崎台風が鹿児島県枕崎市付近に上陸。日本列島に沿って東北まで移動し、少なくとも死者2473人、行方不明者1283人、負傷者2452人を出す。 |
| 9月20日 | 昭和新山の噴火がほぼ終了する。 |
| 9月27日 | 昭和天皇・マッカーサー会談。 |
| 9月29日 | 昭和天皇・マッカーサーの並んだ写真が新聞に掲載され、国民に衝撃を与える。 |
| 10月 1日 | 連合国軍が、インドネシアに蘭印連合軍司令部を開設。以後、英印軍主体のイギリス軍とオランダ軍が上陸するが、暴力事件を起こすなどしてインドネシア人の反感を高める結果となる。 |
| 10月 4日 | GHQから治安維持法と特別高等警察の廃止命令が出される。 |
| 10月 9日 | 東久邇宮内閣が総辞職。 |
| 10月10日 | 朝鮮半島のアメリカ軍政府が、朝鮮人民共和国を否定。南北分断の要因の一つとなる。 |
| 10月10日 | インドネシアのバンドンで、日本軍からの武器引き渡し要求をしていた住民らが武装蜂起、連合軍から治安維持を命じられていた駐留日本軍との間で戦闘になる。 |
| 10月15日 | 勅令により治安維持法廃止。 |
| 10月15日 | インドネシアのスマランで、独立派の人民治安団が、日本人や外国人2000人以上を拘束監禁して武器引き渡しを要求するなどしたため、駐留日本軍側が攻撃に踏み切る。通称スマラン事件。 |
| 10月19日 | 日本軍と人民治安団の間で停戦協定が結ばれ、スマラン事件は終息。一連の戦闘でインドネシア側に1000人以上の死者が出た他、日本側も戦闘や監禁中に殺害されるなどして約200人の死者を出している。 |
| 10月24日 | ノルウェーのナチス占領下の首相だったヴィドクン・クヴィスリングが処刑される。「クヴィスリング」は「売国奴」という意味の単語にまでなっている。 |
| 10月26日 | 李承晩らが独立促成中央協議会を設立。 |
| 11月 3日 | 曺晩植らが朝鮮民主党を結成。独立主権の確立と民主主義を目指したが、共産主義に否定的であった曺晩植がソ連の提案した信託統治案に反対したことで失脚、消息を絶ち、その後、党は朝鮮労働党の衛星政党に組み込まれていった。 |
| 11月12日 | 二又トンネル火薬大爆発事故。占領軍が実施した、日田彦山線の二又トンネルに保管されていた旧日本軍の火薬焼却処分中に大爆発が起こる。上部の山が吹き飛び、爆風と落下した土砂で147人が死亡、149人が重軽傷を負う。 |
| 11月16日 | 国際連合教育科学文化機関創立総会で「ユネスコ憲章」が採択される。 |
| 11月20日 | ナチスの戦犯を裁くニュルンベルク裁判がはじまる。 |
| 12月 1日 | 陸軍省・海軍省が廃止され、復員業務を行う、第一復員省、第二復員省が設置される。 |
| 12月 5日 | バミューダトライアングルで訓練飛行中だったアメリカ海軍のアヴェンジャー雷撃機5機が消息を絶つ。 |
| 12月24日 | 生田警察署襲撃事件。多数の朝鮮人が、武装強盗事件の捜査に反発して神戸の生田署を襲撃。進駐軍に抑えられる。 |
| 12月27日 | ブレトン・ウッズ協定の29カ国が署名しIMF(国際通貨基金)が組織化される。 |
| 1946年(昭和21年) | |
| 1月 1日 | 昭和天皇の人間宣言。戦後最初の年頭詔書「新日本建設に関する詔書」。新日本の建設の希望と、天皇の神格性を否定した内容。 |
| 1月 3日 | アメリカ人ファシストで、ナチスの対英宣伝放送を担当したウィリアム・ジョイスがイギリスによって処刑される。元イギリスファシスト連合の幹部で、ドイツに渡る前はイギリスで活動していたが、国籍はアメリカのため、イギリスで裁くことができるのか論争になった。宣伝放送はイギリスでも有名だったため「ホーホー卿」とあだ名され、いくつかの創作作品でモデルにされた。 |
| 1月15日 | 中国国民党が汪兆銘の墓を暴き、遺体を焼却して、遺灰を投棄する。 |
| 1月18日 | 熊沢天皇の出現。名古屋で雑貨商をしていた熊沢寛道が、南朝の後亀山天皇の子孫であるから、皇位継承の正当性があると主張。 |
| 1月 | 桜島が噴火。 |
| 2月 1日 | 松本憲法改革草案を元に作成されていた憲法改正要綱の元ととなる内容が、毎日新聞によって記事にされ、その内容が保守的とマスコミの批判を浴びる。 |
| 2月 3日 | 通化事件。中国共産党によって占領されていた旧満洲帝国通化省通化市で、国民党軍と関東軍による武装蜂起事件が発生。蜂起は失敗に終わるが、このとき、中国共産党八路軍と朝鮮義勇軍の兵士らによって、避難してきていた無関係の日本人や朝鮮人、中国人ら市民3000人以上も虐殺され、多数の女性が強姦された事件。 |
| 2月 8日 | 松本憲法改革草案「憲法改正要綱」がGHQへ提示される。松本烝治国務大臣の私案をもとにしたもの。保守的というマスコミの批判などを受け、GHQは独自に憲法草案を作ることになる。 |
| 2月 8日 | 金日成らが北朝鮮臨時人民委員会を設立。 |
| 2月19日 | 昭和天皇の日本全国巡幸が始まる。 |
| 3月 4日 | フィンランドの大統領カール・グスタフ・エミール・マンネルヘイムが辞職。病気と、連合国との休戦条約締結、ラップランド戦争の終結を受けて。 |
| 3月 5日 | ウィンストン・チャーチル英首相が、アメリカ・ミズーリ州フルトンのウェストミンスター大学で「鉄のカーテン演説」を行なう。 |
| 3月 9日 | 桜島の噴火で溶岩の流出が始まり、流れが二本に分かれて山腹を下る。 |
| 3月12日 | ハンガリーのファシスト政治家サーラシ・フェレンツが人民政府により処刑される。 |
| 3月26日 | GHQがオフリミッツ令を発し、特殊慰安施設協会は表向き閉鎖される。以降も民間主体で存続しており、慰安婦の多くは民間施設へ移ったり、いわゆるパンパンガールとなった。なお設立されていた間も米兵などによる一般女性への強姦事件は跡を絶たず、武装した複数の米兵が慰安所を襲撃する事件も起きている。 |
| 4月 1日 | イギリスの植民地である英領マラヤと海峡植民地でマラヤ連合が成立。しかしスルタンの影響力を排除し、民族平等を示した結果、マレー人と華僑の対立を招く。 |
| 4月 5日 | 桜島の溶岩流の一つが黒神集落を飲み込んで海岸に到達。 |
| 4月15日 | 占領下の沖縄で軍票B円が公式通貨となる。 |
| 4月22日 | 『サザエさん』が福岡の地元紙フクニチ新聞に掲載が始まる。 |
| 4月26日 | 占領下の沖縄本島に沖縄民政府が設置される。 |
| 4月27日 | 日本でも婦人警察官制度が導入され、62人が採用される。 |
| 5月 4日 | 日中戦争の影響で昆明に疎開設立されていた中華民国国立西南聯合大学が閉校し、もとの国立北京大学・国立清華大学・私立南開大学が再開する。西南聯合大学師範学院は残り、国立昆明師範学院となる(現雲南師範大学)。 |
| 5月 7日 | 東京通信工業(現ソニー)が設立される。 |
| 5月 7日 | 葫芦島在留日本人大送還事業が始まる。中国大陸に残っていた日本人約170万人が主にソ連軍や共産党八路軍から殺人暴行略奪などの被害に遭っていることを受けて、密航して帰国した新甫八朗、丸山邦雄、武蔵正道らがGHQや日本政府、ローマ教皇庁などと交渉し、国民に呼びかけるなどした結果、アメリカ軍、中国国民党の協力を得られて行った日本帰還事業。遼寧省の葫芦島に日本人を集めた上で、華南からアメリカ軍の運行する艦船に国民党軍を乗せて葫芦島まで運び、その船に日本人を乗せて日本まで運び、日本で在留中国人や物資を乗せて華南まで運ぶ三角輸送方式をとった。この結果、170万人のうち105万人が帰国できた。一方で取り残された人、殺害された人、連れ去られて消息を絶った日本人も数十万人いるとされる。 |
| 5月16日 | 吉田茂に組閣の大命が下る。最後の大命降下。 |
| 5月21日 | 桜島の溶岩流のもうひとつが、有村集落を経て海岸に到達する(昭和溶岩)。死者1名、噴出物総量は約1億立方mに達する。 |
| 5月21日 | ロスアラモス研究所で、物理学者ルイス・スローティンらがプルトニウムコアの周りに置いた中性子反射体ベリリウムの半球同士をどのくらい近づけることで臨界に達するかの手動実験を行っている最中、手を滑らせて反射体をくっつけてしまい、内部のプルトニウムコアが核分裂臨界状態になる事故が起こる。スローティンは急いでベリリウムを除去したが、21シーベルトもの中性子線を照射されたスローティンは9日後に死亡。そのそばにいたアルバン・グレイブスも重度の放射線障害となる(デーモン・コア第二の事件)。 |
| 5月22日 | 第1次吉田内閣が成立。 |
| 6月 9日 | ラーマ9世、ラーマ8世の急死を受け、タイ国王に即位。 |
| 6月15日 | 第一復員省と第二復員省が統合し、復員庁となる。 |
| 7月 1日 | ビキニ原爆実験クロスロード作戦が始まる。アメリカ、日本、ドイツの艦船約70隻が動員される。最初の核爆発実験エイブルで日本の軽巡洋艦酒匂を含む5隻が沈没。デーモン・コア事件で使われたプルトニウムコアを使用。B-29からの投下地点が想定していた場所(戦艦ネバダ)から大きくはずれてしまい、実験映像ではきのこ雲が端に映っているものなどもある。 |
| 7月 5日 | ルイ・レアールが、ツーピースの水着を発表。サイズは小さくても大きな衝撃をもたらす、原爆級の衝撃として、原爆実験の行われたビキニ環礁になぞらえて、ビキニと称する。 |
| 7月19日 | 渋谷事件。渋谷駅そばの渋谷警察署前で、警察署員・武装したヤクザの落合一家と武田組・愚連隊の万年東一一派が、警察署前を3台のトラックで通過していた武装在日台湾人のグループと銃撃戦になる。警察官1名と台湾人7名が死亡、負傷者多数をだし、28人が逮捕される。その直前に起きた新橋闇市での関東松田組と在日台湾人との銃撃戦の騒動で台湾人は武装していたが、一方警察側も、台湾人が警察署を襲撃するという噂を信じてヤクザに協力を依頼していたことから事件に発展した。台湾人らは通りがかっただけで渋谷警察署を襲撃する予定はなかったという見方もある。 |
| 7月22日 | エルサレムのキング・デイヴィッド・ホテル爆破事件。パレスチナを統治していたイギリスのユダヤ人武装勢力への強行政策に反発したシオニスト強硬派非合法組織イルグンによって引き起こされたテロ事件。イギリス兵、パレスチナ人、ユダヤ人ら91人が死亡。 |
| 7月25日 | ビキニ原爆実験クロスロード作戦ベーカー実験が実施される。戦艦アーカンソーと空母サラトガの間に停泊した中型揚陸艦LSM-60から吊るされたMk.3A型原爆「Helen of Bikini」による水中核爆発実験が行われ、200万tの水と共に爆心地点に近かった戦艦アーカンソーが跳ね飛ばされる。 |
| 7月29日 | ビキニ原爆実験クロスロード作戦ベーカー実験で、損傷していた戦艦長門が沈没。同実験では空母サラトガや戦艦アーカンソーを含む8隻が沈没した。予想以上の放射性物質による汚染が判明し、3回目のチャーリー実験(水中核爆発実験)が中止になったと言われる。クロスロード作戦には影響を見るために多数の動物も使われた。この作戦に参加して汚染のひどかった空母インデペンデンスは、放射性廃棄物を載せてカリフォルニア州沖のファラロン諸島近海に自沈処分となった。 |
| 8月16日 | カルカッタの大虐殺事件。インドでジンナーらムスリム連盟によるイスラム住民の分離独立運動「直接行動の日」が暴動に発展。イスラム、ヒンドゥーの住民同士が衝突。数千もの犠牲者を出す。 |
| 9月 4日 | 日本初の南極探検を行った白瀬矗が死去。 |
| 9月 6日 | 持株会社整理委員会令にもとづき、三井、三菱、安田、住友、中島(富士)の5財閥を持株会社に指定。財閥解体の始まり。 |
| 9月30日 | 三井・三菱・安田の3財閥が自主解散。 |
| 10月 1日 | ナチスの戦犯を裁くニュルンベルク裁判が結審。12人が死刑、3人が終身刑などの判決が出される。戦勝国による恣意的なもので、法の不遡及・控訴が認められない、被告への暴力制裁や自白強要など、裁判としてはかなり不備があり、ナチス政権下の諸政策の真実がわからなくなった要因の一つともなり、後に大きな問題となった。 |
| 10月 1日 | 大邱10月事件。アメリカ軍政下の南朝鮮大邱市で軍政に抗議した市民が警察に銃撃され死亡。抗議活動が激化。 |
| 10月 1日 | 大邱10月事件。大邱市での市民射殺事件に対する市民の抗議運動を受けアメリカ軍は戒厳令を布告。これに反発した市民ら230万人が南朝鮮各地で蜂起する。鎮圧されるまでに少なくとも136名が死亡。アメリカ軍政への失望はのちの朝鮮戦争の遠因にもなった。抗議運動の背景には食糧不足、コレラの流行などで、日本統治時代より状況が悪化したこともある。 |
| 10月 3日 | 占領下の奄美群島に臨時北部南西諸島政庁が設置される。 |
| 10月 | 田岡一雄が山口組三代目組長を襲名。芸能興行と港湾荷役に力を入れ、合法経済活動にも進出するなど、経済ヤクザの元祖とも言える人物。ヤクザ組織が金銭目的主体の暴力団に変貌する原因の一つにもなった。また日本各地に進出して数多くの抗争事件も起こしている。襲名時にはさほど大きくはなかった山口組を日本最大の組織にまで拡大させた。 |
| 11月12日 | オランダ政府とインドネシア政府はリンガジャティ協定を締結。オランダはインドネシア連邦構想を打ち立て、オランダとの連合政府を企図し、外交交渉によってオランダの承認を得て独立を狙ったシャフリル首相と合意するが、これが反発を買い、シャフリルは支持を失う。まもなく、オランダ政府は武力による制圧に動き出す。 |
| 11月15日 | 東京池袋で、米軍MPが警察と共同で、通行中の女性を無差別に逮捕して、吉原病院で膣検査を強制する「板橋事件」が起きる。 |
| 11月16日 | 昭和21年内閣告示第33号によって、内閣が「現代かなづかい」と「当用漢字表」1850字を告示。GHQの「国語改革」により将来の廃止を前提に制限したもの。 |
| 12月 2日 | 内務省が「特殊飲食店地帯」いわゆる「赤線」を制定。 |
| 12月 2日 | 国際捕鯨取締条約成立に基づいて国際捕鯨委員会(IWC)設立。当初は反捕鯨が目的ではなかった。 |
| 12月 2日 | アメリカ海軍による大規模な南極調査プロジェクト「ハイジャンプ作戦」が始まる。 |
| 12月21日 | 昭和南海地震が発生。高知県を中心に津波の被害が大きく、死者は1330人。 |
| 12月27日 | 第1次吉田内閣が石炭と鉄鋼を重点にした傾斜生産方式を決定。対象分野の企業に対し、復興金融金庫による融資、物資の配給優先などが行われる。 |
| 12月 | 国民党軍に監禁されていた嵯峨浩と次女を陸軍連絡官の田中徹雄(のちの山梨県副知事)が単独潜入して救出し日本へ脱出。 |
| 1947年(昭和22年) | |
| 1月 3日 | 「眠らない男」アル・ハーピン死去。フランス系アメリカ人で、休息は取るが一度も睡眠を取ったことがないと主張した。 |
| 1月12日 | パレスチナのユダヤ人武装組織レヒが、ハイファのイギリス植民地警察署を爆破。140人以上が死傷。 |
| 1月14日 | 長谷川テルが旧満洲の佳木斯で死去。エスペランティストで反ファシズムの立場から国民党の対日宣伝も担当。作家としても活動した。中国では緑川英子の名で知られる。 |
| 1月27日 | 英国首相クレメント・アトリーと、ビルマ(現ミャンマー)の独立運動家アウンサンが、ビルマの1年以内の完全独立を約束する「アウンサン・アトリー協定」に調印。 |
| 2月10日 | 連合国とイタリアの間で平和条約が結ばれる。イタリアとの戦争状態が終了し、イタリアの軍備縮小、ファシスト党の禁止、大戦時までのイタリアの与していた領土、飛び地、植民地のうち、地中海やアドリア海の島々の帰属がイタリアから離れ、フランスとの国境が移動。アルバニア、リビア、エリトリア、ソマリランドの各植民地は切り離され、リビアは独立国、エリトリアはエチオピアと連邦制となる。戦略上重要な地域で帰属問題が残るトリエステ市からイストリア半島北部にかけての沿岸部はトリエステ自由地域として英米軍が占領している北部と、ユーゴスラビア軍が占領地している南部に分割。 |
| 2月12日 | ソビエト沿海州のシホテアリニ山脈上空で隕石が爆発。少破片が多数降り注ぐ。100t程度の小惑星と考えられる。 |
| 2月28日 | 台湾で二・二八事件が起こる。台北でタバコ売りの女性が摘発されたのをきっかけに、大陸から進駐してきた国民党軍と台湾住民が衝突。少なくとも2万8千人が殺害される。 |
| 3月 1日 | 済州島で南北統一を訴えるデモ行進に警察が発砲し6名が死亡。 |
| 3月10日 | 済州島で住民射殺事件を受けてゼネストが起きる。アメリカ軍政庁は警察官や右翼青年らを送り込んで弾圧。 |
| 3月15日 | 東京都の35区が22区に整理統合される。 |
| 3月21日 | 占領下の宮古・八重山諸島に、宮古民政府・八重山民政府が設置される。 |
| 3月31日 | 帝国議会衆議院解散(GHQ解散)。帝国議会終了。 |
| 4月10日 | ブルックリン・ドジャースに黒人選手ジャッキー・ロビンソンが入団し、メジャー・リーグの黒人選手の道を切り開く。 |
| 4月14日 | 最初で最後の東京都長官選挙で安井誠一郎が当選。 |
| 4月16日 | テキサスシティ貨物船爆発事故。テキサスシティの港に入港していたフランス船籍の貨物船グランドキャンプ号で火災が発生。約1時間後に大爆発を起こし、停泊していた貨物船ハイ・フライヤー号、ウィルソン・B・キーン号にも延焼し爆発。少なくとも581人が死亡、5000人以上が重軽傷を負い、港湾施設・石油関係施設に大きな被害が出る。 |
| 4月18日 | ヘルゴラント島爆破計画が実施される。大戦中ドイツ軍が基地を置いていた北海のヘルゴラント島の軍事施設を、余剰弾薬など4000t以上を使って爆破。ブリティッシュ・バン作戦とも呼ばれる。 |
| 4月20日 | 第1回参議院議員選挙。 |
| 4月20日 | 飯田大火。長野県飯田市で昼前に住宅から出火。初期消火に失敗して、火は強風に煽られて延焼。中心市街地の7割が焼失。城下町だったため街路が狭く木造家屋が多かったことも被害を大きくした。そのため復興の際に拡幅道路で市街地を4分割し、避難路として裏界線と呼ばれる路地を多数造成している。 |
| 4月25日 | 第23回衆議院議員選挙。 |
| 4月28日 | コンティキ号の冒険。人類学者トール・ヘイエルダールが、南米からイースター島へ向けて大型の筏で航海に出発する。 |
| 5月 2日 | 皇室令と華族令が廃止される。 |
| 5月 3日 | 日本国憲法施行。地方自治法施行。戦時法制の東京都制が廃止され、地方自治法による東京都となり、東京都長官はそのまま東京都知事へシフトする。 |
| 5月20日 | 新憲法による第1回特別国会開会。第1次吉田内閣総辞職。 |
| 6月 4日 | インド総督ルイス・マウントバッテン卿が、ジンナーらムスリム州独立派の主張を受け入れ、イギリス領インド帝国を「インド」と「パキスタン」に分割することによる独立を、同年8月15日をもって行う案を声明。 |
| 6月14日 | ロズウェル事件。アメリカ・ニューメキシコ州のロズウェル近郊の牧場にUFO(異星人の宇宙船)らしき物体が墜落しているのが発見され、その残骸を政府が密かに持ち去った、として後に最も有名なUFO事件となった出来事。軍の公表は7月8日だが、なにかの物体が堕ちた日付は正確には不明。軍は宇宙船説を否定している。 |
| 6月24日 | ケネス・アーノルド事件。アメリカの実業家ケネス・アーノルドが、ワシントン州レーニア山付近で自家用機を操縦中、物体9機が高速で飛行しているのを目撃したことがきっかけで、「空飛ぶ円盤」騒ぎに発展する。 |
| 7月18日 | 日本の信託統治領だった南洋庁が消滅し、南洋群島(ミクロネシア)はアメリカの信託統治領「太平洋諸島信託統治領」となる。 |
| 7月19日 | 朝鮮半島の独立と左右両派の統合を図っていた中道派の呂運亨が右派によって暗殺される。 |
| 7月21日 | オランダ軍がインドネシアへ全面侵攻。インドネシア独立戦争が本格化する。 |
| 7月19日 | ビルマ(現ミャンマー)の独立運動を主導していたアウンサン行政参事会議長が、旧植民地政庁で閣僚6人らとともに暗殺される。犯人は諸説あるが、一般には植民地政府首相でこのとき行政参事会委員だったアウンサンの政敵ウー・ソオが黒幕とされている(戦時中日本と協力関係にあったことでアフリカで拘束されていたウー・ソオが、同じく戦時中日本と協力関係にあったアウンサンを快く思っていなかったイギリス政府の圧力で実行したという説もある)。 |
| 7月26日 | アメリカ国家安全保障法発効。この法律によって、その後、国家安全保障会議、国家軍政省(のち国防総省)、アメリカ中央情報局が設立される。 |
| 7月28日 | 民衆芸術劇場(第一次民藝)が結成される。 |
| 7月28日 | フランス西部のブレスト港に入港していたノルウェーの貨物船オーシャンリバティが爆発。3300tの硝酸アンモニウムを積んでいたため大規模な爆発となり、ブレスト市街に甚大な被害をもたらす。死者26人、数百人が負傷。 |
| 8月 1日 | 板橋区から練馬区が分離し、東京特別区は現行の23区となる。 |
| 8月 1日 | 国連安全保障理事会で、オランダ軍によるインドネシア侵攻に対し、停戦決議が採択される。しかしオランダは侵攻作戦を止めず。 |
| 8月 7日 | コンティキ号がツアモツ諸島のラロイア環礁で座礁。 |
| 8月15日 | ネルーによって、インドがイギリスより独立したと発表。ジンナーらも、イスラム教徒の国家として、東西パキスタンがインドより分離独立したことを宣言。イギリス領インド帝国は正式に解体。 |
| 8月17日 | ソ連軍が引き上げて接収した旧ドイツ軍の空母グラーフ・ツェッペリンを、軍事演習の標的艦に使い撃沈。 |
| 8月18日 | カディス爆発事故。スペインのカディスで潜水艦基地の弾薬保管庫が爆発。少なくとも約150人が死亡、5000人が負傷する。近くの造船所が大きな被害を受けた。 |
| 9月15日 | カスリーン台風が関東南部をかすめ、関東全域に豪雨をもたらし、利根川、荒川水系が決壊。大洪水となる。死者1077名、行方不明者853名。 |
| 9月18日 | アメリカ国家軍政省(のち国防総省)が設立される。 |
| 9月30日 | 帝国大学令に代わり、国立綜合大学令が制定される。 |
| 10月 4日 | 物理学者マックス・プランクが死去。黒体放射の研究から「プランクの法則」を発見したことで量子力学への道を開いたことから、「量子論の父」と呼ばれている。アインシュタインを見出したことでも知られる。 |
| 10月11日 | 食糧難の中、ヤミ米を拒否した山口良忠判事が病死する。 |
| 10月13日 | 11宮家51人の皇籍離脱が決定。世襲親王家と呼ばれる皇族で、いずれも維新ころの伏見宮家の子孫である。伏見宮家は1428年に後花園天皇が即位した際に分かれた家柄で、女系としては天皇家と近い親族だが、男系では20世代離れた皇族。「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」では宮家の長男でも皇族を離れることになるため、もともと臣籍降下する予定だったとも言われる。 |
| 10月14日 | 安田銀行荏原支店に厚生省技官を名乗る人物が、行員らに薬物を飲ませる事件が起こる。死者はなし。 |
| 10月14日 | チャールズ・エルウッド・イェーガーが、実験機ベルXS-1で、人類史上初の有人超音速飛行を達成。 |
| 10月15日 | 復員庁が廃止される。 |
| 10月21日 | インドとパキスタンの独立に伴い、パキスタンの民兵がカシミール地方に侵入。ヒンズー教徒のカシミール藩王はインド併合を決め、インド軍が介入。第一次印パ戦争に発展。 |
| 11月 2日 | ハワード・ヒューズが、巨大水上飛行艇H-4ハーキュリーズの初飛行を行う。高度25mほどを1分ほど飛行して着水。この短時間の飛行1回で引退した。同機は2017年にロケット空中発射用プラットホームであるモデル351ロックが登場するまで世界最大の航空機だった。 |
| 11月 6日 | 東京の多摩川河畔で集団お見合いが行われる。386人が出席。 |
| 11月 6日 | 東大理学部人類学科の長谷部言人教授が明石原人の写真を発見し、石膏模型を見つける。 |
| 11月12日 | ナチスに偽のフェルメールを売った画家で贋作者のハン・ファン・メーヘレンに対し、フェルメールなどのサインを偽造した罪で禁固1年が言い渡される。贋作は罪だが、ナチスを騙し代金の代わりに貴重な絵画を取り戻したとして英雄扱いされたため、同罪では軽い刑となった。なおメーヘレンの贋作は、実在の絵を模したのではなく、画風を真似たオリジナルの作品に画家のサインを入れたもの。現在『エマオの食事』はメーヘレン作として美術館で展示されている。 |
| 11月29日 | 国連決議181号が採択される。パレスチナに、アラブ人とユダヤ人の国家を創設し、エルサレムを中立とする、いわゆるパレスチナ分割決議。アラブ・ユダヤ双方とも、穏健派などから1国共存案などもあったが、決議に対してパレスチナ人の反発が高まり、現地は騒乱状態に。アラブ諸国もアラブ救世軍などが結成されて現地へ派兵される。 |
| 12月 9日 | インドネシアで展開中のオランダ軍がラワゲデ村虐殺事件を引き起こす。 |
| 12月19日 | ソ連極東マガダンの港に入港したリバティ船の貨物船ヴァトゥーチンが大爆発を起こす。少なくとも90人が死亡、500人以上が負傷する。マガダン港が甚大な被害を受け、市街地にも被害が出た。 |
| 12月19日 | スイス・ベルン州の村ミトルツにあったスイス軍の弾薬庫で大規模な爆発が起きる。山を掘って作られた保管庫で、爆発のために山の一部が吹き飛び崩壊。爆風と土砂ででミトルツ村の40軒ほどの家はすべて全壊し、住民9人が死亡、20人が負傷。2020年に軍は、まだ山中に膨大な弾薬が残っているとして、その撤去のため、住民全員の退去移住を決定。 |
| 12月30日 | ルーマニア王ミハイ1世がソ連軍の圧力で退位を強制され国外追放となり、スペインへ亡命。共産主義政府が倒れた後の1997年からルーマニアに定住し、国王に準じる扱いを受ける。 |
| 12月30日 | 画家で贋作者のハン・ファン・メーヘレンが病死。 |
| 1948年(昭和23年) | |
| 1月 7日 | マンテル大尉事件。アメリカケンタッキー州のゴドマンで、未確認飛行物体の目撃が相次ぎ、空軍のマンテル大尉率いる4機のP-51戦闘機に追跡を命じたところ、マンテル大尉の機体が消息を絶ち、間もなく墜落しているのが発見される。UFOを追跡していて墜落したと言った話が広まるも、公式発表では海軍のスカイフック計画で使用した気球を誤認したものとされている。 |
| 1月15日 | 寿産院事件。寿産院という施設がお金目当てに引き受けた嬰児を大勢殺害した事件。犠牲者は推定85人から169人。 |
| 1月17日 | アメリカの仲介で、オランダとインドネシア政府が停戦協定を結ぶ。米軍輸送艦レンヴィルで締結されたためレンヴィル協定という。しかしインドネシア政府の統治領域をジャワ島の一部に限るなどしたため、反発を買う。 |
| 1月19日 | 三菱銀行中井支店に、厚生省技官を名乗る人物が、行員らに薬物を飲ませようとするが、支店長が不審に思って対応したため、薬物をまいて立ち去る。帝銀事件と関係があるとされる。 |
| 1月20日 | 国際連合安全保障理事会決議39により、インドとパキスタンに停戦を求める。 |
| 1月23日 | インドネシアのシャリフディン内閣が総辞職。スカルノ大統領はハッタに超党派内閣を樹立させる。 |
| 1月26日 | 帝銀事件。帝国銀行椎名町支店で、厚生省技官を名乗る人物が、行員らに毒物を飲ませた上で現金と小切手を奪い逃走。12人が死亡する。 |
| 1月30日 | マハトマ・ガンディーが、イスラム教徒との融和と、宗教を超えた世俗的統一インドの建設を主張したことで、イスラム教徒に妥協したと反発を買い、ヒンドゥー教徒の原理主義組織「民族義勇団」に暗殺される。 |
| 1月31日 | イギリスの植民地マラヤ連合に属するマレー半島9州とペナン島、マラッカ(ムラカ)によってマラヤ連邦が結成される。 |
| 2月 1日 | 大磯に孤児院のエリザベス・サンダース・ホームが設立される。設立者は三菱創設者岩崎弥太郎の孫娘の澤田美喜。彼女が外交官の夫沢田廉三と英国へ行った際に孤児院活動を知り、1947年に岐阜県の列車内で黒人との混血児の遺棄遺体と遭遇した経験から、米兵による強姦や、米兵相手の売春によって生まれ捨てられた孤児(GIベビー)の養育施設として私費を投じて設立された。施設名は活動に共感し最初に寄付した英国人エリザベス・サンダースにちなむ。正確な記録はないが、日本と沖縄に進駐していた米兵・英兵・豪兵による強姦事件は数万件以上あったと見られ、困窮から6大都市だけで4万人以上のいわゆるパンパンガール(売春婦)がいたと言われる。 |
| 2月 4日 | セイロンがイギリスから英連邦自治国として独立。初代首相はセーナーナーヤカ。のち国名をスリランカに変更。 |
| 2月29日 | イギリス統治領パレスチナのレホヴォトで、ユダヤ人武装組織レヒが鉄道を爆破。兵士28人が死亡。 |
| 3月25日 | 満洲の愛新覚羅家の皇族で、「東洋のマタ・ハリ(女スパイ)」「男装の麗人」と呼ばれた川島芳子(粛親王善耆の第14王女)が、中国国民党によって「漢奸」として北平第一監獄で処刑される。川島浪速の養女で、日本で育ち、上海や天津などで様々な活動をしていたが、彼女が実際に日本軍のために諜報・工作に携わっていたかは不明。 |
| 3月31日 | イギリス統治領パレスチナのビンヤミナで、ユダヤ人武装組織レヒが鉄道を爆破。40人が死亡。 |
| 4月 3日 | 済州島四・三事件。済州島で南朝鮮単独選挙の実施に反対する住民らが武装蜂起。軍政庁による一連の弾圧に反発したのも要因の一つ。李承晩は鎮圧のため軍を派遣。左派系住民はパルチザンとなって抵抗。済州島全土は内乱状態になり、1957年までに李承晩政権によって殺害された住民は推定5万人以上、日本へと逃れた住民は20万人以上と言われ、済州島の人口は終戦時から9分の1に激減した。 |
| 4月 9日 | イギリス統治領パレスチナのデイル・ヤシーン村で、ユダヤ人武装組織イルグン(エツェル)やレヒの部隊が、パレスチナ住民を襲い、女性や子どもを含む100人以上を虐殺する。これ以降、パレスチナ難民が急増し始める。 |
| 4月13日 | イギリス統治領パレスチナのエルサレムのスコプス山近郊で、ヘブライ大学のハダサー病院に向かっていたユダヤ人医療関係者の車列にアラブ人武装勢力が数時間に渡って銃撃を行い。医者や看護婦、ハガナー(ユダヤ人武装組織)の兵士など79人が死亡。 |
| 4月15日 | 第3次東宝争議で、組合員や俳優ら2500人が、撮影所を占拠。 |
| 4月27日 | 庭坂事件。福島県庭坂村で追う本線を走行中の402列車が脱線転覆。乗員3名が死亡。線路の継目板、犬釘、ボルトが抜かれていたことによるもので、整備不良か故意による事件かは不明。 |
| 4月30日 | エニウェトク環礁でアメリカの核実験サンドストーン実験が始まる。このため、事前に住民およそ140人がウジェラング環礁へ移住させられる。 |
| 5月 9日 | 日比谷公会堂で母の日大会開催。 |
| 5月10日 | 朝鮮の李承晩が総選挙を強行。 |
| 5月14日 | ユダヤ国民評議会が、テルアビブでイスラエル建国を宣言。これを受け、周辺のアラブ連盟5ヵ国(エジプト、シリア、レバノン、トランスヨルダン、イラク)はイスラエルに宣戦を布告。 |
| 5月15日 | アラブ連盟諸国軍15万人が、イスラエルへ侵攻を開始。第一次中東戦争勃発。イスラエル側は民兵を含めて兵力3万人程度。 |
| 5月18日 | アラブ連盟諸国軍によるエルサレム包囲戦が始まる。 |
| 6月 5日 | アメリカ、YB-48試作機墜落事故。グレン・エドワーズ大尉ら5人が、試作機のテスト飛行中、エンジンストールの試験を行ったため、機体が失速反転。その負荷で両翼が折れて墜落した。この事故でミューロック陸軍飛行場は、エドワーズ空軍基地と改名することになった。 |
| 6月11日 | 国連が介入して第一次中東戦争は、4週間の停戦に。イスラエル側は、武装組織のハガナーとイルグン(エツェル)が対立するも、ハガナーが改編したイスラエル国防軍に統一。世界中のユダヤ系の支援を受けて兵器を購入。一方、アラブ側は主力のヨルダン軍を動かすトランス・ヨルダンの影響力を他のアラブ諸国が警戒して足並みがそろわず。 |
| 6月13日 | 玉川上水で太宰治と愛人の山崎富栄が心中。 |
| 6月19日 | 桜桃忌。玉川上水で太宰治と山崎富栄の遺体が発見される。 |
| 6月22日 | イギリス国王ジョージ6世が「インド皇帝」の称号を放棄。 |
| 6月24日 | ソ連によって西ベルリンが完全に封鎖される。米英両軍は西ベルリン市民のために大空輸作戦を実施することになる。 |
| 6月28日 | 福井地震。 |
| 6月30日 | アメリカのAT&Tベル研究所のジョン・バーディーンとウォルター・ブラッテン、ウィリアム・ショックレーの3人がトランジスタの研究結果を発表。 |
| 7月 9日 | 第一次中東戦争の停戦期間が終わり、戦闘が再開。イスラエル軍がアラブ連盟軍を圧倒するようになる。 |
| 7月13日 | 優生保護法公布。望まぬ妊娠をした場合の中絶を認め、同時に優生学に基づいた国民優生法以来の「断種」も継続した法律。革新系(主に日本社会党)の女性議員らもこの法案を強く推した。この法律に基づき、科学的とは言えない理由で多くの不妊手術が行われたとみられる。 |
| 7月28日 | ドイツの化学メーカーBASFのルートヴィヒスハーフェンの工場で、ジメチルエーテルを積んだタンク車が爆発。207人が死亡、3818人が負傷する大惨事となる。 |
| 8月 6日 | 伊江島で5000発の砲弾を積んだ米軍弾薬輸送船が爆発。107人が死亡、70人が負傷する。 |
| 8月15日 | 李承晩、大韓民国の成立を宣言。 |
| 8月17日 | 午後8時から日本のプロ野球で初のナイター試合。横浜ルー・ゲーリック・スタジアムで、巨人軍対中部日本ドラゴンズ戦。3-2で中日が勝利。なお、日本最初のナイター試合は、1933年7月10日の戸塚球場で行われた早大ニ軍対新人戦。 |
| 8月19日 | 第3次東宝争議で、撮影所を占拠した組合や俳優ら2500人に対し、施設明け渡しの判決が出され、警察だけでなく、米軍が戦車や航空機まで出す大騒動となる。 |
| 8月21日 | 帝銀事件で、テンペラ画家の平沢貞通を北海道小樽市で逮捕。 |
| 8月 | 宝塚歌劇団の星組が10年ぶりに復活。 |
| 9月 9日 | 金日成、朝鮮民主主義人民共和国の成立を宣言。 |
| 9月12日 | 満州の中国共産党軍が京哈線に沿って錦州方面へ侵攻を開始。 |
| 9月13日 | インド内陸にあるインド帝国時代最大の藩王国、ニザーム藩王国が、インド軍のポロ作戦によって事実上併合される。同藩王はイスラム教徒だが国民の大半はヒンドゥー教徒で、インドとパキスタンのどちらに帰属するかで問題になっていた。 |
| 9月17日 | 第一次中東戦争の仲介に乗り出していた国連パレスチナ調停委員でスウェーデン赤十字総裁のフォルケ・ベルナドッテが、ユダヤ人武装組織レヒのメンバーに暗殺される。欧米の批判を受け、形式的には国防軍に編入していたレヒは解散に追い込まれる。 |
| 9月18日 | インドネシア共産党傘下の武装組織がマディウンで反乱を起こし、革命政府樹立を宣言。 |
| 9月19日 | ニザーム藩王国がインド吸収併合により消滅。 |
| 9月24日 | 本田宗一郎が本田技研工業を設立。 |
| 9月29日 | アメリカの高速艦上戦闘機F7Uカットラスの試作機XF7U-1が初飛行。高速飛行の目的で水平尾翼がなく機体後方についた主翼から双垂直尾翼が出ているという、海軍機では非常に珍しい形状の戦闘機。この特異な構造が空母離発着時に必要な揚力を得られず短期間で退役した。 |
| 10月 3日 | 中国人民解放軍が錦州を包囲。蒋介石は瀋陽に入って援軍派遣を決める。 |
| 10月14日 | 中国人民解放軍が錦州を攻略。 |
| 10月19日 | 麗水・順天事件(麗順14連隊叛乱事件)。韓国全羅南道麗水郡の韓国軍第14連隊が、北朝鮮工作員の煽動で反乱。麗水邑を襲い警察官や右派市民など多数を殺害。 |
| 10月20日 | 韓国政府、麗水郡の反乱に対し派兵するも、兵士らが反乱軍に加わる事態に。反乱軍は順天郡も制圧。 |
| 10月21日 | 韓国政府、麗水・順天郡の反乱に対し10個大隊を派遣することを決定。 |
| 10月21日 | 中国人民解放軍、長春を占領。 |
| 10月23日 | 韓国正規軍の反乱鎮圧部隊、順天郡へ進撃。順天市街地をほぼ解放。 |
| 10月24日 | 麗水の反乱軍が鎮圧部隊に反撃。 |
| 10月25日 | 麗水鎮圧部隊、麗水邑に進攻し、反乱軍と2日間に渡って交戦。反乱はほぼ鎮圧される。兵士、市民ら4000人以上が死亡し、152名が反乱の罪で処刑される。また李承晩大統領は、大規模な粛清を実施。多数の難民が日本に逃れる。 |
| 10月25日 | 中国人民解放軍が瀋陽と営口を占領。国民党軍は葫芦島から華南へと退却。日本によって重工業化が進んでいた満洲地方はすべて共産党側の手に落ち、戦力増強につながった。この結果、中国共産党と中国国民党の勢力は逆転する。 |
| 11月 6日 | 中国で人民解放軍と国民党軍による淮海戦役が始まる。国共内戦で最大の戦役であり、総数200万にもなる兵力が衝突した。 |
| 11月12日 | 極東国際軍事裁判の判決が出される。絞首刑7人、終身刑16人、有期禁固刑2人、訴追免除1人。 |
| 11月16日 | 7人の女性を強姦し殺害した小平事件の犯人である小平義雄に死刑判決が下る。犯人の名前は小平(おだいら)だが、事件名は「こだいら」と呼ばれる。 |
| 11月26日 | ポラロイド社が世界初のインスタントカメラ「ポラロイド・ランド・カメラ」を発売。 |
| 11月30日 | 国有鉄道法が成立。 |
| 12月 1日 | 韓国で国家保安法成立。麗水・順天事件を受けて独裁体制が強化される。 |
| 12月 3日 | 江亜号沈没事件。中国の黄浦江と長江の合流点の近くで、貨客船「江亜」が突如爆沈。爆発の原因は触雷か。少なくとも2750人が死亡。国共内戦から逃れる難民が多数乗船していたことから、死者数はもっと多いと見られる。江亜は元々日本で建造された貨客船「興亜丸」で、終戦後に中華民国が接収して、上海-寧波間で運行していた。同船は後に引き上げられ「東方紅8号」と改名して再運用された。 |
| 12月 7日 | 昭和電工事件で芦田均前首相が逮捕される。 |
| 12月10日 | パリで行われた第3回国連総会で「世界人権宣言」が採択される。 |
| 12月11日 | インドネシアの内乱状態を受け、オランダは和平は壊れたとして、第二次侵攻作戦を発動。 |
| 12月17日 | ライト兄弟が初飛行時に使ったライトフライヤー号が、イギリスからアメリカに戻され、初めてワシントン国立博物館に展示される。アメリカではスミソニアン協会のサミュエル・ラングレーや、チャールズ・ウォルコットが、ライト兄弟の功績を認めなかったことや、その後の目覚ましい航空機の進歩にライト兄弟がついていけなくなったこともあり、兄弟の評価が低く、倉庫に眠っていたライトフライヤー号はロンドン科学博物館が展示のため、オーヴィル・ライトの許可を得てイギリスへ運んでしまっていた。このことがアメリカ世論を動かし、最終的にスミソニアン協会が公式に謝罪し取り戻すことになった。 |
| 12月19日 | オランダ軍、インドネシアへ全面侵攻。 |
| 12月23日 | A級戦犯の死刑が巣鴨プリズンで執行される。板垣征四郎、木村兵太郎、土肥原賢二、東條英機、武藤章、松井石根、広田弘毅の7名。 |
| 12月23日 | オランダ軍、インドネシアの首都ジョグジャカルタを陥落させ、スカルノを始め、インドネシア政府関係者を逮捕。インドネシア側はスマトラ臨時政府を樹立。これにより、これまで外交交渉を主軸にしていたインドネシア側が武力による独立へ方針を転換。侵攻作戦はアメリカの反発も買ったため、オランダは国際的に孤立することに。 |
| 12月31日 | カシミールをめぐって起こった第一次印パ戦争が停戦に合意。カシミールは分割されて実効支配されることに。 |
| この年開かれたオスロ世界火山会議で、昭和新山の隆起を定点観測したミマツダイヤグラムが高い評価を得る。 | |
| 1949年(昭和24年) | |
| 1月 2日 | 硫黄島で日本兵二人が投降する。 |
| 1月10日 | 中国国共内戦で最大の戦役となった淮海戦役が終結。国民党軍は壊滅的な敗北を喫し、長江以北は共産党側のものとなった。また長江流域にあった国民政府の政治的首都の南京や最大都市上海も風前の灯火となる。 |
| 1月26日 | 法隆寺金堂の火災により、古代仏教美術の傑作だった法隆寺金堂壁画が焼失。 |
| 1月27日 | 太平輪沈没事故。上海発台湾基隆行の中華民國中聯企業公司運行の大型客船「太平輪」が、舟山群島近海を無灯火で航行中、前方にいた貨物船「建元輪」に衝突。建元輪はすぐ沈没。太平輪もまもなく沈没した。乗員乗客約1000人のうち、900人以上が死亡。翌日通りがかったオーストラリア軍艦と舟山群島の漁師らによって50人ほどが救助された。国共内戦から逃れるため、軍関係者や政治家、文化人などが多数乗船し、大量の物資や文化財なども積載していた。 |
| 2月23日 | イスラエルとエジプトが休戦協定を締結。アメリカの外交官ラルフ・バンチの調停による。以降、アラブ連盟各国とも協定。イスラエルはパレスチナの大半を占領し、エジプトはガザ地区を、トランスヨルダンはヨルダン川西岸地区を編入する。トランスヨルダンはヨルダン・ハシミテ王国と改称。 |
| 3月10日 | イスラエルが最後の軍事作戦として、アカバ湾に面する都市ウム=ラシラシ(現エイラート)を占領。手製の国旗「インクの旗」を掲げる。 |
| 3月30日 | 名立機雷爆発事件。新潟県西頸城郡名立町(現上越市名立区)で海岸近くに不審な物体が漂着。海軍出身の巡査が危険と判断し移動させようと準備していたところ、その物体が岩に接触して爆発。巡査や見学に来ていた子供59人を含む63人が死亡、21人が重軽傷を負い、周囲の建物103棟が全半壊した。ドラム缶型の形状に取手のようなものが付いていたと言われ、大型の沈底機雷ではないかとみられる。 |
| 4月 1日 | アイルランド(エール)共和国がイギリス連邦を離脱。 |
| 4月 4日 | 欧米の12カ国(アメリカ合衆国、イギリス、フランス、カナダ、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、デンマーク、ノルウェー、アイスランド、イタリア、ポルトガル)が反共・反ファシズムの軍事同盟として北大西洋条約に調印。 |
| 4月18日 | アメリカ海軍超大型空母ユナイテッド・ステーツの起工。 |
| 4月20日 | 中国国共内戦で、中国共産党と中国国民党との停戦協議が決裂し、人民解放軍が侵攻を再開。30万の兵力が長江を渡河し「渡江戦役」が勃発する。兵力では防衛する国民党のほうが倍もあったが、戦意に乏しい上に、寝返りや離反が相次ぎ、各地で敗走。 |
| 4月20日 | アメジスト号事件。国共内戦中の中国で、戦火が迫る首都南京のイギリス大使館員らの避難護衛のために派遣されたブラックスワン級スループ艦アメジスト号が長江を遡上中に人民解放軍の沿岸砲台から砲撃を受けて交戦となり破損。長江沿岸に拘留される。救援に向かった重巡洋艦ロンドンとスループ艦ブラックスワンも攻撃を受け退却。アメジストのスキナー艦長ら多数が戦死し、人民解放軍にも被害が出た。 |
| 4月23日 | アメリカ空軍と海軍の対立で超大型空母ユナイテッド・ステーツの建造が中止となる。 |
| 4月23日 | 人民解放軍が南京を制圧。 |
| 4月27日 | 人民解放軍が蘇州を占領。 |
| 5月 9日 | 予讃線事件。予讃線浅海駅付近を走行中の準急列車が脱線転覆。乗員3名が死亡、乗客3名が負傷。継目板、犬釘、ボルトが外されレールがずらされており、工具の遺留品があったことから、故意の事件と断定。列車を狙ったテロ説の一方、謀略説もある。容疑者が自殺するなどしたため、未解決のまま時効となる。 |
| 5月12日 | ソ連、西ベルリン封鎖を解除。西ベルリンで共産革命が起こらず、逆に非人道的という批判にさらされたため。 |
| 5月12日 | 人民解放軍が上海攻略を開始。 |
| 5月17日 | 小説家海野十三が結核で死去。日本SF小説の祖の一人。SFのほか、推理小説、科学小説、軍事小説、工学専門書なども執筆。翻訳家、漫画家でもあった。横溝正史、江戸川乱歩、高木彬光、小栗虫太郎らと親しかった。 |
| 5月21日 | アメジスト号事件で、イギリスと中国共産党が交渉を開始。共産党はイギリスの謝罪を要求するが、国民党政府を支持するイギリスは合法として拒否。交渉は膠着。 |
| 5月22日 | アメリカ初代国防長官で、予算をめぐる大統領との対立や、超大型空母ユナイテッド・ステーツの建造に関わる空軍との対立から精神衰弱で辞職し入院していたジェームズ・フォレスタルが自殺。 |
| 5月25日 | 商工省と貿易庁、石炭庁が統合し、通商産業省が発足。 |
| 5月27日 | 人民解放軍が上海の主要部分を制圧。 |
| 5月31日 | 国立学校設置法が公布・施行され、帝国大学は廃止となる。 |
| 6月 1日 | 戦時中に鉄道省から運輸通信省・運輸省に移管されていた日本国内の鉄道事業を受け継ぐ日本国有鉄道が発足。三公社五現業のひとつ。 |
| 6月 2日 | 人民解放軍が浙江省を制圧し、渡江戦役はほぼ終結。 |
| 6月 5日 | 松前城天守が、城内にあった役場から出火した火災で焼失。 |
| 6月 8日 | ジョージ・オーウェルの近未来小説『1984』が刊行。 |
| 7月 6日 | 下山事件。前日、出勤途中に行方不明となっていた下山定則国鉄総裁が、常磐線の北千住駅-綾瀬駅間で轢死体で発見される。 |
| 7月 6日 | オランダ軍に拘束されていたスカルノらが釈放され、ジョグジャカルタ政府が復活。 |
| 7月15日 | 三鷹事件。三鷹駅車両基地の列車が暴走し、三鷹駅構内で脱線転覆。商店街に突入して6人が死亡。20人が重軽傷を負う。裁判で解雇された運転士による単独犯行と認定されたが、被告の供述が次々と変わる、アリバイ証言が採用されない、共産党系の弁護士が犯行を認めるよう示唆する、死者数が多いのに無期懲役判決など不可解なことがあり、現在でも係争中。 |
| 7月15日 | 西ドイツのラインラント=プファルツ州プリュム近郊の丘陵にあったトンネル式掩体壕を利用した火薬保管庫で大規模な爆発が発生。爆風と吹き飛んだ大量の土砂でプリュムの街全体が破壊され、死者行方不明者12人、15人が負傷。フランス軍がドイツのジークフリート線を破壊するために用意していた弾薬500tを置いていったもので、同日夜火災が発生し消火作業中に大爆発を起こした。火災は人為的なものという説もある。 |
| 7月19日 | GHQ民間情報教育局顧問ウォルター・クロスビー・イールズが、新潟大学開学式で共産主義教員の排除を訴える挨拶を行う。以降も各地で同様の演説を行い、「赤化教員」追放の動きに発展する。いわゆるレッドパージのはじまり。 |
| 7月27日 | イギリスの世界初のジェット旅客機デ・ハビランドDH.106コメットが初飛行。 |
| 7月30日 | 長江沿岸に勾留されていたイギリス海軍のアメジスト号が、夜間に灯火で客船風に偽装した上で通りがかった客船に随行するふりをして離岸。人民解放軍に発見されて砲撃を受けるが、射程圏外への脱出に成功する。アメジスト号事件の顛末は映画化された他、艦内で飼われていて最初の交戦時に負傷した猫のサイモンは、生き延びて乗員の士気を高めたとしてディッキンメダル(動物用の勲章)を猫で唯一受賞した。 |
| 8月 6日 | 弘前大学教授夫人殺害事件が発生。まもなく近所の男性が逮捕されるが、これがのちに冤罪事件であったことで知られる。 |
| 8月10日 | アメリカ国家軍政省が「国防総省」に改められる。国家軍政省の略称NME (National Military Establishment)がエネミー(敵)と聞こえたためとも。 |
| 8月17日 | 松川事件。青森発上野行き上り412号旅客列車が福島県松川町内で脱線転覆。3人が死亡。線路に露骨な細工がしてあったことから、意図して起こされた事件。東芝労組と国労の犯行とされ容疑者多数が逮捕されるが、アリバイなどの証拠から後に全員無罪判決。犯人は不明だが、捜査機関が無罪の証拠を隠したことや目撃証言を無視していること、後に事件を告白する証言や手紙が出てくるなど不可解なことが多く、戦後の一連の列車脱線事件の中でもっとも「米軍などによる謀略説」が強い。またこの事件がのちに「東大ポポロ事件」につながる。 |
| 8月24日 | 北大西洋条約機構(NATO)が発足。 |
| 8月29日 | ソビエトが最初の核実験RDS-1に成功する。核出力は22Kt。核の拡散が始まり、核戦争の危険性が高まる。 |
| 9月 4日 | ピークスキル事件。アメリカのニューヨーク州で、公民権運動団体主催のコンサート会場で、保守派や退役軍人、KKKらが客らを襲撃し、140人が重軽傷を負う。 |
| 9月23日 | ソビエトの核実験成功をアメリカのトルーマン大統領が公表。 |
| 9月24日 | ソビエトも核実験成功を認める。 |
| 9月30日 | 米英両軍による西ベルリンへの物資大空輸作戦が終了。 |
| 10月 1日 | 中国国共内戦の終盤、毛沢東が北京の天安門壇上に立ち、中華人民共和国の建国を宣言。 |
| 10月20日 | 日本戦歿学生手記編集委員会から戦没学徒兵の残した遺書を集め『きけ わだつみのこえ』が刊行される。学徒兵の悲劇とその心情が大きな同情を生む一方、反戦にそぐわない遺書は意図的に削除したことなどから、捏造・改竄の批判も起こる。 |
| 11月 2日 | インドネシア独立を話し合うハーグ円卓会議で独立が決定。インドネシア共和国は各島政府による連邦共和国となり、オランダと連合するというもの。オランダは影響力を保とうとした。インドネシア独立戦争は終結。 |
| 11月24日 | 貸金業「光クラブ」を設立し、独特の宣伝手法で成功したが、物価統制令で取り締まられた東大生の山崎晃嗣が自殺(光クラブ事件)。 |
| 11月26日 | プロ野球「パ・リーグ」結成。新規球団参入と正力松太郎の2リーグ構想に対する賛否で当時の日本野球連盟が分裂。2リーグ賛成派で既存球団の阪急、南海、東急、大映に、毎日、西鉄、近鉄が加わり太平洋野球連盟(パシフィック・リーグ)が結成される。 |
| 11月30日 | NATOを中心に西側諸国が対共産圏輸出統制委員会(ココム)を設立。 |
| 12月 7日 | 中華民国政府が台湾に移る。 |
| 12月15日 | 分裂した日本野球連盟の球団の内、パシフィック・リーグに入らなかった4球団(読売、中日、大陽、大阪)と新規球団(大洋、広島、西日本)がセントラル・リーグを創設。2リーグ制となる。 |
| 12月17日 | 南米大陸最南端の島のひとつフエゴ島で大地震。 |
| 12月24日 | 韓国で聞慶虐殺事件が起きる。韓国軍が「共産匪賊」に協力したとして非武装の女性や子供、老人ら88人を射殺。「共産匪賊」による犯行と喧伝した。李承晩政権による国民虐殺事件の一つ。 |
| メリーランド悪魔憑依事件が起こる。悪魔祓いを行ったことが話題になった事件。のちの映画『エクソシスト』のモデル。 | |
| 東京駅北東側に第一鉄鋼ビルディングが完成。戦後大型ビルのはしり。 | |
| 堺市にあった百舌鳥大塚山古墳が、住宅地造成のために破壊される。墳丘だけで全長168mとかなり大きな前方後円墳で、多数の刀剣などが出土している。墳丘・周濠とも破壊は順次進められ、1986年までに完全消滅。住宅地となった。 | |
| 1950年(昭和25年) | |
| 1月 1日 | 年齢のとなえ方に関する法律が施行。すでに法的に定めていた「満年齢」計算方式に対して、社会ではまだ「数え年」計算方式が混在していたことから、これを満年齢に統一化するため。配給において数え年で不正が横行したことも理由の一つ。 |
| 1月 8日 | 探偵小説雑誌「新青年」の新年会で、木々高太郎、大坪砂男、永瀬三吾、宮野村子、氷川瓏、本間田麻誉の文学派6人と本格派の岡田鯱彦が抜打座談会を行う。文学派が本格派を批判する展開となり、その内容は同誌4月号に掲載され、江戸川乱歩や横溝正史、高木彬光らの猛反発を買う。「抜打座談会事件」。推理雑誌「宝石」は出席者の作品掲載を拒否。「新青年」はこの出来事でも売れ行きが伸びず同年7月号で廃刊。 |
| 1月12日 | トルーマン政権のディーン・アチソン国務長官が、アメリカは、フィリピン・沖縄・日本・アリューシャン列島のラインの軍事防衛に責任を持つと声明。いわゆるアチソンライン。朝鮮半島が除外されていたため、朝鮮戦争の要因の一つとなる。 |
| 2月 3日 | 終戦直後に3人の女性を強盗目的で殺害した第2小平事件の犯人の死刑が確定する。事件名は「小平事件」と内容が似ていたために付けられたもので、直接犯人や地名とは関係がない。 |
| 2月12日 | シベリア抑留から帰還した日の丸梯団のメンバーが、日本共産党の徳田球一書記長がソ連に依頼して共産主義者以外の帰還を妨害したと証言。GHQが問題にするなど政治問題に発展する。 |
| 3月16日 | シベリア抑留者帰還妨害の徳田要請問題で、日本共産党の徳田球一書記長が衆議院に証人喚問される。 |
| 3月17日 | カリフォルニア大学バークレー校のカリフォルニア大学バークレー校のグレン・T・シーボーグ、スタンリー・G・トンプソン、アルバート・ギオルソ、ケネス・ストリートらが、キュリウム242にα粒子(ヘリウム4原子核)を衝突させて、超ウラン元素カリホルニウムの生成に成功する。 |
| 3月25日 | 瀬戸内海の宇高連絡船だった紫雲丸と鷲羽丸が衝突し、紫雲丸が転覆沈没。7人が死亡。第一次紫雲丸事故。紫雲丸は引き上げ後に再度大事故を起こす。 |
| 3月28日 | 女子プロ野球、日本女子野球連盟が発足。 |
| 4月 5日 | シベリア抑留者帰還妨害の徳田要請問題で、シベリア抑留時代にソ連軍の通訳を担当した哲学者の菅季治が衆議院に参考人招致を受け、事前に提出した徳田要請の内容について、意図的に改竄したのではないかと批判される。 |
| 4月 6日 | シベリア抑留者帰還妨害の徳田要請問題で、衆議院に招致され責められた菅季治が苦悩し吉祥寺駅近くで列車に飛び込み自殺。 |
| 4月15日 | 東久邇稔彦がひがしくに教を開教。 |
| 5月 3日 | 吉田茂首相が、全面講和・永世中立論を主張する南原繁東大総長を「曲学阿世の徒」と批判。「曲学阿世」とは「世間におもねって学問を捻じ曲げる」と言う意味。前漢の儒学者轅固生が公孫弘を諭して言ったことば。 |
| 5月22日 | 那覇市の首里城跡地に琉球大学が開学。 |
| 6月 6日 | 日本共産党中央委員24名が公職追放。レッドパージがはじまる。 |
| 6月25日 | 北朝鮮軍10個師団10万人が宣戦布告なしに韓国へ向けて侵攻を開始。朝鮮戦争勃発。半島統一を狙う金日成が、ヨーロッパでの西側軍事力の低減を狙ったソ連のスターリンの後押しと中共の毛沢東の容認で起こした。この当時、韓国軍は規模が小さく装備も貧弱で、米軍も大半が日本へ引き揚げていた。北朝鮮軍の侵攻を察知した情報をマッカーサーは信じなかったと言われ、米韓側は後手に回る。 |
| 6月27日 | 韓国の李承晩大統領は、共産主義からの再教育団体「国民保導連盟」に加盟していた自国民の殺害を指示した上で、自身は閣僚らも見捨ててソウルから逃亡。「保導連盟虐殺」は韓国全土で行われ、さらにアメリカ軍や侵攻した北朝鮮軍からも虐殺されたため、死者は60万人から120万人とも言われる大虐殺事件に発展した。 |
| 7月 2日 | 金閣寺放火事件。放火したのは、同寺の見習い僧侶で大谷大学の学生だった林承賢。 |
| 7月11日 | 小倉黒人米兵集団脱走事件。朝鮮へ派遣される予定で小倉市の城野基地に到着していた米陸軍第25歩兵師団第24歩兵連隊の黒人兵約200人(少数の白人兵を含む)が武装したまま基地を脱走。近くの住宅街などを襲い、強盗・略奪・強姦事件を多数引き起こす。事態を知った米陸軍憲兵隊と小倉市警が出動するが対応しきれず、さらに米陸軍から二個中隊が出撃し、脱走兵との間で銃撃戦を展開しこれを鎮圧。強盗などの被害は訴えがあったが、多数あったと見られる強姦事件は、被害者側がひた隠ししたこともあり報告例がない。米軍内部の黒人兵への差別や激戦地へ送られるのを恐れたことが背景にある。第25歩兵師団は朝鮮戦争で壊滅的な被害を出した。 |
| 7月31日 | カナダ最北部エルズミア島北端に建設が進められていたカナダ軍の気象台(後のアラート基地)で、補給物資を投下中のアブロ・ランカスターが墜落。乗員9名全員が死亡。 |
| 8月 4日 | インドネシア連邦政府は、各島政府を統合して、単一のインドネシア共和国に再編。オランダの影響力を排除。なお、この時点では西イリアンはオランダ領ニューギニアのまま。 |
| 8月15日 | 沖縄各民政府を統合し、群島政府に改められる。 |
| 8月29日 | 文化財保護法施行。法隆寺金堂の火災をうけ、戦前の文化財保護関係の法律(史蹟名勝天然紀念物保存法、国宝保存法、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律)を統合して制定。旧国宝の指定を解除し、新たに重要文化財が設定され、その中でも特別に重要なものをあらためて国宝に指定。 |
| 8月31日 | トランスワールド航空903便墜落事故。インドのボンベイ発、エジプトのカイロ、イタリアのローマ経由、アメリカ・ニューヨーク行のロッキード・コンステレーションが、カイロ国際空港を離陸した直後、火災を起こして墜落。乗員乗客55人全員死亡。。 |
| 9月 5日 | 画家で贋作者として知られたハン・ファン・メーヘレンの遺産がオークションに掛けられる。 |
| 9月22日 | 日大ギャング事件(オー・ミステーク事件)。日本大学で運転手をしていた若者が日大職員の給料を輸送中に奪った強盗事件。犯人は恋人である日大教授の娘と逃走。アプレゲール犯罪のひとつ。24日に逮捕された際に「オー・ミステーク」と言ったことから事件名になった。 |
| 9月27日 | 伊藤律会見捏造事件。朝日新聞が、潜伏中の共産党幹部、伊藤律との会見記事をスクープ掲載するがすべて捏造と発覚。 |
| 11月 8日 | 朝鮮戦争でジェット機同士が初の空中戦。 |
| 11月 8日 | 朝鮮戦争で国連軍が鴨緑江橋梁を爆撃。北朝鮮側半分が崩落。修復はされず「鴨緑江断橋」としてそのまま現在も保存。 |
| 11月23日 | 市街地建築物法に代わって建築基準法が公布される。高さ百尺規制は例外を設けて継続。 |
| 12月22日 | 劇団民藝(第二次)が創立。 |
| 1951年(昭和26年) | |
| 1月24日 | 山口県熊毛郡麻郷村八海で瓦製造業の夫妻が殺害される。いわゆる「八海事件」。すぐに犯人は逮捕されるが、警察が複数犯の可能性を疑ったことと、犯人が罪を軽くしようとして、事件と無関係の知り合いの名前を出したことから、4人が逮捕され、冤罪事件に発展した。 |
| 1月27日 | アメリカ・ネバダ核実験場での初めての核実験レンジャー作戦が始まる。従来より核物質の量を削減して効率よく核爆発を起こすための検証実験。 |
| 2月 7日 | 山清・咸陽虐殺事件が起きる。韓国慶尚南道で韓国軍第11師団が共産パルチザン殲滅を狙った「堅壁清野作戦」と称して山清郡・咸陽郡で住民ら705名を虐殺。 |
| 2月 9日 | 居昌事件が起きる。韓国慶尚南道で韓国軍第11師団が共産パルチザン殲滅を狙った「堅壁清野作戦」と称して居昌郡で11日までに住民719名を虐殺。山清・咸陽虐殺事件とともに李承晩政権による国民虐殺事件の一つ。 |
| 4月 5日 | ソ連のスパイ容疑でローゼンバーグ夫妻に死刑判決がくだされる。全世界で冤罪を訴える運動が広がる。 |
| 4月 8日 | エニウェトク環礁の太平洋核実験場でアメリカの核実験グリーンハウス作戦が始まる。核融合による熱核兵器(水素爆弾)開発の前段階の検証実験。 |
| 4月11日 | トルーマン大統領と対立したマッカーサー元帥が更迭される。朝鮮戦争での認識の甘さによる作戦の失敗、軍との対立、さらに中国本土への核攻撃と軍事侵攻を主張したことなどでトルーマンに切り捨てられた。 |
| 4月16日 | マッカーサー元帥が羽田空港からアメリカへ帰国。沿道には20万人もの日本人が見送りに駆けつける。 |
| 4月19日 | アメリカに帰国したマッカーサー元帥が議会で「老兵は死なず、ただ消え去るのみ」の演説を行う。その後、ワシントンD.C.市内をパレード。 |
| 4月24日 | 国鉄桜木町電車火災事故。106人が焼死、92人が重軽傷を負う。架線工事の事故で垂れ下がった架線に接触した電車の塗料に電気着火し車体の1両目が炎上。戦時設計の車両で絶縁塗料ではなく、窓も中段固定三段式だったこと、自動扉がショートで使えなくなったこと、非常扉の開け方を乗務員が知らなかったこと、貫通扉が内開きだったため乗客の圧力で開けられなかったことなどの要因が重なり、乗客が脱出できず、場所も高架上だったため救助にも行けず、かろうじて3両目以降は切り離せたが、大勢が焼死する結果となった。被害が大きかったことから、すぐに対策が取られることになった。 |
| 5月 1日 | 過度経済力集中排除法により、日本発送電株式会社が全国9地域の電力会社に分割。 |
| 5月 9日 | エニウェトク環礁でのアメリカの核実験グリーンハウス作戦ジョージ実験ではじめて、重水素を搭載した核融合検証実験が行われる。核出力は225Ktだが、その殆どは核分裂によるもの。 |
| 5月17日 | 貞明皇后(皇太后節子)崩御。 |
| 5月17日 | まりも号脱線事件。根室本線の新得駅付近を走行中の急行まりもが脱線。登坂中だったため速度が出ておらず負傷1名で済むも、故意に線路の継目板を外してレールをずらしたことが原因であったことから、労働争議中の組合などを対象に大規模な捜査が行われる。しかし犯人は特定できず。 |
| 5月20日 | 毛沢東が映画『武訓伝』を批判。公開後大評判で、共産党幹部も称賛した映画だったが、一転して批判の的となった。武訓は清朝末期に実在した教育者で乞食をしながら資金を集めて、貧困児童のための無料学校を創設した人物。毛沢東が批判して以降、攻撃の対象となり、文化大革命で墓は暴かれ遺体は焼却された。 |
| 5月25日 | エニウェトク環礁でアメリカの核実験グリーンハウス作戦アイテム実験が行われる。核融合の原料となる重水素を使った核分裂ブースト(強化原爆)検証実験。核分裂出力を高めることに成功。後の水爆の原型。 |
| 6月 5日 | 相互銀行法施行。民間の金融システムである無尽会社を相互銀行に転換。 |
| 6月14日 | 世界初の商用コンピュータUNIVAC Iがレミントンランド社から販売される。1号機は米国勢調査局に納入される。 |
| 9月 8日 | サンフランシスコで対日講和条約署名式。49カ国が署名。 |
| 10月16日 | 日本共産党第5回全国協議会開催。中国に亡命中の徳田球一らの指示で、「農村から都市を包囲する」という中国式革命路線(51年綱領)の暴力革命方針が採択される。これと前後して、日本共産党軍事部門として、山村からのゲリラ作戦を担う山村工作隊や、民兵組織である中核自衛隊が編成された。方針や武力手段を伝える山村工作隊の機関紙「球根栽培法」も発行され、数々の事件も起こしている。 |
| 10月22日 | ネバダ核実験場で、核実験バスター・ジャングル作戦が行われる。核攻撃下での兵士らの作戦行動を検証するデザート・ロック演習が行われ、参加した兵士6500人は被曝。 |
| 12月20日 | アメリカアイダホ州の国立原子炉研究所に建設されたEBR-1実験用原子炉で、世界初の原子力発電に成功する。同原子炉は世界初のプルトニウム燃料原子炉であり、世界初の高速増殖炉でもあった。 |
| アルフレッド・ベスターの小説『分解された男』が雑誌「ギャラクシー・サイエンス・フィクション」誌1952年1月号から連載開始。1953年にハードカバーが出版され、第1回ヒューゴー賞を受賞。 | |
| 1952年(昭和27年) | |
| 1月18日 | 大韓民国の李承晩大統領は、李承晩ラインを一方的に設定し、連合国が、講和条約で日本の領土から外すべきだという韓国の要求を認めなかった竹島を占領。 |
| 1月21日 | 札幌で札幌市警の白鳥警部が射殺される。いわゆる白鳥事件。裁判では日本共産党関係者の犯行と断定された。いわゆる「白鳥決定(再審でも少しでも疑わしき時は被告人の利益に)」が出された事件でもある。ただし白鳥事件そのものは、再審を認めなかった。 |
| 1月 | ネパールのトリブバン王が権力を握り、傀儡から脱し、立憲君主制を確立してシャー王朝が復活。 |
| 2月 6日 | イギリス国王ジョージ6世が就寝中に崩御。娘のエリザベス王女が即日即位。 |
| 2月10日 | トカラ列島が日本に返還される。 |
| 2月20日 | 東大ポポロ事件。東京大学の本郷キャンパスで、学生劇団のポポロ劇団が「松川事件」を題材にした演劇を上演した際、観客の中に内偵中の私服警官が4名いることが判明。うち3名を学生らが捕まえ、暴行を加える。暴行をした学生二人が起訴されるが、これが「大学の自治、学問の自由」とはどの範囲までを指すのかで論争に発展した。 |
| 3月29日 | 北海道阿寒湖のマリモが天然記念物から、特別天然記念物に変更指定される。これをもって3月29日はマリモの日となる。 |
| 4月 1日 | 琉球政府が正式発足。 |
| 4月 1日 | アメリカの核実験タンブラー作戦が始まる。核爆発の有効高度の測定などを実験。 |
| 4月 9日 | 羽田-名古屋-伊丹-福岡の日本航空旅客機「もく星号」が消息を絶つ。 |
| 4月10日 | 「もく星号」が伊豆大島三原山中腹で残骸となっているのを、同僚機の「てんおう星号」が発見する。乗員乗客37名全員死亡。 |
| 4月17日 | 鳥取大火が起こる。城下町特有の道の狭さで消火活動が進まず、5228戸が焼失。 |
| 4月28日 | サンフランシスコ講和条約が発効。 |
| 5月 1日 | アメリカの核実験スナッパー作戦が始まる。夜間核実験も実施。バスター・ジャングル作戦に続き、核爆発直後の兵士の作戦行動を検証する演習(デザート・ロック演習)が行われた。 |
| 6月14日 | 世界初の原子力試験潜水艦ノーチラス号(SSN-571)が起工される。 |
| 7月19日 | ワシントンUFO事件。アメリカの首都ワシントン上空に謎の光が複数出現して、戦闘機が出撃するなど大騒ぎになる。 |
| 7月23日 | イギリスの保護国であったエジプト王国で、ガマール・アブドゥン=ナーセル率いる反英の自由将校団がクーデターを起こし、国王ファールーク1世を追放して政権を掌握。エジプト革命。 |
| 7月26日 | アルゼンチンの大統領フアン・ペロンの妻で元女優のエバ・ペロンが癌のため死去。33歳。その国葬には数十万の市民が集った。 |
| 7月26日 | ふたたびワシントン上空に謎の光が複数出現。大統領がアインシュタインに助言を求める。上空に逆転層ができて地上を走行している自動車の明かりの蜃気楼が見えたという説などがある。 |
| 9月 6日 | 著作権保護の方式主義と、無方式主義の国の間を調整する、万国著作権条約がジュネーブで作成される。 |
| 9月12日 | 宇宙人フラット・ウッズモンスター事件。ウェストバージニア州フラットウッズで、墜落した謎の物体を見に行った住民が、近くの森の中にいる3mを超える「怪物」を目撃。全米で大ニュースとして伝えられる。樹上にいた大型のフクロウなどの見間違いと言われるも、真相は不明のまま。 |
| 9月16日 | 電源開発促進法により電源開発株式会社が設立される。過度経済力集中排除法によって9社に分割された日本発送電株式会社に代わり、発電所建設などを行う特殊法人。 |
| 9月24日 | 明神礁噴火で新島の調査に向かった海上保安庁の海洋測量船「第五海洋丸」が遭難。31名が消息を絶つ。明神礁の噴火か、もしくは同じカルデラの海底火山高根礁の噴火に巻き込まれたものと考えられる。 |
| 10月 3日 | イギリスが初の核実験ハリケーン作戦を実施。核出力25Kt。西オーストラリアのトリムイユ島沖合に停泊したフリゲート艦プリムの艦内で起爆(艦船で核爆弾を輸送し攻撃する事態を想定していたため)。 |
| 11月 1日 | アメリカ軍による史上初の水爆実験アイビー作戦マイク実験がエニウェトク環礁のエルゲラブ島で実施される。核出力10Mt。液体水素を燃料としたため、装置が巨大で実用的ではないが、核融合に成功した。エルゲラブ島は消滅し礁湖内に巨大なクレータが出来る。 |
| 11月16日 | 核実験アイビー作戦キング実験がエニウェトク環礁ルニット島で行われる。核分裂兵器(原爆)としては最大出力に近い500Kt。プルトニウムではなく、臨界量を大きく上回る高濃縮ウランを使った爆縮式原爆という特徴を持っていた。そのためスーパーオラロイ爆弾とも呼ばれる(オラロイとはオークリッジ合金(Oak Ridge Alloy)の略で、兵器級高濃縮ウランのこと)。純粋な核分裂の場合、発生したエネルギーで核燃料が飛散してしまうため、核燃料を増やしても核出力には上限がある。逆に核融合(水爆)には原理上上限はないとされる。 |
| 11月18日 | 丸ノ内ビルヂングの隣に、新丸ノ内ビルヂングが竣工する。1937年6月28日に着工したが戦争で中止されていたオフィスビル。 |
| 12月 5日 | ロンドンスモッグが発生。最終的に1万2000人を超える死者を出す。 |
| 12月 7日 | 鹿地事件。小説家の鹿地亘が、アメリカの諜報機関「キャノン機関」に拉致される。戦時中に中国国民党のもとで工作活動をしていたことなどから、ソ連のスパイと疑われたためとされる。 |
| 12月12日 | チョーク・リバー原子炉事故。カナダオンタリオ州チョーク・リバーのチョーク・リバー原子力研究所で試験原子炉NRXが制御ミスにより暴走。燃料棒が溶融する事故が発生する。 |
| 12月22日 | 名古屋の東亞合成化学工業の工場で爆発事故。死者22名、負傷者363名を出す。 |
| エチオピアとエリトリアが連邦制に移行。 | |
| この年、アメリカの物理学者ドナルド・グレーザーによって「泡箱」が発明される。液体水素等を満たした容器に粒子を通すとその軌跡が小さな泡となって残るため、「霧箱」に変わる物理学実験用の装置として用いられた。グレーザーは1960年にノーベル物理学賞を授与。 | |
| 1953年(昭和28年) | |
| 1月 6日 | 鶴田浩二襲撃事件。俳優の鶴田浩二が大阪天王寺の旅館で他の芸能人らと飲食しているところを、山口組組員4人に襲撃され、暴行を受けて重症を負った事件。山口組3代目の田岡一雄が、鶴田浩二のマネージャー兼松廉吉に美空ひばりとの公演をオファーしたところ断られたことに腹を立てたのが原因。田岡に逆らうとひどい目に合うというイメージが芸能界に広がり、芸能興行で山口組が巨大化する要因ともなった。 |
| 1月13日 | ソ連で、ユダヤ人医師9人がアメリカ政府の工作で政府高官暗殺を図ろうとしたとして逮捕される。これをきっかけにソ連国内で大規模な反ユダヤキャンペーンが展開され、多数のユダヤ人が逮捕投獄される。いわゆる医師団陰謀事件。 |
| 1月28日 | 銀座の洋菓子店チョコレートショップで、お客に配っていた風船に詰める水素が漏出して爆発。1棟が全焼、4棟が半焼。死者1名、重軽傷者78名を出す。この事故を機に水素ボンベ使用規制が進められることになる。また風船に詰める気体も、徐々に安価な水素から安全なヘリウムへと移行していく。 |
| 2月 1日 | 日本放送協会がテレビ本放送開始。 |
| 2月14日 | 東京都府中町の小勝多摩火工府中工場で、保安隊から依頼を受けた擬砲弾用火薬を生産作業中、火薬配合室で爆発。14棟全棟が全壊。周辺1kmの建物にも大きな被害を出す。工場関係者24名中20名と一般市民1名が死亡。 |
| 3月 1日 | ソ連書記長のスターリンがマレンコフ、ベリヤ、フルシチョフ、ブルガーニンら要人との夜食中に倒れる。秘密警察長官でスターリンの側近だったが関係が悪化しつつあったラブレンチー・ベリヤがマレンコフらと組んで毒をもったという疑惑もある。 |
| 3月 5日 | ソ連のスターリンが死去。ゲオルギー・マレンコフが最高指導者の地位(閣僚会議議長兼共産党筆頭書記)を継ぐ。 |
| 3月13日 | ゲオルギー・マレンコフが権力を分散させる集団指導体制を狙って共産党筆頭書記の地位をニキータ・フルシチョフに譲り、閣僚会議議長(首相)のみとなる。ラブレンチー・ベリヤは副首相兼内相に付き、実質の最高権力を握る。 |
| 3月17日 | アメリカ軍の核実験アップショット・ノットホール作戦が始まる。引き続き、核爆発下での作戦遂行演習であるデザート・ロックIV演習が行われ、2万人以上の兵士が参加。 |
| 3月23日 | 出光興産のタンカー日章丸が、極秘に神戸港を出港。イランへ向かう。この時イランは、イギリスの石油会社アングロ・イラニアン石油の施設を国有化したことでイギリスより海上封鎖状態に置かれていた。 |
| 3月24日 | 国際電信電話株式会社が設立される。 |
| 3月31日 | 核実験アップショット・ノットホール作戦ルース実験が行われる。ウランに減速材の水素を混ぜ反応効率を高めて核燃料を減らす目的の実験だったが失敗に終わる。 |
| 4月 3日 | ソ連のベリヤがユダヤ人医師団による陰謀はなかったとして医師らを釈放。この問題でソ連国家保安省(MGB)関係者を逮捕。MGBによる反ユダヤキャンペーンは終息へ向かう。 |
| 4月10日 | 日章丸がイギリスの封鎖線を突破してイランのアーバーダーン港に入港。 |
| 4月11日 | 核実験アップショット・ノットホール作戦レイ実験が行われる。ふたたび水素化ウランを利用したが失敗に終わり、水素化ウラン原爆は廃案。 |
| 4月15日 | 日章丸がアーバーダーン港を出港。イギリスの海上封鎖線突破を図る。 |
| 4月19日 | 尾崎行雄が第26回衆議院議員総選挙で落選し、63年間守った議席を失う。 |
| 4月25日 | この日発行の『ネイチャー』誌に、フランシス・クリックとジェームズ・ワトソン、モーリス・ウィルキンスの3人がDNAの二重らせん構造について説明した論文が発表される。研究にはロザリンド・フランクリンの撮影したX線写真が利用された。 |
| 4月27日 | 阿蘇山中岳第一火口が噴火。大量の噴石が噴出し、観光客ら6人が死亡、90人が重軽傷を負う。 |
| 5月 9日 | 日章丸が川崎港に無事入港し、世論の大喝采を浴びる。通称「日章丸事件」。 |
| 5月25日 | アメリカ・ネバダ核実験場で、アップショット・ノットホール作戦グレイブル実験が行われる。W9核砲弾が口径280mmアトミックキャノンから発射される。核出力15Kt。唯一の核砲弾発射実験。 |
| 5月25日 | 世界最初の実用型超音速戦闘機F-100の試作機YF-100Aが初飛行で音速を突破する。F-100は正式採用されるもすぐに旧式化したことや墜落事故が多く、輸出は4カ国のみでデンマーク、トルコ、台湾が主力機として、フランスが核攻撃用途に少数採用している。制空戦闘機として開発されたが実際は爆撃機としての運用が多かった。 |
| 5月29日 | エドモンド・ヒラリーとテンジン・ノルゲイがエベレスト登頂に初成功。 |
| 6月18日 | エジプトのアフマド・フアード2世が退位し、ムハンマド・アリー朝は崩壊。共和制に移行する。 |
| 6月19日 | アメリカの原爆開発に関する機密情報をソ連に流したスパイ行為を理由に、ジュリアスとエセルのローゼンバーグ夫妻が処刑される。長いこと、これは冤罪事件だと思われていたが、暗号解読作戦ヴェノナ計画の情報が解禁された際に、実際にスパイ活動をしていたことが明らかになった。アメリカ政府が夫妻および妻エセルの弟の容疑について、情報源である暗号解読などの機密活動を明かすわけに行かないことから、証拠をはっきり出せず、冤罪だと思われた部分もある。 |
| 6月22日 | ホロウ・ニッケル事件(中空5セント硬貨事件)。アメリカで14歳の新聞売りの少年が、新聞代金で受け取った5セントのニッケル硬貨に不審を抱き、落とした所、割れて中から多数の数字が書かれたマイクロフィルムが出てきた。その内容を専門機関で調査した所、国家機密だったため、スパイ事件の捜査に発展し、ソ連のスパイ「ルドルフ・イワノビッチ・アベル」ことウィリアム・フィッシャーが逮捕された。彼は後にベルリンでの捕虜交換でソ連に帰国している。 |
| 6月26日 | ソ連の政治局会で突如フルシチョフが主導してベリヤを批判。ベリヤを国家反逆罪容疑で逮捕する。ベリヤが秘密警察を動かして要人らの生殺与奪を手中にしていたため、不意を突く必要があったとされる。 |
| 7月26日 | キューバ・バティスタ軍事政権に対するフィデル・カストロらが率いた青年ら119人の部隊がサンチアゴ・デ・キューバのモンカダ兵営を襲撃するも失敗に終わる。 |
| 7月27日 | 朝鮮半島中部38度線付近の板門店で、国連軍のクラーク総司令官と、中共の彭徳懐人民志願軍司令官、北朝鮮指導者の金日成が、朝鮮戦争休戦協定を締結。北進を主張していた韓国の李承晩大統領は反発して参加せず。朝鮮戦争は休戦に。韓国軍は20万人が死傷、アメリカ軍は4万人以上が死亡し10万人が負傷、北朝鮮は約30万人が死亡、中共は40万から最大150万人が死亡したと言われる。また市民は南北合わせて400万人前後が死亡したと言われるが、戦闘による死亡もさることながら、南北両政府による、収監中の政治犯の処刑や、無関係の一般市民に対する虐殺事件によるものが多い。韓国の李承晩政権は自国民60万から120万人以上を虐殺したと言われるが、今でも認めないメディアや勢力もある。また多数の住民女性が連行され慰安婦にされたと言われる。日本人も国連軍に後方支援や機雷除去などで動員されており、多数が戦闘に巻き込まれて戦死している。半島から戦火を逃れて日本に渡った市民もかなりいるとされる。 |
| 8月 1日 | ローデシア・ニヤサランド連邦が成立。現在のザンビア、マラウィ、ジンバブエにまたがる白人政権。アパルトヘイト政策を行った。 |
| 8月 8日 | ラズエズノイ号事件。ソビエトのスパイ船ラズエズノイ号が北海道の知来別海岸に現れたため巡視船が停戦命令を発するが、銃撃しながら逃走。巡視船が応戦し被弾した同船は停止。船長と乗員4人が逮捕される。のち全員強制送還。 |
| 8月12日 | ソビエトが初の核融合兵器実験RDS-6を行なう。核出力400Kt。実際には核融合は殆ど起こらなかったと言われるが、ソビエト政府は誇大宣伝。アメリカの実用型水爆開発を加速させる要因となった。 |
| 8月28日 | 日本テレビが民間テレビ放送の本放送を開始。また日本初のテレビCMが放送されるが、裏返しに表示してしまう日本初の放送事故も起こる。 |
| 9月 7日 | 溶融金属冷却型原子炉を搭載した潜水艦シーウルフ(SSN-575)が起工される。 |
| 10月29日 | アングロ・イラニアン石油による日章丸積荷の所有権を求める裁判で、アングロ・イラニアン石油が訴えを取り下げたため、出光興産の事実上の勝訴となる。この独断でイランから石油を運んだ日章丸事件は、石油メジャーに抑えられていた石油製品自由取引の解禁へと繋がった。 |
| 11月 5日 | 徳島ラジオ商殺人事件が起こる。のち内縁の妻が逮捕され有罪となるが、再審で無罪判決。 |
| 12月23日 | ソ連で失脚したベリヤが銃殺刑に処される。なおベリヤの最期は諸説あり、6月26日の政治局会のクーデターの際に射殺された、あるいは自宅で軍の急襲を受け殺害されたという説もある。 |
| 12月25日 | 奄美群島が日本に返還される。これ以降、奄美群島の住民は、沖縄へ行く際パスポートが必要になる。 |
| 12月31日 | 紅白歌合戦が初の公開放送。本来は元日放送だったため、翌1954年元日の開催予定だったが、会場となる日本劇場の予約が取れず、大晦日の公開放送となった。これがきっかけで以降は年末に行われることになる。 |
| 大阪第一生命ビル竣工。例外的に百尺規制を超えた大型ビル。 | |
| グリーンランドが、デンマーク植民地からデンマーク海外郡に昇格。 | |
| 1954年(昭和29年) | |
| 1月 5日 | ソ連の最初の超音速戦闘機MiG-19の直接の試作原型機SM-9が初飛行。MiG-19は9500機が生産されて共産主義国にも大量に輸出され、各国の派生型も多い。北朝鮮では21世紀初頭まで現役だった。優れた格闘戦能力を持ち整備もしやすい一方、航続距離とエンジンの寿命が短かった。 |
| 1月10日 | シンガポール発ロンドン行の英国海外航空781便コメットがイタリア沖の地中海上空で空中分解、乗員乗客35人全員が死亡。コメットの運行を停止して検査を行う。 |
| 1月12日 | 米国務長官ジョン・フォスター・ダレスが、ニュールック戦略(大量報復戦略)を表明。ソ連が攻撃を仕掛けてきた場合、あらゆる場所で即座に戦略核兵器で報復攻撃を行うよう整えておく核抑止力戦略。また技術的に超長距離の精密攻撃が難しかったため、目標をある程度外れても効果を挙げられる大出力の水爆開発が進められる。 |
| 1月20日 | 営団地下鉄丸ノ内線の池袋 - 御茶ノ水間が開業。 |
| 3月 1日 | ビキニ環礁でアメリカが水爆実験キャッスル作戦ブラボー実験を実施。核出力15Mt。第五福竜丸を含む日本漁船多数やマーシャル諸島の住民が被曝。兵器として実用的な乾式水爆の実験で、核出力を小さく見誤ったことが、実際の被害を大きくしたと言われる。 |
| 3月13日 | KGB(ソ連国家保安委員会)が独立組織として誕生。スターリン時代のGRUを受け継いだ秘密警察。 |
| 3月27日 | アメリカの核実験キャッスル作戦ロメオ実験実施。核出力は想定を大幅に上回る11Mt。 |
| 4月 5日 | 集団就職のための最初の列車、青森発上野行き臨時夜行列車が出発する。 |
| 4月 8日 | コメット運行再開直後に、ロンドン発ヨハネスブルグ行南アフリカ航空201便のコメットがイタリア沖のティレニア海上空で空中分解。コメットの運行が停止され、安全問題に発展する。のちに金属疲労が原因と判明し、安全対策を施して復活するが、国際競争に敗れた。 |
| 4月12日 | アメリカでマッカーシズムが吹き荒れる中、マンハッタン計画で原爆開発を主導したロバート・オッペンハイマーが、原子力委員会から追放される。オッペンハイマーの家族らがアメリカ共産党に関わっていたことが問題にされたためで、諮問に対し多くの科学者はオッペンハイマーを擁護したが、エドワード・テラーが告発したことが大きな要因となった。オッペンハイマーが水爆開発に否定的だったのに対し、テラーは水爆開発を推進してきたことも影響したといわれる。オッペンハイマーは表舞台から去り、一方のテラーはその後出世するも友人を失い、後にこのことを後悔したという。 |
| 4月13日 | ジョセフィン・ベーカーが来日。ダンサーとして世界的に活躍した公民権運動家。 |
| 4月26日 | 映画『七人の侍』が公開される。 |
| 4月26日 | アメリカの核実験キャッスル作戦ユニオン実験実施。核出力はこれも想定を上回る6.9Mt。 |
| 5月 5日 | アメリカの核実験キャッスル作戦ヤンキー実験実施。核出力はこれも想定を上回る13.5Mt。 |
| 5月14日 | アメリカの核実験キャッスル作戦ブラボー実験による漁民の被曝をアメリカ政府が認めなかったことや、アメリカ原子力委員会が広域海域で放射性物質の影響は薄まるという見解を受けて、水産庁主導で科学調査が始まる。科学者22人を乗せた水産講習所の練習船俊鶻丸が出港。 |
| 6月27日 | 社会主義政権となったグアテマラに対し、アメリカがPBサクセス作戦を実施。ホンジュラスからカスティージョ・アルマスの軍勢が首都へ侵攻。グスマン政権が崩壊する。グアテマラ内戦の始まり。 |
| 7月 4日 | 核実験海域調査の俊鶻丸が帰国。アメリカの説明とは異なり、海域で汚染が薄く拡散するわけではないことを確認。 |
| 7月21日 | J・R・R・トールキン作『指輪物語』第一部『旅の仲間』がイギリスで出版。ファンタジー作品に大きな影響を与えた。 |
| 7月23日 | キャセイパシフィック航空撃墜事件。バンコク発香港行のキャセイパシフィック航空ダグラスDC-4型機が、海南島沖を飛行中に、突如、中国人民解放軍のLa-11戦闘機2機に銃撃され、操縦不能となり海上に墜落。機体は大破し、乗客12名乗員6名のうち乗客8名と乗員2名の計10名が死亡。救助活動中に米中両軍の戦闘機による空中戦も起きる。のちに中共政府は賠償金支払いに応じたが、公海上空を飛行中の旅客機を何故攻撃したのかは不明。 |
| 8月16日 | 京都鴨川の花火大会で、花火の火が飛び火して京都御所内の小御所が炎上、焼失する。安政時代の造営で建てられた建物で、明治維新時の小御所会議の舞台となった場所。 |
| 8月 | 雑誌『アスタウンディング・サイエンスフィクション』にトム・ゴドウィンの『冷たい方程式』が掲載され、「多数の緊急避難のためには少数の命を犠牲にしてよいか」という賛否両論の大論争となる。いわゆる「方程式もの」と呼ばれる創作ジャンルが確立した。 |
| 9月 3日 | 神戸市内の麻雀店で山口組と谷崎組のメンバー同士が口論になったことがきっかけで、山口組若衆らが谷崎組若頭を襲撃、重症を負わせる抗争事件に発展。 |
| 9月14日 | ソビエトでトツコエ軍事演習が実施される。南ウラルのオレンブルク州トツコエにある核実験場で、兵士45000人が参加する演習中に、核出力40ktの原子爆弾RDS-4を投下。核爆発直後の爆心地付近を約3000人の兵士が横断し影響を受ける実験を行う。兵士への影響は不明。付近の集落の一部住民は移住を余儀なくされたともいう。 |
| 9月26日 | 洞爺丸台風が接近した北海道岩内郡岩内町で大火が発生。暴風が吹き荒れる中、次々と延焼していき、また漁港の燃料タンクに引火するなどして市街地の大半が焼け、3298戸が焼失。35名が死亡、3名が行方不明。16622人が被災した。 |
| 9月26日 | 洞爺丸事件。洞爺丸台風(台風15号)が通過した北海道で青函連絡船洞爺丸、北見丸、日高丸、十勝丸、第十一青函丸が転覆・沈没、岩内町で大火となるなど、死者・行方不明1761名。 |
| 9月29日 | 欧州原子核研究機構(CERN)が設立される。 |
| 10月 8日 | 内郷丸遭難事件。神奈川県津久井郡与瀬町(現相模原市)の相模湖で、遊覧船の内郷丸が沈没、中学生22名が死亡。遠足に来ていた麻布中学校の生徒と教師らが遊覧船に殺到し、全長12m・幅3mに満たない乗員2名・乗客定員19名の船に、教師2名と生徒75名が乗ったことで、その重みで浸水しそのまま沈没した。船舶も無許可で増設改造していたという。 |
| 11月 3日 | 『ゴジラ』の第一作が公開。第一次公開館だけで空前の961万人を動員する大ヒットとなる。 |
| 11月23日 | ニューヨーク株式市場が、1929年の大暴落以前の水準に戻る。 |
| 11月30日 | アメリカ・アラバマ州タラディーガ郡シラコーガに隕石が落下。その破片の1つがホッジス家の屋根を突き抜け屋内にいたアン・エリザベス・ホッジス夫人に当たる。人に直接当たったことが明確なのは、この例と2013年のチェリャビンスク隕石の例しかないが、この他に幾つかの記録が残っている。 |
| 12月 2日 | アメリカ上院でマッカーシーに対し不信任を決議し、アメリカで吹き荒れたマッカーシズム(赤狩り)が終息に向かう。 |
| 12月 9日 | もうひとりの「吉田茂」死去。首相と同姓同名でしばしば間違われた吉田茂は、内務省系の「革新官僚」出身で、戦時中は大臣も務め、戦後は神社本庁の設立に奔走した人物。 |
| 12月10日 | アメリカ空軍のホロマン基地で、MX-981プロジェクトの急減速実験が行われる。ジェット戦闘機の脱出用射出座席など、人体に急減速がかかるときの影響を調べたもので、プロジェクトリーダーのジョン・スタップ少佐自らロケットスレッドに乗り、時速632マイル(時速1017km)から急減速するテストを行う。スタップ少佐は負傷するも無事。なおこのプロジェクトに技術者として参加していたマーフィー大尉の発言が「マーフィーの法則」の原点とも言われる。 |
| 1938年に渋谷駅の脇に完成した4階建ての玉電ビルを増築して、11階建ての東急会館が完成。 | |
| 1955年(昭和30年) | |
| 1月 2日 | ナイロンザイル事件。前穂高岳東壁を登攀中の岩稜会の3人パーティの1人がナイロンザイルが切れて滑落し死亡。犠牲者の兄である石岡繁雄は、実験でナイロンザイルの弱点に気づく。 |
| 1月17日 | 原子力潜水艦ノーチラスの原子力航行に成功。 |
| 1月17日 | 中国人民解放軍が、浙江省沖合の中華民国(台湾)が領有する大陳列島の有力拠点一江山島攻略を開始。 |
| 1月18日 | 中国人民解放軍が、一江山島を攻略。隣接する大陳島も射程圏内に入ったため、中華民国政府は大陳島放棄を決定。これには米華相互防衛条約に同列島が入っていなかったこともある。 |
| 2月 6日 | 中華民国政府による大陳島撤退作戦(金剛計画)が開始。蒋介石の息子蒋経国自ら現地に入り、米軍の支援のもとで、揚陸艦や上陸用舟艇などを使い駐留軍と住民をすべて台湾に移す作戦。 |
| 2月11日 | 中華民国政府による大陳島撤退作戦が終了。軍民28000人が台湾へと移った。 |
| 2月18日 | アメリカの核実験ティーポット作戦が始まる。ワスプ実験(核出力1.2Kt)では核爆発直後の爆心地付近で陸軍兵士による作戦行動を検証するデザート・ロック演習が行われる。 |
| 2月28日 | 台湾独立運動をしていた廖文毅が、東京で台湾共和国臨時政府を立ち上げる。 |
| 3月24日 | 埼玉県のジョンソン基地(入間基地)を飛び立ったF-94戦闘機が、同県の名細村に墜落。墜落地点の傍にあった民家など4棟も炎上し、住人2名と乗員2名の計4名が死亡、5名が負傷。 |
| 3月25日 | F-8クルセイダー艦上戦闘機の試作機XF8Uが初飛行と超音速飛行に成功。世界初の超音速艦上戦闘機。F-8は高い運動性能と多用途性に優れていたため長期にわたって運用された。 |
| 4月10日 | 京都五番町事件。京都市の五番町にあった歓楽街で、男性が刺されて死亡する事件が発生。直前に男性と揉め事を起こした学生4人が逮捕され、拷問・脅迫を伴う取り調べで刺殺したと自白。さらに学生らが目撃した若い男と同じ人物を目撃した証言者まで、偽証罪で逮捕される。ところが、その目撃された若い男が凶器を持参して自首したために、少なくとも死因となった傷害と偽証は冤罪であったことが発覚。実際には、2つの傷害事件が偶然重なったもので、被害者は最初に若い男と揉め事を起こしたあと、今度は学生4人と揉め、そこから逃走中に最初の相手とふたたび遭遇して刺され、そこへ学生が駆けつけて暴行を加えたというもの。自白を強制する取り調べ方法が国会でも取り上げられる事態となった。 |
| 4月11日 | バートランド・ラッセルとアルベルト・アインシュタインが、核戦争による人類絶滅を危惧し、核兵器廃止を訴える宣言をまとめ、署名する。ラッセル=アインシュタイン宣言。 |
| 4月11日 | インドネシアのバンドン会議に向かう予定の周恩来を暗殺するため、乗機のカシミールプリセンス号に発火装置が仕掛けられ、南シナ海上空で装置が作動し炎上。機体は不時着水したが、乗員3名が助かったものの、他の乗員乗客16名は死亡。なお、周恩来は搭乗予定だったが虫垂炎のためキャンセルして難を逃れた。台湾の国民党政府が仕組んで、買収された香港の空港勤務者が装置を仕掛けたとされているが詳細は不明。 |
| 4月18日 | アジア・アフリカ会議が、インドネシアのバンドンで開催。通称バンドン会議。インド、インドネシア、パキスタン、セイロン、ビルマ、エジプト、中華人民共和国が主導した。欧米諸国の植民地主義から独立した非白人国家が招待され、インドネシアと友好関係にあった日本も招待された。 |
| 4月18日 | アルベルト・アインシュタイン死去。 |
| 4月29日 | ナイロンザイル事件で、メーカーが強度実験を行うが、実験用の岩の角を丸く工作して強度に問題はないとの結果を公表。滑落事故を起こした岩稜会の問題にすり替える。実験を日本山岳会の篠田軍治が指導したこともあって、日本山岳会はナイロンザイルの弱点を無視し続け、その後も犠牲者が相次ぐ(法整備までに20人が死亡したという)。 |
| 5月 5日 | アメリカの核実験ティーポット作戦アップル2実験が行われる。核戦争下の民間防衛の検証のため、実験場の砂漠に都市を作り、様々な種類の住宅や店舗、変電設備などを建て、マネキンを多数設置し、服の種類や缶詰に至るまで、核爆発の影響を調べた実験。 |
| 5月11日 | 瀬戸内海の宇高連絡船だった紫雲丸と第三宇高丸が衝突し、紫雲丸が沈没。168人が死亡。第五次紫雲丸事故。 |
| 5月14日 | アメリカの核実験ウィグワム作戦をカリフォルニア州サンディエゴの沖合で実施。1946年のクロスロード作戦で中止になったチャーリー実験と同じ水中核爆発実験。核爆雷の検証実験でもある。 |
| 5月25日 | 広辞苑初版発行。辞苑の改訂版国語辞典だが、出版社は博文館から岩波書店に変更され、改めて出版された。 |
| 5月26日 | 宮崎県椎葉村の耳川に上椎葉ダムが完成。アーチ式では初めての高さ100mを超す大型ダムで、戦後の大型土木工事のモデルとなった。総工費130億円(当時)、工事関係者は述べ500万人、死者105人、建設地は道路が未整備の九州山地の奥部であるため、南延岡から現地まで資材輸送用の超長距離ロープウェーまで建設された。ダム湖は吉川英治によって「日向椎葉湖」と命名されている。 |
| 5月 | キューバのバティスタ政権が、恩赦で政治犯を釈放する。カストロ兄弟らも釈放され、メキシコへ亡命。 |
| 6月11日 | ル・マン24時間レースが行われていたサルト・サーキットで大事故。選手、観客やスタッフら86人が死亡、200人以上が重軽傷。各国で自動車レースが中止や禁止になる。 |
| 7月 9日 | ラッセル=アインシュタイン宣言が発表される。ほかに9人の科学者が署名。 |
| 7月27日 | 日本共産党第6回全国協議会開催。徳田球一の死去を受け、その指示のもとで進められていた「農村から都市を包囲する」という中国式革命路線が「極左軍事冒険主義」として否定され、「平和革命路線」が採択される(暴力革命を放棄した訳では無い)。もっともこの時点で山村工作隊など武装方針は市民に受け入れられず完全に失敗に終わっている。宮本顕治らが党内権力を奪還。一方、方針転換に反発した山村工作隊関係者、学生らは、新左翼を結成していく。 |
| 8月 1日 | 東京都墨田区厩橋の花火問屋・井上花火店の工場で火災が発生し大爆発。14名が死亡し、80名以上が負傷、13棟が全焼し周囲300mの建物に大きな被害を出す。 |
| 9月 3日 | 由美子ちゃん事件。米国占領下の沖縄嘉手納村で、6歳の幼稚園児が、嘉手納基地所属のハート軍曹によって拉致され強姦された上に殺害、遺体を切り裂かれた事件。遺体は米兵によって発見され通報。米陸軍捜査機関と琉球警察の合同捜査で、目撃者などの証言からハート軍曹が逮捕される。沖縄では特に凶悪事件として知られ、反米・反基地闘争が激化するきっかけとなった。現在でも沖縄で類似する強姦事件などの度にこの事件の話が出る。のちに軍法会議と軍事上訴裁判所で被告に死刑判決。アイゼンハワー大統領による異例の減刑採決に米軍法務部が抗議。さらにフォード大統領によって釈放された。同時期に起きた黒人兵による類似事件と比較されて白人に対する恩赦措置と評されている。 |
| 9月13日 | 砂川事件。米軍立川基地の滑走路拡張問題で、延長路上にあった砂川村の住民と学生や労働団体が、拡張に反対して、測量を警備していた警官隊と衝突。 |
| 9月16日 | 万国著作権条約が発効。 |
| 9月 | アメリカの原子力飛行機計画「MX1589計画」の試験航空機X-6の事前テスト機であるNB-36Hの飛行試験が始まる。X-6は吸気した外気を原子炉の熱で高温に熱し、後方へ噴射する仕組みだが、NB-36Hは、爆撃機B-36を改造して原子炉を搭載し、機内で稼働する試験を行ったもので動力には使われていない。冷却水放出などでの汚染を調べるためのB-50が随伴飛行した。1957年まで飛行試験を47回行ったが放射線遮蔽のための防護設備などで異常に重くなり、安全性と実用性・コスト面で疑問がついたため、開発は中止となった。 |
| 10月 1日 | アメリカ戦後空母第一世代で最初の超大型空母フォレスタルが就役。艦名は超大型空母部隊を計画しながら自殺に至った初代国防長官ジェームズ・フォレスタルから採用。 |
| 10月 9日 | 立川基地を離陸したB-26爆撃機が日野町に墜落。付近の民家5棟も炎上。住民に犠牲者は出なかったが乗員2名が死亡。 |
| 10月10日 | 焼失した金閣寺が再建され、落慶法要が行われる。再建では焼失前の姿ではなく、創建当時の姿を模して設計された。 |
| 10月25日 | スウェーデン国産の要撃戦闘機サーブ35ドラケンが初飛行。世界初のダブルデルタ翼の実用機。フィンランドとデンマークにも輸出され、オーストリアも中古機を購入。 |
| 10月26日 | フランスの傀儡国家ベトナム国の首相であったゴ・ディン・ジエムが国民投票で大統領に就任し、ベトナム共和国(南ベトナム)が成立。 |
| 10月 | 桜島南岳山頂火口で爆発噴火。死者1名、負傷者11名。南岳山頂付近は立ち入り禁止となる。 |
| 10月 | ファッションデザイナーのマリー・クヮントと夫のアレグザンダー・プランケット=グリーンが、ロンドンのキングスロードにショップ「バザー」を開店。ミニスカートブームなど流行の発信源となった。 |
| 11月15日 | 保守合同による自由民主党結党。合同を推進した緒方竹虎、鳩山一郎、三木武吉、大野伴睦が総裁代行委員となる。 |
| 11月29日 | アメリカアイダホ州のEBR-1原子炉で操作ミスにより炉心溶融事故が起きる。同原子炉は世界で初めて原子力発電に成功した施設。 |
| 1956年(昭和31年) | |
| 1月 1日 | 新潟県弥彦村の弥彦神社で参拝客が将棋倒し事故。死者124人・重軽傷者77人を出す。 |
| 1月 1日 | 英埃領スーダンがイギリス・エジプト共同統治領から独立。スーダン共和国となる。 |
| 1月 9日 | 世界で最も生産されたソ連の超音速戦闘機MiG-21の直接の原型試作機Ye-5が初飛行。MiG-21は1万機以上生産され、東欧、アジア、アフリカ各国に輸出された。各国でも改良されており、21世紀現在でも現役の機体は多い。 |
| 1月28日 | 日本、万国著作権条約を批准し関連法を公布。ベルヌ条約に加盟している著作権無登録認可(無方式主義)の国と、それ以外の著作権登録制度の国との権利保護を、©+著作権者名+年号表記によって連携させるための条約。 |
| 1月28日 | 緒方竹虎急死。元朝日新聞社副社長で、小磯内閣で政界入りし、吉田内閣副総理も努め、戦後の保守合同の立役者となったが、自民党の初代総裁就任目前(つまりは首相就任目前)にして心臓疾患により急逝した。緒方の急死はその後の歴代自民党政権にも影響したといわれる。 |
| 2月 2日 | 宝塚線庄内駅乗客通せんぼ事件。沿線人口増加に車両の対応が追いつかずにいた阪急宝塚線で、車両故障に遭った乗客1000人が、約束された臨時列車が来ないことに腹を立て、後続列車の前に立ちふさがるなどの騒動に発展。阪急が代替バスを、警察が警察車両を使って輸送したことなどの結果収まる。阪急は宝塚線に大型車両の導入を進めることに。 |
| 2月 9日 | スターリン時代の大粛清を調査していたポスペーロフ委員会の報告がソ連共産党中央委員会幹部会に対して行われる。その内容の大きさに、これを共産党大会で報告するか問題となる。 |
| 2月14日 | ソ連共産党第20回大会開会。幹部らによる、暗にスターリンを対象とした個人崇拝を否定する演説が次々と行われ、フルシチョフ体制による「スターリン批判」がはじまる。 |
| 2月25日 | ソ連共産党幹部らに対するフルシチョフ報告の秘密会が行われ、スターリンの大粛清を始めとする一連のスターリン時代の問題が内々に公開される。一般向けには公表されず、各国共産党の代表にだけ順次公開されることとなった。これがハンガリー動乱や北朝鮮内部の反金日成運動へと発展することになる。なお、日本共産党は報告公表の対象になっていないが、この内容が伝わると、反発や混乱が起き、同じくフルシチョフに反発した中国共産党と接近することになる一方、一部党員は日本共産党を離れ新左翼組織結成へと繋がっていく。 |
| 3月 2日 | モロッコがフランスから独立。 |
| 3月 7日 | 金閣寺を放火した林承賢が肺結核で病死。 |
| 3月20日 | チュニジア王国がフランスから独立。国王にムハンマド8世アル・アミーン、ハビーブ・ブルギーバが首相に就任。 |
| 4月 5日 | 自由民主党総裁選挙で鳩山一郎が初代総裁となる。 |
| 4月19日 | モナコ大公レーニエ3世と女優グレース・ケリーとの結婚式がサン・ニコラ大聖堂で行われる。 |
| 4月21日 | 東ベルリンの地下に掘られた、西側の電話盗聴用トンネルをソビエト軍と東ドイツ軍が急襲。ソビエトは掘削前から西側のトンネル掘削作戦「金工作」の情報を得ていたが、英国MI6に入っていた二重スパイジョージ・ブレイクの存在が発覚しないよう、黙認していたとされる。 |
| 5月 1日 | 熊本県水俣市の保健所へ、新日本窒素附属病院の細川一医師から「原因不明の奇病」の報告があり、保健所が公表。水俣病が世間に知られるきっかけとなる。 |
| 5月 4日 | アメリカの核実験レッドウィング作戦が始まる。実用的な熱核兵器(水素爆弾)の検証実験で、水爆を起爆させるプライマリー原爆の実験も含まれる。 |
| 5月20日 | 核実験レッドウィング作戦チェロキー実験で、航空機から投下する初の水素爆弾実験がビキニ環礁で行われる。核出力3.8Mt。 |
| 5月27日 | 核実験レッドウィング作戦ズニ実験で、初の三段階式水素爆弾実験がビキニ環礁で行われる。核出力3.5Mt。 |
| 6月30日 | アメリカアリゾナ州のグランドキャニオン上空で、トランス・ワールド航空2便のスーパーコンステレーションと、ユナイテッド航空718便のDC-7の2機のレシプロ大型旅客機同士が空中衝突。乗員乗客128人全員が死亡。航空管制が曖昧だったことで飛行コースが重なったことが原因とみられる。管制システムを導入するきっかけとなった。 |
| 7月10日 | 核実験レッドウィング作戦ナバホ実験で、核反応のうち95%が核融合という最も純粋水爆に近い実験が行われる。核出力4.5Mt。 |
| 7月20日 | 核実験レッドウィング作戦テワ実験で、核反応のうち87%が核分裂というナバホ実験とは逆の水爆としては汚染の大きい実験が行われる。核出力5Mt。 |
| 8月 7日 | カリ爆発事件。コロンビアのカリ市で1053箱のダイナマイトを積んだ軍用トラック7台が駅前に駐車していたところ、早朝に大爆発を起こし次々と誘爆。市街地に大きな被害をもたらす。すぐそばの兵舎にいた兵士500人を含む死者は少なくとも1300人以上、負傷者は4000人以上という大惨事となる。トラックはブエナベントゥラから来たもので、13台は首都のボゴダへそのまま向かい、7台が残っていた。グスタボ・ロハス・ピニージャ大統領はテロの可能性を指摘したが、エンジンの加熱説、兵士による誤射説などがある。 |
| 8月20日 | 原子力潜水艦シーウルフ、繋留状態で全力運転中に冷却材漏出事故を起こす。 |
| 8月30日 | 8月宗派事件。朝鮮労働党中央委員会全体会議で朝鮮労働党延安派・ソ連派のメンバーが金日成の独裁体制を批判。しかし逆に金日成の反撃で失脚する。両派のほとんどが後に粛清された。延安派は中国共産党の有力者彭徳懐が支持していた。 |
| 9月 1日 | 政令指定都市制度施行。戦時中の1都5大都市制を受け継いで、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市が政令指定都市と定められる。 |
| 10月17日 | 映画『八十日間世界一周』公開。原作はジュール・ベルヌの同名小説。80日間で世界一周出来るかを賭ける冒険ストーリー。多数の著名俳優がカメオ出演している。 |
| 10月19日 | 日ソ共同宣言がモスクワで調印。 |
| 10月23日 | ハンガリー動乱。ハンガリーで民衆の自由を求める運動にソ連軍が介入。大勢の市民が殺害される。市民1万7000人が死亡し、20万人が難民となって国外へ出る。日本では日本共産党や日本社会党にソ連の武力侵攻を支持する意見も出て論争になる。 |
| 10月28日 | 大阪に二代目通天閣が完成。 |
| 10月31日 | アメリカ海軍のジョージ・J・デュフェク少将が、輸送機R4D-5 スカイトレインで南極点に降り立つ。アムンゼン、スコット以来。 |
| 10月 | ロバート・A・ハインラインの小説『夏への扉』が雑誌『ザ・マガジン・オヴ・ファンタジイ・アンド・サイエンス・フィクション』に連載が始まる。翌年ハードカバー版が刊行。タイムトラベルSFの代表作の一つ。猫小説としても人気が高い作品。 |
| 11月 8日 | 日本初の第1次南極観測隊(南極地域観測予備隊)を乗せた南極観測船「宗谷」が東京港を出発。 |
| 11月25日 | カストロら「7月26日運動」のメンバー82人が、亡命先のメキシコからヨット・グランマ号で出港。 |
| 12月 2日 | カストロらが、ヨット・グランマ号でキューバに戻る。バティスタ政権の待ち伏せ攻撃で12人にまで減るも、以後、ゲリラ戦を展開して徐々に勢力を拡大する。 |
| 12月26日 | シベリア抑留者の最後の引揚船「興安丸」が舞鶴港に入港。 |
| 1957年(昭和32年) | |
| 1月29日 | 日本初の第1次南極観測隊(南極地域観測予備隊)が、南極の東オングル島プリンスハラルド海岸に上陸、昭和基地と命名。 |
| 2月12日 | アメリカのロスアラモス国立研究所にある臨界集合体ゴディバⅠで臨界事故が発生。装置が破損したため廃棄され、ゴディバⅡへ切り替えられる。臨界集合体は原子炉研究用の低出力実験装置のこと。ゴディバは放射線遮蔽シールドがなかったため、「裸」という意味でゴディバ夫人の名をとって名付けられた。 |
| 3月 6日 | イギリス領ゴールドコーストとイギリス領トーゴランドが統合の上で、ガーナとしてイギリスから独立。近代ブラックアフリカ最初の独立国。初代大統領は汎アフリカ主義でアフリカ合衆国構想を打ち立てたことで知られるクワメ・ンクルマ。 |
| 3月13日 | 猥褻か表現の自由かを問われた『チャタレイ夫人の恋人』の日本語訳をめぐって、出版社社長小山久二郎と作品を翻訳した伊藤整の罰金刑が確定する(「チャタレー事件」)。 |
| 4月 1日 | 暴力団山口組が興行部を法人化し、芸能興行会社「神戸芸能社」を設立。社長は山口組三代目田岡一雄組長。美空ひばりが所属していたほか、著名な芸能人の興行に関わる。 |
| 5月15日 | イギリス軍がキリバスのキリスィマスィ島で初の水爆実験グラップル作戦を行う。最初のグリーン・グラナイト実験は核出力が300Ktと予想をかなり下回っている。 |
| 5月15日 | ソ連が開発した世界初の大陸間弾道ミサイルR-7の最初の試験が行われる。ミサイルは安定飛行に失敗し空中で爆破。 |
| 5月28日 | 10月7日まで、アメリカ・ネバダ実験場で核実験プラムボブ作戦がはじまる。29回の実験が行われ、小型核兵器の性能実験、構造物に対する影響実験、生物への影響実験、兵士への心理実験、偶発事故による核爆発を防ぐ安全性検証実験、初の地下核実験などが行われ、18000人の兵士が被験者として参加した他、膨大な量の放射性物質が大気圏内に放出される。 |
| 6月 5日 | 沖縄にアメリカ政府の代表機関、琉球列島高等弁務官が設置される。 |
| 7月13日 | アメリカ軍は、超長距離巡航ミサイルSM-64と、その試験機であるX-10の開発計画を中止する。アトラス大陸間弾道ミサイルの開発が順調に進んだため。SM-64は最大射程1万kmにもなる核弾頭搭載型巡航ミサイル。 |
| 7月25日 | チュニジアでハビーブ・ブルギーバ首相が、王制を廃止し、ムハンマド8世アル・アミーンは失脚。ブルギーバが大統領となり共和制に移行。 |
| 8月 3日 | 米軍機母子殺傷事件。アメリカ空軍水戸補助飛行場で離陸した米軍機が低空飛行し、歩いていた親子に接触して殺傷する。 |
| 8月21日 | ソ連が世界で初めて開発した大陸間弾道ミサイルR-7(セミョールカ)の4回目の飛行試験でバイコヌールからカムチャツカ半島への6000kmの弾道飛行に成功。隠密性がなく燃料の維持もできないなど緊急時の実用性には乏しかったが、大陸を越えての直接攻撃が現実味を帯びた。また多くのロケットの基礎ともなった。 |
| 8月27日 | 日本初の原子炉JRR-1が臨界に達する。 |
| 8月31日 | マラヤ連邦(現在のマレーシアの大部分)が英連邦に所属する形でイギリスから独立。独立を運動したトゥンク・アブドゥル・ラーマンが首相に就任。 |
| 9月 1日 | ムッソリーニの遺体が正式に故郷プレダッピオに埋葬される。イタリアでは現代に至るまでムッソリーニを好意的に見る人も多い。国家ファシスト党の後継政党も存続している。またレーニンやチャーチルもムッソリーニを高く評価していた。一方で戦後はファシズムの原点を作った人物、ヒトラーと手を組んだ人物として批判されている。 |
| 9月20日 | 初の国産観測用ロケット「カッパ4C型」が打上げられる。成層圏を観測するためのロケット。目標には到達しなかったが、以降の国産ロケットの原点となった機体の一つ。 |
| 9月22日 | 南大西洋で、西ドイツの大型帆船パミール号がハリケーンに遭遇し沈没。乗員と実習生など80人が死亡。生存者は6人のみ。パミールは当時現存していた数少ない大型商用帆船の一隻で、戦前フィンランドのグスタフ・エリクソン船団に所属した後、戦時中はニュージーランドが接収し太平洋で輸送船として使用、戦後西ドイツが購入して貨物輸送兼訓練用に使われていた。 |
| 9月29日 | ウラル核惨事。ソ連の核開発秘密都市チェリヤビンスク65で放射性廃棄物タンクの冷却装置が故障し、放射性物質の崩壊熱によって高温になった結果、タンクが爆発、放射性物質が広範囲に飛散。付近にいた1000人以上が被曝し、幅約9km、長さ105kmの地域が汚染され、住民1万人が退去した。 |
| 9月30日 | サンマリノ共和国でロヴェレータ事件が勃発。共産主義政府が「執政」(大評議会議員から選ばれる国家元首で定員2名)の選挙に絡んで強硬姿勢を取ったのに対し、大評議会の野党ら反共勢力がクーデターを起こしロヴェレータ村に臨時政府を樹立した事件。イタリア、アメリカ、フランスなどが臨時政府を承認。政府と臨時政府は武装して対立。 |
| 10月 1日 | 西ドイツで、サリドマイド入り睡眠薬「コンテルガン」が発売される。各国でも同様の睡眠薬が順次発売されていくが、のちに催奇性があることがわかり世界規模の薬害を引き起こす。一方でサリドマイドは腫瘍やハンセン病の治療薬としては有効なため、現在でも治療薬としては販売されている。 |
| 10月 1日 | 売春汚職事件発覚。安藤恒新宿カフェー喫茶協同組合理事長の業務上横領被疑事件を取調べていた検察が、赤線業の業界団体である全国性病予防自治連合会の横領容疑、さらに売春防止法の阻止を意図した政治家への贈賄疑惑が浮上。 |
| 10月 4日 | 世界初の人工衛星スプートニク1号が打ち上げられ、世界に大きな衝撃(スプートニク・ショック)を与える。ソ連の先駆的ロケット研究者ツィオルコフスキーの生誕100年を記念して行われた。打ち上げに使われたロケットは直前に成功した大陸間弾道ミサイルR-7の改良型。 |
| 10月10日 | イギリスウィンズケール原子炉火災事故。カンブリア州シースケール近郊にある原爆用核燃料製造用施設(発電所ではない)にある空冷型原子炉で火災が発生。 |
| 10月11日 | ウィンズケール原子炉火災で、現場に残った副所長トーマス・トゥーイの対応で送風停止と注水により消火には成功するが燃料棒は溶解。放射性物質は外部へ放出された。ただチェルノブイリや福島第一の事故と比べるとかなり少ない。少なくとも14人が被爆。事故原因は水爆用三重水素増産のための安全性を軽視した設計変更により高温と化した炉心が発火したものと言われる。イギリス政府は水爆製造に関する無理な増産を隠すため、所員の運転ミスと発表し、所員は世間の批判にさらされた。また周辺の広い地域で生産された牛乳はすべて廃棄処分となっている。 |
| 10月11日 | サンマリノ共和国のロヴェレータ事件で、「執政」がロヴェレータ臨時政府を承認して終息し、無血で政権交代となる(その後総選挙を実施)。 |
| 10月18日 | 読売新聞が売春汚職事件に絡んで、宇都宮徳馬・福田篤康両議院の収賄容疑を報道。これが検察情報リークを調べる意図的な偽情報だったため、読売新聞の立松和博記者に対する名誉毀損、さらに検察内部の対立抗争にまで発展する事態に。 |
| 11月18日 | 文化放送、ニッポン放送、東宝、松竹、大映が、フジテレビを設立する。 |
| 12月 6日 | アメリカ、ヴァンガードロケットによる初の人工衛星打ち上げに失敗。点火直後に発射台で大爆発を起こす。スプートニクにかけて「カプートニク(壊れた衛星)」などと称される。 |
| 12月10日 | 天城山で、愛新覚羅慧生と学習院級友の大久保武道のピストル心中遺体が発見される。二人を乗せたタクシー運転手などの証言から、慧生に死ぬ意図はなく、大久保による一方的な殺害(無理心中)という説もある。 |
| 1958年(昭和33年) | |
| 1月20日 | 日本でもサリドマイドの発売が始まる。 |
| 1月31日 | アメリカが人工衛星エクスプローラー1号の打ち上げに成功する。ヴァンガードロケットではなく、陸軍弾道ミサイル局に所属していたフォン・ブラウンが開発に関わったジュノーⅠロケット。 |
| 2月 1日 | エジプトとシリアが「アラブ連合共和国」を樹立。 |
| 2月14日 | 第二次南極観測隊の越冬隊を載せた宗谷が悪天候で接岸できず、第一次越冬隊員はかろうじて小型機とヘリで昭和基地を脱出。メス犬1匹と子犬らを運ぶことはできたものの、15頭の樺太犬は鎖につないだまま取り残される。 |
| 2月24日 | 第二次南極観測隊の越冬を断念。帰国することになり、15頭の樺太犬は鎖につないだまま置いていくことになる。 |
| 3月 3日 | 富士重工業が軽自動車スバル360を発表。はじめて軽自動車で成功をおさめる。 |
| 3月 5日 | アメリカ大統領科学技術諮問委員会委員長ジェームズ・キリアンが、アイゼンハワー大統領に書簡を送り、民間宇宙計画のための文民統制された国家宇宙機関として、国家航空宇宙諮問委員会(NACA)の大幅拡張を進言。 |
| 4月 5日 | カナダのセイモア海峡にある岩山リップルウッドが、複雑な海流を生み、船舶事故の元になっているとして、大量の爆薬で吹き飛ばされる。 |
| 4月28日 | アメリカの核実験ハードタックⅠ作戦が太平洋核実験場で始まる。実験休止期間に新たにデザインされた核兵器の検証実験。 |
| 4月 | インドネシア北スラウェシ州でペルメスタの反乱。反乱を支援したCIAが武力介入を行い問題に。 |
| 6月16日 | ハンガリー動乱時の首相だったナジ・イムレがKGBの秘密裁判の上で処刑される。 |
| 6月24日 | 阿蘇山中岳第一火口が噴火。死者12名、負傷者28名。 |
| 6月28日 | アメリカ軍の核実験ハードタックⅠ作戦オーク実験がエニウェトク環礁で行われる。核出力8.9Mt。 |
| 7月 9日 | アメリカアラスカ州のリツヤ湾で、地震により山体崩壊が発生。土砂が湾内に流れ落ちて津波が発生し、波は湾の沿岸の高さ524mに到達する。漁船1隻が遭難して2人が死亡。人類が観測記録した中で、もっとも大きな津波。 |
| 7月12日 | アメリカ軍の核実験ハードタックⅠ作戦ポプラ実験がビキニ環礁で行われる。核出力9.3Mt。 |
| 7月14日 | イラクで軍がクーデターを起こし、国王ファイサル2世と摂政アブドゥル=イラーフらを処刑。 |
| 7月29日 | アイゼンハワー大統領が国家航空宇宙決議に署名し、国家航空宇宙諮問委員会(NACA)が発展的解消をして、アメリカ航空宇宙局(NASA)が発足。10月1日より活動を開始する。 |
| 8月 1日 | アメリカ軍の核実験ハードタックⅠ作戦ティーク実験がジョンストン島上空75.6kmで行われる。核出力3.8Mt。大規模な電磁パルスが発生し、電気設備や電子機器などが甚大な被害を受ける。 |
| 8月 1日 | 本田技研工業の小型オートバイ「スーパーカブC100」発売。マイナーチェンジを繰り返しながら超ロングセラー製品となる。全世界で累計1億台以上売られている。 |
| 8月 3日 | 原子力潜水艦ノーチラス、浮上せずに北極点通過に成功。 |
| 8月23日 | 中国人民解放軍が、福建省沿岸沖合に残っている中華民国(台湾)の領土、金門島を攻略すべく、激しい砲撃を加える。いわゆる「金門砲戦」。金門島側に死傷者440名以上を出す。 |
| 8月24日 | 「金門砲戦」を受け、アメリカ政府が中華民国側支援に乗り出し、空母7隻を台湾海峡へ派遣。また厦門核攻撃の準備を整える(大統領の攻撃承認はなかった)。 |
| 8月25日 | 日清食品創業者の安藤百福が世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」を発売。 |
| 8月27日 | アメリカの核実験アーガス作戦が始まる。他の核実験より秘密性の高い作戦で、南アフリカの沖合1800kmの南大西洋に派遣された空母タラワなどの艦艇が参加。小型核弾頭搭載のX-17ミサイルを3基打ち上げ、高度200kmから500kmの宇宙空間で核爆発を行い、大気圏上層で敵ミサイル弾頭にダメージを与える「放射能帯」を作れるか確認する実験。放射能帯はできたがすぐに消滅したため、膨大な数の核爆発が必要と判明し、この計画は中止となった。 |
| 8月 | 中国で毛沢東主導のもと、大躍進政策が開始される。非科学的でノルマ主義な増産運動により、森林破壊、農機具の不足、蝗害を招き、農地が荒廃し、大規模な飢餓を引き起こして、数年で2000万~5000万人が死ぬ大惨事となる。 |
| 9月 2日 | 九二海戦。金門砲戦にからんで、中華民国海軍と中国人民解放軍海軍の艦艇同士が料羅湾で戦闘。両軍とも自軍の勝利を主張しているため、戦果ははっきりしていない。 |
| 9月12日 | アメリカの核実験ハードタックⅡ作戦の実験がネバダ核実験場で始まる。極低出力の地下核実験及び安全性確認テストのための実験。 |
| 9月16日 | 沖縄での公式通貨を軍票の一種であるB円から米ドルに切り替える。 |
| 9月26日 | 狩野川台風(台風22号)が伊豆半島近海を通過。大豪雨となり、伊豆半島の狩野川流域で氾濫・土砂崩れが多発。死者行方不明者は1269名。 |
| 10月 2日 | ギニアがフランスより独立。 |
| 10月 5日 | 中華人民共和国が、金門島砲戦を一方的に停止。 |
| 10月 7日 | アメリカの有人宇宙飛行計画「マーキュリー計画」が正式にスタートする。 |
| 10月18日 | アメリカからフラフープが輸入され発売。爆発的なブームが起こる。 |
| 10月28日 | 中華人民共和国側が、金門島への砲撃を隔日にすると一方的に発表。以後は、毎週月・水・金曜日に炸薬のない砲弾(宣伝ビラなどが入ったもの)を、無人地区に向けて撃つ程度となり、実質戦闘は終息。中ソの関係悪化や、アメリカの核攻撃計画で最悪の事態を恐れたソ連の圧力などもあったと見られる。1979年11月の米中国交樹立で正式に金門島攻撃は終了した。 |
| 11月 7日 | 呪いの伝説があるホープダイヤモンドがスミソニアン協会に寄贈される。 |
| 11月22日 | フラフープのやり過ぎで「胃に穴が開いた」「腸捻転を起こした」という噂が広がり、千葉県東金市の小学校でフラフープが禁止される。フラフープが体に悪いというのは噂に過ぎず、実際には医学的に問題はない。 |
| 11月23日 | 全アフリカ人民会議開催。アフリカ合衆国構想が提案される。 |
| 11月27日 | 宮内庁が皇太子・明仁親王と正田美智子の婚約を発表。ミッチーブームが始まる。 |
| 12月30日 | ロスアラモス研究所にてセシル・ケリー臨界事故が発生する。プルトニウムを精製する際に、溶剤に投入するプルトニウムの量を誤って、大量に投入撹拌してしまった担当者のセシル・ケリーが、直後に起こった核分裂臨界反応によって被曝。35時間後に死亡した。 |
| 1959年(昭和34年) | |
| 1月14日 | タロとジロの生存確認。南極に取り残されていた第1次越冬隊の樺太犬15頭のうち2頭。首輪抜けをし、アザラシやペンギンを食べて生き延びていた。他に6頭が首輪を抜けていたが、行方不明。7頭は鎖につながれたまま死亡。海に水葬処分された。 |
| 2月 3日 | アメリカン航空320便墜落事故。シカゴ・ミッドウェイ空港発、ニューヨーク・ラガーディア空港行ロッキード L-188エレクトラが、イースト川に墜落。乗員乗客73人中65人が死亡。通常より低い高度で着陸を行い滑走路手前の川に墜落したもので、操縦ミスとされている。植物学者で光合成のエマーソン効果を発見したロバート・エマーソン・イリノイ大学教授も死亡している。 |
| 2月 6日 | タイタンIのテスト飛行が行われる。アメリカ合衆国が初めて開発し導入した多段式大陸間弾道ミサイル(ICBM)で、発射サイロから発射する最初のミサイルでもある。 |
| 2月26日 | インパール作戦で兵士を救うために上官の命令を無視して撤退し、戦後批判された佐藤幸徳中将が病死する。 |
| 3月 9日 | ニューヨークで開催された国際おもちゃフェアで、マテル社がバービー人形を発表。 |
| 3月15日 | 地下鉄丸ノ内線のうち、霞ケ関-新宿間が開業し、「荻窪線」を除く全線開通。 |
| 3月17日 | 講談社から「週刊少年マガジン」が、小学館から「週刊少年サンデー」が創刊される。 |
| 4月30日 | 小説家永井荷風が千葉県市川市の自宅で死亡しているのを、通いのお手伝いさんが発見。当日に胃潰瘍で大量吐血したのが直接の死因と見られる。永井荷風の日記『断腸亭日乗』は前日まで記載がある。 |
| 4月 | ダニエル・キイスの小説『アルジャーノンに花束を』(中編版)が雑誌『ファンタジイ・アンド・サイエンス・フィクション』に掲載される。 |
| 5月 1日 | メリーランド州グリーンベルトにNASAの衛星の管制を担当するゴダード宇宙飛行センターが設立される。先駆者だったロバート・ゴダードがようやく評価され、彼の名を冠することとなった。 |
| 5月26日 | 西ドイツのミュンヘンにて開催されたIOC総会で、第18回夏季オリンピック東京大会の開催が決定。 |
| 5月29日 | 長野県下伊那郡上郷村の内山煙火製造所で、打ち上げ花火用の花火玉を製造中に爆発。爆風によって工場内の作業場、火薬庫、経営者宅が全壊し、周囲の民家など15棟も全半壊。百数十棟で窓ガラスが割れるなどした。従業員6名と、近くの浜井場小学校の校庭で体操授業を受けていて吹き飛ばされた児童のうち女児1名が死亡、重軽傷者266名を出す。 |
| 6月 8日 | 硫黄鳥島が噴火。残っていた住民全員の那覇や久米島などへの移住が決まり、硫黄鉱山を除いて無人化。 |
| 6月10日 | 国立西洋美術館開館。松方コレクションを展示。 |
| 6月30日 | 嘉手納基地を飛び立ったアメリカ空軍の戦闘機F100Dが、エンジン故障で市街地に墜落。宮森小学校に激突して炎上し、死者17人、重軽傷者210人を出す。 |
| 7月 2日 | 中国で廬山会議がはじまる。大躍進政策の修正を行うはずが政治闘争と化し、彭徳懐ら多数が失脚。 |
| 7月13日 | アメリカカリフォルニア州シミバレーのサンタスザーナフィールド研究所で、原子炉の冷却不能事故から一部の燃料棒が溶融し、2週間に渡って膨大な量の放射性物質が大気中に漏洩する事故が起こる。大規模な放射性物質漏洩事故だが、詳細は不明。 |
| 7月24日 | キッチン討論。ソビエトのモスクワで開かれたアメリカ博覧会の会場に置かれたアメリカ住宅のキッチンで、フルシチョフソ連共産党第一書記とニクソン米副大統領が資本主義と共産主義の利点と欠点について討論。ニクソンが庶民に電化製品が普及したことをアピールしたのに対し、フルシチョフは人工衛星や原爆開発を誇ろうとした。 |
| 7月30日 | 小型軽量の超音速戦闘機F-5が初飛行。運動性能の高さの割に操縦しやすく運用コストが安いことから、世界中の中進国・途上国で採用された。そのため改良派生型も多数存在する。姉妹機のT-38超音速練習機も世界中で採用されている。日本では防衛庁官房長の海原治が自衛隊役立たず論を展開し戦闘機はF-5で十分と主張したことがある。 |
| 7月31日 | スペインのバスク地方の分離独立を目指す民族組織「バスク祖国と自由」が結成される。 |
| 8月21日 | ハワイ準州がアメリカ50番目の州として昇格。 |
| 9月12日 | ソビエトの原子力砕氷船レーニンが竣工。 |
| 9月24日 | 藤沢飛行場に米軍の偵察機U-2が緊急不時着。米軍が日本人市民の目撃者調査を行う騒ぎとなる(黒いジェット機事件)。 |
| 9月26日 | 伊勢湾台風(台風15号)が上陸、大規模な高潮と暴風で、名古屋市を中心に死者行方不明者5098人。 |
| 10月 7日 | ソ連の無人月探査機「ルナ3号」が世界で初めて月の裏側を撮影。 |
| 10月 | ウォルター・M・ミラー・ジュニアの小説『黙示録3174年』(リーボウィッツ賛歌)が発売。 |
| 11月 5日 | ロバート・A・ハインラインの小説『宇宙の戦士』が発売。未来を舞台に宇宙陸軍に入隊した若者の成長を描いた内容だが、独自色の強い軍国主義体制を肯定的に描いたことで賛否両論となった。映画『スターシップ・トゥルーパーズ』の原作。 |
| 11月18日 | 映画『ベン・ハー』公開。ルー・ウォーレスの小説の3度めの映画化。ローマ帝国時代を舞台にユダヤ人青年ベン・ハーの波乱の人生と、キリストを絡めて描いた作品。アカデミー賞で最多の11部門で受賞。 |
| 11月20日 | 東洋化工横浜工場でTNT火薬の脱色精製試験中に火災が起き、溶融釜内の約450kgの火薬が爆発、さらに1.5トンの精製前TNTに誘爆し、従業員3名が死亡、従業員や付近の住民、付近の小中高校及び大学の学生生徒、京浜急行の乗客ら少なくとも386名が重軽傷を負う。火災現場そばに貯蔵されていた200tの火薬には、消防隊の消火活動で延焼せずに済んだ。 |
| 12月 2日 | フランスのマルパッセダムが崩壊。ダム湖の水が下流へ落ち、マルパッセ村とボゾン村が飲み込まれ死者421名を出す惨事となる。同ダムはアーチ式で、完成して初めて満水状態になった際に、その圧力に耐えられなくなったアーチ左側の岩盤が押し崩れてダム全体も決壊した。評価計算を甘く見た結果であった(アーチ式ダムはアーチの左右の岸で水圧に耐える構造になっている)。 |
| 12月 4日 | 清朝のラストエンペラー愛新覚羅溥儀が、劉少奇国家主席の特赦令で収容所から釈放され、北京植物園の庭師となる。のち中国人民政治協商会議全国委員に選出。 |
| 12月 4日 | アメリカの宇宙飛行マーキュリー計画で脱出ロケット試験のため、アカゲザルを載せて打ち上げ。飛行に成功する。 |
| 12月11日 | 早朝、横浜市神奈川区子安台の第二京浜国道でTNT火薬を満載したトラックに、居眠り運転をしていた砂利運搬トラックが突っ込み、火薬が爆発。両方の運転手4名が即死。付近500mの家屋31棟が全半壊し99名が負傷。砂利運搬トラック運転手の超過勤務が原因。 |
| 12月14日 | 在日朝鮮人の北朝鮮への帰還事業がはじまる。北朝鮮政府や朝鮮総連のプロパガンダに乗せられて、日本国内の知識人や左翼勢力、マスコミを中心に、保守系勢力まで含めて「北朝鮮は地上の楽園」と宣伝し多くの在日朝鮮人や日本人配偶者などが北朝鮮に渡った(当時韓国が日本と敵対関係にあった反動もある)。しかし、北朝鮮での階級「出身成分」では日本からの渡航者は「動揺階層」か「敵対階層」であり、楽園どころか激しい差別の対象となった。強制収容所へ送られたものも多いと言われ、後に脱北したものもいる。一方で、日本共産党員などは特別待遇を受けたほか、金正恩らの母親である高英姫は在日朝鮮人2世であるため、例外もある。 |
| 12月29日 | 物理学者のリチャード・ファインマンがアメリカ物理学会で『ゼアーズ・プレンティ・オブ・ルーム・アット・ザ・ボトム』と名付けた講演を行う。原子を直接操作してナノサイズの機械を製造し化学製造や医学治療への応用を訴えたもの。この講演自体は注目されなかったが、後にナノテクノロジーのアイデアの嚆矢として再評価される。 |
| 1960年(昭和35年) | |
| 1月 1日 | カメルーンがフランスから独立。 |
| 1月 7日 | ケープカナベラルでポラリスミサイルの発射実験が行われる。アメリカ初のSLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)。 |
| 1月 9日 | ナイル川にアスワン・ハイ・ダムの起工式が行われる。1970年完成。 |
| 1月29日 | 日本のアラビア石油が、クウェート沖合の海底でカフジ油田を発見。自主開発油田の最初。 |
| 2月13日 | フランス初の核実験「ジェルボアーズ・ブルー」がアルジェリアのサハラ砂漠で行われる。核出力70Kt。ジェルボアーズとは砂漠に住むトビネズミのこと。ブルーはフランス国旗の最初の色「青」。実験は続けて、ジェルボアーズ・ブランシュ(白)、ジェルボアーズ・ルージュ(赤)と続いた。 |
| 3月 5日 | フランス領アフリカ共同体オートボルタ自治共和国(現ブルキナファソ)のガオ・ギニー一帯に空中で崩壊したとみられる隕石の破片が多数落下する。 |
| 3月21日 | 南アフリカで人種差別のパス法に反対するパン・アフリカニスト会議が抗議集会を行い、警察が発砲。多数の犠牲者を出すシャープビル虐殺事件が起こる。 |
| 4月 4日 | セネガルがフランスより独立。 |
| 4月19日 | 韓国四月革命勃発。不正選挙を批判した学生デモが武力鎮圧され死者が出たことから、大規模な市民デモが起きる。 |
| 4月21日 | ブラジル政府、人工計画都市ブラジリアに遷都。 |
| 4月26日 | 韓国で大規模なデモが続く中、李承晩大統領が辞職し政権が倒壊。自由党関係者が相次いで逮捕され、崔仁圭内務長官ら学生デモ鎮圧に関わったものは後に処刑される。 |
| 4月27日 | トーゴがフランスより独立。 |
| 4月28日 | 李承晩の養子の李康石が、実父の李起鵬副大統領ら家族を殺害して自殺。 |
| 5月 1日 | U-2撃墜事件。ソ連のミサイル基地を偵察するため、パキスタンから飛び立った偵察機U-2が、ソ連領内で対空ミサイルS-75によって撃墜される。パイロットのフランシス・ゲーリー・パワーズは無事着地したが逮捕され、公開裁判にかけられたため、アメリカのスパイ偵察が明らかになった。 |
| 5月16日 | 雅樹ちゃん誘拐事件が起こる。マスコミが事件を過熱気味に報道するのを見た犯人が、誘拐した男児を殺害して逃走。誘拐事件の報道に関して自粛協定ができるきっかけとなった。犯人は大阪へ逃亡後逮捕され、死刑判決。のち執行された。 |
| 5月19日 | 新日米安保条約が、日米安全保障条約等特別委員会で与党の強行採決。翌日衆議院通過。反安保闘争が激化し、国会をデモ隊が包囲。 |
| 5月29日 | 李承晩が妻とともにアメリカへ亡命。 |
| 6月 3日 | セガ設立。ゲーム制作、アミューズメント施設運営会社。 |
| 6月10日 | ハガチー事件。米大統領報道官ジェイムズ・ハガティが羽田空港でデモ隊に包囲されヘリに救出される。 |
| 6月15日 | 国会前で機動隊とデモ隊が衝突し、東大生の樺美智子が圧死する。 |
| 6月17日 | 新聞七社共同宣言。暴力による革命運動を批判する社告を掲載。宣言を出したマスコミに対する批判も起こる。 |
| 6月19日 | 新日米安保条約、参議院の議決がないまま午前零時に自然成立。 |
| 6月23日 | 新日米安保条約批准書交換。これをもって岸内閣は総辞職する。 |
| 6月24日 | ベルギー領コンゴの総選挙でコンゴ国民運動が躍進。各党と連立政権を樹立。大統領にジョゼフ・カサブブ、首相にパトリス・ルムンバが就任。 |
| 6月26日 | イギリス領ソマリランドが、ソマリランド国としてイギリスから独立。 |
| 6月26日 | マダガスカルが、フランスから独立。 |
| 6月30日 | ベルギー領コンゴがコンゴ民主共和国として独立。直後に独立した隣接するコンゴ共和国と同名だったため、コンゴ・レオポルドビルとも呼ばれた。1971年から1997年まではザイール。 |
| 7月 1日 | イタリア領ソマリランドがイタリアから独立し、先に独立したソマリランドと統合して、ソマリア共和国が成立。 |
| 7月 8日 | コンゴ民主共和国に駐留を続けていたベルギー軍が、首相官邸を襲撃。翌日キンシャサ国際空港を占領。コンゴ動乱が始まる。 |
| 7月 9日 | 樺太犬のジロが第4次越冬中に昭和基地で病死。のち剥製となる。 |
| 7月10日 | コンゴ民主共和国のルムンバ首相は、ベルギーとの国交を断絶。 |
| 7月11日 | ベルギー政府、コンゴ民主共和国でコナカ党を率いるモイーズ・カペンダ・チョンベを支援。チョンべは、コンゴの収入の半分を持つと言われる南部のカタンガ州をカタンガ国として独立宣言。カサブブ大統領は米国に、ルムンバ首相は国際連合とソ連に支援を求めて対立。 |
| 7月14日 | コンゴ・カタンガ州問題で、国連安全保障理事会は、ベルギー軍の撤退を求める決議143号を採択。コンゴ国連軍が結成され、コンゴへ派遣される。 |
| 7月22日 | コンゴ・カタンガ州問題で、国連安全保障理事会は、コンゴとカタンガは単一国家とし、ベルギー軍の撤退を再び求める決議145号を採択。 |
| 8月 1日 | ベナンがフランスから独立。当初の国名はダホメ共和国。 |
| 8月 1日 | パキスタンの首都が南部沿岸部の大都市カラチから、北部内陸にあるイスラマバードに遷る。 |
| 8月 3日 | ニジェールがフランスから独立。 |
| 8月 5日 | オートボルタがフランスから独立。国名は1984年にブルキナファソと改める。 |
| 8月 7日 | コートジボワールがフランスから独立。国名は「象牙海岸」という意味。 |
| 8月11日 | チャドがフランスから独立。 |
| 8月13日 | 中央アフリカがフランスから独立。 |
| 8月15日 | コンゴ共和国がフランスから独立。隣接するコンゴ民主共和国と国名が同じであるため、コンゴ・ブラザビルとも呼ばれた。 |
| 8月16日 | キプロスがイギリスから独立。 |
| 8月16日 | 高高度降下人体実験プロジェクト・エクセルシオが行われ、高度31.3kmの気球からアメリカ空軍のパイロット、ジョゼフ・キッティンジャーがダイブ。乗物等を使わない人間そのものの最高速度時速988kmを記録。 |
| 8月17日 | ガボンがフランスから独立。 |
| 8月19日 | 撃墜されたアメリカ空軍の偵察機U-2のパイロット、フランシス・ゲーリー・パワーズに対し、禁錮10年の判決がくだされる。一方で、米ソ両国は釈放についての条件交渉に入る。 |
| 8月27日 | 氷川丸による横浜-シアトル航路の最後の出港。横浜港ボート・トレインもこの日をもって終了。 |
| 9月 6日 | コンゴ民主共和国でルムンバ首相とカサブブ大統領の対立が激化。ルムンバが閣議でカサブブ解任決議を決定すると、カサブブは、ルムンバを更迭し、ジョゼフ・イレオを首相に任命。 |
| 9月 8日 | コンゴ民主共和国議会でカサブブ大統領解任決議案が審議されるが、下院で可決するも上院で否決。 |
| 9月14日 | コンゴ民主共和国国軍参謀長ジョゼフ=デジレ・モブツがクーデター。カサブブ大統領側と手を組む。 |
| 9月22日 | フランス領スーダンがフランスから独立し、マリ共和国となる。 |
| 9月24日 | 世界初の原子力航空母艦「エンタープライズ」が進水。 |
| 10月 1日 | ナイジェリアがイギリスから独立。 |
| 10月12日 | 日比谷公会堂で、自民党・社会党・民社党3党党首の立会演説会中に、社会党委員長の浅沼稲次郎が右翼少年の山口二矢に暗殺される。 |
| 10月24日 | ニェジェーリンの大惨事。ソ連のバイコヌール宇宙基地で開発中だったR-16大陸間弾道ミサイルの発射試験準備中に、人為的ミスで第2段ロケットが点火し、第1段がロケットが爆発。ICBM開発を主導し、当時現場で指揮していた戦略ロケット軍初代総司令官ニェジェーリン元帥を含む100人以上が死亡。ソ連政府はこの事故を隠し、ニェジェーリンは飛行機事故で死亡したと発表。 |
| 11月 2日 | 浅沼稲次郎を暗殺した山口二矢が少年鑑別所で自殺。 |
| 11月25日 | ドミニカ共和国でトルヒーヨ独裁政権に対する反政府運動を主導していたミラバル四姉妹のうち、長女パトリア・メルセデス、三女ミネルバ・アルヘンティーナ、四女アントニア・マリア・テレサの3人が、トルヒーヨの手の者によって暴行殺害される。有力な反政府運動指導者を抹殺したトルヒーヨだったが、これが国民の反発を買うことになる。国際デーの一つ「女性に対する暴力撤廃の国際デー」は、この事件をもとに11月25日に定められている。 |
| 11月28日 | モーリタニアがフランスから独立。 |
| 12月 1日 | コンゴ民主共和国国軍参謀長ジョゼフ=デジレ・モブツがカサブブの指示でルムンバを逮捕。 |
| 12月16日 | 1960年ニューヨーク上空旅客機空中衝突事故。シカゴからニューヨークへ向かっていたユナイテッド航空826便のDC-8型機が、オハイオ州デイトンからコロンバス経由でニューヨークに向かっていたトランス・ワールド航空266便ロッキードL-1049スーパーコンステレーション機に後方から衝突。トランス・ワールド機は空中分解してスタテン島のミラー空軍基地に墜落。ユナイテッド機は急降下してブルックリン市街のパーク・スロープにあるアパート群に墜落した。両機の乗員乗客128名全員と地上の住民6名の計134名が死亡。 |
| 12月27日 | 池田内閣で「所得倍増計画」が閣議決定。目標として1961年からの10年間で国民総生産を26兆円に倍増させるというもの。科学技術の振興、重工業化、エネルギー転換、教育促進、貿易の自由化などを柱とする。当初は野党や経済学者、マスコミなどから「非現実的」「インフレを引き起こす」などと批判が相次いだが、結果的には倍増以上となった。また交通や物流の整備、消費社会の拡大、新たな文化も生み出すことになる。一方で、公害などの環境問題、受験戦争、都市への一極集中と地方の過疎化などを生むことになった。 |
| 1961年(昭和36年) | |
| 1月 3日 | アメリカアイダホ州の国立原子炉試験場で、原子炉の修理作業中、制御棒の操作ミスで爆発。作業員3人が被曝して死亡。事故原因の詳細は不明だが、何らかの理由で強制的に制御棒を引き抜いたためとみられる。 |
| 1月 3日 | アメリカ政府、キューバのカストロ政権に対し国交を断絶。 |
| 1月 4日 | 物理学者エルヴィン・シュレーディンガーが死去。量子力学の基本方程式シュレーディンガー方程式を発見する一方、思考実験「シュレーディンガーの猫」でその問題点も指摘し、量子力学の発展に寄与した人物。 |
| 1月17日 | コンゴ民主共和国の元首相ルムンバら3人が、カタンガへ運ばれ、エリザベートビル(ルブンバシ)で処刑される。 |
| 1月24日 | ゴールズボロ空軍機事故。アメリカノースカロライナ州でマーク39核爆弾2発を搭載したアメリカ空軍のB-52爆撃機が空中分解し、核爆弾が地表に落下。乗組員のうち5人は脱出し、3人が死亡。核爆弾のうち1発は、4段階の起爆装置の3つ目までがアクティブとなったが、地表激突直前に落下傘が開き木に引っかかって起爆しなかったとみられる。もう1発は湿地帯に突入し大破。こちらも起爆直前の状態だったと見られている。湿地帯に落ちた方は回収できず現在もそのまま。 |
| 1月30日 | アメリカのマーキュリー宇宙飛行計画で、チンパンジーのハムが宇宙へ打ち上げられ、16分39秒後、無事大西洋に帰還する。ハムは訓練によって簡単な機器操作のテストもできるようになっていたが、飛行中の故障で装置がうまく作動しなかったと言われる。 |
| 2月 1日 | 風流夢譚事件。中央公論社から発刊された深沢七郎の短編小説「風流夢譚」で、皇室の人々が「左慾」革命で殺害されるシーンに反発した右翼の少年が、中央公論社社長の嶋中邸に侵入。室内で遭遇した社長夫人及びお手伝いの女性を刃物で襲い、社長夫人が重症、お手伝いの女性が死亡する。少年は翌日出頭。同作は、皇族の実名を上げての殺害シーンと、その表現の仕方が露骨で下品だとして一般的には不評で、宮内庁も抗議する事態となったが、一方で左翼運動を批判したものでもあり、思想的には一概には言えない内容だった。また表現方法としても賛否両論となった。中央公論社の嶋中社長はその矢面に立たされた格好となり事件につながった。言論の自由を訴える意見が出る一方で、これ以降、皇室に関する言論は自粛傾向となった。無関係の女性を殺害したことについては右翼からも批判が出ている。この事件で深沢七郎は謝罪会見をした後、執筆活動から離れ放浪している。また同作の復刊依頼はあったが作者として了承しなかった。そのため生前公式の出版はされていない(勝手に海賊版が出たことはある)。 |
| 2月11日 | イギリス領カメルーンで、帰属問題の国民投票が実施される。イスラム教徒の多い北部はナイジェリアに、キリスト教徒の多い南部はカメルーンに統合することが決まる。 |
| 2月16日 | ポール・W・キャラウェイ中将(この時点では少将)が第3代琉球列島高等弁務官に就く(1964年7月31日まで)。強権的な統治方法は「キャラウェイ旋風」と呼ばれた。 |
| 2月14日 | 人気若手俳優の赤木圭一郎が、日活撮影所で映画撮影の休憩中、ゴーカートに乗って操縦を誤り事故。頭蓋骨骨折の重傷を負う。 |
| 2月20日 | 塩原温泉ホテル日本閣殺人事件の犯人の女性が逮捕される。女性は1952年に夫を殺害(裁判中に発覚)、1960年にホテル日本閣の経営者と組んで経営者の妻を、さらに同年末に経営者も殺害。女性は同温泉郷の食堂や土産物店の経営者で、共犯の男も逮捕。女性は後に死刑判決を受け1970年に処刑された(戦後最初の女性死刑囚の死刑執行)。 |
| 2月21日 | 赤木圭一郎が搬送先の慈恵医大病院で死去。 |
| 3月23日 | ソ連で宇宙飛行士候補のワレンチ・ボンダレンコが、モスクワにある生物医学研究所で高酸素低圧力耐久実験中に起きた火災で死亡する事故が起きる。 |
| 4月11日 | イスラエルでアイヒマン裁判がはじまる。ナチスのユダヤ人虐殺に関与したアイヒマンに対する裁判で、大量虐殺を命令されただけでそれを行えるのか、という問題を提起した。 |
| 4月12日 | ソ連のガガーリンがボストーク1号(3KA-2)で人類初の軌道周回飛行に成功する。打ち上げから108分後に地球に帰還。 |
| 4月15日 | ピッグス湾事件(コチノス湾事件)。キューバのカストロ政権を倒す目的で、CIAがお膳立てした反カストロ亡命キューバ人軍による侵攻作戦がはじまる。キューバ軍に偽装した反カストロ軍の爆撃機がキューバ軍空軍基地を空襲するが、想定通りに行かず。 |
| 4月17日 | ピッグス湾事件(コチノス湾事件)。反カストロ軍1500人がコチノス湾に上陸。しかしキューバ軍が迎え撃ったため、米軍の参戦を求めるが、ケネディ大統領が拒否したため大敗。 |
| 4月19日 | ピッグス湾事件(コチノス湾事件)で、反カストロ軍は戦死者114名、1189名が降伏して壊滅。ケネディ大統領が作戦に消極的で、作戦が二転三転したこと、そもそもCIAの見込みが甘く、計画自体がずさんだったことが原因。 |
| 4月22日 | フランス領アルジェリアで、「将軍たちの反乱」が勃発。フランスのド・ゴール大統領が、独立戦争の続くアルジェリアに対して進める宥和政策に反発したモーリス・シャール、エドモン・ジュオー、アンドレ・ゼレール、ラウル・サランの4人の退役将軍が軍事政権樹立を目指して反乱。即日、アルジェリアの主要都市を占拠。反独立派のOAS(秘密軍事組織)も参加。 |
| 4月23日 | フランスのド・ゴール大統領が、反乱に対処するテレビ演説を行う。フランス各地で反乱に反発してゼネスト。 |
| 4月25日 | フランス軍、アルジェリアの核実験場にあった原子爆弾「ジェルボアーズ・ヴェール」を、反乱軍の手に渡らぬよう起爆させる。核爆発と、ラジオ放送による呼びかけを受けて、反乱軍の投降者が相次ぐ。 |
| 4月26日 | アルジェリア反乱軍の4将軍のうちモーリス・シャールがフランス軍に降伏。反乱は終息へ向かう。 |
| 4月27日 | シエラレオネがイギリスから独立。 |
| 5月 1日 | キューバのカストロ首相が、メーデーの演説で社会主義革命を宣言する。それまでカストロ首相は必ずしも社会主義を明確にしてなかったが、ピッグス湾事件の結果、反米が強まり、東側諸国と接近する結果となった。 |
| 5月 4日 | 樺太犬のタロが日本に帰国する。北海道大学植物園で飼育される。 |
| 5月 5日 | アメリカが宇宙船フリーダム7で初の有人弾道飛行を行う。搭乗したのはアラン・バートレット・シェパードJr.。 |
| 5月14日 | アメリカで、プルート計画による原子力ラムジェットエンジン「Tory-IIA」の初試験を行う。前方から吸い込んだ空気を原子炉の熱で加熱膨張して噴射する仕組み。 |
| 5月16日 | 韓国で韓国陸軍士官学校第8期生の金鍾泌らによる5・16クーデターが勃発。反共や経済発展、腐敗一掃を公約とした軍事革命委員会が設立される。第二共和政の内紛、経済の低迷、学生等による北朝鮮との融和運動に危機感を抱いた軍部によるクーデター。 |
| 5月18日 | 韓国の張勉首相、尹潽善大統領らが、軍事革命委員会への政権移譲を承認。 |
| 5月19日 | アメリカ政府、韓国の軍事クーデターを容認。軍事革命委員会は国家再建最高会議となる。朴正熙少将が国家再建最高会議議長に就任。 |
| 5月30日 | ドミニカ共和国の独裁者、ラファエル・トルヒーヨが側近の軍人らによって射殺される。CIAなどの工作によるが、ミラバル姉妹の謀殺が国民の反発を買い、アメリカを始め中南米各国政府とも対立しており、政権はすでに崩壊寸前だった。あとをラファエルの弟エクトルが継ぐが、トルヒーヨ政権の重臣だったホアキン・バラゲールが権力を握り、トルヒーヨ一族を追放した。 |
| 5月31日 | イギリス領カメルーンのうち、北部が、ナイジェリアの北部州に統合される。 |
| 5月 | ソ連の原子力飛行機Tu-119の試験機であるTu-95LALが初飛行。飛行中に原子炉起動にも成功。8月まで複数回の試験を行った。公式には乗員の被曝はなかったとされているが、乗員の殆どが短命だったため、疑問視されている。Tu-95LALは取り込んだ外気を原子炉の熱で高温化し、その気体でタービンを回して後方へ噴射すると同時にタービンの同軸でプロペラも回す熱核ターボプロップ式。実用性や安全性などの問題で開発中止となった。 |
| 6月 1日 | ロバート・A・ハインライン『異星の客』出版。火星生まれの青年が地球で独自の宗教を起こす内容で、賛否両論を巻き起こした。ヒューゴー賞とローカス賞を受賞。ヒッピーの経典と呼ばれることもあり、カルト宗教に影響を与えたとする説もある。 |
| 6月17日 | インド国産の超音速戦闘爆撃機HF-24マルートが初飛行。設計したのはかつてドイツ・フォッケウルフ社で航空機設計をしていたクルト・タンク。 |
| 6月24日 | 7月10日にかけて大雨が続く。昭和36年梅雨前線豪雨。天竜川とその支流沿いでは山崩れなどが相次ぎ、横浜市や神戸市では住宅造成地で斜面が崩壊。全国で死者302人、行方不明者55人、負傷者1320人。「三六災害」とも呼ばれる。 |
| 6月29日 | 長野県下伊那郡大鹿村の大西山が山体崩壊し、小渋川対岸の集落を飲み込み、42名が死亡。伊那谷一帯は氾濫や土砂崩れなどで甚大な被害を受ける。 |
| 7月 4日 | ソビエトのK-19原子力潜水艦が、グリーンランド近海で冷却システムの事故を起こす。原子炉の加熱溶融を防ぐため応急修理を行い、冷却に成功するも、放射線防護をしてない状態で作業した8名が死亡。 |
| 7月 | ナチス戦犯アイヒマンの心理を探る目的で、アメリカで心理学者によるミルグラム実験が始まる。閉鎖環境で、権威のある人間に、責任を問わないことを条件に命令されると、他者の命を奪いかねないことでも実行してしまうかどうかを多数の一般市民を対象に実施したテスト。 |
| 8月 6日 | ソビエトがボストーク2号機を打ち上げる。ゲルマン・チトフ宇宙飛行士が搭乗し25時間滞在。 |
| 8月13日 | 東ドイツ政府が、突如東西ベルリン市の間に壁の建設を始める。 |
| 9月15日 | アメリカの核実験ヌガ作戦がネバダ核実験場で始まる。すべて地下核実験。 |
| 9月17日 | 第2代国際連合事務総長ダグ・ハマーショルドがコンゴ動乱調停に向かう途中、搭乗機がローデシアのンドラ空港着陸に失敗し死亡。暗殺の噂が流れる。 |
| 10月 1日 | 国鉄の大規模白紙ダイヤ改正(サンロクトオ)が実施される。新型電車や寝台車の投入による全国規模での特急列車と急行列車の大幅増発が行われた。北陸本線能生駅では、特急白鳥が同駅ですれ違い運転停車することになったのを、国鉄側の手違いで客扱いの特急停車駅になったと地元で間違って受け止められ、歓迎式典が行われる珍事も起こったという。 |
| 10月 1日 | イギリス領カメルーンのうち、残っていた南部地方が、カメルーンに統合される。ただしカメルーン共和国がフランス語圏なのに対し英語圏であるため、早くから分離独立の動きが見られる(南カメルーン連邦共和国、アンバゾニア共和国)。 |
| 10月18日 | 映画『ウェスト・サイド・ストーリー』公開。同名のブロードウェイミュージカルを映画化したもの。 |
| 10月21日 | アメリカ軍がウェスト・フォード計画に基づき軌道上に数億本の針状のダイポールアンテナをばらまいて通信用リングを作る実験を行うが失敗に終わる。 |
| 10月30日 | 史上最大の水爆ツァーリ・ボンバの核実験RDS-220が、ソ連のノヴァヤゼムリャ島で実施される。出力50Mt。大型爆撃機の爆弾倉に入りきらないほど巨大な水爆を空中投下して行った。 |
| 11月17日 | ロックフェラーの一族で、政治家ネルソン・ロックフェラーの息子の民族学者マイケル・ロックフェラーが、ニューギニア島イリアンジャヤで研究中に消息を絶つ。食人族に食べられた、などという噂が広がった。 |
| 11月18日 | 学会でサリドマイドの催奇性が指摘される。 |
| 12月 9日 | タンガニーカがイギリスから独立。 |
| 12月10日 | アメリカの核実験ヌガ作戦の一環として、ニューメキシコ州カールスバットで平和利用目的の地下核実験(プロウシェアー作戦)が行われる。汚染などにより失敗に終わる。 |
| 12月12日 | 三無事件。旧軍関係者、自衛隊関係者、右翼、学生、韓国軍関係者、韓国や台湾の財閥関係者などが参加したクーデター未遂事件。破壊活動防止法で初の有罪判決が出た事件でもある。 |
| 12月17日 | インド軍が兵力4万5千、軽空母ヴィクラントなどを動員し、ポルトガルの植民地であるゴア、ダマン、ディーウ島への侵攻作戦を開始。 |
| 12月18日 | ゴアなどで戦闘が続く中、ポルトガルは国連安全保障理事会に提議。 |
| 12月19日 | ゴア総督とゴア駐留ポルトガル軍が、本国サラザール政権の「焦土作戦」の指示を受けいれず、インド軍に降伏。ポルトガル領インドは消滅し、あらたにゴア・ダマン・ディーウ直轄領となる。一連の戦闘でポルトガル人30人と、インド人22人が死亡。 |
| 1962年(昭和37年) | |
| 1月 1日 | フィリップ・k・ディックの小説『高い城の男』が発売。第二次世界大戦が枢軸側の勝利で終わったあとの分割されたアメリカを舞台にした歴史改変SFの代表作であり、メタフィクションにもなっている。 |
| 2月10日 | ソ連が捕虜にしていた偵察機U-2のパイロット、ゲーリー・パワーズと、アメリカが逮捕したソ連のスパイ、ルドルフ・アベル大佐を、東西ベルリンの境界にあるグリーニケ橋で身柄交換。 |
| 2月20日 | 宇宙船フレンドシップ7によるアメリカ初の軌道周回飛行。 |
| 3月19日 | フランスとアルジェリア暫定政権、独立派のアルジェリア民族解放戦線の3者によって、エヴィアン=レ=バンでエヴィアン協定が締結。アルジェリアのフランスからの独立が決定。アルジェリア戦争は終結。この際、フランス側に付いて戦った現地のムスリム兵「アルキ」が見捨てられ多大な犠牲を出すことに。 |
| 4月24日 | アメリカコロラド州デンバー付近で地震が発生。以降1967年まで多いときで一日に数十回もの小地震が頻発。のちに、同地のロッキーマウンテン兵器廠にある化学兵器及び民生品生産による汚染廃液の廃棄用井戸への注入が原因と判明する。 |
| 5月 1日 | フランスがアルジェリアのサハラ砂漠エッカーで行った地下核実験で、想定より大きな爆発となり、大量の爆風が地上へ吹き出す。実験に立ち会っていたピエール・メスメル国防相ら2000人が被曝。 |
| 5月 3日 | 東京荒川区東日暮里の常磐線で、多重衝突の三河島事故が起こる。160人が死亡し、325人が重軽傷。 |
| 5月17日 | 大日本製薬がサリドマイドの出荷を停止。 |
| 5月20日 | ホテルオークラ開業。元帝国ホテル会長の大倉喜七郎が帝国ホテルを超えるホテルとして設立。 |
| 5月27日 | ペンシルベニア州セントラリアで、ゴミ集積所から起こったとみられる火災が、地下の炭鉱に広がる。これにより地表が高温化し道路が使用不能に。有毒ガスも地下から噴出。さらに地下水が失われるなど、生活環境が悪化。鎮火も困難なことから、セントラリアは放棄される。 |
| 6月21日 | 司馬遼太郎の代表的な小説『竜馬がゆく』が産経新聞で連載が始まる。 |
| 6月30日 | 北海道の十勝岳が大規模噴火。大正火口付近にあった硫黄採掘場の施設を火山弾が直撃し、死者行方不明者5名、負傷者11名を出す。 |
| 7月 1日 | 王貞治がはじめて実戦で一本足打法を試す。 |
| 7月 1日 | ブルンジ王国がベルギー委任統治領ルアンダ=ウルンディから独立。 |
| 7月 1日 | ルワンダがベルギー委任統治領ルアンダ=ウルンディから独立。 |
| 7月 5日 | アルジェリアがフランスから独立。フランス軍は15年間駐留することとなる。 |
| 7月 6日 | アメリカ・ネバダ州で、核爆発による掘削テストのための地下核実験ストラックス作戦(プロウシェアー作戦)セダン実験が行われ、爆煙とともに広がった放射性物質により市民1300万人もの被曝者を出す。核出力104Kt。 |
| 7月 7日 | アメリカの核実験サンビーム作戦リトルフェラー実験が始まる。デイビー・クロケット(無反動砲から発射する超小型核砲弾)などの検証実験。核出力は20t程度で、飛距離は2~4km程度。破壊力は低いが、半径500m以内の放射線による致死力は非常に高い。射手自身が巻き込まれる危険性の高い兵器でもあった。 |
| 7月 9日 | アメリカ軍による核実験ドミニク作戦(フィッシュボール作戦)スターフィッシュ・プライム実験が行われる。ジョンストン島の上空高度400kmの宇宙空間で核爆発を実施。大規模な電磁パルスが発生し、1445km離れたハワイ諸島は停電。またアメリカの位置測位衛星トランシット4Bや、イギリス初の人工衛星アリエル1号に深刻なダメージをもたらしたと言われる。 |
| 7月11日 | YS-11記念日。国産初の旅客機YS-11が完成する。 |
| 7月16日 | 建築基準法のビルの高さを百尺(31m)に規制する「百尺規制」が廃止され、高層ビルの建設が可能になる(すでにこれ以前に規制の高さを超えるビルも複数ある)。代わりに容積率の規制が導入される。 |
| 8月17日 | ペーター・フェヒター射殺事件。東ベルリンに住んでいた青年ペーター・フェヒターが、家族のいる西ベルリンへ亡命しようと、友人とともにベルリンの壁を乗り越えようとして東ドイツ警備兵の銃撃を受け負傷。そのまま壁の東側の無人地帯に落ちたが、苦しむ彼に気づいた西側住民らの要請にも関わらず、警備兵らは救助しないまま死亡するまで放置された。 |
| 8月24日 | 第4回アジア競技大会1962年ジャカルタ大会がインドネシアのジャカルタで開催。しかしインドネシア政府が、同じ社会主義国の中華人民共和国と、同じイスラム系のアラブ諸国との関係強化のため、中華民国(台湾)とイスラエルの参加拒否を打ち出したことから、国際オリンピック委員会(IOC)と対立。IOCはインドネシア国内オリンピック委員会を資格停止処分にしたため、インドネシア政府はIOC離脱を表明。IOCが正式に認めない国際大会への出場選手は、オリンピック参加資格を失うという問題があり、一方インドネシアやアラブ諸国の反発で東京オリンピックボイコットの動きも出たことから、日本は苦慮の末に今大会へ参加することを決定。その責任をとって、東京オリンピック開催を目指して主導してきた津島壽一は東京オリンピック組織委員会を、田畑政治は日本オリンピック委員会を、それぞれ辞任することになった。 |
| 8月30日 | 日本国産旅客機YS-11が初飛行。 |
| 9月 9日 | 台湾空軍の第8航空大隊第35中隊(通称『黒猫中隊』)に所属するU-2C偵察機が中華人民共和国内を偵察飛行中、南昌市で撃墜される。パイロットの陳懐生は戦死。14年間で計5機が撃墜されて、3人が戦死し、2人が捕虜となった後、釈放されてアメリカへ移住した。100回を超える偵察飛行で得た膨大な中共の核兵器基地などの撮影データをアメリカ政府に提供したと言われる。 |
| 9月24日 | 中国共産党第8期十中全会で、毛沢東が小説「劉志丹」を反党反人民的と批判。出版に関わった人物らの失脚、粛清へと発展する。いわゆる「反党小説『劉志丹』事件」。劉志丹は1936年に国民党軍との戦闘で戦死した共産党軍の指揮官。この時代には後に毛沢東と対立して粛清された人物が多数いるため、作中にそれらの人物が出ていることを毛沢東が問題視したとみられる。結果、英雄と称されていた劉志丹自体も否定されるようになった。 |
| 9月26日 | 長崎県五島列島の福江市街地で大火。市街地の大半に当たる39,930坪を焼失。死者はなし。 |
| 10月 5日 | 映画007シリーズ第一作『007 ドクター・ノオ』がイギリスで公開。 |
| 10月 9日 | イギリス・ウガンダ植民地で保護国化されていたブガンダ王国を中心に、ブニョロ王国、アンコーレ王国、トロ王国、ブソガ王国などが連邦制となって、英国女王を元首とするイギリス連邦王国としてイギリスから独立。 |
| 10月15日 | 前日にキューバ上空を飛行したU-2偵察機が撮影した写真を解析したところ、キューバ国内にソ連軍のミサイル基地が建設されているのが発見される。 |
| 10月16日 | アメリカのケネディ大統領が緊急国家安全保障会議を招集。メンバーの多くはキューバ空爆を主張するが、ロバート・ケネディは事前警告なしの空爆はソ連からの攻撃を招くと反対。ロバートやマクナマラは海上封鎖案を主張。 |
| 10月17日 | ケネディ大統領は事態が容易ならざる状況になっていることを受け、ジャクリーン夫人と子供を核シェルターへ避難させる準備を進めるが、夫人はこの話を聞いて「全アメリカ人とともに運命に立ち向かう」と称して避難を断ったと言われる。 |
| 10月18日 | 国連総会出席のために訪米していたソ連のグロムイコ外相がホワイトハウスを訪問。ケネディ大統領と会談。どちらも方針を明かさず。 |
| 10月19日 | 緊急国家安全保障会議の方針として、海上封鎖案を優先、事態が進展しないときはキューバを空爆することでまとまり、選挙遊説中のケネディ大統領に報告。 |
| 10月20日 | 選挙遊説中のケネディ大統領は、風邪と称してワシントンに戻る。ケネディは海上封鎖実施を決定。この頃からメディア側にキューバ危機の情報が広まり始める。 |
| 10月20日 | 中華人民共和国軍が、カシミールのアクサイチン地方を実効支配に置くため、対立するインド側へ侵攻。中印国境紛争が始まる。 |
| 10月22日 | アメリカ政府は同盟国に特使を派遣。事態の説明を行い、同意を取り付ける。その上で東部時間午後7時からケネディ大統領が国民向けにキューバ危機についてメディアを通じて演説。海上封鎖とミサイルの撤収をキューバとソ連に求めることを発表。アメリカ軍はデフコン3に移行。 |
| 10月22日 | 大統領演説を事前に察知したソ連側はアメリカ政府が軍事行動に移すとの疑念から中央委員会幹部会を緊急招集。対米戦争勃発の場合の核兵器使用に関して議論される。演説聴取後にフルシチョフはキューバのミサイル基地建設続行を決定。また同日、ソ連側の軍事情報をアメリカに流していたオレグ・ペンコフスキーGRU大佐がモスクワ市内で逮捕される。ペンコフスキーは後に処刑されたが、第3次世界大戦を防いだと評される。 |
| 10月23日 | 米州機構会議がアメリカによるキューバからのミサイル撤去措置を賛成20・棄権3で承認。ケネディ大統領は海軍艦艇による海上封鎖命令にサイン。 |
| 10月24日 | アメリカ海軍によるキューバ海上封鎖が始まる。全世界の米軍に総動員令発令。フルシチョフはケネディに対し批判と封鎖には応じない旨の書簡を送付。国連のウ・タント事務総長代行は、基地建設停止と海上封鎖停止の仲介案を提示。 |
| 10月25日 | フルシチョフは、党中央委員会幹部会で、アメリカがキューバに侵攻しないと確約するなら、キューバのミサイル基地を撤去する、という案を示し、出席者の賛意を取り付ける。ミサイル撤去案は共産党の有力古参ミコヤン第一副首相の考えとする説もある。 |
| 10月25日 | アメリカのスティーブンソン国連大使は、国連安全保障理事会の場で、ソ連のゾーリン国連大使にキューバでのミサイル基地建設を追及。ゾーリン大使が否定すると、偵察写真を出席者に示し、再度追及する方法で事態をアピールすることに成功。ゾーリン大使も詳細は伝えられていなかったとされる。 |
| 10月26日 | アメリカが本格的に海上臨検を開始。一方、キューバの基地建設は停止していないとして、緊急国家安全保障会議ではキューバ侵攻も議題に上がる。ケネディは軍事侵攻に反対するも決定せず。国務省の報道官が誤ってさらなる行動に移ることを示唆する発言をしたため、ケネディが叱責する事態に。 |
| 10月26日 | アメリカ軍は市場初めてデフコン2に移行。全世界のアメリカ軍が臨戦態勢に入る。メディアがこの状況を報じたため、全米で市民が買い出しに走るなどの大騒ぎとなる。ソ連はアメリカの報道官の会見や報道、アメリカ軍の動きを受けて、事態が深刻な段階にあると判断。同日昼、駐米ソ連大使館員でKGBのファーミンが、旧知のアメリカABCテレビ特派員スカーリと会合、ソ連側の提案をケネディは飲むか探ってほしいと依頼。スカーリは政府内部の情報を伝えたとされる。フルシチョフは同日、すでに決定していた方針(アメリカがキューバに侵攻しなければ、ソ連もミサイルを撤去する)を公式にアメリカに提示。 |
| 10月27日 | 通称「暗黒の土曜日」。キューバのミサイル基地建設は大詰めとなり、さらに海上封鎖線にソ連を含む東側の船舶9隻が接近。フルシチョフはアメリカ軍が侵攻する様子はないと判断、前日の交渉条件にプラスしてトルコのアメリカ軍ミサイル基地撤去を要求。アメリカ政府内部では前日から強硬姿勢に変わったことに疑念が高まる。この直後、米軍のU-2偵察機がキューバ上空を飛行中に撃墜されパイロットが死亡。これを受けて緊急国家安全保障会議はキューバのミサイル基地を攻撃し、相手が反撃すれば全面攻撃で一致。ケネディは猶予を求めるが、米軍参謀本部は大規模空爆とキューバ侵攻を主張。またアラスカでU-2偵察機が誤ってソ連領を侵犯する事件が起こったため、ソ連側の攻撃を誘発するとの警戒が広がる。さらにキューバ海域でソ連のフォックストロット級潜水艦B-59が海上封鎖線を越えようとしたため、米海軍は警告の爆雷を投下。この時、同艦は攻撃を受けた場合、核魚雷で反撃する命令を受けていたため、発射体制に入るが、同艦副艦長アルヒーポフが反対し、浮上して抗戦の意志がないことを示して引き換えしたため、危機を回避することができた。悪条件が重なり、史上最も核戦争が起きかねない日だったと言われる。 |
| 10月27日 | ケネディは、トルコのミサイル基地撤去はNATOとの関係を壊すと危惧し、26日に先に届いたフルシチョフの書簡に対して応じる返事をすることを決定。その上で、ロバート・ケネディが駐米ソ連大使ドブルイニンと密かに会談。すでに米政府・軍部では戦争も辞さない状況にあると事態の深刻さを伝え、キューバのミサイル基地撤去が確認できたら、トルコのミサイル基地撤去に応じると示す。 |
| 10月28日 | フルシチョフのもとに、米軍機撃墜の情報、アメリカ政府・軍部が強硬姿勢に転じたこと、そしてキューバのカストロ首相から強硬姿勢を求める書簡が届く。事態を理解していないかのようなカストロの姿勢に激怒したフルシチョフは、ケネディの書簡を受け取ると、すぐに応じる旨の返信をし、そのことをモスクワ放送で流し、キューバのミサイル基地撤去の命令を発する。その放送を聞いたアメリカのルメイ空軍参謀長や、アンダーソン海軍参謀長は侵攻を強く主張、カストロ首相も猛反発する。しかし危機は終息の方向へ。 |
| 11月20日 | フルシチョフはアメリカが追加で要求した条件も飲むことに同意し、これを受けて、ケネディは海上封鎖を終了。キューバ危機は終わることになる。以後、米ソはホットラインの設置などデタントへ進むことになる。一方で米ソとも同盟国との間でギクシャクし、フランスは安全保障で独自路線へシフト。中国もソ連との関係が悪化し独自に核開発に乗り出す。フルシチョフがアメリカに譲歩したのは、当時のソ連の核兵器の数が、アメリカの10分の1未満であったことから、全面戦争になっても勝てないとわかっていたからともされる。 |
| 11月21日 | 中印国境紛争は中国側の勝利に終わる。 |
| 12月10日 | 映画『アラビアのロレンス』公開。 |
| 12月21日 | ピッグス湾事件でキューバの捕虜になった亡命キューバ人および、キューバ政府に勾留されている市民らについて、5300万ドル分の食料と医薬品を条件に釈放することが決定する。交渉にあたったのは、ソ連のスパイ・アベルの弁護を担当し、ソ連に抑留されていたゲーリー・パワーズ飛行士の釈放にも関わったアメリカのジェームス・ドノバン弁護士で、捕虜1113人と市民9703人が解放されることになった。 |
| 12月24日 | カタンガ州の首都エリザベートビルでカタンガ軍とコンゴ国連軍が衝突。 |
| 1963年(昭和38年) | |
| 1月 2日 | 愛知大学山岳部13名が、富山県の薬師岳で遭難。全員が死亡。三八豪雪と呼ばれる異例の大雪の中、薬師岳に愛知大学山岳部と日本歯科大学山岳部が登頂に挑み、日本歯科大学山岳部は登頂後に悪天候でキャンプに避難。4日に無事下山したが、愛知大学山岳部は、登頂断念後、視界不良の中でコースを誤り東南尾根へ移動してしまい消息を絶つ。豪雪により捜索も断念。軽装と悪天候で、疲労と低体温症による凍死、または滑落死したものと思われる。 |
| 1月21日 | コンゴ国連軍がカタンガ州をほぼ制圧し、モイーズ・カペンダ・チョンベは敗北を受け入れ武装解除を指示し、北ローデシアへ亡命。 |
| 1月23日 | イギリスのMI6(秘密情報部)の有力者ながら、実はソビエトのスパイだったキム・フィルビーが、KGBからの亡命者アナトリー・ゴリツィンの供述から始まった捜査で、二重スパイであることが発覚し姿を消す。その後、ソ連に亡命したことが明らかにされた。ソ連のスパイ網で最も成功したと言われる「ケンブリッジ・ファイヴ」のリーダーであった。 |
| 2月28日 | 吉田巌窟王事件で、吉田石松に対し名古屋高裁で無罪判決。裁判長が吉田を巌窟王になぞらえ、「吉田翁」と呼びかけて謝罪。 |
| 3月23日 | 名古屋大学山岳部パーティが、富山県薬師岳付近に入山し、愛知大学山岳部の学生5名の遺体を発見。中日新聞がヘリを出して連携し、遺体を捜索。5月までに11名を発見。10月14日に最後の2名の遺体も発見される。 |
| 5月 9日 | アメリカ軍が1961年に続いてふたたび、軌道上に数億本の針状のダイポールアンテナを散布して通信用リングを作る実験を行い成功する。しかし科学者や各国の猛烈な抗議を受け、国連でも議題に取り上げられる事態に。通信衛星が発達したことで、結局利用されることはなかった。大量の針は徐々に大気圏へ再突入しているとみられる。 |
| 5月15日 | アメリカの核実験ローラーコースター作戦がネバダ州ネリス空軍射爆場で始まる。事故による核物質飛散に対処する実験で、核爆発を伴わないテスト。 |
| 6月16日 | ソ連の女性宇宙飛行士、ワレンチナ・テレシコワが、ボストーク6号で宇宙へと飛び立つ。 |
| 7月18日 | オーストラリアのヨーク岬半島で、熱帯雨林での核爆発の影響を調べるブローダウン作戦が行われる。オーストラリア軍、イギリス軍、カナダ軍、アメリカ軍が参加。熱帯雨林の中に建設した塔の上に設置した45tのTNT火薬を爆破させ、ジャングル内での爆風の影響を調査。核兵器は使用せず。 |
| 8月 5日 | アメリカ、イギリス、ソ連の3国外相により部分的核実験禁止条約がモスクワで調印される。地下核実験を除く、地上や水中、宇宙での核実験を禁止する条約。 |
| 8月13日 | コンゴ共和国の首都ブラザビルで市民による反乱が起きる。フルベール・ユールー大統領によるアフリカ人利益擁護民主連合(UDDIA)一党独裁制移行へ反発したことが直接的な要因だが、旧宗主国フランスとの連携が、植民地時代と変わらぬ政策として不満が高まっていたことが背景にある。 |
| 8月15日 | コンゴ共和国のフルベール・ユールー大統領が失脚。この市民革命は「栄光の三日間」と呼ばれる。 |
| 8月28日 | 人種差別撤廃を訴えたワシントン大行進が行われ、リンカーン記念館でキング牧師が有名な「I have a dream」の演説を行う。 |
| 10月 8日 | 英連邦王国であるウガンダで、ブガンダ王ムサテ2世が大統領となり、総督が廃止されて共和制に移行。 |
| 10月 9日 | イタリアのバイオントダムのダム湖岸にあったトック山が大規模な地すべりを起こし、土砂がダム湖に流れ込む。高さ250mの津波が発生し対岸の中腹にあったカッソ村が飲み込まれた他、ダムの天端を超えて、下流へと流れ落ち、ピアーヴェ川沿いの村々を押し流す。死者行方不明者2000人以上。ダム湖が出来たことで地質が脆くなったためだが、ダムそのものは崩壊しなかった。 |
| 11月 1日 | ベトナム共和国(南ベトナム)でズオン・バン・ミン将軍らによる軍事クーデターが起き、ゴ・ディン・ジエム大統領と弟で大統領顧問のゴ・ディン・ヌーが殺害される。ゴ大統領がカトリックで仏教徒を大弾圧し、秘密警察を動かしていたゴ・ディン・ヌー、その妻で焼身自殺した僧侶を「人間バーベキュー」と呼んで嘲笑したマダム・ヌーに対する反感が大きな要因。アメリカはクーデター情報を得ていたが、ゴ政権を見捨てたといわれる。 |
| 11月 9日 | 鶴見列車事故。鶴見近くの国鉄東海道本線で貨物列車の脱線に旅客列車2編成が多重衝突事故を起こす。死者161人、負傷者120人。 |
| 11月 9日 | 三井三池三川炭鉱炭塵爆発事故。三川坑内で石炭を積んだトロッコが暴走脱線し、大量の炭塵が構内に充満して粉塵爆発が生じたもので、救援が遅れたこともあり死者458名、一酸化炭素中毒患者839名を出す。 |
| 11月10日 | 新興国競技大会がインドネシアのジャカルタで開催される。国連やIOCとの関係が悪化していたインドネシアが、オリンピックに代わる大会として呼びかけたもので、最終的に新興国だけでなく、ヨーロッパ諸国や共産圏諸国、日本も含めた51カ国が参加した。参加選手はオリンピック出場資格を失うことになったが、大学生選手や、オリンピック出場候補選手以外を出すなどして調整した国もあった。 |
| 11月22日 | アメリカ大統領ジョン・F・ケネディが、訪問先のテキサス州ダラス市街でパレード中に何者かに狙撃され死亡。テキサス州のジョン・ボウデン・コナリー知事も胸を撃たれ重症を負う。公式には現場近くの教科書ビルにいたリー・ハーヴェイ・オズワルドが犯人とされているが、狙撃位置や単独犯行では不可解な点が多く、今もって謎の多い事件。 |
| 11月23日 | 日米間初のテレビ放送の衛星中継が行われ、前日に起こったケネディ暗殺のニュースが伝えられる。 |
| 11月24日 | ケネディ暗殺の容疑者として逮捕されたリー・ハーヴェイ・オズワルドがジャック・ルビーに射殺される。 |
| 12月 8日 | プロレスラーの力道山が赤坂のナイトクラブ「ニューラテンクォーター」で暴力団員に刺される。 |
| 12月12日 | ケニアが英連邦王国としてイギリスから独立。 |
| 12月15日 | 力道山が化膿性腹膜炎で死去。 |
| 12月19日 | 東アフリカにあるスルタンのザンジバル王国がイギリスから独立。 |
| 12月31日 | ローデシア・ニヤサランド連邦が解体。ニヤサランドは分離。 |
| 1964年(昭和39年) | |
| 1月 3日 | 福岡・静岡・東京で計5人を殺害した犯人、西口彰が、熊本県で逮捕される。福岡で起きた殺人事件の犯人と目されて早くから全国に指名手配されていたが、弁護士を装うなどして全国を転々として逃走。各地で殺人や詐取事件を繰り返す。熊本県玉名市の教誨師宅を尋ねた際に、同家の10歳の娘が正体を見破り、通報された。 |
| 1月 5日 | ローマ教皇パウロ6世が、コンスタンディヌーポリ全地総主教アシナゴラス1世とエルサレムで会談し、東西教会の和解を図る。 |
| 1月12日 | 独立したばかりのザンジバル王国で、警官ジョン・オケロ率いる40人ほどが警察署や放送局を襲撃。国王一家が国外へ脱出する。抑圧されていたアフリカ系黒人住民が、支配層のアラブ系住民を襲撃。最終的に1万2000人以上が殺害される。社会主義のザンジバル人民共和国が成立。 |
| 1月30日 | スタンリー・キューブリックの代表作の一つ『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』がアメリカで公開される。ケネディ暗殺事件の影響で公開が延期されていた。 |
| 3月18日 | 早川電機が卓上電子計算機(電卓)の商品化を発表。 |
| 3月20日 | 学習院大学ヨット遭難事故。荒天の中、ヨットレースに向かうため、横浜から出港した学習院大学ヨット部の翔鶴号が三浦半島南端付近で遭難。乗っていた学生5名全員が死亡。吉田茂の孫と、元自衛隊幹部の松平永芳の長男がいたためか、捜索に自衛隊までが出動したことへの批判を受けた。 |
| 4月24日 | ソコロUFO事件。ニューメキシコ州ソコロの郊外で、スピード違反の車を追跡していたロニー・ザモラ保安官が、大きな爆発音と炎が上がるのを見たため、そこへ駆けつけると、大きな球体があり、そこに2人の人物が立っていて、なにかの事故と思った保安官が近づくと2人は物体に乗り込み、物体は轟音を発して離陸し飛び去っていった、という目撃事件。そのあと数件の似たような目撃例が警察に寄せられた。UFO説の他に気球説もあり、ニューメキシコ工科大学の学生が起こしたいたずらという説もある。 |
| 4月26日 | ザンジバル人民共和国のカルメ大統領が、情勢の安定とオケロの失脚を図り、隣国のタンガニーカに軍事介入を要請。この日、タンガニーカ・ザンジバル共和国が成立。のちのタンザニア連合共和国。連合初代大統領はジュリウス・ニエレレ。 |
| 6月11日 | 昭和電工川崎工場のプロピレンオキサイド製造プラントで爆発があり、18人が死亡、重軽傷者117名。酸化プロピレンタンクの増設工事の火花が、超可燃性の酸化プロピレンに引火したため。 |
| 7月 6日 | 1949年の下山事件で、仮に殺人とした場合の時効が成立する。 |
| 7月 6日 | ニヤサランドが英連邦王国のマラウィとして独立。 |
| 7月14日 | 品川勝島倉庫爆発火災事故。寶組勝島倉庫で火災が発生し、保管していたメチルエチルケトンパーオキサイドに引火爆発。倉庫が崩壊し消火活動中の消防士ら19人が死亡、158人が重軽傷。 |
| 7月21日 | シンガポール人種暴動。シンガポールでマレー政府の優遇政策を求めるマレー系住民と中国系住民との間でデモ隊同士が衝突。暴動に発展。 |
| 7月23日 | サンフランシスコ沖でオペレーションチェイス1が実施される。不要になった大量の弾薬をリバティー船ジョン・F・シャフロスに乗せて爆沈処分するもの。 |
| 7月24日 | ウッドリバー臨界事故。アメリカロードアイランド州ウッドリバージャンクションのユニオン・ニュークリア社ウッドリバーウラン回収施設で、ウラン濃縮装置に詰まったウラン溶液を回収して薬品容器に入れておいたところ、薬品と勘違いした作業員が調整タンクに入れたため、核分裂臨界状態になり、作業員1人が大量の放射線を浴びて死亡。その事故処理中に再度臨界状態が起きて被曝する事故が起きる。 |
| 7月31日 | 第3代琉球高等弁務官キャラウェイが退く。後任はアルバート・ワトソン2世。強権的な統治をしていたキャラウェイは、ライシャワー駐日大使と対立。事実上の失脚であった。 |
| 8月 2日 | アメリカ海軍の駆逐艦マドックスが、北ベトナムのトンキン湾で哨戒活動中、北ベトナム軍の魚雷艇3隻に攻撃される。いわゆるトンキン湾事件。 |
| 8月 4日 | この日トンキン湾で再び米艦艇が北ベトナム軍の攻撃を受けた、という発表がある。これを理由に、アメリカはベトナム戦争に本格的に参入する。4日の事件は、後にアメリカ政府によるでっち上げだったと判明する。 |
| 8月17日 | 人気俳優の佐田啓二が、別荘から帰京する途中、山梨県韮崎市で乗っていた車の事故により死去。運転手と同乗者2名も重軽傷を負う。主役で出演中だったNHKドラマ『虹の設計』は、脚本を変更の上で、撮影済みのVTR映像などを使い最後まで放送された。 |
| 8月31日 | ホテルニューオータニ・ザ・メインが竣工。東京オリンピックの需要のためで、高さ72m、17階建て。規制緩和後初の高層ビルで、国会議事堂を抜いて日本一の高さとなる。翌日開業。 |
| 9月17日 | オペレーションチェイス2がニュージャージー沖で実施される。リバティ船に6666tの爆薬と弾薬などを積んで海没処分するが、沈没5分後に立て続けに3回大規模な爆発が起きる。世界各地の地震計で観測された。これを受けてチェイス計画を水中核爆発を検出する研究に利用するようになる。 |
| 9月21日 | アメリカ軍の試作超音速爆撃機XB-70の1号機が初飛行。 |
| 9月28日 | 初のプライバシー侵害を争った『宴のあと』事件で、侵害を認める判決が出される。 |
| 10月 1日 | 東海道新幹線開業。当初運行は0系12両編成で最高速度は時速210km。東京駅-新大阪駅間が「ひかり」で4時間、「こだま」で5時間と、日帰りが可能になる。開業時は東京・新横浜・小田原・熱海・静岡・浜松・豊橋・名古屋・岐阜羽島・米原・京都・新大阪の12駅。 |
| 10月 7日 | シドニー・ルメットの『未知への飛行』がアメリカで公開。同じコロンビア映画で、同じ米ソ核戦争を描いた『博士の異常な愛情』とかぶったが、『博士の異常な愛情』がコメディ要素が強いのに対し、『未知への飛行』はシリアスな内容になっている。『博士の異常な愛情』を撮ったキューブリックの要請と盗作疑惑訴訟の影響で、『未知への飛行』は公開が8ヶ月遅れた。 |
| 10月10日 | 第18回夏季オリンピック東京大会開催。 |
| 10月16日 | 中国がロプノールで初の核実験「596工程」を実施し成功する。核出力22Kt。各国が非難する中、日本共産党は「防衛のための措置」としてこれを容認。 |
| 10月21日 | 映画『マイ・フェア・レディ』公開。 |
| 10月24日 | イギリスの植民地北ローデシアが、ザンビアとして独立。東京オリンピック出場国だったため、開会式時点では北ローデシア代表、閉会式時点ではザンビア代表となった。 |
| 10月27日 | 中国が準中距離弾道ミサイル東風2号Aを使い核実験を実施。核出力20kt。 |
| 11月12日 | 核爆発の艦船への影響を調べるセーラーハット作戦アルファ実験がハワイ・カホオラウェ島の近海で行われる。核兵器は使わず、TNT火薬20tで水中爆発実験。14日に同じ内容で再度実験。 |
| 1965年(昭和40年) | |
| 1月15日 | チャガン核実験。ソ連が農地開拓灌漑用の貯水湖を造成するために行った地下核実験。クレーターに水が流れこんでチャガン湖が形成されるも、大規模な汚染により灌漑できず失敗に終わる。 |
| 2月 1日 | ソ連の核実験の是非をめぐって、容認派の共産党系の原水爆禁止日本協議会(原水協)から批判派の社会党・総評系のグループが分裂し、原水爆禁止日本国民会議(原水禁)が結成される。 |
| 6月19日 | アメリカ国防原子力支援局とアメリカ海軍によって、ハワイでセーラハット作戦ブラボー実験が実施される。核兵器の爆風が艦船に及ぼす影響を調べるもので、実験では核兵器は使わず、カホオラウェ島の海岸に454tのTNT火薬を積み上げ点火。すぐ沖合に停泊した軽巡洋艦アトランタなど3隻を標的艦として行われた。 |
| 2月10日 | 自衛隊で行われた戦争時の対応を研究した「三矢研究」が国会で問題にされる。 |
| 2月14日 | 全日空のDC-3型貨物機が知多半島上空での連絡を最後に消息を絶つ。遭難地点がわからず三河湾から房総半島に至る海岸線と南アルプス一帯を捜索するも発見できず。1966年に機体は発見される。 |
| 2月18日 | ガンビアがイギリスから独立。 |
| 2月21日 | アメリカの黒人運動指導者マルコムXが、マンハッタンのオードゥボン舞踊場で演説中に暗殺される。 |
| 3月 2日 | 映画『サウンド・オブ・ミュージック』公開。オーストリアからアメリカへ亡命し、音楽興行で人気を得たトラップ一家のマリア・フォン・トラップの自叙伝をもとに創作されたブロードウェイミュージカルを映画化したもの。世界的に大ヒットした映画だが、子どもたちの年齢や、亡命時の脱出ルート、登場人物の設定、社会背景など、史実とはかなり異なっている。 |
| 3月14日 | 西表島に生息しているヤマネコが日本哺乳動物学会により新種と鑑定される。のちイリオモテヤマネコと名付けられる。 |
| 3月14日 | 北海道日高山脈の札内川上流十の沢付近で、北海道大学山岳部のパーティ6名が雪崩に遭い遭難。全員が死亡。悪天候の中雪洞を掘って避難していたところに非常に大規模な雪崩が起きたもので、大量のデブリの下に埋もれた。所有していた地図に遺書を残したリーダーの沢田義一は遭難後4日程生存して脱出を図ったが果たせなかった(ほかは即死か)。6月13日と16日に全員の遺体が発見された。 |
| 3月18日 | 歴史的建造物を保存展示する博物館「明治村」が開園。 |
| 3月28日 | 横浜市戸塚区に五重塔のようなデザインのホテルエンパイア(現横浜薬科大学図書館、高さ68m)が開業。 |
| 4月16日 | セーラハット作戦チャーリー実験が実施される。前回同様、カホオラウェ島の海岸に454tのTNT火薬を積み上げ点火。すぐ沖合に停泊した軽巡洋艦アトランタ、ミサイル巡洋艦イングランド、カナダ海軍駆逐艦フレイザーなどを標的艦として行われた。 |
| 5月18日 | イスラエルのスパイでシリア政府中枢にまで浸透していたエリヤフ・コーヘンがダマスカスのマルジェ広場で処刑される。のちの第3次中東戦争が短期間でイスラエルの圧勝に終わったのは、コーヘンのもたらした情報があったためだとも言われる。 |
| 6月19日 | セーラハット作戦デルタ実験が実施される。前回同様、カホオラウェ島の海岸に454tのTNT火薬を積み上げ点火。すぐ沖合に停泊した軽巡洋艦アトランタ、駆逐艦タワーズを標的艦として行われた。いずれの実験でも艦の上部構造物に被害は出たが、艦自体には大きな影響は出ていない。 |
| 6月22日 | 日韓基本条約成立。 |
| 8月 9日 | シンガポールがマレーシア連邦から追放される形で独立。 |
| 8月11日 | ロサンゼルスの郊外にあったワッツ市で警察の交通取締に反発した黒人住民が暴動を起こす。ワッツ暴動。背景には人種差別や貧困による不満の高まりがあり、各地で同様の事件が相次ぐ。 |
| 8月27日 | フランスを中心に世界的に活躍していた建築家ル・コルビュジエが没する。 |
| 8月 | パキスタンの民兵がカシミール地方インド側の実効支配地域に進出していたため、インドがパキスタンを攻撃。第二次印パ戦争が勃発する。 |
| 8月 | フランク・ハーバートの小説『デューン』シリーズの第一作『デューン/砂の惑星』が発売される。 |
| 9月23日 | 国連の仲介で、第二次印パ戦争が停戦。 |
| 9月30日 | インドネシアで「9・30事件」が発生。大統領親衛隊第一大隊長のウントゥン・ビン・シャムスリ中佐がクーデターを起こし、陸軍の将官6人らを殺害。放送局などを占領する。スカルノ大統領から委任された戦略予備軍司令官スハルト少将がこれを鎮圧。スハルトは親共路線のスカルノ政権の有力支持政党であるインドネシア共産党が事件に関わったとして弾圧。50万人とも、300万人とも言われる犠牲者を出したと言われる。スハルトは権力を手中にし、スカルノは求心力を低下。元々のクーデターに中国が関わっていたという説もあり、一方スハルトにはCIAが支援したとも言われる。 |
| 10月 7日 | マリアナ海域漁船集団遭難事件。マリアナ諸島近海で操業していた、日本のかつお・まぐろ漁船の船団が台風29号に遭遇して遭難。死者1名、行方不明者208名を出す。 |
| 11月 1日 | 南ローデシアが、ローデシアとしてイギリスからの独立を宣言。ただし国際社会が要求していた黒人への権利を認めない白人政権だったため、国際的には承認されず。 |
| 11月 9日 | 北アメリカ大停電。カナダのオンタリオ州と、アメリカの北東部7州で大規模な停電が発生。ナイアガラにある発電所で、寒波到来による需要急増が供給を上回ったことで送電システムが停止したことによるもの。ニューヨーク大停電と呼ばれる出来事の一つ。 |
| 11月10日 | 中国共産党員の姚文元が上海の新聞『文匯報』に「新編歴史劇『海瑞罷官』を評す」という論稿を発表。歴史学者呉唅が京劇のために書いた『海瑞罷官』という作品を、社会主義政策を批判したものだと攻撃。毛沢東も同調し後に膨大な犠牲者を出した文化大革命のきっかけとなる。海瑞は明朝の官吏で腐敗する地方役人を処罰し、嘉靖帝にも諫言したことで知られる人物。地方役人が農民から奪った土地を海瑞が農民に返すくだりが、人民公社を解体して土地所有を認めさせるものだと姚文元は主張した。呉唅はこれが原因で投獄され獄死した。 |
| 11月19日 | 佐藤栄作内閣が戦後初の赤字国債発行を閣議決定。1年限りとする。 |
| 12月 4日 | 1965年ニューヨーク上空旅客機空中衝突事故。イースタン航空853便ロッキード1049Cスーパーコンステレーションと、トランス・ワールド航空42便のボーイング707が、ニューヨーク上空で空中衝突。イースタン機の機長がトランス・ワールド機が接近していると誤認して回避しようとしたために逆に衝突してしまったもので、トランス・ワールド機は左翼の一部を失ったが緊急着陸に成功。イースタン機は右側の水平尾翼と垂直尾翼を失ったが、エンジンの出力で調整しながら郊外のノースセーラムの原野に不時着し、機長と乗客3名が死亡したもののほとんどが助かった。空中衝突事故では珍しく軽微で済んだ事故。 |
| この年、ガーナにアコソンボダムが完成。世界最大の人造湖ヴォルタ湖が出来る。 | |
| 1966年(昭和41年) | |
| 1月 4日 | フランス・リヨンの近郊フェーザンの製油所でプロパン流出事故から爆発(BLEVE=沸騰液膨張蒸気爆発)が起き、球状プロパンタンクが次々と倒壊。ガソリンタンクなどにも引火し、大規模な火災となる。消防士ら18人が死亡、81人が負傷する。 |
| 1月14日 | セルゲイ・パーヴロヴィチ・コロリョフが心臓手術の最中に死去。アメリカで活躍したフォン・ブラウンと並ぶ、ソ連を代表するロケット研究者。ソ連の大陸間弾道ミサイルの開発を行ったため、その存在が明らかになったのは死後になってから。 |
| 1月17日 | パロマレス米軍機墜落事故。スペイン南部で米軍のB-52戦略爆撃機が空中給油機と衝突して墜落し、水爆4発のうち3発が地上に激突して起爆用爆薬が爆発、核爆発には至らなかったが、核物質が飛散し大規模な汚染を引き起こす。1発は海中に没する。 |
| 1月23日 | タイヴィン虐殺事件。ベトナム戦争に参戦した韓国陸軍首都機械化歩兵師団の部隊が、2月26日にかけて、ビンディン省タイソン県タイヴィン村の15集落の住民1200人あまりを虐殺。 |
| 2月 9日 | 日本共産党の代表団が中国へ向けて出発。ベトナム、中国、北朝鮮と「ベトナム侵略反対国際統一戦線」の結成を目的としたもの。 |
| 2月25日 | 第二次印パ戦争の停戦合意を受け、両軍が完全撤退。国連軍事監視団がカシミール地方に配備される。 |
| 2月26日 | ゴザイ虐殺事件。ベトナム戦争に参戦した韓国陸軍首都機械化歩兵師団の部隊が、ビンディン省タイソン県タイヴィン村のゴザイ集落で住民380人を虐殺。ビンディン省ではビンアン村でも韓国軍により虐殺事件が起きている。 |
| 2月28日 | 「ベトナム侵略反対国際統一戦線」の結成をめぐり、中国共産党と日本共産党の間で、「反米」か、「反米・反ソ連」とするかで意見が対立(中国側は反ソも含める主張)。共同コミュニケが作られず。 |
| 3月 5日 | 英国海外航空(BOAC)の911便、ボーイング707旅客機が富士山上空で空中分解。124名全員が死亡する。 |
| 3月11日 | 前年の9月30日事件を受けて求心力を失ったインドネシアのスカルノ大統領が、スハルトに権限を譲渡する命令書を出し、事実上の失脚。 |
| 3月21日 | 1960年のシャープビル事件の日に合わせて、国連総会で国際人種差別撤廃デーが決議され、3月21日は「人権の日」と定められる。 |
| 3月21日 | 北朝鮮を訪問していた日本共産党代表団が、帰国のため北京に寄った際、中国側から「ベトナム侵略反対国際統一戦線」に関する共同コミュニケの発表を再度持ちかけられる。その後、ふたたび反ソ連を入れるかで揉めるが、妥協して意見の異なる内容を排除したコミュニケを作成。しかしこれが毛沢東の反対で頓挫する事態に。日本共産党が中国に対し態度を硬化する原因となる。中国共産党も日本共産党を修正主義と批判。 |
| 4月27日 | 日本共産党第四回中央委員会で、帰国した宮本顕治が毛沢東を批判。これに対し中国派のメンバーが反発。日本共産党は内部分裂状態となる。後に中国派は追放され新左翼へと変わる。また善隣学生会館事件などの遠因となった。 |
| 5月 1日 | 文化大革命の余波を受けて、北京に来ていた内モンゴル自治区主席のウランフが捕らえられる。 |
| 5月22日 | スウェーデンの民間パイロットであるカール・グスタフ・フォン・ローゼンが、ビアフラ戦争でのビアフラ支援のため、スウェーデン製の小型飛行機マルメMFI-9Bを5機購入してロケット弾で武装(ビアフラベイビーと呼ばれるミニコイン機)、これでナイジェリア軍の空軍基地を数度に渡り空爆する。ナイジェリア軍はミグ戦闘機などを多数破壊され、軽飛行機でも十分戦力になることが証明された。ローゼンはスウェーデンの伯爵で、KLM航空のパイロットをした後、主にアフリカで国連や赤十字のための航空作戦に関わり、のちにオガデン戦争で死亡した。父親は探検家でフィンランド空軍の創設に関わったエリック・フォン・ローゼン、叔母はドイツのヘルマン・ゲーリングの最初の妻カリン。 |
| 6月 2日 | ロバート・A・ハインラインの『月は無慈悲な夜の女王』発売。 |
| 6月 8日 | アメリカ軍の試作超音速爆撃機XB-70がゼネラル・エレクトリック社の宣伝映画撮影中に、一緒に飛行していたF-104N戦闘機が急接近して衝突し墜落。 |
| 6月13日 | アメリカ連邦最高裁の「ミランダ対アリゾナ州事件」の再審で、逮捕する際に被疑者の権利を述べるミランダ警告が義務付けられる。 |
| 6月29日 | ビートルズが初来日。大規模な警備が敷かれる。 |
| 6月30日 | ビートルズ日本公演始まる。2日まで。 |
| 7月 4日 | 閣議で新首都空港建設予定地が千葉県成田市三里塚に決定。 |
| 7月10日 | 新首都空港建設予定地が千葉県成田市三里塚に決定したことをうけて、地元住民による三里塚芝山連合空港反対同盟が結成される。 |
| 7月10日 | ウルトラマンの日。ウルトラQの後継番組としてウルトラマンが放送されるに先立ち、杉並公会堂でのイベント『ウルトラマン前夜祭 ウルトラマン誕生』が放送される。 |
| 8月 1日 | アメリカのテキサス大学オースティン校の高層棟テキサスタワーから、同大学大学院の院生であるチャールズ・ホイットマンが、カービン銃やライフル銃で人々を銃撃。市民や警官ら15人が死亡する。 |
| 8月 1日 | プリンス自動車が日産自動車に吸収合併される。プリンス自動車は旧立川飛行機と旧中島飛行機という2つの航空会社に系譜を持つ自動車メーカーでプリンスやスカイラインを開発した。 |
| 8月 2日 | ずさんなインパール作戦を強行して多くの兵士を死亡させ、最後まで自己弁護し、部下のせいにした牟田口廉也中将が病死。 |
| 8月16日 | 内モンゴル自治区主席のウランフが失脚。以降、内モンゴル人民革命党は粛清の対象とされ、無関係のモンゴル人も含め、70万人以上が逮捕され、数万人が処刑されたとみられる。 |
| 8月18日 | 毛沢東が天安門で、紅衛兵の女性最高指導者である宋彬彬(八大元老のひとり宋任窮の娘)と会談。宋彬彬は毛沢東の腕に赤い腕章を巻いた。この直後から、天安門広場に詰めかけていた大勢の紅衛兵が興奮して暴徒と化し、北京市内で多数の市民を殺害する事件を引き起こす。通称「赤い八月」事件。暴力的な紅衛兵運動は全国へと拡大する。当時宋彬彬は北京師範大学附属女子中学の生徒で、自ら副校長の女性教師卞仲耘を撲殺したほどの急進的な「造反派」として知られた人物。 |
| 9月 3日 | 深谷駅急行停車指示問題が起こる。佐藤第2次改造内閣で運輸大臣だった荒舩清十郎が、自身の選挙区内にある高崎線深谷駅に急行を停車させるよう国鉄に指示したとして、問題になった事件。 |
| 9月 6日 | 産児制限運動家として知られたマーガレット・サンガーが死去。 |
| 9月30日 | イギリス保護領ベチュアナランドがボツワナとして独立。初代大統領は、独立運動を率いた地元ングワト族の王子セレツェ・カーマ。カーマは、独立後に発見されたダイアモンド鉱山からの収益を私腹せず、教育やインフラ投資に回したことで、ボツワナは世界最貧20カ国からアフリカ上位5カ国の一つにまで発展した。 |
| 10月 4日 | レソト王国がイギリスから独立。初代国王は、バストランド首長であるバモコテリ朝セーイソ家のモショエショエ2世。 |
| 10月 5日 | 東京皇居堀端の、解体された東京海上ビルディング(1918年竣工)の跡地に建築家前川國男らが高さ127.768m、30階建ての超高層ビル建設計画を提出する。 |
| 10月 5日 | アメリカミシガン州ラグーナビーチの高速増殖炉フェルミ1号炉で汚染ガスが屋内に漏出する事故が発生。原子炉を停止した際に燃料棒が溶融する。炉心溶融事故の最初の例とみられる。 |
| 10月15日 | ニューメキシコ州アラモゴルドの世界最初の核実験場がアメリカの史跡に指定される。 |
| 10月21日 | カザフの首都アルマトイを泥流や土石流から守るため、メデオ渓谷にダムを建設することになり、硝酸アンモニウム3600tを使って大規模な発破作業を行う。 |
| 11月12日 | モスマン事件が起こる。アメリカ・ウェストバージニア州で、赤い目をして翼の生えた不気味な人物が目撃される。以後、同州各地や周辺の州でも目撃例が相次ぐ。大型のフクロウなどの誤認説から、同地でかつて虐殺されたインディアンの呪い説、宇宙人のペット説まで様々に取り沙汰されたが、正体は不明。 |
| 11月13日 | 全日本空輸533便YS-11が、悪天候の中、松山空港への着陸に失敗し、やり直そうとして海上に墜落。乗員乗客50人全員が死亡する。 |
| 11月15日 | ローマ教皇庁教理省教令により禁書目録が公式に廃止される。 |
| 11月 | 徳島ラジオ商殺人事件で有罪となった冨士茂子が模範囚として出所。のち再審で無罪判決となる。 |
| 12月 3日 | マカオ暴動。中共系住民と総督が対立。武力鎮圧されるが、中華人民共和国が、これを外交問題に発展させる。 |
| 12月26日 | 中華人民共和国が中距離弾道ミサイル「東風3号」の発射実験に成功。 |
| 12月27日 | 佐藤首相が、相次ぐ不祥事を受けて、勢力回復を図るため、第54回国会が召集された初日に衆議院を解散。黒い霧解散。 |
| 12月29日 | 前年に消息を絶った全日空の貨物機が、静岡県磐田郡の南アルプス中ノ尾根山の頂上付近で発見される。乗員2名の遺体も発見。墜落の原因は不明。 |
| 1967年(昭和42年) | |
| 1月27日 | アポロ計画のAS-204宇宙船が、ケープ・カナベラル基地の34番発射台での発射予行演習中に火災を起こし、乗員のガス・グリソム、エドワード・ホワイト、ロジャー・チャフィーの3名が死亡。船内機器の火花、可燃物質による素材、船内の高濃度の酸素が火災を一気に拡大したものとみられる。 |
| 2月 8日 | スウェーデンの国産戦闘機サーブ37ビゲンが初飛行。デルタ翼にカナードをつけるという当時としては異色のデザイン。またトンネルや小型シェルターでも整備できるように設計されており、高性能で運用もしやすいことから、世界中で高評価を得たが、サポートへの懸念や航続距離の問題から採用国はなく輸出は失敗に終わった。 |
| 2月11日 | 戦前は神武天皇の即位日として祝日だった紀元節が、建国の記念日として復活する。 |
| 2月28日 | 善隣学生会館事件。文京区にあった善隣会館で、同館の後楽寮に住む中国人留学生らと、同館に間借りしていた日本共産党系の日中友好協会が対立。中国共産党と日本共産党の関係悪化に影響したもので、この日、留学生らと協会関係者が口論になり、そこへ日本共産党員と、同党連携組織の民主青年同盟(民青)のメンバーが援軍として殺到。暴力沙汰に発展する。その後も対立は解消せず。 |
| 3月 2日 | 善隣学生会館事件で、日本共産党中央委員会のメンバーらが指揮して華僑学生らを襲撃し、7人が重症を負う。日本共産党は華僑学生側に襲撃された正当防衛と主張。しかしこの頃の民青は暴力組織と化しており、新左翼系学生ともしばしば事件を起こしている。 |
| 3月 6日 | スターリンの娘であるスヴェトラーナ・アリルーエワがインドのニューデリーにあるアメリカ大使館に亡命を申請し認められる。 |
| 3月29日 | 北海道恵庭町の酪農家が演習の騒音に対し、自衛隊が約束を守らなかったとして演習場のケーブルを切断し、自衛隊の憲法問題にまで発展した「恵庭事件」の一審判決で、被告人全員が無罪。検察は上訴せず確定する。なお憲法問題は、被告人無罪により判断されず。 |
| 4月14日 | カザフのメデウダム建設で、再度、硝酸アンモニウム3900tを使い大規模な爆破を行う。 |
| 4月15日 | 超高層ビル計画だった東京海上ビルディング本館建設申請が東京都より却下される。ここから美観論争、皇居を見下ろすことの是非などが大論争となる。超高層ビル第一号は霞が関ビルディングに抜かれることに。 |
| 4月16日 | 東京都知事に美濃部亮吉が当選。 |
| 4月23日 | ソビエトの有人宇宙船ソユーズ1号が打ち上げられるも、軌道上でのトラブル発生により帰還途中にメインパラシュートが開かず地上に激突。乗員のウラジーミル・コマロフ飛行士が死亡。 |
| 4月24日 | NASAは火災事故で宇宙飛行士3人が死亡したアポロ宇宙船AS-204の通称だったアポロ1号を正式名称と決定。遺族などの要望を受けたもの。 |
| 4月29日 | モハメド・アリが徴兵拒否を理由にヘビー級王座のタイトルを剥奪される。 |
| 5月 4日 | 北朝鮮の朝鮮労働党中央委員会第4期第15次総会で、それまで金日成を支えてきた有力派閥「甲山派」への粛清が始まり、トップの朴金喆常任政治局員は修正主義者の批判を受けて自殺未遂を図る(翌年処刑)。甲山派壊滅で、朝鮮労働党は満州派のみとなり、金日成の独裁は完成する。 |
| 5月30日 | ロータリーエンジンを搭載した世界初の量産型実用車マツダコスモスポーツ発売。 |
| 6月 2日 | ベンノ・オーネゾルク事件。イラン皇帝モハンマド・レザー・パフラヴィーの西ベルリン訪問に反対するデモを警察が鎮圧しているさなか、西ベルリン警察上級刑事長カール=ハインツ・クラスが、デモに参加していた大学生オーネゾルクを取り押さえた上で頭部を撃って射殺。クラスの銃撃は居合わせた警官たちも驚いたが、デモ隊が武装していたという証言が相次ぎ、裁判では無罪となった。それに反発した学生らは、東ドイツなどの支援を受けてテログループ「ドイツ赤軍(RAF)」などを結成し、数々のテロを引き起こすことになる。さらに事件の40年後、実はクラス自身が東ドイツ秘密警察シュタージのエージェント(スパイ)として活動していたことが判明する事態となり、この銃撃事件は反政府運動を起こすための東ドイツによる工作も疑われたが、証拠はない。 |
| 6月 5日 | 第三次中東戦争勃発(6日間戦争)。イスラエルの空・陸軍による電撃作戦で、短期間でヨルダン川西岸、ガザ地区、シナイ半島全域、シリアのゴラン高原を占領。アラブ側は初戦で大敗を喫する。アラブを支援し中東への進出を図るソ連が、イスラエルとシリアの紛争を利用してエジプトに働きかけて軍事動員させ、それにイスラエルが危機感をいだき先制攻撃に踏み切ったとされる。 |
| 6月 8日 | イスラエルとエジプトが停戦。 |
| 6月 8日 | シナイ半島沖でアメリカ海軍のベルモント級技術調査艦リバティーがイスラエル空軍と海軍の攻撃を受け大破する事件が起きる。沈没は免れたが34人が戦死し173人が負傷。誤認攻撃かは不明。アメリカは事故として処理。リバティは情報収集のために活動していた。 |
| 6月10日 | イスラエルとシリア停戦。第三次中東戦争停戦。小規模な紛争はこのあとも継続して続く。イスラエルは圧勝したものの、これによって欧米の支援を失い、イスラエル独自の兵器開発に乗り出すきっかけにもなっている。また勝利は慢心へとつながり、次の第4次中東戦争の緒戦での敗北へとつながったと言われる。 |
| 6月17日 | 中国が初の水爆実験「第6テスト」をロプノールで行う。核出力3.31Mt。 |
| 6月18日 | 山陽電鉄爆破事件。電車内に置かれていた爆弾が爆発し、乗客2名が死亡、29名が重軽傷。犯人は捕まらず時効。 |
| 7月 2日 | アメリカの核実験監視衛星ヴェラがガンマ線を捉える。その後、天体から放出されたガンマ線バーストと初めて確認される。GRB 670702と命名。 |
| 7月 6日 | ナイジェリア東部州の州知事だったチュクエメカ・オドゥメグ・オジュク中佐がビアフラ共和国を称して東部の独立を宣言。北部のハウサ族と西部のヨルバ族主体の政府の偏重政策と東部のイボ族に対する虐殺などに反発し、豊富な資源を前提に独立を図ったもの。ビアフラ戦争が勃発。米英ソを含む主要各国とアラブ勢力はナイジェリアを、フランス・南アフリカ・イスラエルなどがビアフラを支援。 |
| 7月29日 | 北ベトナムの爆撃作戦に参加していた米空母フォレスタルの甲板でロケット弾誤射による爆発事故が起こり、死者132名、重軽傷者62名、行方不明者2名を出す大惨事となる。 |
| 8月 3日 | 北京空港事件。日中の共産党の関係が悪化する中、赤旗北京特派員の紺野純一と、中国を訪問していた日本共産党中央委員の砂間一良が、北京首都空港から平壌経由で日本へ帰国しようとした際、紅衛兵や日本人留学生等による「日本人紅衛兵」を名乗る集団に暴行を受け重症を負う。両名は平壌で治療を受けた後に帰国した。事件現場には当時中国に移住していた西園寺公一もいた。 |
| 8月13日 | 映画『俺たちに明日はない』公開。 |
| 9月 2日 | シーランド公国独立宣言。元イギリス陸軍少佐のパディ・ロイ・ベーツが、イギリスの領海外にある放棄されていた海上要塞跡を占拠し、「シーランド公国」と称して独立を宣言。 |
| 9月21日 | ロッキード社の攻撃ヘリコプター、AH-56Aシャイアンが初飛行。世界初の攻撃ヘリともされるが、後にアメリカ陸軍の採用が取り消しになり量産はされなかった。最後尾に推進用のプロペラがついている独特の形状をしている。 |
| 10月 9日 | チェ・ゲバラが、ボリビア軍に捕らえられ射殺される。 |
| 10月10日 | 宇宙条約が発効。宇宙空間や月、他の天体での国家活動を制限する国際条約。 |
| 10月17日 | 清朝のラストエンペラー愛新覚羅溥儀が北京で死去。 |
| 10月18日 | ソ連の金星探査機ベネラ4号が金星に到達し、観測用カプセルを投下。はじめてその大気圏を調査する。 |
| 10月19日 | アメリカの金星探査機マリナー5号も金星に到達し、金星の周りをフライバイ飛行しながらベネラ4号と共に金星を調査。 |
| 11月15日 | アメリカのロケットプレーンX-15の3号機の弾道飛行試験中に機体がコントロールを失い回転。高度19800mで空中分解する事故が起こる。パイロットのマイケル・J・アダムスが死亡。 |
| 11月22日 | 国連安保理決議242が理事国15カ国の全会一致で採択。イスラエルの占領を無効とし、パレスチナ難民の解決を促す一方で、イスラエルを含む全ての国の主権と独立を認め、占領地からの撤退については、期限を定めないこと、制裁を行わないことなど、イスラエル側に有利な内容となっている。そのため、アラブ側は承認しなかった(シリアは第4次中東戦争後に承認、エジプトとヨルダンはそれぞれイスラエルと講和し、パレスチナは1995年のオスロ合意がある)。 |
| 11月25日 | 硫黄鳥島が噴火し、硫黄採掘所も閉鎖。島は完全に無人化する。 |
| 12月15日 | オハイオ州カナウガとウエストバージニア州プリーザント間を結ぶ吊橋シルバー・ブリッジが崩落。橋上で渋滞していた多数の車両が落下し、46人が死亡、18人が負傷。建設された1928年当時最新と言われていた、ケーブルではなく鉄板チェーンで吊る構造(実は構造欠陥)が老朽化により破損したため。同日、この付近でモスマンが目撃されたという噂があり、前年より続いていたモスマン騒動が、この事故を予言していたなどと噂された。 |
| 1968年(昭和43年) | |
| 1月21日 | グリーンランドのチューレ米軍基地近海の海氷上に、機内火災を起こした核爆弾搭載のB-52爆撃機が墜落。搭載水爆の起爆用火薬が爆発して核物質が飛散。広範囲が汚染され、また、水爆1つが行方不明となる。 |
| 1月21日 | 北朝鮮の特殊部隊による青瓦台襲撃未遂事件が起こる。朴正熙大統領の暗殺を狙い、第124部隊の31人が韓国に侵入。青瓦台近くまで接近したが、先に遭遇した市民からの通報で警戒していた韓国軍と2週間に渡って銃撃戦となり、1名を逮捕、1名が自爆し、29名が射殺された(射殺されたのは27名で残りは逃走したとも)。韓国軍兵士や、事件に巻き込まれた韓国市民など68名が死亡。朴正熙は激怒して北朝鮮への侵攻を主張するがアメリカの支持が得られず断念し、金日成暗殺計画を立てるが、後の実尾島事件の原因となった。 |
| 1月23日 | プエブロ号事件が起こる。アメリカの情報収集艦プエブロが北朝鮮東部元山の沖合で通信傍受作戦中、北朝鮮海軍の艦艇4隻から攻撃を受けて拿捕される。米軍兵1名が死亡、少なくとも7名が重軽傷を負う。米軍はベトナムに派遣していた空母エンタープライズなどを朝鮮半島沖合へ派遣。嘉手納基地などにB-52戦略爆撃機24機を展開し核攻撃も辞さない方針を取るも、ベトナムとの二正面作戦を避けるため、「領海12海里内に侵入した」と主張する北朝鮮側に譲歩して謝罪し、乗員はアメリカに返還された。プエブロはその後も北朝鮮にある。 |
| 1月29日 | 戦後、戦争協力者のレッテルを貼られて日本を追われフランスに移住した洋画家の藤田嗣治が、スイスのチューリッヒで死去。 |
| 2月16日 | 民航空運公司10便墜落事故。香港から台北へ向かっていた台湾の航空会社民航空運公司の第10便ボーイング727旅客機が、台北松山空港に着陸しようとして失敗。墜落炎上して乗員乗客63人中21人が死亡。同社の役員が、操縦は出来たがライセンスがないまま、職権乱用で操縦しており、その操縦ミスが墜落原因。 |
| 2月12日 | フォンニィ・フォンニャット虐殺事件。ベトナム戦争に参戦した韓国海兵隊の部隊が、フォンニィ・フォンニャット村で女性らを集めて虐殺。69人から79人が犠牲になる。 |
| 2月20日 | 金嬉老事件が起こる。金嬉老が金銭トラブルのあった暴力団員2名を射殺。 |
| 2月21日 | 金嬉老が寸又峡温泉の旅館で人質をとって籠城事件を起こす。警察官による差別発言の謝罪を人質解放の条件にしたため、民族差別問題に発展。88時間後に逮捕される。 |
| 2月25日 | ハミ虐殺事件。ベトナム戦争に参戦した韓国海兵隊の部隊が、クアンナム省のハミ村で、女性子供ら135人を虐殺。ベトナム戦争での韓国軍による住民虐殺の犠牲者数は9000人から30万人まで諸説ある。また多数の女性が強姦されているが、いずれも韓国政府は一切認めていない。 |
| 2月26日 | 三里塚・芝山連合空港反対同盟や砂川基地拡張反対同盟の学生や地元住民らが成田市営グランドで三里塚空港実力粉砕・砂川基地拡張阻止現地総決起集会を開催。機動隊と衝突して多数の負傷者を出す。 |
| 3月12日 | モーリシャスが英連邦王国としてイギリスから独立。 |
| 3月16日 | ソンミ虐殺事件。ベトナム戦争の中、クアンガイ省ソンティン県ソンミ村ミライ地区などで、アメリカ陸軍第23歩兵師団の部隊が住民を次々と虐殺し家屋などにも放火。事件を起こした中隊のアーネスト・ルー・メディナ中隊長の指揮のもと、ウィリアム・ロウズ・カリー小隊長らが実行したと言われる。犠牲者は347人から504人の間。現場を通りがかった偵察ヘリなどの通報で発覚するが、アメリカ軍上層部はこれを隠蔽。ジャーナリストらの告発で明るみになり、大規模な反戦運動へと発展することになる。軍法会議にかけられた士官らの中でカリー中尉以外は無罪となったため、一人だけに責任を追わせることも含め批判が殺到した。 |
| 3月17日 | ダグウェイ羊事件。アメリカ・ユタ州スカルバレーの牧場で飼われていた羊6000頭以上が死んでいるのが明らかになる。すぐ近くのダグウェイ性能試験場では連日化学兵器の各種放出実験(神経ガスの空中散布や化学砲弾発射テストなど)を行っており、それが原因と疑われた。羊の状態が神経ガスの効果と異なっているものもあり、疑問視する意見もあったが、最終的に化学兵器実験の影響と結論づけされた。国際的批判を浴びたアメリカ政府は、化学兵器部隊の縮小や、化学兵器の屋外実験の禁止に追い込まれた。 |
| 3月27日 | 登録医制度に反対する東大医学部自治会が、卒業式阻止を狙って安田講堂を一時占拠。 |
| 4月 6日 | 映画『2001年宇宙の旅』がアメリカで公開。 |
| 4月12日 | 日本初の超高層ビル、霞が関ビルディングが竣工。高さ147m、36階建て。 |
| 5月10日 | フランスでバリケードを築いた学生と警官の間で衝突事件が起こる。 |
| 5月19日 | 「第21回カンヌ国際映画祭粉砕事件」が起きる。開催中の会場に、学生運動に呼応していた映画監督のジャン・リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーらが現れ、政府の強権的な対応や、官僚主義的な映画界を批判して映画上映の中止を訴える。これに会場にいたテレンス・ヤングやロマン・ポランスキー、ルイ・マルら監督や女優モニカ・ヴィッティらが呼応したため、映画祭は中止に追い込まれた。これが21日の大ゼネストに大きく影響したといわれる。 |
| 5月21日 | フランスで学生運動から1000万人が参加する大ゼネストに発展。通称「フランス五月革命」。 |
| 5月30日 | フランスのド・ゴール大統領が、国民議会の解散と総選挙を決定。5月革命は終息し、選挙は右派が勝利。一方で社会的・文化的影響は大きく、各国の学生運動にもつながった。 |
| 6月 2日 | 建設中の九州大学電算センターに米軍のファントム偵察機が墜落。 |
| 6月15日 | 東大医学部自治会がふたたび東大安田講堂を占拠。機動隊が投入されたことから、医学部以外の学生らも反発し、東大紛争が激化していく。 |
| 6月16日 | 横須賀線電車爆破事件。電車が大船駅付近を走行中に、網棚に置かれた爆弾が爆発。乗客1名が死亡、14名が重軽傷を負う。遺留品から逮捕された犯人は、男女関係の破局が動機で爆弾を仕掛けたと自供。後死刑判決を受け執行された。 |
| 7月 2日 | 東大生らが東大安田講堂付近にバリケードを築く。 |
| 7月 5日 | 「東大闘争全学共闘会議」が結成される。 |
| 8月 1日 | 九州大学電算センターファントム墜落事件で、機体の残骸を残すべきだと主張する学生が一帯を占拠。 |
| 8月 3日 | ポルトガルの独裁者アントニオ・サラザールが、静養先でハンモックから転落して意識不明の重体に陥る。サラザール率いるエスタド・ノヴォ政権は幹部マルセロ・カエターノを後継首相に。2ヶ月後、サラザールは意識を回復したが、政権幹部は政権交代したことや各植民地で起きている反乱などについては一切伝えず、ご都合的なニセの新聞まで作ってサラザールが死ぬまで嘘を貫いたという。 |
| 8月 8日 | 和田寿郎を中心とした札幌医科大学胸部外科チームが、日本初の心臓移植手術を行う。 |
| 8月12日 | ザ・タイガースによって日本初のスタジアムライブが後楽園スタヂアムで行われる。 |
| 8月18日 | 岐阜県白川町で土砂崩れに巻き込まれた観光バス2台が飛騨川に転落し104人が死亡する。史上最悪のバス事故。決壊のリスクの中、ダムの放水を止めて捜索が行われた。 |
| 8月20日 | チェコ事件。プラハの春と呼ばれたチェコスロバキアの改革を脅威とみなしたソ連が、ソ連軍主体のワルシャワ条約機構軍でチェコスロバキアに侵攻。世界中の非難を浴びる中、日本社会党はソ連を支持。 |
| 8月24日 | フランスが初めての水爆実験カノープス作戦を行う。核出力2.6Mt。 |
| 9月 6日 | 南アフリカのスワジランドがイギリス保護領から独立。現在のエスワティニ王国。 |
| 9月22日 | エジプトでナイル川のアスワン・ハイ・ダムの建設にともない、水没の危険があったアブ・シンベル神殿の移転完了。世界文化遺産登録制度のきっかけとなる。周辺の遺跡も移転。 |
| 9月26日 | 厚生省がようやく、水俣病の原因が新日本窒素水俣工場の排水に含まれているメチル水銀化合物による中毒であると断定し、新潟阿賀野川の同種の病気も昭和電工鹿瀬工場の排水が原因であることを認める。 |
| 10月 1日 | 国鉄が大規模な白紙ダイヤ改正(ヨンサントオ)を実施。全国で複線化や電化区間を増やし、特急列車を増発して、列車輸送の高速化を図ったもの。これにともない準急列車がなくなり、蒸気機関車の定期運行も大幅に減ることとなった。またたくさんあった列車の愛称を統一するようになった。 |
| 10月12日 | 東シナ海の国際資源調査が始まる。石油資源が埋蔵されているという判断が出されることになり、中国と台湾の両政権が尖閣諸島の領有権と中間線の大陸棚線の主張をはじめるきっかけとなった。 |
| 10月12日 | 赤道ギニア(ギネア・エクアトリアル)がスペインから独立。名前に赤道とあるが、赤道上にあるわけではない。 |
| 10月16日 | カネミ油症事件。カネミが販売した食用油にPCBが混入し、ダイオキシン汚染で多くの被害者を出す。 |
| 10月21日 | 新宿騒乱事件。左翼テログループの中核派、共産主義者同盟マルクス・レーニン主義派、第四インターナショナル日本支部など各派のメンバーや学生ら2000人ほどが新宿駅に集結。機動隊と衝突しながら、駅施設に放火。野次馬なども集まり大騒乱に発展する。 |
| 10月22日 | 政府、新宿騒乱事件を受けて騒擾罪の適用を決定する。逮捕者743人。 |
| 10月25日 | 最高裁は、1951年に山口県で起きた殺人事件「八海事件」で逮捕された5人のうち、4人について、事件とは無関係の冤罪であったことを認める。差し戻しも含めて7回も判決が出され、その都度、判決内容が二転三転、映画も作られるなど、裁判史上に残る冤罪事件となった。 |
| 10月29日 | 日本初の心臓移植手術を受けた高校生が死亡し、移植の必要性や、ドナーへの処置が疑惑を招く事件に発展。 |
| 11月 4日 | 林健太郎監禁事件。全学共闘会議が東京大学の学内人事に反発して、新文学部長の林健太郎教授と「団体交渉(団交)」を実施。教授をほぼ監禁状態にして11月12日まで続いたことから、三島由紀夫や阿川弘之らが仲介に乗り出すなどの事態に発展した。この間、林教授は全学連の要求には一切応じなかったが、学生と積極的に議論を重ねたことから、全共闘側が交渉に応じたことを評価するに至り、最終的に解放された。 |
| 11月22日 | 羽田発サンフランシスコ経由ニューヨーク行き日本航空002便が、濃霧の中、サンフランシスコ国際空港に着陸しようとして位置を間違え、空港手前5kmのサンフランシスコ湾に着水。水深がほとんどない浅瀬だったため大惨事には至らず、死傷者なし。 |
| 12月 1日 | 日本相互銀行が、「金融機関の合併及び転換に関する法律」に基づいて普通銀行に転換し、名前も太陽銀行となる。日本相銀は日本無尽を原型とし、預金量では相銀の中でも桁違いに大きかったため、普通銀行転換で「都市銀行」となった。 |
| 12月22日 | 「人民日報」が毛沢東の「若者を農村で再教育させる」指示を掲載。以後10年間に渡り「上山下郷運動」で都市部の若者1600万人が辺境へと下放させられた。表向きは都市と地方の格差撤廃という建前であったが、実際には、文化大革命の担い手として当初は毛沢東から絶賛された紅衛兵が、過度の暴力運動から内紛状態となり、統制が効かなくなったことが主な原因。この世代は高等教育も受けられず、辺境の過酷な環境で人生の多くを過ごすことになり、あとから出てきた世代に追い抜かれるなど、見捨てられた世代として文学などにもしばしば登場する。 |
| 12月25日 | この日発売の「SFマガジン」に掲載された覆面座談会がSF作家をこき下ろしているとして、俎上に載った作家らが反発。SF界が分裂する事件に発展。「覆面座談会事件」。座談会は同誌編集長で作家の福島正実、副編集長で作家の森優(南山宏)、作家でSF評論家の石川喬司、翻訳家の稲葉明雄・伊藤典夫の5人による。 |
| アーシュラ・K・ル・グインの『アースシーシリーズ』第一作『A Wizard of Earthsea』が発売される。同シリーズは他作家のファンタジー作品にも大きな影響を与えている。日本では『ゲド戦記』と呼ばれて、スタジオジブリがアニメ化しているが原作とはかなり異なるオリジナル作品。 | |
| 1969年(昭和44年) | |
| 1月 5日 | 九州大学電算センター建設現場に残っていたファントムの残骸を、何者かが重機で引き下ろし運び去る。九大総長が辞職。 |
| 1月18日 | 学生と機動隊による東大安田講堂攻防戦が始まる。 |
| 1月19日 | 東大安田講堂陥落。 |
| 2月 8日 | メキシコ・チワワ州のアエンデ付近一帯に隕石の破片が降り注ぐ。 |
| 3月 2日 | コンコルドの原型機が初飛行。 |
| 4月28日 | フランス大統領ド・ゴールが政界を引退。 |
| 5月10日 | 国鉄客車等級廃止。モノクラス制が導入される。 |
| 5月13日 | マレーシアで5月13日事件が起こる。言語など政策的優遇策を受けているが貧困層の多いマレー系住民と、経済的には豊かだが優遇政策から外されている中国系住民が対立する中、総選挙で中国系の支持する野党が議席を伸ばしたことから、マレー系住民と中国系住民との間でデモ隊同士が衝突。暴動に発展し、196人が死亡、439人が重軽傷を負う。 |
| 5月13日 | 三島由紀夫が、東大全共闘と討論会を実施。東京大学教養学部900番教室を会場とし、千人もの学生が集まった。討論の内容は出版されベストセラーになっている。 |
| 5月20日 | 九州大学のキャンパスを学生らが占拠、封鎖する。 |
| 6月12日 | 原子力船むつ進水。 |
| 7月 4日 | ソ連のバイコヌール宇宙基地で、N-1ロケット2号機の発射試験中に爆発事故が発生。多数の死傷者が出たと見られるが詳細は不明。原因はロケット1段目が30本のロケットを束ねた巨大クラスターでこの制御が困難だったため。結局、同ロケットの開発は進まずソ連の有人月探査計画(ソユーズL3計画)は1974年に中止に追い込まれた。 |
| 7月 5日 | ローリング・ストーンズが、ロンドンのハイドパークでフリーコンサートを開催。創設メンバーで脱退したブライアン・ジョーンズが亡くなったことへの追悼と新メンバーのミック・テイラーのお披露目を兼ねたもので、大きな混乱もなく終了。この際、警備を担当したバイカーギャング「ヘルズ・エンジェルス」が評価されるが、これが半年後のオルタモントの悲劇へとつながる。 |
| 7月 8日 | 沖縄の米軍が保管していた毒ガス兵器からガス漏れ事故が起こって負傷者が出ていたことが判明。毒ガス兵器撤去運動が起こる。 |
| 7月18日 | チャパキディック事件。アメリカ・マサチューセッツ州のチャパキディック島で、エドワード・ケネディ上院議員が飲酒運転で海に転落する事故を起こしながら、同乗者を救助せずに死亡させ、警察にも通報しなかったスキャンダル。 |
| 7月18日 | 沖縄県美里村(現沖縄市)の知花弾薬庫「レッドハットエリア」で、神経ガスVXの漏洩事故が発生。軍人・軍属24人が負傷する。 |
| 7月20日 | 人類、初めて月に降り立つ。アポロ11号の月着陸船が月面「静かの海」に着地し、アームストロング飛行士とオルドリン飛行士が月面に降り立ち船外活動。コリンズ飛行士は上空の司令船で撮影などを行う。 |
| 8月 4日 | TBS系列で時代劇『水戸黄門』が放送開始。 |
| 8月 7日 | 大学の運営に関する臨時措置法(大学管理法)成立。 |
| 8月15日 | ウッドストック・フェスティバルが、ニューヨーク州サリバン郡ベセルのヤスガー農場で開催。18日午前まで行われ、チケット購入者数の倍以上となる40万人が集まった。ヒッピー文化の頂点、野外音楽フェスの原点ともいわれる。ウッドストックというのは隣のアルスター郡にある芸術村の名前で、もともとはここで開催の予定だったが出来なかったため、名前だけが継承された。 |
| 9月 1日 | リビアで無血クーデター。国王イドリース1世が追放され、カダフィ政権が樹立。 |
| 10月 1日 | 科学技術庁宇宙開発推進本部から、宇宙開発事業団(NASDA)が設立される。 |
| 10月11日 | 著作した京劇作品『海瑞罷官』を文化大革命の口実にされてしまい、投獄されていた、歴史学者で元北京副市長の呉晗が獄死。自殺説もある。 |
| 10月12日 | 三島由紀夫主催の民間防衛組織「楯の会」の幹部だった持丸博が会を退会。「論争ジャーナル」系の会の古参メンバーが三島との間で齟齬になり、同誌の運営資金の問題で離脱する事態となったことで、両者の板挟みになったことが理由とされる。三島由紀夫にとっては右腕とも言える存在だったため、非常に落胆したという(その後も協力関係は続いた)。後任に森田必勝が就く。「楯の会」が大きく変わる結果となったとも言われる。 |
| 10月14日 | 九州大学に機動隊4400人が投入され、キャンパス占拠している学生を排除。 |
| 10月29日 | ARPANETによるコンピュータネットワークがはじまる。インターネットの原型。当初はUCLA、UCサンタバーバラ、スタンフォード研究所、ユタ大学の4箇所のコンピュータのみ。 |
| 11月12日 | 中華人民共和国第2代国家主席だった劉少奇が病死。文化大革命での激しい迫害で、家族から引き離され、病気の治療も受けられず、悲惨な最期だったという。死亡が公表され名誉回復したのはずっと後だが、現在でも劉少奇のことは表立って取り上げられることは少ない。 |
| 11月13日 | 革労協のメンバーが銀座駅、泉岳寺駅で火炎瓶放火事件を起こし、乗客ら16人が重軽傷。 |
| 11月15日 | アメリカの原子力潜水艦ガトーと、ソビエトの原子力潜水艦K-19が、バレンツ海を潜水航行中に、水深200フィート(約60m)で衝突事故を起こす。どちらも沈没は免れる。 |
| 11月17日 | アメリカとソビエトの間で、核兵器の配備を制限する、第一次戦略兵器制限交渉(SALT I)がヘルシンキで始まる。 |
| 11月20日 | アルカトラズ島占拠事件。インディアン(ネイティブアメリカン)のモホーク族やサンテ・スー族の76人が、サンフランシスコ湾の無人島になっていたアルカトラズ島を占拠。ここに「インディアン文化センター」を設立すると宣言。ラジオなどで情報を発信した。占拠は1971年6月11日まで続く。 |
| 11月 | 神戸商工貿易センタービル(26階、107m)がオープン。西日本初の超高層ビル。 |
| 12月 6日 | 北陸トンネルで寝台特急「日本海」が火災事故を起こすが、運転手がとっさの判断で、火災時にはトンネル内で停止すること、という規定を破り、トンネル外まで走行して消火。一人の犠牲者も出さずに済むが、規定違反として国鉄内部で処分を受けた。のち「きたぐに」火災事故の大惨事で、トンネル内停車が問題視され、運転手の処分は撤回される。 |
| 12月 6日 | ローリング・ストーンズが、アメリカツアーに続けて、カリフォルニア州のオルタモント・スピードウェイで、フリーコンサートを開催。しかし会場が二転三転した混乱と、運営の不手際もあり、20万人以上が殺到した会場は大混乱に陥る。警備を引き受けたバイカーギャング「ヘルズ・エンジェルス」のメンバーが観客の黒人青年を殺害する事件も発生。乱闘騒ぎに加え、事故も発生して計4人が死亡、多数が負傷する事態となった。「オルタモントの悲劇」と呼ばれ、規模の大きさの割に比較的穏便に終了した「ウッドストック」と比較されることも多い。 |
| 12月22日 | 名古屋大学教養学部の封鎖解除を巡って、学生同士が大規模な内ゲバ事件を起こす。60人が負傷。 |
| この年、ホイタッカーによって生物の分類法として五界説が発表される。栄養摂取法と体の構造から、動物界・植物界・菌界・モネラ界・プロチスタ界の5種類に分類。分子生物学によって見直されるまで主要な説となった。 | |
| 1970年(昭和45年) | |
| 1月10日 | 国土全体が飢餓状態になっているビアフラ戦争を終わらせるため、指導者チュクエメカ・オジュク大統領ら主要閣僚がコートジボワールへ亡命。ビアフラ政府はナイジェリアに降伏し、150万人が死亡したビアフラ戦争は終結。ナイジェリア大統領のアクブ・ゴウォンは、国民融和を図り報復に出なかったが、イボ族に対する差別待遇は暫く続いた。 |
| 2月 2日 | コーンフィールドボンバー事故。アメリカモンタナ州で、演習中のF-106A戦闘機が、きりもみ状態となり、パイロットは脱出。その後機体は偶然水平になり、無人のままの雪の積もった農地に不時着。損傷が少なかったため、修理して再使用された。 |
| 2月11日 | 日本初の人工衛星「おおすみ」が打ち上げられる。世界で4番目の人工衛星打ち上げ国となる。 |
| 3月14日 | 日本万国博覧会(大阪万博)が開幕。 |
| 3月18日 | アメリカ主導のクーデターによって、カンボジア王政が倒れ、ロン・ノル政権が樹立する。 |
| 3月20日 | フランコフォニー国際機関が設立される。 |
| 3月31日 | 赤軍派による「よど号」ハイジャック事件が起こる。北朝鮮へゆくよう要求され、板付飛行場を経由し、韓国の金浦空港に向かうも、平壌に偽装したのがバレ、膠着状態になる。 |
| 3月 | 東京浜松町に世界貿易センタービルが完成(40階、152m)。高さ日本一の座に付く。再開発により解体予定。 |
| 4月 3日 | 「よど号」ハイジャック事件で、金浦空港に到着した山村新治郎運輸政務次官が、自ら人質となることで乗客を解放させ、乗員と共に北朝鮮へ向かう。赤軍派は北朝鮮当局に投降。乗員と山村次官は身柄を確保される。 |
| 4月 5日 | 乗員と山村次官を乗せた「よど号」が帰国。 |
| 4月 8日 | 大阪天六ガス爆発事故。大阪市北区の天六交叉点で、地下鉄工事中に都市ガスが漏れ出し引火。大爆発を起こして、死者79人、重軽傷420人を出す。 |
| 4月13日 | 月へ向かって飛行中のアポロ13号で酸素タンクが爆発する事故が起こる。 |
| 4月17日 | アポロ13号の司令船が太平洋に無事着水。乗員3人は強襲揚陸艦イオージマに無事収容される。 |
| 5月 8日 | ファントム墜落事故と学生占拠で建設が中断していた九州大学電算センターが開所。 |
| 5月11日 | 松浦輝夫、植村直己の二人が、エベレスト日本人初登頂。 |
| 5月12日 | 瀬戸内シージャック事件発生。広島の宇品港で瀬戸内航路のぷりんす号が武装犯に乗っ取られる。 |
| 5月13日 | 瀬戸内シージャック事件の犯人が警察の狙撃隊によって射殺される。 |
| 5月23日 | 沖縄県で知花弾薬庫毒ガス漏洩事件に対する「毒ガス即時撤去要求、アメリカのカンボジア侵略反対県民総決起大会」が開かれる。主催は沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)。 |
| 7月 9日 | 東京教育大学構内で中核派活動家が機関紙を販売していたところ、革マル派活動家に襲われる。のちの東京教育大生殺人事件のきっかけとなった事件。 |
| 7月18日 | 東京都杉並区の東京立正中学校・高等学校で、グランドにいた生徒らが次々と倒れ、日本初の光化学スモッグと確認。 |
| 7月28日 | 鹿児島県十島村の臥蛇島から全世帯が鹿児島や周辺の島へ移住し、無人島となる。 |
| 8月 3日 | 東京教育大学生リンチ殺人事件(海老原事件)。中核派メンバーが池袋駅東口付近で革マル派メンバーの東京教育大生を見つけて襲い、法政大学の六角校舎地下室に拉致してリンチにかけ、発覚報復を恐れてそのまま殺害。遺体を東京厚生年金病院の入り口に投棄し、証拠品を焼却。事件を知った革マル派は報復を宣言。凄惨な内ゲバ殺人が拡大するきっかけとなった。犯人の学生らはその後相次いで逮捕される。 |
| 8月11日 | 南極から帰り、北海道大学植物園で飼育されていた樺太犬のタロが死去。剥製にされ同園で保存。 |
| 8月14日 | 革マル派が海老原事件の報復で法政大学を襲い、中核派学生10人に重軽傷を負わせる事件を起こす。 |
| 8月26日 | イギリス・ワイト島で、ワイト島音楽祭が開催。1968年から続いた同島音楽祭の3回目で、60万人以上の観客が集まったと言われる、世界最大の野外音楽祭となる。しかしこれが問題にもなり、同島音楽祭は2002年に復活するまで行われなかった。 |
| 9月13日 | 日本万国博覧会(大阪万博)が閉幕。最終的な総入場者数は6421万8770人。 |
| 9月18日 | 沖縄県糸満町で米兵が運転する車が住民の女性を轢き死亡させる事故が起こる。付近の住民が証拠を残すために現場を包囲。コザ暴動の遠因となった事件。 |
| 10月10日 | フィジーがイギリス連邦に属してイギリスから独立。 |
| 10月28日 | ピューリッツァー賞を受賞した戦場カメラマン沢田教一がカンボジアのプノンペンで銃撃を受け死亡。 |
| 10月 | ラリー・ニーヴン作『リングワールド』発売。ヒューゴー賞・ネビュラ賞受賞。 |
| 11月25日 | 作家の三島由紀夫と、彼が創設した「楯の会」のメンバーが、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地の陸上自衛隊東部方面総監部総監室を訪問し、総監を監禁して占拠。招集をかけられ集まった自衛官らに憲法改正の決起を促す演説をしたあと割腹自殺。森田必勝も割腹自殺を図る。取り押さえようとした自衛官数人が負傷。ノーベル賞候補者として知られた著名作家の行動に、国内外に衝撃を与え、賛否両論で大論争となった。 |
| 12月18日 | 上赤塚交番襲撃事件。日本共産党(革命左派)神奈川県委員会のメンバー3人が、拳銃入手目的で板橋区赤塚の上赤塚交番を襲撃。駐在警察官に重症を負わせるが、奥にいた別の警察官も襲おうとして、警察官が警告の上で発砲。襲撃犯のうち横浜国立大学生の柴野春彦が死亡、同大生渡辺正則と神奈川県立川崎高生の佐藤隆信が重症を負い逮捕。3人が銃入手を計画した理由は、革命左派の指導者で獄中にいた川島豪から自分を獄外へ奪還するよう幹部の永田洋子や坂口弘らに指示したため。日本共産党(革命左派)神奈川県委員会は、日本共産党が中国問題で内部対立を起こした際に除名された毛沢東主義派のメンバーなどで結成された同名別組織で、後に凄惨な事件を起こす連合赤軍の母体。 |
| 12月20日 | コザ暴動。返還前の沖縄コザ市で、米兵の交通事故に憤慨した住民が車両に放火し、基地内に侵入するなど大規模な暴動に発展。ただし規模の割に死者はなく、略奪も行われなかった。 |
| 1971年(昭和46年) | |
| 1月 5日 | 米軍が、コザ暴動を受けて、米軍法会議に琉球政府代表がオブザーバーとして参加することを認める。 |
| 1月13日 | 米軍が沖縄の知花弾薬庫から、ジョンストン島へ化学兵器を移送する「レッドハット作戦」の1回めが行われる。米軍天願桟橋までの輸送路周辺の住民は避難。 |
| 2月17日 | 真岡銃砲店襲撃事件。前年に銃入手のために交番を襲って失敗した日本共産党(革命左派)神奈川県委員会のメンバーが、栃木県真岡市の銃砲店を襲い、店主を負傷させ、猟銃10丁、実弾2300発などを強奪。これを受けて組織幹部の永田洋子、坂口弘らも手配されることになり、隠れるための山岳ベース建設へシフトし、山岳ベース事件へとつながっていく。 |
| 2月22日 | 成田空港建設をめぐり、建設予定地で第一次行政代執行。反対派3千人が集結し、警官隊と衝突。 |
| 3月26日 | 多摩ニュータウンの諏訪・永山地区で第一次入居開始。 |
| 3月26日 | パキスタン領だったベンガル地方の東パキスタンが、政府の偏った政策に反発して独立戦争を起こし、インドがこれを支持して介入。第三次印パ戦争となる。 |
| 3月27日 | 日本精神神経学会で、石川清東大講師が、臺弘東大教授が1950年代にロボトミー手術に関連した人体実験を行っていたと告発。医学界を巻き込む大論争に発展。石川や臺も関係していた赤レンガ闘争(東大病院精神病棟占拠事件)の問題とも関係がある。 |
| 4月19日 | ソビエトが世界初の宇宙ステーション「サリュート1号」を打ち上げ。 |
| 5月14日 | 連続女性強姦および殺人事件の犯人、大久保清が逮捕される。殺害された女性は8名、その他複数の強姦事件、強姦未遂事件、脅迫事件なども起こしている。画家を装い自家用車で移動しながら多数の女性に声をかけ、誘いに乗った女性と関係を持った上で殺害する手口で、強姦されて殺害された被害者もいる。被害者の一人の家族が独自に捜索して捕まえた。しばらく大久保清の名前は強姦魔の代名詞ともなり、映画やドラマ化もされている。 |
| 5月28日 | 1949年に起きた弘前大学教授夫人殺害事件の真犯人が名乗り出る。犯人とされ服役した那須隆は、その後の再審請求の裁判の結果、冤罪であったことが確定する。ずさんな鑑定も問題になった。真犯人は別事件で服役したことのある人物で、那須とも幼馴染だった男。三島事件に影響を受けて名乗り出た。本事件に関しては公訴時効が成立したが、のちにわいせつ事件を起こして本事件を含め世間に報道された。 |
| 6月 5日 | 西新宿に最初の超高層ビルである京王プラザホテルが開業(47階、169m)。高さ日本一の高層ビルとなる。 |
| 6月 6日 | ヒューズ・エア・ウエスト706便空中衝突事故。ロサンゼルス空港発、ソルトレイクシティ経由、シアトル行きのヒューズ・エア・ウエスト706便に、海兵隊のF-4BファントムII戦闘機が空中衝突。戦闘機はネバダ州リノ基地からカリフォルニア州エルトロ基地へ移動する途中だった。旅客機は機体を裂かれてフィッシュキャニオンに墜落。乗員乗客49人全員が死亡。戦闘機はパイロットが死亡し、レーダー要員が脱出して生存。軍民の管制連携ができてなかったことと、あまりの高速で避けようがなかったと見られる。 |
| 6月17日 | 明治公園爆弾事件。15日から明治公園で中核派が沖縄返還協定調印反対集会を開いていたが、暴徒化したため、機動隊が鎮圧しようとしたところ、その場にいた赤軍派メンバーが鉄パイプ爆弾を投げつけ爆発。機動隊員37人が重軽傷を負う。 |
| 6月30日 | ソビエトの宇宙船ソユーズ11号が、地球へ帰還するため、宇宙ステーションサリュートから離脱する際、換気弁が開き、船内の空気が流出。宇宙船は無事着陸したが、ゲオルギー・ドブロボルスキー、ビクトル・パツァーエフ、ウラディスラフ・ボルコフの乗員3人は死亡。宇宙船が小さいため、3人では気密服を着て乗ることが困難だったためと言われる。 |
| 7月 7日 | 国民のマナー向上の啓蒙活動を目的とした、関西公共広告機構が関西の財界人によって設立される。のちのACジャパン。 |
| 7月15日 | 米軍が沖縄の知花弾薬庫から、ジョンストン島へ化学兵器を移送する「レッドハット作戦」の2回めが始まる。9月9日まで神経ガスなどを天願桟橋まで輸送。 |
| 7月23日 | 松江相互銀行米子支店に、猟銃などで武装した極左赤軍派の4人が押し入り、600万円を奪って逃走。猟銃は真岡銃砲店強盗事件で盗まれたもの。 |
| 7月24日 | 松江相互銀行米子支店を襲撃した赤軍派のうち2人を目撃した通報を受け、警察が2人の乗った車両を止め、2人に職務質問。所持バッグを開けるよう要求したが拒否されたため、警察官は承諾を得ずに開き盗まれた紙幣を確認。緊急逮捕する。承諾を得ずに所持品検査をするのが違法かどうかが争われ、緊急時には捜索に至らない程度で検査は許容される場合があるという最高裁判例になった。 |
| 7月30日 | 雫石衝突事故。全日本空輸の58便ボーイング727-200型機と、航空自衛隊の訓練機ノースアメリカンF-86セイバーが岩手県上空で空中衝突。旅客機は尾翼を破損して操縦不能となり墜落、音速を突破して空中分解した。乗員乗客162人全員が亡くなる。訓練機の訓練生は脱出して生還。また地上で堕ちてきた旅客機の車輪で住宅が破損し住民1人が負傷。自衛隊の訓練飛行の設定の不備、軍民の航空管制の不備の結果、自衛隊の教官機と訓練機が旅客機の飛行ルートに入ったことが主な要因。裁判では訓練生に事故は予見できなかったとして無罪、教官は有罪となったが、そもそもの訓練計画がずさんであり、個人に全責任を負わせるのは酷であるとして執行猶予付きで確定した。 |
| 7月30日 | アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコのサンフランシスコ国際空港で、経由のために降りたロサンゼルス発羽田行のパンアメリカン航空845便が、離陸の際に誤って短い滑走路から離陸しようとして進入灯に衝突。機体は大きく損傷したものの、かろうじて空港に着陸。29人が重軽傷を負う。ボーイング747初の事故。 |
| 8月 3日 | 印旛沼事件。日本共産党(革命左派)神奈川県委員会の男女2人のメンバーが組織から脱走。その話を聞いた当時赤軍派の森恒夫の粛清すべきという意見を聞いた革命左派幹部永田洋子と坂口弘の指示で、脱走した女性メンバーが拉致され暴行殺害される。10日に脱走男性メンバーも襲われて殺害。ともに印旛沼近くに埋められた。同志殺害のタブーが失われ、のちの山岳ベース事件へとつながっていく。 |
| 8月15日 | アメリカのニクソン大統領が、ドルと金の交換停止を発表。いわゆるニクソン・ショック。固定相場制が崩壊し、現在の変動相場制に移行する。 |
| 8月21日 | 朝霞自衛官殺害事件。陸上自衛隊朝霞駐屯地で、夜間動哨任務中の士長が刺殺される。残されていた遺留品から当時正体不明の「赤衛軍」の犯行とされた。捜査は困難するが、週刊プレイボーイと産経新聞のスクープ記事から、日本大学と駒澤大学生5人と元自衛官2人を割り出し逮捕。また捜査の過程で、週刊プレイボーイの記者と朝日ジャーナルの記者が犯人に協力していたことも判明。 |
| 8月23日 | 韓国で実尾島事件が起こる。北朝鮮の金日成暗殺作戦のために訓練していた特殊部隊の兵士24人が、待遇の悪化に反発して武装反乱。軍や警察との銃撃戦を経て、20人が自爆し、4人が逮捕され死刑となる。 |
| 8月31日 | 昭和の大落語家、8代目桂文楽が、国立小劇場で三遊亭圓朝作の「大仏餅」を演じている最中に台詞を忘れ、「勉強しなおして参ります」と頭を下げて謝罪した後、高座を降りるが、二度と高座に上がることはなかった。 |
| 9月 8日 | 林彪事件(毛沢東暗殺計画)。中華人民共和国副主席の林彪と息子の林立果が毛沢東の乗る列車の爆破を計画するが、事前に漏れて失敗に終わる。 |
| 9月13日 | 林彪が人民解放軍所有の旅客機でソ連に亡命を図るが、ソ連・モンゴル国境で旅客機が墜落し死亡する。墜落の原因は不明。 |
| 9月16日 | 成田空港建設をめぐり、建設予定地で第二次行政代執行。反対派と警官隊が衝突。反対派に囲まれた警官多数が襲撃されて重軽傷を負い、そのうち3人が左翼活動家によって執拗な暴行(鉄パイプでの殴打、竹槍で刺される、濃硫酸をかけられる、ガソリンで放火されるなど)を受け殺害される(東峰十字路事件)。これを知った機動隊は怒りで反対派の拠点の一つ駒井野鉄塔に殺到し引き倒したため、学生らに多数の負傷者を出す。地元農家らの「反対同盟」指導者が活動家を擁護したため、同情世論が冷め、地元民同士の対立にまで発展することになるが、新左翼の各セクトでは逆に競うかのように暴力先鋭化が進むことになる。 |
| 9月25日 | 皇居坂下門に中核派のメンバーが突入し、宮内庁庁舎玄関付近で取り押さえられる。のちに同様の事件が起きたため、第一次坂下門乱入事件と呼ばれる。 |
| 10月11日 | ソビエトの宇宙ステーションサリュート1号が大気圏に突入し崩壊。ソユーズ11号の事故を受けて有人実験が中止となり、機器も故障したため、軌道遷移を諦め放棄が決定した。 |
| 10月25日 | 国連総会アルバニア決議により、中華人民共和国が国連に加盟、常任理事国になり、常任理事国だった中華民国(台湾政権)は抗議のために国連を脱退する。 |
| 11月10日 | 沖縄で沖縄返還協定に反対する労働組合などがゼネストを実施。そのさなかのデモ行進で、中にいた左翼テログループのメンバーが、警備中の琉球警察の機動隊員数名を襲い、火炎瓶などで放火。事態に気づいたデモの参加者が救助して病院へ搬送したが巡査長1名が死亡。 |
| 11月11日 | 川崎ローム斜面崩壊実験事故。関東ローム層の豪雨災害を研究するために人工的に水をかけて行った実験で、予想以上の土砂崩れが起こり、研究者・マスコミ関係者ら15人が巻き込まれて死亡する。 |
| 11月14日 | 渋谷暴動事件。沖縄返還協定に反対する中核派など極左テログループが、渋谷宮下公園での「11・14 全国総結集・東京大暴動闘争」を企図し、機関紙などで喧伝。警視庁も厳戒態勢で臨んだが、中核派活動家らは火炎瓶などで派出所を襲撃。新潟県警から派遣されていた機動隊員1名が捕まりガソリンをかけられ焼殺される。また周辺の民家や商店なども放火され市民に負傷者多数を出したほか、池袋では山手線の車両内でも放火事件が起き乗客が負傷。横浜や仙台でも放火事件が起きている。 |
| 12月 2日 | アラブ首長国連邦が結成される。アブダビ、ドバイ、シャールジャ、アジュマーン、ウンム・アル=カイワイン、フジャイラ、ラアス・アル=ハイマのアラブ系部族国家のうちラアス・アル=ハイマを除く6つが連邦国家を結成(ラアス・アル=ハイマは翌年参加)。 |
| 12月 4日 | 関西大学構内内ゲバ殺人事件。関西大学千里山キャンパスで、ステッカー貼りをしていた革マル派に対し、中核派が襲撃するも、劣勢となって逃走。しかし逃げ遅れた2人が革マル派に捕まり、撲殺される。 |
| 12月16日 | 第三次印パ戦争でインド側が勝利したため、バングラデシュがパキスタンから独立。 |
| 12月18日 | スミソニアン協定締結。金本位固定為替相場制(ブレトンウッズ体制)から金本位制が廃止され、各国通貨価値を上げ、変動幅のあるドル連動性へ。1973年に変動為替相場制へ移行する。 |
| 12月18日 | 土田邸爆弾事件。警視庁警務部長土田国保宅で、お歳暮品に偽装した爆弾が爆発。土田夫人が死亡し、四男が重症を負う。時効が成立したが共産主義者同盟戦旗派の犯行とされる。上赤塚交番襲撃事件で犯人が射殺されたのを、佐々淳行警備第一課長が正当防衛と発言したのを土田部長がかばったことが、マスコミで土田談話として報道されたために狙われたという。 |
| 12月31日 | 連合赤軍山岳ベース事件の最初の犠牲者が出る。以降、事実上のリーダーだった赤軍派幹部森恒夫と革命左派の幹部永田洋子らの命令で、次々とメンバーが総括の名のもとにリンチを受けて殺害される。リンチに加わったメンバーがその後殺された例もある。12名が死亡。殺害の理由に革命の理屈(総括)を唱えているが、実際は森恒夫や永田洋子の嫉妬など個人的感情によるもの。その後多くが逮捕されるが、逃走したメンバーがあさま山荘事件を起こす。あまりの凄惨な内容に左翼運動は大衆の支持を失い、左翼運動への共鳴をアピールしていた自称知識人の多くが面目を失った。 |
| 1972年(昭和47年) | |
| 1月 9日 | 豪華客船の初代クイーン・エリザベス号が、香港で洋上大学へ改装中に火災で転覆。 |
| 1月24日 | グアム島で旧日本軍の横井庄一伍長が発見される。 |
| 1月26日 | ユーゴスラビア航空367便爆破事件。スウェーデンのストックホルム発、デンマークのコペンハーゲン、ユーゴスラビアのザグレブ経由、同ベオグラード行、同航空DC-9型機が、チェコスロバキアのスルブスカー・カメニツェ上空で爆破され墜落。乗員乗客28人中27人が死亡。客室乗務員のヴェスナ・ヴロヴィッチが重症を負った。クロアチア民族主義を名乗る人物が犯行声明を出している。高度10160m付近で爆破され空中分解しながら、ヴェスナが助かったのは、機内の残骸内部に取り残された上に落下地点が森林地帯で斜面だったため、衝撃を吸収したこと、墜落直後に発見され応急処置を受けられたことによると言われる。パラシュート無しでもっとも高い高度から落下して生還した記録としてギネスブックに認定された。彼女は1年4ヶ月後に復帰し、再び航空会社で勤務した。 |
| 1月30日 | 北アイルランド「血の日曜日事件」(ボグサイドの虐殺)。北アイルランドのロンドンデリーでイギリス政府への支配に抗議のデモを行った市民に、イギリス陸軍落下傘部隊の兵士らが銃撃。27名が撃たれ14名が死亡。 |
| 2月 3日 | 札幌オリンピック開催。アジアで初めて開催された冬季オリンピック。 |
| 2月 6日 | 札幌オリンピック・スキージャンプ70m級で、笠谷幸生が金メダル、金野昭次が銀メダル、青地清二が銅メダルを獲得し、日本が表彰台を独占。日の丸飛行隊と呼ばれる。 |
| 2月17日 | フォルクスワーゲン・タイプ1(ビートル)の累計生産台数が1500万7034台となり、フォード・モデルTの生産記録を抜き世界一になる。 |
| 2月19日 | あさま山荘事件。逃走中の連合赤軍のメンバー5人が、軽井沢の「さつき荘」に潜入していたところ、警官隊に発見され、「あさま山荘」に逃げ込み、居合わせた管理人の妻を人質に籠城。 |
| 2月24日 | ソビエトの原子力潜水艦K-19が、カナダニューファンドランド島の沖合海中で機関室の火災をおこし緊急浮上。28人が死亡。 |
| 2月28日 | あさま山荘事件で機動隊が山荘に突入。 |
| 3月 1日 | 奈良県明日香村で住民が見つけた高松塚古墳の調査が始まる。 |
| 3月 2日 | 木星探査機パイオニア10号が打ち上げられる。 |
| 3月15日 | 国鉄山陽新幹線岡山開業に合わせてダイヤ改正が行われる(ヨンナナサン)。中国・四国地方の特急列車の新設定と、東北などでの特急列車増発が主な変更。 |
| 3月19日 | 富士山で悪天候による大量遭難事故が起きる。死者18人、行方不明者6人。低気圧の発達によって急速に天候が悪化。死亡者は風雨による低体温症と雪崩に巻き込まれたことが主な要因。経験豊富な地元の登山家のグループが下山を強行して遭難する一方、経験の浅い登山者らがテントで天候回復を待って助かるなど明暗が分かれた。 |
| 3月21日 | 高松塚古墳の石室から彩色壁画が発見される。 |
| 3月24日 | 映画『ゴッドファーザー』公開。 |
| 4月 4日 | 火災を起こして機能停止していたソビエトの原子力潜水艦K-19が、曳航されてセヴェロモルスクに到着。閉じ込められたままの乗員も救助される。 |
| 4月16日 | ノーベル文学賞作家の川端康成が逗子の仕事場で死去。自殺説と事故死説とがある。 |
| 4月28日 | 大阪城公園で革マル派と反帝学評(社青同解放派)の集団同士で騒乱となり革マルメンバー1人が撲殺される。 |
| 5月13日 | 大阪千日デパートビル火災。118名が死亡。 |
| 5月15日 | 沖縄日本返還(本土復帰)。琉球政府が終了し、沖縄県が設置される。 |
| 6月11日 | 通産大臣田中角栄の著書『日本列島改造論』が刊行される。 |
| 6月17日 | ウォーターゲート事件が発生する。アメリカ大統領ニクソンの大統領再選委員会のメンバー5人が、敵である民主党の本部があったウォーターゲートビルに侵入。以前に仕掛けていた盗聴器の不具合を確かめているところを警察官に逮捕される。侵入事件自体はお粗末なもので、国民の関心も呼ばなかったが、後にこれをもみ消そうとする政治的陰謀が発覚し大問題に発展する。 |
| 6月25日 | 沖縄返還にともない、沖縄県議会選挙が行われる。 |
| 8月10日 | 北米時間14時30分ころ、アメリカ・ユタ州から、ワイオミング州、カナダのアルバータ州にかけての上空を火球が目撃され、映像にも撮られる。2m~10mほどの隕石が浅い角度で大気に侵入し、そのまま弾かれるように宇宙空間へ飛び去っていったと考えられる。 |
| 8月14日 | 東ドイツのインターフルーク航空イリューシン62型チャーター便が、ベルリンからブルガリアのブルガス空港へ向かう途中、機内後部貨物室で火災が発生。引き返しているさなかに、高温で破損した機体後部が脱落、急降下した結果、ポツダム県のケーニヒスヴスターハウゼン付近で空中分解し墜落。乗員乗客156人全員が死亡。 |
| 9月25日 | フランス政府は、アフリカのガボン共和国オートオゴウェ州オクロのウラン鉱山の中に、20億年前に存在した天然原子炉の跡を発見したと発表。ウラン235が一定以上存在し、同時代の酸素濃度の上昇にともない、地下水と反応して核分裂臨界に達していたものとみられる。 |
| 9月29日 | 日中共同声明調印。日本と中華人民共和国の国交が成立。 |
| 10月 2日 | 午後10時19分に桜島南岳山頂で爆発噴火。 |
| 10月 9日 | 岩手県内陸を走っていた松尾鉱業鉄道が廃止。硫黄鉱山だった松尾鉱山が閉山になったため。 |
| 10月28日 | 中華人民共和国から日本に贈られたパンダ「カンカン」と「ランラン」が上野動物園に到着。パンダフィーバーが起こる。 |
| 11月 6日 | 北陸トンネルで急行「きたぐに」が火災事故を起こす。規定に従い、トンネル内で停車したため、死者30人、重軽傷者714人を出す。トンネル内停車規定が問題視され、69年に同様の「寝台特急日本海火災事故」でトンネル内に停車せずに走行し、一人も犠牲者を出さなかったものの、規定違反として処分された運転士への処分が撤回される。 |
| 11月 8日 | 川口大三郎事件。早稲田大学で、第一文学部の学生だった川口大三郎が角材などで滅多打ちにされて殺害されたもので、遺体は東大医学部附属病院前に放置された。犯行は革マル派で、川口を対立する中核派のメンバーと誤認して襲ったとみられるが、川口は中核派の集会に顔を出した程度の関係しかなかった。革マル派は遺体発見の翌日に犯行声明を出して正当を主張したが、これが学生の猛反発を買い、早稲田大学では大規模な革マル糾弾集会が連日行われた。同大学は教授会が革マル派とつながっていた関係で自治会や学生祭なども革マル派が運営しており、2005年まで革マル派の牙城だった。 |
| 11月12日 | 東京の路面電車「都電」が、三ノ輪-早稲田間を残して廃止。残存線は荒川線と呼ばれることになる。 |
| 11月30日 | ボウリング雑誌「週刊ガッツボール」で、ストライクを取った時のポーズを「ガッツポーズ」と命名。これが最初のガッツポーズという表現と言われる。 |
| 12月 7日 | アポロ計画の最後であるアポロ17号が打ち上げられる。地球の写真「ザ・ブルー・マーブル」を撮影。 |
| 12月22日 | 「アンデスの聖餐」事件。ウルグアイの軍用機がアンデス山中に墜落し、乗っていた学生ラグビー選手ら生存者が発見されるが、食糧が無くなり止む得ず遺体を食べて生存したことが問題になる。 |
| 1973年(昭和48年) | |
| 1月 1日 | 連合赤軍の中央委員会委員長で、山岳ベース事件を引き起こした森恒夫が東京拘置所で自殺。 |
| 1月 8日 | ウォーターゲート事件で、ウォーターゲートビルに侵入して逮捕された5人と、彼らに指示を出していたホワイトハウスの情報漏えい工作担当者2人の7人(ウォーターゲートセブン)が、大陪審で審理される。5人が侵入に関して有罪を認めるも、背後については口を閉ざす。 |
| 1月22日 | マラム・アミヌ・カノ国際空港着陸失敗事故。サウジアラビア・ジッダ発、ナイジェリアのラゴス行アリア・ヨルダン航空のチャーター便(ナイジェリア航空運行)ボーイング707型機が、悪天候によるダイバートでカノ国際空港に着陸しようとして失敗。機体は滑走路を外れて火災を起こし、乗員乗客202人のうち176人が死亡。 |
| 1月27日 | ベトナム戦争和平のためのパリ協定が北ベトナム、アメリカ、ベトコン主導の南ベトナム共和国臨時革命政府、南ベトナムの間で調印され、ベトナム戦争が終結する。 |
| 2月 | 各国が市場原理に基づいた通貨の変動為替相場制へと転換。スミソニアン体制が終わる。 |
| 3月 3日 | 青山学院大学の春木猛教授が教え子を強姦したとして逮捕される。のち懲役3年の実刑判決。ただ春木猛は合意を主張し、また被害者が教授と対立する別の教授グループと近い関係にあったことから、冤罪説もある。 |
| 3月13日 | 上尾事件。国鉄高崎線上尾駅で国鉄の労働組合が起こしていた遵法闘争で通勤電車が遅延、駅に来ていた数千人の乗客が反発する中運行停止が伝えられたことが火に油を注ぐ結果となり、暴動が発生。周辺の駅にも波及し、高崎線は不通となる。 |
| 3月19日 | ウォーターゲート事件の被告ウォーターゲートセブンのひとりであるマッコードが、スケープゴートにされることを恐れ、裁判での偽証と、事件が大統領側近らの指示であったことを暴露。 |
| 3月27日 | 京都の方広寺大仏殿と大仏が失火による火災で焼失。大仏殿と大仏は天保14年に民間有志で再建されたもので大仏殿は3代目、大仏は4代目になる。 |
| 4月 4日 | ニューヨークに完成したワールド・トレード・センタービルの落成式典。高さ526.3m、110階建てのツインビル。エンパイア・ステート・ビルディングを抜いて世界一となる。内部の柱ではなく、外壁の構造でビルを支えるという独特の設計になっていた。 |
| 4月23日 | 高松塚古墳壁画が特別史跡に指定される。 |
| 4月24日 | 首都圏国電暴動。国鉄の労働組合である国労と動労が起こしたストライキで電車多数の運行が停止・遅延したことに通勤客が反発。赤羽駅で駅施設と駅員を襲う暴動が起きたことを皮切りに上野駅、新宿駅などへ波及。地方も含め38駅に及び、駅施設と車両多数に甚大な被害をもたらした。政府は事態を重視し道路運送法に基づいて民間業者に代行輸送を初めて命令。また大手民鉄(私鉄)各社も終夜運行で対応した。しかし労働組合は一時的にストライキを中断したのみで、逆に国鉄当局と乗客を批判。2年後の国鉄大ストライキ(スト権スト)実施へと進み、結果、国鉄の信頼は失墜し、解体へとつながることになる。 |
| 4月29日 | ツクダがボードゲーム「オセロ」を発売。 |
| 4月30日 | ニクソン米大統領の補佐官であるハルデマンとアーリックマンが、ウォーターゲート事件をめぐって辞職に追い込まれる。また大統領の法律顧問だったジョン・ディーンが解雇される。 |
| 4月30日 | 小説家大佛次郎が死去。代表作は『鞍馬天狗』シリーズ。時代小説のほか、ノンフィクションや童話もある。 |
| 5月 3日 | シカゴにシアーズタワー(現ウィリス・タワー、527.3m)が完成し、ワールド・トレード・センターを抜いて、超高層ビルで高さ世界一の座につく。 |
| 5月30日 | 小笠原諸島の西之島の東南600mで海底火山が噴火。 |
| 6月25日 | ニクソン米大統領の法律顧問だったジョン・ディーンが、上院特別調査委員会でウォーターゲート事件のもみ消し工作を大統領が知っていたと証言。ウォーターゲート事件は、単なる建造物侵入事件から、大統領のもみ消し工作の疑惑へと発展。 |
| 6月26日 | ソビエトのプレセツク宇宙基地でコスモス3Mロケットが爆発する事故を起こす。9人が死亡。 |
| 6月 | アーサー・C・クラークの小説『宇宙のランデヴー』がイギリスで発売。太陽系内に侵入した異星人の巨大構造物を巡る物語を描いている。地球に衝突する天体を監視する目的で設立された国際プロジェクト「スペースガード」は、本作中に出てくる同様の組織をモデルにしている。 |
| 7月13日 | ニクソン米大統領のアレクサンダー・バターフィールド副補佐官が、ホワイトハウスの録音システムの存在を明らかにする。ウォーターゲート事件のもみ消し工作疑惑の真相を知るべく、このテープの公開を求める動きが高まる。 |
| 7月24日 | 活動火山対策特別措置法が制定される。 |
| 8月23日 | ストックホルムで銀行立てこもり事件。人質が犯人に共感して協力するようになる「ストックホルム症候群」のモデルとなった事件。 |
| 9月 6日 | 伊豆半島石廊崎の奥石廊崎展望台下の海岸で男女4人の遺体が発見される。死亡していたのは立教大学の大場助教授とその妻子で、一家心中であったが、大場助教授は7月20日に不倫関係にあった女子大学生を殺害し遺体を埋めており、そのことを知り合いの大学職員、別の大学の複数の助教授らにもほのめかしていた。話を聞いた人たちが自首を勧める一方で、前代未聞の不祥事から警察には通報しておらず、当初は開き直っていた大場助教授も、最後は追い詰められて家族を巻き込んで自殺するという最悪の結果となった。 |
| 9月 6日 | 北朝鮮の平壌に地下鉄千里馬線が開業。 |
| 9月11日 | 西之島の海底噴火で、新島が発見される。 |
| 9月14日 | 翌日にかけて、革マル派の150人ほどが、神奈川大学に籠もっていた社青同解放派50人を襲撃。両派で騒乱となり2人が死亡、多数が重軽傷を負う。 |
| 9月24日 | ギニア・カーボベルデ独立アフリカ党が、ギニアビサウのポルトガルからの独立を宣言。翌年ポルトガルもこれを承認。もともとは沖合の島嶼国家カーボベルデとの統合のために独立運動が行われたが、ギニアビサウ市民の反発もあり、現在まで両国とも独立国家として続いている。 |
| 9月29日 | 西之島の海底噴火で、2つ目の新島が発見される。 |
| 10月 6日 | 第4次中東戦争勃発。エジプト軍がユダヤ教の安息日「ヨム・キプール」に合わせて、イスラエルが占領していたシナイ半島へ侵攻。シリア軍もゴラン高原でイスラエル軍を攻撃。情報分析を甘く見たイスラエルは奇襲を受ける形となる。 |
| 10月 7日 | ラタキア沖海戦。第四次中東戦争開戦を受けて、イスラエル海軍のミサイル艇が、シリア海軍のミサイル艇など5隻を撃沈。両者が艦対艦ミサイルを使い、電子的対抗手段も行われた史上初の海戦。 |
| 10月 8日 | イスラエル軍は各地で反撃を試みるも失敗に終わる。イスラエルは戦術核兵器の使用も検討。 |
| 10月 9日 | 西之島の海底噴火で、3つ目の新島が発見される。まもなく3つの新島はつながる。 |
| 10月11日 | イスラエル軍は反撃に転じ、シリアの首都ダマスカス近郊へ侵攻。 |
| 10月14日 | イスラエル軍はシナイ半島でエジプト軍に対し猛攻をかけ、エジプト軍に大きな被害が出る。 |
| 10月15日 | イスラエル軍はシナイ半島からスエズ運河を超えてエジプト側へ逆侵攻する。 |
| 10月17日 | アラブ石油輸出国機構(OAPEC)の緊急閣僚会議が開かれ、原油生産削減、供給制限が決定。第1次オイルショックが始まる。 |
| 10月20日 | ニクソン米大統領の録音テープ提出問題で、ニクソン大統領は裁判所の提出要求を無効にするよう検察などに圧力をかけるが、エリオット・リチャードソン司法長官とウィリアム・D・ラッケルズハウス司法副長官が反発して辞任。これに市民からの反発が沸き起こる。 |
| 10月22日 | 第4次中東戦争停戦を目的とした国連安保理決議第338号が決議。イスラエルは従わず、イスラエルを支持するアメリカと、アラブを支持するソ連の対立にまで発展。 |
| 10月25日 | イスラエル軍が侵攻作戦を中止。国連安保理決議第340号により、第二次国際連合緊急軍が編成され、中東での停戦監視の任につく。 |
| 10月31日 | ニクソン米大統領は、ホワイトハウスの録音テープの一部を提出するも不完全であったために、逆に一連の疑惑の不審を買うことになる。 |
| 11月 1日 | 民間教育テレビの日本科学技術振興財団テレビ事業本部がテレビ東京に、NETテレビがテレビ朝日となって総合放送局へ移行。 |
| 11月13日 | 1936年に恋人の杉本良吉とソ連に駆け落ち亡命していた女優の岡田嘉子が帰国。杉本良吉は亡命直後にソ連当局にスパイ容疑で処刑されている。 |
| 11月29日 | 熊本大洋デパート火災。103名が死亡。 |
| 12月 3日 | パイオニア10号がはじめて木星に接近。 |
| 12月21日 | 海上保安庁は、西之島の海底噴火で生まれた島を「西之島新島」と命名。 |
| 12月23日 | ペルシャ湾岸の6カ国が石油の値段を引き上げる。各国で石油を始め、物価の値上がりが拡大する。 |
| 1974年(昭和49年) | |
| 1月26日 | トルコ航空301便、イズミル・ジュマオバス空港発、イスタンブール国際空港行きフォッカーF28型機が、離陸直後に失速して地面に接触し炎上。乗員5人中4人と乗客68人中62人が死亡。低温で機体に着氷したことで制御不能に陥った上、機長と副操縦士が飲酒で酔っていたことも原因とされる。 |
| 1月30日 | パンアメリカン航空806便、ニュージーランドのオークランド空港発、アメリカ領サモアのパゴパゴ空港、およびハワイ・ホノルル空港経由ロサンゼルス空港行きボーイング707便が、パゴパゴ国際空港手前で気象によるウインドシアが起こり急降下、即応できなかったことで墜落。乗員10人全員と乗客91人中87人が死亡。 |
| 2月 4日 | パトリシア・ハースト誘拐事件。アメリカの左翼過激派グループ「シンバイオニーズ解放軍」に拉致される。父親の新聞会社社長に、カリフォルニア州の貧民6万人にそれぞれ70ドル分の食料を与えることを要求。 |
| 2月 8日 | 琉球大学内ゲバ誤認殺人事件。琉球大学首里キャンパスで、物理概説の講義の最中、中核派のメンバー数人が、「自治会長(革マル派)はいるか」とわめきながら乱入。驚いて逃げ出そうとした学生の一人を、自治会長と誤認して捕まえ、鉄パイプなどで滅多打ちにして殺害する。殺された学生は革マル派とはなんの関係もない、いわゆる「誤爆」であったが、中核派は間違いを認めず、被害者を革マル派のメンバーにしたてて制裁を加えたかのように機関紙で発表した。8年8ヶ月後に被疑者が逮捕される。 |
| 2月21日 | 朝日新聞に掲載されていた『サザエさん』が休載となる。 |
| 3月 1日 | ウォーターゲート事件に関して、7人の大統領側近が捜査妨害容疑で起訴される。さらにニクソン大統領自身も、起訴はされないが、共謀者として指名される。国民の間で大統領弾劾への支持が広がりはじめる。 |
| 3月 2日 | 西之島新島で新たな海底噴火により新島が出現。 |
| 3月 3日 | トルコ航空981便、イスタンブール・アタテュルク空港発、パリ・オルリー空港経由、ロンドン・ヒースロー空港行きDC-10型機が、オルリー空港を離陸してまもなく、高度3600m付近で、完全に閉まってなかった貨物ドアが吹き飛び、発生した貨物室の減圧で、客席の床が陥没、日本人乗客6人が吸い出されたあと、陥没による操縦ケーブルの破損で操縦不能に陥り、パリ近郊のオワーズ県エルムノンヴィルの森に高速で激突。乗員乗客346人全員が死亡。ほとんどの遺体は破損がひどく身元が判明できなかった。300人以上が亡くなった初の航空機事故。 |
| 3月 6日 | 西新宿に新宿住友ビルディングが竣工。日本初の200m級超高層ビルで日本一となる(52階、210.3m)。 |
| 3月19日 | 兵庫県西宮市にあった知的障害者施設、甲山学園で、浄化槽から幼児2名の遺体が発見される。施設職員の冤罪事件に発展した、いわゆる甲山事件。 |
| 4月11日 | ガッツポーズの日。ボクシングWBC世界ライト級タイトルマッチで挑戦者のガッツ石松がとったポーズをスポーツ報知がガッツポーズと報道したから。しかしガッツポーズという表現自体は1972年11月30日のボウリング雑誌「週刊ガッツボール」の記事に見られる。 |
| 4月15日 | サンフランシスコで銀行を襲ったシンバイオニーズ解放軍の一味に、拉致されたはずのパトリシア・ハーストが加わっていることが判明。 |
| 4月17日 | 高松塚古墳壁画の極彩色壁画が国宝に指定される。 |
| 4月24日 | 西ドイツのブラント首相の秘書であるギヨームとその妻のクリステルが、東ドイツ国家保安省のスパイであるとして逮捕される。西ドイツ政界を揺るがす大問題に発展。 |
| 4月25日 | ポルトガルでカーネーション革命が勃発。ポルトガル軍の青年将校らの「国軍運動」がクーデター起こし首都リスボンを制圧。カエターノ首相は降伏し、ほとんど戦闘もなく革命は成功。エスタド・ノヴォ独裁政権は崩壊。同政権の政策の失敗による貧困に苦しんだ市民は、カーネーションの花を持って革命成功を祝ったため、カーネーション革命と呼ばれる。 |
| 5月 7日 | 首相秘書スパイ事件を受けてブラント西ドイツ首相が辞任に追い込まれる。 |
| 5月15日 | セブンイレブン日本一号店が、東京江東区豊洲に開店。 |
| 5月15日 | ポルトガルに臨時革命政府樹立。アントニオ・デ・スピノラ大将が首相となる。しかし9月30日には失脚。翌年にかけて政権の主導権争いが続く。 |
| 5月17日 | FBIがシンバイオニーズ解放軍のアジトを急襲。銃撃戦で6人を射殺。 |
| 5月18日 | インドが初の地下核実験(作戦名Smiling Buddha)を実施。出力は8~20Kt。 |
| 6月 7日 | 誘拐拉致されていたはずのパトリシア・ハーストが、テレビ局にテープを送りつけ、父や婚約者を批判し、シンバイオニーズ解放軍のために命をかけると宣言。 |
| 6月10日 | 西之島新島と旧島が一つの島になっていることを確認。噴火の方はほぼ終息。その後、島は少しずつ波で侵食される。 |
| 6月14日 | ソ連のゲオルギー・ジューコフ元帥が死去。18日に国葬。大祖国戦争時代の総司令官でナチス侵攻を撃退してからベルリン陥落に至るまでソ連軍を指揮した人物。戦後、スターリン時代とフルシチョフ時代にニ度失脚したが、後に復権し、ロシアでは最も人気のある歴史上の人物のひとりとなっている。 |
| 6月17日 | 桜島第1古里川の砂防工事現場で土石流が発生し作業員2名が死亡し1名が行方不明。 |
| 6月23日 | ソ連が月有人探査計画ソユーズL3計画を中止。先に無人ロケットで物資を運び、あとに有人宇宙船を送り込む計画で、月宇宙船や着陸船、自動操縦システム、乗組員の装備などは完成していたが、肝心の有人ロケットが完成できなかった。 |
| 7月 1日 | アルゼンチンの大統領フアン・ペロンの3番目の妻で副大統領だったイサベル・ペロンが、夫の死去に伴い大統領となる。世界最初の女性大統領。 |
| 7月13日 | 映画「エクソシスト」日本公開。 |
| 7月15日 | キプロスのギリシャ併合派がクーデターを起こす。マカリオス大統領を追放。 |
| 7月20日 | キプロスのギリシャ併合派クーデターに反発したトルコが、キプロスに侵攻。 |
| 7月22日 | キプロスのギリシャ併合派クーデターが失敗に終わる。しかしトルコ軍は駐留を継続。 |
| 7月24日 | ウォーターゲート事件をめぐり、裁判所によるホワイトハウスの録音テープ提出要請を、大統領が行政特権で拒否できるかどうかが争われた裁判で、裁判官の全員一致で、係争中の裁判の特定の証拠となりうることから、大統領特権の申立は無効との判決が下る。 |
| 7月27日 | ウォーターゲート事件をめぐり、下院司法委員会で大統領に対し「司法妨害」の弾劾を勧告する評決が行われ、賛成27票、反対11票で可決。 |
| 7月28日 | 新潟焼山が噴火。登山に来ていた千葉大学の学生3名が噴石に当たり死亡。 |
| 7月29日 | ウォーターゲート事件をめぐり、下院司法委員会で大統領に対し「権力の乱用」の弾劾を勧告する評決が行われ、賛成28票、反対10票で可決。 |
| 7月30日 | ウォーターゲート事件をめぐり、下院司法委員会で大統領に対し「議会への侮辱」の弾劾を勧告する評決が行われ、賛成21票、反対17票で可決。 |
| 8月 5日 | ウォーターゲート事件をめぐり、ニクソン大統領は、この日までにすべてのホワイトハウスの録音テープを裁判所に提出する。 |
| 8月 8日 | ニクソン米大統領が、夜、テレビ演説を行い、翌日正午に辞任することを表明。 |
| 8月 9日 | ニクソン米大統領が辞任し、ジェラルド・R・フォード副大統領が昇格して大統領となる。 |
| 8月 9日 | 桜島野尻川の砂防工事現場において土石流が発生し作業員ら5名が死亡。 |
| 8月13日 | トルコ、キプロスに追加派兵。キプロスとの北部3分の1を占領。 |
| 8月14日 | 日本国内の極左テログループ東アジア反日武装戦線が、昭和天皇を狙った荒川鉄橋爆弾テロ「虹作戦」を計画するも、準備中に第三者に遭遇したため、断念。なお、爆弾を仕掛けようとした鉄橋は、実際には天皇のお召し列車が通過する橋ではなく、警察による安全調査も考慮していないため、作戦自体はどちらにしても失敗したと考えられている。 |
| 8月15日 | 文世光事件。在日朝鮮人文世光が、ソウルの国立劇場で行われていた光復節の会場で、韓国大統領朴正煕暗殺を図り失敗。大統領夫人陸英修が射殺され、銃撃戦の巻き添えで合唱団の女子高生、張峰華が死亡する。暗殺計画は北朝鮮の指導によって朝鮮総連の指示で行われたと言われる。 |
| 8月28日 | 原子力船むつの原子炉が臨界に達する。 |
| 8月30日 | 日本国内の極左テログループ東アジア反日武装戦線が、三菱重工ビルを爆破。社員や通行人ら8人が死亡、376人が重軽傷を負う大惨事となる。虹作戦で鉄橋爆破用に用意していた爆薬を流用したため、威力が大きく、ビルが立て込んでいた場所だったこともあって、その分被害も大きかった。また直前に爆破予告の電話をしたが間に合わなかった。犯行声明では一般市民の死傷者を犯罪者扱いするなど自らを正当化したが(裁判では殺意を否定)、一方で一般市民への被害の大きさから、以降の爆破テロ事件は深夜などに行うようになったと言われる。左翼運動が市民の支持を失った要因の一つ。 |
| 9月 1日 | 試験航海中の原子力船むつで中性子線を観測したため、航海を中止する。母港のあるむつ市では、帰港に反対する騒ぎとなり、むつは約1ヶ月、「漂流」することになる。 |
| 9月 8日 | トランス・ワールド航空841便が爆破され墜落。乗員乗客88人全員が死亡。同機はイスラエルのテルアビブ発、アテネ、ローマ経由、ニューヨーク行きで、アテネを離陸したあと、イオニア海上空で爆破されケファリニア島近くに墜落した。同便は事件の2週間前にも爆弾を仕掛けられる未遂事件があったが、検査等の警戒は採られなかった。パレスチナ解放機構が犯行声明を出す。 |
| 9月12日 | エチオピア帝国で陸軍主体の軍事クーデターが起こり、皇帝ハイレ・セラシエ1世が逮捕され失脚。エチオピア革命。ソロモン朝エチオピア帝国は崩壊し、共産主義を掲げるエチオピア暫定軍事行政評議会「デルグ」が政権を発足。エチオピア内戦も勃発。 |
| 9月12日 | 首都圏女性連続殺人事件の犯人として、そのうちの松戸OL殺害事件に関して、建設作業員の小野悦男が逮捕される。同事件は1968年から1974年にかけて首都圏各地で起きた若い女性を殺害した事件で、犯行の手口や遺留物に共通点があったため、同一犯と考えられた。マスコミが煽るように加熱報道。支援団体が起こされ、松戸事件については無罪判決が出て冤罪事件となった。本人や支援者の間で勝利を勝ち取ったことが広く宣伝された。しかし小野悦男は他の婦女暴行などは有罪となっている他、釈放後に別の殺人事件を起こして無期懲役となっていること、犯人しか知り得ない証言をしていることなどから、連続殺人事件のいずれかに関わっていたとみなす意見もある。 |
| 9月 | 西新宿に新宿三井ビルディングが完成(55階、225m)。高さ日本一となる。当時異色だった黒色のガラスビル。 |
| 10月 6日 | 『宇宙戦艦ヤマト』の放映開始。その後の物語性の強いSFアニメの走りとなった作品。 |
| 10月12日 | 中日ドラゴンズの優勝が決まり巨人の10連覇が消える。同日、長嶋茂雄が現役引退を表明。 |
| 10月14日 | 長嶋茂雄の引退セレモニーが行われ、「わが巨人軍は永久に不滅です」という言葉を残す。 |
| 11月 9日 | 第十雄洋丸事件。東京湾を京浜港へ向けて航行中の大型タンカー「第十雄洋丸」に木更津港を出港した鋼材貨物船「パシフィック・アレス」が突っ込む。第十雄洋丸は炎上。多数の消防艇による消火作業中に第十雄洋丸は爆発し、2隻は炎上しながら横須賀方向へ漂流。夜、パシフィック・アレスを引き離すことに成功し、第十雄洋丸も富津沖で座礁させることに成功する。 |
| 11月11日 | 第十雄洋丸事件。第十雄洋丸とパシフィック・アレスの犠牲者を収容後、第十雄洋丸は東京湾外へと曳航することになるが、黒潮に乗ったところで再び爆発炎上。曳航できなくなり漂流を開始。パシフィック・アレスの方へ短時間で延焼したため、1名を除く28名が死亡したのに対し、先に炎上した第十雄洋丸のほうが避難が間に合い、乗員38名の内、死者は5名。 |
| 11月22日 | 第十雄洋丸事件。第十雄洋丸の鎮火までに4000時間以上かかるとみられることから、国際問題になることを懸念した日本政府は自衛艦によって撃沈することを決定。 |
| 11月22日 | エチオピア革命を起こした勢力のうちメンギスツ・ハイレ・マリアムら急進派が再クーデターを起こし、穏健派の臨時軍事評議会議長アマン・アンドム、皇孫であるエスキンデル・デスタ海軍司令官らを次々と殺害。 |
| 11月24日 | エチオピアのアワッシュ川下流ハダールで、アアウストラロピテクス・アファレンシス(アファール猿人)の化石「ルーシー」が発見される。318万年前ころの猿人で二足歩行をしていた特徴が見られる。 |
| 11月26日 | 第十雄洋丸事件。第十雄洋丸に対し、護衛艦4隻が砲撃。これは積荷を船外へ放出させ炎上させるのが目的。非常に頑丈にできていることから72発を打ち込む。 |
| 11月28日 | 第十雄洋丸事件。第十雄洋丸に対し、P-2J対潜哨戒機ロケット弾と対潜爆弾を投下。ついで潜水艦なるしおが、魚雷4発を発射し2発が命中(1発は故障により発射管で止まったため投棄され、1発は外れて行方不明に)。さらに護衛艦から砲撃し、18時47分、犬吠埼灯台東南東約520kmの海域で沈没。 |
| 12月 4日 | パイオニア11号が木星までおよそ34000kmまで接近する。 |
| 12月12日 | 映画『ゴッドファーザー PART II』公開。マフィア組織を受け継いだマイケルの物語と、父親ヴィトーの子供時代から組織のドンになるまでの若い頃を描く2パート構成。 |
| 12月20日 | 文世光事件の犯人、文世光がソウルで処刑される。 |
| 12月22日 | コモロ諸島でフランスからの独立をめざす住民投票が行われ、マヨット島を除く3島が独立を選択。マヨット島のみフランス領継続を選択する。 |
| 12月27日 | イギリス領マン島の漁師で、マン島語(マンクス・ゲール語)を話せた最後の話者エドワード・ネッド・マドレルが死去。 |
| 1975年(昭和50年) | |
| 1月23日 | 大阪万博の際に会場に作られた岡本太郎の太陽の塔を存続してほしいという署名運動などを受けて、会場の解体を進めていた施設処理委員会が永久保存を決定。元々丹下健三デザインの「お祭り広場の大屋根」を見た岡本太郎がこれをぶち抜く巨大なオブジェを独断で構想。丹下がこれを容認した経緯がある。岡本太郎は当初、万博終了後まで残すつもりはなかったが、市民の運動を受けて存続に同意した。 |
| 3月10日 | 新幹線の博多開業に合わせて国鉄のダイヤ改正が行われる(ゴーマルサン)。関西と九州を結ぶ昼行特急・昼行急行が全廃され、新幹線運行に合わせた九州内での「エル特急」が大増発された。 |
| 3月14日 | 中核派書記長内ゲバ殺人事件。埼玉県川口市戸塚のアパートに午前3時半ころ、15・6人の男が現れ、2階の住人を襲撃。鉄パイプやハンマーなどで滅多打ちにされて死亡。殺されたのは中核派書記長(最高指導者)の本多延嘉41歳で、襲撃したのは革マル派。本多は黒田寛一とともに「革命的共産主義者同盟全国委員会」を結成した人物。黒田とはその後決裂し、黒田が作ったのが革マル派、残った本多の組織が「中核派」と呼ばれるようになった。 |
| 3月24日 | 国鉄の集団就職列車の運行が終了する。 |
| 4月 5日 | 『秘密戦隊ゴレンジャー』が放送開始。戦隊モノの最初の作品。 |
| 4月 5日 | ソビエトの有人宇宙船ソユーズ7K-T(18a号)が、ロケット打ち上げ上昇中に高度145kmで第2段ロケットが完全に分離できず、そのまま第3段ロケットが点火。軌道をそれはじめたため、再突入カプセルを切り離し、そのまま地球へ落下。着陸に成功し、乗員2名のうち1名が負傷したものの無事帰還。 |
| 4月 9日 | 北ベトナム軍が南ベトナムの最後の要衝スアンロクへの攻撃を開始。 |
| 4月17日 | カンボジア共産党(クメール・ルージュ)が首都プノンペンに侵攻。ロン・ノル政権が崩壊する。市民の強制移住と大虐殺が始まる。 |
| 4月21日 | スアンロク陥落。南ベトナム軍は壊滅し継戦能力を喪失。なお北ベトナム軍も甚大な被害を出したとみられる。南ベトナムのグエン・バン・チュー大統領が辞任し、台湾へと脱出。チャン・バン・フォンが大統領職を継ぎ、北側と休戦交渉へ乗り出す。 |
| 4月28日 | 北ベトナム側の要求により、南ベトナム大統領チャン・バン・フォンが辞任。ズオン・バン・ミンが大統領となる。南ベトナムでは野党勢力であり、かつ北ベトナム側とも距離をおいていた人物。 |
| 4月30日 | 北ベトナム軍が南ベトナムの首都サイゴンに侵攻し、サイゴン陥落。ミン大統領は降伏し、ベトナム戦争は終結。なお北ベトナム政府は南ベトナム政府を認めていなかったため、降伏とは取らず傀儡政権からの解放とした。アメリカは、アメリカ軍関係者、アメリカ市民、南ベトナム市民、在南ベトナム外国人らを脱出させるフリークエント・ウィンド作戦を実施。沖合の空母などにヘリで輸送。 |
| 5月12日 | アメリカのコンテナ船マヤグエース号がカンボジア近海のタイ湾でカンボジア軍により拿捕される。乗員はコー・タン島を経てカンボジア本土へ輸送される。 |
| 5月14日 | アメリカ軍がマヤグエース号乗員救出作戦を実施。コー・タン島に海兵隊員を降ろす。乗員は移送後だったため救出は出来ず、カンボジア兵と交戦。 |
| 5月15日 | カンボジア政府、マヤグエース号の乗員を国外退去としたため、アメリカ軍も撤退。 |
| 5月16日 | 田部井淳子が女性として初めてエベレストに登頂。 |
| 6月24日 | 歌手の加藤登紀子の伊豆伊東市の別荘を革マル派が襲撃、別荘にいた革労協の幹部1人が死亡、9人が重軽傷を負う。加藤登紀子の夫で当時獄中にあった元ブントの藤本敏夫との関係で革労協のメンバーが滞在していた。 |
| 6月25日 | モザンビークがポルトガルから独立。 |
| 7月 4日 | ボーイング747-SPが初飛行。パンアメリカン航空元会長の、ニューヨーク-東京間ノンストップの航空機開発の提案を受けて、ボーイング社が輸送力はあるが航続距離の短かった747-100型機を短胴化して尾翼を大きくし航続距離を1万2000kmまで伸ばした機種。2階部分をそのままにしたことでエリアルール(断面積の法則)の効果(速度向上)が出ることも発見され747-300以降は2階部分が長くなっている。日本では採用されず。のちに長距離機が次々と登場したため、45機の生産に終わったが、世界中で政府専用機などに採用された。 |
| 7月 5日 | カーボベルデがポルトガルより独立。ギニアビサウとの統合を目指すも、反発したギニアビサウでクーデターが起きたことで頓挫し、現在まで独立国家として続いている。 |
| 7月 6日 | コモロ諸島のうち、マヨット島を除く3島がコモロとしてフランスから独立。コモロ政府はマヨット島も含むとしているが、マヨット島の住民投票の結果ではフランス海外領土として残ることを選択したとしている。 |
| 7月12日 | 西アフリカの諸島国家サントメ・プリンシペがポルトガルから独立。 |
| 7月12日 | 皇居坂下門に左翼系学生組織「首都圏青年連絡会議」のメンバーが突入。宮内庁庁舎を目指すも途中で取り押さえられる。第二次坂下門乱入事件。 |
| 7月17日 | 沖縄国際海洋博覧会を訪問するために沖縄を訪れていた皇太子夫妻(のちの天皇・皇后両陛下)がひめゆりの塔で献花中に、左翼テロリストに火炎瓶を投げつけられる事件が起こる。夫妻は無事。 |
| 7月17日 | 東京新橋駅で、中核派と革マル派の約800人が大規模な内ゲバ事件を起こす。ホームや電車内の乗客も巻き込まれ、1名が死亡。重軽傷者多数を出す。321人が逮捕。 |
| 7月20日 | 沖縄国際海洋博覧会開幕。翌1976年1月18日まで。 |
| 8月 3日 | ロイヤル・エア・モロッコ航空チャーター機墜落事故。フランスのパリ・ル・ブルジェ空港発、モロッコのアガディール・イニズギャン空港行、ロイヤル・エア・モロッコ航空がロイヤル・ヨルダン航空からチャーターしたボーイング707型機が、アガディールの手前で山中に激突。乗員乗客188人全員死亡。パイロットの操縦ミスにより降下しすぎたため。 |
| 8月 4日 | テログループ日本赤軍のメンバー5人が、マレーシアの首都のクアラルンプールにある、アメリカとスウェーデンの大使館を襲撃し、館内にいたアメリカの総領事ら52人を人質に取る。日本政府に活動家7人の釈放を要求し、日本政府は5人を釈放し出国させる(2人は拒否)。 |
| 8月 5日 | 河南75・8潰壩事件。台風に伴う豪雨の中、中国河南省にある板橋ダム・石漫灘ダム・竹溝ダム・田崗ダムの大中型ダムと、58基の小型ダムが次々と決壊。河南省と安徽省で大洪水となり、公式には2万2546人が溺死、1633人が病死したといわれる。実際には、関連死も含めて、8万6千人から23万人が死亡、1015万人が被災したという。ダムに関する事件・事故では人類史上最悪とされる。 |
| 8月 7日 | クアラルンプールで人質事件を起こした日本赤軍のメンバー5人と、彼らの要求で釈放された5人が、日航機でリビアへ向かう。翌日、リビアに到着し、リビア政府に投降する。 |
| 8月27日 | エチオピア帝国の最後の皇帝ハイレ・セラシエ1世が殺害される。犯人は不明だが、後に大統領となった独裁者メンギスツ・ハイレ・マリアムが殺害を指示したものと考えられる。 |
| 9月16日 | パプアニューギニアが、オーストラリアから独立。独立運動を指導したマイケル・ソマレが初代首相となる。平和的に独立を達成したが、同じニューギニア島の旧オランダ領だった西半分はインドネシアに併合されている。 |
| 9月18日 | 自分を誘拐した左翼過激派シンバイオニーズのメンバーになっていたパトリシア・ハーストが逮捕される。主張が一転し、洗脳されていた、殺されないように味方になったふりをしていたと主張。 |
| 11月 6日 | モロッコが西サハラの領有を主張して市民35万人を越境させる「緑の行進」を実施。 |
| 11月10日 | イタリアとユーゴスラビアがオージモ条約を締結。19世紀以来領土の帰属が確定していなかったトリエステからイストリア半島北部にかけての地域(トリエステ自由地域)を両国で分割するもの。 |
| 11月11日 | アンゴラがポルトガルから独立。 |
| 11月22日 | スペイン「王制」復古。独裁者フランシスコ・フランコの遺言により、前国王アルフォンソ13世の孫にあたるフアン・カルロス1世がスペイン国王に即位。 |
| 11月22日 | 韓国の情報機関KCIAが、在日韓国人留学生21人を北朝鮮のスパイだとして逮捕したと発表。「学園浸透スパイ団事件」。再審で無罪が確定するなど現在ではいずれも冤罪であるとされている。 |
| 11月26日 | 国鉄大ストライキ(スト権スト)がはじまる。国労などが公務員のストライキ権を求めて大規模なストライキを実施。国鉄各路線と貨物輸送の殆どが運行停止となる。大手民鉄(私鉄)各社はストライキに同調せず、利用者が私鉄路線へ殺到。混雑で電車内の窓ガラスが割れるなどの被害も相次ぐ。他業種の組合からの批判や、国鉄内の各組合同士でも方針を巡って対立。各地で学校が休校になるなど社会的な混乱も発生。当初はスト権についてある程度譲歩を見せていた政府は強硬姿勢に変化し、トラック輸送業界に支援を要請する。一方、日本社会党や日本共産党など野党各党はストライキを支持。 |
| 11月28日 | ポルトガル領東ティモールが独立宣言。しかしすぐに隣国インドネシアの侵攻を受ける。 |
| 12月 3日 | 国鉄大ストライキ(スト権スト)が終了。ストライキは8日間続けられたものの、市民の大きな反感・反発を招き、トラック輸送へのシフトが加速して、国鉄および組合運動・野党への信用が失墜しただけの結果に終わる。なお、生鮮業界などではその前からトラック輸送への転換が進んでいたが、国鉄の組合幹部はそれをよく理解していなかったとも言われる。またストに関係なく、国鉄職員の勤務実態の悪さが社会問題化されたことも信用低下の要因。国鉄の経営悪化が加速し、スト権獲得どころか逆に雇用維持の危機的状況にまで悪化したことから、国鉄の労働組合はこれ以降、特に貨物輸送をストライキの対象から外すようになるがもはや手遅れであった。 |
| 12月15日 | 旧日本海軍最後の海軍大将の一人井上成美が死去。実戦指揮では評価が低い一方で教育者としては評価が高かった人物。日独伊三国同盟や日米開戦に反対し、早くから終戦工作を行ったことでも知られる。 |
| 12月16日 | 中国共産党副主席で文化大革命を主導した康生が病死。毛沢東の信頼を得て多くの無実の人に罪を着せて処刑したことで恐れられた人物。毛沢東の死後、共産党より除名される。 |
| 12月24日 | 蒸気機関車の定期牽引運転が、北海道の夕張線(現・石勝線)で終え、廃止される。 |
| 1976年(昭和51年) | |
| 1月 8日 | 中華人民共和国建国以来の国務院総理、周恩来が死去。 |
| 1月20日 | 大和運輸(現在のヤマト運輸)が「宅急便」のサービスを開始。各家同士を結ぶ小口宅配業の本格的なサービスのはじまり。 |
| 1月22日 | 連続女性強姦及び殺人事件の犯人、大久保清の死刑が執行される。 |
| 1月24日 | 全欧安全保障協力会議のヘルシンキ宣言を批判したイギリス保守党党首マーガレット・サッチャーを、ソビエト国防省機関紙「クラスナーヤ・ズヴェーズダ」が、「鉄の女」と非難。しかし本人に気に入られて、これが彼女のあだ名となる。 |
| 1月31日 | ミランダ警告のもととなった「ミランダ対アリゾナ州事件」のアーネスト・ミランダが喧嘩で殺害される。 |
| 2月27日 | 西サハラのポリサリオ戦線が「サハラ・アラブ民主共和国」の独立宣言を行なう。 |
| 2月29日 | N-Iロケット2号機によって日本初の実用衛星「うめ」が打ち上げられる。 |
| 3月 7日 | 北朝鮮の元将軍で副首相、中央人民委員会委員、政務副総理などを歴任した南日が地方視察中に自動車事故で死去。後に南日が金平一(金正日の異母弟で金日成の後継候補の一人)の後見についていたことから、暗殺されたのではないかという疑惑が出た。 |
| 3月 8日 | 中国吉林省吉林市付近に、上空で爆発四散した隕石の破片が多数降り注ぐ。 |
| 3月23日 | 児玉誉士夫邸セスナ機特攻事件。右翼の大物で政財界のフィクサー児玉誉士夫邸に俳優の前野光保(芸名前野霜一郎)が操縦する小型機(セスナ機ではなくパイパー機)が突入自爆。前野は死亡。児玉は無事、家政婦が軽傷を負う。右翼でもあった前野が尊敬していた児玉誉士夫が、ロッキード事件の利権に関わっていたことを知り反感を持ったためと言われる。 |
| 3月24日 | アルゼンチンのホルヘ・ラファエル・ビデラ・レドンド陸軍総司令官ら軍部がクーデターを起こし、イサベル・ペロンは失脚。軍事政権が樹立。ペロン政権時代から進んでいた市民弾圧政策「汚い戦争」が激化し、多くの市民が殺害される。 |
| 6月16日 | ソウェト蜂起。南アフリカ政府のアフリカーンス語強制に反発した黒人学生・生徒らがソウェトで行ったデモに警察が発砲し、少なくとも176人が死亡、1139人が負傷。 |
| 6月27日 | ギリシアのアテネからパリへ向かったエールフランス139便が、パレスチナ解放人民戦線と西ドイツの過激派の4人にハイジャックされる。犯人はウガンダのエンテベに移動し、イスラエル人乗客を人質に政治犯解放を要求。ウガンダのアミン大統領が犯人を支援。 |
| 6月29日 | セーシェルがイギリスから独立。 |
| 6月 | スーダンのヌザラで、ザイール(コンゴ)出身の男性が急な激しい出血を伴って死亡。ヌザラの街で次々と同様の症状をもつ人が現れる。最終的に151人が死亡。最初に発症した男性の出身地の川の名前からエボラ出血熱と名付けられる。 |
| 7月 3日 | イスラエル軍がオペレーション・エンテベを実施。ハイジャック機を急襲して犯人を射殺。人質3人が死亡。ウガンダ軍との戦闘で兵士指揮官1人とウガンダ兵士多数も死亡。病院に収容されていた乗客1人もウガンダ政府により殺害される。 |
| 7月10日 | セベソ事件。イタリアのミラノの近郊、セベソにある除草剤製造工場で爆発事故が起こり、大量のダイオキシンが拡散する。 |
| 7月13日 | パイパー宅放火事件。元ナチスドイツ親衛隊将校として、マルメディ事件やボーヴェス事件に関与したとされ、戦後、偽名でフランスのオート=ソーヌ県に暮らしていたヨアヒム・パイパーが、正体を暴露されて自宅を放火され焼死。家族は無事だった。フランス共産党の犯行ともされている。 |
| 7月14日 | タンザン鉄道(TAZARA)が完成する。ローデシアのアパルトヘイト政策に対する国際社会の経済制裁で、ローデシアを中継して南アフリカから輸出していたザンビアは輸出できなくなり苦境に陥ったことから、逆方向のタンザニアから輸出するために、中国の支援で国際鉄道路線を建設した。 |
| 7月24日 | セベソ事件で、ようやく周辺住民に避難命令が出される。 |
| 7月28日 | 唐山大地震。中国河北省唐山市を中心とした地域で巨大地震が起こり、少なくとも24万人が死亡する。 |
| 8月 3日 | 本白根山で、登山中の女子高生3人が、火山ガス(硫化水素)を吸って死亡する事故が発生。 |
| 8月18日 | ポプラ事件。朝鮮半島の軍事境界線にある板門店で、北朝鮮側が植樹したポプラ並木が成長して視界を遮るようになったことから、国連軍側が北朝鮮に通告した上で枝の剪定を実施。これに対し北朝鮮側が抗議し止めようとしたが、そのまま継続したため、金正日の指示で北朝鮮兵士が、持ち込まれていた斧などを使って指揮をしていたアメリカ軍の士官2名を殺害。 |
| 8月19日 | ポプラ事件を受けて、国連軍・韓国軍と朝鮮人民軍が緊急協議。国連軍に属するアメリカ軍は並木の伐採を主張。アメリカ・韓国両政府は北朝鮮に対し強硬姿勢を見せる。 |
| 8月21日 | ポプラ事件を受けて、国連軍・韓国軍は「ポール・バニヤン作戦」を実施。ヘリ27機の警備の元、車両23台を投入して板門店のポプラ並木の伐採を実施。不測の事態を想定して空軍機も警戒飛行し、空母機動部隊まで動員。北朝鮮側は兵士を動員したものの軍事行動には移らず、金日成主席が同日ポプラ事件について遺憾の意を示す親書を国連に提出したため終息した。北朝鮮ではその後の1年間戦時動員体制が継続し、それを利用して内部の金正日後継に批判的な勢力への粛清が行われたともいう。 |
| 8月23日 | 第一回安楽死国際会議が東京で開催。 |
| 9月10日 | ザグレブ空中衝突事故。ユーゴスラビアのザグレブ上空で、ロンドン発イスタンブール行きブリティッシュ・エアウェイズ476便ホーカー・シドレートライデント3B機と、スプリト発ケルン・ボン行きイネックス・アドリア航空550便DC-9型機が空中衝突。ザグレブ管制当局のミスでアドリア機がブリティッシュ機の飛行高度に入ってしまい、前を横切る格好でブリティッシュ機の操縦室を破壊。アドリア機も左翼が破壊され、両機とも墜落。両機の乗員乗客あわせて176名全員が死亡。 |
| 9月12日 | 諏訪之瀬島で台風17号の集中豪雨により土石流が発生し、5人が死亡。5人が負傷。日本航空の旅客機が救援の無線を傍受して通報。 |
| 10月 6日 | 中華人民共和国で江青ら四人組が逮捕される。膨大な犠牲者を出した文化大革命が崩壊。犠牲者数は公式には40万人だが、実際には数百万から一千万を超えるとも。何らかの被害を被った人は1億人以上。知識人の多くが殺害され、文化財にも甚大な被害を残した。 |
| 10月 6日 | クバーナ航空455便爆破事件。ガイアナ発、トリニダード・トバゴ、バルバドス、ジャマイカ経由、キューバ行のクバーナ航空455便DC-8型機が、バルバドスを離陸まもなく、カリブ海上空を飛行中に、トイレに仕掛けられていた爆弾が爆発。機長は空港に引き返そうとしたが、2回めの爆弾が爆発し、機体は操縦不能になり墜落。乗員乗客73人全員死亡。キューバ出身の反共ベネズエラ人で元CIA工作員のルイス・ポサダ・カリレスらによって計画され、ベネズエラ人2人によって引き起こされたとみられる。この事件はポサダの身柄引き渡しをめぐり、アメリカと中南米諸国で長期にわたり問題となる。 |
| 10月16日 | ソビエトの宇宙船ソユーズ23号がサリュート5号とのドッキングが出来ず地球に帰還。その際、帰還カプセルはカザフスタンの一部凍ったテンギス湖に着水。氷点下22度の極寒で悪天候の中救助が遅れ、飛行士は水没したカプセルの中で一夜を過ごす事態に。9時間後に乗員2名は無事救助。 |
| 11月21日 | 映画『ロッキー』公開。自堕落な生活で実力を発揮できないボクサーが、チャンピオンの気まぐれで試合に出ることになり、愛する女性のために努力して勝負に挑むアメリカンドリームの物語。無名の俳優だったシルベスター・スタローンが脚本を書き主演を務め人気俳優の仲間入りをした。テーマ曲も有名。アカデミー賞受賞。 |
| 12月 4日 | 中央アフリカ共和国の独裁者ジャン=ベデル・ボカサが、皇帝を称し、国号を中央アフリカ帝国とする。 |
| 1977年(昭和52年) | |
| 1月 3日 | 青酸コーラ無差別殺人事件が起こる。 |
| 1月 3日 | スティーブ・ジョブズと、スティーブ・ウォズニアック、マイク・マークラによって、アップルが法人化される。 |
| 1月 6日 | 水本事件。江戸川の下流で腐爛した水死体が発見され、市川警察署が調べた結果、行方不明になっていた革マル派のメンバー、日大芸術学部の学生水本潔と判断。遺体はそのまま焼却されるが、遺品と遺体写真を見た母親が、遺品は息子のものだが遺体は別人と証言。このことから、革マル派が、水本は国家とCIAによって謀殺され、遺体はすり替えられたと主張。それに対し、中核派や革労協はデマだと革マル派を批判。文化人らも巻き込んだ論争に発展する。 |
| 1月10日 | コンゴ民主共和国の東部にあるニーラゴンゴ山が噴火。溶岩が麓まで流れ、約70人が死亡。 |
| 2月11日 | 革労協書記長内ゲバ殺人事件。茨城県取手市の取手駅前で、車に乗っていた笠原正義革労協書記長が、革マル派メンバーに取り囲まれ、鉄パイプで滅多打ちにされて死亡。革労協は報復を宣言。浦和車両放火事件を引き起こす。 |
| 2月15日 | スペースシャトルの実験機「エンタープライズ」の滑空飛行に成功。 |
| 2月17日 | 沖縄で唯一の降雪を観測。この日、沖縄県の久米島にある測候所で、みぞれを観測する。 |
| 2月25日 | 超音速戦闘機F-1の量産1号機がロールアウト。戦後初の国産戦闘機。 |
| 3月10日 | インド洋上を飛行中のカイパー空中天文台が、天王星の大気を観測中に偶然、輪を観測。 |
| 3月27日 | スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島にあるロス・ロデオス空港で、史上最悪と言われるジャンボ機衝突事故が発生。濃霧の中、管制官と2機のジャンボ機の乗員の意思疎通の不備が原因で、離陸を始めたKLM航空機が滑走路上にいたパンナム機に激突。583名が死亡。 |
| 4月 7日 | 西ドイツ連邦検事総長ジークフリート・ブーバックが、ドイツ赤軍の手で射殺される。 |
| 4月15日 | 浦和車両放火内ゲバ殺人事件。浦和市内で、革マル派の戸田市にある印刷工場から来た装甲ワゴン車を革労協のメンバーが大型トラックで挟んで停止させ、ガソリンで車内へ放火。乗っていた革マル派活動家4人が焼死する。 |
| 4月17日 | 三里塚芝山連合が三里塚で空港粉砕を唱えた大規模な反対集会を開催。1万7500人が参加。反対集会では最大規模となる。またこの集会で革労協が、浦和市内で起きた車両放火事件の犯行声明を書いたビラを配る。一方、革マル派はこの集会を妨害するため、京葉道路下り線に重油などを撒く事件を起こす。 |
| 5月 3日 | イギリスで軽空母インヴィンシブルが進水。コストカットのため、大型空母を建造しない代わりに、垂直離着陸型の戦闘機シーハリアーを搭載することで小型化した空母。離陸時の揚力を稼ぐためスキージャンプ台式甲板を採用した。当初は役に立つか疑問視されたが、フォークランド紛争で戦果を上げたことで各国で採用されることになる。 |
| 5月 6日 | 新東京国際空港公団が、千葉地裁の仮処分を受けて、反対派の建設した岩山鉄塔の解体を行う。周辺では2100人の機動隊が出動、反対派と衝突。 |
| 5月 8日 | 東山事件。機動隊と空港建設反対派が衝突し、反対運動に参加していた活動家が頭部を負傷して10日に死亡。反対派は機動隊の催涙弾が当たったとし、警察は反対派の投石が当たったと主張。 |
| 5月 9日 | 空港建設反対派の共産同の活動家50人余りが、芝山町長宅のそばにあった臨時派出所を襲撃。火炎瓶で放火し、炎上した警察官を執拗に襲い、派出所の警察官6人が重軽傷、うち2人が瀕死の重傷を負い、1人が21日に死亡。 |
| 5月22日 | ソ連の多用途戦闘機Su-27が初飛行。アジア、アフリカ諸国にも輸出されており派生型も多い。アメリカも中古機を第三国経由で購入したと言われ、ソ連崩壊後にはロシアから日本にも売り込みが行われたという。 |
| 5月25日 | 映画『スターウォーズ』がアメリカで公開。第1作だが、シリーズのうちではエピソード4に当たる。後に映画史上最大のヒットシリーズ作品になったが、公開前は非常に低評価だったため、公開時の映画館は50館ほどだったと言われる。監督で原作者でもあるジョージ・ルーカスは失敗したと思いハワイに逃避。ヒットを知らせに来たスピルバーグ監督と会い、そこでのちの『インディ・ジョーンズ』の構想ができたと言われる。 |
| 5月28日 | アメリカケンタッキー州サウスゲートのナイトクラブ「ビバリーヒルズ・サパー・クラブ」で火災が発生。初期消火に失敗したこともあるが、客が事態の深刻さに気づくのが遅れたために避難が遅れて165人が死亡。200人以上が重軽傷を負う。 |
| 6月16日 | ロケット研究者フォン・ブラウンが病気で死去。アメリカの主なロケット開発全てに関わる。ドイツ宇宙旅行協会、ナチス、アメリカと立場を替えながらロケット開発にこだわり、その態度が様々な批判にさらされるも、一貫して月を目指すロケット開発に情熱を燃やした生涯が評価もされている人物。 |
| 6月27日 | フランス領アファル・イッサが、フランスから独立し、ジブチ共和国となる。 |
| 7月13日 | ソマリア軍7万が、エチオピアへ軍事侵攻。オガデン戦争勃発。ソマリアのシアド・バーレ政権は、大ソマリア主義を主張し、ソマリ族がケニア東部やエチオピア東部オガデン地方にも居住していることから、これらをすべて統合した国家建設を掲げた。これに呼応したオガデン地方のソマリ族とエチオピアのメンギスツ・ハイレ・マリアム政権が対立。ソ連の支援を受けたメンギスツは、軍事作戦を計画し、逆にアメリカやアラブ諸国はソマリアを支援したため、バーレはエチオピアに侵攻した。しかしオガデンの6割ほどを制圧したところでエチオピア軍の反撃に遭い、ソマリア軍は大敗。バーレの権威は失墜し、更にソマリア内戦へと発展することになった。 |
| 7月14日 | 気象衛星ひまわりが、アメリカ・ケープカナベラルのケネディ宇宙センターから打ち上げられる。 |
| 7月30日 | 西ドイツドレスナー銀行の頭取ユルゲン・ポントが自宅でドイツ赤軍メンバーに射殺される。 |
| 8月16日 | エルヴィス・プレスリーが自宅で急死。42歳。処方薬の誤用が死因とされている。 |
| 9月 3日 | 王貞治が通算756号ホームランを達成。ハンク・アーロンを抜いて世界一の「ホームラン王」となる。 |
| 9月 5日 | メルセデス・ベンツの重役でドイツ経営者連盟会長・ドイツ産業連合会長のハンス=マルティン・シュライヤーがドイツ赤軍に誘拐される。一連のドイツ赤軍による事件を受け、ドイツ政府、与野党が超法規的に協力体制を構築。西ドイツメディアも報道の自粛を開始。 |
| 9月 7日 | 横浜米軍機墜落事件。厚木基地の米軍偵察機が横浜の市街地に墜落。巻き込まれた母子が死亡する。操縦士は脱出。 |
| 10月 6日 | ソ連の制空戦闘機MiG-29が初飛行。東欧、アジア、アフリカ・中南米諸国にも幅広く輸出された。のちにドイツは統一しているため、西側諸国ながらMiG-29を保有しているほか、アメリカも第三国経由で購入保有している。ほぼ同時期に開発されたSu-27とは競合ライバル関係にある。 |
| 10月13日 | ルフトハンザ航空181便(ランツフート号)ハイジャック事件。スペイン領マヨルカ島からフランクフルトへ向かっていた便の乗客男女4人によって起こされた。ドイツ赤軍によるシュライヤー誘拐事件に対して西ドイツ政府が強硬な態度で応じたことを受け、ドイツ赤軍と連携していたパレスチナ解放人民戦線が支援のために起こしたもの。西ドイツ政府に対し、ドイツ赤軍メンバー11人の釈放と、1500万米ドルを要求。機体をキプロスのラルナカ、さらにバーレーン、ドバイへと移す。西ドイツ政府のシュミット首相は交渉に応じつつも連邦警察特殊部隊GSG-9の投入を決定。イギリス政府は陸軍特殊空挺部隊SASでこれを支援。 |
| 10月15日 | ルフトハンザ航空181便(ランツフート号)ハイジャック事件で、中東各国は受け入れを拒否。ドバイを離陸した機体はオマーンのサラーサへ向かうが、オマーン政府が許可しなかったため、その先の南イエメンへ移動。南イエメン政府も着陸を認めず空港を封鎖したが、燃料不足に陥り、アデン空港脇の砂地に強行着陸。機長が機体の状態を調べるため機外に出るが、南イエメン当局の足止めを受けたため、犯人に疑われ射殺される。 |
| 10月17日 | ルフトハンザ航空181便(ランツフート号)ハイジャック事件で、機体はアデン空港を離陸し、ソマリアのモガディシュ空港に着陸。西ドイツ政府は交渉を引き伸ばしつつ、ソマリアのモハメド・シアド・バーレ大統領と交渉。協力を取り付ける。 |
| 10月18日 | ルフトハンザ航空181便(ランツフート号)ハイジャック事件で、西ドイツの特殊部隊GSG-9は、ソマリア軍の協力の下、機体に突入。犯人3人を射殺し1人を逮捕。乗員乗客を脱出させることに成功。先に収監されていたドイツ赤軍の創設者アンドレアス・バーダーと幹部のヤン=カール・ラスペが獄中でピストル自殺。同じく創設メンバーのグドルン・エンスリンは首をつって自殺した。刑務所内でのピストル自殺は異様だとして陰謀説もあるが、公式にはシンパの弁護士が持ち込んだとされている。一方、ドイツ赤軍に誘拐されていたシュライヤーも赤軍メンバーの手で射殺される(遺体は翌日発見)。 |
| 10月26日 | ソマリアのメルカの病院で料理人をしていたアリ・マオ・マーランが、天然痘患者の輸送を手伝ったあとに発症する。軽症ですみ、それ以上の感染拡大にもならなかったため、判明している最後の自然感染患者となった。バイオハザードによる感染例としては、翌年9月のイギリス天然痘アウトブレイク事件がある。 |
| 11月 3日 | フランスの作家アルマン・リュネルがモナコで死去。フランス南部プロヴァンス地方でのみ話されていたシュアディート(ユダヤ=プロヴァンス語)の最後の話者でもあり、その死によりシュアディートは死語となった。 |
| 11月 4日 | 気象衛星ひまわり、定常運用開始。 |
| 11月11日 | 韓国の全羅北道裡里市にある裡里駅で、火薬など40tを積んだ貨物列車が爆発。駅及び周辺500mの建物など1800棟が全半壊。59人が死亡する。酔った乗員が灯のためにろうそくに火をつけたところ、それが火薬箱に落ち引火したためという。 |
| 11月30日 | 東京の米軍立川基地が日本に全面返還される。防災基地、国営昭和記念公園へ再開発。 |
| 11月 | ROMカセット式の家庭用ゲーム機アタリ2600(当時はアタリVideo Computer System)が発売される。 |
| 12月 4日 | 中央アフリカ帝国皇帝ジャン=ベデル・ボカサが、皇帝の戴冠式を行う。国家予算の2倍をかけた贅沢三昧な式典に各国から批判を浴びる。 |
| 12月22日 | アメリカルイジアナ州ウェストウィーゴのコンチネンタルグレイン社の穀物サイロ群にある穀物用のエレベーターで粉塵爆発が発生。サイロが崩壊し近くのカフェテリアにいた従業員37人が破片の下敷きになり死亡。 |
| 12月27日 | アメリカテキサス州ガルベストンのファーマーズ・エクスポーツ・カンパニーの穀物輸出用エレベーターで大規模な粉塵爆発が発生する。 |
| 12月31日 | カンボジアの民主カンプチア政権がベトナムと国交を断絶。 |
| 1978年(昭和53年) | |
| 1月14日 | 数学者クルト・ゲーデルが死去。「完全性定理」「不完全性定理」「連続体仮説」を発見したことで知られる。晩年は極度の人間不信と猜疑心により、妻の手料理以外は口にせず、直接的な死因も妻が病で緊急入院したことによる餓死であった。 |
| 1月24日 | 原子炉を搭載したソ連のレーダー海洋偵察衛星コスモス954号が、墓場軌道への移動に失敗し、大気圏へ突入。カナダ北西部へ墜落。広範囲が放射性物質で汚染される。 |
| 2月18日 | 嫌煙運動の日。東京の四谷で「嫌煙権確立をめざす人々の会」が設立される。 |
| 2月18日 | キプロスのニコシアで開催されていたアジア・アフリカ人民連帯機構代表者会議の会場で、2名の武装した男が、エジプトのユーセフ・エル・セバイ書記長を射殺する暗殺事件が起こる。アラブ系の犯人は会議出席者の要人らを人質に取り、キプロス政府に要求して、旅客機で逃走を図るも、受け入れ先がなく戻ってくる。 |
| 2月19日 | ラルナカ国際空港襲撃事件。キプロスでの暗殺事件に、人質をとったままキプロスに戻ってきた犯人が東ヨーロッパに亡命する様相が見えたため、エジプト軍が逃走用の旅客機を襲撃。キプロス軍と交戦しエジプト兵15人が死亡する。犯人は投降し、人質は無事。 |
| 3月 8日 | のちに世界中でヒットするイギリスのSFラジオドラマ『銀河ヒッチハイク・ガイド』の放送開始。 |
| 3月26日 | 開港直前の成田空港に左翼ゲリラが侵入。管制塔の設備を破壊。開港が延期となる。 |
| 4月 6日 | 気象衛星ひまわり、本格運用開始。 |
| 4月 6日 | 東京豊島区東池袋の旧巣鴨拘置所跡地に「サンシャイン60」が開館する(60階建て、240m)。完成時は東洋一、日本一の超高層ビル。 |
| 5月 5日 | 成田空港開港に反対する左翼ゲリラが京成スカイライナーの車両を放火破壊。 |
| 5月20日 | 前年からの少雨により、福岡市で夜間断水が始まる。通称「福岡大渇水」。 |
| 5月21日 | 前日開港の成田空港の運用が始まる。 |
| 6月 1日 | 福岡大渇水で5時間限定給水が始まる。 |
| 6月13日 | ソビエトの物理学者アナトリ・ブゴルスキーが、高エネルギー物理学研究所のU-70粒子加速器の故障箇所を点検している最中に76GeVの陽子線を頭部に浴びる事故が起きる。致死量を遥かに超える線量によって頭部に大きな損傷を受けたが、死ぬこともなく、知能活動にも影響がなかったため、その後も研究を続けた。 |
| 7月11日 | スペインカタルーニャ州アルカナーのロス・アルファケス・キャンプ場で、通過中の液体プロピレン23tを積んだタンクローリーが事故を起こし、漏れたガスがキャンプ場と隣接のディスコに流れ込んで引火。大爆発を起こし、ディスコの客全員を含む、少なくとも217名が爆死もしくは焼死し、重傷者の死亡も含めると270名以上が亡くなる大惨事となる。過積載の上、高い気温、タンクの使い回しによる腐食などが重なって起きた事故。 |
| 7月25日 | 世界初の体外受精による赤ちゃん、ルイーズ・ジョイ・ブラウンが誕生する。 |
| 7月30日 | 沖縄県で交通が右側通行から左側通行へ切り替えられる。通称「730」。 |
| 9月 5日 | キャンプ・デービッド会談。カーター米大統領が、アンワル・アッ=サーダートエジプト大統領、メナヘム・ベギンイスラエル首相を大統領山荘キャンプ・デービッドに呼んで、和平交渉を行う。 |
| 9月11日 | イギリス天然痘アウトブレイク事件。イギリスのバーミンガム大学で、微生物学講座の研究室からダクトを通じて漏れた天然痘ウイルスに、上階の解剖学講座で働いていたジャネット・パーカーが感染し死亡。現時点では天然痘で死亡した最後の例とされている(母親も感染したが回復)。強毒性のタイプだったこと、自然の天然痘は1977年以降確認されておらず確認に時間がかかったこと、バイオハザードの認識が弱かったことも要因。微生物学講座の責任者だったヘンリー・ベドスン教授が、責任を感じて自殺している。 |
| 9月25日 | サンディエゴ空中衝突事故。サンディエゴ空港へ着陸しようとしていたパシフィック・サウスウエスト航空182便ボーイング727機が、計器飛行訓練中のセスナ172Mに空中衝突。セスナの存在は旅客機側に伝えられていたが、視認を見失った際に追い抜いたと勘違いし、管制は目視していると勘違いしたため、そのまま着陸を続行。前方を上昇中のセスナに気づいたときは手遅れで、旅客機の右翼がセスナを破壊。セスナは分解し、旅客機は制御を失い、右翼から火を吹きながら住宅街に墜落した。旅客機の乗員乗客135名全員、セスナの乗員2名、住宅街の住人7名が死亡。 |
| 9月28日 | ローマ教皇ヨハネ・パウロ1世が在位33日目で急死。バチカン政府が死に関する嘘の発表をした他、遺体発見後すぐに死因を調べず葬儀の準備を進めたり、遺言状や人事リストなどが行方不明になったことや、マフィアと深い関係があったポール・マルチンクス大司教が総裁を務める「宗教事業協会」(通称バチカン銀行)の改革を進めていたことから、暗殺されたという見方が強い。また初めて複合名を用い、ラテン語ではなく平易な言葉遣いをし、避妊を容認する立場を表明するなど、歴代教皇と異なる独自の立場を取ったことは改革派の信者らの支持を得たものの、保守派から反感を買ったと言われる。2022年9月4日に列福。 |
| 10月 2日 | 国鉄が大規模な白紙ダイヤ改正を実施(ゴーサントオ)。これまでの白紙ダイヤ改正とは異なり、輸送実績の減少に伴う運行削減方向への改正。特に労働組合の大規模ストライキによる信用低下、赤字による度重なる料金値上げ、航空機・自動車・私鉄との競争などで、利用者が大幅に減少したことが主な要因。急行列車と貨物列車の大幅削減が行われた。 |
| 10月 5日 | 環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約が発効。自然現象(台風や地震など)を激化する(あるいはコントロールする)ような技術を使って敵国に対し軍事攻撃を行うことを禁止した条約。発効時の技術だけでなく、将来的に生み出されるであろう兵器も含まれる。環境改変技術自体を禁止していないことや、架空の兵器も含んでいるなど、効果に関しては疑問もある。 |
| 10月17日 | 靖国神社にA級戦犯14人が合祀される。実施したのは第6代宮司の松平永芳。合祀した理由は「東京裁判は国際法に認められてない」「14人は国内法によって戦死者と同列に扱われてる」「靖国神社が祭神の評価をして祀るかどうかを決めるのは僭越」とされる。松平自身は靖国神社の政治利用には反対していたが、合祀が発覚した翌年以降、大きな論争を生むことになる。 |
| 10月30日 | ウガンダ・タンザニア戦争勃発。ウガンダの独裁者アミンに対する反政府軍と、アミンの権力に反発したウガンダ軍の一部部隊が、アミン側の政権軍と交戦。反政府軍らはウガンダと関係の悪化していた隣国タンザニアに逃走したため、ウガンダ政権軍がタンザニアに侵攻。対するタンザニアのニエレレ政権はこれに応戦して逆にウガンダへ侵攻。ウガンダ側にはリビアとパレスチナ解放機構が、タンザニア側にはウガンダの反乱軍(国民解放軍)やモザンビーク軍、アルジェリア軍が加わった。 |
| 11月11日 | 無限連鎖講の防止に関する法律公布。 |
| 11月18日 | 人民寺院事件。アメリカのカルト教団「人民寺院」が、ガイアナのジャングルに作ったコミューンの非道な内情が、アメリカの調査団で暴露されそうになったため、調査団一行を銃撃した上、信者ら914人が集団自殺。 |
| 11月21日 | 巨人が江川卓のドラフト外入団を決める。クラウンライターを引き継いだ西武の交渉権が切れ、ドラフトが始まる1日の空白を利用したもの。他球団の大きな反発を買い、日本野球機構コミッショナーの金子鋭は巨人との契約を無効と判断。 |
| 12月25日 | ベトナム軍15万が、カンボジア救国民族統一戦線とともにカンボジアへ侵攻。 |
| 12月28日 | 俳優の田宮二郎が散弾銃で自身を撃ち自殺。43歳。二枚目ながら様々な役をこなし、クイズ番組の司会でも人気があったが、躁鬱病を患い、またM資金詐欺にあったとも言われている。主役を務めた人気ドラマ『白い巨塔』は放映中だった。 |
| 1979年(昭和54年) | |
| 1月 7日 | ベトナム軍が、カンボジアの首都プノンペンに到達し、ポル・ポト政権(民主カンプチア)が崩壊。ヘン・サムリン政権が樹立。 |
| 1月31日 | 阪神に入団した江川卓投手が、小林繁投手とのトレードで、即日巨人に移籍。一連の江川問題が世間に大きな波紋を投げかける。 |
| 2月17日 | ベトナム軍のカンボジア侵攻に反発した中国がベトナムに侵攻。中越戦争が勃発する。中国はカンボジアのポル・ポト政権を支持していたため。 |
| 3月 5日 | 惑星探査機ボイジャー1号が木星に最接近。 |
| 3月 6日 | ベトナムに侵攻した中国軍が撤兵を開始。ベトナム北部の占領には成功したが、寡兵ながら戦闘経験の豊富なベトナム軍の抵抗に大きな被害を出し、カンボジアからベトナム軍主力が戻ったため継戦を断念したと言われる。 |
| 3月16日 | 映画『チャイナ・シンドローム』が公開される。原子力発電所のメルトダウン事故を扱った内容で、偶然にもその直後にスリーマイル島事故が発生する。 |
| 3月25日 | 福岡市の給水制限が、287日ぶりに解除される。 |
| 3月26日 | エジプトとイスラエルの間で平和条約が締結され、両国は相互承認。シナイ半島はイスラエルからエジプトに返還される。 |
| 3月28日 | アメリカのペンシルベニア州都ハリスバーグ近くにあるスリーマイル島原子力発電所でメルトダウン事故が起こる。 |
| 4月 7日 | テレビアニメ『機動戦士ガンダム』の放送が始まる。 |
| 4月10日 | タンザニア軍がウガンダの首都カンパラに侵攻。ウガンダのアミン大統領はリビアへと脱出し、ウガンダ反政府軍が政権を樹立。ウガンダ・タンザニア戦争は終結。 |
| 5月 4日 | イギリス保守党のマーガレット・サッチャーが首相に就任。イギリス初の女性首相。 |
| 5月11日 | 無限連鎖講の防止に関する法律施行。 |
| 5月12日 | 本州四国連絡橋の最初の橋、大三島橋が完成。 |
| 5月 | グリーンランドがデンマークの海外郡から、自治権を持つ自治領となる。 |
| 6月12日 | 元号法が公布・施行。一世一元の詔に代わり、一世一元の制度があらためて定められる。 |
| 6月 1日 | ローデシアが、黒人の参政権を認めてジンバブエ・ローデシアに名称を変更。ただし政権と軍は引き続き白人主導であったため、黒人勢力との内戦状態は継続。 |
| 7月 9日 | 惑星探査機ボイジャー2号も木星に最接近。2機の探査機の画像から新たな発見が相次ぐ。 |
| 8月11日 | 中国の人口抑制策である一人っ子政策がはじまる。 |
| 9月20日 | 中央アフリカ帝国で、皇帝ボカサがリビアに外遊中、フランス軍主導の無血クーデターが起こる。初代大統領ダッコが復位し、ボカサ王朝崩壊。 |
| 9月22日 | アメリカの核実験監視衛星ヴェラが、南アフリカのはるか沖合で謎の二重閃光を観測。隕石の落下、太陽光の反射、流星物質の衛星への衝突、観測機器の故障による電気信号など諸説あるが、二重閃光は大気圏内核爆発の特徴と一致していること(核爆発では瞬間の強い閃光と火球による強い光が出る)、このタイプの衛星がほかの観測で捉えた二重閃光がすべて核実験であったこと、オーストラリアで微量の放射性物質を観測したという報告、アレシボ天文台での異常な電離層波の観測があったことなどから、当時孤立していた南アフリカとイスラエルによる共同の核実験という説も有力視された(イスラエルは核保有国・南アフリカも一時核保有国)。アメリカ政府は公式には自然現象としている。仮に実際の核実験だった場合、数Ktの規模であるため、小型核兵器か、中性子爆弾の実験という説もある。 |
| 9月26日 | ロボトミー殺人事件。ロボトミー手術の一種チングレクトミー手術を受けた元スポーツライター・翻訳家の男性が、手術の結果、意欲を失いてんかんの発作が起こるようになって人生を狂わされたとして、執刀した桜ヶ丘保養所の医師宅に押し入り、医師と心中を図ろうとするが帰宅してこないため、監禁した医師の妻と義母を殺害。男性が手術を強制されたのは、家族内の些細なトラブルがきっかけだったが、過去に職場の不正を追求しようとして逆に恐喝容疑で逮捕された経歴があり、精神に問題があると見た医師は男性の母親を言いくるめて同意書を取り手術を強行していた。男性は責任能力ありとして無期懲役判決。 |
| 10月25日 | スペインの自治州であるバスク州が、自治憲法を制定する。 |
| 10月26日 | 朴正煕韓国大統領が側近の金載圭中央情報部長によって酒席の場で射殺される。同席していた車智澈警護室長も撃たれて死亡。金載圭は翌日逮捕され、翌年処刑された。事件を起こした動機は不明。 |
| 10月28日 | 木曽御嶽山が噴火。登山者1名が負傷。同日中に噴火の規模は弱まり、30日にはほぼ終息したが、それまで死火山と言われてきたため、死火山という定義がなくなるきっかけとなった(気象庁はもともと御嶽山を活火山としていたため、御嶽山が死火山というのは専門外の一般的な認識だったとみられる)。 |
| 11月 2日 | フランス国民の人気が高かった犯罪者ジャック・メスリーヌが警官との銃撃戦で射殺される。 |
| 11月 4日 | イランのアメリカ大使館人質事件が起こる。シーア派宗教指導者らに示唆された若者らが大使館を襲い、職員や家族らを人質に取って暴行を加え、アメリカに亡命したイラン皇帝モハンマド・レザーの引渡しを要求。 |
| 11月15日 | 徳島ラジオ商殺人事件で有罪となった冨士茂子が再審請求中に病死する。翌年再審が決定し無罪。 |
| 11月28日 | エレバス山墜落事故。ニュージーランド航空の南極遊覧飛行のDC-10型旅客機が、南極ロス島にある火山エレバス山に激突。日本人乗客24名を含む257名全員が死亡。操縦士の経験不足、南極飛行の特殊な航法、コンピュータへの誤入力、気象によるホワイトアウトが重なり、低空飛行状態の中で操縦士が対地警報音で機首を起こしたが間に合わず激突したと見られる。原因と責任を巡っては現在も論争がある。 |
| 12月10日 | 台湾で美麗島事件が起きる。政府を批判する活動を行っていた雑誌『美麗島』主催のデモを当局が取り締まり、関係者ら多数が逮捕され、軍法会議にかけられた事件。後に誕生する政党「民進党」は、この事件がきっかけとなっている。 |
| 12月14日 | 月その他の天体における国家活動を律する協定(通称「月協定」)が第34会期国際連合総会で採択。月を含む天体の探査に関する原則を定めたもので、探査・利用の基準、平和利用(軍事利用の禁止)、探査・利用の国際協力、情報の提供、調査の平等、環境の維持、土地や資源の共有財産化(所有の禁止)、違反通報の義務などを定めている。しかし批准したのはわずか13カ国のみで、いずれも宇宙へ独力で出られる技術を持っておらず、ほぼ無効な国際協定と化している。 |
| 12月15日 | 『ルパン三世 カリオストロの城』が公開される。 |
| 12月21日 | 国鉄が研究中の浮上式リニアモーターカーが、宮崎実験線での無人運転で当時世界最高速の時速517kmに達する。 |
| 12月24日 | アフガニスタン人民党政府の要請を受けて、ソ連軍がアフガニスタンに侵攻する。 |
| 1980年(昭和55年) | |
| 1月27日 | イスラム革命が勃発したイランから、拘束をまぬがれカナダ大使館関係者の手で密かに匿われていたアメリカ人外交官ら6人が、架空のSF映画『アルゴ』の撮影のために訪れていたカナダ人を装い、密かに用意されたカナダのパスポートを使ってスイス航空機で国外脱出に成功する。通称「カナダの策謀」事件。後にこの出来事を描いた『アルゴ』という映画も制作された。 |
| 3月18日 | ソビエトのプレセツク宇宙基地で、衛星を打ち上げる準備中のボストーク2Mロケットが爆発。作業員ら48名が死亡。 |
| 3月30日 | 世界初の原子力潜水艦ノーチラス退役。 |
| 4月18日 | 国際的には未承認の状態だったジンバブエ・ローデシアの総選挙の結果を受けて、黒人主導の国家ジンバブエ共和国がイギリスからの独立という形で誕生。儀礼上の元首としてカナーン・ソディンド・バナナが大統領に、実質の権力者としてロバート・ムガベが首相となる。ムガベ政権は2017年まで続いた。 |
| 4月14日 | 富士山で大規模な雪崩が起きる。八合目から五合目まで落ち、スバルラインも寸断される。 |
| 4月24日 | アメリカ政府が、イランのアメリカ大使館人質奪還作戦を行うが、輸送機の事故で失敗。 |
| 5月 8日 | WHO、天然痘根絶宣言。 |
| 5月16日 | 日本社会党が大平内閣不信任案を衆議院に提出。自民党内の分裂で大平内閣不信任が成立してしまう。 |
| 5月18日 | アメリカのセントヘレンズ山が大爆発。山体が崩壊し、大規模な火砕流が周囲へ広がる。57人が死亡。 |
| 5月19日 | 予想外の内閣不信任が成立したことを受け、大平首相は衆議院を解散する。いわゆるハプニング解散。 |
| 6月12日 | 大平正芳首相が急死。現職首相の死は、犬養毅暗殺以来48年ぶりの事態。 |
| 6月22日 | 初の衆参同日選挙。きっかけを作った社会党にとって予想外の自民党が大勝する。いわゆるハプニング解散。なお選挙期間中に大平首相は亡くなったため、当選しなかった唯一の現職首相となった。 |
| 8月 2日 | 午前10時25分頃、イタリア・ボローニャのボローニャ中央駅が爆破される。待合室のあった駅舎が崩壊。85名が死亡、200人以上が重軽傷を負う。当初は事故とみられたが、遺留物から爆破テロと判明。極左テロ組織「赤い旅団」とネオファシストの「武装革命中核(NAR)」が犯行声明を出す。NARはその後犯行を否定するも、NARによる犯行と断定された。フリーメイソンのロッジP2が関与したとも言われる。 |
| 8月14日 | 富士山大規模落石事故。午後2時前、山頂の久須志岳で大規模な崩落が起こり、多数の巨石が落下。吉田砂走にあった下山道の八合目付近と七合目の下で下山客多数が巻き込まれる。死者12人、重軽傷者29人。砂走の下山道は整備されたものではなく、砂地で歩きやすいために自然にできたものだが、落石に遭う可能性も高く、被害を大きくする結果となった。 |
| 8月16日 | 静岡駅前地下街爆発事故。静岡第一ビルの地下にあった寿司店で、湧水処理槽で発生したメタンガスが小規模の爆発を起こし、その影響で都市ガスのガス管が破損。調査に来た消防士がガス漏れに気づくも手遅れで、直後に大規模なガス爆発が発生。死者15人、重軽傷者223人を出し、同ビルを始め、周囲のビルに大きな損害を与える大惨事となる。 |
| 8月19日 | 新宿西口バス放火事件。新宿駅西口バスターミナル20番のりばに停車中の京王帝都電鉄のバスに、元建設作業員の男がガソリンと火の付いた新聞紙を投げ込んで放火。乗客6人が焼死、14人が重軽傷を負う。新聞が遺体の写真を掲載する一方、京王帝都電鉄が被害者の治療費を立て替えたり、政府が犠牲者の労災を認めるなどの救済の動きもあった。犯人は裁判で心神耗弱により無期懲役となったが、1997年に刑務所内で自殺。 |
| 8月19日 | サウジアラビア航空163便火災事故。パキスタンのカラチ発、サウジアラビア・リヤド経由、ジッダ行きのサウジアラビア航空163便トライスターL1011-200型機が、リヤド空港を離陸直後、貨物室で火災を起こし、引き返して緊急着陸に成功するが、機長が緊急脱出を指示しなかったことと、空港の救助隊が非常ドアの解錠に時間がかかったため、内部に入ったときは乗員乗客301名全員が死亡していた。死因は火災で発生した有毒ガスと酸欠によるもの。機長以下乗員の対応に問題があった。火災の原因は不明。 |
| 10月 1日 | アメリカとイギリスが、ソ連の暗号を解読して情報を入手するヴェノナ計画を終了する。 |
| 10月10日 | 北朝鮮指導者の金日成主席が、第6次朝鮮労働党大会で、韓国に対して南北統一案「高麗民主連邦共和国構想」を提唱。 |
| 10月16日 | 中国、最後の大気圏内核実験を実施。以降は地下核実験のみとなる。 |
| 12月 8日 | ジョン・レノンがマーク・チャップマンに射殺される。 |
| 12月13日 | 徳島ラジオ商殺人事件の再審が決定する。 |
| 12月16日 | ケンタッキーフライドチキンの創設者カーネル・サンダースことハーランド・デーヴィッド・サンダースが死去。フランチャイズチェーンのビジネスモデルを初めて導入した人物といわれる。カーネルは本名ではなく、ケンタッキー州に貢献した人物に贈られる称号「ケンタッキー名誉大佐」から。 |
| 12月26日 | 逗子開成高等学校山岳部の生徒5名と引率の教師が、長野県白馬村の八方尾根に登山に行き遭難。6名全員が死亡。学校の許可をとってなかったことから、学校側が賠償金支払いを拒否し、裁判沙汰に発展する。のち、同校出身の徳間書店社長徳間康快が乗り出し、和解が成立。 |
| 12月27日 | 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法制定。昭和60年度までに経営改善計画を進めることを主眼とした法律。これに基づき廃止・バス転換対象の特定地方交通線(赤字路線)を決定した。 |
| 1981年(昭和56年) | |
| 1月20日 | イランのアメリカ大使館人質事件で、人質が444日ぶりに解放される。 |
| 1月23日 | 1月11日からこの日までに佐渡で野生のトキ5羽を捕獲。 |
| 3月30日 | ワシントンD.Cでレーガン米大統領暗殺未遂事件が起こる。大統領と補佐官、警察官、シークレットサービスが重症を負う。女優ジョディ・フォスターのストーカーをしていたジョン・ヒンクリーが、彼女に認めてもらおうとして起こした事件。 |
| 5月23日 | 中国陝西省で野生のトキ7羽が発見される。 |
| 6月 7日 | イスラエル軍によりイラクで建設中の通称「オシラク原子炉」(タムーズ1原子炉)が爆撃される。バビロン作戦。核兵器開発を懸念したイスラエルが、自衛として行ったもので、爆弾を搭載したF-16戦闘機8機と護衛のF-15戦闘機6機が、ヨルダン、サウジアラビアの国境沿いを侵犯しながらイラクに侵入。建設中の原子炉に14発を命中させて完全破壊した。兵士10人とフランス人技術者1人が死亡。領空侵犯も含め国際問題に発展。 |
| 6月17日 | 深川通り魔殺人事件。東京都江東区森下で、覚醒剤中毒の元寿司店員が、解雇や不採用になった事に対して逆恨みし、通行人の女性や子供らを包丁で襲い4人が死亡、3人が重軽傷を負う。裁判では心神耗弱として無期懲役。 |
| 7月17日 | アメリカミズーリ州カンザスシティのホテルハイアットリージェンシー・カンザスシティの吹き抜けロビーで、ダンスコンテストの最中に2階と4階のスカイウォークが約60人の見物客とともに、1階ロビーの大勢の見物客の上に落下。死者114人、重軽傷者216人の大惨事となる。設計ミスによる強度不十分が原因。 |
| 7月30日 | セネガルとガンビアが国家連合を成立し、セネガンビア国家連合となる。国政は統合し、主権はそれぞれが持つ形態となる。 |
| 8月 6日 | 香川県仁尾町(現三豊市)に電源開発の太陽熱発電所が作られ、実用化を検証する実験が開始される。 |
| 8月12日 | 現在のパソコンの系統につながるPC/AT互換機の元祖IBM Personal Computer 5150が発売される。 |
| 8月19日 | シドラ湾事件。リビアが領海を主張しているシドラ湾北方の地中海で、アメリカ海軍が演習中、リビア空軍のSu-22戦闘爆撃機2機が接近。米海軍のF-14戦闘機と空中戦となり、Su-22が撃墜される。その後、リビア空軍のMiG-25戦闘機2機が米艦隊に接近したが、引き換えしたため交戦にはならなかった。 |
| 8月28日 | アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が同性愛者の間で広がる病気を公表。1983年に後天性免疫不全症候群(AIDS)と名付けられる。ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による難病の発見。なお、これは発見したことの公表で、実際には1950年代から似たような病気が見つかっていることから、徐々にアフリカで広がっていた可能性もある。 |
| 9月21日 | 中米ユカタン半島にある英領ホンジュラスが独立し、ベリーズとなる。 |
| 10月 6日 | エジプト大統領サーダートが第四次中東戦争開戦日の戦勝記念日パレードを観閲中に、ジハード団のハリド・イスランブリ中尉によって暗殺される。 |
| 10月16日 | 北炭夕張新炭鉱ガス突出事故。北海道炭礦汽船の関連会社北炭夕張炭鉱の経営する夕張新炭鉱鉱内でメタンガスが突出。更に救助作業中に引火爆発し、死者93名を出す。斜陽化していた石炭業界の立て直しのため、安全性を軽視して増産を図った結果の事故。この影響で北炭夕張炭鉱は経営破綻。石炭採掘業界へ致命的なダメージとなった。 |
| 10月23日 | 新潮社から初めての写真週刊誌「フォーカス」が創刊される。創刊当初は芸術や社会性を主体にしていたがすぐに大衆化する。また各出版社から似たような写真週刊誌が発売されるが、いずれもエロ・スキャンダルなどより低俗な雑誌となる。 |
| 10月27日 | ウィスキー・オン・ザ・ロック事件。ソ連のウィスキー級潜水艦が、操船ミスでスウェーデンの領海にはいり込み座礁した事件。 |
| 11月13日 | 山階鳥類研究所が、沖縄本島北部の山間部やんばるで、アガチと呼ばれていた鳥が、新種であることを発見。ヤンバルクイナと名付ける。 |
| 12月11日 | 防衛庁が、新型南極観測船(砕氷艦)の進水命名式で「しらせ」と命名。日本では軍艦名には、基本的に人名を使わないため、南極の白瀬氷河から採用したが、同氷河は日本初の南極探検を行った白瀬矗の功績を賞して付けられており、艦名公募でも上位候補には入ってない同名をあえて選んでいる。 |
| 12月17日 | アルバニアのメフメット・シェフー首相が不審死を遂げる。公式には自殺とされているが、独裁者ホッジャと対立して謀殺されたという見方もある。妻子も投獄された。 |
| 12月21日 | 気象衛星ひまわりが、2号機にバトンタッチ。 |
| 1982年(昭和57年) | |
| 2月 7日 | 大阪市西成区で覚醒剤中毒者によって7人が殺傷される事件が起きる。覚醒剤常習による中毒から被害妄想を起こし、妻を殺害し子供に重症を負わせたあと、次々と近隣住民を襲って3名を殺害し2名に重症を負わせる。裁判では心神耗弱により無期懲役。 |
| 2月 8日 | ホテルニュージャパン火災が起こる。利益主義のための安全対策のカットによる不備から火に巻かれた宿泊客33人が死亡する(20人が中毒や焼死。13人が飛び降りて死亡)。 |
| 2月 9日 | 日本航空機350便墜落事故。羽田空港着陸寸前の旅客機が、統合失調症の機長の逆噴射操作によって墜落。乗客24名が死亡。乗員乗客149名が重軽傷を負う。 |
| 3月10日 | 惑星直列。全ての惑星が太陽から見て95度以内に入る。各惑星の重力の影響で大異変が起こるなどの噂が広まる。しかし実際には何も起こらず。 |
| 3月19日 | フォークランド戦争勃発。イギリス領フォークランド諸島沖合のイギリス領サウスジョージア島に、アルゼンチン海軍輸送艦が寄航し、一方的に民間人60人を上陸させる。イギリスは反発し、巡視船とヘリ2機を派遣。上陸民間人に退去を命じると同時にアメリカに仲介を要請。アルゼンチンの軍事政権が、国民の支持率回復を狙って同諸島の領有権問題を煽った結果、後に引けなくなったためとされる。チリを除く南米諸国・東側諸国・非同盟諸国の多くはアルゼンチンを支持。アルゼンチンと険悪だったチリと欧米諸国はイギリスを支持。 |
| 3月26日 | アルゼンチン海軍砕氷艦が海兵隊員500人を載せ、サウスジョージア島に到着。 |
| 3月30日 | アルゼンチン政府は、空母1隻を含む15隻の艦隊をフォークランド諸島へ向けて出撃させる。 |
| 4月 1日 | 同日夜、アルゼンチン艦隊に乗っていた陸軍兵4000人がフォークランド諸島に順次上陸を開始。 |
| 4月 2日 | アルゼンチン軍がフォークランド諸島を制圧し、圧倒的兵力差を受け、同諸島のイギリス軍が降伏。アルゼンチン軍はサウスジョージア島へも本格的に侵攻を開始。同島のイギリス軍との間で激しい戦闘となるも、2時間で終結。イギリス軍は降伏。イギリス政府はアルゼンチン政府と国交を断絶。イギリス下院は艦隊派遣を決定。 |
| 4月 5日 | 空母2隻を含む49隻のイギリス海軍艦隊が出港。長距離戦略爆撃機も出撃。両国は外交交渉に乗り出す。 |
| 4月12日 | イギリス海軍による海上封鎖が始まる。 |
| 4月20日 | 八王子市の歯科医院で来院した女児に、歯のう蝕予防のフッ化ナトリウムを塗布しようとして猛毒のフッ化水素酸を塗布し女児は間もなく死亡する事件が起こる。歯科医師の歯科材料業者への誤発注と誤認が原因。 |
| 4月25日 | イギリス軍がアルゼンチン海軍潜水艦サンタフェを攻撃し同艦はサウスジョージア島に擱座。イギリス軍はサウスジョージア島に上陸し同島を奪還し同島のアルゼンチン守備隊は降伏。 |
| 5月 1日 | イギリス軍がブラックバック作戦を発動。アセンション島から飛び立った長距離爆撃機がフォークランド諸島を空爆。ついで空母艦載機が空爆を実施。更に沖合から艦砲射撃を行う。また両国の戦闘機によって夜間空中戦も行われる。一方、アルゼンチン艦隊によるイギリス艦隊への航空攻撃計画は、空母べインディシンコ・デ・マヨの機関不調などで運用が出来ず中止となる。 |
| 5月 2日 | イギリス海軍原子力潜水艦コンカラーが、アルゼンチン海軍巡洋艦へネラル・ベルグラノを撃沈。 |
| 5月 2日 | エクソンはコロラド州で進めていた大規模なオイルシェール計画を中止。石油との競合の影響による。オイルシェールが再び脚光を浴びるのは21世紀に入ってから。 |
| 5月 4日 | アルゼンチン海軍航空隊のシュペール・エタンダール攻撃機2機がエグゾセミサイルを発射し、イギリス海軍駆逐艦シェフィールドに命中。爆発はしなかったものの火災が発生し同艦は5月10日に沈没。 |
| 5月10日 | イギリス海軍フリゲート艦アラクリティが、アルゼンチン海軍輸送艦イスラ・デ・ロス・エスタドスを砲撃して撃沈。 |
| 5月12日 | アルゼンチン海軍のスカイホーク戦闘爆撃機がイギリス海軍駆逐艦グラスゴーを爆撃し命中するも不発。 |
| 5月14日 | イギリス軍がペブル島へ上陸し同島飛行場のアルゼンチン軍航空機11機をすべて破壊し撤退。 |
| 5月16日 | アルゼンチン海軍輸送艦バイア・ブエン・スセソがイギリス軍のシーハリアー攻撃機によって撃沈される。 |
| 5月21日 | イギリス軍が東フォークランド島西側に上陸。同日、アルゼンチン軍の反撃で、イギリス海軍フリゲート艦アーデントが撃沈され、複数の艦艇にも被害が出る。 |
| 5月23日 | アルゼンチン軍の攻撃により、イギリス海軍フリゲート艦アンテロープが爆沈。 |
| 5月25日 | アルゼンチン軍の攻撃により、イギリス海軍駆逐艦コヴェントリーが撃沈される。またエグゾセミサイルが命中したイギリス側コンテナ船アトランティック・コンベイヤーが沈没し、大量の兵器と軍需物資を喪失する。 |
| 5月26日 | イギリス陸軍部隊が東フォークランド島制圧のため侵攻を開始。 |
| 5月28日 | イギリス陸軍部隊とアルゼンチン陸軍部隊が、グース・グリーンで交戦。アルゼンチン軍の兵士ら250人以上が戦死し、同軍は降伏。イギリス側も指揮官ら17人が戦死する。 |
| 5月30日 | イギリス・アルゼンチン両軍のコマンド部隊が、ケント山で交戦。 |
| 6月 8日 | イギリス海軍は、フィッツロイへ揚陸作戦を実施。アルゼンチン軍の反撃で揚陸艦サー・ガラハドが撃沈され、揚陸艦サー・トリストラムも大破。多数の戦死者を出す。フリゲート艦プリマスも爆撃を受け大破。 |
| 6月12日 | アルゼンチン軍の陸上から発射されたエグゾセミサイルがイギリス海軍駆逐艦グラモーガンに命中し、同艦は中破。 |
| 6月13日 | イギリス陸軍・海兵隊が、フォークランド諸島の中心都市ポート・スタンレーへの総攻撃を開始。一部で激しい交戦となる。 |
| 6月14日 | ポート・スタンレーのアルゼンチン軍守備隊が降伏。 |
| 6月15日 | アルゼンチンのガルチェリ大統領が戦闘終結宣言を出す。 |
| 6月17日 | アルゼンチンのガルチェリ大統領が失脚。退役中将レイナルド・ビニョーネが後を受け継ぐも、軍事政権への支持を回復することは出来ず。 |
| 6月17日 | ロンドンのテームズ川にかかるブラックフライアーズ橋の塗装工事用足場で首吊り死体が発見される。死亡していたのはイタリアのアンブロシアーノ銀行の頭取だったロベルト・カルヴィで、同銀行はバチカンの宗教事業協会(通称バチカン銀行)の資金管理を担当しており、そこを経由してマフィアのマネーロンダリングに関わっていた人物。ヨハネ・パウロ1世の「暗殺」に関与した疑惑もあった。発見場所が自力で自殺しにくいことから、マフィアによる暗殺と考えられている。 |
| 6月20日 | イギリス軍がサウス・サンドイッチ諸島を奪還。フォークランド戦争は終結。 |
| 6月21日 | レーガン大統領暗殺未遂事件を起こしたジョン・ヒンクリーに、精神異常を理由として無罪判決が出される。ヒンクリーは、病院に収容。精神異常者の犯罪に対する免罪の廃止を求める動きがアメリカ全土に広がる。 |
| 6月24日 | ブリティッシュ・エアウェイズ9便事故。ロンドン・ヒースロー空港発でインド・マレーシア・オーストラリア経由、ニュージーランド・オークランド空港行のブリティッシュ・エアウェイズ9便ボーイング747型が、ジャワ島の上空を飛行中、異常な現象に遭遇して4つのエンジンがすべて停止する事態となる。滑空して高度3000m近くまで下がったところでエンジン再始動に成功し、ジャカルタのハリム・ペルダナクスマ国際空港に緊急着陸した。事故の原因は大噴火したガルングン山の噴煙に夜間で気づかず突入してしまい、エンジンが大量の火山灰を吸い込んだため。 |
| 6月28日 | アエロフロート8641便墜落事故。ロシア・サンクトペテルブルクのプルコヴォ空港発、ウクライナ・キーウのジュリャーヌィ空港行Yak-42型機がベラルーシのマズィル付近で、降下中に操縦不能となり急降下空中分解。乗員乗客132人全員死亡。構造欠陥によるスクリュージャッキの破損が原因。Yak-42は設計変更まで全機運行停止となった。 |
| 8月19日 | ソ連の女性宇宙飛行士スベトラーナ・サビツカヤが、ソユーズT-7で宇宙へ出る。 |
| 8月30日 | 世界中で採用されたF-5戦闘機の改良型F-5Gが初飛行。元々台湾向けに計画されたが中国との関係悪化を考慮して中止になりノースロップ社が輸出用に独自に開発。F-20タイガーシャークと改称した。性能は高かったが、ライバル機でアメリカ空軍が採用していたF-16が輸出解禁となり大量生産でコストダウンしたためにそちらを採用する国が相次ぎ、3機生産されただけに終わった。日本では人気漫画「エリア88」の主人公が乗る機体として知名度が高い。 |
| 9月 1日 | アメリカ空軍内に宇宙軍団(スペースコマンドー)が設置される。 |
| 9月 2日 | 国鉄が研究中の浮上式リニアモーターカーが、宮崎実験線で有人走行に成功する。 |
| 9月12日 | スパイ粛清事件。新右翼による内ゲバ殺人事件。統一戦線義勇軍の書記長だった高橋哲夫(見沢知廉)らが、右翼団体の結成に関わっていたメンバーの一人を公安のスパイと決めつけ、他のメンバーと集団でリンチ。絞殺した上で富士の青木ヶ原樹海に埋める。その後埋める場所を変えるが、事件に関与したメンバーの出頭で事件が判明。 |
| 11月 2日 | 千葉県佐倉市のニュータウン、ユーカリが丘に、山万ユーカリが丘線が開業。新交通システム。 |
| 11月 7日 | 世界屈指の陶磁器コレクションである安宅コレクションを収蔵するため、大阪市立東洋陶磁美術館が設立される。 |
| 12月18日 | ナチスドイツ時代のエースパイロットで英雄だったハンス・ウルリッヒ・ルーデルが死去。葬儀には軍の戦闘機が飛行し、軍関係者やネオナチも参列する騒ぎとなった。 |
| 12月 | 人気を誇ったゲーム機アタリ2600のクリスマス商戦が大失敗に終わる。いわゆるアタリショック。 |
| 1983年(昭和58年) | |
| 1月 8日 | アメリカ・ニュージャージー州ニューアークにあるテキサコの燃料貯蔵施設で、燃料タンクが相次いで爆発。1人が死亡、22人が負傷。原因は過剰充填したことによる人為ミス。爆風はニューヨーク市などにも到達した。 |
| 1月19日 | アップルLisa発売。はじめてGUI環境を持った一般向けパソコン。1万ドルもしたため、商業的には失敗に終わる。 |
| 3月 7日 | 赤坂プリンスホテル新館開業。 |
| 4月 4日 | NHK連続テレビ小説『おしん』が放送開始。 |
| 5月 1日 | イスラエルのネゲブ砂漠で、訓練中のイスラエル空軍のF-15D戦闘機と、A-4N攻撃機が空中衝突。A-4Nのパイロットは脱出。一方F-15Dは右翼の殆どを失って制御不能に陥ったが、アフターバーナーで増速したことにより回復。墜落せずに、約15km離れたラモン基地への帰投に成功。航空機が片翼をほぼ全損しながら墜落せずに着陸できた稀有の例。 |
| 5月26日 | 日本海中部地震発生。マグニチュードは7.7。死者104人。うち津波での死者が100人に達する。 |
| 6月 7日 | 四街道市にある成田空港パイプライン建設用の作業員宿舎が左翼テログループの中核派に放火され、2人が死亡。 |
| 6月13日 | パイオニア10号、海王星軌道を横断。太陽系外縁へと向かう。 |
| 7月 7日 | アメリカ人少女サマンサ・スミスがアメリカ史上最年少の親善大使としてソ連を訪問。きっかけは彼女がアンドロポフ書記長に米ソ戦争の可能性についての疑問をしたためた手紙を送ったことから。 |
| 7月 8日 | 連続射殺事件犯永山則夫の第1次上告審判決で、死刑にする場合の基準として「永山基準」が示される。 |
| 7月15日 | 任天堂が家庭用ゲーム機ファミリーコンピュータを発売。価格は14800円。 |
| 7月23日 | 映画『南極物語』公開。タロとジロの生存を描いたドラマに、880万人を動員するヒットとなる。 |
| 8月21日 | フィリピンの反体制政治家ベニグノ・アキノ・ジュニアが、アメリカから帰国したマニラ空港で暗殺される。 |
| 9月26日 | ソビエトのバイコヌール宇宙基地で、有人宇宙船ソユーズT-10-1を搭載したロケットが発射直前に火災を起こす。ロケットが爆発する直前に緊急脱出システムが作動し、宇宙船は分離発射され、4km先に着陸。乗員2名は脱出に成功する。脱出システムが成功したはじめての例。 |
| 10月 3日 | 三宅島の各所で噴火が発生。多数の割れ目火口から噴火し溶岩が流出。阿古地区集落の7割が溶岩に飲み込まれる。家屋や学校など400棟あまりが焼失・溶岩に埋没したが、人的被害はなく、溶岩流出も翌4日にほぼ止まった。 |
| 10月 9日 | ラングーン事件。ビルマ(現ミャンマー)の首都ラングーン(現ヤンゴン)にあるアウンサン廟で、同国訪問中の韓国大統領全斗煥らの暗殺を狙って、爆弾が炸裂。先行して到着していた韓国閣僚ら17名とビルマ政府関係者4名が爆死。47名が負傷する大惨事となる。全斗煥大統領は直後に到着して無事だったが各国歴訪は中止となった。ビルマ政府が逮捕した北朝鮮工作員2名の公開裁判で、射殺した1名を含む3名の工作員によるテロと判明。ビルマ政府は建国の父の廟をテロの舞台にされたこともあって激怒、北朝鮮との国交を断絶し、国家承認も取り消す。北朝鮮政府が、ソウルオリンピック阻止を狙って引き起こしたものだったが、事件に反発した各国はソウルオリンピック参加を表明する結果となった。 |
| 11月14日 | 3代目の南極観測船「しらせ」が観測隊派遣に就役。 |
| 11月15日 | キプロスのトルコ側支配地域であるキプロス連邦トルコ人共和国が、北キプロス・トルコ共和国として独立を宣言。ただし承認したのはトルコ1国のみ。国連加盟国193カ国のうち、キプロスを承認している国はトルコ以外の192カ国に及び、国際的にはキプロス島の正統政府はキプロス共和国となっている。北キプロスはキプロス共和国に対し、ギリシャ系とトルコ系の対等な合併を提案しているが、キプロス側は分裂以前の体制に戻すことを主張している。 |
| 12月10日 | アルゼンチンの大統領選挙で、急進党のラウル・アルフォンシンが当選。軍事政権が終わり民政移管する。 |
| 1984年(昭和59年) | |
| 2月 1日 | 国鉄ダイヤ改正。全国で貨物輸送の大幅整理が行われ、操車場の多くがこの時点で廃止となった。またこの影響で、貨物輸送を主体としていた兵庫県加古川市の別府鉄道全線が廃止となった。 |
| 2月12日 | 世界的冒険家、植村直己がマッキンリー(デナリ)の冬季単独登頂に成功。 |
| 2月13日 | 植村直己との交信が、この日を最後に途絶える。現在命日とされている日。 |
| 3月14日 | 朝日新聞が、報徳会宇都宮病院で前年に患者2名が職員によって暴行を受け殺されていたことを報道。また同病院では日常的に虐待、違法な診療、無許可の遺体解剖などが頻発しており、それを関係の深い東大医学部関係者も知っていながら黙っていたことが判明。のちに院長と職員らは実刑判決を受けた。また、この実態が報道で広まり、さらに世界へと伝えられたため、人権問題に発展。精神保健福祉法成立へとつながる。 |
| 3月22日 | アメリカでマクマーティン事件の訴えが起こされる。カリフォルニアのマクマーティン保育園で児童虐待が行われていると児童の母親が関係者を訴えたもので、一時はマスコミが扇動的に報道し、国際児童研究所が調査し事実と証言したため、全米中を巻き込む騒動に発展した。しかし、訴えた女性のアルコール中毒や調査した人物が専門家でなく誘導尋問していたことが明らかになり、結局虐待はなかったことが判明。モラル・パニックが引き起こした一大冤罪事件となった。 |
| 6月 1日 | 通信・電話事業自由化を睨んで、京セラやソニーなどによるマイクロ波中継長距離通信の第二電電(DDI)が設立される。 |
| 4月 1日 | 西日本相互銀行と高千穂相互銀行が統合して、普通銀行に転換し、西日本銀行が設立される。西日本相銀は戦時統合で出来た西日本無尽を前身とし、高千穂相銀は宮崎県高千穂町の高千穂無尽を元としているが、高千穂相銀の経営困難に伴い政府主導での統合計画となった。規模の大きな西日本相銀が普通銀行になることについて全国相互銀行協会の反発を買ったほか、九州全域に支店を持つ相銀だったため、各地銀への影響を懸念して全国地方銀行協会からも難色を示されるなど紆余曲折を経ての設立となった。後の第二地銀転換の先例ともされる。 |
| 6月 6日 | ソ連の科学者アレクセイ・パジトノフがテトリスを開発。落ち物パズルの元祖。 |
| 6月22日 | ヴァージン・アトランティック航空の運航が開始される。 |
| 7月 1日 | ウィリアム・ギブスンの小説『ニューロマンサー』が発売。サイバーパンクを代表する作品でスプロール三部作の第一作。 |
| 7月12日 | 島根県斐川町の荒神谷遺跡と呼ばれる弥生時代の遺跡から、銅剣358本がまとまって発見される。それまでに発掘された銅剣の総本数よりも多い数。 |
| 7月25日 | ソ連の女性宇宙飛行士スベトラーナ・サビツカヤが宇宙船の外に3時間35分滞在し、女性として初めて宇宙遊泳を行う。 |
| 9月14日 | 長野県西部地震。マグニチュード6.8。御嶽山の南斜面で大規模な山体崩壊が発生し、15人が死亡。 |
| 10月 1日 | 国鉄の鉄道電話を母体に三井・三菱・住友などによって日本テレコムが設立される。 |
| 11月11日 | 菊花賞でシンボリルドルフが中央競馬史上初の無敗でのクラシック三冠を達成。 |
| 11月16日 | 高速道路の通信網を母体に道路施設協会とトヨタによって日本高速通信が設立される。 |
| 11月19日 | メキシコのメキシコシティ郊外メヒコ州トラルネパントラ・デ・バス市のサン・フアン・イスアテペクにあるペメックスの液化石油ガス貯蔵施設で大規模な爆発が発生。ガス輸送パイプからガスが漏出し、なにかの原因で引火。沸騰液膨脹蒸気爆発を引き起こし、15個の大型貯蔵タンクが次々と爆発。500人以上が死亡し5000人以上が重症を負う大惨事となる。 |
| 12月 8日 | ロケット技術者ウラジーミル・チェロメイ死去。ソ連の大陸間弾道ミサイルや有人月飛行計画を推奨し、後に宇宙ステーション建設や補給に使われることになったプロトンロケットの技術開発にあたった人物。 |
| 12月19日 | 性風俗の特殊浴場「トルコ風呂」がトルコ政府の抗議により「ソープランド」と改称。 |
| 12月25日 | 通信・電話事業の自由化のため、公衆電気通信法は電気通信事業法に改正。 |
| 1985年(昭和60年) | |
| 1月18日 | 元リトアニア・カウナス日本領事代理で、大勢のユダヤ人を救った杉原千畝に対し、イスラエル政府から、「諸国民の中の正義の人」としてヤド・バシェム賞が贈られる。杉原自身は病床にあったため、4男がイスラエルの式典に出席。 |
| 2月 5日 | 和光大学で革マル派メンバーが、中核派を襲撃。両派に多数の負傷者を出す。事件の1時間から1時間40分後に逃走したメンバー3人が相次いで見つかり警察に逮捕され所持品も押収されたが、時間が経ち、場所も離れたところでの逮捕と押収が、準現行犯逮捕として違法かどうかが裁判で争われた。 |
| 2月19日 | 中華航空006便事故。台湾の台北発、アメリカ・ロサンゼルス行中華航空006便ボーイング747SPが、サンフランシスコ北西300海里の高度12500mを飛行中、第4エンジンが停止し機体が傾いたため、自動操縦を解除したところ、速度低下により失速。機体は逆さになった状態で高速急降下したが、海面激突40秒前に機体の破損で降着装置が降りたことで減速、高度2900mで機体の立て直しに成功した。2人が重傷、50人余りが軽症を負った。エンジン停止は人的ミス。 |
| 4月 1日 | 日本電信電話公社が民営化され、NTTが発足。 |
| 4月11日 | アルバニアの独裁者で労働党第一書記のエンヴェル・ホッジャが死去。自らこそ正当なマルクス・レーニン主義者だとして、ソ連や中国など世界中の共産党政府を修正主義と非難。周辺国との領土問題もあり、あらゆる国との国交を断絶して完全な鎖国体制を築いた。一方で世界中の左派勢力とは交流し、それらはホッジャ主義と呼ばれた。遺言に基づき、その葬儀も各国政府からの弔問を拒否、弔電すら受け取らなかったという。 |
| 6月 6日 | 島根県荒神谷遺跡出土品が国宝に指定される。 |
| 6月18日 | 金の売買をめぐる豊田商事事件で、同社の永野一男会長がマスコミの見ている中で、自称右翼の男二人によって刺殺される。 |
| 6月27日 | アメリカ・ニューメキシコ州ホワイトサンズミサイル実験場で、核爆発が兵器などに及ぼす影響を調べるマイナースケールテストが行われる。TNT換算で4.2kt相当のアンホ爆薬を使用。西側諸国で「非核通常爆薬」による最大の爆発と言われる。 |
| 7月 9日 | 徳島ラジオ商殺人事件の再審で無罪判決。 |
| 8月 2日 | アメリカ・テキサス州ダラスのフォートワース空港で、着陸直前のデルタ航空191便トライスター機がダウンバーストに巻き込まれ滑走路手前に墜落。乗員乗客163名中134名と、事故に巻き込まれた車両の運転手1名が死亡。また、IBM_PCの開発者フィリップ・ドナルド・エストリッジらメンバー多数がこの事故でなくなっている。 |
| 8月 8日 | マカオにあるコロアネ島のハクサ海岸で、少なくとも4人分の人の手足が見つかる。「八仙飯店一家殺害事件」の発覚。人肉饅頭事件として流布したマカオの八仙飯店の経営者一家10人が殺害されバラバラにされた事件。 |
| 8月12日 | 羽田発伊丹行の日本航空123便ボーイング747型旅客機が群馬県と長野県の県境にある高天原山の御巣鷹の尾根に墜落。乗員乗客524人中520人が死亡。単独機では史上最悪の事故(日航機123便事故)。 |
| 8月25日 | バー・ハーバー航空1808便墜落事故。同航空ビーチクラフト99がアメリカ・メイン州のルイストン=オーバーン市営空港への着陸に失敗し空港手前で墜落。アメリカ史上最年少の親善大使となってソ連を訪問したサマンサ・スミスが事故死(享年13歳)したため、マスコミが大きく取り上げる。 |
| 9月13日 | ファミコン用のゲームソフト『スーパーマリオブラザーズ』が発売。 |
| 9月13日 | 米国が、高度555kmにある老朽化した太陽観測衛星ソルウィンドP78-1を、F-15戦闘機から発射した対衛星ミサイルASM135で破壊する実験を行う。大量のスペースデブリが発生。 |
| 9月25日 | 奈良・斑鳩の藤ノ木古墳で石室と家形石棺が発見される。 |
| 10月16日 | 阪神タイガース優勝大騒動。21年ぶりの優勝に興奮したファンが道頓堀に飛び込み、ケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダース像を放り込む事件が起こる。 |
| 10月20日 | 成田空港建設反対現地闘争(10.20現地闘争)が行われる。 |
| 11月 6日 | コロンビア最高裁占拠事件。軍が突入し、翌日までにゲリラ35人全員を殺害。巻き添えで最高裁長官と判事11人、市民60人ら人質115人も死亡。 |
| 11月13日 | コロンビアのアンデス山中にある標高5389mのネバドデルルイス火山の噴火で、大規模な泥流が発生。麓の都市アルメロが飲み込まれ、2万1000人が死亡。 |
| 11月20日 | Microsoft Windows 1.0のリリース。完全なウィンドウ表示ではなく、ウィンドウをタイル状に並べて表示する仕組み。 |
| 11月28日 | 吉田茂のブレーンだった実業家、白洲次郎が死去。 |
| 11月29日 | 国電同時多発ゲリラ事件。極左テロ組織の中核派が首都圏と大阪の国鉄の電車線区施設33ヶ所を同時に破壊し、首都圏で2896本、大阪地区で378本の列車が運休。通勤通学客など600万人以上に影響が出る。国鉄民営化反対に乗っかった事件だったが、皮肉にもこの結果、民営化を支持する動きが加速したと言われる。 |
| 1986年(昭和61年) | |
| 1月14日 | 西船橋駅ホーム転落事件。総武線西船橋駅のホームで女性の乗客に対し泥酔した男性がしつこく絡み、女性が男性を突き飛ばしたところ、男性はホームから転落。泥酔していたため、上がってこれずそのまま電車に轢かれて死亡。女性は傷害致死罪で起訴されたが正当防衛が認められ無罪となった。女性を支援した団体がセクシャル・ハラスメントと言う言葉を最初に使ったと言われる。 |
| 1月28日 | スペースシャトルチャレンジャー号が打ち上げ73秒後に爆発墜落。乗員7名全員が死亡。発射延期の間に凍りついた補助ロケットのゴム製密閉リングが発射の衝撃で破損し、燃焼ガスが吹き出して補助ロケットと外部燃料タンクが爆燃崩壊したのが原因。発射前にその危険性を訴える技術者らの声を無視したために起こった。 |
| 2月 7日 | フィリピン大統領選挙。コラソン・アキノが大差で票を得るが、マルコス大統領は票数を不正操作。 |
| 2月 9日 | ハレー彗星が接近するが、位置関係が悪く地上ではうまく観測できず。各国が観測衛星を打ち上げる。 |
| 2月19日 | ソビエト連邦が宇宙ステーション「ミール」の本体を打ち上げ。 |
| 2月22日 | フィリピン大統領選挙のマルコス大統領による得票不正操作に反発した軍と市民が蜂起。コラソン・アキノが選挙結果に基づき、大統領に選出される。 |
| 3月15日 | シンガポールでホテルニューワールド崩壊事故が発生。市内セラングーンの6階建てのリアンヤックビルが突如、一瞬のうちに崩壊。ニューセラングーンホテル(ホテルニューワールド)などが入居しており、50人が巻き込まれ、33人が死亡。17人が負傷した。原因は強度計算のミス。シンガポールの都市高速鉄道(マス・ラピッド・トランジット)の建設を行っていたイギリス、アイルランド、日本の建設関係者が、地下にトンネルを掘って下から生存者を救出している。 |
| 4月15日 | アメリカ軍によるリビア首都トリポリ爆撃。カダフィ暗殺を図った作戦。暗殺には失敗。 |
| 4月26日 | チェルノブイリ原子力発電所事故。定期保守点検で停止する予定だった4号機で、外部電源喪失時の非常用発電系統の冷却水ポンプへの給電実験中に起こったとされ、制御不能で暴走したのち、大爆発を起こす。14エクサベクレルという大量の放射性物質が拡散。 |
| 4月27日 | スウェーデンのフォルスマルク原子力発電所で、労働者の衣服に放射性物質が付着していることが判明し、フィンランドなどの汚染情報から、チェルノブイリ原子力発電所の事故が発覚する。同日、ソ連政府はチェルノブイリ発電所関係者の住むプリピャチ市に避難命令を出す。住民は3日分の食料と貴重品だけを持って市外へ一時避難。 |
| 5月27日 | ファミコン用ソフトでドラゴンクエスト第1作が発売。 |
| 5月 2日 | ソ連政府、チェルノブイリ原子力発電所周辺30km圏内住民の避難を決定。6日までに13万5千人が避難。プリピャチ市は完全に無人化し、住民の多くは東に約50km離れた地に作られた都市スラブチッチに移住。南方にあるチョルノーブィリ市も住民はほぼ退去したが、高齢者などが残っている。 |
| 7月31日 | 元リトアニア・カウナス日本領事代理の杉原千畝が死去。 |
| 8月21日 | カメルーンの北西にあるオク火山の火口湖ニオス湖で二酸化炭素飽和による湖面爆発が起こり、160万tもの二酸化炭素が麓へ流れ、住民1746人と家畜3500頭が二酸化炭素中毒もしくは窒息により死亡。 |
| 8月31日 | ロサンゼルス国際空港で、着陸中だったアエロメヒコ航空498便DC-9型機に、トーランス空港を離陸した自家用機パイパーPA-28が空中衝突。旅客機の水平尾翼に激突したため、パイパー機のコックピットが吹き飛び、操縦士と乗客2人は首を切断して死亡。機体はセリトス小学校に墜落。旅客機は水平尾翼全てと垂直尾翼の殆どを失って制御不能に陥り、逆さになってセリトス市の住宅地に激突。こちらも乗員乗客64人全員が死亡し、住宅などにいた15人も死亡、8人が負傷した。自家用機が航空管制の許可を得ずにターミナル・コントロール・エリアに侵入したのが主な原因。 |
| 10月 3日 | ソ連の原子力潜水艦K-219がバミューダの沖合でミサイルサイロの火災爆発事故を起こし緊急浮上。貨物船による曳航計画を立てるも被害が大きく失敗に終わり、艦長は上層部の命令に反して乗員を退艦させて曳航船に移し、同艦は核ミサイルを積んだまま沈没する。爆発で3名が死亡、原子炉緊急停止作業を行った1名も被曝して死亡、後に2名も死亡した。 |
| 10月31日 | 最初の新橋駅だった汐留貨物駅が廃止される。オフィス街に再開発へ。 |
| 11月15日 | 伊豆大島の三原山で噴火が始まる。溶岩の流出も伴う大規模噴火へ発展。 |
| 11月21日 | 三原山の各所で割れ目噴火が始まり、溶岩噴泉が多数発生。全島民が一時島を脱出することが決定する。割れ目噴火はまもなく沈静化。 |
| 11月23日 | 桜島古里地区のホテルに直径約2m、重量約5トンの噴石が直撃、宿泊客と従業員の合わせて6名が負傷。 |
| 11月26日 | 成田空港の第二期工事が始まる。 |
| 12月28日 | 山陰線余部鉄橋列車転落事故。突風に煽られ車両が落下。下の水産加工工場を押しつぶし、車掌と従業員5名が死亡。 |
| 1987年(昭和62年) | |
| 1月20日 | ズ・ダン号事件。老朽化した船に乗った北朝鮮からの脱北者が日本に漂着。北朝鮮は故障による漂流と説明するが、乗っていた金萬鉄らは亡命を主張。身柄引き渡しをめぐって、朝鮮総連と韓国民団が対立。 |
| 2月 3日 | 高松宮宣仁親王が肺がんのため死去。昭和天皇の弟。海軍軍人で太平洋戦争開戦に反対し、戦時中は戦争終結を唱えて有力軍人、政治家らと終戦工作を進めた。『高松宮日記』は昭和期の貴重な史料。 |
| 2月 8日 | ズ・ダン号事件で亡命を求めていた金満鉄らが、日本政府によって密かに出国。沖縄を経由して台湾へ亡命。すぐに韓国の手配した特別機で韓国へ亡命する。 |
| 2月23日 | 大マゼラン星雲167,800光年の距離にある超新星SN1987Aが出現。カミオカンデなど3箇所の施設でニュートリノが観測され、ニュートリノ天文学が誕生。三重連星サンデュリーク-69°202の1つである青色超巨星が爆発したことが判明している。 |
| 3月 9日 | 超音速戦闘機三菱F-1の77号機が納入されて生産は終了。 |
| 3月 9日 | トヨタなどが日本移動通信(IDO)を設立。 |
| 3月14日 | 南氷洋での日本の商業捕鯨が終了。船団が帰国。 |
| 3月20日 | ウイスキーキャット・タウザー亡くなる。スコットランドのグレンタレット蒸留所で飼われていたメスのネコで、わかっているだけでもネズミ2万8899匹を捕った猫としてギネス記録をもつ。 |
| 3月30日 | 初期の原子力潜水艦シーウルフ(SSN-575)が退役。 |
| 3月30日 | 水俣病第三次訴訟で、熊本地裁がはじめて国や県の責任を認める判決を出す。 |
| 3月31日 | 国鉄が廃止され、JRグループ各社が発足。資産売却のため、日本国有鉄道清算事業団が設立される。 |
| 4月 1日 | 岐阜県徳山村が、徳山ダムによって全村水没することとなったため、藤橋村に吸収合併される。住民は2001年までに全て離村。 |
| 5月 3日 | 赤報隊事件。兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局を散弾銃を持った男が襲撃。記者1名が死亡。1名が重傷を負う。 |
| 5月 9日 | ワルシャワ発ニューヨーク行のポーランド航空5055便イリューシン62がエンジントラブルでワルシャワ郊外に墜落。乗員乗客183名全員が死亡。トラブル後、軍用空港への緊急着陸を拒否され、ワルシャワ空港へ戻る途中燃料漏洩と見られる火災となり高速で地上に激突したとみられる。機体の欠陥と老朽化が原因とされるが、ソ連政府はこれを認めず、パイロットの操縦ミスとしたため、ポーランド側と対立した。 |
| 5月10日 | 帝銀事件で犯人とされた平沢貞通が死去。 |
| 5月19日 | 女性SF作家ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア(アリス・ブラッドリー・シェルドン)が、認知症の夫を同意の上で射殺し、自らも自殺。その男性風のペンネームと軍歴や学歴、公に姿を見せなかったことから長いこと男性だと思われていた。ジェンダーに関する作品も多い。 |
| 5月28日 | ルスト事件。西ドイツに住む19歳の青年マチアス・ルストが、セスナ172Bを操縦して、フィンランドからソビエト領内へ侵入。そのまま飛行し、モスクワのクレムリン赤の広場のそばに着陸した。ソ連軍はこの航空機に気づいていたが、小型の民間機であることから、大韓航空機撃墜事件の前例もあるため、撃墜許可が降りなかったと言われる。ゴルバチョフ書記長は、この事件の責任を問うとしてソコロフ国防省ら軍強硬派を解任。これにより原潜K-219事故で乗員を退去させソコロフの怒りを買ったブリタノフ艦長は訴追を免れている。 |
| 6月20日 | 「流転の王妃」嵯峨浩が北京で死去。 |
| 7月23日 | 猛暑の中、関東の1都5県で280万世帯が停電する大規模停電事故が起こる。首都圏大停電事故。 |
| 8月17日 | ナチ党副総統ルドルフ・ヘスがシュパンダウ刑務所で自殺。93歳。 |
| 9月13日 | ゴイアニア被曝事故。ブラジル・ゴイアニア市の廃病院に残されていた医療用放射性物質セシウム137を、住民が知らずに触るなどして、4人が死亡、250人が被曝。 |
| 9月17日 | 「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択。フロンガスなどの規制が国際的に決定する。 |
| 10月19日 | ニューヨーク株式市場で22.6%という史上空前の大暴落が起こる。アメリカの財政・貿易の赤字に、コンピュータによる株売買のプログラムが逆効果となって売りが加速した結果。 |
| 11月 8日 | 後楽園スタヂアムが閉鎖される。 |
| 11月28日 | 南アフリカ航空295便火災墜落事故。 |
| 11月29日 | 大韓航空機爆破事件。北朝鮮が引き起こした民間航空機爆破テロ事件。 |
| 12月 7日 | パシフィック・サウスウエスト航空1771便墜落事件。アメリカ・ロサンゼルス国際空港発、サンフランシスコ国際空港行、同航空BAe146-200A型機が、カリフォルニア州サンルイスオビスポ郡カユコスで墜落。原因は乗客の中にいた元USエアの従業員による自殺行為で、不祥事で解雇されたことを逆恨みした同従業員が、元上司が利用する同機内で、持ち込んだ銃を使い元上司、操縦士、客室乗務員らを射殺。機体を急降下させ音速突破の状態で丘陵に激突させた。犯人を含む乗員乗客43人全員死亡。 |
| 12月23日 | フィンエアー915便撃墜未遂事件。日本の新東京国際空港発、北極経由、フィンランドのヘルシンキ・ヴァンター国際空港行DC-10型機に対して、ノルウェー領スヴァールバル諸島エッジ島近くで、ソ連軍がミサイルを発射したとされる事件。2014年のマレーシア航空17便撃墜事件を受けて明らかにされた。ミサイルは機体の衝突20秒前地点で爆発。ソ連軍が旅客機を軍事演習の標的に利用したという説もある。 |
| 1988年(昭和63年) | |
| 1月 9日 | ベータとVHSのビデオ戦争で、ベータ側だったソニーがVHSの発売を決定。 |
| 3月13日 | 青函トンネル開通。長さ53.9kmの世界最長の海底トンネル。 |
| 3月16日 | ハラブジャ事件。イラン・イラク戦争の末期に、イラク政府がイランに協力したという理由で、東部ハラブジャのクルド人民間人を化学兵器で虐殺。約5000人が死亡。当時、イラクに味方していたアメリカ政府は、イラクの行為と認めず、イランによる爆撃と発表。 |
| 3月17日 | 日本初のドーム球場、東京ドームの落成式が行われる。 |
| 4月15日 | ソ連で、石油以外の液体水素などを燃焼して飛行する試験機Tu-155が初飛行。 |
| 4月28日 | アロハ航空243便事故。マウイ島近海上空高度7200mで飛行中の旅客機の機体上部の半分ほどが金属疲労で吹き飛ぶ大事故に遭遇しながら墜落せずにマウイ島のカフルイ空港に生還。破損時に乗員1名が吸い出され行方不明。 |
| 5月 4日 | アメリカ・ネバダ州ヘンダーソン市にあるペプコンの工場で火災が発生。ロケット用酸化剤過塩素酸アンモニウムの貯蔵施設が2度大爆発を起こし、爆風でヘンダーソン市や11km離れたラスベガス市でも大きな被害を出す。コロラド州の国立地震情報センターでマグニチュード3.0~3.5の揺れを観測。これほどの大規模爆発だったが、従業員はほぼ脱出に成功し死者は2名。 |
| 5月 8日 | 作家ロバート・A・ハインライン死去。SF界の第一人者。アシモフ、アーサー・クラークとともにSF三大作家。科学考証を重んじた作品を書いた最初期の作家の一人。一般向けの人気ある作品も多いが、多様性がすぎて物議を醸した作品も多い。 |
| 6月 4日 | アルザマス列車事故。ソ連のアルザマスで、カザフへ火薬を輸送中の貨物列車が大規模な爆発を起こし、病院や学校、発電所などを破壊。91人が死亡、約1500人が負傷。原因は不明。危険物輸送の規定に違反したことが原因とも、テロとも言われる。 |
| 7月 3日 | イラン航空655便撃墜事件。イラン・イラク戦争のさなか、ペルシャ湾岸に展開していたアメリカ海軍ミサイル巡洋艦ヴィンセンスが、バンダレ・アッバース発ドバイ行きのイラン航空旅客機A300型機を軍用機と誤認して攻撃。同機は撃墜され、乗員乗客290人全員が死亡。民間機と十分認識できたとして、アメリカ政府はイランを含む6カ国の犠牲者家族へ6180万ドルの賠償に応じた。 |
| 7月15日 | 映画『ダイ・ハード』公開。TV俳優だったブルース・ウィリス演じる一見冴えない刑事がテロリストと戦う内容は前評判が悪かったが、公開後に予想を覆して大ヒットした。 |
| 8月10日 | レーガン大統領が、市民の自由法に署名。第二次世界大戦中にアメリカによって行なわれた日系人の強制収容を謝罪し、一人当たり20000ドルの補償を行う。 |
| 8月26日 | 奈良市の奈良そごう建設予定地で調査中の遺跡から大量の木簡が発見され、長屋王邸跡と判明する。 |
| 8月28日 | ラムシュタイン航空ショー墜落事故。西ドイツのラインラント=プファルツ州にある米軍ラムシュタイン空軍基地で行われた航空祭で、イタリア空軍の曲芸飛行隊フレッチェ・トリコローリの曲芸飛行実演中に、アエルマッキMB339型3機が空中で衝突。1機が炎上して客席に突入、1機は滑走路上のヘリに激突、1機は滑走路に墜落し、3機のパイロットと、ヘリの乗員、観客67人が死亡、500人を超える人が重軽傷を負う。 |
| 9月29日 | チャレンジャー事故以来32ヶ月間の中断の後、スペースシャトル・ディスカバリーが打ち上げられる。 |
| 10月 5日 | チリでピノチェト大統領の任期延長を諮る国民投票が行われるが、不信任の結果となり、ピノチェト政権崩壊へ。 |
| 11月10日 | 自民党が消費税関連法案を強行採決。 |
| 11月15日 | ソ連版スペースシャトルのブランが打ち上げられる。無人飛行して、無事帰還。ソ連が崩壊してしまったため、この1回で終わる。 |
| 12月 9日 | スウェーデンの国産戦闘機サーブ39グリペンが初飛行。ビゲンに続きカナード・デルタ翼機。軽量化され、整備もしやすくなっている。売却やリースなど輸出にも積極的で複数の国が採用している。 |
| 12月21日 | リビア政府の工作によって、ロンドン発ニューヨーク行きのパンナム機103便がスコットランド上空で爆破される。乗員16名、乗客243名全員と、墜落した地上の住民11名の計270名が死亡。 |
| 1989年(昭和64年・平成元年) | |
| 1月 4日 | シドラ湾事件。リビアが領海と主張するシドラ湾北方の地中海でアメリカ海軍が演習中、リビア空軍のMiG-23戦闘機2機が繰り返し接近したため、アメリカ海軍機が警告の上でこの2機を撃墜。シドラ湾での交戦は1981年以来。 |
| 1月 7日 | 昭和天皇が崩御。元号法と「元号を改める政令」(昭和64年政令第1号)によって改元へ。 |
| 1月 8日 | 「元号を改める政令」が施行され、元号の昭和が終わり、平成となる。修文、正化、平成の3候補の中から選ばれた。 |
| 1月19日 | 潜水調査船「しんかい6500」が進水。 |
| 2月15日 | ソ連軍がアフガニスタンから撤退を終える。 |
| 2月22日 | 吉野ヶ里遺跡で大規模な環濠集落が発見されたとメディアで報道される。 |
| 3月 1日 | アメリカ合衆国が無方式主義(登録などをしなくても自然に認められる)著作権保護を定めたベルヌ条約に加盟。1988年までアメリカの法律では著作物は登録しなければ著作権は認められなかったため、アメリカ以外の国の作品は、アメリカでは万国著作権条約によって©表記が必要だった。 |
| 3月13日 | 大規模な太陽フレアが発生。発生した大量の電磁波などが地球に到達し磁気圏と電離層に衝突。低緯度地方でもオーロラが発生した他、人工衛星の機能停止、ラジオ放送の中断、カナダケベック州では電力会社の送電システムのブレーカーが落ちて大規模な停電を引き起こした。 |
| 3月29日 | 女子高生コンクリート詰め殺人事件が発覚。 |
| 4月19日 | アメリカ海軍の戦艦アイオワが、プエルトリコの沖合で訓練中に第2砲塔の中央砲が爆発する事故を起こす。砲塔内にいた47人が死亡。 |
| 4月20日 | 朝日新聞所属のカメラマンが、西表島の巨大サンゴに傷をつけ、いかにも他人が起こしたイタズラのように捏造した写真を、朝日新聞夕刊が現代日本人のモラルを批判する記事とともに掲載。のちに捏造と発覚して謝罪。 |
| 5月12日 | アメリカ・カリフォルニア州サンバーナーディーノで、サザン・パシフィック鉄道の貨物列車が暴走脱線し住宅街に突入。7棟をなぎ倒し、乗員2人と住民4人が死亡。原因は過積載とブレーキの故障、それらの情報が乗員間で共有されていなかったため。 |
| 5月22日 | アメリカカリフォルニア州サンバーナーディーノで、先の貨物列車事故に由来するとみられる線路沿いの石油パイプライン破裂火災が発生。11棟が焼失し、2人が死亡。 |
| 5月26日 | ダン・シモンズの小説『ハイペリオン』発売。ハイペリオン/エンディミオン4部作の第一作。 |
| 6月 4日 | 中国で六四天安門事件が起こる。民主化を要求した知識人や学生のデモ隊を軍が武力鎮圧。多数の犠牲者を出す。 |
| 6月 4日 | ソ連のバシキール自治共和国イグリンスキーで、クイビシェフ鉄道を走行中の上下線2つの列車が爆発。乗客1300人の内、少なくとも575人が死亡、800人が負傷。780人が死亡したと言う説もある。ソ連時代最悪の列車事故とも。爆発の原因は、鉄道の近くを走る天然ガスパイプラインからガスが漏洩し、窪地に溜まっていたところを、2つの列車が通過、車輪の火花で引火したものと思われる。ウファ列車事故とも呼ばれるが、ウファ市からは50km離れている。 |
| 6月18日 | ビルマの軍事政権が、国名をビルマからミャンマーに変更。ミャンマーはビルマ語系の名称。ビルマはインド系言語の呼称からポルトガル語を経て英語化したものと言われる。軍事政権に対して批判的な立場を取る人や、英語圏の諸国ではビルマを、それ以外の欧州や南米、アジア諸国ではミャンマーを使うようになった。メディアも対応が分かれたが、その後はミャンマー使用にシフトしつつある。なおビルマ族のことはバマーともいい、口語的にはビルマも使われる。 |
| 6月25日 | 革労協永井派の永井啓之が、居住する埼玉県川口市のアパートで、敵対する革労協狭間派のメンバーに拉致され、全身を滅多打ちにされて殺害される。狭間派が犯行を認めたため、革労協の内部分裂が加速した他、他の新左翼が穏健路線に変わる中で、革労協狭間派の暴力主義が目立つようになる。 |
| 6月26日 | 初代の気象衛星ひまわりをより高い墓場軌道へと移動させる。 |
| 6月30日 | 初代の気象衛星ひまわりの運用が終了する。 |
| 7月 4日 | ポーランドに駐留していたソ連空軍のMiG-23戦闘機が、飛行中にトラブルを起こしてパイロットが脱出したあとも無人飛行を続け、東ドイツを横断して西ドイツに入り、更にオランダ、ベルギー領空を通過して、フランス国境近くに墜落。地上にいた住民一人が巻き込まれて死亡。米軍が迎撃に向かうが無人だったため、北海上空で撃墜する予定だった。 |
| 8月11日 | 潜水調査船「しんかい6500」がテスト潜航で6527メートルの海底に到達。 |
| 8月19日 | 東欧共産国のハンガリーと中立国のオーストリアが、ショプロンの国境ゲートを開いて東ドイツ市民の西側への大挙亡命を黙認する「ヨーロッパ・ピクニック計画」が実施される。ベルリンの壁崩壊、ドイツ統合、東欧革命のきっかけとなった国際的大事件。 |
| 9月19日 | UTA航空772便爆破事件。コンゴ共和国ブラザビルのマヤマヤ国際空港発、チャドのンジャメナ国際空港・フランスのマルセイユ空港経由、フランスのパリ・シャルル・ド・ゴール空港行の同便が、ンジャメナを離陸直後に、貨物室内の手荷物に入っていた爆弾が炸裂。操縦席が吹き飛び、機体胴体部はニジェールのテネレ近郊に墜落。乗員乗客170人全員が死亡。犯行は、チャドと敵対するリビアが、チャドを支援するフランスに対して起こしたテロ。 |
| 9月30日 | セネガンビア国家連合が解消。セネガルとガンビアの関係が悪化したため。 |
| 10月 2日 | 奈良市の奈良そごうが多くの反対意見を無視し、長屋王邸跡を破壊して建築開業。 |
| 10月10日 | ソ連のロケット技術者ヴァレンティン・グルシュコ死去。死ぬまで対立したコロリョフの第1設計局(エネルギア。現S.P.コロリョフ ロケット&スペース コーポレーション エネルギア社)を受け継ぎ、宇宙ステーションやソ連版スペースシャトル輸送ロケット・エネルギアの開発にあたった。 |
| 10月31日 | 三菱地所がロックフェラー・センターにある19のビルの内、14のビルを買収する。 |
| 11月 9日 | ベルリンの壁崩壊のはじまり。東ドイツ政府が、ハンガリーによる国境通過の自由を受けて混乱する国内を収拾するため、旅行の部分自由化を認める政令を発表する際、報道官が誤って「ベルリンの壁を含むすべての国境から出国できる。それもただちに」と説明してしまい、歓喜した市民がベルリンの壁に殺到。事態に驚いた警備部隊指揮官が許可を得ずに国境ゲートを開放する。報道官は意図して嘘の公表をしたのではないかという憶測もあるが、真実は謎のまま。 |
| 11月10日 | 前日に続き、ベルリンの壁に殺到したベルリン市民は、勝手に壁を破壊し始め、東ドイツ政府ももはや取り締まることができなくなり、のちに政府自ら壁の大部分を撤去した(一部は記念に残された)。 |
| 11月17日 | チェコスロバキアで、反体制の大学生らがデモを計画、軍の特殊部隊と衝突して多数の負傷者を出す。これがきっかけで、全土で反体制デモとゼネストが拡大。共産党政権が倒壊するビロード革命の始まりとなる。 |
| 12月 3日 | マルタ島に停泊したソ連客船マクシム・ゴーリキー内で、アメリカのブッシュ大統領(父ブッシュ)とソビエトのゴルバチョフ書記長が会談、冷戦が終了する。 |
| 12月14日 | ソビエトの物理学者アンドレイ・サハロフが死去。ソ連の水爆開発に関わり「ソ連水爆の父」と呼ばれる一方で、その後は、核実験の制限や、人権活動を進め、ソ連国内の反体制の代表となった。ソ連の体制改革を訴え、「ペレストロイカの父」とも呼ばれる。 |
| 12月16日 | 中国民航機ハイジャック事件。北京発、上海・サンフランシスコ経由ニューヨーク行き中国国際航空CA981便ボーイング747型機がハイジャックされ、犯人は韓国行きを要求したが、韓国側が受け入れを拒否。やむなく日本へ向かい、福岡空港に緊急着陸を要請。許可を得て着陸。まもなく犯人は客室乗務員によって非常口から突き落とされて重症を負い逮捕された。犯人は政治亡命を主張したため、身柄を中国へ引き渡すべきかで論争になったが、ハイジャックしたことを問題視して中国へ引き渡した。中国で裁判にかけられ懲役8年の判決。 |
| 12月16日 | ルーマニア西部の都市ティミショアラで、抑圧されていたハンガリー系住民が反政府抗議デモを行い、治安警察が発砲。死傷者を出す事態に発展。 |
| 12月21日 | ルーマニアで、政府が主催した政権支持の大集会で爆弾事件が起こり、それをきっかけに反政府市民が抗議集会を開催。チャウシェスク大統領が、軍の出動と市民への発砲を命じるが、国防大臣ワシーリ・ミリャがこれを拒絶。直後に彼が死亡したため、軍は大臣が暗殺されたとして反乱。市民側に味方し、首都ブカレストの軍事制圧に乗り出す。 |
| 12月25日 | ルーマニアの内乱で逮捕されたチャウシェスク大統領夫妻が、特別軍事法廷で死刑判決をうけ、即日処刑される。 |
| 12月28日 | ドイツのロケット工学研究者ヘルマン・オーベルト死去。ロケット開発のきっかけを作ったとも言える人物。 |
| 12月29日 | 市場の大納会で、日経平均株価が算出開始以来の最高値を記録。バブルは頂点に。 |
| 12月31日 | ソ連の多用途戦闘機Su-30が初飛行。Su-27の発展型。ロシアと関係の深いアジア・アフリカ諸国に輸出されている。 |
| 1990年(平成2年) | |
| 3月21日 | ナミビアが南アフリカから独立。南アフリカからの独立を掲げて起きたナミビア独立戦争と、北隣のアンゴラ内戦への南アフリカ介入の失敗の結果。 |
| 3月22日 | 弾道学・超長距離砲の研究者で、イラクの長距離砲計画「バビロン計画」に関わっていたカナダ人科学者ジェラルド・ブルがベルギー・ブリュッセルの自宅で射殺される。イラクと対立するイスラエルやイランの諜報機関の犯行とも言われるが、犯人は不明。長距離砲で人工衛星を打ち上げる研究などもしていた。 |
| 4月24日 | ハッブル宇宙望遠鏡をスペースシャトル・ディスカバリー号で打ち上げる。 |
| 7月16日 | フィリピン・ルソン島でマグニチュード7.8の大地震が起きる。 |
| 8月 2日 | イラク軍がクウェートに侵攻。国連安保理は即時無条件撤退を求める決議660を採択。 |
| 8月 8日 | イラク政府がクウェートの併合を宣言し、「カーズィマ県」と称する。 |
| 8月27日 | アメリカの先進戦術戦闘機計画の候補としてYF-23が初飛行。菱形の主翼にV字尾翼という独特の形状をしている。先進的で性能も高かったが、競合するYF-22(F-22)に選定で敗れたため、量産はされなかった。 |
| 9月 2日 | モルドバがソ連からの主権移譲を宣言したのを受けて、「沿ドニエストル共和国」がモルドバからの分離独立を宣言。 |
| 9月12日 | ドイツに関する最終規定条約に東西ドイツと、アメリカ、イギリス、フランス、ソビエトが調印して、ドイツは再統一が決定。 |
| 9月27日 | 阪急航空チャーターヘリ墜落事故。宮崎空港発、延岡ヘリポート行の旭化成社用定期便204便(川崎BK117型機)が、台風の悪天候の中、日向市の牧島山山頂付近に墜落。乗員乗客10名全員が死亡。機体は阪急航空のチャーター機。旭化成発祥の地である延岡には同社の工場群があり、社員が東京や大阪と頻繁に行き来していたが、同市には当時高速道路はなく、宮崎市とつながるJR日豊本線はあるものの宮崎空港は鉄道のアクセスが不便だったため、社用定期便を運行していた。この事故を受け、旭化成は日豊本線の高速化(直線及び高架化)と、JR宮崎空港線の建設に資金を出すことになった。 |
| 9月30日 | アメリカの先進戦術戦闘機計画の候補として、のちのステルス戦闘機F-22の原型試作機YF-22が初飛行。選定されることになるが、量産型のF-22とは形状がかなり異なる。 |
| 10月 2日 | 廈門航空機ハイジャック事件。犯人と機長が揉み合いになり、広州白雲空港で着陸に失敗。離陸準備中の中国南方航空の旅客機に激突する。ハイジャックされた厦門航空機の乗員乗客104人のうち犯人を含む84人と、激突された上海行ボーイング757の乗員乗客118人のうち47人、地上の作業員1人が死亡。 |
| 10月 3日 | ドイツ連邦共和国(西ドイツ)にドイツ民主共和国(東ドイツ)が編入され、東西ドイツが統合。 |
| 10月25日 | カザフ・ソビエト社会主義共和国最高会議が国家主権宣言を採択。独立国家へと動き出す。 |
| 11月17日 | 雲仙普賢岳が噴火。 |
| 11月22日 | マーガレット・サッチャー、英国首相、保守党党首を辞職する意向を示す。 |
| 12月 2日 | TBSの記者だった秋山豊寛がソビエトの宇宙船ソユーズTM11号で宇宙へ出る。 |
| 12月20日 | 『ゴッドファーザー PART III(ゴッドファーザー・コーダ:マイケル・コルレオーネの最期)』が公開。パート2から16年後に制作された第3作。前2部作の後日譚的な内容で評価は分かれた。バチカンの内部腐敗も描いているため、映画賞を受賞できなかった理由にする説もある。 |
| 12月23日 | 第35回有馬記念。オグリキャップの引退レースで、ファンら17万7779名が中山競馬場に入場。その中で、オグリキャップが勝利するという劇的な結果に。 |
| 12月 | 東京都庁第一庁舎が完成。48階建て、高さ243.4mで日本一に。隣接して第二庁舎も完成(34階建て、163.3m)。丹下健三の独特のデザインや、公共施設としては破格の巨大さに「バブルの塔」などと批判も出るが、新たな新宿のランドマークとしての人気も出る。 |
| 1984年ころからアメリカで猛威をふるった「クラックブーム」(クラック・コカインの蔓延)が終息する。純度が高い割に安価だったためまたたく間に全米に拡大し流行した。しかし、景気が回復したこと、身近な中毒者の悲惨な状況を目の当たりにした若者らの忌避感、取り締まりの強化、マリファナ(乾燥大麻)の合法化への動きで終息したと見られる。 | |
| 1991年(平成3年) | |
| 1月17日 | 多国籍軍がイラクに対し空爆攻撃「砂漠の嵐作戦」を開始。湾岸戦争が始まる。 |
| 1月17日 | アメリカ軍がイラク軍のタリル空軍基地を爆撃。同基地の弾薬庫が誘爆し大爆発を起こす。核兵器を除き、航空攻撃で史上最大の爆発とも言われている。 |
| 2月11日 | 代表なき国家民族機構(UNPO)が設立される。 |
| 2月24日 | 多国籍軍が空爆を停止し、イラクに対し地上攻撃「砂漠の剣作戦」を開始。 |
| 2月27日 | 多国籍軍がクウェートを解放。 |
| 2月 | 原子力船むつの原子力運転による試験航海が始まる。8万2千kmの航行結果を残す。 |
| 3月 3日 | ロドニー・キング事件。黒人男性ロドニー・キングがスピード違反で捕まった際に、無抵抗だったにもかかわらず警察官20人によって暴行され重症。その様子を近隣の住民がビデオで撮影して公開。ビデオから4人の警官の身元が特定され(白人3人、ヒスパニック系1人)、人種差別騒動へ発展。4人は告訴されるが、やむを得なかったとの主張が認められる。 |
| 3月15日 | ルソン島のピナトゥボ火山付近で地震が起き始める。 |
| 3月16日 | ラターシャ・ハーリンズ事件。15歳の黒人少女ラターシャ・ハーリンズがロサンゼルスの韓国系商店に買い物に来た際、女性店主トゥ・スンジャに万引き犯と疑われ言い争いに発展。少女は品物を置いて店を出ようとしたところ、その背後から店主に拳銃で頭を撃たれて死亡。店主は正当防衛を主張したが、防犯カメラの映像や目撃者の証言で故意の殺人と認定され、陪審員は懲役16年相当の評決を下す。しかし実際の判決は5年間の保護観察処分など軽いものとなり黒人社会と韓国人社会の対立に発展。 |
| 4月 2日 | ルソン島のピナトゥボ火山が水蒸気爆発。噴火活動が始まる。 |
| 4月 6日 | イラクのフセイン大統領が、安保理決議687号を受け入れ停戦に合意。 |
| 5月14日 | 信楽高原鐵道事故。信楽町で開催されていた「世界陶芸祭セラミックワールドしがらき'91」の観光客を輸送するため、信楽高原鐵道の車両と同線に乗り入れていたJR西日本の臨時快速列車が小野谷信号場と紫香楽宮跡駅間で正面衝突。乗員乗客42名が死亡、614名が重軽傷を負う大惨事となる。陶芸祭への輸送対応のために導入したシステムの不備と誤作動、手続き無視の運行の常態化、確認ミスなどが重なったもの。事故を受けて陶芸祭も同日で終了となった。 |
| 5月14日 | 毛沢東の第4夫人であった江青が自殺。「四人組(四人帮)」の一人で、文化大革命を主導し、直接間接的に多くの人の殺害に関与、大規模な文化破壊を担って中国に深刻な後遺症を残した。その動機は多分に嫉妬や個人的恨みによるものといわれる。その絶大な権力で「紅色女皇」と呼ばれたが、人民に人気のあった周恩来の死を侮辱して第一次天安門事件が勃発。その直後の毛沢東の死により失脚し、執行猶予付き死刑判決を受けた。その後、無期懲役に減刑され、病気療養のため仮釈放となっていた。四人組の中では最後まで罪を認めなかった。 |
| 5月21日 | エチオピアで、エリトリア人民解放戦線とティグレ人民解放戦線が首都アディスアベバに侵攻し、メンギスツ独裁政権が崩壊。メンギスツ・ハイレ・マリアムはジンバブエへ亡命。 |
| 5月24日 | ソマリランドが、ソマリアからの分離独立を宣言。現時点では台湾を除き公式に承認した国はないが、代表処をおいている国が十数カ国ある。なお、政治状況では内戦状態のソマリアより安定しており、冷戦下に作られた巨大な港湾などがあるため中継貿易が盛んに行われている。 |
| 5月29日 | エリトリアが、エチオピアからの独立を宣言。 |
| 6月 3日 | 雲仙普賢岳大火砕流発生。学者、マスコミ、消防団員、警察官、住民ら43名が死亡、9名が重軽傷を負う。著名な火山学者クラフト夫妻も死亡。 |
| 6月 4日 | ソビエトの原子力潜水艦K-19が原子炉のトラブルを起こしたため、正式に引退廃艦が決まる。事故やトラブルに再三巻き込まれたことで有名な潜水艦。後に映画化もされた。 |
| 6月 7日 | ルソン島のピナトゥボ火山が大爆発を起こす。 |
| 6月12日 | 15日にかけてルソン島のピナトゥボ火山が連続して大爆発を繰り返す。噴煙が高度40kmに達する。ルソン島全体で降灰し、灰は東南アジア方向へと流れる。大規模な火砕流が発生。規模の大きい地震も多発。台風が通過して豪雨が降ったため、大規模な土石流の発生と濡れた灰による重みで家屋倒壊が相次ぐ。15日夜の噴火でほぼ終息し、火口付近にカルデラが形成される。 |
| 6月20日 | ドイツの首都がベルリンに戻る。 |
| 6月25日 | スロベニアとクロアチアがユーゴスラビア連邦からの独立を宣言。 |
| 6月27日 | スロベニアとセルビア主体のユーゴ連邦軍の間で十日間戦争が始まる。ユーゴスラビア紛争の始まり。 |
| 6月28日 | ソ連主体の共産主義国経済相互援助会議COMECONが解散。 |
| 7月11日 | ナイジェリア航空2120便墜落事故。サウジアラビアのジッダ空港発、ナイジェリアのソコト行きDC-8型機が、ジッダを離陸する際、タイヤから出火。そのまま離陸して機内に引き込んだため、機内で延焼。管制とのやり取りミスで滞空時間が伸びた上に、空港へ引き返す途中、車輪を外に出した際に空気が入って火災が強まり、客室が崩壊。空港手前で墜落した。乗員乗客261名全員が死亡。火災の原因は、タイヤ圧が弱まっているのを放置して滑走したため、タイヤが次々と破裂。破片を噛み込んだ車輪が固定し、滑走路との摩擦で高温になり発火したもの。機体をナイジェリア側に貸し出していたカナダのネーションエアの運行管理者(この事故で死亡)のいい加減な対応が最大の要因。 |
| 7月17日 | カンボジアの親ベトナム派ヘン・サムリン政権と反ベトナム三派(シアヌーク派、ソン・サン派、ポル・ポト派)が最終合意し、カンボジア最高国民評議会が成立。シハヌークを議長に選出。 |
| 8月 8日 | 当時世界一高い人工物だったポーランドのワルシャワラジオ塔が、塔を支えるワイヤー交換作業中のミスでバランスを崩し倒壊する。 |
| 8月19日 | ソ連でゴルバチョフ大統領の改革に反発する保守派が軍事クーデターを起こし、保養地にいたゴルバチョフを軟禁。しかし軍と市民が反発。 |
| 8月22日 | ロシア共和国の代表エリツィンらが軍部とともに抵抗した結果、ソ連保守派のクーデターは失敗に終わり、関係者は逮捕される。 |
| 8月24日 | クーデター派に軟禁されていたゴルバチョフ大統領がソ連共産党書記長を辞任し、ソ連共産党中央委員会の自主解散を要求。 |
| 8月26日 | 海上自衛隊の最初のイージス護衛艦、こんごう型の1番艦「こんごう」が進水。 |
| 8月27日 | モルドバが正式にソ連から独立。 |
| 8月29日 | ソ連議会がソビエト共産党の活動の停止を決定。 |
| 8月29日 | ソ連のセミパラチンスク核実験場が閉鎖。 |
| 9月 4日 | 外務省審議官実父宅放火殺人事件。東京・埼玉・千葉の数カ所で同時放火事件が発生。そのうち東京大田区の元千葉工業大学講師宅放火事件では、在宅していた老夫婦が大やけどを負い後に死亡。中核派が一連の放火事件の犯行声明を出し、大田区の放火は、堤功一外務省大臣官房審議官宅を放火したとし、天皇皇后のASEAN諸国歴訪担当者だったので襲ったとしたが、実際には審議官の実父宅で、しかも審議官は歴訪には無関係という、完全に「誤爆」の事件だった。しかし中核派の幹部北小路敏は罪人の家族は巻き込まれても仕方がないといった開き直り発言をした。 |
| 9月19日 | アルプス山脈で約3300~3200年前ころの男性「アイスマン」の遺体が発見される。年代には異説あり。 |
| 9月22日 | セルビア軍がクロアチアの首都ザグレブを攻撃。クロアチア紛争が本格的な戦争に発展。 |
| 9月25日 | フランスの刑務所で、クラウス・バルビーが死亡。元ナチス親衛隊大尉で、ヴィシー政権下のフランスでパルチザンやユダヤ人の虐殺を行い、「リヨンの屠殺人」と恐れられた。戦後、対共産主義の情報戦に役立つとしてアメリカの庇護を受け、フランスの追求を受けると偽名でボリビアに移住し、同国の軍事政権に関わった。後に正体を明かしたが罪を認めず、フランスに引き渡されたあとも無実を主張した。 |
| 10月15日 | アメリカユタ州の陸軍ダグウェイ性能試験場にある高解像度フライズアイ宇宙線検出実験施設(HiRes)で、超高エネルギー宇宙線が観測される。通称「オーマイゴッド粒子」。ほとんど光速という速度で、エネルギーは約300エクサ電子ボルト。5×10の19乗eV以上の高エネルギーは、宇宙マイクロ波背景放射と衝突してエネルギーを失うと予想されることから、100メガパーセク(3億光年)の距離以上は飛来しないと考えられる(GZK限界)。そのため、比較的近い時代に、なにかの天体現象で発生したものと考えられる。観測されるのは非常に稀。 |
| 10月18日 | アメリカの核実験ジュリン作戦が始まる。地下核実験。 |
| 10月23日 | カンボジア紛争の包括的な政治解決に関する協定(パリ和平協定)が調印され、カンボジア内戦が終結。 |
| 10月30日 | カナダ最北部エルズミア島北端のカナダ軍アラート基地で、C130輸送機が着陸に失敗。極寒の中で救助作業が行われたが乗員18人中4人が死亡。 |
| 11月12日 | 東ティモールで、デモ行進をしていた地元住民がインドネシア軍に銃撃され多数が殺害される(サンタクルス事件)。 |
| 11月24日 | イギリスのロックバンド「クイーン」のボーカル、フレディ・マーキュリーが死去。45歳。 |
| 12月 4日 | アメリカ合衆国の事実上のフラッグ・キャリアとして世界中に路線を持っていたパンアメリカン航空が倒産。 |
| 12月 8日 | ソ連邦を構成するロシア、ベラルーシ、ウクライナの首脳が密かに会談し、ソ連からの離脱と国家共同体の設立を決める。 |
| 12月10日 | 都営地下鉄12号線が光が丘-練馬間で部分開業。のちの大江戸線。 |
| 12月21日 | ソビエト連邦内のロシアを始めとする12の国々が連邦から離脱し独立国家共同体を結成。 |
| 12月29日 | トーヨコカップシャパン・グアムヨットレース92遭難事故。荒天の中、レースに参加していた「たか」が小笠原諸島聟島沖で転覆沈没、翌30日に八丈島沖で「マリンマリン」が故障で漂流中に船体が破損して転覆沈没。「たか」の乗員のうち6名が死亡、1名が27日間漂流して救助、「マリンマリン」の乗員のうち8名が死亡した。「たか」は乗員が救命ボートで脱出した際に食料などが流されてしまい5名が衰弱死した(1名は転覆時に死亡)。また遭難したことがすぐにはわからず救援要請も遅れた。「マリンマリン」は救援要請で来援した巡視船の目の前で転覆したが夜間と波浪で救助が遅れた。 |
| 12月25日 | もはや有名無実と化した「ソビエト連邦」のゴルバチョフ大統領が辞任を表明。ソ連が崩壊する。 |
| 1992年(平成4年) | |
| 2月 5日 | 旧ソ連の海外留学生向け思想教育機関だったパトリス・ルムンバ名称民族友好大学がロシア諸民族友好大学に改められる。留学生向けの教育機関としては継続。 |
| 2月 7日 | EC加盟12か国が「マーストリヒト条約」に調印。欧州連合結成へ。 |
| 2月 8日 | 第16回冬季オリンピック・アルベールビル大会開催。夏季オリンピックと同じ年に行われた最後の冬のオリンピック。 |
| 2月25日 | ホジャリ虐殺事件。ナゴルノ・カラバフ戦争のさなか、ホジャリでアルメニア人武装勢力と独立国家共同体軍の将兵によって、アゼルバイジャン人市民が多数殺害される。少なくとも161人以上、アゼルバイジャン政府によれば613人が殺害されたとされる。この事件後6000人以上が住んでいたアゼルバイジャン人住民が去り、代わりにアルメニア人が入って、名前も同地出身の将軍からイヴァニアンと改められた。 |
| 3月17日 | アルゼンチンのブエノスアイレスにあるイスラエル大使館が自爆テロによって爆破される。犯人1人を含む死者30人、負傷者242人。 |
| 4月 6日 | 作家アイザック・アシモフが死去。ロボット工学三原則を生んだ「ロボット」シリーズや、「ファウンデーション」シリーズなどで知られた三大SF作家の一人(他はアーサー・クラーク、ハインライン)。ミステリー、科学啓蒙書も多数執筆。ボストン大学生化学教授。サイコップ(CSI)創設者。メンサ副議長。死因は10年前の手術時の輸血がHIVに汚染されていたことによる後天性免疫不全症候群といわれる。 |
| 4月22日 | メキシコのグアダラハラ市で、ペメックス社の製油所から下水道に流入したガソリンが引火し爆発。206人が死亡し、500人近くの負傷者を出す。その3日前から市民は異常に気づき訴えていたが、市の対応がいい加減だったため、大惨事となった。 |
| 4月29日 | ロサンゼルス暴動。前年のロドニー・キング事件の控訴審で、訴えられた4人の警察官に対し、陪審員の無罪評決が出される。しかし検察側が市民の殆どが白人であるシミバレー市での評決を指定したこと、陪審員の大半も白人の元軍人などであったことから、黒人住民の怒りが噴出。ロサンゼルス市街で大規模な暴動に発展。各地の都市にも波及する。前年のラターシャ・ハーリンズ事件の影響もあり、韓国系商店多数が襲撃され、商店主らが武装して応戦する事態に。またこの時、通りがかった白人運転手レジナルド・デニーが黒人集団に襲われる場面が空撮される(デニーは直後に黒人住民に助けられて病院に搬送され一命を取り留める)。白人警官が襲撃対象になったこともあり、ロサンゼルス市警は出動も出来ない状態になる。 |
| 4月30日 | ロサンゼルス暴動で、黒人市長トム・ブラッドリーは非常事態宣言を発令。連邦軍が鎮圧のため出動する。 |
| 5月 2日 | モルドバが国連に加盟。また、同国内で独立を宣言していた沿ドニエストルに侵攻。ロシアも派兵し、トランスニストリア戦争が勃発する。 |
| 5月 4日 | ロサンゼルス暴動がほぼ沈静化する。死者53人、負傷者約2000人。放火などによる建造物の損壊も多数に上った。 |
| 5月17日 | タイで軍事政権と反体制市民が衝突し、300人もの死者を出す。国王が調停に出て政権が倒壊。 |
| 5月22日 | 細川護煕らが日本新党を結成。 |
| 5月27日 | 『サザエさん』の作者長谷川町子死去。 |
| 6月 3日 | ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された国連環境開発会議(地球サミット)で「気候変動枠組条約」と「生物多様性条約」の調印が行われる。 |
| 6月26日 | 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律が施行。相互銀行法が廃止され、相互銀行が普通銀行に転換される。 |
| 7月21日 | モルドバ、ロシア、沿ドニエストルの間で休戦協定が結ばれ、トランスニストリア戦争が停戦。同地にロシアとモルドバの平和維持軍が進駐。 |
| 7月28日 | 長谷川町子に国民栄誉賞。 |
| 9月23日 | アメリカの核実験ジュリン作戦ディバイダー実験が実施される。核爆発を伴った最後の核実験。核出力20Kt未満。以降は核爆発を伴わない臨界前核実験に移行。 |
| 10月 7日 | トルコのウビフ文化の記録活動を行ったテヴフィク・エセンチが死去。ウビフ語の最後の話者でもあった。 |
| 10月31日 | ガリレオの死から350年で、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世は、ガリレオ・ガリレイに対する裁判の誤りを認め、破門を解く。 |
| 11月 3日 | 首里城正殿などが復元され、首里城公園が完成する。江戸時代に作られ、太平洋戦争で焼失した建物群、庭、石垣など。のち他のグスクなどとあわせて世界遺産に指定。 |
| 11月23日 | 「風船おじさん」こと鈴木嘉和が、ヘリウム入りの風船を多数つけたゴンドラ「ファンタジー号」で飛び立ち行方不明になる。 |
| この年、太陽から980光年にあるパルサーPSR B1257+12で、初めて太陽系外惑星が発見される。 | |
| 1993年(平成5年) | |
| 1月 1日 | 新しい宝塚大劇場が開場。 |
| 3月 7日 | 気象庁が花粉飛散情報の発表を始める。 |
| 3月14日 | ピレネー山脈の小国アンドラで、憲法が国民投票によって可決。これにより、それまでのスペイン・ウルヘル司教とフランス元首による共同統治から、両者を共同元首とする議会制民主主義となる。 |
| 4月 6日 | ロシアのセヴェルスクにあるトムスク7再処理施設で放射性物質の貯蔵タンクの爆発事故が起きる。 |
| 4月 8日 | カンボジア国民議会総選挙の監視要員として派遣されていた国際連合ボランティア中田厚仁とカンボジア人通訳のレイ・ソク・ピープがコンポントム郊外の路上で武装勢力に銃撃され殺害される。犯行はクメール・ルージュとも軍関係者とも諸説ある。 |
| 4月27日 | ザンビアのサッカー代表チームを載せたザンビア空軍のAF-319型機が給油地のガボンのリーブルヴィル空港を離陸直後に、大西洋に墜落。選手18人を含む、乗員乗客30名全員が死亡。原因は機体の整備不良とパイロットの操縦ミスが重なったと見られるが、事故原因と対応を巡ってザンビアとガボンの両国の関係が悪化している。 |
| 5月 4日 | カンボジア国民議会総選挙の国際連合カンボジア暫定統治機構(UNTAC)の文民警察官として派遣されていた日本人5人と護衛のオランダ軍が、クメール・ルージュと見られる武装勢力の攻撃を受け、高田晴行警部補が死亡。4人が重症を負う。一連の襲撃で選挙監視にあたったUNTAC要員の死者は11人に達した。 |
| 5月23日 | カンボジア国民議会総選挙が行われる(28日まで)。ポル・ポト派による武装襲撃という妨害にあうも高い投票率を得る。選挙結果はフンシンペック派が勝利。 |
| 5月24日 | エリトリアの独立が認められる。 |
| 5月29日 | 北朝鮮がノドン1号を試射。 |
| 6月 1日 | アンドラの憲法が成立したこと受けて、スペインとフランスがアンドラを国家承認。これによって外交権を持つ正式な独立国家となる。 |
| 7月14日 | 北硫黄島の遺跡調査団で2名が亡くなる事故が発生。同島の調査は中止。北硫黄島には、石野遺跡と呼ばれる、巨石とその周囲に多数の出土品が見つかった遺跡がある。1世紀ころのものという説もあるが、絶海の孤島で、ルーツが定かではない。特徴から、西の沖縄か南のマリアナ諸島から渡ったとも考えられるが、北方の小笠原諸島から出土する遺物との関連も指摘されている。 |
| 7月16日 | 横浜市西区みなとみらい地区に日本一高い高層ビル、ランドマークタワーが開業。70階建て、高さ296m。 |
| 8月 9日 | 非自民連立政権、細川内閣が誕生。 |
| 8月20日 | イスラエルとパレスチナの暫定自治政府原則の宣言(オスロ合意)が調印される。 |
| 9月24日 | 国民議会総選挙の結果を受けて、シハヌークを国王とする立憲君主制のカンボジア王国が成立。 |
| 10月20日 | 新右翼「風の会」代表の野村秋介が朝日新聞東京本社社長室で拳銃自殺。選挙に立候補した際に、週刊朝日で揶揄され、選挙妨害を受けたことへの抗議などから。 |
| 12月 9日 | 日本で初めて、自然遺産として屋久島と白神山地が、文化遺産として法隆寺地域の仏教建造物と姫路城の4か所が世界遺産に登録される。 |
| 12月29日 | 生物の多様性に関する条約が発効。環境の保護、生物資源の持続的な維持、遺伝資源の製品開発と資源国の両者への公平な利益配分を定めたもの。 |
| クリントン米大統領、ハワイ併合を非合法なものだったと謝罪。 | |
| 1994年(平成6年) | |
| 2月25日 | マクペラの洞窟虐殺事件。ヨルダン川西岸地区のヘブロンにある「マクペラの洞窟」で、礼拝中のイスラム教徒に対し、ユダヤ人極右思想カハネ主義の活動家バールーフ・ゴールドシュテインが銃を乱射。パレスチナ人のイスラム教徒29名が死亡、125名が重軽傷を負う。ゴールドシュテインも群衆によって殺害される。イスラエルでもこのテロには多数の批判の声が上がるが、パレスチナ人を始め、周辺国のイスラム教徒が各地で暴動を起こし、パレスチナ人・イスラエル人双方に多数の死傷者が出る。この洞窟は「旧約聖書/創世記」に出てくるアブラハムとその家族が埋葬された墓で、アブラハム(イブラヒム)は、ユダヤ・キリスト・イスラムのすべてで始祖とされている。そのためここにはユダヤ教徒用とイスラム教徒用の礼拝所がある。 |
| 4月 1日 | マレーシアのクアラルンプールに、ペトロナス・ツインタワーが完成。アンテナなどを除いたビル本体の高さ452mは、シアーズタワー(本体442.3m、アンテナ含めて527.3m)を抜いて世界一となる。 |
| 4月 6日 | ルワンダのハビャリマナ大統領とブルンジのンタリャミラ大統領の乗った航空機がミサイル攻撃を受けて、キガリ国際空港近郊に墜落。両大統領とも死亡。 |
| 4月 7日 | ルワンダで大統領警護隊が武装蜂起し、フツ族によるツチ族への「ルワンダ大虐殺」が始まる。 |
| 4月27日 | 南アフリカ初の全人種総選挙。 |
| 4月28日 | 細川内閣が総辞職(閣議決定は25日)。 |
| 4月30日 | 樺太アイヌ語の最後の話者、浅井タケが死去。 |
| 5月10日 | 南アフリカでの全人種総選挙で勝利したANCのネルソン・マンデラが大統領に就任。初の黒人政権。 |
| 6月12日 | ボーイング777が初飛行。 |
| 6月24日 | アメリカ合衆国ワシントン州フェアチャイルド空軍基地で、航空ショーの最中にB-52爆撃機が墜落。乗員3名が死亡。機長のアーサー・ホランド中佐が機体の運用限界を超えた操縦をしたため制御不能となり失速墜落したのが原因。 |
| 6月27日 | オウム真理教による松本サリン事件が発生。教団が猛毒のサリンを散布したことで住民8人が死亡し、660人が重軽傷。被害住民が警察やマスコミから犯人扱いされる冤罪事件に発展。 |
| 7月 4日 | 虐殺の続くルワンダで、隣国ウガンダからツチ族のルワンダ愛国戦線が侵攻し首都を制圧。 |
| 7月 8日 | 北朝鮮の金日成主席が急死。北朝鮮政府は平壌の錦繍山議事堂で死去したとしているが、実際には平安北道香山郡の金日成の別荘があった香山官邸で死去したとみられる。 |
| 7月16日 | シューメーカー・レヴィ第9彗星が分裂しながら木星に次々と衝突。22日まで続く。 |
| 7月16日 | 青森県の三内丸山遺跡で巨大建造物の木柱が発掘される。 |
| 7月18日 | ルワンダ愛国戦線のポール・カガメ司令官が、戦争の終結を宣言。フツのパステール・ビジムングを大統領に立てて新政権を樹立する。 |
| 7月18日 | アルゼンチンのブエノスアイレスにある、アルゼンチン・イスラエル相互協会のビルが爆破される。死者85人、負傷者200人以上の大惨事となる。 |
| 8月14日 | 数々のテロ事件を起こした国際テロリストのカルロスこと、イリイチ・ラミレス・サンチェスが、スーダンで逮捕される。フランスに移送後、裁判で終身刑。 |
| 8月18日 | マクドナルド・コーヒー事件判決が出される。マクドナルドで購入したコーヒーを誤って足にこぼして火傷を負った高齢の女性に対して、マクドナルド側に計276万ドルの支払いを求める評決が出される。その上で判事の判断で減額され、最終的に60万ドル未満の和解金の支払いで和解となった。賠償額の高さから裁判天国などと評されたが、女性は移植が必要な大やけどを負っており、マクドナルドが危険性を告知してなかったことや、事故後の補償交渉等で同社の対応に問題があったことも高額の理由となっている。 |
| 9月28日 | 大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件が発生(10月8日にかけて)。1府2県で不良少年らがたまたま近くにいただけの一般市民を拉致監禁して凄惨な暴行をくわえ4人を殺害し1人に重傷を負わせた凶悪事件。特に主犯的役割を担った3人は後に死刑確定したが、死刑廃止運動団体などの支援で不服を申し立てている。 |
| 10月 1日 | アメリカ合衆国とパラオ共和国が、自由連合盟約を発効させ、太平洋諸島信託統治領は消滅。 |
| 10月14日 | 第12回成田空港問題円卓会議により国と反対派の一部が、学識経験者の調停を受け入れ、円卓会議終了。政府は空港用地選定と収用のやり方が間違っていたことを認め公式に謝罪することになる。 |
| 10月21日 | 韓国ソウルの漢江に架かっていた聖水大橋の中央部分が突如落下。通行中の乗用車やバスも一緒に落下し、32人が死亡、17人が負傷する。原因は手抜き工事によるもの。 |
| 1995年(平成7年) | |
| 1月 1日 | 読売新聞がオウム真理教の本部がある上九一色村でサリンの残留物を検出したと報道。 |
| 1月17日 | 阪神・淡路大震災。最大震度は7。神戸市と淡路島で大きな被害を出し、神戸市長田区では大規模な火災。死者6434名、行方不明者3名、負傷者43792名。 |
| 1月26日 | 中国西昌衛星発射センターより発射された長征2E型ロケットが、打ち上げ直後に爆発。近くの村民20人が死亡。 |
| 2月 8日 | 野茂英雄がロサンゼルス・ドジャースと契約。当時は日米の野球界で明確な移籍ルールがなかったため、近鉄を任意退団しての移籍となり、報酬も近鉄が提示した1億以上を断りメジャー最低ラインの1千万弱となった(近鉄は最終的に移籍に同意している)。 |
| 2月11日 | 中部縦貫自動車道の安房トンネル建設工事中、国道158号線への取付道路建設現場で火山ガスを含む水蒸気爆発が発生。工事作業員4名が死亡。爆発で大規模な土砂崩れとなだれも起きる。この事故を受けて、設計が変更され、トンネルは20mほど延長されたほか、近くの中の湯温泉旅館も移転を余儀なくされる。このトンネルは焼岳火山群の活火山アカンダナ山の直ぐ側にあり、観測所も設置された。 |
| 3月18日 | 空知炭鉱閉山。北海道炭礦系の国内鉱山はすべて閉山となる。 |
| 3月20日 | 地下鉄サリン事件が発生する。営団地下鉄の丸ノ内線・日比谷線・千代田線3路線の5編成車両でオウム真理教による無差別の神経ガス「サリン」散布事件が発生。松本サリン事件を始め、一連のオウム真理教の起こした事件への警察の捜査妨害が目的で、警察・司法関係者の利用する地下鉄路線・駅を狙ったもの。13人が死亡、約6300人が重軽傷を負う。通報を受けた消防庁がすぐに緊急部隊を出動させたほか、聖路加病院は外来を中止し被害者の受け入れを決定。また化学戦に詳しい自衛隊はすぐにオウム真理教によるサリンテロと判断したという。 |
| 3月22日 | 警視庁がオウム真理教教団施設25箇所の強制捜査を開始。 |
| 3月30日 | 國松孝次警察庁長官が、東京荒川区南千住の自宅マンションを出た所で狙撃され、瀕死の重症を負う。オウム真理教への強制捜査を中止するよう要求する電話があり、同教団の犯行が疑われる。 |
| 4月 8日 | 石川県警がオウム真理教の幹部林郁夫を自転車窃盗容疑で逮捕。このあと教祖麻原の言動に不信感を持っていた林は、自供するようになり捜査が進むことになる。林は全面自供して事件を明らかにしたことや、悔恨・改悛がみられることから、実行犯の中で唯一無期懲役の求刑・判決となった。 |
| 5月 2日 | 野茂英雄がメジャーリーグ初登板。事前の予想に反して以後大活躍したことから、メジャーは移籍ルールを制定。日本人をはじめ、非アメリカ人のメジャー進出に道を開くことになる。また前年のストライキによるメジャーの人気低迷から人気復活につなげたと言われている。 |
| 5月28日 | ネフチェゴルスク地震。サハリン島北部で発生したマグニチュード7.6の大地震で、ネフチェゴルスク市では高層アパート群が多数倒壊。市民の3分の2に当たる1989名が死亡。市街地は壊滅し、復興を断念する。 |
| 6月 7日 | ボーイング777がユナイテッド航空に初就航。 |
| 6月29日 | ソウルの三豊百貨店のA棟ビルが突如崩壊。512人が死亡し、5人が行方不明、937人が負傷。ずさんな強度設計、鉄筋の削減、フロア改装に伴う柱の撤去に加え、最上階1階分の増設と屋上の給水タンク増設により荷重に耐えられなくなって建物全体が崩壊した。経営者らは前日に天井のひび割れの報告で非常事態に気づいていたが対処せず、崩壊前に逃げ出しており、責任追及が起きて三豊百貨店は倒産に追い込まれることになる。なお最後に救助された女性客は17日間瓦礫に閉じ込められて生存していた。 |
| 7月18日 | カリブ海モントセラトのスーフリエール・ヒルズ山が300年ぶりに噴火。 |
| 7月 | アメリカとイギリスが、ソ連の暗号を解読して情報を入手していたヴェノナ計画の機密情報の一部が公開される。 |
| 8月 5日 | クロアチア紛争で嵐作戦が終了する。クロアチア国内でクロアチアからの独立を宣言したセルビア人の「クライナ共和国」をクロアチア軍が総攻撃、首都クニンなどを占領。 |
| 8月20日 | インドのウッタル・プラデーシュ州フィロザバードで列車衝突事故。午前2時55分頃、牛に衝突した急行列車カリンディ・エクスプレスが故障して立ち往生しているところに、後ろから来た別の急行列車プルショッタム・エクスプレスが衝突。少なくとも358人が死亡する大惨事となる。 |
| 10月 4日 | テレビ東京系列で『新世紀エヴァンゲリオン』放映開始。 |
| 10月 6日 | ペガスス座51番星に太陽系外惑星が発見される。 |
| 11月 4日 | イスラエルのテルアビブでイツハク・ラビン首相が暗殺される。アラブ側との和平を進めたことに反発した保守派のイスラエル青年による犯行。 |
| 11月11日 | スーパーカミオカンデ完成。岐阜県の神岡鉱山にある、ニュートリノを観測する巨大な地下観測研究施設。 |
| 11月22日 | 航空自衛隊小松基地の第6航空団所属のF-15戦闘機2機が、空中戦闘機動訓練のさなかに、一方がサイドワインダーミサイルを誤射、僚機を撃墜する事故が起きる。パイロットは脱出して無事。 |
| 12月 7日 | 木星探査機ガリレオの大気圏観測プローブが木星に突入。57分間に渡ってその大気の状態を観測し消滅。 |
| 12月 8日 | 高速増殖炉「もんじゅ」ナトリウム漏洩事故。 |
| 12月27日 | 東海道新幹線三島駅乗客転落事故。同駅で停車中の新幹線こだま475号で、乗客の高校生が、発車に遅れそうになって乗車しようとしたところ指が挟まれ、抜けないまま発車。高校生は引きずられた上ホームから転落。車両に轢かれて死亡。新幹線初の死亡事故となる。ドアの戸閉検知装置では検知できなかった。 |
| 1996年(平成8年) | |
| 1月31日 | 百武彗星が発見される。彗星で初めてX線の放射が観測される、非常に長い尾を持つ、非常に地球に近い位置を通過するなど独自の彗星。 |
| 2月15日 | 中国西昌衛星発射センターより発射された長征3号Bロケットが、発射直後に進路を逸れて近くの山腹に墜落。大爆発を起こして付近の街を破壊。住民や見学に来ていた人など500人以上が死亡したとも言われるが、公式発表は死者6人。 |
| 2月24日 | 欧州連合とカトリック教会による最後の2月24日の閏日。ローマ以来の伝統と宗教的理由から、2月29日ではなく、2月24日に閏日を設定していたが、この年を最後に29日に改める。 |
| 5月10日 | エベレストで多数の登山家が遭難する事故が起きる。8人が死亡し、複数の重篤な凍傷者を出す。天候の悪化も要因だが、エベレスト登山が商業化し、経験不足の参加者が増えたことや多数の登山チームが集まって渋滞化し下山が遅れたことも大きな要因。 |
| 5月28日 | 岡山県邑久町(現瀬戸内市)の幼稚園と小学校で集団食中毒が発生。腸管出血性大腸菌O157流行の始まり。 |
| 6月26日 | 優生保護法の断種に関する条項が削除され、母体保護法と改められる。 |
| 7月 5日 | 哺乳類で初めての体細胞クローン羊ドリー誕生。 |
| 7月10日 | 京都府八幡市で山口組若頭補佐の中野会会長中野太郎が、会津小鉄会の組員2人に銃撃される。中野は無事、襲った2人は返り討ちにあって射殺される。山口組と会津小鉄会の抗争で起きた事件。事態収拾のため会津小鉄会側から幹部が山口組を訪れ謝罪。山口組No.2の宅見勝がこれに応じて和解が成立するが、中野太郎には一切の相談がなかったため、中野の恨みを買うことになる。翌年の宅見殺害事件の遠因。 |
| 7月13日 | 大阪府堺市の小学校33校で、児童が次々と食中毒症状を訴える出来事が発生。検査の結果O157が検出される。カイワレが疑われて風評被害に。 |
| 7月17日 | トランス・ワールド航空800便墜落事故。ニューヨーク・ジョン・F・ケネディ空港発、パリ・シャルル・ド・ゴール空港経由、ローマ・フィウミチーノ空港行、ボーイング747-100型機が、ケネディ空港から離陸後の上昇中に、ロングアイランド島沖合の上空1万5000フィート付近で爆発。機体前部が離脱して落下し、主翼付近から後方部分がそのまま上昇したあと墜落した。乗員乗客212人全員が死亡。付近で飛行中の複数の旅客機から目撃された。爆弾テロや軍の誤射なども疑われたが、海底から引き上げた膨大な残骸を組み立てて機体を復元した結果、燃料が気化しやすい真夏の条件下で、燃料タンク付近の電気配線の経年劣化による腐食で起きたショートで爆発したと判明。経営の悪化していたトランス・ワールド航空はこの事故で経営改善ができず倒産した。 |
| 7月29日 | 中国が核爆発を伴う最後の核実験を実施。公式には45回行ったと発表している。 |
| 9月26日 | パラオのコロール島とバベルダオブ島を結ぶ橋が突如崩落。2名が死亡、4名以上が負傷。橋は韓国のSOCIO社によって1977年に建設されたが、ずさんな設計が原因で10年ほどしてたわみ始めたことから、補修を繰り返していた。崩落でライフラインも寸断して首都機能が麻痺したため、クニオ・ナカムラ大統領が非常事態を宣言。橋は後に日本の鹿島建設が作り直している。 |
| 11月12日 | サウジアラビア航空763便ボーイング747型機と、カザフスタン航空1907便イリューシンIl-76型機が、インド・ニューデリーのインディラ・ガンディー空港近くの高度1万4000フィートで空中衝突。両機の乗員乗客計349人全員が死亡。同空港を離陸したサウジアラビア航空機が上昇中、同空港へ向かっていたカザフスタン航空機の機長・副操縦士が英語をよく理解できず誤認し、さらに通信士が指示を適切に機長らへ伝えなかったため、誤った高度へと降下。雲中で前方から接近するサウジ機に気づいて上昇を試みたが間に合わず、その数秒後に衝突。サウジ機は空中分解し、カザフ機は失速して墜落した。 |
| 11月21日 | 台湾で桃園県の県長であった劉邦友と側近ら数名が、桃園県公邸で射殺される事件が起きる。犯人は不明。 |
| 11月23日 | エチオピア航空ハイジャック事件。犯人がオーストラリアへ行くよう要求するが、燃料切れでコモロ沖の海上に墜落。乗員乗客175人中123人が死亡。 |
| 12月17日 | ペルーの首都リマにある日本大使公邸で、天皇誕生日祝賀のレセプションが行われているさなかに、武装したトゥパク・アマル革命運動(MRTA)のメンバー14人が突入し、大使館関係者、来賓のペルー政府要人、各国大使、ペルー駐在日本企業の関係者など約600人を人質に取る。 |
| 12月29日 | 36年続き、深刻な人権侵害をもたらしたグアテマラ内戦が終結。 |
| 1997年(平成9年) | |
| 1月 2日 | ロシアのタンカー「ナホトカ号」が隠岐諸島近海で船体が折れて沈没。積載していたC重油約19000キロリットルのうち、約6240キロリットルが流出。各沿岸に漂着して汚染を引き起こした他、沈まなかった船首部分が三国海岸沖に漂着。 |
| 1月16日 | アルバニアで大規模な市民暴動が発生し、8月まで続く。軍による鎮圧などで1700人以上が死亡。暴動の背景は、国内で広がった無限連鎖講(ねずみ講)に多くの市民が関わってしまい、このねずみ講が周辺の紛争国に武器を売却する形で資金が還元されていたことから、紛争終結により破綻したため。ホッジャ独裁政権の鎖国政策で経済犯罪に対する知識がなかった上に経済自体脆弱だった。 |
| 2月23日 | ロシアの宇宙ステーション「ミール」で火災が起こる。 |
| 3月19日 | 東電OL殺人事件発生。 |
| 3月28日 | 国際連合安全保障理事会決議第1101号により、アルバニアに多国籍軍の派遣が決定される。 |
| 7月 1日 | 「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」が施行され、「北海道旧土人保護法」と「旭川市旧土人保護地処分法」は廃止される。 |
| 4月 5日 | 丸ノ内ビルヂングが閉鎖。解体され、超高層ビルへ再開発されることに。耐震基準に引っかかったことも大きな要因とされる。 |
| 4月 7日 | 京浜急行本線の京急田浦-安針塚間でがけ崩れが起き、上り普通電車が突入し脱線。乗員乗客19名が重軽傷。運転士が防護無線を発したことで運行中の電車が停止し、多重衝突は避けられた。 |
| 4月14日 | 白暁燕拉致事件。台湾の人気女優白冰冰と梶原一騎との間に生まれ、台湾でタレント活動をしていた白暁燕が、通学途中に拉致される。事件を嗅ぎつけたマスコミが過剰報道合戦を引き起こす事態になる。 |
| 4月22日 | ペルー日本大使公邸占拠事件でペルーの特殊部隊が突入。MRTAの14人全員が射殺され、人質の最高裁判事1名と特殊部隊隊員2名も死亡。最後まで人質になっていた71名が救出される。 |
| 4月28日 | 白暁燕が遺体で発見される。拉致されてまもなく、強姦された上に殴る蹴るの暴行を受けて死亡したものと見られる。犯人は3人で、金銭目的だったとされる。事件後逃走を図り、さらに複数の誘拐事件を起こす。李登輝政権は射殺も辞さない捜査を厳命。 |
| 4月 | クロアチアの総選挙で、セルビア人が多く住む東スラヴォニア、バラニャ、西スレムなどが、クロアチアへの帰属を決める。 |
| 5月14日 | 初の国際航空連合、スターアライアンスが設立される。創設メンバーは、エア・カナダ、スカンジナビア航空、タイ国際航空、ルフトハンザドイツ航空、ユナイテッド航空。 |
| 5月20日 | 明治製菓とロッテが日本初のキシリトール入りガムを発売。 |
| 6月20日 | 国際電信電話株式会社法の改正により、国際電信電話株式会社(KDD)が国内電話事業に進出することが可能となる。 |
| 6月25日 | カリブ海モントセラトのスーフリエール・ヒルズ山が再び大噴火を起こし、火砕流がモントセラトの首都プリマスを飲み込む。死者20人。プリマスは放棄され、島北部の村ブレイズに事実上の遷都。 |
| 6月25日 | ロシアの宇宙ステーション「ミール」と輸送船プログレスが衝突する事故が起こる。空気が漏れ、緊急ハッチを締めた際に電源ケーブルを破損。 |
| 6月29日 | アルバニア議会総選挙。暴動の原因となったねずみ講を生んだ経済の自由化政策を進めた与党アルバニア民主党が惨敗し、サリ・ベリシャ大統領は失脚。 |
| 7月26日 | フジロックフェスティバルが、山梨県の富士天神山スキー場で開催。天候不順や運営の不慣れさで課題を残す。翌年東京豊洲で行われるが、3回目以降は新潟県苗場スキー場で実施し成功を収めた。2回目以降も名前は受け継いでいる。世界のアーチストが出演する日本を代表する野外音楽フェスとなる。 |
| 8月 1日 | 永山則夫死刑囚の死刑が執行される。 |
| 8月12日 | 東海道本線沼津-片浜間で、踏切支障通報で停止していた第67貨物列車に、無閉塞運転をしていた後続の下り普通列車が運転士の勘違いから加速し追突。43名が重軽傷。 |
| 8月19日 | 白暁燕拉致事件の犯人のうち2人が台北市内で発見され、警官隊との激しい銃撃戦となり、犯人1人が負傷し自殺。2人がさらに逃亡。 |
| 8月28日 | 山口組宅見若頭射殺事件。山口組のNo.2だった宅見勝若頭が、新神戸オリエンタルホテルのラウンジで、同じ山口組系中野会の組員に7発の銃弾を撃ち込まれ死亡。近くにいた無関係の歯科医も流れ弾が当たり9月3日に死亡する。事件は、前年の7月10日に起きた、中野会会長銃撃で、宅見が中野に相談なく会津小鉄との間で和解したことを恨んだため。 |
| 8月25日 | 弘南鉄道弘南線飯田駅で列車交換の待ち合わせをしていた上り列車が、下り列車通過と勘違いして出発してしまい、下り列車と正面衝突。乗員乗客32名が重軽傷。 |
| 9月 7日 | ステルス戦闘機F-22Aが初飛行。第5世代戦闘機に分類され、ステルス性、超音速巡航、STOLの機能を持つ非常に高性能な機体。一方で非常に高額で、冷戦終結という世界情勢の変化もあり、750機の配備計画から大幅に削減され、試験機8機を含む195機の生産に終わった。日本・イスラエル・オーストラリアなどへの輸出計画もあったが機密保持の問題もあり輸出はされていない。 |
| 9月21日 | アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦ヨークタウンが、民生用ソフトウェアを使った試験航行中、バージニア州ケープ・チャールズ沖合で、乗組員がデータベースに0を入力した結果、システムがゼロ除算エラーを引き起こしてダウン。2時間30分にわたって航行不能に陥いる事故を起こす。 |
| 10月12日 | 中央本線大月駅内で、特急「スーパーあずさ13号」に、入換中の通勤電車車両が衝突。特急の乗客77名が負傷。 |
| 10月23日 | 白暁燕拉致事件の犯人2人が、医者ら3人に整形手術を強要した上で殺害。 |
| 11月17日 | エジプトのルクソールにあるハトシェプスト女王葬祭殿の前で、イスラム原理主義組織の「イスラム集団」に属するテロリスト7人が、外国人観光客らを襲撃し、日本人10人を含む61人が殺害される。 |
| 11月17日 | 白暁燕拉致事件の犯人1人が、警官隊との銃撃戦で自殺。 |
| 11月18日 | 白暁燕拉致事件の犯人の最後の1人が、南アフリカ大使館駐在武官官邸に人質をとって立てこもる。翌日投降。1999年10月に処刑された。マスコミによって事態が悪化した典型的な事件。また南アフリカ政府は、翌年台湾と断交し、中華人民共和国と国交を樹立している。 |
| 11月24日 | 株の大暴落と債務飛ばしの粉飾決算で、日銀特融が受けられなくなった山一證券が、経営が立ち行かなくなって自主廃業を決定。 |
| 12月 3日 | 対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(オタワ条約)の署名が行われる。 |
| 12月11日 | 地球温暖化防止京都会議(COP3)で京都議定書が採択される。 |
| 12月12日 | 1944年に撃沈された児童疎開船「対馬丸」が海底で発見される。 |
| 12月19日 | シルクエア185便墜落事故。インドネシアのスカルノハッタ国際空港発、シンガポール・チャンギ国際空港行同便が、インドネシアのスマトラ島パレンバン近郊のムシ川に墜落。乗員乗客104人全員死亡。墜落の原因は確定していないが、ボイスレコーダーが意図的に切られていること、ほぼ垂直に墜落しているが回復の操作をしていないこと、機長の私生活に問題があったことから、機長の自殺の可能性が高い。 |
| 1998年(平成10年) | |
| 1月 | 宝塚歌劇団に宙組が新設される。 |
| 2月14日 | カメルーンの首都ヤウンデで、石油輸送列車が別の貨物列車と衝突し脱線。流れ出た石油をすくって利益を得ようとした貧困住民らが現場に殺到したところ引火爆発し、200人以上が死亡。 |
| 3月23日 | 中国国産の多用途戦闘機J-10(殲撃十型)の原型試作機が初飛行したとされる。 |
| 3月31日 | 日本原子力発電株式会社東海発電所の営業運転終了。日本の商用原子炉で初めての廃炉プロジェクトに入る。 |
| 4月15日 | カンボジアの民主カンプチア政権時代の独裁者ポル・ポトがジャングルの奥地で死亡。タ・モク派に軟禁されており、毒殺されたとも言われる。 |
| 5月11日 | インドが核実験(シャクティ作戦Ⅰ~Ⅲ)を実施。同日、水爆、兵器用原爆、原子炉級プルトニウム原爆の実証実験を3回同時に実施。 |
| 5月13日 | インドが小規模の核実験(シャクティ作戦Ⅳ、Ⅴ)を実施。0.2~0.3Kt。 |
| 5月28日 | パキスタンが初の核実験をチャガイ実験場で実施。最大30~35Kt。 |
| 5月30日 | パキスタンが2回目の核実験をチャガイ実験場で実施。 |
| 6月 3日 | ドイツの高速鉄道ICEでエシェデ鉄道事故が起こる。101人が死亡。 |
| 6月11日 | 土佐くろしお鉄道中村線で、故障して立ち往生した普通車に、救援列車が衝突。38人が重軽傷を負う。 |
| 7月 1日 | 映画『アルマゲドン』アメリカで初公開。 |
| 7月 5日 | 香港の啓徳空港が閉港となる。 |
| 7月 6日 | 香港の新香港国際空港であるチェクラップコク国際空港が開港。 |
| 7月29日 | 国際電信電話株式会社(KDD)が日本高速通信を吸収。 |
| 8月15日 | ガチャピンがロシアの宇宙ステーション「ミール」を訪問。通信障害で放送はされず。 |
| 8月31日 | 北朝鮮が日本海方向へテポドンを発射。第二段部分は日本列島を飛び越え、太平洋に落下。日本は激しく抗議。なお、日本以外では、ミサイル実験ではなく、ロケットによる人工衛星の発射失敗と見ている。 |
| 10月22日 | 日本国有鉄道清算事業団が解散。 |
| 10月29日 | かつて宇宙船フレンドシップ7でアメリカ初の周回飛行を行い、その後民主党の政治家となったジョン・グレンが再び宇宙飛行士として、77歳でスペースシャトルディスカバリー号に搭乗する。 |
| 11月20日 | 国際宇宙ステーションの建設開始。ロシアのモジュール「ザーリャ」がカザフスタンのバイコヌール宇宙基地からプロトンロケットで打ち上げられる。 |
| 1999年(平成11年) | |
| 1月14日 | インドネシアのアルー諸島でキリスト教ととイスラム教徒による宗教紛争が起こる。 |
| 1月19日 | インドネシアのマルク諸島アンボンで、アルー諸島での紛争が波及し、キリスト教ととイスラム教徒による大規模な宗教紛争が起こる。同日、周辺諸島にも拡大し、4000人の死者を出す。 |
| 2月21日 | 目黒区の山手貨物線で保安工事作業中の作業員5名が、臨時回送列車にはねられ死亡する事故が発生。人為的ミスが重なったことによる。 |
| 2月25日 | エチオピア・エリトリア国境紛争で、エチオピア軍のSu-27と、エリトリア軍のMiG-29が空戦する。ともにロシア製で武装もほぼ同じ戦闘機同士の空中戦となった。エチオピア側がエリトリア機を撃墜したとされる。 |
| 3月22日 | 能登半島沖不審船事件。防衛庁の美保通信所が不審な電波を捉え、護衛艦と海上保安庁の巡視船が出動。2隻の不審船を発見。警察が沿岸警戒に当たる。 |
| 3月23日 | 能登半島沖不審船事件。逃走する不審船に対処するため、初めて海上警備行動が発令され、海上自衛隊護衛艦や哨戒機が追跡・威嚇攻撃を行う。日本からの連絡を受けてロシア軍も出動。しかし不審船は北朝鮮方面へ逃走。 |
| 4月20日 | アメリカ・コロラド州ジェファーソン郡のコロンバイン高校で、二人の生徒が銃を乱射。12人の生徒と1人の教師が死亡し、24人の生徒が負傷する事件が起こる。 |
| 5月 1日 | 新尾道大橋、多々羅大橋、来島海峡大橋が完成し、しまなみ海道はすべて架橋される。 |
| 5月13日 | 日本橋が重要文化財に指定される。 |
| 6月 1日 | ソニーのペットロボットAIBOが発売される。 |
| 7月 2日 | 革労協赤砦社派メンバーが、拠点とする明治大学の元生協理事で、敵対する革労協現代社派メンバーを襲撃し殺害。 |
| 7月21日 | 革労協現代社派メンバーが、敵対する革労協赤砦社派の明治大学生協職員を襲撃して殺害。 |
| 7月22日 | 革労協現代社派メンバー37人が、敵対する革労協赤砦社派の拠点であった明治大学生田キャンパスを襲撃するが、赤砦社派は応戦せずに構内から退去したため、取り残された現代社派メンバー全員が駆けつけた機動隊に全員逮捕される。現代社派は大きな打撃を受ける結果となる。 |
| 8月13日 | 国旗及び国歌に関する法律(国旗国歌法)が公布・施行。 |
| 8月17日 | トルコ・イズミット地震。マグニチュード7.6。断層が動いたことによるもので、歴史的にも地震の多い地方。断層が通るマルマラ海では津波も発生。人口が多く、工業地帯での大規模な火災などにより、死者1万7000人~4万5000人の甚大な被害を出す(死者の数は正確には不明)。重軽傷者約4万5000人。 |
| 9月29日 | 下関駅通り魔殺人事件。運送業者の男が自暴自棄になって車で駅構内に突入し7人をはね、更に車を降りて包丁で8人に斬りつける事件を起こす。5人が死亡し10人が重軽傷を負う。精神鑑定で責任能力が認められ死刑判決。後執行された。なお車での被害者には自賠責で保証されたが、刃物による被害者は犯罪被害者等給付金のみ支給されたことから、差額が問題になり、被害者給付金の法改正へと繋がった。 |
| 8月30日 | 東ティモールで、独立の是非を問う住民投票が行われる。将来の独立が決定。 |
| 9月30日 | 東海村JCO臨界事故。核燃料製造のマニュアルに従わず、ステンレス製の大きなバケツ(冷却水に囲まれた沈殿槽)で大量のウラン化合物の溶解作業を行ったため核分裂が起こり、周囲の水が中性子反射材となって臨界に達したため、発生した大量の中性子線を浴びた作業員3人のうち2人が死亡。住民を含む少なくとも667人が被曝した。 |
| 10月11日 | ボツワナのセレツェ・カーマ国際空港で、エアボツワナのパイロットが同社の小型旅客機ATR42を乗っ取って飛び立ち、駐機してあった同社の他のATR機に衝突させ自殺を図る。同社の運行機全てが使えなくなる事態に。 |
| 10月26日 | 桶川ストーカー殺人事件が起こる。警察のあまりにもいい加減な対応や、でたらめなマスコミの報道がのちに大問題になる。 |
| 12月 3日 | サイクロンアナトールがデンマーク、ノルウェーなどに上陸。 |
| 12月20日 | マカオが中国に返還され、澳門特別行政区が発足。 |
| 12月24日 | イギリスにサイクロンクルトが上陸。北海へ出てノルウェー方向へ移動。 |
| 12月25日 | フランスにサイクロンロタールが上陸。東へ移動し、ベルギー、ルクセンブルク、ドイツ、ポーランドまで移動。暴風で110人が死亡。ベルサイユ宮殿とその庭園が大きな被害を受け、フランス全土で大規模な停電となる。 |
| 12月27日 | フランスにサイクロンマーティンが上陸。スイス、イタリア方面へと移動。暴風で30人が死亡。この12月初めから翌1月末にかけて複数の発達した低気圧が西ヨーロッパに相次いで上陸し、大きな被害をもたらした。 |
| 12月31日 | パナマ運河がパナマ政府に返還される。 |
| 2000年(平成12年) | |
| 1月10日 | 多摩都市モノレールの上北台-多摩センター全線が開業。上北台から箱根ヶ崎方面への延伸などの計画は引き続き継続。 |
| 1月30日 | ケニア航空431便墜落事故。ケニア・ナイロビ発、ナイジェリア・ラゴス経由、コートジボワール・アビジャン行431便が、悪天候のため先にアビジャンに降りた後、ラゴスへ向かうため離陸した直後に海に墜落。乗員乗客179人のうち169人が死亡。10人が重症を負う。装置の誤作動で失速警報が出たあと操縦士のミスが重なり、夜間だったために外部の状況がわからないまま海面に激突した。 |
| 2月 8日 | 革労協赤砦社派の福岡拠点で、派遣されてきていた福井大生が、敵対する革労協現代社派の男女メンバー2人に襲われ殺害される。 |
| 2月10日 | 革労協赤砦社派のメンバーが、前日の事件の犯人2人を追跡。2人が熱海駅で寝台列車から普通列車に乗り換えてまもなくの真鶴駅に到着直後に襲いかかり、車内で包丁で滅多刺しにし、男性メンバーが死亡。女性メンバーも瀕死の重傷を負う。襲った側は逃走。 |
| 2月29日 | グレゴリオ暦による400年に一度の閏日、そしてコンピュータの2000年問題が懸念された日。 |
| 3月 8日 | 東京中目黒駅で営団日比谷線の電車が脱線し対向電車と衝突。乗客5人が死亡、60人以上が重軽傷を負う。 |
| 3月12日 | アフガニスタンのイスラム原理主義勢力タリバーンがバーミヤンの大仏破壊に着手。 |
| 3月17日 | ウガンダのカヌングにあるカルト教団「神の十戒復古運動」の施設で、信者530人が閉じ込められて焼き殺される事件が起きる。1999年大晦日で世界は滅びると終末論を唱えて勢力を広げていたが、実際には何も起きなかったため、信者が反発。教団幹部らによって殺害されたと見られる。毒を入れたコーラを使った毒殺もあったという。また各地の教団関連施設でも多数の遺体が見つかり、924人が殺害されたことが判明。当初ともに死亡したとされていた教団創設者のジョセフ・キブウェテーレとクレドニア・ムウェリンデは逃亡している可能性が高い。 |
| 3月18日 | 中華民国総統選挙で民主進歩党の陳水扁が当選。国民党による長期一党独裁政権が終わる。 |
| 3月27日 | 有珠山の付近で火山性地震が頻発。 |
| 3月29日 | 気象庁が有珠山の臨時火山情報を出し、噴火が近いことを予報。周辺住民が避難を開始する。 |
| 3月31日 | 有珠山が23年ぶりに噴火。はじめて完全に予知できた噴火。 |
| 5月 5日 | さいたま新都心が街開き。旧国鉄大宮操車場跡地24.9haなどを再開発。 |
| 5月 7日 | ウラジーミル・プーチンがロシア大統領に就任。 |
| 5月24日 | ストーカー規制法公布。 |
| 6月10日 | 群馬県新田郡尾島町(現太田市)の日進化工群馬工場でヒドロキシルアミンの蒸留塔が爆発。工場従業員4人が死亡、周辺住民30人が重軽傷を負う。爆風で尾島庁舎の窓ガラスが粉砕。爆音が周辺20km圏に響いたという。 |
| 6月26日 | 三宅島で群発地震が始まる。気象庁は緊急火山情報を発令。 |
| 7月 1日 | 三宅島から地震の震源地が移動し、神津島で震度6弱の地震が発生。1人が死亡、15人が負傷。 |
| 7月 8日 | 三宅島雄山で噴火が始まる。雄山の山頂が陥没し、カルデラが生成。 |
| 7月25日 | フランスのシャルル・ド・ゴール空港で、離陸滑走中のコンコルドが、金属片を踏んでタイヤがパンクし、その破片が当たって燃料タンクから出火。すでに離陸速度に達していたことから離陸し、近くのルブールジェ空港に向かうも墜落、ホテルに激突して爆発炎上。地上にいた人も含め113人が死亡。 |
| 8月 3日 | 革労協赤砦社派の女性幹部で明治大学生協職員が、出勤途中の鶯谷駅で、敵対する革労協現代社派のメンバーに襲われ、めった刺しにされて死亡。一連の革労協内ゲバ事件を受け、革労協赤砦社派が拠点にしていた明治大学は、両派の活動の排除を決定し、資金源となっていた最大の学園祭「駿台祭」の廃止も決めた(学園祭は各キャンパス祭で継続)。 |
| 8月10日 | 三宅島雄山にできたカルデラで規模の大きい水蒸気爆発が発生。 |
| 8月18日 | 三宅島雄山が大噴火。火砕サージが発生。 |
| 8月25日 | 三宅島雄山が再度大噴火。火砕流が海岸に達し、住民も飲み込まれるが、幸い温度が40度程度だったため人的被害はなし。火山活動は終息していくが、二酸化硫黄の大量放出が確認されたため、全住民が一時避難。 |
| 8月 | ロシア革命のさなかに殺害された最後のロシア皇帝ニコライ2世がロシア正教によって列聖される。 |
| 9月18日 | アメリカの統合打撃戦闘機計画による、ボーイング社の概念実証機X-32Aが初飛行。ステルス機。無尾翼デルタ型で、機体下部が大きく膨らんだような独特の形状をしている。X-35に敗れて正式採用とはならなかった。 |
| 10月 1日 | DDIと日本移動通信がともにKDDに吸収合併され、現KDDIが誕生。 |
| 10月10日 | 日本政府が、杉原千畝の名誉回復を公式に認める。1940年に外務省の訓令に違反しながら、6000人以上のユダヤ人にビザを発給してその生命を救ったが、そのことを理由に政府・外務省は不名誉な扱いをしていた。 |
| 10月23日 | 沖縄国際海洋博覧会で建設された浮上構造体アクアポリスが、解体のため上海へ曳航される。 |
| 10月23日 | 1989年開業の奈良そごうが売上低迷などにより閉店。長屋王邸の遺跡を破壊して建設開業したことから、長屋王の呪いと称される。 |
| 10月24日 | アメリカの統合打撃戦闘機計画による、ロッキード・マーティン社の概念実証機X-35Aが初飛行。多用途ステルス戦闘機F-35の原型機。 |
| 11月 5日 | 毎日新聞が、考古学研究者藤村新一による遺跡の捏造場面を密かに撮影し、この日の朝刊でスクープ報道。捏造された旧石器時代の遺跡は33ヶ所にのぼり、考古学界始まって以来の大事件に発展する。藤村は他のアジアと比べても古い70万年も前の遺跡を発見したと発表。石器に金属でできた傷があったり、発見される日時が偏っているなど、学問的に明らかにおかしな状況だったにもかかわらず、学界やメディアなどからも「神の手」などと称賛されており、旧石器研究に対する考古学界の検証能力の低さ、学閥体質も問題視されることになる。この事件を受けて東日本の広範囲の遺跡が見直されることとなり、教科書まで書き直される事態となった。その後の研究で、日本列島の遺跡は、現生人類のもので古くても3万年前頃、旧人(デニソワ人など)の旧石器でも12万年前ころまでしか遡れない。 |
| 12月12日 | 都営地下鉄大江戸線が全線開通。 |
| 12月17日 | 京福電鉄越前本線東古市駅で、永平寺線の電車が止まらずに本線に進入し、下り列車と正面衝突。運転士は緊急事態を無線通報した後、乗客に後部への退避を指示したが自身は衝突で死亡した。乗客24名が重軽傷。ブレーキの故障によるもの。 |
| 2001年(平成13年) | |
| 1月26日 | 新大久保駅乗客転落事故。転落した人と、救助しようとした計3名が死亡。緊急列車停止ボタン、ホーム下の避難場所、ホームドアなど、事故防止への取り組みが始まる。 |
| 1月26日 | 韓国地質学会が東シナ海の中韓の間にある蘇岩礁を「離於島」と正式に命名。同暗礁は事実上韓国が支配。なお、「離於島」とは本来は死後に行けるとされる伝説の島の名前。 |
| 1月31日 | 駿河湾上空で日本航空の旅客機同士がニアミス。羽田発那覇行きの907便ボーイング747-400型機と、釜山発成田行き958便DC-10型機が、焼津沖の駿河湾上空で急接近。東京航空交通管制部の管制官2名が907便に回避降下を指示したが、両機の空中衝突防止装置(TCAS)は、907便に上昇、958便に降下を指示。しかしTCASの指示が管制側に伝わらないことや、管制官の便名の間違いなどから、907便は降下を継続。両便のパイロットが目視で事態に気づき、958便は機首を上げ、907便はさらに急降下して、衝突はギリギリで回避された。907便は急降下したため、乗務員や乗客が投げ出されるなどして100名が重軽傷を負い、機内各所が破損。同機は羽田空港へと引き返した。このインシデントの報告は国際民間航空機関(ICAO)に提出されたが生かされることなく、翌年、全く同じ要因からユーバーリンゲン空中衝突事故の大惨事が起きる。 |
| 3月 3日 | スポーツ振興くじ(toto)が全国発売開始。 |
| 3月23日 | 運用終了したロシアの宇宙ステーション「ミール」が大気圏に突入し崩壊、消滅する。 |
| 6月24日 | 京福電鉄越前本線保田-発坂間で上り普通列車と下り急行列車が正面衝突。乗員乗客24名が重軽傷。信号見落としによるもの。半年で2回の正面衝突事故が起きたことを重視した中部運輸局は運行停止を命じ、業務改善命令を出すが、経営状態の厳しかった京福電鉄は越前本線・永平寺線・三国芦原線の廃止を打ち出す事態に発展。10月に廃止届を国土交通省に提出。これが地域交通の麻痺につながったことから、翌年えちぜん鉄道が設立されることとなった。 |
| 6月27日 | ムーミンの原作者で、画家でもあるトーベ・ヤンソンが亡くなる。 |
| 7月25日 | この頃から9月にかけて、インドのケーララ州南部の一部地域で赤や黄色など様々な色のついた雨が繰り返し降る。この色は、雨に含まれていた数マイクロメートルほどの粒子の色で、調査の結果から、地元によく見られる地衣類の胞子が大量発生して雨水に混ざったという説が有力。他にも流星の塵説、砂漠の砂説、火山の粒子説、隕石とともに宇宙から飛来した生物説などもある。 |
| 7月28日 | 小説家山田風太郎が死去。当初は推理小説が中心で、その後、伝奇小説、時代小説、SF、官能小説、戦争小説など多岐に渡った。 |
| 8月 7日 | 写真週刊誌フォーカスが廃刊となる。 |
| 8月29日 | H-IIAロケット1号機が打ち上げられる。 |
| 9月 1日 | 新宿歌舞伎町ビル火災。雑居ビル「明星56ビル」で放火によると見られる火災が発生。同ビル3階と4階の風俗店にいた従業員と客の計44人が一酸化炭素中毒で死亡。逃げ出したゲーム店の従業員3名が負傷。大勢の死者が出たのは、防火扉が閉まらない、火災報知器が機能しない、避難誘導も行われず、避難器具も使えなかったなどが原因。 |
| 9月10日 | 農水省が、千葉県の牛でBSE(牛海綿状脳症・狂牛病)の発生を発表。食した人間にも影響することから狂牛病パニックが起こる。 |
| 9月11日 | アメリカ同時多発テロ。イスラム原理主義勢力にハイジャックされた旅客機による世界貿易センタービル2棟、国防総省への突入、及び、墜落により、死者行方不明者約3000人を出す最悪のテロ事件。アメリカの対テロ戦争が始まるきっかけとなる。 |
| 9月18日 | アメリカ炭疽菌事件(1回目)が発生。マスコミ各社に炭疽菌の入った封筒が送られ1人が死亡。 |
| 10月 9日 | アメリカ炭疽菌事件(2回目)が発生。上院議員2名の事務所に炭疽菌の入った封筒が送られるが、1通は郵便のZIPコードが間違っていたため届かなかった。2回の事件で22人が感染、新聞社員、郵便局員など5人が死亡(2人は感染経路不明)。イスラム原理主義勢力の犯行に見せかけているが、兵器級炭疽菌の生成は知識ときちんとした設備がないとできず、送られた人物が対イスラム強行派ではなくリベラル派だったことから、イスラムに見せかけた国内の保守派による犯行と推定され、アメリカ陸軍感染症医学研究所に勤めていた炭疽菌研究者でキリスト教原理主義者のブルース・エドワーズ・イビンズによる可能性が濃厚となった。ただイビンズは2008年に自殺したため真相は不明なところが多い。 |
| 10月10日 | ソ連のロケット研究者・教育者ヴァシーリー・ミシン死去。コロリョフの右腕で後継者となったものの、進めていた超大型ロケットN-1による月有人飛行計画が失敗に終わり、ロケット技術者の教育の道へと移った人物。 |
| 11月21日 | 北海道でも、BSE(牛海綿状脳症・狂牛病)の発生を確認。マスコミの騒ぎから、責任を感じた獣医師が自殺する事態に発展。 |
| 12月19日 | J・R・R・トールキン作の『指輪物語』を映画化した第1作の『ロード・オブ・ザ・リング』が公開。 |
| 12月30日 | M-1グランプリ第1回決勝戦。 |
| 1939年におきたポーランド住民によるユダヤ人虐殺のイェドヴァブネ事件についてポーランド大統領が謝罪。 | |
| 2002年(平成14年) | |
| 1月11日 | パラオのコロール島とバベルダオブ島を結ぶ新橋が完成。旧橋は1996年に崩落したため、日本の無償援助で再建された。「日本・パラオ友好の橋」(通称KB橋)。 |
| 1月17日 | コンゴ民主共和国の東部にあるニーラゴンゴ山が噴火。大量の溶岩が南麓のゴマ市に達する。市街地の4割程度に被害があり、火山ガスなどで150人余りが死亡、35万人が避難を余儀なくされる。溶岩は二酸化炭素が大量に溶存しているキヴ湖に接近。キヴ湖に溶岩が入れば、大規模な湖水爆発を引き起こし、200万人が被害に遭うとされたが、幸いに溶岩は直前で停止した。 |
| 1月28日 | 高松塚古墳の修復を担当していた担当者が2回、誤って壁画を損傷。公表せず密かに修復する。のち壁画がカビに覆われていることが判明した際に発覚。 |
| 1月29日 | アメリカ合衆国のジョージ・ウォーカー・ブッシュ大統領が、一般教書演説で北朝鮮・イラク・イランを「悪の枢軸(axis of evil)」と名指しで指摘。 |
| 2月14日 | 人間以外で初めて、ロボットのASIMOがニューヨーク証券取引所のスタートベルを鳴らす。 |
| 2月17日 | イギリスとスペインの係争地となっているイギリス領ジブラルタルで演習を行っていたイギリス海兵隊の部隊が、誤ってすぐ北隣のスペイン領ラ・リネアの海岸に上陸。地元警察の指摘で気付き、部隊はすぐに撤収し、イギリス政府は正式にスペイン政府に謝罪。 |
| 3月31日 | 台湾大地震。建設中の超高層ビル台北101の建設現場の高さ250mからクレーンが落下。5人が死亡する。ビル自体に問題はなく、のち完成。 |
| 4月 1日 | フィンランドの凄腕のスナイパーだったシモ・ヘイヘ(スィモ・ハユハ)が死去。96歳。冬戦争に参加し、わかっているだけで542人のソ連兵を射殺し白い死神と恐れられた(実際の射殺人数はそれ以上とも。スナイパーとしては史上最多)。左顎を撃ち飛ばされて重症を負い引退。戦後は猟犬のブリーダーとして暮らした。 |
| 5月 7日 | 中国北方航空6136便放火墜落事件。北京首都国際空港発、大連周水子国際空港行のMD-82型機機内で、乗客の男が放火し、それが原因で操縦不能となり大連沖の海上に墜落。乗員乗客112人全員が死亡。放火した男は事業に失敗し、自身に多額の保険をかけており、自殺することで負債に当てようとしたもので、乗員乗客はその巻き添えを食った。 |
| 5月 8日 | 在瀋陽日本国総領事館に、北朝鮮からの亡命者が駆け込み、後を追ってきた中国武装警察の警官が、許可なく敷地内に入り、亡命者を取り押さえる事件が起きる。領事は前日の中国北方航空6136便放火墜落事件に日本人3人が巻き込まれたことの対応で出張しており、応対に出た副領事らが武装警察官に抗議せず友好的態度を見せたことや、阿南惟茂駐中国特命全権大使が、亡命者を追い出すよう指示していたことなどが問題となる。亡命者5人は後に韓国への出国が認められた。 |
| 5月20日 | 東ティモールが独立。実態はインドネシアの占領からの独立だが、国際法的には旧宗主国ポルトガルからの独立。 |
| 5月28日 | 経済団体連合会(経団連)と日本経営者団体連盟(日経連)が統合して日本経団連が発足。 |
| 5月31日 | サッカー日韓ワールドカップ(第17回FIFAワールドカップ)開催。 |
| 6月 6日 | ギリシャのクレタ島とリビアの間の地中海上空で大規模な火球が目撃される。大気圏に突入した小惑星が起こした爆発と考えられる。 |
| 7月 1日 | ユーバーリンゲン空中衝突事故。ドイツ南部のユーバーリンゲン上空で深夜、ロシア・モスクワ発スペイン・バルセロナ行きバシキール航空チャーター便Tu-154M型機と、バーレーン発イタリア・ベルガモ経由ベルギー・ブリュッセル行きDHLボーイング757型貨物機が空中衝突。衝突コースに入ってしまった両機の空中衝突防止装置(TCAS)は正常に作動していたが、同地方の航空管制を行っていたスイスの民間会社スカイガイドの管制官はチャーター機側に回避降下の指示を出したため、そのあと上昇の指示を出したTCASには従わずチャーター便は降下、一方DHL機はTCASの降下指示に従ったため、両機は直前に気づいて回避行動を取ったが間に合わず衝突。DHL機の垂直尾翼がチャーター機を分断、チャーター機は空中分解して墜落し、尾翼を失ったDHL機も急降下して地上に激突した。チャーター機には、ユネスコの招待でバルセロナに向かっていたロシア・バシコルトスタンの子供45名と家族の計60名と乗員9名が乗っていたが全員死亡。DHLの乗員2名も死亡した。スカイガイド社が規律に反し1人で担当する勤務体制にあったことや、当日設備の修理などで管制がうまく行っていなかったのが大きな要因で、同社も最終的には責任を認めたが、管制を担当したスカイガイド社のニールセン管制官は、2004年2月24日に、事故で妻子を失った建築士のカロエフによって刺殺された。この事件は後に複数映画化されている。同じようなニアミス事故が前年に日本で起きていたが、その報告が生かされなかった。 |
| 7月27日 | リヴィウ航空ショー墜落事故。ウクライナのリヴィウ近郊のスクヌィーリウ空軍基地で開催された航空ショーにおいて、曲技飛行を行っていたウクライナ空軍チーム「ウクライィーンスィキ・ソーコルィ」のスホーイSu-27UBが急降下中に滑走路に接触、輸送機に衝突したあと、観客席に突入炎上。操縦士2人は脱出するが、観客77名が死亡、543名が重軽傷を負う大惨事となる。主原因はパイロットのミス。 |
| 8月 5日 | 住民基本台帳ネットワークが起動。 |
| 9月 6日 | 丸ノ内ビルヂングの解体跡地に超高層化された丸の内ビルディングが完成。 |
| 9月17日 | 日朝首脳会談。北朝鮮の金正日総書記が日本人拉致を認める。一方で認めたのは工作機関の独断とし、拉致も一部のみ。北朝鮮と友好関係を持ち、その主張を無条件に受け入れ、拉致問題をでっち上げと主張していた社民党に衝撃が走る。 |
| 9月25日 | アメリカ軍の偵察衛星がシベリア・イルクーツク州の上空で発生した火球を観測。彗星の核が大気圏に突入して爆発したものと考えられる。 |
| 10月 8日 | ノーベル物理学賞にニュートリノ天文学を開いた小柴昌俊東京大学名誉教授とペンシルベニア大学のレイモンド・デイビス・ジュニア教授が選ばれる。 |
| 10月 9日 | ノーベル化学賞に島津製作所の社員、田中耕一が選ばれる。 |
| 10月15日 | ロシアのプレセツク宇宙基地から打ち上げられたソユーズロケットが、発射直後にエンジンが正常に作動せず、発射を中止。ロケットは基地内に墜落し爆発。地上にいた1人が死亡、8人が負傷。科学実験用のフォトンM1衛星を打ち上げる予定だった。 |
| 10月23日 | ロシア軍と内戦状態になっていたチェチェンの独立派テログループ42人が、モスクワのドブロフカ・ミュージアム劇場を占拠。 |
| 10月26日 | ドブロフカ・ミュージアム劇場に特殊部隊スペツナズが突入し、犯人全員を殺害。その際に、無力化ガスで人質129人も死亡。 |
| 10月27日 | 成田空港敷地内を通るミニ私鉄、芝山鉄道東成田-芝山千代田間が開業。路線距離は滑走路より短い。 |
| 11月 1日 | 国営沖縄記念公園の美ら海水族館が開館。 |
| 11月 8日 | 国連安全保障理事会がイラクの武装解除を求める決議1441を全会一致で採択。 |
| 11月21日 | メキシコの麻薬カルテルの中でも、特に凶悪とされる「ロス・セタス」の創設者アルトゥーロ・グスマン・デセーナが軍によって射殺される。26歳。 |
| 11月24日 | 地球から1435光年のオリオン座に「オリオン座S星70」が発見される。初めて発見された自由浮遊惑星(T型褐色矮星)。質量は木星の3倍程度と小さすぎて核融合が起きず、恒星になれなかった星。 |
| 12月 5日 | ビルマ(現ミャンマー)の独裁者だったネ・ウィンが死去。推定92歳。戦時中日本軍南機関の指導で独立運動に関わり、1962年から1988年まで独裁政権を率いてきた。権威主義的独裁者と異なり、自らは表に出ず、黒幕として活動した。非同盟中立主義で、先進諸国では日本とのみ交流をもっていた。社会主義経済政策には失敗し、ビルマを最貧国に転落させた。また国民を武力で弾圧したことでも知られる。 |
| 12月18日 | 指輪物語の映画化第2作『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』公開。 |
| 2003年(平成15年) | |
| 1月22日 | パイオニア10号との通信が途絶する。太陽から82.1天文単位(太陽から約123億km)地点。 |
| 2月 1日 | 帰還中のスペースシャトル、コロンビア号が空中分解。打ち上げ時に剥落した外部燃料タンクの断熱材がオービターの翼に当たり、出来た傷から大気圏突入時に高温の空気が入り込んで内部から機体が崩壊した。 |
| 2月 1日 | えちぜん鉄道が開業。事故を受けて廃止された京福電鉄の福井県内3線のうち、越前本線を改めた勝山永平寺線と、三国芦原線を引き継ぐ形となる。なお京福電鉄時代から廃止が取り沙汰されていた永平寺線はそのまま廃止。 |
| 2月14日 | 体細胞クローン羊ドリー、ヒツジ肺腺腫で死亡。死後剥製となる。 |
| 2月18日 | 韓国大邱市地下鉄放火事件。火災の中、駅に入ってきた列車に類焼し、むしろそちらのほうが被害が大きくなる。死者192名、重軽傷者148名を出す大惨事に。火災が迫ってるのに乗客が逃げ出そうとしなかったとして「正常性バイアス」という言葉が広まった。 |
| 2月19日 | イランのケルマーンにあるケルマーン国際空港に着陸しようとしたイラン革命防衛隊のイリューシン76型輸送機が、郊外の山中に墜落。乗員と兵士の計275人全員が死亡。 |
| 3月 7日 | スペインの研究者らによって準惑星のハウメアが観測される。観測データを元に発見されたのは2005年。なお2004年にもアメリカのグループが観測・「発見」しており、1955年のスカイサーベイの写真にも写っている。 |
| 3月19日 | アメリカとイギリスが、イラクの自由作戦を開始。イラク戦争開戦。 |
| 3月28日 | 日本初の情報収集衛星「光学1号機」「レーダ1号機」打上げ。 |
| 5月 9日 | 小惑星探査機はやぶさ、内之浦より打ち上げ。 |
| 5月23日 | 個人情報保護法成立。 |
| 6月 6日 | 武力攻撃事態対処関連3法が国会で可決成立。初の有事法制。 |
| 7月12日 | カリブ海モントセラトのスーフリエール・ヒルズ山が大噴火。モントセラト島の南半分は1995年以降の3度の噴火で甚大な被害を受け、エクスクルージョンゾーンとして放棄される。 |
| 7月12日 | ロシアのスタブロポリで、キャビア密輸の捜索を担当していた警察猫のルーシクが、任務中に車にはねられ死亡。密輸に関わっていたものの犯行とも言われている。 |
| 8月 2日 | 日本最初の人工衛星「おおすみ」が33年にして大気圏に突入して消滅。 |
| 8月23日 | ブラジルのマラニョン州にあるアルカンタラロケット発射場で、ブラジル宇宙機関が開発したVLS-1ロケットの1段目が突如点火して爆発。21人が死亡。ブラジルの国産ロケット開発は大幅に遅れることとなった。 |
| 8月24日 | 地球近傍小惑星2003 QQ47が発見される。その発表の際に2014年3月21日に25万分の1の確率で地球に衝突する可能性があると報道されたことがマスコミに大げさに取り上げられたため、天体衝突のリスクに関するトリノスケールの表記が書き換えられる事態に発展。実際にはかなり遠くを通過するため衝突の可能性はほぼゼロだった。直径が1.24kmと地球近傍小惑星では比較的大きい天体。 |
| 9月 9日 | 物理学者エドワード・テラー死去。アメリカの水爆開発を強力に推進した人物で「水爆の父」と呼ばれる。最後まで水爆開発については肯定的だった。 |
| 9月21日 | アメリカの木星探査機「ガリレオ」が木星の大気に突入して消滅。機能停止した探査機が、生物がいる可能性のあるエウロパに落下しないよう調整した結果。 |
| 10月 1日 | 東海道新幹線に品川駅が設置される。 |
| 10月 1日 | 宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所、宇宙開発事業団の3機関が統合して一本化され、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が誕生。 |
| 10月10日 | 佐渡のトキ保護センターで飼育されていた最後の1羽キンが死んで、日本のトキは絶滅。 |
| 10月15日 | 中華人民共和国が、有人宇宙船「神舟5号」の打ち上げに成功する。史上3カ国目。 |
| 10月24日 | ブリティッシュ・エアウェイズがコンコルドによる営業飛行を終了し、コンコルドは全機引退。 |
| 11月 4日 | 大規模な太陽フレアが発生し、電磁波などが地球圏に到達。 |
| 11月14日 | 太陽系外縁天体の一つ「セドナ」が発見される。赤い色をして、公転周期は11809年、直径1000km程度の比較的大きな天体。 |
| 11月26日 | コンコルドの最後の飛行。 |
| 12月 1日 | 指輪物語の映画化第3作『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』公開。 |
| 12月13日 | イラク戦争で、米軍がダウルに潜伏中のフセイン大統領を拘束。 |
| 12月24日 | 韓国で映画『シルミド』が公開。韓国国内で映画の元ネタである実尾島事件の調査を求める動きが起こる。 |
| 2004年(平成16年) | |
| 1月 3日 | フラッシュ航空604便墜落事故。エジプトのシャルム・エル・シェイク発、カイロ経由、フランスのシャルル・ド・ゴール空港行604便、ボーイング737-3Q8型機が、離陸直後に海に墜落。乗員乗客148人全員死亡。操縦士の誤操縦と空間識失調が原因。問題のある航空会社の「EU域内乗り入れ禁止措置」が設定されるきっかけとなった。フラッシュ航空はこの事故が原因で倒産。 |
| 2月18日 | イランのニーシャープールのアブー・ムスリム駅に停車していた化学物質を満載した貨物列車が暴走し、20km離れたハイヤームの村で脱線。火災が発生したため、地元のレスキュー隊や、住民、政府職員らが集まって救助活動を始めたところ、積荷が爆発。ハイヤームは完全に破壊され、付近の3つの町も大きな被害を出す。死者はわかっているだけで295人、負傷者多数を出す。 |
| 3月15日 | ジョージア(グルジア)中央サアカシュヴィリ政権と、分離独立を目指すアジャリア自治共和国アバシゼ政権との間で対立が激化。 |
| 3月17日 | セルビアのコソボ自治州で、セルビア人とアルバニア系コソボ人との間で暴動が起こる。多数の古いセルビア正教系の教会が破壊される。一方、セルビアでもイスラム教の施設が破壊される。 |
| 4月 1日 | 戦時下で設立された特殊法人、帝都高速度交通営団が廃止され、東京地下鉄(東京メトロ)に事業が受け継がれる。 |
| 4月22日 | 北朝鮮龍川の龍川駅で、硝酸アンモニウムを積載した列車が爆発。駅周辺500m四方を吹き飛ばし少なくとも161名(うち小学生76名)が死亡。最大で3000人ともいわれる負傷者を出す。硝酸アンモニウムと石油を積んだそれぞれの貨車同士が作業ミスで衝突し、倒れた電線がショートして爆発したというのが公式発表。直前に金正日総書記の乗った列車が通過しているためテロ説も出たが、専用列車の通過に伴うダイヤの混乱等が原因で起きた事故説もある。北朝鮮から兵器級プルトニウムの提供を受ける予定でいたシリアの核技術者が巻き込まれ全員死亡したという話もある。 |
| 5月 2日 | アジャリア自治共和国アバシゼ政権が、ジョージア(グルジア)とつながる境界の橋を爆破して交通を遮断。ジョージアのサアカシュヴィリ政権が最後通告。一触即発の事態に。 |
| 5月 5日 | アジャリア自治共和国のアバシゼ議長がロシアの勧告を受けて辞任し出国。ジョージア(グルジア)中央政府が同地域を掌握し紛争は終結。 |
| 6月 2日 | 東京台東区三ノ輪にある革労協赤砦社派拠点前で、同派メンバー3人が、敵対する革労協現代社派メンバーに襲撃され、2人が死亡。これ以降、革労協内部の凄惨な内ゲバ事件はほぼ収まっている。 |
| 6月14日 | 国民保護法など有事関連7法が可決成立。 |
| 6月20日 | 高松塚古墳壁画がカビなどでひどく破損していることが朝日新聞によって報道される。この時点で関係者には知られていたが一般には発表されていなかった。 |
| 7月30日 | 千葉県九十九里町の「九十九里いわし博物館」で大規模な爆発があり、職員1人が死亡、1人が重症を負う。建物は大破。爆発の原因は、地下の南関東ガス田から出てきた天然ガスが空調配管を通って室内に充満し、無色無臭で気づかなかった職員が殺虫用燻煙剤に点火したところ引火したため。 |
| 8月13日 | 沖縄のアメリカ海兵隊、普天間基地所属の大型ヘリコプター、シコルスキーCH-53Dシースタリオンが、訓練飛行中に、沖縄国際大学の敷地に墜落。同大1号館北側に接触し大破する。パイロットら3人が重軽傷を負うも、休暇中で職員や学生に被害はなし。普天間基地返還運動が広がる。 |
| 10月 4日 | 民間宇宙船スペースシップワンが、民間の有人宇宙飛行を競うAnsari X Prizeを達成。 |
| 12月13日 | ジャスダック証券取引所業務開始。 |
| 12月24日 | アメリカ航空宇宙局(NASA)は、この年たびたび観測された地球近傍小惑星アポフィスが、2029年4月13日に地球に非常に接近し、衝突する可能性が300分の1であると発表。同日、確率62分の1に修正し、はじめてトリノスケール4(天文学者が注意を払うべき天体で、衝突した場合広域の破壊がもたらされる可能性が1%以上)とされる。後の観測結果から確率は下がる。 |
| 12月26日 | スマトラ大津波。アンダマン・ニコバル諸島付近を震源とするマグニチュード9.1のスマトラ沖地震で、巨大津波がインド洋沿岸を襲う。死者行方不明者は22万7898人。 |
| 12月31日 | 世界一高いビル台北101が台湾台北に開業。尖塔高509.2mと初めて500mを超えた。 |
| 2005年(平成17年) | |
| 1月14日 | 欧州宇宙機関とNASAが共同で行った土星探査計画の土星探査機「カッシーニ」が衛星タイタンに惑星探査機ホイヘンス・プローブを着陸させる。メタンの大気、地上の風景、風の音、メタンの雨が降っていること、メタンやエタンの川が流れている場所があることを確認。 |
| 2月15日 | YouTubeが設立される。 |
| 2月 | おとめ座銀河団の中に、全く恒星が存在しないにも関わらず銀河サイズの天体VIRGOHI21(乙女座中性水素21cm線天体)が見つかる。ダークマターで出来た暗黒銀河の可能性が指摘されている。 |
| 3月 3日 | テキサススーパーノバサーチによって観測史上最大光度の超新星爆発が発見される。距離にして地球から47億光年。クォーク星の候補とされている。 |
| 3月 6日 | 愛知万博に合わせて日本初の実用磁気浮上式リニアモーターカー「リニモ」開業。 |
| 3月 8日 | 南アフリカの行政首都プレトリア市議会が、市の名称をツワネに変更することを決議。プレトリアはオランダ系移民アフリカーナーのアンドリース・プレトリウスの名前から、ツワネは先住民ンデベレ族の首長の名前から来ている。ただし自治体名としての変更で、行政首都の通称名としてはプレトリアで呼ばれることも多い。 |
| 3月15日 | 東武伊勢崎線竹ノ塚駅踏切事故。職員が電車接近の中、手動式踏切の遮断器を上げたことで通行人4人が準急電車にはねられ死傷。 |
| 3月25日 | 愛知万博開園。 |
| 4月 1日 | 決済性預金を除くペイオフ解禁。 |
| 4月 2日 | ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が死去。世界中を訪問して反戦を訴え、他の宗教との和解も促進し、教会の過去の罪についても謝罪し、教会によって異端とされた人々の名誉回復を図った。一方、教会内部の改革に関しては保守的で、女性聖職者を認めず、中絶や安楽死を非難し、前教皇ヨハネ・パウロ1世が進めようとした宗教事業協会(通称「バチカン銀行」)の改革も行わず、マフィアのマネーロンダリングなどに利用された。2011年5月1日に列福、2014年4月27日に列聖。 |
| 4月 8日 | ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の葬儀が行われる。生前各国を訪問したこともあり、世界各国から弔問に訪れ、弔問外交も盛んに行われる。一般弔問は200万人にも達した。 |
| 4月25日 | 兵庫県尼崎市の福知山線(JR宝塚線)の7両編成の通勤電車が、速度超過状態で塚口駅と尼崎駅の中間のカーブに差し掛かったところで脱線・転覆し、線路そばのマンションに激突大破。運転士1名を含む乗員乗客107名が死亡、562名が重軽傷を負う。 |
| 4月28日 | 映画版『銀河ヒッチハイク・ガイド』公開。 |
| 5月 9日 | イギリスのカンブリア州セラフィールドにあるソープ核燃料再処理工場で、高レベル放射性溶液が大量に漏洩していたことが公表される。漏洩は前年の7月ころから始まっており、2005年4月19日まで気づかれてなかった。外部への漏洩は無し。 |
| 7月29日 | 冥王星クラスの天体「2003 UB313」が発見されたことが公表される。のちエリスと名付けられる。その大きさから惑星の定義論争を引き起こす。2003年に撮影された画像に写っていたことから発見につながった。 |
| 8月 6日 | ギネス・ワールド・レコーズにも記載された記録上最長命のメス猫クリーム・パフが死去。アメリカ・オースティンで1967年に生まれ、死んだときの年齢は38歳だったという。 |
| 9月 1日 | セブンイレブンジャパン、イトーヨーカドー、デニーズジャパンの株式を移転し、あらたに持ち株会社を設立。セブン&アイ・ホールディングスが誕生。 |
| 9月12日 | 小惑星探査機はやぶさ、小惑星イトカワの上空20kmに到着。 |
| 9月20日 | サイモン・ヴィーゼンタール死去。ホロコーストの生存者で、戦後はナチス戦犯を追い続け、1100人以上の逮捕に関与したとして知られる。 |
| 9月25日 | 愛知万博終了。 |
| 10月22日 | ベルビュー航空210便墜落事故。ナイジェリアのラゴスから、首都アブジャに向かうため離陸した同機が、まもなく空港の近郊に墜落。乗員乗客117人全員死亡。高速で地上に衝突したが原因は不明。ただ会社の安全体制の不備、機長の勤務状況などが問題視された。 |
| 10月23日 | 菊花賞でディープインパクトが無敗の三冠達成。シンボリルドルフ以来2頭目。 |
| 11月20日 | 小惑星探査機はやぶさ、小惑星イトカワに着陸。 |
| 11月23日 | 国連開発計画アフリカ局長だったエレン・ジョンソン・サーリーフが、リベリア大統領選挙で勝利し、アフリカ初の選挙による女性大統領となる。 |
| 11月26日 | 小惑星探査機はやぶさ、再び小惑星イトカワに着陸し、微粒子サンプルを収納して離陸。 |
| 12月 8日 | 小惑星探査機はやぶさ、姿勢が不安定になり消息不明となる。 |
| この年、アンゴラでマールブルグウイルスによる感染症が広がり、374人が感染し、329人が死亡する。 | |
| 2006年(平成18年) | |
| 1月16日 | ライブドア・ショック。東京地検特捜部が証券取引法違反容疑(決算報告の有価証券報告書虚偽記載など)で六本木ヒルズのライブドア本社を捜索。 |
| 1月19日 | 冥王星探査機「ニュー・ホライズンズ」がアトラスロケットで打ち上げられる。 |
| 1月23日 | 行方不明となっていた小惑星探査機はやぶさから送られてくるビーコンを受信。 |
| 1月23日 | ライブドア・ショック。ライブドアの堀江貴文社長ら4人が逮捕。ライブドア関連株が急落。 |
| 2月16日 | 衆議院予算委員会で「堀江メール問題」事件が起こる。民主党の議員が証券取引法違反で取調べ中の堀江貴文ライブドア社長が出したとされるメール(実際は偽物)にだまされて、自民党を追求した事件。 |
| 2月16日 | 神戸市のポートアイランドの沖合に神戸空港が開港。 |
| 3月23日 | インド・コルカタのアリポア動物園で飼われていたアルダブラゾウガメのアドワイチャが死亡。同動物園に贈られたのが1875年であり、また1760年代半ばにベンガル知事だったイギリス人ロバート・クライブ男爵に飼われていた記録があるため、250年以上生きていたとみられる。 |
| 3月26日 | ファッションデザイナー小篠綾子死去。コシノ三姉妹の母親でもある人物。 |
| 3月27日 | ミャンマー政府が国軍記念日のパレードを新首都で行い、新首都の名前をネーピード(王都)と命名したことを発表。 |
| 3月 | AIBOの生産が終了する。 |
| 4月20日 | 北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河線の営業が終了する。 |
| 4月23日 | ブルーノ事件。シエラレオネで保護区から脱走していたチンパンジーの群れが現場を通りがかって事故を起こしたタクシーを襲撃し、運転手を殺害。乗客のシエラレオネ人が重傷、アメリカ人3人も軽症を負う。チンパンジーの群れはかつて商品として捕まり母猿を殺され、その後保護されたブルーノと呼ばれる個体に率いられており、ブルーノは身長が180cmを超える規格外の大きさで人間に育てられたことからか知能も高く、保護区の錠を外して逃走していた。地元民を優先的に襲ったことから、母を殺され売り飛ばされた小猿時代の恨みを抱えているという俗説も広がった。グループのチンパンジーの多くは保護区に戻ったり捕まったりしたが、ブルーノはいまも行方不明。 |
| 4月29日 | 富山ライトレール開業。富山市内を走るJR西日本のローカル路線を改良した新しいタイプの路面電車。 |
| 6月14日 | 金融商品取引法公布。 |
| 6月22日 | チャールズ・ダーウィンがガラパゴス諸島から連れて帰ったとされたゾウガメのハリエットがオーストラリア動物園で死亡。推定175歳。ダーウィンが訪れたことがないサンタクルス島のサンタクルスゾウガメとみられることから、ダーウィンと関係ないという説もある。 |
| 7月12日 | ポーランドの石油資源探索会社ペトロバルティックが、バルト海の海底に沈んでいる航空母艦を発見。 |
| 7月26日 | ポーランド海軍がバルト海の海底に沈んでいる大型艦が旧ドイツ軍の空母グラーフ・ツェッペリンと確認。 |
| 8月 7日 | 兵庫県丹波市山南町の篠山川河床の篠山層群より、ティタノサウルス「丹波竜」が発見される。 |
| 8月24日 | チェコのプラハで国際天文学連合総会が開かれ、惑星の定義が定められる。これにより惑星、準惑星、その他の太陽系内小天体があらたに分類され、冥王星は惑星から外されて準惑星となり、太陽系9惑星時代が終わる。 |
| 8月 | 俳優の緒形拳が、番組の取材で潜水調査船「しんかい6500」に搭乗し沖縄近海に潜る。 |
| 9月13日 | 太陽系の外縁を回る天体2003 UB313をエリスと命名する。 |
| 9月16日 | スポーツ振興くじ(toto)に、ランダムで14試合の結果を当てるBIGが登場。 |
| 9月18日 | 観測史上最大規模の超新星SN 2006gyを観測。ペルセウス座方向の銀河NGC 1260内、距離にして2億3800万光年。元は太陽の約150倍の質量をもつ超巨星だったとされ、電子と陽電子の対生成を伴う対不安定型超新星爆発だったと考えられている。 |
| 9月20日 | フランスのワイン醸造家アンリ・ジャイエが死去。戦後広まった化学農薬の使用を抑制し、ブドウ畑の土壌改良を推進、発酵を遅らせて醸すコールド・マセレーション(低温浸漬)法を発明しブルゴーニュワインの発展に貢献した人物。ブルゴーニュの神様とも呼ばれた。 |
| 10月 2日 | 高松塚古墳壁画の解体修復作業が始まる。 |
| 10月21日 | クリント・イーストウッド監督の硫黄島プロジェクト『父親たちの星条旗』がアメリカで初公開される。 |
| 11月19日 | 任天堂の据え置き型ゲーム機「Wii」が北米で発売開始。直感的コントローラーで大ヒットとなる。 |
| 11月 6日 | ニューヨーク・マンハッタン島の海上航空宇宙博物館として86番桟橋に係留されている航空母艦イントレピッドを改修・修繕するために移動させようとしたが、ハドソン川の浚渫が足りず座礁事故が起きる。12月5日に離礁に成功し無事ドック入りとなった。 |
| 12月 9日 | クリント・イーストウッド監督の硫黄島プロジェクト『硫黄島からの手紙』が日本で初公開される。その後アメリカなどでも公開。 |
| 12月13日 | 長江に生息していた淡水のイルカの一つ、ヨウスコウカワイルカが「絶滅」と認定される。 |
| 12月21日 | 世界で最初に体外受精で生まれた女性ルイーズ・ジョイ・ブラウンが、自然妊娠した男の子を無事出産する。 |
| 12月24日 | ディープインパクトが有馬記念を最後に引退。最後のレースも圧勝。翌年から種牡馬に。父サンデーサイレンスも子孫に多数の名馬を残したが、ディープインパクトはその上をゆく数々の名馬を国内外で残している。 |
| 12月25日 | 広島タクシー運転手連続殺人事件の犯人に死刑が執行される。1996年に、広島市内でタクシー運転手の男が、相次いで女性4人を殺害し、遺体を遺棄した事件。 |
| 12月27日 | フランスの太陽系外惑星探査用宇宙望遠鏡COROTがカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられる。 |
| 12月29日 | 東シナ海の蘇岩礁の側にある大きな暗礁「丁岩礁」(中国名)を韓国の海洋水産部が伝説の島「波浪島」から「波浪礁」と命名。 |
| 2007年(平成19年) | |
| 1月 5日 | 台湾高速鉄道(いわゆる台湾新幹線)が板橋駅-左営駅で営業を開始。 |
| 1月11日 | 中国が中距離弾道ミサイルを改良した衛星攻撃兵器で、自国の気象衛星風雲1号Cを破壊するテストを実施。大量のデブリが軌道上へ飛び散る事態に。衛星破壊実験はアメリカに続き2例目。 |
| 2月22日 | ノルウェー政府の提案で、クラスター爆弾を禁止する話し合い「オスロ・プロセス」会議が開かれる。 |
| 2月23日 | 志布志事件で無罪判決。警察による選挙法違反のでっち上げによって、住民が違法に捜査され逮捕された事件。 |
| 4月17日 | 長崎市長選のさなかに、現職の市長が暴力団幹部に銃撃され死亡。選挙運動妨害ではなく、個人的恨みとされている。 |
| 4月17日 | アメリカ・バージニア工科大学銃乱射事件。教授、学生及び犯人の計33名が死亡。犯人は韓国籍の同大学学生で、韓国で大きな衝撃が走る。 |
| 4月19日 | 丸の内の「新丸ノ内ビルヂング」を解体して再開発した超高層ビル「新丸の内ビルディング」が竣工する。 |
| 4月24日 | エチオピア東部のオガデン地方で反政府独立運動を行う、オガデン民族解放戦線が、同地で資源探査をしていた中国国営のシノペック(中国石油化工集団公司)の施設を襲撃。中国人9人と、警備をしていたエチオピア軍兵士ら65人を殺害。中国人7人を拉致する。 |
| 4月25日 | 小惑星探査機はやぶさの地球帰還へ向けた巡航運転を開始。 |
| 5月 5日 | ケニア航空507便墜落事故。乗員乗客114人全員死亡。コートジボワールのアビジャン発、カメルーン経由、ケニア・ナイロビ行の同機が、カメルーンのドゥアラ空港を離陸直後に機体が傾き、そのまま空港近郊の湿地帯に墜落。同機はドゥアラの管制官の許可を得ずに離陸しており、操縦士が自動操縦装置切替と手動操縦を同時に行ったことや、操縦士と副操縦士のトラブル、夜間で空間識失調により機体の状態を把握するのが遅れたことなど、様々な要因で墜落したとみられる。 |
| 5月13日 | 初のPFI方式の刑務所、美祢社会復帰促進センター開所。 |
| 5月25日 | ドイツのバーデン=ヴュルテンベルク州ハイルブロン市で、駐車場で休憩していた2人の警察官が銃撃され、女性警官が死亡、男性警官が重症を負う事件が起きる。のちに<全ヨーロッパ規模で様々な事件を起こした謎の人物「ハイルブロンの怪人」>によるものと誤認された前代未聞の捜査ミス事件の始まり。実際の犯人は移民などを襲撃していたネオナチによるもの。 |
| 6月19日 | 東京渋谷区の会員制温泉施設「松濤温泉シエスパ」で別棟が大爆発を起こす。従業員3人が死亡、従業員2人と通行人1人が重傷、数名の軽傷者を出す。爆発の原因は地下から温泉を汲み上げた際に出たメタンガスが設備の問題で排出されずに溜まり、温泉組み上げ装置の制御盤の火花で引火したためとされる。 |
| 7月31日 | 兵庫県豊岡市で、一度は絶滅した国内の野生のコウノトリが、46年ぶりに巣立ちをする。 |
| 8月 1日 | アメリカ・ミネアポリスを通る州間高速道路I35号W線のミシシッピ川に架かる橋が崩落。60台の車が転落し、少なくとも13人が死亡・行方不明、100人以上が負傷する。 |
| 8月12日 | アメリカ・マサチューセッツ州スターリングの、童謡「メリーさんのひつじ」のエピソードのもとになったとされるメリー・エリザベス・ソーヤーの生家(アメリカ合衆国国家歴史登録財)が放火で焼失。1756年に建築された建物だった。 |
| 8月16日 | 埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市で最高気温40.9℃を観測し、74年ぶりに日本最高記録を更新。 |
| 8月23日 | 海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦ひゅうが型一番艦「ひゅうが」が進水。基準排水量13950t(満載19000t)。全通甲板を持つ初のヘリ空母。 |
| 9月14日 | 月の探査を行なう月周回衛星かぐやがH2Aロケットで打ち上げられる。 |
| 9月15日 | ペルー・プーノ県カランカス村の標高3800m付近の湿地帯に隕石が落下。付近の土壌にヒ素化合物が含まれていたため、熱で有毒の水蒸気が発生し、駆けつけた住民600人以上が被害に遭う。 |
| 10月15日 | エアバスA380がローンチカスタマーのシンガポール航空に納入される。 |
| 10月25日 | シンガポール航空に納入されたエアバスA380が商業飛行を開始。 |
| 2008年(平成20年) | |
| 1月21日 | アラスカ中南部で話されていたイヤック語の最後の話者マリー・スミス・ジョーンズが死去。固有語の消滅を危惧し、国連で訴えたり、イヤック語の辞書作成にも協力した。 |
| 1月 | 劉慈欣の小説『三体』が発刊。2006年に雑誌『科幻世界』に連載されたSFで、英訳版が出たあと全世界で大ヒットする。地球往事三部作の第一作。 |
| 2月13日 | オーストラリアのケビン・ラッド首相が、「アボリジニ」と「盗まれた世代」に対して初めて公式に謝罪。盗まれた世代とは、政策として親から隔離され虐待されたアボリジニの子供たち。 |
| 2月21日 | アメリカが、制御不能になった偵察衛星を、イージス艦から発射したSM-3ミサイルで破壊。 |
| 3月10日 | チベット自治区ラサ市で暴動が起こり、チベット騒乱が始まる。チベット族と漢族、回族が衝突。治安部隊が投入される。多数の犠牲者と逮捕者を出す。 |
| 3月16日 | チベット騒乱で、治安部隊が暴徒を強制鎮圧。四川省アバ州では、ラサ暴動の影響で、チベット族と回族と中国治安部隊が三つ巴で衝突。多数の犠牲者を出す。 |
| 3月19日 | うしかい座の方角で過去最大のガンマ線バーストGRB 080319Bが観測される。直後に作家アーサー・C・クラークが死去したことから、「クラークイベント」と呼ばれる。5.8等級に達し肉眼で見えた唯一のガンマ線バーストで、実距離が103億6000万光年あるため、肉眼で最も遠くに見えた星になった。3週間以上も残光が輝く。 |
| 3月19日 | イギリスのSF作家アーサー・C・クラーク死去。SF三大作家の一人(他はアシモフ、ハインライン)。科学者でもあり科学的作品や、人類の進化を描いた作品が多い。空軍時代にレーダー早期警戒システム構築に関わる。静止衛星による通信ネットワークを考案しており、静止軌道はクラーク軌道とも呼ばれる。「クラークの三法則」でも知られる。英国惑星間協会会長。メンサ会員。ナイトの称号授与。 |
| 4月16日 | 海上自衛隊の新型の南極観測船(砕氷艦)の艦名を先代に続き「しらせ」とすることが宣言され進水式が行われる。 |
| 5月28日 | ネパール王制廃止。共和制へ移行。 |
| 5月30日 | アイルランドの首都ダブリンで開かれたオスロ・プロセス会議で、クラスター爆弾に関する条約が参加107ヶ国の全会一致で採択される。 |
| 6月21日 | フィリピンのシブヤン島沖のシブヤン海で、マニラからセブ島へ向けて航行中の大型客船プリンセス・オブ・ザ・スターズが台風による荒天の中、高波を受けて転覆沈没。乗員乗客825名のうち死者行方不明者773名を出す。農薬エンドスルファンを大量に積んでいたことが判明し捜索が中断したことも死者数に影響。 |
| 7月 7日 | フランスボレーヌのトリカスタン原子力発電所で、ウラン溶液貯蔵タンクから1万8000リットルのウラン溶液が溢れて地上に流れ出し、付近のガフィエール川とロゾン川を汚染。職員約100名も被爆。 |
| 7月15日 | アメリカのユタ試験場で、大型爆弾BLU-82デイジーカッターの最後の1発が使用される。ベトナム戦争や湾岸戦争などでも使われた爆風爆弾で、後継爆弾としてMOABが導入される。 |
| 8月15日 | ハワイのイオラニ宮殿を「ハワイ王国」を名乗る20人ほどが占拠する事件が起こる。 |
| 8月20日 | スパンエアー5022便離陸失敗事故。スペインマドリード=バラハス発、カナリア諸島グラン・カナリア行MD82型機が、離陸した瞬間に右に傾き、そのまま地面に激突。爆発炎上して、乗員乗客162人のうち154人が死亡、18人が重症を負う。生存者が川で見つかっていることから死者の多くは焼死か。離陸時に主翼のフラップやスラットが動かなかったのが原因だが、乗員による作動チェックの形骸化も問題となった。 |
| 9月10日 | 未知の素粒子を発見するための、CERN(欧州原子核研究機構)の大型ハドロン衝突型加速器(LHC)が稼動。実験でブラックホールが生成するのではないかと騒ぎになる。 |
| 9月15日 | サブプライムローン問題で、アメリカ証券大手リーマン・ブラザーズが連邦破産法11条の適用を申請して倒産。いわゆるリーマン・ショック。 |
| 9月28日 | アメリカの民間企業スペースX社が開発したロケット「ファルコン1」の打ち上げに成功。 |
| 10月 7日 | スーダンのヌビア砂漠上空37kmで大気圏に突入した小天体2008 TC3が爆発四散。航空機などから目撃される。地球の大気圏に衝突する20時間前に発見され、観測できた初めての天体となる。直径はおよそ2m~5m。地上で発見された破片は、アルマハータ・シッタ隕石と名付けられた。 |
| 10月 9日 | 地球近傍小惑星2008 TS26が地球から12500km付近を通過したことで発見される。計算上では推定直径が84cmしかないもっとも小さな小惑星の一つ。 |
| 10月22日 | インドの国産月探査機「チャンドラヤーン1号」が打ち上げられる。 |
| 11月28日 | 日本政府、クラスター爆弾の廃棄を決定。 |
| 12月 3日 | 日本政府、クラスター爆弾禁止条約に署名。 |
| 12月14日 | 新幹線0系の運用が終了。 |
| 2009年(平成21年) | |
| 1月15日 | USエアウェイズ1549便事故。ニューヨークのラガーディア空港を離陸した旅客機がバードストライクによりエンジンがすべて故障。機長のとっさの判断でハドソン川に不時着水。犠牲者は出さずに済む。 |
| 1月20日 | 第44代アメリカ大統領にバラク・オバマが就任。アメリカ初の黒人大統領。 |
| 2月 1日 | ヨハンナ・シグルザルドッティルがアイスランドの首相に就任。世界で最初の「同性婚をした首脳」でもある女性。 |
| 2月11日 | ロシアの運用を終えていた軍事衛星コスモス2251と、イリジウム社の運用中の通信衛星イリジウム33が、ロシアのタイミル半島上空高度789kmで衝突。両衛星とも大破し大量のデブリを生成。意図せずして起きた衛星同士のはじめての衝突事故。 |
| 3月27日 | ドイツ警察は、ハイルブロン市で起きた警察官殺害事件を含む、ヨーロッパ各国で起きた殺人事件・麻薬事件など40件の事件現場遺留品から見つかった共通のDNAを元に広域捜査していた謎の犯人「ハイルブロンの怪人」が、実は検査に使う綿棒に付着していた綿棒製造業者従業員のDNAを検出していただけだったと公表。一連の事件に関連性はなく、「ハイルブロンの怪人」も存在していなことが明らかとなった。この結果を受けて国際規格「ISO 18385」が誕生。科学研究で起きるコンタミネーションが注目されるようになった。 |
| 4月 5日 | 北朝鮮が弾道ミサイルに転用可能な大型ロケット「銀河2号」を発射。 |
| 4月13日 | メキシコ南部オアハカ州で、新型インフルエンザの感染を確認。 |
| 4月24日 | WHO(世界保健機関)が新型インフルエンザH1N1亜型のヒトヒト感染を確認断定。 |
| 6月 4日 | 石川県七尾市で空からおたまじゃくしが降ってくる現象が起きる。マスコミが取り上げ、他にも全国各地で目撃例が出て大騒ぎになる。鳥が吐き出したもの、という説が有力で、騒動は1ヶ月ほどで終息。降ってくるはずのないものが降る現象をファフロツキーズ現象と呼び、古代から記録は多いが、水生生物の落下に関してはそれほど珍しい現象ではない。 |
| 6月11日 | 月の探査を行なう月周回衛星かぐやが月面へ落下。観測を終える。 |
| 6月11日 | WHO(世界保健機関)が新型インフルエンザをフェーズ6(パンデミック)に指定。 |
| 6月25日 | マイケル・ジャクソンが死去。 |
| 7月 1日 | 公共広告機構がACジャパン(ADVERTISING COUNCIL JAPAN)に改称する。政府機関という誤解を払拭するため。 |
| 7月11日 | 東京お台場の潮風公園内に建造された実物大のガンダム・モデルが一般公開。GREEN TOKYO ガンダムプロジェクトの一環。 |
| 7月16日 | トムラウシ山遭難事故。悪天候となり10名が死亡。真夏だったが死因は全員低体温症。ガイドの対応ミスが被害を大きくした。 |
| 7月17日 | 飛鳥山公園モノレールが開業。東京北区の観光地「飛鳥山」にバリアフリーのために作られた全長48mのミニモノレール。法律上はエレベーター。 |
| 7月19日 | 木星の南半球の表面に長さ8000kmの黒い模様が出現。その後の調査で大きさ約500mのヒルダ群の小惑星が衝突した跡と考えられる。 |
| 8月21日 | 海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦ひゅうが型2番艦の「いせ」が進水。 |
| 8月25日 | バラク・オバマを大統領に推したアメリカ民主党の有力者、エドワード・ケネディ上院議員が病死。 |
| 8月30日 | 第45回衆議院議員総選挙。麻生政権下で行われ、自由民主党が大敗、民主党が圧勝して衆議院で第一党となり、民主党政権が誕生。 |
| 8月 | タレントの中川翔子が、番組の企画で潜水調査船「しんかい6500」で深海に潜る。 |
| 9月11日 | H-IIBロケット初号機打ち上げ。国際宇宙ステーションへの物資輸送船HTVを搭載。HTVは無事ステーションとのドッキングに成功。 |
| 11月10日 | リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件で、逃亡中だった市橋達也容疑者を逮捕。 |
| 11月30日 | 朝鮮民主主義人民共和国でデノミネーション(通貨切り替え)が実施されるも、10万ウォンを上限にしたため、国民が反発。失敗に終わる。朴南基労働党計画財政部長が責任を取らされ処刑される。 |
| 12月15日 | 様々なトラブルで開発が遅れていたボーイング787が初飛行。 |
| 2010年(平成22年) | |
| 1月 4日 | 世界一高い超高層ビル「ブルジュ・ハリファ」がアラブ首長国連邦のドバイに開業。高さは828.0m。台北101(尖塔高509.2m)を追いぬく。 |
| 1月 4日 | 二重被爆者として初めて認定された山口彊が死去。長崎の三菱造船の技術者だったが、広島へ出張中に被爆し、長崎に戻った直後に再度被爆した。戦後は通訳、技術者として生活しながら、核兵器廃絶を訴えた人物。 |
| 1月29日 | ロシアのステルス多用途戦闘機Su-57の原型試作機T-50が初飛行。 |
| 3月10日 | 国松警察庁長官狙撃事件が午前0時に公訴時効。警視庁公安部が記者会見で、オウム真理教によるテロと断定し、識者の批判を浴びる。 |
| 4月 3日 | セネガルのヴェルデ岬にアフリカ・ルネサンス像が完成する。制作は北朝鮮の万寿台海外開発。高さ50mの巨大な像の建設を巡って、その資金の出処などが論争となる。 |
| 4月10日 | ロシア・スモレンスクでポーランド空軍Tu-154型機が墜落。ポーランド大統領レフ・カチンスキら政府・軍部の要人96人が死亡。 |
| 4月27日 | 日本で刑事訴訟法改正法が公布・施行され、公訴時効が廃止される。 |
| 6月 4日 | 鳩山由紀夫内閣総辞職。対米外交に失敗し、全面返還を主張していた普天間基地返還を自民党時代の日米合意に準じて辺野古移転に決めたため、反発した社民党離脱による連立崩壊が最大の原因。 |
| 6月13日 | 小惑星探査機はやぶさ、60億kmの旅を終えて大気圏へ突入。本体は高温により分解。切り離したサンプルカプセルも大気圏へ突入し、無事オーストラリア・ウーメラに不時着する。 |
| 6月16日 | シベリア抑留者に特別給付金を支給する「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」(シベリア特措法)が成立し、施行される。ただし施行日以前に死亡したものは対象外。 |
| 7月 3日 | オグリキャップが転倒で複雑骨折し、安楽死にされる。 |
| 7月22日 | 1976年に起こった唐山大地震を描いた映画『唐山大地震』が公開され、中国で大ヒット。 |
| 8月 5日 | チリのコピアポ鉱山で落盤事故が発生。地下700mのシェルターに33人が取り残される。 |
| 8月22日 | チリのコピアポ鉱山の落盤事故で、地下700mのシェルター付近までドリルで掘ったところ、そのドリルに「33人全員無事」のメモが取り付けられ、生存が判明する。 |
| 9月 7日 | 尖閣諸島中国漁船衝突事件。 |
| 10月 3日 | ドイツ、第一次世界大戦のアメリカに対する賠償金を払い終える。 |
| 10月 8日 | 中国の民主活動家で投獄中の劉暁波がノーベル平和賞を受賞。 |
| 10月13日 | チリのコピアポ鉱山落盤事故で地下700mに閉じ込められた33人の救出が始まる。 |
| 11月 4日 | 政府の一部関係者のみ閲覧となっていた尖閣諸島の漁船衝突事件の映像が海上保安官の手でYouTubeに流出。情報漏洩問題に発展するが、国民は政府が閲覧を規制していたことに対し反発。 |
| 11月 4日 | カンタス航空32便エンジン爆発事故。インドネシアのバタム島上空を飛行中のカンタス航空32便エアバスA380型機(ロンドン発チャンギ経由シドニー行)の左翼第2エンジンが爆発。主翼や胴体も破損したが墜落せずシンガポールのチャンギ空港へ引き返し着陸。操縦系統の破損で第1エンジンが止まらず、火災消火後、エンジン強制停止まで5時間かかったが、乗員乗客に死傷者はなく、破片の落下した民家などでも死傷者はなかった。潤滑油漏れによる発火で強度が落ちたタービンが破損したものでエンジンの製造ミスが原因。 |
| 12月 4日 | 東北新幹線の内、最後の未開業区間だった八戸駅~新青森駅が開業。 |
| 12月 9日 | 中国が、劉暁波へのノーベル平和賞受賞に対抗して創設した孔子平和賞の授賞式が行われるが、受賞者である台湾の連戦国民党名誉主席が受賞を拒否したため、授賞式では無関係の少女が代理で賞を受け取る。 |
| 12月17日 | イギリスBBCのクイズ番組で、二重被爆者だった山口彊を世界一運の悪い男と揶揄する場面が放送される。 |
| 12月17日 | チュニジアで露天で青果を売ろうとした貧困の青年モハメド・ブアジジが警察に取り締まられた上、暴力を振るわれ、賄賂を要求されたことから、県庁前で焼身自殺をはかり病院に収容される。これが翌年の革命のきっかけとなる。 |
| 12月26日 | M-1グランプリが第10回で終了。 |
| 2011年(平成23年) | |
| 1月 4日 | チュニジアで前年末の12月17日に警察の取締に抗議して焼身自殺を図ったモハメド・ブアジジが収容先の病院で死亡。 |
| 1月 5日 | チュニジアで、前日に死亡したモハメド・ブアジジの葬儀を警察が阻止したため、民衆が反発。チュニジア全土へ抗議のデモが拡大。いわゆるジャスミン革命の始まり。 |
| 1月11日 | チュニジアの首都チュニスで暴動。「アラブの春」として各国へと波及。 |
| 1月13日 | チュニジアのベン・アリー政権が、政治犯の釈放や物価の引き下げ、失業対策を約束するが、暴動は拡大。 |
| 1月14日 | ジャスミン革命でベン・アリー大統領がチュニジアを脱出。政権崩壊。 |
| 1月17日 | 前年12月に放送されたBBCのクイズ番組で二重被爆者の山口彊を揶揄したことを、在英日本大使館が抗議。その後、BBCや番組制作会社が謝罪する。 |
| 2月 1日 | ヨルダンのサミール・リファーイー内閣が総辞職。 |
| 2月 2日 | 大相撲の野球賭博問題の捜査から、八百長が発覚。 |
| 2月 6日 | 相撲協会が臨時理事会を開き、平成23年3月場所の中止を決定。地方巡業、伊勢神宮と靖国神社の奉納相撲も中止や延期に。 |
| 2月11日 | エジプトのムバラク政権が倒壊。ムバラク一族はシナイ半島のシャルム・エル・シェイクに脱出。 |
| 2月22日 | ニュージーランド・カンタベリー地震。クライストチャーチのカンタベリーテレビの入ったビルが倒壊。同ビルに入っていた語学学校に留学していた日本人が多数巻き込まれ、日本人28人を含む185人が死亡。 |
| 3月11日 | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)発生。東日本の広範囲で震度5強~7の大きな揺れを観測。また10m~40mに達する巨大津波が青森、岩手、宮城、福島、茨城の各県を襲い(津波自体は日本全海岸および太平洋沿岸国で観測)、直接の死者・行方不明者は1万8425人、重軽傷者6157人。この他に震災関連死(避難所での環境悪化などによる)が3700人以上いる。40万4893戸が全半壊流出。2万8612隻の漁船が被害を受ける。経済被害は16兆円~25兆円。大津波による電源喪失で福島第一原子力発電所の冷却機能が停止。 |
| 3月12日 | 九州新幹線鹿児島ルートが全線開業する。 |
| 3月12日 | 福島第一原子力発電所の1号機核燃料がメルトダウン。7時頃、菅直人首相が福島第一原発を視察するも、これがさらなる対応の遅れにつながったとされる。15時36分頃、1号機水素爆発。建屋の上部が崩壊する。海水とホウ酸の注入が行われる。 |
| 3月13日 | 福島第一原子力発電所の3号機の圧力弁開放に成功。真水、海水、ホウ酸の注入を行う。周辺の放射線の数値が上昇。 |
| 3月14日 | 福島第一原子力発電所の海水冷却が中断。11時過ぎ、3号機が爆発、建屋崩壊。電力関係者、自衛隊員など11人が負傷。放射線の数値が高まる。 |
| 3月15日 | 関東各地で、福島第一原子力発電所から出たものと思われる放射性物質による放射線を観測。4号機で火災。 |
| 3月17日 | 福島第一原子力発電所3号機へのヘリからの放水、および地上からの放水が始まる。 |
| 3月19日 | 福島第一原子力発電所5・6号機の電源機能回復による冷却が再開。 |
| 3月20日 | 福島第一原子力発電所4号機への放水開始。 |
| 4月17日 | 19日にかけてソニーのPSNがクラッカーとみられる何者かに不正侵入されて膨大な情報が漏洩。 |
| 4月 | 焼肉店で病原性大腸菌O111が流行、24人が発症し4人が亡くなる。生肉の規制問題に発展。 |
| 5月 2日 | 米海軍特殊部隊が、パキスタンの首都郊外アボッターバードで国際テロ組織アルカイダのリーダー、ウサーマ・ビンラーディンを殺害と発表。 |
| 5月21日 | アイスランドのグリムスヴォトン山が大規模噴火。西ヨーロッパの広範囲に大量の噴煙が流れる。 |
| 5月 | ヨーロッパ各国で病原性大腸菌O104が流行し50人を超す死者を出す。 |
| 7月 9日 | 南スーダンがスーダンから独立。 |
| 7月20日 | ナチ党副総統ルドルフ・ヘスの墓標が遺族と教会関係者によって撤去される。ネオナチのシンボルにされることを警戒したため。 |
| 8月 6日 | イギリスのロンドンで、黒人男性が警察官に射殺されたのをきっかけに、若者らの暴動が起こり、全土へ拡大。 |
| 8月24日 | リビアの首都トリポリが反政府軍の手で陥落。カダフィ政権が倒壊。カダフィは逃走。 |
| 9月 7日 | ヤク・サービス9633便墜落事故。ロシアのプロアイスホッケーチーム「ロコモティフ・ヤロスラヴリ」がチャーターしたYak-42型機が、ベラルーシのミンスクへ向けてヤロスラヴリ近郊のトゥノシナ空港を離陸するも、上昇せずに進入灯に衝突。そのまま前方のヴォルガ川支流トゥノシナ川岸に墜落。乗員乗客45人中44人が死亡。副操縦士のミスでブレーキをかけた状態で滑走し、かろうじて離陸したが揚力が得られず墜落したとみられる。 |
| 9月23日 | 「国際研究実験OPERA」の国際研究チームが、人工ニュートリノ1万6000個を、スイス・ジュネーブのCERNから約730km離れたイタリアのグラン・サッソにあるイタリア国立物理学研究所研究施設に向かって飛ばしたところ、2.43ミリ秒後に到着し、光速より60.7ナノ秒速いことが計測される。1万5000回をおこない、ほぼ同じ結果となったため、特殊相対性理論を覆す物理学上の重大な問題であるとして、この結果を公表し、世界中の学者に再検証を求める。のち計測機器の誤りとされた。 |
| 9月24日 | 人工衛星UARSの地球落下騒動が起こる。 |
| 9月28日 | 2010年に中国がノーベル平和賞に対抗して創設した孔子平和賞が、突如廃止と発表される。初代受賞者の連戦台湾国民党名誉主席が受賞拒否したため、受賞者なしのまま消滅(のち復活してプーチン首相に贈られる)。 |
| 10月16日 | ケニア軍がソマリア南部に軍事侵攻。ソマリア南部で勢力を拡大していたテロ組織アル・シャバブを掃討するのが目的。軍事作戦は翌年5月まで継続。 |
| 10月20日 | リビアの独裁者だったカダフィ(ムアンマル・アル=カッザーフィー)が潜伏していたスルトをリビア国民評議会軍に攻撃されたため、車列で脱出を試みたが、フランス・アメリカ両軍の空爆を受けたため、排水管に逃れたところを発見され引きずり出された後殺害される。殺害の経緯は諸説あり確定していない。カダフィの5男も同時に殺害された。 |
| 10月25日 | 冷戦時代アメリカの大型核兵器の象徴とも言えたB53熱核爆弾の最後の1発が解体される。主に戦略爆撃機に1発、もしくはICBMタイタンⅡに単弾頭で搭載され、核出力は9Mt。350発が製造された。 |
| 10月31日 | ユネスコの総会で、国連で加盟を拒否されたパレスチナの加盟が認められる。 |
| 11月15日 | ブータンの第5代国王ジグミ・ケサル・ナムゲル・ワンチュクとジェツン・ペマ王妃が、結婚後初の外遊で日本を訪れ、福島の被災地を訪問。多くの市民の歓迎を受ける一方、歓迎の宮中晩餐会を、内輪の民主党のパーティを優先して欠席した一川保夫防衛大臣や晩餐会前の立食パーティの席上で携帯電話を触っていた蓮舫行政刷新担当相のマナー違反が批判を浴びる。 |
| 2012年(平成24年) | |
| 1月13日 | イタリアトスカーナ州ジリオ島近海海上で地中海クルーズの客船コスタ・コンコルディア号が島に接近しすぎて座礁転覆。事故原因と事故直後の船長の行動が問題となり、避難誘導が遅れたこともあり、乗客3276人と、1023人の乗組員の計4299人のうち30人が死亡、2人が行方不明となる。 |
| 1月21日 | エジプトで11月から行われていた議会選の最終結果が確定し、ムスリム同胞団傘下の自由公正党が235議席(全体の約47%)を獲得し第一党となる。 |
| 2月 6日 | 重慶市副市長の王立軍が成都のアメリカ総領事館に駆け込む亡命申請事件が発生。 |
| 2月 7日 | 王立軍亡命申請事件で、米中は協議の結果、中国政府が王立軍の身の安全を保証することで、王立軍の身柄引き渡しで合意。ところが、この事件が、前年11月に発生した英国人実業家不審死事件の捜査に絡んで起きたことが判明。重慶市長薄熙来の妻による英国人殺害、および薄熙来の汚職事件へと展開することに。 |
| 2月29日 | 東京スカイツリーが竣工。高さ634mは、自立式電波塔としては世界一、現存建造物としては世界二位の建物となる。 |
| 3月 4日 | ロシア大統領選挙が行われ、第一回投票でウラジーミル・プーチン候補が6割を越える得票で当選する。任期は2018年まで。 |
| 3月 4日 | コンゴ共和国の首都ブラザビルのウエンゼにある軍の弾薬庫で、電気系統のショートから戦車砲弾に引火、火災となり、5回の大規模な爆発を引き起こす。周辺の住宅街を爆風が襲い多数の建物が倒壊。火災は市街地へと広がり、少なくとも250人が死亡、2315人が重軽傷を負う。政府は爆発事故であると公表、戦争や反乱、クーデターではないことを説明し、市民に落ち着くよう訴える。またコンゴ川を挟んだ対岸のコンゴ民主共和国の首都キンシャサにも爆風は到達。戦闘による可能性を警戒して軍が出動する騒ぎに。 |
| 3月21日 | マリで軍事クーデターが勃発。軍部が首都バマコを制圧。北部トゥアレグ族の反乱に対応できない政権打倒と軍の強化が目的。各国が非難し制裁決議。この混乱でトゥアレグ族のアザワド解放民族運動が攻勢を強める。 |
| 4月 1日 | ミャンマー議会補欠選挙。アウンサンスーチー率いる国民民主連盟(NLD)は同氏を含む44人の候補者を擁立し、同氏を含む40人が当選。 |
| 4月 2日 | アメリカ・カリフォルニア州オークランドのオイコス大学で、韓国籍の学生コ・スナムが銃乱射事件を起こし、学生7人が死亡、3人が負傷する。 |
| 4月 6日 | 混乱するマリでトゥアレグ族のアザワド解放民族運動がマリの北半分を領土とするアザワド独立宣言を発表。クーデターを起こした軍部は事態収拾のため、ディオンクンダ・トラオレ国会議長に権限移譲を決定。クーデターで地位を追われたトゥーレ大統領が正式辞任して政権が交代し民政に戻る。 |
| 4月11日 | 北朝鮮で金正恩が朝鮮労働党の第一書記に就任。 |
| 4月14日 | 新東名高速道路御殿場JCT─浜松いなさJCT開通。 |
| 4月16日 | 渡米中の石原東京都知事が尖閣諸島の都による購入を発表。 |
| 5月21日 | 日本を含む北太平洋地域、中国、アメリカなどで金環日食を観測(アメリカなどでは20日になる)。 |
| 5月22日 | 東京スカイツリー開業。 |
| 5月26日 | マイアミゾンビ事件。マイアミで、全裸の男が別の男の顔に噛みつき、駆けつけた警察官に射殺されるまで被害者の顔の大部分を食いちぎり続けた。被害者は重症を負ったものの助かった。猟奇的犯行に及んだ要因として、当時アメリカで流行っていたドラッグ「バスソルト」の影響だと報道されたが、後に否定された。 |
| 6月 3日 | ダナ・エア992便墜落事故。ナイジェリアの首都アブジャのンナムディ・アジキウェ国際空港発、同国ラゴスのムルタラ・モハンマド国際空港行、MD83型機がムルタラ・モハンマド空港に着陸する直前、空港手前の住宅地に墜落し大規模な火災となる。乗員乗客153人全員が死亡。原因は両エンジンに供給する燃料パイプの損傷による停止。操縦士らの対応にも問題があった。ダナ・エアは一時運行証明書を取り消された。 |
| 7月 4日 | 欧州合同原子核研究機構(CERN)は新たな粒子を発見したと発表。後にヒッグス粒子と判定。 |
| 7月20日 | アメリカコロラド州オーロラの映画館でバットマンシリーズの新作上映中に、作中のシーンに合わせる形で銃乱射事件が発生。死者12人、重体者10人、負傷者48人を出す。 |
| 7月23日 | 大規模な太陽フレアが発生。1859年9月1日の大規模フレアとほぼ同規模と見られ、放出された膨大な電磁波や物質は地球軌道に達したが、わずかの時間差で地球を外れたと言われる。もし地球に直撃していた場合、大規模な電力網やコンピュータネットワークの断絶につながり、生産も社会体制も電気やコンピュータに依存していること、復旧までに長時間を要するため、19世紀に逆戻りするほどの大被害を出したとも言われる。 |
| 7月27日 | 第30回夏季オリンピック・ロンドン大会開催。8月12日まで。 |
| 8月 6日 | NASAの火星探査機キュリオシティが火星に着陸。 |
| 8月10日 | 李明博韓国大統領が竹島(独島)に上陸。歴代大統領で初めて。日本政府反発。 |
| 8月14日 | 李明博韓国大統領が天皇陛下に対し、「痛惜の念などという単語ひとつを言いに来るのなら、訪韓する必要はない」「天皇が韓国に来たければ、独立運動家に心から謝罪せよ」と発言。日本で竹島上陸以上の反発を買い、日韓関係は過去にないほど悪化する。 |
| 8月16日 | 香港の保釣行動委員会の活動家らが尖閣諸島に接近。7人が上陸し、船に残ったものも含めて逮捕される。翌日強制送還。 |
| 8月19日 | 「日本の領土を守るため行動する議員連盟」と「頑張れ日本!全国行動委員会」が参加者を募って 尖閣諸島戦時遭難事件の慰霊祭を現地で行い、10人が魚釣島に上陸。逮捕はされず。 |
| 8月25日 | ボイジャー1号が太陽から約190億kmの地点でヘリオポーズに達し、人工物として太陽圏を離脱した初めての人工物となる。星間物質を観測。 |
| 8月29日 | パラリンピックロンドン大会開催。9月9日まで。 |
| 8月 | 大阪市阿倍野区で建設中の超高層ビル「あべのハルカス」が300mに達し高さ日本一の超高層ビルとなる。 |
| 9月 4日 | 薔薇戦争のボズワースの戦いで戦死した国王リチャード3世の遺体を探す「リチャード3世を探してプロジェクト」で、記録から推定されたイングランドのレスターにある修道院跡地の調査で見つかった30代の男性の遺骨を発掘。その後の分析で場所や遺体の状況、DNA検査などから、リチャード3世と確定。シェイクスピアの作品で悪人として描かれたことから、その名誉回復も兼ねて遺体の行方が調査された。 |
| 9月11日 | 日本政府が尖閣諸島を地権者から20億5千万円で購入。 |
| 9月11日 | リビアの東部ベンガジにあるアメリカ領事館を暴徒が襲い、クリストファー・スティーブンス米大使と職員3人の合計4人が殺害される。同日、エジプトのカイロでもアメリカ大使館が群集に襲われる。こちらは死傷者は出なかった。アメリカでイスラム教の開祖ムハンマドを非難する映画が公開されたことに対する反発で起こった事件。 |
| 9月14日 | 中国政府の公船6隻が同時に尖閣諸島周辺の領海に侵入する。 |
| 9月15日 | 中国各地で反日デモが発生。官製デモの様相だったが暴動に発展し、日本企業の工場、スーパーが襲われて略奪され、日本車が襲撃されて乗っていた中国人が重軽傷を追う。前後して日本人にも複数の負傷者が出る。 |
| 9月27日 | 韓国慶尚北道亀尾にある工業団地のヒューブグローバル社の工場で移送中の毒性の強いフッ化水素酸8tが漏出。5人が死亡し、4000人以上が健康被害を受ける。 |
| 10月 8日 | iPS細胞を開発した山中伸弥医学博士のノーベル生理学・医学賞受賞が決定する。 |
| 10月 9日 | ブログなどでターリバーンの恐怖政治を批判し、女性教育のために活動していたパキスタンの少女マララ・ユサフザイがターリバーンとみられる男たちに銃撃されて頭部に銃弾を受け瀕死の重症を負う。のちイギリスへ移送され奇跡的に回復。 |
| 10月26日 | Microsoft Windows 8発売。 |
| 11月29日 | 国連総会で、パレスチナ自治区の参加資格をオブザーバー組織からオブザーバー国家として格上げする決議がなされる。 |
| 12月 2日 | 中央自動車道上り線笹子トンネルで天井板のコンクリート板(1枚1.2t)270枚ほどが約130mにわたって落下。走行中の車両3台が下敷きになり、9人が死亡、2人が負傷する。 |
| 12月12日 | 北朝鮮が人工衛星を搭載した銀河3号を発射。衛星は軌道に投入される。各国は北朝鮮の核やミサイル拡散に関する安保理決議に違反するとして批判。 |
| 12月16日 | 第46回衆議院議員総選挙。野党第一党の自由民主党が大勝し与党に復帰。 |
| 12月29日 | モスクワのヴヌーコヴォ国際空港で、回送のため着陸したレッドウィングズ航空9268便がオーバーランし建物に激突・炎上。乗員8名のうち5名が死亡。 |
| 2013年(平成25年) | |
| 1月 1日 | 石川島播磨重工業系のアイ・エイチ・アイマリンユナイテッドと日本鋼管・日立造船系のユニバーサル造船が合併しジャパン マリンユナイテッドが誕生。 |
| 1月 3日 | 中国のリベラル紙『南方週末』の検閲済みの新年社説が共産党幹部の圧力で内容を差し替えられ、発行される事件が起こる。情報がネットで広まったことから、編集部と記者の対立も表面化。識者や市民を巻き込む騒動に発展する。 |
| 1月16日 | アルジェリアのイナメナスにある天然ガス精製プラントをイスラム武装勢力が襲撃。日本人10人を含む48人が死亡。武装勢力側もアルジェリア政府の武力鎮圧により32人が死亡。事件は、隣国マリ北部のトゥアレグ族の反乱に便乗して同地を支配下においたイスラム原理主義勢力に対し、フランス軍とマリ政府が掃討作戦を行ったことへの対抗策と言われている。 |
| 2月11日 | バチカン教皇ベネディクト16世は通常枢機卿会議の席上で2月28日をもって生前退位することを表明。生前退位は1415年のグレゴリウス12世以来。 |
| 2月12日 | 北朝鮮が3度めの核実験を実施。核出力7~40Kt程度の原爆か強化原爆(核融合材質を混ぜることで中性子発生量を増やし核分裂をさらに進める原爆)と推定されている。 |
| 2月15日 | ロシア連邦チェリャビンスク州付近に隕石が落下。上空で爆発した際の衝撃波が地上に到達し、4474棟で倒壊やガラスの粉砕などがあり、1491人が負傷、うち1人は隕石の破片に直接当たって重症を負った。明確な記録がある隕石では過去最大の人的被害を出す。NASAの推定では直径17m、質量1万t程度の小惑星だったとみられる。 |
| 3月 5日 | 反米強硬派で知られたベネズエラのウゴ・チャベス大統領が病死。8日に国葬。 |
| 3月13日 | バチカンの教皇を選出するコンクラーヴェの結果、ブエノスアイレス大司教のホルヘ・マリオ・ベルゴリオ枢機卿が266代ローマ教皇に選出され教皇フランシスコとなる。使徒座空位は解消し、前教皇ベネディクト16世は名誉教皇の称号を与えられる。 |
| 3月14日 | 欧州合同原子核研究機構(CERN)が昨年7月発見した新たな粒子について、データの解析からヒッグス粒子の可能性を示唆しているとの見解を発表。 |
| 3月16日 | アメリカでリーヒ・スミス米国発明法が施行され、同日より特許の出願制度は、先発明主義から先願主義に切り替わる(先に発明したものではなく、先に出願したものに特許を認める)。 |
| 3月27日 | 旧相模川橋脚が天然記念物に指定される。関東大震災の際に液状化で地中から現れた木製の橋脚で、鎌倉初期に稲毛重成によって架けられた大橋のものとされる(源頼朝の死に関連した橋)。地震学的な意味から天然記念物に指定された人工物としては2例目(1例目は北伊豆地震の際に揺れで地震波の擦過傷がついた展示魚雷)。 |
| 4月15日 | ボストンマラソンで爆弾テロ。8歳の子供を含む3人が死亡、282人が負傷する。 |
| 4月24日 | バングラデシュの首都ダッカ近郊のシャバールで、8階建ての商工業ビル「ラナ・プラザ」が突如崩壊。1127人が死亡し、2500人以上が重軽傷を負う大惨事となる。違法な建て増し建築、内部の工場に置かれた発電機の振動などが要因で、オーナーらには前日に異常が報告されていたにもかかわらず対処していないなど、韓国の三豊百貨店崩落事件とよく似ている。 |
| 5月20日 | アメリカの元CIA職員で、NSA職員のエドワード・ジョセフ・スノーデンが、滞在中の香港でNSAによる個人情報収集活動をマスコミに告発。世界中で大問題に発展する。 |
| 6月22日 | NSA職員のエドワード・ジョセフ・スノーデンが、NSAによる個人情報収集活動をマスコミに告発したことを受け、アメリカ政府から逮捕命令が出される。スノーデンは香港経由でロシアへ向かい、複数の国に亡命を申請。 |
| 6月26日 | カンボジア・プノンペンで開かれたUNESCO第37回世界遺産委員会で、日本の富士山を含む世界文化遺産14件、世界自然遺産5件が登録される。 |
| 7月 1日 | クロアチアがEUに加盟。28カ国となる。 |
| 7月 3日 | エジプトで軍部がクーデター。ムハンマド・ムルシー大統領の権限を剥奪、同国憲法を停止し、アドリー・マンスール最高憲法裁判所長官を暫定大統領に任命。「アラブの春」で自由選挙の結果誕生したムルシー政権の憲法改正への強硬的な動きや経済の不振などへの失望感から国民が反発しているのを見て動いたとされる。 |
| 7月 6日 | サンフランシスコ国際空港で、アシアナ航空214便が着陸に失敗して炎上。乗客2名が死亡、180名が負傷。ボーイング777就航以来初の死亡事故となる。乗員の対応の不備、死亡したうちの1名は生存中か死亡後かは不明だが緊急車両に轢かれた跡があったこと、韓国での事故報道で非人道的発言があったこと、原因を巡ってアメリカと韓国が対立するなど複数の問題点が生じた。 |
| 7月 6日 | アメリカ・ミシガン州デトロイト市が、ミシガン州の連邦地方裁判所に連邦倒産法第9章適用を申請。負債総額は180億ドル(約1兆8000億円)。 |
| 7月 6日 | カナダのラック・メガンティックで、ナントから暴走してきた無人列車が脱線転覆し、積荷の石油が炎上爆発、すくなくとも死者行方不明者50人を出す。 |
| 7月 6日 | 赤坂プリンスホテル新旧館の解体作業が終了。100m以上のビルでは国内2例目。旧館の旧李王家邸は移築予定。 |
| 7月22日 | 中国湖南省長沙市で超高層ビル「天空都市」(838m、202階)の着工式が行われる。本体を7ヶ月、全体で10ヶ月で完成させるという話で疑問視された上に、着工式の直後に当局から中止命令が出て工事は中断し話題となる。 |
| 7月24日 | スペイン・ガリシア州のサンティアゴ・デ・コンポステーラで、高速列車アルビアが脱線転覆。79人が死亡。速度超過のままカーブに入ったためとみられる。 |
| 8月 1日 | 元NSA職員でNSAの情報活動を告発しロシアへ亡命を申請していたエドワード・ジョセフ・スノーデンの1年間の亡命をロシア政府が認める。 |
| 8月12日 | インド初の国産空母ヴィクラント(排水量3万7500t)が進水。 |
| 9月 5日 | 日本の東1600kmの北太平洋海底に超巨大火山タム山塊が発見されたと発表される。シャッキー海台の中にあり、大きさ26万平方km以上。太陽系で最大級の火山。 |
| 9月 7日 | アルゼンチンのブエノスアイレスで開かれた第125次IOC総会において、2020年夏季オリンピックの開催都市が日本の東京に決定(立候補都市はバクー、ドーハ、イスタンブール、マドリード、ローマ、東京の6都市)。東京で夏季オリンピックが開催されるのは1964年以来、56年ぶり2回目となる。また、同大会での正式種目とする最後の1競技にレスリングが決定。 |
| 9月27日 | 国際連合安全保障理事会は、シリアの化学兵器全廃を義務付ける決議案を全会一致で採択。9月14日にそれまで対立していた米ロが合意に至ったことを受けて。 |
| 10月 1日 | アメリカで予算不成立による政府機関閉鎖。医療保険制度改革「オバマケア」の修正案を巡って、共和党が多数の下院と、民主党が多数の上院で採決が異なり、予算案が成立しなかったことから、政府機関が1996年以来17年ぶりに閉鎖。連邦政府公務員のうち約80万人も一時帰休となり、国立公園局が管轄する各地の観光名所は閉鎖。 |
| 10月 4日 | 欧州合同原子核研究機構(CERN)が昨年7月に発見した新たな粒子がヒッグス粒子であると確定。標準理論では粒子が質量を持つための要因であるヒッグス場の存在を証明するのが場を満たすヒッグス粒子の検出だったため、標準理論を完成させる発見となる。 |
| 10月10日 | 水銀と水銀化合物を管理し、その汚染や汚染に伴う健康被害を抑えるため、製造と輸出入を規制する国際条約(水俣条約)が熊本で採択される。 |
| 10月16日 | アメリカ連邦議会上下両院で、1月15日までの暫定予算が成立。連邦政府債務限度額引上げ法案も可決され、大統領が署名して翌日政府機関閉鎖が解除。連邦政府による債務不履行(デフォルト)も回避される。 |
| 10月16日 | ラオス国営航空301便ATR72-600型機が、台風のさなかラオス南部パークセーにあるパークセー国際空港へ着陸しようとしてメコン川に墜落。乗員乗客49人全員が死亡。 |
| 10月28日 | 北京の天安門広場に車両が突入。観光客や歩行者をはね、天安門の手前、金水橋の欄干に激突して炎上。車内にいた3人を含む5人が死亡、38人が重軽傷を負う。新疆からきたウイグル族によるとみられるが、政府発表による「テロ行為」に対し、同乗者の情報から、ウイグル族への弾圧が続くことへの抗議だったという説もある。 |
| 11月 3日 | タイの首都バンコクで反政府デモが拡大。反タクシン派とステープ元副首相によるもので、タクシン派インラック政権を打倒し、選挙制度によらない政権移譲を要求。元々は地方の発展に貢献したタクシン政権の支持者(地方出身者・貧困層・選挙制度支持者)と、タクシン政権の汚職体質を批判する反タクシン派(都市出身者・エリート層・軍・王室支持者など)の対立だったが、両派とも複雑に分裂し、そこへアピシット政権時代の民衆虐殺で訴追されているステープ元副首相が便乗したものとされる。 |
| 11月 5日 | インド宇宙研究機関 (ISRO)が同国初の火星探査機「マンガルヤーン」を、サティシュ・ダワン宇宙センターよりPSLV-XLロケットで打ち上げる。 |
| 11月20日 | 西之島の南南東沖で海底の火口から噴火が始まる。新島が出現しているのを確認。 |
| 11月21日 | ラトビアの首都リガ市ゾリトゥーデ区にあるスーパーマーケット・マキシマの屋根が突如崩落。下敷きになった買い物客を救助しようとした消防士らの上に再び屋根が崩落し、消防士・客ら54人が死亡、39人が負傷する。 |
| 11月23日 | 中華人民共和国政府が、日本が領有する尖閣諸島を含む東シナ海上空の広範囲に防空識別圏を設定する。防空識別圏は領空ではないが、防衛のため、領空に接近する航空機に対し警告と確認を行う範囲のこと。日本は占領時代に定められた防空識別圏がある。また中国が定めた識別圏には韓国の防空識別圏も入っている。 |
| 11月26日 | 米国が日本に事前通告の上で、中国が防空識別圏内とした尖閣諸島付近で、中国に対し通告しないままB-52戦略爆撃機2機を飛行させる。 |
| 11月27日 | ラトビアのドムブロフスキス首相がスーパーマーケット屋根崩壊事件の政治的責任をとって辞任。 |
| 11月28日 | アイソン彗星が近日点を通過。NASAの事前の発表では当初の予想より小さいことから、太陽の熱で崩壊するとしていたが、翌日以降、遠ざかる彗星を捉えているため、完全には崩壊しなかったとみられる。 |
| 12月 3日 | 韓国国家情報院は、北朝鮮のナンバー2である張成沢の側近、李龍河行政部第1部長と張秀吉行政部副部長の2名が処刑されたと発表。 |
| 12月 4日 | アゼルバイジャンの首都バクーで開催されたユネスコ政府間委員会で、『和食 日本人の伝統的な食文化』が無形文化遺産に登録される。 |
| 12月 5日 | ネルソン・マンデラ死去。15日に南アフリカ政府によって故郷のクヌで国葬後、葬られた。 |
| 12月 6日 | 西アフリカのギニア・ゲケドゥでエボラ出血熱によると見られる死者が出る。以後拡大。 |
| 12月 8日 | 北朝鮮の朝鮮労働党中央委員会政治局拡大会議で、金日成の娘婿で、金正日の妹の夫である同国ナンバー2の張成沢国防副委員長が、反党・反革命的分派行為を理由に、全職務を解かれ党から除名される。その場で会議場から連行(政権による演出という説もある)。経済政策を主導し、軍部を抑え、内外に豊富な人脈を持ち、潜在的に大きな力を持っていたことから、金正恩によってその脅威を除くために粛清されたと見られている。本人の贅沢な私生活の問題や崔竜海朝鮮人民軍総政治局長との対立も背景にあるとされる。 |
| 12月12日 | 張成沢が北朝鮮国家安全保衛部特別軍事法廷で国家転覆陰謀行為などを理由に死刑判決を受け、即時処刑される。 |
| 12月14日 | 中華人民共和国の無人月探査機「嫦娥3号」が月面着陸に成功。アメリカ合衆国、ソビエト連邦に次ぐ3ヶ国目。 |
| 12月26日 | 西之島の海底噴火で、新たに生まれた島からの溶岩流が、西之島本島に到達し、両島がつながる。 |
| 2014年(平成26年) | |
| 1月 1日 | 大きさ5m未満の小惑星2014 AAが発見される。翌日未明地球に最接近しおそらく大西洋上空で大気圏に突入して消滅。 |
| 2月18日 | ウクライナでEU派市民の反政府デモ隊と警官隊が衝突。両方合わせて少なくとも82名が死亡。ヤヌコーヴィチ大統領が国外へ脱出。ウクライナ騒乱。 |
| 2月26日 | NASA(アメリカ航空宇宙局)は、ケプラー宇宙望遠鏡で探査した恒星のうち305の恒星系で、715個の太陽系外惑星を発見したと発表。そのうち4つは、生命が存在しやすいハビタブルゾーンにあることが判明。 |
| 3月 1日 | ロシアがウクライナのクリミア半島へ派兵。同地を占領。大きな戦闘はなかったが、欧米各国はロシアを非難。この「成功」が後のロシアによるクリミア侵略の要因の一つになっている。 |
| 3月 7日 | あべのハルカス開業。日本一の高層ビルで日本初のスーパートール(世界標準の超高層ビル)となる。 |
| 3月 7日 | ソチオリンピック開催。~16日。 |
| 3月 8日 | マレーシア航空機370便がタイの沖合を飛行中に消息を絶つ。乗員乗客239名は行方不明に。インド洋の広範囲にわたって大規模な国際捜査が行われるが行方はつかめず。 |
| 4月 9日 | ウィンドウズXPのサポート期間が終了。 |
| 4月16日 | 韓国の珍島付近で、修学旅行中の高校生らを乗せ済州島へ向かっていた旅客船セウォル号が沈没。294名が死亡。 |
| 4月26日 | アメリカ・ニューメキシコ州アラモゴードの市の処分場で、1983年にアタリ社が売れなかった大量のゲームソフトを密かに埋設処分したとしてその真偽が都市伝説にまでなった場所の発掘を実施。実際に大量のゲームソフトが発見され、都市伝説が真実だったことが判明する。 |
| 5月17日 | ラオスで政府要人らを乗せたラオス空軍のAN-74が墜落。 |
| 5月20日 | タイで軍部が前年より続く政治の混乱に対して戒厳令を施行。 |
| 5月22日 | タイ軍が、クーデターを宣言。立憲君主に関する部分を除く憲法と内閣の機能を停止し、通常のテレビ放送の中止と集会の禁止を宣言。政府関係者および反政府関係者の身柄を拘束。 |
| 6月12日 | FIFAワールドカップ・ブラジル大会い開催。~7月13日まで。 |
| 6月18日 | 東京都議会セクハラやじ事件が起こる。 |
| 6月29日 | イラクでスンニ派の武装組織「イスラム国」が樹立を宣言。以降、住民虐殺、ジャーナリストの公開処刑などを繰り返す。 |
| 6月 | 西アフリカ各国でエボラ出血熱が急拡大。 |
| 7月 8日 | イスラエル軍がガザ地区の武装勢力に対処するためとしてガザ地区に侵攻。 |
| 7月17日 | ウクライナ東部ドネツク付近で、オランダからマレーシアへ向かっていたマレーシア航空機17便が同地を占拠する親ロシア派のミサイル攻撃で撃墜される。乗員乗客298名全員死亡。 |
| 7月23日 | 西之島が噴火前の6倍まで大きくなっていることが判明。 |
| 8月 1日 | 台湾高雄市で、地下埋設のプロピレンガス管が広範囲にわたって爆発炎上。30人が死亡、300名以上が負傷する。 |
| 8月 5日 | 5日と6日、朝日新聞は、1991年から掲載を行った従軍慰安婦の強制連行があったとする吉田清治の証言記事などが、裏付けのない虚偽内容であったことを認めると発表。 |
| 8月 8日 | 西アフリカでこれまでにない規模でエボラ出血熱が広がっていることに、WHOが「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言。 |
| 8月27日 | デング熱の日本国内感染が69年ぶりに確認される。以後、患者の発生が相次ぐ。 |
| 8月 | 朝日新聞の従軍慰安婦記事問題に関して、ジャーナリスト池上彰の批判的内容のコラムを、朝日新聞が掲載拒否し問題となる。9月4日朝刊で謝罪とともに掲載。 |
| 9月11日 | 朝日新聞社長が会見し、5月20日の朝刊で報じた、福島第一原子力発電所事故に関する吉田所長証言を元にしたとする記事の内容が事実と異なっていたとして謝罪。 |
| 9月18日 | スコットランド独立を問う住民投票が実施され、接戦を制して反対派の勝利に終わる。 |
| 9月27日 | 木曽御嶽山が山頂付近の3つの火口から水蒸気噴火。噴火としては小規模だったが、当時噴火警戒レベル1で、標高の割に難易度が低く好天で数百名の登山客が訪れていたため、噴火に巻き込まれて死者行方不明者58名と多数の負傷者が出る惨事となった。小規模の火砕流も発生したが火砕流での犠牲者はなし。 |
| 10月31日 | 民間宇宙飛行計画スペースシップツーの1号機VSSエンタープライズが試験飛行中に墜落。乗員1名が死亡、1名が重傷。加速中に減速用のフェザリングモードへ切り替えたための操縦ミスとみられる。 |
| 11月 3日 | ニューヨークの同時多発テロで崩壊したワールドトレードセンター跡地に作られた1ワールドトレードセンタービルが完成。高さ541m。 |
| 11月12日 | 欧州宇宙機関の無人彗星探査機ロゼッタがチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に着陸機フィラエを投入し、初の彗星着陸を成功させる。 |
| 12月 5日 | ナッツリターン事件。大韓航空機86便A380型機が、ジョン・F・ケネディ国際空港で離陸のため滑走路へ移動中、機内にいた乗客で大韓航空の趙顕娥副社長が、客室乗務員が袋ごと出したナッツに激怒、マニュアルに沿った対応であると説明したが怒りが収まらず、乗務員に降りるよう命令。機長にも引き返すよう命じ、管制の許可を得て戻りチーフパーサーを降ろした後離陸。これが国外で報道されて発覚。更にこの事件の説明がなかった上に、関係者を買収しようとしたことから、これが航空法上、及び労働管理上の問題に発展し、財閥経営者一族への批判につながった。 |
| 12月28日 | インドネシア・エアアジア航空8501便(スラバヤ・ジュアンダ国際空港発シンガポール・チャンギ国際空港行)がジャワ海カリマタ海峡に墜落。乗員乗客162人全員が死亡したとみられる。墜落原因は不明だが、急に失速して海面に激突したと考えられている。 |
| 2015年(平成27年) | |
| 1月 7日 | フランスの政治風刺系の週刊誌シャルリー・エブドの本社がイスラム原理主義系のテロリストに襲撃され12人が死亡する。また同時多発的にフランス国内で立てこもり事件なども発生。襲撃の主な動機は同誌にムハンマドのイラストが載せられたことだったため、表現の自由と文化・宗教の違いのバランスが世界中で問題になった。 |
| 1月15日 | スイス国立銀行が、スイス・フランの対ユーロ上限を廃止。投資家の間で騒ぎとなる。 |
| 1月25日 | ギリシャ総選挙が行われ、EUが財政支援の代わりに求めていた緊縮政策に反対する急進左派連合のチプラス政権が樹立。 |
| 2月 4日 | 台湾・台北市の松山国際空港を離陸した金門島行きのトランスアジア航空235便ATR72型機が、離陸直後にエンジン停止し、横転した状態で急降下、高速道路上のタクシーに激突した後、基隆川に墜落。乗員乗客58人のうち43人が死亡。タクシーの乗員らは軽傷。2基のエンジンのうち1基が故障し、乗員がその対応の際に誤ってもう1基のエンジンを止めてしまったのが原因とみられる。 |
| 2月27日 | モスクワで、反プーチン政権の急先鋒だったボリス・ネムツォフロシア共和党・人民自由党党首が射殺される。 |
| 3月 5日 | ソウルでマーク・リッパート駐韓アメリカ大使が韓国人の男に襲撃され重症を負う。犯人は2010年に駐韓日本大使襲撃事件を起こし執行猶予となった反日団体代表の金基宗とされているが、同団体は韓国政府の支援を受けたこともあった。 |
| 3月25日 | 海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦いずもが就役。基準排水量19500t。いずも型の一番艦で将来の空母改装を視野に入れた大型艦。ひゅうが型より一回り大きく、ひゅうが型にあった対潜攻撃用武装は全て廃止され、より航空運用に重点を置いている(そのため単艦運用ではなく艦隊運用が前提)。 |
| 3月 | イギリスが第一次世界大戦時の戦費確保のためにアメリカから借り入れた債務の償還が完了。 |
| 4月25日 | ネパール大地震発生。モーメントマグニチュード7.8。断層のズレによるものとみられる。5月15日の発表で死者8460人。寺院などの歴史遺産の多くが崩壊。インド、バングラデシュ、チベットなどでも死者。エベレストでは大規模な雪崩が発生し、1000人以上がいたとみられるベースキャンプが飲み込まれ登山者ら20人前後が死亡。 |
| 5月 2日 | 英国王室のケンブリッジ公爵ウイリアム王子とキャサリン夫人との間に第2子となる女児が誕生。シャーロット・エリザベス・ダイアナと名付けられる。この時点で王位継承順位第4位。 |
| 5月 6日 | インドとバングラデシュの領界が複雑に入り組んでいたことから、両国政府は162の飛び地を交換することで合意し国境を再画定。住民はどちらの国籍を取得するか選択を認められる。世界で唯一の三重飛び地とされたインドのダハラ・カグラバリはバングラデシュ領となる。 |
| 5月 7日 | EU離脱が大きな争点となっているイギリス総選挙が行われ、保守党が勝利。前年にスコットランドのイギリスからの独立投票を行って敗れたスコットランド国民党が大躍進し、あおりを受けた労働党は、有力議員で選挙対策担当でもあったアレクサンダー議員がスコットランド国民党から立候補した20才の女子大生ブラック候補に敗れるなど大敗。メディアや専門家の事前予想が大きく外れる結果となった。 |
| 5月 9日 | リベリア政府、42日間新規感染者が確認できなかったとして、同国でのエボラ出血熱終息を宣言。 |
| 5月12日 | ペンシルベニア州フィラデルフィアでアムトラック北東回廊の高速特急が脱線横転。8人が死亡、乗員乗客のほとんどが重軽傷を負う大事故となる。制限速度を大幅に超えてカーブに侵入したのが直接の原因。 |
| 5月17日 | 大阪都構想の賛否を問う住民投票が行われ、反対派が勝利。推進してきた橋下徹大阪市長は任期をもって政界引退を表明。中高所得者と若い世代は賛成が多く、低所得者と高齢者には反対が多かったこと、区によってはっきりと分かれたこともあり、投票後も賛否両論が続いた。 |
| 5月17日 | 川崎市川崎区日進町の簡易宿所「吉田屋」で火災が発生し、隣の簡易宿所「よしの」に延焼。両棟は全焼し、11人が死亡。17人が重軽傷を負う。被害者の多くは生活保護受給者で、アパートなどを借りることも出来ない立場の人達であった。なお火災の原因は放火と考えられるが、犯人は不明。 |
| 5月20日 | 韓国の平沢聖母病院に入院中の患者がMERS(中東呼吸器症候群)である確定。しかし当局の対応の遅さによりそれまでに院内感染が広がっており、院外へも拡大。3週間で4次感染にまで広がり10人以上が死亡。100人以上が感染する。 |
| 5月27日 | アメリカ合衆国の司法当局が、FIFAの組織的不正を理由に関係者14人を起訴。スイス警察当局がそのうち7人を逮捕する。 |
| 5月28日 | FIFA汚職事件騒動の最中、FIFA会長選挙が行われ、ブラッター会長が5回目の当選を果たす。 |
| 6月 3日 | FIFA汚職事件に関連して、ICPO(国際刑事警察機構)は、元副会長らを国際手配。 |
| 6月 5日 | FIFA会長に5度目の当選を果たしたばかりのブラッター会長が突如辞任を表明(12月実施の再選挙まで留任)。捜査対象になっていることが判明したためとも言われる。 |
| 6月22日 | 和歌山電鐵貴志川線貴志駅の駅長を務めた三毛猫のたまが死去。 |
| 6月27日 | 八仙水上楽園爆発事故。台湾新北市八里区のウォーターパーク八仙水上楽園で、カラーパウダー散布によるステージショーの最中、タバコの火によるとみられる粉じん爆発が起こり、少なくとも11名が死亡、525名がやけどなどの重軽傷を負う。 |
| 6月30日 | 同日23時59分59秒の後にうるう秒が1秒挿入される。日本時間では7月1日午前8時59分59秒の後。不規則に増減速する地球の自転を基準とし法的な基礎となる世界時と、原子時計を使い精密に計測する国際原子時との誤差を調整するため。 |
| 7月14日 | 冥王星探査機ニュー・ホライズンズが冥王星に到着し観測を開始する。観測後はエッジワース・カイパーベルトの調査のため、辺縁系へ向けて離れていく予定。 |
| 8月12日 | 中国天津市浜海新区の沿海地区にある物流センターの化学倉庫で火災が発生。2度大規模な爆発を起こし、少なくとも150人前後が死亡、700人以上が負傷(正確な数字は不明)。周囲2km四方に大きな被害を出し、大量の有毒物質が放出。厳しい情報統制が行われる。 |
| 8月26日 | アメリカ・バージニア州で、ニュースの屋外インタビューの生放送中にリポーターとカメラマンが射殺される事件が起こる。 |
| 8月27日 | 海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦いずも型の2番艦「かが」が進水。基準排水量19500t(満載27000t)、全長248mで旧海軍空母加賀とほぼ同じ大きさ。 |
| 9月 5日 | 2015セネガル空中衝突事故。セネガルの首都ダカールのレオポール・セダール・サンゴール国際空港から赤道ギニアのマラボ国際空港を経由してベナンのコトヌー・カジェフォウン空港へ向かっていたCEIBAインターコンチネンタルC2-71便ボーイング737-800型機が、セネガルエアの救急便ホーカー・シドレーHS125-700A型機とセネガル東部タンバクンダの上空で接触。CEIBA機は右翼先端のウイングレットが破損し、同社の本社があるマラボへの緊急着陸に成功したが、セネガルエアの救急便は応答がないまま55分後に大西洋に墜落。乗員乗客7人全員が死亡。おそらく機体が破損して減圧し乗員乗客全員が意識を失ったまま飛行し燃料切れで墜落したものと見られる。同じ高度で飛行した原因は不明だが、救急便の計器に問題があった可能性がある。 |
| 9月10日 | 南アフリカ・スワルトクランスのライジングスター洞窟の奥で、ヒトの絶滅種の一つであるホモ・ナレディの化石が多数発見される。 |
| 9月11日 | サウジアラビアのメッカで、カアバを囲むモスク、マスジド・ハラームに強風を受けた工事用クレーンが倒れ、少なくとも103人が死亡。230人以上が重軽傷を負う。 |
| 9月24日 | サウジアラビアのメッカ近郊にあるメナーで巡礼者が将棋倒しになり少なくとも2181人が死亡する大惨事となる。 |
| 10月29日 | 中国共産党中央委員会第5回全体会議が閉幕。人口抑制のための一人っ子政策が廃止される。社会の急速な高齢化「未富先老」、男女比率の崩壊、一人っ子のモラルの欠如、未登録の子供「黒孩子」の存在、子を失った「失独家庭」の問題、誘拐の頻発などの深刻な社会的影響を考慮したもので、以降は二人目までの出産を認める。 |
| 10月31日 | エジプトのシナイ半島で、シャルム・エル・シェイク国際空港発サンクトペテルブルク・プルコヴォ空港行コガリムアビア航空9268便が墜落。乗員乗客224人全員が死亡。ISILのテロとの見方が有力。 |
| 11月13日 | パリ同時多発テロ事件。パリ市サン・ドニのスタッド・ド・フランススタジアムの外で自爆テロが、10区と11区の4箇所の店舗で銃撃事件がほぼ同時に発生。少なくとも130人が死亡、300人以上が負傷。 |
| 11月24日 | トルコとシリアの国境で、シリア空爆に参加中のロシア空軍の爆撃機が領空侵犯を理由にトルコ軍に撃墜される。乗員2名のうち少なくとも1名は脱出後に銃撃で死亡。ロシアとトルコの関係が悪化。トルコは、シリア政府に近いロシアが、反体制派のトルクメン人などを攻撃していたと主張。逆にロシアはトルコがISILに協力していると非難。第三国の調査ではトルコ側の主張通り、ロシア軍機が侵犯し、警告の上で撃墜したとみられる。 |
| 11月25日 | アメリカで天体の所有や営利目的の資源採掘を認める「2015年商業宇宙打ち上げ競争力強化法」が成立。 |
| 12月31日 | ヒトラーの死後70年に当たるこの年の最終日をもって、ヒトラーの著書『我が闘争』の著作権保護期間が消滅。 |
| 12月31日 | 翌日の朝にかけて、ドイツのケルン市街地で、難民の若者ら1000人による400件を超す女性への集団暴行事件が発生(他の強盗や物損被害なども含め900件以上)。しかし難民受け入れを国策にしていたメルケル政権下で、ケルン警察は捜査を行わず隠蔽。メディアも放送せず。 |
| 12月31日 | 113番元素(ウンウントリウム)について、理化学研究所が3回生成に成功したことがIUPAC評議会によって認定される。これにより理化学研究所に命名権が与えられる。 |
| 2016年(平成28年) | |
| 1月 2日 | ベトナムにスペースデブリの燃え残りとみられる球体3つが落下する。 |
| 1月 2日 | サウジアラビア政府、シーア派指導者のニムル・バキル・アル・ニムル師(シャイフ・ニムル師)と、その他に46人をテロ容疑などで処刑(大半はスンニ派)。各国のシーア派市民の反発を招き、イラン政府はサウジアラビアに抗議。イラン首都テヘランでは市民が反サウジ暴動を起こして、大使館を襲う。 |
| 1月 3日 | サウジアラビア政府、イランと断交を発表。イランの首都テヘランで起きた大使館襲撃事件を受けて。 |
| 1月 5日 | ドイツのケルンで大晦日から元日にかけて起きた集団暴行事件が明るみになり、市民による抗議デモが発生。しかしケルン市長は被害者よりも難民を擁護するような発言をしたことで市民が反発。100万人の難民を受け入れたメルケル政権の批判も高まり、政権は3月に、難民受け入れを制限する方針転換を表明。 |
| 1月 6日 | 北朝鮮が核実験を実施。北朝鮮政府は水爆実験と発表。しかし観測結果からは推定数Kt規模で、前回の実験時の波形とも近いことから、失敗したか、もしくは水爆開発過程で行われるブースト型原爆(核融合物質を使って核分裂の効率を高める原爆)の実験だったという見方もある。中国は事前通告がなく反発。韓国では、軍が事前に兆候を捉えられなかったとして問題になる。 |
| 1月11日 | ドイツのケルンで大晦日から元日にかけて起きた集団暴行事件が明るみになったことで、スウェーデンでも、2014年と2015年のストックホルムフェスティバルの際に、難民による集団暴行事件があったことが明るみになる。検察も警察も事件を把握していたが、難民庇護を理由に捜査せず、政府にも報告していなかった。ロベーン首相は警察を批判、警察に対する調査を命じる。 |
| 1月14日 | WHO、西アフリカでのエボラ出血熱終息を宣言。ただし翌日も感染者が見つかっている。2015年10月18日の段階で少なくとも28512人が感染し、11313人が死亡。致死率はおよそ40%。 |
| 1月16日 | 台湾(中華民国)の総統選挙で、野党民進党の蔡英文が当選。立法院議員選挙でも民進党が過半数の68議席(定数113議席)を獲得。 |
| 1月20日 | カリフォルニア工科大学などの研究チームが「海王星軌道の20倍も遠いところに地球の10倍程度の質量をもつ大型の惑星が存在する可能性がある」と発表。公転周期は1万年から2万年。6つの外縁天体の軌道の方向と傾きがいずれも共通していることから、それら6天体とは太陽を挟んで反対の場所に大型の天体が存在すれば、その影響を受けていると計算上説明できるため。 |
| 1月26日 | 「空飛ぶスパゲッティモンスター教」がオランダで宗教団体として認可される。 |
| 2月 6日 | 台湾南部地震。台南市、高雄市など大きな揺れを観測。台南市永康区にある地上16階、地下1階建ての「維冠金龍大樓」ビルが倒壊するなど、全体で死者117人、重軽傷者551人を出す。 |
| 2月 7日 | 北朝鮮が衛星ロケットの発射と称する大型の弾道ミサイル発射実験を行う。 |
| 2月11日 | 重力波を観測していたLIGO(レーザー干渉系重力波天文台)が、重力波を直接観測したことを発表。新観測施設の運用を開始して2日後の2015年9月14日に捉えたもので、13億光年離れた2個のブラックホールの衝突によって生じた重力波だとみられる。 |
| 3月 3日 | ニュージーランドで国旗を変更するかどうかの国民投票が行われ、変更反対派が56%となり、現行の国旗が続くこととなる。 |
| 3月20日 | オバマ米大統領、キューバを訪問。現役の米大統領としてはカルヴァン・クーリッジ大統領以来88年ぶり。 |
| 3月22日 | ブリュッセル連続爆破テロ事件。ブリュッセル国際空港のカウンターと、地下鉄のマールベーク駅で連続して爆弾テロがあり、犯人3人を含む35人が死亡。 |
| 3月26日 | 北海道新幹線(新青森駅~新函館駅)が開通。 |
| 4月12日 | ロシアの富豪ユーリ・ミルナーと、宇宙物理学者スティーブン・ホーキングが、4.37光年先のケンタウルス座α星への恒星探査計画「ブレークスルー・スターショット」を発表。超小型のレーザー推進宇宙船を多数送り込み、α星から15000auの距離を周回する地球に最も近い恒星プロキシマ・ケンタウリを撮影する、というもの。宇宙船を加速し続ける事ができれば、光速の20%程度になり、およそ20年で到達すると考えられる。撮影できても、地球への送信に4年以上かかる。 |
| 4月14日 | 午後9時26分、熊本県益城町で震度7を観測する大地震が発生。震源の深さ11km、マグニチュード6.5。 |
| 4月15日 | 民進党の公式Twitterで、熊本地震に絡めて、自民党が東日本大震災時に原発事故に関するデマを流して政権の足を引っ張ったというツイートを書き、党が個人の見解であるとして謝罪。 |
| 4月16日 | ふたたび熊本県益城町、西原村などで震度7を観測する大地震が発生する。震源の深さは12km、マグニチュード7.3。内陸型の地震で連続して大規模な地震が発生するのは異例。気象庁は14日の地震を前震、16日の地震を本震と発表。報道もそれに従うが、研究者の間では、別々の地震が2回起こったとする意見もある。その後、阿蘇付近と大分県由布市付近で地震が多発。また地震との関連ははっきりしないが、阿蘇山で小規模の噴火が起こる。一連の地震の死者は関連死も含めて88人。全壊8125棟、半壊28424棟、熊本城や阿蘇神社、宇土市役所庁舎などで大きな被害が出たほか、土砂崩れで阿蘇大橋が崩落する。 |
| 4月20日 | 中華人民共和国の元政治家で、文化大革命で劉少奇などを激しく攻撃して失脚させた戚本禹が死去。中央文化革命小組メンバー生存者で最後の人物。 |
| 4月28日 | 沖縄県うるま市で女性が嘉手納基地所属の軍属の男に襲われ殺害される事件が起こる。遺体は5月19日に発見。沖縄で反基地感情が高まる。 |
| 5月17日 | イラクの首都バグダードのサドルシティで爆弾テロ事件が発生。少なくとも101人が死亡。ISILによる犯行。 |
| 5月27日 | オバマ米大統領が広島を訪問。 |
| 5月28日 | ハランベ事件。アメリカのシンシナティにあるシンシナティ動植物園で、ゴリラの園舎内に入って堀に落ちた3歳の男の子を雄のローランドゴリラのハランベが抱きかかえたり引きずって運んだりしたのを見て、動物園側が危険だと判断しハランベを射殺した出来事。一部始終の映像がYou Tubeで拡散し、世界中で射殺の是非や責任問題で論争となった。 |
| 6月 1日 | スイスのゴッタルドベーストンネルが開通。青函トンネルを抜いて世界最長となる。 |
| 6月 8日 | IUPACと理化学研究所は、生成に成功し命名権を得られた113番元素(ウンウントリウム)の名称案について、ニホニウムとすることを発表。名称は日本(ニホン)から。同時にIUPACは、115番元素(ウンウンペンチウム)をモスクワからモスコビウム、117番元素(ウンウンセプチウム)をテネシーからテネシン、118番元素(ウンウンオクチウム)を、研究者ユーリー・オガネシアンからオガネソンとする名称案を発表。 |
| 6月12日 | フロリダ・ゲイナイトクラブ銃乱射事件。アフガニスタン系の男性がゲイナイトクラブ店内で自動小銃を乱射。店内にいた50人が死亡。アメリカの銃犯罪事件では最悪となる。ISILが犯行声明を出したが、イスラム過激派によるテロなのか、同性愛に対する嫌悪から起こしたのかははっきりしていない。 |
| 6月23日 | イギリスで、EUからの離脱を問う国民投票が実施され、事前の予想に反し、離脱派が勝利。イギリスのEU離脱が決定。市場が一時暴落したほか、独立運動のある各国に波紋を投げかける。なお予想されたイギリス経済の破綻には至らず。 |
| 6月26日 | パナマ運河の拡張工事が終了。開通する。 |
| 7月 1日 | バングラデシュの首都ダッカにあるガルシャン地区で7人のテロリストが立て籠もり人質を次々と殺害する事件が起こる。日本人7人を含む22人が死亡。軍も投入され、銃撃戦により犯人6人と警官2人も死亡。 |
| 7月 3日 | イラクの首都バグダードの繁華街カッラーダで爆弾テロ事件が発生。少なくとも220人が死亡。 |
| 7月 6日 | ポケモンGOの配信が始まる。各国で賛否両論の大騒ぎとなる。 |
| 7月20日 | 神奈川県在住の男性が、熊本地震の際に動物園からライオンが逃げ出したかのようなデマツイートを流したとして、熊本市動植物園に対する偽計業務妨害容疑で逮捕される。 |
| 8月 5日 | 第31回夏季オリンピック・リオデジャネイロ大会開幕。21日まで。 |
| 8月 7日 | 天皇陛下が、生前退位について言及したビデオメッセージを発表。 |
| 9月 9日 | 北朝鮮が豊渓里核実験場で核実験を実施。核出力は10Ktクラスか。 |
| 10月21日 | 鳥取県中部地震が発生。マグニチュード6.6。倉吉市などで震度6弱を観測。 |
| 11月 8日 | アメリカ大統領選挙一般投票が行われ、多くの予想に反しドナルド・トランプが306人の選挙人を獲得し、第45代アメリカ合衆国大統領に当確(公式集計結果は翌年1月発表)。政治経験、軍人経験のない初めての大統領となる。なお得票数ではヒラリー・クリントン候補のほうが上であった。株価が乱高下した他、その言動に批判的な人々によって、当選後も反トランプデモが盛んに行われる。 |
| 11月28日 | ブラジルのサッカークラブチーム「アソシアソン・シャペコエンセ・ジ・フチボウ」の選手・関係者ら50名を含む乗員乗客77名を乗せたラミア航空2933便アブロRJ85型機が、コロンビア・メデジン郊外の山中に墜落。71名が死亡。複数の要因で燃料不足に陥ったことを正確に管制官へ伝えなかったことが原因という説が有力。 |
| 2017年(平成29年) | |
| 1月20日 | ドナルド・トランプが第45代アメリカ合衆国大統領に就任。一期目の就任年齢70歳は、この時点で歴代大統領で最も高齢。その言動などから世界中で抗議デモが発生。 |
| 1月27日 | アメリカのドナルド・トランプ大統領が、イラク、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、シリア、イエメンの全国民のアメリカ入国90日間禁止の大統領令(13769号:テロリストの入国からアメリカ合衆国を守る大統領令)に署名。全米各地の空港などで当該国からの入国者が禁足される自体が相次ぐ。これに対する抗議デモが起きた他、裁判所への訴えも相次ぐ。 |
| 2月 3日 | アメリカ・ワシントン州シアトルの連邦裁判所が、大統領令13769号の執行一時差止の判決を出す。これにより、禁足されていた当該7カ国からの旅行者は入国が認められることになる。 |
| 2月13日 | 北朝鮮第2代最高指導者金正日の長男で、現最高指導者金正恩の異母兄である金正男が、マレーシアのクアラルンプール国際空港内で、VXによって暗殺される。北朝鮮による犯行の疑惑が濃厚。 |
| 2月14日 | 西之島の噴火が収まったことを受けて、気象庁は火口周辺警報を解除。 |
| 4月 3日 | ソウル市に高さ555mのロッテワールドタワーがグランドオープン。平壌にある建設途中で止まったままの柳京ホテルを抜いて朝鮮半島で一番高いビルとなる。 |
| 4月 4日 | シリアのイドリブ県ハーン・シェイフンで、シリア政府軍によるものと見られるサリンを使った攻撃が行われ、市民89人が死亡。 |
| 4月 9日 | アメリカのシカゴ・オヘア空港で、出発待ちのユナイテッド・エクスプレス3411便にユナイテッドの乗員移動で追加乗機させるとして、無作為に選んだ乗客4人に降機と翌日の便への振替を命じ、応じなかった医師に暴行を加えて重症を負わせて強制降機させる事件が起きる。 |
| 4月20日 | 西之島で噴火を確認。溶岩の流出が活発化。 |
| 4月22日 | フランス大統領選挙第1回投票が海外領土で始まる。 |
| 4月23日 | フランス大統領選挙第1回投票がフランス本土で実施。11人の候補者のうち過半数の票を得た候補者がいなかったため、上位2人である新党アン・マルシェ!を率いる、中道の元経済産業大臣のエマニュエル・マクロン候補と、極右国民戦線党首のマリーヌ・ル・ペン候補が決選投票へ進むこととなる。 |
| 5月 7日 | フランス大統領選挙決選投票実施。エマニュエル・マクロン候補が第25代大統領に当選。39歳で史上最年少。なお棄権や白票などを合わせると3割以上に上り、マクロン、ル・ペン候補のどちらも希望しなかった国民が多数いたことが明らかに。また従来支持の少なかった極右候補者が躍進したのは、EUの経済政策の影響で困窮する人が増加したことも背景にあるとみられる。 |
| 5月12日 | コンゴ民主共和国でエボラ出血熱発生。感染拡大。 |
| 5月18日 | 1971年に起きた渋谷暴動事件で機動隊員を殺害した容疑のある中核派メンバーのうち、最後まで逃走していた大坂正明が、広島市内の中核派の拠点捜索の際に公務執行妨害で逮捕される。本人と判明し殺人罪での逮捕は6月7日。他の容疑者6名は1975年までに逮捕起訴。 |
| 5月31日 | ロケット運用会社「ストラトローンチ・システムズ」がロケットを空中で発射するためのプラットホームとなる巨大航空機「モデル351ロック」を初公開。全長72.5m、翼幅117.3m、エンジン6基の双胴機で、中央にロケットを搭載する。ボーイング747ジャンボ2機の部品を流用して作られた。H-4ハーキュリーズやアントノフ225を凌駕する巨人機だが、ロケット発射に特化しているため、航続距離は短い。 |
| 5月31日 | アフガニスタンの首都カブールで、大規模な爆弾テロ。死者80人以上、負傷者350人以上。 |
| 6月 1日 | アメリカのトランプ大統領が、地球温暖化対策の「パリ協定」からの離脱を表明。各国の反発を買っただけでなく、アメリカ国内の州政府からも批判が出る。 |
| 6月 3日 | イギリスのロンドンで、イスラム教徒3人が、自動車で市民を次々とはねた上に、車を降りて襲撃。7人が死亡、48人が重軽傷を負う。犯人3人は射殺。 |
| 6月 5日 | サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、イエメンが、カタールと断交。テロ組織を支援したという理由で。 |
| 6月 6日 | リビア、モーリタニア、モルディブも、カタールと断交。 |
| 6月 7日 | ミャンマー空軍のY-8型輸送機が墜落。搭乗していた軍人とその家族122人全員が死亡。Y-8は中国製の旧式ターボプロップ輸送機。嵐雲に突入して空中分解したものとみられる。 |
| 6月17日 | ポルトガルで大規模な森林火災。62人が死亡。 |
| 6月25日 | パキスタンのバハーワルプルで、横転したタンクローリーから漏出した石油を求めて住民らが殺到。そのさなかに引火爆発し少なくとも219人が死亡、多数の負傷者を出す。 |
| 6月29日 | イラク軍が、ISILの拠点であるモスルのヌーリ・モスクを制圧。 |
| 7月 7日 | スイスで行われていたキプロス再統合交渉が失敗に終わる。 |
| 7月18日 | スイスのレ・ディアブルレ氷河で1974年に遭難した夫婦の遺体が発見される。 |
| 7月27日 | イランが衛星搭載可能な国産ロケット「シモルグ」の打ち上げに成功。 |
| 7月29日 | スリランカ政府、赤字のため、ハンバントタ港の運営権に必要な株式を中国の国有企業に売却。 |
| 8月10日 | イエメンで人身売買組織が、捜査を逃れようと輸送中の移民300人を海に投げ捨てる事件があり、少なくとも56人が死亡。多数が行方不明に。 |
| 8月14日 | 世界保健機関は、イエメンでのコレラ感染拡大で2000人近くが死亡、50万人に感染の疑いがあると発表。 |
| 8月14日 | シエラレオネの首都フリータウンで地すべりが起き、1141人が死亡、3000人が家を失う。 |
| 8月17日 | スペインのバルセロナとカンブリスで暴走車によるテロが相次ぎ15人が死亡(犯人が逃走時に奪った車両の運転手を含む)、100人以上が重軽傷を負う。カンブリスの実行犯5人は銃撃戦の末射殺。 |
| 8月23日 | イエメンの首都サヌアにあるホテルが、サウジアラビア主導の連合軍の空爆を受け、少なくとも48人が死亡。 |
| 8月24日 | 西之島の噴火に伴う海への溶岩流出が収まる。島の面積は拡大。 |
| 8月25日 | ミャンマーのラカイン州で、紛争から逃れるため、ロヒンギャ族の住民多数が隣国バングラデシュに越境。 |
| 8月29日 | 北朝鮮が北東方向に長距離ミサイルを発射。襟裳岬東方1180kmに落ちる。 |
| 9月 3日 | 北朝鮮が核実験を実施。 |
| 9月 5日 | 国連難民高等弁務官事務所は、ミャンマーのロヒンギャ族の越境難民が12万3600人達していると発表。政府とロヒンギャ武装組織との戦闘で400人以上が死亡。 |
| 9月11日 | シンガポール第8代大統領に、ハリマ・ヤコブが当選。同国初の女性大統領。 |
| 9月15日 | 土星探査機カッシーニが土星大気圏に突入して消滅。大気のある衛星タイタンと、水のある衛星エンケラドゥスは、独自の生命がいる可能性があるため、探査機に付着した地球の微生物が持ち込まれる可能性を考慮し、土星の大気へ突入させる措置となった。 |
| 9月16日 | オックスフォード大学は、同大学図書館に保管されている、19世紀にパキスタンで発見された4世紀ころの数学の古書「バクシャーリー写本」に記載のある点が「ゼロ」を表す最古の記録であると発表。 |
| 9月19日 | メキシコ・プエブラ州でM7.1の地震が発生。少なくとも293人が死亡。 |
| 9月23日 | 1977年にハイジャック事件の舞台となり、突入作戦の見本となった機体ランツフート号が、売却されていたブラジルからドイツへ大型輸送機アントノフ124とイリューシン76で分解輸送され博物館へ収められる。 |
| 9月25日 | イラクのクルド人自治区で独立を当住民投票を実施。住民の92.7%が独立を支持。 |
| 9月26日 | サウジアラビア政府、女性の自動車運転を翌年6月より解禁する勅令を発布。 |
| 9月27日 | 国連は、バングラデシュへ逃れたロヒンギャ難民を48万人と発表。 |
| 9月29日 | イラク政府、クルド人自治区の住民投票で独立支持が圧倒的多数だったことを受けて、同自治区の首都アルビールへの航空便乗り入れを停止する。 |
| 9月30日 | エールフランス66便エンジン爆発事故。パリ・シャルル・ド・ゴール発ロサンゼルス行エールフランス66便エアバスA380型機が、グリーンランドのパーミュート南東150km地点を飛行中、右翼第4エンジンが爆発破損。墜落はせず、カナダのグースベイ空港に緊急着陸。乗員乗客に死傷者は無かったが、グースベイ空港が大型機に対応できなかったため、乗客は機内で待機後、翌日到着した2機の代替機に乗り換えロサンゼルスへ移動した。爆発の原因は不明。 |
| 10月 1日 | アメリカ、ラスベガスのホテル「マンダレイ・ベイ・リゾート アンド カジノ」32階からメインストリート「ラスベガス・ストリップ」へ向けて銃乱射事件が起き、58人が死亡、546人が重軽傷を負う。同通りでは野外音楽祭が行われており多数の犠牲者を生む結果となった。犯人の男は拳銃自殺。 |
| 10月 1日 | スペイン・カタルーニャ州で、独立を問う住民投票を実施。 |
| 10月 2日 | パレスチナ自治政府のラーミー・ハムダッラー首相が、ガザ地区を訪問。ガザ地区を支配するガザ政府は、強硬派ハマースによって構成されてるため、同じパレスチナでも自治政府とは敵対関係にある。 |
| 10月 5日 | 全米ライフル協会は、ラスベガスの銃撃事件での批判を受け、銃規制には反対する一方で、半自動銃火器を疑似フルオートに改造できるバンプストックなどの改造部品の法適合について検討を求める声明を出す。 |
| 10月10日 | スペイン・カタルーニャ州のプチデモン首相が、独立賛成派が90%以上(投票率は43%)となった住民投票の結果を受けて、カタルーニャ共和国の独立宣言に署名。 |
| 10月13日 | アメリカのトランプ大統領、イラン核合意の離脱を示唆する演説。 |
| 10月14日 | ソマリアの首都モガディシュのホテルで、自動車爆弾によるテロがおき、ホテルは倒壊。358人が死亡、56人が行方不明。 |
| 10月19日 | 太陽系内に飛来した恒星間天体オウムアムア(1I/2017 U1 ('Oumuamua))が発見される。恒星間天体としては初めての発見で、独自の双曲線軌道を通り、太陽の近くを通過して太陽系外へと飛び去る。長さ800m未満の細長い形状をしており、色は赤系、回転していると見られる。太陽系内を通過中に加速したことから、異星文明の宇宙船か観測機ではないかという説も出た。現時点では自然の天体と考えられている。 |
| 10月20日 | ノルウェーのソルベルグ内閣改造に伴い、首相、国防相、財務相が女性となる。 |
| 10月25日 | クルド自治政府、独立を問うた住民投票の結果を凍結すると発表。 |
| 10月27日 | スペインのカタルーニャ州議会は、独立宣言を賛成多数で承認。スペイン中央政府のラホイ首相は、上院の決議に基づき、カタルーニャ州議会の解散と、プチデモン首相の罷免を決定。 |
| 10月28日 | 国際刑事裁判所からブルンジが脱退。 |
| 10月29日 | サウジアラビア政府、翌年から女性のスポーツ競技場入場を条件付きで認めると発表。 |
| 10月30日 | 座間9人殺害事件が発覚。行方不明の女性の捜索過程で座間市緑が丘のアパートを家宅捜索したところ、翌日にかけて9人の遺体が発見される。犯人の白石隆浩が短期間の間にSNSで知り合った女性8人を相次いで暴行した上殺害し、遺体を解体。さらに被害者の女性の1人を探しに来た男性も殺害した。白石は死刑判決・確定。 |
| 11月 2日 | スペイン司法当局、カタルーニャ州のプチデモン前首相ら5人を国際指名手配。 |
| 11月 4日 | サウジアラビアのサルマーン王太子が、汚職容疑で王子11人を含む王族ら数十人を拘束。 |
| 11月 5日 | 国際調査報道ジャーナリスト連合が、タックスヘイブンに関する電子文書1340万件、いわゆる「パラダイス文書」を公開。 |
| 11月12日 | イラン・ハラブジャ地震。イランとイラクで少なくとも死者430人。 |
| 11月12日 | ペルーのベンタロン遺跡で、保護設備が火災に遭い、紀元前2000年ころのアメリカ大陸最古級の壁画が損傷。 |
| 11月13日 | シリアの「安全地帯合意」に指定されていたアタリブで空爆により市民61人が死亡。シリア政府軍機かロシア軍機によるものとみられる。 |
| 11月13日 | クリスティーズのオークションに、レオナルド・ダ・ヴィンチのキリストの肖像画「サルバトール・ムンディ」が出品され、4億5031万2500ドル(約508億円)の史上最高額で落札。かつて行方不明になり、発見後も複製品と思われたことのある作品。ダヴィンチ自筆かダヴィンチを含む複数人による作品かなど今でも論争になっている。 |
| 11月15日 | アルゼンチン海軍のTR-1700型潜水艦S-42サンファンが消息を絶つ。乗員44人。 |
| 11月15日 | ジンバブエで国防軍が事実上のクーデターを起こす。高齢のムガベ大統領の後継をめぐる、ムガベの妻のグレース・ムガベと、軍の支持を得たエマーソン・ムナンガグワの対立から、軍が武装蜂起し首都を制圧。ムガベ政権側の有力者らを拘束。ただしムガベ大統領自身には手を出さず。 |
| 11月17日 | イギリス上院の儀式等を司る黒杖官に、ウインブルドン・チャンピオンシップの運営者であるサラ・クラークが指名される。女性が選ばれるのは、上院の歴史650年で初めて。女性であるため「The Lady Usher of the Black Rod」となる。 |
| 11月20日 | イスラエルで、ユダヤ教超正統派に対する兵役義務化をめぐって抗議デモが行われる。超正統派は教義を学ぶことを最優先するため、就職もせず、兵役義務にもつかず、近代化を拒否し、イスラエル政府からの補助金で暮らす。婚姻も規則に従うため、非常に出生率が高く、年々その人口に占める割合が増加している。そのため、一般のイスラエル人の反感を買うことも多いことから、兵役義務を課すことになった。 |
| 11月21日 | ジンバブエのムガベ大統領が辞任し、独立以来37年間続いたムガベ政権は崩壊。 |
| 11月24日 | エジプトの北シナイ県ビール・アルアベドで、金曜礼拝中のモスクを武装集団が襲撃。235人が死亡、109人が重軽傷を負う。エジプト空軍は、武装集団のものとみられる家屋や車両を空爆。 |
| 11月24日 | ジンバブエでムナンガグワ政権が誕生。 |
| 11月27日 | イギリス王室は、ヘンリー王子とアメリカの女優メーガン・マークルの婚約を発表。 |
| 11月27日 | イギリスのオックスフォード市は、アウンサンスーチーに対し授与した「市の自由」称号を剥奪。ロヒンギャに対する迫害に対処しなかったことが理由。 |
| 11月29日 | オランダのデンハーグにある旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で、元クロアチア防衛評議会司令官のスロボダン・プラリャクに懲役20年の判決を下したところ、プラリャクは判決を拒否し、その場で服毒自殺。ムスリムへの迫害等に関わっていたとされる一方、クロアチアやボスニアの一部クロアチア人の間ではプラリャクを英雄視する人々もいる。 |
| 11月29日 | 北朝鮮が大陸間弾道ミサイル「火星15型」の発射実験を実施。北朝鮮政府は、実験成功と国家核戦力完成を発表。 |
| 12月 1日 | 皇室会議によって天皇の退位が翌年4月30日と決定。 |
| 12月18日 | アメリカ司法省は、連邦法を改正し、バンプストックをマシンガンに準ずるものとして、製造や販売・所有を禁止。 |
| 12月21日 | 国連総会に於いて、イスラエルの首都をエルサレムと認定したアメリカ政府の決定を無効とする決議案で、賛成128、反対9、棄権35で採決。 |
| 12月28日 | イラン全土で大規模な反政府デモが発生。特定の指導グループによるものではなく、経済悪化へ不満などから第2の都市マシュハドで発生し、各都市へ広まったもので、ハメネイ政権への批判も出る。抗議運動は翌年にかけて断続的に各都市で発生。 |
| 2018年(平成30年) | |
| 1月 6日 | 上海沖の東シナ海で、パナマ船籍の大型タンカーと香港船籍の貨物船が衝突。タンカーは炎上し14日に沈没。32人が行方不明。 |
| 1月17日 | イギリスのメイ政権、社会的孤独者問題の担当大臣を設置。 |
| 1月23日 | 本白根山の鏡池近くから噴火。草津国際スキー場に多数の噴石が落下し、訓練中の自衛隊員1名が死亡、火口に近い白根火山ロープウェイにも被害が出て乗客らが負傷。 |
| 2月 6日 | 台湾の花蓮で大地震。17人が死亡。負傷者250人以上。 |
| 2月 9日 | 第12回冬季オリンピック平昌大会開催。 |
| 2月11日 | ロシアのモスクワにあるドモジェドヴォ空港を離陸したサラトフ航空703便が間もなく墜落乗員乗客71人全員死亡。 |
| 3月25日 | ロシアのケメロヴォにあるショッピングセンターで火災が起き、64人が死亡。 |
| 4月11日 | アルジェリアの首都アルジェのブファリック空港を離陸したアルジェリア空軍のイリューシン76型輸送機がまもなく墜落。乗員乗客257人全員が死亡。 |
| 4月13 | シリアが反政府勢力に対して化学兵器を使用した疑惑で、米英仏連合軍がシリアの化学兵器施設と見られる3箇所をミサイル攻撃。 |
| 4月19日 | スワジランドが、国名を現地の言葉に基づいてエスワティニ王国と改称。 |
| 4月27日 | 板門店で南北首脳会談。 |
| 5月19日 | イギリスのヘンリー王子と、アメリカの女優メーガンがウィンザー城で挙式。 |
| 6月 8日 | 第21回目のFIFAワールドカップ・ロシア大会開幕。7月8日まで。 |
| 6月23日 | タイのタムルアン洞窟で、現地の少年サッカーチームの少年たちとコーチが増水で閉じ込められる。 |
| 6月28日 | 7月8日にかけて、平成30年7月豪雨(通称西日本豪雨)が発生。死者行方不明者232人。 |
| 7月 6日 | オウム真理教の教祖と幹部7人の死刑執行。 |
| 7月12日 | 西之島で噴火を確認。溶岩流出。 |
| 7月23日 | ラオスで、韓国・タイ・ラオスの合弁で建設中だったセーピアン・セーナムノイダムの副ダムが決壊。50億立方メートルの水が流れ出し、下流の19ヶ村が飲み込まれ、少なくとも42人が死亡。行方不明者は1000人以上に上るとみられる。 |
| 7月26日 | オウム真理教の幹部6人の死刑執行。 |
| 8月 5日 | インドネシアのロンボク島でマグニチュード6.9の地震が発生。死者381人。 |
| 8月14日 | イタリア・リグーリア州の高速道路A10号線のモランディ橋が崩落。走行していた多数の車両が巻き込まれ、43人が死亡。 |
| 9月 6日 | 北海道胆振東部地震。厚真町で震度7。死者42人、負傷者762人。北海道電力苫東厚真発電所でボイラーが損傷して停止し、その影響で他の発電所も緊急停止。北海道全域が停電となる。 |
| 9月28日 | インドネシアのスラウェシ島北部でマグニチュード7.5の地震が発生。水平に移動する横ずれ断層だったが、大規模な液状化を起こした他、地震による地すべりが要因とみられる大津波も発生。少なくとも死者2081人、行方不明者1309人。行方不明者は5000人以上とも。 |
| 10月 7日 | 9月に消息不明となっていた国際刑事警察機構の孟宏偉総裁が中国当局の取り調べを受けていることが判明し、中国から辞任の意向が伝えられる。 |
| 11月 4日 | フランスの海外領土ニューカレドニアの独立を問う住民投票実施。独立反対が56.4%で独立を否決。 |
| 11月16日 | 1年前に消息を絶ったアルゼンチン海軍のTR1700型潜水艦S-42サンファンが、コモドーロリバダビア沖水深800mの海底で、アメリカの海底探査企業によって発見される。 |
| 12月25日 | アメリカの天文学者ナンシー・グレース・ローマンが死去。女性天文学者の先駆者で、各大学、天文台、海軍、NASAで天体観測に従事。軌道天文観測所計画に参画し、数多くの天文観測衛星打ち上げに関わる。大型宇宙望遠鏡計画に関わったことから「ハッブルの母」と呼ばれている。赤外線宇宙望遠鏡WFIRSTの名前になっている。 |
| 12月31日 | アメリカが、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)を脱退。 |
| 2019年(平成31年・令和元年) | |
| 1月 1日 | 台風1号(パブーク)が発生。元日に発生を観測した初の例。西進し5日に東経100度線を越えてサイクロンへと切り替えられ、7日にアンダマン諸島付近で衰えてサイクロンではなくなる。 |
| 1月 3日 | 中国の月探査機嫦娥4号が月の裏側に着陸。月面車「玉兎2号」を降ろす。月の裏側への着陸は史上初。 |
| 1月 7日 | ガボンでクーデター事件。 |
| 2月15日 | アメリカのトランプ大統領、メキシコ国境に壁を建設する問題で、議会で予算承認がうまくいかないことから、非常事態を宣言。 |
| 3月10日 | エチオピア航空302便、ボーイング737MAX8がエチオピアのオロミア州で墜落。操縦システムの問題が疑われ、全世界で同型機の運用が停止になる。 |
| 3月15日 | ニュージーランドのクライストチャーチにある2つのモスクで、オーストラリア人の男が銃を乱射。50人が死亡、50人が重軽傷を負う。 |
| 3月15日 | シアトル・マリナーズのイチロー選手が、東京ドームで行われたメジャーの開幕戦のあと、引退を表明。 |
| 3月27日 | 国際刑事警察機構総裁だった孟宏偉が、中国当局により、収賄と職権乱用の罪で共産党籍を剥奪され、訴追される。 |
| 4月 1日 | 新元号「令和」が発表される。 |
| 4月10日 | 国際天文学研究グループの「イベントホライズンテレスコープ」が、複数の観測機器を使い、M87銀河の中心にある巨大ブラックホールの直接撮影に成功したと発表。 |
| 4月15日 | フランス・パリの中心部シテ島のノートルダム寺院で火災が発生。屋根の大部分と中央の尖塔が焼け落ちる。同寺院は修復工事の最中だった。 |
| 4月21日 | スリランカで同時多発自爆テロ。地元のイスラム系過激派の7人のテロ犯によって、複数のホテル、キリスト教会で発生し、45人以上の子供を含む死者253人、重軽傷者500人以上の惨事となる。 |
| 4月15日 | ウクライナ大統領選挙の決選投票で、新人のウォロディミル・ゼレンスキー候補が当選。ロシア外交と経済政策を焦点に争われた。ゼレンスキー候補は人気俳優で、ドラマで大統領を演じたこともあるが(率いる政党の名前とドラマの題名も同じ)、政治家としては全くの新人。親欧米派だがロシアとの関係改善、内戦の終結も掲げた。 |
| 4月30日 | 天皇陛下が退位。近代憲法下での生前退位は初。 |
| 4月30日 | スペイン総選挙で中道左派の現政権が議席を増やして勝利。しかし過半数には届かず。一方、極右政党ボックスも台頭。 |
| 5月 1日 | 皇太子徳仁親王が天皇に即位される。改元され、平成は31年で終了し、令和元年となる。退位された前の天皇は上皇に。 |
| 5月12日 | ホルムズ海峡でタンカーなど4隻の民間商業船が攻撃を受ける。 |
| 6月 9日 | 香港で「逃亡犯条例改正案」に反発する市民100万人が民主化デモを起こす。 |
| 6月13日 | 日本の安倍首相がイランを訪問。ハメネイ師と会談。そのさなかにホルムズ海峡で日本とノルウェーのタンカーが攻撃を受ける。 |
| 6月18日 | 山形県沖地震。山形県鶴岡市や新潟県村上市など局所的に大きな揺れを観測。 |
| 7月18日 | 京都アニメーション放火事件。同社第1スタジオが侵入した男によってガソリンで放火され、急激な火災となり36人が死亡、34人が重症を負う。 |
| 8月 2日 | アメリカとソ連の間で結ばれた中距離核戦力全廃条約が失効する。 |
| 8月 2日 | 福岡連続女性強盗殺人事件の主犯と、大和連続主婦強盗殺人事件の主犯に、同日死刑執行。 |
| 9月 4日 | 香港政府は市民の反発を招いた「逃亡犯条例改正案」を撤回。 |
| 9月 9日 | イランで女性が観戦することを禁止していた男子サッカーの試合をスタジアムに見に行って警察に拘束された女性サハール・コダヤリが、釈放後に抗議のため裁判所前で焼身自殺。 |
| 9月20日 | 日本でラグビーワールドカップ開催。11月2日まで。 |
| 10月12日 | 台風19号が東日本に上陸し、関東甲信越地方で河川洪水が相次ぎ、甚大な被害を出す。 |
| 10月22日 | 即位礼正殿の儀が行われる。 |
| 10月26日 | オーストラリアのウルル(エアーズロック)が入山禁止となる。 |
| 10月31日 | 那覇市の首里城正殿で火災が起き、復元された正殿・南殿・北殿など殆どの建造物が焼失。また正殿内部の展示品421点も焼失した。一方、耐火性の収蔵庫にあった文化財は、損傷を免れたものも多い。当初は原因追及の動きもあったが、途中から地元メディアは追求をやめ、再建キャンペーンにシフトした。調査した警察・消防も原因は不明としているが、1階の分電盤か、当日そこから電源を取っていたコードから出火した可能性が高い。なお地元でよく使われる赤い塗料の桐油が火勢を強めた可能性もある。首里城が焼失したのは今回も含め歴史上5回。 |
| 11月10日 | 祝賀御列の儀のパレードが行われる。 |
| 11月13日 | 「はやぶさ2」が小惑星リュウグウを離れ、地球への帰還の途に付く。 |
| 12月 6日 | 西之島で噴火を確認。溶岩が流出。 |
| 12月 8日 | 中国湖北省武漢で謎の肺炎患者が確認される。新型コロナウイルスによる肺炎と後に判明。もっと早くから流行が始まっていた可能性もある。 |
| 12月15日 | 西之島で新たな火口が出現しているのを確認。溶岩が海にまで流出。 |
| 12月20日 | 『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』が公開。「スターウォーズ」シリーズの続三部作(シークエル・トリロジー)の第三作で、スター・ウォーズ本編(スカイウォーカー・サーガ)9部作の最終作品。 |
| 12月20日 | アメリカ宇宙軍が設立される。複数の軍種を機能的・地域的に統合した場合の編成である「統合軍」アメリカ宇宙コマンドではなく、6番目の軍種に当たる軍組織(陸軍、海軍、空軍、海兵隊、沿岸警備隊、宇宙軍)。当面は空軍の宇宙関連要員を異動させる。軍政上は空軍省に属し、空軍長官のもとで宇宙軍作戦部長が担当する。軍令上は主に衛星の運用などを行う統合軍宇宙コマンドに組み込まれる。 |
| 12月28日 | 恒星間彗星ボリソフが観測される。 |
| 12月30日 | ネット上に新型肺炎の流行に関する地元政府の報告書がリークされる。 |
| 12月31日 | 中国中央政府が、肺炎患者が増加している湖北省武漢の調査を行う。武漢市政府も肺炎の発生を認めるが、事態を過小評価。 |
| 12月31日 | 保釈中の日産の元CEOカルロス・ゴーンが、音楽機材の箱に隠れ、ビジネスジェットで関西空港から海外へ密出国し、トルコ経由でこの日レバノンに到着。 |
| 12月 | オリオン座のベテルギウスが減光を始める。 |
| 2020年(令和2年) | |
| 1月 1日 | 武漢市政府が、新型コロナウイルスによる新型肺炎の発生が疑われる華南海鮮卸売市場を閉鎖。 |
| 1月 3日 | アメリカ軍が、イラク・バグダードでイラン革命防衛隊のソレイマニ司令官を空爆し殺害。 |
| 1月 3日 | 武漢市政府が、新型肺炎に関する情報を公開した医療関係者など8人を訓戒処分。 |
| 1月 8日 | イラン軍がイラク国内の多国籍軍基地を短距離弾道ミサイル15発で攻撃。その数時間後に、テヘラン空港を飛び立ったウクライナ国際航空の旅客機を誤って撃墜。乗員乗客176人全員が死亡。 |
| 1月 8日 | 新型コロナウイルス感染症による新型肺炎で死者が出る。 |
| 1月 9日 | WHOが武漢で広がっている新型肺炎について初めて声明。この時点ではまだヒトヒト感染については否定。 |
| 1月10日 | オマーンのカブース国王が死去。 |
| 1月11日 | 台湾の総統選挙で民進党の蔡英文が再選。前年夏からの香港の民主化運動に対する中国の強硬姿勢が追い風になったと言われる。 |
| 1月23日 | 中国政府は、新型肺炎の流行している武漢市と黄岡市の出入りを制限する封鎖措置に入る。また周辺の鄂州市・天門市・仙桃市など主な13の都市の公共交通機関を停止。 |
| 1月28日 | トランプ米大統領は、独自のパレスチナ和平案を発表。イスラエルの首都をエルサレム全市とする。パレスチナを独立国とし、東エルサレムの郊外に首都を置く。イスラエルの建設した入植地はイスラエルの主権を認める。パレスチナ難民の元の土地への帰還は認めず現住地の住民とする。イスラエルの領土の内、エジプト国境近くの2箇所をパレスチナの領土とし、工業都市と住宅都市を建設する。アメリカはパレスチナの経済支援を行う。ヨルダン川西岸地区とガザ地区を結ぶトンネルを建設する。パレスチナ国は軍を持たない。と言った内容。イスラエル寄りの案のため、パレスチナの猛反発を買うが、アラブ諸国の中には賛意を示すところも。イスラエルはこの案を了承。 |
| 1月28日 | 新型コロナウイルス感染症による新型肺炎の死者が100人を超える。 |
| 1月29日 | 日本政府は、武漢市および湖北省在住の日本人の帰国輸送を開始。全日空のチャーター機を使用。 |
| 1月31日 | イギリスがEUから離脱。移行期間に入る。 |
| 1月31日 | WHOが武漢で広がっている肺炎について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言。しかしテドロス・アダノム事務局長が中国の対応を称賛し、緊急事態宣言を遅らせたことから、批判が各国から上がる。日本政府は「新型コロナウイルスを指定感染症とする政令」を前倒しして施行。アメリカ政府も緊急事態を宣言。 |
| 2月 1日 | 確認された新型コロナウイルスの感染者が1万人を超える。 |
| 2月 2日 | 中国以外で初めて、フィリピンで新型コロナウイルス感染症の死者が出る。 |
| 2月 4日 | 新型コロナウイルスの感染者が2万人、死者が400人を超える。 |
| 2月 6日 | 新型肺炎の注意喚起を行って当局から処分を受けた眼科医の李文亮が新型肺炎により死亡。中国国内で当局に対する反感が広がる。 |
| 2月11日 | 新型コロナウイルス感染症の死者が1000人を超え、SARSの全世界の死者数を上回る。感染者も4万2600人を超える。 |
| 2月18日 | 韓国の新興宗教団体「新天地イエス教証しの幕屋聖殿」で新型コロナウイルスの感染拡大が起きていることが判明。 |
| 2月22日 | 過去にない減光現象を起こしていたオリオン座のベテルギウスが増光に転じたことが報告される。末期の赤色超巨星であることから超新星爆発の前兆現象かと騒がれたが、表面温度の低下によって放出された大量のプラズマガスが凝固してベテルギウスの周囲を覆ったことによる減光と思われる。ただこれまでの400日周期の変光現象が変わってしまうなど何かしらの影響があったと見られる。 |
| 2月25日 | この頃からヨーロッパで、イタリアを中心に新型コロナウイルスの感染が拡大を始める。 |
| 2月27日 | 日本政府は、新型コロナウイルスの感染拡大阻止のため、学校の休校措置を求める異例の発表を行う。 |
| 3月 6日 | 日本政府は、中国と韓国からの入国者(日本人を含む)に14日間の待機措置を決定。強制力はない。中国は理解を示したが、韓国は猛反発し、日本からのビザを停止。韓国の当局者は会見で、日本以外の国に対しては行っていない措置を日本にだけ行う理由を問われて返答できず。 |
| 3月 7日 | 福建省泉州にある新型コロナウイルス感染症患者を隔離していたホテルが突如倒壊。多数が死傷。 |
| 3月 7日 | 台湾の野党国民党の主席選挙で、江啓臣が当選。中国の強硬姿勢、香港の暴動、新型コロナウイルス感染症などで中国に対する不信感が強まる中、国民党は従来の「中国との統一」を視野に入れた主張を取り下げる。 |
| 3月 8日 | 新型コロナウイルス感染が広がるなか、イタリア政府は、北部各州の事実上の封鎖を実施。対象は1660万人。ヨーロッパ各国でも感染が急拡大。 |
| 3月 9日 | 新型コロナウイルスの感染が全世界へと拡大する中、ニューヨーク証券取引所は、株価が暴落。2013年の導入以来初めて、サーキットブレーカーが発動し、取引は自動停止。 |
| 3月11日 | WHOは、新型コロナウイルス感染をパンデミックと認定。 |
| 3月11日 | 新型コロナウイルス感染症の影響で、選抜高等学校野球大会が初めて中止となる。 |
| 3月24日 | 第32回夏季オリンピック・東京大会が、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により1年延期となる。なお、「2020」の名称はそのまま。 |
| 3月28日 | 内戦中のイエメンからサウジアラビアの首都リヤドへ向けて弾道ミサイル2発が発射される。サウジ軍がこれを撃墜。 |
| 5月22日 | パキスタンのラホールからカラチへ向かっていた、パキスタン国際航空8303便エアバスA320型機が、カラチのジンナー国際空港近くの住宅街に墜落し、乗員乗客97人と地上の住民1人が死亡。一旦着陸を試みた際に、速度超過だった上に着陸装置を格納してしまい、機体が滑走路に接触、この際にエンジンが破損、着陸復航(再上昇)を行い、再度着陸に向かっているさなかにエンジン全停となって墜落した。人為的ミスが大きいとされる。 |
| 5月29日 | アメリカのトランプ大統領が、WHOが中国寄りだとして、アメリカはWHOと関係を断つと宣言。 |
| 6月16日 | 北朝鮮が、開城工業団地の南北共同連絡事務所を爆破。先に韓国の脱北者団体が北へ向けて飛ばした反体制ビラの内容に激怒したためとされる。 |
| 6月28日 | 新型コロナウイルスの感染者が世界で1000万人を超える。 |
| 7月 1日 | ロシアの憲法が改正され、プーチン大統領の任期が最大で2036年まで可能となる。 |
| 7月 1日 | 台湾とソマリランドが相互に代表機関の設置に合意。ソマリランドはソマリア北部の独立地域で、同国内では比較的治安が安定しており、国際承認はされてないが十数カ国が窓口を置いている。 |
| 7月 4日 | 前年から噴火が続いている西之島で大規模噴火。 |
| 7月20日 | アラブ首長国連邦の火星探査機「アル・アマル」を搭載したH2Aロケットが、日本の種子島宇宙センターから打ち上げに成功。 |
| 7月27日 | 中国の火星探査機「天問一号」が打ち上げられる。 |
| 7月30日 | アメリカ合衆国が火星探査機パーサヴィアランスを打ち上げる。 |
| 8月 4日 | レバノンの首都ベイルートで、港の倉庫に保管されていた約2750トンの硝酸アンモニウムが火災で大規模な爆発を引き起こし、死者192人、行方不明3人、重軽傷者6500人以上の惨事に。市街地に甚大な被害をもたらし、30万人が家を失ったほか、傍にあった巨大穀物倉庫も崩壊し、大量の備蓄穀物も失われた。爆風はイスラエルやキプロスにも達し、爆発の威力は小型核爆弾並みの数キロトンもあったという説もある。保管倉庫は消滅してクレーターとなった。 |
| 8月 7日 | インドのケーララ州コーリコードで、エア・インディア・エクスプレス1344便が着陸に失敗。乗員乗客190人 のうち21人が死亡。 |
| 8月10日 | アメリカのアレックス・アザー保健福祉長官が台湾を訪れ、蔡英文総統と会談。国交断絶以来、米政権の閣僚が訪れるのは異例。 |
| 8月11日 | 全世界で新型コロナウイルスの感染者が2千万人を超える。 |
| 8月13日 | イスラエルとアラブ首長国連邦が、アメリカの仲介で国交樹立に合意。 |
| 8月28日 | 安倍首相が、持病の潰瘍性大腸炎再発を理由に辞職を表明。 |
| 9月16日 | 第4次安倍内閣が総辞職。衆議院と参議院で内閣総理大臣指名投票が行われ、安倍内閣の官房長官だった菅義偉が内閣総理大臣となる。 |
| 9月18日 | 全世界で新型コロナウイルスの感染者が3千万人を超える。 |
| 9月27日 | ナゴルノ・カラバフ戦争勃発。アゼルバイジャン西部の、アルメニア人が実効支配するナゴルノ・カラバフ地方(自称アルツァフ共和国)を巡り、アゼルバイジャン軍と同地に駐留するアルメニア軍が衝突。過去の同地域での戦争・紛争とは異なり、攻撃型無人兵器などを大量に投入したアゼルバイジャン軍の圧勝に終わる。 |
| 9月28日 | 新型コロナウイルス感染症の世界の死者が100万人を超える。 |
| 10月 2日 | アメリカのトランプ大統領とメラニア夫人が、新型コロナウイルス感染の陽性となったことを発表。株価が値下がりする。 |
| 10月19日 | 全世界で新型コロナウイルスの感染者が4千万人を超える。 |
| 11月 3日 | アメリカ大統領選挙一般投票。コロナ感染対策のための郵便投票が導入されたことや、両陣営の主張が社会を分断したことで関心を呼び高投票率に。大接戦となる。 |
| 11月 9日 | 全世界で新型コロナウイルスの感染者が5千万人を超える。 |
| 11月10日 | ロシアの仲介でアゼルバイジャンとアルメニアの間でナゴルノ・カラバフ停戦協定が発効。ナゴルノ・カラバフ地方を実効支配する「アルツァフ共和国」がこれまでに拡大してきた領地のうちアゼルバイジャンが今回奪回した南部以外の残りの地域も、アゼルバイジャン側に返還。従来のアルツァフのみとする。またアルメニアの南にあるアゼルバイジャンの飛び地「ナヒチェヴァン自治共和国」とアゼルバイジャン本土をつなぐ回廊をロシア管理のもとでアルメニア国内に作ることも決定した。実質の敗北となったアルメニアでは反発する意見が噴出。 |
| 11月13日 | アメリカ大統領選挙で、民主党のバイデン候補が当選を確実とする(選挙人数が確定)。トランプ陣営や支持者は不正があったと反発。どちらの候補者も過去最高の得票数を得る。 |
| 11月26日 | 全世界で新型コロナウイルスの感染者が6千万人を超える。 |
| 12月 1日 | 中国の月探査機「嫦娥5号」が、月に着陸。 |
| 12月 3日 | 中国の月探査機「嫦娥5号」の上昇機が、月のサンプルを積んで月を離陸。 |
| 12月 6日 | 小惑星探査機「はやぶさ2」が地球軌道へ帰還。小惑星リュウグウの土壌を格納したカプセルを地球へ投下し、探査機自身は、地球の重力でフライバイし、次の目標である小惑星「1998 KY26」へと飛び去る。カプセルは無事オーストラリアのウーメラに着地。 |
| 12月 6日 | 中国の月探査機「嫦娥5号」の上昇機と帰還機がドッキングし、月のサンプルを積み込む。 |
| 12月12日 | 全世界で新型コロナウイルスの感染者が7千万人を超える。 |
| 12月14日 | アメリカ大統領選挙で、選挙人投票が実施される。 |
| 12月17日 | 中国の月探査機「嫦娥5号」の帰還機が地球に帰還。 |
| 12月18日 | BLC-1の報告が発表される。2019年4月と5月に観測されたプロキシマ・ケンタウリ方面から来た信号で、地球外知的生命体探査(SETI)の信号候補の最初の報告となった。現在では異星人の発した信号ではないという結論になっている。プロキシマ・ケンタウリは地球に最も近い恒星で、ハビタブルゾーンに惑星がある。 |
| 12月27日 | 全世界で新型コロナウイルスの感染者が8千万人を超える。 |
| 2021年(令和3年) | |
| 1月 4日 | 西之島で噴火を確認。 |
| 1月 6日 | アメリカ大統領選挙で、トランプ大統領支持者が、バイデン候補の次期大統領指名を行う予定だった合衆国議会議事堂を襲撃し占拠する。アメリカ合衆国の国是とも言える民主主義制度を揺るがす事件として大問題に発展。 |
| 1月 7日 | アメリカ大統領選挙に関して、トランプ大統領がツイッターを使った声明で政権移行に同意を示す。 |
| 1月 9日 | スリウィジャヤ航空182便がジャワ海に墜落。乗員乗客62人全員が死亡。 |
| 1月11日 | アメリカ・サンディエゴの動物園でゴリラ2頭が新型コロナに感染。 |
| 1月11日 | 新型コロナの感染者数が9000万人を超える。 |
| 1月13日 | アメリカ合衆国議会議事堂占拠事件で、トランプ大統領が扇動したとして、下院本会議で弾劾訴追が賛成多数で可決される。弾劾訴追は2回め。 |
| 1月17日 | ロシアの反体制指導者アレクセイ・ナワリヌイがシェレメーチエヴォ国際空港で当局に拘束される。ロシア国内では反発する大規模デモが起きる。 |
| 1月20日 | ジョー・バイデンがアメリカ合衆国46代目大統領に就任。カマラ・ハリスが第49代副大統領に就任。 |
| 1月22日 | 核兵器禁止条約が発効。 |
| 1月27日 | 全世界で新型コロナウイルスの感染者が1億人を突破。ここまでに215万人が死亡。 |
| 2月 9日 | 日本から打ち上げられたアラブ首長国連邦の火星探査機「アル・アマル」が火星周回軌道の投入に成功。火星周回軌道投入成功は、アメリカ、ソ連、欧州、インドについで5番目、初の打ち上げで成功した2番めの国(1番目はインド)となる。 |
| 3月 7日 | 赤道ギニアの都市バタの軍事基地で爆発事故があり、死者98人、負傷者615人を出す。 |
| 3月 8日 | 『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』公開。新劇場版4部作の最終作で、TVシリーズからのすべてのエヴァンゲリオンの完結編とも言える作品。興行収入が100億円を超える大ヒットとなる。 |
| 3月23日 | スエズ運河で大型コンテナ船が座礁して運河を塞ぐ。日本の正栄汽船が保有し、台湾の長栄海運が運用。スエズ運河の通行がストップする。 |
| 4月14日 | アメリカのバイデン大統領は、9月11日までにアメリカ軍をアフガニスタンから完全撤退すると発表。 |
| 4月19日 | アメリカの火星探査計画マーズ2020で、小型ヘリコプター「インジェニュイティ」の飛行試験に成功。地球以外の天体での動力飛行試験に成功したのは初めて。 |
| 4月20日 | チャドの大統領で、前日の選挙で6選を果たしたばかりのイドリス・デビが、北部の反政府軍と戦闘中の国軍を視察中に銃撃され死亡。後継として息子のマハマト・デビが暫定軍事評議会による政権を樹立。 |
| 4月 2日 | 台湾東部で、台湾鉄道の特急太魯閣自強号が線路に落ちたクレーン車と衝突。脱線した状態でトンネルに突入し、49人が死亡、245人が重軽傷を負う。 |
| 4月29日 | 中国が、独自の宇宙ステーション(天宮号)のコアモジュール「天和」を打ち上げる。 |
| 5月 8日 | アフガニスタンのカブールで、女子高校で爆弾テロが起き、85人が死亡、147人が負傷。 |
| 5月23日 | ベラルーシのルカシェンコ大統領が、同国の反体制派ジャーナリストで海外で活動していたラマン・プラタセヴィチの乗ったギリシャ・アテネ発、リトアニア・ヴィリニュス行のライアンエアー4978便を空軍機を動員して強制着陸させ、ラマンと同行者を拘束。ギリシャとリトアニアは反発。また機体の所有者であるポーランドも捜査に乗り出す。 |
| 5月26日 | 欧州連合と欧州航空安全機関は、欧州の航空会社がベラルーシの領空を飛行することを停止する命令を出す。 |
| 6月 4日 | 欧州連合は、ベラルーシの航空会社の航空機の飛行を禁止。 |
| 6月24日 | アメリカフロリダ州マイアミの近郊で、12階建てのマンションが突如崩壊。少なくとも98人が死亡。 |
| 7月 3日 | 熱海市の逢初川流域で、大規模な土石流が発生。死者行方不明者27人。最上流の大規模な土砂埋め立て地が崩落していることから違法投棄も問題に。 |
| 7月 7日 | ハイチのジョブネル・モイーズ大統領が、自宅を二十数人の傭兵と見られる武装した集団に襲われ射殺される。夫人も銃撃を受け重症。 |
| 7月 8日 | アメリカのバイデン大統領は、アフガニスタン撤退を前倒しして8月31日までに完了すると発表。すでにこの時点でアメリカ中央軍の殆どはアフガニスタンを離れており、同国内の主要米軍基地も、アフガニスタン軍に引き渡されていた。イギリス軍も大半が撤退を完了。 |
| 7月14日 | アメリカのバイデン政権は、アフガニスタンからの米軍撤退に合わせ、米軍やNATO軍に協力してきたアフガン人を国外へ逃がす「協力者避難作戦」を発表。アメリカ、イギリス、ドイツなどが部隊や航空機を派遣。 |
| 7月16日 | タリバンとアフガニスタン政府関係者などがカタールの首都ドーハで協議。すでに国土の9割を制圧しているタリバンはガニ政権の総辞職を求め、交渉は決裂。 |
| 7月23日 | 東京2020オリンピック開催(第32回オリンピック東京大会)。コロナ禍の影響で1年遅れの開催となったが、2020はそのまま使用。またこのため、はじめて奇数年の開催となった(次回は3年後のパリ大会で予定通り)。国内では立憲民主党と日本共産党が開催反対を唱える。1年延期というオリンピックでは初めての出来事に加え、感染防止のため殆どの競技で無観客となるなど、異例づくしだったが、事前に参加を予定していた国・地域のうち、北朝鮮を除く205の国と地域が参加。33競技339種目1エキシビションが行われた。入場行進が国名の50音順で行われ、ゲーム音楽を使うなど日本独特の内容にもなっている。 |
| 8月 5日 | 全世界で新型コロナウイルスの感染者が2億人を突破。死者425万人。感染力の高いデルタ株が猛威を振るう。 |
| 8月 7日 | タリバンが攻勢に出てニームルーズ州、ジョウズジャーン州を攻略。 |
| 8月 8日 | タリバンが北部のクンドゥーズ州、サーレポル州へ攻勢。 |
| 8月 8日 | 東京2020オリンピック閉幕。殆どの競技で無観客だった一方で、ネットでの視聴はリオ五輪の倍に達したという。大会に参加したベラルーシとミャンマーの選手が、生命の危険があるとして帰国を拒否し、ベラルーシのツィマノウスカヤ選手はポーランドに亡命が認められ、ミャンマーのピエ・リアン・アウン選手は日本で難民申請が受理された。 |
| 8月 9日 | タリバンがタハール州、サマンガーン州などを攻略。 |
| 8月10日 | タリバンが西部のファラー州、北東部のバグラーン州とバダフシャーン州も攻略。 |
| 8月12日 | タリバンが中部の首都に近いガズニー州、西部のヘラート州を攻略。 |
| 8月13日 | タリバンが南部の要衝カンダハールを含むカンダハール州やヘルマンド州も攻略。 |
| 8月13日 | 福徳岡ノ場の海底火山が大噴火を起こす。 |
| 8月14日 | ハイチで大地震が発生。 |
| 8月14日 | タリバンが北部で残っていたバルフ州、東部のナンガルハール州も制圧。 |
| 8月15日 | タリバン勢力がアフガニスタンの首都カブールを包囲。ガニ政権は政権移譲を表明。夜、タリバン軍がカブールに進駐。ガニ政権は崩壊。アメリカは自国の都合で民主主義勢力を見捨てるという悪評が広がり、バイデン政権関係者が弁護する状況に。 |
| 8月16日 | アフガニスタンの首都カブールでは、アメリカ関係者、各国関係者、アメリカ軍に協力した人々などが、国外へ脱出するため、アメリカ軍の抑えているカブール国際空港に殺到。大混乱となる。 |
| 8月24日 | 第16回下記パラリンピック東京大会開催。 |
| 9月 5日 | ギニアで国軍のママディ・ドゥンブヤ大佐が軍事クーデターを敢行。アルファ・コンデ大統領を拘束し、国家和解発展委員会による政権を樹立。野党支持者などはこれを支持。 |
| 9月19日 | スペイン領ラ・パルマ島のケンブレビエハ山が噴火。住民5000人が避難。 |
| 9月29日 | 自民党総裁菅義偉の任期満了に伴う総裁選挙で岸田文雄が第27代自民党総裁に就任。 |
| 10月 4日 | 菅義偉内閣総辞職。岸田文雄が第100代内閣総理大臣となり、岸田内閣が成立。 |
| 10月14日 | 衆議院解散。 |
| 10月 | 沖縄県や、伊豆諸島などに、福徳岡ノ場の海底噴火で出来たと思われる膨大な量の軽石が漂着しはじめる。漁業活動に大きな影響をもたらす。 |
| 12月 6日 | アメリカのバイデン政権は、中国の人権問題などを理由に、2022年北京冬季オリンピックに政治関係者などを派遣しない外交ボイコットを表明。選手は派遣。 |
| 12月 9日 | アメリカ主催で、民主主義サミット開催。欧州諸国や日本などが招待されるが、中国やロシアなどは招待されず。ネットを使った会議形式となる。 |
| 12月10日 | アメリカ中南部8州で、季節外れの大規模な竜巻が相次いで発生。59個の竜巻が観測され、少なくとも91人が死亡。 |
| 12月22日 | イギリスの商用通信衛星インマルサット6F1が種子島宇宙センターからH2Aロケットで打ち上げられる。 |
| 12月25日 | 南米フランス領ギアナのギアナ宇宙センターから、次世代のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を搭載したアリアン5ロケットの打ち上げに成功。同望遠鏡は主鏡が6.5mもある大きなもので、地球から150万kmの宇宙空間に配置され、ファーストスターや系外惑星の探索に使われる予定。 |
| 2022年(令和4年) | |
| 1月 5日 | カザフスタンで液化石油ガスの高騰に伴う市民の抗議運動に対し、政府が警察部隊を投入。市民200人を拘束。アスカル・マミン内閣が総辞職。 |
| 1月 6日 | The Astrophysical Journalに、2020年に超新星爆発が起きる一部始終の観測に成功した記事が掲載される。観測されたのは、NGC5731銀河の超新星SN2020tlf。それまで超新星は始まってから観測していたため、超新星爆発には目立った前兆現象はないと考えられていたが、同年夏に発見された赤色超巨星が激しい活動をしていたため、複数の天文台で観測していたところ、発見の130日後に超新星爆発を起こした。 |
| 1月 6日 | カザフスタンのトカエフ大統領の要請を受け、集団安全保障条約機構(CSTO)が平和維持軍をカザフスタンに派遣すると発表。 |
| 1月13日 | トンガのフンガ・トンガ島とフンガ・ハアパイ島の間にある、フンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ海底火山が大規模噴火。 |
| 1月15日 | トンガのフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ海底火山が再び大爆発を起こし、大きな空振と津波が発生。太平洋沿岸各地に津波が襲来する。トンガの首都ヌクアロファなどに大きな被害。 |
| 1月18日 | インドネシア議会で首都移転法案が可決。新首都はカリマンタン島に建設される新都市で名称はジャワ語で「島々の間」を意味するヌサンタラと決定。 |
| 1月23日 | ブルキナファソで軍事クーデター。 |
| 2月 3日 | ISILの指導者アブー・イブラッヒーム・アル=ハシーミー・アル=クラーイシーが米軍の特殊作戦で急襲され自爆死。経歴の不明な人物。後任の3代目はアブー・ハッサン・アル・ハシーミー・クラーイシーとされる。 |
| 2月 4日 | 第24回冬季オリンピック北京大会開催。 |
| 2月16日 | 南米の世界最南端の民族ヤーガン族の女性で作家でもあったクリスティーナ・カルデロン・ハーバンがチリのプンタ・アレーナスの病院でコロナ合併症によって死去。純血なヤーガン族では最後の人と言われ、ヤーガン語を母語とする最後の話者でもあった。 |
| 2月21日 | ロシアのプーチン大統領が、ウクライナ東部の親ロシア派が支配する地域の独立を承認すると一方的に発表。欧州諸国が制裁を決定。 |
| 2月24日 | ロシアのプーチン大統領の命令で、ロシア軍がウクライナへ軍事侵攻を開始。ウクライナ軍の各基地へのミサイル攻撃と、国境から陸軍部隊が侵攻。ロシア軍がチェルノブイリ発電所を武力で占領。ウクライナはロシアと断交。ロシアに隣接するリトアニアとモルドバも非常事態を宣言。米国は米軍のNATO追加派兵を決定。ただしウクライナには非加盟国であるため、派兵しない。ルーブルは大幅に下落、ロシア関連株も売りが殺到して暴落し、モスクワ市場は取引を一旦停止。ロシアの約50都市で反戦デモが起きるが、当局により鎮圧。3000人以上が拘束されたと見られる。 |
| 2月25日 | ロシア軍の軍事侵攻を受けて、ウクライナ政府は総動員令を発令。ウクライナ軍は各地で対戦車ミサイルジャベリンや、トルコ製の無人機バイラクタルTB2で応戦し、ロシア軍に少なからぬ被害が出たと見られる。ミクロネシア連邦がロシアと断交を発表。国連安全保障理事会は、緊急会合を開催。ロシア軍の即時撤退を賛成11カ国、棄権3カ国で決議したが、ロシアの拒否権発動で否決。アノニマスのハッカーがロシアに対するサイバー攻撃を実施。 |
| 2月26日 | ロシア軍とウクライナ軍は、ウクライナの首都キーウの郊外、北東部のハルキウ、南東部のメリトーポリなどで交戦。アメリカがウクライナへ武器供与を発表。欧米各国は、ロシアの金融機関のSWIFT(国際銀行間通信協会)からの排除を決定。世界各地でロシアへの批判デモが開催され、各スポーツ国際団体は相次いでロシアに関係するスポーツ大会の中止または開催地変更を決定。ロシア関連の文化イベントも相次いで中止に。中国の歴史学者5人が戦争に反対する声明を投稿したが、まもなく中国当局によって削除。 |
| 2月27日 | ロシアのプーチン大統領は、核抑止部隊の高度警戒態勢を取るよう軍司令部に命じる。世界各国でこれに反発の声が上がる。ウクライナ政府、世界中へ義勇兵募集を呼びかけ、義勇軍を創設。ロシアとの外交交渉を優先していたドイツとフランスが、ウクライナへの武器供与を決定。オランダもウクライナへの武器供与を発表し、中立国のスウェーデンもウクライナへ武器供与を決定。ロシアの同盟国ベラルーシは、ルカシェンコ大統領が「国民投票」によって、憲法の中立条項と非核条項の削除を決定。核保有を可能にするとして各国が批判。EUはロシア航空機のEU空域の閉鎖を決定、EU各国もロシア機の飛行禁止を決定。ロシアも対抗してEU各国のロシア空域の飛行禁止を発表。安倍元首相は核兵器のシェアリングについてタブーなき論議を主張。 |
| 2月28日 | ウクライナとロシアの代表団による停戦交渉が行われるが、条件交渉のみで合意はなし。国連緊急特別総会開催が決定。中立国のノルウェーとフィンランドもウクライナへの武器供与を決定。岸田首相は核兵器のシェアリングについて非核三原則を堅持するとして否定。 |
| 3月 1日 | ポーランド、スロバキア、ブルガリアが、空軍戦闘機のウクライナ供与を決定。衆議院本会議でロシア軍の侵略を非難する決議を採択。れいわ新選組のみ効果がないとして決議に反対。多くの世界企業がこの日までにロシアでの販売、サービス、合弁事業の中止を発表。 |
| 3月 2日 | 国連の緊急特別総会で、ロシアを非難し、即時撤兵を求める決議案が賛成141・反対5・棄権35で採択。アメリカ政府はロシアへの追加制裁とベラルーシへの制裁を発表。 |
| 3月 4日 | ロシア軍がウクライナ南部にあるヨーロッパ最大のザポリージャ原子力発電所を攻撃し占拠。施設の一部が火災を起こすも鎮火。稼働中の原発を攻撃するのは歴史上初めての出来事。 |
| 3月 4日 | 北京パラリンピック開催。13日まで。 |
| 3月 8日 | 国際ハッカー集団アノニマスが、ロシア国営放送を短時間乗っ取ったと発表。 |
| 3月 9日 | 韓国大統領選挙で、野党候補の尹錫悦が当選。 |
| 3月10日 | ハンガリー大統領選挙で、与党のノヴァーク・カタリンが当選。同国初の女性大統領。なおハンガリーは政治の実権が首相にあり、大統領は儀礼的象徴的元首。 |
| 3月11日 | チリ大統領に大統領選挙で当選したガブリエル・ボリッチが就任。36歳。 |
| 3月12日 | トルクメニスタン大統領選挙でセルダル・ベルディムハメドフが当選。2月11日に辞任を表明した現職のグルバングル・ベルディムハメドフ大統領の息子で、実質の権力移譲となった。 |
| 3月13日 | ウクライナ南東部の都市マリウポリの市長が、ロシア軍によって一時拉致される。 |
| 3月15日 | ロシア国営放送の夜のニュース番組で生放送中、女性の職員が、戦争反対、プロパガンダに騙されないで、と書かれたパネルを掲げる事件が起きる。 |
| 3月16日 | 宮城県・福島県境の沖を震源とするマグニチュード7.4の地震が起きる。宮城県と福島県で震度6強を観測。走行中の東北新幹線車両が脱線。 |
| 3月16日 | ポーランド、チェコ、スロバキアの首相が、鉄道でキーウを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談。 |
| 3月19日 | ロシア軍は極超音速兵器の実戦投入を発表。またプーチン大統領は、クリミア併合8周年記念大会なるものを開催。 |
| 3月20日 | ロシア軍はマリウポリの女性や子供が避難していた劇場を爆撃。多数の死傷者が出る。 |
| 3月22日 | 16日の地震で火力発電所が停止したことと、気温の低下から政府は電力需要逼迫警報を発令。企業などに電力使用を控えるよう依頼。 |
| 3月22日 | 中国広西チワン族自治区梧州市の山間部に、中国東方航空5735便ボーイング737型旅客機が墜落。乗員乗客132人全員死亡。 |
| 3月23日 | ウクライナの首都キーウに迫っていたロシア軍が撤退を開始。戦力再編と東部への転進が目的とされる。兵糧不足、ウクライナ軍の反撃による犠牲者の増加、指揮系統の乱れ、各部隊の無連携など、ずさんな作戦も露呈。 |
| 3月24日 | ロシアが占領しているベルジャンシク港でロシアの大型揚陸艦サラトフ、ツェーザリ・クニコフ、ノヴォチェルカスクの3隻がウクライナ軍の攻撃をうけ、サラトフが沈没。ロシアの大統領顧問を務めている政治家アナトリー・チュバイスがロシアから出国。またロシアの比較的豊かな市民から、数少ない運行中の国際ルートであるフィンランド・ヘルシンキ行の特急で国外脱出が相次ぐ。 |
| 3月28日 | 米アカデミー賞で、国際長編映画賞を濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』が受賞。 |
| 3月31日 | ロシア軍がチェルノブイリ原発から撤退。管理権がウクライナ側に戻される。汚染を知らないロシア兵が周辺で塹壕を掘るなどして深刻な放射線被ばくを受けたという報道も。 |
| 4月 1日 | 改正民法が施行され、成人年齢が18歳に引き下げられる。あわせて改正少年法も施行。 |
| 4月 2日 | ウクライナ政府は、キーウ州をロシアから奪還したと発表。一方でキーウ周辺で多数の殺害された市民の遺体が発見される。 |
| 4月 3日 | キーウ郊外のブチャで、市民400人以上がロシア軍によって虐殺されていたことが判明。またロシア兵による女性への性的暴行も多数に上っているとみられる。アメリカ政府は、一連の虐殺・レイプは、一部兵士の凶行ではなく、ロシア軍の組織的計画的犯行との見方を示す。 |
| 4月 3日 | セルビア大統領選挙、国民議会選挙。現職のアレクサンダル・ヴチッチが再選。 |
| 4月 7日 | ロシア軍による深刻な人権侵害の情報をうけて、国連総会で、ロシアの人権理事会メンバー資格の停止決議が行われ、有効投票数の3分の2に当たる賛成98カ国(反対24カ国・棄権58カ国など)となったため、資格停止が可決。先の国連総会による非難決議より棄権国が多いのは、実態調査が行われる前に決議に持ち込まれたことへの反発だとされる。 |
| 4月 9日 | イギリスのボリス・ジョンソン首相がウクライナのキーウを電撃訪問。ウクライナに対し装甲車120台や対艦ミサイルの供与を発表。 |
| 4月10日 | ロッテの佐々木朗希投手が完全試合達成。13者連続奪三振の記録更新(64年ぶり)。 |
| 4月10日 | パキスタンでイムラン・カーン首相に対する内閣不信任決議案が可決。 |
| 4月10日 | 台風2号(メーギー)がフィリピン中部に上陸し停滞。最終的に214人が死亡、132人が行方不明に。 |
| 4月12日 | 新型コロナウイルスの感染者が全世界で5億人を突破。 |
| 4月12日 | ドイツ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、エストニアの大統領らがウクライナのキーウ訪問を打診するが、ウクライナ側はドイツのシュタインマイアー大統領の訪問を拒否。同大統領がメルケル政権時代に外相を務め、ロシアと友好的外交を進めたため。 |
| 4月13日 | フィンランドのサンナ・マリン首相とスウェーデンのマグダレナ・アンデション首相が、ストックホルムで記者会見し、NATO加盟しなければ安全保障が得られないと表明。両国は武装中立国だが、ロシアによるウクライナ侵略をうけて、単独での防衛は難しいとの考えが広がっている。 |
| 4月15日 | ロシアの黒海艦隊旗艦でミサイル重巡洋艦モスクワが、ウクライナの地対艦ミサイル「ネプトゥーン」の攻撃を受けて2発が被弾炎上し、黒海艦隊は曳航を試みたが、モスクワは誘爆して転覆沈没。ミサイルランチャーが舷側にあるなど、弱点の多い旧式艦だが、黒海艦隊の指揮艦でもあり、同艦の喪失はロシア軍の作戦に影響するとされる。現時点で第二次世界大戦後もっとも大きい戦闘艦の撃沈となった(1万トン級の軍艦ではフォークランド紛争で撃沈されたアルゼンチン海軍巡洋艦ヘネラル・ベルグラノ以来)。ロシア側は兵器の火災事故による損傷後悪天候で沈没したと発表。攻撃を受けたとは認めていない。 |
| 4月19日 | 東ティモール大統領選挙で、元大統領ジョゼ・ラモス=ホルタが当選。 |
| 4月23日 | 知床半島沖合で、悪天候の中で出港した知床遊覧船の観光船が沈没。乗員乗客26人のうち死者14人、行方不明者12人を出す。国後島とサハリン南部でも乗員か乗客とみられる遺体が見つかっており、SAR協定に基づきロシアの地元当局から日本側に連絡。海上保安庁も捜索の範囲に北方領土が含まれることを連絡。 |
| 4月24日 | フランス大統領選挙で、エマニュエル・マクロンが再選。 |
| 4月25日 | テスラ創業者イーロン・マスクがTwitter社の買収を発表。 |
| 4月26日 | アントニオ・グテーレス国連事務総長がモスクワを訪問し、プーチン大統領と会談。異様に長いテーブルの端に座らされての会談となったが、マリウポリの住民避難の進展を除いてほぼ成果はなし。 |
| 4月26日 | モルドバから分離独立状態にあるロシア系の沿ドニエストル共和国にある2つの電波塔が爆破され、モルドバ政府は、ロシア軍介入を狙う沿ドニエストル共和国側の自作自演(偽旗作戦)と判断。一方、沿ドニエストル共和国側はモルドバ側のテロと批判。 |
| 4月28日 | アントニオ・グテーレス国連事務総長がウクライナの首都キーウを訪問。ゼレンスキー大統領と会談。会談直後、ロシアが長距離ミサイル数発をキーウに撃ち込む。 |
| 4月28日 | モンテネグロ議会は、首相に前副首相のドリタン・アバゾビッチを選出。 |
| 5月 9日 | フィリピン大統領選挙。フェルディナンド・ロムアルデス・マルコス・ジュニアが当選。元大統領フェルディナンド・マルコスとイメルダ夫人の息子。また前大統領の娘サラ・ドゥテルテが副大統領に当選する。 |
| 5月 9日 | スリランカ反政府運動の激化により、 スリランカ首相のマヒンダ・ラージャパクサが辞任。一族で独裁体制を築き、中国に接近したが、その債務で財政は破綻、経済崩壊も引き起こした。後任にラニル·ウィクラマシンハ元大統領・元首相。 |
| 5月21日 | オーストラリア連邦議会議員総選挙。野党の労働党が勝利し政権交代。ただ外交や安全保障では前政権の政策を継続するとしている。 |
| 5月27日 | 1986年に公開されて大ヒットした映画『トップガン』の36年ぶりの続編『トップガン マーヴェリック』が公開。 |
| 6月14日 | カナダとデンマークの間で続いたハンス島の領有権争い(通称ウイスキー戦争)が、同島の分割領有で合意し終結。ハンス島はグリーンランドとエルズミーア島の間のネアズ海峡の中間に浮かぶ小さな無人島。周辺海域の漁業権などにも影響したため、長らく武力を伴わない紛争(両軍が交互にやってきては自国の国旗を立てて自国のお酒を置いていく)が続いた。お酒を置きあいっこしたので「ウイスキー戦争」と呼ばれた。 |
| 6月15日 | マイクロソフトのウェブブラウザ『Internet Explorer』のサポート終了。OSではWindows95から標準搭載され、Windows10まで搭載されていた。しかし後発のウェブブラウザGoogle Chromeが市場を奪い、マイクロソフトもウェブブラウザをMicrosoft Edgeにシフトして、Internet Explorerの更新は終了した。 |
| 6月19日 | フランス議会総選挙第2回投票で与党の保守連合「アンサンブル」は多数派となったものの過半数割れの敗北。急進左派連合の「新人民連合環境社会」、急進右派「国民連合」が躍進。 |
| 6月22日 | アフガニスタン東部の山岳地帯ホースト州を震源とするマグニチュード5.9の地震が発生。深夜に起きたこと、日干しレンガを積み上げただけの住宅が多かったことから、多数の倒壊により死者は1000人以上、負傷者も2000人を超える惨事となる。タリバン政権を承認していない国が多いことから、国際的な救援や支援は進んでいない。 |
| 6月24日 | 「ドブス対ジャクソン女性健康機構事件」判決。アメリカ合衆国最高裁判所は、「アメリカ合衆国憲法は人工妊娠中絶の権利を保障していない」として、1973年の「人工妊娠中絶は憲法修正第14条のプライバシー権に含まれるため、母体の生命を保護するために必要な場合を除き妊娠中絶手術を禁止したテキサス州法を違憲無効」としたロー対ウェイド事件を覆す判決を下す。アメリカでは中絶は女性の権利とする主張と、胎児も生命であるため中絶は違法とする主張で、国論が二分されている。さらに細かい意見の違いも多い。最高裁判事は大統領が任命する終身制であるため、追加任命時の政権が保守かリベラルかで構成が変わる。トランプ政権時に追加任命で保守派が増えたために判断が覆った。 |
| 6月30日 | 京都大学の数学者望月新一教授の「ABC予想」の証明に成功したとする論文が掲載される。 |
| 7月 8日 | 奈良県で参議院選挙の応援演説を行っていた安倍晋三元首相が、背後から手製の銃で撃たれ、搬送先の病院で死去。銃規制が厳しく、銃犯罪が稀な日本で起きたことから各国でニュースとして取り上げられる。安倍元首相が外交活動で多くの国と関わったこともあり、欧米や中露、民主国から威主義国まで多数の国家、各国際機関などからも弔意が示された。 |
| 7月14日 | サル痘の感染者が全世界で1万人を超える。 |
| 7月23日 | 世界保健機関は、世界中で流行しているサル痘について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言。 |
| 7月24日 | アルバニア大統領に軍参謀総長だったバイラム・ベガイが就任。 |
| 7月27日 | トルコのイスタンブールにウクライナの輸送船の安全航行を監視する「共同調整センター」が設置される。 |
| 7月29日 | ロシア側が支配下においているウクライナ東部ドネツク州オレニウカの捕虜収容所が攻撃され、ウクライナ兵の捕虜50人以上が死亡。ロシア側の攻撃とみられるが、ロシアはウクライナ側の攻撃と発表。ロシアの軍事会社ワグネルの攻撃とする説も。 |
| 7月31日 | 国際テロ組織アルカーイダのトップ、アイマン・ザワーヒリーがアフガニスタンの首都カーブルで、米軍の無人機によるAGM114R9Xヘルファイアミサイル攻撃を受け死亡。弾頭に爆薬ではなくブレードを搭載したもので、ザワーヒリー本人のみを殺害し、家族や周辺住民には被害はなかったとされる。アフガニスタンのタリバーン政権は、アルカーイダとの関係を否定していたが、ザワーヒリーは国外から家族に会うため入国し、カーブルの中心にある高級住宅街シェルプールに潜伏していたので政権の支援があったとみられる。 |
| 8月 9日 | ロシア側が支配下においているクリミア半島西部のサーキ海軍航空基地で大規模な爆発が起き、駐機してあった軍用機少なくとも9機が破壊。ロシア側は弾薬庫の事故としているが、ウクライナ側のミサイル攻撃とみられる。 |
| 8月 9日 | アメリカ・バイデン政権によって半導体法(CHIPS and Science Act)が成立。アメリカ国産の半導体開発生産のために527億ドルを投資するというもの。 |
| 8月10日 | ロシア側が支配下においているウクライナのザポリージャ原発周辺で砲撃が相次ぐ。以降も施設内外に相次いで砲撃が行われる。 |
| 8月11日 | ベラルーシ南部にあるジャブロフカ軍用飛行場で大規模な爆発が発生。ロシア軍が使用していたともされる。ベラルーシ政府は事故と発表し、ウクライナ政府はベラルーシの反政府パルチザンによるものとしている。 |
| 8月19日 | ウクライナのリビウで、ゼレンスキー大統領、トルコのエルドアン大統領、国連のグテーレス事務総長が会談。砲撃が相次いでいるザポリージャ原発に対する対応策を協議。原発の非武装化とロシア軍の撤退を求めることでまとまる。 |
| 8月25日 | 国土の3分の1が大規模な洪水に見舞われたパキスタン政府が非常事態を宣言。洪水は例年を遥かに超える降雨と、熱波による氷河の溶融が原因。 |
| 8月26日 | 新型コロナウイルスの感染者が全世界で6億人を突破。 |
| 8月30日 | ソ連の最後の指導者だったミハイル・ゴルバチョフ元大統領が死去。 |
| 8月30日 | 国連は、6月から8月にかけて起きたパキスタンの大水害について、1億6千万ドルの緊急支援を各国に要請。死者は1500人以上とされるが、国土の大半が被害を受けており、被災者は3300万人以上。温暖化による南アジア全体での異常な降雨が原因とされるが、特に乾燥地のパキスタンで甚大な被害を出した。 |
| 9月 1日 | アルゼンチンの元大統領クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネルが、自宅前で支持者に挨拶しているときに群衆の中にいた男フェルナンド・アンドレ・サバグ・モンティエルに至近から銃で狙撃される。弾丸が発射されなかったため未遂に終わる。モンティエルは逮捕される。 |
| 9月 5日 | イギリスの政権与党保守党の党首選挙で外相などを務めたリズ・トラスが選ばれる。 |
| 9月 5日 | 静岡県牧之原市の認定こども園で、送迎バスに女児が取り残されて熱中症で死亡する事件が起きる。 |
| 9月 6日 | リズ・トラスがエリザベス2世女王によってイギリス首相に任命される。エリザベス2世女王が生涯最後に任命した首相。 |
| 9月 8日 | イギリスの女王エリザベス2世(エリザベス・アレクサンドラ・メアリー)がスコットランドのバルモラル城で崩御。享年96歳。ウィンザー王朝第4代王で、イギリスの歴史で最も長く在位に付いていた王であり最長命の王でもあった(世界史上ではルイ14世の次に長い在位期間)。即日チャールズ皇太子が第5代王に即位。 |
| 9月10日 | ウクライナ軍が東部ハルキウ州の都市でドンバス地方の入り口に当たるイジュームを奪還。 |
| 9月12日 | アゼルバイジャンとアルメニアが国境付近で軍事衝突。ロシアが仲介し停戦したと発表するも実際には効果なく戦闘が継続。 |
| 9月14日 | ロシア軍がウクライナのインフレツィ川のダムをミサイル攻撃で破壊。ダム下流で浸水被害。 |
| 9月14日 | アゼルバイジャンとアルメニアが停戦で合意。両軍合わせて少なくとも284人が死亡。アルメニアを軍事的に支えてきたロシアがウクライナへの侵略でアルメニアどころではなく、そのためアルメニアはこの後、ロシア離れが加速し、EUへの接近が進むことになる。 |
| 9月15日 | 上海協力機構の首脳会議がウズベキスタンのサマルカンドで開催。ロシアのプーチン大統領と中国の習近平主席が会談。プーチン大統領の中国へ配慮する言動に対し、習近平主席の対応は簡潔にとどまる。また以前と異なり、各国首脳のプーチン大統領への対応が悪くなっていることが明らかになる。 |
| 9月16日 | イランの首都テヘランで、クルド人女性マフサ・アミニがヒジャブの付け方が不適切だとして風紀警察に逮捕され、その後死亡。同じく逮捕された女性の証言から、警察官に暴行を受けた疑いが生じ、全土で大規模な抗議デモに発展。年末までデモが頻発し、当局の弾圧で死傷者が多数発生。逮捕された参加者の死刑も執行されている。国外でも抗議デモが相次いだ。また女子生徒に毒ガスを噴射する事件も相次いでいる。 |
| 9月16日 | キルギスのジャパロフ大統領と、タジキスタンのラフモン大統領が、ウズベキスタンで開かれた上海協力機構の会談で国境での軍事衝突に関して停戦で合意。 |
| 9月16日 | 上海協力機構の首脳会談で、インドのモディ首相とロシアのプーチン大統領が会談。モディ首相は「今は戦争の時ではない」と苦言を呈する。 |
| 9月21日 | プーチン大統領が部分的動員令の大統領令に署名。30万人を想定。少なくとも38都市で反対のデモが起き、1400人以上が拘束される。また周辺国との国境に、ロシアから逃げ出す市民が殺到。バルト三国などヨーロッパ側ではロシア人の入国禁止措置に動き、中央アジア諸国では逆に入国を歓迎する動きもでる。 |
| 9月21日 | ウクライナとロシアの間で捕虜交換が行われる。ロシアは捕虜にしていたアゾフ連隊の司令官など205人や外国人傭兵10人を、ウクライナは親露派政治家ヴィクトル・メドヴェチュクやロシア兵55人などを解放。トルコとサウジアラビアが仲介。 |
| 9月23日 | 西九州新幹線のうち、佐賀県の武雄温泉と長崎県長崎市を結ぶ66kmが先行開業。博多から武雄温泉までの在来線リレー特急と武雄温泉で対面乗換方式でつなぐ。並行在来線の長崎本線のうち、肥前山口(江北駅に名称変更)と諫早の間は上下分離方式となり(肥前浜-諫早間は非電化に移行)、諫早-長崎間は従来どおりJR九州となる。大村線、佐世保線などの周辺路線も含めてダイヤ改正。博多-長崎間は従来より30分短縮。一方で新鳥栖-武雄温泉間は、効果が低い割に負担の大きい佐賀県の反対もあり計画は進んでいない。全線開業した場合は、博多から新鳥栖までは九州新幹線の路線を利用する。 |
| 9月23日 | 国連人権委員会は、ウクライナに侵攻したロシア軍によって住民の処刑、拷問、レイプが行われたと結論。処刑は少なくとも16箇所で確認。4歳から82歳までの女性がレイプされたとしている。一方、ウクライナ軍によるロシア兵への虐待も2件あったとしている。 |
| 9月27日 | ロシアが占領しているウクライナの東部と南部の4州で、親露派武装勢力による「住民投票」が終了。ロシア併合が賛成多数となったと発表。武器を持った兵士が各戸を訪問して投票させるなどまともな投票とはいえないものだった。 |
| 9月30日 | ロシアが、占領しているウクライナの東部と南部の4州を一方的に併合宣言。併合を急いだのは、戦況が悪化していることに対して、国内強硬派からの突き上げがあったためとも言われる。また併合宣言で当地域をロシア国内と認定し、そこへのウクライナ側の攻撃はロシアへの攻撃とみなして安全保障を理由に核兵器による反撃もあると脅し戦況を打開しようとする狙いも指摘される。ウクライナはこれを受けて、これまでの方針を撤回し、NATO加盟を申請する。 |
| 10月 2日 | ウクライナ軍が東部の交通の要衝リマンを奪還。 |
| 10月 4日 | 北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、日本上空を通過。日本政府はJアラートを発令。 |
| 10月 6日 | タイ北部のノーンブワラムプー県ウタイサワンナクランで、託児施設に男が侵入して銃を乱射し職員らを射殺、さらにナイフで子どもたちを次々と刺し、車で逃走中に発砲し通行人を轢く。子供24人を含む36人が死亡。10人が重軽傷を負った。犯人も自殺。 |
| 10月 8日 | ロシアが占領しているクリミアとロシア本土とを結んで建設したクリミア大橋で大きな爆発が起き、道路橋の一部が崩落。走行中の燃料輸送列車が炎上。ロシアはウクライナによる破壊工作と非難。 |
| 10月10日 | ロシアがクリミア大橋爆破の報復としてウクライナ全土にミサイル攻撃。少なくとも75発のミサイルが発射される。住宅地やインフラ施設を狙ったものとみられる。 |
| 10月11日 | ロシアが引き続き、ウクライナ全土にミサイル攻撃。ただ2日ともミサイルの命中精度は低く、市民に死傷者多数を出すも、ウクライナ軍に対するダメージは殆どなかった模様。欧米がロシアを非難。ドイツやフランスなどがウクライナに防空システムの供与を表明。 |
| 10月12日 | 国連総会緊急特別会合で、ロシアによるウクライナ東南部4州の一方的併合を違法とする非難決議案が、193カ国中143カ国の賛成多数で採択。反対は5カ国、棄権は35カ国。 |
| 10月12日 | ロシアの独立系メディア「バージニエ・イストーリー」が、連邦保安局や軍関係者からの情報を総合して、開戦以来のロシア兵の死傷者を9万人以上と報道。 |
| 10月14日 | カザフスタンのアスタナで、ロシアと中央アジア5カ国の首脳会議が開催される。タジキスタンのラフモン大統領は、ロシアのプーチン大統領に対し、旧ソ連時代のように中央アジア諸国を属国扱いせず、対等な国家関係を求める。カザフスタンのトカエフ大統領も旧ソ連圏の国境問題は平和的手段で解決すべきだとしてウクライナ侵略を批判。 |
| 10月15日 | ウクライナの検察当局が、ロシア軍による戦争犯罪について、捜査対象案件は4万233件と発表。ロシア軍は同日頃からウクライナのインフラ施設への攻撃を本格化。 |
| 10月16日 | 中国共産党第二十回全国代表大会が開催され、習近平国家主席が異例の3期目に入る。 |
| 10月19日 | ロシア、占領したウクライナ東部と南部4州に戒厳令を導入。 |
| 10月20日 | 第22回目のFIFAワールドカップ・カタール大会開幕。 |
| 10月20日 | アメリカ政府と欧州連合は、イラン政府がロシアのウクライナ侵攻に関して軍事ドローンを供給していると非難。 |
| 10月22日 | ロシア軍がウクライナ南部ヘルソン州の一部から撤退を開始。 |
| 10月24日 | ロシア国営メディアRTの放送した番組で、司会者が「ウクライナの子供達を溺死させるか焼き殺す必要がある」と発言し、RTは同司会者を解雇し謝罪。 |
| 10月28日 | アメリカの下院議長ナンシー・ペロシ宅が襲撃され夫のポール・ペロシが重傷を負う。犯人のデヴィッド・デパペは陰謀論者。 |
| 10月29日 | 韓国ソウルの梨泰院の繁華街にある坂道で、群衆雪崩が発生。158人が死亡、196人が重軽傷を負う大惨事となる。また事故現場に来ていて友人亡くした高校生1人が自殺。また後に管轄の龍山警察署の情報課係長や市役所の安全支援課の担当官も自殺している。 |
| 10月31日 | 中国が宇宙ステーションの実験棟「夢天」を打ち上げドッキングに成功。中国宇宙ステーションは完成。 |
| 11月 1日 | 愛知県長久手市の愛・地球博記念公園にジブリパークが開業。 |
| 11月 2日 | エチオピア内戦で、政府とティグレ人民解放戦線が停戦に合意する。 |
| 11月 3日 | パキスタンでイムラン・カーン前首相がワズィーラーバードで演説中に銃撃され足を負傷。他に1人が死亡、9人が負傷する。犯人の1人は射殺、1人が逮捕される。 |
| 11月 5日 | イラン政府がロシアにイラン製軍事ドローンを提供していることを認める。 |
| 11月11日 | ロシア軍がウクライナ南部ヘルソン州のドニエプル川西岸地区からの撤退を完了。ウクライナ軍が同地を奪還。 |
| 11月11日 | 日本政府は、ウクライナ側で参戦していた日本人が死亡したことを発表。 |
| 11月15日 | 世界人口が80億人に到達したと推測される日。 |
| 11月15日 | 国際度量衡委員会総会で、SI接頭語にクエタ(10の30乗)、ロナ(10の27乗)、ロント(10の-27乗)、クエクト(10の-30乗)が追加される。 |
| 11月16日 | ロシアによるウクライナへのミサイル攻撃の最中に、ウクライナ軍の迎撃ミサイルが、誤ってポーランドに着弾。住民2人が死亡。 |
| 11月20日 | 2022 FIFAワールドカップ カタール大会開催。 |
| 11月30日 | ISILは第3代指導者アブー・ハッサン・アル・ハシーミー・クラーイシーが死亡したと発表。10月中旬に自由シリア軍の作戦で死亡したとみられる。4代目にアブ・アル・フセイン・アル・フセイーニー・アル・クラーイシーとされる。 |
| 12月 5日 | ウクライナ軍が、ロシアのリャザン州のジャーギレボ航空基地とサラトフ州のエンゲルス航空基地を無人機で攻撃。 |
| 12月 7日 | ドイツでクーデター未遂事件が発覚。貴族ロイス家の一族や極右団体「愛国者連合」の関係者のほか軍人、警察官、陰謀主義者など25人が逮捕される。 |
| 12月 7日 | ペルーのカスティジョ大統領が議会による自身の弾劾裁判審議に反発し、議会解散を強行。しかし議会は大統領解任を決議し、ボルアルテ副大統領の昇格を決議。内閣は総辞職し、カスティジョは国外脱出を図るも逮捕される。左派政権を率いたが、議会では少数与党で、軍の支持も得られず、閣僚が問題を起こして次々と辞任するなど安定政権とは言えなかった。 |
| 12月 8日 | ロシアで拘留されていたアメリカの女子バスケットボール選手と、アメリカで収監中だったロシアの武器商人の身柄がそれぞれ解放され、アラブ首長国連邦で身柄交換が行われる。 |
| 12月21日 | ウクライナのゼレンスキー大統領が、ロシア軍の侵攻後初めて国外へ出てアメリカを訪問。 |
| 2023年 | |
| 1月 5日 | ロシアが一方的に36時間の停戦を宣言。ロシア正教会のクリスマスに合わせたものだが、実際にはこの期間中もウクライナへの攻撃は行われた。またウクライナも停戦には応じず。 |
| 1月 8日 | ブラジルの首都ブラジリアでボルソナーロ前大統領の支持者が大統領宮殿、議会、最高裁判所などを襲撃する事件が起きる。 |
| 1月 8日 | ロシア軍は、ウクライナのドネツク州クラマトルスクにあるウクライナ軍陣地2箇所をミサイル攻撃し、600人を殺害したと発表。ウクライナ側は否定。 |
| 1月11日 | ロシア政府は、ウクライナ侵攻作戦の総司令官にゲラシモフ参謀長を任命し、スロヴィキン司令官を副司令官に降格。参謀総長が司令官を兼任するのは異例。 |
| 1月14日 | イギリス政府、ウクライナにイギリスの主力戦車「チャレンジャー2」を供与すると発表。 |
| 1月14日 | ウクライナのドニプロにある集合住宅にロシア軍のミサイルが命中し、住民40人が死亡。 |
| 1月14日 | イスラエル各地で反ネタニヤフ政権デモが行われる。 |
| 1月16日 | ウクライナ東部バフムト近郊のソレダルでウクライナ軍とロシア軍およびロシアの民間軍事会社ワグネルの部隊が交戦。ロシア側が勝利しソレダルを占領。 |
| 1月18日 | ウクライナの内相ら政府関係者の乗った非常事態庁のヘリがキーウ郊外のブロヴァリーにある幼稚園に墜落。内務大臣、内務副大臣、国務長官ら搭乗者10人全員と、幼稚園の園児3人を含む地上にいた4人が死亡。園児11人を含む25人が負傷。 |
| 1月20日 | ウクライナ軍が、ポーランドでドイツ製主力戦車レオパルト2の訓練を開始すると発表。 |
| 1月25日 | ドイツ政府、ウクライナに主力戦車レオパルト2の供与すると発表。他国に輸出した同戦車の供給も許可する。 |
| 1月25日 | 森元首相が「ウクライナに力を入れて良いのか、ロシアが負けるとは思えない」とウクライナを支援する日本政府を批判。森元首相は、ロシア寄りの態度で繰り返しウクライナを批判しており、ロシアの侵略を擁護している。 |
| 1月25日 | オーストラリアの西オーストラリア州で鉱石測定用の放射性物質が輸送中にボルトが外れて落下し行方不明になっていたことが発覚。市民に警報が出されるなどの騒ぎになる。2月1日に無事発見。 |
| 1月26日 | カナダ政府も、保有するドイツ製主力戦車レオパルト2のウクライナへの供与を発表。 |
| 1月29日 | パキスタンの氷結したタンダ・ダム湖で遠足に来ていたイスラム新学校の教師と生徒が乗ったボートが転覆し51人が死亡。うち49人は生徒。助かったのは5人のみ。定員の倍の人数が乗船したことが原因。 |
| 2月 1日 | アメリカのモンタナ州上空で中国の大型の偵察用と見られる気球が飛行しているとして騒ぎに。中国政府は民間の科学研究用気球と主張。 |
| 2月 2日 | 欧州連合のフォンデアライエン欧州委員会委員長と、ミシェルEU大統領がキーウを訪問。ロシア軍による戦争犯罪を調査する機関の設置を発表。 |
| 2月 4日 | アメリカ空軍は、アメリカ上空を横断した中国の大型気球がサウスカロライナ州から大西洋に出たところでF22戦闘機によるミサイル攻撃で撃墜。残骸を回収する。大西洋に出るまで対応しなかったのは墜落の危険回避のためとも。中国は激しく反発。このような偵察気球は過去何度も確認されている。 |
| 2月 6日 | トルコ南部からシリア北部にかけてマグニチュード7.8と7.6の大地震が2回発生。小規模の津波も観測。北はルーマニア、ジョージアから、南はレバノンまで揺れを観測。地震はカフラマンマラシュ付近の断層で起き、少なくとも5万6千人が死亡。シリアの被災地は反政府勢力の支配地域であることから、被害の実態がよくわかっていない。アナトリア半島はプレート境界の上にあり、活断層が多く地震多発地帯の一つ。トルコには耐震基準があるが、行政の腐敗で違法建築が多く被害を拡大させた。シリアは内戦の影響も大きい。 |
| 2月 8日 | ウクライナのゼレンスキー大統領がイギリスを訪問。 |
| 2月11日 | カナダでも中国の気球を発見し撃墜。 |
| 2月12日 | ウクライナ東部ドネツク州のブフレダール攻防戦で、ロシア軍が第155海軍歩兵旅団が壊滅する大敗をしたと見られる。 |
| 2月13日 | モルドバのマイア・サンドゥ大統領が、ロシア寄りの勢力によるクーデター計画の存在を主張する。 |
| 2月14日 | アメリカ政府は、ロシアがウクライナから6000人以上の子供を連れ去り、再教育を行っていると発表。 |
| 2月15日 | ポーランドのワルシャワで、ウクライナ復興国際商談会が開かれる。22カ国300社が参加。 |
| 2月20日 | アメリカのバイデン大統領が、ウクライナの首都キーウを電撃訪問。首脳会談を実施。アメリカ大統領が、米軍が駐留していない戦地へ訪問するのはかなり異例。 |
| 2月23日 | 国連総会で、ロシア軍の無条件撤退決議案が、賛成141カ国、反対7カ国、棄権19カ国、無投票13カ国で採択。 |
| 2月24日 | 中国政府がウクライナ危機に関する立場を声明。戦争の早期停戦、核兵器使用の反対、ロシアへの制裁の反対などを主張するも、ロシア軍の撤退などには言及せず。これについてロシア以外に大きな反応なし。 |
| 2月26日 | サウジアラビアの外相がウクライナを訪問。ウクライナへの人道支援と石油製品支援で合意。 |
| 2月28日 | ギリシャのアテネ発テッサロニキ行の旅客列車がテンピで走ってきた貨物列車と衝突して脱線。57人が死亡、130人が重軽傷を負う大惨事となる。ギリシャでは最悪の鉄道事故となった。 |
| 3月 1日 | ベラルーシのルカシェンコ大統領が中国を訪問し、習近平国家主席と首脳会談。中国の和平案を支持。 |
| 3月 2日 | ロシア義勇軍団が、ウクライナからロシア西部のブリャンスク州へ越境して攻撃を行う。 |
| 3月 9日 | ドイツのハンブルクで、「エホバの証人」の宗教施設が銃撃され8人が死亡。 |
| 3月 9日 | ロシア軍が、ウクライナ全土に対し大規模なミサイル攻撃を実施。各種巡航ミサイル、地対空ミサイル、空対地ミサイルなど81発、ドローン8機。11人が死亡。7つのエネルギー関連施設が被害を受ける。ザポリージャ原発も外部電源が途絶える。 |
| 3月10日 | サウジアラビアとイランが国交正常化。中国の仲介による。 |
| 3月10日 | シリコンバレーバンクが経営破綻。 |
| 3月14日 | アメリカ軍は、黒海上空で偵察飛行をしていたMQ-9無人偵察機がロシア軍のSu-27戦闘機の妨害により墜落。両国はお互いに相手を批判するも軍高官同士で電話会談。 |
| 3月16日 | ポーランドがウクライナに対しMiG-29戦闘機4機の供与を発表。ウクライナにとって西側の航空機は訓練が必要だが旧ソ連系の航空機はすぐに使用できる。 |
| 3月17日 | スロヴァキアがウクライナに対しMiG-29戦闘機13機の供与を発表。 |
| 3月17日 | 国際刑事裁判所が、ロシアのプーチン大統領と、マリヤ・リボワベロワ大統領府大統領全権代行(子供の権利担当)の2人を、ウクライナの占領地から子供を不法に移送した戦争犯罪に対する責任があるとして、逮捕状を発行。 |
| 3月19日 | ロシアのプーチン大統領がウクライナの占領地を訪問。ただこれまでのリスク回避の行動とそぐわないことから影武者という説が広がる。 |
| 3月21日 | インドを訪問していた岸田首相がウクライナの首都キーウを電撃訪問。ゼレンスキー大統領と会談し、支援の継続と、G7広島サミットへのオンライン参加を招請。第二次世界大戦後に日本の首相が戦地を訪問するのは初。 |
| 3月24日 | ロシア前大統領メドヴェージェフが、記者のインタビューで、ウクライナがクリミアを攻撃すれば、核兵器を使用する根拠となると、脅迫めいた発言を行う。 |
| 3月25日 | ホンジュラスが中華人民共和国との外交関係を樹立し台湾と断交。 |
| 3月25日 | ロシアのプーチン大統領は、ベラルーシに戦術核兵器を配備すると表明。 |
| 3月27日 | ドイツ政府は、ウクライナに主力戦車レオパルト2を18両引き渡したと発表。またイギリスの主力戦車チャレンジャー2がウクライナに到着。 |
| 4月 2日 | ロシアのサンクトペテルブルグのカフェで、ウクライナ侵攻を支持していた軍事ブロガーのウラドレン・タタルスキーことマキシム・ユーリェヴィチ・フォミンが爆殺される。 |
| 4月 4日 | フィンランドのNATO加盟が、加盟国の全承認を受けて正式に決定。承認を保留していたトルコとハンガリーが承認したことによる。ロシアのプーチン大統領はNATOの脅威をウクライナ侵攻の口実の一つに上げていたが、結果的にフィンランドのNATO加盟を招くことになり、NATOとの国境が1300kmも増えることとなった。 |
| 4月 6日 | 宮古島近海で陸上自衛隊のヘリコプターが墜落。第8師団長や宮古警備隊長ら10人全員が死亡。直前に中国の艦艇が近海を通過していたため、中国軍に撃墜されたという話がネットなどで拡散する。 |
| 4月 6日 | ロシア義勇軍団がふたたびロシア領内へ越境侵攻。 |
| 4月11日 | ミャンマー北西のザガインで、民主派の式典会場をミャンマー軍が空爆。市民100人以上が死亡。 |
| 4月11日 | アメリカ軍などの機密文書がSNSで公開されていたことが判明し、アメリカのブリンケン国務長官とウクライナのクレバ外相が協議していたことが判明。 |
| 4月15日 | 和歌山県和歌山市の雑賀崎港で、遊説に来ていた岸田首相めがけてパイプ爆弾が投げつけられる。爆弾は炸裂したが、SPがすぐに気づいて首相は避難したため無事。破片で警察官と市民1人が負傷。犯人はその場で取り押さえられる。 |
| 4月15日 | スーダンで政府軍と準軍事組織の即応支援部隊との間で戦闘が勃発。 |
| 4月15日 | ケニアでカルト教団の「グッドニュース・インターナショナル教会」で集団自殺が起きていることが発覚。400人以上が死亡。 |
| 4月19日 | インドが中国を抜いて人口世界一に。 |
| 4月20日 | NATOのストルテンベルグ事務総長が、ウクライナの首都キーウを訪問。ゼレンスキー大統領と会談し、将来のウクライナNATO加盟を協議。 |
| 4月21日 | 中国の盧沙野駐フランス大使が、フランスのテレビに出演して「旧ソ連から独立した国々に主権国としての地位を明文化した国際合意は存在しないため、国際法上の地位はない」と述べたため、東欧諸国、バルト三国が一斉に反発。フランス政府も中国に説明を要求。中国政府は大使個人の発言だとし、「中国はすべての国の独立と主権を尊重している」と火消しの対応に追われる。 |
| 4月25日 | ロシア軍はウクライナ侵攻に、最新鋭の主力戦車アルマタを投入したと発表。 |
| 4月26日 | ウクライナのゼレンスキー大統領と、中国の習近平国家主席が電話会談。 |
| 4月28日 | ロシア軍によるウクライナへの多数のミサイル攻撃で、子供を含む23人が死亡。 |
| 4月29日 | クリミアのセヴァストポリで石油施設の大規模火災が発生。 |
| 4月29日 | ISILは第4代指導者アブ・アル・フセイン・アル・フセイーニー・アル・クラーイシーが、トルコ情報機関の作戦で、シリア国内で死亡。5代目にアブ・ハフス・アル=ハシーミー・アル=クラーイシーが就く。 |
| 5月 1日 | アメリカのファースト・リパブリック・バンクが経営破綻。 |
| 5月 3日 | ウクライナのゼレンスキー大統領と、フィンランド・スウェーデン・ノルウェー・デンマーク・アイスランドの北欧5カ国の首脳が、フィンランドのヘルシンキで会談。 |
| 5月 3日 | モスクワのクレムリン宮殿にある大統領府の上空で、2機の無人機が撃墜される。無人機による攻撃について、アメリカの指示でウクライナが行ったとロシアのペスコフ報道官は声明。ウクライナは否定。ウクライナ国境からは距離がありすぎ、その中を防空システムをかいくぐってクレムリンを攻撃できるかはロシア国内でも疑問視され、ロシア国内の反政府勢力の仕業説やロシアの自作自演説まで飛び交う。 |
| 5月 5日 | 世界保健機関は、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言終了を発表。 |
| 5月 5日 | ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジンが、多数の兵士の遺体の映像とともに、ショイグ国防相とゲラシモフ参謀総長を名指して呼び捨てにし、ロシア国防省の補給体制を非難する映像を投稿。 |
| 5月 6日 | ロシアの民族主義者の作家ザハル・プリレピンの乗った車が爆破され、運転手が死亡、プリレピンは重症を負う。 |
| 5月 8日 | 日本政府は、新型コロナウイルス感染症を、2類相当から、5類へ変更。 |
| 5月10日 | ウクライナ東部バフムトの攻防戦で、ロシア陸軍の第72自動車小銃旅団が大きな被害を出す。 |
| 5月11日 | イギリス政府は、ウクライナに対し条件付きで巡航ミサイル「ストームシャドー」を提供。条件とはロシア国内を攻撃しないこと。 |
| 5月12日 | 日本政府は、「ウクライナ経済復興支援準備会議」の設置を決定。 |
| 5月13日 | ウクライナのゼレンスキー大統領がイタリアを訪問。同国のメローニ首相と、バチカンのフランシスコ教皇と会談。 |
| 5月13日 | ロシアのブリャンスク州でスホイ34戦闘爆撃機2機、ミル8ヘリコプター2~3機が撃墜される。 |
| 5月14日 | タイの下院総選挙で野党の前進塔が第一党に躍進。 |
| 5月14日 | ウクライナのゼレンスキー大統領がドイツ、フランスを訪問。 |
| 5月15日 | ウクライナのゼレンスキー大統領がイギリスを訪問。 |
| 5月16日 | ロシア軍がウクライナ各地へミサイル攻撃を実施。全機撃墜するも、破片などで負傷者が出る。アメリカが供与したパトリオットミサイルシステムも損傷。 |
| 5月16日 | ロシア政府は、ウクライナの穀物輸出に関する4者合意の期限切れ後の失効を主張。 |
| 5月16日 | イギリス政府とオランダ政府は、ウクライナに対してF16戦闘機を供与する国家連合の構築を進めていると明らかにする。 |
| 5月16日 | ウクライナのゼレンスキー大統領の特使としてオレナ夫人が韓国を訪問。 |
| 5月16日 | 中国の李輝ユーラシア事務特別代表が、ウクライナを訪問。中国の提案する和平案を説明するも、ウクライナは領土の喪失を伴う提案は受け入れられないと拒否。 |
| 5月17日 | ウクライナの穀物輸出に関する4者合意が2ヶ月間延長されることで合意。 |
| 5月18日 | 日本政府、ウクライナの負傷兵を自衛隊中央病院で治療するために受け入れることを表明。 |
| 5月19日 | G7広島サミット開幕。 |
| 5月19日 | ウクライナのゼレンスキー大統領がサウジアラビアを訪問。アラブ連盟首脳会議に出席。 |
| 5月20日 | ウクライナのゼレンスキー大統領が日本を電撃訪問。サウジアラビアから、フランスの政府専用機で来日。各国首脳と会談。 |
| 5月20日 | ロシアの民間軍事会社バフムトの創設者プリゴジンは、バフムトを制圧したと声明。 |
| 5月22日 | 自由ロシア軍が、ウクライナからロシア西部ベルゴロド州に侵攻し、一部を占拠したことを発表。またモスクワ市内でも同軍の旗が気球で掲げられる。 |
| 5月24日 | 日本政府、自衛隊車両約100台のウクライナへの供与を開始する。 |
| 5月24日 | ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジンが、ロシアの侵攻の結果、ウクライナは世界最強の軍隊を持つようになったと皮肉る談話を投稿。 |
| 5月24日 | ウクライナ軍は黒海でロシアの情報収集艦「イワン・フルス」を無人ボートで攻撃。ロシア側はボートを撃沈したと発表。 |
| 5月24日 | カザフスタンのトカエフ大統領は、ユーラシア経済同盟の会合で、ロシアがベラルーシに戦術核兵器を配備する計画を進めていることを批判。 |
| 5月24日 | 韓国政府がアメリカを経由してウクライナに弾薬を供与する手続きをしていると報道される。 |
| 5月26日 | 韓国が国産ロケット「ヌリ」を使った観測衛星の打ち上げに成功。 |
| 5月28日 | トルコ大統領選挙決選投票で現職のレジェップ・タイイップ・エルドアンが勝利。 |
| 5月30日 | モスクワに少なくとも8機のドローン攻撃が行われる。 |
| 6月 1日 | スウェーデン政府は、同国が開発したサーブ39グリペン戦闘機のウクライナ人パイロットの訓練を行う用意があると発表。ただ供給する予定はないとも。 |
| 6月 2日 | インドのオリッサ州で旅客列車と貨物列車の三重衝突事故。バハナガ・バザール駅でコロマンデル急行列車が誤って待避線に冒進し貨物列車に衝突。21両脱線して転覆しそのうち3両がちょうど対向してきたSMVTベンガルール・ハウラー間高速急行列車に衝突しこちらも2両が脱線。296人が死亡、少なくとも1175人が重軽傷を負う大惨事に。被害者の多くはコロマンデル急行の前方にあった自由席の乗客と見られる。 |
| 6月 2日 | ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジンが、同社の戦闘員の撤退ルートにロシア軍が地雷を敷設していると主張し批判。 |
| 6月 4日 | ウクライナ軍は、大規模反転攻勢に関して開始時期を明らかにしない、と兵士らが指を口に当てている動画を作成して公開。クリミアのケーブルテレビ局でも何故かこの動画が放映される。 |
| 6月 5日 | ロシア義勇軍は、ロシア西部ベルゴロド州のノバヤ・タボルジャンカ集落を制圧したと発表。また同州ではラジオなどでプーチン大統領の緊急演説なる放送が流れる。 |
| 6月 6日 | ウクライナのヘルソン州にあるドニエプル川のノーバ・カホフカ水力発電所が爆破され、ダムが決壊。下流域が大洪水となる(大半はロシア軍が占領していた地域)。ロシアはウクライナ軍の攻撃と主張したが、ウクライナ軍が下流域の奪還作戦を開始するところだったことから、阻止するため同ダムを占拠していたロシア軍によって爆破された可能性が高い。 |
| 6月 8日 | オーストラリア政府は、同国が保有するFA18戦闘攻撃機をウクライナに対し供与する方向で調整に入ったと発表。同国は新型のステルス戦闘機F35に切り替えるため、41機のFA18を退役させる予定。 |
| 6月 8日 | ウクライナ軍による本格的な反転攻勢が始まる。 |
| 6月11日 | ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジンは、ショイグ国防相がワグネルに対し国防省と契約するよう命じたことについて、ロシア国防省といかなる契約も結ばないと述べる。 |
| 6月14日 | ギリシャ沖で大量の難民を乗せた船が転覆。少なくとも81人が死亡で、500人以上が行方不明に。 |
| 6月15日 | ウクライナのゼレンスキー大統領は、スイス連邦議会でビデオ演説し、スイス製武器の再輸出を認めるよう要請。中立国のスイスは、スイスからの紛争国への武器供与だけでなく、第三国から紛争国へ供与することも認めていない。 |
| 6月18日 | 大西洋の海底にある豪華客船タイタニック号の観光目的の潜水艇タイタン号が、タイタニック号の近くの深海で圧潰。乗員乗客5人全員が死亡。安全性への懸念は事前に指摘されていた。 |
| 6月19日 | モルドバの憲法裁判所は、モルドバ政府から出されていた親ロシア系野党「ショル」の非合法化を認める。 |
| 6月21日 | ウクライナ復興会議がロンドンで2日間の日程で開幕。60カ国以上が参加。 |
| 6月22日 | クリミアとヘルソン州を結ぶチョンガル橋がミサイル攻撃で破損。ウクライナ軍の「ストームシャドー」によるとみられる。 |
| 6月23日 | ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジンは、ショイグ国防相とゲラシモフ参謀総長を「大統領と国民を欺いている」として武力で排除する可能性を示唆。ロシア政府はこれに反発。 |
| 6月24日 | ロシアの民間軍事会社ワグネルが武装反乱。ウクライナの占領地からロシアのロストフ州に侵攻し、ロストフナドヌーのロシア軍南部軍管区司令部を制圧。さらに軍を北上させる。プーチン大統領は急遽テレビ演説を行って、プリゴジンは国家反逆だと批判。 |
| 6月25日 | ロシアの民間軍事会社ワグネルの武装反乱について、モスクワの南200kmまで侵攻していたが、ここでベラルーシのルカシェンコ大統領が仲介に入り、プリゴジンは侵攻を停止し引き返すことを決定。反乱は急速に終息する。ワグネルの攻撃でロシア軍の輸送機やヘリなどが撃墜されている。 |
| 6月27日 | ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジンは、政府転覆の意図はなかった、国防省の陰謀に対する抗議の行進だったと主張。 |
| 7月 3日 | ロシアによる戦争犯罪の調査・情報収集を行う「国際センター」が、オランダのハーグにある欧州司法機構に開設。 |
| 7月 3日 | イスラエル軍がヨルダン川西岸のジェニンで武装勢力に対し大規模な軍事作戦を実施。 |
| 7月 4日 | ロシア政府は、黒海経由のウクライナ産穀物輸出についての4者協定の更新はしないとの見解を示す。 |
| 7月 4日 | ウクライナ政府は、ロシア軍が占拠しているザポリージャ原発の建屋の屋上に、ロシア軍によって爆発物が仕掛けられたと非難。ウクライナ軍が原発を攻撃しているように見せかけるためとの観測も。 |
| 7月 4日 | ベラルーシの反政権派は、ルカシェンコ政権が、ウクライナの子どもたちの強制移送に関与しているとして、国際刑事裁判所に告訴。 |
| 7月 6日 | ウクライナのゼレンスキー大統領が、ブルガリア、チェコ、スロバキアを訪問。 |
| 7月 6日 | アメリカ政府が、ウクライナに対し、クラスター爆弾の供与を決定したと報道各社が報じる。両国ともクラスター爆弾禁止条約には加盟していおらず、すでにロシアがウクライナ侵攻でクラスター爆弾を使用しているため、懸念が広がる。 |
| 7月 6日 | ブルガリア政府が、ウクライナに対し、ブルガリア北部で建設が中断しているベレネ原発のロシア製原子炉2基をウクライナに売却する計画があると報じられる。 |
| 7月 7日 | ウクライナのゼレンスキー大統領がトルコを訪問。トルコのエルドアン大統領は、ウクライナのNATO加盟を支持。穀物輸出協定の延長についても言及。 |
| 7月 7日 | ウクライナ政府は、環太平洋パートナーシップ協定への加入を申請。 |
| 7月 8日 | ウクライナ東部バフムトで再び戦闘が激化。 |
| 7月10日 | アメリカがユネスコに復帰。 |
| 7月15日 | 韓国の尹錫悦大統領がウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談。軍事物資の供与や人道支援で合意。 |
| 7月17日 | ロシア政府はウクライナ産穀物の黒海経由の輸出に関する合意が不履行になったと発表。 |
| 7月23日 | ロシア軍はウクライナ南部の港湾都市オデーサに大規模なミサイル攻撃を行う。港湾施設や、住宅のほか、正教会の救世主顕栄大聖堂が破壊される。オデーサはドナウ川経由でルーマニアから穀物を輸出する拠点ともなっているため、意図して狙っていると見られる。 |
| 7月26日 | ニジェールで軍事クーデター。大統領警護隊が大統領らを拘束。当初は国軍が鎮圧に乗り出していたが、午後には軍がクーデター側に付き、政府機関と憲法の停止を宣言。国内に駐留している旧宗主国フランスに対する反感も要因の一つ。ロシアはクーデターを批判しているが、ロシアの民間軍事会社ワグネルのプリゴジンはクーデターを支持。 |
| 7月28日 | ウクライナのゼレンスキー大統領は、クリスマスを旧ユリウス暦に基づく1月7日から、グレゴリオ暦と同じ修正ユリウス暦の12月25日に変更すると声明。旧ユリウス暦はロシア正教と関係が深いため。 |
| 7月30日 | パキスタンのカイバル・パクトゥンクワ州で、政党の集会の最中に自爆テロが起き、少なくとも63人が死亡、200人が負傷する。イスラム国の犯行と見られる。 |
| 8月 1日 | 東京で「ロシア後の自由な民族フォーラム」が開催。ロシア構成国の分離独立を議論する会議で、各地域の独立派や自由ロシア軍幹部が来日。 |
| 8月 4日 | ウクライナ軍の水上ドローンが、ノボロシスク海軍基地に停泊していた大型揚陸艦「オレネゴルスキー・ゴルニャク」を攻撃し同艦は大破。 |
| 8月 4日 | ロシアで徴兵対象年齢の上限を2024年より27歳から30歳に引き上げる法案と、召集令状が出された国民の出国禁止の法案が成立。 |
| 8月 5日 | ロシアのウクライナ侵攻の終結を目指す会合がサウジアラビアのジッダで開催。40カ国以上が参加。 |
| 8月 5日 | ウクライナ軍の水上ドローンが、ケルチ海峡付近を航行中のロシアタンカー「シグ」を攻撃し、同船は損傷。 |
| 8月 6日 | ウクライナ軍は、巡航ミサイル「ストームシャドー」でクリミアとヘルソンをつなぐチョンガル橋とヘニチェスク橋を攻撃。ヘニチェスク橋は大きく破損。 |
| 8月 6日 | ウクライナ政府は、キーウに立つ「母なる祖国像」に付いていたソ連国章を取り外し、ウクライナ国賞に置き換える。 |
| 8月 8日 | ハワイのマウイ島西部ラハイナで山火事が相次いで発生。原因の一つは、強風で倒れた電柱の送電線からの発火とされている。火は風に煽られてラハイナやクラなどで延焼していき、逃げ遅れた住民など少なくとも97人が死亡。多数の負傷者を出す。 |
| 8月 8日 | ウクライナのゼレンスキー大統領は、反転攻勢が予定よりも遅れていることを認める。また穀物輸送を可能にするため、黒海でロシアに対し反撃をすることも表明。同日、ウクライナ軍はザポリージャ州ですでにロシアの第1防衛線に達したとしており、ヘルソン州のドニエプル川の東岸でもロシアの防衛線を突破したと見られる。 |
| 8月10日 | 西アフリカ諸国経済共同体は、クーデターの起きたニジェールに軍事介入する選択肢を保持すると決定。 |
| 8月11日 | ウクライナ軍は南部ザポリージャ州で、トクマクの北郊にあるロボティネに到達。 |
| 8月11日 | マウイ島の大規模山火事がほぼ鎮火する。ラハイナの街はほぼ焼失。 |
| 8月11日 | ウクライナ政府は、徴兵センターでの汚職捜査で関係者33人が刑事責任を問われると発表。 |
| 8月13日 | ロシア軍は、黒海南西部でパラオ船籍の貨物船に対し、威嚇射撃をして臨検を行ったと発表。停船させられず臨検も出来なかったとする情報も。 |
| 8月13日 | ロシア西部のベルゴロド州とクルスク州で、ドローン攻撃が行われる。ウクライナによる攻撃と見られる。 |
| 8月15日 | ウクライナのイリナ・ベレシュチュク副首相は、戦闘が2024年春以降も続くとの見通しを示す。 |
| 8月15日 | NATOのストルテンベルグ事務総長の首席補佐官が、インタビューで「ウクライナのNATO加盟の代わりに一部領土をロシアに割譲する停戦案」が議論されていると発言したと報道され、NATO幹部が打ち消す状況に。 |
| 8月16日 | ウクライナ産穀物の輸出合意が停止になって初めての貨物船がオデッサ港を出港。ルーマニア領海を通ってトルコへ向かう。 |
| 8月18日 | ロシアの航空宇宙軍総司令官でウクライナ侵攻の副司令官だったスロビキン上級大将が解任される。民間軍事会社ワグネルと近い関係にあり、ワグネルの反乱の情報を事前に得ていたとされる人物。 |
| 8月19日 | ロシア軍は、ウクライナ北部のチェルニーヒウをミサイルで攻撃。7人が死亡、100人以上が負傷。 |
| 8月19日 | ウクライナ軍は、ロシア西部ノブゴロド州の航空基地をドローンで攻撃し、TU22M3超音速戦略爆撃機1機を破壊。 |
| 8月19日 | ウクライナのゼレンスキー大統領はスウェーデンを訪問。スウェーデンが開発した戦闘機サーブ39グリペンの供与について話し合う。 |
| 8月20日 | ウクライナのゼレンスキー大統領はオランダを訪問。F16戦闘機をオランダは42機、デンマークが19機、ウクライナに供与することを決定。ロシアは反発。 |
| 8月21日 | ウクライナのゼレンスキー大統領はギリシャを訪問。F16戦闘機のパイロット訓練で協力することで合意。 |
| 8月22日 | 南アフリカのヨハネスブルグで、BRICs首脳会議が開催。2024年1月からアルゼンチン、エジプト、エチオピア、サウジアラビア、イラン、アラブ首長国連邦が加盟することが決定。 |
| 8月22日 | ロシア軍は、黒海のスネーク島近海で、ウクライナ兵を乗せた高速艇を破壊したと発表。ウクライナ側は否定。 |
| 8月22日 | ウクライナのゼレンスキー大統領は、訪問先のギリシャで、セルビア、クロアチア、ブルガリア、モルドバの首脳らと会談。主に穀物輸出のルートに関して協議。 |
| 8月22日 | アメリカ政府は、アメリカ国内でウクライナ軍パイロットのF16戦闘機の訓練を支援する用意があると発表。 |
| 8月22日 | ロシア政府がイランからの支援で、タタルスタンに年間6000機のイラン製ドローンの製造を行う計画があるとワシントン・ポストが報じる。 |
| 8月23日 | モスクワ郊外のトヴェリ州で、エンブラエル製のビジネスジェット機レガシー60型機が墜落。搭乗者の中に、民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジンと、幹部のドミトリー・ウトキンがおり、乗員も含む他の8名も含め全員が死亡。機内に積み込まれた爆発物を使った政権側による暗殺との見方が出ている。 |
| 8月23日 | インドの月面探査機チャンドラヤーン3号が、月の南極付近に着陸。着陸成功はアメリカ、ソ連、中国に続き4番目。 |
| 8月23日 | ロシア軍が、ウクライナ南部オデーサ州の内陸ドナウ川沿いのイズマイール港などを多数のドローンで攻撃。穀物倉庫や貨物船施設が破壊され、1万3千トンの穀物が被害を受ける。 |
| 8月24日 | ノルウェーのストーレ首相がウクライナを訪問。ゼレンスキー大統領と会談し、F16戦闘機の供与を表明。 |
| 8月25日 | ウクライナ軍は、ザポリージャ方面でロシア軍の防衛線を突破しさらに進攻、あわせてクリミアのロシア軍基地に対して大規模なドローン攻撃を実施。ロシア軍はドローンを全機撃墜したとしている。 |
| 8月26日 | ウクライナ中部ジトーミル州で、ウクライナ空軍の練習機2機が空中衝突し3人が死亡。うち1人は「キーウの幽霊」と称された部隊のメンバーでコールサイン「ジュース」のベテラン戦闘機パイロットだったことが判明。 |
| 8月28日 | ウクライナ軍は、南部のロボティネを完全に奪還したと発表。要衝トクマクの手前の集落。ロシアはこれを否定。 |
| 8月29日 | 日本の岸田首相とウクライナのゼレンスキー大統領が電話会談。ゼレンスキー大統領はウクライナと日本の安全保障に関する2国間協定について協議の意向を示す。 |
| 8月30日 | ウクライナ軍がロシア国内の6州に対し大規模な無人機による攻撃を実施。プスコフ州の空港ではロシア軍の輸送機4機などを破壊。ロシア国内から発射されたドローンや、ウクライナ国産の長距離無人機などの見方がある。 |
| 8月30日 | ガボンで軍事クーデター。26日の大統領選挙で50年以上の長期政権が続くオンディンバ一族の現職が当選したことに軍が反発したもの。オンディンバ一族が拘束され、ブライス・クロテール・オリギ・ンゲマが暫定大統領に就任。 |
| 8月31日 | ロシア政府は、ウクライナの占領地4州で一方的に9月10日まで選挙を開始。 |
| 9月 1日 | ロシアの宇宙機関ロスコスモスのボリソフ社長が、大陸間弾道ミサイル「サルマート」が実戦配備されたと発表。 |
| 9月 3日 | ウクライナのゼレンスキー大統領は、レズニコウ国防相を更迭。国防省の汚職疑惑などの責任を取らせる形での解任と見られる。後任はクリミア・タタール・クリルタイの代議員ルステム・エンヴェロヴィチ・ウメロウが最高議会の承認を得て就任。 |
| 9月 4日 | トルコのエルドアン大統領と、ロシアのプーチン大統領が会談。ウクライナ産穀物の輸出合意が停止していることについて意見を交わすも、合意に至らず。 |
| 9月 4日 | キューバ政府は、人身売買ネットワークが、内外のキューバ人をウクライナに侵攻するロシア軍に参加させるため勧誘活動をしていることを突き止め、取り締まると発表。 |
| 9月 7日 | 故ジャニー喜多川の少年らに対する性加害に関して、ジャニーズ事務所が会見。性加害を認め謝罪。被害者への救済も表明。責任を取って藤島ジュリー景子が社長を退任し、所属タレントの東山紀之が新社長に就任すると発表。 |
| 9月 8日 | モロッコで大地震。震源はアトラス山脈で、マラケシュの旧市街や山岳地帯の各集落で甚大な被害を出す。少なくとも死者2900人。 |
| 9月 8日 | 天皇陛下は、皇居内でG7各国の下院議長およびウクライナ最高会議のステファンチュク議長と面会。 |
| 9月 9日 | ウクライナで人道支援の活動をしている国際NGO「ロード・トゥ・リリーフ」のメンバー4人が乗った車両がロシア軍の攻撃を受け、スペイン人のエマ・イグアルとカナダ人のアンソニー・イナットが死亡、ほか2名も負傷。 |
| 9月 9日 | ルーマニア国内で、相次いでロシア軍の無人機の残骸が見つかる。ルーマニア政府は領空侵犯であると反発。 |
| 9月 9日 | インドでG20首脳会談が行われる。首脳宣言が採択されるも、ロシアを名指しで非難することは盛り込まれず。ウクライナ政府は不満を表明。 |
| 9月 9日 | 日本の林外務大臣が、ウクライナを訪問。日本の複数の企業関係者も同行。 |
| 9月10日 | リビア東部で地中海熱帯低気圧「メディケーン」による豪雨があり、東部の都市デルナ近郊の2つのダムが決壊。ワジ(涸れ川)を濁流が流れ、デルナ市街は甚大な被害を受ける。死者は1万人以上。東部は軍事組織「リビア国民軍」の支配地域。地中海の北側ギリシャでも豪雨で被害が出る。 |
| 9月10日 | ウクライナ政府は、クロアチアの港湾を通じて、穀物輸出が始まったと発表。 |
| 9月11日 | ウクライナ国防省の特殊部隊が、オデーサ沖の石油採掘プラットフォーム「ボイコ・タワーズ」を奪還したと発表。 |
| 9月13日 | ウクライナ軍はロシアが実効支配しているクリミア半島のセヴァストポリにある軍の造船所を攻撃。ロシア軍の大型揚陸艦ミンスクと潜水艦2隻ロストフナドヌーが損傷。 |
| 9月13日 | 北朝鮮の金正恩総書記が専用列車でロシアを訪問。アムール州のボストチヌイ宇宙基地でプーチン大統領と会談。ロシアはこの訪問を大歓迎しているが、これまで格下に見下していた北朝鮮に対するこの対応はロシアの苦境を物語っているという指摘も。 |
| 9月14日 | ウクライナ軍はロシアの哨戒艦セルゲイ・コトフ、ミサイル艦サムームなどを攻撃して損傷を与えたと発表。またクリミアのロシア軍の防空システムを破壊したとしている。ロシア側はこれを否定。 |
| 9月15日 | ユネスコはウクライナの文化遺産「キエフの聖ソフィア大聖堂と関連する修道院群及びキエフ・ペチェールシク大修道院」と「リヴィウ歴史地区」を危機遺産に指定。 |
| 2024年 | |
| 7月26日 | 第33回夏季オリンピック・パリ大会開催予定。8月11日まで。 |
| インドネシアはこの年までに首都をカリマンタン島のヌサンタラへ移転予定。 | |
| 月の周回軌道に新たな国際宇宙ステーション「ゲートウェイ」の建設が始まる予定。有人月探査計画「アルテミス」の拠点になる他、火星探査計画の中継点としても想定。 | |
| 中国が宇宙望遠鏡「巡天」を打ち上げる予定。単独の衛星だが、中国の宇宙ステーション「天宮」とはドッキングできる構造。 | |
| 東京虎ノ門・麻布台再開発事業が完了。高さ330mの超高層ビルを含む超高層ビル3棟が完成する予定。 | |
| 2025年 | |
| 有人月面探査計画「アルテミス」で人が月面に降り立つ予定。 | |
| オランダの民間団体が進めているマーズワン計画では、この年に4人の人間を火星へ到着させる予定。帰還計画はなく、順次人を増やしていく構想。 | |
| カザフスタンは、この年までにカザフ語の表記をキリル文字から、ラテン文字へ変更する予定。 | |
| アメリカは長距離打撃爆撃機計画に基づき、B-21戦略爆撃機を導入予定。これにともないB-1超音速爆撃機とB-2ステルス爆撃機は順次退役予定。なおB-1、B-2よりも遥かに古くから就役しているB-52戦略爆撃機は改良の上でさらに運用を継続する予定。 | |
| 2026年 | |
| アントニ・ガウディの没後100年のこの年にサグラダ・ファミリア(聖家族贖罪教会)が完成予定。 | |
| 2027年 | |
| 渋谷駅の改良と周辺の再開発を目的とする「渋谷駅街区土地区画整理事業」が完了する予定(26年度)。 | |
| 3月 | ITERによる重水素-トリチウム核融合実験炉の運転開始予定。 |
| 中央リニア新幹線が、品川-名古屋間で開通予定。 | |
| 東京駅北側常盤橋の再開発計画でTORCHタワー(高さ390m)が完成予定。 | |
| 2028年 | |
| 7月21日 | 第34回夏季オリンピック・ロサンゼルス大会開催予定。8月6日まで。 |
| 2029年 | |
| 小惑星アポフィスが地表からおよそ32500kmの距離まで近づく。衝突の可能性は極めて低いが、衝突した場合は約510Mtのエネルギーを放出するため、局所的には大きな被害を引き起こす可能性がある。またこの接近でアポフィスの軌道は変わる恐れが高いため、2036年以降の接近距離は未確定。 | |
| 2030年 | |
| パリ協定で多くの国が温室効果ガスの排出削減目標の基準としている年。削減目標は国ごとに異なる。 | |
| 国際宇宙ステーションの運用を終了する予定の年。 | |
| 2031年 | |
| 国際宇宙ステーションの一部は、南太平洋上のポイント・ネモ(スペースクラフト・セメタリー)に落下させる予定。 | |
| 2033年 | |
| NASAが火星有人探査飛行を計画している年。 | |
| 2036年 | |
| 2月 7日 | 2036年問題。NTP(Network Time Protocol=コンピュータの時計を同期させるシステム)で、「1900年1月1日0時0分0秒の起点」からの積算秒数桁表記がこの日限界に達するため、誤動作を起こす可能性があるとされる。 |
| 2037年 | |
| 中央リニア新幹線が、名古屋-大阪間で開通予定。 | |
| 2038年 | |
| 1月19日 | 2038年問題。UNIX時間(1970年1月1日0時0分0秒を起点)を使用しているコンピュータでは、32ビットの秒桁数がこの日限界に達するために、誤動作を起こす可能性があるとされる。 |
| 2045年 | |
| リニア中央新幹線の名古屋-大阪間開通予定。 | |
| 2045年シンギュラリティ問題。コンピュータが技術的特異点に到達し、知性的に人間を超えることで人間社会に大きな変化が起きると一般的に指摘される年代。社会的問題が顕在化しやすくなることであり、コンピュータの知性化自体はもっと早いとも言われる。またコンピュータの知性化以外の技術的革新も含まれる。 | |
| 2060年 | |
| 7月28日 | 小惑星ベンヌが地球に接近する。 |
| 2061年 | |
| 7月28日 | ハレー彗星が地球に接近する。 |
| 2135年 | |
| 9月25日 | 小惑星ベンヌが地球に接近する。 |
| 2140年 | |
| ビットコインの発行枚数が上限に達する予定。ビットコインは価値の維持のため上限が2100万枚と決まっており、最後の33回目の半減期(21万ブロックごとにマイニング成功の報酬が半減する時点)がこの頃に到達する計算となっている。なお発行の99%は2033年ころに達する。 | |
| 2175年 | |
| 9月25日 | 小惑星ベンヌが地球に接近する。地球に衝突する可能性は24,000分の1ほどと考えられるが、その構造によっても変わる可能性がある。ベンヌは地球近傍小惑星のひとつで、頻繁に地球に近づく。直径は560mほど。 |
| 2880年 | |
| 3月16日 | 小惑星(29075) 1950 DAが地球に接近する。地球に衝突する可能性は8,300分の1ほどと考えられる。直径は1.1kmでアポロ群に所属する地球近傍小惑星。 |
| 2999年 | |
| 12月31日 | 人類史上最も長い曲「ロングプレイヤー」の演奏終了予定日。 |
| 3200年 | |
| この頃までにおおいぬ座VY星が超新星爆発するという説がある。 | |
| 4100年 | |
| この頃ケフェウス座γ星が天の北極に最接近。3100年頃から天の北極に最も近い星になるため、すでに北極星となっている。 | |
| 4200年 | |
| この頃 カメレオン座γ星が天の南極に最接近。 | |
| 5200年 | |
| 2月28日 | グレゴリオ暦と修正ユリウス暦の日付が一致する最後の日。 |
| 5800年 | |
| この頃りゅうこつ座ω星が天の南極に最接近。 | |
| 5900年 | |
| この頃ケフェウス座β星が天の北極に最接近。 | |
| 6939年 | |
| 1939年と1964年のニューヨーク万博で会場のフラッシング・メドウズ・コロナ・パークに埋設されたタイムカプセルが開封される予定。 | |
| 6970年 | |
| 大阪万博の松下館で展示され大阪城公園本丸跡に埋設されたタイムカプセル1号機が開封される予定。 | |
| 10000年 | |
| この頃、デネブが北極星となる。 | |
| 10000年問題。2000年問題が発生した際に、その原因となるコンピュータの「年」を2桁から4桁に変更したが、西暦10000年に5桁になるため、コンピュータが誤動作するといわれる問題。ただしこの頃まで同じシステムを使用しているとは考えにくい。 | |
| 11800年 | |
| この頃、バーナード星が太陽から3.75光年以内にまで接近する。 | |
| 1万2000年後 | |
| この頃、ベガが北極星となる。 | |
| 1万8851年後(20874年) | |
| 5月 | ヒジュラ暦とグレゴリオ暦が同じ年月になる。西暦622年を元年とするイスラム教のヒジュラ暦は太陰暦で閏月を入れないので1年は354日か355日とグレゴリオ暦と約11日ずれる。イスラム教の国でも通常はグレゴリオ暦を使う。 |
| 10万年後 | |
| この頃までにはベテルギウスが超新星爆発を起こしている可能性が高い。 | |
| この頃までにはハワイ島南東のカマエワカナロア(旧ロイヒ)海底火山が島になっているとみられる。 | |
| 地球のその後 | |
| 24万年~74万年後 | 恒星HIP 85605が太陽から0.13~0.65光年にまで近づくという計算もある。ただしこの恒星は22光年から200光年と距離がはっきりしていないため、280万年後に30光年くらいにまでしか接近しないという見方もある。 |
| 122万年~135万年後 | 恒星グリーゼ710が太陽から0.2光年前後付近まで近づくという計算もある。オールトの雲より内側、エッジワース・カイパーベルトに入るため、その影響で多数の彗星が内惑星軌道に落ちてくるという説も。 |
| 200万年後 | もし惑星探査機パイオニア10号が壊れずに飛行を続けていれば、この頃アルデバランに到達する。距離にして約65.3光年。 |
| 1000万年後 | アフリカ大陸の大地溝帯に海水が流れ込んで海となり、アフリカ大陸東部は分離する可能性がある。 |
| 5000万年後 | アフリカ大陸が北上してヨーロッパと衝突するため、地中海は消滅し山脈になる可能性がある。 |
| 1億8000万年後 | 地球の自転は徐々に遅くなり、この頃1日が25時間になる。 |
| 2億年後 | アメイジア大陸説。アジア東部の地下にあるコールドプルームの沈降により、太平洋側でユーラシア大陸とアメリカ大陸が接近合体し、それに南からオーストラリア大陸が接近することで、北上しユーラシア大陸にくっつくアフリカも含めた超大陸アメイジア大陸となる。太平洋は消失。南極については諸説ある。 |
| 2億5000万年~4億年後 | パンゲア・ウルティマ大陸説。上記のアメイジア大陸説とは異なる説で、北アメリカ大陸東部が沈降して大西洋が狭まっていき消失、北上してユーラシア西部にくっついたアフリカ大陸南西から南部にかけてと南北アメリカ大陸が衝突、超大陸パンゲア・ウルティマが出来る。オーストラリアと南極の両大陸については諸説ある。 |
| 6億年後 | 地球と月の距離が離れて、地球からの見かけ上の月と太陽の大きさが合わなくなるため、皆既日食は見られなくなる。 |
| 宇宙のその後 | |
| 10億年後 | 太陽の光度が10%ほど増え、地球表面の温度が上昇。生物の大部分はこの頃までに絶滅すると思われる。 |
| 35億年後 | 太陽の水素核融合が進み、膨張が徐々に進んでいく。水星と金星はやがて失われ、地球は大きく外側に軌道遷移し、地表は強烈な太陽光と水蒸気により千度前後の高温となると考えられる。生物はこの頃までに死滅。 |
| 36億年後 | 海王星の衛星トリトンがロシュ限界に達して崩壊。海王星に大きな環ができると見られる。 |
| 40億年後 | 銀河系とアンドロメダ銀河が衝突。恒星間には広い空間があるため、恒星系同士の衝突といったことは殆ど無いとみられるが、両銀河の形状は融合して一つになり大きく変化すると考えられる(ミルコメダ銀河)。 |
| 63億年後頃 | 太陽の核で水素はほぼ消費しつくされ、核の周辺の水素が核融合を起こすようになる。膨張が進み、赤色巨星と化し、最大で現在の250倍程度になる。 |
| 76億年後頃 | 太陽の核の温度が3億Kほどに達し、ヘリウムの核融合が始まる。核融合の暴走的な現象ヘリウムフラッシュが生じる。超高温となり、20倍未満程度にまで一旦収縮。水素とヘリウムの2層核融合が進み、核が核融合生成物である炭素や酸素で満たされるに連れて、2層核融合は外部へ移動し、再び膨張を始める。最大で800倍程度にまで膨れ上がり、地球はさらに外へと押し出されるか、飲み込まれて消滅。放出された物質は惑星状星雲となっていき、放出が終わると太陽は地球とほぼ同じ大きさの白色矮星となる。この時点で核融合もなくなり、事実上太陽の寿命は尽き、太陽系の各惑星は軌道を外ればらばらに去っていく。さらに宇宙がそのまま存在すれば、白色矮星となった太陽も、数百億年から1兆年もの時間をかけて黒色矮星へとゆっくり弱まっていく。 |
| 200億年後頃? | ダークエネルギーが宇宙の膨張を加速し続けた場合、最終的には4つの基本的な力(重力、電磁力、弱い力、強い力)が光速を超えてしまい、原子が維持できなくなってバラバラになり宇宙は終焉を迎える(ビッグリップ理論の場合)。 |
| 10の13乗年? | 星間物質がほぼ尽きて、星の形成ができなくなる。以降、残っている星が徐々に燃え尽きて減少していく(曲率が負の宇宙の場合)。 |
| 10の27乗年? | 宇宙の膨張が停止した後、逆に収縮していき、ビッグクランチと呼ばれるビッグバンの時と似たような状態になる(曲率が正の宇宙の場合)。 |
| 10の30乗年? | ブラックホールが合体しながら成長していき、銀河を飲み込むほどの大きさになる(曲率が負の宇宙の場合)。 |
| 10の67乗年? | 太陽ほどの大きさのブラックホールがホーキング輻射で蒸発する(曲率が負の宇宙の場合)。 |
| 10の100乗年? | 宇宙の膨張による低温化で、銀河質量の巨大ブラックホールもホーキング輻射で蒸発して消滅。宇宙は光子のみとなり、膨張だけが続く(曲率が負の宇宙の場合)。 |
| 10の200乗年? | 宇宙の核子が崩壊(曲率が負の宇宙の場合)。 |
| 10の1500乗年? | 陽子崩壊が起きなかった場合、宇宙のすべての物質は鉄56に変換する。(曲率が負の宇宙の場合)。 |
| 10の10乗の50乗年? | 真空の量子ゆらぎにより宇宙ではなくボルツマン脳が現れる可能性がある。 |
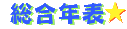
テーマごとには分けず、あらゆる事象をまとめて年代順に記載する年表です。